« ホントに判らなかったの、、、それともまた隠してたの。。。 | メイン | そのとおり!!!Vol.9 »
様々な立場と視点。。。Vol.8
■東日本大震災と阪神・淡路大震災の真の教訓
東京一極集中・地域間競争から協力・共創の時代へ
――池田清 神戸松蔭女子学院大学教授
東日本大震災の歴史的位置
歴史の教えるところによれば、大災害は、その時代の政治や経済、社会が抱える矛盾や本質を露呈させるとともに、大きな政治変動、経済変動、社会変動の引きがねとなっている。たとえば1855年に起きた安政地震は、その後の徳川幕府の総合的な復興対策の失敗と、ペリーの浦賀来航という外圧とも重なり幕府倒壊の契機となった。さらに関東大震災(1923年)は、第一次大戦後の不況とあいまって社会、政治、経済不安を煽った。なかでも朝鮮人大虐殺、社会主義運動の取り締まり、戒厳令による言論、表現の自由に対する弾圧などの一連の諸事件は、その後の治安維持法や1929年の大恐慌という経済混乱のなかで太平洋戦争へ突入するという日本の動向に重大な影響を与えた。
また戦前の軍国主義から戦後の平和と国民主権の憲法体制への転換は、戦災と広島・長崎被爆などの大災害という幾多の苦難を経て得られたものである。今世紀最大の世界史的出来事の一つであるオバマ米国大統領の誕生も、2005年8月のハリケーン・カトリーナ災害とそれに対するブッシュ政権の失政が大きく影響している。なぜならハリケーン被害は、自然災害というより人災であったからだ。ブッシュ政権は、テロ対策とイラク戦争を重視したため、連邦政府の危機管理がおろそかとなり、国内の緊急事態への対応を遅らせ被害を拡大させた。そのためブッシュ政権の支持率が急速に低下し、世論はオバマ大統領誕生へと傾いたのであった。
本稿で問題とする東日本大震災は、明治以降のわが国の近代化過程、特に戦後日本の東京一極集中による高度経済成長を下支えした東北地域の矛盾を顕在化させた。この地域は、首都圏の経済活動に必要な電力、食料、労働力、そして輸出産業である自動車や電機などの部品、素材などを提供してきた。だがそれは、危険な原子力発電と、公共事業や原発交付金、原発関連企業に依存する地域体質を生み出し、人口減少や高齢化などの過疎問題をもたらした。その意味で、東日本大震災は、戦後日本の中央集権的官僚機構と東京一極集中の国土・地域政策、産業政策、エネルギー・原子力政策を根本的に問い直す機会を提起した。と同時に大型施設・設備と生産・エネルギーの広域的分業システム、そして大量生産・流通・消費・廃棄システムによって立つ文明と生活の質そのものの転換を迫るものである。なによりも、相当の確率で予測される、首都直下型地震や東海、東南海、南海地震による津波、原発被害を防ぐためにも転換は必須である。
東日本大震災の特徴
東日本大震災は第1に、地震、火災、津波という従来型の災害と、原発事故、放射能汚染など新しいタイプの大規模な複合災害である。
大江健三郎氏は、東日本大震災後に『ニューヨーカー』へ次のような記事を寄稿している。「地震や津波やその他の天災と同様に、広島の体験は人類の記憶に刻みこまれるべきです。それはまさに人為であるがゆえに、これらの自然災害以上に劇的な大災害です。原子炉を建設することを通して、人間の生命への同じ冒涜を繰り返すことは、広島の犠牲者の記憶への考えうる最悪の裏切りです」。大江によれば、戦後、日本人は、消費文明をひたすら追い求め、戦争の悲惨を底辺に置きざりにして上へ、上へと逃げ、オリンピックを頂点とするピラミッド型をつくりあげた。しかし、このピラミッドの内部の暗闇の空洞は決してうずめつくされず、広島の人間的悲惨はそこに存在しつづけているという。
筆者も、昨年の日本災害復興学会において、近代日本の大災害は、関東大震災や阪神・淡路大震災など自然現象に起因する災害だけでなく、広島の原爆投下にみられる戦災・被爆の人災を対象としなければならない旨の報告をした。その骨子は、 ① 近代日本の都市づくりと災害復興を貫く思想と政策が、為政者の「創造的復興」と被災者の「人間復興」との対抗関係として把握しなければならないこと。② 「創造的復興」とは、為政者が大災害をバネとして開発・成長と近代化をより強力に推し進め権力維持を図ることを目的としている。それは、大災害以前の都市を再建する「復旧」ではなく、都市の構造や外観を抜本的につくりかえる「復興」であった。
だが関東大震災では、大規模な区画整理によって東京下町の人口は、復興直前(1922年)の147万人から直後(1930年)の119万人へと大幅に減少し、郊外は143万人から289万人へ急増した。区画整理は、「表通り及び準表通りのみの市街地を形成し、従来の露地、裏店と称せる消費的客人即ち商品に対する純需要者を排除」したのであった。
一方、「人間復興」は、大正デモクラシーの旗手の一人であった経済学者福田徳三が関東大震災後に提唱したもので、被災者の人間としての「生存権」と営生の機会を保障するものである。それは、核のない平和で環境・経済・社会が持続可能な地域・都市を創りあげる力量を有する「人間発達」につながる、というものだった。
今回の東日本大震災は、電力会社と政府、一部の学者、研究者が「科学・技術」による「安全神話」をつくりだし、原発の危険性を置きざりにして業界の利益を追い求めてきた結果である。そこから学ぶべきは、「われわれの消費生活繁栄のピラミッドの空洞をうずめる」ことである。と同時に、大震災復興において、「人間復興」を期すべく、東京を頂点とする大都市と地方の過疎、東京電力などエリート企業・富裕層と下請け・非正規雇用の貧困層などの格差・差別構造のピラミッドの型そのものを問うものでなければならない。
第2に、今回の特徴は、津波による被害で街が壊滅状態となったことである。国土交通省によれば、青森、岩手、宮城、福島の4県33市区町村の浸水面積は443平方キロメートルで、JR山手線の内側の面積約63平方キロメートルの約7倍に相当する。このうち市街地の浸水面積は92平方キロメートル。「建造物の多くが流失した区域」が23平方キロメートル、「ほとんどが流失した区域」が28平方キロメートルに達する。関東大震災の焼失面積35平方キロメートルや、阪神・淡路大震災で土地区画整理事業が行われた約2.6平方キロメートルと比較しても、過去に例のない大規模な災害である。
政府は、東日本大震災による住宅や道路などの直接的な被害額が16兆-25兆円に上ると試算した。この試算には、原発事故は織り込んでいない。これに、福島の原子力発電施設の被害と廃炉などを加えれば、被害額は合計30-35兆円規模に達するであろう。さらに福島県内外の漁業や農業が、原発事故による放射能汚染と風評被害を受けていること、計画停電による経済的損失など間接的被害額をも加えれば、50兆円を大幅に越えるのではなかろうか。その意味で、死者・行方不明2万7千人余もだした東日本大震災は、関東大震災と広島被爆の二重災害にたとえられるような大惨事なのである。それゆえ関東大震災時のような、総合的な情報収集力と、特別法や予算、規制づくりに強い勧告権を持つ「復興院」的機関を設けるべきとの提案もだされる。だが復旧、復興の主体は、あくまで被災者と被災地であり、その意思やニーズに基づいたきめ細かい復興計画が求められる。政府の役割は、被災地が歴史や産業、文化の異なる多様な地域であることから、人的、組織的、財政的な強力なサポート体制をつくることである。
また戦災復興も「創造的復興」であった。戦後日本は、戦争で被災した人々の「個人の人間としての尊厳」(憲法13条)や「命と暮らし」(憲法25 条)をまもる「人間復興」よりも、経済成長を優先する政策を推進してきた。それは、1945年の「戦災地復興計画基本方針」が、将来の経済成長にともなう自動車交通などに対処するため広幅の道路と羅災地全体の土地区画整理事業を打ち出したことにもあらわれている。さらに1946年の特別都市計画法は、広島市など115都市を「戦災都市」に指定した。広島の戦災復興は、被爆者を救済・援護する「人間復興」よりも、百メートル道路など都市を抜本的に改造する「創造的復興」を目的としたものであった。
本稿は、東日本大震災の復興をすすめていくうえで、阪神・淡路大震災の教訓の意義について検証する。たしかに今回の被災地が、農業、漁業などの第一次産業を主体とする人口減少と高齢化の進む過疎地であるのに対し、阪神・淡路大震災は主に阪神間の都市部であったという相違点がある。だが大規模災害からの復興という点で共通点も有している。さらに今回の大震災復興ビジョンを提起する「復興構想会議」(財界人、有識者、被災自治体の首長などで構成)が、阪神・淡路大震災直後の1995年2月に発足した「阪神・淡路復興委員会」を手本としている。復興計画も、阪神・淡路大震災の復興計画をならい直接被害を 3年間で回復するケースを想定していることからも、阪神・淡路大震災の経験と教訓は、今後の復興を展望する上で貴重な示唆を投げかけるのではないか。
阪神・淡路大震災の教訓
教訓の第1は、政治・行政と被災者との信頼関係が決定的に重要だということである。そのためには、政治・行政は被災者に寄り添い、被災者の声に耳を傾け、刻々と変化する被災地のニーズに対応することが大切である。阪神・淡路大震災直後の応急段階で被災者が願ったことは、人間としての最低限の生活を保障してほしいということであった。小中学校など大規模な避難所は、プライバシーがない上に寒くて眠れないなど生活環境は劣悪であった。そのため高齢者や病弱者は、肺炎などを患い919人もの震災関連死をうみだした。今回の東日本大震災は、水と食料、暖房などがきわめて不十分で阪神大震災よりも劣悪な生活を強いられている。今からでも、政府や被災自治体は、災害救助法を拡大解釈するなどして、小規模施設や保養所、旅館、ホテルなどの宿泊施設を借り上げ、日常生活を感じることができる、ほっとする空間と時間を保障すべきである。また高齢の病弱者に対しては、介護保険制度を適用し福祉施設に入居していただくなどきめ細かい対応が必要であろう。
被災者の願いは、「元住んでいたところで生活や営業を再建したい」ということであった。だが仮設住宅や工場、災害公営住宅などは、遠く離れた山間部の郊外や人工島につくられた。また入居の際に地域のつながりを考慮せず抽選など画一的対応をしたため、いままでのコミュニティが引き裂かれ、仕事場やかかりつけの医者、学校などに行くのに多額の交通費と労力、時間を要し生活が困難となった。さらに多くの孤独死(仮設住宅233人、災害公営住宅681人)や自殺者も生み出された。
阪神・淡路大震災の復興委員会の議論を仕切った藤田正晴氏(元副総理)も、復興は「開発復興」に偏ったきらいがあるとし、「もう少し生活の復旧の議論をすべきだった」と反省したようにインフラ重視の「創造的復興」であった。政府や被災自治体は、被災者の願いである「個人補償」などの生活再建よりも、神戸空港や大規模な区画整理、再開発事業を優先したのであった。
宮城県南三陸町の避難所生活者(約9500人)の意向調査によれば、回答約5千人中約2/3が集団移住を希望せず、元住んでいた町に残留することを望んでいる。また移住希望の1700人の半数は隣接する登米市を希望している。被災者の思いはどの災害においても共通したものなのだろう。特に農民や漁師は、そこの土地と海とともに生き大切な食料をつくっていることに誇りとアイデンティティを感じてきた。であるがゆえに、元住んでいたところで仕事を続けていきたいという。
このような被災者の願いと政治・行政との信頼関係を決定的に打ち砕いたのが、福島原発事故と放射能汚染に対する東京電力の幹部、経済産業省の原子力関連官僚、一部の政治家や学者の言動と態度であった。彼らの対応は、「想定外」「ただちに健康に影響はない」「自主的屋内退避」など責任逃れに終始し、被災者と国民の疑心暗鬼を高めても信頼にほど遠いものだった。「知らしむべからず、依らしむべし」は、為政者の本質ともいうべきものであるが、正確な情報にもとづく事態の説明がなされず後手後手の対応である。私たちは、そこに官僚主義、秘密主義、偽善主義があることを見抜くべきであろう。
政府や東京電力に対する不信感は、住民だけでなく地元首長にも及んでいる。南相馬市長の桜井氏は、「これは天災ではなく、人災だ。燃料がなく避難を希望する住民を移動させられないほどつらいことはない。住民の移動手段の確保は国の最低限の責任だ」と語気を強める。「放射能漏れの風評で物流も断絶している」、「原発の事故発生は報道で知るばかりで、情報は市には全く来ない。怒りさえ覚える。国や東電は現場に来て直接支援してほしい」と訴えている。被災者と被災地は、国や社会からも見棄てられるのではないかと不安と怯えを感じているのである。
『災害ユートピア』を著したレべッカ・ソルニットによれば、災害時には3つの異なる現実があらわれると言う。普通の人は、不幸のどん底にありながら、困っている人に手を差し伸べ、見ず知らずの人間に食事や寝場所を与え、知らぬ間に話し合いのフォーラムができる。利他主義や相互扶助や団結により、そして恐怖ではなく愛や希望により動機づけられた行動がみられる。まさに「災害ユートピア」である。
一方、一部の少数のエリートは、災害時にはパニックを起こすが、それは解き放たれた人間は野蛮で危険だという思い込みから来ているという。そう信じる人たちは、彼ら自身、自分の身や利益を守るためにしばしば粗野な行動に出る。さらにマスコミの思い込みと歪んだ鏡の役割がある。たしかに為政者は、関東大震災時に戒厳令を出し言論の自由を禁止し、GHQは広島被爆に関する報道や文学などの表現を事実上禁止した。そして今回の大災害における為政者やマスコミの対応も、被災者や国民の不安と動揺、疑心暗鬼を煽り、風評被害とも相まって未曽有の二次災害をもたらしている。「市民の社会への参加、活動、目的、自由がすべてほどよく存在している社会では、災害は単なる災害で収まる」のであるが。
教訓の第2は、道路、港湾、空港などのインフラが、震災前の状態より「創造復興」しても、被災者の生活と地場産業が復興しない限り被災地は再生しないことであった。阪神・淡路大震災で強調された「創造的復興」は、まちを単に元の状態に戻すのではなく、防災と多国籍企業の受け皿となる新たな都市を創造することであった。
防災まちづくりの土地区画整理事業は、その区域内は建築基準法、土地区画整理法に基づき建築制限が課される。自分の土地であるからといって建物を自由に建てることができず、仮換地など土地の区画決定に何年もかかり、生活と営業の再建を急ぐ被災者の足かせとなった。たとえば神戸市長田区の土地区画整理区域の人口は、震災前の13,221人(1990年)から9,388人(2005年)にまで減少している。従前の借家人はほとんど戻れず、元の居住者も約50%に過ぎないという地域もある。さらに飲食店や工場、店舗なども半減するなど地域経済の衰退が進んだ。特に問題なのは、この地域の被災者が、ケミカルや機械、金属などの職人として自立した暮らしを営んでいたが、仕事を失い郊外の仮設住宅や災害公営住宅などに転居せざるをえなくなったことは、生きる支えとコミュニティを失い孤独死や自殺の温床ともなった。
JR新長田駅南地区開発事業は、面積20ヘクタール、総事業費2710億円、44棟もの高層の商業ビルやマンションなどを建設する巨大公共事業である。たしかにまちの建物や外観は近代化されたが、ほとんどの店舗で経費に見合う売り上げが上がっていない。シャッターが閉まった店舗が点在し街は死んでいる状態である。もともとこのまちは、ケミカルや機械産業などを基盤とした住・商・工の混在地域であったが、同産業の衰退と人口減少により、大量に建設された商業ビルは、地域内の消費需要を大幅に上回ったのである。この地域は、被災者の意思やニーズを尊重し、震災復興や高齢化に対応した公営住宅、介護、医療、文化施設など、住民が助け合う福祉型まちづくりが必要だった。つまり地域の個性と身の丈に合ったコミュニティが求められた。
阪神・淡路大震災の10年間の復興事業費は、直接被害額約10兆円に対し約16兆円(内訳は国6兆円、県2兆円、市町3兆円、復興基金3500億円で公的資金は11兆3500億円、その他4兆6500億円)である。16兆円のうち約8兆円余りはインフラ復興など「創造的復興」に充てられた。「創造的復興」は、被災者の「個人補償」よりも神戸空港、港湾、高速道路、医療産業都市、土地区画整理事業、市街地再開発事業など、一部の大企業や多国籍業のためのインフラ整備が推進された。これらは、震災復興とは直接関係のない大プロジェクトであり、受注できるのは県外の大手ゼネコンやマリコンなのであって、そのため復興の追加的需要の多くが県外へ流出したのである。
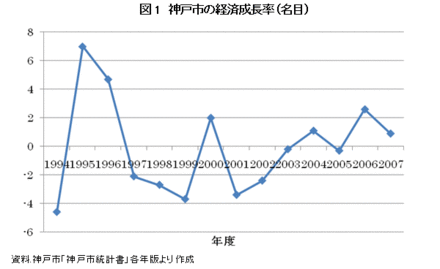
たしかに震災直後の94-95年度の補正予算で3.2兆円の災害復旧の公共事業が打ち出され、5年間で約9兆円の公的資金が投下された。その結果、右図1のように95年度、96年度の神戸市の経済成長率は5-8%で推移した。また下の表1のように300万円未満の低所得世帯は、1992年と 1997年を比べてみると大きな変化は見られない。むしろ1,000万円以上世帯は13.0%から16.3%にまで上昇している。ところが1997年から 2002年に300万円未満の低所得世帯が27.5%から38.4%にまで増加している。同時期の全国が、26.0%から32.3%と増加しているのに対し、神戸市の増加率が極めて高くなっている。つまり、当初の3年間ぐらいは復興特需があるが、その後に急激に落ち込み地域経済の衰退がみられる。

これらの背景には、第1に、仮設の住宅や工場、災害公営住宅、災害復興工場が、被災者の住み営業していたところから遠く離れた郊外などにつくられたため、人口が減少し生活再建が困難となった。第2に、被災者は、住宅や家財、そして仕事も失っているため、生活再建のための公的資金の支給など強力なサポートが必要であった。だが国や兵庫県、神戸市は「私有財産制度に抵触する」との理由で認めなかった。そのため自営業や雇用者などの被災者は、「自立・自助」を強いられ生活再建が困難となり都市中間層の没落と貧困層の増大が進んだ。
第3に、ケミカルシューズ、機械、清酒などの製造業、そして小売業など地域に根ざす産業の衰退がある。表2のように神戸市の製造業従事者は、 1993年の105,159人から2007年の72,248人へと減少し、特に激震地の長田区、須磨区の落ち込みが著しい。さらに地域に根ざした商業やサービス業も激変している。「神戸市と神戸商工会議所の調査」によれば、運営団体数は表3のように、1993年には商店街259、小売市場104だったが、2008年は商店街223、小売市場55で、計85団体が消えている。地域別の減少数は、灘区20団体、長田区16団体、中央区12団体、東灘区11 団体で、この間の復興政策が有効でなかったことを示している。

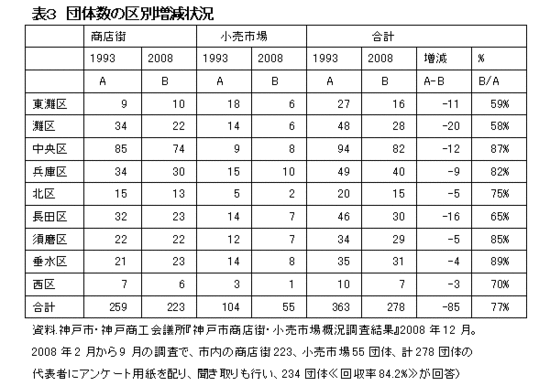
以上、道路、港湾、空港などのインフラが復興したとしても、「人間復興」すなわち被災者の生存の機会の復興である生活、営業、及労働機会と、その基盤である地場産業と地域に根ざした産業の復興が成功しなければ、被災者の生活再建と被災地の再生ができないことである。
東日本大震災の復興
東日本大震災の復興も「創造的復興」をめざしている。日本経団連の幹部は、「元に戻すというより、災害に負けない町づくりを練り直す。〈復興〉より〈創造〉に近いイメージ」、「企業の技術やノウハウを注ぎ込み、被災地を『災害に強く高齢者や環境に優しい町』に作り替える」と話す。菅直人首相も、「世界で一つのモデルになるような新たな街づくりをめざす」として「山を削って高台に住むところを置き、海岸沿いの水産業(会社)、漁港まで通勤する」防災まちづくりを提起している。そして「植物やバイオマスを使ったエコタウンをつくり」、「福祉都市としての性格を持たせる」と主張している。さらに「今回の震災は戦後65年の中で最も大きな危機だ。創造的な復興をぜひ示してほしい」と「復興構想会議」に注文を付けた。
たしかに東日本大震災の復興は、従来のような地震、津波に脆弱な地域に復旧することでなく、新たなまちを創る復興でなければならない。かつて柳田国男は、明治三陸大津波(1896年)から25年後に三陸地方を旅し「雪国の春」を著した。安全のために「元の屋敷を見捨てて高みへ上った者は」経済的利便性を欠いたために「それ故にもうよほど以前から後悔して居る」。「之に反して夙に経験を忘れ、またそれよりも食ふが大事だと、ずんずん浜辺に近く出た者は、漁業にも商売にも大きな便宜を得て居る」と述べ、防災と経済との矛盾を突いた。さらに高台のニュータウンや人工基盤を造成する復興は、「災害に強いまちづくり」として土地区画整理が多用される。だが区画整理事業は、秩序ある街並みを創るということで、被災者が自主的に家屋や店舗を建設することを規制し完了まで長い期間を要する。そのため、被災者が自分の住宅や店舗、工場を再建できず元の生活や営業を再建できなくなる恐れがある。被災者の生活再建と産業の復興による被災地の再生のためには、以下の3つの課題を検討しなければならない。
第1は、「仮設まちづくり」の検討である。これは、本格的復興のまちづくりがかなり長期間かかることから、5年から10年くらい生活できるまちをつくる案である。
仮設まちづくりは、① 被災者が意欲を持って生活できる住まいの場を確保することを目的としている。今なお15万人近くの人びとが避難所での不自由な生活を強いられ在宅の被災者も大勢いる。政府は7万戸以上もの仮設住宅を予定しているが、仮設住宅は、元の住まいの近くにつくるか、移転する場合でも集落やコミュニティを重視したものでなければならない。さらに仮設住宅は、雨露をしのぐハコモノを提供するだけでなく、日常の暮らしに必要な買い物ができる店舗や、手づくりの喫茶店などを整備する。さらに仮設のまちは、病院や福祉施設、近くに畑栽培などができる空間をつくるなど、被災者が意欲を持って暮らしを創る場である。被災者を孤独に追いやるのでなく、生きる希望が持てるコミュニティを大切にしたい。これは、阪神・淡路大震災の教訓でもある。そのためには、仮設住宅を明記している災害救助法の柔軟で弾力的な適用が求められる。
② 水産業では船や港の施設の再建を急ぐことである。当面、政府は仮設の岸壁、水揚げ場、加工場、流通施設などをつくり、漁業の再生を後押しすべきである。農業も塩害対策、風評被害対策を強化し、農業、漁業を再開しようとする人に対し長期資金を無利子で融資するなど手厚い支援が求められる。現在、住宅や生活再建に最高3百万円の「個人補償」など公的支援制度がある。上限3百万円をアップするとともに、この制度を零細自営の農業、漁業、製造業、サービス業などの営業手段にも拡大適用すべきであろう。これらは、「生存」に欠くことができない権利であるからだ。
③ 企業の中には震災を機に部品の調達を東北から海外に求める動きもある。部品製造を担ってきた下請けなど中小零細企業の再建のために、金融、財政面の支援が必要となろう。国内産業の空洞化を避けるために知恵をしぼり、仕事起こしの支援が求められる。
以上の仮設まちづくりによって、被災者が本格的復興に取り組む意欲と生活力を培うことができる。大きな被害を受けた宮城県の気仙沼市では、「森は海の恋人」と森林の保全と漁業の発展を結びつけた活動が取り組まれ、地場産業を支えてきた。自然環境も産業も大切にするという思想である。東北の人たちのふるさとへの愛着は人一倍強いものがある。こうした東北の人たちの心を大事にするまちづくりが求められている。
第2は、地域の個性や多様性を無視した市町村合併を推進することの問題である。政府は、復興の効率化を目的として、被災した市町村に合併を促す特別立法の検討に入っている。機能を果たせなくなった市町村の規模を拡大し、行政機能と財政基盤を強化し、国主導の復興政策の受け皿をつくる狙いである。庁舎や住民基本台帳が流されたり、原発事故で役場ごと集団避難したり、行政機能が著しく損なわれた自治体は少なくない。広大な被災地域で道路や港湾の整備、都市計画などを効率的に進めるには、市町村合併を進める必要がある、というのだ。
効率性のみをめざす市町村合併は、集落単位の農協・漁協の合併を促進するであろう。それは、集約化・効率化による近代的経営をめざし、拠点大漁港や大規模農業を形成するが、有機農業や小魚漁など多様な暮らしを営んできた小さな漁村や農村は駆逐されるであろう。
さる3月24日、福島県須賀川市の有機野菜農家の男性(64歳)が、自宅の敷地内で首をつり自ら命を絶った。福島第一原発の事故の影響で、政府が一部の福島県産野菜について「摂取制限」の指示を出した翌日だった。震災の被害に落胆しながらも、育てたキャベツの出荷に意欲をみせていたという男性。遺族は「原発に殺された」と悔しさを募らせる。これは、原発事故が誘因となっているが、市町村合併、農協・漁協合併も同様の問題が起きないとは断言できない。集落・コミュニティは、その経済的基盤が失われれば衰退するしかない。阪神・淡路大震災の教訓は、復興の原動力は人と人とのつながりと絆であった。被災者が希望を以て前向きに生きるには、生活と産業とが一体となったコミュニティが大切なのである。
市町村合併の行きつく先に何があるのか。日本経団連は、道州制の導入も視野に入れた自治体間協議(県間および基礎自治体レベル)の促進を打ち出し(「緊急提言」3月31日)、経済同友会も環太平洋連携協定(TPP)などの成長戦略を遅滞なく実行することを主張している(「第二次緊急アピール」4月 6日)。だが道州制では、多様な地域性をもつ被災地のニーズや被災者の声を反映した復興は困難である。さらにTPPは、大規模農業で有機農業や中山間地の小規模農家は駆逐し、豊かな漁場の共有空間でもある三陸海岸が外資導入により買い占められ、取り漁られ、棄てられていくのではないか。
第3は、地域・都市間競争から協力・共創の時代へ転換すべき課題である。阪神・淡路大震災は、「ボランティア元年」として1998年のNPO法の契機となった。だが国際競争力強化など都市間競争型の「創造的復興」は、被災者の生活再建と被災地の再生に必ずしも成功したとはいえなかった。今回の大災害は、市町村の職員や役場が被災し、災害応急、復旧、復興を担う最前線基地が十分に機能しないことから、他の自治体の支援なくして被災者と被災地の再生はあり得ない。今まで日本の地方自治体は、中央集権的官僚機構のもとで地域の経済発展を期すべく、道路、工業造成地、新幹線、空港、など地域間のインフラ競争を進めてきた。だがそれは、地域の国や大企業への依存体質と東京一極集中をもたらした。これからのまちづくりに求められるのは、地域・都市間の協力と、共に地域を創造する仕組みである。その意味で、今回の自治体間の協力は、新しい地方自治への挑戦、実験ともいうべきものである。
総務省は被災した5県の県庁と市町村から計550人(3月30日現在)の派遣要望を受け、全国市長会と全国町村会を通じて派遣を進めている。片山善博総務相は、①被災した市町村には同じ県内の市町村や県庁から職員を派遣し、地域のニーズに応じた支援をしやすくする。土木関係や保健婦など中長期的に不足が見込まれる職種も対象とする。それは、地域の実情を知る県内の被災していない自治体が支援することが好ましいからである。② 派遣に伴なって職員が不足する被災地周辺の自治体には全国から職員を派遣する-という「玉突き方式」を検討している。国は、職員派遣を復興が軌道に乗るまで最低3年間の期間とする他、自治体が独自に相互援助する場合にも財源の手当てを行うべきであろう。
自治体だけでなく、企業の中にも売り上げや利益よりも復興を優先する社会的企業も出てきている。地元の銀行は、損失を被るリスクを負っても支援したい、被災の証明がなくても積極的に融資に応えようとしている。企業は自然や社会から遊離したまま、利益を生み続けることはできない。社会問題の解決を政府や非営利法人にまかせず、企業自ら取り組むことで持続的な富とイノベーションが可能となる。企業と自然・社会とが互いに支え合う重要なテーマである。
その点で検証されるべきは、東京電力の「計画停電」である。東日本(50ヘルツ)と西日本(60ヘルツ)で異なる周波数を調整する変換施設が3ケ所しかなく、東西の電力会社間で送電する「電力融通」に上限があったためである。計100万キロワットしか送電できないため、首都圏で不足する1000万キロワットを満たせない。「東西の周波数の変換施設を増設するには数千億円の投資が必要で、「巨額の投資をするなら、各社で発電所を新設するほうが有効」(電力関係者)などとして、後回しにしていたツケが露呈した。この背景には、「戦後、電力会社による地域独占体制によって、他の地域との電力融通がほとんどできない鎖国的な設備が形成されてきたこと」がある。そのためには、「電力会社から送配電事業を分離して、全国を一つにした新しい電力市場をつくること」も必要となるであろう。
以上のように、自社の利益のみ追求し、各社が協力し合うことを考えなかった日本企業の体質が露呈した。これからは、食料と自然エネルギーを中心とした地域的自給のうえに、それぞれの自治体、企業、地域が協力しあい、ともに地域を創造していく多極協力型の国土を構築すべきであろう。そのためには、「人間発達の『知識結』」の取り組みが求められる。この場合の「知識」とは、同じ志を持って一つの事業をおこなう友のことである。「結」とは、田植えや稲刈り、住居の普請、冠婚葬祭など民衆の暮らしにかかわる共同作業のことである。今を遡ること約1400年の天平時代、政変、飢餓、疫病、大地震などのさなかにあって仏僧行基は、「人々がそれぞれの能力・資財・技能を提供し協力して民衆を救済」する「知識結」による「人間復興」とコミュニティづくりを指導した。阪神・淡路大震災での市民ボランティアや今回の自治体間協力と共創の取り組みも、日本の伝統に根ざしつつ、それぞれの持ち味や専門性を生かし被災者と支援者がともに人間として発達していく「人間発達の『知識結』」というべきものなのであろう。
<著者プロフィール>
池田清(いけだ きよし)
北九州市立大学教授、下関市立大学教授を経て、現在、神戸松蔭女子学院大学教授。専攻は都市政策、地方財政論。経済学博士号を京都大学で取得
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2011年05月13日 12:10