上手な「自分(=こだわり)」の捨て方Vol.5/また旅立つ君へVol.137
■「貴方自身」を生きること。それは楽ではなくともハッピーなこと
幸せな人生とは何だろう。よい仕事、立派な夫にできのよい子供、おしゃれな街の一戸建て、人もうらやむ優雅な人生?、、、
それとも、才能がありながら名声は望まず、仕事も家族も二の次で、田舎に移り住んでひたすら画を書く生き方?、、、
言えることはただ一つ、それでその人が幸せなら、それが「その人自身」なのだ。
幸福は、どけだけ楽をできるか、では計れない。無難に世間を渡っていくために、しっかり被せた「自分」の鎧ではなく、「その人自身」がハッピーかどうか。モノサシは、それだけなのだ。
もっと「本当の貴方」を信じてみよう。人が羨むから幸せなのではなく、心から「ああいい気持ち」と言えるのが幸せなのだ。傍から見れば絵に描いたような幸福なのに、本人がちっともいい気持ちになっていないのであれば、その人には無理をして傷つき、抑え過ぎて病んだ本体が隠れている。
あれは楽、これは苦、という「自分」の判断ではなく、貴方自身の声に、もっと耳を傾けて、何が本当にやりたいか、それだけが貴方を本当に幸せな人生に導いてくれるのだから。
私たちは生まれてきた。その理由はわからない。だが目的はわかっている。幸せに生きるためだ。楽に生きるためではない。
作りものの「自分」で用心深く生きるのはもうやめよう。自らの足で立って、私本体を丸ごと受け容れ、信じて生きてみよう。生きている、という手応えのあるハッピーな毎日が、その時から本当に始まるのだ。。。
Posted by nob : 2018年02月20日 15:23
上手な「自分(=こだわり)」の捨て方Vol.4/また旅立つ君へVol.136
■本当の貴方を生き始めるには、まずはその声を聞くことから
さあ、決心がついたとしよう。では、いったいどうすれば「自分」を捨てることができるのか。
まず一つ覚悟をしなければならない。覚悟というと大げさだが、難しいことではない。自らがすべてを引き受ける、と心に決めるのだ。
人間関係がうまくいかないなら、相手を責める前に、貴方の中を見る。今の仕事に不満があるのに、動こうとしないのは、他人のせい、社会のせいではなく、私のせいだと認める。
具体的にはこんなふうだ。入社以来5年も続けた経理の仕事にうんざり、としよう。「いい子の自分」は、そんな貴方を責める。「うんざりなんてぜいたく。今どき、ほかの仕事があると思うの?お給料がもらえるだけで、ありがたいことなんだから」
だが、「本当の貴方」はこう言うはずだ。「だってこういう仕事、好きじゃないんだもの」
その、好き、あるいは嫌い、気持ちがいい、悪いという、いわば原始的な貴方の感覚に、ここはひとつ従ってみることが肝心だ。
もちろんそれで“しまった”と思う結果になることもあるだろう。だが、これだけは言える。貴方は本来の内なる声を信じて自ら行動し、その結末を引き受けたのだ。その充実感、爽快感は、貴方に生きている実感を与えてくれるだろう。そしてそれは、私は悪くないのに、と始終文句をつけていた今までの「自分」では決して味わえなかった実感のはずた。
Posted by nob : 2018年02月20日 15:04
上手な「自分(=こだわり)」の捨て方Vol.3/また旅立つ君へVol.135
■これからは本当の「私」を見つめ、丸ごと受け容れる勇気がものを言う
確かに、ちらりと頭をのぞかせた私の奥にあるものは、可能性に溢れていて魅力的だった。
しかし、窮屈だったり、うまくいかないこともあったけれど、型にはまった「自分」で生きていく、あの気楽さ、無難な味も捨てがたい、、、貴方はきっと迷うだろう。
「自分」の蓋をおしのけて頭を出した「あれ」は、たぶん本当の私自身なのだ。でも、変幻自在のパワーを秘めている、ということはコントロールが難しい、ということでもある。それに、“こういう「自分」”の枠にはめられていないぶん、嫌なところも、醜いものも持っていそうではないか。
そう、残念ながらそのとおり。「自分」が作りものだったとわかって、その下から「貴方本体」を解放しようとしている貴方は、パンドラの箱の前に立っているようなものだ。気まぐれだったり、分裂気味だったり、とんでもなく悪い子だったりする貴方が、そこから飛び出してくるかもしれない。
でも、それが本当の「私」、生まれてからそこまでぶん、成長した正直な姿なのだから。まず真っすぐに見つめてみよう。作りものではない貴方はキレイなだけではない。でもそれが本物なら受け容れて磨くよりほかに道はない。
本当の貴方は、嫌な部分を補って剰りある、可能性やエネルギーが秘められている宝石の原石のはずなのだ。けれど、それでも貴方はまだ「自分」で蓋をして、ぎこちなく演技をして生きていくほうを選ぶだろうか?
Posted by nob : 2018年02月20日 14:43
上手な「自分(=こだわり)」の捨て方Vol.2/また旅立つ君へVol.134
■思い込みの「自分」とは本人の「ご都合」に過ぎない
もし貴方がコンクリートのビルのようなものなら、その行動は、すべて決まったパターンを踏むだけになるだろう。。。
私っていい子。私って頑張り屋。私は気まぐれ人間だから。私は強い女のはず。そういうシナリオにそって生きていると、貴方は周囲の人々に、ある決まったパターンを押し付けているのに気付くはずだ。。。
例えば恋愛。同じような相手と付き合っては失恋の繰り返し。あるいはオフィスで。自己主張をはっきりするデキる女で、上司とトラブルの連続。
頼れて護ってくれる男性が好きな「自分」は、甘えて楽をしたがっているだけなのかもしれない。
自分の考えをはっきり(ずけずけ)言う「自分」は、手間のかかる根回し作業を避けたいだけかもしれない。
「自分」はこういう人間だからという思い込みを言い訳にしているだけで。。。
うまくいかないのなら、一度そのシナリオを捨ててみたらどうだろう。
甘えるには頼りなくても、なんでも対等に話し合える同年齢の男性と付き合う。
上司の提案が的を射ていたら、こっちが大変でも「私もそう思います」と言ってみる。
誰かが貴方のために何かをしてくれたなら、その方法や結果が気に入らないものであっても(それは貴方のやり方を相手に押し付けているということ)、「嬉しい。どうもありがとう」と言ってみる。
そのちょっとした変化が、人間関係を驚くほど変えるはずだ。
そして貴方は、「自分」の下から、何かもっと生き生きとしたものが顔をのぞかせているのに気付くだろう。
その時、しっかりとした「自分」と思っていたものが、色褪せたシナリオに変わる。。。
Posted by nob : 2018年02月20日 14:06
上手な「自分(=こだわり)」の捨て方/また旅立つ君へVol.133
■自分というのはそんなに確固たるものなのだろうか?
「自分」というと、よく添えられる形容詞はなんだろう。
「しっかりした」?「確固たる」?、、、
おまけに「自分」をどうするかといえば、「探す」に、「確立する」に、、、
そんな言葉がすぐに思い浮かぶ。。。
「自分」といえば、まず筋金入りの確固たるもので、人はそれを一生かけて知ろうとする、、、
私たちの頭の中には、そんな図式がしっかりと出来上がってしまっているかのようだ。。。
でもどうだろう。
生理学的に見ると、人の身体の細胞は、どんどん入れ替わっている。
皮膚のような新陳代謝の激しい部分では1ヶ月弱、あの堅固な見本のような骨でさえ、1年もたてば新しい細胞に変わるのだという。
つまり、「自分」を探して何年もうろうろしているうちに、肉体のほうの貴方は、まったくの別物、いや別人になってしまっているわけだ。。。
そんな入れものに、果たして永久不変の「自分」などというものが収まるのだろうか?
答えはNOだ。
本当の貴方=「貴方自身」は、変わることができる。むしろ、変幻自在の可能性こそ、その本質といってもいい。。。
私たちが“変わらない”と見るのは、世の中や周囲と折り合いをつけるためにかぶった仮面のほうだけだ。
その“殻”たる「自分」でうまく生きられなくなったその時にこそ、貴方に変わるチャンスが訪れる。。。
Posted by nob : 2018年02月20日 11:15
結局のところ珈琲は???
■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~
「からだに悪いコーヒー」が「飲むべきくすり」に!
第1回 “コーヒー悪者説”が覆された歴史――東京薬科大学名誉教授 岡 希太郎さんに聞く
柳本操=ライター
みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、体にいいことづくめだった! 以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。第1回目となる今回は、12年間にわたりコーヒーの薬理効果を研究してきた“コーヒーの伝道師”岡 希太郎さんにコーヒー悪玉説が覆った経緯などを伺った。
最新の研究により、「コーヒーは健康にいい」ことが次々と明らかになっている。「コーヒーを飲む習慣があるとがんにかかりにくい」「肝臓にいい」「脂肪燃焼効果がある」など、“コーヒーの健康効果”が相次いで発表されている。
とはいえ、「子どもは飲んじゃダメ」「妊婦には危険」などとよく言われるように、タバコや飲酒などと同様、健康を損ねるというイメージがいまだにある。コーヒーはカラダにいいのか悪いのか――半信半疑の方も多いと思う。
日経グッデイのコーヒー特集では、「コーヒーの健康効果」の最新事情を専門家の方々に聞いた。初回にご登場いただくのは、東京薬科大学名誉教授でコーヒー研究家の岡 希太郎さん。「毎日コーヒーを飲みなさい。」(集英社)、マンガ「珈琲一杯の元気」(医薬経済社)などコーヒーと健康に関する著書を多数手掛けている “コーヒーの伝道師”だ。
◇ ◇ ◇
「コーヒーが健康にいいのは間違いない」
ここ数年、「コーヒーは健康にいい」というニュースを目にする機会が増えました。「がんにかかりにくい」「肝臓にいい」「糖尿病にもいい」「脂肪を燃やす」など効果もさまざまですね。
岡さん 「コーヒーはカラダにいい」という研究成果が毎年のように出てきています。多方面にわたって健康効果が確認され続々と報告されるので、コーヒーの研究をしている私自身が、その多さに参ってしまうくらいです。コーヒーが健康にいいのは間違いないでしょう。私自身は「コーヒーはくすり」だとよく言っています。
最近、一番話題になったのが、昨年5月の東京大学と国立がん研究センターによる発表です。「緑茶やコーヒーを飲む習慣のある人は、心臓病や脳卒中などによる死亡リスクが低下する」という疫学調査です。「コーヒーを1日3~4杯飲むと、心臓病死の危険性が4割減る」と新聞・テレビなどで大きく取り上げられました。私はコーヒーの健康効果について取材を受けることが多いのですが、このときは各メディアから取材依頼が殺到して大変でした。この発表で、「コーヒーはカラダにいい」という認識がより一層定着してきたように感じます。
岡さん コーヒーとお茶は、ともに世界中の人々に飲まれている存在ですが、どちらにも共通するのが、カフェインとポリフェノールという炎症予防作用と抗酸化作用がある物質を両方含んでいることです。カフェインやポリフェノールは、脂肪を燃やす働きがあるなど、さまざまな薬理効果を持っているのですが、両方あると相乗効果が出るのです。「カフェインとポリフェノールの相乗効果」と呼ばれるものです。
コーヒー1杯に含まれるカフェインとポリフェノールは、浅煎りのレギュラーの場合でそれぞれ100mg、200mg程度です。緑茶(煎茶)の場合はそれぞれ半分の50mg、100mg 程度となっています。コーヒーほどではありませんが、お茶も両成分を多く含みますから、健康効果を期待できます。ただ、疫学研究ではコーヒーの研究が圧倒的に多いため、コーヒーの健康効果の方がマスコミなどで多く取り上げられるのです。日本で緑茶の疫学研究が少ないのは残念ですね。
いま注目は「血液サラサラ」効果!
さまざまあるコーヒーの健康効果の中で、今、岡先生が一番注目しているものは何ですか?
岡さん コーヒーの健康効果は、がん予防や2型糖尿病の改善、脂肪燃焼の予防などいろいろあります。それらの中で、私が今、最も注目しているのが「血液サラサラ効果」です。
主なコーヒーの健康効果 がん予防(肝がん、子宮体がん)
2型糖尿病の予防
気分しゃっきり、覚醒効果
血液サラサラ効果
脂肪燃焼の促進
運動時のパフォーマンスを上げる
コーヒー特集ではこれらの効果のうち代表的なものを順次取り上げていきます。次回は、誰もが気になる「がん」との関係を取り上げます
血液サラサラですか? コーヒーには、タマネギや納豆のような効果があるのでしょうか。
岡さん コーヒーにも、血液サラサラ成分が入っています。コーヒーにはポリフェノールの一種であるクロロゲン酸が多く含まれています。クロロゲン酸は、コーヒーの健康成分として一番知られている存在です。クロロゲン酸は、体に入ると肝臓で代謝されて半分以上がフェルラ酸という成分に変わります。これが血管内で血小板が固まるのを防ぎ、血液をサラサラにするのです。
脂っこい食事を取ると血液はドロドロになり、血小板が活性化して血が固まりやすくなります。これによって血栓ができて血管を塞ぐと、脳梗塞や心筋梗塞などの突然死につながる病気となるわけです。ところが、食事といっしょにコーヒーを飲んでおけば、フェルラ酸が血液をサラサラにしてくれます。
コーヒーの香り成分も血管の若返りに貢献します。コーヒーのなんともいえない馥郁(ふくいく)たる香りは、鼻腔から脳に到達し、リラックス回路を活性化します。このコーヒーの香り成分は空気中に漂う分の何百倍もの量がコーヒーの液体中に溶け込んでいます。コーヒーの香りの中心的存在であるピラジン酸は、血小板が固まるのを強く抑制することがわかっています。
「人は血管とともに老いる」といわれます。「しなやかで丈夫」な血管をキープしたいなら、毎日コーヒーを飲んでおくといいわけです。
昔は発がん性があると考えられていた
「コーヒーが健康にいい」という認識が定着したのは比較的最近のことのように思います。個人的な印象ですが、20~30年くらい前は、カラダに悪いという印象が強かったように思います。いつごろから変わったのでしょう。
岡さん 「コーヒーが健康にいい」と言われるようになったのは、ここ10年ぐらいのことです。それまでは、医師の間でも「健康のためにコーヒーは控えたほうがいい」という意見が多くありました。
コーヒーは、昔は「がんを促進する食品」と思われていたんです。コーヒーは見た目も黒いですし、カラダにいいイメージは持ちにくかったのでしょう。
岡さん 日本の病理学者、山極勝三郎博士は、1915年に世界で初めて人工的にがんを作り出すことに成功したのですが、彼は、煙突掃除夫に皮膚がんの罹患者が多いことに着目して、すすの成分であるコールタールをウサギの耳にひたすら塗り続ける実験を行いました。ほかの研究者が半年、1 年であきらめる中、彼は3年間コールタールを塗り続け、世界で初めて人工的にがんを発生させることに成功しました。コールタールが発がん性物質だということを明らかにしたわけです。
コーヒーは真っ黒だし、焙煎して焦がすから、何となくコールタールに似ていますよね。コーヒーは発がん物質に違いない、という考えが世の中に広まって行ったのです。
調べ始めたら、実は「カラダによかった!」
岡さん コーヒーは欧米を中心に多くの人に飲まれていましたから、当然、コーヒーのカラダに対する影響を調べる研究も盛んに行われました。そして実際に研究を進めたところ、出た結果は逆だったのです。つまり、コーヒーはがんだけでなく、生活習慣病を防ぐし、パーキンソン病などの神経疾患も予防するようだ、といったポジティブな研究成果がどんどん発表され始めたのです。
私が研究テーマをコーヒーに絞ることに決めたのは2004年のことです。当時、コーヒーが健康にいいという研究が世の中に出始めていて、そこに関心を持ったわけです。
2002年には、オランダのヴァン・ダム教授らが「コーヒーを1日7杯飲む人は、1日2杯以下の人に比べて2型糖尿病の発症リスクが50%下がる」という報告を出しました。同教授の追跡調査によって、「コーヒーを1日6杯まで飲んだ人でも、がんや心血管疾患などあらゆる原因による死亡リスクには関係しない」という結果が出ています。
2005年には、日本の国立がん研究センターから「コーヒーをよく飲んでいる人は肝臓がんの発症率が低い。1日5杯以上飲む人は肝臓がん発生率が4分の1になる」という発表も出ました(次回で詳しく紹介します)。
「コーヒー悪者説」は、このように続々と明らかになる研究成果によりひっくり返されることになるのです。今では、医者の間でもコーヒーの健康効果は広く認知されるようになりました。例えば、肝臓関係の医師なら、コーヒーは肝臓にいい効果を及ぼすから、1日1~2杯程度を飲むことを勧めるという人が増えました。
津軽藩士の命を救ったコーヒー
コーヒーはカラダに悪いという前提で研究が始まったのに、出てきた結果は逆だったのですね。科学の進歩で従来の常識が逆転することはありますが、コーヒーはその典型ですね。
岡さん もっと以前は、コーヒーは「くすり」として扱われてきたのですよ。コーヒーが9世紀から10世紀ごろ アフリカ・エチオピアからアラビア半島にわたってきたとき、イスラム教の僧院ではコーヒーを秘薬として珍重したのです。コーヒーを飲めば徹夜の修業にも耐えられるためです。
日本にコーヒーが入ってきたのは江戸時代のことですが、コーヒーはビタミン不足による壊血病に効くという記録が日本にも残っています。
江戸時代末期の文化2年(1805年)。帝政ロシアは植民地を開発しようと、当時鎖国していた日本の蝦夷地(北海道)周辺にまでロシア船を出没させていて、これに対抗するため、江戸幕府は本州最北端の津軽藩士に宗谷岬の北方警備を命じました。ところが、苛酷な自然環境により一冬で100人中72人の越冬死者が出ました。ビタミン不足による壊血病が原因です。
それから50年後の安政2年(1855年)には幕府は蘭学者の指導のもと、コーヒー豆を藩士に配給しました。その結果、一人の死者も出なかったのです。当時の記述には『和蘭コーヒー豆、寒気をふせぎ湿邪を払う。黒くなるまでよく煎り、細かくたらりとなるまでつき砕き二さじ程を麻の袋に入れ、熱い湯で番茶のような色にふり出し、土瓶に入れて置き冷めたようならよく温め、砂糖を入れて用いるべし』と記されています。
◇ ◇ ◇
次回 からは、コーヒーと病気予防の関係について、さらに掘り下げていく。明日、1月27日には、コーヒーとがんの最新事情について、国立がん研究センター 社会と健康研究センター予防研究部部長 笹月静博士に話を聞く。コーヒーは特定のがんに対する予防効果があることが、国立がん研究センターの長年にわたる研究から明らかになっている。
[日経Gooday]
Posted by nob : 2018年01月24日 20:46
意識してこそ。。。
■寒い冬の水分補給、それほど気にすることはない?
執筆:藤尾 薫子(保健師・看護師)
医療監修:株式会社とらうべ
夏は発汗も盛んで、喉が渇くという自覚症状がありますし、熱中症対策などの観点からも水分補給の習慣ができていますが、冬はおろそかになりがちです。
実は、人間の身体に必要な水分量というのは一年中変わりません。
ですから、冬こそ水分補給を怠らない意識づけが大切になります。
また、冬ならではの水分補給の必要性もあります。
今回は冬の水分補給について、確認していきましょう。
◆身体に必要な水分
人間の身体の水分が占める割合は、成人男性で体重の約60%、女性は約55%、新生児は約75%、高齢者は約50%といわれています。
そのうちおよそ3分の2が細胞の中に、残りの3分の1が、血液・リンパ・唾液・細胞間質液に配分されます。
「脱水症」とは体内の水分が不足する状態ですが、体重の2%(50㎏で1リットル)の水分が失われると、口やのどの渇き、食欲不振などの不快感に襲われます。
さらに、6%以上失われると「脱水症状」に陥り死に至る危険性もでてきます。
ちなみに、人間は食べ物がなくても水があれば2〜3週間は生きられますが、水分を一切摂取しないとせいぜい4〜5日で死んでしまうといわれています。
◆基本的な水分補給
環境省熱中症環境保護マニュアルによると、体重約70㎏の成人男性の場合、1日の水分の出入りは「2.5リットル」とされていて内訳は次のとおりです。
●入ってくる水
・食事に含まれる水分:1リットル
・たんぱく質、炭水化物、脂肪が体内で燃焼して出る水分:0.5リットル
・飲み水:1リットル
●出ていく水
・呼気:0.5リットル
・皮膚からの蒸発:0.5リットル
・尿や便:1.5リットル
このように、通常は1日に1リットルほどの水分補給をしていれば脱水状態には陥りません。
喉が乾いたときに200mlくらいを1日5回飲めばよい計算となります。
夏場は暑さや運動などにより発汗が促進されますので、その分余計に水分補給をする必要がありますが、身体も自然と水分を欲してくれます。
【参考】
環境省熱中症予防情報サイト『熱中症環境保健マニュアル』
◆冬の脱水
それに対して、冬の場合はどうでしょうか。
いくつか脱水にいたる重要な要因がありますので見てみましょう。
・乾燥による脱水
外気の乾燥、エアコンや暖房の使用による室内の乾燥、住宅の気密性により湿度が低いなど、冬は外的な要因から乾燥しやすくなります。
また、身体の体感温度が低くなり喉の渇きを感じにくい、身体を冷やしたくないために水分を控える…などといった状態になりがちです。
呼気や皮膚からの水分の蒸発は夏場でも感じることはなく、「不感蒸泄(ふかんじょうせつ)」と呼ばれていますが、まさに冬は脱水状態に気がつきにくくなるのです。
・ウィルス感染などによる脱水
風邪やインフルエンザなどの感染症は、脱水症発症の原因となります。
嘔吐や下痢などの症状から大量の体液が体外に排出されたり、高熱による体温調節のため発汗が促進されたりするためです。
・脱水による脳卒中や心筋梗塞のリスク
冬は脳卒中や心筋梗塞が増加します。
これは、寒くなって血圧が上昇することに加え、水分の摂取不足から血液の粘度が高くなり、いわゆる血液ドロドロ状態になることが要因として挙げられています。
・アルコールによる脱水
冬場も飲酒の機会は多いでしょう。
お酒を飲むと喉が渇く、という現象はご存知だと思いますが、アルコールには利尿作用がありお酒を飲むと脱水状態になっていきます。
お酒を水分とみなして「水分補給をしているから大丈夫」、という解釈は誤りです。
最近では、飲酒しながら水分補給をする「和らぎ水」(洋風にいえばチェイサー)が奨励されています。
【参考】
二本酒造組合中央会「『和らぎ水』のすすめ」
◆冬の水分補給
寒い上に汗をかかないため、タイミングがつかみにくい冬場の水分補給。
夏と同じように、通常であれば1日1リットルほどの水を、ちびちび(1回にコップ一杯半ほど)飲みましょう。
ただし、冷たい水は身体を冷やしますから、常温や白湯などがよいでしょう。
また、大量に汗をかきネラル分を失う夏場とは違いますので、スポーツ飲料の常飲はおすすめしません。
さらに、風邪やインフルエンザにかかったときやお酒を飲むときにも、適切な水分補給を忘れずに。
冬は夏以上に意識して、水分補給を心がけてください。
[Mocosuku Woman]
Posted by nob : 2018年01月20日 20:19
睡眠はやはり時間よりも質。。。
■“深い眠り”を導く! 3分間でOKの快眠ストレッチ
深部体温と自律神経の状態を改善、心地良く深い眠りに
伊藤和弘=フリーランスライター
仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削ってしまうのが「睡眠」ではないだろうか。また、年齢とともに、眠りが浅くなったり、目覚めが悪くなったりする人も多いに違いない。もう眠りで悩まないための、ぐっすり睡眠術をお届けしよう。
なかなか寝付けなかったり、就寝できても夜中に目が覚めてしまったり…。睡眠の質の低下に悩む人が増えている。
企業向けに睡眠コンサルタントを行うニューロスペースが、2017年11~12月に、20~50代の男女846人に「睡眠に関するアンケート」を行ったところ、「睡眠に満足していない」と答えた人は実に58.0%と半数以上だった。睡眠に関する悩みは、多い順に「夜中に目が覚める」(中途覚醒)が32.5%、「寝つきが悪い」(入眠困難)が30.1%、「朝の目覚めが悪い」が29.1%、「しっかりと寝たはずなのに体がだるく爽快感がない」が27.8%という結果だった。
また、2016年の国民健康・栄養調査を見ても、19.7%の人が「睡眠で休養が十分にとれていない」と感じている。
睡眠時間を7~8時間確保することはもちろん大事だが、睡眠には量だけでなく、質の問題もある。時間的には十分眠ったはずなのに満足感がない、という経験は多くの人が持っていることだろう。そもそも“ぐっすり眠る”とは、どういう睡眠を指すのだろう?
「結論から言えば、“深睡眠”がよく取れている状態のことです」と明快に答えるのは、RESM(リズム)新横浜 睡眠・呼吸メディカルケアクリニック(横浜市港北区)院長の白濱龍太郎さんだ。
最初の4時間で深睡眠を2回以上
睡眠には、筋肉は休んでいても脳は活動して夢を見ているレム睡眠と、脳も体もともに休んでいるノンレム睡眠がある。ノンレム睡眠は俗に「深い睡眠」と呼ばれるが、深さによってさらに3段階に分かれており、それらの中で最も深い眠りが深睡眠(徐波睡眠)だ。レム睡眠とノンレム睡眠は90分から120分で1セットになっており、深睡眠は眠った直後に現れ、明け方には見られなくなっていく。
「脳内にたまった疲労物質(アミロイドβ)の除去、細胞を修復する成長ホルモンの分泌は、深睡眠のとき最も盛んになります。そのため、この時間が長いほど疲れが取れて睡眠の満足感がある。1000名以上の脳波(終夜睡眠ポリグラフ検査)と眠気(ESS検査)の関係を調べた結果から、ぐっすり眠るためには、眠りについてから4時間以内に深睡眠を2回以上取ることが必要と考えています」(白濱さん)
睡眠時間が少々短い日でも、最初の4時間で深睡眠を2回取れれば「検査データを見ると、脳と体の疲れの8割程度は取れています」と白濱さんは言う。
睡眠の質を確認したければ、目が覚めたとき布団の中で脈を測ってみるといい。ぐっすり眠れたときは、いつもより脈の回数が少なくなっているはずだ。また、電車の座席に座るとたいてい眠ってしまう、昼食後は必ず眠くなる、布団に入るとバタンキューで意識がなくなる、といったことが多い人もきちんと深睡眠が取れていない可能性が高い。
深部体温と自律神経のリズムを整える
では、どうすれば“ぐっすり眠る”(眠ってから4時間以内に深睡眠を2回以上取る)ことができるのだろう? ポイントは「深部体温と自律神経にあります」と白濱さんは続ける。
深部体温とは、内臓など体の内部の体温。これは1日の中でも規則的に変動する。最も低いのが明け方で、目覚める前から上がり始め、起床11時間後に最も高くなる。夜になって深部体温が下がると眠くなる。
「睡眠の質が悪い人は、この深部体温のリズムが乱れていることが多い。夕方になっても体温が上がらない、眠る時間になっても体温が下がらないので眠くならないというわけです」と白濱さんは指摘する。
一方、血圧、呼吸、代謝などを調節する自律神経には、活動状態にあるときに優位に働く交感神経と、休息状態で優位になる副交感神経がある。
健康な人は夜になると副交感神経が優位になって、体がリラックスした状態になる。しかしストレスが強く、遅くまで働いている現代人は、眠る時間になっても交感神経が優位のまま。そのためベッドに入ってもなかなか寝つけず、眠っても良質な深睡眠が得られない。
3分ストレッチで浅い眠りを改善
そこで白濱さんが考案したのが“ぐっすりストレッチ”だ。
夜になったら3種類のストレッチをそれぞれ1分ずつ行うだけ。ぐっすり眠るために必要な深部体温のリズムを整え、副交感神経を優位にする効果があるという。では早速、具体的なやり方を説明しよう。
首もみストレッチ
(1)シャワーを固定し、少し熱めのお湯をうなじに当てる。湯船に首を沈めてもOK。(2)親指以外の指を組む。(3)シャワーは当てたまま。うなじの横のくぼみに親指を当てて、手をゆっくり上下に動かしてマッサージする。強すぎると逆効果なので、あくまで優しく行う。
このストレッチは浴室で1分行うとよい。最初に深部体温を上げておくと、寝るときに下がりやすい。多くの血管が集中しているうなじを温めることで、効率よく血行を改善し、深部体温を上げることができる。マッサージによってさらに血行を良くするとともに、首の筋肉の緊張をほぐし、リラックス効果も得られる。
腕まわしストレッチ
(1)眠る準備を整え、部屋の明かりを消す。(2)腕を曲げ、脇を開いてひじを上にあげる。(3)そのまま後ろに向かって、ひじを大きくゆっくり回す(A)。左右の肩甲骨を寄せるようなイメージで。次に、(4)ひじが体の前に来たら手を組み、前方に腕を伸ばす(B)。(5)そのまま腕を頭の上まで持ち上げ、ぐっと伸ばす。2~3秒間キープしてから手を下ろす。(6)以上の動作を5~6回繰り返す。
このストレッチは寝室で行う。肩甲骨の周辺には褐色脂肪細胞が多く、ここを刺激することで深部体温が効率よく上がる。肩の筋肉の緊張をほぐすことでリラックス効果もある。
足首曲げ深呼吸
(1)布団に入る。(2)3秒ほどかけて鼻からゆっくり息を吸いながら、左右の足首を手前に曲げる(C)。(3)3~5秒ほどかけて口からゆっくり息を吐きながら、ふくらはぎと足首から力を抜く(D)。(2)(3)の動作を5~6回繰り返す。
仕上げのこのストレッチも寝室で行う。手足の末端から熱が放散されることで深部体温が下がる。足の血行を良くすることで熱が放散されやすくなり、スムーズに深部体温が下がる。さらに、ゆっくり息を吐くことで副交感神経が優位になり、リラックスすることができる。
以上、浴室で1分、寝室で2分、計3分間で3種類の“ぐっすりストレッチ”は手軽に行える。「40人の患者さんに2週間続けてもらい、9割以上の人が睡眠改善効果を感じました」と白濱さん。寝る前の習慣にしてしまえば、条件反射でより眠りやすくなっていく。今の睡眠に満足していない人は、早速今夜から実行してほしい。
白濱龍太郎(しらはま りゅうたろう)さん
RESM新横浜 睡眠・呼吸メディカルケアクリニック 院長
[日経Gooday]
Posted by nob : 2018年01月09日 19:20
隠れていても兆候は至るところに、、、自らの心身との対話力こそすべて。。。
■見逃すと過労死の恐れ 「隠れ疲労」蓄積に3つのサイン
長時間労働による「過労死」の問題が相次ぎ、政府は躍起になって働き方改革を推進している。とはいえ、これで労働環境がどこまで改善されるかはわからない。自分自身で過労死から身を守る必要がある。そのためには「隠れ疲労」を見逃してはいけない。「東京疲労・睡眠クリニック」院長の梶本修身氏(大阪市立大学大学院医学講座特任教授)に聞いた。
仕事や運動をした後は、誰もが「疲れた」と感じる。エネルギーを消費したことで体が疲れてしまったと思っている人がほとんどだろうが、これは大きな勘違いだという。
「仕事や運動くらいでは、エネルギーが枯渇して疲労を起こすことはほとんどありません。それでも疲れたと感じるのは、脳の中にある自律神経の中枢に大きな負担がかかったからです。自律神経は、脈拍、呼吸、血圧、体温、睡眠といったあらゆる身体活動をコントロールしています。仕事や運動によってその自律神経が酷使されると、脳は『疲労感』を自覚させようとします。それ以上、体を動かすなどして自律神経に大きな負荷をかけないようにするためです。疲労というものは実は脳の疲労なのです」
脳疲労によって発せられる疲労感は“危険信号”といえる。しかし、疲労感という生体アラームを無視してそれ以上の無理を続けると、最悪の場合、過労死を招く結果になりかねない。
■前頭葉が疲れを隠してしまう
ただ、実際に疲労が蓄積していても、人間は疲労感を覚えないケースがあるという。
「自律神経の中枢が疲弊し、『疲労した』という情報を収集して疲労感として自覚させるのは大脳の前頭葉にある眼窩前頭野という部分です。前頭葉は『意欲や達成感の中枢』と呼ばれていて、人間は他の動物にはみられないほど前頭葉が発達しています。そのため、眼窩前頭野で発した疲労感という生体アラームを意欲や達成感によって隠してしまう。実際は疲労が積み重なっているのに、疲労を感じなくなるのです。これは人体にとって最も危険な状態で、『隠れ疲労』と呼んでいます」
過労死は、前頭葉が発達して疲労感を隠してしまう人間だけにしか起こらないという。過労死を避けるためには、隠れ疲労が蓄積していないかどうかをチェックすることが重要だ。
?飽きる
長時間のデスクワークやパソコン作業で脳を使い続け、「飽きた」という感覚を覚えたことが誰にでもあるだろう。この飽きるという感覚は、脳が疲労し始めている最初のサインだという。
「仕事や勉強などで使い続けている特定の脳の神経細胞を休ませてほしいというシグナルです。『飽きた』というサインを無視して作業を続けていると、特定の神経回路が疲弊して機能が低下し、全身がだるいなどの症状が表れるようになります」
飽きたらすぐに作業は中断して、休息をとることが大切だ。
?寝落ちが増える
飽きるというサインを無視すると、次は「眠くなる」サインが出る。
「電車で席に座った途端、隣の駅に着くまでの間に眠ってしまったり、大事な会議中なのにウトウトしたりするなど、公的な場で無意識に寝落ちしてしまう場合は、隠れ疲労を抱えているケースが多い。疲労が蓄積してピークに近い状態になると、脳は強制的に意識をシャットダウンして休ませようとするのです」
?毎日の習慣が面倒に感じる
脳に疲労がたまると「疲れる」というサインが出る。隠れ疲労の場合は疲労を感じないが、無意識のうちに表面に表れるという。
「たとえば、駅から自宅までといった普段は歩いている1キロ程度の区間なのに、『なんとなく、きょうは歩きたくない』と感じてタクシーに乗ってしまう。普段は楽しめる友達や彼女からお誘いがあっても、『きょうは出向くのが、おっくうだ』と感じて断ってしまう。こうした衝動的な『面倒くさい』という感覚は、隠れ疲労が表面化している可能性が高いといえます」
◇ ◇ ◇
これら隠れ疲労の3大サインが表れたら、無理はせずに休息をとり、しっかり睡眠をとる。蓄積した疲労を回復させるには、ぐっすり眠ることが何よりも効果的だ。
[日刊ゲンダイDIGITAL]
Posted by nob : 2017年12月17日 06:13
すべてはバランスに尽きると、、、正解はあくまで自らの心身との対話を重ねていく先にあります。。。
■炭水化物「毎食7割超え」死亡リスク上昇、脂質の摂取多いと死亡リスク低いと調査結果
記事まとめ
* 11月7日付NIKKEI STYLEで『「炭水化物が毎食7割超え」は注意 死亡リスク上昇』掲載
* 元の論文は、世界18の国と地域の13.5万人以上を対象にした食と死亡リスクの観察調査
* 植物油には健康を害する負の作用があると指摘も、砂糖の有害性の米研究打ち切りも話題
日本人が年間13リットルも飲む「植物油」が体を壊す
先日、興味深い記事が発表されました。それは11月7日付NIKKEI STYLE記事『「炭水化物が毎食7割超え」は注意 死亡リスク上昇』で、8月29日付ランセット誌電子版に掲載された論文を基にした記事です。ちなみに、ランセットは世界五大医学雑誌のひとつです。
元の論文は、世界18の国と地域の13.5万人以上を対象にした食と死亡リスクの観察調査です。低所得国、中所得国、高所得国を網羅し、人数も多く期間(中央値で7.4年)も長いので、今までに例のない調査といえます。
記事では主な調査結果として、次の2点を取り上げています。
(1)炭水化物については、最低群(総エネルギーに占める炭水化物の割合の中央値が46.4%)と比較した最高群(同77.2%)の総死亡のリスクは28%高く、摂取量が多いほど死亡リスクは高い傾向が見られました。
(2)脂質については、炭水化物とは反対に、最低群(総エネルギーに占める脂質割合の中央値が10.6%)に比べ最高群(35.3%)の総死亡リスクは23%低くなっていました。
記事では、この結果を受けて、炭水化物の摂取が非常に多いと死亡リスクが高く、脂質の摂取が多いと死亡リスクが低いことが「意外」と受け止めています。しかし、筆者はこの結果を「意外」とすることにかなりの違和感を覚えます。
●栄養素は単独では働かない
私たちが生きてゆく上で必要な三大栄養素は「たんぱく質、脂質、炭水化物(糖質)」で、どれもエネルギー源ともなります。これにビタミン、ミネラルを含めた五大栄養素の相互作用で生命活動を維持します。その際に重要なのは、栄養の摂取バランスです。調査では、栄養素を単独で扱っているので誤解しがちですが、実際には栄養素は単独では働かないので、摂取バランスで捉えないとあまり意味がありません。
栄養の摂取バランスで捉えると、炭水化物の摂取量が多いというのは、その他の栄養素は必然的に少なくなります。脂質もたんぱく質も少ないと考えられます。炭水化物摂取の最高群(同 77.2%)の死亡リスクが高いのは、栄養バランスが悪い、もしくはかなり偏っているためだと考えられます。
逆に、脂質の摂取量が多い群(35.3%)は、炭水化物が少なくなります。脂質は肉類や卵などに多く含まれます。これらにはたんぱく質も豊富に含まれるので、その摂取量も自動的に増え、摂取される栄養バランスが良くなると考えられます。つまり、死亡リスクの少ない脂質摂取の多い群は、栄養バランスが良いと言い換えられます。
したがって、この調査結果は決して「意外」なものではなく、栄養の摂取バランスが悪い群は死亡リスクが高く、栄養の摂取バランスが良い群は死亡リスクが低いという栄養学の常識と一致した結果にすぎないのです。
●日本人は栄養バランスの変化と寿命の関係を体現した
今回の調査の特徴のひとつは、対象に低所得国、中所得国、高所得国を加えたことです。低所得国と高所得国では摂取する栄養バランスの良し悪しに差があることも、平均寿命が違うことも容易に想像ができます。
低所得国が経済発展し、中所得国、高所得国へと姿を変えると、食糧事情も変化し、栄養バランスも変わり、寿命も延びることは、我々日本人がこの70年の間に体験しています。
米を主食とした日本人の食生活は、世相の安定した江戸中期以降、少ないおかずで大量の米を食べる炭水化物偏重の食生活が戦前まで続き、その間、平均寿命が50歳を超えることはありませんでした。この食生活が急変するのは、第二次世界大戦以後のことです。
前述の調査結果の死亡リスクが高い群と符合するように、炭水化物の摂取割合が78%と高率だった1955年の平均寿命は63歳で、脂質の摂取量が増えるとともに寿命は延び続けます。
平均寿命を延ばす要因は食生活ばかりではありませんが、1955年は高度経済成長の始まりの年であり、経済大国になるにつれ食卓にいろいろな食材が並ぶようになったことは事実です。ちなみに、日本人の平均寿命が50歳を超えたのは1947年で、今からわずか70年前のことです。
●寿命が延びると病気が増える
摂取する栄養バランスがよくなり寿命は世界のトップクラスまで延びましたが、新たな問題として、病気が増えました。特に慢性疾患である高血圧、脂質異常症、糖尿病は「三大生活習慣病」と呼ばれ、罹患者は増加の一途をたどっています。これらの病気は直ちに死に結びつくものではなく、長い時間をかけて合併症とともに重篤な状態に至るのが特徴です。つまり、ある程度の長生きはできるが、不健康な時間も長いというおかしな時代になっています。
生活習慣病の原因として、偏った食生活、運動不足、喫煙、過度の飲酒、過度のストレスなどが挙げられますが、なかでも食生活の占める割合は大きく、最近はがんや認知症なども食生活に原因があるケースが指摘され、生活習慣病の範疇に入れる傾向にあります。
栄養豊富な飽食の時代なのに病気が増えているのは、食生活における栄養の質と食の安全性に関する誤った情報に問題があると考えられます。本連載で一貫して指摘しているように、ヘルシーだと誤認識され多量に消費される植物油はその筆頭です。サラダ油やマヨネーズの主原料である大豆の輸入自由化は1961年で、キャノーラ油の原料である菜種の輸入自由化は1971年です。この時期を境に植物油の大量消費が始まっていますが、生活習慣病が急増する時期と一致します。今では一人当たりの植物油の年間消費量は13リットルにも及んでいます。
●調理油以外にも加工食品には大量の“隠れ油”
糖尿病の原因は炭水化物の過剰摂取にあるといわれますが、上図から読み取れるように炭水化物の摂取量は減り続けており、炭水化物だけでは増える糖尿病の説明がつきません。動物実験の結果から、糖尿病の原因としてキャノーラ油などが指摘されています。これは植物油の消費量の増加と合致します。
厚生労働省が推奨する「食事バランスガイド」などでは、動物性の脂肪を控え、植物性の脂肪に置き換えることを推奨していますが、こうした一見“常識”とも思える指導が生活習慣病を助長する原因にもなります。植物油には健康を害する隠された負の作用があるからです。
先日も、砂糖の取りすぎの有害性について指摘しようとした研究を、米国の砂糖業界が50年前に打ち切っていたという事実が報道されたばかりです。
食材に含まれる成分には、判明している栄養素以外に解明されていない未知の成分があり、人体への影響も解明されていません。栄養の摂取と死亡リスクの関係が解明され、それが公正に発表され、正しく活用されることを望みます。
(文=林裕之/植物油研究家、林葉子/知食料理研究家)
[ビジネスジャーナル]
Posted by nob : 2017年12月13日 15:00
運動は健康の源。。。
■運動はがんの進行を抑えるってホント?
「運動とがん」
がんは長年、日本人の死因第1位の座を独占し続けています。多くの人にとって最も怖い病気でしょう。
では、がんだと宣告されたら、私たちはどうしたらいいのでしょうか。もちろん、医師と相談しながら、積極的に治療に取り組むことになりますが、自分でできることもあります。そのひとつが「運動」です。
がんといえば重病です。運動なんかしていいの? と思われるかもしれません。確かに症状や進行度にもよりますが、「運動できる人はした方がいい」というのが最近の定説になっています。
報告されているエビデンス(科学的根拠)をいくつか紹介しましょう。1つは、大腸がんと診断され、転移のない男性668人を20年間観察した研究です。20年間で258人が死亡し、うち88人は大腸がんが原因でした。「1週間の運動量」を見ると、運動量が多いほど死亡率が低く、最も運動量が多かったグループは、まったく運動しなかった人たちに比べて大腸がんによる死亡リスクが47%も下がっていたそうです(*1)
前立腺がん患者を追跡調査した米国ハーバード大学の研究でも、「週3時間以上のウォーキング」をしている人たちのがん再発・転移、死亡のリスクは57%下がっていたそうです(*2)。
*1 Arch Intern Med. 2009 Dec 14;169(22):2102-8.
*2 Cancer Res.2011 Jun 1;71(11):3889-95.
ドクターランナー(事故にそなえて選手と一緒に走る医師)として多くの市民マラソン大会やトライアスロン大会に出場している、よこすか女性泌尿器科・泌尿器科クリニック(神奈川県横須賀市)院長の奥井識仁さんは、「運動によって大腸がんや前立腺がんの進行は抑えられます。実際、米国にはランニングやウォーキングでがんを抑えようという患者のサークルがいくつもあります」と話します。
奥井さん自身も、長いこと前立腺がんと運動の研究を続けています。前立腺がんと診断された患者102人(平均74.8歳)に、ホルモン治療と併行してウォーキングを指導しました。8年間で48人が死亡、うち20人(41.7%)は前立腺がんが原因でしたが、「1カ月に120km以上のウォーキング」をしている人たちは、死亡率が半分に抑えられたそうです。
ウォーキングは前立腺がん患者の死亡リスクを抑える
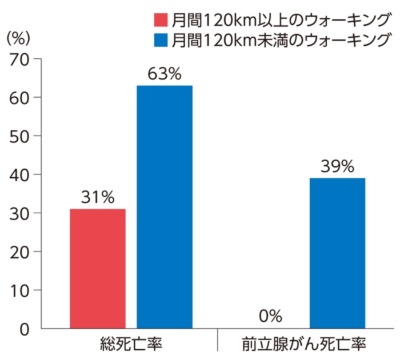
平均74.8歳の前立腺がん患者に、治療と併行してウォーキングを指導した。1カ月120km以上のウォーキングを実行した人たちは死亡リスクが半減。前立腺がんによる死亡はゼロだった。(データ提供:奧井院長)
「雨の日も風の日もやる必要はありません。1日6km、月20日を目安に指導しています」(奥井さん)
筋肉の成長に男性ホルモンが使われる?
では、なぜ運動によって前立腺がんの進行が抑えられるのでしょうか? 奥井さんはテストステロン(主要な男性ホルモン)が筋肉で消費されるからではないか、と考えています。
前立腺がんはテストステロンをエサにして増殖する性質を持ちます。そのため、治療はテストステロンの分泌を抑えることが基本になります。運動によってテストステロンが筋肉で使われると、前立腺がんのエサになる量が減るのではないか、というのが奥井さんの仮説です。「大腸がんの場合も同じく、運動でIGF(インスリン様成長因子)が筋肉で使われることが、がんの進行を抑える大きな要因になっているように思います」(奥井さん)。
これらはまだ解決しないといけない問題が多くあります。運動とがん抑制の関係については、いまだにメカニズムがほとんど分かっていないためです。「もっと多くのサンプルを集めて、日本全体で考えていくべきテーマだと思います。米国のように、がん生存者が積極的に治療データを後世の研究のために残して、日本のがん治療に役立てるシステムが必要です」と奥井さんは話します。
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年11月28日 12:03
目指せPPK!
■「ピンピンコロリ」を実現する5つの習慣
長寿国・日本の現実は「寝たきり大国」だ。ほかの国に比べて「ピンピンコロリ」は少なく、「ネンネンコロリ」が際立って多い。なぜなのか。そして、「ピンピンコロリ」を実現するための5つの習慣とは――。
日本は世界でも指折りの長寿国として知られています。しかし、その実態は、最期まで元気に活動して天寿をまっとうするピンピンコロリ(PPK)は少なく、男性は平均9年、女性は同12年も介護された末に死んでいくという、ネンネンコロリ(NNK)が他国に比べて際立って多い「不健康長寿国」なのです。
■病院は決して安全な場所ではない
なぜでしょうか。最大の理由は、病院などの病床数の多さにあります。日本では人口当たりの病床数がアメリカの4倍以上あり、患者の入院期間も3倍近く長いのです。
病床数が多ければ、いざというときすぐに入院できるので安心だと日本人は考えがちですが、後期高齢者の場合、病院のベッドで点滴の針を刺したままトイレにも行かず過ごしたら、間違いなく寝たきりになるでしょう。ベッドがたくさんあってすぐに入院できる一見理想的な環境が、逆に寝たきりの高齢者を増やしている。これが日本の現実です。
また、これも多くの人は誤解していると思いますが、病院は決して安全な場所ではありません。病院に近づけば医療事故や薬害などの危険にさらされます。
たとえば肝臓がん。酒の飲みすぎが原因だと思われがちですが、男性の肝臓がんによる死亡率を見ると、新潟、岩手、秋田など酒どころといわれる県では低く、比率の高い福岡や大阪の3分の1程度でしかありません。実は、肝臓がんは飲酒ではなく、医療事故によるC型肝炎ウイルスの感染が最大の発症要因なのです。
医療事故がどれくらい起こっているか知ったらびっくりすると思います。EUの公式資料によれば、病院の医療事故で死亡した人数は年間約15万人。そのため、EU域内に住む人の約53%が、病院は危険なところだと認識しています。
わが国の実態は公表されていませんが、数十万人規模での医療事故や薬害が起こっていると思われます。
■歯科医にはこまめにかかったほうがいい
では、どうすればNNKを避け、PPKを実現できるのでしょうか。それはなんといっても医師に頼りすぎず、自分の健康は自分で保つのだという気概が持てるような支援環境を公的に整備することです。そのうえで各種の情報を調べ、納得のいく治療を受けるようにしましょう。
一方で、歯医者さんにはこまめにかかったほうがいいようです。私たちの調査では、「かかりつけの歯科医師がいる」と答えた人が長生きでした。どんなメカニズムが働いているのか明確なところはわかりませんが、私は次のような仮説を立てて追跡調査をしています。
まず、歯科医の支援を受けることで望ましい口腔ケアの知識が得られ、高齢になっても歯と口の健康を保つことができる。食は生きることの基本ですから、歯や口が健康であることには大きな意味があります。また、定期的なケアを受けるため、歯医者さんへ「お出かけ」していることも健康長寿には望ましいのです。
■「ピンピンコロリ」を実現する5つの習慣
生活習慣という切り口から見ると、次の5つの習慣を身に付けることがPPKには大事だということがわかってきました。
1、運動。毎日やらなくても週に1回運動していれば、生存率がかなり高くなることが証明されています。
2、質のいい睡眠。
3、朝食。食べないと脳や身体機能が活性化しません。その際、納豆、ヨーグルトなどの発酵食品を食べ腸内細菌を増やして体温を高めると免疫力が高まり、がんになりにくくなります。
4、禁煙。発がん物質を含むたばこは百害あって一利なし、確実に寿命を縮めます。
5、適度な飲酒。私たち研究チームが高齢者1.3万人を対象に3年間追跡調査したところ、男性では毎日飲酒する群、女性では週に1、2回飲酒する群の死亡率が最も低く、逆に死亡率が高かったのは男女とも「ほとんど飲まない」と回答した人たちでした。
■「地域活動にも積極的」がPPKの必須条件
日本では多くの人が誤解しているのがコレステロール値の評価です。高コレステロール群と低コレステロール群では、明らかに前者のほうが長生きです。コレステロールはビタミンDや細胞膜、がん免疫細胞の材料であり、体の中で重要な役割を担っています。その一方、コレステロールを下げる薬の服用により死亡率が高まることが証明されています。
環境や住居も健康長寿に大きな影響を与えます。都市部よりも長野県のような地方で平均寿命が長いのは、水や空気がきれいだというのも理由のひとつ。夏になるとホタルが乱舞するなど、多様な生物が生きられるところでは、人間も長生き。考えてみたら当たり前のことなのです。
日本では毎年約1万7000人がヒートショックで亡くなっていますが、風呂場が寒すぎるなど家の中の温度較差が原因です。これは住宅の断熱・気密性能を向上させる無垢材の活用で改善します。また、クロス張りの壁を珪藻土や土壁に変えればホルムアルデヒドなどの害がなくなり、湿度調整もうまくいくため睡眠の質が高まります。こうした住環境の良質化もPPKのためにはぜひ取り組みたいポイントです。
そして、忘れてはならないのが心の健康。年をとっても生きがいを持ち、地域や趣味の活動にも積極的に参加しているというのはPPKの人の特徴であり、必須条件だともいえます。65歳を過ぎても生きがいを持って働くというのも、要介護にならないための賢明な選択だといっていいでしょう。
----------
▼これがピンピンコロリの条件だ!
・かかりつけの歯科医師を持つ
・口腔をケアし良好な状態を保つ
・やや太めの体形である
・総コレステロール値が高い
・お出かけが好き
・断熱に優れ土壁を使った健康住宅に住む
首都大学東京名誉教授
放送大学客員教授
星 旦二
[PRESIDENT online]
Posted by nob : 2017年11月23日 15:30
確かに、、、私の心身は共感しています。。。
■「睡眠は90分サイクル」は誤り、眠りの科学は俗説だらけ
『最新の睡眠科学が証明する 必ず眠れるとっておきの秘訣!』
「90分の倍数の睡眠時間をとれば、目覚めがよい」「22時から深夜2時までが睡眠のゴールデンタイム」「7時間睡眠が寿命を延ばす」。知ってる、知ってる、とうなずく人が大半なのかもしれない。が、実はこれらすべて間違い、もしくは不正確な「睡眠神話」なのだそうだ。本書『最新の睡眠科学が証明する 必ず眠れるとっておきの秘訣!』では、「睡眠神話」はじめ、睡眠にかかわる俗説が次々に論破されていく。その過程を読み進めると、私たちはなんとたくさんの根拠のない話に縛られてしまっていることか、と驚くことになるだろう。
著者は、脳内物質の研究をしていたが、発見した物質がたまたま覚醒にかかわっている物質だったため、睡眠研究の道に入ったという(ちなみに、要約本文でも紹介している、覚醒を維持する「オレキシン」という物質が、著者が発見したものだ)。以後、睡眠について、学問的に研究を積み重ねてきた。著者の提案する、必ず眠れる睡眠法は、「眠りへのこだわりを捨てる」ことを基本に据えた、ごくシンプルな方法だ。けれどそれこそまっとうな方法なのだろう、と自然に納得させられる説得力が、本書にはある。
また、本書は、病としての不眠の解説や、睡眠薬の種類や使い方にまで言及している。眠りについて真剣に悩んでいる方には、まず本書をおすすめしたい。人間の健康は、よく食べて、よく活動して、よく寝ることで成り立っている。その要素のひとつである「眠り」について、誠実に、真摯に語られた1冊である。(熊倉 沙希子)
本書の要点
(1)睡眠システムと覚醒システムは互いに抑制しあっており、優勢なほうに切り替わるようになっている。この切り替えに影響するのが、体内時計と、睡眠負債という概念である。加えて、覚醒を促す要素としてストレスや情動がある。
(2) 眠りを意識しすぎると、その情動によって覚醒が促されてしまうので、眠りにこだわりすぎないことが安眠へつながる。
(3) 寝ないといけないと意気込まず、寝室で15分眠れなかったら居間にいったん戻り、眠気を感じたら寝室に行く、というふうにするとよい。
要約本文
◆巷にあふれる睡眠神話
◇「睡眠は90分周期」ではない
睡眠にまつわる話の中には、根拠が乏しいのに多くの人が信じている、「睡眠神話」と呼ぶべきようなものがある。
そのうちのひとつが、「睡眠のサイクルは90分周期である」というものである。睡眠の状態として、「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」があることはよく知られている。眠っているときには、この2種類の状態が規則正しく交互に繰り返されるのだ。繰り返しの1単位が「ノンレム睡眠+レム睡眠」であり、それが90分だというのが、「90分周期」という俗説の根拠となっている。
しかし、じつは、「ノンレム睡眠+レム睡眠」にかかる時間には個人差があり、また日によっても変わってくる。1時間以内のこともあれば120分のこともあるのだ。
加えて、ノンレム睡眠とレム睡眠が、それぞれ深い眠りと浅い眠りだという言い方も間違っている。それぞれの状態は、質的に全く異なるものなのだ。ノンレム睡眠のあいだは脳の活動が低下しており、そのため筋肉の活動も低下している。自律神経は副交感神経が優位になっているので、心拍数や血圧や、呼吸数も下がっている。一方で、レム睡眠のあいだ、脳は覚醒しているとき以上に強く活動している。自律神経も激しく変動しているが、体が暴走しないように神経系や感覚系は完全に遮断されている。そのため、こちらは金縛りのように体に力が入らない状態となっている。
◇睡眠に「ゴールデンタイム」はない
よく「22時から深夜2時までが睡眠のゴールデンタイム」であり、そのあいだに「成長ホルモンが活発に分泌される」から、ゴールデンタイムにきちんと眠ろうと言われる。こちらも根拠がない睡眠神話である。
成長ホルモンが睡眠中に分泌されるのは確かだが、それは特定の時間に起こることではなく、就寝後最初にあらわれるノンレム睡眠のときに起こる。睡眠中、「ノンレム睡眠+レム睡眠」の組み合わせは4~5回繰り返されるが、そのうちで一番深いノンレム睡眠があらわれるのが、就寝後最初のサイクルなのだ。そのときに成長ホルモンが分泌されるので、「何時に寝るか」はじつはあまり関係がない。要は深いノンレム睡眠に入れるかどうかなのである。大切なのは寝る時間帯ではないのだ。
◆睡眠をつくりだす脳、覚醒をつくりだす脳
◇なぜ夜眠くなって、朝起きるのか?
私たちは、朝起きて、夜眠くなる。このことには、2つの要素がかかわっているという。
ひとつは、「概日時計」、つまり体内時計である。24時間ぴったりの周期ではないが、おおむね1日周期で、昼夜で覚醒の出力を調整するリズムを刻んでいる。もうひとつは「睡眠負債」である。これは一種の考え方で、起きている時間が続くにつれて脳内になにかが溜まっていって、睡眠をとるとそれが解消されるという概念だ。睡眠物質の存在について研究が進められているが、今のところその正体については明らかになっておらず、物質が存在するにしてもひとつの物質では説明できないということがわかってきている。
◇脳内のシステム
「概日時計」と「睡眠負債」が睡眠と覚醒に影響を与えているとして、そのとき脳ではどのようなシステムが働いているのだろう。
睡眠にかかわるのが「視床下部」という領域だ。視床下部は4グラム程度しかない、ごく小さい領域だが、自律神経系の中枢であり、様々なホルモンの分泌をコントロールしている。視床下部の前のほうにある「視索前野」では、睡眠中に、神経細胞から「GABA」という抑制系の神経伝達物質をつくっている。その物質が覚醒にかかわる領域を抑制するため、睡眠という状態がつくりだされるのである。
一方、覚醒にかかわる領域が、視床下部と隣り合う「脳幹」である。脳幹は、呼吸や血液循環などを統制する中枢であり、生命維持を司る。この中の、「脳幹網様体」という部分には神経細胞が集合しており、ここから脳全体へさまざまな命令が出されている。そのなかで、「モノアミン」や「アセチルコリン」といった神経伝達物質を介した命令は、覚醒状態をつくりだしながら、睡眠にかかわる領域を抑制している。
睡眠システムと覚醒システムは、お互いに抑制しあっており、どちらかが優勢になるとスイッチがパチンと切り替わるという関係だ。そして、覚醒を適切に維持するための脳内物質が、オレキシンという物質である。
◇時間帯や状態によって眠れないときがある
体内時計の時刻に合わせて、体は体温や血圧、ホルモン濃度などを調整している。前述のオレキシンも、体内時計の情報を受け、朝に活発になる。
ただ、この体内時計をもとにした、覚醒のための体の出力は、単純に昼にピークがあって夜に下がるというものではない。午後2~3時ごろは一時的に出力が下がり、毎日の就寝時間の前にはぐんと上がり、寝る直前から急に下がる。
意外なことだが、就寝数時間前は眠くならない時間帯なのだ。これは、おそらく、就寝時間に向けてどんどん増えている睡眠負債を抑えるために、覚醒のための出力が上がるのだと考えられている。
しかし、こうした時間帯に関係なく、授業中に眠くなったり、夜中に見たい番組があれば起きることができたりする。これは、モチベーションや気持ちの高ぶり、ストレスによる興奮などが、脳幹の覚醒にかかわる機能や、オレキシンをつくる神経細胞に影響するからである。また、満腹と空腹の場合の血糖値の違いは、オレキシンの生成に影響するため、栄養状態も覚醒に大きくかかわるといえる。このように、睡眠と覚醒には、体内時計と睡眠負債に加え、モチベーション・情動・ストレス・栄養状態も関係しているのだ。
【必読ポイント!】
◆よりよい睡眠をとるためのTips
◇眠りにこだわりを持たない
よりよい睡眠をとるためのコツを考える前に、不眠のしくみについて著者はページを割いている。
何か気になることがあって眠れない、というのは自然なことだ。というのは、前述したとおり、感情の高ぶりやストレスが、脳に作用して覚醒状態をつくるからである。この場合、眠れるようになるには、ストレスや不安のもとになっているものを解決するしかない。
「夜に眠れなくて日中に障害がある」ということが週3回以上、3ヵ月以上続くと、臨床上不眠と診断される。眠れない原因が解消されているのに、不眠が続いてしまうのは、「眠れない」ということ自体に意識が向いてしまうからだ。毎日同じ寝室で「眠れない」苦痛を味わうと、いつの間にか寝室と苦痛な体験が結びつき、無意識に操作されてますます眠れなくなってしまうのである。
以上をふまえると、逆説的に、眠りにこだわりを持たなければ、不眠恐怖をつくらないで済む。睡眠をとらないとうまくいかない、とか、特定の時間に眠らなければ、という思い込みをなるべく排し、眠りに関心を向けすぎないことが安眠への第一歩である。
◇15分眠れなかったら居間に戻る
ほかにも、本書で紹介されているTipsの中から、いくつかを紹介しよう。
不眠に陥るのを避けるためには、寝室で眠れない体験を繰り返さないようにするのが大切だ。だからこそ、眠くてしょうがなくなるまで寝室には行かず、また、寝室で15分眠れなかったら居間に戻ってみるとよい。寝つけないのに寝ようとすると、情動が高まって、体が覚醒状態に向かってしまう。
「寝ないといけない」と意気込まず、眠くなったら寝室に行く、15分眠れなかったら居間に戻る、ということを淡々と繰り返す。すると、眠気は溜まっているはずなので、最終的には必ず眠れる。
ワンルームに住んでいる人は、「寝室」を「寝床」と考えて、同じように15分眠れなかったら寝床を離れるというふうにすればだいじょうぶだ。
◇必要以上に早く寝ようとしない
スムーズに眠りにつくためには、「いつ寝るか」も大切である。体内時計のくだりで述べたように、夕方から夜にかけて、人間には「眠れない時間帯」がある。溜まってくる睡眠負債に対抗するために、覚醒出力が上がる時間帯である。たとえば、夜11時に寝る人ならば、直前の8時から10時くらいにかけては、一日で一番眠れない時間帯だ。これは「睡眠禁止帯」と呼ばれている。
そのため、翌朝早く起きなければいけないという場合に、早めに寝ようとすると寝つけなくなってしまう。睡眠禁止帯にあたってしまうからだ。翌朝早く起きる必要がある時にも、普段どおりの時間に寝て、次の日の睡眠で睡眠不足を解消するのがよい。
また、睡眠禁止帯は、夜に明るい光を浴びると後ろにずれてしまう。体内時計そのものが光によって後ろにずれこむからだ。そうすると、いつも寝る時間が睡眠時間帯に入ってしまって眠れなくなる。睡眠に悩んでいる人は、夕方以降明るい光を浴びるのは避けたほうがよいだろう。
◆眠りのギモン
◇忙しくて寝る時間が取れないときにはどうすれば?
OECDの調査によると、日本人は世界で2番目に睡眠時間が短い国だという。一律何時間眠れば健康ということはなく、一人ひとり最適な睡眠時間があるものだが、それよりも短い睡眠時間でやりくりしている人は多くいることだろう。
短い睡眠時間に慣れるという人もいるが、残念ながら、短時間睡眠が習慣になったとしても脳や体が慣れるということはない。夜間の睡眠時間を一定の時間に制限して反応速度を観察する実験でも、日を追うごとに反応は遅くなるだけで、慣れるという現象は起こらなかったという。
したがって、7時間睡眠が必要な人は、じゅうぶんなパフォーマンスをするには7時間寝るしかない。休日にリズムをくずさないよう「プラス30分以内」に多く寝るか、平日のすき間の時間で短い睡眠をとるしかない。足りない睡眠は別のなにかで代用することはできないのだ。
◇シフトワーカーは不眠になりやすい?
現代人の眠りの特徴のひとつとして、仕事の都合で生活リズムが不規則な人も多いということがある。
体内時計によっていろいろな機能が低下している夜に働くというのは、本来は良くないことだが、シフトワーカーを続けていても普通に生活できているのなら、心配はいらない。日中の活動に支障がないのなら、睡眠は十分にとれているということなのだ。
多くの動物は、まとめて夜眠るのでなく、寝たり起きたりしている。人間も、大昔は今とは違ってまとめて眠るスタイルではなかったかもしれない。
だから、シフトワーカーの人は、多少負担があるとしても生体として適応する能力があるのだといえる。したがって、普通に生活できているとしたら問題はない。ただ、シフトワーカーの人には一方で不眠症やうつ病が多いことも知られており、そうなってしまった場合は働き方を変えることだ。
櫻井武(さくらい・たけし)
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2017年11月10日 16:03
すべては諸刃の剣、良薬も過ぎれば毒薬に、、、そして個人差、何よりまず自らの身体を知ることから。。。Vol.3
■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~
「コーヒーはがんに効果あり」は本当か?
“肝臓がんを抑制する”は「ほぼ確実」――国立がん研究センター 笹月静さんに聞く
柳本操=ライター
みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、体にいいことづくめだった! 以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが続々と明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。第2回となる今回は、わが国の大規模疫学調査によって明らかになってきた「コーヒーとがん」について。日本のがん研究の総本山ともいえる国立がん研究センターに最新事情を伺った。
「健康な状態で長生きしたい」と思いつつも、誰もが「いつかかかるのでは」と心配になるのが「がん」という病気。今や、日本人の2人に1人がかかるといわれる国民病だ。
若いうちは「自分には無縁」と思っていても、40代、50代になり、身近な人や有名人ががんにかかったという話を耳にすれば、「発症を防ぎたい」「予防できる方法があるなら知りたい」と思うようになる。コーヒーががんに効くなら、コーヒーを飲む機会を増やそうと思う人も少なくないはずだ。
前回の記事でも触れたように、以前、コーヒーは「発がん性がある」と思われていた時期がある。しかし最近では、コーヒーは「がんに効果がある」という報道を耳にするようになった。最新の研究ではどう判断されているのか。効果があるとしたら、どの部位のがんなのか――。
先に結論をいうと、肝臓がんと子宮体がんの予防に効果が期待できる。国立がん研究センターによる調査・研究によると、肝臓がんを抑える効果は「ほぼ確実」、子宮体がんを抑える効果は「可能性あり」と判定されている。肝臓がんのような特定のがんについては、コーヒーを日々飲むことで発生リスクを抑えられる可能性があるわけだ。
今回は、「日本人にとってどのような生活習慣ががん予防につながるのか」をテーマに研究を行っている国立がん研究センター 予防研究部部長の笹月静さんに詳しく話を聞いた。
◇ ◇ ◇
日本人の生活習慣とがんの関係を20年以上にわたって調査
そもそもの話になりますが、国立がん研究センターでは、食事などの日々の生活習慣とがんとの関係について、どのように調査、研究しているのでしょうか。
笹月さん 国立がん研究センターでは、がんなどの病気と生活習慣との関連を長期間にわたって研究してきました。ここで用いられているのが「コホート研究」という手法です。国立がん研究センターでは、1990年から国内で開始、現在も追跡調査が続けられ、研究結果が日々蓄積されています。
「コホート」とは、年齢や居住地など一定の条件を満たす特定の集団のことです。現在、岩手県、長野県、東京都、沖縄県、大阪府、高知県など全国の一般住民14万人を対象に研究が行われています。余談ですが、「コホート(cohort)」の語源は古代ローマの歩兵隊で、300~600人ほどの兵隊の群を意味します。
最初に対象者に主に対面でアンケート用紙を配布し、健診に参加する方の場合は血液試料や健診データについても提供していただきます。さらに5年後、10年後、というふうにアンケート調査を行っていきます。その中で、がんにかかる方、糖尿病にかかる方などが出てくるので、それらの病気と生活の関連をみていく研究です。扱う内容は、食事内容はもちろん、喫煙や飲酒、体格、運動、さらに睡眠やストレスといった社会心理学的要因など、多岐にわたります。
お酒が好きな人、喫煙者、熱心に運動をする人などが混在する一般住民の大集団を対象に、まっさらの状態からスタートし、10年、20年と追跡していくわけです。
時間も手間もかかりそうな調査ですね。
笹月さん だからこそ研究結果の信頼性が高まると考えています。
私達の研究グループは、国内で行われている研究を基に、日本人のがんと生活習慣との因果関係の評価を行っています。同様の研究は国際的な研究機関でも行われていますが、欧米人と日本人は体格も違うし、食べているものも違うために、海外の研究が主体の評価基準をそのまま日本人に当てはめて考えるのは難しい面があります。日本人を対象とした研究に限定して、がんとの因果関係を評価し、がんを予防する手立てをお伝えすることが重要と考えています。
国立がん研究センターのコホート研究は、10年、20年という追跡期間を経て、2000年代から続々と結果がまとまってきました。その研究を含めて、科学専門誌などに掲載されたがんの研究結果から、評価の対象になる方法(コホート研究と症例対照研究)で実施された論文をピックアップして、それぞれについて科学的根拠や信頼性なども併せて評価しています。
その評価の結果を、全体および個々の部位について、国立がん研究センターのホームページで公開しています。
コーヒーの「肝臓がんのリスクを下げる」効果は「ほぼ確実」
具体的に、コーヒーとがんの罹患については、どんなことがわかってきたのですか。
笹月さん 現在は、肝臓がん、子宮体がん、大腸がん、子宮頸がん、卵巣がんの評価を掲載しています。それぞれ以下のような評価になっています。
* 「肝臓がん」のリスクを下げる効果=ほぼ確実
* 「子宮体がん」のリスクを下げる効果=可能性あり
* 「大腸がん」「子宮頸がん」「卵巣がん」のリスクを下げる効果=データ不十分
「ほぼ確実」「可能性あり」といった言葉は「科学的根拠としての信頼性の強さ」を示す指標のことです。最も信頼性が高い評価から順に「確実」→ 「ほぼ確実」→「可能性あり」→「データ不十分」となっています。例えば、「喫煙」と「肺がん」との因果関係の評価は、最も信頼性が高い「確実」。つまり、たばこは肺がんのリスクを高めるのは確実というわけです。昨年話題になった「保存肉/赤肉」は、大腸がんのリスクを高くする「可能性あり」になっています。
コーヒーについては、肝臓がんに対する予防効果が「ほぼ確実」になっています。つまり、コーヒーをよく飲む人は肝臓がんにかかりにくいわけですね。
笹月さん 肝臓がんのがん予防効果は、2000年代から「効果あり」というエビデンスが集まり始めました。これ以降、複数のコホート研究によって一致して「コーヒーはがんに予防的に働く」となったために、上から2番目の「ほぼ確実」の評価となっています。
国立がん研究センターのコホート研究では、40~69歳の男女約9万人について、調査開始時のコーヒー摂取頻度により6つのグループに分けて、その後の肝臓がんの発生率を比較しました。調査開始から約10年間の追跡期間中に、肝臓がんにかかったのはそのうち334名(男性250名、女性84名)です。
その結果は、「コーヒーをほとんど飲まない人と比べ、ほぼ毎日飲む人は肝臓がんの発生リスクが約半分に減少する」というものでした。1日の摂取量が増えるほどリスクが低下しました。1日5杯以上飲む人では、肝臓がんの発生率は4分の1にまで低下していました。
これらの結果からも、コーヒーをたくさん飲んでいる人が肝臓がんの発生リスクが低くなるのは、おそらく事実といっていいでしょう。特に「ほとんど毎日」「毎日1~2杯」「毎日3~4杯」「毎日5杯以上」飲む人についてのデータは、統計学的に有意なデータが出ています。「ほとんど毎日」以上の方々は、はっきりリスクが下がっていると言えます。さらに、多く飲んでいる人ほどリスクは下がっているという傾向も出ています。
世界のがん研究をとりまとめる米国がん研究機構による最新の要約を見ても、肝臓がんリスクを下げる飲み物としてコーヒーが浮上しています。肝臓がんの最大のリスク要因である肝炎ウイルス感染の有無で分けても、同様に肝臓がん発生リスクが低くなることがわかっています。
大腸がんに関しては、以前はリスクを下げる「可能性あり」に分類されていましたが、最新の情報では「データ不十分」となっています。
笹月さん 一昨年まとめられたコホート調査によって、がんリスクを上げるという新たな結果が出てきたためです。多くの結果はがんリスクを下げるか、中立的なものなのですが、研究を統合して解析するメタ解析の結果、関連性は見えなくなり、研究班で討議を行い、判定を下げたほうがよいだろうという結論になりました。このように、常に新しい研究結果も追加しながら判定して、その都度情報を更新しています。
子宮体がんについては、2008年の多目的コホート研究の結果から、1日1~2杯、3杯以上飲むグループではそれぞれ、罹患リスクが低下しているという結果や、他の研究結果から「可能性あり」に分類しています。
このように、大腸がんについては「データ不十分」となりましたが、がん予防に効果的な部位も示されています。コーヒーを適度に飲むことは予防的な手段の一つと判断できるでしょう。
「糖尿病予防」効果と「抗酸化作用」の両面から効いている?
数あるがんの中で、なぜ肝臓がん、子宮体がんに対して、効果が期待できるのですか。
笹月さん 私たちは、コーヒーががんに作用するメカニズムの研究を直接しているわけではありませんが、肝臓がんや子宮体がんは糖尿病を発症するとかかりやすくなるがんであることがわかっています。一方で、コーヒーが糖尿病を予防することも、すでに多数報告されています。コーヒーによって糖尿病リスクが下がればがんリスクも下がる、ということは十分に考えられます。
また、コーヒーにはポリフェノールの一種である抗酸化物質のクロロゲン酸が豊富に含まれています。クロロゲン酸には、血糖値を改善するほか、体内の炎症を抑える作用があります。クロロゲン酸を継続摂取することもがんに予防的に働いているのではないかと考えています。あくまで推測ですが、コーヒーは「糖尿病予防」効果と「抗酸化作用」の両面からがんを抑制する働きをしていると考えられます。
コーヒーを飲むと、心臓病のリスクが軽減
話が変わりますが、国立がん研究センターは昨年5月に、「コーヒーを飲むと、心臓病のリスクが軽減する」という研究報告を発表されましたね。ニュースなどで大きく取り上げられました。
笹月さん 緑茶やコーヒーなどについての研究結果に対する関心は一般に高いのですが、予想以上に大きくマスコミに取り上げられたので驚きました。
この調査も、国立がん研究センターのコホート研究に基づいて導き出されたものです。緑茶とコーヒーの摂取と、全死亡リスク、がん、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患などの死亡リスクとの関連を解析しました。
コーヒーについては、「1日3~4杯飲む人は、ほとんど飲まない人に比べ、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患の病気で死亡するリスクがそれぞれ4割程度減少する」といった結果が出ています。全死亡リスクについては、コーヒーを1日3~4杯飲む人の死亡リスクは、24%低いという結果になりました。ただ、今回の取材のテーマであるがん死亡の危険度については、この調査では有意な関連性は見られませんでした。
◇ ◇ ◇
国立がん研究センターでは、数年前に新たなコホート調査を立ち上げた。1990年代当時に比べ国民のコーヒー摂取量は増えていることもあり、今後、新たな知見が報告される可能性は十分にあるだろう。
来週のコーヒー特集では、コーヒーの糖尿病などの生活習慣病への効果について、国立健康・栄養研究所の古野純典所長に話を聞く。コーヒーは糖尿病だけでなく、痛風や肝機能にも効果があるという、ミドル必見の効果が明らかになる。
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年10月02日 15:34
すべては諸刃の剣、良薬も過ぎれば毒薬に、、、そして個人差、何よりまず自らの身体を知ることから。。。Vol.2
■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~
カラダにいいコーヒーの淹れ方とは!?
煎り方によって成分が違う? 飲むベストタイミングは?
柳本操=ライター
みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、カラダにいいことづくめだった!以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが続々と明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。最終回となる今回は、実践的なコーヒーの「淹れ方」「飲み方」を紹介する。“カラダに効く”飲み方のノウハウを習得して、コーヒーのよさを余すことなく引き出そう。
これまで7回にわたってコーヒーの健康効果について紹介してきた。専門家の方々から話を伺い、糖尿病や痛風などの生活習慣病から、肝臓がん、血液サラサラ、シミ予防の可能性まで驚きのコーヒー効果が明らかになった。カフェインの摂り過ぎに気をつけつつ、成人なら1日3~5杯程度を目安に適量のコーヒーを楽しむことはカラダにいい影響を及ぼす。
最終回となる今回は、これまでインタビューでご登場いただいた専門家の方々直伝の、実践的なコーヒーの飲み方を紹介する。同じ1杯のコーヒーでも、コーヒー豆の煎り方によって成分は違ってくる。また、コーヒーをお湯で抽出する際、フィルターを使うかどうかによっても健康への影響は変わってくる。コーヒーの健康効果を引き出すには「淹れ方」がとても大切だ。さらに、「どのタイミング」で飲むかを意識することで、コーヒーパワーを最大限に取り込むことができる。
「浅煎り」と「深煎り」、カラダにいい成分はどう違う?
まず、コーヒーの“煎り方”による成分の変化から見ていこう。ご存じのように、コーヒーは、生豆を焙煎したものを挽いて、お湯で抽出する。この焙煎には、浅煎りのライト、シナモンなどから、深煎りのフレンチ、イタリアンまでさまざまな煎りの度合いがある。一般に、浅煎りは酸味が強く、深煎りになればなるほど苦味が強くなる。エスプレッソなどに使われるのは深煎りだ。
焙煎の度合いにより熱を加える時間が変わるため、コーヒー豆に含まれる成分も変化する。コーヒーの重要成分の一つであるカフェインは熱を受けてもほとんど変化しないが、コーヒーに含まれるポリフェノール「クロロゲン酸」は熱により変化するという。
深煎りにはクロロゲン酸はほとんど含まれていない
その変化について、第1回でご登場いただいた東京薬科大学名誉教授の岡希太郎さんが説明してくれた。
「コーヒーに含まれるポリフェノールであるクロロゲン酸は生豆に多く含まれています。焙煎して熱を加えることによって、その含有量は低くなります。私が行った実験では、焙煎を開始して最初のパチパチというハゼ音が終わった浅煎りの段階で、クロロゲン酸の含有量は半分程度になりました。クロロゲン酸を摂取するなら浅煎りで飲むのがおすすめです。フレンチロースト(深煎りの焙煎)やエスプレッソなどにはほとんどクロロゲン酸は含まれていません」
一方、焙煎することによって増える成分もあるという。
「生豆に含まれるトリゴネリンという成分は、焙煎する熱によって分解され、抗血栓作用を持つニコチン酸や、副交感神経を刺激してリラックス作用をもたらす NMP(N-メチルピリジニウムイオン)といった物質に変化します。特にNMPは焙煎するほどに含有量が増え、シティロースト(第2ハゼ音の始まりで浅めの深煎り)なら1杯あたり10mg程度。数杯飲めば、薬理学的に意味のある量に達します」
このような結果を踏まえ、岡さんは「浅煎りと深煎り、いずれにもいい成分が含まれています。ですから、過度に意識する必要はありません。可能なら1日の中で深煎りと浅煎りの両方を飲むと理想的ですね」と話す。
自宅で飲むときには、両方の煎り方の豆を用意して、組み合わせて飲むのも一つの方法だ。なお、深煎りと浅煎りの成分を同時に摂取できるように、両方をブレンドしたコーヒー豆も販売されている(愛知県豊橋市の会社ワルツが販売している「カラダ想いブレンド<爽><快>」)。
健康を意識するなら「フィルターで抽出」
自宅でコーヒーを楽しむ際に、健康に配慮するならぜひ気を配りたいのが「抽出する方法」について。フィルターを使うかどうかは実は大きなポイントなのだ。ペーパーフィルターやネルなどでドリップしている、という人は大正解だ。
東京薬科大学名誉教授の岡さんは、「コーヒー豆には、ジテルペン類(カウェオール、カフェストール)という精油成分が含まれていて、コレステロール値や中性脂肪値を高くする働きがあります。水やお湯には溶けませんがコーヒーの油分に溶けて液面に浮かびます。抽出する際にフィルターを使っていれば、この油分がフィルターに引っかかって除去されるので心配する必要はありません。抽出液に粉が混ざっていたり、沸騰させて強く煮出したコーヒーを飲むと高脂血症につながる可能性があります」と話す。
そもそも、1980年代前半まで「コーヒーはカラダに悪い」と思われていたのは、当時、北欧で、「コーヒーは心筋梗塞を引き起こしやすい」という報告があったためだ。北欧では挽いたコーヒー豆を鍋で煮出してして抽出する飲み方が行われており、精油成分を摂取していたのが原因だと考えられている。
日本ではコーヒー豆を鍋で煮出してして飲む習慣はないが、最近は、コーヒーの粉を容器に入れ、プランジャーという金属フィルターを押し下げて抽出する「フレンチプレス」という方式で楽しむ人も増えている。「フレンチプレスでは抽出された精油成分が十分に除去されません。蒸気で勢いよく抽出するエスプレッソにも精油成分は含まれるので、飲む頻度は控えめにしたほうがいい」と岡さん。
その点、ペーパーネルでドリップすれば安心してコーヒーを飲むことができる。コーヒーのさまざまな有効成分を余すことなく抽出するには、「蒸らし時間を長くとりながら、ゆっくり抽出するのがコツ」と岡さんはアドバイスする。
「カラダが弱っているときは、いつもより湯量を増やして薄めにして飲む」「苦くして飲みたいときは挽いた粉の量を多めにして湯温を熱めにする」など、自分で好みに調節できるのも、ハンドドリップの醍醐味だ。
飲むタイミングを考慮して、効果を最大に!
次に、コーヒーを飲むタイミングを見ていこう。第5回では運動の1時間前にコーヒーを摂取すると脂肪燃焼効果が高まるという話を紹介した。このように、目的に合ったタイミングでコーヒーを飲むと、その効果をより多く享受できる。我々ビジネスパーソンがコーヒーを飲むタイミングで意識するといいのは、以下の4つのタイミングだ。
* ベストタイミングその1:昼寝と組み合わせる
* ベストタイミングその2:運動と組み合わせる
* ベストタイミングその3:食後に飲む
* ベストタイミングその4:飲酒の後に飲む
昼寝前に飲んで、午後の集中力を高める
それでは順に見ていこう。まずは、「ベストタイミングその1 昼寝との組み合わせ」だ。
「朝食時にコーヒーを飲んでいる人は多いと思います。カフェインの覚醒作用で、寝起きの頭がスッキリします。この覚醒作用を朝だけしか使わないのはもったいないですね。“昼寝の前”に飲むことで、その後の集中力をぐっと高めることができます」とアドバイスするのは、ネスレ日本の福島洋一さん。
広島大学大学院総合科学研究科行動科学講座の林光緒教授らの研究では、10人の大学生が「昼寝なし」「昼寝あり」「昼寝+目覚めた直後に洗顔する」「昼寝+目覚めた直後に明るい光を浴びる」「コーヒーを飲んでから昼寝する」という5つの条件で実験が行われた。その結果、洗顔や光を浴びるなど、いかにも覚醒効果が高そうな方法よりも、「昼寝前にコーヒーを摂取」したときがもっとも昼寝後の眠気が抑えられ、作業ミスも減少することがわかったという。
また、イギリスの研究でも、ドライバーの眠気対策として、「コーヒーを飲んで15分までの昼寝をすると、コーヒーを飲まなかった場合よりも眠気が低減された」という報告がされている(Psychophysiol,33(3),306-9,1996)。
「コーヒーに含まれるカフェインが脳に届くまでには20~30分かかるといわれます。眠気を感じたときにコーヒーを飲んでも、すぐには覚醒効果は表れません。そこで、昼寝前にコーヒーを飲み、すぐさま短時間眠るのです。すると、起きるころにカフェインが効きはじめるので、しゃきっと起きられるのです。このコーヒーの活用法は、 “コーヒーナップ”(ナップとは昼寝の意味)」として世界的な話題になっています」と福島さん。
運動の1時間前に飲んでダイエット効果を高める
次に、押さえておきたいタイミングは「運動前」だ。第5回で紹介したように、コーヒーは、クロロゲン酸とカフェインという2つの脂肪燃焼効果がある成分を含んでいる。運動習慣がある人や、今日は出先でたくさん歩くぞ、というようなときにはぜひ、運動前にコーヒーを1杯飲んでおこう。
「運動する1時間前ぐらいにコーヒーを飲んでおくと、運動することによって脂肪が燃焼し始めるころに、カフェインも血中でピークになり、脂肪燃焼効果を高められます」と、日本ポリフェノール学会の理事長で、品川イーストワンメディカルクリニック理事長の板倉弘重医師は話す。
コーヒーの抗酸化物質であるクロロゲン酸は、肝臓での脂質の代謝を活発にし、脂肪燃焼によるエネルギー消費を増加させる。カフェインも、脂肪細胞にあるリパーゼという酵素を活性化することによって脂肪をエネルギーとして活用しやすくする。
食事と合わせて血液サラサラ
コーヒーを食事と組み合わせるのも有効だ。東京薬科大学名誉教授の岡さんは、「食事と一緒にコーヒー」をおすすめしている。
「コーヒーには血液サラサラ効果があります。クロロゲン酸などのコーヒーポリフェノールは体内に入ると肝臓で代謝され、フェルラ酸という成分などに変わります。これが血管内で血小板が固まるのを阻止し、血液をサラサラにする作用があると考えられています」
飲酒の後もコーヒーを飲むといい。国立健康・栄養研究所所長の古野純典さんがおすすめするのが、「お酒の後はラーメンで〆ずに、コーヒーで〆る」方法だ。
「コーヒーには肝機能を保護する効果があります。その効果は飲酒量が多い人ほど高くなります。そこで、お酒の後はラーメンで〆ずに、カフェイン抜きのデカフェのコーヒーで〆てはどうでしょうか。また、翌朝、コーヒーを飲めばアルコールの代謝で疲れた肝臓を元気づけることができますよ」
飲酒時はカフェインに注意、クスリはコーヒーで飲まない
覚えておきたいのは、飲酒時のカフェインの摂取には注意が必要だということ。ネスレ日本の福島さんは、「アルコールと同時にカフェインを摂取すると、カフェインの覚醒作用により酔っている実感を得にくくなります。つまり、酔っているのにそれが自覚できず、ハイペースでアルコールを摂取しかねないので、飲み過ぎに注意しましょう」とアドバイスしてくれた。
また、薬とコーヒーの同時摂取についても注意が必要なことも覚えておきたい。コーヒーのカフェインは肝臓で代謝されるが、同じく肝臓で代謝される薬の成分の効果を邪魔する可能性があるからだ。またカフェインが入った薬もいろいろとある。コーヒーをたくさん飲んでいる人は、いつも通りコーヒーを飲んでよいか、処方してくれる医師や薬剤師に確認したほうがよいだろう。
◇ ◇ ◇
2016年1月から8回に渡ってお届けしてきたコーヒー特集も、今回でひとまず終了します。1日3~5杯という適量を意識しながら、コーヒーを楽しんでいただければ幸いです。なお、コーヒーの健康効果はまだまだあります。日経グッデイでは今後も引き続きコーヒーを取り上げていきます。ご期待ください!
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年10月02日 15:13
ウィスキーなら糖質はゼロです。。。
■日本酒、ビール、ワイン、糖質が一番低いのはどれ?
クイズで学ぶ「お酒と糖質」
みなさん、「カラダにいいこと、毎日プラス」していますか? このクイズでは今知っておきたい健康や医療のネタをQ&A形式でおさらいします。ぜひ、今日からのセルフケアにお役立てください。では、さっそくクイズを始めましょう。
「お酒と糖質」に関する問題
ダイエットのために、食べ物や飲み物の糖質を気にしている人も多いかと思いますが、では、日本酒、ビール、ワインのうち、最も糖質が低いのはどれでしょうか?
* (1)日本酒
* (2)ビール
* (3)ワイン
正解は、(3)ワイン です。
赤ワインの糖質は“シイタケ”並み
ここ数年は「第7次ワインブーム」と言われ、日本のワインの消費量は過去最大を更新しています。その人気には、「健康にいい」というイメージが定着してきたことも背景にあります。
ワインの健康効果としては、赤ワインに含まれる「ポリフェノール」がよく取り上げられますが、低糖質であることも大きなメリットです。山梨大学ワイン科学研究センター客員教授の佐藤充克さんは、「あまり知られていませんが、ワインは醸造酒の中でも圧倒的に糖質が少ないお酒です。糖質を気にする方はワインを選ぶといいでしょう」といいます。
日本酒、ビール、ワインに含まれる糖質
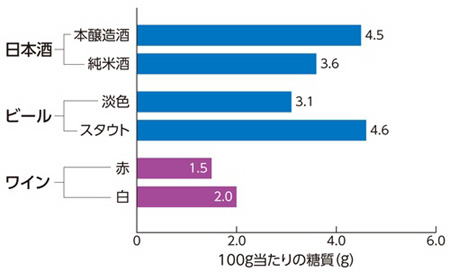
赤ワイン、白ワインの糖質は100g当たりそれぞれ1.5と2.0gと他の醸造酒の60%から3分の1程度と低い。糖質の量は炭水化物の総量から食物繊維を引いて算出した(出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂))
「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」(文部科学省)によれば、赤ワイン、白ワインの糖質は100g当たりそれぞれ1.5と2.0g。これは、日本酒の3.6~4.5g、ビールの3.1~4.6g(いずれも、純米酒と本醸造酒、淡色とスタウトなどタイプによって異なる)の60%から3分の1程度です。ちなみに、100g当たり糖質1.5gというのは、糖質が少ない食品として知られるシイタケ(菌床栽培・生、1.5g)と同等の数値なのです。
糖質の量だけでいえば、焼酎やウイスキーは0(ゼロ)gと断トツに低いですが、トータルのカロリーで比較すると、焼酎は100g当たり 146~206kcal(単式か連続式蒸留かで異なる)、ウイスキーは237kcalなのに対して、ワインは赤白共に73kcalと低く、ワインは全体のバランスがとれたお酒なのだといえます。
適量のワイン摂取が血圧を下げる!?
佐藤さんによると、「適量のワインは血圧を下げる効果が期待できます。イギリスのリバプール・ジョン・ムーアズ大学の研究者が、6000 人を対象に、運動、食事、肥満度と血圧の関係を調べたところ、ワインを多く摂取する人は血圧が統計的に有意に低かったという調査結果が出ました。一方、ビールの場合は血圧は上昇しました」(Annals of Human Biology;24(3):1997,229-247.)。この調査では、ワインを飲む人の中で1日約250ml程度たしなむ人が最も血圧が低いという結果が出たそうだ。
ワインの血圧を下げる効果について、佐藤さんは「ワインにはカリウムが多く含まれています。カリウムには、ナトリウム(塩分)を体から排出する働きがあります」と説明する。
また、ワインの味わいの特徴の一つである酸味の基となっている酒石酸や乳酸などの有機酸は、腸内で悪玉菌の生成を抑え、善玉菌を活性化させる働きがあり、腸内環境を整える効果が期待できるそうです。さらに、ワインに豊富に含まれるポリフェノールも腸内環境を良くするのに一役買っているとか。
低糖質であり、血圧を下げたり腸内環境を整えたりする効果も期待できるとなれば、健康が気になる人にワインが人気なのも納得ですね。
この記事は、「ワインは低糖質だった! ポリフェノールだけじゃない、これだけの効能」(執筆:大塚千春=フリーエディター・ライター)を基に作成しました。
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年09月26日 17:49
すべては諸刃の剣、良薬も過ぎれば毒薬に、、、そして個人差、何よりまず自らの身体を知ることから。。。
■「コーヒーもう一杯」で死亡リスク数%減 欧州調査
コーヒーは世界で最も多く飲まれている飲料の1つで、さまざまな成分を含んでいます。これまでにも、コーヒーの摂取は健康に良い影響を及ぼすという報告は複数ありましたが、それらは主に米国人を対象に行われた研究の結果でした。
そこで、フランスの国際がん研究機関(IARC)のMarc J. Gunter氏らは、コーヒー摂取と死亡の関係が、他の人種や他の地域に住む人々にも見られるのかどうか、そして、コーヒーの摂取が特定の死因による死亡のリスクを減らしたり高めたりするのかどうかを明らかにしようと考え、欧州10カ国の市民を対象に研究を行いました。
■欧州45万人のコーヒー摂取頻度を調査し、16年間追跡
分析対象にしたのは、欧州10カ国(デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、英国)の一般市民で、主に35歳以上の45万1743人(男性13万662人と女性32万1081人)です。
コーヒーの摂取量は食物摂取頻度調査の中で尋ね、ライフスタイル質問票を用いて、学歴、喫煙、飲酒習慣、運動量などに関する情報も収集しました。
当初のコーヒーの摂取量に基づいて、国ごとに対象者を分類しました。まず、全く飲まないグループを参照群として設定し、残りの人々を、摂取量が最も少ない人から最も多い人まで並べて4等分しました。主に比較したのは、参照群と、最もコーヒー摂取量が多かったグループ(1日当たり摂取量の中央値は男性 855mL、女性684mL)です。
コーヒーの摂取量調査から平均16.4年追跡したところ、4万1693人(男性1万8302人、女性 2万3391人)が死亡していました。うち1万8003人ががん、9106人が循環器疾患、2380人が脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)、3536人が虚血性心疾患(心筋梗塞など)、1213人が消化器疾患、1589人が呼吸器疾患で死亡しており、1571人が外傷性の死亡、418人は自殺による死亡でした。
■死亡リスクは男性で12%、女性で7%低下
これらの死亡とコーヒー摂取量との関係を分析したところ、コーヒーを全く飲まない人々に比べ、コーヒーを最も多く飲む人々の、あらゆる原因による死亡(総死亡)のリスクは、男性で12%、女性では7%低下していました(表1)。これらの差は、統計学的に意味のあるレベルでした。また、コーヒーを飲む量が多い人ほど総死亡リスクが低いことも示唆されました。コーヒー1杯を237mLとすると、1日の摂取量が1杯増加するごとに、総死亡リスクは、男性が3%、女性は1%低下していました。
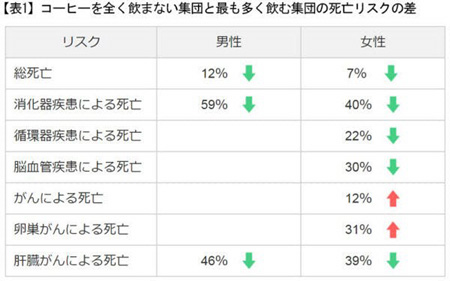
統計学的に意味のある数字になったものを抜粋して記載。下向きの矢印は、コーヒーを多く飲む人においてリスク低下が見られることを意味し、上向きの矢印は、逆にリスク上昇が見られることを意味する
欧州では国ごとに、好まれるコーヒーの抽出方法が違っています。しかし、各国のコーヒー摂取量と死亡との関係に差はなく、抽出方法にかかわらず、より多く飲む人の死亡リスクが低い現象が一貫して認められました。
コーヒーの摂取は、消化器疾患による死亡リスクの低減とも関係していました。1日の摂取量が1杯増加するごとのリスク低下は、男性が23%、女性は14%でした。
消化器疾患による死亡の3分の1強は、肝臓の病気による死亡でした。男女合わせて分析したところ、コーヒーを全く飲まない人と比較して、最も多く飲む人々の肝臓病による死亡リスクは80%も低いことが明らかになりました。一方で、肝臓病以外の消化器疾患による死亡のリスクは、統計学的に意味のある低下を示しませんでした。また、コーヒーを最も多く飲む人では、肝硬変による死亡のリスクも79%低くなっていました。
また、男女ともに、コーヒー摂取量が多い人の肝臓がんによる死亡リスクは、全く飲まない人に比べ40%前後低いことが分かりました。
男女に差が見られた項目もありました。循環器疾患による死亡と脳血管疾患による死亡では、女性においてのみ、コーヒー摂取量が最も多いグループでリスク低下が認められました。一方で、がんによる死亡、および卵巣がんによる死亡は、いずれも女性においてのみ、コーヒー摂取量が最も多いグループでリスクが上昇していました。
以上のような関係は、カフェインを含むコーヒーと含まないコーヒーの摂取量を別々に分析しても同様に認められました。
■コーヒー多飲者で肝臓の病気が少ない理由は?
著者らはさらに、対象者の中から無作為に選んだ1万4800人を対象に、コーヒーの摂取と、血液中の肝機能や炎症、代謝の状態を示す検査値との関係を調べてみました。
すると、コーヒーの摂取量が多い人々では、肝機能の指標である、ALT(アラニンアミノ基転移酵素)、AST(アスパラギン酸アミノ基転移酵素)、γ- GTP(γ-グルタミルトランスフェラーゼ)、ALP(アルカリホスファターゼ)の値が低く、肝機能は良好であることが示されました。
さらに女性では、コーヒー摂取量が多い人で、炎症の指標であるCRP(C反応性蛋白)や、動脈硬化の危険因子であるリポ蛋白(a)、血糖値を反映する HbA1c(糖化ヘモグロビン)が低く、いずれも状態は良好であることが明らかになり、コーヒーが健康に利益をもたらす仕組みがおぼろげながら見えてきました。
得られた結果は、コーヒーの摂取が、総死亡といくつかの死因別死亡の低減に関係していること、ただし女性では、がんによる死亡のリスク上昇に関係することを示しました。
論文は、2017年7月11日付の「Annals of Internal Medicine」誌電子版に掲載されています[注1]。
[注1] Gunter MJ, et al. Ann Intern Med. 2017 Jul 11. doi: 10.7326/M16-2945.
■知っていますか? 自分のカフェインの「安全量」
多くのビジネスパーソンが、「あと一息頑張ろう」というときにエナジードリンクや栄養ドリンクを手に取り、「ほっと一息」というときにコーヒーに手を伸ばす生活を送っているのではないでしょうか。そんな日常に一石を投じたのが、先ごろ報道された、20代日本人男性の「カフェイン中毒死」の事故でした。
カフェインの大量摂取による死亡は非常にまれといわれても、実際に死亡例がでてしまうと、心配になります。自分にとっての安全なカフェイン量とはどのくらいなのでしょうか。
■眠気をはらい、集中力を高めるカフェイン、取りすぎると…
カフェインは、コーヒー豆、茶葉、カカオ豆、ガラナなどの成分で、それらを原料とするさまざまな飲料や食品に含まれています。また、抽出されたカフェインが、食品添加物としてコーラなどに使用されています。
カフェインは、中枢神経系を興奮させて眠気をはらい、集中力を高めるといった効果をもたらします。一方で、摂取しすぎると、頭痛、心拍数の増加、不安、不眠、嘔吐(おうと)、下痢などを引き起こします。妊婦の場合には、流産のリスクが高まったり、胎児の発育が阻害されたりする可能性があります。
繰り返しカフェインを摂取していると、体が反応しにくくなり(カフェイン耐性)、より多くのカフェインを求めるようになります(カフェイン依存症)。そうなった時点でカフェインの摂取をやめると、頭痛、眠気、神経過敏、便秘、うつ、悪心・嘔吐、不安、集中力の低下といった離脱症状が現れます。
■安全に摂取できるカフェインの量は、体格によって異なる
悪影響を心配することなく、日常的に安全に摂取できるカフェインの量はどのくらいなのでしょう。厚生労働省と食品安全委員会によると、日本では、カフェインの食品添加物としての使用量や、1日当たりの摂取許容量の基準はありません。現在、食品安全委員会などが、カフェインの健康被害に関する情報を収集している段階です。一方、海外のいくつかの国は、成人が摂取しても体に影響がないとみられる1日当たりの最大摂取量を設定しています。
表1は、欧州食品安全機関(EFSA)が2015年5月27日に発表した、カフェインの安全性に関する科学的意見書に記載されている、健康な成人が摂取しても安全と考えられるカフェインの量を示しています。体重によってかなりの幅があることが分かります。
表1 欧州食品安全機構(EFSA)が、健康な成人が摂取しても安全とみなしたカフェインの量
安全とみなされる量
成人:1回に3mg/kgまで
体重40kgの人なら1回120mgまで
体重60kgの人なら1回180mgまで
体重80kgの人なら1回240mgまで
成人:1日に5.7mg/kgまで
体重40kgの人なら1日228mgまで
体重60kgの人なら1日342mgまで
体重80kgの人なら1日456mgまで
小児~青年:1日に3mg/kgまで
体重40kgの人なら1日120mgまで
体重60kgの人なら1日180mgまで
体重80kgの人なら1日240mgまで
妊婦・授乳婦:1日200mgまで
参考文献:EFSA explains risk assessment. Caffeine
続いて表2で、日常的に摂取している、または摂取する機会がある製品のカフェイン含有量を確認してください。
表2 主なカフェイン含有製品とカフェイン含有量(その1)
飲料/食品/薬剤
カフェイン量
備考
レギュラーコーヒー抽出液
約60mg
100mL当たり
インスタントコーヒー
約60mg
同上(粉末2gを溶かす)
ピュアココア(無糖)
約10mg
同上(粉末5gを溶かす)
ミルクココア(加糖)
微量
同上(粉末20gを溶かす)
玉露
約160mg
同上
煎茶
約20mg
同上
紅茶
約30mg
同上
ウーロン茶
約20mg
同上
コーラ
10~19mg
同上
ミルクチョコレート
25~36mg
100gあたり
高カカオチョコレート
68~120mg
同上
カフェインサプリメント
200~600mg/日
輸入品
燃焼系サプリメント
100mg/日
国産品
缶コーヒー
100~150mg/本
ショート缶
エナジードリンク
22~142mg/本
栄養ドリンク
30~50mg/本
ほとんどが50mg/本
眠気覚ましドリンク
100~150mg/本
(社団法人全日本コーヒー協会、五訂増補日本食品標準成分表、飲料会社、国民生活センター、製薬会社などが提供している情報に基づく)
表2 主なカフェイン含有製品とカフェイン含有量(その2)
薬局で買える製品
カフェイン量(1回量、1日に使用可能な最大量)
備考
眠気予防薬
錠剤
100~200mg/回、300~500mg/日
口腔内速崩壊錠(SP錠)
167mg/回、500mg/日
水なしで飲める
ドロップタイプ
167mg/回、500mg/日
水なしで飲める
顆粒
200mg/回、200mg/日
水なしで飲める
アンプル剤タイプ
200mg/回、200mg/日
20mL/本
ドリンク剤タイプ
200mg/回、200mg/日
50mL/本
総合感冒薬
25mg/回、75mg/日
ノンカフェイン製品あり
解熱鎮痛薬
80mg/回、240mg/日
ノンカフェイン製品あり
鼻炎用カプセル
100~150mg/日
ノンカフェイン製品あり
(社団法人全日本コーヒー協会、五訂増補日本食品標準成分表、飲料会社、国民生活センター、製薬会社などが提供している情報に基づく)
いかがでしょうか。表1と表2を参考にすると、体重が40kg程度の痩せた女性では、缶コーヒー1本、またはエナジードリンク1本でも、安全な1回量を超えてしまうことが分かります。鎮痛薬などの市販薬を買うときは、ノンカフェインの商品を選んだほうが良いかも知れません。また、薬局で購入できる眠気予防薬は、カフェイン含有量が群を抜いて高いことに注意が必要です。
カフェインの半減期(*1)は4~6時間です。安全な1回量以下でも、短時間のうちに繰り返し摂取すると、体内にあるカフェインが代謝・排せつされる前に新たに取り込まれることになるので、血中濃度が上昇することに注意してください。
*1 体内で代謝されることにより、血中濃度が半分に低下するまでに要する時間
■カフェイン感受性が高い人は“安全量”でも不眠や頭痛が出現
さらに注意してほしいのは、個人差です。表1はあくまで参照値で、同じ体格なら安全なカフェイン量も同じとは限りません。なぜなら、カフェイン感受性は人ごとに異なるからです。もし、表1に記載されているより少ない量を摂取した後に不快な症状を感じたら、あなたはカフェイン感受性が高いといえます。健康な成人には有益な量のカフェインでも、感受性の高い人には不眠や頭痛などの害をもたらします(カフェイン不耐症)。
カフェイン感受性に影響を与える要因としては、年齢、病歴、医薬品の使用、心身の健康状態などが知られており、子どもはカフェインに対する感受性が高く、女性より男性の方が感受性が高い可能性も示されています。さらに近年、いくつかの遺伝子がカフェイン感受性レベルに関係していることが明らかになりました。
たとえば、日本人においては、4人に1人が、カフェイン150mgを摂取した後に、不安感が高まる等の害が現れる可能性が高い遺伝子を持っていることが示唆されています(筑波大学技術報告. 2011;31:33-38.)。
また、米国人12万人を対象に、カフェインを摂取したときの反応と摂取量に関係する遺伝子を探した研究では、カフェインの代謝にかかわる遺伝子など、計6個の関与が明らかになりました(Molecular Psychiatry. 2015;20:647-656.)。
■非常にまれだがカフェインアレルギーも起こりうる
最後に、極めてまれではありますが、カフェインに対するアレルギーの患者が日本で報告されています。カフェイン摂取後にアナフィラキシー(*2)を経験したそうです(Asia Pac Allergy. 2015;5:55-56.)。アレルギーになったら、ごく微量の摂取でも症状が起こる危険性があります。
すでに日常生活になくてはならないものになっているカフェインですが、安全とされている量が意外に少ないことに驚いたかと思います。取りすぎは健康被害をもたらすことを忘れずに、その利益を上手に引き出すことが大切です。
*2 蕁麻疹(じんましん)、皮膚のかゆみなどの皮膚症状、咳(せき)、ゼーゼー、くしゃみ、息苦しさなどの呼吸器症状、目のかゆみ、唇の腫れなどの粘膜症状、血圧低下などの循環器症状が組み合わさって出現する
※参考文献:食品安全委員会 ファクトシート 食品中のカフェイン
いずれの記事も大西淳子
医学ジャーナリスト
[日経Gooday 30+]
Posted by nob : 2017年09月26日 09:25
出掛ければ、、、何かをすれば、、、生きて行くこと自体が疲れます、、、、、それでも。。。(苦笑)
■「週末のアウトドア」が
絶対おすすめできないたった一つの理由
梶本修身:医学博士
なぜあなたの疲れはとれないのか?
同じような生活をしているはずなのに、「あの人は疲れていないのに、私はすっごく疲れている」と思ったことはないでしょうか。そう、世の中には、「すごく疲れている人」と「ほとんど疲れていない人」がいるのだ。なぜそのような違いが生まれるのか? 実は、日々の「習慣」がその違いを生んでいたのです。本連載では、その具体的な違いをまとめた書籍『なぜあなたの疲れはとれないのか?――最新の疲労医学でわかるすっきり習慣36』から、疲れとは無縁の生活を手に入れるための方法を一部紹介する。
「あの人はまったく疲れていないのに、私はどうしてすごく疲れているのだろう」
そんな経験をしたことはないだろうか。それには、実は理由がある。疲れていないあの人は「疲れない行動」をしていて、疲れている人は「疲れる行動」をしていたのだ!
では、どんな行動が疲れを生み、どんな行動なら疲れないですむのか?
たとえば、アウトドア。週末は外に出かけて、気分をリフレッシュしてエネルギーを養う、という人は、いますぐやめたほうがいい。
その理由を、日本で唯一の疲労医学の教授・梶本修身氏が、最新科学にもとづく「疲れない習慣」についてまとめた話題の新刊『なぜあなたの疲れはとれないのか?』から、一部抜粋して紹介する。
1日を過ごすなら、「家の中」「家の外」どっち?
「疲労」をコントロールするうえで、一番に考えたいのが「習慣」です。
疲労は、何か大変な作業をしたあとにドシッと体にのしかかってくる感じがあるので、常日頃の習慣を変えたところで、あまり大した影響がないように思うかもしれません。
でも、日々の小さな習慣を見直すことは、「疲労」をとるうえで実に効果的なのです。
そのうえで、まず考えたいのは、1日の過ごし方です。
「遠くに出かけて、思い切り気分転換したい」
「山あいの宿で温泉につかってのんびりしたい」
「家の中に1日いると、体がなまってしまう」
そんなふうに考えて、外に出かけようという人は多いと思います。
確かに家の中でごろごろしていると、なんだか穴倉にこもっているようで、心も体もなまってしまうような気にもなるかもしれません。
外に出かければ、いろいろな刺激や新しい発見もあるわけで、気分もリフレッシュして、また仕事をする元気が出てくるかもしれません。
ところが、外に出かけると、疲れがとれるどころか、もっと疲れてしまうのです。
ですから、疲れているときに遠出するのは基本的にNG。自分の家でくつろいでふだんの疲れを癒すというのが正解です。
なぜ「アウトドア」がおすすめできないのか?
なぜアウトドアが疲れてしまうのかを考えてみます。
そのために、まずは「ホームとアウェイ」についてお話ししたいと思います。
日常生活の中で、ホームとアウェイを意識したことはあるでしょうか。
サッカーや野球などのスポーツで、ホームやアウェイという言葉はよく使われますが、ふだんの生活の中においては、ホームが文字通り「家」「自宅」などで、アウェイはそれ以外の「外」すべてです。会社であったり、学校であったり、スーパーであったり、「家」の外のすべての空間がアウェイです。
何の気兼ねもなく自由にくつろげる自分の家(ホーム)と比べ、アウェイ、すなわち家の外は危険がいっぱいです。
いつどこで不測の事態に遭遇するかわかりませんし、他人の目にさらされることもあって、無意識のうちに常に「緊張状態」を強いられます。つまり、交感神経が常に優位な状態になっているわけです。
家から外に出た瞬間、もうそこはアウェイの世界。ということは、毎日8時間以上、外で働いている人は、通勤時間を含めると1日10時間以上をアウェイで過ごしていることになります。
アウェイで過ごす時間が1日10時間以上もあるということは、動物にとって大きなストレスです。
「外出時の◯◯」が、さらに脳を疲れさせる!
アウトドアには、他にも私たちを疲れさせる原因が隠れています。
目的地までの移動手段は電車、自動車、バスなどが考えられますが、そこに着くまでの間、常に緊張した状態が続きます。とくに初めて行く場所への移動は不安や緊張で交感神経が高ぶっています。これが脳を疲れさせるのです。
目的地に着いたら着いたで、「見知らぬ土地に来た」ということで、警戒する意識が働きます。初めての場所は、本能的に警戒するように脳ができていて、これはヒトに限らず、動物はすべてそうです。
旅行などで初めての土地に行くと、多くの人がホテルに着いたら1回はホテルの周りを探索します。
「周りにどんなお店があるのか」
「夜の買い出しはどこでしようか」
そうした動機があるにせよ、本能的には、自分が寝泊まりするところが安全かどうか、危険はないかを調べたくなっているのです。
こうした行動すべてが疲労の原因です。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2017年09月12日 11:42
どんなものでも諸刃の剣、、、あらゆるものをバランス良く。。。
■飲酒が大腸がんのリスクを上げるのは確実!?
酒量は日本酒2合程度までに抑え、葉酸、食物繊維を積極的にとろう
エッセイスト・酒ジャーナリスト 葉石かおり
数あるがんの中でも、ミドル以上のビジネスパーソンが最も気にするがんは「大腸がん」ではないだろうか。大腸がんにより、毎年約5万人もの人が命を落としている。この恐ろしい大腸がんが、飲酒と深い関係があることをご存じだろうか。一昨年には赤身・加工肉による大腸がんリスクがマスコミで盛んに取り上げられたが、飲酒も大腸がんのリスクを高める要因の1つだという。そこで、日本人の飲酒と大腸がんリスクについて論文を発表している国立国際医療研究センターの溝上哲也さんに話を聞いた。
こよなく酒を愛し、日々、酒を愛飲する左党にとっても、「がん」はやはり気にせずにはおられない病気である。
何といってもがんは日本人の死因のNo.1、生涯でがんになる確率は男性63%、女性47%にも達する(詳しくはこちらの記事を参照)。そして、飲酒はがんのリスクを上げる大きな要因の1つであることは、多くの方がご存じだろう。特に、喉頭がんや食道がんのリスクが飲酒によって上がることはよく知られている。この連載でも以前紹介したが、私の身近にも、ウイスキーのロックを水のごとく飲んでいたことが原因で食道がんにかかったと思われる知人がいた。
働き盛りの世代を襲う「大腸がん」
さて、数あるがんの中でも、ミドル以上のビジネスパーソンの多くが気にするがんというと「大腸がん」ではないだろうか。国立がん研究センターが2016年8月に発表したデータによると、がんの部位ごとの罹患数では、大腸がんは男女ともに2位、男女合わせると大腸がんが最多となっている。さらには女性のがん死亡原因の1位になっている(男性は3位:詳しくはこちらの記事を参照)。大腸がんは50歳を過ぎたころ、そう「働き盛り」とも言える年代から発症率が高くなるという。
ううむ、アラフィフの私としても、黙って見過ごせない。そういえば自分の周囲の左党たちからも、「人間ドックで大腸にポリープが見つかった」だの、「大腸がんの初期で手術した」という話を聞く機会が増えたように思う。昨今は、著名人でも大腸がんを患った方や、闘病の末、惜しくも大腸がんが原因で他界された方も少なくない。
大腸がんというと、私は肉や脂質を多く摂取する食生活が原因だとばかり思っていた。2015年には、「赤身肉や加工肉の摂取が大腸がんのリスクを上げる」と発表され、マスコミなどで広く取り上げられたのは記憶に新しい。しかし、どうやらそれだけではないらしい。
この大腸がん、飲酒と深い関係があるとも聞くが、これは本当なのだろうか。そして、なぜ飲酒が大腸がんに影響するのだろうか。詳しく知りたいところだ。そこで今回は、国立国際医療研究センター 臨床研究センター 疫学・予防研究部 部長の溝上哲也さんに大腸がんとアルコールの関係について話を伺った。
今や大腸がんによる死亡者数は約5万人に!
まずは大腸がんの現状について溝上さんに聞いてみた。
溝上さんは、「かつて大腸がんは欧米に多いと言われていましたが、近年は日本でも大きな問題となっています。日本における大腸がんによる死亡者数は、最近では約5万人に達しています」と話す。
ううむ、やはりそうか。これは、食生活の欧米化が主たる原因なのだろうか?
「ご指摘のように、生活習慣の変化が影響していると考えられます。腸の長い日本人が欧米型の食事、つまり赤身肉や脂質の多い食事をすることが腸に悪影響を及ぼすと言われていました。一昨年の赤身肉・加工肉のリスクが指摘されて、話題になったのはご存じでしょう。しかし、大腸がんのリスクを上げるのはそれだけではありません。意外と知られていないのですが、飲酒も大腸がんのリスクを高める重要な要因の1つです」と溝上さんは話す。
飲酒が大腸がんのリスクを高めるのは「確実」
前回も紹介したように、国立がん研究センターでは、日本人のがんと生活習慣との因果関係の評価を行っている。国内外の最新の研究結果を基に、全体および個々の部位のがんについてリスク評価を「がんのリスク・予防要因 評価一覧」としてホームページで公開している。「データ不十分」⇒「可能性あり」⇒「ほぼ確実」 ⇒「確実」の順に科学的根拠としての信頼性が高くなる。
この評価によると、大腸がんのリスクを高める要因の中で「確実」になっている唯一の要因が飲酒だ。次に信頼性が高いのが「肥満」で「ほぼ確実」となっている。
では、アルコールの摂取は大腸がんのリスクをどのくらい上げるのだろうか。
溝上さんたちの研究グループは、5つのコホート研究のデータを合わせた合計約20万人を対象にしたデータを解析して、日本人の飲酒と大腸がんのリスクを評価、2008年に専門誌に発表している(Am J Epidemiol. 2008;167:1397-1406.)。それによると、「男女ともに過度の飲酒で大腸全体、そして結腸、直腸がんのリスクが上がるという結果になりました。特に男性の場合は顕著に現れています」(溝上さん)
溝上さんの解析結果を見ると、男性では、純アルコールに換算して23~45.9g/日、46~68.9g/日、69~91.9g/日、92g以上/日のグループでまったく飲まないグループよりもそれぞれ1.4倍、2.0倍、2.2倍、3.0倍と、アルコールの量に比例して、リスクが確実に高くなっていることが分かる。女性の場合も、男性ほど顕著ではないが、アルコール摂取量が23g以上/日のグループは、飲まないグループよりリスクが1.6倍に高まるという結果になっている。
正直なところ、飲酒の影響がここまではっきり出るとは思わなかった。これは、大腸がんを気にする左党にとっては、かなり厳しいデータではないか。純アルコール23gは日本酒にして約1合。左党からすれば大した量ではない。
なお、大腸は大きく、肛門近くの直腸と、その上の急カーブしている部分(S状結腸)より上の結腸に分けられるが、そのいずれも飲酒によりがんのリスクが高くなる傾向が見られた。
なぜ飲酒が大腸がんを引き起こすのか?
溝上さんは、日本人と欧米人に分けて、飲酒量と大腸がんの関係性を分析している。これによると、日本人は明らかに酒量が増えるほど極端に右肩上がりになるが、欧米人は実に緩やかである。
これは、やはり日本人はアルコール耐性が弱いことが原因なのだろうか?
「ご存じのように、日本人は人種的に見てもアルコール耐性が弱い方が多くいます。アルコール耐性の強い欧米人は、1日2合未満の飲酒では大腸がんのリスクが上昇していないのに対し、日本人は1.4~1.8倍もリスクが上がっています」(溝上さん)。「人種による違い」と割り切るしかないのだが…、日本人としてはとても残念なデータである。
ではいったい、どんなメカニズムによって大腸がんが引き起こされてしまうのだろうか?
溝上さんによると、「飲酒が大腸がんを引き起こすメカニズムはまだはっきりと解明されていない」のだという。
「まず原因として考えられるのは、アセトアルデヒドによる毒性です。アルコールの代謝産物であるアセトアルデヒドには発がん性があることが実験でも確認されています。日常的に多量飲酒が習慣化している方、そしてアルコールを飲んで、顔が赤くなるような方は、アセトアルデヒドの毒性にさらされる時間も長くなることから危険が高まる可能性があるわけです」(溝上さん)
「しかし、アルコールの代謝に関わる遺伝⼦型と⼤腸がんの関連性を調べた最近の研究では、必ずしも明確な関連性は出ていません。このため遺伝的な体質ではなく、腸内細菌の働きによってアルコールから生成されたアセトアルデヒドが葉酸の吸収や働きを阻害することにより、⼤腸がんの発生リスクが高まるのではないかという説が有力になっています」(溝上さん)
葉酸は積極的に摂取するといい
「葉酸はビタミンB群の一種で、名前の通り葉野菜などに多く含まれています。葉酸は、細胞の合成や修復に深く関わる重要な栄養素で、細胞の遺伝情報が入ったDNA(遺伝子)の合成に必要な成分です。ところが、前述のようにアセトアルデヒドは、腸内の葉酸の吸収を妨げる効果があります。これにより、細胞の合成・修復作用が阻害され、大腸がん発生の初期段階となる遺伝子の損傷が引き起こされるのではないかと考えられています」(溝上さん)
メカニズムこそ明確になっていないものの、がん予防と葉酸に何らかの関係があることは確かなようだ。葉酸の登場で何だかちょっと明るい兆しが見えたような気がする。では日常的に葉酸を摂取すれば、飲み続けていても大腸がんを防ぐことができるのだろうか?
「残念ながら、葉酸をたくさん摂取しても、大腸がんの罹患リスクが下がるとは言い切れません。タバコが明確な要因である肺がんとは異なり、大腸がんの場合、要因が非常に複雑に絡んでいるためです。とはいえ、葉酸不足にならないよう積極的に摂取するといいでしょう。葉酸はブロッコリーやホウレン草や小松菜などの青い野菜、そして柑橘系のフルーツに多く含まれています。できれば、サプリメントに頼らず、食物から摂取することをお勧めします」(溝上さん)
やはり飲み過ぎは避けたほうがいい
最後に、溝上さんに、大腸がんを防ぐためのポイントを整理していただいた。
溝上さんがまず指摘したのが、酒量である。「前ページのグラフからも明らかなように、酒量が増えると大腸がんのリスクが上がります。まずは酒量を純アルコールに換算して23~45.9g未満(日本酒1~2合程度)に抑えること、これが大前提です」(溝上さん)。ああ、やはり今回も「節酒」を免れることはできなかったか…。
食事については、食物繊維も重要なポイントになるという。「穀物由来の食物繊維を積極的にとることをお勧めします。かつては、ゴボウなどをはじめとする野菜からの摂取がいいとされていましたが、最新の研究によって米や麦などの穀類に含まれる繊維が有効なことも分かってきました。⽩⽶に雑穀を混ぜるなどして⾷べるといいでしょう。その他、牛乳などカルシウムを豊富に含んだ食品も積極的にとってほしいですね」(溝上さん)
玄米や大麦などは、すでに日々の食生活に取り入れられている方も多いだろう。特殊なものでなく、誰もがすぐに実践できる食材なのがありがたい。
また、肥満も大腸がんのリスクを高めると溝上さんは警告する。「BMIが25を超えないよう注意してください。そのためにも週 150分を目安に運動することを習慣づけましょう」(溝上さん)。肥満はがんをはじめ、様々な病気の元凶だ。メタボと診断されている方は、さらに注意が必要だ。溝上さんが推奨する週150分の運動は、1日に換算すれば20分ちょっと。1駅分歩く、エレベーターより階段を使うなど、少し意識することで無理なく達成できそうである。
◇ ◇ ◇
大腸がんは昔に比べ、確実に増えている。多くの人が心配するのも無理はないが、その一方で、「大腸がんは早期発見であれば治る確率が高いがん」だと溝上さんは指摘する。だからこそ「早期発見がとても重要です。40歳を超えたら年1回、大腸がん検診を受けてください」と溝上さん。過度に恐れることなく、定期的にがん検診を受けながら、日々の食生活に留意し、酒と長く付き合っていってほしい。
溝上哲也(みぞうえ てつや)さん
国立国際医療研究センター 臨床研究センター 疫学・予防研究部 部長
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年09月09日 11:24
休煙という禁煙のすすめ、休んでいるだけと思えば止められる。。。ホントに美味しく呑めば、自ずと飲酒量も減らしていける。。。
■飲み続けたいならまず禁煙 がんのリスクたばこが助長
2020年の東京オリンピックを控え、喫煙問題が改めて注目されている。喫煙が、がんをはじめとした様々な病気の原因になることは広く知られている。一方で、お酒の飲み過ぎが体に悪いことも繰り返し紹介してきた。では、タバコと飲酒の2つが重なるとどうなるのだろうか。がんになる危険性が一層高まるといったことはないのだろうか。酒ジャーナリストの葉石かおりが、日本のがん研究の総本山である国立がん研究センターに取材して話を聞いた。
◇ ◇ ◇
■タバコと酒、ダブルになったときのリスクは?
昔と比べ、今はだいぶ少なくなったものの、左党には喫煙者が案外多い。現に新橋あたりの渋い居酒屋に行くと、タバコの煙で視界が曇るほどである。実際、「お酒を飲むときはタバコも吸わずにはいられない」という左党の読者も少なくないだろう。
私的なことだが、実父は喫煙が主な原因のCOPD(慢性閉塞性肺疾患)で他界していることもあって、個人的にはタバコの煙がもくもくの中での飲酒は苦手である。タバコはアルコール同様、嗜好品なので、個々が楽しむ分には問題ないと思っている。しかし以前から問題視されている受動喫煙の被害を考えると、クリーンな空気の中で心おきなく酒をおいしく飲みたいと思う。国でも2020年の東京オリンピックを前に、受動喫煙防止の法整備の議論が交わされている。国レベルでの対策となると、気にせずにはいられない。
タバコが体に悪影響をもたらし、がんをはじめとした様々な病気の原因になることは、論をまたないところだと思う。また、飲酒も適量以内ならいい影響もあるとはいえ、飲み過ぎが体に悪いことは、これまで記事で幾度となく紹介してきた。では、タバコと飲酒の2つが重なるとどうなるのだろうか。
実際、私の周囲の左党で、かつ喫煙する人の中には、がんに罹患した人が何人かいる。このため、私はかねがねタバコと飲酒の因果関係を疑っていた。それぞれ単独ではよくないことは分かっているが、ダブルになるとリスクがより高まるのではないだろうか。具体的には、タバコががんの原因になることは周知の事実だが、飲酒によってその危険性がより高まるのではないだろうか。
そこで今回は、国内におけるがん研究の総本山ともいえる国立がん研究センターで、がんや慢性疾患の疫学研究や大規模コホート研究[特定の集団(コホート)を対象として長期的に経過を追跡する調査手法のこと]を手がけてきた、社会と健康研究センター コホート連携研究部部長の井上真奈美さんに、タバコと飲酒のコンビによるリスクについて話を伺った。
■タバコは百害あって一利なし
まずは、タバコのがんへの影響を改めて井上さんに確認してみた。
「タバコにはニトロソアミン、ヒ素、カドミウムといった発がん物質が約70種類含まれています。このため、肺がん、咽頭・喉頭がん、胃がん、食道がんなど、さまざまな部位のがんの発症リスクを確実に高めます」(井上さん)
国立がん研究センターでは、日本人のがんと生活習慣との因果関係の評価を行っている。国内外の最新の研究結果を基に、全体および個々の部位のがんについてリスク評価を「がんのリスク・予防要因 評価一覧」としてホームページで公開している。最も信頼性が高い評価から順に「確実」→「ほぼ確実」→「可能性あり」→「データ不十分」となっている。
「タバコとがんの罹患については、全がん、肺がん、肝がん、胃がん、食道がん、膵臓がん、子宮頸がん、頭頸部がん、膀胱がんの発症リスクの信頼性が、最も高い『確実』と評価されています。他の部位のがんについても、乳がんや大腸がんが『可能性あり』となっており、リスクがあると考えられます。そう、タバコは百害あって一利なしなのです」(井上さん)
百害あって一利なし――。
ある程度予測できたこととはいえ、ここまでハッキリ断言されると、改めてその怖さがよく分かる。実際、上のがんのリスク評価の表を見ても、信頼性が「確実」である濃い茶色の欄が、圧倒的に多いのが「喫煙」であることがよく分かる。さらに井上さんはこう続ける。
「世界的には、今は、タバコにはどういった健康への害があるかを研究する段階を脱し、『どうやってタバコのない環境を実現するか?』という『対策』のフェーズにあるといえます。言い換えれば、それほどタバコによる健康被害は甚大で、確実に体に影響があるということです」(井上さん)
喫煙リスクをはっきり示されると、周囲の愛煙家に禁煙を勧めたくなる。では、ここに飲酒によるリスクが加わると、どうなるのだろうか。
■飲酒とタバコを同時進行させると、がんのリスクが2倍以上に!
「コホート研究の結果から、飲酒量が多くなると、将来がんになりやすいことが明らかになっています。飲酒量が1日2~3合の男性は、時々飲む人に比べて、がん発生率が1.4倍に、1日3合以上の人は1.6倍になっています。そして、ここに喫煙が加わると、がんに罹患するリスクがさらに高まるのです」(井上さん)
「ああ、やっぱり……」という声が聞こえてきそう。予想通り、喫煙と飲酒のセットは最悪のリスクなのだ。それはデータにも明確に表れている。
「喫煙習慣別に飲酒とがんの発生率のデータを見てみると、非喫煙者と喫煙者とでは大きな差があります。『時々飲む』人を1としたときの相対リスクは、適量といわれる『1日1合未満』では非喫煙者が0.87であるのに対し、喫煙者は1.69と、この段階でも倍近い差が出ています。1日3合以上の多量飲酒の場合、非喫煙者は1.02に対し、喫煙者では2.32と倍以上のリスクがあります。非喫煙者は、飲酒量が増えてもがんの発生率はそう高くならないのに対し、喫煙がプラスされると確実に高くなっていきます。つまり飲酒によるがんのリスクは、喫煙によって助長されるのです」(井上さん)
バブル時代のトレンディードラマ(既に死語?)では、主人公が酒を飲みながらタバコをふかすシーンが当たり前だったが、それはもはや過去のこと。飲酒と喫煙のセットは超危険なのだ。
■セットにすると、なぜがんのリスクが上がるのか?
では、喫煙と飲酒をセットにした際、がんの発生率が上がる原因は何なのだろうか?
「詳しいメカニズムは分かっていませんが、現時点で示唆されているのが、アルコールの慢性摂取によって酵素誘導[酵素の合成が誘導され、酵素量が増加すること]される薬物代謝酵素CYP(チトクロームP450)の影響です。アルコールを飲むと、特にCYP2E1の酵素誘導が進みます。CYPは、ニトロソアミンをはじめとする、タバコ中のがん原物質を活性化する作用があると考えられています」(井上さん)
また、アルコールが体内で代謝される際に生じるアセトアルデヒドにも発がん性があることが知られている。酒を飲んで顔が赤くなる、いわゆる酒に弱い人は、アセトアルデヒドの分解能力が弱いため、アセトアルデヒドが残りやすい。つまり、発がん性のあるアセトアルデヒドにさらされる時間が長くなるわけだ。井上さんは、「このように酒を飲んで赤くなる人は、喫煙とセットにするとがんになる危険性がさらに上がる可能性があります」と話す。
以前「お酒で赤くなる人、ならない人 がんのリスクも違う」という記事でも紹介したように、日本人は、黒人や白人に比べて、顔が赤くなる人(アセトアルデヒドの分解能力が低い人)の割合が多いので、より気をつけたほうがよさそうだ。しかし、こうなると、もうタバコをやめる以外に対策はないということだろうか……?
「そうですね、やはりタバコをやめる以外に選択肢はありません。先ほどのデータからも明らかなように、アルコールとタバコのセットは厳禁。酒とタバコのどちらをやめたほうがいいかと言われれば、間違いなくタバコです」(井上さん)
読者の中にも、酒とタバコを両方とも愛してやまない人は少なからずいると思う。もし、酒を飲み続けたいなら、やはりタバコはやめたほうがよさそうだ。
■受動喫煙による肺がんの発症リスクも「確実」に
ここで受動喫煙についても触れておきたい。日本の居酒屋や喫茶店では、いまだ喫煙可の店が目立つ。国民健康・栄養調査(2013年)によると、受動喫煙が月に1回以上ある人の割合は家庭で16.4%、飲食店で46.8%、職場で33.1%と、ダントツで飲食店での受動喫煙率が高い。私のように非喫煙者であっても、タバコの煙もくもくの居酒屋で飲んでいたら、どんなリスクがあるのだろうか?
「受動喫煙による肺がんの発症リスクの信頼性も昨年の8月に『ほぼ確実』から『確実』へと格上げされました。他のがんの発症リスクについてはデータがまだ不十分ではありますが、副流煙のほうが主流煙より有害物質が多いので、安心とは言い切れません。配偶者が喫煙者だと、家族に喫煙者がいない人の1.3倍も肺がんの発症率が上がるという報告もあります」(井上さん)
◇ ◇ ◇
飲酒は「適量(1日1合)を守ろう」という救いの言葉があるが、喫煙の場合、残念ながら卒煙または禁煙以外、手立てがない。現在、日本において男性のがんの30~40%、女性のがんの3~5%がタバコが原因のがんだという。酒を長~く、おいしく飲むためにも、タバコとの付き合い方をちょっと考えてみてはいかがだろうか?
(エッセイスト・酒ジャーナリスト 葉石かおり)
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年09月09日 11:14
これも前向きな一つの選択。。。
■がん 治療受けていない高齢者が年々増加
高齢者のがん患者の中で、治療を受けていない人の割合が年々増えていることが、国立がん研究センターの調査でわかった。
この調査は、全国のがん診療を専門とする病院で2015年、がんと診断された約70万人を対象としたもの。85歳以上で、がんが他へ転移している「ステージ4」の患者を調べたところ、治療を受けていないことを意味する「治療なし」の患者が、肺がんでは58%、胃がんでは56%と半数を超えていたことがわかった。
また、治療を受けていない高齢の患者は年々増えており、ステージ4の大腸がんの患者の場合、「治療なし」が36.1%と、3年前に比べて約4ポイント増えていた。
国立がん研究センターでは、高齢者は他の病気を併発していたり、治療による体への負担が大きかったりするため、個別性を重視した治療を考える必要があるとしている。
[日テレNEWS24]
Posted by nob : 2017年08月11日 06:00
賛が否を大きく上回ってきている昨今の珈琲健康論議。。。Vol.4
■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~
コーヒーを飲むと痩せる!? ダイエット効果はあるか
第5回 コーヒーポリフェノールの脂肪燃焼効果とは――日本ポリフェノール学会理事長の板倉弘重さんに聞く
柳本操=ライター
みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、カラダにいいことづくめだった! 以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが続々と明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。第5回となる今回は、コーヒーに含まれるポリフェノールの脂肪燃焼効果に迫る。日本ポリフェノール学会の理事長で、品川イーストワンメディカルクリニックの理事長の板倉弘重医師に、コーヒーポリフェノールの効能や効果的な摂取方法について聞いた。
これまで4回にわたって、がん予防、糖尿病予防、血液サラサラ効果など、コーヒーの多彩な働きをお届けしてきた。取材した専門家の方々が口を揃えたのが、「クロロゲン酸」という、コーヒーの健康効果を支えるポリフェノールの一種の働きについてだった。
そもそもポリフェノールとは何なのか。コーヒーに含まれるクロロゲン酸はどういったポリフェノールなのか。そしてその効果は――。こう聞かれても漠然と「ポリフェノールはカラダにいいらしい…」くらいにしか説明できない人が多いのではないだろうか。
そこで今回は、赤ワインやチョコレートなどの「ポリフェノールブーム」の火つけ役の1人で、日本ポリフェノール学会の理事長も務める板倉弘重医師に詳しく話を聞いた。板倉さんは、国立・栄養研究所 臨床栄養部に在籍していた時に、赤ワインに含まれるポリフェノールの抗酸化パワーを世界に知らしめた1人だ。
クロロゲン酸は、強い抗酸化作用によって体内の炎症を抑えたり、LDLコレステロールを低下させるといったさまざまな効果がある。また、肝臓にいい影響を及ぼすことも第3回でも紹介した。
今回特に注目したいのが「脂肪燃焼効果」だ。クロロゲン酸には、脂肪を燃やす働きがある。つまり、コーヒーはダイエットにも効果があるのだ。さらにコーヒーには、脂肪を燃やす働きがあるもう1つの成分「カフェイン」も多く含んでいる。これらが両方あると相乗効果が出る。そのダイエットパワーの神髄に迫っていこう。
◇ ◇ ◇
そもそもポリフェノールとは?
今回は、コーヒーに含まれるポリフェノールについて伺いたいと考えています。板倉先生は、長年にわたってポリフェノールの抗酸化作用について研究されてきました。まず、そもそも「ポリフェノールとは何か」から教えていただけますか。
板倉さん ポリフェノールは、植物由来の抗酸化物質の1つです。植物が自らを守るために作りだした成分なので、ほとんどの野菜や果物に含まれています。その種類は7000~8000種類ともいわれています。ちなみに、フェノールというのはベンゼン環にOH基(ヒドロキシ基)が1つ付いた有機化合物で、これが複数つながったのがポリフェノールです(詳しくは「健康効果というと、なぜ赤ワインばかりが取り上げられるのか」を参照)
コーヒーのクロロゲン酸をはじめ、大豆のイソフラボン、お茶のカテキン、タマネギのケルセチン、赤ワイン、ブルーベリーに含まれるアントシアニンなどもポリフェノールの仲間です。植物由来の抗酸化物質には、ポリフェノール以外にも、ビタミンCやE、色素成分のカロテノイドなどがあります。
ポリフェノールは、活性酸素による酸化からカラダを守ってくれます。これが抗酸化作用と呼ばれているもので、カラダにいい影響を及ぼすのです。
そもそも私がポリフェノールに着目したのは、動脈硬化についての研究を始めたことがきっかけでした。
1960年代に大学を卒業して医師になったばかりのとき、私は東京大学の第三内科に入局したのですが、そこで教授から「動脈硬化について研究しないか」と誘われたのです。当時は、動脈硬化を促進する要因となる「油」についての研究を主に行っていましたが、その後、国立健康・栄養研究所に移ってからは、「動脈硬化を促進するのは活性酸素によって血管内にできる酸化コレステロールである」という視点で研究を進めました。
そこで赤ワインに豊富に含まれるポリフェノールの抗酸化作用に注目して研究を進め、赤ワインのポリフェノールが動脈硬化を予防する作用があることや、脂肪の吸収を抑制する効果があることなどを明らかにしたのです。その結果を、1994年に英国の医学雑誌「Lancet(ランセット)」において発表しました。その後は、ココアポリフェノール、お茶のカテキンなど、さまざまなポリフェノールの研究をしてきました。
コーヒーは日本人最大のポリフェノール源
コーヒーのポリフェノールには、どういった利点があると先生は考えているのですか。
板倉さん コーヒーに含まれるポリフェノール「クロロゲン酸」は、日本人にとってとても重要な役割を果たしていると考えています。なぜなら、日本人のポリフェノールの摂取量の多くはコーヒーによるものだからです。
ネスレリサーチセンターが日本人の男女8768人を対象に行った研究があります。1日に摂取する全ての飲み物のうち、どの飲料からどのくらいのポリフェノールを摂取しているかを調べたものです。第一位の飲み物はコーヒーで50%、緑茶からは35%、ということがわかりました。また、1日あたりのコーヒー摂取量が多いほど、ポリフェノール摂取量が多くなることもわかっています(J Agric Food Chem. 25;57(4):1253-9.2009)。
日本人の食品・飲料からのポリフェノール摂取比率
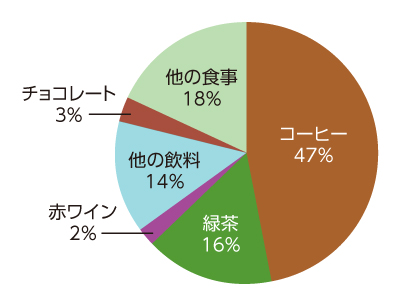
首都圏在住の主婦109人、食事、飲料などを1週間記録してもらい、ポリフェノールをどこから摂取しているかを算出した(Fukushima Y et al.,J Nutr Sci,2014)
[画像のクリックで拡大表示]
飲み物だけでなく野菜や大豆製品なども含めた食事全体からのポリフェノール摂取量の調査を見ても、ポリフェノール摂取量の47%がコーヒーからの摂取になっています。コーヒーは日本人にとって最大のポリフェノール源なのです。これはネスレが2010年に、首都圏在住の主婦109人に、食事、食材、飲料を一週間記録してもらったデータから算出したものです。主婦を対象にした調査ということでデータに多少偏りがあるのではないかと思われますが、それを差し引いても、コーヒーが最大級のポリフェノール源であることは間違いないでしょう。
クロロゲン酸は強い抗酸化力で動脈硬化を予防
コーヒーと緑茶に含まれるポリフェノール量
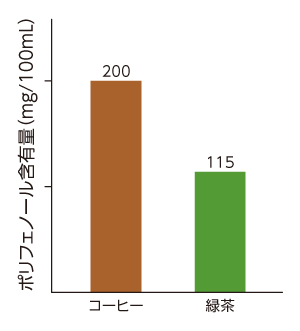
コーヒーには、緑茶の倍近くのポリフェノールが含まれている(Fukushima Y et al.,J Agric Food Chem,2009)
[画像のクリックで拡大表示]
日本人がコーヒーから最もポリフェノールをとっているとは、驚きですね。緑茶や野菜などのほうが多いのかと思っていました。
板倉さん そうですね。コーヒーは、緑茶のおよそ2倍のポリフェノールを含んでいることも、ポリフェノール源として寄与率が高い要因ではないでしょうか。
コーヒーのポリフェノール「クロロゲン酸」は、その強い抗酸化作用によって体内の炎症を抑え、血管壁にプラークを作りにくくし、血管壁の内皮細胞に作用して血管をしなやかに保ちます。動物実験によって、クロロゲン酸を投与すると動脈硬化を抑え、LDLコレステロールが低下する、肥満を改善するといった研究が集積されてきました。その他、コーヒーによる肝機能への効果は、クロロゲン酸によるものと言われています(詳しくは第3回を参照)。
板倉さん 最近は、「コーヒーがカラダにいい」というのはもはや周知の事実になっていて、現在は飲む量と病気の関係についてさかんに研究が進められています。多くの研究を見渡すと、どうやら1~2杯では足りないようで、3~4杯ぐらいが適当ではないかという意見が多いようです。
私が医師になった1960年代は、医学会でも「ポリフェノールは人間の必須栄養素ではないから、あまり役に立つ成分ではない」というふうに考えられていました。しかし、それ以降、世界中で疫学調査が行われ、「コーヒーをある程度飲むと心筋梗塞を予防できる」「死亡率も低くなる」という事実が続々と発表されたため、その意識も大きく変わりました。
欧米では心臓病が死因のトップであるため、動脈硬化を予防することは非常に重要な課題となっています。また、糖尿病や肥満については、日本を含む先進国だけでなく、アジアやアフリカなどの途上国でも深刻な事態となっています。特に中国とインドでは糖尿病が今後爆発的に増加すると予測されています。そんな中、コーヒーを飲む習慣は糖尿病予防にもつながるとして、世界的にも注目されています。この血糖値を下げる効果も、クロロゲン酸によるものと考えられています(詳しくは第4回を参照)。
コーヒーには脂肪燃焼効果がある
クロロゲン酸にはさまざまな効果があるのですね。コーヒーには脂肪燃焼効果があるという話を聞きますが、これもクロロゲン酸によるものですか?
板倉さん ご指摘のように、コーヒーには脂肪燃焼効果があります。飲むと、脂肪の燃焼が促進されるわけです。そうした効果をうたった商品も登場しています。
コーヒーの脂肪燃焼作用を詳しく見ると、クロロゲン酸の働きとカフェインの働きという2つの側面があります。両方とも脂肪を燃焼させる効果がある成分ですが、それぞれ働き方が異なります。
クロロゲン酸とカフェインがダブルで効く
板倉さん クロロゲン酸を摂取すると、肝臓での脂質の代謝が活発になり、結果として脂質の燃焼によるエネルギー消費が増加します。つまり、脂肪が燃えやすいカラダを作る。これはトクホでもおなじみのお茶のカテキンと共通する働きです。
一方、カフェインは、体内に入ると交感神経が優位になります。眠気が覚めるのはこのためですが、同時にカフェインは体内にあるリパーゼという酵素を活性化させます。このリパーゼにより、脂肪がエネルギーとして活用されやすい遊離脂肪酸に分解され、血液中に放出されます。そして、エネルギー源として消費されるのです。つまり、カフェインによって、脂肪がエネルギーとして消費されやすくなり、脂質の代謝が高まるのです。
コーヒーには、このような脂肪をエネルギーに変えていくための2つの成分が同時に、しかも豊富に含まれています。ここが大きなポイントです。
運動とセットで摂取するのが効果的
個人的な疑問になってしまうのですが、よろしいでしょうか。私は毎日3~4杯はコーヒーを飲んでいます。ですが、ちっとも体重が落ちないのですが…。
板倉さん 脂肪燃焼効果があるといっても、それだけで痩せるわけではありません。体重を落としたい場合は、まずエネルギー摂取量とエネルギー消費量のバランスを考えないといけません。
当たり前の話ですが、エネルギー消費量よりもエネルギー摂取量のほうが多いと、消費しきれなかった分のエネルギーが体脂肪として蓄積されます。反対に、消費エネルギーが摂取エネルギーを上回れば、体脂肪が燃焼しエネルギーとして利用されるので、体重を落とすことができます。食べ過ぎているのに、コーヒーを飲むだけでダイエットできるというわけではないんですよ。
もちろん脂肪燃焼効果はあるわけですから、それをうまく引き出せばダイエットにつなげることはできますよ。効果を高めるポイントは「運動との組み合わせ」です。「運動とコーヒー摂取を組み合わせると、体重減少、内臓脂肪や皮下脂肪の減少効果が出る」という報告が複数出ています。つまり、運動による脂肪燃焼効果をコーヒーが底上げしてくれるわけです。
話が少しそれますが、「運動前にカフェインを摂取すると運動能力がアップする」という研究成果もあります。だからこそ、以前はスポーツ競技でドーピングの対象となる薬物にカフェインが含まれていたのです。ただし、2004年以降禁止物質から除外されています。つまり、運動前にカフェインを含むコーヒーを飲むことは、脂肪の燃焼を促進すると同時に、運動能力がアップするのでおすすめです。
痩せ効果を得たいなら、運動の1時間前に飲む
運動と組み合わせて飲むならどのようなタイミングが良いでしょうか。
板倉さん クロロゲン酸は、やや溶けにくいものの、水溶性の性質を持っています。口から入ると1~2時間後に血中でピークになり、4 時間後ぐらいにはカラダの外に排泄されてしまいます。もともとポリフェノールは異物とみなされるので、カラダはすぐに排泄しようとするのです。体内への吸収率も高くはなく、数パーセントほどしか吸収されない、といわれています。カフェインも、クロロゲン酸と同様に1~2時間後で血中においてピークになります。
ですから、運動する1時間前ぐらいにコーヒーを飲むのがおすすめです。ちょうど運動をして脂肪が燃焼しはじめる頃に、クロロゲン酸とカフェインも血中でピークとなり、その燃焼効果を高められると考えられます。
また、運動時には活性酸素もたくさん体内で生じますから、クロロゲン酸の抗酸化作用によって活性酸素の害を抑えられるというメリットもあるでしょう。
クロロゲン酸はタンパク質と結合しやすい性質を持っているため、コーヒーにミルクをたくさん入れると、牛乳のカゼインというタンパク質と結合して、その吸収が落ちる可能性があります。クロロゲン酸のパワーをフルに引き出したいなら、ブラックで飲むのがおすすめです。
コーヒーの有効成分は、素早く吸収され、排泄される。この性質を知っておくことで、うまく体内で効かせられそうですね。
板倉さん 人間は、ポリフェノールのことなど知らないずっと昔から、ティータイムの習慣を持っていました。イギリスやオランダでは紅茶、アメリカではコーヒー、日本では緑茶、というふうに、種類は違えど、こまめにポリフェノールを体内に入れることによって健康効果が得られることを知っていたのだと考えると、人間の知恵はすごいと思いますね。
時代は変わり、現代は飽食で運動不足の時代です。メタボなどの“現代病”の予防効果を持つコーヒーの価値はより高まっているように感じます。
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年08月01日 19:10
賛が否を大きく上回ってきている昨今の珈琲健康論議。。。Vol.3
■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~
コーヒー習慣は血糖値も下げる! 驚きのコーヒー効果
第4回 メタボに悩むビジネスパーソンはコーヒーを!――国立健康・栄養研究所 古野純典さんに聞く(後編)
柳本操=ライター
みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、体にいいことづくめだった! 以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが続々と明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。今回は、前回に引き続き国立健康・栄養研究所所長の古野純典さんに、生活習慣病とコーヒーの関係について話を伺っていく。コーヒーは、肝機能や痛風に効果があるだけでなく、糖尿病にも効果があるという。
前回のお話を聞くと、コーヒーには、肝機能に効果があり、さらに痛風の原因となる尿酸値も下げる、といいことばかりですね。しかし、昔はカラダに悪いという印象が強かったですよね。
古野さん そうですね。ご指摘のように、1980年代前半ぐらいまでは、今とは逆で、カラダに悪いと思われていました。だから、コーヒーの研究が盛んに行われたわけです。当時北欧では「コーヒーは心筋梗塞を引き起こしやすい」という研究も発表されていました。
北欧には、挽いたコーヒー豆をボイルして(沸かして)、固形成分を沈殿させた上澄みを飲む「ボイルドコーヒー」を飲む習慣がありました。このような飲み方では、コーヒー豆に含まれる特殊な脂質成分を体内に取り込むことになります。実はこのコーヒーの脂質成分は、コレステロール値を高め、脂質異常をもたらす一因となるのです。だから、こういったネガティブな研究結果が出たわけです。
ただ、安心してください。この脂質成分はフィルターを通すと除去されます。日本や米国ではコーヒーはフィルターを通して飲む方法が一般的なので、心配する必要はありません(編集部:コーヒーの飲み方と健康効果については、特集の後半で紹介する予定です)。
当時はこのような理由から「コーヒーは体に良くない」という論調が優勢でした。しかし、前回もお話ししたように、私どもが実際に研究を始めてみると、飲酒による肝機能障害の保護効果がわかり、さらに痛風の原因となる尿酸値も下げることもわかってきた。実は、「コーヒーを飲んでも悪いことは何もないのではないか」と思ったわけです。「コーヒーの効果をもっと探りたい」と私の中での興味が高まっていったのです。
糖尿病患者、予備軍は2000万人!
古野さん そんななか、2002年にオランダのヴァン・ダム教授らが「コーヒーを1日7杯飲む人は、1日2杯以下の人に比べて2型糖尿病発症リスクが50%下がる」という発表を「ランセット(Lancet)」という科学雑誌に発表しました。約1万7000人のオランダ人男女を平均で7年間追跡した結果をまとめたものです。この研究結果は世界中に大きな影響を及ぼしました。
それ以降、フィンランド、スウェーデン、米国でも続々と糖尿病に対して効果があるという報告が発表されました。それらによって「コーヒーが2型糖尿病の発症を予防する」ことはほぼ確実ではないか、と考えられるようになったわけです。
すみません。2型糖尿病というのは…。
古野さん 糖尿病には、遺伝的素因が強い1型糖尿病と、生活習慣病としての2型糖尿病があります。成人で発病する糖尿病のほとんどは2型糖尿病です。
厚生労働省の2012年「国民健康・栄養調査」結果の推計によると、糖尿病が強く疑われる人が約950万人にも達しています。病気の可能性を否定できない「糖尿病予備群」も1100万人と非常に多い。
ヨーロッパなどの研究は、患者の自己申告や薬を投与しているかどうかなどのデータを基に行われていました。しかし、糖尿病かどうかを正しく判定するには、「75g経口ブドウ糖負荷試験」を行う必要があります。
「75g経口ブドウ糖負荷試験」というのは、空腹時血糖値を測定した後に、ブドウ糖を投与して、血糖値がどう変化するかを測定する検査です。ブドウ糖を投与した2時間後の血糖値をみると、その人の糖の処理能力、つまり血糖値を下げるインスリンがしっかり機能しているかという「耐糖能」を見ることができます。2時間後の血糖値が200mg/dLを超えていたら完全に糖尿病です。140mg/dL未満なら正常、140以上200未満は「耐糖能障害」と診断されます(なお、空腹時血糖値が126mg/dL以上なら、2時間後血糖値の値によらず糖尿病と判断される)。
75g経口ブドウ糖負荷試験の結果を基に、コーヒーと糖尿病の関係を調査した研究はそれまではありませんでした。私どもは、前回お話しした男性自衛官の研究で検討しました。その結果、コーヒーを飲まない人に比べて、コーヒーを1日に1~2杯飲む人は4割も耐糖能障害が少ないことがわかったのです。この結果は2004年に発表しました。
コーヒー1日5杯で血糖値が下がった
古野さん 2008年からは九州大学で「介入研究」に着手しました。介入研究というのは、病気と因果関係があると考えられる要因に積極的に介入して、その有効性を検証しようというものです。つまり、コーヒーを飲まないようにしたグループと飲んでもらうグループで、糖尿病に関わる数値がどう変化するかを実際に確かめたわけです。
研究に参加してくれた対象者は、新聞などに広告を出して募集しました。その中から、40~64歳の男性で、BMIが25~30の太り気味の人、コーヒーを毎日飲む習慣がない人などの条件をクリアした人を選び、49名が試験に参加しました。最終的に、43人を対象にして結果を分析しました。
試験は、具体的にどのように進められたのですか。
古野さん 被験者には、インスタントコーヒーを1日5杯ずつ、16週間にわたって飲んでもらいました。海外の同様の研究では、2週間、4週間といった短期間の研究ばかりだったので、思い切って16週継続したのです。参加者は無作為に3グループに分けました。ちなみにコーヒーには砂糖やミルクは一切入れないというルールです。
* 1. 普通のコーヒー(カフェインを含む)を毎日5杯飲むグループ
* 2. デカフェコーヒー(カフェイン抜き)を毎日5杯飲むグループ
* 3. 非コーヒー(ミネラルウォーター)グループ
試験開始前の2週間は、全員にカフェイン摂取を禁止してもらい、飲用期間の前後3回にわたって「75g経口ブドウ糖負荷試験」を行いました。実施された負荷試験によって、飲用スタート前と16週後の変化率を示したのが次ページのグラフです。
デカフェでも効果あり!
古野さん 普通のコーヒーを飲んだグループは、2時間後の血糖値が実験前、つまり16週前よりも平均で10%弱低下し、非コーヒーのグループはプラスとなりました。つまり、コーヒーを飲まなかったグループは、時間経過によって血糖値が上がり、コーヒーを飲んだグループは血糖値の上昇が抑えられたわけです。デカフェコーヒーを飲んだグループは、血糖値に変化はなかったものの、肥満度の変化を補正したデータを見ると、通常のコーヒーとほぼ同等の結果になりました(グラフ内のデータは補正済みのもの)。
調査開始時と16週後の血糖値の変化(九州大学調査、2008-2009年)

普通のコーヒーを飲んだグループは、「75g経口ブドウ糖負荷試験」の2時間後の血糖値が 16週前よりも平均で10%弱低下した。デカフェコーヒーを飲んだグループは、血糖値には変化はなかったが、肥満度の変化を考慮して調整したところ、通常のコーヒーとほぼ同等の結果となった(グラフは肥満度の変化を調整した数値、Journal of Nutrition and Metabolism 2012)
[画像のクリックで拡大表示]
なるほど、何もしないでいるとじわじわと上がっていく血糖値を、コーヒーが抑えたのですね。血糖値上昇を抑える効果も、コーヒーのクロロゲン酸によるものなのですか?
古野さん そうですね。血糖値上昇を抑える効果も、おそらくクロロゲン酸の作用が効いているのではないかと考えています。インスリンを分泌する「膵β細胞」にクロロゲン酸が保護的に働く、クロロゲン酸が腸管での糖の吸収を抑制する、血糖値を上昇させる酵素の働きを抑えるなどの報告があります。
私は主に、コーヒーの肝機能、痛風、糖尿病への効果を研究してきましたが、他にも肝臓がんの予防に効果があるなどコーヒーの効用は多く報告されています。人間が長く飲み続けてきた日常的な飲み物が、このようにいろいろな側面で健康に役立つというのは素晴らしいことだと思います。
◇ ◇ ◇
次回は、男女を問わず誰もが気になるコーヒーのダイエット効果に迫る。ポリフェノールや体内の脂質の代謝に詳しい、品川イーストワンメディカルクリニックの理事長で、日本ポリフェノール学会の理事長も務める板倉弘重医師に詳しく話を聞いた。
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年08月01日 18:53
賛が否を大きく上回ってきている昨今の珈琲健康論議。。。Vol.2
■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~
「コーヒーはがんに効果あり」は本当か?
第2回 “肝臓がんを抑制する”は「ほぼ確実」――国立がん研究センター 笹月静さんに聞く
柳本操=ライター
みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、体にいいことづくめだった! 以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが続々と明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。第2回となる今回は、わが国の大規模疫学調査によって明らかになってきた「コーヒーとがん」について。日本のがん研究の総本山ともいえる国立がん研究センターに最新事情を伺った。
「健康な状態で長生きしたい」と思いつつも、誰もが「いつかかかるのでは」と心配になるのが「がん」という病気。今や、日本人の2人に1人がかかるといわれる国民病だ。
若いうちは「自分には無縁」と思っていても、40代、50代になり、身近な人や有名人ががんにかかったという話を耳にすれば、「発症を防ぎたい」「予防できる方法があるなら知りたい」と思うようになる。コーヒーががんに効くなら、コーヒーを飲む機会を増やそうと思う人も少なくないはずだ。
前回の記事でも触れたように、以前、コーヒーは「発がん性がある」と思われていた時期がある。しかし最近では、コーヒーは「がんに効果がある」という報道を耳にするようになった。最新の研究ではどう判断されているのか。効果があるとしたら、どの部位のがんなのか――。
先に結論をいうと、肝臓がんと子宮体がんの予防に効果が期待できる。国立がん研究センターによる調査・研究によると、肝臓がんを抑える効果は「ほぼ確実」、子宮体がんを抑える効果は「可能性あり」と判定されている。肝臓がんのような特定のがんについては、コーヒーを日々飲むことで発生リスクを抑えられる可能性があるわけだ。
今回は、「日本人にとってどのような生活習慣ががん予防につながるのか」をテーマに研究を行っている国立がん研究センター 予防研究部部長の笹月静さんに詳しく話を聞いた。
◇ ◇ ◇
日本人の生活習慣とがんの関係を20年以上にわたって調査
そもそもの話になりますが、国立がん研究センターでは、食事などの日々の生活習慣とがんとの関係について、どのように調査、研究しているのでしょうか。
笹月さん 国立がん研究センターでは、がんなどの病気と生活習慣との関連を長期間にわたって研究してきました。ここで用いられているのが「コホート研究」という手法です。国立がん研究センターでは、1990年から国内で開始、現在も追跡調査が続けられ、研究結果が日々蓄積されています。
「コホート」とは、年齢や居住地など一定の条件を満たす特定の集団のことです。現在、岩手県、長野県、東京都、沖縄県、大阪府、高知県など全国の一般住民14万人を対象に研究が行われています。余談ですが、「コホート(cohort)」の語源は古代ローマの歩兵隊で、300~600人ほどの兵隊の群を意味します。
最初に対象者に主に対面でアンケート用紙を配布し、健診に参加する方の場合は血液試料や健診データについても提供していただきます。さらに5年後、10年後、というふうにアンケート調査を行っていきます。その中で、がんにかかる方、糖尿病にかかる方などが出てくるので、それらの病気と生活の関連をみていく研究です。扱う内容は、食事内容はもちろん、喫煙や飲酒、体格、運動、さらに睡眠やストレスといった社会心理学的要因など、多岐にわたります。
お酒が好きな人、喫煙者、熱心に運動をする人などが混在する一般住民の大集団を対象に、まっさらの状態からスタートし、10年、20年と追跡していくわけです。
時間も手間もかかりそうな調査ですね。
笹月さん だからこそ研究結果の信頼性が高まると考えています。
私達の研究グループは、国内で行われている研究を基に、日本人のがんと生活習慣との因果関係の評価を行っています。同様の研究は国際的な研究機関でも行われていますが、欧米人と日本人は体格も違うし、食べているものも違うために、海外の研究が主体の評価基準をそのまま日本人に当てはめて考えるのは難しい面があります。日本人を対象とした研究に限定して、がんとの因果関係を評価し、がんを予防する手立てをお伝えすることが重要と考えています。
国立がん研究センターのコホート研究は、10年、20年という追跡期間を経て、2000年代から続々と結果がまとまってきました。その研究を含めて、科学専門誌などに掲載されたがんの研究結果から、評価の対象になる方法(コホート研究と症例対照研究)で実施された論文をピックアップして、それぞれについて科学的根拠や信頼性なども併せて評価しています。
その評価の結果を、全体および個々の部位について、国立がん研究センターのホームページで公開しています。
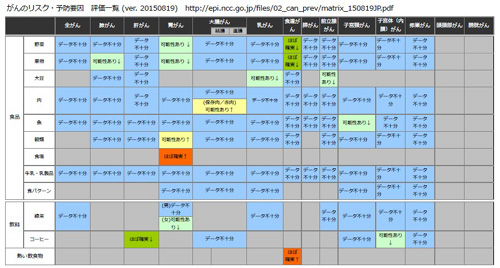
国立がん研究センターの「科学的根拠に基づく発がん性・がん予防効果の評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究のエビデンス評価」の一部。コーヒーの評価は図下側の飲料の欄にある(国立がん研究センターのホームページより一部抜粋)
画像を拡大
コーヒーの「肝臓がんのリスクを下げる」効果は「ほぼ確実」
具体的に、コーヒーとがんの罹患については、どんなことがわかってきたのですか。
笹月さん 現在は、肝臓がん、子宮体がん、大腸がん、子宮頸がん、卵巣がんの評価を掲載しています。それぞれ以下のような評価になっています。
* 「肝臓がん」のリスクを下げる効果=ほぼ確実
* 「子宮体がん」のリスクを下げる効果=可能性あり
* 「大腸がん」「子宮頸がん」「卵巣がん」のリスクを下げる効果=データ不十分
「ほぼ確実」「可能性あり」といった言葉は「科学的根拠としての信頼性の強さ」を示す指標のことです。最も信頼性が高い評価から順に「確実」→ 「ほぼ確実」→「可能性あり」→「データ不十分」となっています。例えば、「喫煙」と「肺がん」との因果関係の評価は、最も信頼性が高い「確実」。つまり、たばこは肺がんのリスクを高めるのは確実というわけです。昨年話題になった「保存肉/赤肉」は、大腸がんのリスクを高くする「可能性あり」になっています。
コーヒーについては、肝臓がんに対する予防効果が「ほぼ確実」になっています。つまり、コーヒーをよく飲む人は肝臓がんにかかりにくいわけですね。
笹月さん 肝臓がんのがん予防効果は、2000年代から「効果あり」というエビデンスが集まり始めました。これ以降、複数のコホート研究によって一致して「コーヒーはがんに予防的に働く」となったために、上から2番目の「ほぼ確実」の評価となっています。
国立がん研究センターのコホート研究では、40~69歳の男女約9万人について、調査開始時のコーヒー摂取頻度により6つのグループに分けて、その後の肝臓がんの発生率を比較しました。調査開始から約10年間の追跡期間中に、肝臓がんにかかったのはそのうち334名(男性250名、女性84名)です。
その結果は、「コーヒーをほとんど飲まない人と比べ、ほぼ毎日飲む人は肝臓がんの発生リスクが約半分に減少する」というものでした。1日の摂取量が増えるほどリスクが低下しました。1日5杯以上飲む人では、肝臓がんの発生率は4分の1にまで低下していました。
これらの結果からも、コーヒーをたくさん飲んでいる人が肝臓がんの発生リスクが低くなるのは、おそらく事実といっていいでしょう。特に「ほとんど毎日」「毎日1~2杯」「毎日3~4杯」「毎日5杯以上」飲む人についてのデータは、統計学的に有意なデータが出ています。「ほとんど毎日」以上の方々は、はっきりリスクが下がっていると言えます。さらに、多く飲んでいる人ほどリスクは下がっているという傾向も出ています。
コーヒー摂取量と肝臓がんの発生率の関係
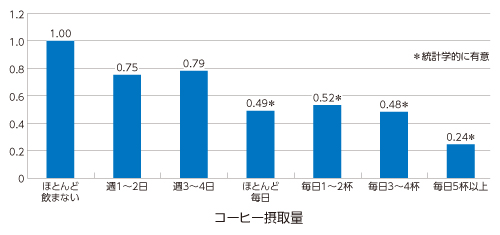
コーヒーをほとんど飲まない人と比べ、ほぼ毎日飲む人では肝臓がんの発生リスクが約半分に減少した。1日の摂取量が増えるほどがん発生リスクが低下した。また、リスクの低下は男女に関係なく見られた(国立がん研究センターの多目的コホート調査による結果、2005年)
[画像のクリックで拡大表示]
世界のがん研究をとりまとめる米国がん研究機構による最新の要約を見ても、肝臓がんリスクを下げる飲み物としてコーヒーが浮上しています。肝臓がんの最大のリスク要因である肝炎ウイルス感染の有無で分けても、同様に肝臓がん発生リスクが低くなることがわかっています。
大腸がんに関しては、以前はリスクを下げる「可能性あり」に分類されていましたが、最新の情報では「データ不十分」となっています。
笹月さん 一昨年まとめられたコホート調査によって、がんリスクを上げるという新たな結果が出てきたためです。多くの結果はがんリスクを下げるか、中立的なものなのですが、研究を統合して解析するメタ解析の結果、関連性は見えなくなり、研究班で討議を行い、判定を下げたほうがよいだろうという結論になりました。このように、常に新しい研究結果も追加しながら判定して、その都度情報を更新しています。
子宮体がんについては、2008年の多目的コホート研究の結果から、1日1~2杯、3杯以上飲むグループではそれぞれ、罹患リスクが低下しているという結果や、他の研究結果から「可能性あり」に分類しています。
このように、大腸がんについては「データ不十分」となりましたが、がん予防に効果的な部位も示されています。コーヒーを適度に飲むことは予防的な手段の一つと判断できるでしょう。
「糖尿病予防」効果と「抗酸化作用」の両面から効いている?
数あるがんの中で、なぜ肝臓がん、子宮体がんに対して、効果が期待できるのですか。
笹月さん 私たちは、コーヒーががんに作用するメカニズムの研究を直接しているわけではありませんが、肝臓がんや子宮体がんは糖尿病を発症するとかかりやすくなるがんであることがわかっています。一方で、コーヒーが糖尿病を予防することも、すでに多数報告されています。コーヒーによって糖尿病リスクが下がればがんリスクも下がる、ということは十分に考えられます。
また、コーヒーにはポリフェノールの一種である抗酸化物質のクロロゲン酸が豊富に含まれています。クロロゲン酸には、血糖値を改善するほか、体内の炎症を抑える作用があります。クロロゲン酸を継続摂取することもがんに予防的に働いているのではないかと考えています。あくまで推測ですが、コーヒーは「糖尿病予防」効果と「抗酸化作用」の両面からがんを抑制する働きをしていると考えられます。
コーヒーを飲むと、心臓病のリスクが軽減
話が変わりますが、国立がん研究センターは昨年5月に、「コーヒーを飲むと、心臓病のリスクが軽減する」という研究報告を発表されましたね。ニュースなどで大きく取り上げられました。
笹月さん 緑茶やコーヒーなどについての研究結果に対する関心は一般に高いのですが、予想以上に大きくマスコミに取り上げられたので驚きました。
この調査も、国立がん研究センターのコホート研究に基づいて導き出されたものです。緑茶とコーヒーの摂取と、全死亡リスク、がん、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患などの死亡リスクとの関連を解析しました。
コーヒー摂取と全死亡リスク
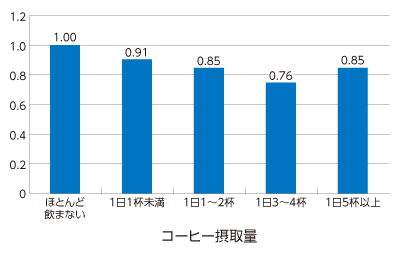
コーヒーをほとんど飲まない人と比べ、コーヒーを飲んでいる人の死亡率は低下する傾向が確認された。コーヒーを1日3~4杯飲む人の死亡リスクは、ほとんど飲まない人に比べ24%低い。飲む量が増えるほど危険度が下がる傾向が、統計学的に有意に認められた(国立がん研究センターの多目的コホート調査による結果、2015年)
[画像のクリックで拡大表示]
コーヒーについては、「1日3~4杯飲む人は、ほとんど飲まない人に比べ、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患の病気で死亡するリスクがそれぞれ4割程度減少する」といった結果が出ています。全死亡リスクについては、コーヒーを1日3~4杯飲む人の死亡リスクは、24%低いという結果になりました。ただ、今回の取材のテーマであるがん死亡の危険度については、この調査では有意な関連性は見られませんでした。
◇ ◇ ◇
国立がん研究センターでは、数年前に新たなコホート調査を立ち上げた。1990年代当時に比べ国民のコーヒー摂取量は増えていることもあり、今後、新たな知見が報告される可能性は十分にあるだろう。
来週のコーヒー特集では、コーヒーの糖尿病などの生活習慣病への効果について、国立健康・栄養研究所の古野純典所長に話を聞く。コーヒーは糖尿病だけでなく、痛風や肝機能にも効果があるという、ミドル必見の効果が明らかになる。
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年08月01日 17:59
賛が否を大きく上回ってきている昨今の珈琲健康論議。。。
■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~
「からだに悪いコーヒー」が「飲むべきくすり」に!
第1回 “コーヒー悪者説”が覆された歴史――東京薬科大学名誉教授 岡 希太郎さんに聞く
柳本操=ライター
みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、体にいいことづくめだった! 以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。第1回目となる今回は、12年間にわたりコーヒーの薬理効果を研究してきた“コーヒーの伝道師”岡 希太郎さんにコーヒー悪玉説が覆った経緯などを伺った。
最新の研究により、「コーヒーは健康にいい」ことが次々と明らかになっている。「コーヒーを飲む習慣があるとがんにかかりにくい」「肝臓にいい」「脂肪燃焼効果がある」など、“コーヒーの健康効果”が相次いで発表されている。
とはいえ、「子どもは飲んじゃダメ」「妊婦には危険」などとよく言われるように、タバコや飲酒などと同様、健康を損ねるというイメージがいまだにある。コーヒーはカラダにいいのか悪いのか――半信半疑の方も多いと思う。
日経グッデイのコーヒー特集では、「コーヒーの健康効果」の最新事情を専門家の方々に聞いた。初回にご登場いただくのは、東京薬科大学名誉教授でコーヒー研究家の岡 希太郎さん。「毎日コーヒーを飲みなさい。」(集英社)、マンガ「珈琲一杯の元気」(医薬経済社)などコーヒーと健康に関する著書を多数手掛けている “コーヒーの伝道師”だ。
◇ ◇ ◇
「コーヒーが健康にいいのは間違いない」
ここ数年、「コーヒーは健康にいい」というニュースを目にする機会が増えました。「がんにかかりにくい」「肝臓にいい」「糖尿病にもいい」「脂肪を燃やす」など効果もさまざまですね。
岡さん 「コーヒーはカラダにいい」という研究成果が毎年のように出てきています。多方面にわたって健康効果が確認され続々と報告されるので、コーヒーの研究をしている私自身が、その多さに参ってしまうくらいです。コーヒーが健康にいいのは間違いないでしょう。私自身は「コーヒーはくすり」だとよく言っています。
最近、一番話題になったのが、昨年5月の東京大学と国立がん研究センターによる発表です。「緑茶やコーヒーを飲む習慣のある人は、心臓病や脳卒中などによる死亡リスクが低下する」という疫学調査です。「コーヒーを1日3~4杯飲むと、心臓病死の危険性が4割減る」と新聞・テレビなどで大きく取り上げられました。私はコーヒーの健康効果について取材を受けることが多いのですが、このときは各メディアから取材依頼が殺到して大変でした。この発表で、「コーヒーはカラダにいい」という認識がより一層定着してきたように感じます。
岡さん コーヒーとお茶は、ともに世界中の人々に飲まれている存在ですが、どちらにも共通するのが、カフェインとポリフェノールという炎症予防作用と抗酸化作用がある物質を両方含んでいることです。カフェインやポリフェノールは、脂肪を燃やす働きがあるなど、さまざまな薬理効果を持っているのですが、両方あると相乗効果が出るのです。「カフェインとポリフェノールの相乗効果」と呼ばれるものです。
コーヒー1杯に含まれるカフェインとポリフェノールは、浅煎りのレギュラーの場合でそれぞれ100mg、200mg程度です。緑茶(煎茶)の場合はそれぞれ半分の50mg、100mg 程度となっています。コーヒーほどではありませんが、お茶も両成分を多く含みますから、健康効果を期待できます。ただ、疫学研究ではコーヒーの研究が圧倒的に多いため、コーヒーの健康効果の方がマスコミなどで多く取り上げられるのです。日本で緑茶の疫学研究が少ないのは残念ですね。
いま注目は「血液サラサラ」効果!
さまざまあるコーヒーの健康効果の中で、今、岡先生が一番注目しているものは何ですか?
岡さん コーヒーの健康効果は、がん予防や2型糖尿病の改善、脂肪燃焼の予防などいろいろあります。それらの中で、私が今、最も注目しているのが「血液サラサラ効果」です。
主なコーヒーの健康効果
がん予防(肝がん、子宮体がん)
2型糖尿病の予防
気分しゃっきり、覚醒効果
血液サラサラ効果
脂肪燃焼の促進
運動時のパフォーマンスを上げる
コーヒー特集ではこれらの効果のうち代表的なものを順次取り上げていきます。次回は、誰もが気になる「がん」との関係を取り上げます。
血液サラサラですか? コーヒーには、タマネギや納豆のような効果があるのでしょうか。
岡さん コーヒーにも、血液サラサラ成分が入っています。コーヒーにはポリフェノールの一種であるクロロゲン酸が多く含まれています。クロロゲン酸は、コーヒーの健康成分として一番知られている存在です。クロロゲン酸は、体に入ると肝臓で代謝されて半分以上がフェルラ酸という成分に変わります。これが血管内で血小板が固まるのを防ぎ、血液をサラサラにするのです。
脂っこい食事を取ると血液はドロドロになり、血小板が活性化して血が固まりやすくなります。これによって血栓ができて血管を塞ぐと、脳梗塞や心筋梗塞などの突然死につながる病気となるわけです。ところが、食事といっしょにコーヒーを飲んでおけば、フェルラ酸が血液をサラサラにしてくれます。
コーヒーの香り成分も血管の若返りに貢献します。コーヒーのなんともいえない馥郁(ふくいく)たる香りは、鼻腔から脳に到達し、リラックス回路を活性化します。このコーヒーの香り成分は空気中に漂う分の何百倍もの量がコーヒーの液体中に溶け込んでいます。コーヒーの香りの中心的存在であるピラジン酸は、血小板が固まるのを強く抑制することがわかっています。
「人は血管とともに老いる」といわれます。「しなやかで丈夫」な血管をキープしたいなら、毎日コーヒーを飲んでおくといいわけです。
昔は発がん性があると考えられていた
「コーヒーが健康にいい」という認識が定着したのは比較的最近のことのように思います。個人的な印象ですが、20~30年くらい前は、カラダに悪いという印象が強かったように思います。いつごろから変わったのでしょう。
岡さん 「コーヒーが健康にいい」と言われるようになったのは、ここ10年ぐらいのことです。それまでは、医師の間でも「健康のためにコーヒーは控えたほうがいい」という意見が多くありました。
コーヒーは、昔は「がんを促進する食品」と思われていたんです。コーヒーは見た目も黒いですし、カラダにいいイメージは持ちにくかったのでしょう。
岡さん 日本の病理学者、山極勝三郎博士は、1915年に世界で初めて人工的にがんを作り出すことに成功したのですが、彼は、煙突掃除夫に皮膚がんの罹患者が多いことに着目して、すすの成分であるコールタールをウサギの耳にひたすら塗り続ける実験を行いました。ほかの研究者が半年、1 年であきらめる中、彼は3年間コールタールを塗り続け、世界で初めて人工的にがんを発生させることに成功しました。コールタールが発がん性物質だということを明らかにしたわけです。
コーヒーは真っ黒だし、焙煎して焦がすから、何となくコールタールに似ていますよね。コーヒーは発がん物質に違いない、という考えが世の中に広まって行ったのです。
調べ始めたら、実は「カラダによかった!」
岡さん コーヒーは欧米を中心に多くの人に飲まれていましたから、当然、コーヒーのカラダに対する影響を調べる研究も盛んに行われました。そして実際に研究を進めたところ、出た結果は逆だったのです。つまり、コーヒーはがんだけでなく、生活習慣病を防ぐし、パーキンソン病などの神経疾患も予防するようだ、といったポジティブな研究成果がどんどん発表され始めたのです。
私が研究テーマをコーヒーに絞ることに決めたのは2004年のことです。当時、コーヒーが健康にいいという研究が世の中に出始めていて、そこに関心を持ったわけです。
2002年には、オランダのヴァン・ダム教授らが「コーヒーを1日7杯飲む人は、1日2杯以下の人に比べて2型糖尿病の発症リスクが50%下がる」という報告を出しました。同教授の追跡調査によって、「コーヒーを1日6杯まで飲んだ人でも、がんや心血管疾患などあらゆる原因による死亡リスクには関係しない」という結果が出ています。
2005年には、日本の国立がん研究センターから「コーヒーをよく飲んでいる人は肝臓がんの発症率が低い。1日5杯以上飲む人は肝臓がん発生率が4分の1になる」という発表も出ました(次回で詳しく紹介します)。
「コーヒー悪者説」は、このように続々と明らかになる研究成果によりひっくり返されることになるのです。今では、医者の間でもコーヒーの健康効果は広く認知されるようになりました。例えば、肝臓関係の医師なら、コーヒーは肝臓にいい効果を及ぼすから、1日1~2杯程度を飲むことを勧めるという人が増えました。
津軽藩士の命を救ったコーヒー
コーヒーはカラダに悪いという前提で研究が始まったのに、出てきた結果は逆だったのですね。科学の進歩で従来の常識が逆転することはありますが、コーヒーはその典型ですね。
岡さん もっと以前は、コーヒーは「くすり」として扱われてきたのですよ。コーヒーが9世紀から10世紀ごろ アフリカ・エチオピアからアラビア半島にわたってきたとき、イスラム教の僧院ではコーヒーを秘薬として珍重したのです。コーヒーを飲めば徹夜の修業にも耐えられるためです。
日本にコーヒーが入ってきたのは江戸時代のことですが、コーヒーはビタミン不足による壊血病に効くという記録が日本にも残っています。
江戸時代末期の文化2年(1805年)。帝政ロシアは植民地を開発しようと、当時鎖国していた日本の蝦夷地(北海道)周辺にまでロシア船を出没させていて、これに対抗するため、江戸幕府は本州最北端の津軽藩士に宗谷岬の北方警備を命じました。ところが、苛酷な自然環境により一冬で100人中72人の越冬死者が出ました。ビタミン不足による壊血病が原因です。
それから50年後の安政2年(1855年)には幕府は蘭学者の指導のもと、コーヒー豆を藩士に配給しました。その結果、一人の死者も出なかったのです。当時の記述には『和蘭コーヒー豆、寒気をふせぎ湿邪を払う。黒くなるまでよく煎り、細かくたらりとなるまでつき砕き二さじ程を麻の袋に入れ、熱い湯で番茶のような色にふり出し、土瓶に入れて置き冷めたようならよく温め、砂糖を入れて用いるべし』と記されています。
◇ ◇ ◇
次回 からは、コーヒーと病気予防の関係について、さらに掘り下げていく。明日、1月27日には、コーヒーとがんの最新事情について、国立がん研究センター 社会と健康研究センター予防研究部部長 笹月静博士に話を聞く。コーヒーは特定のがんに対する予防効果があることが、国立がん研究センターの長年にわたる研究から明らかになっている。
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年08月01日 17:41
歯の健康Vol.4/結局のところは日常の自らのケアと信頼できる歯科医探し。。。
■本当に「いい歯医者」を見分ける5つの条件
「自宅の近所だから」と選んでいませんか?
日本全国に約6万9000カ所。何の数字かといえば、これは歯医者(歯科医院)の数だ。何とコンビニエンスストアの1.3倍にも上るだけに、街のあちこちで見かける。虫歯や歯周病の治療、歯の矯正、親知らずの抜歯など、口腔内にかかわる何らかの悩みを解決してくれる存在である。
歯医者をどんな基準で決めていますか?
ここで、読者の皆さんに伺いたい。あなたはどんな基準で「かかりつけの歯医者」を決めていますか?
「自宅や仕事場に近いから?」「知人が紹介してくれたから?」
人それぞれに事情はあるだろうが、いい歯医者の見つけ方がわからず、「何回通っても治療が終わらない」などという不満を抱えていても、ズルズル同じところに通っている……そんな人も多いのではないだろうか。
いい歯医者と、そうではない歯医者。見分ける方法はあるのだろうか。TBSテレビ「この差って何ですか」(6月14日<日>放送)取材班は、この差を徹底調査。全国174人の現役歯科医に、「いい歯医者だと思う条件」を聞いた。現職のプロが考える本当にいい歯医者。そのベスト5を紹介しよう。
【第5位】すぐに虫歯を削ろうとしない(38人/174人が回答)
聞いたことがある人も多いかもしれないが、虫歯だからといってすぐに歯を削るのはどうやらあまりよくないらしい。基本的に歯は削れば削るほどもろくなり、削ったところからまた細菌に感染して虫歯になりやすい状態になってしまうようだ。
どうしても削るなら、マイクロスコープを使う
そのため、どうしても削らなければならない場合は、マイクロスコープなどの拡大鏡をのぞきながら、なるべく虫歯のところだけを削るように努力するのが、いい歯医者。
さらに今は、ドックスベストなどという薬を使って虫歯の進行をおさえるなど、従来であれば削る虫歯でも、削らなくても大丈夫なケースも出てきている。ただし、この治療は保険がきかないようなので、主治医との十分な相談が必要になる。
【第4位】治療前に歯科衛生士が口の中を掃除する(52人/174人が回答)
歯科衛生士とは、虫歯の予防などを指導する専門職であり、医師による診察・治療の前に患者の口の中をきれいに掃除をしてくれる専門スタッフ。口の中は細菌だらけのため、十分なクリーニングをせずに治療を行った場合、汚れごと歯の型をとったり、汚れを巻き込んだ状態で詰め物をしたりして、治療の結果がよくならない。
今回取材したクリニックの中には、3名の医師に対して9名の歯科衛生士がいるところも。歯科衛生士による口内クリーニングは医師による治療と同じぐらい、とても重要なのだ。
【第3位】治療のたびに歯の写真を撮影する(66人/174人が回答)
歯の写真といわれて「レントゲンのこと?」と思う人も多いかもしれないが……「写真」である。専用のマウスピースをはめて口の中をカメラで撮影するのだ。
レントゲンを撮るのではなく・・・
これには一体どういう意味があるのか。実際、写真撮影を行っているクリニックに聞くと、歯の写真を撮影することで、患者自身に自分の口の中をしっかりと確認してもらい、治療の方針説明などに使うという。
中には患者が帰ったあと、撮影した写真を見ながら症例を振り返り、スタッフ一同で検討会をするというケースも。「ボクの中で写真撮影のない臨床は考えられない!」と断言する歯医者さんもいた。
丁寧な診察を心がける歯医者は良い
【第2位】自分が不得意な治療は断る(81人/174人が回答)
いちばん意外だったのがこれ。なんと、本当にいい歯医者は自分が不得意(専門性が低い)と思う治療が必要な患者にはきちんとその旨を伝え、診察・治療は行わず、患者が希望すれば、適任の医者を紹介するというのだ。
私たち患者側からすれば、ちょっと意外だが、「歯医者」といっても虫歯や歯周病治療を主とする一般的なクリニックから、審美歯科専門のクリニック、抜歯・インプラントなどを得意とするクリニック、さらには手術を必要とするようないわゆる口腔外科治療が中心のクリニックまでさまざま。
いまどきは病院のホームページなどをチェックすると、そのクリニックの先生の経歴などが記載されていて、どんなジャンルの治療をより得意としているかが分かるが、そうした情報をチェックしないまま来院した患者には、より適したクリニックを紹介する必要があるというのだ。
ちなみに、今回取材したインプラント専門の歯医者さんは、「もう何十年も虫歯治療はしていない。自分の家族に頼まれてもやらない!」と衝撃の告白。もちろん、インプラント治療をメインに掲げているクリニックの先生でも、虫歯が治療できないということはないのだが、自分が治療してもらうなら、やはりより専門性の高い先生に診てもらいたいものだ。
【第1位】初回の診療時間が長い(96人/174人が回答)
最も多くの歯科医師が「いい歯医者」を見分けるためのポイントとして挙げたのが、「初回の診療時間の長さ」だった。
歯の痛みが改善しない原因は2つあるといわれる。「診断を間違えている」または「治療を間違えているか」。そのため、治療の技術は勿論のこと、大事なのは正しい診断をすること。そのためには患者の話をよく聞きよく会話をする必要があるのだという。ケースによっては、初診時は説明だけで終わってしまうこともあるというから驚きである。
「あの歯医者は話ばかり長くて、さっさと削ってくれない!」などと思ったら大違い。その歯医者さんは素晴らしい歯医者さんかもしれません。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2017年08月01日 17:27
虫に刺され易く、また極端に腫れ易い私にとっては深刻な課題です。。。Vol.2
■“蚊に刺されやすい人”必見! 専門家がすすめる蚊刺され対処法
子どもはダメ? 蚊の虫よけ剤、選び方、塗り方のコツ
成分濃度の差は何か…などプロに聞いた!
足立雅也=日本防疫殺虫剤協会技術委員
肌の露出が増える夏は、蚊も血を吸おうと活発になる季節。蚊に刺されないためには、人の体に直接使い、血を吸わせないようにする「虫よけ(忌避剤)」をうまく使うことが重要です。虫よけの選び方・使い方について、日本防疫殺虫剤協会技術委員を務める足立雅也さんにお話を伺いました。「虫よけはこまめに塗り直して、効果を持続させるようにしてください」と足立さんは話します。
この記事のポイント
* 蚊の防除には「医薬品」または「防除用医薬部外品」を使用する
* 有効成分「ディート」の濃度の濃度の違いは持続時間。蚊の忌避効果の程度に差はない
* 蚊は虫よけのかかっていないわずかな隙間を刺してくる。「塗りムラ」はなくす
* 子どもにディートを使用する際は回数に制限があることに注意
* 天然成分は栽培の時期や方法によって品質にバラつきが出ることがある
虫よけは医薬品または防除用医薬部外品を選ぼう
蚊の防除対策の一番の目的は、感染症の発生と流行を防ぐことです。そのため、まずは蚊に刺されないための対策から始めましょう。一般的に「虫よけ」と呼ばれる市販の忌避剤にはさまざまなタイプがありますが、その効果や品質、安全性の面から、厚生労働省の製造販売承認を受けた「医薬品」または「防除用医薬部外品」を使用してほしいと思います。
医薬品と部外品の違いは「対象の虫」と「濃度」
虫よけ(忌避剤)の医薬品と医薬部外品の違いは、簡単にいうと、適用害虫(*1)と有効成分の濃度によります。医薬部外品は「人体に対する作用が緩和」なものと定義されており、防除用医薬部外品の適用害虫は、蚊成虫、ブヨ(ブユ)、サシバエ、ノミ、イエダニなどが中心です。一方、医薬品は防除用医薬部外品の適用害虫に加えて、重大な感染症「ツツガムシ病」を媒介するツツガムシに対する忌避効果が適用されています。
*1 適用害虫とは、対象となる虫のことを指します。
体に使用する虫よけの多くは、「ディート(ジエチルトルアミド)」という有効成分が含まれています。現状では、ディートの濃度が12%以上のものは「医薬品」、10%以下は「医薬部外品」と医薬品医療機器等法(旧薬事法)上の分類が異なります。
「濃度の高いほうが、効果が高い」と思われるかもしれませんが、実は蚊の忌避効果に違いはありません。濃度の高いほうが、持続時間が長いということです。
持続時間は、医薬品では6~8時間、医薬部外品でディートの濃度が8%以上だと3~4時間が目安になります。なので、一般的な医薬部外品の場合は、3時間程度を目安に付け直すといいでしょう。また、汗をかいたり、肌を拭いたりした場合は、その都度付け直します。
ディートはもともと、米軍がマラリア予防のために開発したもので、海外では以前から濃度30%以上の虫よけも使用されています。日本では最近まで 12%が最高濃度とされていましたが、厚生労働省が2016年6月に30%まで高めることを通知。製造販売承認の審査を経て、2016年秋には30%濃度の製品が発売されました。
ディート濃度12%と30%の違いも、効力の持続時間です。ディート濃度12%の製品は6時間程度、30%の製品は8時間程度となります。蚊が媒介する感染症(デング熱やジカウイルス感染症など)の流行地域を訪れる場合や、本格的なアウトドアを楽しむ場合などは、より持続時間の長いディート濃度 30%の製品を選ぶとよいでしょう。ただし、汗や水遊びの水で流れてしまうことがあるので、その場合は塗り直す必要があります。
よく勘違いする人が多いのですが、「虫よけは蚊を寄せつけない」わけではありません。塗った皮膚からディートが揮発することで、寄ってきた蚊の感覚をマヒさせ、刺せないようにするものです。
蚊に狙われないよう、虫よけはまんべんなく塗る
ディートが入った虫よけは、高圧ガスが充填してある「エアゾルタイプ」、霧状にミストが広がる「スプレータイプ」、「液体・ジェルタイプ」、「シートタイプ」など、商品の剤型(種類)は多岐にわたります。
「エアゾルタイプ」や「スプレータイプ」は、吹き付けることができます。しかし、ムラができてしまうので、吹き付けた直後に手のひらで塗り広げることがポイントです。蚊は塗りムラを感知して、虫よけのかからなかったわずかな隙間を刺してきます。顔の付近に吹き付けると目に入ったり、吸い込んだりして刺激を受けることがあるので、顔や首筋、耳などには、一度手のひらに吹き付けてから塗り広げるといいでしょう。
「液体・ジェルタイプ」と「シートタイプ」は、手にとって肌にムラなく塗り広げるように使用します。ただし、「エアゾルタイプ」「スプレータイプ」よりディートの濃度が低い傾向があり、1~2時間ごとに塗り直す必要があります。
このほかに、シールタイプやバンドタイプといった身に付けるタイプのものもありますが、ユスリカやチョウバエを対象とし、蚊成虫が対象になっていないものが多く見受けられます。たいていは医薬部外品ではありません。身に付けるタイプを使用する場合は、適用害虫に蚊成虫が表記された医薬品、または、防除用医薬部外品を選ぶようにしましょう。
子どもにディートを使っても大丈夫?
ディートを12歳未満の子どもに使用する場合は、以下のような使用回数の目安と、顔には使用しないことが決められています。これは、カナダ保健省農薬管理規制局の規制に準じたものです。デューク大学の研究で子どもに対する健康被害が報告されたことから、カナダではこのような規制が設けられていますが、厚生労働省による検討会の検証では、その事実は確認されていません。しかし、安全性と適正使用を考慮して、カナダの規制を参考にすることになりました。
子どもへの使用の目安
* 生後6カ月未満:使用しないこと
* 生後6カ月以上2歳未満:1日1回
* 2歳以上12歳未満:1日1~3回
新しい成分「イカリジン」、子どもに年齢制限なく使用できる
ディートの使用に不安がある人には、「イカリジン」の虫よけがお勧めです。イカリジンは、日本では2015年に承認されましたが、1980年代にドイツで開発されたもので、世界50カ国以上で使用実績があります。30年以上にわたって、子どもに対する大きな健康被害の報告もないため、より安全に使用できるといえます。
イカリジンの虫よけには、濃度5%と濃度15%の2種類の製品があり、いずれも防除用医薬部外品です。ディートと同様に、濃度の高いほうが効果の持続時間が長く、濃度5%は6時間程度、濃度15%は5~8時間程度です。
虫よけは原則的には、肌に使用するものです。特にディートは、衣類の上から吹き付けると、繊維を傷めて変色変形が生じることがあるので注意が必要です。一方、イカリジンにはそのような影響はないため、生地の薄い衣類やストッキングの上から蚊が刺してくるような場合には、使用してもよいかもしれません。
天然成分=安全・安心というわけではない
市販の虫よけには「ディート無添加」「化学物質不使用」とする、天然植物由来の製品も多く出回っています。確かに、ユーカリ油(レモンユーカリ油)は、厚生労働省も虫よけ剤成分として推奨しています。ただし、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は、ユーカリ油に含まれるシネオールという物質には中枢神経系や呼吸の問題を引き起こす可能性があるため、虫よけに関して、3歳未満の子どもには使用しないよう注意喚起しています。また、これらの天然植物由来の抽出物を、人の皮膚に塗って、蚊による虫刺され予防の効果効能を表すことは、医薬品医療機器等法上の違反になります。
天然成分は栽培時期や方法などによってバラつきが出る
このほか、レモングラス、ローズマリー、ローズゼラニウム(蚊連草:かれんそう)、ゼラニウム、ミントなどにも虫よけ作用があるといわれていますが、天然植物やそこから抽出したオイルなどは、いつ、どこで、どのように栽培・収穫したかなどによって、品質にバラつきが生じることがあります。
冒頭でもお話ししましたが、蚊の防除対策の一番の目的は、感染症の発生と流行を防ぐことです。その効果と製品の安定性が確かめられているのは「医薬品」「防除用医薬部外品」の承認を受けている虫よけです。天然成分の虫よけは、メーカーによってその効果をアカイエカを使って検証していますので、ある程度の満足感が得られるかもしれません。しかし、中には効果や安全性などの検証をしていないところもありますので、お勧めできません。
(ライター 田村知子)
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年07月28日 16:49
歯の健康Vol.3/歯と歯茎と舌の状態は健康のバロメーター。。。Vol.2
■歯周病という身近な病気の恐ろしすぎる真実
成人の8割がかかる国民病を甘く見るな
小林 保行
歯科医師/キーデンタルクリニック院長
真冬の風物詩でもあり、流行のピークを迎えているインフルエンザ。学校や職場でマスクをする人も増えてきて、日本全国を見渡すと学級閉鎖を余儀なくされている地域もあります。空気が乾燥しやすい季節でインフルエンザに限らず、ノロウイルスなどの細菌・ウイルスによる感染症の警戒ムードが高まっています。
一方、インフルエンザやノロウイルスのように突発的なニュースにはなりにくいものの、厚生労働省の調べによると成人(30~64歳)の7~8割がかかっているとされる感染症をご存じでしょうか。それは「歯周病」です。筆者は歯科医師としての知見や経験を基に、歯や口周りの情報を「ムシバラボ」というサイトで発信していますが、その中でも強く訴えていることのひとつが、歯周病の予防と治療の重要性です。
歯が抜けるだけではない!? 歯周病が及ぼす影響
そもそも歯周病とは何でしょうか。耳にしたことがあっても、正しく知っている人は少ないかもしれません。日本歯科衛生士会ホームページより概要を抜粋しますと、「歯肉・歯根膜・セメント質・歯槽骨で構成される歯周組織が、口の中の細菌感染によって破壊される慢性炎症性疾患のこと」で、成人だけではなく小・中学生などの若年層も多く罹患しているとされています。
適切に歯磨きができていないと、健康な歯ぐき(歯肉)に炎症が起こり、それを改善しないまま深部の歯周組織まで炎症が波及すると、歯と歯肉の境目の溝が深くなり、歯周ポケットが形成されます。これが重症化してしまうと歯がぐらつき始め、残念ながらたくさんの歯を失ってしまうことになりかねません。しかも歯をしっかり磨いていても、気づかずに歯周病になっている人がかなり多いのです。
歯周病を「単に歯が抜けるだけの病気」と片付けてしまうのは大間違いです。最近の研究で歯周病は全身に悪影響を及ぼすことがわかってきているのです。特に糖尿病と密接な関係があるほか、突然死の原因になりかねない心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めたり、失明や手足の切断につながるような重症になってしまったりするのです。
歯周病菌を顕微鏡で観察すると、粒状の物やヘビのようにクネクネ動くものなどさまざまなタイプを無数見ることができます。ある研究によるとこの種類と数が増えるほど歯周病の症状は悪化するようです。ありふれた細菌として見過ごされてきましたが、最近はこの歯周病菌が「さまざまな病気と密接にかかわっているのではないか」と世界中の研究者から報告されています。
恐怖のスパイラルを作り出す! 糖尿病と歯周病の関係
まずは糖尿病です。頻尿や喉の渇き、倦怠感のほか足がつるのは糖尿病の症状。食べ物が歯に挟まる、歯ぐきから出血するのは歯周病の症状です。この2つの病はお互いを悪化させていくという恐怖のスパイラルを作ります。
何がお互いを悪化させてしまうのでしょうか? そのメカニズムを説明しましょう。歯周病になってしまったことで形成された歯周ポケットに歯周病菌が溜まってしまうのが発端となります。ここに免疫細胞である白血球が菌を退治しに集まってきます。
この時、白血球が歯周病菌の出す毒素に触れることで、「TNF―α」と呼ばれる阻害物質を出します。これが血液中のインスリンの働きを妨げてしまう作用があるのです。インスリンは健康な人の体内で変動する血糖を適度に調整する役割があるのですが、この働きが低下すると、糖尿病の症状が悪化してしまうことがあります。
そして糖尿病が悪化すると血糖値が高くなり、今度は歯ぐきの毛細血管の血流が悪化して、血液が行き渡らず歯周病菌を退治できなくなってしまいます。こうして歯周病による歯ぐきの炎症が糖尿病を悪化させ、さらに歯ぐきの炎症を進行させる――。という悪循環に陥りかねません。わずか半年で重度の糖尿病で倒れてしまった患者もいるぐらいです。
逆に糖尿病患者に歯周病菌を減らす治療をしたところ、それまでよくならなかった「ヘモグロビンA1c」と呼ばれる過去1~2カ月の血糖値の状態を示す指標が劇的に改善して、症状がよくなったケースが報告されています。
歯周病菌が血管内に入ると血栓ができやすくなり、突然死を引き起こしかねない心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めるという研究結果も出ています。歯周病菌は心筋梗塞の原因である動脈硬化を進行させることがあるのです。
メカニズムを説明しましょう。口の中に住んでいた歯周病菌は、食事中などで傷ついた口の中の粘膜の毛細血管から血管内に入り込みます。その歯周病菌の刺激により動脈硬化を誘導する物質が出てきて、血管内にプラークと呼ばれるお粥状の沈着物ができることで血液の通り道が狭められ、心臓の冠動脈を硬化させると言われています。このことはヒトの大動脈の動脈硬化症と呼ばれる患者さんの血管の中から5~20%ぐらいの割合で歯周病菌の遺伝子が見つかっていることからも確認されています。
難病・バージャー病の患者は歯周病も診断されていた
もうひとつ、おそろしいのは「バージャー病」という聞き慣れない病気と歯周病の関係です。手足の末端の血管が詰まり、炎症がおき、皮膚に痛みや潰瘍を起こし、最悪の場合は手足を切断しなければならないこともある病気です。
実はバージャー病にかかったすべての患者が歯周病だと診断され、その進行度合いは中度から重症です。痛み、または潰瘍がある部分の血管から採血し、検査を行った結果、血液からは歯周病菌が検出された一方で、正常な箇所からは歯周病菌が検出されませんでした。
歯周病菌は血栓をつくりやすく、皮膚の内側の細胞に進入するとの報告がされています。口の中にとどまらず、体全体に行ってしまい、最悪の場合バージャー病を引き起こすとみられます。これが心臓の近くで起これば心筋梗塞、脳の近くで起これば脳梗塞となる可能性があるのです。
このように放置できない歯周病を予防・治療するにはどうしたらよいでしょうか。まず基本は歯磨き=ブラッシングです。歯と歯ぐきの間を意識して、1 本1本丁寧に磨く意識が必要です。こまめなうがいも欠かせません。一度のうがいでお口の中の細菌がかなり出て行くと言われています。ガラガラうがいだけでなくブクブクうがいもこまめに行いましょう。
とはいえ、毎日しっかりブラッシングしていても、必ず歯石はついてきます。目安としては3カ月に1回、つまり季節ごとに定期検診を受診して歯石を取っていくのが理想です。しっかりと定期的な検診で歯のクリーニングを行い、口の中全体の細菌数を減らすことが免疫力の低下を防ぐことにもつながります。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2017年07月27日 12:01
歯の健康Vol.2/歯と歯茎と舌の状態は健康のバロメーター。。。
■頭痛、肩こり、腰痛の原因は「舌」かもしれない
噛み合わせの悪さが引き起こす体調不良
安藤 正遵
安藤歯科クリニック院長
原因不明の体調不良に悩んでいませんか
「長年、原因不明だった頭痛や肩こりが嘘のように消えました」。筆者が経営する歯科クリニックの患者Aさんは、喜びを口にしました。
頭痛や肩こり、慢性疲労、腰痛など、はっきりとした原因がわからず、なんとなく体が不調だという人は少なからずいます。これを専門的には「不定愁訴」といい、一筋縄では治療できないとても難しい症状とされています。整体や鍼灸などで改善しようとしている患者も少なくないようです。
一方、私は長年の研究と実体験から歯科治療のノウハウが不定愁訴の改善に有効性を示すケースをいくつも知っています。治療から15分足らずで症状が改善した例もあるほどです。ポイントは噛み合わせと「舌」の位置。実際に1996~2013年までに私の経営する歯科クリニックで噛み合わせ治療を行った295人のうち、76%が偏頭痛を、67%が首のこりを改善するなど、さまざまな症状に対する有効性を示しました。無気力、難聴、背中の痛み、肩こり、腰痛などが改善した人も少なくありません。
つらい不定愁訴は、下あごの位置のズレが原因になる場合があります。下あごにズレが生じると頭蓋骨が傾き、首や肩や脊椎のバランスが崩れます。これが不定愁訴に繋がります。
その下あごのズレは、どのようにして引き起こされるのでしょうか。歯科大学では、上下のあごの位置は歯で決まると教えられています。しかし、私はこれまで300人以上の患者さんの噛み合わせ治療を行う中で、この理論に疑問を抱いてきました。
今、これを読んでいるあなたは、つねに上下の歯を食いしばっているでしょうか。答えは「ノー」だと思います。私たちの上下の歯は、食べ物を噛むとき以外は触れ合ってはいません。2mm程度の隙間が空いた状態をキープしています。普段は、下あごは咀嚼筋群という噛むための筋肉によってブランコ状態となっているのです。
歯が下あごのズレの原因でないならば、本当の原因は何なのでしょうか。そうです、その理由が「舌」なのです。「歯並びが悪い」「かぶせものをしている」などの理由で、舌が収まるスペースが狭くなったり、鋭利な歯が舌にストレスをかけていたりすると、舌はつねに緊張した状態を強いられることになります。その舌の状態によって、下あごの位置は左右されているのです。
以前、右下の歯が舌側へ倒れ込むように生えている症例を目にしたことがあります。舌は刺激を避けるために、左へ逃げるようになり、それにともなって下あごも左へずれていました。大きな歪みが生じ、頭痛や腰痛などの体の不調も抱えていました。
歯のアーチが小さく、歯が直立して生えることができずに舌側に倒れ込んでいる症例の治療にあたったこともあります。舌に歯がめり込んでいる状態のため、舌が受けるストレスが相当なもので、不定愁訴の症状も重度なものでした。
戦後、食生活が改善し、飽食の時代に突入したことにより、現代人の歯は変化しました。そのさまざまな変化により、現代人はあごのズレを引き起こしやすくなっています。
あごのズレを引き起こす原因
あごのズレを引き起こす原因は以下の4つが挙げられます。
①歯が大きくなった
現代は栄養状態がよくなったため、日本人の平均身長は50年前に比べて1.08倍になり、それにともなって歯も大きくなりました。歯が大きくなれば、必然的に舌の収まるスペースは狭くなり、舌へのストレスは増大します。
②あごが細くなった
食生活の変化により、噛む回数が減ったことで、現代人のあごは細くなりました。現代人の咀嚼回数は縄文時代の7分の1にまで減っています。あごが細くなったことで、舌の収まるスペースはますます狭くなっているのです。あごが小さくなったため、歯がきれいに収まらず、舌側に倒れ込んでしまう傾向にあります。
③歯が尖っている
現代人はやわらかいものを食べる機会が多いため、歯がすり減らずに尖っている傾向にあります。歯が尖っていると、舌は口の中でつねに緊張状態になり、下あごのズレにつながるのです
④舌の肥大化
現代では、熱中症や健康維持のために水を飲むことを勧める傾向にあります。水を飲むこと自体はいいのですが、舌は血管が豊富な組織のため、体内の水分量に敏感に反応します。水分過多になると、舌も大きくなる傾向にあります。
このように、現代の食生活の変化により、舌が置かれている口内環境は悪化の一途をたどってきました。舌の収まるスペースが狭くなり、さらに舌の肥大化も相まって、下あごのズレが引き起こされています。現代では、ほぼすべての人が何らかの形で舌にストレスをかけているといえます。まさに、下あごのズレとそれにともなう不定愁訴は現代人特有の現代病だといえるのです。
下あごのズレが原因の不定愁訴は、舌が歯から受けるストレスを取り除くことで症状を改善させることができます。私の経営する歯科クリニックでは、わずかに歯を削ることで舌のストレスを無くす独自の咬み合せ治療を実施しています。
従来の咬み合せ治療では、歯の矯正やマウスピースを活用していましたが、その治療法では、歯と舌の関係に問題がある場合は改善ができませんでした。そこで、舌の問題を解決するため、歯の高さだけでなく、大きさ・傾き・尖り具合・被せ物の状態など総合的に診たうえで治療を行っています。
この治療法では、舌のストレスを大幅に取り除くことが期待できます。治療の際は、歯の一番外側のエナメル層を0.1~0.5ミリ程度削って調整します。エナメル層には神経が通っていないので、治療には痛みはありません。早い人は、治療後15分程度で不定愁訴の症状改善を実感できます。他ではどうしても治らなかった不定愁訴の原因を解消し、症状の改善が見込めるのです。
もし、あなたが原因不明の体調不良に悩まされているなら、下記の項目にどれだけ当てはまるかチェックしてみてください。
チェックしてみましょう
□ 噛んだ時のカチカチ音が小さいか、二重音である
□ 首か肩がいつもこっている
□ 口が開きにくい
□ 口を開けるとあごが痛い
□ 口を開けるとあごで変な音がする
□ 腰痛がある
□ 胃腸の調子が悪い
□ 歯ぎしり、食いしばりがある
□ いつもあごの周りの筋肉がこっている
□ 歯科で詰めたかぶせものが高いと感じている
□ 口の中で歯の尖りや邪魔を感じる
【チェック判定】
当てはまる項目の数
●3個未満 噛み合わせの影響は少ないようです
●3~5個 噛み合わせが影響しています
●5~7個 不調は噛み合わせからもきています
●8個~ すぐに咬み合わせ治療を受けることをお勧めいたします
医療機関で治療を試みたにもかかわらず、効果が見られない肩こりや腰痛、偏頭痛、慢性疲労などの症状をお持ちの人は、一度、噛み合わせを疑ってみる必要があるかもしれません。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2017年07月23日 17:41
歯の健康/へえっ〜(驚)
■注意!その体の不調、銀歯が原因かもしれない
アレルギー性皮膚炎や脱毛症だってありえる
小林 保行
歯科医師/キーデンタルクリニック院長
あなたは虫歯を治療したことがありますか?
心当たりのある人の多くは、口の中に金属の詰め物が入っているかもしれません。いわゆる「銀歯」と呼ばれるアレです。
金属のアクセサリーをつけてかぶれてしまう人は、「自分は金属アレルギーじゃないか?」と自分で気づきやすく、アクセサリーをつけることを極力控えることでしょう。歯科治療においても金属はよく使われていますが、この歯科金属も例外なく金属アレルギーを引き起こすことがあります。
ところが、問題は歯科金属がアレルギーの原因になっていても自分では気づきにくいということにあります。自分で気づかなければ対処のしようがありません。筆者は歯科医師としての知見や経験を基に、歯や口周りの情報を「ムシバラボ」というサイトで発信していますが、その中でも強く訴えていることのひとつが、歯科金属アレルギーのこわさです。その特徴や症状、またその対処法について詳しくご説明していきます。
歯科金属アレルギーの特徴
歯科治療では、詰め物やかぶせ物以外にも根の治療後につける土台や、ブリッジ、入れ歯などありとあらゆるものに金属が使用されています。この歯科金属アレルギー患者が日本で年々増加しているという報告があります。
①歯科金属がアレルギーの原因になっていても気づかれにくい
皮膚に身につける金属アレルギーと違うのは、「口の中だけでなく、金属の触れていない全身にも症状が出ることがある」というところです。そのため、症状の原因が歯科金属アレルギーと分からずに苦しんでいる人も少なくありません。
②保険の金属は口の中で錆びやすい
保険で使われている金属は、高温多湿の口の中では錆びて唾液に溶け出してしまいやすいという欠点があります。その溶け出した金属イオンが体のタンパク質と結びついてアレルギー源となってしまいます。
③長年入れていることで体内に蓄積される
口の中に入っている金属は何年、何十年と入りっぱなしになるため、溶け出した金属は体に蓄積され、それが過剰になることでアレルギー反応が起こるとされています。
④2種類以上の金属が入っているとアレルギーになりやすい
口の中でよく使われる金属にはパラジウム、ニッケル、コバルト、銀などがあります。口の中に種類の違う金属が入っていると、微弱な電流である「ガルバニー電流」が発生し、アレルギーが起こりやすくなることがわかっています。
⑤口の中に炎症があると金属アレルギーが起こりやすい
重度の歯周病や口内炎などの炎症状態が続いているお口の中では特に金属がイオン化しやすく、金属アレルギーを起こしやすいと言われています。
口の中・周囲だけでなく全身にも出る
そして、歯科金属アレルギーの症状は口の中やその周囲に出る場合と、全身に出る場合の2つに大きく分けられます。
口の中・周囲に出る場合は、唾液に溶け出した金属イオンが口の中や周囲にアレルギー反応を起こします。次のような病気があります。
●口内炎・舌炎
口内炎が頻繁にできたり、舌に炎症を起こすことがあります。
●口唇炎・口角炎
唇の周りが赤くただれたり、口の両端(口角)が赤く炎症を起こして切れたりすることがあります。
●口腔扁平苔癬(こうくうへんぺいたいせん)
口の中の粘膜(特に頬っぺたの粘膜)に白い線状、レース状、網目状の模様が現れ、周囲が赤くただれます。触れるとピリピリ痛むことがありますが、無症状の場合もあります。
●味覚障害
アレルギー反応が舌の表面の味の受容体(味蕾)に起こると、味が分かりづらくなることがあります。
全身に出る場合は、体に取り込まれた金属イオンが体内のタンパク質と結合してアレルゲンとなり、汗として排出されるときにその皮膚の表面でアレルギー反応を起こします。重篤化すると鎮痛剤も効かないくらいの痛みを伴う状態になることもあります。
●掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)
掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)とは手のひら、足の裏に多数の膿疱ができる難治性の慢性炎症性疾患です。膿疱は数日で乾燥し、黄褐色となりぽろぽろと皮がめくれてきます。 爪にも膿疱が出来ることもあり、爪が分厚く変形したり、褐色に変色することもあります。掌蹠膿疱症は周りの人にうつることはありません。膿疱はウイルスや細菌によって起こるものではなく無菌性であるからです。また、家族で体質が似て発症することはありますが、遺伝することはないといわれています。
●アトピー性皮膚炎、湿疹
アトピー性皮膚炎、いわゆるアトピーは、花粉症などのアレルギー疾患とともに増加しています。アトピー性皮膚炎の原因としてダニやハウスダストなどが有名ですが、意外に知られていないのが歯科材料(特に金属)です。一般的な治療を行っても、改善が見られない場合は、歯科材料が影響している可能性があります。アトピー性皮膚炎の治療は、現在もなおステロイド外用剤を中心とした対症療法ですが、最も大切なのは原因を見つけ出し除去する事です。
●脱毛症
蓄積された金属が一定のアレルギー許容量を超えると、一気に髪の毛が抜けてしまうことがあることが分かってきています。銀歯による金属アレルギーから円形脱毛症を発症し、髪の毛がほとんど抜け落ちてしまったケースがあります。皮膚科で円形脱毛症と診断され、ステロイド剤による治療を行ないましたが、全く効果が出ず、別な医師による診断で、金属アレルギーであることが発覚し、お口の中の歯科金属を除去したところ、抜け毛が止まり完治に至ったというケースの報告があります。
どうやって治療すればいいか?
口の中に金属が入っていて、上記の症状に心当たりがある人は歯科金属アレルギーの可能性があります。そのような場合はまず、原因となっている金属を特定する「パッチテスト」と呼ばれる検査を行います。これは、皮膚の表面に金属を含んだ試薬を貼り付けて、アレルギーの反応が起こるかどうかを調べるものです。もしもそれでアレルギー反応の出た金属があれば、原因となる金属を全て取り除く必要があります。
原因となる金属を取り除いた後は、アレルギーを起こさない材料で詰め替えやかぶせ直しを行います。具体的にはプラスチックやセラミック、パッチテストで金属アレルギーを起こさないと分かった金属などです。金属アレルギーを起こさないような入れ歯や矯正治療の装置もあります。
もともとアレルギー体質の人、例えば花粉症や喘息、食物アレルギーなどがある人、またはアレルギー体質の人が家系にいる場合には金属アレルギーになりやすい傾向があります。ずっと治らない原因不明の皮膚のただれや湿疹などで悩んでいる人はもしかしたら歯科金属アレルギーが原因かもしれません。放置してしまうと全身へも症状が広がってしまいます。心当たりのある人は一度歯科医院で相談してみることをおすすめします。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2017年07月23日 17:40
虫に刺され易く、また極端に腫れ易い私にとっては深刻な課題です。。。
■蚊、ネコノミ、ヒアリ… 虫に刺されたらどう対処?
夏秋優
兵庫医科大学皮膚科准教授
蚊に刺された後のあのかゆみ。人によっては、長い間かゆみに悩まされます。虫刺され用の市販薬は数多く販売されていますが、どのように選べばよいのでしょうか。虫刺されに詳しい、兵庫医科大学皮膚科准教授の夏秋(なつあき)優先生に、蚊などの吸血性の虫の話を中心にお話を聞きました。最近話題のヒアリについても最後に少し触れています。「蚊などに刺されてかゆい場合は、保冷剤などで刺された所を冷やすと局所の感覚を鈍らせ、かゆみを感じにくくすることができます」と夏秋先生は話します。
■刺されてかゆい蚊はアカイエカ? ヒトスジシマカ?
日本ではアカイエカやヒトスジシマカに吸血されることがほとんどですが、ヤブカの仲間のヒトスジシマカのほうが、かゆみや赤みといった炎症が強く出るのが一般的です。刺された部位による違いはあまりありませんが、例えばまぶたや指など、もともと炎症が起こると腫れやすい部位や、感覚が敏感な部位では、かゆみや腫れがひどくなります。
■炎症がひどい場合はステロイド
蚊に刺された後、症状が軽い場合は自然に治るのを待つとよいですが、かゆみが強いときには、虫刺され用の市販薬で対処するとよいでしょう。
炎症によるかゆみには、原因となるヒスタミンをブロックする抗ヒスタミン成分(ジフェンヒドラミンなど)、スーッとした刺激でかゆみを感じにくくする清涼成分(l-メントールなど)の入ったものが有効です。かゆみが強いときや、もともと炎症が強く出やすい人は、炎症を抑えるステロイド(デキサメタゾン、プレドニゾロンなど)が入った外用薬を選びます。市販薬のパッケージには、有効成分が記載されているので、そこを参考にしてください。薬剤師や登録販売者に尋ねてもよいでしょう。
もし、かき傷があるときは、清涼成分がしみて痛むことがありますが、必ずしも使わないほうがよいというわけではありません。多少しみる程度の刺激があるほうが、かゆみが和らいでよいという場合もあります。それぞれの好みで判断するとよいでしょう。
■かゆみがぶり返す人は予防的にステロイドを塗っておく
刺されてすぐにかゆくなり、一度治まるが翌日再びかゆくなる「ステージ3」(表)の人は、刺されてすぐのかゆみが一旦治まった後に、ステロイド外用薬を塗ると、翌日に再び来るかゆみや赤みがかなり軽くなります。
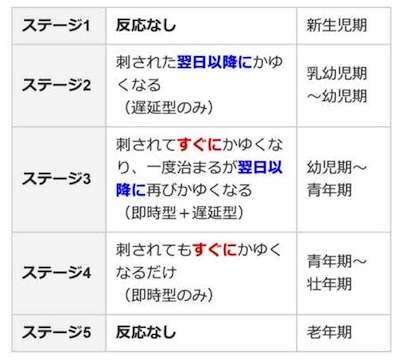
蚊を含む虫刺されに対する反応と日本人に見られやすい年齢の目安(夏秋先生による)
■爪でバツ印をつける、たたく、冷やす、温める…効果はある?
薬剤を使わずにかゆみに対処するとき、いろいろな方法を見聞きします。爪で押さえてバツ印をつける、たたく、冷やす、蒸しタオルで温める、ばんそうこうを貼る、お茶のティーバッグや出がらしを当てる……果たしてこれらに本当に効果があるのか? と聞かれれば、「かゆみを和らげる」という意味では、効果があるといえるものもあります。
◇「爪でバツ印」は傷をつけない程度ならOK
爪でバツ印をつけるというのは、私自身もやることがあります。これは、爪で刺激を与えることで、かゆみを痛みに替えて和らげているのです。ただしこの場合、かゆみから逃れることはできても、力を入れ過ぎて皮膚に傷をつけてしまうと、そこから細菌に感染する可能性があるという別の問題が出てくるので、注意する必要があります。
◇お茶の成分がかゆみを抑えるかは不明
お茶のティーバッグや出がらしをのせるという方法は、お茶の渋みの成分であるタンニンに、炎症を抑える作用があるといわれていることからかもしれませんが、科学的な根拠による実証はされていません。
◇ばんそうこうはかゆみを抑えないものの、かき壊し防止に有効
ばんそうこうを貼るという方法は、それでかゆみがなくなるわけではありませんが、かけなくすることで、患部を守ることになります。特に、子どもの場合はかゆみを我慢できずにかきむしってしまうと、傷から細菌が入ってとびひ(伝染性膿痂疹:でんせんせいのうかしん)になることも多いので、有効かもしれません。ただし、蒸れてしまわないように、通気性のある紙タイプのものを選ぶようにしてください。
◇保冷剤などで皮膚を冷やして感覚を鈍らせるのがベスト
かゆみを抑えるのに一番よいのは、冷やすことです。冷やすと血管が収縮して、かゆみの神経伝達も遅れるので、局所の感覚を鈍らせ、かゆみを感じにくくすることができます。家庭などでは保冷剤を使ったり、外出時なら冷たい缶飲料を買ったりして、刺されたところを冷やすといいでしょう。
人間の知覚には、「生命に危険を及ぼす感覚を優先する」という原則があります。極端な話をすれば、左手がかゆくてたまらないときに、右手を針で刺されたら、左手のかゆみは吹き飛びます。つまり、爪でバツ印をつけるほか、たたく、冷やす、温めるといったほとんどの方法は、かゆみに替わる刺激を与えることで、かゆみを感じにくくさせているのです。
■蚊をつぶしたときの血は、拭き取るか洗い流す
「蚊をつぶしたらどうしたらいいか」ということも、よく患者さんから尋ねられます。吸血中の蚊に気づいてつぶしたとき、自分の血がついてしまったら、ティッシュなどで拭き取ります。
飛んでいる蚊をつぶして、手に血がついた場合は念のため、せっけんで洗い流しておくといいでしょう。例えば、病院の待合室などで吸血して満腹になった蚊をつぶしたときは、その蚊がウイルス感染症の人の血を吸っていた可能性もあります。自分の手に傷があれば、感染のリスクはごくわずかとはいえ、ゼロとは限らないからです。
■蚊以外の虫に刺された場合はどう対処する?
虫に刺された現場を見ていないと、赤みやかゆみが蚊によるものなのか、それ以外の虫によるものなのか、判断するのは難しいもの。人間が薄着になり、虫たちが活発に動き回る夏場は、蚊以外の虫に刺されることも少なくありません。
今の時期に蚊刺されと似た症状が出るのが、ネコノミによる刺症です。ネコノミは、ネコやイヌの体に寄生して吸血します。特にノラネコの移動とともに、庭や公園などに発生していて、そこを通りかかると足元を刺されます。足首やすねのあたりに症状が集中していて、水ぶくれもできるような場合は、ネコノミの可能性が高いでしょう。素足にサンダル履きで出かけるようなときは注意してください。
また、数日前に野山に出かけていたようなときはブユ(ブヨ)に刺された可能性もありますし、家にいて脇腹や下腹部、大腿部の内側などにかゆいブツブツなどの症状があるときはイエダニの可能性も考えられます。
こうしたノミ、ブユ、ダニなど吸血性の虫(有害節足動物)に刺されたときは、基本的にはかゆみや赤みといった局所の炎症が主な症状なので、蚊と同様に対処すればいいでしょう。
ただし、最近話題のヒアリやハチ、あるいはムカデといった虫の場合は、刺咬(しこう)による激しい痛みや腫れだけではなく、体質によっては「アナフィラキシーショック」と呼ばれる、命にかかわる恐れのある強いアレルギー症状が表れることもあります。刺されてから30分以内にじんましんや吐き気、腹痛、呼吸困難といった症状が表れた場合は、速やかに救急車を呼び、医療機関を受診するようにしてください。
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年07月23日 17:39
あくまで主治医は自分自身、、、自らの生を救えるのは自分自身だけとの覚悟をして初めて、医療スペシャリストたちや家族や友人といったサポーターたちを最大限有効に活用できる。。。
■小林麻央さんも悩んだ、日本のがん医療の「運任せ」な側面
窪田順生:ノンフィクションライター
乳がんで亡くなった小林麻央さんが度々、ブログで触れた「後悔」の思い。「もっと別の治療法があったのではないか」とは、多くのがん患者や家族たちが抱く思いなのだが、そもそも日本のがん医療は、病院や医師によって質のばらつきが大きく、運任せのような側面がある。
ステージ4でも回復する人も
なぜがん患者の明暗が分かれるのか?
先月、34歳の若さで亡くなった小林麻央さんが闘病中に綴っていたブログは、人々の心にさまざまなメッセージを突きつけた。
筆者が特に考えさられたのは、4月13日の「浪漫飛行」と題した記述である。
癌だって、ステージ1の時点で診断される人もいれば、気づいた時にはステージ4の人もいる。順調に治る人もいれば余命宣告から奇跡みたいに治る人もいて、そうでない人もいる。
良い方をみても きりがないし、悪い方をみても きりがない。良い方をみてしまうとき、私は、なぜここまでにならなければならなかったのかな、と思うことがありました。もちろん自分自身の過ち 積み重ねなどあるにせよ何故、順調に治っていく道ではなかったのだろう、と。
2010年の結婚から7年、34歳の若さでこの世を去った小林麻央さんの闘病ブログからは、一般人よりも遥かに金銭的に恵まれていても、必ずしも良い病院、医師に最初から出会えるというわけではない、ということが読み取れる
筆者の周囲にも、がんが発覚してから、あっという間に亡くなってしまった人もいれば、ステージ4で余命宣告を受けてから奇跡の回復を遂げた人もいる。彼らの運命を分けた「差」は何だったのか、という思いがかねてからある。
このような「がん格差」に、本人の決断が関係していることは言うまでもない。麻央さんもブログで、「あのとき、もうひとつ病院に行けばよかった あのとき、信じなければよかった」と綴っている。
もし自分が「がん」を宣告された時、果たして悔いのない決断ができるだろうか。なにか「がん格差」を是正するような仕組みはないものか。そんなことをぼんやりと考えていたら、先日発売された『日米がん格差 「医療の質」と「コスト」の経済学』(講談社)の中に、自分なりの「答え」を見つけた。
日米でがん治療を体験した
著者の提案とは?
筆者が見つけた答えが何なのかということを説明する前に、まずはこの仕組みを教えてくれたこの本について簡単に触れておこう。
本書は米スタンフォード大学で医療政策部を設立し、医療ベンチマーク分析の第一人者として知られる医療経済学者・アキよしかわ氏が、医療ビッグデータに基づいて日米の医療を比較し、日米の「がん治療」を巡るさまざまな問題を考察している。
それだけでも十分に興味深いのだが、さらにこの本の価値を高めているのは、筆者自身ががん患者だという点だ。日本とアメリカを行き来きしながら、自らが行ってきた「がん闘病」を赤裸々に語っている。
2014年10月、アキ氏は「ステージ3B」の大腸がんを宣告される。がん研有明病院で手術を受けるも、その後の治療は、ハワイのクィーンズメディカルセンターで受けることとなった。家族と自宅はアメリカで、自分が設立した医療経営コンサルティング会社「グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン」が日本にあるということで、その中間点で治療をすることにしたのだ。
この「日米両国でのがん治療体験」が、本書にさらなる深みを増している。医療経済学者という立場からの客観的なデータ分析をベースに、実体験に基づく調査も加わったことで、データから読み取ることができない、がん患者が直面する問題が浮かび上がり、その具体的な解決策まで導きだされているからだ。
それこそが「キャンサーナビゲーション」である。
アキ氏自身が「本当にこの本で紹介したいこと」と語り、日本にも導入すべきだと主張するこの制度について、端的に説明している箇所があるので、引用させていただく。
「これは現在、アメリカの医療現場で注目されているがん患者支援サービスのひとつです。ひと言でいうと、がんの闘病生活に必要な知識を有する専門家が、がん患者一人ひとりを個別にサポートする仕組みです。たとえば、低所得者層のがん患者が金銭的な問題から治療の継続を断念していた場合、キャンサーナビゲーションの担い手である「キャンサーナビゲーター(Cancer Navigator)」は患者の自宅を訪れてヒアリングし、本当に治療が困難か検討します。そのうえで、必要であれば医療の専門家、財務アドバイザー、地域の支援団体への橋渡しを行う――というようなサポートを行います」(P25)
キャンサーナビゲーターは、がん拠点病院で研修を受けるが、治療法を提案したりすることはなく、あくまで患者自身を支えることに徹する。
だから、身につける知識は、患者やその家族を「誘導」しないという、支援者ならではの「話法」や「表現」から、心の悩みに対する向き合い方、さらには怪しい治療法などの情報が溢れかえるネット上での「信頼できるサイト」の見極め方など多岐にわたる。
ビッグデータ解析で明らかに!
「日本の病院は当たり外れが大きい」
小林麻央さんのケースからもわかるように、日本のがん患者とその家族は、「本当にこの選択でいいのか」という不安を抱えながら孤独な戦いを強いられる。あくまで決断するのは本人だが、その決断を後押ししてくれる「伴走者」がいない。だから、時に「あのとき、もうひとつ病院に行けばよかった」という後悔も生まれる。
つまり、アキ氏が提言するように「キャンサーナビゲーション」という仕組みが日本にも導入されれば、「がん格差」に悩む人たちの苦しみが軽減される可能性があるのだ。
そう言うと、「アメリカみたいな医療を受けられない人がたくさんいるような国ならそういうサポートも必要だろうけど、日本のような誰もが質の高い医療を受けられる国では余計な混乱を招くだけじゃない?」というような人もいるだろうが、個人的にはアメリカよりも日本の方が、この仕組みを必要としていると感じている。
なぜかというと、アキ氏の専門分野である日米の医療ビックデータで分析してみると、実は日本の「がん医療」というのは、アメリカよりもはるかに「質」のバラつきがあるからだ。本書に詳しいデータが多く掲載されているので、ここでは詳述しないが、この現象をアキ氏は以下のように総括している。
「(アメリカの)多くの学会では病院のガイドライン遵守率を調査し、公表しています。その結果、アメリカの患者は等しく最新の標準治療を受けることができるようになっているのです。一方で、日本にも専門分野ごとの学会があり、それぞれの学会で診療ガイドラインを出しています。しかし、それが遵守されているかといえば、遵守率の調査は行われておらず、結果も公表されていないためわかりません。日本では、病院のやり方、医師個人の判断や経験に左右され、ガイドラインが遵守徹底されているとはいいがたい現実があるのです」(P85)
もちろん、アキ氏は日本の医療の「質」が低いなどということを主張しているわけではない。むしろ、がん研有明に術後入院した際には、アメリカでは見られない日本の医療従事者の献身ぶり、特に看護師の役割の大きさを評価し、ベンチマーク分析では見えてこない、患者の「救い」となっていると指摘している。ただ、事実として、医師や病院の個人によっておこなわれている医療にバラつきが多いということを指摘しているのだ。
要するに、当たり外れが激しいのだ。
金持ちであっても
「ハズレ医師」に会う
よく日本の医療は「世界一」といわれる。その評価についてはここでとやかく言うつもりはないが、もし日本の医療が「世界一」だとしても、あなたの目の前にいる医師が「世界一」だという保証はないのだ。
医療ビッグデータによる分析とともに、著者自身が日米両国で受けたがん治療の実体験からは、日本のがん治療の弱点が見えてくる
このように病院や医者ごとの格差の激しいがん医療を受けなくてはいけない日本人は、外れを少しでもリスクヘッジしなくてはいけない。
かといって、がんになってから本人と家族が専門書を読み漁って勉強をしても間に合わない。患者とその家族が悔いのない決断をするための、正しい知識を提供してくれる「キャンサーナビゲーター」は、大きな手助けになるはずだ。
さらに、「信頼できる相談相手」という存在も大きい。人生で初めての「戦い」を前に、心が折れそうになるのは当然だ。医師との話し合いももちろん大切だが、それ以外の「(正しい知識を身につけた)伴走者」がいてくれれば、患者本人のみならず、家族も心を落ち着けて、納得のいく方策を選び取っていくことができる。
日本人にとって「がん」はもはや国民病であり、金持ちも貧しい者も関係なく誰もが等しくかかる。そして金持ちだからといって、「当たり医師」に診てもらえるとは限らないのだ。社会主義国家ではないので、経済的な「格差」はいたしかたないとしても、「がん格差」くらい国家の力で是正していただきたい、と思うのは筆者だけだろうか。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2017年07月12日 13:41
何よりもまず患者と家族の関係性の問題が第一。。。
■小林麻央さんが選んだ「在宅ホスピス」の実態
どんな医療ができるの?容態が急変したら?
加藤眞三
慶應義塾大学看護医療学部教授
小林麻央さんは、5月末から在宅医療に切り替え、6月22日夜に家族に囲まれて最期を迎えました。いったいどのような医療が行われ、どのような利点があるのでしょうか。
乳がんで闘病中だった小林麻央さんが、2017年6月22日夜に旅立たれたことが報じられました。麻央さんは自分のがんを公表し、その闘病生活をブログ上でつづってこられました。そして、200万人を超える人がその記事を読み、共感し、励まされ、勇気づけられました。
人生の最期を迎えようとするその生き方を、リアルタイムでこれ程多くの人から注目されてきた人は、今までいなかったのではないでしょうか。幼いお子様を遺して他界しなければならなくなったことに悔しい思いをされてきたことと思いますが、心からご冥福をお祈りしたいと思います。
小林麻央さんがブログにつづってきた闘病生活は、多くの人にとって病気になったときの生き方を考えさせられるだけでなく、人生そのものについて再考させられるよい機会となりました。
「自宅で最期を迎える」という選択
麻央さんは、2017年5月29日に病院を退院され、在宅医療に切り替えられました。
在宅で麻央さんが受けた医療とは、いわゆるホスピス医療であり、現在は「緩和ケア」や「エンド オブ ライフ・ケア」と呼ばれているものです。がんなど病気に伴う症状を緩和することによって、最後の時間を少しでもよりその人らしく生活してもらうことを目指します。がんを治すという有効な治療法を失った時、医療の中心が治療を優先する「キュア」から生活を大事にする「ケア」へと向かうのです。
緩和ケア病棟(いわゆるホスピス)は、わが国では1990年に施設の認定が始まり、その後飛躍的に増加してきました。2016年11月の集計では 378施設7695床あります(日本ホスピス緩和ケア協会調べ)。そして、このような終末期医療の専門施設である緩和ケア病棟ではなく、麻央さんのように自宅で最期を迎える人も次第に増えてきています。全死亡の中でがんの病気により自宅で亡くなる人の割合、がん在宅死率は2007年までは6%台でしたが、 2015年には10.4%となり急速に増加しています(厚生労働省「人口動態統計」)。
緩和ケアの中で、大きなテーマとなるのが身体の疼痛コントロールです。WHO方式の「がん疼痛治療法」が発表されてからすでに4半世紀が過ぎ、現在は世界各国で実施されて、70~80%で鎮痛効果が得られると報告されています。特にここ10年間、疼痛治療に使うことのできる薬物の種類も増え、急速に進歩してきた領域です。
特に患者さんに知ってもらいたいことは、身体的な痛みのコントロール目標として次の3つの状態があることです。
① 痛みにより夜間の睡眠が妨げられない状態
② 静かにじっとしていれば痛みがない状態
③ 体を動かしても痛みがない状態
つまり、身体を動かす生活をできる状態へもっていくことが疼痛コントロールの最終目標になるのです。
さらに、症状緩和においては、痛みのコントロールだけでなく、呼吸困難、咳、吐き気と嘔吐、下痢や便秘、脱水、悪液質(衰弱状態)と食思(欲)不振、腹水、吃逆(しゃっくり)など、その他の症状を和らげることも目標となります。
患者さんが、このような症状コントロールの目標を知っておくことは大切です。なぜなら、医療者と共通の目標をもつことによって、医療が患者と医療者の協働作業となり、よりよい緩和医療を実現することが可能になるからです。そのためには、患者さんが医療者に対して遠慮することなく対話をできることが前提となります。また、そのようなことが可能な医療者を探すことが大切です。
在宅でも施設と同程度のケアが可能に
ただ、自宅で死を迎えることに対して不安を抱く方も少なくないでしょう。自宅でも痛みのコントロールはきちんとできるのだろうか、容態が急変した時にはどうすればよいのだろうか、家族が介護で疲労してしまうのではないか、医療者はすぐに対応してくれるのだろうか、などです。
わが国で在宅ホスピスを開拓してきた第一任者である川越厚医師は、現在では制度も整備され、在宅でも施設ホスピスと同程度のケアを提供できると断言されています。そして、在宅ホスピスの利点を、次のように述べられています。
・自宅では束縛のない“生”を全うできる
・家には最期までその人の役割(生きる希望)がある
・住みなれた場所であり最も居心地が良い
・いつも家族がそばにいるため孤独から開放される
・家族は病院と家の二重生活をしないですむ
麻央さんも在宅医療であったからこそ、家族と濃密な時間を過ごすことができたのではないでしょうか。
さらに、在宅ケアをする家族をサポートする「レスパイトケア」というサービスも注目されてきています。レスパイトケアとは、難病をもつ乳幼児を在宅でケアしている家族の精神的疲労を軽減するため、小児ホスピスなどで一時的に子供をあずかりケアの代替を行うサービスです。在宅ケアで介護につかれた家族にとって、そのケアを持続して行うためには、このようなサービスが必要でしょう。このようケアもあることを知っておくと、将来必要となったときに自分の身近に見つけることができ、利用が可能となるかもしれません。
「心の痛み」のケアにも注目が集まってきた
最後に、緩和医療の分野で今起きてきている大きな変化についても知っておいて欲しいと思います。それはスピリチュアルケアにようやく焦点が当てられるようになってきたことです。
がんなど、いのちに関わる大病や進行性の難病を抱えたとき、「なぜ私はこんなに苦しまなければならないのか」「何のために生きているのだろうか」「自分の一生は何だったのだろう」「私が死ねば、残された家族はどうなるのだろう」「他人(家族)に迷惑をかけたくない」「他の人にお世話になるのはつらい」「もう逝かせて欲しい」「死んだ後はどうなるのだろう」など、様々な悩み、すなわち「スピリチュアルペイン」を抱えます。スピリチュアルケアはそれらに対処しようとするケアです。
欧米の病院では、病院の中に祈る場所やこころのケアをする人(チャプレンなどと呼ばれる)が存在することが当たり前になっています。ただ、明治の初期にわが国に西洋医学を導入し病院が創られたとき、スピリチュアルケアをすっかりはずす形で行われたのです。それ以来、医療が科学中心となりスピリチュアルなことは疎まれてきたのです。
1990年頃からようやくその重要性が注目されはじめ、2007年には、日本スピリチュアルケア学会が起ち上がり、教育や認定の制度が整えられてきました。また、2016年2月にスピリチュアルペインに関わる宗教者の会、臨床宗教師の会も発足しました。
このようなこころのケアが医療の中に導入され、上手く機能することになれば、患者さんが受ける終末期医療自体に大きな変化が訪れるだけでなく、医療そのものが人間全体をみるものになることでしょう。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2017年07月03日 17:13
お茶は人生の友、、、その時々の気分とそれぞれの効能に応じて様々なお茶がいつも私の傍らに。。。♪
■ダイエットから腸活まで 侮れない「緑茶」の健康効果
近年、お茶に秘められた健康パワーが次々と明らかになっている。
お茶(緑茶)は世界に誇れる日本の文化の一つです。「緑茶がダイエットに効く」「緑茶でうがいすると風邪の予防になる」――といったうれしい話を耳にする機会が増えました。今、緑茶の健康効果についての研究が国内外で進行しており、緑茶に秘められた健康パワーが次々と明らかになっています。
2015年5月には、緑茶を飲む習慣が死亡リスクを減らし、長寿につながるという研究結果が国立がん研究センターから発表され、マスコミなどで大きく取り上げられました。
がんや循環器疾患にかかっていなかった40~69歳の男女約9万人を、約19年間にわたって追跡調査した結果、緑茶を飲む量が多くなるほど、死亡率が下がることが明らかになっています。さらに、死因別で見ると、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患では緑茶を摂取する量が多くなるほど危険度が有意に低下しています。
緑茶を飲まない人に比べ、緑茶を飲んでいる人の死亡率は下がる傾向が確認された。さらに摂取量が多くなるほどリスクは低くなる傾向も確認された(国立がん研究センターの多目的コホート調査による結果、2015年)
そのほかにも様々なことが分かってきています。そこで、最新の「緑茶の健康効果」と摂取のポイントをまとめました。
■お茶をちょこちょこ飲むといい理由
緑茶の健康効果というと、まず挙がるのが「カテキン」です。カテキンは、植物中に数千種類あるといわれる「ポリフェノール」の一種で、緑茶の渋みの主成分。ダイエットや、血圧、血糖値の抑制から、抗菌、抗ウイルス効果(インフルエンザ予防)にいたるまで、さまざまな効果があるといわれています。
大妻女子大学名誉教授の大森正司さんによると、カテキンのさまざまな効果の秘密は、カテキンの2つの特徴によるものだそうです。1つは吸着性の強さ。これにより、虫歯菌にくっつき増殖を抑えたり、ウイルスの体内への侵入を防いだりするのです。腸内では悪玉菌に付着してやっつけるため、腸活効果も期待できます。2つ目は、体内で生まれる活性酸素を消去する抗酸化機能です。ストレスや紫外線、疲労などによって発生した活性酸素を消去する作用が期待できます。
大森さんによると、カテキンの血中濃度は、緑茶を飲んだ後、およそ1~2時間でピークになるそうです。このため、緑茶を机において、ちょこちょこと飲むのがいいそうです。
■今、注目の成分「テアニン」とは?
テアニンをたっぷり抽出する「氷水出し茶」。水80~100cc(氷を除く)に対して茶葉10gを急須に入れ、10分待って湯飲みに注ぐ。カフェインはほんのわずかしか抽出されない
お茶の健康効果で、最近注目されているのが、うまみ成分である「テアニン」です。テアニンにはリラックス作用があり、ストレス緩和や睡眠の質を改善する効果なども期待できるといわれています。
テアニン入りの水溶液を摂取後、40分くらいすると脳波にアルファ波(α波)が出るという研究結果があります。さらに摂取後、40分後くらいまで副交感神経の活性度が増すことも明らかになっています。
大森さんによると、テアニンをしっかりとりたい場合は、“氷水出し茶”にするといいそうです。低温で抽出すると、渋み成分であるカテキンが少なくなるため、テアニンによるうまみがより強く感じられるとのこと。
■緑茶は「血液サラサラ」食材の基本
「血液サラサラ」という言葉の名付け親である、栗原クリニック東京・日本橋院長の栗原毅さんは、緑茶は血液サラサラ食材の「基本」となる存在だと話してくれました。
「血液をサラサラにするには、血液の材料となる日頃の食事を改善することが極めて大切です。なかでもお茶は、食品と健康、という視点で考えたときに基本中の基本となるとても重要な存在です」(栗原さん)
がんに関しても、説得力のある国内の研究報告が積み上がってきています。栗原さんが注目しているのが、厚生労働省が発表する市区町村別の「がん死亡率」のデータです。「がんによる死亡率が少ない市区町村ランキングで、男性の2位と3位に静岡県の掛川市と藤枝市、女性の1位と2位に掛川市と藤枝市が入っています。いずれも緑茶の産地として有名な場所です。緑茶を飲む習慣ががんを遠ざける、と考えて正解だといえるでしょう」(栗原さん)
■緑茶は、肝臓をダメージから守ってくれる
緑茶はビジネスパーソンの多くが気になる「肝臓」への効果も期待できます。
「肝臓は活性酸素に極めて弱い臓器で、ストレスの影響も受けやすいのです。そこで患者さんにお勧めしているのが、緑茶です。緑茶に含まれるカテキンには、肝臓を攻撃する活性酸素を消去する強い抗酸化作用があります。つまり、肝臓をダメージから守ってくれるわけです」(栗原さん)
さらに栗原さんは、インフルエンザや風邪予防のために「お茶うがい」を推奨しています。お茶に含まれるカテキンが、インフルエンザウイルスの表面にある突起にくっつき、粘膜にウイルスが吸着するのを邪魔して感染を防ぐのだそうです。
■抗アレルギー作用を持つ注目のお茶とは
日本のお茶の7割以上は「やぶきた」という品種です。日本人なら、多くの人が「やぶきた」という言葉を聞いたことがあるでしょう。その一方で、最近では、香味や機能性などに優れた品種の開発も進んでいます。今注目されている品種が「べにふうき」という品種です。
べにふうきには抗アレルギー作用があり、べにふうき緑茶を日々飲んでいると、ハウスダストや花粉などによるアレルギー症状を抑える効果が期待できます。2015年4月から始まった「機能性表示食品」制度で受理された商品も登場しています。
農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門の山本万里さんによると、花粉が飛び始めてから飲むより、飛散する前から飲んでおいたほうがいいそうです。「早めに飲むことによって症状はより効果的に抑えられます。スギ花粉が辛いという人は、クリスマス前後を目安に飲み始めるといいでしょう」(山本さん)
(日経Gooday編集部)
[NIKKEI STYLE]
Posted by nob : 2017年06月07日 14:28
私にもかつて身体を壊してしまう以前にこんな頃が。。。
■遅めの夕食・夜食が常態化! 危険すぎる夜食症候群
遅めの夕食や夜食が習慣化している人はもしかしたら厚生労働省も警鐘をならす「夜食症候群かもしれません。治す方法はあるのでしょうか?
夕食は遅めでも仕方ない? 夜食症候群のメカニズム
名前の通り、夜遅くに多くの量の食事をとってしまう「夜食症候群」。1日の摂取カロリーのうち、25%以上を夕食および夜食で摂ることを言います。さらに、夜食症候群の状態になると、睡眠中に起きて、何かを食べたくなることもあり、実際に食べてしまうことも。習慣化してしまうと、肥満などのメタボリックシンドロームの原因にもなるため、厚生労働省も注意を呼びかけています。
体の中には、脂肪を溜める脂肪細胞があり、この脂肪細胞は、体の現状を維持するために、食欲を抑制したり、エネルギー代謝を促進させるレプチンというホルモンを出したりしています。しかし夜遅い食事が習慣化すると、レプチンの作用が低下してしまいます。レプチンの作用が低下すると食欲が増し、さらに夜食が食べたくなってしまいます。一方でエネルギー代謝は低下し、肥満になりやすくなってしまうのです。睡眠中は体の代謝が低下するため、寝る前の食事による余分なエネルギーは脂肪として蓄積されてしまいます。さらに夜間は、消化管の吸収もよくなります。
飲み会、晩酌も多い人は注意! お酒と夜食の負の関係
さらに気をつけたいのが晩酌などの習慣がある場合。お酒などのアルコール飲料は、胃への血流がよくなり、消化酵素が多く分泌され、動きもよくなるために、胃の内容物は腸に流れます。胃が空になると、当然ながら食欲が増します。さらにアルコールは、血液中の糖分を減らすインスリンの作用を強めますので、血液中の糖分が少なくなります。つまり、ただ空腹を感じるだけでなく、甘い物や炭水化物を食べたくなってしまうのです。
炭水化物を中心とした夜食を取ってしまうことで、高血糖を起こし、これは糖尿病の危険性につながります。寝る前の高血糖状態は睡眠中も続いてしまうために、睡眠障害も引き起こします。夜寝る前にお酒と一緒につまみなどを食べてしまうのも夜食症候群の一因になります。
増加している夜食症候群……その原因は?
今、私たちの身の回りには、24時間営業や深夜営業の店、コンビニが当然のようにあります。そうした店舗で深夜に働いている人も増えているということですし、それらの店やコンビニの利用者も増え、生活時間のボーダレス化が進んでいます。
朝食欠食者を対象にした国の調査によると、40代男性の36.6%、女性の19.2%が、21時以降に夕食を摂っていることがわかりました。さらに、男性全体では、10.8%もの人が23時以降に夕食を摂っているのだそうです。つまり、遅い夕食を摂る人が多く、その傾向は男性に強いと言えます。女性がやや少ないのは、ダイエットを意識している割合が男性より多いからかもしれません。
いつでも、食べ物を買うことができる環境、夜遅くまでの仕事をすることで、全体的に夜食症候群が増えていると言えます。
習慣化すると危険! 夜食症候群が招く病気
肥満からメタボリックシンドローム、高血糖などから糖尿病、高コレステロール血症などから動脈硬化、高血圧など、まさに生活習慣病になり、脳梗塞、脳出血、心筋梗塞などの心血管の病気を起こすことになります。夜食症候群と思ったら、まずは、食生活を見直す必要があります。
太らない夜食の取り方に似ている? 夜食症候群の対策法
まずは、食事時間を早くすることができないかどうか生活を見直しましょう。できれば、寝る2時間前には食事を終えておきたいものです。夜食として食べるにしても低脂質、低炭水化物で消化に良い良質なタンパク質を含むものを選ぶようにし、カロリーを抑えておきましょう。1日の食事バランスも、できれば、朝食をしっかりと摂るようにしましょう。
残業が避けられない時には「残業前に軽食を摂っておく」「残業後に食べるものは考えて選ぶ」ことが大切です。残業後に食事を取る場合、魚の練り物、豆腐、おでんなどタンパク質を中心とした食材、春雨やコンニャクなどの満腹感が得られやすいカロリーの少ない食材を選ぶようにしましょう。遅い時間に食べ過ぎてしまうことを防ぐためにも、残業がある日には昼食をしっかりと摂っておくようにすることも大切です。生活習慣や仕事の時間はすぐには変えられないかもしれませんが、健康に直結する毎日の食生活、できることから自分でできる対策を取っていきましょう。
(文:清益 功浩)
[AllAbout]
Posted by nob : 2017年05月24日 23:41
なかなか良い気がします。。。
■「第二の心臓」ともいえる臓器が疲れると体の中が…
J-WAVE月曜−木曜朝6時からの番組「J-WAVE TOKYO MORNING RADIO」(ナビゲーター:別所哲也)のワンコーナー「SUNSTAR PLEASURE PICK UP!」。9月12日のオンエアでは、整体・マッサージなどを行う寺林治療院の院長、寺林陽介さんをゲストにお迎えしました。
さて、人間の内臓の中で、「第二の心臓」ともいえる大切な臓器は次のうちどれでしょう?
①腎臓 ②脾臓 ③小腸 ④肝臓
みなさんご存じですか? ちなみに別所が選んだのは③の「小腸」。このとき「あ!小腸は『第二の脳』だったかな…どっちだったかな…」と、記憶が少し曖昧そうでしたが、結局③をチョイス。
さて、寺林先生からの正解は…①の「腎臓」でした! 別所の選んだ③の「小腸」は、迷った通り、「第二の脳」。惜しかったですね(笑)。
では、なぜ「腎臓」は「第二の心臓」といわれているのでしょうか? 寺林先生に詳しく解説していただきました。
「腎臓は老廃物が混じった血液をろ過し、いらないものを尿として体の外に出してくれます。腎臓の働きが悪くなると、血液の中がゴミだらけに。お風呂の水を 2〜3日変えていないようなものです。血液を全身に送るポンプの役目をするのは心臓ですが、汚れた血液を掃除してくれるのは腎臓なのです」
そんな「第二の心臓」といわれる腎臓、できるだけ健康な状態にしておきたいですよね。そこで寺林先生に“腎臓に負担がかかってしまう原因”、そして“腎臓の疲れを取るマッサージ”を教えていただきました。
■腎臓に負担をかける原因
「夏の暑い日にクーラーに当たりすぎたり、こってりラーメンが好きでついつい塩分を摂り過ぎてしまう。また、仕事が忙しくて寝不足になっている。これらはいずれも腎臓に負担をかけてしまいます」
中には全部、当てはまってしまう人もいるのでは? しかし、オフィスやお店のクーラーの温度設定や仕事の都合は、自分一人ではなんともできませんよね…。
そういったお疲れの腎臓の人にオススメなのが「腎マッサージ」!
■カンタン1分! 腎マッサージのやり方
① 握りこぶしを作り、おへそのすぐ横に当てる
② 止まるところまでこぶしをグッと押し込む
③ そのままこぶしをグリグリと3回ほど上下に動かす
④ 次に指二本分ほど外側にずらして、同様に握りこぶしをグッと押し込み、3回ほどグリグリと動かす
※これを3セット繰り返す
これで腎臓の疲れが取れ、冷えやむくみ、お通じも良くなるそうです。腎臓の疲れを意識している人はあまり多くないと思いますが、「第二の心臓」と言われると、健康を心がけないと! と思ってしまいますよね。そんな方はまずは腎マッサージから始めてみてはいかがでしょうか。
[J-WAVE NEWS]
■自分で簡単にできる腎臓マッサージ
東洋医学では、腎臓が疲れると老化が進むといわれています。
腎臓は身体の老廃物を排出する重要な役目があり、この機能が低下すると、老廃物が溜まり疲れも
取れにくくなります。それにより身体に不要なものがたくさん取り込まれてしまい腎臓が疲れてしまいます。
その結果、水分代謝がうまく機能しなくなり身体にに余剰な水分が停滞し、むくみ・だるさ・体重増加に
繋がるとされています。又、腎臓は、からだが冷えると一番最初に影響を受ける臓器とも言われています。
身体が冷えると、途端に腎臓の働きが悪くなります。つまり「冷え」と「むくみ」には密接な関係があり、
腎臓に血液が十分送られないと、腎機能は徐々に低下し病気の症状が現れます。
腎臓は第3チャクラ・太陽神経叢(たいようしんけいそう)みぞおちの部分、まさに太陽の如く「自己価値」を
認識するパワーがあるところです。
そこで・・・・・
●腎臓マッサージの方法を習いました● 自分で簡単にできる腎臓マッサージ
やや前かがみに腰を曲げ、背中側の腰より少し上の腎臓がある部分に左右手の平を当て、約1分程激しく
擦ります。(手のひらで背中からお尻にかけて、じかに肌の上から摩擦します)すると手も腰の上部も
暖かくなるので、次に動きを止め、その熱を感じながらしばらく手をその場に当てたまま大きく深呼吸。
暖かくて気持ちいい感触を全身で受け止めながら、大きく息を吐くことで、腎臓がほぐれていきます。
更にこの部分を叩いてみて、強く痛みを感じる方は、腎臓が弱っている可能性があります。
外傷等がなければ、大きく息を吐きながら軽く叩くのもお勧めだということでした。
腎臓マッサージ → 膀胱マッサージ の順番でやるとさらに代謝が上がります。
●膀胱マッサージ●
横向きに寝ます。両手をよくこすり合わせ、温めた手の平で上になった足の付け根の上部をよく摩擦します。
反対向きになり、同じように温めた手のひらで、上になった足の付け根の上部をよく摩擦します。
最後に仰向けになり両手でそれぞれの足の付け根の上部を摩擦します。1か所30回程やります。
必ず腎臓マッサージのあとに膀胱マッサージをすること!
自分で簡単にできる腎臓マッサージ自分で簡単にできる腎臓マッサージこのマッサージは朝起きて食事を取る前に行うと有効的とのこと。
もちろんヨガやチベット体操など、流れのあるものを全体を通して
バランス良く行うのが大切ですが この腎臓マッサージ→ 膀胱マッサージで、素早い機能UPも
これからぜひ取り入れていこうと思います
[ビビアンさんのプログ]
Posted by nob : 2017年05月20日 15:59
私も休煙中、、、きっぱり止めようと考えずにしばらく休むつもりで気楽に取り組めば止められ、いや休み続けられます。。。Vol.2
■喫煙者の「口の中」で一体何が起きているのか
口臭、歯周病、虫歯・・・リスクはてんこ盛りだ
小林保行
歯科医師/キーデンタルクリニック院長
タバコのさまざまな悪影響が問題視されています。国立がん研究センターではタバコを吸う人は吸わない人に比べて4倍以上肺がんになりやすいと報告していますし、厚生労働省でも喫煙と低出生体重児・早産との因果関係、周囲の人への健康侵害について指摘しています。
数え切れないほどの害があるとまでいわれるタバコ。筆者は歯科医師としての知見や経験を基に、歯や口周りの情報を「ムシバラボ」というサイトで発信していますが、その中で紹介していることのひとつが、タバコが歯や口の中の環境に与える害です。
タバコを吸うとヤニ(タール)が歯に付着しますので、歯全体が黄色っぽく見えてしまいます。ヤニは粘着性が高いので歯の表面についてしまうと、簡単には落ちません。また、歯の表面についたヤニはほかの汚れもくっつけてしまいますので、歯の黄ばみが徐々に濃くなっていったり、黄色いのを通り超えて黒ずんでしまったりすることもあります。
ヤニが吸着するのは食べ物などの汚れだけではありません。虫歯菌も吸着してしまいます。そのため、表面にヤニがついていない歯と比べると、虫歯にかかりやすくなってしまうのです。
また、タバコに含まれるニコチンによって唾液の分泌量が落ちてしまうことも、虫歯菌の繁殖を誘発しています。唾液には虫歯を予防する効果がありますので、唾液量が少なくなると虫歯になりやすくなるのです。
タバコは歯茎などにも悪影響を与えます。タバコを吸うことで口内環境にどのような害が起こりうるのでしょうか。
(1)歯周病が発見しにくくなる
タバコに含まれるニコチンには、血管を収縮させる作用があります。血液の流れを悪くしてしまいますので、傷口があっても出血しにくくなり、病気やけがの治りも遅くなってしまうのです。
歯周病は歯茎の病気ですが、早めに発見することで適切な治療が可能となります。ところがタバコを吸っていると出血や歯茎の腫れといった歯周病を見分ける症状が出にくくなりますので、すぐには発見することができません。
歯周病が重度に進行すると、タバコを吸っていても痛みや腫れ、出血などの症状が出るようになりますので大抵の人は気づきます。しかし、その時には重篤な状態になっているために治療が思ったよりも進まないことや、タバコによって白血球の働きも抑制されているために治りが遅くなることもあり、つらい状態が長く続くことになるのです。
(2)歯が抜けやすくなることも
歯周病が重度に進行すると、歯茎が後退し、歯が抜け落ちてしまうこともあります。タバコによって歯周病の進行に長く気付かないでいると、歯が抜け落ちる確率も高まると言えるでしょう。
(3)口臭の原因にもなる
タバコのヤニは、独特の悪臭を発します。繰り返し喫煙することで、口内に付着するヤニの量が増え、悪臭も増えていきます。粘着しやすい成分ですので、長期にわたって口内に残り、悪臭もますます強くなっていくのです。
また、唾液には、虫歯を予防するだけでなく口臭を予防する効果もあります。朝、起きたとき、口臭が強いと感じたことはありませんか? これは消化がうまくできていないこと等も関係がありますが、起きたばかりのときは唾液の分泌量が少なく、口の中が渇いていることも原因の1つです。タバコに含まれるニコチンは唾液の分泌量を減らしてしまいますから、結果的に口臭が強まることになるのです。
(4)歯茎に色素沈着することも
タバコを吸っていると、歯の色が黄色っぽくなるだけではありません。ヤニは歯茎にもしっかりと吸着しますので、歯茎の色も黒っぽくなってしまいます。とは言っても、歯茎は歯とは異なり丈夫な組織ではできていません。汚れを取ろうとこすりすぎてしまうと、歯茎を傷つけ、擦り傷のようになってしまいます。
タバコをやめれば口内環境は変化するか
歯と歯茎の色を着色させ、見た目を悪くするタバコ。もちろん害は見た目だけではありません。虫歯や口臭、歯周病の悪化などの悪影響を与えます。では、タバコをやめれば、すぐに口内環境は良好になるのでしょうか?
タバコをやめることで、血液中のニコチン濃度が徐々に下がっていきます。すると、血液は正常に流れるようになりますので、赤血球のヘモグロビンに乗って末端まで酸素が運ばれるようになります。顔や肌の色が明るくなり、歯茎の血行も良くなりますので、歯茎の色の黒ずみも徐々に解消されていくでしょう。
血流が正常になると、皮膚や歯茎の色が良くなるだけではありません。傷ができたときには正常に出血しますので、歯周病の発症もすぐに気づくことができるようになります。
白血球も正常に作用するようになりますので、口内に傷や病気ができたときも、早く正常な状態に治癒することが期待できます。
歯についてしまったヤニや汚れは歯科医院で
タバコをやめれば徐々に体内環境も改善されますので、歯周病などの口内トラブルの早期発見と治癒が期待できます。ですが、歯にくっついてしまったヤニは、放っておいては取れません。歯ブラシを使っても限界がありますので、歯科医院で歯のクリーニングをして取ることがオススメです。
歯のクリーニングは、審美歯科はもちろん一般的な歯科でも実施しています。一般的な歯科では、虫歯と歯周病との検査も同時に行ってくれ、しかも保険適用になりますので、3000円~3500円ほどの自己負担で済みます。
喫煙歴が長くなると、歯茎も黒っぽく着色していきます。これも、歯科医院でキレイに落とすことが可能です。歯茎の着色除去に特化したレーザー治療や、歯茎のピーリングを行っている歯医者さんで処置は受けられます。保険適用外で1万~5万円ほどの自己負担で歯茎のヤニを除去できます。
歯茎が黒い原因が歯周病の場合は、レーザー治療等で瞬時に歯茎の黒ずみを解消することはできません。歯科医院に通い、時間をかけて歯周病の治療に取り組みましょう。もちろん、治療中の喫煙はNGです。タバコによって治癒力が低下してしまいますので、歯周病治療が長引いてしまいます。タバコをやめ、歯周病を治療し、健康な歯茎と口内環境を取り戻してくださいね。
ニコチンやタール以外にも、タバコには健康を害する成分がたくさん含まれています。また、健康を害するだけでなく、歯や歯茎への色素沈着や口臭悪化など、見た目やにおいなどへの悪影響もあります。
確かに、タバコには中毒性があります。大勢の人が禁煙を決意しては脱落していくことも、タバコの中毒性を証明しています。ですが、タバコをやめることができれば少なくとも、美しく健康な歯と歯茎を取り戻せるのです。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2017年05月10日 11:20
私もグルテンは最小限に、(酵素)玄米と雑穀白米の恩恵を最大限に享受しています。。。
■グルテンフリー食の功罪、2型糖尿病の発症率上昇リスクも
プロテニス選手、ノバク・ジョコビッチ氏の著書で注目されたグルテンフリー食。
タンパク質の「グルテン」を含むパンやシリアル、うどんなど麦類を排除、制限することで、体重が減るばかりか「集中力や記憶力が高まる!!」と、ダイエット情報に敏感な女性だけでなく、ビジネスマンの間にも広まっている。
米国では2009~14年の間で、グルテンフリー食を実践する人が3倍にも増えたそうだ。
グルテンフリー食はもともと、グルテンに対する免疫反応で小腸の粘膜が傷つくセリアック病の患者を対象とした食事療法だ。アレルゲンを排除し、過剰な自己免疫反応(炎症)を抑えることを目的としている。
食物をアレルゲンとする消化管アレルギーが重症化すると、慢性の下痢や栄養不良のほか、感染症にかかりやすくなるなど影響があり、生活の質が大きく低下する。近年は、非セリアック性グルテン過敏症の人にも食事療法が行われている。ただ、消化機能が正常で、グルテン過敏症ではない人にメリットがあるかは不明だ。
コメや雑穀を主食とする習慣が薄い米国では、グルテンフリー食を「加工品」に頼らざるを得ない。グルテンを除く加工過程で、必要な栄養素が失われるばかりか、グルテンの「口当たりの良さ」を補うために添加物や余分な糖質が加えられる。ダイエットどころか「エンプティ・カロリー」を摂ることになりかねないのだ。
先日、米国心臓病学会誌に掲載された報告でも「健康な人に良いという根拠はない」とばっさり。
また、米国で30年以上続く医療従事者(男女合計およそ20万人)を対象とした疫学研究のデータから、グルテン摂取量が1日4グラム未満の場合、 12グラム未満の場合と比較し、2型糖尿病の発症率が上昇するという知見が得られた。研究者は、グルテンを制限すると、2型糖尿病の予防に働く食物繊維の摂取量が減る、と指摘している。
一つの食品や一つの栄養素に焦点を当てたダイエット法には思わぬリスクが付きものだ。食べる量には気を配りつつ、雑食の幸せを噛みしめましょう。
(取材・構成/医学ライター・井手ゆきえ)
[DIAMOND男の健康]
Posted by nob : 2017年05月01日 15:54
呼吸、姿勢、歩行が健康づくりのキホンのキ。。。Vol.4/実践している方も多いかと思いますが、私もお薦めします。。。
■健康や美を損なう「口呼吸」を「あいうべ体操」でストップ!
第1回 お風呂や就寝前に舌の体操を!
「口をぽかんと開けて無意識に行う“口呼吸”が、健康や美を損なう元凶」──そう確信する医師が、口呼吸をストップさせるメソッドを考案。そのメソッドとは、口呼吸の原因である“たれ下がった舌”を引き上げるというもの。不調が改善するほか、顔のたるみがなくなる人が続出! 驚くほど簡単な舌の体操、ぜひ身に付けて。
舌の体操で顔のたるみは取れる!
「口呼吸の害に向き合うきっかけは、関節リウマチ患者特有の“におい”だった」と話すのは、みらいクリニックの今井一彰院長。「病気が治るとにおいが消えることから、においの一番のもとと思われる口臭を消せば病気が良くなると考えた」(今井院長)。
今でこそリウマチの症状の悪化は歯周病が関係し、歯周病菌を増やす原因となる口腔乾燥を防ぐことが大切だと分かってきた。しかし、2000年当時は口呼吸を止めるとリウマチの症状が改善するのが不思議だったという。今井院長は、花粉症やアトピー性皮膚炎なども、口呼吸をやめて劇的に良くなる患者を数多く見てきた。
どうすれば口呼吸をやめられるのか─と考えたところ、自然と口が開く人は、舌の位置が下がっていると判明。「原因は、舌筋(ぜっきん)が弱くなっていることだった」(今井院長)。
舌の筋肉には下あごを支える働きもある。舌の筋肉が弱って舌の位置が下がると、下あごの上にべったりのって、その重みで下あごが下がり、口が自然と開いてしまうと分かった。「舌が下がっている人は女性全体の9割」(今井院長)という。あなたも、舌の位置を知るチェック法(次ページに紹介)でぜひ確認しよう。また舌が下がる要因には、舌の筋肉の構造も大きく関係するようだ。
新発見! 口呼吸は「舌のたるみ」が原因だった
舌が下がり、前歯の裏についている
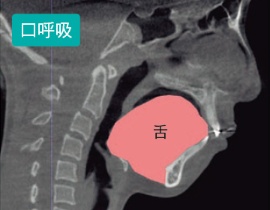
舌が上の歯の裏側についているのが分かる。これは舌が下がっている証拠で、口呼吸をしている可能性が高い。もっと舌が下がっている人は下の歯の裏側につく。
舌が上あごにべったりつく
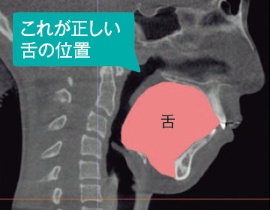
上あごの歯茎の上にあるくぼみ、硬口蓋(こうこうがい)に舌がぴったりくっついている。この状態だと自然と口が閉じ、逆に開けづらい。
美容面でも大きな影響がある。“舌のたるみ”で、あごがたるみ、ほうれい線やシワができてしまう。さらには乾燥肌を招く一因にも。「口呼吸は体内の水分をどんどん気化させ、水分量を減少させてしまう一因に」(今井院長)。まさに顔のエイジングにかかわる舌のたるみ。舌の体操で舌を引き上げて口呼吸をストップさせよう!
あなたの「口呼吸」レベルをCheck!
確かめてみよう! 正しい舌の位置はココ
音を鳴らしたときの場所が正解!
舌先を丸め、上あごにつけ、「カッ♪」と音を出そう。最初に舌が当たる場所が、本来舌があるべき位置になる。
次回は、あいうべ体操の実践編を紹介する。
■「あいうべ体操」で舌筋を鍛えて舌と顔のたるみをとろう!
第2回 舌はどこででも鍛えられる!
「口をぽかんと開けて無意識に行う“口呼吸”が、健康や美を損なう元凶」──そう確信する医師が、口呼吸をストップさせるメソッドを考案。そのメソッドとは、口呼吸の原因である“たれ下がった舌”を引き上げる「あいうべ体操」。今回はいよいよ「あいうべ体操」を実践してみよう!
あいうべ体操で、舌&顔のたるみをとる!
前回の記事(「健康や美を損なう「口呼吸」を「あいうべ体操」でストップ!」)では、口呼吸が美容や健康に与える悪影響を紹介した。口呼吸の原因は「舌のたるみ」。みらいクリニックの今井一彰院長は、「舌のたるみは顔のたるみに直結する」という。だから、下あごを支える舌筋と口まわりの表情筋をストレッチして、舌とフェイスラインをぐ~んと引き上げよう。まずは上の「あ」「い」「う」「べ」の動作を1セットとし、連続して10回行ったあと、口を閉じて舌の位置を確認してほしい。舌の先が引き上がっているのが分かるはずだ。
大げさなくらいに大きく口を動かしゆっくり行うのが効かせるコツ。お薦めは入浴時や就寝前だ。「浴室は湿度が高く口の中が乾燥しない。また就寝前に行うことで、就寝中に極端に少なくなる唾液の分泌をカバーする効果もある」(今井院長)。顔や首の血行も良くなる。
舌先が上あごについているか、そうでないかの舌の位置は1cm差。「この1cmが顔のたるみや健康を大きく左右する」(今井院長)。さあ始めよう!
step 1 : 「あ~」と口を大きく開ける。
縦の楕円形に近くなるようにして、のどの奥が見えるくらい口を大きく開ける。
step 2 : 「い~」と口を横に開ける。
ほおの筋肉が両方の耳の前に寄る感じがするくらいが目安。首に筋が浮き出るくらいに。
step 3 : 「う~」と口をとがらせる。
思い切り唇を前に突き出すようにする。
step 4 : 「べ~」と舌を伸ばす。
舌の先を舌あごの先端まで伸ばすような気持ちで、舌を出す。
「あいうべ体操」のポイント
* 口を大きく動かすことを意識する。
* 1つの動作(例:「あ」)を約1秒で。1セット(「あ」「い」「う」「べ」)を約4秒かけて行う。
* 1セットを10回続けて行う。
* 1日に3度に分けて(10回×3=計30回)行うのがお薦め。
* お風呂や就寝前がベスト。
* 声は出さなくてOK、少し声を出して行うとストレッチ効果がアップ。
あいうべ体操直後、下あごが持ち上がった。
さらに舌を鍛えるなら…
舌を唇と歯の間でぐるぐる回そう。
舌先を出す角度を変えても複数の舌筋が鍛えられる。どこでもできるので、気付いたときにどんどんやろう。
「あいうべ体操」終了60分後も、表面皮膚温度が持続。
29歳の女性があいうべ体操を30回行った直後と60分後のサーモグラフィーによる表面温度の測定結果。あごや鎖骨のデコルテ部分の血流改善効果が長時間持続した。
寝ているときに口が開いてしまう…
マウステーピングをして寝よう。
「うつぶせ寝や横向きに寝ると、口が開きやすい」(今井院長)。12mm幅のテープを5cmの長さに切り、唇の真ん中に縦に貼って寝る。「あくまで対症療法であることを忘れずに」(今井院長)。
テープはなんでもOK。サージカルテープだと、はがすとき痛みが少ない。
いずれの記事も
今井一彰さん
みらいクリニック(福岡市博多区) 院長
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年04月26日 12:01
呼吸、姿勢、歩行が健康づくりのキホンのキ。。。Vol.3/そして生活習慣。。。Vo.2/まずは睡眠。。。Vol.2/8時間睡眠も昼寝もなかなか難しい。。。
■人間が本当に必要な「睡眠時間」は何時間か?
Popular Science : 睡眠には本当に時間を取られますよね。推奨されている1日の睡眠時間(成人の場合は8時間)に平均寿命(アメリカでは78.8歳)を掛けると、なんと約9,587日になります。人生の3分の1は意識の無い状態で過ごすわけです。
進化論的見地からは、睡眠は文字通り時間の無駄ですが、そうは言っても、果てしない歳月を重ねて地球上のほとんどすべての生物が睡眠を取るように進化してきたわけですから、きっと重要に違いありません。
現に、身体のほぼすべての器官が機能するには睡眠が極めて重要な役割を担っていることが科学的に実証されています。
同時に、病気の有無、多忙なスケジュール、そして、加齢という単純にして回避不可能な現象により、睡眠に充てられる時間が違ってきます。そうなると、私たちには実際には何時間の睡眠が必要なのでしょうか。睡眠時間を短くする訓練はできるのでしょうか?
世間一般に知られている8時間睡眠
睡眠時間は何時間でもいいというわけでは決してありません。8時間は、間違いなく人間が自然に必要とする睡眠時間数であり、これには確固たる論拠があります。
太陽の光も一切の視覚的手がかりも無い実験室に被験者を入れて、夜は必ず9時間の睡眠を取る機会を与えるという実験が行われました。数週間にわたり被験者が毎晩これを実行したところ、常に同じ結果が出ました。それは、人間はどれだけたくさん時間があっても、睡眠に費やす時間は通常平均8時間になるということです。
8時間睡眠を支持する研究は他にもあります。さかのぼること1938年、Nathaniel Kleitmanという名の睡眠学者とその学生の1人がケンタッキー州のマンモス洞窟で32日間過ごしたという研究があります。
マンモス洞窟は、世界で一番深い洞窟で、太陽の光が完全にシャットアウトされた環境です。そこで過ごした期間の睡眠パターンを分析した結果、やはり1晩に8時間から8時間半の睡眠を取っていたことがわかりました。
では、睡眠時間が8時間より少ないとどうなるのでしょうか?
それに関しては、多くのことがわかっています。2003年に、ペンシルべニア大学の睡眠学者、David Dinges氏と『Walter Reed Army Research Institute』の睡眠学者、Gregory Belenky氏が睡眠不足の結果に関して極めて重要な研究を行いました。この研究の目的は、人間は認知能力に影響を及ぼすことなく、どこまで睡眠時間を減らせるか調べることでした。
睡眠については多くの実験で証明されている
2週間にわたって実施されたこの2つの研究では、被験者の睡眠時間をさまざまに変える実験が行われました。実験を始める前に、被験者に8時間睡眠を取らせ、翌日一連の認知テストを受けてもらいました。
これにより、被験者の回答速度、文章の読解力、1秒か2秒ウトウト居眠りをする回数(専門用語では『マイクロ睡眠』といいます)を測定して、各被験者の平常時の認知能力の基準値を割り出しました。
Dinges氏の研究チームは被験者を4つのグループに分け、それぞれのグループに8時間、6時間、4時間の睡眠時間を割当て2週間観察しました。最後のグループには全く睡眠時間を与えずに最長で連続3日間観察しました。
カリフォルニア大学バークレー校睡眠神経画像研究所のディレクター、Matthew Walker氏によれば、最後のグループを観察することで、たった1晩全く睡眠を取らなかっただけで認知能力がどれだけ低下するかがわかりました。Dinges氏のチームは、1晩徹夜しただけで脳の認知能力が酩酊状態とされる状態と同じぐらい低下することを発見しました(これは、その後に続く諸研究でも証明されています)。
残りのグループから得られた結果もそれほどかけ離れたものではありませんでした。
8時間睡眠のグループは2週間の実験期間を通して認知能力に目立った変化は見られませんでした。6時間睡眠のグループは、実験を初めて10日目以降は、1晩全く睡眠を取らなかった人たちと同じ程度の認知能力の低下が認められました。それと同程度の認知能力の低下が4時間睡眠のグループの場合は、たった3日目で起こり、実験10日目には、2日間徹夜した人たちと同程度に認知能力が低下しました。こうした認知能力の低下は日を重ねても緩やかになることはありませんでした。
「データのグラフを見ると、どこまでも限りなく低下していきます。これは実に恐ろしいことです。」とWalker氏は語っています。
『Walter Reed』でも同時期に全く同じ実験が、睡眠時間を7時間、5時間、0時間という奇数の時間数にして行われましたが、得られた結果はDinges氏のチームが得た結果と基本的には同じでした。
1晩に7時間睡眠を取ったグループでさえ(7時間も眠るなんて贅沢だと考える人もいますが)、実験5日目にして、ウトウト居眠りをする率が8時間睡眠のグループに比べて3倍も高くなったとWalker氏は言います。ですから、認知能力を低下させずに睡眠時間を8時間から何時間減らせるか、と言えば、その答えは、1時間未満ということになります。
残念ながら「例外なく、1日8時間は睡眠を取るべきだ」ということに確定のようです。
そうは言っても、誰もが特に平日はとても忙しい生活をしています。週末だけエクササイズしているのに健康でいられるツワモノの例もあることから、平日に不足した睡眠を週末に補うことはできるのでしょうか。それにより平均睡眠時間を8時間にできるなら何よりです。この疑問の答えを見つける研究も実施されました。
睡眠時間を削る実験をした後で、同じ被験者に「睡眠を取り戻す」ために3日間を与え、その間はいくらでも好きなだけ眠っていいことにしました(予想通り、ほとんどの被験者は8時間以上寝ました)。
3日目の終わりに、同じ認知力テストを受けてもらうと、最初に割り出した各人の基準値レベルには戻っていませんでした。言い換えれば、睡眠時間が1日7時間以下だと睡眠不足になり、週末に補完しただけでは本来の認知能力には戻れないということになります。どれだけ長く回復期間を取れば本来の能力に戻れるのかは、わかっていません。
「睡眠は貯金できると思われています。借金がかさんでも、ある時点で巻き返せると思いたいからです。しかし、睡眠に関してはそうはいかないことがわかっています。」とWalker氏は言います。
脳には失ったものを全部取り戻す能力はありません、とWalker氏は説明しています。なぜでしょうか。カロリーを脂肪にして蓄えることで飢えをしのぐのと同じやり方で睡眠不足を補う方法が進化しなかったのはなぜでしょうか。
「その答えは簡単です」とWalker氏は言います。「意図的に睡眠時間を削る種は唯一人間だけだからです。」地球上の生物は睡眠を蓄えるシステムを作る必要が無かったので、脳の中にそういうシステムがないのです。
この記事を読んで、「いつも6時間睡眠で問題なく暮らしているのに、どうしてそれ以上の睡眠時間を無理に作らなければならないのだ。そんなことは時間の無駄だ。」と冷笑している人も多いことでしょう。
そんな人には、こんな実験結果をご紹介しましょう。Dinges氏の実験チームが、6時間睡眠の被験者が6時間睡眠の夜を1晩経た後で受けた認知テストの出来栄えを聞くと、誰もが「良くできた」と回答しました。
しかし、実際には、8時間睡眠後に受けた実験開始前のテストの結果と比較すると、著しく劣っていました。
「睡眠不足のときは、自分が睡眠不足だと自覚していないのです」とWalker氏は言います。
「多くの人が、自分は6時間睡眠かそれ以下で大丈夫だという誤った考えを持ってしまうのです。」睡眠時間を削る効果的な訓練の方法は存在しないとWalker氏は主張しています。慢性疲労に慣れてしまうことはあっても、疲労を実際に抑制できるわけでもなければ、認知力テストで8時間眠ったときと同じ成績を出せるわけでもありません。
午後の昼寝はパフォーマンスを上げる
さらに、タンザニアのハッツア族のような、いまだに電気が全くないままの文化に目を向けてみると、特に夏場は、2回に分けて睡眠を取る傾向があることがわかりました。
夜に6時間眠り、午後に2、3時間眠るのです。これにより、人間は果たして16時間連続して起きていた方が良いのかという問題が提起されるとWalker氏は言います。
実際、誰でも午後はちょっと能力が低下する時間帯があります。このように注意力が生理的に低下することは専門用語で食後性低下と呼ばれており、代謝システムの変化や脳波や認知反応時間の調整を通して測定できます。
誰でも認知能力が一時的に低下するなら、その時間帯に昼寝をすると良いのかもしれません。「まだ明確にはされていませんが、もしかしたら、人間のパフォーマンスを真に最適化するためには、睡眠を2回に分ける必要があるのかもしれません。」とWalker氏は語っています。
1点科学的に実証されていることは、毎晩の睡眠が少ないほど、日を追うごとに認知能力が低下し続けるということです。
Walker氏いわく、睡眠が1時間減ると人間にどの程度の影響が及ぶか立証したいなら、アメリカなら毎年3月に冬時間から夏時間に変わった直後の感覚を思い出してみることです。そのときは、全国一斉に睡眠時間を意図的に1時間減らすことになるからです。
しかしWalker氏に言わせれば、一番覚えておくべきことは、「やるべきことが多すぎて睡眠時間は5時間しか取れない」と言う人に対して、次のように言い返すことです。
「残念ながら、それは皮肉な話だね。そんなにやることがたくさん残っているのは、5時間しか眠らないせいで認知機能が低下しているからかもしれないよ。だからいつまでたっても仕事が終わらないんだよ。」
How many hours of sleep do you actually need? | Popular Science
Claire Maldarelli(訳:春野ユリ)
[ライフハッカー]
■夜の睡眠は「5時間」でもOK グーグル、ヤフーが勧める「昼寝」の方法
□睡眠のプロが提案する「5時間快眠法×朝5時起き」とは
2017年の年明けから、はや4カ月。皆さんは、毎日、「自分の時間」を確保できていますか? このまま時間に追われてしまえば、あっという間に年末です。それを避けるために、自由な時間をつくる方法を考えてみたいと思います。キーワードは「睡眠」です。
日本睡眠学会所属の医師・坪田聡さんは、著書『朝5時起きが習慣になる5時間快眠法 睡眠専門医が教えるショートスリーパー入門』(ダイヤモンド社)のなかで、「5時間快眠法×朝5時起き」というスタイルを提案しています。睡眠の質を向上させれば5時間でもぐっすりと眠ることができ、朝早く起きることもできる。また、睡眠時間が5時間になれば、自分が自由に使える時間も確保しやすくなります。
たとえば、23時に寝て7時に起きるようなサイクルだと、勉強やワークアウトに使える時間、趣味にあてられる時間などはほとんど確保できないはずです。ベッドのなかでスマホを見るくらいがせいぜいでしょう。
これを24時に寝て5時に起きるサイクルに変えるとどうなるでしょう。寝る前と起きた後、合計で3時間の余裕が生まれることになります。これを「自由に使うことができる時間」として活用するわけです。
朝の時間帯はしっかりと休んだ後なので頭がよく働きます。また、日を浴びれば心身も活性化します。早朝は周囲も静かですから、集中して物事に取り組むこともできます。語学や資格の勉強には最適でしょう。こうした時間をつくるためには何をすればいいのか。大切なのは睡眠の質を上げることです。
坪田さんは、著書の中で「いたずらに長いだけの睡眠に費やす時間の多くは『無駄」」と指摘しています。
睡眠のよしあしは、単純に「時間」だけで測れません。一般的に「1日の疲れをとるには6時間〜8時間程度の睡眠が必要」などといわれますが、坪田さんの考えによれば、重要視すべきは「睡眠時間の長さ」よりも「睡眠の質」だというのです。
これを数式にすると<時間×質=満足度>。仮に睡眠時間が短くても、睡眠の質が高ければ得られる満足度は同じという考え方です。
同書では次のような例が紹介されています。これまで7時間睡眠をしていたとしましょう。1時間あたりの睡眠の質が50点だった場合、7時間×50点で満足度は350ということになります。一方、睡眠の質が70点だったとしたらどうでしょう。5時間睡眠でも、同じ満足度が得られるわけです。
□朝5時起きはクリエイティブな作業と相性良し
その他、坪田さんが推奨する、睡眠の質を上げるための条件はこちらです。
・寝付きを良くするために就寝3時間前までには食事を終える。
・ラベンダーの香りなど寝室でアロマを焚く。
・興奮を鎮める効果がある緑色の寝具に揃える。
さきほど「就寝前にベッドの中でスマホをみる」という生活スタイルを例に出しましたが、そんな方は要注意。この行為は「エスプレッソ2杯分の興奮状態になる」と説明されています。
睡眠の質を高めるには、部屋着ではなくパジャマで寝る、というのも効果的なようです。オムロンヘルスケアとワコールが行った実験によると、スウェットやジャージなどの部屋着で寝た場合は一晩で平均3.54回目覚めてしまう一方、パジャマで寝た場合は平均3.01回と、中途覚醒(夜中の目覚め)の回数が約15%も下がりました。
筆者も、この3年ほど朝5時起きに挑戦しています。この原稿も朝5時から書き始めました。3歳の子供が起きてくるのは毎朝7時ごろ。それまでの2時間は、本当にひとりになれる時間だと実感しています。
まだ家族が寝ているうちに、コーヒーを淹れ、気になっていた本を開き、窓の外を眺める。そうすると、とてもリフレッシュできるのです。また、クリエイティブな作業とも相性がよく、原稿執筆や企画書作成も非常に捗ります。とはいえ、私の場合は24時まで起きていられず、22時〜23時には寝入ってしまうので、坪田さんの提案する効率的なショートスリープはまだ実践できていません。
筆者の周囲にも短時間睡眠を上手に取り入れている人がいます。ハフィントンポスト編集長・竹下隆一郎さんは、24時ごろに寝て、朝5時に起床するスタイル。早朝の時間は、ニューヨークで暮らす仕事仲間とSkypeで会話しながら現地の最新情報を収集したり、子どもの朝ごはんを作ったりして過ごしているといいます。子どもの宿題をみてあげることも多く、「朝は雑音が少ないので、普段より集中して勉強してくれる」と語ります。
「早起きのため、寝る前にはユーカリの香りを嗅ぎながら瞑想します。息の色を想像しながら、ゆったりとした呼吸を繰り返し、心を落ち着かせるんです」(竹下編集長)
ショートスリープを実践している人の多くは、眠りに入るためのルーティンを持っているようです。寝室には、心地のよい香りやリラックスできる音楽、落ち着いて過ごせる照明を用意します。そして、歯を磨き、パジャマに着替え、ベッドに座って瞑想する……。自分なりの“眠りの作法”を見つけることができれば、睡眠の質も自ずと高まるのでしょう。
□グーグルやヤフーは社員に仮眠を推奨
睡眠の満足度をあげる方法は、夜だけではありません。日中の「仮眠」も重要です。『朝5時起きが習慣になる5時間快眠法』には、「中世のころには1日の睡眠を2、3回にわけてとっていた」「多くの動物も、1日に短時間の睡眠を繰り返す『多相睡眠」をおこなっている』という記述があります。
現在、日米のIT企業では、社員に仮眠を推奨する企業が増えています。たとえばグーグルは、米シリコンバレー・マウンテンビューの研究機関に「睡眠マシン」を導入しています。上半身をドームが覆い、睡眠を促す音楽が流れて、外部からの光と音を遮断。体を休めるのに最適の姿勢をとることができ、短時間でもぐっすり眠ることができるのです。タイマーをセットしておけば、振動でやさしく起こしてくれるので、寝過ごす心配もありません。
また日本では、昨年9月に社屋を移転したヤフーが、千代田区紀尾井町の新オフィスに「仮眠スペース」を設けました。従業員が好きな時に「昼寝」のために利用できるスペースで、予約制の「個室」もあるそうです。狙いは、従業員の集中力を高め、生産性を向上させること。就業時間のなかで「昼寝」をとったほうが残りの就業時間の効率が高まる、という考え方のようです。
こうした「昼寝」の効果に、科学的な根拠はあるのでしょうか。睡眠に詳しい東京福祉大学の栗原久教授は、「仕事中の仮眠にはメリットが多い」といいます。
「仕事を続けると脳が疲れて集中力や記憶力が低下して、間違いや事故のリスクが高まります。とくに、午後は疲労の影響が強まります。そこで、午後の早い段階で仮眠をとると、脳の疲労を解消することができ、仕事の能率を保つことにもつながるのです」
つまり仕事で高いパフォーマンスを発揮したい人ほど、仮眠を積極的に取り入れたほうがいいようです。具体的にはどんな環境で「昼寝」をしたほうがよいのでしょうか。栗原教授は次のように解説します。
「刺激が多いと脳は休まりません。通常、脳に入力される刺激の内訳は、視覚が85%、聴覚が10%、皮膚・筋肉感覚が4%、嗅覚・味覚が1%です。そのため、仮眠をうまく取るには、刺激がマイルドな淡い暖色系の照明、超音波(※1)を含む適度な音楽、心地よい香り、そして身体全体を均等に支えてくれる自分にフィットした寝具が大事です。すべてが整った環境を用意するのは難しいと思いますが、できるだけ脳への刺激が少ない場所を選ぶことで、仮眠の質は高まりますよ」
「昼寝」をとる時間帯にもコツがあるそうです。
「午前中に一仕事を終えて、昼食を済ませた12時から14時ごろは生理的に眠気が出てくる時間帯です。そのため、ランチ後に仮眠をとり、脳機能を回復させることが、午後の仕事の効率アップに有効となります。ただし、深い眠りは覚醒までの時間が長くなるので逆効果になりかねない。寝入りすぎてしまうのを回避するには、昼寝の前にコーヒーを飲んで眠り、カフェインの効果が強まる30分後くらいに目覚めるようにするのが効果的でしょう。昼食後の仮眠は生産性の向上に大きく寄与しますから、その仕組みづくりに真剣に取り組んだ企業ほど、成長できる可能性も上がると考えます」
栗原教授は「今後、社員に仮眠をすすめる企業はますます増えていくだろう」といいます。日々の忙しさにてんてこ舞いの皆さん。思い切って「昼寝」を取り入れてみてはいかがでしょうか。
※1:超音波は2万ヘルツ以上の音。人間の耳では音として聞き取れないが、音波が脳に働きかけ、リラックス感を向上させるという説もある。MP3などのデジタル音源は、人間が聞き分けられない音域をカットしてデータ量を圧縮しているが、最近広まりつつあるハイレゾ音源はデータ量も多く、超音波域まで収録している。なお、テープやレコードには超音波が含まれているので、従来からリラックス効果が高いとされてきた。
(上沼祐樹=文)
[プレジデントオンライン]
Posted by nob : 2017年04月19日 10:54
確かに運動後のリセット体操は面倒そうですが、早速試してみたいものです。。。
■【ニッポン柔道式】最先端トレーニングで体力復活!
仕事や運動の疲れを速攻回復、日本柔道式エクササイズを伝授
長時間の仕事で凝り固まった筋肉を伸ばして疲れを取る
松尾直俊=フィットネスライター
2016年のリオデジャネイロ五輪で全7階級でメダルを獲得し、復活と躍進を遂げた柔道男子日本代表。これには科学的なトレーニングによるフィジカル強化に加え、疲労を素早く回復させて、次の日も効率的な練習を繰り返すことができるようになったことも大きい。そこで、井上康生監督のもと、総務コーチとしてトレーニングプログラムの組み立てや疲労回復メニューの指導に当たった日本体育大学准教授の岡田隆氏に、ビジネスパーソンが仕事やオフタイムの運動で感じる疲れの回復にも役立つ“日本代表式ストレッチ”を教えてもらった。
トレーニングや練習を行うと、大きな力を出した筋肉には小さな損傷が起こり、エネルギー代謝によって作り出された代謝物が残る。これらが疲労を感じる主な原因だ。できるだけ早く回復させないと、筋肉痛が長引いたりして、次の練習が効率的にできないことになる。また、回復しきらないうちに新たな負荷がかかることで、筋肉の損傷が重なって大きなケガにつながることにもなりかねない。
「練習や筋トレで大きな力を出した後は、以前より筋肉が短くなったままの状態になります。すると、血管が圧迫されて血液の流れが悪くなり、老廃物の排出が遅くなる可能性があります。また、損傷を起こした筋肉を補修するために必要な、たんぱく質を中心とした栄養の補給も滞るかもしれません。それが選手たちのパフォーマンスを落とす原因となるのです」
こう語るのは柔道男子日本代表の総務コーチを務める、日本体育大学の岡田隆准教授。疲労回復を促すには、筋肉が何度も強く収縮し硬くなって阻害された血流を、いかに早く元に戻すかが大切ということだ。
縮んだままの筋肉が疲労につながる
「シンプルに考えれば分かることですが、筋肉が収縮して固まっているのですから、伸ばしてあげるストレッチが最も適した方法です。意外に思われるかもしれませんが、一流アスリートの中にも、練習前の準備運動は念入りに行っても、練習後のリカバリーやケアをおろそかにする人が結構いるのです。選手たちには、それがパフォーマンスを落とし、けがの原因になることを伝え、練習後のケアをしっかりするように言いました」
これは、一般のスポーツ愛好家も陥りがちなミスだ。例えば久しぶりにジョギングなどを行う時、走り出す前にはストレッチを行うのに、終わってしまえばそのままシャワー、そしてビール…というパターンになる人が多いだろう。すると、翌日からは筋肉痛が続くということになってしまうのだ。
選手たちも同じだ。キツイ練習が終わった後は、早く食事をしてリラックスしたいがために、リカバリーのためのエクササイズを軽く終わらせてしまうことが多いのだという。
「練習を始める前にはできるだけ体を動かす動的ストレッチや、以前にも紹介したHIITなどを行って体を温めることが必要です。しかし練習で動かし、力を出して収縮固定の状態になっている筋肉に対しては、ゆっくり静的ストレッチをすることで血行を回復させてあげるほうが、柔軟性を取り戻すことができて、疲労回復の役に立ちます」(岡田さん)
これはスポーツを行う時だけではない。ビジネスパーソンであれば、長時間のパソコン作業や会議、海外出張時の長時間のフライトなどによって同じ姿勢を強いられることでも、筋肉は収縮して硬くなってしまう。それが筋肉の不快感やコリとして現れ、疲れと感じるのだ。
オフィスでもできる疲労解消ストレッチ
柔道の日本代表選手たちも、練習後に収縮した筋肉を伸ばすストレッチを日々実践している。今回は、一般ビジネスマンの疲労回復にも有効なストレッチを、岡田准教授が実演してくれた動画で見ていこう。
1.胸部と肩甲骨周辺のストレッチ
長時間のパソコン作業で固まりがちな肩周辺の疲労を取る。
動画
両腕を左右に開き、背骨が動くことを意識しながら背中を丸めて行き、顔の前で手のひらを顔のほうへ向けて合わせるようにする。元に戻す時は、肩甲骨を背骨に向かって引き寄せるような感じで動かし、胸を広げる。5往復1セットが目安だが、気持ちよく感じるのであれば、数セット行ってもいい。※音声は入っておりません
2.股関節周辺のストレッチ
意外と盲点。座りっぱなしで動きが悪くなる股関節を回復させる。
動画
膝からすねにかけて、脚を椅子の座面に載せる。反対の脚を曲げていき、太ももの内側にある内転筋とお尻の大臀筋をゆっくりと伸ばしていく。15秒程度伸ばしたら、反対側も同様に行う。※音声は入っておりません
3.ハムストリングスのストレッチ
太もも裏を伸ばし、脚の血流を促進する。
動画
椅子の背もたれに片手を添えて立つ。膝を軽く曲げるようにして、少しお尻を突き出しながら上半身を前に曲げていく。太ももの裏のハムストリングが伸びるのを感じるはず。15秒程度伸ばしたら、反対側も同様に行う。※音声は入っておりません
4.上部体幹のストレッチ
肩甲骨周辺と首後面の疲労感を軽減する。
動画
椅子に浅く座る。背もたれに背中をつけて両腕を上げ、その重みで体を後ろに反らせるイメージで上半身前面の筋肉群を伸ばし、背面の筋肉を押しほぐす。力で無理やり伸ばすのではなく、脱力する感じで15秒程度その姿勢をキープする。ゆっくり元の姿勢に戻す。※音声は入っておりません
どのストレッチもオフィスで簡単にできるものだ。少し疲れを感じたら、どれか一つでもいいので実行すると、疲れが蓄積して不快感が強くなるのを防げるはず。また、仕事中にこのような小さなブレイクタイムを入れることで、作業の効率もアップするはず。ぜひ試してみてほしい。
岡田隆(おかだ たかし)さん
日本体育大学 准教授
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年04月18日 20:05
ほどほどにバランス良く。。。Vol.2/尽きぬ珈琲と緑茶論議。。。
■何杯飲めばいい? 飲むタイミングは? コーヒーVS.緑茶
日本人が好む飲み物の代表格であるコーヒーと緑茶。2015年の国内でのコーヒーの消費量は約46万トン、緑茶の消費量は約8万トンだ。1日にどちらかを必ず飲んでいる人は多いのでは。この2大嗜好飲料は健康にもいいと、ニュースにもなっている。いったいどれだけ飲めばいいのだろうか。
まずは国立がん研究センターの「多目的コホート研究」を見てみよう。この研究では長期観察型の疫学調査を行い、これまでに約14万人を追跡している。
「1990年から調査を続けていて、5年に1回、生活習慣に関するアンケートをとっています。開始時から追跡してデータを蓄積しているので、たとえば病気になった人が20年前にどんな生活をしていたのかがわかるというのがコホート研究です」(同センター社会と健康研究センター疫学研究部室長・澤田典絵氏)
直近のコーヒーと緑茶に関わる調査では、「コーヒーを1日に3杯以上飲む人は脳腫瘍(しゅよう)のリスクが低下する」という結果が出た。
一方で、緑茶をよく飲む人には同様の結果は見られなかったという。
なぜだろうか。東京大学医学系研究科特任助教の齋藤英子氏は言う。
「コーヒーに含まれているクロロゲン酸という抗酸化物質が作用しているのではないかと考えられます。クロロゲン酸はほかにも血糖値の改善や血圧を適切にする効果があると言われています」
では、がぶがぶとコーヒーを飲めば脳腫瘍リスクはぐんぐん減るのか。どうやらそうでもないようだ。澤田氏は言う。
「脳腫瘍に関して言えば答えは出ていないです。海外ではコーヒーを7杯以上飲むとリスクが上昇するという報告もあるんです」
センターでは、日本人の主要死因であるがん、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患と、大きなくくりでの全死亡リスクも調査している。それによれば、1日にコーヒーを3〜4杯飲む人はまったく飲まない人に比べて24%低いという。やはり量をたくさん飲めばいいのかと希望を持ちたくなるが……。
「1日4杯の人まではリスクが下がっているのですが、5杯以上の人になると結果がぼやけているんです。まったく飲まない人と5杯以上飲む人で効果に差はないように見えます」(齋藤氏)
とはいえ、無類のコーヒー好きでも1日に5杯以上飲む人はなかなかいない、と語るのは全日本コーヒー協会専務理事の西野豊秀氏だ。もちろんコーヒーミルで豆をひいていれるコーヒー党だが、それでも毎日4〜5杯だという。
「午前中に2杯、昼に1杯、午後に1〜2杯です。あくまでも嗜好品ですから、健康のためと言って義務的に飲むことはやめてほしいですね。エナジードリンクなどに含まれるカフェインの過剰摂取でアメリカや日本でも死者が出ています」
コーヒーといえば、カフェイン効果を期待して眠気覚ましに飲むという人も多いだろう。その際の注意点はあるのだろうか。
「カフェインの錠剤を併用したり、極端な量を飲んだりというのでなければ問題ないです。140ミリリットルのカップ1杯で約80ミリグラムのカフェインが入っているのですが、カフェイン摂取にうるさいヨーロッパでは、1日400ミリグラムに抑えましょうと言われています。これは単純計算でも5杯以上。やはり飲みすぎはよくないですね」(西野氏)
対して、緑茶はどうだろうか。前述どおり、脳腫瘍に関する調査では緑茶を飲む人にリスクの低下は見られなかった。
「ただ、主要死因による全死亡リスクの調査では、緑茶を飲めば飲むほどきれいにリスクが下がっているんです。これはコーヒーとは異なる点です」(齋藤氏)
緑茶については、1日1杯未満から5杯以上までの調査で、男女ともに摂取量が増えるにつれリスクが低下しているが、特に脳卒中との関連性に注目したい。
「データを見ると、1日に4杯以上飲む人には脳卒中や脳梗塞、脳出血に対して有効に働いています」(澤田氏)
飲めば飲むほど効果抜群!とも言えそうな緑茶だが、飲みすぎることで弊害はないのか。大妻女子大学「お茶大学」校長で農学博士の大森正司氏に聞いた。
「飲みすぎて悪いということはないです。嗜好品として飲む形であれば、飲みたいだけ飲んでください。ただし、実際にはものすごく飲む人でも5杯から10杯。現実的な量で、ということです」
また大森氏によれば、緑茶に含まれているカテキンは、がんの抑制や認知症予防にも効果があるとされているという。
「がん細胞を植え付けたネズミによる実験で、緑茶を飲ませたほうが発がんしなかったんです。加齢による衰えを調べるために迷路の出口に餌を置いた実験では、飲ませていないネズミは出口まで来られなかったんですが、飲ませたほうはちゃんとたどり着くといった結果が出ています」
カテキンにはコーヒーに含まれるクロロゲン酸と同様に抗酸化作用があるため、体によいとされる。バランスのいい摂取方法はあるのだろうか。
「体に吸収されるカテキンの量は飲んだ量の約100分の1です。ですので一気に大量の茶を飲むのではなく、1日に何度もこまめに飲めば、成分を効率よく吸収できます」(大森氏)
緑茶のいれ方にもコツがあると大森氏は力説する。
「お湯の温度によって成分のバランスが変わってくるんです。カフェインは熱湯でしか溶け出しませんが、カテキンはぬるま湯でも溶けます。ですので、カフェインを抑えてカテキンをとりたければ50度ぐらいのぬるま湯でいれるのがいいです。味も温度によって変わりますから、なんでもかんでも熱いお茶というのではなく、おいしいいれ方を探してほしいですね」
コーヒーと緑茶。どちらも共通して言えるのは「1日にほどよい量」を「好んで飲む」のが肝要なようだ。澤田氏は言う。
「私たちのデータは無理やり飲むことをおすすめするものではないです。飲んでいればよい効果があると言えますが、人それぞれの適量があると思いますし、普通に飲んでいただくのなら害はないと言えますね」
[週刊朝日]
Posted by nob : 2017年04月18日 12:09
呼吸、姿勢、歩行が健康づくりのキホンのキ。。。Vol.2/そして生活習慣。。。/まずは睡眠。。。
■あの習慣は逆効果? 睡眠を改善する「4つのNGと3つの法則」
「4つのNG」を回避、「4-6-11の法則」を守ればOK
伊藤和弘=フリーランスライター
仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削ってしまうのが「睡眠」ではないだろうか。また、年齢とともに、眠りが浅くなったり、目覚めが悪くなったりする人も多いに違いない。もう眠りで悩まないための、ぐっすり睡眠術をお届けしよう。
作業療法士・睡眠健康指導士の菅原洋平さんが、企業の依頼を受けて「睡眠マネジメント研修」を行うユークロニアを設立したのは5年前のこと。当初は外資系企業が中心だったが、最近は国内企業からの依頼も増えてきたという。
「事故防止、社員のメンタルヘルス、生活習慣病の予防、生産性の向上、といった目的で依頼される企業が多いです。特に外資系では“スリープ”はビジネススキルの一つと見なされていますので、社内研修に取り入れる企業が多かったのですが、日本でもストレスチェックの義務化をきっかけに昨年から睡眠改善に関心を持つ企業が増えてきました」(菅原さん)
菅原さんが睡眠研修を担当した出光興産で研修に参加した人たちに聞くと、82%が研修による睡眠の改善を自覚したという。加えて、生産性の向上も確認された。
その菅原さんが指導する睡眠改善法の基本は、「4つのNG」を解消することと、「4-6-11の法則」を守ることだ。それはどんなものなのか、順番に説明しよう。
良かれと思ってやっている習慣が逆効果に
まず、「4つのNG」から。例えば「眠る前にコーヒーを飲むと良くない」なんていうのは誰でも知っているだろう。問題は「いい睡眠を取ろうとして逆効果になっている習慣」だ。
1. 寝室で本を読む
眠る前に本を読む習慣がある人は少なくない。それ自体は悪くないのだが、「まずいのはベッドの上で読むこと」と菅原さん。テレビを見る、スマホをいじるといった行為も同じ。要するに、「ベッドの上で眠ること以外の何かをやる」のが良くないという。
菅原さんは「脳にはフィードフォワードという働きがあり、場所と行為をセットで記憶するんです」と説明する。その結果、次にその場所に行ったとき、よりスムーズに同じ行為ができるようになる。本を読んでいれば「ベッドは本を読む場所」、テレビを見ていれば「ベッドはテレビを見る場所」と脳は思い込んでしまうわけだ。それが安眠を妨げてしまう。
それを防ぐには、眠らないうちはベッドに入らないこと。睡眠以外の行為は極力しない。そうすることで、「ベッドは眠る場所」と脳に覚えさせるのだ。
ただし、これまでの生活習慣をやめろというわけではない。「ワンルームマンション暮らしだったら、就寝前にベッド以外のイスなどに座って本を読んだり、テレビを見てもいい。とにかく、ベッドの上でしなければOKです」と菅原さんはアドバイスする。
2. 眠くないのに早起きするため早くベッドに入る
翌朝、出張で早く起きなければいけないときなど、睡眠時間を確保するためにいつもより2時間も早くベッドに入る。ところが、なかなか眠れず、深夜になるまで悶々と過ごしてしまった――こんな経験はないだろうか?
「人間は目覚めて光を見てから16時間後に眠くなるようにできています。無理に早く眠ろうとしても、なかなか眠れるものではありません」と菅原さん。眠れないと、いろいろなことを考える。それが前述のフィードフォワードによって、「ベッドは考え事をする場所」と脳が信じてしまうと、慢性の不眠症にもつながりかねない。
例えば、朝7時に起きたとしたら、「寝るのに丁度よいのは、16時間後の午後11時くらい」などと計算してベッドに向かうといい。多少の早寝は構わないが、眠くもないのに、いつもより早い時間にベッドに入って、無理に寝ようとしてはいけない。
3. 毎日同じ時刻にベッドに入る
規則正しい睡眠リズムを作るため、毎日同じ時刻にベッドに入る。いいことに思えるが、まず意識すべきなのは就寝時刻ではなくて起床時刻が正解だ。一般的には目覚めて光を見てから16時間後に眠くなるので、「就寝時刻ではなくて、起床時刻を一定にすることが大切なんです」と菅原さんは話す。
毎日同じ時刻に眠って同じ時刻に起きられれば確かに理想的だが、仕事に追われるビジネスパーソンが毎日同じ時刻に就寝するのは難しい。ときには眠くならない日もあるだろう。そんなときに無理にベッドに入っても、なかなか快適な眠りはやって来ない。
一方、毎日の起床時刻を同じにして、同じ時間に朝日を見ていると、少しずつ就寝時刻もそろってくるようになるという。
特に注意してほしいのは休日だ。平日は出社のため早く起きなければいけないが、休日なら昼まで寝ていることもできる。しかし、そうすることで平日にできていた体内時計のリズムが崩れてしまう。平日と同じ時刻に起きるのは無理でも、「寝坊による起床時刻の遅れはせめて3時間以内に。そうしないとメンタルの不調が起こりやすくなります」と菅原さんは注意する。それでは足りないという人は、前日に少し早めに寝るようにしよう。
4. 帰りの電車で睡眠不足を補う
通勤電車で睡眠不足を補っているビジネスパーソンも多い。行きの電車で寝るのはまだいいが、帰りの電車で寝るのはいけない。睡眠圧といって、起きている時間が長いほど直後の睡眠は深くなる。「夕方以降に眠ると睡眠圧が減って、夜間のメジャースリープが浅くなってしまうんです」と菅原さん。
特に通勤時間の長い人は要注意だ。夕食後のうたた寝も同じく良くない。夕方以降は眠くてもガマン。たっぷり睡眠圧をためて爆睡しよう。
3種類の生体リズムを整える
「4つのNG」を覚えたら、次は「4-6-11の法則」を実行してほしい。これは睡眠に関係する3つの生体リズムを整える方法で、数字はそれぞれの時間を表している。
■起床後4時間以内に光を見る(メラトニンリズムを整える)
夜になると、脳の松果体からメラトニンというホルモンが分泌されて眠くなる。一方、早朝を迎えて強い光を見ると、メラトニンの分泌が止まって眠気が消える。だから、起きたら光を見ることが大切なわけだ。前に触れたように、光を見ると16時間後に再びメラトニンが増加する。
起きても窓を開けずに薄暗い部屋で過ごしていると、メラトニンの分泌が止まらず、いつまでも目が覚めない。メラトニンを止める感度が最も高いのは起床後1時間以内。時間が経つほど感度が落ちて、起きてから4時間以上経つと光を見ても反応しなくなる。起きたら1時間以内に朝日を浴びるのがベスト、自宅に籠もりっきりの日でも4時間以内には光を見るようにしよう。
■ 起床後6時間経ったら仮眠タイム(睡眠-覚醒リズムを整える)
目覚めてから最初の眠気がやって来るのは8時間後。朝7時に起きている人なら午後3時頃だ。「この時間に眠くなりやすい人は、起床後6時間が経った頃、一般的には昼休みの時間に仮眠を取るといいでしょう」と菅原さん。
昼間の仮眠のポイントは「眠くなる前に」「1~30分以内」「イスに座ったまま」「起きる時刻を3回唱える」ことだ。
わずか1分目を閉じるだけでも、脳を休めることができる。6分以上の仮眠で、その後のパフォーマンス低下を防ぐことも確認されている。ただし、30分以上寝ると睡眠が深くなって、夜のメジャースリープに影響するのでNG。仰向けにならず、イスの背もたれにもたれて寝たほうがいいのも同じ理由だ。
「自己覚醒法といって、寝る前に起きる時刻を3回唱えると意外とスムーズに起きられます。夜の就寝前にも、ぜひやってみてください」と菅原さん。目覚まし時計を使わずに決めた時刻に起きると、気分がいいのはもちろん、日中の居眠りも少なくなるという(Psychiatry Clin Neurosci. 2002 Jun;56(3):223-4)。
■起床後11時間経ったら体を動かす(深部体温リズムを整える)
睡眠中は体温が下がる。起床後は体温が上がり出し、起床してから11時間経つと、体温が最も高くなる。このタイミングで運動すると、さらに体温が上がり、眠るときスムーズに下がりやすい。逆にこの時間帯に眠ってしまうと、夜中に体温が下がりにくくなり、眠れなくなってしまうという。
朝7時に起きた場合、11時間後となるのは午後6時だ。快眠のためには、運動は夕方から夜のほうがいい。会社からの帰りに、一つ前の駅で降りて歩くのもいいだろう。特に気をつけてほしいのは休日の夕方だ。つい家でゴロゴロしがちな時間帯だが、散歩でも買い物でもいいので体を動かすことを心がけてほしい。
この「4-6-11の法則」すべてを実行しようと思わなくてもいい。「一つ整えば自然と他のリズムも整っていきます。やりやすいものを一つ注意するだけでも効果はあるはず」と菅原さんは話す。睡眠を改善したい人は早速今日から試してみよう!
菅原洋平(すがわら ようへい)さん
ユークロニア社長、作業療法士、睡眠健康指導士
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年04月16日 23:40
重傷ですね、、、薬剤は即効性はありますがあくまで対症療法、私はじっくりと自然療法で克服というよりも協調できるようになりました。。。
■ライブ続行で荒療治…円広志さん「パニック障害」を語る
「パニック障害」と診断されるまでが苦しかったですね。診断されたときはホッとしました。「気持ちの問題じゃなくて病気なんだ」とわかって、とてもうれしかったんです。
この病気は、脳の中の不安や危険を感じたりする神経が誤作動を起こし、不安や危険がないのに恐怖や回避行動を起こしてしまう病気です。今でもトイレが怖い日もあるのですが、薬で劇的に良くなりました。
発症したのは、約20年前。そのころは、毎日の生放送を含め週10本以上の仕事があって、ものすごく忙しかったんです。にもかかわらず、金曜は学生時代の友人とほぼ毎週、夜遊びに興じていました。当時は二日酔いと寝不足を楽しんでいたんです。忙しいのがうれしかったし、仕事がどんなに忙しくても夜遊びもちゃんとするのが“ザ・芸能人”みたいなね(笑い)。「たぶん、関西で一番寝不足なのは俺ちゃうかな」なんて言っていた時期でした。
■スタジオが怖くて生放送では時計ばかり見ていた
いつごろからか、クルマを運転していたらなんとなくトンネルが怖くなっていて、「嫌だな」と思っていたら、ある日異変が起こりました。渋滞でブレーキを踏んでいるのに景色の方が動いている感覚になったのです。「このままじゃぶつかる」とブレーキをさらに踏むけれど、止まっているからぶつかるわけがない。でも、景色はまた動きだす。そんな現象が帰宅するまで続いたのです。それをきっかけに、急にすべてのことが怖くなりだしました。
症状としては、小さい音がやたら大きく聞こえてびくびくするとか、夕暮れになるとなぜか怖くて泣いてしまうという状態。仕事でもスタジオが怖いのです。1時間の生放送の前半はずっと怖くて、「倒れるんじゃないかな」「いつ終わるんだろう」と時計ばかり見ていました。最後の10分ぐらいになると落ち着くんですが、日に日に恐怖感が増していくばかり。
そしてある日、番組終わりのテレビ局の駐車場で「俺を責めないでくれ!」と号泣してしまったんです。景色が動きだした症状が出てから、たぶん半年後ぐらいでしょうか。マネジャーもさすがにおかしいと思って、すぐにすべての番組を降板。病院へ行きました。
でも、当時はパニック障害という病気はあまり知られていなくて、「精神的な病気」と言われました。確かに食欲もなくなるし、ゴハンの味もない。一番ひどいときは「死ぬんじゃないか」とか「本当に生きているんだろうか」と思ったりして、「鬱」のようにもなりました。
脳の検査もしました。過呼吸や心臓が痛くなったりもしたので、心臓の検査もやりましたけど異常なし。トイレはドアを開けっぱなしにしても怖いし、散髪も怖い。行きつけの散髪屋ですら、店内が怖いので路上で切ってもらっていたほど。店内で大丈夫になったのは最近です。でも、10分ぐらいが限界ですよ。
故郷の高知に帰った時期もありました。それでも、夕暮れになるとメソメソ泣く症状は治まりません。ただ、お酒を飲むと落ち着くのです。だから、この病気でアルコール依存症になる人もいるらしいですよ。
■番組降板後もライブは続行。“荒療治”が運よく功を奏した
病名がわかったのは、番組降板から2〜3カ月後のことで、とある病院の「めまい科」でした。ふらつきがあったので受診したら三半規管に異常はなく、「パニック障害」と診断されました。処方された薬は毎食後に飲む安定剤のような薬と、症状が出たときに飲む頓服薬。で、その頓服薬がすぐ効きました。神経を鈍らす薬なんでしょうかね。そこから少しずつ楽になりました。
実は番組降板後も、ライブはキャンセルすると違約金が発生してしまうのでやるしかなくて、ステージ脇にベッドを置いたり、ピンスポットが怖いので客席が見えるように明かりをつけてもらったりしながら続けました。普通は外出なんてできず、今日は1歩だけ外へ、明日は2歩……といった経過をたどるわけですから、いわばかなりの荒療治です。でも、その荒療治が運よく功を奏したことと、頓服薬のおかげで今に至っています。運転も大丈夫になりました。
ただ、寝不足になるとお約束のように体調が悪くなります。医師には「君の病気は死ななきゃ治らないよ」と言われました。つまり、病気は自分そのもの。顔と同じで「持って生まれたものなんだ」と病気を受け入れました。多くの人は今の社会のスピードや仕組みに追いついているけれど、それに馴染めない人もいる。私も若いころははね返せたけれど、年齢とともに無理ができなくなったのだと思います。
今言えるのは、「がむしゃらに頑張るのもいいけれど、勇気を出して自分の生き方を探すことがあってもいい」ということ。私にとってのパニック障害は、今や体調のバロメーターです。
▽まどか・ひろし 1953年、高知県生まれ。78年、自身が作詞・作曲した「夢想花」でレコードデビュー。森昌子の「越冬つばめ」など数々の作曲を手掛ける。現在は関西テレビ「よ〜いドン!」にレギュラー出演中。著書に「パニック障害、僕はこうして脱出した」がある。
[日刊ゲンダイDIGITAL]
Posted by nob : 2017年04月11日 15:32
ほどほどにバランス良く。。。
■「酒は百薬の長」はあくまで“条件付き”だった
「適量の飲酒なら健康にいい」は、すべての病気でいえるわけではない
葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト
お酒は一般に、「適量の摂取なら健康にいい」といわれている。左党の多くにとって、これがお酒を飲む際の安心材料の一つとなっている。しかし、これは本当なのだろうか。そして、すべての人に対して言えることなのだろうか。そこで今回は、“適量飲酒”の健康への影響をまとめた。
「適量の飲酒は長生きにつながる」は本当か
「酒は百薬の長」―。
そんな言葉を裏付けるよう、昔から「お酒は適量摂取」なら健康効果があるといわれている。まさに左党にとっては印籠のような言葉になっているといってもいいだろう。「酒を飲まないより、飲んでいるほうがカラダにいい」と勝手に解釈し、飲む言い訳にしている人も多いのではないだろうか。
この「適量の飲酒は長生きにつながる」ことを裏付けるデータがある。専門用語で「Jカーブ効果」と呼ぶものだ。飲酒量を横軸に、死亡率を縦軸にとると、グラフの形状が「J」の字に似ることからそう呼ばれている。
つまり、適量を飲む分には死亡率が下がるが、一定量を超えてくると、死亡率が上がってくるというものだ。このグラフは、酒の健康効果を示す図としてさまざまなシーンで登場するので、左党はもちろん、そうでない方も少なからず目にしたことがあるのではないだろうか。かくゆう筆者もそうで、酒を飲む際の安心材料の一つとして、ありがたく崇めている。
しかし、ふと冷静になって考えてみると、このJカーブ効果は、実際のところどうなのだろうか。死亡率が下がるというのはもちろんだが、すべての病気、すべての人に対して同じ傾向を示すのだろうか。世の中には、例えば高血圧などの持病を抱えている人は多いし、アルコールに対する耐性が強い人もいれば弱い人もいる。男女差、年齢などなど、考え出すときりがない。
うううむ、ここはひとつ、より安心して酒を飲むためにも、真偽を確かめねばならない。ということで独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター院長の樋口進さんにお話をうかがった。
Jカーブ効果は、すべての病気にいえるわけではない
「結論から言いますと、コホート研究などにより、飲酒と総死亡率についてはJカーブ効果が認められています。ただし、すべての疾患に対してあてはまるわけではありません。つまり、病気によっては、少量の飲酒でも悪影響を及ぼす可能性があります。少量の飲酒がすべてに対していい効果が出るというわけではないのです」(樋口さん)。コホート研究とは、一般住民の集団を対象にした長期にわたる観察型の疫学研究のことだ。
樋口さんによると、飲酒量と健康リスクについては、欧米や日本で研究が進められており、飲酒量と総死亡について「Jカーブ」の関係にあることが示唆されているそうだ。「欧米人を対象とした14の研究をまとめて解析し、1996年に発表された報告では、男女ともに1日平均アルコール19gでの飲酒者の死亡リスクは非飲酒者より低くなっています」(Holman CD,et al. Med J Aust. 1996;164:141-145.)。
国内でも、大規模コホート研究により、適量飲酒が死亡リスクを低下させているという結果が出ている(Ann Epidemiol. 2005;15:590-597.)。これは国内の40~79歳の男女約11万人を9~11年追跡した結果で、総死亡では男女ともに1日平均23g未満(日本酒1合未満)で最もリスクが低くなっている。
このような国内外での報告から、「適量飲酒は死亡率を下げる」ということが通説となっているわけだ。なお、樋口さんは、次のように補足する。「コホート研究の結果によって、少量飲酒者の死亡率が低いという結果が出ていることは確かです。しかし、これは飲酒との因果関係を示すものではありません」。また、「Jカーブ効果が認められているのは、先進国の中年男女だけ」(樋口さん)だという。
高血圧、脂質異常症などは少量飲酒でもリスクは高まる
先ほど樋口さんが話したように、Jカーブ効果が認められるのは、ある一定の疾患に限られるという。
私はこれまで、「酒は百薬の長」で、「適量飲酒はカラダにいい!」と長年信じてきたが、樋口さんの一言でかなり怪しくなってきた…。では一体、少量飲酒であってもリスクが高くなるのはどんな疾患なのだろう。
「少量飲酒であっても、リスクが上がるのは主に高血圧、脂質異常症、脳出血、乳がん(40歳以上)などです。これらの疾患は、飲酒量に比例してリスクは直線的に上がっていきます。つまり、少量でも飲酒すればリスクは上がります。乳がんは遺伝的な要素が強い疾患ですが、それでもアルコールを飲まないより、飲むほうが罹患リスクは上がります」(樋口さん)
「肝硬変の場合は、指数関数的な傾向を示します。飲酒量が増えるとリスクが上がるのは同じですが、少量の場合のリスクの上がり方は穏やかで、ある水準を超えると一気にリスクが高くなります」(樋口さん)
樋口さんの挙げる疾患名を聞いて、恐れおののく。高血圧も脂質異常症も乳がんも、いずれもミドル以上におなじみの病気だ。しかしそうであれば、なぜ全体の死亡率については、「適量の飲酒でリスクが低くなる」という傾向が見られたのだろうか。
「上のグラフにあるように、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患、脳梗塞、2型糖尿病などは、少量飲酒によって罹患率が下がる傾向が見られます。そして、心筋梗塞などの心疾患が死亡率に及ぼす影響はとても大きいのです。つまり先に挙げた少量飲酒によってリスクが上がる疾患より、心疾患などリスクの下がる疾患の影響が大きいために、全体の総死亡率としては、Jカーブのパターンになっているのです」(樋口さん)。このほか、樋口さんによると、(高齢者の)認知機能低下についても、発症するリスクが低くなることが確認されているという。
なるほど、そういうことだったのか。では、これらの結果をどう受け取り、飲酒をどうしていけばいいのだろうか。樋口さんに聞いてみた。
樋口さんは、「高血圧、脂質異常の持病を持った方、肝機能の数値がおもわしくない方、乳がんに罹患した人が身内にいる方などは、少量飲酒でもリスクが高まるわけですから、通常の方より飲酒量を抑えるように注意したほうがいいのは確かです」と話しながら、こう続けた。「とはいえ、飲酒はコミュニケーションツールであり、日常のストレスから解放してくれる楽しみの一つでもあります。例えば高血圧の方が飲酒量を抑えた方がいいのは確かですが、過度に神経質になる必要はありません」(樋口さん)
注意するに越したことはないが、過度に神経質になり過ぎることはない。これを聞いてちょっとホッとする。ムチャ飲みせず、楽しむ程度にたしなめば、酒は決して怖いものではないのだ。
お酒を飲んで顔が赤くなる人は注意
ここまでの説明で、飲酒によるリスクが病気により異なることはよくわかった。では、アルコールに対する耐性が弱い人、つまりお酒を飲んですぐ顔が赤くなる人はどうなのだろうか。
久里浜医療センター院長の樋口進さんは、「高血圧や脂質異常症などの疾患がある方はもちろん、アルコールが弱い方、高齢者の方も飲酒量を抑えた方がいいでしょう」と話す。
「アルコールを飲んで顔が赤くなる人、つまり生まれつきアルコールの分解能力が低い人は注意が必要です。こうした体質の人は飲酒によって食道がんなどのリスクが高まることがわかっています。飲酒量は、飲める人に比べて抑えた方がいいでしょう」(樋口さん)
さらに、樋口さんによると、リスクがより高いのは高齢者なのだという。「高齢者はアルコールを分解するスピードが遅く、体内の水分量も少ないため、血中アルコール濃度が高くなりやすいからです。持病を抱えている人が多いですしね。また、飲酒時の転倒リスクも高まります。これが原因で骨折して、寝たきり生活になってしまうというケースも少なくありません」(樋口さん)
高齢者の飲酒は、さまざまなリスクとの背中合わせということか…。筆者はまだ高齢者に分類されるに至ってないが、確かに年齢を重ねるごとに、酒が抜けにくくなっているのは事実。樋口さんの言葉がザクザクと突き刺さる。
「結局、飲まないに越したことはないの?」と悲観的になってしまいそうだが、樋口さんは「無理に断酒することはない」と話す。飲み過ぎの人は飲む量を減らすことから始めてほしいと話す。
「アルコール健康障害で病院を訪れる患者さんにも同じことが言えるのですが、習慣化している飲酒をいきなり断つことはストレス以外の何ものでもありません。『飲酒をやめなさい』という上から目線の指導は逆効果です。ではどうしたらいいか? それは“無理のない範囲”で量を減らすこと。その量も本人が決めることが大切です」
少しでもいいから減らすことが大切! 記録をつけよう
「よく飲酒量の目安として、男性の場合、アルコール換算で20g程度(ビール中瓶1本、日本酒なら1合程度)などと言われますが、いつも飲んでいる量をいきなり3分の1や2分の1に減らせと言われてもなかなかできません。ですから、目標をつけて、少しでもいいから減らすことが大切です。お酒の量を多少減らしただけでも、リスクは確実に下がります」
「例えば、一日に焼酎を2合飲むのが通例なら、1.5合に減らすといった具合に小さな目標を設定するのです。そして、さらに大切なのが目標をクリアできたら手帳に〇(マル)をつけること。すると、自然と飲む量を頭でモニターするようになります。そうした日々の小さな成功体験を重ねることで、飲む量は自然と減っていきます」(樋口さん)
ダイエットにも言えることだが、飲酒においても「レコーディングする」ことで飲酒量を減らす成功率はアップする。また樋口さんによると、「周囲に公言することも効果的」だという。公言してしまった手前、やらずにはいられなくなるからだ。
なるほど、断酒はできなくとも、これだったらすぐにでも実践できそうだ。
前述のように、アルコール摂取の適量は、男性なら純アルコール換算で20gだが、女性は半分の10g(ビール小1缶)程度だ。「す、少ない…」と思う方も多いだろう。左党にとって、この量を守るのはかなりハードルが高いが、飲み過ぎの自覚がある人は、この量に少しでも近づこうとする努力はしたほうがよさそうだ。
しかし、量を減らしたり、休肝日を作ったりすると、やってしまいがちなのが「どか飲み」。左党は「昨日、休肝日だったから倍の量を飲んでも大丈夫」と自分に都合のいい言い訳をつけてしまいがちだ。
「適量である20gを一週間続けるのと、一日にまとめて140g飲むのとでは、後者のほうが数段、カラダに負担がかかります。休肝日をつくりつつ、まとめてどか飲みするのではなく、日々適量を守ることが大切です」(樋口さん)
樋口さんによると、そもそも休肝日という言葉は日本だけのものだという。「欧米では肝臓を休めるというよりも、アルコールに依存しないために飲まない日を作るという考え方をします」(樋口さん)
◇ ◇ ◇
地道に毎日、適量を守る。飲み過ぎの人は少しずつでも量を減らす―。
結局のところ、さまざまな疾患のリスクを減らすには、これ以外の得策はないようだ。といってもJカーブのからくりを知ってしまった以上、少量、適量であっても安心はできないということを心しておかねばならない。「酒は百薬の長」という言葉は、あくまでも条件付きなのだから。
樋口 進(ひぐち すすむ)さん
独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター院長
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年04月09日 17:30
呼吸、姿勢、歩行が健康づくりのキホンのキ。。。
■あの人のカラダマネジメント術
正しい姿勢で「ドローイン」それだけで体幹は鍛えられる
人気トレーナー・木場克己さんのカラダメンテ術
松尾直俊=ライター
年齢を重ねるに従って筋力は低下し、そのまま高齢になると健康な生活を送れなくなってしまう。それを防ぐために日々できることと、自らが実践している方法を体幹トレーニングで有名なトレーナー、木場克己さんに聞いた。
木場克己さんは、サッカーの長友佑都選手をはじめ、多くのアスリートや有名人、将来を有望視されるサッカーのジュニアユース選手などに“体幹バランストレーニング”を指導し、実績を上げている人物。第1回「腹を凹ますだけ! プロ直伝、太りにくい体になる体幹トレーニング」では「ドローイン」を紹介したが、今回は、体幹部や下肢の強化につながる「姿勢の正し方のコツ」について教えてもらった。
◇ ◇ ◇
第1回では「ドローイン」について話しましたが、ちょっとしたコツを覚えると、より効果的にドローインで体幹深層部にある筋肉、インナーマッスルを鍛えることができます。そのコツとは「姿勢を正すこと」です。実は、日常生活の中で正しい姿勢を意識するだけでも、体幹を強化していくことができるのです。
最近は会社での長時間のパソコン作業や、電車の中などでのスマートフォン(スマホ)いじりなどの影響で、背中の丸まった、いわゆる「猫背」の人が増えています。猫背は見た目が悪いばかりでなく、胸を圧迫するために呼吸が浅くなり、体に十分な酸素を取り入れられない状態を作り出します。また、頸椎(けいつい)の自然な湾曲がなくなる「ストレートネック」の原因にもなり、肩こりや頭痛、ひどい場合は頚椎ヘルニアになることもあります。さらに、脳から頸椎を通って全身に張り巡らされている神経を圧迫したり、脳への血行を阻害したりするために、内臓の不調やうつ症状を促すという医療関係者もいます。
正しい姿勢のコツは、肩甲骨を意識すること
猫背になっていないかをチェックするには、まず、いつも通りの姿勢でまっすぐに立ってみてください。この時に、ご自分の手が太ももの横にまっすぐに来ていれば、まず大丈夫です。しかし、猫背になっている人は、手が太ももの前に出ます。この状態だと頭が前に下がって重心が前になるので、脚を引き上げられずに階段や段差でつまずきやすくなるんです。
まっすぐに立った時、自分の手が太ももの真横に来ていればOK。猫背になっている人は、手が太ももの前に出る。
正しい姿勢を作るコツは、胸を張るよりも肩甲骨を意識することです。多くの人が長時間のパソコンやスマホ操作のために肩が前に入り、肩甲骨周りが広がっています。つまり胸の大胸筋が縮んでしまっているんです。それが猫背の原因ですが、是正するにはまず腰に軽く手を当てて、肩甲骨を背骨に寄せるようにします。肩こりがある人は、それだけでも気持ちがいいはずですよ。
そして自然に肩周りの力を抜き、頚椎の上に頭部がのるように意識します。すると横から見た時に、背骨が自然なS字を描く姿勢をつくることができるのです。
姿勢を正して体を固定すると、体幹部や腰の周りの筋肉を使うので、その強化につながります。そうして膝とつま先をまっすぐに前に向け、膝をしっかり引き上げて歩けば、全身に刺激が入ります。
これは私も意識して実行していることで、特別な時間を作らず、日常生活の中でできる体幹バランストレーニングの方法です。そうした姿勢で日々過ごしていると、体幹にある太ももを引き上げるインナーマッスル(腸腰筋)が強くなりますから、下肢もよく動かせるようになります。すると、脚全体の筋肉の衰えを防ぐこともできます。買い物や通勤途中の移動、散歩の時などに試してみてください。
正しい姿勢でドローインをすると、より効果的
今こうして話している間もドローインをしています。
正しい姿勢でドローインをすると、インナーマッスルの腹横筋や多裂筋、腹斜筋群、腸腰筋などをうまく刺激することができます。時間がある時には、ドローインをしたまま3秒で鼻から息を吸って、5秒かけて吐き出すというのを10回くらい繰り返してみてください。息を吐き出す時に、ドローインした腹部が緩まないように気を付けることが、効かせるためのコツです。そうすることで効率良くインナーマッスルが鍛えられます。
正しい姿勢を保つことやドローインは、今こうして話している間にもできます。実際に私も取材や打ち合わせの時、そして移動で電車に乗っている時や歩く時にも、肩甲骨を引いて胸を開き、ドローインを実践しています。そうすればわざわざトレーニングの時間を取らなくても、常に体幹を鍛えることになりますから。
ただ、最初のうちは四六時中やっているのは難しいかもしれません。その場合は、日常生活の中で気がついた時に、正しい姿勢とドローインを30秒から1分くらい維持することから始めるのでもいいです。
インナーマッスルは加齢とともに衰え、その衰えは、首・肩のこりや腰痛、脚の筋力低下、ダイエット後のリバウンドしやすさなど、様々な体の不調につながります。そのインナーマッスルを鍛えるのに役立つ体幹トレーニングは、1回や2回で効果を出すことを求めるのではなく、地味な運動と心がけを継続することが大切です。選手たちにもそう言って指導しています。私も50歳を過ぎましたが、インナーマッスルを意識しながらここで紹介したような方法で日々体を鍛えています。こうしてメンテナンスしながら、求められる限りはトレーナーとしての仕事をやっていこうと思っています。
木場克己(こば・かつみ)さん
鍼灸師、柔道整復師、日本体育協会公認アスレティックトレーナー
[日経Gooday]
Posted by nob : 2017年04月06日 21:17
私は極端に身体が固いのですが、特に疲れやすくはありません、、、それでも柔らかくなりたい。。。
■疲れやすいのは「体が硬い」せいかもしれない
べたーっと開脚したり前屈する姿を見ると感心しますが、体が柔らかいことは健康面でメリットがあることを知っていますか?
「私は体が硬いもので」「歳のせいかめっきり体が硬くなって」などと嘆く人は多い。確かに硬いより柔らかいほうがいいような気がするが、実際のところ体が硬いとどのような不都合があるのだろうか。そもそも体のどこがどのように硬いのだろうか。
体の「柔軟性」という言葉があるように、柔らかさの定義を調べたほうが話が早そうだ。厚生労働省によれば、柔軟性とは「筋肉と腱が伸びる能力」のことで、筋力、瞬発力、持久力、調整力とともに基本的な運動能力のひとつとされている。つまり体が硬いということは、筋肉と腱が伸びる能力に欠けるということである。
体力テストの「前屈」の意味
柔軟性は代謝や血行に影響する
柔軟性には「静的柔軟性」と「動的柔軟性」がある。静的柔軟性はいわゆる体の柔らかさで、一般に柔らかいほど普段の生活でのケガが少なく、疲労も回復しやすいとされる。動的柔軟性は体の動かしやすさ、つまり運動のしなやかさのことで主に競技能力に関わるものだ。言い換えれば、体が硬いと動作が不自由なだけでなくケガをしやすく、疲れやすいということになる。また体が硬く緊張状態にあると代謝や血行が悪くなりやすい。つまり腰痛や肩こりなどの不調や、免疫や代謝などあらゆる体機能の低下につながるとの説もある。
体力テストの立位体前屈で体を深く曲げられたとして、「それに何の意味があるの?」とお思いの人もいるかもしれないが、柔軟性が高いということには大きな意味があるわけだ。
前述のように体の柔軟性は「関節可動域」により左右される。関節可動域とは字面のとおり、体の各関節が自然に動くことのできる範囲のことで、「骨格構造」と「軟部組織(筋肉や関節など)」によって決まる。骨格の構造は生まれつきのものであり、努力によりどうにかなるものではないが、体の組織なら変えることはできる。
関節可動域を変えるための手段がストレッチ運動だ。私たちはストレッチをすると関節が動きやすくなったり、筋肉が伸びやすくなること、運動前や後のストレッチが大切であることを経験から知っているが、もともと筋肉や関節の柔軟性を高めるための運動なのである。
ラジオ体操は優秀なエクササイズ
過度な効能を謳うストレッチにはご用心
ストレッチには、比較的軽い運動というイメージがある。やりようによってはいくらでもキツくできるのだが、一人でもできる、時間や負荷を簡単に調節できる、場所を選ばないという意味でとっつきやすい運動なのは確かだ。
運動の習慣がなく体の硬い人が、どれストレッチでも始めてみようというとき、困るのが選択肢の多さだ。ほとんど「効能」に近いことを謳う様々なストレッチやその類があり目移りしてしまう。
無難なのは定評のあるストレッチを選ぶこと。例えばラジオ体操第一・第二もいいだろう。全身の筋肉や関節を動かすようにデザインされた体操だから、ストレッチとしても優秀である。体が覚えているはずだからとっつきやすく、見かけ以上にカロリーを消費するのでダイエット向きでもある。
あえて流行に乗ってしまうのもよい。メディアに当たれば、ここ最近話題となっているストレッチがいくつかみつかるはず。現在は背中柔軟性ストレッチ、横隔膜ストレッチが話題に上り続けている。極端な内容だったり、ありえないほど多くの効能を謳っていない限り、どれでもいい。その場で試してみて「キツいけれど気持ちいい」と感じたら、そのストレッチに決めてしまおう。続けるにはまず始めてみることだ。
(ライター 工藤 渉)
[DIAMOND男の健康]
Posted by nob : 2017年03月15日 15:30
アレルギーとまでは言わないまでも、私の場合はウェイトロスはもちろん、乾燥肌や蕁麻疹などが大幅に改善しました。。。
■ジョコビッチ選手を変えたグルテンフリーの食事法の効果(前編)
文:山本奈緒子
錦織圭選手の大活躍とともに、テニスが注目を集めています。その錦織選手が2014年、準優勝をした全米オープンで、決勝進出をかけて死闘を繰り広げた相手が、現在、世界ランク1位のノバク・ジョコビッチ選手。
そのジョコビッチ選手の著書が、いま驚異的な売り上げを記録中です。その著書のタイトルは、『ジョコビッチの生まれ変わる食事〜あなたの人生を激変させる14日間プログラム』というもの。10万部を超え、Amazonでも総合3位に入るなど、その勢いはとどまるところを知りません。
実は世界トップのアスリートであるジョコビッチ選手、ある食事法を取り入れた途端、劇的に成績がアップ。いきなり3つのグランドスラム大会を制し、一躍、世界ランキング1位に躍り出ました。好調は現在も続いており、2015年もウィンブルドンや全米オープンなどグランドスラム大会3勝。さらに4度目の年間世界ランキング1位が確定するなど、まったく他を寄せ付けません。
ではジョコビッチ選手は、一体どんな食事法を実践したのでしょうか?それこそが、ダイエットだけでなく、実は今や多くの一流スポーツ選手やアスリート達が取り入れ始めている食事法、“グルテンフリー”なのです。
そこで、グルテンフリーの目を見張る効果と、実践する上でのポイントなどを、その著書から抜粋してご紹介しましょう。「疲労感が抜けない」「いつも頭がボンヤリしている」という人は、ぜひ試してみてください。
そもそもグルテンフリーとは?
グルテンとは、小麦や大麦、ライ麦といった穀物に含まれるタンパク質のこと。実は、自分では気付いていないことも多いのですが、このグルテンのアレルギーを持っていて、小麦などの穀物を食べると、息切れやめまいといったさまざまな不調を起こす人が、意外にも多いのだそうです。
ジョコビッチ選手は、まさにそのアレルギーの持ち主だったのです。そこで、パンやパスタなど、グルテンを含むあらゆる小麦製品を断って、健康を取り戻そうとしました。それが、グルテンフリー食事法というわけです。
グルテンフリーで得られる効果
ジョコビッチ選手は、グルテンフリーの食事法を14日間取り入れたところ、1週間たったあたりから、次のような効果があったそうです。
・身体が軽くなり、やる気が湧いてきた
・体重が減少した
・脳内の霧が晴れ、思考が明瞭になった
・長年悩まされていた鼻詰まりが消えた
その後、試しに再びグルテン製品を摂取したところ、あっという間に、めまいとさまざまな不調が再発したといいます。
このグルテンアレルギーは、気付きにくいのですが、「5人に1人が持っている」といわれています。いつも身体が重い、すぐ気弱になる、という人。「ストレスのせいだ」と片付けているかもしれませんが、実はグルテンアレルギーによるものかもしれません。試しに14日間だけ、小麦製品をやめてみてはいかがでしょうか?
グルテンアレルギーか調べるテスト方法
「もしかしたら、自分もグルテンアレルギーかも」と思った人には、簡単に調べられるテストがあるので、ご紹介します。それは、以下の方法です。
1.まず、左手をお腹に当て、右手は真横にまっすぐ伸ばす。
2.誰かに右手を下方向へ押してもらい、自分は右手を下へ押されないよう抵抗する。このときの右手の反応が、健常な状態のときの身体の反応である。
3.次に、左手にパンを持ち、お腹の前に当てる。右手は2と同じく、真横にまっすぐ伸ばす。
4.再び、右手を上から下方向へ強く押してもらう。このとき、パンを持っていないときより抵抗する力が弱い場合、身体がパンに含まれる小麦を拒絶している証拠といえる。
このテストは、パン以外の物でも応用できます。試しに携帯電話を持ってやってみると、「その電磁波が腕の力を弱めていることに気付くだろう」とのことです。
グルテンフリーはダイエットに最適
アレルギーでなくても、小麦は糖分が多いので、血糖値を急激に上げてしまうという弊害があります。糖質の多いものを食べると、身体は血液から血糖を取り除こうとします。そして脂肪細胞を血中にたくさん送り込んで、血糖を取り込ませようとするのです。
逆に考えれば、小麦製品を食べないようにしさえすれば、血糖値が急激に上がることもなくなるし、脂肪細胞を血中に送り込む必要もなくなる。つまり、太りにくくなるということです。
実際にジョコビッチ選手は、グルテンフリーの食事を始めてから、それまでなかなか落ちなかった体重が5kgも落ち、身体が軽くなったそうです。グルテンフリーは健康的に体重を落とせるので、ダイエットをしている人にもお勧めの方法といえます。
グルテンを含む食べ物
では、グルテンはどんな食べ物に含まれているのでしょうか?例を幾つか挙げてみましたので、参考にしてください。
・パン
・パスタなど小麦から作られた麺類
・揚げ物の衣
・ケーキやドーナツなど小麦から作られたスイーツ
・クッキーやクラッカーなどのスナック
・ビールなど麦芽から醸造されたアルコール飲料
・醤油や味噌などの調味料
・加工チーズ
・インスタントのお茶やコーヒー
……などなどです。
ひと口にグルテンフリーの食事をとるといっても、グルテンを含む穀物は実に多くの食品に使われているので、常に原材料をチェックする必要がありますね。
今回は、ジョコビッチ選手の著書から、グルテンフリーの効果と実践する上でのポイントを、簡単に抜粋してみました。
原因不明の体調不良に悩まされていたり、ダイエットしてもなかなか痩せないという人は、ジョコビッチ選手にならって、まずは14日間だけ、グルテンフリーを取り入れてみてはいかがでしょうか?
■ジョコビッチ選手を変えたグルテンフリーの食事法の効果(後編)
現在、世界ランク1位のテニス選手、ノバク・ジョコビッチ。その彼が著書『ジョコビッチの生まれ変わる食事〜あなたの人生を激変させる14日間プログラム』で明かした“グルテンフリー(小麦や大麦、ライ麦といった穀物に含まれるタンパク質を一切摂らない食事法)”は多くの人の注目を集め、今や一流スポーツ選手、アスリートの多くが取り入れるようになっています。
前回は、そのグルテンフリーについて、効果や実践法などを中心に解説しました。
後編の今回では、実際にジョコビッチ選手がおこなっている食生活の内容について紹介したいと思います。
起きたらまず摂取するもの
ジョコビッチ選手には、朝の習慣が2つあります。
1つ目は、グラス1杯の常温の水を飲むこと。寝ている間、身体は何時間も水分を摂っていません。そのため、起きて活動を始めるための水分を必要としています。
ただし、このとき氷水を飲むことは避けているそうです。身体は、入ってきた水を体温と同じ温度まで温めようとして、消化器官へ血液を送り込んできます。冷たい水を飲むと、そのプロセスに多くの血液が使われ、消化が遅くなるだけでなく、筋肉への血流が妨げられてしまうのです。
ちなみにジョコビッチ選手は、朝だけでなく、一日を通して温かい水を飲むようにしているそうです。
2つ目は、スプーン2杯の蜂蜜を摂ること。身体は糖分を必要としていますが、悪い糖分を摂ると、血糖値が乱高下することになります。そこで良い糖分である蜂蜜を毎朝摂っているそう。さらに、ジョコビッチ選手は、通常の蜂蜜より抗菌作用の高いマヌカハニーを、できるだけ摂るようにしているそうです。
ジョコビッチ選手の朝食
それではジョコビッチ選手は、どんな朝食を摂っているのでしょう?彼は“パワーボウル”と称して、普通サイズのボウルに次の材料を混ぜて、毎朝食べています。
・グルテンフリーミューズリー、またはオートミール ※ オーツ麦を脱穀し、平たく押し潰したものがオートミール。そのオートミールにドライフルーツやナッツを加えたものがミューズリー。
・一握りの分量の様々な種類のナッツ(アーモンド、クルミ、ピーナッツなど)
・ひまわり、またはカボチャの種
・スライスした果物(バナナや様々な種類のベリーなど)
・ココナッツオイルをスプーン1杯
・ライスミルク、アーモンドミルク、またはココナッツウォーター
毎朝、これらの材料の割合を変えて、味に変化を付けています。日本人には馴染みの薄い食材も多く含まれていますが、輸入食品を扱うお店やネットショップなら、入手が可能です。ぜひ試してみてください。
これだけでは足りず「もう少し何か食べたい」と思ったときは、パワーボウルを食べてから20分後に、グルテンフリーのトーストやツナ、アボカドを食べているそうです。
20分の時間を空けるのは、消化を良くするため。胃は、炭水化物とタンパク質を同時に消化することができません。そのため、このパワーボウルのような炭水化物と、間食に含まれるタンパク質を同時に摂取すると、消化にエネルギーと時間を要します。
すぐにタンパク質が入ってくると、胃に負担をかけてしまうので、胃が適応できる時間を20分与えているのです。
ジョコビッチ選手のランチ
ジョコビッチ選手の典型的なランチは、“野菜入りグルテンフリーパスタ”です。グルテンフリーパスタは、キノアかソバで作られています。
野菜は、次のものを混ぜています。
アブラナ、トマト、キュウリ、ブロッコリー、カリフラワー、インゲン豆、ニンジンなど。このグルテンフリーパスタと野菜に、オリーブオイル、少量の塩を混ぜるのが定番です。
反対にジョコビッチ選手が食べないのは、トマトソースなどのソース類。とくに缶詰のトマトソースは添加物が多く含まれているうえ、胃がもたれるので消化が遅れてしまうそうです。
ジョコビッチ選手の夕食
夕食は、肉か魚といったタンパク質を中心に摂ります。具体的には、牛肉のステーキか鶏肉、サーモンが多いそう。肉はローストかグリル、魚は蒸すか短時間茹でる、という調理法を取ります。これに、蒸したズッキーニやニンジンなどの野菜類、またはヒヨコ豆やレンズ豆、スープなどを加えます。
アルコールは、ときどきグラス1杯の赤ワインを飲むのみ。ビールやウォッカなどは、麦から作られているので飲むことができません。
摂取していい水分は?
お茶は、いつ飲んでもOKな飲み物です。とくにジョコビッチ選手は、リコリスティーとジンジャーレモンティーを好んで飲むそう。リコリスティーはカフェインが入っていないのに目覚まし効果があるので、オススメです。
“食べ方”で心がけていること
ジョコビッチ選手が食事を摂るときのルールとしているのが、「ゆっくりと意識的に食べること」です。
早く食べると、胃に一度に大量の食べ物が押し寄せてくるため、胃は得た情報を処理する時間がなくなり、消化が遅くなってしまいます。そのため「満腹」のサインが出なくなり、食べ過ぎてしまうのです。
さらにジョコビッチ選手は、食事中は次のことを実施しています。
・テレビを観ない
・メールを見ない、送らない
・誰かと長々話さない
このようにして、食事中は噛み砕くことに集中します。それにより、唾液に含まれるエンザイムが食物と混ざり、より正確に胃に「情報」が伝わるからだそうです。
いかがですか?ジョコビッチ選手もそうであったように、自分では気付いていないけれど、実は小麦アレルギーを抱えており、それによって様々な不調に悩まされている人は意外と多いようです。ぜひ、彼の食事内容を参考に、14日間のグルテンフリーを試してみてください。
[いずれもRhythm(リズム)]
Posted by nob : 2017年03月04日 17:01
心がけてはいても7時間はなかなか難しい、、、夢を見ないで眠ることもほぼ皆無ですし。。。
■「7時間睡眠」がもっとも長生きできる理由
満尾 正 [満尾クリニック院長・医学博士]
質の高い人生は
「脳の休養」から生まれる
「7時間睡眠がもっとも長生きする」
これは、日本やアメリカ、イギリス、それぞれの国の研究チームの調査で明らかにされていることです。
もとより、人には個体差がありますから、6~8時間が健康的な睡眠時間と考えてよいでしょう。
脳は、さまざまな心の作用と結びついています。
睡眠が足りずに脳の疲労が回復されないと、たちどころに心が不安定になります。感情のコントロールが効かなくなる障害も出てきます。倦怠感や集中力の欠如などの不調も現れてきます。
日中、働きづめの脳は、十分な休養、つまり「睡眠」が与えられることで、いくつになっても最高のパフォーマンスを発揮します。
感情や気力は、生命力の構成要素です。脳の休養は、強い生命力を保つうえで欠かせない条件なのです。
睡眠時間がどうしても短くなりがちな人は、昼寝をとり入れるといいでしょう。ただし、長時間ダラダラと寝るのは禁物です。せいぜい20~30分ほどの昼寝が、脳の休養にとても有効とされています。
寝すぎも、無気力などの気分障害を引き起こします。
睡眠時間以上に
熟睡できているかが重要
良い睡眠とは、睡眠時間の長さではなく、むしろ「熟睡」できているかどうかといった睡眠の質の問題と考えられています。
睡眠には体を休める「レム睡眠」と、脳を休める「ノンレム睡眠」があります。レム睡眠は浅い眠り、ノンレム睡眠は深い眠りです。ノンレム睡眠から始まって徐々に眠りの深度を増し、熟睡度のピークを過ぎると浅くなってレム睡眠に変わります。約90分を1サイクルとして、4~5サイクル経て、心地よい目覚めに至ります。
ぐっすり眠る脳は、夢をほとんど見ることがありません。このノンレム睡眠の間に、成長ホルモンが分泌され脳の機能回復や細胞の新陳代謝を高めたり、免疫力を増強したりといった体のメンテナンスが行なわれます。
いつも決まった時間、夜10時に就寝し、朝5時に目覚める――。入眠して3時間の間にしっかりと成長ホルモンが分泌する眠りが、理想的な熟睡です。
過不足ない睡眠は、朝の目覚めの状態でわかります。前向きな気持ちがあふれた目覚めであれば、熟睡が得られた証拠です。朝目覚めたときの気分を尺度に、自分に合った睡眠時間を見つけるといいでしょう。
「質の良い眠り」を
与えてくれるメラトニン
規則正しい起床・就寝の習慣は、「誘眠ホルモン」とされるメラトニンの性質を活用してつくります。
メラトニンは、脳の中心部の「松果体」と呼ばれるところから分泌されています。大量に分泌されると眠気をもよおし、少なくなってくると目覚めます。
メラトニンの分泌量は7歳ごろをピークに、50代以降では半減しますが、「幸せホルモン」と言われるセロトニンを増やすことで分泌量が高まります。
セロトニンは、納豆をはじめとした大豆製品や、ゴマ、しらす干しなどに豊富なトリプトファン(必須アミノ酸の一種)を原料につくられます。セロトニンからメラトニンへの合成は暗くなると始まると言われています。
規則正しい睡眠習慣をつけるとともに、こうした食品を積極的にとって、脳を健康に保っていきたいものです。
メラトニンにはまた、「不老長寿ホルモン」の異名があります。強力な抗酸化作用を持ち、脳細胞を守る働きがあります。さらに熟睡を得ることで免疫力が増強するという間接的な効果で、がん、骨粗しょう症、心臓血管疾患、糖尿病の合併症、肥満にもかなりの予防効果があることが報告されています。
朝日を浴びることで
ストレスから解放される
昔から、日本人の勤勉さは「早起き」に象徴されています。江戸・元禄時代に井原西鶴が著したわが国初のビジネス小説『日本永代蔵』には、「金持ちになる秘訣5カ条」が書かれています。そのなかで「いの一番」に挙げられているのが、早起きです。
じつは朝は、ストレスと闘う「ストレスホルモン」の分泌量がもっとも多くなります。体に活動のエンジンがかかる際にエンジンの役割を果たすのです。
しかし、ストレスをためやすい人だと、体は一日中、ストレスホルモンであふれてしまいます。気持ちがうしろ向きになり、愚痴っぽくなったり、ひがみっぽくなったりして、ストレスがさらにストレスを呼ぶといった「ストレススパイラル」にはまってしまいます。
そうならないためには毎朝、決まった時間に起床して朝日を浴びます。いわば「心を洗う朝の儀式」です。
朝日を浴びると、前述のセロトニンが脳内に分泌されます。セロトニンは、ストレスが生まれにくい体内環境をつくります。このとき、笑顔をつくれば、ストレスホルモンの分泌量がスーッと下がります。心を洗う儀式は、脳をリフレッシュする習慣でもあるのです。
[DIAMOND男の健康]
Posted by nob : 2017年02月23日 10:27
これからがそれまでを変える。。。/闘病のかたちは千差万別十人十色、、、負けない人々はまずそれまでの自分と決別する。。。
■会社を辞めたらガンになりました、ついでに治療も止めました
でも8年経った今でも元気です
山口 ミルコ
文筆家
8年前に会社を辞めた。
オバマ氏が「チェンジ」を世界に呼びかけて、アメリカ大統領になった頃のことだ。
リーマンショックの折、20年に亘る出版社勤めをやめようと決意した筆者は、2009年初頭、会社に辞表を出した。と同時に、乳ガンに罹患していることが判明し、退社後は闘病生活を送った。
「リーマンショックからさほど経っていないのに、なかったことのようになっていないか?」
これは会社を辞めて闘病生活に入った私――毎日を静かに暮らしていた私から見えた世の中、の感想だった。
自分と同じく会社を辞めた人たちが、いまどこでどうしているのか気になっている。
あの日「世界の終わり」に気づいた人は少なくないはず、しかし私は彼らになかなか会えない。
バブル期に向かって思春期を過ごし、雇用機会均等法で就職、充実した社会人生活と賑やかな業界でのキャリアを手にして、その経験の貯蓄を元手に、失われた20年以降には自分なりのアイディアで食いつないだ――筆者と同世代の、会社の中核的存在だった人も多かったにちがいない。
そういう人たちがなかなか出てこられない世の中になっているのか、私が孤立しているせいなのか、何事もなかったかのようになっているこの世界。
リーマンショックが突き破った袋から弾け飛んだ、生き残りを賭けた闘いの空気は、オバマが4年2期をつとめるあいまにみるみるよどんで地球上をただよい、世界各地に沈澱、いよいよ不気味な様相を呈するなかトランプ米大統領が誕生した。
会社を辞めた直後から、私はガン治療を受けた。
主なメニューは手術→放射線治療→抗ガン剤、それと並行してホルモン治療と作業療法(リハビリ)。やりたくなかったが、やるしかなかった。その体験は、拙著『毛のない生活』(2012年)に書いた。
ぜんぶ合わせると入院・通院していたのが1年、その後の歯の治療や口内炎の頻発の繰り返しや手の不自由、免疫不全、帯状疱疹……などなど、いろんな回復を待つこと約3年、再発におびえながらも「まあ調子いいよね」となるまでになんだかんだかかってしまい、現在に至っている。
それでものらりくらりとやってきたせいか、ぼちぼち<がんを克服した>と言っていいだろうラインに、ようやっと立つことができた。
あのとき会社を辞めなければどうなっていたかと考えてみる。
会社を辞めたのは、もう辞めようと思ったからであり、ガンになったからではないが、筆者の場合、退社とガンの発覚がほぼ同時期だったので、すぐに周囲の人びとの知れるところとなった。
多くの関係者が思ったにちがいない。
「あのひとはもう、仕事できないよね」
そういった目にさらされることは、独立したばかりの者にとって、こたえた。
社長に朝から電話で叩き起こされることは当然なくなり、誰からも連絡が来なくなった。
朝は寝床でグーグーグー、昼はのんびりお散歩、しけんも仕事もなんにもない、ゲゲゲのおばけ状態になるのにそう時間はかからなかった。以前がモーレツ社員だった分、すがすがしくさえあり、変わり果てたライフスタイルには我が事ながら、ときおり呆れた。会社時代の自分は、幻だったのではないかと。
それでもあのまま会社にいては治らなかったと、いま振り返ってハッキリ言える。
ガンと会社はある意味似ているからだ。
ガンになったら「チェンジ」せよ
ガンは人によって違い、治療も違う。
ガン治療には波があり、体調にも波がある。
調子の良い時もあるので仕事できそうな気がするし、じっさいすることも可能かもしれないが、筆者の体験をもって言わせていただくならば、やっぱりやらないほうがよい。
会社を辞めずにガンと戦うことは、2つ会社に行くようなものだ。
「ながら」が通用しないのがガンであり会社――たいていの日本の会社では、同種療法は無効、ということだ。
冒頭の「チェンジ」を、ここであえて挙げたい。リーマンショック後に叫ばれて、いまだになされていないそれ、である。
ガンになったら、いったんぜんぶをやめること。
会社が大事なのは、よくわかる。筆者も会社を愛していた。会社員の人で自分の会社を愛してない人などいないと思う。しかしそんな人間がガンをこさえたのだ。
会社にいれば、日々目の前にやるべきことが生まれ、会いにくる人もいる。
そうした場所を持っていた人が持たなくなると心身不安定になることも自ら退社したいまではわかる。
また、お金のことは当然ある。ご承知のとおり、がん治療にはお金がかかる。
同時期に治療を受けていた筆者の友人のなかに、会社員は少なからずいた。仕事を続けなければ治療も続けられない、そう言っていた。
彼女たちは独身であったり、独身でなかったのに乳がんになったことで離婚に至ったりした。筆者も独身であったが、退職金がまとめて入ったこと、そして実家があったことで治療に専念できたのは幸運だった。
“無収入”の時代が訪れる不安なく仕事できた自分は、これまでずっと会社に助けられてきたのだと、よくわかっている。
それでも一度すべてを絶つことをおすすめするのは、<過去と決別する>ためである。もうそれ以外にすることなど、ほとんどないと言っていい。
いったん素(す)になる必要がある。
1人になって、閉じこもり、じっと考える。
ガンは自分の細胞の変貌なので、本来の自分を取り戻す時間が必要なのだ。
孤独と向き合い、徹底的に考える。
そうしないと、そもそも自分はなんだったのか、わからないからだ。
生きていると、いろんなものがくっついてくる。元のかたちを分らなくさせているそれをはがしてゆく作業が闘病であったと振り返る。
自分をとりまく環境、人間関係、ライフスタイルすべてを見直した。
変わらなければならない、しかしそれができたなら終わりも同然、あとやることは、決まっていた。
1) 病人である自分と、とことんつきあう。
2) 病院をよく検討したうえで、この主治医についていくと決めたらば、その方針に従い、覚悟して治療を受ける。
治療中の方がマシだった!?
この病気が難儀なのはある時期、戦争になるところであり、そこも会社とそっくりだ(前ページの1)と2)、病人を会社員に、病院を会社に、主治医を社長に、「治療を受ける」を「仕事する」に置き換えて読むことができる)。
戦闘や混乱は免れない。
人によってガンは違い、100人いたら100通りのガンがあるので、戦い方や期間も100通りあるだろう。人それぞれなのだけれど、あるときには激しく必死で戦わねばならない。そこを戦わないと、ガンはどこまでも追いかけてくる。
戦闘中は、真剣に戦う。そして、ここで和平と思ったら、ただちに武器を置いて戦場から去る。いつまでも戦場に立ち尽くし、呆然としたり、戦友と傷をなめ合ったり、異国に立ち入って勝手に国境線を引いたりしてはならない。去るタイミングを逃してしまうと、平時より戦時のほうがよかった、なんてことに。こうなるとタチがわるい。戦後が長引く。
和平を決めたら武器は保持しない。同じ手は二度と使えない。戦力は全て戦場に置いていくことになる。ここも会社と似ている。
私は治療を途中でやめているので、戦闘のさなかにガンと和平協定をむすんだようなことになっている。そのことについては、次回書かせていただこうと思う。
さて、戦場を去ってどこへ行くか?
待ってくれる人がいたらそこに帰れるが、よく考える必要はある。
会社に戻るな、とは言わない。しかし以前と同じ生き方では、敵はまた追いかけてくるので、居ながらにしてやり方を変えることをおすすめする。
会社を辞めなかった人には会社が、離婚にならなかった人は家庭が、そこがもしもあたたかく迎え入れてくれる場合それに越したことはないにしても、乳がんのように長期間治療の病ほど、そのサイクルに呑み込まれ、うっかりすると治療の世界が居心地よくなってしまうケースがあることも、ここで言っておきたい。
とかく人は慣れた場所にいてしまうものだ。
病院の中にいれば守られるし、みんな優しくしてくれる。同じ病の友もいる。精神的なケアサポートとして同じガンの患者同士が交流できる場を設けている病院も多い。そこに専門医や経験者が出入りして、患者にヒアリングをしたり、アドバイスをしたり、の交流が生まれる。その交流がいっとき患者を支えることも否定はしないが、批判をおそれず書くならば、用が済んだらとにかくその場から離れるほうがいい。
一歩病院を出れば、外の世界が待っている。
そこにあらゆる問題が待ち受けていることはいうまでもない。
治療中のほうがまだよかったというほど、厳しいことがそこには待っているかもしれないが、治療の世界が居心地いいからといって居座らず、とっとと社会復帰したほうがいい。
素(す)に戻った本来の自分が、必ず新しい場所を引き寄せるはずだから。
おさらいする。ぜんぶをやめて、ひたすら治療に専念、そして治療が済んだら、そこもやめる。闘病前の自分と決別し、闘病中の自分とも決別する。この道しかなかった。
退社から8年、いまになって、会社がどういう場所だったのか、思い返すことが多い。
元気になった証拠かもしれない。
では、次回は「なぜ私は治療をやめたのか?」について書かせていただきます。
■「ガン再発」と「副作用」を天秤にかけた結果、治療をやめました
後悔なんてしてません
8年前、勤めていた出版社を退社したと同時に乳ガン罹患が発覚した文筆家の山口ミルコさん。手術、抗がん剤、放射線、ホルモン剤、リハビリなど、辛い治療をこなしつつも、快方に向かっていた。が、山口さんは途中で治療を一切放棄してしまった。そのココロは一体?
ガン探偵ミルコの捜査結果
退社することなく、ガンになったと仮定してみる。
おそらく丸1年は会社を休まなければならなかったし、その後の不調を抱えながら前と同じ仕事を続けるに困難がつきまとったことは想像に難くない。
闘病は身体の厄介だけでない、心が厄介だ。
それに会社というのは待ってくれるものだろうか、以前のようには稼げなくなった人を。
なぜガンになったのか? それをずっと考えてきた。
<私がなぜ?>の問いは、多くのガン経験者の方々にも共通のものと思う。
ストレスか、食生活か、何者かの怨念もしくは邪気なのか、はたまた自らの行ないの悪さによるものか、前世からの因縁か……自問自答は止まらない。
けっきょく自分自身を責めることになる。私もはじめはそうだった。
ところが年数が経つにつれて、ほんとうにそうだろうか?と思うようになった。
考えてばかりいるうちに、自分がいいとか悪いとか、そういうものを超えた真相に迫りたい、どうにかしてそこへたどり着けないだろうかということになった。ヒマだったのだ。
原因は何か?
犯人は誰か?
犯人逮捕までの捜査プロセスについては、これから出る新しい本に書いた。
ガン探偵ミルコは、日本で、中国で、ロシアで、考えた。
考えに考えぬいてわかったことの1つには、結果はもう出ている、ということがある。
<ガンになった>は結果だ。
原因はどうであれ、結果が出ている。
ガンになったことも、会社をやめたことも、もう済んだこと。
なのになぜ私はそこにいつまでもこだわり続け、本まで書いたのだろう。
会社も治療もやめたのに、考える続けることはやめられなかったのである。
私を導いたものがなんであるのか、そこも知りたい。
ひとつ、いいアイデアが浮かんだことがある。
「私は嵌められた」というものだ。
私は罠にかかった小動物のようだった。
まったく自分は悪くない、すべて私以外の何者かのしわざであると。そこで片づけられたらすぐに終わったのだが、しかしそうはならなかった。
私もいつか再発するのかな……?
<ガンを克服した>と言っていいだろうラインにようやっと立つことができたと前回書いた。筆者は会社を辞めると同時にガンが発覚、闘病をへて現在に至っている。
ここまでに、まる8年。退社からもガンからも、まる8年。
この時間の長さをどうみよう?
ずいぶんかかってしまったという気もするが、こんなもんだとも思える。
ガンができるのにはそれ相当の時間がかかっているのだから、ガンが治るのにもそれ相当の時間がかかる、ものごととはきっとそういうものだろう、といまならわかる。
<いままでの自分>がガンをこさえたのだから、<いままでの自分>とは変わらなければ、そうすることでしかぜったいに治らない、そうきつく我を戒めて、この8年を暮らしてきた。
入院中に、「7年で再発した」と言って病院に来た人と一緒になったことがあった。
「ああ、私もいつかまた、なるのかなあ……」
初発を治してもいないのに私は再発を心配した。
あれ以降「7年で再発」の話がなかなかアタマから離れず、再発におびえてきた。
退社以降、ときおりガンについて書いたり発言する機会をいただいてきたが、その中で「克服」という言葉を、私は使ったことがない。むしろまだ病人なのだ、調子にのるなよと自分に言い聞かせてきた。それがここへきて<ガンを克服した>と言っている。わけがわからない。ただ、<終わり>だと思う自分がいる。
私は長年編集者としての仕事に注いでいた全力を、一気にガン研究へ傾けていたので、治療が一年も経つころにはすっかりクタクタになっていた。
もう私はじゅうぶんやったのではないか?
そんなずうずうしい考えがうかんでいた。
当初、主治医の方針では、2種類のクスリをやることになっていた。
パート1は入院で点滴、およそ4ヵ月。
パート2を通院で点滴、およそ半年の予定。
パート1では完全に脱毛し、吐いて吐いて吐きまくったが、なんとかノルマを終えた。
そしてパート2に入ると、全身がグラグラし、耳の奥に痛みを感じた。これまでに経験したことのない、具合の悪さだった。
このままでは耳が聞こえなくなるかも――?
「私、やめます」
医師に言った。
治療も社交もやめたら体質改善
たしかあのときも――会社をやめるときとも、おんなじだった。
もう戦えないのなら、そこに居場所はないのである。
あえて言葉にするなら、もうここには呼ばれない、この場所には来なくていい、いなくてもいい、自分。
自分を失う一歩手前で、私は逃げた。
「私、やめます」の宣言は、この肉体から発せられた言葉であるはずなのに、自分が言った気がしない。それは神かご先祖様か、誰かがクレーンのような恰好で私をひょいと摘(つま)み上げ、私を危機から救い出した。
クレーンで私はいったん高い所へ引き上げられて、その直後に地面に落とされた。
高い場所から勢いよく落ちたので、ダメージは大きかったが、大怪我も辞さないその助けがなければ私はいつまでもあの場でモタモタした。だから救われた。生と死の境を超えたのである。
そして私は会社からもクスリからも引き離されて、あらためて自分のかたちを眺めることになったのだった。
そこには少々まちがったかたちの、歪んだ私がいた。
まだ数回残っていた抗がん剤をこうして途中でやめた私は、どうしたか?
こたえ、何もしなかった。
なにもかも、やめてしまったのである。
経口の抗がん剤も、ホルモン剤も、検査に行くことも、やめてしまった。
ガン治療というのは主治医の決めたスケジュールをまっとうしないと再発率がぐんと上がるといわれており、再発はおそろしいのだが、何もする気がおこらなかった。
ついでに社交もやめた。
こうでなきゃいけないものとかお金や知名度が価値基準になっている場所ともあいついでお別れした。それは、ある意味カンタンだった。向こうからさよならしてきたからである。
ウソは前から嫌いだったがいっそう嫌いになった。
あとは自然にまかせた。
するとふしぎなことに、本来のかたちにもどっていった。
贅肉が落ち、視覚、聴覚、嗅覚が冴え、いったんゴワゴワになった髪質がサラサラになった。
啓蟄が近づくと、手術跡の古傷に痒みをおぼえるようになった。
こうなるともう、大きな地球のサイクルにのっかっていくしかなく、私がずっとこだわってきた「なぜ?」の問いには、すでに何の意味もなかったのだと、解明されるのは時間の問題だった。
以前のように稼げるかなど、質問自体がばかげていると、わかっただけでもガンで儲けたものだった。
[いずれも現代ビジネス]
Posted by nob : 2017年02月23日 09:50
すべての食材は諸刃の剣、、、何が正しいのか、何がその時々の自分に合っているのかを見極める目を養うことが肝要。。。
■日本人が実践する健康法の「大ウソ」このままでは寿命が縮みます!
ウコンは肝臓に悪い、海藻で髪は生えない…
週刊現代の特集「逆さま健康法」には大きな反響があった。信用に足るかどうか怪しい情報が溢れているのは、食品も同じ。身体に良かれと思っていた食生活が、実は寿命を縮めていた――。
ウコンは肝臓に悪い
二日酔い対策のため、飲み会の前にウコン入りのドリンクをコンビニで買って飲む――。ウコンは肝臓の機能を回復させ、アルコールの分解を促進するため「身体にいい」と思い込んでいる人は少なくない。ところが近年そのウコンが人によっては、健康被害をもたらしていることが明らかになっている。
「以前、全国の肝臓学会の会員施設に対して、健康食品が原因となった肝障害について調べた結果、原因の1位になったのがウコンだったのです」
こう語るのは名古屋大学大学院医学系研究科・教授の石川哲也氏だ。同氏によれば肝機能が落ちている人は、ウコンを飲むことでかえって肝障害を悪化させる危険性もあるという。
「肝機能の数値が悪いのを回復させようとしてウコンを飲むのはおすすめしません。特に、C型慢性肝炎や非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)は肝臓に鉄分が溜まりやすい病気です。そのため鉄分を多く含むウコンを飲むと余計に悪化してしまう危険性がある。
肝臓の数値が悪いからと自己判断でウコンを飲み続けると、知らないうちに肝障害がより悪化する危険もある。
まずは医者に相談し、正しい診断を受け、ウコン入りの健康食品を摂る場合は成分表示をしっかり見て鉄分量を確認してください」(石川氏)
ウコンは、別名ターメリックと呼ばれ、胆汁の分泌を促すというメリットもある。しかし、それ以上に「同時に鉄分を摂りすぎてしまう」というデメリットのほうが大きいのだ。
帝京大学ちば総合医療センターで消化器内科を専門とする小尾俊太郎医師が解説する。
「体内の鉄分が多くなってくると、肝臓の中に余剰となった鉄分が蓄積されます。すると活性酸素というタチの悪い酸素ができやすくなる。活性酸素は大気中に含まれる酸素に比べ、反応性が高く、周囲の細胞(DNA)を傷つけます。
こうなると肝臓の働きがますます悪くなり、肝臓に沈着した脂肪が活性酸素に刺激され脂肪肝炎を引き起こし、肝硬変や肝がんの原因になりかねないんです。
もちろん、鉄分は人間にとって必要な栄養素の一つです。特に女性の場合は月経により貧血になりやすいので、鉄分を多めに摂っても問題ないのですが、男性の場合は普通に食事をしていれば鉄分が不足することはありません。むしろ摂りすぎに注意するべきなんです」
実際、飲酒による肝機能低下を防ぐ目的でウコンとシジミエキスを毎日摂取した結果、数ヵ月後に劇症肝炎を発症した例もある。
さらには、二日酔い防止にウコンを多量摂取したら肝機能が劇的に低下し死亡したり、肝硬変を患っていた女性が、ウコンの粉末を毎日スプーン1杯程度飲み続けたところ、かえって症状が悪化し、3ヵ月後に多臓器不全に陥って死亡したケースもある。
昔から二日酔いにはシジミの味噌汁がいいと言われ、シジミ=「肝臓にいい」と思いがちだが、これもウコンと同じく、鉄分の摂りすぎにより、よけいに肝臓が悪くなる危険性がある。肝臓そのもののレバーも肝臓にいいとされがちだが、鉄分が多いので注意が必要だ。
前出の小尾氏が言う。
「肝炎や肝臓の病気の原因となっていたものが、昔と今とではガラっと変わっています。歴史的にみると、日本は栄養が不足する時代がありました。そうしたことから古来より、ウコンも肝臓に良いとされてきたわけです。
ところが、現代では生活の質も変わってきて、肝臓が悪くなる原因はむしろ肥満やアルコールといった生活習慣病による脂肪肝になってきた。そのためウコンの鉄分が逆に体を害するようになってきたのです」
社会の変化と共に、病気も変化している。過去の常識にとらわれず、まずは自分の体と向き合うことが先決だ。
ブルーベリーは目の健康に無関係
ブルーベリーは目にいい――。いつの間にか常識のように刷り込まれている情報である。だが、実際はそれを証明する客観的データはない。
彩の国東大宮メディカルセンターの眼科医である平松類氏が言う。
「巷にはブルーベリーは目にいい、視力が回復すると謳った健康食品が溢れていますが、視力回復にはあまり効果がないのが事実です。ブルーベリーに含まれるアントシアニンが目にいいとされていますが、目に特異的に効くものではありません」
国立健康・栄養研究所のホームページには「ブルーベリーは、視力回復に良い、動脈硬化や老化を防ぐ、炎症を抑える、などと言われているが、ヒトでの有効性・安全性については信頼できるデータが十分ではない」といった趣旨のことが明記されている。
そもそもなぜ「ブルーベリーが目にいい」と言われるようになったのか。そのきっかけは第二次世界大戦中のこと。イギリス人のあるパイロットが『暗がりでも敵機がよく見える』と言うので、彼の食生活を調べると、毎日ブルーベリージャムを塗ったパンを食べていたという。
そういった逸話が現在まで一人歩きしてきたにすぎない。そこにブルーベリーのサプリメントが発売され、NHKやワイドショーが紹介したことで一気に火がついたのだ。
「確かにアントシアニンには、抗酸化作用と、視神経の伝達物質であるロドプシンの再合成を助け、疲労を回復する作用があるので、目の疲れによる景色のかすみやぼやけなどの症状を改善する可能性はあります。ただしそれはあくまで一時的なもので、ブルーベリーをいくら食べても、視力自体が回復することはありません」(平松氏)
では、本当に目の健康に効果がある食材は何なのか。
「近年注目されているのは『ルテイン』という成分です。これはほうれん草などに多く含まれる成分で、白内障や黄斑変性の予防に効果的であることが明らかになりつつあります。また青魚に含まれるDHAも目の健康にいいとされています」(平松氏)
昨今、パソコンやスマホの使用時間が増えたため「ドライアイ」に悩まされる人が増加。眼球が乾いた状態が続くと、目の老化を早めると指摘されている。効果が実証されていないブルーベリーを無理に食べるより、定期的に目を休めることに気を配ったほうが、よっぽど効果的だろう。
海藻を食べても毛は生えない
海藻をたくさん食べると毛が生えてくる。逆に海藻を食べないと薄毛になる。昔からよく言われていることだが、こちらもブルーベリーと同じく、根拠がはっきりしない。真実はどうなのか。
発毛治療を専門とするAGAスキンクリニック新宿アイランドタワー院の西垣匠院長が語る。
「髪の毛は主にタンパク質の一種であるケラチンを主成分としています。このケラチンの合成を促進する作用を持つのがミネラルです。海藻類はミネラルを多く含んでいるので『ワカメなどの海藻が髪にいい』のは間違いではありません。ただ海藻を一生懸命に食べると髪が増えるかというと、それはまったく別次元の問題です」
薄毛には遺伝的要素や普段の生活環境、ストレスなど様々な要因がある。そのため海藻を食べたからといって髪が生えるほど単純なものではない。
それどころか海藻を食べすぎることによって、思わぬ弊害が身体に出ることもあると、西垣氏は言う。
「海藻はヨウ素を含んでいます。このヨウ素を取り込みすぎると、甲状腺の機能にダメージを与えます。ホルモンバランスを司る甲状腺に異常が出ると、すぐにイライラする、手足が痺れる、無気力で鬱状態になる、などの症状が現れます。
本来、ヨウ素にはタンパク質や炭水化物、脂質の代謝を高める働きがありますが、摂りすぎると、それが過度に働きすぎて逆効果になってしまうのです」
海藻に多く含まれるヨウ素だが、その中でも昆布に含まれる量は、ワカメやひじきに比べて極端に多い。特に昆布の食べすぎには注意が必要だ。
髪の毛を生やすために効果的なことは何か。
「人間の体は、基本的に主要な臓器に優先的に栄養が行き渡るようになっています。つまり心臓や脳にまっさきに栄養分が行き、髪の毛は最終地点なのです。髪の毛まで栄養分を巡らせるためにも血流を良くすることが大切です。
また、髪の毛の成長を促すホルモンは、夜の10時~2時に最も多く分泌される。この時間にいかに睡眠を取っているかが重要です」(西垣氏)
ひたすら海藻を食べるより、普段の生活を整えることが、髪にも健康寿命にも効果がある。
油っこいものは食べたほうがいい
ダイエットの天敵といえば「揚げ物」。痩せたいのなら、まず油っこいものを控えるのは常識だ。
しかし「それは大きな間違い」と語るのは、沖縄徳洲会・こくらクリニック院長の渡辺信幸氏。同氏は『唐揚げダイエット』の提唱者でもある。
「未だに多くの人が肥満の原因は油だと思っていますが、それは誤解で、実は太る一番の要因は、白米やパンなどの『糖質』なんです。そのため油っこいものを食べてもまったく問題はないのです。我慢しているほうがよくない。
肉の脂身もしっかりと摂ることで、身体の代謝が上昇し、脂肪燃焼の働きも良くなるので、痩せやすく太りにくい体質に変わっていくのです。まずはお腹がすいたら、コンビニでおにぎりを買うところを唐揚げに代えてみてください」
タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルは「必須栄養素」と呼ばれる。つまり、痩せるためだけでなく、人間が健康に生きるためにも肉や油はちゃんと食べる必要がある。
ただ、一つ注意したほうがいいのは油の種類だ。
「揚げ物などをする時は、植物性油より、ラードやバターなどの動物性油を使用することをおすすめします。理由は動物性油のほうがより人間の脂に近いからです。そのため吸収、消化がよく健康的です。さらに植物油より必須脂肪酸のバランスもいい」(渡辺氏)
とはいえ、そんなに揚げ物ばかりを食べていると、コレステロールが気になるという人もいるだろう。だがそれも心配ない。基本的に摂りすぎた脂質は、肝臓で分解されて水分と二酸化炭素として排泄される。コレステロールは悪だという考え方はもはや古いのだ。しかも、こんな相乗効果もある。
「高齢者の中には便秘に悩んでいる人も少なくありませんが、実は脂質をしっかり摂ることで便秘も解消できるのです。大概の人が食物繊維の豊富なゴボウやニンジンなどの根菜類を一生懸命食べていますが、それでは便秘は改善されません。
なぜなら人間は元来、食物繊維を消化する酵素を持っていないから。特に根菜類は固い細胞で覆われているので、消化しきれず、便がより大きくなってしまうのです。その解消法が実は油なんです。吸収しきれなかった油は排出されるので、それによりお通じが良くなります」(渡辺氏)
油は体を元気にする。まさに「潤滑油」なのだ。
野菜ジュースよりコーヒーのほうが身体に良い
一本で一日分の野菜が摂れるとして、毎日市販の野菜ジュースを飲み続け満足している人は多い。だがそれは実は危険な行為だとしたら……。管理栄養士の梅原祥太氏はこう警鐘を鳴らす。
「ジュースにすることで、野菜に含まれる水溶性ビタミンなどが、かなり壊れて無くなってしまう。野菜は本来アルカリ性食品ですが、ジュースにすると酸性食品に変化するため、野菜本来の恩恵がほとんど受けられません。
それどころか野菜ジュースは糖質がほとんどです。100%の野菜ジュースでも、たいていは糖質が入っている。野菜ジュースに含まれるのは、ショ糖(ブドウ糖+果糖)が多く、そういった液体の糖質を空腹状態で飲むと、急激に吸収されてしまい、脂肪になりやすくなってしまいます。
また一時的に血糖値も上昇してしまう。すると体は血糖値を下げようとするので、血糖値の上げ下げが激しくなり、体に負担がかかるのです」
健康にいいと思って飲んでいた野菜ジュースが、知らぬ間に肥満を促進し、糖尿病や高血圧のリスクを上昇させているのだ。
一方でコーヒーはどうか。コーヒーは大好きだけど、健康によくないからと我慢している人もいるだろう。
だが、近年の研究によると、コーヒーには、害どころか様々な効能があることが解明されてきた。
たとえば'15年にはハーバード大学が「コーヒーを一日4杯以上飲んでいる人は、大腸がんの再発リスクが抑えられる」と発表。さらに国立がん研究センターの研究によれば、「コーヒーをまったく飲まない人に比べ、一日3~4杯飲む人は、死亡リスクが24%も低い」ことが明らかになった。
健康増進クリニック院長の水上治氏が力説する。
「私はコーヒーを『天然の薬』だと考えています。コーヒーには、カフェインとクロロゲン酸が含まれていますが、このクロロゲン酸はポリフェノールの一種で、老化の原因となる活性酸素を抑えることがはっきりと証明されている。
つまりコーヒーは、がん予防だけでなく、動脈硬化を防ぎ、血糖値を下げる効果もあるので生活習慣病も改善する可能性があるのです。
それでいて薬と違って副作用もないので、安心して飲める。もしコーヒーがダメな人は、日本茶やココアでも同じ効果が得られます」
砂糖たっぷりの野菜ジュースを飲むより、コーヒーを飲んだほうが、メリットは明らかに多い。
サプリメントにも気をつけろ
最近、「トクホ」という言葉をやたらと見聞きする。トクホとは「特定保健用食品」の略称。血圧、血中のコレステロールを正常に保つことを助ける、お腹の調子を整えるなど、国から特定の保健効果があると科学的に証明されている健康商品だ。
普通に考えれば「国がお墨付きを出しているのだから、当然効果がある」と思うだろう。しかし、実際はそうとは限らない。
文教大学・健康栄養学部教授の笠岡誠一氏が解説する。
「たとえば、あるメーカーのトクホ炭酸飲料などは、食後の中性脂肪の上昇が抑制されると謳っていますが、その実験条件としては、一日に必要な脂質を一度に摂るような食事をしてから、トクホの炭酸飲料と普通の炭酸飲料の効果を比べていたりするんです。
つまり、かなり限られた条件下で実験が行われている可能性があるのです。それにもかかわらず、誰にでも効果があるかのように、メーカー側が販売している点には疑問を持っています」
管理栄養士の梅原祥太氏はトクホについて、さらに手厳しい。
「トクホは、健康に何の意味もないと思います。トクホのコーラやお茶は、水溶性の食物繊維である『難消化性デキストリン』というものを添加しただけ。ただの水にこれを入れたら、もうトクホになっちゃうんです。
トクホのコーラを飲み続けるとよけいに脂肪過多になる可能性もある。なぜならコーラ自体に糖質や人工甘味料が含まれているからです。難消化性デキストリンで脂質を抑えるメリットより、コーラを飲むことで摂取する砂糖のデメリットのほうが大きい」
手軽に足りない栄養素を補えるとして今や多くの現代人が飲んでいるサプリメント。様々な種類が出ているが、その効果のほどは定かではない。
「人間の体は、いわゆる体内でエネルギーを作ることができる物資以外は、異物として認識します。サプリメントは、そういった体の条件を無視したものが多い。そのためいくらサプリを摂っても、体が必要ないと判断し、便として体外に排出してしまうのです」(吉備国際大学・地域創成農学部教授の金沢和樹氏)
『病気になるサプリ』の著者である左巻健男氏もこう指摘する。
「今、高齢者の間で一番人気なのが『グルコサミン』です。関節の動きを滑らかにして膝などの痛みを軽減させると宣伝されていますが、効果はないとする研究もあります。それどころか長期にわたり摂りつづけると、血糖値、血圧、コレステロールが上昇するリスクもある。
老化を防ぐとして、売り上げ上位に位置する『コエンザイムQ10』も、実際に効果があるというデータはない。肌を綺麗にするコラーゲンも定番の人気サプリですが、体内でアミノ酸などになって吸収されるため、飲んでも肌にそのまま届くわけではない。
以前『この商品を飲めばうるおう』と宣伝していた健康食品メーカーに問い合わせたところ『飲むときに喉がうるおう』と回答されました。このようにいい加減なサプリメントは、世の中にごまんと出回っているのです」
飲むだけで健康になる――そんな魔法のようなサプリは存在しない。
[週刊現代]
Posted by nob : 2017年02月14日 10:39
野菜をたくさん食べる(ことは当然として)、、、それからの話。。。
■「野菜をたくさん食べる」べき本当の理由
健康に(少しは)気をつけているビジネスパーソンから「野菜が健康にいいことはわかっているんだけど、なかなか食べられないんですよね〜」という言葉をよく聞く。本当に野菜は健康にいいのか、今回は驚くべき事実をお伝えする。
野菜がヘルシーだというのは勘違い
最初にお伝えしたいのは野菜の「栄養的価値」だ。テレビ等では食品として野菜が登場すると、出演者(タレント、アナウンサー、料理研究家、ときには栄養士や医師までも)が「野菜たっぷりなのでヘルシーですよ」などと発言することがきわめて多い。しかし、これは勘違いである。少なくとも「野菜を食べれば健康になれる」という証拠はない。
それどころか、野菜ばっかりの食生活では「健康で長寿」は望めない。たとえば、アフリカや南アメリカや東南アジアには、ほぼ毎日、野菜と穀物だけを食べて暮らしている子供たち(子供だけに限らない)が大勢いる。その子たちは健康でもなければ長寿でもない。タンパク質(とりわけ動物性タンパク質)や適度な量の脂肪などが不可欠である。彼ら(彼女ら)にとってはタンパク質や脂肪こそがヘルシーな食材なのであり、野菜はヘルシーでも何でもない。
ビジネスパーソンは「野菜を食べてさえいれば健康になれる」などと勘違いしないことが、まず肝要。動物性脂肪やタンパク質やアルコールや糖類を過剰に食べている現代人は、野菜不足のためにバランスが偏っていることが多いので、バランス上「野菜をたくさん食べましょう」というだけの話である。
「野菜一日350グラム」にたしかな根拠はない
カタイ話になって恐縮だが、ビジネスパーソンの皆さんは、厚生労働省が「健康のためには一日350グラム以上の野菜を食べましょう」といっているのをご存じだろうか? 知っている人でも「350グラム」という数値がどこからきているかは、おそらく知らないだろう。それもそのはず、「野菜一日350グラム」にはたしかな根拠がないからだ。
たとえば、一日に「野菜350グラム以上食べるグループ」と「350グラム未満のグループ」を作り、長期間その食生活を続けてもらう。そして5年後あるいは10年後に「350グラム以上食べていたグループ」の人が健康で、「350グラム未満」の人が不健康になった、という実験があれば、「野菜を一日350グラム以上食べれば健康になれる」といえることになる。しかし、そういう実験は、日本には(世界にも)1つもない。なので「野菜350グラムを食べれば健康になれる」という根拠はない。
「野菜ジュースを飲むこと」は
「野菜を食べること」と同じではない!
ただし、「健康で長生きしている日本人」の食事内容を調べたら「一日に野菜を約300グラム以上食べていた」という調査はある。現在、日本人の野菜の摂取量は一日に平均290グラムくらいなので、「もう少し野菜を多く食べましょう。できれば350グラムくらい」という目標が設定されている。
また(これはアメリカの調査だが)野菜と果物を合わせて400グラム以上食べた女性(看護師)のほうが、それ未満の野菜摂取量の女性よりも健康だった、という研究もある。アメリカは、栄養上、野菜と果物を分けては考えないが、日本では野菜と果物をかなり明確に分けてある。そのうえ、日本では果物の摂取量がかなり少ないため「野菜で350グラム以上を摂取」しないと、この「アメリカの研究結果」を生かすことができない。その点からも「健康のために野菜を一日 350グラム以上食べよう」という目標が設定されてある。
これらの研究からも推察できるように、健康のためには「野菜350グラムに含まれる栄養素」を体内にとり入れればいい、というわけではない。野菜(と果物)をたくさん(数値でいえば、日本人ならばだいたい350グラム以上)食べることが健康にいいらしい、ということがわかっているだけなのだ。
「野菜350グラム分の栄養素を摂取すれば健康になれる」という科学的事実はない。つまり、野菜350グラム入りのジュースを飲めば健康になれるという保証はない。野菜ジュース(青汁も)を飲むことは野菜を食べることとは同じではないからだ。
野菜ジュースが逆効果を招く“落とし穴”
「野菜をたくさん食べる」という行為(とりわけ食習慣)の中には(野菜の栄養素を摂取できるということ以外に)さまざまな要素が含まれる。野菜をたくさん食べる人は、たとえば(その分だけ)主食の食べすぎになっていないかもしれない。たとえば、脂肪やタンパク質の過剰摂取になっていないかもしれない。結果的に「栄養バランスがいい人」なのかもしれない。
さらにいえば、このご時世に「野菜をたくさん食べている」という人は、食事以外でも健康に気をつけている人なのかもしれない。運動もしっかりやっている人なのかもしれない。それらの総合的な習慣が、その人を健康にしているという可能性もある。野菜の栄養素だけの影響ではないかもしれないのだ。
この点を理解しないで「野菜ジュースさえ飲めば健康問題は解決する」と思ってはならない。ただし「野菜ジュースは健康的に何の役にも立たない」というわけではない。ふだん健康的な食生活を心がけている人が、たまたまその日は野菜不足になるからという理由で野菜ジュースを(補助的に)飲用する、ということであれば、きわめて有効な使い方(食べ方)になるであろう。
しかし、多くの人は逆になる。どういうことかというと「野菜ジュースを飲んだから(飲んでいるから)野菜を食べなくてもいい」となる。さらには「健康を考えた食生活などしなくてもすむように、とりあえず野菜ジュースを飲んでおく」という人さえいる。これではまさしく逆効果で、野菜ジュースを飲むことが不健康を招くことになりかねない。
忙しいビジネスパーソンこそが陥りやすい落とし穴なので、充分に気をつけたい。
[Wedge]
Posted by nob : 2017年02月07日 17:14
90度は開くけれど、、、それにしてももう少し柔らかくなりたい。。。
■プロが断言! 「180度開脚は必要ありません」
90度くらいで柔軟性は十分
話題の「180度開脚」にはリスクがある? 日本を代表するトップアスリートの指導も行うパーソナルトレーナーの第一人者、中野ジェームズ修一氏が解説します。
健康診断で思わしくない結果が出てしまったときや、お腹についた脂肪が気になり始めたとき。ウォーキングやランニングとともに、チャレンジしようとする人が多いのが「ストレッチ」だと思います。脂肪を燃焼させることを考えると、ストレッチではなく筋力トレーニングと有酸素運動を行ってほしいのですが、“今まで運動をしていなかった人がストレッチを始める”というのはすばらしいことです。ストレッチをすることで、ウォーキングや筋トレへの意欲が出てくることもあるでしょうから、ぜひチャレンジしてほしいと思います。
ストレッチをして体の柔軟性を高めようとするとき、よく聞く目標の1つが「180度開脚ができるようになりたい」というもの。バレエダンサー、フィギュアスケーター、体操選手などの肉体美と華麗な動きに憧れて、ということなのかもしれませんが、特殊な競技スポーツやダンスなどをする方以外にはお薦めできる目標ではありません。
まず知っていただきたいのは、関節には可動域というものがあること。関節ごとにどの方向にどれだけ動かせるかというのは決まっていて、それ以上は人体の構造的に制限がかかります。実際に手首の関節や肘関節を動かして観察してみてください。当たり前ですが、手の甲が腕につくまで反らせることはできませんし、肘が360度ぐるりと回転することもありません。言うまでもなく、それは悪いことではありません。骨と骨がぶつからないように、骨と骨をつないでいる靭帯が伸びて切れてしまわないように、構造的に動かせないようになっているのです。
股関節に話を戻しましょう。股関節の可動域を考えると、横方向に開脚した場合、股の間の角度は90度ほどあれば柔軟性は十分。90度と書きましたが、これもあくまで基準の一つ。当然個人差はありますし、大腿骨頸部や大腿骨骨頭を骨折したことのある方は可動域が狭くなっていることが多く、無理に開こうとする必要はありません。
なぜバレエダンサーは自在に開脚ができるのか?
それでも「実際に180度開脚をしている人がいるし、気持ちが良さそうだ」と思う方もいるでしょう。しかし、可動域を超えて無理に関節を動かそうとすると、クッションの役割を果たしている軟骨や、骨と骨をつないでいる靭帯を傷つけてしまいます。典型的な例が「捻挫」です。捻挫とは外部からの圧力によって関節可動域を超えて関節が動いてしまったことで、靭帯を損傷したということです。
では構造上制限があるはずなのに、どうしてバレエダンサーや体操の選手は自在に開脚ができるのでしょうか。
成人の骨は骨と軟骨がはっきりと分かれており、骨の中には血管が通っているのですが、軟骨部分には通っていません。よって、骨折しても骨は修復されますが、軟骨部分が一度すり減ってしまうと修復は困難です。一方、成長期にある子供たちの骨は全体的にまだ軟らかく、骨と軟骨の境界があいまいです。この段階で過度な負荷を徐々に与えると構造自体が少々変形し、本来の可動域よりも関節を動かせる範囲が広がるのです。まさに“鉄は熱いうちに打て”といったところでしょうか。
180度開脚によって直接的に「脚のむくみがとれる」「脚が細くて美しくなる」「歩くのがラクになる」といったメリットがあるのであれば目指す価値がありますが、現在そのようなことは科学的に証明されていません。軟骨や靭帯を損傷するリスクがあるのに、メリットがないことをやろうと思う人はいませんよね。
軟らかすぎると老後に関節が不安定になる?
過剰な柔軟性によって、老後に関節が不安定になるリスクもあります。
靭帯が骨と骨をつないでいるという話を先ほどしましたが、筋肉はそれらを覆うサポーターのような役割をしています。筋肉は筋線維という線維状の細胞の集合体で、これを筋膜が覆っています。筋線維は無数の筋原線維で構成され、筋原線維はサルコメア(筋節)からできています。ストレッチを定期的かつ継続的に行うとサルコメアの数が増えると考えられていて、増加したぶんだけ筋原線維が長くなり、柔軟性が高まるのです。サポーターが少し弛むぶん、可動域が広がるというイメージですね。
筋肉量が多くてサポーターが厚いうちはいいのですが、老化とともに筋肉量が減ってサポーターが薄くなると、関節が不安定になってしまいます。それが股関節であれば、脚に力が入れにくく、歩きづらくなってしまうでしょう。
特殊なスポーツをしている人以外には180度開脚は必要ありませんが、適度な柔軟性は必要です。体全体をバランス良くストレッチしていただきたいですが、特に念入りに行ってほしい部位を挙げるとするなら「腸腰筋」です。
腸腰筋とは骨盤と大腿骨、腰椎を結ぶ筋肉群で、歩くときなどに脚を持ち上げる動作で働く場所です。加齢とともに硬くなりやすいとされていて、腸腰筋が硬くなると骨盤が前傾して前かがみになり、いわゆる“老化姿勢”になってしまいます。
どの部位が硬いのか、硬くなりやすいのかというのは、個人差があります。お勧めしたいのは、一度専門家にストレッチをしてもらうこと。スポーツジムでパーソナルトレーナーに見てもらうのもいいでしょうし、近年増えているストレッチサロンでもいいでしょう。自分のどの部位が硬く、どこが柔らかいのかが分かれば、より効率的に柔軟な体になれるはずです。
ストレッチ関連の書籍を購入する場合は、1カ所の部位に対していくつかのポーズが載っているものがおすすめです。同じ筋肉をストレッチする場合でも、体格などによって“伸びる”と感じるポーズが違うからです。
(構成/神津文人)
[日経トレンディネット]
Posted by nob : 2017年01月31日 13:55
最近なかなか行けませんが。。。
■サウナで認知症リスク低下、本場フィンランドの報告
お父さんたちの疲労回復に、若い女性の美肌・痩身にと根強い人気がある「サウナ」。さらに昨年末、サウナの本場フィンランドから「認知症予防に良い」という報告があった。
研究者らは、フィンランド在住の中年男性(42~60歳)2315人を対象に、サウナを利用する頻度とアルツハイマー型認知症(以下AD)および、その他の認知症リスクとの関係を検討。サウナの利用頻度は(1)週に1回、(2)週に2~3回、(3)週に4~7回の3群で比較している。参加者の登録時期は1984~89年。平均20.7カ月間追跡が行われ、この間に327人が認知症を発症、このうち123人がADと診断された。
2型糖尿病の病歴や高血圧、飲酒・喫煙歴などの影響因子を排除して、認知症発症リスクとサウナ習慣との関係を調べた結果、(1)週に1回の群の認知症発症リスクと比べて、(3)週に4~7回の群の発症リスクは66%低下、ADに限っても65%の低下率を示した。また、(2)週に2~3回の群でも(1)と比較して、認知症発症リスクは22%、AD発症リスクは20%それぞれ低下している。
今回の研究は、フィンランドの「Kuopio(クオピオ)」地域に住む男性の生活習慣と虚血性心疾患──心筋梗塞や狭心症との関係を調べた研究のいわば「スピンオフ」調査。
本調査では、サウナの利用が増えるほど心疾患が原因の突然死が減り、心血管疾患の発症リスクが低下することが示されている。
研究者は「サウナの頻繁な利用は心臓と脳機能を保護する可能性があり、サウナに入っているときのリラックスした感じが良いのかも」としている。
ADの発症予防と治療法の開発は全世界の課題だが、ADの新薬が承認されたのは14年前の2003年が最後。それ以降の開発成功率は0.5%にも満たない。しかも現在、使えるAD治療薬はすべて「症状を抑える」のみ。日々の発症予防が何よりも重要なのだ。
普段の生活で実践できる予防法は禁煙と食生活の改善とウオーキングなどの運動。これにサウナの適度な活用を加えてもいい。
(取材・構成/医学ライター・井手ゆきえ)
[DIAMOND男の健康]
Posted by nob : 2017年01月31日 09:15
病状は千差万別、、、自分自身を主治医とする医療専門家や家族・友人など、周囲との信頼関係で結び付く共闘チームを如何に築き上げるかということ。。。
■故・川島なお美さんの「選択」に惜しむこと
医師への「反発」でも「従属」でもない関係とは
加藤眞三
慶應義塾大学看護医療学部教授
川島なお美さんが2015年9月24日に胆管がんのために亡くなって、もう1年以上が経ちます。同年12月には、ご主人でパティシエの鎧塚俊彦さんとの共著として『カーテンコール』が出版されました。その本の中には、川島さんがご自分の病気に対して正面から真剣に向かい合ってきた様子が詳細に書かれています。
「納得のいく」療養生活を続けたことには意味がある
川島さんが亡くなられた後に、マスコミは川島さんのがんの闘病生活に関して、あれこれと報じていました。がんの手術後に抗がん剤治療を受けなかったこと、発酵玄米や豆乳ヨーグルトを中心とする食事療法をしたり、ビタミンCの濃縮点滴治療・電磁波などを使った民間療法を受けていたことなどが、主な批判の内容です。
私はこれらの民間療法に効果があると思っていません。それでも川島さんが療養生活について自分で一生懸命に調べ、納得しながら続けてこられたことを高く評価します。亡くなられる直前の9月7日、シャンパンの発表会でご夫婦がそろってにこやかにテレビカメラの前に出ることができたのは、このような療養生活を送っていたからこそではないかと考えます。
悔やむべき点があるとすれば、最初にMRI検査で1.7センチの腫瘍が見つかったときに早く手術を受けていれば、ということです。その決断をしていれば、もしかしたら現在も再発することなくお元気に舞台生活を送ることができていたのではないでしょうか。
では、なぜ手術に踏み切れなかったのか。闘病記の中には、医師から100%がんであるとの言質を得られなかったから、がんであることを信じたくないから、女優として・楽器としての体に傷をつけたくないから、舞台の仕事を中止できなかったから……など、いくつもの理由が挙げられていました。
一方、同じく俳優の渡辺謙さんは、2016年のニューヨーク・ブロードウェーでのミュージカル「王様と私」が3月1日に開幕するという直前の2月上旬に人間ドックで胃がんが発見され、2月8日に内視鏡手術を受けました。ブロードウェーの開幕を延期してでも直前に手術を受けるということは、大変な決断であっただろうと想像できます。
渡辺さんの場合、それ以前にも白血病を患った経験があり、夫人の南果歩さんも乳がんの経験があります。こうした経験の中で「患者力」を身につけていたことが、勇気ある決断につながったのかもしれません。医師と十分に対話し、自分の中での優先順位をつけることは、「患者の力」としての大きな要素です。
川島なお美さんも、腫瘍が見つかった段階で生検(直接体内のがんの一部を取って調べる検査)を受け、がんであることを確信できていれば、舞台を中止してでも手術にもっと早く踏み切れたのではないでしょうか。そして、そのための対話を医師との間で最初からうまくできていたならば、川島さんの決断も違ったものになったかもしれません。科学的思考を持つ医師が、画像だけを見て100%がんであると断言することはまずない、ということを知るだけでも、川島さんの対応は違っていたかもしれません。
医師に言われたことに従うだけ、あるいは反発するだけではなく、患者が医師とうまく対話をできる協働作業の関係を創りあげていくことが、これからの医療に望まれます。
これからの医療に必要な「コンコーダンス」って何?
「コンコーダンスの医療」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。医療者の間にもまだ十分に浸透していない用語ではありますが、私はこれが、これからの時代に必要な新しい医療のキーワードだと考えています。患者と医療者の関係性を表す医療用語のトレンドは、「コンプライアンス」から「アドヒアランス」、そしてこの「コンコーダンス」へと移り変わってきました。そういっても、多くの方には何が何やらわからないでしょう。そこで、これらの用語の普及に関して、歴史的な変遷をたどってみましょう。
患者と医療者の関係性において、最初に問題になったのは、「患者コンプライアンス」の問題でした。コンプライアンスとは一般的に、「法令順守」と訳され、企業の活動の中で法令に従って行動するという意味で使用されます。しかし、医療の中でコンプライアンスといえば、通常「医療者の処方や服薬指導、療養生活の注意に従わない」という意味で使われます。たとえば、医師が「あの患者はコンプライアンスが悪い」と言ったとき、「あの患者は医師の言うことに従わない、困った患者だ」という意味が含まれています。
病棟や自宅などで医療者の期待に背き、療養生活を勝手に(自由に)行動する患者の場合も「病識がない患者」と呼ばれてきました。病人であることの意識が欠如しているという意味です。患者に病識があれば、医療者の言うことに従うのが当然であり、病識がないからコンプライアンスが悪いという論理です。
ここでは、患者は医療者の指示や命令に従うことが当然であるという、上下関係が前提とされています。「医療者の指導に従わないのだから、従わない患者がいけない。従わないのは患者側の問題である」といった考え方がされてきたのです。こうした患者に対して医療者はあきらめの境地に至り、いずれ責任を放棄する態度で接することになります。
医療者たちがこのような考え方をする背景には、患者は医療を提供される、あるいは学校や仕事を休むことが許されるという恩恵を社会から受けるのだから、患者は医療者のいうことに従い、自分の楽しみなどは我慢するのが当然であるという社会全体の意識もありました。まさに、我慢(patience)するのが患者(patient)の務めであったわけです。
しかし、現代の社会では病気が多様化し、慢性病が多くなっています。患者であるからと働かないことが許されるわけではなく、病気を抱えながら生活することが要求されます。また、社会の成熟とともに患者の教育レベルが高まり、自律心が高まっています。多様性を重んじることの必要性が社会全体に認識され、患者中心の医療が進められてきた過程の中で、欧米諸国の医療ではコンプライアンスがアドヒアランスに置き換わってきたのです。
アドヒアランスは、固守、執着などと訳される単語です。医療においては、処方された薬を処方どおりに服薬するという意味で使われます。しかし、その前提として、いくつかの選択肢の中から患者が主体的に選び、納得・同意したうえで、服薬する意思を固守し継続するという意味が含まれます。したがって、治療の決定権がより患者側にあります。患者自身が納得したうえで治療を続けようとする気持ちがアドヒアランスと表現されるのです。
私が専門とする飲酒に関連する身体問題のある患者に対しても、私はあえて「禁酒」ではなく「断酒」という言葉を使います。禁酒と断酒の間には、コンプライアンスとアドヒアランスに似た違いがあると考えているからです。
アドヒアランスを重視する医療では、医療者側のやるべき仕事が増えてきます。アドヒアランスの悪さは、単なる患者側の資質の問題ではなく、治療者側の要因、薬物側の要因、周囲の人や環境の問題なども挙げられ、それぞれの要因への対処が要求されるのです。
アドヒアランス向上のために、たとえば、患者へ病気や治療に関する十分な情報提供を行い、処方の簡便化や剤型の工夫を進め、家族や周囲の人の協力を得るように調整し、患者が持つ固有の服薬に対する不安について一緒に考え、援助することなどが必要となります。
患者にも努力と責任が要求される
一方で、患者の側にも、それなりの努力と責任が要求されます。自分の病気について理解し、療養生活や治療についても十分の知識を備え、自ら決定することが要求されるのです。アドヒアランスを重視する医療は、患者がより主体的・能動的になることが要求され、患者側にも責任が生じます。同時に医療者の側も、情報提供などやるべき仕事が増え、それに対する責任も生じるのです。
アドヒアランスを高める医療が欧米諸国で普及する中で生まれてきた概念がコンコーダンスです。コンコーダンスは、一般的には一致や調和と訳されます。1996年に、英国の保健省と薬学会でつくられた薬剤パートナーグループ(Medicines Partnership Group)は、コンコーダンスを「病気について十分な知識をもつ患者が病気の管理にパートナーとして参加し、医師と患者が合意に至った治療を協働作業として行うプロセスである」と定義しています。
コンコーダンス医療では、医療者と患者が対等の協働する関係性にあります。医療者が処方を一方的に決定し、それに患者を説得して従わせるのではなく、患者も自分の状況や希望を医療者に説明し、医療者はそれに基づき、いくつかの案を提案するなど、対話と合意が大切にされます。
はたして、このようなコンコーダンス医療がわが国で可能となるでしょうか。私は楽天的に考えています。青山学院大学の駅伝チームも、原監督の業界の常識を疑うチーム作り、選手の自主性と対話の重視により優勝に導かれました。わが国の医療においても、業界の常識の先にあるのがコンコーダンス医療であり、遠からず(今後10年以内?)徐々に普及し始め、20年後にはそれが当たり前になるだろうと信じています。
“患者側”の意見が「治療ガイドライン」を変えた!
コンコーダンス医療につながる一つの兆しを、日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン」に見ることができます。2004年版で使われていた「コンプライアンス」という用語は、2009年版では「アドヒアランスとコンコーダンス」に置き換わっています。その後に改訂された2014年版においても、「コンコーダンス」の医療を続けるための方法が詳細に書かれています。
たとえば、治療の有益性について話し合うこと、わかりやすく情報提供すること、患者の合意、自主的な選択を尊重すること、処方の単純化をすること、患者による血圧測定(家庭血圧)を励行し、それに基づいて処方すること、家族を含めた支援体制を作ること、服薬忘れの原因や理由について話し合い、不安があれば必要に応じて薬剤の変更を考えることなどが挙げられています。
高血圧症は、わが国において最も頻度の高い疾患の一つであり、その治療ガイドラインは当然多くの医師の目に触れます。また、医学教育にも今後大きな影響を与えるだろうと考えられます。
実は、高血圧学会がコンコーダンスをガイドラインにとりあげるきっかけとして、患者の自立・成熟を目指すNPO法人「COML」の理事長であった辻本好子による提言があります。ガイドラインの策定過程において、辻本さんから「コンプライアンスは医者目線でパターナリズム(父権主義)の言葉であって、コンコーダンスの概念を採り入れるべき」との発言があり、まさに鶴の一声によって、コンプライアンスを服薬アドヒアランスに改め、コンコーダンスの重要性が加えられたというのです〔萩原俊男(2009年版ガイドライン作成委員長)「私と高血圧」〕。こうして作られた高血圧治療ガイドラインは他の領域のガイドライン作りにも大きな影響をもたらしました。
新しい時代が要求する医療は、その医療の専門家だけで創るものではなく、専門家に反対する医師や市民などからの多様な意見が反映されて開かれていくのです。エンドユーザーである患者が社会で声を上げること、医療者と対話をしていくことが、そのための第一歩でもあるのです。
[東洋経済ONLINE]
■小林麻央さんの「後悔」から一体何が学べるか
医療の不信を煽る週刊誌で患者は進化した?
加藤眞三
慶應義塾大学看護医療学部教授
医者に治療方針を丸投げする患者からはもう卒業して、「協働」の関係を築くべきです。
小林麻央さんのオフィシャルブログ、「KOKORO.」 が注目を集めています。以前、ニュースキャスターを務めていたことや、人気歌舞伎俳優、市川海老蔵さんの夫人であることもその一因でしょう。
ただ、注目されている最大の理由は、進行性乳がんという大病を抱えながらも、敢えてそのことを公表し、病気とわかってからの日々の思いを赤裸々につづっていることで、感性豊かな麻央さんの言葉の中に多くの人がハッと気付かされ、共感を覚えていることにあるのではないでしょうか。
小林麻央さんがつづった「患者としての後悔」
特に、9月4日の「解放」と題する記事には、患者としての気持ちが見事に表されており、心が揺さぶられます。
私も
後悔していること、あります。
あのとき、
もっと自分の身体を大切にすればよかった
あのとき、
もうひとつ病院に行けばよかった
あのとき、
信じなければよかった
あのとき、、、
あのとき、、、
「KOKORO.小林麻央のオフィシャルブログ」byAmeba 9月4日
病気であることが発覚すると、その日から突然色々な問題に巻き込まれ、各局面で決断を迫られます。しかも、それらは普段考えてもいなかったことであり、てきぱきと判断するだけの心の準備も十分ではありません。
病気発覚後の患者には、次から次へと疑問がわいてくるのです。「わたしの病気は、一体どんなものなのだろう」「私の状態はどの程度なのか。その病気に対してどんな治療法があり、それにはどんな副作用がある?」「これからの経済的な負担はどうなるのか」「仕事は続けられるのだろうか」「安静にしていた方がよいのだろうか。あるいは、身体を動かしてよいのだろうか。動かしてよいのなら、どの程度まで?」「食事は制限されるのか」「医師にこんなことを質問して聞いてもよいのだろうか。自分の希望を伝えて、生意気だと思われないだろうか」「他の医療職の方に相談できる機会はあるのだろうか」「一体、どこの病院で診療を続けるのが良いのだろうか」「あの時の決断があるいは間違っていたのかもしれない。もう、手遅れだろうか。あるいは、もっといい方法があるのでは」…。
われわれは、「患者学」で武装するべきだ
このように、患者としての悩みはつきません。そして、これらの問題に対して時間の猶予なく決断していかなければならないのです。いや、決断することに時間の猶予があるのかないのかさえ、よく判らないかもしれません。
そんな患者さんに対し、私は「患者のための患者学」を学びませんか、と呼びかけてきました。患者学の前に「患者のための」とわざわざ付けているのは、医療者が患者から学ぶ患者学、すなわち「医療者のための患者学」と区別するためです。患者と医療者の双方が患者学を学ぶことにより、よりよい医療が実現するのではないかと、考えているからです。
そして、小林麻央さんの後悔を知ると「患者のための患者学」は患者になる前からしっかりと身につけておく必要性があることに気付かされます。ですから、むしろ「市民のための患者学」と名付けて、一般市民の方にも準備してもらいたいと考えるようになりました。
「市民のための患者学」で身につけるべき内容を、わたしは以下の3つに分類してみました。
(1)患者と医療者の関係性
(2)医療情報の集め方・読み方(医療情報リテラシー)
(3)病気を抱えた自分の生き方の決断
3つの分野はお互いに関連し合いますし、これだけを学んでおけば完璧だというものではありません。しかし、少しずつでも前進できていれば、いざ患者になった時に役立つことは間違いありません。そこで、ここから「市民のための患者学」の入門編について、解説し紹介していきたいと思います。
現在、医療の現場では、医療者に対する患者さんの不信感が募っています。週刊誌などで、医療の不信を煽る特集記事が頻繁に組まれているからです。
「高血圧の薬は飲まない方がよい」、「がんになっても手術は受けてはいけない、抗がん剤治療は受けてはいけない」――。こうしたセンセーショナルな特集を組めば、その雑誌がよく売れ、よく売れるから次号にも特集記事を続けるという状況が続いているのです。そして、一つの雑誌が医療の特集で売れると、それを見た他の週刊誌もこぞって同様の特集を組むという現状です。
週刊誌の医療特集に「煽られる」のも1つの進化
実際、私の外来にも、これまで副作用の症状が現れていないのに「高血圧のこの薬は飲んでいて大丈夫ですか」と心配してたずねてくる患者さんがいました。「この高コレステロール血症の薬は、週刊誌に筋肉が壊されると書いてあり、怖いのでやめたい」と言われたこともあります。医療機関に助けを求めて訪れた患者さんが、医療者を信用できないとしたら、それはとても不幸なことです。何とかしなければなりません。
ただ、医療の歴史を俯瞰的に眺めてみると、このような対立は生じるべくして生じていることがわかります。この対立を経ることで、次の時代の医療に移らなくてはならないのです。
それでは、今までの医療はどんなものだったのでしょうか。それは専門家に患者が「お任せ」する、依存的な医療であったということができます。患者は受け身で説明を受け、ただ同意をするだけ。医師のいうことには逆らえません。「先生にすべてお任せしますから、魔法の薬で治して下さい」。そんな気持ちで医療機関を訪れる患者も多いのも事実です。
実際、ある程度治療方針の決まった病気なら、専門家に判断を委ねて患者は受け身となっているだけでも、問題はさほどありません。たとえば、肺炎になったり、膀胱炎をおこしたりすると、診療により投与される薬で菌が排除され、病気が軽くなります。骨折を起こしても、医師に任せて固定してもらったり、手術をうけることで、具合が良くなります。
ただ、自覚症状に乏しい慢性病の場合は、患者さんの療養生活が大きな鍵を握ります。たとえば、糖尿病や高血圧などの生活習慣病では、日々の生活をどう変えられるかが大切なのです。あるいは、がんやその他難病になったときの療養生活でも、患者さんの意志が大きくその経過を変えてしまいます。
1956年に、米国のサッシュ博士とホレンダー博士が論文に発表した医師(医療者)と患者関係のモデルによれば、病気の種類や状況に応じて、医師と患者関係は変わってくることを予言しています。
この表が作られたのは、60年も前のこと。それにもかかわらず、日本では現時点でやっと「説明ー協力」の関係の医療が出来つつある段階であり、まだ「協働作業」の医療は実現できていないことに驚かされます。しかも、60年前と比べて、今はメタボリック症候群などに代表される慢性病が一般的になっています。がんも、診断されてから5年以上生存する人が多くなっています。こうした病気の療養生活では、医師と患者の協働作業こそが大切なのです。
しかし、患者の側も医療者の側もその準備が充分にはできていないのが、現在の状況ではないでしょうか。
[東洋経済ONLINE]
■日本全国で「がん難民」が生まれる深刻な理由
「専門医を見つけたから安心」という勘違い
加藤眞三
慶應義塾大学看護医療学部教授
専門医だから安心して任せられる。そう思っていませんか?
「がん難民」という言葉をご存知ですか。全国各地のがんセンターや大学病院などの高機能病院で、治療ができなくなったがん患者が、医師から見放されてしまい、行き場をなくしてしまうという問題です。
がんセンターで「がん難民」が発生している?!
高機能病院には、一般的な病院にはないような高度な治療機器があり、専門医がいます。一見治療が困難な患者を受け入れてくれそうなイメージがあるのにも関わらず、患者が「難民」になってしまうのはなぜなのでしょうか。その理由を理解するには、専門医の思考法を知ることが必要になります。
現代の医師が患者を診療するとき、その思考法にもっとも影響を与えているのは、言うまでもなく「科学」です。言い換えれば、医師は科学者として教育され、働いているのです。
科学者としての医師に期待されるのは、①論理的である(理屈が通る)、②実証的である(科学的手法により確率・統計的に証明できる)、③普遍的である(世界のどこでも、誰にでも当てはまる)、④客観的である(冷静である)ことです。そして、そのような医師を育てる医学教育が行われます。このことによって、ある一定以上の医療水準を維持することにつながっている面もあります。客観的である(冷静である)ことであり、そのように医学教育がなされます。これによって、ある一定の医療水準を維持することにもつながっている面もあります。
こうした科学を主とする現代医療は、「医学モデル」と呼ばれます。医学モデルでは、病気には(1つの)原因があり、その原因の結果として病気が生じていると考えます。そして、病気の原因を見つけ出して、それを取り除くことが医療の目標となります。感染症であれば、細菌やウイルスを薬により除去すること、がんであればがんの組織を手術で切り取ったり、放射線でたたいたり、薬でつぶすといった具合です。そして、このモデルにおいて医療を行う主体は、専門家である医療者となります。
こうした科学的な医学においては、専門分化が進んできました。医学の進歩とともに、知識と技術の範囲が広くなり、奥が深くなってきたための当然のことです。医学全般を1人の医師で全てをカバーすることなど、とてもできません。専門医として、専門分野を決めてカバーする範囲を狭くすることで、その専門分野における知識と技術に精通することができるのです。
専門医は専門分野に対して責任を持つ
専門医は、自分が専門分野とする病気に対して責任感を持ちますが、専門でない分野の病気に対しては、自分には関係ないし、責任もないと考えがちになります。そして、専門分野の病気であっても科学的に治療効果などのエビデンス(科学的証拠)が積み上げられた問題の範囲内で、医療をしようとします。治療法が確立していない病気や治療が望めない進行度になると、どうしても興味を失いがちになります。
例えば、私が過去に経験したこんなケースがあります。ある日救急外来に来た患者さんは、主に心不全の症状が見て取れました。そこで、私は循環器内科の医師に、この患者さんを診てくれないかと依頼しました。しかし、その医師は、一般内科で診てもらえばよいと、その依頼を断りました。彼の発想はこうです。心臓カテーテルなどによる治療が必要な心筋梗塞や狭心症であれば、その専門である自分の出番だけれども、そうでないならば自分が診なくても良い、という考え方をするのです。
話だけ聞くと、ずいぶん了見の狭い医師のように見えますが、これは専門医にとってけっして珍しい考え方ではありません。患者が専門医を受診すると、専門医はまず、自分の専門分野の対象となる患者かどうかを判断するものです。そして、対象から外れてしまうと、関心を失ってしまいます。専門外のことはよく解らないから、なるべく関わりたくないと逃げ腰になるのです。
自分の専門の範囲内の患者であることが解れば、次に、命に関わる病気かどうかを判断します。そして、命に関わらないものであれば、まあ放置しておいて良いのではないかと考えがちです。専門医は、原因を明らかにして対処する「原因療法」を第一と考えますから、症状を抑えておくだけの治療は「対症療法」として軽視しがちになります。
したがって、血液検査や画像検査で異常が見つからなければ、とりあえずは命に関わる病気ではないと判断し、「検査をしたけれども、どこも悪いところは見つからない」と答えてしまいます。
また、専門の範囲内ではあっても、自分が治せない、あるいは治せなくなった患者とは関わりたくないという気持ちが働いても不思議ではありません。医師にとって、治せないことは「敗北」となるからです。
医師という職業は、自分が提供した医療によって治すことのできる患者が相手であれば、治療が成功したあかつきには喜ばれ、感謝されます。しかも、医師不足の状態が続いていますから、治療の可能な患者がいつも沢山待っている状態にあります。そんな状況の下で診療をしていると、治せない、あるいは治せなくなった患者とは関わりたくないという気持ちがはたらいても不思議とは言えません。
冒頭で紹介したように、現在全国各地のがんセンターや大学病院などでは、治療ができなくなって患者が医師から見放されてしまうという「がん難民」の発生が問題になっています。これは、上に述べてきたように治すことのできない患者が医師の「自己効力感」を打ちのめすことを避けようとする、医師側の心理の問題でもあるのです。
治せる患者を優先して診療、という使命感の裏返し
ただ、これは単に医師が敗北を嫌うだけではなく、治せる患者を優先して診療しなくてはならないという使命感の裏返しでもあります。重装備の医療機器を備えた急性期病院であるほどそう考えるでしょう。また、重装備の病院では、重装備を必要とする医療を行わなければ無駄が出てしまう、という医療経済や保険診療上の問題もあるのです。つまり、「がん難民」の発生はある程度仕方がない面があるのです。
では、それを避けるためにはどうすれば良いのでしょうか。高機能病院がその規模を大きくして、治療ができない進行したがんや難病の診療を行う部門をつくることは解決法の1つです。しかし、それはおそらく医療経済的にも実現は難しいと思います。また、進行したがんの患者が、家族のいる自宅から離れた場所で医療を継続して受けなければならないという問題も生じます。私は、その様な方向に医療が進んでいくことは理想ではないと考えています。
それに代わる解決法は、患者ががんセンターや大学病院などの医師に頼りすぎず、「かかりつけ医」をほかに持つことです。高機能病院はあくまで、その機能を患者が利用するだけの場所であると割り切ってしまい、自分が心から頼りにできる主治医は別に持つのです。そうすれば、高機能の病院での医療の対象とならないような病状になっても、その後の医療について相談できることができます。
つまり、高機能病院から離れることになっても、自分は「がん難民」とは感じないような仕組み作りをすることが必要なのです。高度な専門医は、その機能を利用するだけだ、と患者側が見限ることが1つの解決法です。
さて、ここまで専門医に頼りすぎないようにということで話は進めてきましたが、もちろん専門医の中にも素晴らしい医師が沢山いることは事実です。治療の難しい病気であればなおさら、専門医の中からよい人を見つけることが一番大切になります。
『治るという前提でがんになった』(幻冬舎)の著者、高山知朗さんは、40歳代前半に悪性脳腫瘍と白血病という2つのがんを発症しましたが、IT関連会社を立ち上げたその経験と能力、そして人脈をフルに活用して、両者を克服してこられました。患者学を自然に身につけているお手本となる方です。
高山さんは、治療法に関する情報の収集を行い、どの病院が良いかを的確に判断し、良い主治医に巡り会っています。脳腫瘍を治療した脳外科医も、白血病を治療した血液内科医も、専門医でありながら高圧的な態度をとることはなく、患者の自律性を重んじ、患者の気持ちをとても大切にしておられるようです。
両方のがんが治ったからこそ、「がん難民」にならなかったと言うこともできますが、おそらく高山さんなら高度機能病院での治療法がなくなったときでも、その病院にしがみつくことなく、別の道を探されるのではないかと思います。
専門医の悪口(本当は悪口を書こうとしているのではありませんが、悪口のように聞こえる人もいるでしょう)をさんざん書いていながら、専門医にもこんなに人間的な医療を提供する医師がいることを知ることで、ホッと胸をなでおろす気持ちになりました。
患者が医者を見限ることも大切
加えて、わたしが研修医だった30年以上前にはごく当たり前な存在だった患者に高圧的な医師は、今では少数派になっています。時代とともに医師の側も変化してきています。
そのような変化の時期だからこそ、自分に合った医師を主治医として選択することが、よい医療を受ける上で決定的に大事となるのです。
医療者に変化を促すのも患者の力です。高圧的な医師は見限ってあげれば次第に絶滅機種となっていくのですから。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2017年01月17日 13:37
利益と弊害はいつも共存する、、、結局何を目指すのかということ。。。
■ゆるやかな糖質制限食「ロカボ」で健康的に痩せられる理由
今年こそはダイエットを! そう誓いながらも、ビールやから揚げ、ケーキの誘惑に負け、新年早々に挫折してしまう――、そのような経験はありませんか。「お酒も揚げ物もスイーツも食べて大丈夫」。そう話すのは、ゆるやかな糖質制限食「ロカボ」を提唱する北里大学北里研究所病院糖尿病センター内分泌・代謝内科センター長の山田悟さんです。おいしく痩せて健康になるロカボについて山田さんに聞きました。
ダイエットだけじゃないロカボの効果
「ロカボ」で正月太りを解消!
糖質制限という言葉を耳にしたことのある方は多いのではないでしょうか。私の提唱するゆるやかな糖質制限食「ロカボ」は、英語で低糖質の意味を持つ「ロー・カーボハイドレート(Low Carbohydrate)」の略称です。毎日の食事から糖質を抑え、たんぱく質、脂質などを満腹感が得られるまで食べて、無理せず、おいしく、ダイエットできる食事法です。
2012年、国際肥満学会(ICO)の機関紙『Obesity Reviews』に掲載された、最も信頼性の高い研究試験法である無作為比較試験のメタ解析(複数の研究を統計的に分析する手法)の結果によると、糖質制限食は体重減量だけでなく、脂質、血糖、血圧の改善にも有効であるとされています(*1)。
糖質とは、多糖類(デンプン、グリコーゲンなど)、二糖類(麦芽糖、ショ糖など)、単糖類(ブドウ糖、果糖など)、そしてオリゴ糖、糖アルコール類に分類されます。糖質を多く含む食品は、ごはん、芋類、根菜、果物、お菓子、ジュースなどで、みりん、蜂蜜などの調味料にも多く含まれます。
一方で、糖質含有量の少ない食品は、肉、魚、大豆製品、葉野菜、ナッツなどです。

出典:一般社団法人 食・楽・健康協会
糖質量を守れば満腹感を得るまで食べてOK
ロカボは、1日3食とし、1食当たりの糖質量を20~40g、おやつとしてのスイーツは糖質10gまでとし、トータルの糖質を1日に 70~130gとする食事法です。日本人は平均で、一食当たり90~100g、1日270~300gの糖質を取っているので、その半分弱と考えてください。
ごはんやパンなどを通常の半分~3分の1程度にして、おかずを満腹感が得られるまで食べます。肉、野菜、乳製品、植物性脂質、動物性脂質などは、栄養バランスやカロリー、コレステロールを気にせずに摂取してください。
なお、マーガリンやショートニングなどのトランス脂肪酸、過酸化脂質は避けましょう。食品100g当たりの糖質量(g)については、「食・楽・健康協会」サイト内の表「食品100g中の糖質量」(PDF)が参考になると思います。
お酒も「百薬の長」程度であれば、ロカボの面では問題ありません。比較的糖質の多い日本酒でも1合に含まれる糖質は8~9gなので、主食を抜けば 2合程度までは楽しめます。スイーツも大丈夫。糖質の少ない人工甘味料の活用した「ロカボスイーツ」もコンビニや洋菓子店でも販売されています。
血糖値を上昇させるのは糖質のみ
糖質制限の目的は、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)の上昇を抑えることです。血糖値を上げる唯一の栄養素である糖質は体内でブドウ糖に変換され、血糖値を下げることができるホルモン「インスリン」により、細胞のエネルギー源として活用されます。
しかしエネルギーとして使い切れないブドウ糖は肝臓と筋肉にグリコーゲンとして貯蔵され、さらに余剰のブドウ糖は脂肪細胞(特に内臓脂肪)に運ばれ、中性脂肪として蓄えられます。糖質の摂取過多がメタボリックシンドロームにつながるのはこのためです。
通常、食後約2時間で血糖値は低下し、空腹時の状態に戻ります。食後高血糖とは、インスリンが何らかの原因で効かず、血糖値が140mg/dL以上に上昇することです。食後高血糖や極端な血糖値の上下動は、血管を傷つけ、心臓病や脳梗塞などのリスクを高めます。
さらに、食後高血糖により生じる酸化ストレスは、がんの発症に関わっています。また、食後高血糖は糖尿病の初期にみられ、放っておくと空腹時血糖値も高い状況が続く糖尿病へと進行していくのです。
日本人は、約2000万人、6人に1人が血糖異常であると言われています。特に、東アジア人は欧米人に比べ、インスリンを分泌する力が弱い人種です。糖質を抑えることで、血糖値を低く抑えるのが特に日本人で大切なのはそのためです。
血糖値を上げないためには、食べる順番も重要。最初に脂質とたんぱく質、最後に炭水化物を取ると血糖値の上昇を抑えられます。ご飯も単品ではなく、魚や肉などと一緒に食べましょう。
100gの糖質を単独で摂取した時に比べ、同量の糖質を「たんぱく質と一緒に摂取したとき」の方が、さらに「たんぱく質と脂質と一緒に摂取したとき」の方が、血糖値が上がりにくくなります。ご飯だけよりも卵かけご飯、卵かけご飯よりチャーハンの方が血糖値は上がりにくいのです。
栄養バランス、カロリー制限神話を疑え
食事は栄養バランスが大切、と聞いたことはありませんか。厚生労働省の『日本人の食事摂取基準(15年版)』では、三大栄養素の構成比率を、たんぱく質13~20%、脂質20~30%、炭水化物50~65%と定めています。しかし、この数値にそもそも科学的根拠はありません。
カロリー制限食に関しても同様です。肥満症の人が治療目的で医師のもと安全性を確保しながら行うのであればその意義を否定しませんが、一般の人にはお勧めできません。
13年に米国糖尿病学会(ADA)で報告された「Look Ahead研究」では、10年間、腹八分目のカロリー制限を続けた結果、体重は減り、HbA1c(ヘモグロビン・エイワンシー:1~2ヵ月の血糖の平均値を示す数値)も低下しましたが、心臓病のリスクは全く減っていませんでした(*2)。逆にカロリー制限により、大腿骨近位部の骨密度は減少してしまっていたのです(*3)。
ゆるやかな糖質制限を目指す理由
ロカボでは糖質の摂取量に下限(1食20g、1日70g)を設けていますが、それには理由があります。
細胞はブドウ糖と脂肪酸をエネルギー源にできるものの、赤血球はブドウ糖のみをエネルギー源とします。また、脳には血液脳関門という障壁があり、脂肪酸が入れません。脳と赤血球が使うブドウ糖の量は1日約130g~150gです。一方、たんぱく質や脂質の摂取により、肝臓は150gのブドウ糖を生成できるので、理論的には、糖質を口から摂取する必要はありません。
ただし、糖質の摂取量を50g以下に抑えると、肝臓は脂肪酸からケトン体という物質を生成します。ブドウ糖が枯渇すると、ケトン体は脳のエネルギー源となります。そのため、糖質摂取量が少ない際にブドウ糖を利用するのは赤血球だけとなり、脳を含め、赤血球以外の細胞はブドウ糖の利用を避けることができるのです。
しかし、ケトン体産生食により血管内皮細胞に障害を起こす可能性(*4)や、ケトアシドーシスという危険な状態を引き起こす可能性もあります(*5)。そのため、現時点では安全性は担保されていないと考えられ、私はケトン体の生成を避けるべく、糖質摂取量の下限を設けています。
今年、米国糖尿病学会の機関誌『Diabetes Care』に、血糖降下作用を持つ「SGLT2阻害薬」の投与により、体内で増加したケトン体が心臓や腎臓でエネルギー源として利用された結果、心不全、心血管死亡や腎臓病を防いだ可能性があるという2つの報告が掲載されました(*6)。
これから、ケトン体が生体内に及ぼす医学的な影響についての研究がさらに進展することになるでしょう。その結果を待ってから、改めてケトン体産生食の意義、安全性を判断したいと思っています。
一方、野菜や乳製品などにも糖質が含まれています。厳密に糖質をカットするとビタミン不足になる恐れがあり、サプリメントが必要になります。さらに、食べられる食品が極めて限られてしまうことになり、食事の楽しみを奪う可能性が高くなります。これらが極端な糖質制限食の最大の問題点だと言えるでしょう。
なぜ糖質制限は批判されてきたのか
1970年代に糖質制限を世界で初めて実践したのは、アメリカ人医師のリチャード・K.バーンスタインです。同時期に、アメリカ人医師のロバート・アトキンスも、肥満の治療食として糖質制限を導入し、『ダイエット・レボリューション』という書籍を出版しました。
しかし当時、脂質の摂取量と動脈硬化の発生頻度が比例関係にあるという研究データが報告されており(*7)、糖質制限食は批判されました。
時を経て07年3月、米国医師会雑誌『JAMA』に、BMI値(Body Mass Index:日本肥満学会ではBMI25以上を肥満と定義(*8))27を超えるアメリカ人女性311人を対象に行われた4つの食事法の比較試験(ATOZ試験)において、糖質制限食が最も減量に成果があったとする研究論文が掲載されました(*9)。
08年には、糖質制限食の検証試験(ダイレクト試験)の結果が臨床医学雑誌『The New England Journal of Medicine』に報告されました(*10)。
BMI値27を超える322人のイスラエル人を対象に行われた減量法の実験において、体重減少に最も一番効果があったのが「C.カロリー、脂質、たんぱく質を気にせず摂取。糖質のみ上限120g」、続いて「B.脂質をしっかり摂取するカロリー制限食」、最も効果がなかったのが「A.脂質を控えたカロリー制限食」でした。また、最も血糖中の中性脂肪、HbA1cを低下させ、善玉コレステロールを増やしたのもCでした。
私たちも、200人の日本人にロカボを実践してもらい、体重と血糖の改善度合いを体格別に見ました。すると体格にかかわらず、ロカボ食によって血糖が改善。肥満度の高いグループは大幅に体重が減り、肥満度が中程度のグループでも体重は減り、普通体形では変化なし、低体重のグループでは体重が増えました。ロカボは全ての人を理想的なプロポーションにする食事法であることが判明しました。
私自身も、カロリー制限でダイエットを試みた経験がありますが失敗しました。その後、糖質制限を実践して成功。米国糖尿病学会では08年から糖質制限食を糖尿病の正規の治療法として取り入れています。そこで私も糖尿病の患者さんにもロカボを勧めたところ「これなら続けられる」と喜んでくれました。
私たちは、おいしく楽しく食べて、健康になれる世界を実現し、広めていくことを目的に、一般社団法人食・楽・健康協会を設立しました。ロカボを実践しやすいロカボフーズや、ロカボメニューのあるレストランなどの最新情報を提供しています(https://locabo.net/dictionary/)。
手軽に誰でも実践できるロカボでおいしく健康な毎日を実現しましょう。
(*1)Obes Rev 2012,13,1048-1066
(*2)N Engl J Med 2013,369,145-154
(*3)Diabetes Care 2014,37,2822-2829
(*4)Br J Nutr 2013,110,969-970
(*5)N Engl J Med 2006,354,97-98
(*6)Diabetes Care 2016,39,1108-1114、Diabetes Care 2016,39,1115-1122
(*7)J Mt Sinai Hosp NY 1953,20,118-139
(*8)BMI=体格を表す指数。算出方法は、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
(*9)JAMA 2007,297,969-977
(*10)N Engl Med 2008,359,229-241
山田悟(やまだ・さとる)/北里大学北里研究所病院糖尿病センター内分泌・代謝内科センター長。一般社団法人 食・楽・健康協会理事長。
(取材・構成/西田佐保子)
[DIAMOND男の健康]
Posted by nob : 2017年01月16日 15:43
がんや病気とは一緒に生きていく時代、、、まずはすべてを受け容れてさてそれからというスタンスで。。。
■全身がんの樹木希林、元気なときの姿は「あれは瞬間芸」
【樹木希林、がんを語る】
鹿児島県にあるクリニック『UMSオンコロジークリニック』で最新がん治療「四次元ピンポイント照射」により、全身がんの治療をした女優の樹木希林(73才)。そんな樹木に本誌・女性セブンは幾度かにわたって「がんと生きる」ことについて話を聞きたいと
鹿児島県にあるクリニック『UMSオンコロジークリニック』で最新がん治療「四次元ピンポイント照射」により、全身がんの治療をした女優の樹木希林(73 才)。そんな樹木に本誌・女性セブンは幾度かにわたって「がんと生きる」ことについて話を聞きたいと取材依頼をしてきた。毎回固辞されたが、このたび「なんだかあまりにも電話が来ないから、こっちからかけちゃったわよ」と電話が来た。
「ずっと死ぬ死ぬ詐欺をやっている」と言う樹木は、全身がんでありながら、2016年も映画『海よりもまだ深く』に出演し、カンヌ国際映画祭にも出席した。娘婿の本木雅弘(51才)が主演した映画『永い言い訳』の完成披露試写会にも応援に駆けつけ、正月に公開する映画『人生フルーツ』でもナレーションを担当するなど、相変わらず私たちに元気な姿を見せてくれている。
2016年11月、樹木は『UMS』開業10周年のパーティーに出席した時、ついでに胃や腸の検査をしたというが、もしやがんが消えていたのではないか?
「いやいや、大丈夫じゃないよ。あれは瞬間芸だもん(笑い)。だってあなた、舞台挨拶に行ってさ、『いやぁ、もう。ほんとに大変なんですけど来ました』って言うのなら、行かないほうがいいじゃない。人と会うとき、こうしてしゃべってるときだけ元気で、あとはぐて~んとしてるんだから、瞬間芸なのよ(笑い)。こうやってしゃべってると、おかしいね(笑い)。
でもまあ、大丈夫じゃないけど、だいたい、これ(がん)をやっつけようとかって思わないのよ。『がんと真剣に向き合って』とかも思わない。こんないい加減な感覚で生きてるから、私がお話できることはないんですよ。
まして責任がある命のことなんかに、私がそんな、あなた。私だって明日をもしれない身なんですから、無責任なことは言えないんですよ」
ここまで話してくれたのだ。記者は改めて会って話を聞きたいと切り出した。しかし…。
「今日は、養老院に入ってる人のところに行くの。その人はお金がなくて、散髪できないから、私がはさみと櫛とコンビニの袋を持って行って、毛を切ってあげるのよ。だから、もう、すぐ出るのよ。
もう、自分も面白く生きてるからさ、私は。『女性セブン』の意向に沿えないのよ。沿えないっていうか、沿う気がないんだね。まあ、だいたい何でもそうだけどさ、だから、自分の本も書けないのよ。どうせまあ、考えが変わるんだろうなと思うから、自分自身に対してもね。
だから、そのときの話っていうだけで、一過性のものっていうふうに、世の中に出ているものはだいたい思ってるのね。もう、そこにいちいちかかわっていくのは、くたびれるなっていうふうに思うの。
そういうわけだから私のことは放っておいて。もう、佐藤愛子さんとか、黒柳徹子さんとか、パワーがあってさ、元気な人から話を聞いてちょうだい」
それでも誰しもが「がんと生きる」可能性のある時代に、闘病しながらも元気に働く樹木の話をまだ聞いていたい。
そこで、「死ぬときぐらい好きにさせてよ」とのキャッチコピーが話題になった樹木の広告について聞いた。それは2016年1月5日、全国紙に掲載された宝島社の企業広告。そこには樹木の写真とともに、こんな文章が綴られた。
《人は必ず死ぬというのに。長生きを叶える技術ばかりが進化して、なんとまあ死ににくい時代になったことでしょう。死を疎うとむことなく、死を焦ることもなく。ひとつひとつの欲を手放して、身じまいをしていきたいと思うのです。人は死ねば宇宙の塵芥。せめて美しく輝く塵になりたい。それが私の最後の欲なのです》
「あのコピーは、『私は違うよ』と言ったんです。だって私は死ぬときじゃなくって、普段から好きにしてるから。でもそのあとの文言は、まあそんなもんだったのでオッケーしたけど。でもね、自分勝手に生きてるとみんな長いんです。これからはがんや病気とは一緒に生きていく時代ですよ」
※女性セブン2017年1月5・12日号
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2017年01月05日 17:04
そのとおり!!!Vol.53/「肉体的・精神的に私たちが行うそのほかのあらゆる選択が、総合的な健康の増進に役立つ」
■健康な食事も「ストレス」で台無しに? 新たな研究結果
あなたは、あなたが食べたものでできている――ここ数年、この栄養学の鉄則に反する指摘が幾つかなされている。
例えば、「何を」食べるかだけでなく、いつ食べるか、何を飲むか、日々どのような習慣を実践しているかも重要だという指摘などだ。
こうしたなか、分子精神医学の学術誌「モレキュラー・サイカイアトリー(Molecular Psychiatry)」に発表された新たな研究報告では、ストレスによって健康的な食の選択に悪影響が及ぶ可能性があるという所見が示された。
ストレスが健康な食事を阻害する
オハイオ州立大学が実施したこの研究で、研究チームは乳がんを克服した女性を含む中年女性グループに、2種類の朝食を食べてもらった。
いずれの朝食にも卵、七面鳥のソーセージ、ビスケットとグレイビーが含まれる(そもそも最も健康的な部類に入る朝食ではないが)。片方の朝食(A)はパームオイルを使用して飽和脂肪が多く、もう片方の朝食(B)はヒマワリ油を使用して不飽和脂肪が多かった。
女性たちは2つの異なる状況の中でどちらか一方の朝食を食べ、研究所で血液検査を行い、自分たちの精神衛生に影響を及ぼし得る出来事について報告した。ストレスフルな出来事には、たとえば子どもが床にこぼした絵具の掃除や、認知症の親の介護などの自然発生的なストレス要因が含まれる。
その結果、不飽和脂肪が多い朝食(B)を食べた女性の方が、飽和脂肪が多い朝食(A)を食べた女性よりも4つの異なる炎症マーカーの数値が良かった。だが検査前日にストレスフルな出来事があったと報告した参加者には、より健康的な油を摂取した(B)効果はみられなかった。
研究者たちは報告書で「ストレス要因がヒマワリ油を使った食事(B)に対する反応が高まり、飽和脂肪を含む食事(A)に対する反応により近くなった」と指摘した。
ストレス要因がなぜ、食べ物に対する私たちの身体の反応に影響を及ぼすのかは興味深い問題だ。
ひとつ考えられるのは、ストレスによる炎症反応の高まりが、不健康な脂肪の心理的効果を”真似て”、より健康的な油の効果を弱める可能性だ(特定の脂肪や加工食品、過剰な糖分は体内の炎症反応を上昇させる)。
しかしストレスを感じている上に、さらに不健康な食事をとった女性については、炎症マーカーのさらなる上昇は確認されなかった。研究者たちはこの理由について、これらのマーカーに何らかの天井効果がある可能性があると考えている。
だが、だからといってストレスを感じた時に何を食べてもいいということにはならない。これはむしろ私たちが、自分のストレスレベルを深刻に受け止め、ストレス軽減に役立つと分かっていることをすべきだということを示している。慢性的なストレスも不健康な食の選択も、蓄積されていくと思われるからだ。
研究の1つの限界は、いずれの種類の食事も不健康だったということだ。実際にはこれは、意図的に現実の欧米の食事を真似たものだった。だが真に健康的な食事(たとえば野菜や魚)の場合はどうなるのかが分かりにくい。
ストレスフルな出来事が、単に油を変えただけの食事ではなく、真に健康的な食事の効果をいかに弱めるのか(あるいは弱めないのか)の解明が、次のステップになるだろう。またどのような種類のストレスが小さな”健康的な選択を台無しにし得るかということも不明瞭なままだ。
これらの問題が解明されるまでは、健康的な食事をして心の健康にも気を配るのが最善の策だろう。健康のためには、食の選択は確かに重要だが、私たちが日々行っているそのほかのあらゆることも同様に重要だ。
「あなたは、あなたが食べるものでできている」だけではなく、肉体的・精神的に私たちが行うそのほかのあらゆる選択が、総合的な健康の増進に役立つのだ。
Alice G. Walton
[フォーブス ジャパン]
Posted by nob : 2017年01月01日 15:15
治療をしないという、生き方(逝き方)の一つの選択。。。
■放置してもなかなか進まない高齢者のがん 安らかに死ねる
よく「高齢者はがんの進行が遅い」と耳にするが、実際にはどうなのだろう。横浜悠愛クリニック理事長の志賀貢医師の話。
「進行が遅いのは間違いない。胃がんから肝臓に転移するとか、肺に転移するということが少なくなります。患者が若いと別の部位に飛び移る力が強いのに、年齢が高くなるとその力が衰える」
がんに伴う疼痛も、高齢になると薄らいでいくという。在宅医療を実践する長尾クリニック院長・長尾和宏氏がいう。
「若い末期がん患者は痛みが強いため、ほぼ全員がモルヒネなどの医療用麻薬を要します。
しかし80~90代以上の超高齢者になると、3~4割は医療用麻薬を使わなくても在宅で看取ることができます。高齢になるほどに痛みに対して鈍感になっていくのではないでしょうか」
家族の負担も少なくなると長尾医師が続ける。
「がん死は壮絶だという印象があるかもしれませんが、超高齢者になると、平穏に死を迎えられる。最後まで自宅で食事をして、老衰のように穏やかに亡くなることができるのが高齢者のがんなのです」
前出の志賀医師が振り返る。
「ある80代半ばの患者さんが胃がんであることが分かりました。その方は達観しており、自然に任せると決め、一切治療を受けませんでした。
3年間元気に暮らしたのち、最後は胸に転移しましたが、家族に見守られて苦しむことなく眠るように亡くなりました。このように、放置してもなかなか進まないのが高齢者のがんなのです」
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2016年12月02日 11:47
私も入浴後就寝まではできる限りモニター画面を見ないように心がけています。。。
■スマホの「ブルーライト」は何がマズイのか
害するのは「目」じゃなくて「健康」だ
小木曽 健
グリー 安心安全チームマネジャー
「スマホの「ブルーライト」は何がマズイのか 害するのは「目」じゃなくて「健康」だ | インターネット、正しく怖がろう!
パソコンやスマホの「ブルーライト」は何がマズイのか
突然ですが、読者のみなさんに質問です。
「ブルーライトは好きでしょうか」
「目に悪いものだから嫌いに決まっている。当たり前のことを聞くな」と怒ることでしょう。では「今度一緒に、ブルーライトをたっぷり浴びに行こう」と誘われたとしたらどう思いますか。「身体に悪いから浴びたくないよ」と思うかもしれません。
でも、天気がいい日の青空の美しいスカイブルーは、ブルーライトの「ブルー」と同じなのです。つまり日光浴をする、ということはブルーライトをたっぷり浴びる、ということ。そもそも、太陽から届く光の中でも青は特に大気中で拡散しやすいため、空は青いのです。
ここで疑問が浮かび上がります。ブルーライトは本当に目に悪いものなのでしょうか。
ブルーライトは目に悪い?
みなさん、どこかしらで「スマホやパソコンのモニターから出ているブルーライトは目に悪い」という話を聞いたことがあると思います。
でも、実は一般的なスマホ・パソコンの使用時間で、ブルーライトが許容範囲を超えるダメージを目に与えるかというと……。筆者の知る限り客観的・長期的な検証データは、今のところありません。
もちろん、パソコンやスマホで目を酷使するのは良くないですし、その結果、目の疲れや老化、場合によっては目にダメージが発生する可能性があるのは間違いありません。ですが、その原因を考えた場合、目の焦点を長い時間にわたって固定化することによる悪影響のほうが大きいのです。少なくとも、ブルーライトだけのせいにするのは、無理がありそうです。
一般的なスマホ・パソコンの使用時間なら、ブルーライトだけのせいで目が損傷する、という決定的なデータはありません。それなのに……世間には、何がなんでもブルーライトが悪いといわんばかりの情報があふれており、ちょっと違和感を持ってしまいます。
しかもブルーライトの問題点について書かれているウェブページを見ると、なぜか極端な条件下での検証データを多用していたり、なぜかブルーライト対策の商品・サプリの広告が貼られていたりします。「ブルーライト悪玉説」で誰かが得をするのだろうな、と考えてしまいます。
もちろん別にブルーライトに義理立てするつもりはないし、肩を持つ気もありません。もし誰かが客観的で科学的で長期的な検証を行ない、ブルーライトの「ワル」判定がされれば、受け入れます。回りくどくなってしまいましたが、ブルーライトが健康を害するかどうかについては、科学的な検証の余地があるのです。
「目」じゃなくて「健康」を害する
しかし、少なくとも寝る前にスマホやパソコンのブルーライトを見ることが「健康」を害するというのは、ほぼスジの通った話です。「目」ではなくて、「健康」を害するのです。
青空のもとで日光浴をしたら、誰だって頭が冴えます。同じように「寝る前のスマホ」も、まぶしいスマホ画面が脳を活性化させます。そんな状態で眠りにつけば、睡眠の質が下がるわけです。つまり、「ブルーライトが目に悪い」のではなくて、「寝る前のブルーライトは、睡眠の質を下げて健康に悪い」ということなのです。
筆者はこれを逆手にとって、朝は寝床でスマホを手に取り、アプリを立ち上げ、ブルーライトをガンガンに浴び、頭をスッキリさせてから起きているくらいです。
家庭のスマホルールをどう作るべきか
この「寝る前のブルーライト」は、子育てや家庭のルール作りとも関係があります。
家庭のスマホルールでよくあるのが、「我が家では〇時以降、スマホ禁止」というものです。このルールは「子どもがスマホで夜更かし → 翌朝に寝坊 → 朝ごはんも食べずに学校へダッシュ → 母親が激怒」という手続きを踏んで作られることが多いと思いますが、残念ながら効果をあげずに失敗するケースが多いのです。
たとえばある家庭で、「夜9時以降スマホ禁止」というルールが作られたとします。すると、かなりの確率で、こんなことが起きます。ルール初日、この家庭のお子さんは、夜9時ギリギリまで大慌てでLINEをやりまくっています。バタバタです。そして夜9時になった瞬間、「あ~間に合った、疲れたぁ!」って言いながらマンガを読み始めます。結局、寝る時間が早まることはないのです。
でも、これは仕方がないのです。そもそもルールが必要になるのは、何らかの弊害が起きているときです。その弊害を解決するために作られるのがルールですが、「夜9時以降スマホ禁止」には弊害のことが触れられていないのです。ルール作りには、「弊害の見極め」がものすごく重要です。そして多くの家庭で「弊害の見極め」でミスをしているのです。
スマホを夜遅くまで見ていることの「弊害」は何か。弊害はズバリ、「睡眠の質を悪化させて健康を害すること」です。
極端な話、夜更かしだろうが、朝食抜きだろうが、健康であればいいのです。しかし、そんな人は例外的な存在ですから、ほとんどの人にとって、スマホを夜遅くまで見ていることの弊害は、「寝不足によって健康を害すること」です。だからこの弊害に直結したルールを作らないと、問題は解決しません。
先ほどの「夜9時ルール」は睡眠時間の確保にまったくつながっていないため、失敗するのも仕方がないのです。では、どうすればいいのか。
弊害:寝不足で健康を害する状態
対策:質の良い睡眠を△時間以上、摂らなきゃダメというルール
になります。これに「ルールを〇回破ったら、スマホは解約、没収」というペナルティでも加えておけば完璧です。
「やり方は任せるから、ちゃんと睡眠時間を確保するんだよ。もしルールを守れなかったら……わかっているよね」
こんな感じで、シンプルなルールを作ればいいのです。あまり細かい条件は付けないほうがいいです。なにしろ子どもは、ルールに物言いつけるのが仕事みたいなものですから、ルールが細かければ、「このルールの、この部分のせいで失敗した」と言い訳できる逃げ道を作ってしまいます。だから、なるべくシンプルにしましょう。
「やり方は任せるから」もポイントです。裁量権を与えられているんですから、失敗しても自分のせいです。言い訳できません。誰だって、裁量権を与えられれば「挑戦してみるか」という気になります。
軸はブレずに「弊害は何?」
ここでブルーライトの話に戻ります。質の良い睡眠のためにはどうすればいいのか。
「寝る前のブルーライトは質の良い睡眠を害する」ということを説明し、「寝る〇時間前にはスマホを見ない」「〇時以降はベッドにスマホをもちこまない」といった約束をしましょう。この約束を守った場合に限って質の良い睡眠と認めればいいのです。
うまくいかなかったら、なぜ失敗したのかを親子で話し合って検証し、改良していけばいいわけです。ただし、「寝不足で健康を害する状態」という弊害を取り除く、という軸を変えてはいけません。「ブルーライトは目に悪い(=スマホは目に悪い)からスマホの使用時間を2時間に限定する」といった方向にブレてしまいがちだと思いますが、それだと弊害(寝不足)を取り除くという本来の目的から離れてしまうのです。
この連載のタイトルは、「インターネットを正しく怖がろう」ですが、ブルーライトも正しく怖がるようにしてください。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2016年11月19日 10:14
私もグルテンフリーで乾燥肌やアレルギーの解消など体調が劇的に改善、、、ただ選べる限りは、出された際には美味しくいただきます。。。
■「パンばかり食べる人」がひそかに陥る不調
小麦の多い食生活は簡単なコツで変えられる
フォーブス弥生
一般社団法人グルテンフリーライフ協会 代表理事
ビジネスマンにとって、コンディションは大きな課題です。 しかし、どんなに睡眠や食べ物に気を使っても、頭痛、腹痛、疲労が抜けない人は多いもの。そんな人は、思ってもみない食材が悪さをしているかもしれません。その食べ物こそが、「パン」。パンをつくる小麦の成分が、体に大きな負担となっている可能性があります。
ジョコビッチの食事法で一躍有名になり、世界中の一流セレブが実践している小麦抜きの食事法、「グルテンフリー」。夫のグルテン過敏症を機にこの食事法を8年前から実践している第一人者であり、『長生きしたけりゃパンは食べるな』の著者でもあるフォーブス弥生氏が、日本のビジネスパーソンに合わせた現実的な食事法を提案します。
頭が重い、肩こり、疲れがとれない、集中できない。メタボ、糖尿病、肌荒れ、不眠、生理不順、ボケ、食事のあとの下痢――。
医者から「異常はありません。ストレスはためないでくださいね」と言われ、対処法も見当たらず、あきらめてしまった持病はありませんか?
実は、あなたの不調の原因は、もしかしたら「毎日のパン」にあるかもしれないのです。
小麦の成分「グルテン」が原因かも
近年、小麦に含まれるたんぱく質「グルテン」が、脳に炎症を起こし、腸に小さな穴を開けると注目されています。米国でベストセラーになった神経科医デイビッド・パールマター氏などがその著書の中で指摘しています(邦訳『「いつものパン」があなたを殺す』)。世界屈指のテニスプレーヤー、ジョコビッチが実践し、話題になった小麦抜き食事法「グルテンフリー」という言葉を聞いた人もいるかもしれません。
ケーキやラーメン、パスタ、うどん、クッキー、菓子パン……。小麦粉の食品は私たちの生活に深く入り込んでいます。知らず知らずに、グルテンを大量に摂取しているのが現代人の食生活です。それだけではありません。
●グラノーラは塩分が控えめだから、朝食にピッタリ!
●全粒粉のパンはカラダにいい
●パスタの食物繊維で美容効果が期待!
そんな間違った情報や思い込みが一般に広がっています。では、いったいなぜ、これほどの症状が現れてしまうのでしょうか。
小麦の主成分はブドウ糖ですが、グリアジンとグルテニンという2つのたんぱく質も含みます。グリアジンとグルテニンは水を含むと、ネバネバとしたグルテンとなります。この「グルテン」が、腸の粘膜を傷つけ、リーキーガット症候群と呼ばれる症状を生みだすといわれています。
リーキーガット症候群とは、腸管壁における過度の浸透状態のことをいいます。腸壁の粘膜に細かな損傷があるため、腸内にあるべき物質が分子レベルで漏れだしてしまう状態のことです。
こうなると、腸は十分に働けず、消化と吸収の作業が妨げられてしまいます。グルテンの消化も進まなくなります。
グルテン不耐症が見つかりにくいのはなぜ?
「もしかしたら、私もグルテンが原因で不調になっているのかもしれない」
ここまで読み進めてきて、そう感じた方も多いかもしれません。しかし現状、症状とパンの害を結びつける診断は、難しいことが多いのです。
現在、米国では、グルテンに耐性がない患者さんは、20人中に1人と言われています。しかし、実際にそれと診断されている人はわずか。ほとんどの人が、心身の不調に悩みながらも、何が原因かもわからず、日常を過ごしている可能性があります。
なぜでしょうか。理由は、遅発型のアレルギーだからです。アレルギーには、摂取後わずか数分のうちに症状が現れる「即時型」と、時間が経ってから症状が現れる「遅発型」があります。
人によっては、少量では発症しない場合があります。摂取後、数日が経って、症状が現れることさえあります。こうなってしまうと、何が原因で症状が起こっているのか、本人も医師もわかりにくいという事態が生じます。
しかし、小麦を一切食べずに、外食や食事を楽しむことなどできるのでしょうか。
「さすがに無理だ」「現実的じゃないんじゃないか」
私たちグルテンフリーライフ協会を訪れる人の多くが、そうおっしゃいます。しかし、難しいことはまったくありません。
なぜ、私がそこまで断言できるのか。それは、私自身がもともと、「大のパン好き」だったからです。
私の夫は、グルテン不耐症、つまり小麦を口にしただけで体調を崩す体質です。私は夫との生活をきっかけに、小麦抜きの生活を始めました。しかし、いくら夫婦の仲とはいえ、自分がパンやパスタをいっさい食べない生活をするなど想像もできません。当初はそう考えていました。
しかし、試しに行った14日間の小麦抜き生活のあと、私の考えは、180度、変わりました。あんなに大好きだったパンを、「食べたい」といっさい思わなくなったのです。
前述の神経科医デイビッド・パールマター氏は、小麦の成分、グルテンには、依存性があると指摘しています。
「小麦をやめる!」と大きな決断をするのではなく、1食1食、小麦を食べなくてすむメニューを考えていくようにすることです。
とにかく14日間、小麦を口にしない食事を積み重ねましょう。そして14日後に、始める前と、今の体調や心の状態を観察してみてください。
忙しい人は、これだけでOK!実践のコツ
「グルテンフリー」健康法は、いくつかの翻訳書が出版されており、ベストセラーにもなっていますが、一方で問題もあります。日本と米国とでは、スーパーの品ぞろえから食への認識までまったく異なるため、実施に際してはなかなか参考にしづらいことが多いのです。
そこで、日本の食卓に合った〈ズボラな人向け〉食事のコツを提案します。それは、「和食中心」の食事にする、これだけです。
いつも朝はパンやシリアルで手軽に済ませていた人は、朝から和食の準備をするのは大変に感じるでしょう。しかし、難しく考えないでください。まずは、朝食のパンやシリアルをやめてみてください。
「和食は塩分が多いので、高血圧になりやすいのではないですか?」
よくそう聞かれます。たびたびやり玉に挙げられるのは、味噌汁です。日本の伝統食でありながら、「味噌汁は血圧に悪いから、あまり飲まないようにしている」という人も多いでしょう。
しかし、最近の研究によって「味噌汁は血圧に影響しない」「味噌汁を1日1杯程度飲む食生活は、血管年齢を10歳ほど若返らせること」が確認されています(出典:共立女子大学上原誉志夫教授による「習慣的味噌汁摂取が血管年齢に与える 影響」、第36回日本高血圧学会総会)
和食以外でも、グルテンフリー生活はもちろん可能性です。そのコツを以下にご紹介します。
① イタリアで話題の「ゼンパスタ」で健康に!
グルテンフリー生活をする私たちも、パスタやラーメンを食べたくなります。そこでグルテンフリーのパスタやラーメンを常備しています。
『長生きしたけりゃパンは食べるな』(書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします)
グルテンフリーの食材は日本ではあまり流通していませんが、ネットショップなどから簡単に入手できます。
グルテンフリーの麺は、主に米粉やトウモロコシ粉を使って作られています。最近は、玄米粉を使ったパスタやペンネも出てきました。本来のものよりも白っぽいものが多いですが、味は一昔前より格段においしくなっています。
パスタの本場であるイタリアでも、小麦抜き生活を実践する人も増えているようです。その影響で、「ゼンパスタ」という麺が大ブームになっています。原料はなんと、「乾燥しらたき」。試してみてください。
② 「米粉パンケーキ」を試してみる
私はもともとパン好きです。今、食べないのは、「小麦粉」でつくったパンだけです。米粉のパンは食べます。昨日も、米粉の食パンでサンドイッチを作りました。最近は、米粉のパンを町のパン屋さんでもよく見かけるようになりました。インターネットを使って購入することもできます。
ただ、小麦粉も扱っているパン屋の場合、米粉だけで焼いたパンであっても、小麦が混入してしまう心配があります。
私は、日本ハムの「米粉パン」をインターネットで購入しています。食物アレルギー対応の専用工場でつくられている米粉のパンです。小麦粉より少々高価ですが、グルテンをいっさい含まないため、安心して食べられます。
大切なのは、諦めないこと
グルテンフリーの効果を実感するためには、まずは14日間続けてみて、その後に小麦食品を一口だけ食べてみるのが、体調の変化を知る、わかりやすい方法です。
「14日目を待たずして小麦食品を食べると、リセットしてしまうのでは?」
そんな心配もいりません。もしも食べてしまったのならば、体調にどんな変化が現れるのか、観察してみましょう。そして、再び始めればよいのです。
グルテンをどの程度許容するのかも、ご自身で決めていきましょう。
ある人は、友人と食事に出かけた時だけは、ほんの少し口にするのは「よし」としているといいます。友人が「おいしいよ」とすすめてくれたものを、「小麦粉は食べられないから」と断り、その場の雰囲気を壊したくないためです。こうした考え方は、とても素敵だと思います。
まずは朝食のパンだけやめてみて、慣れてきたところで、昼、夜と小麦をやめる回数を増やす方法もあります。
「こうしなければならない」という決まりはありません。ご自身が楽しく続けていける方法をどうぞ見つけていってください。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2016年11月16日 14:46
また旅立つ君へVol.117/孤独は自由への扉
■心が強い人は「孤独は妄想」と知っている
簡単な練習で、「独り=至福の時間」になる
草薙龍瞬
僧侶
「独りの時間」は、人生には案外多いものです。仕事の合間や、プライベートなひととき。特にソーシャルメディア全盛の現代では、「つながり」を求めるあまり、逆に疎外感やストレスを感じている人も増えています。
仕事を失ったり、人と別れたりして、不意に孤独におそわれることもあります。
「これからどうなるんだろう?」という将来・老後への不安が、ふとよぎることも――「孤独」が胸に重くのしかかってくるのは、こんなときです。
一般にマイナスのイメージで語られることの多い「孤独」――しかし仏教では、「孤独」は恐れるものではない。孤独は「使いみち次第」で、幸福な時間に変えることができる、と考えます。
独立派の出家僧・草薙龍瞬氏(近著に『これも修行のうち。』がある)が、孤独を「人生の最強の味方」に変える方法を語ります。
「あなた、孤独ですね」といわれて、気持ちいい人はいないですよね。むしろ、ショックを受ける人が大半だと思います。
「孤独」は「人に好かれていない」証拠。人づきあいの希薄な自分には「価値がない」。何より「他人にそう思われることがイヤだ」――人が孤独を恐れることには、そんな心理が隠れている気がします。
はて、しかし? 一般常識にとらわれない自由人・ブッダなら、どう考えるでしょうか。きっと明るくこう答えるはずです――「ぜんぜん良いではありませんか」。
その真意は、「よいか悪いかは“孤独の使い方”による」ということ。今回は、孤独の「合理的な活かし方」を考えてみましょう。
孤独を「上手に使う」方法がある
そもそもなぜ「孤独」には、つらくて寂しいイメージがあるのでしょうか?
・話を聞いてくれる友だちがいない。思いを、ひとりで噛みしめないといけない――というつらさ。
・友だちの多い「ソーシャルな」人が大勢いる。リアルな人づきあいも、ネット上のつながりも、「こんなに頑張っている!」(ように見える)人たち。でも私は……というつらさ。
さらには、
・自分には、恋人も、結婚相手もいない……ということは、自分には魅力がないということ?(と考えてしまう)。
・このまま独りで年を取っていくのかと思うと、不安・寂しさが募ってくる。
といった思いもあります。こうした思いが、「孤独はよくないもの」というマイナスのイメージ(判断)を作り出しているように思えます。
しかし、「孤独」とは、本当につらいものなのでしょうか。仏教では、①ありのままの「事実」と、②それ以外の「妄想」とを、分けて理解します。
「つらい」と感じるのはなぜか
「孤独」と呼ばれる状態を、まずは「事実」として理解してみましょう。たとえば、
・世の中には、孤独に生きている生き物はたくさんいる(むしろそっちのほうが多数かもしれない)のが「事実」――なのに、自分は孤独をつらく感じている。
・そもそも、ひとは、脳も体も違う。個体としては、独りであることが、普遍的な「事実」――なのに、私は孤独を苦しく感じている。
・本来、ネット上のお付き合いなんて、なくても生きていけた(問題なかった)というのが「事実」――なのに、今はどっぷり浸かって、期待通りのリアクションが返ってこないことへのストレスや、振り向いてもらえない寂しさを感じている。
「事実」だけを見てみたら、孤独というのは、案外ふつうの状態です。なのに、「つらい」と感じるのはなぜか――その原因になっているのは「客観的に存在せず、アタマの中にしかない思い」です。つまりそれは、「妄想」だということになります。
つまり、「孤独がつらい」というのは、妄想が生み出す“ちょっとした心の風邪”といっていいかもしれないのです。
「孤独って、妄想なの?」――この発想が、ちょっと違った展開を人生にもたらしてくれます。
【孤独病からの抜け出し方①――とにかく「妄想しない練習」をする】
「孤独は妄想」だとしたら、孤独に悩まなくなるには、「妄想しない練習」が一番効きます。その方法を、いくつか紹介しましょう。
○まずは、「目をつむる」
目を閉じて、アタマの中に浮かんでくる「言葉」や「イメージ」に気づいてください。「目をつむったときに見えるものは、妄想である」と理解します。
「ああ、いま自分は考えているな。何かを追いかけようとしているな」と自覚しましょう。それは「妄想状態」です。
「相手のリアクションが欲しい」「他人の動向が気になる」というのも、「これは妄想」と理解します。「自分って、孤独だな(さみしい)」という思いがふとよぎった時にも、「あ、妄想した」と気づいてください。
できればその上で、深呼吸して「お腹のふくらみ・ちぢみ」を感じとる、歩いているときの「足の裏」を感じとる、目を開いて外の景色・光をよく見つめる――というように、心を向ける先をシフトしてください。
ポイントは「妄想状態に気づいて、体の感覚に意識を向けかえる」ことです。
○孤独こそが“人生の基本”と知る
目をつむったとき、外の世界は見えなくなりますね。仕事も家庭も、社会の動きも、「お付き合いすべき相手」も、その瞬間は、いなくなります。
実は、その「何も見えない(存在しない)」状態こそが、心の基本です。人は、得てして「外の関係」――世間の付き合い・つながり――ばかりに心を奪われがち。しかし、実は「心」――外の世界(関係)とは、別の領域――が、最初に存在するのです。
ひとりでいる自分の心が、基本。
つながり・関わりは、「心」の次にくる“さずかりもの”ということです。
【孤独病からの抜け方②――他人の動向を追いかけない】
「ひとりでいる自分の心」が基本だとすると、周りの人たちの言動や、世間のうわさ話やニュースなど、外の世界・他人の動向は、「おまけ」の部分です。
「おまけ」の部分は、追いかける必要のない「他人事(ひとごと)」であることが多いものです。知ったところで、「へぇ、そうなんだ」「だから何なんだ?」という話がけっこうあります。
「だから何なんだ?」というオマケの部分に振り回されているのは、もったいない話です。
そこで、「基本」と「おまけ」に分けるという発想に立ちましょう。他人の動向は、「自分に必要な情報か、それとも“おまけ”でしかないのか?」と考えてみるのです。
おまけの部分は、時間が空いたとき、ちょっとリラックスしたいときに“時間を決めて”お付き合いする程度のもの。「なくても平気」でいられる自分を、心がけていきたいものです。
つながりは、別の世界にもある
ちなみに、「つながり」だけなら、人間でなくても手に入ります。動物を可愛がる。夜空の星々を見上げる。仮に真夜中に深い森にさまよいこんだとしても、頭上には星々が輝き、木々の緑は呼吸し、大地には無数の命が活動しています。
どこまでも見渡すかぎり命(つながり)の中にある――というのが、仏教が教えてくれる真実です。
孤独は、まったく恐れるものではないのです。
【孤独病からの抜け出し方③――沈黙タイムを保つ】
独りに慣れるために“沈黙タイム”を積極的に作りましょう。
たとえば、仕事帰りや、休日の午後に、ひとりで喫茶店にいって本を読むとか、禅瞑想をするとか。
ほんとは職場でも「沈黙タイム」を作ってみるべきなのです。たとえば、「午後の一時間は、互いに話しかけずに作業に集中する」ことをルールに据えるとか。
ちなみに、古代のインドの修行者たちは「孤独こそ大の親友」という超ポジティブな生き方をしていました。原始仏典に、こんな言葉が残っています――
「三年の間、私が言葉を発したのは、一回だけ。その最後に“無知の闇”――自分の心が見えない状態――を打ち破った」
<「テーラガーター(長老の詩)」より>
極端な話ですが(笑)、それくらい「沈黙=孤独は、心を成長させてくれる」ということです。
【孤独の積極的価値を知る】
孤独だからこそ得られる“積極的な価値”も、たくさんあります。たとえば……
○ムダな反応が減る
独りになることで、ムダな反応は、確実に減ります。心をかき乱すような刺激・情報・他人の目に、いちいち反応しなくてすみます。
これは「心の平穏」という、心にとって何よりも大事な価値――“心の健康”――を、もたらしてくれます。
○大事な物事に集中できる
心が落ち着けば、大切な物事に集中できるようになります。仕事であれ、勉強であれ、趣味であれ、家事であれ、「いっときに、ひとつのことを、集中してやる」ことが、心にとっては、一番の快(すっきりした喜び)なのです。
○ムダなく考えられるようになる
さらに、当面の課題や、将来のゴールを達成するために、自分は何をすればいいか。予定、段取り、交渉、具体的な作業……それらを「正しく(ムダなく)考える」ために、独りの時間は、大切な意味を持ちます。
孤独こそは人生の基本です。そのひとときを、いかに、充実・静寂・集中・クリアな思考などの高い価値に活用するか――そこに目を向けようではないですか。
孤独を人生の味方につけよう
もともと、ブッダの合理的な考え方では、孤独を大事にします。
「犀の一本角のように、ただひとり歩め」
「自らをよりどころとし、ダンマ(真実・方法)をよりどころとして、他の何ものをもよりどころにするな」
つまりは、自分自身の中に「こういう心がけ・心の使い方が大事なんだ」という確かな土台をすえて、そこだけに立って、ひとり毅然と歩んでいけ、というのです。
ひとり歩むというのは、孤立ではありません。むしろ自分にとって本当に大切なつながり・生活・将来を見据えて、それを守ることを第一とする生き方です。
孤独とつながりは、両立できます。孤独――自分自身を軸とすること――が基本であって、その上でいい関係を“さずかって”(育てて)いくのです。
孤独は、孤独としての活かし方がある。孤独だからこその幸せもある。そういう考え方ができれば、孤独は、恐いものではなくなります。
孤独にあっても、つながりの中にいても、自分を肯定できること――それがカギになります。
そのための“心の使い方”を学んでいきましょう。楽しいですよ。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2016年10月28日 11:18
秋バテにご注意を
■秋は体が「老化」する!? 内臓の冷えにご用心
吉岡 名保恵
秋は老化の季節だから気を付けて―ー。そんなドキッとする話をするのは、漢方養生学の専門家、小野満幹彦さん。暑苦しかった夏が終わり、ようやく過ごしやすくなった、と喜んでいる人が多いはず。けれど肌で感じる体感的な心地よさと、体が受ける影響は別のものと考えたほうがいいらしい。
まずポイントとなるのは体温。私たちの体温は、いつも36.5度ぐらいに維持されている。夏の暑さは不快だけれど、無理なく体温をキープできていたので「体にとってはよい季節だったんですよ」と小野満さん。
一方の秋は涼しくなるにつれ、体は体温を保つために頑張って代謝を上げなければいけない。代謝を上げるには酸素を使うので酸化が進み、実はとても老化する季節なのだそうだ。
それに、すがすがしい秋晴れの日は心地よい反面、空気が乾いている。体の中では特に肺が乾燥の影響を受けやすく、咳が出やすいので注意が必要。もちろん肌にとっても乾燥は大敵だ。
日中も温かい食べ物を
「特に注意したいのは、夏のうちに冷房の空間で長い時間を過ごし、肉などをたくさん食べていた人です」。そう小野満さんから指摘され、ギクッとした。冷房の寒さに対応したり、肉を消化したりするには代謝を上げる必要があるので、本来なら体が休息できていたはずの夏にも、体が休まっていない。そのツケが夏バテという形で現れ、秋になった途端、どっと疲れが出て風邪をひきやすくなるという。
また9~10月は気温の変動も大きく、日中は夏のように暑い日もある。汗をかくと毛穴が緩んで冷えが体内に入りやすくなるため、冷たいものを口にしたり、夜間に涼しかったりすると、内臓はいつも以上に冷たくなってしまう。「とにかく温かいものを食べること。日中、暑いと感じる日でも、冷たい飲み物や食べ物は避けるべきです。いまの時期に内臓を冷やしてしまうと、いい状態で冬を迎えられませんよ」(小野満さん)。
体温の面からすると、寒い冬は体にとって過酷な季節。その冬を乗り切るため、秋にしっかり養生して体のコンディションを整えておく必要があるのだという。秋の養生がうまくいかないと、免疫力が下がってウイルスに感染しやすくなるらしい。もちろん風邪もひきやすくなる。
夏に不養生したなら運動
夏に不養生した人も、頑張って養生すれば体の状態を“修復”できる。修復に必要なのは運動だ。夏に食べすぎて蓄えてしまった脂肪など余分なものをそぎ落とし、体をクリーンな状態にする。晩秋の11月ごろ、さまざまな食べ物をおいしく食べて、体に栄養を行き渡らせるようにする準備のひとつでもある。
「実りの秋の恵みを、万全な状態で体内に取り入れることができれば、すべて自分の身になり、パワーになります。パワーとは、体温を36.5度に維持する力のこと。それができれば、寒い冬でも元気に過ごせるんです」(小野満さん)
運動するなら、少し「しんどい」と感じるぐらいのジョギングや速足でのウォーキング、縄跳びなどがお勧め。基礎代謝だけでは間に合わないので、運動をして代謝量を増やし、体温を上げることが秋の養生のポイントになる。
キノコや豆腐、豆乳がいい
秋の始まりは食べすぎず、体を整えることを意識する。お勧めは、キノコや豆類、海藻。豆類は、栄養価が高くて、体に潤いを与えてくれる豆腐や豆乳など大豆製品がいい。
晩秋から冬に向かっていく頃は、食べ物がなんでもおいしく感じられる時期。キノコや果物など秋の味覚を取り入れながら、バランスの良い食事をすることが、冬の乾燥と寒さに耐えられる体を作ることにつながる。秋から冬にかけては栄養を蓄えるため、肉、魚、野菜がしっかり食べられる鍋料理がお勧めだ。
食材は体を温め、潤いをもたらすものを意識して選ぶ。組み合わせるとさらにいい。たとえば、脂の乗ったサンマを焼いて食べるときには、大根おろしと一緒に食べると効果的だ。また、乾燥でダメージを受けやすい肺を潤すには、野菜ではユリ根や白きくらげ、山芋。果物ならミカンや梨、柿がいい。
読書の秋、芸術の秋でもあるけれど、悲しくなるもの、暗い気持ちになるようなことは避けたほうがいいそうだ。冬に向かって日没は早くなり、自然と「気」は下がりがち。小野満さんは「落ち込まないためには、動くこと」と言い、仲間と楽しくバーベキューをする、秋祭りに参加するなど、ワイワイ楽しい時間を過ごすのがよさそうだ。
都会で生活しているなら、休日は秋の自然に親しむといい。フルーツ狩りや酒蔵見学など、実りの秋を実感できる体験をすれば、人間の体は本能的に秋を意識できるようになる。
日本には四季があるため、私たち日本人にはもともと、秋冬で老化した体を、春夏で戻す、というサイクルが自然にできていたそうだ。「四季の意味を知ること、それが養生なんです」という小野満さんの話は、やはりスッと心に入ってくる。
漢方養生学について学べば、涼しくて心地よい秋は、乾燥していて老化を招く厳しい季節でもあることに気づく。だから秋の養生は「冷えと乾燥」への対策が大切。このことをしっかり頭にインプットして、心身ともに心地よい秋を楽しみたい。
[ハレタル]
Posted by nob : 2016年10月24日 19:57
免疫力=精神力、まさにそのとおり!
■がん(ステージ4)からの生還者に共通すること〜小林麻央に奇跡を!
生きたい理由が奇跡を起こす
告知を受けてから2年。今年9月からはブログも開始し、闘病生活を公表している小林麻央。その気丈さ、そして幼い2人の子供を想う母の強さには誰もが心を動かされる。
まだ希望はある
「麻央さんの場合は授乳期の乳がんという非常に特殊ながんです。授乳期は胸が張っていますので、しこりに気づきにくい。そのまま放置されたり、または乳腺炎ということで母乳マッサージをしてしまうんです。
マッサージをすると、がん細胞が皮膚全体に飛び散る。麻央さんのブログを見ると、当時、母乳マッサージをやっていたと書いてありました。遠隔転移すれば根治が不可能ですから、麻央さんはかなり厳しい状態だと言わざるをえないでしょう」(乳腺専門医でナグモクリニック院長の南雲吉則氏)
小林麻央(34歳)は自身のブログに、9月20日、『告知日』というタイトルをつけて、こう書き込んだ。
〈診察室に入った時の先生の表情で、「陽性だったんだな、癌なんだな」と分かった。
心の準備は意外とできており、冷静に先生のお話を伺った。
この時点では、まだ脇のリンパ節転移のみだった。(その後、現在肺や骨などに転移あり)〉
'14年10月に告知を受けた日のことをそう振り返りながら、現在は乳がんが転移していることを自ら明かした。
ステージについて言及はしていないが、肺や骨に転移している段階はステージ4(末期がん)であり、一般的に5年生存率は約30%だと言われる。
「現在の麻央さんは、複数の抗がん剤治療を約2年間も受けて、副作用に苦しんでいます。食欲こそありますが、髪の毛はもちろん、眉毛もすべて抜け落ちていますし、顔も黒ずんでいます。またブログにあるとおり、手指の痺れに悩まされている」(歌舞伎関係者)
麻央は9月23日のブログでこう書く。
〈ごめんね。
病気になっちゃった妻で。
病気になっちゃった娘で。
病気になっちゃった妹で。
きっと、病気になって、皆が一番に思う言葉かもしれない。
「ごめんなさい。。。」〉
胸を打たれる文章だ。もう絶望的なのか。いや、希望がないわけではない。
東京慈恵会医科大学附属病院・乳腺・内分泌外科の鳥海弥寿雄准教授が語る。
「これまでの報道などを見ると、麻央さんの治療は一定の効果を上げていると思います。臨床の現場では、逆転ホームランのように効果がでる薬に巡り会えることがあるんです。
私も乳がんの多発転移で手術をあきらめた患者さんが化学療法ですべてのがんが消えてしまった経験があります。10年以上経った今もその患者さんはお元気ですよ。麻央さんは若いだけに様々な治療にチャレンジできる。
性質のよくないがんであっても抗がん剤などが効くことはよくあることですし、いまは新薬が次々に発売される傾向がありますから、これからも、前向きに治療に臨んでほしいと思います」
現在、麻央や夫である市川海老蔵、家族は最新の治療法を必死に探しているという。実際、最先端の治療法を求めて転院もしているようだ。
乳腺外科医で新宿ブレストセンタークサマクリニック院長の日馬幹弘氏はこう語る。
「麻央さんのお母さんも乳がんの経験者なので、遺伝性のがんの可能性が高い。そうなると、ホルモン療法や分子標的薬は効果がなく、使える抗がん剤も限られる『トリプルネガティブ』だと思われます。
ただし最新の抗がん剤が効くかもしれません。遺伝性のがんに対して、一番新しいものは『ハラヴェン』と『オラパリブ』という薬の併用です。これはまだ承認されていませんが、一部の病院で治験を行っています。麻央さんもこの 2つを試している可能性があります。『ハラヴェン』は比較的副作用も少ない。トリプルネガティブへの効果が期待できます」
がんが消えるとき
さらに日馬氏は、麻央の前向きな姿勢が、大きなプラスだと指摘する。
「英国のデータで、がん患者を(1)闘争心、(2)否定、(3)受容、(4)絶望という4つの心理タイプに分けて、生存率を調査したものがあります。すると(1)闘争心という気持ちの患者さんは5年後の生存率が7割でした。今の麻央さんの姿勢が生存率を上げていることは間違いないでしょう」(日馬氏)
麻央は別の日のブログでこうも書いている。
〈この子たちのママは私ひとりなんだ、という喜びと怖さに、心がふるえた。絶対治す!と誓った〉
実際に進行がんと宣告されながら、手術を受けずに奇跡的に生還した例は世界中にいくらでもある。そうした患者100人以上をインタビューして著書『がんが自然に治る生き方』を書いた、カリフォルニア大学バークレー校博士でがんの研究家であるケリー・ターナー氏はこう語る。
「感情による身体への作用は驚異的です。愛やよろこび、幸福を感じると、脳内の分泌細胞から身体を治癒させるホルモンが血中へと放出されます。この作用による免疫システムが、がん細胞除去の力を向上させることがわかっています。抗がん剤治療中、笑うと免疫細胞が増加することも明らかになっているんです」
ターナー氏によれば、乳がん患者を対象にした大規模調査で、治療に一人きりで対応した人は、10人またはそれ以上の友人からサポートを受けた人よりも、死亡する率が4倍も高かったという。
「人とのつながりは免疫システムの強化をうながします。また身体のふれあいにも治癒を促す要素があります」(ターナー氏)
「生きたい理由」があるから
ターナー氏が出会ったダイアナは、61歳のときに子宮頸がんのステージ4と診断された。彼女はさまざまな治療を受けたものの効果がなく、最期を自宅で迎えるために退院した。
そんなダイアナのために夫は、毎日、ひたすらそばにいたという。体調が悪いときはベッドでずっと抱きしめていた。そして友人や家族を自宅に呼び、ダイアナのために祈ってもらった。
「すると驚くことに彼女の病状は回復に向かったのです。それから5年でがんは消えました。ある研究では一日10秒のハグが血圧を下げ、治癒ホルモンの分泌を増やすことが分かっています。
そしてなにより大切なことは『死にたくない』ではなく、『どうしても生きたい理由』を持つことです。数多くの研究が、抑うつ状態にある、または無力感をいだいているがん患者は、そうではない患者より生存期間が短かったと報告しています。
強烈な生への渇望が、様々な治療に取り組む気力を与え、がんからの生還につながっていくんです」(ターナー氏)
がんに勝てるかどうかを決めるのは、最後は免疫力=精神力である。
元アイドルで現在も歌手活動を続けている、谷ちえ子(57歳)も乳がんから生還した一人だ。
「医師からは『ステージ4』だと言われました。その病院で、すぐに治療に入ることを勧められましたが、私は姉に相談して、別の医師を紹介してもらいました」(谷)
その医師からこう言われたことで、谷はついていこうと決めた。
「患者さんの病気を治そうとする気持ちのお手伝いをしているんです」
谷は抗がん剤治療を1年弱受けた後、手術を受け、さらに放射線治療やホルモン治療を続けた。そして3年前に治療をしなくてもいい段階まで回復した。
「治療期間中は、好きなことをやろうと思いました。カツラを被って派手な洋服を着て、初めてプリクラも撮りました。それまで歌をやめていたのですが、『また歌いたい』という気持ちも生まれました。
麻央さんもどんどん家族に甘えて、その一方で自分で治すんだという強い気持ちを大切にしてほしい。そのためにはとにかく楽しいことを考えることです」(谷)
ステージ4の膀胱がんを克服したボクシングの元世界王者・竹原慎二(44歳)は麻央に激励のメッセージを送り、彼女も「どストレートに深く響きました」と送り返した。
「抗がん剤治療にも賛否両論があります。でも、最後は結果論でしかない。決めたのなら、『効くんだ』と信じて続けるしかありません。
実際にがんになると、『あのときこうすれば良かった』ということばかり、頭に浮かんできます。辛いとは思いますが、麻央さんにはいっぱい笑って、前向きでいてほしいと思います」(竹原)
最愛の家族をはじめ、日本中が麻央を応援している。奇跡が起きる準備はできている——。
「週刊現代」2016年10月15日・22日合併号より
[現代ビジネス]
Posted by nob : 2016年10月24日 19:42
摂ることよりも余分なものを摂らないこと、、、そして運動と睡眠。。。
■便と尿の排出に勝る「デトックス」はない
ハリウッドセレブや成功者に続けと言わんばかりに、巷には意味不明な横文字の健康法が溢れる昨今。そうした「意識高い系」健康法にハマる健康オタクたちに残念なお知らせを発表する。
「毒出し」は日常生活の中で十分できる!
体内に蓄積した重金属や残留農薬、活性酸素などの有害物質を排出して「解毒」することで健康を取り戻すというのがデトックス。血液にオゾンガスを混合して体内に戻す「血液クレンジング」、コールドプレス製法で作ったジュースと水だけで数日間過ごす「ジュースクレンズ」などは、有名人の実践者が多い。
森林浴「体内をキレイな酸素で満たしたいなら森林浴で十分。僕が考案したゾンビ体操をすれば血管が広がってすべての細胞に血液が行き渡りますから、そこでしっかりよい空気を吸えば不要な二酸化炭素などが排出される。これが本当のデトックスだと思いますね」(池谷医院院長の池谷敏郎氏)
おおたけ消化器内科クリニック院長の大竹真一郎氏は「そもそも毒素が何なのか」と根底から疑問を呈する。
「何が決定的な毒素になるかは個人差があるし、コールドプレスジュースの酵素が毒素を排出するなどありえない。本当のデトックスと言えそうなものは、体内に溜まった重金属をキレート剤の点滴で抜く療法や、水銀を抜く薬の服用ぐらいでしょう。ちなみにこちらは1錠10円程度で、慢性肝炎の治療でも使用されるもの。また、汗をいくらかいても有害物質は数パーセントしか排出されません」
「便と尿の排出に勝るデトックスはない。そのためには健康的な食生活と運動」(大竹氏)だそうで……。
【池谷敏郎氏】
医学博士。池谷医院院長。
【大竹真一郎氏】
消化器内科医。おおたけ消化器内科クリニック院長。
Posted by nob : 2016年09月22日 15:27
あらためてナッツの効能
■「太った」「肌あれが気になる」「疲れた」「むくんだ」時に効くナッツの選び方
ナッツといえば、ダイエット中のおやつに最適といわれる存在。しかし、その種類の多さと、それぞれのナッツの効能は多岐にわたり、覚えきれないところがある。そこで、我々が日々直面する「太った」「肌あれが気になる」「疲れた」「むくんだ」などのシーン別に、どのナッツが良いのかを、管理栄養士にピックアップしてもらった。
■ナッツの種類と効果の組み合わせ別!こんなときにはこのナッツ!
こんなときにはこのナッツ!ダイエット、肌あれ、疲れ、むくみにはどれがいい?
一般的なビジネスパーソンが生活の中で直面する次のようなシーンには、それぞれ、どのようなナッツが有効なのだろうか。管理栄養士の鈴木絢子さんによれば、それぞれ、次のようなナッツがおすすめだという。その理由と合わせて見ていこう。
●疲れたなと感じたとき
【クルミ】
クルミにはビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、葉酸などのビタミンB群が多く含まれています。特にビタミンB1は疲労回復に欠かせません。体の代謝がスムーズに行われ、疲労物質が排出されます。
●ストレスを感じているとき
【アーモンド】
アーモンドにはカルシウムが豊富。カルシウムには、イライラを緩和する効果があるため、ストレスが高まってきたら摂っておきたいですね。
●ちょっと太ってきたかもと感じたとき
【ひまわりの種】
ひまわりの種に含まれるリノール酸は、コレステロール値の上昇を抑えてくれます。よって、生活習慣病の予防効果が期待できるため、太りにくい体づくりにつながります。
●ダイエット中
【ブラジルナッツ】
ブラジルナッツ1粒(約4g)の糖質含有量は、たったの0.1g。ダイエット中に糖質を控えたい方の間食として最適です。また、ブラジルナッツに含まれるセレンには、強い抗酸化作用があるため、美容効果も期待できます。
●むくみが気になるとき
【ピスタチオ】
ピスタチオに豊富に含まれるカリウムが、体内の余分な塩分や水分を体の外へ排出してくれます。これにより、むくみの解消につながります。
●肌の調子が良くないとき
【ピスタチオ】
ピスタチオに含まれるルテインという抗酸化成分は、細胞の老化を防ぐ働きがあるため、肌の不調を助ける心強い味方になります。
●朝食のとき
【カシューナッツ】
他のナッツと比べて、糖質が多めなカシューナッツは、朝食に食べるエネルギー原としてオススメです。また、鉄分も豊富なので、「朝は貧血気味…」という方には、重要な栄養源です。
●3時のおやつ
【マカダミアナッツ】
淡白な味と独特の香りは、お茶菓子として最適です。さらに、不飽和脂肪酸が豊富に含まれているので、健康効果も期待できます。
●飲み会の前後
【ピーナッツ】
ピーナッツに含まれるナイアシンが、肝臓内の代謝をサポートしてくれるため、二日酔い予防になります。
●二日酔いの朝
【ひまわりの種】
ひまわりの種には、二日酔いの原因の一つであるアセトアルデヒドの解毒に効果があります。飲みすぎた翌日に食べると良いでしょう。
●寝不足のとき
【アーモンド】
寝不足が続くと頭痛が起きることがあります。アーモンドには、神経の働きを安定化させ、頭痛の痛みを和らげる効果のあるマグネシウムが豊富に含まれています。
●寝つきが良くないとき
【クルミ】
良質な睡眠をとるためには、セロトニンという神経伝達物質の分泌量を増やすことが大切です。クルミには、セロトニンの原料であるトリプトファンというアミノ酸を含んでいます。さらに、糖質量も少ないので夜間の間食にもオススメです。
こんなときにはこのナッツ!ダイエット、肌あれ、疲れ、むくみにはどれがいい?
今回紹介してもらったナッツ類は、コンビニやスーパーで手軽に買えるものがほとんど。ぜひ手に取ってシーンごとに活用してみよう。
また、最近では、ナッツ専門店も多く登場している。一度ナッツを一通り買い揃えてみるのもいいのではないだろうか。
ただし、いずれも食べ過ぎは控えるべき。鈴木さんによれば、一日の目安量として、アーモンドでは20粒前後、クルミは7粒、ピスタチオは30粒前後と、ナッツの種類や大きさによっても適量が変わってくるという。
それぞれの適量を確認し、美味しく食べて、健康・美容に役立てよう。
鈴木絢子さん
“正しく、楽しいロカボ生活”を提案する管理栄養士。ビジネスパーソン向けの食育活動に力を入れている。その活動の一環として、「人生を変える一皿。体質改善ボウル、サラド」のプロジェクトに関わっている。
https://www.makuake.com/project/salad/
取材・文/石原亜香利
[@DIME]
Posted by nob : 2016年08月23日 15:23
自身の身体との対話力が高まってくると、コップ一杯の水が与えてくれる様々な効能をもコントロールできるようになります。。。
■夏の快眠に不可欠!「質のいい寝汗」のかき方
汗っかきの人には「煎餅布団」が最適な理由
寝苦しい夏の夜。「汗の不快感で目が覚めた」「起きたら汗でびっしょりだった」ということもあるのでは?
そんな夏の不快な寝汗を最小限に留めるにはどうしたらよいのでしょうか? 五味クリニック院長で体臭・多汗研究所所長も務める、五味常明先生に伺いました。
季節にかかわらず、人間は寝る間に汗をかく!
五味先生によれば、睡眠時の汗は下記の4種類に分けられるそう。
①寝入りばなにかく汗
②夢を見ているときなどにかく汗
③病気のときにかく汗
④気温など外部の要因によってかく汗
夏の夜は気温が高いため、他の季節に比べ④の温熱性発汗に悩まされます。熱帯夜は200ml〜600ml、多い人は1リットルもの汗をかくことがあるのだとか。④の汗が多い場合は、寝室の気温の調整で対応できますが、重要なのは①の汗なのだと五味先生。
「寝るためには、脳の温度を下げる必要があります。そのためにかくのが①の汗。これは、快眠には不可欠な汗なのです」(五味先生)
①の汗をかかなければ、脳温が高いままでスムーズに入眠できません。例えば、入浴してすぐに寝るつもりでも、脳も含めて身体全体の温度が高い状態なので寝つくのに苦労することがあります。
夏はお風呂上がりにすぐエアコンの効いた部屋へ移動する人も多いと思いますが、そうしてしまうと汗腺が閉じて“必要な”汗をかけず、脳温が下がらないために寝つきが悪くなってしまうのだそう。
「脳温が高いまま寝ようとすると、身体が一生懸命温度を下げようとするので、余計にたくさん寝汗をかくことになります。入浴後、1時間ほど時間を置き、うちわや扇風機を使って自然に脳温を下げてから寝ると、①の寝汗は少なくなりますよ」(五味先生)
脳温を下げるには、外から冷やすことも効果的です。冷やしたタオルや保冷剤などを枕にして、入眠時に頭を冷やすと寝つきやすくなるそう。
ちなみに、五味先生いわく、ふかふかなベッドで寝ている人のほうが汗をかきやすいのだそう。
「身体には“半側発汗(はんそくはっかん)”という仕組みがあり、身体の一部が圧迫されていると、その反対側だけ汗をかくようになっています。例えば、背中側が圧迫されているならお腹側、左半身が圧迫されているなら右半身という具合です。蒸発しやすい方に汗をかくようになっているんですね。しかし、柔らかい寝具だと身体があまり圧迫されないため、身体全体に汗をかいてしまいます。布団と接して蒸発しにくい面にもムダな汗をかいてしまうのです」(五味先生)
この働きを利用して敷布団を固めにし、上掛けは圧迫感がなく汗が蒸発しやすいものにすると、効率的に体温を下げられ、結果的に寝汗の量を抑えられるそうですね。「汗っかきの人はいわゆる“煎餅布団”のような固めの寝具を使うと、身体が圧迫されてムダな汗が少なくなります」(五味先生)
寝る前に必ず水分補給!冷蔵庫には麦茶と牛乳を常備
眠っている間の汗が必要だということはわかりましたが、ただ汗をかくばかりでは、脱水症状になってしまう可能性も。だからといって、寝る前に水を飲み過ぎても夜中にトイレで起きてしまいそう……。どうするのが正解なのでしょう?
「まず、寝る前の水分補給は絶対に必要です。量の目安としては、喉の渇きが収まる量にプラス1、2口くらい。夜中にトイレで起きた時も、ひと口水分を補給して下さい。夜中にトイレに行きたくないからといってあまり水分をとらないと、脳梗塞や心筋梗塞につながる可能性もあります。また、朝起きたときもすぐに水分をとるようにしてください」(五味先生)
寝る前の水分はつい量をセーブしてしまいがちですが、脱水症状防止のためには飲んでも大丈夫そうですね。では、どんなものを飲めばいいのでしょうか。
「“汗をかく=スポーツドリンクを飲む”と思っている人が多いですが、それはビショビショになるほど汗をかいた場合の話です。寝る前に飲むなら、カフェインが少なく身体を自然に冷ましてくれる麦茶がよいでしょう。起きた時に飲むなら牛乳がおすすめ。牛乳に含まれるアルギニンという成分が血管内の水分を増やしてくれるので、脱水対策には非常に効果的なんです。飲むなら牛乳瓶1本分(約200ml)くらいが目安です」(五味先生)
朝の1杯はコーヒーという人も多いと思いますが、起き抜けの1杯は牛乳を飲む習慣をつけるとよさそうですね。
では、びっしょりと寝汗をかいてしまう人もいれば、まったくといっていいほどかかない人もいます。この違いは、何が影響しているのでしょうか。
「人間の汗腺は生まれつき約500万ありますが、そのうち実際に働いている“能動汗腺”は約半分の230万ほど。この能動汗腺の数により、汗のかきかたが変わってきます。能動汗腺は子どものころに汗をかくことで増えるのですが、最近は汗をかかせない親が多いため、能動汗腺が少ない子どもが増えてきているんです」(五味先生)
能動汗腺が少ないと、汗をかけないために身体の熱が発散できず、暑さに弱くなってしまうのだとか。部活中に熱中症になってしまう子どもが増えているのも、そうした背景が考えられるとのこと。
汗腺の機能が弱っていたり、汗腺が少ないことで暑さに弱くなると、寝ている間に熱中症になってしまうこともあります。しかし、五味先生は「汗腺の機能が弱っている人は、トレーニングで汗腺を鍛えれば、少しの汗でも体温の調整ができるようになり、汗のニオイも抑えられる」といいます。
入浴方法を工夫して汗腺を鍛えよう!
教えてもらった汗腺トレーニングの方法はこちら。
(1)43~44℃の熱めのお湯を浴槽の1/3から半分くらいためる。
(2)四つん這いになり、両手は肘から手先まで、両脚はひざから下までを10~15分ほどお湯につけ、手足浴をする。
(3)手足浴が終わったら、ぬるま湯を足して浴槽のお湯を36度ほどにし、今度は普通に10~15分ほど湯船につかる。
能動汗腺の数が少ない人は、「熱中症体質」とも言えます。こうした人は、体温調節がうまくできないため、エアコンを使わないと熱中症になってしまう危険が。
「タイマー機能なども活用して、我慢せずにエアコンを使用するようにしてください」(五味先生)
毎日かいている汗がこんなに重要だったとは! 寝汗をかかないようにするのではなく、汗腺トレーニングなども取り入れて「よい寝汗」をかけるようになることが、気持よく寝るためには必要です。今年の夏は健康的に汗をかいて、ぐっすり眠りましょう!
監修:五味常明(五味クリニック 院長)
[Fuminners/東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2016年08月19日 15:24
慣れてくれば街中でじっと立ったままでもできるようになります(笑)
■誰でも5分でできるリラックス「自律訓練法」とは?
よく眠れない、身体がだるい。こういった症状の背景には、日頃のストレスからくる身体の緊張があるかもしれません。しかし、原因を根本から排除するというのもなかなかむずかしいですよね。自分で自分の身体をうまく休ませる術を身につけておくことが、現実的な対処法と言えるのではないでしょうか。
●自分をリラックスさせる自己暗示、自律訓練法
自律訓練法とは、1932年にドイツの精神科医により開発され、現在ではリラクゼーション方法としてたいへん有効とされているものです。方法としては、自己暗示により、穏やかな眠りにつくことを目指しています。これは、他者から誘導される催眠法と異なり、自分自身でいつでもどこでも行えることが特徴です。
単にリラックスする、といっても効果は様々なところにあります。疲労が回復する、過敏状態が沈静化する、自己統制力が増し、衝動的な行動が少なくなる、身体の痛みや精神的な苦痛が緩和される、向上心が増す、といったものです。
●簡単な手順に沿って行ってみましょう
では自律訓練法はどうやって行えばいいのでしょうか。その手順を、九州大学心療内科の方法などを参考にまとめると、以下のようになります。より詳しく知りたい方や体調に不安のある方は医療機関に相談されることをおすすめします。
まず、体全体の筋肉が弛緩しやすいような姿勢をとります。椅子に深く腰をかけた姿勢や布団の上で仰向けになって行うとよいでしょう。気持ちが落ち着いてきたら、以下の手順で気持ちを向けていきます(人によって、めまいや脱力感などが生じることもあるので、訓練の後は必ず「消去動作※以下8番」を行います)。
1. 気持ちがとても落ち着いている
2. 右腕が重たい→左腕が重たい→両脚が重たい(利き手の方から行います)
3. 右腕が温かい→左腕が温かい→両脚が温かい(利き手の方から行います)
4. 心臓が静かに規則正しく打っている
(心臓に疾患のある人、心臓が気になる人は省略してください)
5. 楽に呼吸している
(気管支喘息、過換気症候群など呼吸が気になる人は省略します)
6. お腹がとても暖かい
(糖尿病の人は,主治医と相談してください)
(胃・十二指腸潰瘍や胃炎がある場合は、医師に確認。また、妊娠中の人は省略します)
7. 額が気持ちよく涼しい
(頭痛、てんかん、その他頭部に疾患のある人は省略します)
8. ここまで進んだら、「消去動作」を行います
両手の開閉運動 → 両肘の屈伸運動 → 大きく背のび → 深呼吸
2番目以降は、2、3分でそれぞれの反応(重たい、温かい)が起こるようになったら、次の手順を付け足していきます。慣れてくると最後まででも2〜3分でできるようになるようです。3番目までスムーズにできるようになると、緊張がほぐれてリラックスした気持ちのよい状態を体験できるようになります。
●試してみて、その効果を実感
実際にスタッフが2週間ほど行ってみたので、報告します。
はじめは2番目、3番目それぞれになんとなく重たく感じるかな、暖かい気もするな、という程度でしたが、繰り返すうちにしっかり感じられるようになりました。3番目までは比較的すぐにできるようになりました。ただ、催眠にかかりやすい体質なのか、ここでついつい眠ってしまいます。それだけ効果があるととらえていいのかもしれません。このあたりは、体質や状態などにより個人差はありそうです。
夜、横になってから行うと深く眠れるようになりました。ということで眠る前に行うといいのではないでしょうか。この場合、消去動作は不要です。
ただ、電車の中で行うとリラックスしすぎて、目的地を乗り過ごすおそれがありますので、十分に気をつけてくださいね。
<参考サイト>
・九州大学心療内科:自律訓練法
http://www.cephal.med.kyushu-u.ac.jp/methods/AT.htm
[10 M TV オピニオン]
Posted by nob : 2016年08月01日 20:57
私のレシピ/豆乳ヨーグルド、バナナスライス、甘酒、スキムミルク、リブレフラワー、ハチミツ、シナモンパウダーのミックスVol.2/今朝はバナナをキウイ&桃に♪
■バナナじゃない!? ダイエットや生活習慣病予防に毎日食べたいフルーツは?
●ビタミンCや食物繊維、女性注目の葉酸がたっぷり!
ゼスプリ インターナショナル ジャパンはこのほど、キウイフルーツ・メディアセミナーを開催した。同セミナーでは、国内におけるキウイフルーツ研究の第一人者である、駒沢女子大学 人間健康学部 健康栄養学科の西山一朗教授が登壇し、「最新のキウイフルーツの栄養と健康に関する研究成果」について講演を行った。
○卓越したビタミンC含有量
キウイフルーツは、1個(約100g)あたり50〜60kcal程度と低カロリー。一年中入手が可能で、熟していないものであれば冷蔵庫で1カ月程度の長期保存ができる。半分にカットするだけで手軽に食べられ、基本的に生食のため、栄養素の損失が少ないのも特徴とされている。
キウイフルーツの代表的な品種には、ゼスプリ・グリーン(ヘイワード種 ※以下グリーン)、ゼスプリ・サンゴールド(ZESY002種 ※以下サンゴールド)、ゼスプリ・ゴールド(ホート16A種 ※以下ゴールド)がある。
その栄養価で驚くべきところは、ビタミンCの含有量だ。100gあたりのビタミンC含有量は、グリーンが約85mg、サンゴールドが約160mg、ゴールドが約110mg(「New Zealand FOODfiles 2014 Ver.01」「日本食品標準成分表2015年度版/七訂」より)。これはフルーツの中で卓越した含有量であり、食品全体で比べた場合でもトップクラスだという。厚生労働省が定める成人のビタミンC推奨量は、1日100mg。キウイフルーツ1個は約100gであることから、1日1個のサンゴールドもしくはゴールド(グリーンの場合は2個)を食べれば、推奨量を満たすことができるというわけだ。
このほか、食物繊維やカリウム、葉酸、ビタミンEなども豊富に含まれる。「キウイフルーツはコンパクトな実の中に、食生活で不足しがちな栄養素をバランスよく含んでいることがおわかりいただけると思います」と西山教授。
○免疫力アップの可能性
今年4月、キウイフルーツの効果に関する国際シンポジウムがニュージーランドのタウランガで開催された。西山教授は、同シンポジウムで報告された内容をもとに、キウイフルーツにおける「ビタミンCと健康効果」「血糖値上昇の抑制作用」「消化器系の働き」について解説した。
まず、ビタミンCには、酵素の働きを助ける作用や抗酸化作用といった生理作用がある。ビタミンCが不足すると、皮膚や歯肉からの出血、倦怠(けんたい)感、衰弱などの症状が起こる壊血病の原因になるといわれるが、その予防のために推奨される血漿(けっしょう)中ビタミンC濃度は30μM程度。一方で生理作用を十分に発揮させ、生活習慣病予防や免疫機能の強化といった機能を期待するためには、血漿中ビタミンC濃度を飽和状態まで高めておく必要があるという。
18〜30歳の非喫煙男性を対象とした実験では、1日2個のゴールドを6週間摂取したときに血漿中ビタミンC濃度は飽和状態となった。また、1日3個食べてもそれを上回る効果は見られず、余剰のビタミンCは尿中へ排出された。このことから、「1日2個のキウイフルーツを摂取することによって、生活習慣病の予防効果などが期待できます」と西山教授。
さらに別の実験において、1日2個のゴールド摂取で気分の改善が認められる可能性が示され、1日2個のサンゴールド摂取で免疫力向上の可能性が示唆されたことにも触れた。
●糖質が気になる人にもおすすめ!
○血糖値を上げにくいフルーツ
ダイエットや糖尿病などの生活習慣病の予防として、「食後血糖値のコントロール」がポイントだといわれることも多い。西山教授はこれを踏まえ、キウイフルーツが血糖値を上げにくい食品であることを指摘する。
食品に含まれる炭水化物は、小腸でグルコース(ブドウ糖)に分解され、血液中に吸収される。食後に血糖値が上昇すると、すい臓からインスリンが分泌され、通常、食後2時間程度で血糖値は元のレベルまで低下。しかし、インスリンの量が少なかったり、分泌されるタイミングが遅かったりすると、食後血糖値がすぐ下がらず、食後高血糖をきたすことがあるという。この食後高血糖は動脈硬化を進行させ、心血管疾患や脳卒中のリスクを高めるとされている。
西山教授は「食後高血糖を防ぐためには、血糖値を上げにくい食品を選ぶことが有用とされています」と話す。
血糖値の上昇度を示す1つの指標とされているのが、「GI(glycemic index: グリセミック・インデックス)」だ。その値が低いほど血糖値が上がりにくい食品であることを表しており、値が70以上は「高GI食品」、56〜69は「中GI食品」、55以下は「低GI食品」にカテゴリーされる。そして、キウイフルーツは低GIに該当する。
「食品1食あたりの血糖値上昇への影響を比較した研究でも、キウイフルーツ100gは、パン30gや白米150g、バナナ120gなどと比べて、血糖値を上げにくい食品であることが明らかになっています」と西山教授。
これを裏づける研究に、ビスケット(炭水化物)のみを食べた場合と、ビスケットとキウイフルーツを一緒に食べた場合とで、食後血糖値の変化を調べたものがある。結果として、どちらも同じ量の炭水化物を摂取したにもかかわらず、キウイフルーツを一緒に食べたほうが血糖値の上昇が緩やかになったことが示された。
○胃に優しく、腸内環境も健やかに
最後に西山教授は、キウイフルーツの消化器系の働きについて語った。
タンパク質を分解する酵素の一種である「アクチニジン」は、グリーンの果肉には100gあたり約300mg含まれているが、ゴールドにはほとんど含まれていない。この酵素の働きによるキウイフルーツの消化促進効果を示す研究として、ヒトの消化器系の環境を模倣した試験管内実験(in vitro)と、ラットや成長期のブタを使った動物実験(in vivo)が発表されている。
試験管内の実験では、消化酵素である「ペプシン」を含む人工胃液にタンパク質を入れ、pH2の酸性条件で30分消化したのち、pHを8に変え、パンクレアチン(消化酵素)を添加して人工腸液の組成とし、さらに120分間の消化を行うという方法で実施した。その結果、人工胃液にグリーン抽出物を添加した場合、カゼイン(乳タンパク質)や食肉タンパク質、大豆タンパク質などのタンパク質において、消化促進効果が観察された。
一方、動物実験では、タンパク質のエサと一緒にキウイフルーツを与えた場合の消化に対する影響を検証。その結果、アクチニジンを豊富に含むグリーンを与えた場合では、アクチニジンをほとんど含まないゴールドを与えた場合に比べて、消化促進効果が認められた。
国際シンポジウムでは、ヒトを対象にした臨床試験結果の速報も発表された。それによると、健康な成人男性を対象に臨床試験を行ったところ、赤身ステーキと一緒にグリーンを食べたグループでは、膨満感など胃における不快な症状が軽減したという。
「これら複数の研究結果から、グリーンにはタンパク質の消化促進作用があると考えられます」と西山教授。
さらに別の研究において、グリーンおよびゴールドは腸内フローラ(腸内細菌叢)の改善効果をもつことが示唆され、グリーンは便秘改善効果を示したことを挙げている。
なお同セミナーでは、キウイフルーツを使ったアレンジメニューもふるまわれた。ハーフカットで手軽に取り入れるのもよいが、パスタや生春巻き、スイーツに添えるなどアレンジを加えてみると、より飽きずに摂取することができるだろう。
手軽に食べられて、栄養バランスにも優れたキウイフルーツ。今回、その栄養機能だけでなく、低GI食品としての評価や、腸内環境を整える役割なども認められつつあることがわかった。まずは健康のために、そしてダイエット・美容のためにも、1日2個の"キウイフルーツ生活"を始めてみてはいかがだろうか。
(須藤妙子)
[マイナビニュース]
Posted by nob : 2016年07月26日 15:22
今さらですけど。。。
■薬と一緒に飲んではいけないものは
スポーツドリンクにも注意
「薬は水で飲む」。だれもが一度は聞いたことのある「常識」ですが、日ごろの忙しさや面倒くささで、つい手近な飲み物と一緒に飲んでしまう人が少なくないようです。しかし、安易な行動が思わぬ悪影響を招いてしまうことも!?
◆かぜ薬や頭痛薬、便秘薬、胃薬に抗アレルギー薬など、薬を飲む機会は日常的にあります。薬の持つ効果を安全に、最大限に引き出すために大切なのは、用法や用量を守る正しい服用。なかでも見落としがちなのが、薬の飲み方です。
◆内服薬の正しい飲み方は、まずコップ1杯の水を用意します。錠剤・カプセル剤・散剤など、どんな内服薬でも、最初に少量の水を飲んで口やのどを湿してから、薬剤を口に含み、飲み込む際に水で追いかけるように服用しましょう。
◆水なしで飲むと、薬がのどや食道にひっかかり、予定外の場所で溶け出してしまうために食道炎などの炎症を起こす場合があります。また、水の量が少ないと、薬の吸収がスムーズにいかず、効き目が低下するケースもあります。ですから、コップ1杯程度の水で追いかけることを心がけてください。
▽▼▽次頁「水以外で飲んだ場合の副作用」など▽▼▽
◆では、水以外で飲んではいけないのでしょうか? 薬の処方せんなどには、「水と一緒に服用する」と明記されています。それには、ちゃんとした理由があります。薬には飲み合わせ(相互作用)があり、水以外の飲み物と一緒に飲むと、薬効が低下したり、逆に増強してしまったり、さらには深刻な健康への影響が生じる場合もあるからです。
◆薬と飲み合わせの悪い飲みものを具体的にあげてみましょう。まずは牛乳です。抗生物質(抗菌薬)、骨粗しょう症の薬と一緒に飲むと、牛乳に含まれるカルシウムがこれらの薬と結合してしまい、薬の吸収が低下することが指摘されています。
◆また、腸で溶けるタイプの下剤などと一緒に飲むと、吐き気などの副作用を起こす場合もあります。牛乳は胃の中のpH値を上昇させてアルカリに傾くためで、本来なら腸で溶ける薬剤が胃で溶けてしまい、吐き気につながるとされています。
◆カフェインを含む飲料も、飲み合わせがいいとは言えません。胃腸薬(H2ブロッカー)と一緒にのむと、カフェインの体外への排出が遅くなり、脈が速くなるなどの症状がみられる場合があります。
◆痛風の治療薬の働きを低下させることも指摘されています。カフェインは、尿酸の排泄を妨げる作用があるためで、薬効が弱まってしまいます。カフェインはコーヒー、紅茶、緑茶、コーラなどの飲料にも含まれていることにも注意。薬の服用期間中はなるべく控えめにしましょう。
◆ほかにもスポーツドリンクやアルコール、グレープフルーツジュースなども薬との飲み合わせが指摘されています。一見、スポーツドリンクは悪くなさそうな印象がありますが、カルシウムなどミネラルが多く含まれており、薬の成分の吸収を妨げる可能性があります。また、体内への水分吸収をよくするため、薬によっては成分の安定性に悪影響がでる懸念もあります。
◆身近な飲料に、薬と飲み合わせが悪く、相互作用を引き起こすものは意外と多いことがわかると思います。薬の注意書きに「薬は水や白湯で飲むこと」が明記されているのは、きちんとした理由があるからです。薬は水以外では飲まないことを徹底するようにしましょう。
(監修:東京医科大学病院 総合診療科准教授 原田芳巳)
[ケータイ家庭の医学SP]
Posted by nob : 2016年07月22日 10:36
日進月歩
■食道がん、ウイルスで破壊…患者に治療効果
がん細胞だけを破壊する特殊なウイルスを使った治療で、食道がん患者7人のうち5人で腫瘍が消えるなどの効果があったとする成果を、岡山大学のチームがまとめた。
28日から東京都内で開かれる日本遺伝子細胞治療学会で発表する。
ウイルスは正常な細胞では増殖しないため副作用も起こりにくいとし、2020年頃の薬事承認を目指す。
このウイルスは、岡山大の藤原俊義教授(消化器外科)らのチームが02年、風邪の原因となるアデノウイルスの遺伝子を操作して開発した。がん細胞に感染して増殖し、細胞を破壊するが、正常な細胞に感染した場合は自然に消える。
また、ウイルスには、がん細胞が放射線などで傷ついた自らのDNAを修復する機能を阻害し、細胞を死滅させる働きもある。放射線治療の効果を高めることも期待できるという。
[読売新聞]
■<膵臓がん>発見に新手法 血液2.5CC 数時間で判定
石川県野々市市末松の医療系ベンチャー企業「キュービクス」が、少量の採血だけで膵臓(すいぞう)がんを見つけ出す新たな検査手法を開発し、金沢大付属病院などと共同で臨床試験に取り組んでいる。膵臓がんは発見が難しく、見つかった時には既に進行しているケースも多い。血液を基に遺伝子レベルでがんの有無を早く正確に識別する方法で、3年後の実用化を目指している。【金志尚】
国内では年間3万人以上が膵臓がんで亡くなっている。胃や腸など他の臓器に囲まれているため発見が難しい上、発症初期には目立った自覚症状も現れないため、気付きにくいという特徴がある。
キュービクスは2004年に設立され、医療関連機器や診断薬の開発を手がけている。がんの検査手法の開発にも力を入れ、11年には血液から抽出したRNA(リボ核酸)と呼ばれる遺伝物質を解析し、膵臓など消化器系がんの有無を調べる「マイクロアレイ血液検査」を実用化した。この検査は1回当たり7万〜10万円程度で、数日で結果が判明する。
今回はより短時間で膵臓がんの有無を識別する手法を開発した。同社が着目したのが、膵臓がんに反応して血液細胞から分泌される特定のRNAだ。特殊な装置でRNAの有無を検査し、膵臓がんの発見につなげる。判定に必要な血液量は2.5CCとわずかで、数時間で結果が出るという。
◇19年の実用化目指す
今年4月からは患者50人と健康な人100人を対象にした臨床試験を金沢大付属病院など北陸地方の10病院と共同で始めた。来年3月まで続け、検査の有効性を確かめる。
検査費用は1回当たり3万〜3万5000円を見込み、2019年中の実用化を目指している。
同社の丹野博社長は「国民の2人に1人ががんになる時代。早期発見は社会的意義がある」と話している。
[毎日新聞]
Posted by nob : 2016年07月22日 10:23
早期発見率と医療技術の向上により今後も自然増が見込まれるかと。。。
■がん5年生存率62.1% ゆるやかに向上 過去2回比
熊井洋美、川村剛志
国立がん研究センターなどの研究班は22日、がん患者を追跡した5年後の生存率(全国推計)を発表した。地域がん登録をしている都道府県のデータを集計するのは3回目。今回は2006~08年にがんと診断された21府県の約64万人を調査、全てのがんの5年生存率は62・1%で、過去2回より3~5ポイント高く、緩やかに向上している。
5年生存率は、がん患者で診断から5年後に生きている人の割合が、日本人全体の5年後に比べてどのぐらいかを示すもの。割合が高いほど治療で生命を救える効果があり、5年が治療や経過観察の目安の一つとされる。前回は03~05年に診断された7府県の約19万人で58・6%、初回は00~02年診断の6府県15・4万人で56・9%だった。
今回の集計を部位別にみると、前立腺が97・5%で最も高く、甲状腺、皮膚、乳房、子宮体部が続いた。膵臓(すいぞう)、胆囊(たんのう)・胆管、肺、肝臓が低かった。一方、悪性リンパ腫、白血病、口腔(こうくう)・咽頭(いんとう)、肝臓などで初回からの改善幅が大きかった。
性別で見ると、女性は66・0%で、男性の59・1%より高い。同じ部位でも肺(女性43・2%、男性27・0%)や食道(女性43・9%、男性36・0%)で差が大きかった。
5年生存率が緩やかに向上した背景には、予後がよい乳がんや前立腺がんが増えている面もあるが、部位別でもほとんどで過去2回より改善している。国立がん研究センターの若尾文彦・がん対策情報センター長は「治療法が改善され、検診で早期発見ができるようになった」と分析する。例えば、白血病で新しい薬が治療に導入され、肝臓がんでは局所療法に効果が出ているという。
若尾さんは「大腸がんや肺がん、乳がんでその後に分子標的薬や新しい抗がん剤が登場しており、次の集計ではさらに生存率の向上が見込まれる」と話す。
■主な部位別のがん「5年生存率」(%、年は診断された年)
2000~02年/03~05年/06~08年(今回)
*
◇口腔(こうくう)・咽頭(いんとう)
54.6/54.3/60.2
◇食道
33.2/33.7/37.2
◇胃
64.3/63.3/64.6
◇大腸
68.4/69.2/71.1
◇肝臓
27.1/27.9/32.6
◇胆囊(たんのう)・胆管
21.8/21.1/22.5
◇膵臓(すいぞう)
5.5/ 7.0/ 7.7
◇喉頭(こうとう)
77.8/75.9/78.7
◇肺
29.0/29.7/31.9
◇皮膚
90.9/90.9/92.4
◇乳房
87.7/89.1/91.1
◇子宮頸部(けいぶ)
72.2/72.2/73.4
◇子宮体部
79.2/79.8/81.1
◇卵巣
53.3/55.0/58.0
◇前立腺
84.6/93.8/97.5
◇膀胱(ぼうこう)
77.2/73.5/76.1
◇腎臓・尿路
65.4/65.7/69.1
◇脳・中枢神経系
32.7/32.6/35.5
◇甲状腺
92.1/92.2/93.7
◇悪性リンパ腫
54.6/58.7/65.5
◇多発性骨髄腫
29.0/32.6/36.4
◇白血病
32.1/37.3/39.2
◇全体
56.9/58.6/62.1
(対象者は00~02年が15万4022人、03~05年が19万404人、06~08年が64万4407人)
<アピタル:ニュース・フォーカス・その他>
http://www.asahi.com/apital/medicalnews/focus/(熊井洋美、川村剛志)
[朝日新聞]
Posted by nob : 2016年07月22日 10:05
私のレシピ/豆乳ヨーグルド、バナナスライス、甘酒、スキムミルク、リブレフラワー、ハチミツ、シナモンパウダーのミックス
■「ヨーグルトは身体に良い」はウソだった!?
夏目幸明 [経済ジャーナリスト]
論文を読むのが日課という「めんどくさいお医者さん」、東京大学病院の地域医療連携部の循環器専門医・稲島司先生。彼は、世に流布する「健康的なイメージ」と、科学的「効果が証明されたもの」を区別するため、今日も人の生活習慣にケチをつけ始めた――。
夏目 前のお話にあった、糖分を少なめにして、とは言ってもやりすぎないっていう食生活は良いですね。お腹周りもすっきりしてきたし、我慢もそれほどしないのに体調が良いです。実は最近もっと身体のことを考えて、毎日ヨーグルトを食べているんですよ。一般的に「ヨーグルトは身体にいい」イメージがあるじゃないですか。
稲島 それ、エビデンスあるんですか?
夏目 え?
稲島 この連載は何回目になりますか?その「イメージ」に科学的根拠があるか、調べましたか? 仕事と同じで、会社のお金を何億円も投資するなら「この会社はよさそうなイメージがある」なんて理由で投資を決めないですよね。業績を徹底的に調べるでしょう。なのに多くの方が身体とか健康のことになると――。
夏目 (相変わらずめんどくさいなぁ…)
「ヨーグルトは身体にいい」は
古典的な医学情報によるもの!?
稲島 ヨーグルトは健康にいい、という通説はよく耳にします。「腸の調子が良くなる」とか、「アレルギーが改善する」、さらには「免疫が高まる」、なんていう説もありますね。
夏目 いかにも身体に良さそうじゃないですか。
稲島 結論を先に言ってしまうと、私はこの3つのうち2つは眉唾だと考えています。
夏目 ええ!?本当ですか?
稲島 そもそもヨーグルトに「身体にいい」イメージがあるのは、イリヤ・メチニコフ(1845~1916)というロシアの学者の研究からのようです。彼は腸は便を貯める袋で、その中にいる、今でいう「悪玉菌」によって老化が進む、と考えたのです。
夏目 「大腸はただの袋」とは、ずいぶんな暴論ですね。
稲島 でも、この時代に常在菌に着目したのはすごいですよね。悪玉菌があるといっても大腸を取ってしまうわけにはいかないので、メチニコフは今でいう「善玉菌」を入れれば良いと考えます。そこで注目したのが「乳酸菌」。乳酸菌は、自分が生き延びるために周囲に弱酸性の環境をつくりだし、周囲に悪玉菌が生きにくい環境をつくります。
夏目 だから、乳酸菌は菌の中でも「善玉菌」なんですね?
稲島 彼はブルガリア地方に長寿の方が多いことに着目します。そして「ブルガリア人が長寿なのは食事に関係があるはず」と考え、様々な食物を調べます。そこでヨーグルトが長寿に影響がある、と考えたんですね。メチニコフ自身も、ヨーグルトを常食していました。そして、この説が注目を集め、世界中で「ヨーグルトは健康にいい」と言われ始めたのです。
世界中で食べられているが
科学的根拠は一部のみ
夏目 先生の話を聞くと、やっぱり、単に「食べていい」感じがしますが?
稲島 たしかに、感染性(菌などによって起こる)腸炎については、1990年代以降の世界中の35論文をメタ解析してみると、ヨーグルトを摂っていると治るまでの期間が短くなる傾向があるという結果でした(Chochrane Database 2010)。しかし、これはあくまでも感染性腸炎に限ってのデータです。いつもヨーグルトを摂っている人が、そうでない人よりも身体的(PCS)にも精神的(MCS)にも健康であるというわけではなさそうなんです。
その調査のあらましをまとめたものが下の図です。詳しい説明は省きますが、この「p値」というのが0.05を下回っていなければ「有意差がない」、つまり効果がないと解釈します。
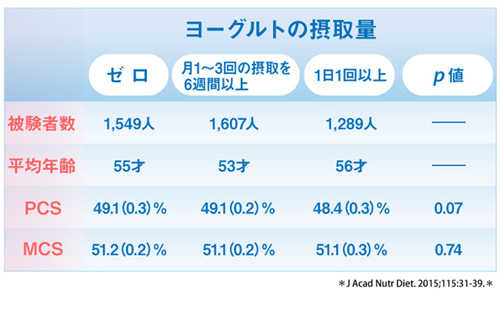
夏目 つまり、ヨーグルトは腸の感染症には多少効くけれど、そのほかの効果は限定的だということですか?
稲島 そういうことです。ヨーグルトは免疫強化に良いとも言われているようですが、そもそも免疫は身体にとっての外敵を排除する力のことですよね。簡単に言えば感染症に対する防衛力のことです。現代日本人は他の時代や地域と比較して、感染症に苦しむリスクは比較的小さいですよね。むしろ、免疫が高すぎて困っている方々の方が多いかもしれません。
夏目 え!?そうなんですか!防衛力なんだから、高い方がいいに決まってるじゃないですか。
稲島 いいえ、リウマチなどの膠原病やアレルギーといった疾患は、免疫過剰によって自分の身体の一部を攻撃してしまうことで発症するんです。こういった疾患に対しては、免疫を抑える治療をすることもあります。
ヨーグルトはアレルギーに効くという説もありましたね。マイアミ大学では、代表的なアレルギー疾患であるアトピー性皮膚炎と気管支ぜんそくを患う子どもたちを対象とした調査を発表しました。ヨーグルトだけでなく、ヒトに良いだろうと思われるいろいろな微生物(プロバイオティクス)を対象にしたのですが、結果、アトピー性皮膚炎(2797人)、気管支ぜんそく(3143人)のどちらも、プロバイオティクスが有効だという結果が得られませんでした(Pediatrics.2013 Sep;132(3):e666-76)。
夏目 うーん、アレルギーにも効果なしか…。
食べていいヨーグルトと
食べなくていいヨーグルトの違いは?
稲島 そもそもヨーグルトが効果的なら、ヨーグルトの売上が増えるとともにアレルギー疾患が減っていくはずじゃないですか?この2枚の表を見てください。実際には、ヨーグルトの販売数が増えても、疾患は減ってないし、むしろ一部は増えているんです。
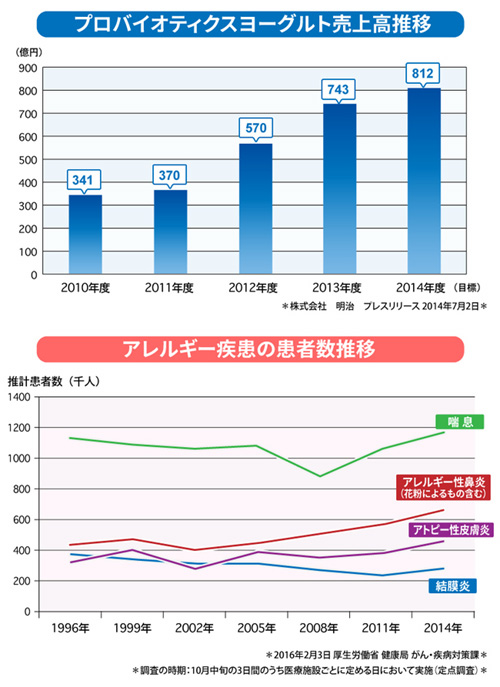
夏目 これだけ見ると、「ヨーグルトが売れるほどアレルギー疾患が増える。アレルギーの原因はヨーグルトだ!」なんて言い出す人もいそうですね。
稲島 あ、敵を作りそうなコメントですね。
夏目 ちょ、ちょっと待ってください!だって、この表は先生が…。あ、でも、エビデンスがないからといって、身体にいい効果がゼロって決まったわけでもありませんよね?
稲島 もちろんそうです。ここから先は「今後の研究が待たれます」としか言いようがありません。それに、先に少しご紹介したように感染性の下痢はヨーグルトを食べると治りやすいという、ゆるやかなエビデンスはあります。
夏目 じゃあ、稲島先生はヨーグルトなんか食べないんですか?
稲島 いえ、毎日のようにヨーグルトを食べてますよ。
夏目 !?
稲島 混乱させてごめんなさい。実は、ヨーグルトにはちょっと期待しているんです。腸炎に関しては良さそうですしね。しかも、以前に説明したある種のサプリのように有害な方向に行く結果はなさそうです((「βカロテン摂取で肺がんが増える!データで読み解く食品のウソホント」を参照)。そして、私はヨーグルトが好きです。
夏目 じゃあ、僕がヨーグルトを食べているのを見て、なんでケチをつけたんですか?
稲島 ヨーグルト自体がダメではないんです。ただ「嗜好」ではなく「健康のため」で摂るなら、一部の商品には気をつけてはいかがかなと思っています。ちょっと考えてみたチェックポイントは2つあります。
夏目 2つ!
稲島 まず、その商品、甘くないですか?精製された糖分の摂りすぎには、夏目さん普段から気をつけてますよね。コーヒーにも砂糖は入れないって言ってたじゃないですか。でもヨーグルトを通して糖分をいっぱい摂っていることになる!その「味」が好きなのではないのに、健康のためと思って。オヤジさんが糖尿病で苦しんでいるアナタがね!!
夏目 ひー!探偵みたいだ!
食べてもいいヨーグルトには
「発酵臭」がする!
稲島 次はもっと大事です。その商品、「発酵臭」はしますか? 納豆やナチュラルチーズは、いずれも独特の「発酵してるんだな」という臭いがしますよね?でも、世の中で売られているヨーグルトのほとんどはいい「匂い」がする。「臭い」じゃなく「匂い」です。それの原因は2つ、微生物や発酵食品が少ししか含まれていない、あるいは発酵臭が帳消しになるほど香料がたくさん使われているから!あなたは健康イメージがあるからといって、香水を飲むようなことをしているんですよ。
夏目 ひー!先生、僕以上にいろんなメーカーを敵に回しそうです!じゃあ先生が食べているヨーグルトは何か別のモノなんですか?
稲島 いえ、特殊なモノではないですよ。牛乳にボチャンと入れると、翌日ヨーグルトになっているタイプです。特別カラダに良いという根拠があるわけではないですが、自宅で作れば余計なものが入りませんし、何より安いですからね。流行った時期もあるようですが、ステマになるのは嫌だから、あえて一部伏せます。「カスピ海ヨ○グルト」ってご存じですか?
夏目 マルの意味がない!
稲島 企業の回し者じゃないですし、他の物でも別にいいのです。この味や香りが好き、という商品であれば、効果や添加物を気にせず食べるのもありだと思います。しかし健康のため、という目的なら、無添加で甘味料も入ってない方が良いのでは?
夏目さんは最近、糖分を頑張って減らして体調が良くなったと言っているにもかかわらず、「健康のため」にヨーグルト風味の甘味料を定期的に摂取してしまっているなら…ちょっと、もったいないように思えます。
夏目 なるほど…。では先生の家のヨーグルトの素を分けてください!
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2016年07月22日 09:45
私も昨年までの二年間断酒するまで長年この思い込みに囚われて生きてきました。今はまたごく少量嗜んでいます。
■酒豪の筆者が、酒をやめて気づいた10のこと
宮崎智之 [フリーライター]
「わかっちゃいるけど、やめられない」のが、お酒の魔力
飲んでいなくても、飲み会を楽しめる
自他共に認める酒豪で、「酒をやめるくらいなら、死んだほうがまし」とうそぶいていた筆者が、3ヵ月前に酒を断った。アルコールによって体を壊し、医者から断酒を説得されたためだ。
基本的には365日、休みなく飲んでいた。休肝日という発想はなく、仕事がない日には昼間から飲んでいたことも度々だ。家系は酒飲みばかりで、同じく体を壊した親戚も多い。「お日様が沈むまでは、飲んではダメ」という母からの忠告も、上の空で聞いていた。
そんな調子だったから、まさか自分が酒をやめられるなんて思ってもみなかった。というか、酒のない生活が、どういったものなのか想像もつかなかったのである。
適度の飲酒は、コミュニケーションを円滑にするなどのメリットがある。しかし、過剰に飲み過ぎれば、筆者のように体を壊すリスクが高まるほか、問題行動を起こしたり、人間関係にひびが入ったりして、社会的信用を著しく損なう事態に発展することもある。
ここ数年を思い返しただけでも、数々の悪行を犯してきた。財布をなくして一文無しになり、友人にお金を借りたこともあったし(そして、そのお金でまた酒を飲むわけだが)、記憶をなくして路上で寝ていたこともあったし、「絶対に言ってはならない暴言」を酒の勢いにまかせて口走ったこともある。連載のタイトルではないが、「めんどい人々」の一員になってしまっていたのだ。同じような心当たりがある人もいるのではないか。
問題なのは、「わかっちゃいるけど、やめられない」ことだ。筆者が、まさにそうだった。
しかし、今となってみれば「○○だから、絶対に無理」と言い訳にしていた理由のほとんどが、思い込みだったことがわかる。むしろ、酒を飲み続ける口実として、そう思い込もうとしていた節があるように感じる。まだ断酒して3ヵ月と日が浅いものの、酒をやめたくてもやめられない人のために、筆者が気づいた10のことを紹介していこう。
酒をやめると、意外に良いことが多いのだ。筆者のようにドクターストップがかかるまでいかずとも、「そろそろ、酒を卒業したいな」と思っている人にも参考にしてほしい。
「酒をやめられない理由」のほとんどは思い込み
・飲んでいなくても、飲み会を楽しめる
一番重要なことなので、真っ先に書いておきたい。このことが、最も驚いた発見だった。
酒を飲むと、気分が良くなり、楽しくなる。気が大きくなり、全能感が味わえる。普段よりも積極的な性格になって、いろいろな人と仲良くなれる。酒のない人生なんて、なんて空虚で華のないものだろう。死んだも同然だ。筆者は、そう強く思い込んでいた。
しかし、実際はそうではなかった。もちろん、酒をやめた直後は手持ち無沙汰になったり、酒への渇望感でイライラしたりするが、慣れてくればなんてことはない。飲んでいる人のテンションが上がっているのだから、それに合わせて自分も少しギアチェンジすればいいだけのことだ。もともと酒の場に慣れているので、楽しみ方は身についている。
むしろ、最近では、以前より酒の場を楽しめるようになった感じすらある。記憶が鮮明に残っているため、楽しい思い出の余韻は翌日まで続くし、気づかぬうちに失態を犯しているのではないかと気を揉むこともなくなる。人の話を、じっくり聞けるのも楽しい。
ついでにいうと、先日あるDJパーティーに参加した時、ノンアルコールビールを飲んでいたのだが、2本目を注文したところ、もう品切れとのことだった。周りを見渡してみると、ノンアルコールビールの瓶がそこかしこのテーブルに置かれていた。思っていたより、多くの人が酒を飲まずにその場を楽しんでいたのだ。これも一つの発見だった。
・「酒を飲むと、なにかが降りてくる」は幻想
筆者はライターを職業にしているため、常に企画を出さなければいけない。別に、ライターではなくとも、なんらかのアイディアを求められる仕事に就いている人も多いと思う。
そのプレッシャーもあり、酒を大量に飲んでしまうことが度々あった。酔っ払った頭に突然、企画が「降りてくる」と信じていたのだ。しかし、そうやって思いついた企画は、翌日に冷静な頭で考え直してみると、たいてい使い物にならない。ならば、初めから素面の頭で考えたほうが効率もいいし、そのほうがより尖った企画が出てくると感じる。
長年、脳がアルコール漬けだった著者にとって、素面の頭のほうがよっぽど「狂気」だ。酒になにか「特別なもの」を求める趣向の人は、そう発想を転換してみてはいかがだろうか。
また、人との会話の中で生まれるアイディアも同じである。筆者の経験によれば、「なにか面白いことを一緒にやりましょうよ」といった酒の場での話は、たいてい「面白いこと」にはつながらない。もっとも、片方が素面であるならば、アイディアがしっかり記憶され、その後の展開に変化が見られるかもしれない。今後はそれを楽しみにしている。
・酒を飲まなくても、普通に寝られる
もともと寝つきが悪く、ある時期から「酒を飲むと寝られる」と思い込んでいた筆者。そのことが酒を断てない大きな一因となっていたが、酒がない生活に慣れ始めた今では、普通に寝られるようになった。眠りも深く、夜中に起きてしまうこともなくなった。
はじめは慣れないかもしれないが、そのうち以前より快適な睡眠が得られるようになる。どうしても寝られない場合は、酒に頼るよりも医者に相談したほうがどれだけ建設的か。
酒をやめれば、バラ色の人生が待っている?
ここまでは、筆者が「酒をやめられない理由」として考えていたことが、いかに幻想かについて説明してきたが、以降からは酒をやめることで得られた「副産物」を紹介する。
・酒を飲んでいるときに沸き起こる感情は、本心なんかではない
これは2つ前の項目にも関連することだが、酒を飲んでいた時に感じていた不満や憤りは、本心なんかではない。酒を飲んで沸き起こってきた感情は、その場の空気に左右されていることが多く、よくよく考えてみるとどうでもいいことだ。ただの一時の感情に過ぎず、本心ではないように思う。
酒をやめてから些細なことで怒らなくなり、安定した精神状態を得られるようになった。愚痴っぽさがなくなり、前向きになった気がしている。
・二日酔いではない状態が、どのようなものか
毎日飲んでいたから当たり前のことだが、筆者は年中、二日酔いの状態で過ごしていた。「二日酔いではない状態が」どういったものだったのか、久しぶりに思い出して、頭と体の軽さを実感している。たとえるなら、「小学生の夏休みの朝」といった感じだろうか。
・お金と時間が節約できる
これも当たり前のことだが、思ったよりもずっとお金が節約できる。新生銀行が発表した「2016年 サラリーマンのお小遣い調査」によると、男性会社員の1回の外飲み代は、平均で5102円にものぼるそうだ。浮いた酒代で自分への「ご褒美」を買うのもいいだろう。ちなみに筆者は、今度、新しいデスクトップパソコンを購入する予定である。
また、酒をやめてから時間も有効的に使えるようになり、読書や運動などといった自分に投資できる時間も増えた。酒飲みが思っているよりも、1日の時間は長いのである。
・酒を飲まないと痩せる
筆者は専門家ではないため、医学的な根拠はないが、酒をやめて4キロほど痩せた。暴飲暴食がなくなったせいだろうか。さらに、顔色が良くなったと言われることも増えた。
・「お茶」という概念の存在
飲酒を続けていた頃は、「お茶」という概念が皆無だった。「人と会って話すなら飲む」。これが基本だったからだ。しかし、世の中には「お茶」という文化が存在する。東京には、美味しいコーヒーやデザートを出すカフェが多いことに、今さらながら気がついた。
・お酒を飲めない人の気持ちがわかるようになった
世の中には体質的にお酒を受け付けない人もたくさんいる。筆者は、そういう人の気持ちがまったくわからなかった。酒を無理強いすることはなかったが、「せっかく楽しい場なんだから飲めばいいのに」くらいに心の中では思っていた。しかし、今は違う。むしろ、彼らは同志だ。そして、もともとが酒飲みだったため、そちら側の気持ちもよくわかる。
飲めない側も、飲める側の気持ちも理解できる。最強のノンアル・ファイターになったのだ。
・記憶力が悪いのは、酒のせいではなかった
筆者は、人の顔や名前を覚えるのが苦手で、それらをすべて酒のせいにしていた。しかし、酒をやめた今でも、まったく治っていない。すべて酒のせいにするのは、酒に失礼である。自分の弱点にはしっかり向き合い、改善していかなければならないことを断酒から学んだ。
最後になったが、アルコール依存症は歴とした病気である。個人の性格や根性のせいにせず、どうしてもやめられない場合は、専門機関への受診をお勧めする。「断酒するなら飲み会の参加は禁止」と指導を受ける場合もあるそうだ。筆者は人間関係が変わるストレスのほうが高いと自身で判断したため、参加しても飲まずに済む方法を模索しているが、依存度によって変わってくると思うので、そこは医者の指示に従って決めてほしい。
筆者がこの記事で伝えたかったことは、酒がない生活は「死んだも同然」ではないということだ。酒のない人生も、けっして悪くない。酒のない人生を、楽しんでほしい。自身や周囲の人の飲酒に悩みを抱えている人にとって、少しでも参考になれば幸いである。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2016年07月20日 10:09
立ち向かうのではなくしなやかに受け流す。。。
■心が強い人は「無感情」を習慣にしている 簡単!マイナス感情はこうしてリセットする
梅雨から夏にかけては、疲れがたまりやすい時期です。体の疲れ以上に、厄介なのが心の疲れ――ストレス、憂鬱、怒り、不安。「癒したくても、癒し方がわからない」ことが、一番の問題です。
しかし、2500年前にすべての苦悩から解放された、あのブッダなら、答えを知っています。
日常のちょっとした工夫で、心の疲れをきれいさっぱり洗い流すには――。中卒→大検→東大→永田町シンクタンク勤務→インドで得度という経歴を持つ独立派の出家僧・草薙龍瞬氏(近刊に『これも修行のうち。』がある)が、その秘訣を語ります。
ストレスや憂鬱は、現代人にはつきものです。欲や怒りを刺激する情報はあふれているし、苦手な人づきあい、気の進まない仕事・残業も次々にやってきます。特に4月から変化が続いたあとの梅雨の時期は、いっそう心が重たくなる季節です。
しかし「何事にも、きっと方法はある」というのが、ブッダの考え方。ストレス・憂鬱を上手に解消して、心を軽くしていく方法を“メンタルヘルスのエキスパート”ブッダは教えてくれます。
悩みの最大の理由は「マイナスの感情」
心が疲れる最大の原因は、「マイナスの感情」です。ムカついたり、緊張したり、落ち込んだりといった負の感情におそわれると、やる気を失い、物事に集中できなくなります。
こうしたとき、多くの人が「元気を出そう」「楽しもう」と考えます。「憂さ晴らしにお酒」とか「ストレス解消にスイーツを」とか。「気分転換についネットサーフィン」が、定番の人もいますね。
ただ、これだと効果は一時的ですし、度をすぎると健康を害したり時間をムダに使ったりします。ネットサーフィンで余計にストレス・モヤモヤが増す、というのはよくある話です。
ブッダなら、まったく違う発想をとります。マイナスの感情を癒す秘訣は、驚かれるかもしれませんが、「感情のない状態をとりもどす」ことなのです。
つまり、怒りも喜びもない“ニュートラルな”精神状態――ここに戻れるようになったら、心は劇的に健康になります。詳しく説明しますね。
感情のないニュートラルな状態がなぜ大事かというと、それが「心の基本」だからです。
実は、感情には3種類しかありません。つまり、
①快の反応 ―― 喜び・うれしさ・楽しさなど
②不快の反応 ―― 怒り・不満・憂鬱・くやしさなど
③快でも不快でもない“ニュートラルな”状態
このうち、人が追いかけるのは、①の快=喜びの反応。食べる、遊ぶ、他人の評価・リアクションを求めて頑張るなどです。
もともと心には、承認欲も含めた「欲求」があります。だから人間は、つらいときや疲れたときでも「欲求の満足」を求めます。結果的にごく自然に「快の反応」――楽しいこと・快楽――を求めようと考えます。
しかし、快の反応は「長続きしない」もの、そして「すぐ元に戻る」ものです。
現実に引き戻されたとき、そこに待っているのは「不快な反応」です。仕事がうまくいかない、人間関係が苦手、人の目が気になる、失敗して落ち込んでしまう……。日々の生活の中では、不快な反応のほうがむしろ多いのが現実ですよね。
つまり私たちの日常は、「快を追いかけながら、実際には不快に反応してばかり」です。人はいつだって「感情に振り回されている」のです。
現代人は、感情の「反復横跳び」で疲れきっている
しかし、「快か、不快か」しかない日常は、かなり疲れます。昔学校でやった「反復横跳び」を思い出してください。端から端まで速足で移動する――人間は「感情」でも、同じことをやっています。
ムカッとして、楽しんで、褒められると舞い上がって、叱られると凹んで……こうした感情的な反応を、休むことなく繰り広げています。
怒って、喜んで、怒って、喜んで、の繰り返し。まるで反復横跳びではありませんか。しかも「真ん中」(ニュートラル)が抜けている(!)。これで心が消耗するのは、ごく自然ですよね。
家に帰ったら、鏡を見てみましょう。「疲れているな」と思ったら、「感情で反応しすぎているのかな」と考えてみてください。
「これからは、感情で反応しない。“ニュートラルな心”を大事にしよう」と唱えましょう。この発想が、これからの人生を変えます。ラクに過ごせる時間が増えていくのです。
ニュートラルな心に帰るプチ修行
では、感情のないニュートラルな心は、どうすれば育つのでしょうか。コツは、「感覚に意識を向ける」ことです。
そのスタンダードな方法は、深呼吸して、①鼻孔の感覚や、②おなかのふくらみ・縮みを感じ取ること。
最近、注目を浴びているマインドフルネスです。その元祖は、もちろんブッダです。【前回の記事:心が強い人が持つ「他人に反応しない」技術】
「感覚に意識を向ける」という発想は、いろんな形で応用できます。たとえば、
①手をグーと握って、パーと開く。その「手の感覚」を意識する。
②「吸う」を「1」、「吐く」を「2」と数えて、10まで数える(感情をリセットするために、50、100まで数えてもOK)。
③道を歩くときに、歩数を1、2と数えて、100までやってみる。
数を決めれば終わりが見えるので、集中しやすいかもしれません。スマホのタイマーを使うのもよいかもしれませんね。
「感情で反応しない。ニュートラルに帰る」ことを方針に、試してみてください。
ちなみに「感情がない」状態といえば、禅の修行僧や、試合に挑むアスリートを思い浮かべるかもしれません。
確かに、その場面の彼らに感情はほとんどありません。なぜならそれが「目的達成に欠かせない」からです。禅僧がめざすのは悟り。アスリートがめざすのは、最高の成果・勝利です。このとき「感情的な反応」は、邪魔にしかなりません。だからニュートラルな心境で、目の前のターゲットに集中しているのです。
こうした心掛けは、私たちの日常にも欠かせません。作業に集中する心。相手をよく理解する心。ムダな考えに気を取られない心。人前で緊張しない心。落ちこまない心――。これらは、仕事・プライベートに大きな力を発揮します。
こうした心の「土台」を作るのが、ニュートラルな精神状態なのです。
ニュートラルな精神状態に戻ることができれば、そこから「ポジティブな方向に」考えることも可能になります。元気も回復していきます。
多くの人が勘違いしていることですが、「ネガティブ」からいきなり「ポジティブ」にもっていこうとするのは間違いです。「ニュートラル」から「ポジティブな反応」に向かうことが、正しい(ムリのない)道なのです。
たとえば、梅雨の季節は、心の健康を回復するチャンスです。雨降りしきる日の駅のベンチに座って、「プチ座禅」をやってみましょう。目を閉じて、雨の音を聞きます。だんだんニュートラルな境地に入っていきます。
もし感情で反応するだけなら、「雨の日ってジメジメしてイヤだな」と思うかもしれません。でも「感覚を意識する」発想に立てば、「空気の潤い」を感じることができます。これは、緑深い禅寺で目を閉じているのと、実は変わらないのです。
ちょっとした心掛けで、心は劇的に回復する
感覚を意識できれば、気が滅入りそうになる梅雨だって心を浄化することに使えるのです。これぞプチ座禅。
他にも簡単に実践できることがあります。
これから猛暑に突入したら、コンビニの冷気に当たって気持ちをリセットする、冷やしたビールやスムージーで気分を変える。こうした日頃のちょっとした動作を「感覚を意識して」やる。そうすることで、マイナスの感情をきれいにリセットするのです。一年中いつでもできる、心の健康回復術です。
辛いことがあるのは、頑張っている証拠。そんな自分を、責めず、裁かず、感情で反応せず、そっと受けとめてあげましょう。そしてこう考えるのです――「きっと方法はある」と。
今回は「感情の疲れを癒す方法」を紹介しました。カギは「感覚を意識して、ニュートラルに帰る」こと。
さっそく練習して、これからの季節を乗りきっていきましょう。イザ、プチ修行!
[東洋経済オンライン]
Posted by nob : 2016年07月19日 18:44
自律神経の乱れは万病のもと。。。
■「自律神経」を整える6つの習慣
プレゼン技術など、スキルアップをしたいビジネスマンは多いのですが、「実力をつける」と同じように「今ある実力を100%発揮すること」の大切さと難しさに気がついている人は、残念ながら少ない。ご存じのように一流のアスリートは、コンディションの調整を怠りません。
スポーツトレーニングは、筋力アップや技術向上を図る「ストレングス」。疲労を取り、故障を治す「ケア」、そして持っている力を発揮するための「コンディショニング」。この3つのアプローチで成り立っています。
練習したことをいかに本番に結びつけるか。これはビジネスの世界でも同じです。100の実力を120に増やしても、70しか発揮できなければ、力がついたとはいえません。調子をあげ、実力を出し切る。コンディショニングのポイントになるのが自律神経です。
自律神経は体を活動させるときに優位になる交感神経と、逆にゆったりしているときに優位になる副交感神経からなります。この2つがバランスよく働くことで健康を維持しているのですが、健康だけではなく、自律神経が整っていてこそ、持っている力を発揮できるのです。アスリートは「ゾーン」という表現をしますが、これは本来、逆の働きをする交感神経・副交感神経がともに高まっている状態で、集中しているにもかかわらず、落ち着いて周りも見えている極限の境地です。
現代人は交感神経が活性化しっぱなしで、副交感神経が高まらない、常にテンパった状態にある人が多い。原因を一言でいえば、ストレス社会だからです。
自律神経を整えようと思っても、頭でコントロールはできません。自律神経へのアプローチ方法は体を動かす運動・行動です。自律神経が乱れない行動を心がけ、必要なときに交感神経や副交感神経を活性化させる方法をご紹介しましょう。
まず窮屈な服装は交感神経の働きを上げます。疲れが取れないときは、通勤時にはネクタイをせず、シャツの一番上のボタンも外して、ネクタイは会社で締めましょう。
シャツといえば、私は「基本的にシャツは白しか着ない」と決めています。服選びの時間が短くて済むということもありますが、ささやかなことでも、なにかを選択する行為はストレスを生みます。「考えるべき重要な問題」と、「考えることなくオートマチックに行動すること」を区別し、さほど重要でないことは徹底的にルール化し、オートマチックに処理する。余計なストレスを招かないというのは、自律神経を乱さないためにとても重要なことです。
これからの季節、外は猛暑、室内は冷房と温度差が激しくなりますが、これも自律神経を乱す要因です。涼しくても、気持ちいいこと=自律神経にいいことではありません。薄手のセーターを着るなどして、温度変化に対応しましょう。
嫌なことがあったら、ゆっくり階段の上り下り
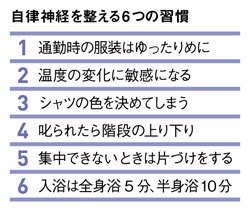
現代社会で、もっとも大きなストレスとなるのが人間関係。ビジネスシーンでも上司や取引先とトラブることがあるでしょう。落ち込んで、心がざわざわしたまま仕事に戻っても作業ははかどりません。上司に叱られた時点で自律神経は乱れ、コンディションは最悪です。
そんな状態では作業能率は上がらず、判断力も低下していますから、ミスを誘発するだけです。しかも、自律神経はいったん乱れると3~4時間は元に戻りません。結局、なにもはかどらず無駄な時間を過ごしてしまうことになります。
「気持ちを切り替えよう」と思っても効果はありません。メンタルの問題をメンタルで処理しようとしても無理です。そういうときこそ体を動かすべきなのです。いったん席を離れ、階段を1~2階分、ゆっくりとリズミカルに上り下りしてください。血流がよくなり、副交感神経の働きが高まり落ち着きます。ミスの後処理をどうするかなどの事後対策は、こうして体を動かしてから考えたほうが、いい方法が見つかります。
現代人はリラックス(副交感神経優位の状態)が苦手ですが、寝る前の正しい入浴は副交感神経を高めます。
湯は39~40度のやや温めにし、掛け湯をした後、ゆっくりと湯船に入り、5分間、首まで浸かります。次に半身浴を10分。これが基本です。半身浴で体を芯から温めると、お風呂から出たときの冷えを感じることが少ないので、温度差の影響を受けずに済むのです。
緊張を和らげるには
●副交感神経を活性化
(1)人さし指、中指、薬指の3本を使って側頭部からおでこ、顔の全体を、軽く触れる程度の力でやさしく叩く。
(2)手で三角形を作り、頂点がへその下に当たるように置く。4秒かけて息を吸い、8秒かけて息をすべて吐き切る。
やる気をアップするには
●交感神経を活性化
(1)足を肩幅ほど開いて真っ直ぐに立つ。頭の上で手首を交差させる。肩甲骨が内側によるのを意識し、息を吸いながら全身を上に伸ばす。
(2)次に息を吐きながら腹に力を入れ、上体を前にゆっくり倒し、ゆっくり吐きながら戻る。
小林弘幸(こばやし・ひろゆき)
順天堂大学医学部教授
[PRESIDENT online]
Posted by nob : 2016年07月19日 18:29
二人に一人が罹患し、三人に一人が亡くなる癌、、、今後ますます身近な病に。。。
■新規がん患者が初の100万人超 高齢化で増加 大腸・胃・肺が上位
国立がん研究センターは15日、2016年に新たにがんと診断される患者は101万200人、がんで死亡する人は37万4000人になるとの予測を発表した。新規の患者が100万人を超えるのは初めてで、高齢者の増加に伴い、発症する人が増えるとみている。
予測は、国や地域のがん対策の目標設定などに役立てるのが目的。患者数の予測は昨年より2万8000人増えた。実際の統計でも患者数は1970年代から一貫して増え続けているという。
予測された部位別の患者で最も多いのは、大腸がんの14万7200人。胃がん(13万3900人)、肺がん(13万3800人)、前立腺がん、乳がんと続き、上位5位は昨年と同じだった。男性
は計57万6100人、女性は計43万4100人。
さらに男女別でみると、男性の1位は前立腺で、胃、肺、大腸と続く。女性は乳房が最も多く、大腸、肺、胃の順となり、5位は子宮だった。
死亡する人は、昨年より3000人増加。肺がんの7万7300人が最多で、2位は大腸がん、3位は胃がんだった。
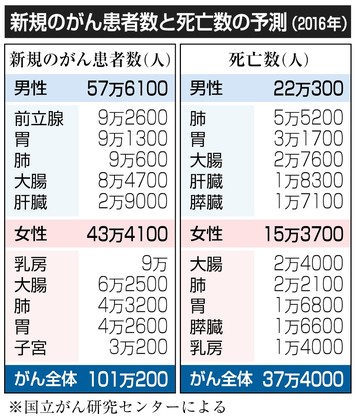
[東京新聞]
■がん新規患者100万人超す 国立がんセンター、16年予測
国立がん研究センターは14日、2016年に新たにがんと診断される人は100万人を初めて突破するとの予測結果を発表した。がんで今年亡くなる人は37万4000人で、過去最高になる。高齢化を背景に、30年ごろまで新たながん患者は増える見通しで、早急な対策が求められる。
実際の統計がまとまるまでに数年かかることから、同センターは毎年春に新規の患者数と死亡者数の予測を公表している。人口動態統計や全国がん罹患(りかん)モニタリング集計などをもとに算出した。
今年新たにがんと診断される人は101万200人で、昨年より約2万8000人増える。男性は57万6100人、女性は43万4100人。部位別では、大腸、胃、肺、前立腺、乳房の順に多かった。死亡者数は37万4000人で、昨年より約3000人増える。部位別では肺、大腸、胃、膵臓(すいぞう)、肝臓の順になった。今後、胃が減り、大腸と肺は増え続ける見通しだ。
米国がん協会が昨年公表した資料によると、米国では、死亡者が過去20年間で22%減った。1980年代にがん検診が普及し、早期発見されやすくなったためとされる。
東京大学の中川恵一准教授は「死亡数が減らないのは問題だ。がん検診の受診率を高めるとともに、生活習慣を改善してがんになりにくくすることも大事だ。そのためには学校での啓蒙が重要になる」と指摘する。
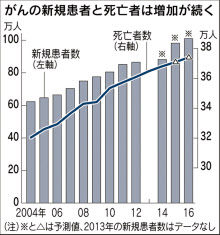
[日本経済新聞]
Posted by nob : 2016年07月15日 08:45
美しい水か美しい身体をつくる。。。
■肌荒れは水が原因? 水の質を変えて改善しよう!
肌荒れ悩みの盲点。それが、「水」。生きているものすべてに必要不可欠な水ですが、実は、肌荒れを引き起こす原因になることがあるのです。
●水が肌にもたらす影響
成人した大人の場合、約60%の水分で体が作られているいいます。老人になってもそれは10%程度しか減りません。私たちは一生を通じて、大量の水分を抱えて生きているのです。水の質が悪ければ、当然、肌のコンディションも落ちてしまいます。天然の水には、ミネラルなどの栄養分が豊富です。本来、体に取り込むべきはそのような水であったはず。
しかし、衛生などの問題もあって、日常で使うのは水道水が主流です。現在、水道水には消毒のために、微量の塩素が含まれています。塩素で刺激を受けると、弱い肌は荒れ始めます。それに気づかずに水道水を使い続けると、ダメージが回復するひまなく刺激が蓄積してしまいます。
アトピーの原因とも言われる塩素水。敏感肌でなくても、蓄積されたダメージで肌荒れを起こす可能性はあるのです。
●触れる水を変えて肌荒れを防ぐ!
一日のうち、直接水を肌につけるのは、まず朝の洗顔。手洗いや食器洗い、夜の入浴なども考えられます。その水を変えるだけで、肌荒れが止まることがあります。
もっとも簡単なのは、蛇口に装着するタイプの浄水器をつけること。また、お風呂では大量の水が必要になりますから、塩素除去にひと工夫すると良いでしょう。
お風呂に入れるだけで、塩素が除去できる物をご紹介します。
・ビタミンC(小さじ1杯程度)
・備長炭1~2kg
・セラミックボール
備長炭は入浴の1~2時間前、セラミックボールは30分ほど前から入れて、お湯を作っておくといいでしょう。塩素は蒸発しやすい性質があるので、汲み置きして半日~1日空気に触れさせれば自然と消えてしまいます。もし追い炊き機能がついているなら、入浴の6時間前くらいから水を張っておくだけでも効果があります。
ビンやボトルに詰めた水は空気に触れられないので、バスタブや洗面器など、口の広い容器でなければできませんが、時間に余裕があるなら、余計な光熱費もかからないオススメの方法です。
●飲む水を変えて肌荒れを防ぐ!
肌に触れる「外側の水」を変えたら、体を作る「内側の水」も意識してみましょう。まず、水道水をコップに注いですぐに飲むのはやめましょう。一度沸騰させれば塩素が抜けるので、湯冷ましを作っておいて、冷蔵庫にいれておくと便利です。
しかし、本当に体に良い水を摂りたいと思うなら、浄水器やウォーターサーバーを利用するか、ミネラルウォーターを購入してみてください。水は透明なので栄養も何もないと思われがちですが、体内では作れないミネラルを含んでいるのです。ミネラルウォーターで肌パックすれば、手触りが格段に変わるほど。
1日1.5~2リットル飲めば便秘の解消にもなりますから、飲む水を変えることで、デトックス効果も感じてみてくださいね。
記事提供/『エンジョイコンプレックス』
(R25編集部)
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2016年07月14日 11:38
常に最良の主治医は自分自身。。。
■医者に任せっきりの「二流患者」は損をする 最高の医療を受けるには「患者力」が必要だ
病院ランキングや名医ガイドのたぐいが相変わらず人気を集めている。だが、『一流患者と三流患者』を書いた米テキサス大学MDアンダーソンがんセンター永代教授の上野直人氏は、こうした風潮に異論を唱える。
同氏は、最高の医療を保証するのはランキングでもブランドでもなく、患者自身がいかに医療に参加するかの「患者力」だと力説する。
一流と二流、三流の違いは
──タイトルの「一流患者」「三流患者」とは?
医者と一緒に考え、治療を選択し、納得のいく治療を選び取れる患者さんを一流患者としました。それに対し、医者の言うことはすべて受け入れ、自ら考えることなしに一言「お任せします」の患者さんを二流患者、文句ばかりで病院との信頼関係を作れないモンスター患者を三流患者としました。最低限のことしか病院から引き出せず、本人が損するタイプです。
あえて一流、三流と呼びますが、その意図は患者間に優劣をつけることではなく、自分の患者力がどのレベルにあるかを見直して、よりよい医療を受けられるよう、スキルを上げることです。
──「お任せします」はもう通用しない?
自分の身を守るためにも、二流患者の物言わぬスタンスは、ぜひ改めてほしいです。新しい治療法や薬が出て治療の選択肢が増え、医療はどんどん高度化、細分化している。医者は膨大な情報と日々格闘しており、正直手いっぱいです。医者も人間。国家試験は医療従事者として最低限の能力を保証するものであって、運転免許証を持っていても自動車事故が起きてしまうのと同じ。丁寧な運転の人もいれば暴走癖の人もいる。この医者は大丈夫か、本当に自分のことを考えてくれているか、患者はつねに質問をぶつけて突っつくことが大切です。医者との会話で医者を試す、といってもいい。
この治療法でいいか、ほかの治療法はないか、組み合わせはどうか。自分の生き方に合った最適な治療を医者から引き出していくのです。
みんな遅かれ早かれ病院の世話になるときがやってくる。病気に向き合う準備を先延ばしにせず、たとえば風邪を引いて受診するときなど、今から練習を始めてほしいのです。
──まずは、この薬は何のための薬ですか、と聞くことからですね。
そう、とにかく質問です。何となく引っ掛かったら必ず聞くことを習慣にする。なぜこの病名か、なぜこの診断か、なぜこの検査をするのか、なぜこの薬か、なぜ効かなかったのか。Why(なぜ)をつねに問う。自分が直面している事実を理解するためです。専門用語の羅列でわからないなら、わからないとハッキリと言う。なぜ?を重ねることで、自分の理解も深まっていく。医者にとっては、質問が気づきのきっかけにもなります。見落としや別の可能性に気づいて、より多くの選択肢が提示できるかもしれない。
それから診察時には必ずメモ帳とペンの持参を。一言断って会話を録音するのもいいし、誰かに付き添ってもらって話の受け手を増やすのもいい。医者とのコミュニケーションは真剣勝負。一言も漏らさず聞くぞという意気込みでいきましょう。疑問は放置せず、その場でも次回でもよいので、必ず聞くようにしてください。
話を理解できたかどうか確認するのにいちばんいい方法は、自分が受けた説明を他人に話すこと。聞かされた側が要領を得ないようなら、自分がちゃんと理解できていないってこと。次回受診時に、医者相手に話して反応を見る。僕の場合は大抵僕のほうから聞きますね。どう、ちゃんと理解してる?ちょっと話してみて、と。これは必ずやります。
ネットで得た情報は医者と共有を
──病気の医学的な正式名を必ず聞くことも強調されていますね。
ネットで調べるとき、正式な病名で検索したほうが情報が精査されます。セカンドオピニオンを取る際にも意思疎通がスムーズになる。
それから、ネットで得た情報は医者と共有し、わからないところは医者に聞くようにしてください。僕の患者さんはネットで見たものをプリントアウトして持ってきますよ。僕もそれを歓迎していて、必ず情報共有しようと約束します。ネットで見つけたサプリメントや代替療法を試したいなら、その前に絶対見せてくださいと。プリントアウトを見ても判断がつかない場合は、自分でもサイトを見に行きます。そこまでするのが医療従事者の責任ですから。
──日米の差は患者力の差だと書かれていますが。
実際には米国の患者だって一流ばかりでは全然ない。ただ米国では、患者力を与えることが重要だという意識を医療側が持っていて、病院全体で患者を一流に引き上げていく仕組みというか、サポートが日本よりはある。まず医者が患者に質問を促します。小児科なら、子供の患者に対し「質問はないか」と必ず聞く。親がいると話しにくいなら席を外してもらう。そうやって医者に質問することが当たり前という感覚を育てていく。そうした中で、優れた患者がキャッチボールを通して育つ可能性が高いというだけ。
──日本ではまだ、躊躇してしまう患者も多いかもしれません。
でも、質問し情報を正しく把握することは、日常生活のあちこちでやっていることでしょう。医者に対してだけ、恐縮して言えないとか遠慮してしまうとか、聖域視する必要はないし、そんな神話はなくさないといけない。医者には説明責任が、患者には医者の言葉を理解しようとする責任があります。
医者が投げたボールをきちんと受け止め、しっかり投げ返す。説明下手だったり面倒がったりするような医者の悪投は「ちゃんと投げて」と投げ返す。大事なのはキャッチボールです。キャッチボールする理由の一つは、相手がまっとうな医者かどうかを見極めることでもある。
患者が要求しないから医者が変わらない
──何といっても「3時間待ち3分医療」の現実があります。
現状のシステムを変えるためには、患者側からの突き上げが必要です。医療側には大きなプレッシャーになる。10年経っても20年経っても何も変わらないのは、誰も要求しないから。もっと説明を受ける時間が欲しい、それが要求である、とわからせないといけない。動かすのは患者団体などではなく、やはり個々の現場です。消費者ベースの市場なのに、消費者が声に出さないから市場ニーズが低い状態のままなんです。
日本のモノやサービスの質が成熟しているのは消費者が要求したから。それと同じ。医療だけを聖域視するのはおかしい。現実に、患者とともに医療を進めていきたいと考える若手や中堅の医者はとても多くなっています。医者が患者の面倒を見る時代から、医者のよさを最大限引き出すために、患者が医者を試し育てる時代へと移行しているのです。
上野 直人(うえの なおと)/1964年生まれ。和歌山県立医科大学卒業。ピッツバーグ大学付属病院にて米国内科専門医取得。現在は腫瘍内科医として研究、臨床に携わ り、専門は乳がん、分子標的療法開発。チーム医療推進にも力を入れ、日本でも医療従事者と患者向けの教育活動を行う。著書に『最高の医療をうけるための患 者学』。
[東洋経済オンライン]
Posted by nob : 2016年06月25日 16:46
技術はもとより心と身体のセルフコントロール力に長けておられる、、、自律神経の切り替わりが迅速かつ円滑なのでしょうね、、、素晴らしい。。。
■トップクラスの心臓外科医が伝授“集中力を保つ”4つの秘訣
今や、残業するほど仕事ができないと思われる時代。限られた時間で最大の成果を出すには──。経営トップ、心臓外科医、3つ星シェフ……斯界のプロにそのテクニックを聞いた。
■30分の昼寝で頭がすっきり
日本の心臓外科医でトップクラスの手術数を誇るのが、埼玉医科大学国際医療センター心臓血管外科の新浪博士教授だ。年間の執刀数は300例を超えている。
「世界に出れば標準的な数ですよ」と新浪医師は謙遜するが、日本の心臓外科医の平均が年間30例ほどなので、その10倍以上は突出した手術数だ。
極めてデリケートな心臓手術を数時間、ときには10時間以上にわたって行うには大変な集中力が必要だろう。しかも、1日に1度しか手術しない外科医も多いなか、新浪医師は必要とあらば2度、3度の手術を平然とこなす。その疲労度は相当なものだと想像できるが、どの手術も集中力を切らすことができない大事なものばかり。彼の集中するための秘策は、なんなのだろうか。
1日数回の手術で集中力を維持する秘策は、「昼寝」だ。
「先の手術が終わって自分の部屋に戻り、ソファに座ってお茶や食事をしていると知らないうちに寝ています。ふと気がつくと30分から1時間過ぎていて、頭がすっきりしています」
手術と手術の間に少し寝るという方法は、新浪医師が順天堂大学の助教授時代に師事した天野篤氏から直々に伝授されたのだという。
「天野先生は、手術と手術の合間に少しでも暇があったら寝たほうがいいよ、とアドバイスしてくれました。天野先生自身も寝るのですが、みんなのいるところで寝るから誰もリラックスできない(笑)。だから私は自分の部屋に戻って寝るようにしています」
それにしても、すぐに寝られるというのは一つの才能だろう。昼寝だけでなく、夜の寝つきもすこぶるいいそうだ。そんな話を実兄でサントリーホールディングス社長の新浪剛史氏にするととてもうらやましがられるという。
「彼はよく『どうやったら寝られる?』と聞きます。逆に、どうして寝られないのかわかりませんね。寝られないならその時間をもらいたいくらいです(笑)」
集中力を高めるためには、新浪医師が習慣化している2つの“儀式”も役立っているようだ。
一つは手術前に必ず達磨にお祈りすること。
「別に宗教を信じているわけではありませんが、難しい手術も多いので、最後は神頼み、仏頼みだと思っています。小さいころから川崎大師にお参りしていた関係で、そこで買ってきた達磨を教授室に置き、『今日の手術もうまくいくようにお願いします』と手を合わせてから手術に向かいます」
もう一つの方法が、夜寝る前に翌日の手術のプランを考えること。
「電子カルテなどをパパッと見て、頭の中でプランを設計します。ここが手術のキモだなとか。それが集中力アップになるかはわかりませんが、決まったパターンに持ち込めるので、最初の手術が何時からで、次は何時からでとスケジュールが組みやすいんです。もちろんイレギュラーも起きますが」
新浪医師は自分で執刀するようになってからの約20年間、この習慣を繰り返してきた。年間300例を超すほどの実績があるので、それに裏打ちされたパターンは豊富なバリエーションを持つ。数が質を担保しているのだ。
プラン通りに手術が進む確率は「通常は95%くらいですが、緊急手術の場合でも80%くらい」とかなりの高率だ。
寝る前に明日の仕事のプランを立てておくことは誰でもできる。翌日スケジュール通りに仕事をこなすためには参考にすべき習慣だ。
■集中と弛緩のメリハリを
だが、いくら昼寝をしたり事前準備をしても、長時間にわたる仕事では集中力が途切れることもあるだろう。
新浪医師の場合は、長い手術の中にオンとオフを設けるという。たとえば心臓の手術は、冠動脈バイパス手術は人工心肺を使用せずにできるが弁の修復や大動脈の手術は心臓や大動脈の中にアプローチするため、人工心肺で患者の心臓をいったん止めることとなる。心臓が停止している間の手術は緊張感、集中力ともにマックスの状態だ。だが、その前後で体温を下げる時間や体温を戻す時間などがあるので、そこはあえてリラックスし、集中力のメリハリをつけている。それによって本当に必要なときに力が発揮できるのだ。
「3〜4時間の手術なら、高い集中力が発揮できるのは、そのうち1時間半ほどです」
一般のビジネスマンは、外科手術ほど緊張感が高まる場面はないかもしれないが、一つの仕事の中で集中すべき大切なところを見極めて、集中するところと気持ちを緩めるところをつくると、うまく集中力を維持できるのではないだろうか。
集中力を長く保つためにはやはり体力も必要だ。心臓の手術が何時間にもわたれば、その間は立ちっぱなしになる。
「最近、週に1度か2度、スポーツジムに通っています。これは兄貴の推薦でね。体力増進だけでなく、栄養面でもアドバイスがもらえるので食生活も改善できます。これはよい仕事につながっていくと思います」
いくらオン、オフのメリハリをつけても、基礎的な体力が不足していれば、集中力は途切れてしまう。日ごろから健康に留意し、体力を高めているからこそ、ここぞというところで最高のパフォーマンスを発揮できるのだ。
▼新浪博士流“集中力を保つ”4つのコツ
[1]昼食後やスキ間時間に寝る
少しでも暇があったら、本を読んだりテレビを見るのではなく、30分でも潔く寝る。そのことで頭がすっきりして次の仕事に集中できるように。
[2]前日の夜に段取りを考える
頭の中で翌日の仕事のプランを練ることで、優先事項がはっきりして、集中すべきポイントが明確に。他の作業効率もあがる。
[3]一つの仕事の中でオンオフを設ける
長時間作業となると、ずっと集中はできない。「ここが一番のキモ」と思われるところにあわせて集中力を高め、ほかでは少しリラックスする。
[4]ジム通いで基礎体力をつける
どんなに集中しようとしても、基礎体力がなければ続かない。新浪教授は実兄の新浪剛史氏推薦で週に1度か2度、ジムに通っている。
[PRESIDENT online]
Posted by nob : 2016年06月07日 15:48
呼吸・姿勢・歩行は、健康生活の根幹です。。。
■日本人の9割ができていない!?「正しい立ち方」
竹下雄真 [デポルターレクラブ代表]
「正しい立ち方」できていますか?
あなたは「胸を張って立ってください」といわれたら、きちんと胸を張れるだろうか。普段、デスクワークが多い人は胸を張っているつもりでも、うまくできていないことが多い。
そういう方が胸を張ろうとすると、胸やアゴが突き出ていたり、お腹が出てしまうこともある。正しい胸の張り方をしている人は、私から見ていてもかなり少数だ。
ここでは、ヨガの「ターダ・アーサナ」という直立したポーズをご紹介する。これは山のポーズとも呼ばれ、立位のポーズのベースとなる。
一見ただの「気を付け」の姿勢に見えるが、実際にやってみると体がグラグラして、まっすぐ立っていられないことに気付くはずだ。現代人は、まっすぐ長時間立つという習慣がなくなってきているのである。
仕事で疲れて家まで帰るとき、電車内では片方の足に体重を乗せて立っていたり、吊り革にだらしなくつかまっていたり、とまっすぐ立っている人は少ない。こういったところから体のゆがみが生じてしまう。
ターダ・アーサナでまっすぐ胸を張って立つ習慣をつけるだけで体のゆがみは取れ、心身ともに健康になっていく。
「正しい立ち方」=「ターダ・アーサナ」とはこれだ!
正しい立ち方(ターダ・アーサナ)とは、以下のとおりだ。
(1)足をそろえて、背筋を伸ばしてまっすぐに立つ。このとき、両足の親指の内側をつけ、足の指はぴったり床につける。
(2)内もも、おしりを締めて下半身全体を安定させる。両手は両脇に下ろし、肩に力が入らないように注意する。
(3)胃が引っ込むように鼻から息を吸い、肋骨を左右に開く。
このとき、頭が上からつられているように背骨をまっすぐにする。肋骨を左右に広げるように意識すると、胃が引っ込む。
(4)吐く息で背中が丸まらないように意識しながら、左右の足全体に体重を乗せたまま呼吸を繰り返す。
ポイントはまず、アゴが出ないようにすること。横から見て、耳たぶのラインから、肩の骨、腰の出っ張っている骨、くるぶしまでのラインがまっすぐになっていることだ。慣れないうちは壁に背中をつけて立ってみるといい。かかとを壁につけて立つと腰が前に出てしまうので、おへその下にある「丹田」を意識してグッとお腹をひっこめると背中がムリなく壁につくはずだ。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2016年06月07日 11:43
私も実践中、、、おすすめします。。。
■家にあるアレを使うだけ!ニキビを早く治すための簡単スキンケア
あのスキンケアでNO MORE!ニキビの悩み
疲れが溜まってしまった時、寝不足が続いている時、お酒や油っこいものを食べ過ぎてしまった時、太陽を浴びすぎてしまった時…など、必ずといっていいほど現れるのが「ニキビ」です。
そんな時に限って、大事な日を控えていたりすることが多く、焦ったことのある女性はたくさんいると思います。
でも、実はニキビは集中ケアをすればいつもより早く治すことだってできるのです。
今回はそのオススメスキンケアについてお話しします。
ニキビを良くするにはコレを使おう!おうちで簡単スキンケア
どこの家庭にもあるといわれるあのアイテムで、ニキビの箇所を集中ケアしましょう。
そのアイテムとは、「絆創膏」です。
まさに傷を守り、治癒する絆創膏ですが、実はニキビにもとても有効的だと言われているのです。
ニキビに薬を塗っても、一晩たつと寝相で薬が落ちてしまいがちですよね。
でも、絆創膏をしっかりと貼っておけばそれを防ぐこともできます。
また、ニキビはとても刺激に弱いです。
寝ている間に枕やシーツで無意識にこすってしまって悪化させている場合があるので、絆創膏を貼り守ってあげましょう。
では、早速ですが絆創膏を使ったニキビ集中スキンケアをしてみましょう!
やり方はとってもシンプルで誰でも簡単にできます。
1.顔全体をしっかりと洗顔し、顔の汚れを落とします。
2.ニキビの箇所に薬をしっかりと塗ります。
3.少しだけ乾いたところで、絆創膏をピッタリではなく、少しスペースの余裕をもたせ貼ります。
たったこれだけの3ステップです!
これなら苦労もせず、簡単に、そして誰にでもできますよね。
たった1つのニキビでも、女性にとっては命取りといっても過言ではないほど大きな存在です。
でも、これからは絆創膏を上手に使いニキビを一気に治し、美しい肌をキープするようにしましょう。
[美BEAUTE]
Posted by nob : 2016年06月07日 11:21
最善の主治医は自分自身、、、すべては自らのファイナルジャッジのためのセカンドオビニオン。。。
■「がん」の診断は、そんなに簡単なものではありません~ある病理医の警告
がんで死亡する人の数は、日本で年間36万人を超える。これは年間総死亡数の3割に当たる数だ。がんの治療法や向き合い方についての情報は氾濫しているが、しかし、がんであるかどうかの診断がどのように行われているかについては、あまり知られていないのではないか。
がん治療といえば、手術を行う外科医や、放射線治療を担当する放射線医などをイメージする人が多いだろう。そうした治療の根拠となる大事な医療が、「病理診断」だ。
例えば患者にがんの疑いがもち上がった場合、疑わしい部分から採られた組織にガンがあるかどうかを診断する。それが「病理診断」である。そしてその診断を行う専門医は、「病理医」と呼ばれる。
この冬、フジテレビで『フラジャイル 病理医岸京一郎の所見』というドラマが放映された。2002年のドラマ『サトラレ』でも病理医が主人公として描かれたことがある。時々にそうした露出はあっても、いまだに病理医の認知度は高くはない。
病理医は、がん診断における「縁の下の力持ち」であると同時に、がんを見つけ出す「最後の砦」だと言える。そして病理医は、私たちとは違う角度から最前列でガンと対峙している存在なのである。
その「最後の砦」のひとり、国内外で活躍する病理医で医学博士である福嶋敬宜・自治医科大学教授が『振り回されない「がん」医療 病理医だけが知っている”本当”の診断最前線』を出版した。福嶋氏に、病理医の見るがん治療の最前線から、巷に伝わるがんに関する情報の危うさまで、話を聞いた。
――まず、「病理医」とは何をする医師なのか、教えてください。
病理医は、病院などで「病理診断」を行う医師です。全身の臓器や細胞、組織など患部の様子をミクロレベルで検査・診断し、患者を直接診療する担当医に病気の診断を与えます。医療における「司令塔」または「審判」のような役割をするのが病理医で、アメリカなどでは「Doctor’s doctor (医師のための医師)」と呼ばれることもあります。
病理診断は、病気の中でも特にがん診療との関わりが強く、重要な役割を果たします。病理医ががんを適切に診断しなければ、その後の治療方針も立てられませんし、間違った治療が行われることにもなりかねません。
――病理というと、組織を精査するだけでなく、病気で亡くなった方の解剖(病理解剖)をイメージしますが。
ご遺族の承諾を得て、病死した患者さんを解剖し、生前の診断の正確性や治療効果などをミクロレベルで細かく調べることもします。解剖して調べてみると生前の診断が間違っていた、ということもあります。
例えば、抗がん剤の投与でも小さくならないと思っていた肺がんの影が実際にはがん細胞はなくなっており線維の塊だけだったと判明したり、がんで死亡したと思っていたが実は病院内での感染症で死亡していたというケースもありました。
間違った認識が広まる危機感
――がんの場合、病理診断ではっきりと分かるものですか?
一目でがんと分かるものから、そうでないものまで色々あるというのが実際です。おそらく、一般の方が思われるよりは、腫瘍が良性なのか悪性なのか、判然としないものが多いと思います。だから、主治医がつける「臨床診断」が誤っていることもありますし、病理医同士でも病理診断に関する意見が分かれることもあります。
患者さんの中には、「担当医がいつもはっきり説明してくれない」、とか「診断もわからないのか」という不満をもつ人もいるようです。ですが、舞台裏では、病理医も担当医も様々な情報から、「病気の実像」を慎重に見極めようとしているのです。
――分かりにくいがんとはどんなものですか?
いくつかのパターンがあります。非常に珍しい病気の場合は、もちろん診断に手こずります。その他では、単純なことのようですが採取した病巣の部位がズレていると正しい診断に到達できません。CT画像などをもとに組織を採取してもがんの周辺部だったということは珍しくないのです。また、がんは進行しながら悪性度を増していくものが多いため、非常に早期にはがんかどうかの判別が難しい場合もあります。
――ということは、治療も個々のがんやその状況で変わるということですね。
そうです。がんの病理診断も単に「〇〇がん」というだけではなく、それぞれのがんで治療のために調べる細かい項目が増えてきています。さらに、患者さんの年齢や他の持病との兼ね合いなどでも治療法の選択は変わってくるでしょう。
ですから、インターネットで闘病記を綴ったブログなどもあふれていますが、鵜呑みにするのは危険だと思います。他人のがん治療などの情報が自分の場合に役立つのか否かの判断は、患者さん自身ではますます難しくなってきているからです。
もちろん発信者は善意で行ってらっしゃる場合もあると思いますし、心構えなどは参考になるかもしれませんが、その治療や経過などについてはあくまで一つの例だと思っておくのが無難でしょう。
――芸能人のがん闘病ニュースは大きな影響力があります。そういう報道を病理医の立場からどう見ていますか?
マスコミの影響力は本当にすごいと思います。それだけに、ニュースやワイドショーで情報を発信する側が、がんについて理解していないな、と感じるケースも時々あり、気になりますね。説明や用語の使い方が間違っていることもありますし…。
例えば、ある女優さんの訃報で、「血液検査でも見つけにくい10万人に1、2人の希少がん」と伝えられていましたが、こういう報じ方をすると、知らず知らずに「珍しいがんでなければ血液検査で見つけられる」と思ってしまうなど、誤った情報が刷り込まれていってしまう危険があるのです。このような積み重ねが、がんに対する誤解を生む原因の一つではないかと思います。
「食事でがんが治る」といったようなタイトルの本もたくさんありますね。さすがに「がん」が食事でなくなることはないと思いながらも、目にする頻度が高くなると、潜在意識の中に入り込んでしまうのではないかと危惧します。
「絶対」がないことの苦しさ
――病理医の視点から、がん治療で気をつける点は?
本著で一番お伝えしたいことは、がんの実像をしっかり把握しようとする事です。そこで大きな役割を担うのが病理診断であり、ここを押さえて初めて適切な治療に進めます。
病理医の岸先生を主人公にしたドラマ「フラジャイル」では、病理医と主治医は敵対関係のように描かれていましたが、実際には連携しながら行っています。また、岸先生のように「ボクの言葉は絶対だ!」と言えるほどの責任感は大切ですが、人の体に起こることに絶対はないのも事実です。
日進月歩の医療にも限界があることを理解しつつ、きちんと主治医などから情報を集めて、そのときどきの選択は自分で行うべきだと思います。どの治療を受けるとか、治療自体を受けないということも含めて。
――今注目されている治療とはどんなものですか?
免疫療法は国際的に注目されています。自分の免疫力を正常化させる免疫チェックポイント阻害剤「抗PD—1抗体」やがんのワクチンである「がんペプチドワクチン療法」などです。ただ免疫療法を謳ったものには怪しげなものもたくさんあるので、ここでも信頼できる情報を得ることが重要なのです。
福嶋敬宜
医師・医学博士(東京大学)、病理専門医・指導医
[現代ビジネス]
■がん治療「革命」の旗手!
夢の薬「オプジーボ」はこんなに効く
皮膚がんに続き、肺がんにも保険適用
人が本来持つ免疫力を利用してがんを退治する新薬が、がん治療の世界で革命を起こしつつある。一回の投与で100万円前後と超高額だが、効果は絶大。人類とがんとの闘いに決着がつく日は近い!?
副作用もほとんどない
「'13年の夏、太ももに大きなホクロのようなものができました。とくに痛くもかゆくもなく、近所の医者で診てもらいましたが、何だかわからなかった。
冬までそのままにしておいたのですが、今度は足の付け根のところにグリグリとしたしこりができた。これは何か変な病気だと思い、慌てて大きな病院に行きました。そこでメラノーマという皮膚がんだと診断されたのです。表面にできたものは手術で取れるけれども、奥のほうのものは手術できない、全部取るには足を切断するしかないといわれました」
こう語るのは千葉県在住の70代の男性。治療法で悩んでいるときに紹介されたのが、国立がん研究センター中央病院で免疫治療を積極的に進めていた山﨑直也・皮膚腫瘍科長だった。
「山﨑先生も、手術では全部取りきれないという判断でした。でも新薬があるからそれで治療しましょうということになった。その薬がオプジーボ(一般名:ニボルマブ)だったのです」
オプジーボを点滴投与し始めて約2年、男性のがんはCTスキャンでもほとんどわからないほど小さくなった。
「今は2週間に一度、病院で点滴をしていますが、副作用もほとんどなく、少し皮膚が赤くなってかゆくなることがあるのと、投与した日に眠気が出るくらいのもの。食事も美味しく食べられて、とても健康です」
腎臓がんにも適用が間近
がん治療の世界で、革命が起こりつつある。その革命の旗手になっているのが、このオプジーボという薬だ。前出の山﨑科長が語る。
「オプジーボが出てくる前は、メラノーマの治療といえば一にも二にも手術という風潮でした。手術で取れないときは、抗がん剤を使うしかなかったのですが、これが30年以上進歩していなかった」
オプジーボが最初に日本で保険適用薬として認可されたのは、'14年7月、メラノーマに対しての使用についてだった。メラノーマは、日本人では10万人に1人といわれる珍しい病気だ。
しかし、オプジーボが効くのは、メラノーマだけではない。
すでに昨年12月に厚労省は切除不能な肺がん(非小細胞肺がん)の治療にオプジーボの使用を認可している。肺がんの患者は、メラノーマの患者に比べて二桁多く、日本人の肺がんのうち85%は非小細胞肺がんなので、今後、がんの治療現場で本格的にオプジーボが使用されることになるのは確実。ちなみにメラノーマの患者3割、肺がんの患者2割に対してオプジーボが有効だとわかっている。
オプジーボの販売元である小野薬品工業広報部によると、すでにアメリカでは腎臓がんにおいても承認されているという。
「国内でも承認申請は終わっています。腎細胞がんについては新薬ではなく、効能追加という扱いになりますので、審査期間はそれほどかからない。年内にも承認される可能性があります」
がん治療の世界で、いま最も熱く語られるオプジーボとは、そもそもどのようなクスリなのか? 慶應大学医学部教授で先端医科学研究所所長の河上裕氏が語る。
「オプジーボは免疫治療薬の一種ですが、これまでのクスリとは、仕組みがまったく違います。これまでの免疫療法は科学的な根拠のない、効果の怪しいものがほとんどでしたが、オプジーボは科学的に効果があることが証明されている」
がんの治療には、がんになった細胞を切り取ったり、殺したりする局所療法(手術や放射線治療)と、クスリを使った全身治療(抗がん剤)がある。免疫療法は後者の治療法だが、いわゆる抗がん剤とは仕組みが異なる。
抗がん剤はクスリの力で直接がん細胞を殺したり、細胞の増殖を防ぐものだ。しかし、免疫療法はそもそも人体に備わっている免疫システムに働きかけて、自分の力でがんを退治させるという治療法である。
免疫力の「ブレーキ」を外す
かつてアメリカのジョンズ・ホプキンス大学に在籍し、オプジーボ開発前の基盤的研究に携わった国立がん研究センター・免疫療法開発分野長の吉村清氏が解説する。
「免疫というのは、病原体やがん細胞といった異物を排除する機能のことです。がんはジワジワと体の中でできていきます。そして、がんができていく過程で、本来がんを攻撃すべき免疫機能が弱まって、がんの存在を許してしまうのです。つまりがんから『返り討ち』にあうのです」
病原体やがんなどを攻撃する機能を担うのが、「キラーT細胞」と呼ばれる免疫細胞だ。体の中にがんができると、「体内にがんという異物ができた」という信号を受けて、キラーT細胞は自動車のようにアクセルを踏んでがん細胞を攻撃しようと近づく。
「ところが、がん細胞は非常に巧妙でキラーT細胞が近づいてくると、『攻撃の必要はない』という偽の信号を送って、攻撃の手をゆるめさせてしまうのです。このブレーキ作用が原因でがんは生き延びることができる。
従来の免疫療法は、キラーT細胞のアクセル部分を強化させようという発想で作られてきました。ところがオプジーボは、『どんなにアクセルを踏んでもブレーキがかかっていれば動かない。ならばブレーキを外してしまおう』という発想で開発されたクスリです。その結果、今までとは段違いによく効く免疫薬が生まれました」(吉村氏)
キラーT細胞はPD-1、がん細胞はPD-L1というブレーキ役の分子を持っている。この二つが手を結んでしまうと免疫チェックポイントが働き、攻撃にブレーキがかかってしまう。
オプジーボはこの二つの分子が結合しないようにする抗PD-1抗体を含む。そのため、オプジーボが効くと、キラーT細胞は偽の信号に惑わされずブレーキが解除され、アクセル全開でがん細胞を攻撃することができるのだ。
「免疫療法の有効性はこれまでずっと『眉唾もの』だと言われてきました。実際、効いていると思われる症例もありましたが、統計学的に有意な差がなかなか出てこなかった。
それがこの3年ほどで、ようやく免疫療法が本当に効く時代がやってきました。手術、化学療法(抗がん剤)、放射線に次ぐがん治療の第4の柱として認められたのです。
'13年には世界的な科学雑誌の『サイエンス』が、科学界における最も画期的な事象を決める『今年一番のブレイクスルー』に免疫療法を選び、一般的にも認知されるようになりました」(吉村氏)
まさに時代の最先端をいく夢の新薬。だが、このクスリを開発し始めて実用化にいたるまでは15年という長い年月がかかっている。当然、そのあいだに費やされた研究開発費は莫大なものになり、それが薬価に反映されることになる。
「オプジーボの国内販売価格は、100mgがワンボトルで73万円です。肺がんの場合、患者さんの体重1kgに対して3mgが必要になり、60kgの人であれば1回の投与あたりで180mg、約130万円の薬代がかかります。投与量は患者さんの体重とがんの種類によって大きく変わってきます」(小野薬品広報部)
仮に体重67kgの男性が2週間に1回、1年間の治療を続けた場合、かかる薬価は約3500万円にも及ぶ。
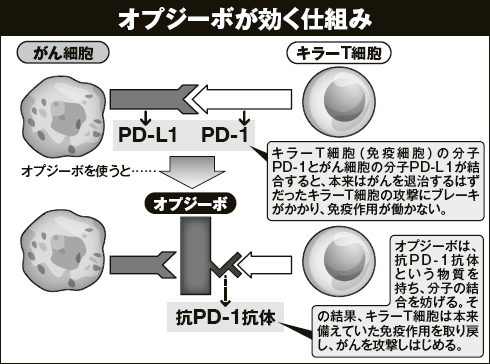
冒頭のメラノーマ患者は130万円分のオプジーボを2週間に1回、2年にわたって投与してきた。48回の投与で、計6240万円ものクスリ代がかかった計算になる。
あらゆるがんに効く!
もっとも、本当にこの金額を、患者が支払うわけではない。
厚労省が保険適用を認可しているクスリには高額療養費制度が適用されるので、患者は自己負担限度額を超える分は払う必要がないのだ。自己負担額は収入によっても異なるが、平均的には月15万円を超えることはまずない。
そうなると、患者負担分を除く3000万円超は国民の健康保険料から出ることになる。「薬価については、2年に1度見直しがあるので、今後、オプジーボの値段も変動する可能性があります」(小野薬品広報部)という声もあり、クスリが多少安くなることもあるだろう。
だが今後、オプジーボの保険適用範囲が拡大されることを考えると、新薬が国庫にかける負担は巨大なものになることは間違いない。
「'13年2月に経産省が発表した日本の再生医療や免疫療法の市場予測によると、今後、がんの免疫療法関連の市場がすべての医療分野の中で最も大きくなるだろうと見られています。'20年で950億円、'30年に1兆円、'50年には2・5兆円という具合です」(前出の吉村氏)
高額な薬価は今後、社会的に議論されるテーマとなるだろう。だが、どんなに高くてもがんが治るとなれば、それを求める人々の気持ちは抑えられない。前出の山﨑氏が語る。
「オプジーボはリンパがん、頭頸部がんなどあらゆるがん種に効くことがわかってきました。私は皮膚科としてメラノーマが治る時代がやってきたなと実感しましたが、今後、おそらく人類ががんを克服する日もやってくると感じています。
かつて抗生物質がなかった時代は結核を治療するのに、感染症であるにもかかわらず外科手術をするようなこともあった。現在、結核で死ぬ人がほとんどいなくなったように、がんも克服できるはずです」
医学は着実に進歩しつつあり、夢の治療薬が一般の患者でも使用できる時代がきた。がんを恐れる必要がなくなる日は、もうそこまで来ている。
[現代ビジネス]
Posted by nob : 2016年04月12日 14:51
白湯、、、私の暮らしにもなくてはならないもの。。。
■お湯を飲むだけ!「白湯」が健康に良いのは本当か
白湯(さゆ)とはある辞書の定義によれば「沸かしただけで何も入れない湯」のことだ。この言ってみればただのお湯を飲むだけで体調を整えることができるというのが、白湯健康法で、この数年静かなブームとなっている。
正しい白湯の作り方と飲み方とは?
白湯健康法、あなたも実践したことがありますか?
まず白湯の作り方。この健康法でいう白湯は、ただ沸かしただけではダメなようだ。水道水をレンジやポットではなく、やかんで10分から15分沸かすのが一般的で、沸騰したお湯は保温ポットなどに移す。
水道水ではだめという説、やかんに蓋をしてはいけないという説、ポットで沸かしても構わないとう説、など諸説ある。要は水道水を適当に沸かしてから、少し冷まして飲めばいいのではないか。
次は飲み方。飲める程度に冷ました150cc程度の白湯を、身体に負担をかけないため少しずつすするように飲むのが基本だ。特に朝起きて一番の白湯は、なるべくゆっくり15分程度かけて飲むこと。水分補給だけではなく起き抜けの身体を温める効果や、便通を促す効果、血液をサラサラにする効果があるという。
さらに一日3回の食事中にも同程度の白湯を、ゆっくりと飲む。これは身体を温め消化力を上げるためとされる。トータルで一日5杯から6杯程度が標準で、これより多いと(白湯健康法としては)飲みすぎということになる。
これらの効果から考えると冷え性や便秘気味の人、胃腸の弱い人、生活習慣病を予防したい人向けの健康法だ。だが加えて、いわゆるデトックス効果、ダイエット効果、免疫力を上げる効果もあるとされるので、万人向けのものともいえる。
なぜ“ただのお湯”が健康によいのか
ただのお湯を飲むことがなぜ「効く」のだろうか。白湯健康法について書かれた書籍では、次のような解説がなされている。アーユルヴェーダ(インドの伝統医学)では人間の身体も、自然界も「水」「火」「風」の3つの要素で成り立つ。水を火にかけることで火の性質が加わる。沸騰することにより気泡が出てさらに風の性質が加わる。つまり白湯は「水」「火」「風」の3要素を完全に満たすものであり、飲むことにより身体の3要素もバランスを取り戻すというのだ。
この説明ではよくわからない人も多いだろう。もちろん別の解釈も成り立つ。まず「水分補給」そのものの効果だ。厚生労働省が昨年から展開している「健康のため水を飲もう」推進運動はその名のとおり水分補給を促すものだ。
熱中症や中高年に多い脳梗塞・心筋梗塞などは、水分摂取量の不足が大きなリスク要因だ。これら脱水による健康障害や重大な事故などの予防として、件の厚生労働省の運動では寝る前、起床時、運動時やその前後、入浴の前後、のどが渇く前などの様々な機会でのこまめな水分補給を奨励している。
さらに水ではなく湯を飲むことで水分補給の効果が高まる。内臓と手から身体を温めることで、胃腸が活性化されるし血行も良くなる。文字通りのウォームアップで、目覚めを促し気分転換にもなるだろう。また身体を温めることには(異論もあるが)代謝機能や免疫力を高める効果もあるとされるから、デトックスやダイエットはもちろん万病に効くということになる。
毎朝ゆっくりと白湯を飲む習慣、それ自体が効くという面もあるだろう。自然と早起きになるし、生活のリズムも整う。毎日の食生活などをトータルに見直す時間と気持ちの余裕も生まれる。結果として心身ともに健康に、という流れも考えられるのだ。生活のバランスを取り戻すという意味では、アーユルヴェーダの発想とさほど変わらない。
いずれにせよ白湯健康法は、手間も費用もさほどかからず、副作用も考えにくいという意味では始めやすい健康法といえる。何か健康法にトライしたいという人にはうってつけの存在である。
(工藤 渉)
[DIAMOND男の健康]
Posted by nob : 2016年03月26日 08:22
終わらない珈琲論議/如何なるメソッドも諸刃の剣、バランスこそがすべて。。。
■コーヒーは結局「1日何杯」なら健康的なのか
適量を守っていても「不健康」の落とし穴が
丸田 みわ子 :シニア野菜ソムリエ
10年ほど前には「体に悪い」と言われていたのに、近年はすっかり「健康飲料」として認識されるようになったコーヒー。コンビニ各社の販売合戦も手伝い、おいしいコーヒーをより気軽に楽しめるようになりましたね。
実際、「脳血管疾患や呼吸器疾患による死亡リスクが、毎日3杯のコーヒーを摂取することで下がった」という研究報告が、国立がん研究センターから出されています。これらの作用は、「コーヒーポリフェノール」とも呼ばれるクロロゲン酸によるものです。
ポリフェノール以外にも注目の健康成分が
クロロゲン酸は、摂取量については諸説ありますが1日500mgも摂取すると、血液をサラサラにしたり、体脂肪を燃焼したりという働きが高まると報告されています。これはマグカップで3~4杯分のコーヒーに含まれる分量。セブン-イレブンのホットコーヒーであれば、R(レギュラー)サイズなら3~4 杯、L(ラージ)サイズなら2~3杯といったところでしょう。
ただ、この分量に収まっている場合でも、飲み方によっては逆効果をまねくことがあります。健康を目指すうえで注意していただきたい点は、のちほど詳しく触れることにして、もう少しコーヒーの健康成分について解説していきましょう。
コーヒーの成分といえば、ポリフェノール以外に真っ先に思い浮かぶのが「カフェイン」ではないでしょうか。よく知られていることですが、カフェインには覚せい作用があるため、仕事の効率アップ、記憶力アップ、脂肪燃焼の促進などに効果を発揮します。
もうひとつ、「ニコチン酸」も健康にいいと言われる、コーヒーの代表成分です。「ニコチン酸アミド」とも呼ばれるこの成分、タバコに含まれるあの「ニコチン」とは、まったく別モノです。
コーヒー豆にはもともと「トリゴネリン」という成分が含まれていますが、豆が焙煎される過程で、これがニコチン酸に変わります。ニコチン酸の主な働きは、血液中の遊離脂肪酸の濃度を下げること。そのため、継続的な摂取は脂質異常症や動脈硬化などの予防につながります。
このようにコーヒーの健康効果が次々と明らかになっていますが、一方で以前から言われているとおり、コーヒーには「弊害」もあります。
先ほど「コーヒーは1日3~4杯が適量」と紹介しましたが、これを超える量を飲んでしまうと、カフェインが血液の生成を阻害するなどして、体内の各器官に疾患リスクが高まるという報告があります。特に心臓疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患が心配な方は注意する必要があります。
適量を守っていても、落とし穴が
コーヒーの飲み過ぎは精神面にも悪影響を及ぼします。カフェイン依存症は胃痛や吐き気だけでなく、不安、不眠、ひいては幻覚、幻聴に発展することもあるのです。
また、妊婦の方は、カフェインを摂り過ぎることで流産や早産、低出生体重児、発達障害のリスクが高まるとされています。摂取量が1日200mgを超えないよう、1~2杯に留めておくか、ノンカフェインのコーヒーを飲むようにしましょう。
そして忘れてはいけないのが、妊娠中の方以外でも、たとえ目安の3~4杯に摂取量を抑えていても健康を害する場合があるということ。コーヒーの健康効果の報告は、いずれもブラックコーヒーを調査対象としています。毎回砂糖をたっぷり入れていたりすれば、当然健康効果どころの話ではなく、糖尿病やメタボを引き起こす原因になりかねません。
とはいえ、砂糖を入れなきゃ苦くて飲めない……という方も多いことでしょう。そこで今回は、コーヒーの苦味をまろやかにしてくれるコンビニアイテムをご紹介。健康効果を手に入れつつ、オフィスでのコーヒータイムを楽しんでみましょう。
〈みわ子流、コーヒーにプラスワンすべきコンビニアイテム!〉
・はちみつ
甘くして飲んでいるという方は、砂糖をはちみつにチェンジしてみましょう。
はちみつは砂糖よりカロリーが低いうえ、「幸せホルモン」と言われるセロトニンの分泌を促すなどリラックス効果も抜群。カフェインとの相乗効果で、落ち着いた気分で仕事が進められるでしょう。
・牛乳、豆乳、アーモンドミルクなど
店頭でカフェラテをオーダーするのもよし、ご自分で淹れて牛乳、豆乳、アーモンドミルクを足すのもよし。砂糖なしでもまろやかにコーヒーが味わえるうえ、3点ともカルシウムを補えます。
・ココナッツオイル
ブームから少し時間が経ち、最近ではコンビニでも買えるようになりました。カップ1杯のコーヒーにティースプーン1杯程度を溶かすのが適量。
ココナッツオイルに含まれる中鎖脂肪酸は体内ですぐに燃焼して、体脂肪を燃やし、血管に詰まった脂質を溶かし出してくれます。牛乳や豆乳と混ぜても美味しくいただけます。
・黒砂糖、てんさい糖、ラカント
店舗によっては、腸の動きを活発にするオリゴ糖やミネラルが含まれる黒砂糖・てんさい糖が見つかります。ラカントはカロリーゼロの天然甘味料。この3つの甘味料ならコーヒーの健康効果を邪魔することなく、甘味も楽しめるでしょう。
朝の通勤時や仕事の合間に飲むコーヒーは、気分転換や眠気覚まし、集中力アップに必須アイテムという方は多いでしょう。コーヒーと上手に付き合い、さらに健康効果を高められれば、言うことなしですね!
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2016年03月16日 15:27
歯と歯茎のケアは身体づくりの礎。。。
■スペシャリストが明かす「歯のケア」新常識〜「口内フローラ」が健康に直結していた!
心筋梗塞、脳卒中にも効果あり
口の中に棲む多種多様な細菌。もしこの細菌たちのバランスが崩壊したら……待ち受けているのは恐ろしい病気の数々だった! 歯のスペシャリストたちだけが知る「口内フローラ」の秘密が明らかに。
菌が口から血管へ侵入する
「腸内フローラ」という言葉を近頃よく耳にする読者も多いはず。腸内細菌叢(そう)と呼ばれる多種多様な腸内細菌の集合体を指すもので、このバランスが悪くなると人間の体に様々な影響を及ぼすと、今注目を集めている。
だが、同じように細菌がたくさんいて、腸内以上に多くの病気と関連した場所があることは、あまり知られていない。
「体の中で唯一、日常的に細菌が体内に入り込む場所、それは口の中です。口内にある無数の細菌がバランスよく保たれた環境、すなわち『口内フローラ』の維持が何よりも健康の近道なのです」
こう指摘するのは、鶴見大学歯学部探索歯学講座の花田信弘教授だ。
口の中には約1000億個の細菌が棲んでいる。そのうち、歯が生える前の新生児期や乳児期から棲みついている菌が優勢な状態にある、赤ちゃんと同じような口の中が、健全な「口内フローラ」といえる。花田教授が続ける。
「虫歯や歯周病を口腔内の問題でしかないと侮ってはいけません。腸内と違って、口の中は細菌が容易に血管へと侵入できるのです。これを『歯原性菌血症』と呼びますが、これが種々の病気の原因になるのです」
歯原性菌血症——聞き慣れない言葉だが、これこそが今、口内フローラを破壊する「元凶」として注目されている症状なのだ。
一般的に歯の悪化に起因する症状といえば、歯肉炎や骨髄炎など歯の周辺部が思い浮かぶ。ところが近年、それまで無関係と考えられてきた病気と、歯原性菌血症との因果関係が認められ始めている。
「虫歯や歯周病などによって口腔内にできた傷口から侵入した細菌が、そのまま血管に入り込み、全身を巡ります。すると気づかぬ間に血管で炎症が起きて、動脈硬化を引き起こします。口の中から侵入した細菌が心臓の血管で血栓をつくると心筋梗塞が、脳なら脳卒中が起こってしまう、というわけです」(花田教授)
歯原性菌血症は命の危機にまで及ぶ。そのメカニズムはこうだ。
血管内に侵入した細菌が炎症を起こす。そこに血管を修復しようとやってきたLDLコレステロールが、活性酸素によって酸化し、悪玉コレステロールに変化。すると今度はそれを除去しようと、細菌を消化する能力をもつ細胞のマクロファージが集まってくる。
そうして凝集したマクロファージが死んで堆積すると、血栓がつくられる。結果的に、多くの病気の原因となる動脈硬化をもたらすのだ。
歯と認知症の密接な関係
そうはいっても、細菌が体内に侵入するのは何も口だけではないはず。たとえば冒頭で説明した腸内で同様の症状が起きることはないのだろうか。
結論から先に言うと、それはほぼない。口から入った細菌が腸とは比較にならないほど危険だと断言できるのには、れっきとした理由があるのだ。
「確かに腸内の血管に細菌が侵入することはまれにあります。しかし、侵入したとしても必ず肝臓に続く門脈という栄養分の通り道に合流するため、肝臓に運ばれた細菌は解毒されてしまうんです。だからそれほど心配する必要はありません。
一方、口の中から細菌が侵入する場合はこの門脈は通りません。したがって解毒されることもなく、直接体内へと運ばれてしまいます」(花田教授)
これだけでも十分恐ろしい歯原性菌血症だが、その影響は動脈硬化だけにとどまらない。なんと細胞内のがん抑制遺伝子の機能にも影響を与えるというのだ。
「これまでがんという病は発がん性物質や紫外線、ウイルスなどが原因で、細胞内の遺伝子に欠損・変異が起こり、がん化すると考えられてきました。ところが、歯原性菌血症による血管内の慢性的な炎症でも、細胞内の遺伝子が後天的変化を起こし、がん抑制遺伝子が機能を停止し、細胞のがん化が進行することが近年わかったのです」(花田教授)
こうした恐ろしい歯原性菌血症の大本にあるのが歯周病だが、その歯周病自体がどうやらアルツハイマー型認知症とも関係があるようなのだ。
波多野歯科医院の波多野尚樹院長が解説する。
「ものを噛むという行為は顔や頭の筋肉を動かしますが、これがポンプの役割となって脳に大量の血液を供給し、活性化させます。もし、歯周病などで歯がなくなってしまうとその働き自体が失われてしまい、アルツハイマー型認知症を促すとされています。
名古屋大学の研究グループがおこなった調査では、70歳後半の健康な高齢者の歯の本数は平均9本だったのに対し、アルツハイマー型認知症患者の歯の本数は平均3本という結果が出ています。加えて認知症の脳にたまるアミロイドβの増加も同様の研究で確認されています」
咀嚼による刺激が脳の劣化を防ぐということはすでに言われてきたことだが、口内フローラが保たれていないと認知症に直結してしまうリスクが生じるわけである。
唾液は副作用のない万能薬
口腔内細菌の増殖を許すことがいかに危険か分かっていただけただろうか。
それではどうすれば増殖を阻止できるのか。ここで威力を発揮するのが唾液である。竹屋町森歯科クリニックの森昭院長も唾液の重要性を示している。
「唾液は、副作用のない唯一の万能薬だと私は断言します。唾液には殺菌効果があり、口内環境を正常に保つのに大きな役割を果たします。この唾液が少ない状態、つまり口の中が乾燥してしまうと、細菌が増殖して虫歯や歯周病が起こりやすくなってしまうのです」
日頃から唾液について意識することは少ないだろうが、生活習慣によって唾液量は大きく変わってくる。唾液を増やす方法を森昭院長が教えてくれた。
「現代人の中には、軟らかい料理の増加による顎の筋力の低下や、運動不足に起因する肥満の影響などで、口呼吸を行う方が増えています。ところが、この口呼吸が唾液量を減少させる原因なのです。
そこでふだんからきっちり口を閉じ、深い呼吸を意識することで鼻呼吸をしましょう。また、唾液が出るためには副交感神経を活発化させることも大切です。入浴時には熱いお湯ではなく、38度くらいのぬるめのお湯に半身浴で浸かることをおススメします」
意外な習慣が唾液を少なくさせていることもある。スマートフォンを操作する姿勢もその一つだ。
「スマホをいじっているときは、うつむき加減でじっとしていますよね。こうすると唾液腺の出口が圧迫されて、唾液が出にくくなってしまいます。メールやゲームに集中していると、緩い過緊張状態に陥り、交感神経が優位になって、さらに唾液が出にくくなるんです」(中城歯科医院の中城基雄院長)
食事の習慣を変えるだけでも、口内の悪玉細菌を減らすことは十分に可能だ。その方法とは糖質中心に偏っている食生活から脱却することにある。
「砂糖などの糖類が虫歯といった歯の病気に影響すると考えがちですが、それは小児期まで。成人以降はむしろ白米の主要成分であるデンプンなどの多糖類も歯に悪い影響を与えます。
多糖類は加熱された状態で口腔内に入ると、唾液により麦芽糖に分解されますが、これが悪玉細菌にとっては絶好のエサになります。白米に加えて、雑穀米や未精製の玄米などを積極的に取り入れてください」(前出の花田教授)
白米を我慢するのは辛いという人は、食べた後こまめに歯みがきしたほうがよさそうだ。
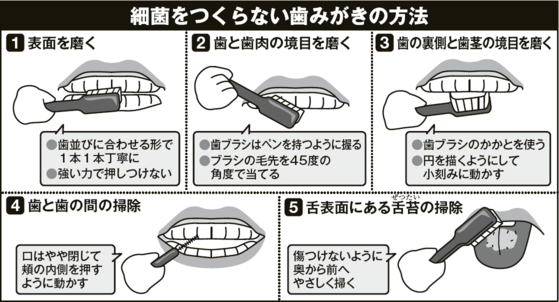
最先端の口腔ケア
では、その歯みがきの方法だが、正しくみがくかどうかで口内フローラの状態はまるで異なってくる。
ポイントとなるのは歯の表裏だけではなく、左右、つまり「歯のすき間」も加えた4面をきちんと磨くこと(上図参照)。歯ブラシでは磨けない歯のすき間には歯間ブラシやデンタルフロスが必須になってくる。
歯だけでなく、舌にも細菌は潜んでいる。特に舌の表面に付着した「舌苔」と呼ばれる汚れも歯ブラシで掃除する習慣をつけることも忘れずに。
正しい歯みがきの仕方を覚えたら、タイミングにも気を付けよう。
「歯みがきのタイミングですが、極端に言えば磨けるときに何度でも磨くべきです。必ず食後に磨かなくてはいけないわけではありません。大切なのは菌の数を減らすことなので、食前でも構いません。歯茎から血が出ても菌の除去のため、血が出なくなるまで磨きます。
ただし就寝前には必ず磨いてください。就寝中は菌が増えますから、その前にできるだけ菌を減らしておくのが重要になります」(前出の波多野院長)
最後に最新の口腔ケアを紹介しよう。それが「3DS」(「デンタル・ドラッグ・デリバリー・システム」の略)という治療法だ。開発者でもある前出の花田教授はこう解説する。
「毎朝、歯みがきのかわりに、歯型をとって作ったマウスピースに殺菌消毒薬を塗布して5分間装着してもらう方法です。この3DSで連日歯の表面を除菌していくことで、虫歯菌も歯周病菌も取り除くことが可能になります。また除菌効果は、一般的な歯みがきの数倍長持ち。前述の歯原性菌血症の予防にも絶大な効果を発揮しますよ」
健康保険はまだ使えないため、歯のクリーニングとマウスピースの作製および各種検査で、合計費用はやや高めのおよそ10万円程度。現在全国約200ヵ所での受診が可能となっている。
口内フローラを健康に保つことが全身の病気予防になる。誰もが知りたかった長生きの秘訣は、「歯」にも隠されていたのだ。
[現代ビジネス]
Posted by nob : 2016年03月14日 15:24
今さらですが、、、Vol.4/自律神経についてVol.3
■心も体もよい状態にシフトできる。自律神経の調整方法(おうち編)
だるい、寝付きが悪い、朝起きられない......。こんな症状はありませんか? 単なる疲労と片付けないで。ひょっとしたら自律神経が乱れているせいで起きている不調かもしれません。詳しいお話を自律神経研究の第一人者である小林弘幸先生に伺いました。
「#1 自律神経とはどんな働きをする神経なの?」、「#2 自律神経の調整方法(オフィス編)」に続く今回は「自律神経の調整方法(おうち編)」をご紹介します。
●過去や未来に想いを馳せる「3行日記」でチャージ
「3行日記」でストレスを客観視する
自律神経の働きについては、#1でご紹介しましたが、交感神経が優位になることがイライラにつながります。
心の状態を文章にして客観的に見つめることで、スーッと冷静になることができるのだそう。このとき、気をつけるポイントは、自分を偽ってきれい事ばかり書かないこと。日記の中まで自分を作っていると精神的にキツくなります。少し言葉が汚くなっても構わないので、正直にストレスを書き出してみましょう。
「3行日記」を続けるコツ
「3行日記」のつけ方はとても簡単。下記の3つを簡潔に書くだけです。
(1)今日1日失敗したこと
(2)今日1日感動したこと
(3)明日の目標
実際に「3行日記」を続けている小林先生に続けるコツと活用方法を伺いました。
「日記は継続しなくてはならないのでプレッシャーに感じてしまうかもしれませんが、忘れた場合は次の日にまとめて書いても構いません。あまり難しく考えずに、気軽に書いてみましょう」
「毎日書かなきゃ」と考えると億劫ですが、次の日にまとめて書いてもいいやと思うと気持ちが楽ですね!
「私は3年間継続して書ける日記帳を使っています。時折読み返して、自分の状態を確認できますよ。どれだけ成長したか確認できるので便利です」
折に触れ読み返せば、成功パターンや失敗パターンも見えて、自分を冷静に分析できますね。自律神経が整うだけでなく成長も実感できる3行日記。気軽にはじめられそうです。
●静かに自分を見つめる「瞑想」
最近話題の瞑想も、自律神経を整えるのに効果的です。眠る前や朝起きてすぐなど1日のうちで時間を決めて、3分間目を閉じてみてください。部屋の明かりを暗くして、静かに自分を見つめます。不思議と心が落ち着くはずです。
小林先生も眠る前に3分、目を閉じて1日のことを振り返るのを習慣にしているのだそうです。自分が実践しやすいタイミングで取り入れてみるのがよさそうです。
●ぬるめのお風呂にゆったり入るのが効果的
1日の終わりにお風呂につかるのも自律神経を整えるのによい方法です。39~40度のお湯をお風呂に張り、そのままじっくりと浸かります。お湯の量は、みぞおちがつかる程度の半身浴がよいそうです。
ぬるめのお湯は体の芯まで温めてくれるので全身ポカポカ。このとき軽いストレッチを取り入れると、さらに血行が良くなって◎。体が心地よく温まったらそのまま眠ります。きっといつもよりぐっすり眠れるはずです。
●無理は禁物、スポーツは楽しめる範囲で
スポーツも自律神経を整えるよい方法ですが、からだによいからといって無理にはじめないのが続けるコツ。
「どんなことでも「〜しなければならない」と思いはじめると辛くなります。自分が心地よいと思える範囲で好きなスポーツを楽しんでください」と小林先生。
●自律神経を整える「音楽」を聞く
人間の脳は、本能的に音楽を「快」と感じるようにプログラムされています。そのため、音楽を聞くことだけで自律神経も整うのだそう。「自分の好きな音楽をよく聞いている」という人は、心に余裕がある状態なんだとか。たしかに反対に不安や心配事があると、音楽を聞く気になれませんよね。
そんなときでも聞きやすいのが自律神経を整える音楽。小林弘幸先生の著書『聞くだけで自律神経が整うCDブック』(アスコム)には、自律神経を整えることを目的として作られた音楽CDがついています。ヒーリング音楽とは違い、自分の過去や未来に想いを馳せることができる音楽。このCDは気分をしみじみさせるメロディーラインをリフレインさせています。それにより、次に来るメロディーを予想できるので、脳内でも過去や未来のイメージを喚起する部分が刺激されるような作りになっているのだそう。
CDを聴くだけで、交感神経と副交感神経の動きが活発になり、自律神経のバランスが取れます。毎日の生活でちょっと空き時間ができたときや、就寝前、満員電車にイライラしたときなどに聞くのがおすすめなんだとか。
●1日の終わりにホッとできる習慣を
日記をつける、瞑想をする、半身浴をする、音楽を聞く。どれも1日の終わりにほんのすこし時間があればできることばかり。特別な道具も技術も必要ありません。全部やろうとするのは大変でも、目を閉じて3分じっとしてみるだけ、3行日記をつけるだけなど、少しずつならできそうな気がしませんか?
夜はインターネットやテレビをついダラダラと見てしまいがちですが、ときには早めに切り上げて、明日を充実させる準備をはじめることも重要です。日々のケアで自律神経の乱れを整えて元気を取り戻し、すこやかな毎日を送りたいですね。
お話を伺った方:順天堂大学医学部教授・小林弘幸先生
[MYLOHAS]
Posted by nob : 2016年03月07日 17:31
今さらですが、、、Vol.3/自律神経についてVol.2
■心も体もよい状態にシフトできる。自律神経の調整方法(オフィス編)
だるい、寝付きが悪い、朝起きられない......。こんな症状はありませんか? 単なる疲労と片付けないで。ひょっとしたら自律神経が乱れているせいで起きている不調かもしれません。詳しいお話を自律神経研究の第一人者である小林弘幸先生に伺いました。
自律神経の基本を伺った#1に続き、今回は「オフィスでできる自律神経の整え方と、ここぞというときの調整法」をご紹介します。
●切っても切れない間柄「呼吸」を味方につける
忙しく仕事をしていると呼吸が乱れてくる、ということがありませんか? 呼吸が乱れると自律神経も乱れます。しかし、ゆっくり呼吸をすれば、自律神経は整うというのです。
小林先生のおすすめは、「1対2の呼吸」。
「ゆっくり息を吸ったら、その倍の時間をかけてゆっくり息を吐いていくだけです。このとき、口からでも鼻からでも良いのであまり気にせず、リラックスをして行うことが重要です」
呼吸を整えるのは、乱れた自律神経を整える最も手っ取り早い方法。ちょっとした隙間時間に試せます。
●仕事や家事もゆっくりとした動作で
仕事や家事をするとき、時間がないと急いでいるとついつい動作が荒っぽくなってします。そんなときは、意識的にゆっくりとした動作に切り替えてみます。動作同様、喋り方もゆっくりにすると、自分のベースが整い呼吸も穏やかに。また、少し立ち止まって深呼吸をするのも効果的だそうです。
●イライラしたらタッピングで自分を取り戻す
机の上などトントンと一定のリズムで叩くタッピングも◎。イライラしてきたら、片手でタッピングをしてみましょう。これなら、仕事や家事をしながらでもできるのでお手軽ですね。
●無理して苦手な人と付き合わない
誰でも、苦手な上司や同僚は少なからずいるもの。仕事でのやり取りは社会人として必要なことですが、飲み会やランチの時間まで無理してお付き合いしていませんか? 苦手な人となるべく付き合わないのも自律神経を整えるのには重要なことです。
一方、友人とのお付き合いなら安心と、馴れ合いでダラダラ会ったりしていませんか? いくら好きな人でも目的もなく会うと逆に疲れて自律神経を乱してしまうのだそうです。
「時間を自分のために使う」「会いたいと思わなければ付き合わない」というのも大切なこと。心当たりのある人は、気をつけてください。
●「ここぞ!」というときの調整法
「明日はプレゼン」「会議で発表しなくてはいけない」など、「ここぞ!」という時の調整法を小林先生に伺いました。
「そういう特別な場では、『意識を変える』ことが緊張を解きほぐします。たとえば、その部屋にある時計を探すなど
一旦意識を変えることで呼吸が深くなります」
小林先生も、「ここぞ!」という時に実践されている方法なのだそう。ぜひ参考にしてみてください。
●自律神経の乱れは日々の積み重ねでリカバリー
「自律神経を整える」と聞くと、特別なトレーニングが必要と感じていましたが、じつは手軽な方法で整えられることがわかりました。毎日意識して、ちょっとだけゆっくり動いてみる。会社の休憩中に深呼吸をしてみる。など、ほんの少し心がけるだけで効果があるようです。
どれも本来の自分の力を呼び戻せる手軽な方法。いまから少しずつ実践してみてはいかがでしょうか?
お話を伺った方:順天堂大学医学部教授・小林弘幸先生
[MYLOHAS]
Posted by nob : 2016年03月07日 17:25
今さらですが、、、Vol.2/自律神経について
■目指すは心も体も心地よい私。自律神経研究の第一人者小林ドクターに聞く自律神経の整え方
だるい、寝付きが悪い、朝起きられない。こんな症状に悩まされている人は要注意。単なる疲れではないかもしれません。
最近、私も同じような症状が気になり、興味を持って調べたら「自律神経の乱れ」が招く体の不調にあてはまり......。でも、自律神経について何も知りません。そこで自律神経研究の第一人者である小林弘幸先生にお話を伺いました。
今回は、自律神経についての基本的な疑問に答えていただきました。
●自律神経の働きとは?
最近、自律神経という言葉をよく耳にしますが、どんな働きをする神経なのかわからない人も多いのでは? そもそ自律神経とはどんな働きをしているのでしょうか?
「自律神経は、心臓や腸、胃、血管などの臓器を24時間休まずコントロールしている神経です。交感神経と副交感神経という2つの神経が、綱引きのように両サイドから影響しあって臓器の動きを調整しています。
たとえば血管の動きですと、交感神経が血管を収縮して心拍数や血圧を上げます。一方、副交感神経は血管を拡張させて心拍数や血圧を下げます。このような反対の役割を持つ2つの神経がうまくバランスをとりながら、ちょうど良い心拍数と血圧に調整しているのです」
●交感神経はアクセル、副交感神経はブレーキ
自律神経は交感神経と副交感神経の2つが影響しあってうまく、臓器をコントロールしているのだということがわかりました。では、どのような状態が良いバランスなのでしょうか?
「交感神経はアクセル、副交感神経はブレーキのような役割をしています。緊張する場面では交感神経が優位になり、夜間などゆったりした場面では副交感神経が優位になります。両方のバランスが高いレベルでキープされているのがベストな状態です。日中は交感神経が、夜間は副交感神経が少し高くなるぐらいが理想です」
●自律神経のバランスが崩れると起こる症状
緊張するシーンが多い現代人は、交感神経が高い状態が続き、副交感神経の機能を落としバランスを崩してしまいがち。このような悪い状態が続くと以下のような症状が出てきます。
・冷え
・疲労感
・むくみ
・イライラ
・肌荒れ(ニキビ、吹き出物、カサカサ肌)
・自律神経失調症
さらに私たち30~40代の女性は、めまいや火照りなど更年期障害に近い症状が出てしまうこともあるそうです。
●うつと自律神経失調症は違うの?
自律神経の乱れが原因で起こる自律神経失調症と、最近メディアでよく取り上げられるうつ病。この2つの病気には関連があるのでしょうか?
「全くの別物ではありません。自律神経失調症はあらゆる不調の前兆です。放っておくと、うつに繋がる可能性も大いにありますよ。サインは、朝起きられない、慢性的な体調不良など。冷え性も自律神経失調症の前触れです」
朝ベッドから起き上がれない人は要注意ですね。
●自律神経はセルフコントロールできる
自律神経を整えるにはどのようにすれば良いのでしょうか? また、自分でコントロールできるのでしょうか?
「生活を見直し、自律神経のバランスを整える習慣を身につければ自律神経はコントロールできます」と小林先生。
お話を伺った方:順天堂大学医学部教授・小林弘幸先生
[MYLOHAS]
Posted by nob : 2016年03月07日 16:17
今さらですが、、、/耳揉み、効きます。。。
■耳マッサージで体ぽかぽか!花粉症にも効くその効果
耳には沢山のツボがあり、耳全体を軽く揉みほぐしてマッサージをするだけで、体が温まるといわれています。しかし本当は体が温まるだけではなく、ダイエットや肩こり、花粉症までも効果が期待できるのだとか。具体的な方法と、どんな効果があるのかをまとめます。
●耳が硬いのはお疲れのサイン?
普段あまりマジマジと触る機会がない耳ですが、実は耳にはツボがたくさんあり、耳をもむだけでもいろんな効果が期待できます。ものは試しで自分の両耳を触ってみてください。もし冷たかったり、固いと感じたときは疲れがたまっているかもしれません。
●マッサージ方法
耳マッサージの方法は簡単! 耳全体を軽くもみほぐしてから耳をぐるぐる回すだけ。耳を包むようにやさしく触りながら、気持ちよい、と思うところを指で強く押していきましょう。すぐに、体がぽかぽかしてきたと感じられるはず。これは耳には110ものツボが集まっているそうで、耳への刺激はツボを通じて内臓に伝わり、体全体を活性化してくれるのだとか。
●耳マッサージの効果
耳マッサージは体が温かくなるだけではありません。その効果はダイエットや肩こり腰痛の改善、肌荒れや小顔効果、冷え性対策に目の疲れ、胃もたれや花粉症対策まで耳のツボを刺激することで効果を得られるそうです。それぞれの効果を最大限に得るためには、具体的に効果のあるツボの位置を調べて、そこを重点的に刺激するのが一番ですが、なんとなく耳のあちこちを押してみて、気持ちの良い場所を重点的に刺激するだけでも効果を期待できるでしょう。そして大事なのは続けること。3週間くらいから効果を実感しやすくなってくるので、飽きずに続けることが大事ですね。
●恋愛運も向上?
そんなバカな…と思うかもしれませんが、耳マッサージはデートの前にも最適です。耳マッサージを行うと、全身がぽかぽかしてきて代謝がよくなり、それにしたがって顔色もよくなります。そして耳もほんのり赤くなるのですが、人がドキドキしたり気分が高揚したときには、頬だけではなく耳たぶも赤くなります。このようなほのかに顔を赤らめた表情は、男性が本能的に可愛いと思う表情であり、思いがけず男性にもててしまうこともあるかも?
耳をもんだり押すだけで、びっくりするほど沢山の効果が期待できる耳マッサージ。これからの季節、冷え性などもつらくなるので、耳マッサージでこの冬を乗り切ってみてはいかがでしょうか?
(文・姉崎マリオ/考務店)
[R25]
Posted by nob : 2016年03月07日 16:06
パニック発症前には、肩甲骨から首、後頭部にかけての極端なこりが来ることから、私も自らの日常的な軽度首こりに着目してこのところ試行錯誤中です。。。
■原因不明の体の不調「不定愁訴」の原因は、ズバリ「首こり」だった
首のこりを解消して、全身の健康を取り戻す
首こりは「うつ症状」だけでなく、様々な体の不調をもたらす。ドライアイやめまい、胃の不調など、自律神経の変調から引き起こされる症状は驚くほど多い。いわゆる「不定愁訴」を改善させるためには、首のこりに着眼することが肝要だ。
監修:松井孝嘉・医学博士
(東京脳神経センター理事長)
構成:宇都宮ミゲル
不定愁訴は、広辞苑で調べると[明白な器質的疾患が見られないのに、さまざまな自覚症状を訴える状態]となっている。医学辞典(南山堂)をみても、[不定愁訴症候群はいわゆる自律神経失調症]と出ている。
そこで、同辞典で自律神経失調症を調べると[自律神経症状や不定の身体的愁訴が見られるが、十分な身体的検索を行っても症状を説明するに足る十分な器質的病変を見出せない全身倦怠、眩暈、のぼせ、冷え症、発汗、頭痛、頭重感、動悸、息切れ、胸部圧迫感、下痢、不眠など多彩であり、通常は複数の臓器、器官にまたがる多愁訴を示す。症状は質、程度とも変動しやすく、他覚的所見に比し自覚症状が強い]となっている。
「不定愁訴が今まで治せなかったのは、眼科、耳鼻科、消化器科、循環器科、整形外科、脳神経外科(神経内科)、精神科などのたくさんの症状が1人の患者さんに出現するので、どこの病院へ行っても受診した診療科だけの症状を少しやわらげる対症療法の薬を投与されるだけだったためです。体のどこに異常があって起こるのか分からないので、治すことができない難病でした。最近、多数の患者さんがいくつもの病院を訪れるのは、この難病が大きな原因の一つでした。世界中、どこの病院でも治せないのです。ところが、私の40年近い研究で不定愁訴の原因の一つは、首の筋肉にあることが分かったのです。首の筋肉は病気を起こさないというのが医学の常識だったのですが、これが誤りでした。今まで、治療法のなかった17疾患が首の筋肉が原因だと分かり治るようになったのです」(松井孝嘉医師、以下同)
「3年前の外来診療の日本の医療費は13兆5000億円でした。外来患者さんの4人に3人が不定愁訴のため、この医療費の4分の3が不定愁訴に使われたと考えられます。つまり、10兆1000億円が不定愁訴に使われたのです。これは国家予算の10%に当たります。そして、不定愁訴の治療法はないので、毎年10兆円以上をドブに捨てているのと同じだと言っても過言ではないのです。このほとんどが治せない不定愁訴の診療に関わった医師とナースの人件費と言えるでしょう。今の外来診療は、無駄ばかりと言われても仕方がない状態です」
首こりの解消できれいに消えていく、緊張性頭痛
うつ症状を感じる原因が、実は首こりにある。この事実にも驚くが、首こりはそのほかおよそ関係ないとも思える症状を多数、引き起こす元凶でもある。
「長年の研究と治療実績によって、首こりを原因とした主な体の不調は17にも及ぶことが分かってきました。これらは、今まで治すことができなかったか原因不明の病気であったのです。うつ症状をはじめ、慢性疲労症候群、頭痛やめまい、パニック障害、ドライアイ、ドライマウス、多汗症、血圧不安定症など、その原因が首にあることはまだほとんど知られていません。特にパニック障害は治らなかったケースがないほど完治しています」
頭痛には代表的なものに片頭痛、緊張型頭痛、群発性頭痛の3種類があり、このうち緊張型頭痛は慢性頭痛の7割を占めるとされている。松井医師によれば、緊張型頭痛の原因はズバリ、首こり。つまり頭痛持ちの7割程度は、首こりを解消することで治せるというのだ。
緊張型頭痛の典型的な症状は、頭がキリキリと締め付けられるように感じたり、頭が重い、圧迫感を感じる、額や目の奥に鈍痛を感じるといったものだ。松井医師の病院ではこれを「頸性頭痛」と呼び、首こりを治すことで症状を劇的に完治させているという。
「首の筋肉の触診で34カ所をチェックしていますが、毎週チェックしていると、この中のCP-1というポイントの異常が消えると頭痛が消失することが経験的に分かってきました。その部位を解剖学的に研究すると、頭痛を起こす原因の神経である大後頭神経(首の2番目の神経)が頭半棘筋という筋肉の中央を貫通しているところだと分かりました。頭半棘筋が異常を起こして、固くなり、大後頭神経を締め上げることが緊張型頭痛の起こるメカニズムであることが分かりました。このことは第38回日本頭痛学会に報告してあります」
長年、薬でだましだまし頭痛を抑えてきた患者でも、首こりを改善することできれいさっぱり頭痛を解消できた例は多いとか。だが残念ながら、緊張型頭痛であるにもかかわらず、薬だけで対処しようとする医師が多すぎると松井医師は嘆く。
「全国に頭痛専門外来がたくさんできていますが、薬で一時しのぎの治療しかできておりません。東京脳神経センターでは、緊張型頭痛はほとんど完治しております。物心ついてから30年も50年も頭痛持ちで頭痛薬を手放せなかった人が生まれて初めて完全に頭痛から解放されて、涙を流して喜んだというケースが多数あります」
目が乾く、目が疲れるといった症状も、首の不調が原因かも
液晶画面を長時間、眺めることで涙の量が減り、目が乾くというドライアイ。この症状にも首こりが深く関わっていると松井医師は指摘する。
「パソコンを眺め続けるとうつむき姿勢になり、首こりになりやすい。そのことで副交感神経の働きが悪くなり、涙の量をコントロールすることが難しくなるのです。瞳孔を収縮させるのは副交感神経ですから、目が疲れるとかぼやけるといった症状が起きます。普段、感じている目の不調が、実は首のこりからきているケースは非常に多いのです。ドライアイは頚筋症候群の治療で90%治癒しております」
我々は、目を酷使しているから異常をきたしたと思いがちだが、こうした症状の背景には多くの場合、頚筋の異常による副交感神経の不調がある。ドライアイだからといってすぐ眼科に駆け込むのではなく、首こりを疑う方が得策かもしれない。
「近年、増え続けているVDT(ヴィジュアル・ディスプレイ・ターミナル)症候群も新疾患として発表された頃は、ディスプレイから目に入る光が原因だと考えられていましたが、実は首こりが原因であることが分かったのです。でもVDT症候群は、パソコンの画面によって目が刺激されて生じるものだという誤解が広まってしまったため、VDT症候群だと診断されれば、目のリフレッシュを勧める眼科医も多いのです。もともと首こりが原因なので、目を休めたところで根本的な改善ができるわけがありません。治療すべきは首こりなのです」
何十年も悩み続けた症状が、1週間で完治する
「めまいに関しても、誤った治療が横行していると言えるでしょう。耳鼻科のドクターは30年前には、メニエール病かメニエール症候群と診断していました。メニエール病は内耳の異常で起こるのですが、数は非常に少ない。そのほかの数多くのめまいはメニエール病に似ているので全部メニエール症候群と診断していました。東京脳神経センターには、メニエール病という診断を受けた患者さんでイソバイドという頭蓋内の水分を少なくする薬を何年も飲まされているにもかかわらず、めまいが治らないという患者さんが多くやってきます。手術までしたけれども治らないという患者さんさえいる。ところが首の治療をしてみると、きれいさっぱりめまいが消えていくのです。耳鼻科の医師は頚の筋肉が原因のめまいが、いかに多いかを知らないのです」
体のあちらこちらに小さな不調を抱え続けているにもかかわらず、複数の病院を訪れても原因がわからないという患者は少なくない。いわゆる不定愁訴と診断されれば、効果的な治療がないと宣告されたも同然だ。
「どこの病院でも外来患者さんの4人に3人までが不定愁訴の患者さんです。でも首こりに着目すれば、不定愁訴は治すことができます。何十年も悩み続けた頭痛やめまい、うつ症状が、1週間で完治したというケースだって少なくない。首はそれだけ重要なのです」
日頃からうつむき姿勢を減らし、首を守る必要がある
たとえば過去、首のケガを経験したことで、何十年も経った後に不定愁訴が表れることもあるという。首こりについての知識がなければ、今、感じているうつ症状と、10年前のムチウチが関係しているとは、なかなか考えにくいだろう。こうした状況を打開するには、自ら熱心に情報収集するしか方法はない。
「様々な病気を診療するはずの総合病院には眼科、神経内科、脳外科、耳鼻科といった専門がそれぞれあるのに、それぞれを横断するような知識を持った医師がほとんどいません。ですから不定愁訴の患者はたらいまわしのような状態になり、どこで診てもらっても治らない。こうした医療のあり方も患者さんを不幸にしています。また、ムチウチは『頚筋症候群』の代表です。追突事故により首の筋肉の異常が起こり、副交感神経が働かなくなり、たくさんの複雑な症状が出るのです。『頚筋症候群』の治療をきっちりすることで、90%以上の人が事故前の状態に戻っています」
不定愁訴やうつ症状に悩まされる前に意識すべきは、長時間のうつむき姿勢を極力減らすこと。そして日頃から、首の筋肉を意識的に休めるといった行動が必要だ。さらに推奨されるのは、首の筋肉を少しでも鍛えるとか、首を冷えから守るといった対策を行うことだ。ほんの少しの意識で、無数の病気から身を守ることができるかもしれないのだ。
首こりから起こる17疾患(頚筋症候群の治療で治癒)
(1)頭痛(緊張型、一部片頭痛)
(2)めまい(頚筋性)
(3)自律神経失調症
(4)うつ(自律神経性)
(5)パニック障害
(6)ムチウチ
(7)更年期障害(難治性)
(8)慢性疲労症候群
(9)ドライアイ
(10)多汗症
(11)機能性胃腸症
(12)過敏性腸症候群
(13)血圧不安定症
(14)VDT症候群
(15)ドライマウス
(16)不眠症
(17)食道嚥下障害(機能性)
[nikkeiBPnet]
Posted by nob : 2016年03月02日 13:29
またまた珈琲の話題(苦笑)、、、毎日いただいていますが、こうした効能を実感したことはないのですが。。。
■仕事、運動、セックスライフまで!コーヒーに秘められた素晴らしい効能
仕事をはじめる前や、ひと段落ついた時の休憩にコーヒーが欠かせないという人は多いだろう。もちろんコーヒーの効能は仕事面だけではない。時には億劫になる運動に対しても、コーヒーで“ヤル気”を起すことができるという。
■コーヒーを飲むと運動が億劫ではなくなる
年明けから早くも2か月が過ぎようとしているが、今年の抱負に運動不足の解消という目標を掲げた向きも少なくないのではないだろうか。しかしお正月太りが話題になる時期を過ぎた今、ちょっとばかりモチベーションが落ちてくることもあるだろう。マラソン大会出場などの目標が設定できれば日頃の運動の励みになるかもしれないが、忙しいビジネスパーソンにはそこまでのスケジュールの余裕がない人も多い。だがそんな向きにも嬉しい研究が先頃発表されている。ついつい億劫になりがちな日々の運動も、コーヒーを飲むと俄然ヤル気が沸き起こってくるというのだ。
英・ケント大学のスポーツ運動科学部が行なった研究によれば、スポーツの練習計画にコーヒーを有効活用できることが指摘されている。例えば新年の抱負などで、現在よりも運動量を増やそうと心に誓う人は多いのだが、残念ながらそのうちの大部分は6ヵ月以内に挫折してしまうということだ。しかしこの事態を避けるのにカフェインが有効に働くという。コーヒーを飲んでカフェインを摂取することで、「身体を動かすこと=億劫なこと」という認識が薄れてくるというのである。
必要に迫られない運動を億劫と感じることは、なるべく“省エネ”状態を保とうする人体にとってはごく自然であり、我々は本質的に怠惰な存在であるとも言える。しかし英・ケント大学のサミュエル・マルコラ教授によれば、カフェインによって運動が努力を伴うものであるという認識が薄らぎ、むしろ身体を動かしたい気分にもなるという。つまりコーヒーが、エンジンのスターターのような役割を果たすのである。運動に限らず特に寒い時期などは身体を動かすのが面倒に感じられることもあるだろうが、やはりそういう時は一杯のコーヒーがまるで“気付け薬”になることを覚えておいても良さそうだ。
しかし今回の研究では、コーヒーがスターターになるのは今のところ日頃から運動や肉体労働をしている人々のみに適用されるということで、机に向かう時間が長い人々にも同じような効果を及ぼすかどうかが判明するのは今後の研究次第であるという。しかしコーヒー好きにとっては、運動をするしないに関わらずコーヒーブレイクが気分をリフレッシュしヤル気を復活させてくれるものであることは周知の事実ではないだろうか。仕事に運動にと、様々な局面でコーヒーをうまく活用していきたいものだ。
■コーヒー好きはストレスに強いことが科学的に判明
このように人をヤル気にさせるなど、コーヒーには様々なポジティブな効能があるのだが、どうしてカフェインがこのような働きを見せるのか、実はこれまであまりよくわかっていなかった。しかし最新の研究によって、コーヒーが身体に影響を及ぼすメカニズムが解明されつつある。その秘密はアデノシンにあるということだ。
細胞の中にあるアデノシン受容体と体内で分泌される化学物質のアデノシンは、お互いに結びつくことで細胞間の情報伝達を行なっているのだが、その中でも興奮や覚醒状態を制御しているのがアデノシンA2a受容体である。このアデノシンA2a受容体にアデノシンが結びつくことで、平静時の人間はあまり興奮することなく過ごすことができるのだが、アデノシンの代わりにカフェインもこのアデノシンA2a受容体と結びつくことができることがわかってきているのだ。ということは、カフェインを摂取することで普段は抑えられている興奮状態や覚醒状態が遮られることなく身体に現れてくるということになる。これによって血圧が上昇して代謝が促進され、眠気覚ましや疲労感の軽減、計算や記憶の効率化などにつながるのだ。
ポルトガル、アメリカ、ブラジルの研究者たちが合同で行なった研究では、マウスを使った実験が行なわれている。マウスを2グループに分け、一方のグループには飲み水にカフェインを混ぜて日常的に摂取させ、まさにコーヒー好きの人間のような状態にしたのである。このグループのマウスにカフェインを与え続けて3週間が過ぎた後、両方のグループのマウスを同一条件の劣悪な環境下に置いたという。その環境とは例えば湿った寝床、傾いた床、狭い空間での共同生活、食糧と水の欠乏といった条件だ。マウスにとってみれば突然“ストレス”が襲ってきたことになるが、カフェインを摂取していないグループのマウスは寝場所を移動するなどそれまでの行動様式を変化させた一方、カフェインを摂取していたマウスは特にこれまでと変わった様子を見せなかったという。つまり、カフェインを摂取していたマウスはよりストレスに強くなっていることが確認されたのである。
この研究によって、カフェイン摂取とストレスへの耐性には因果関係があることが証明されたと、ポルトガル・コインブラ大学のロドリゴ・クンハ准教授は主張している。眠気防止や疲労の軽減、頭脳の明晰化のほかにも、クンハ准教授によればカフェインにはうつ的な気分を遠ざける働きもあるということだ。ただし誤解してはいけないのは、カフェインの摂取で本来持っている能力が向上するわけではなく、眠気など能力を低減させる要素を取り除く働きをしているということだ。そしてもちろん、就寝前にはカフェイン摂取を避けるなどの配慮も必要である。
今回の実験はマウスを使ったものだけだったが、近い将来には人体を使った実験でより詳細なカフェインの“効能”が研究されることになるということだ。コーヒー好きにとっては、1日のカップ数がますます増えてしまいそうな話題が続いている。
■コーヒーを飲んでいる者はEDになり難い
あらためてコーヒーの素晴らしさを確認させられる話題が続いたが、男性にとってはさらに喜ばしき研究も報告されている。日常的にコーヒーを飲むことは、男性機能の向上、維持に多大な貢献をしているというのである。
昨年に米・テキサス大学健康科学センター・ヒューストン校の研究チームが実施した調査によれば、日常的にコーヒーを摂取することと、男性器の機能には関係性があることが発見された。コーヒーを愛飲している男性には嬉しい話題ではないだろうか。
調査で判明したのは、20歳以上の男性で1日に2、3杯以上のコーヒーを飲んでいる者は、まったくコーヒーを飲まない者よりもED(勃起不全)になり難いというということだ。この傾向は体重が重い男性のグループで特に顕著であるという。オーバーウェイト気味の男性はもちろんダイエットを意識すべきであるが、ひとまずはコーヒー(砂糖無し)を飲むことでいろいろな恩恵を受けられることになる。
研究論文の共同執筆者であるワン・ラン博士によれば、実はコーヒーはED治療薬である「バイアグラ」と同じ効能があるという。コーヒーのカフェインが動脈を弛緩させて血流の流れを良くし、男性器の勃起を手助けするということだ。
もちろんカフェインの摂り過ぎや糖分には注意しなければならないが、コーヒーの効能は仕事から運動、セックスライフにいたるまで日々の生活の中で多岐に及ぶものであったのだ。いろんな局面で“コーヒーブレイク”のちょっとした時間を活用していきたいものだ。
文/仲田しんじ
[@DIME]
Posted by nob : 2016年03月02日 10:46
10年生存率データ、、、二人に一人、貴方か私、癌は誰にも身近な病です。。。
■がんの10年生存率を読む
長期戦か短期決戦かで生活設計を
がん診療、研究を実施する国公立病院など32施設が加盟する全国がん(成人病)センター協議会(全がん協)が28種類のがんの10年生存率を公表した。
1999~2002年に診断と治療を受けた約3万5000例のデータで、これだけ大規模な情報公開はわが国では初めて。
それによると、全臓器・全ステージ(病期)の10年生存率は58.2%だった。臓器別では甲状腺がんの90.9%に続き、前立腺がん84.4%、子宮体がん83.1%、乳がん80.4%と続く。
このところ増加傾向の大腸がんの10年生存率は69.8%、がん死因トップの肺がんはぐっと下がって33.2%、ワースト1位は膵がんの4.9%だった。
データを利用する際は、全病期を丸めた生存率を鵜呑みにするのではなく、病期別のデータを参考にする必要がある。病期が1期の「早期」と4期の「進行・末期」とでは条件が違い過ぎるからだ。
実際に経過途中の5年生存率を見ると、前立腺がんの場合1~3期は100%だが、4期では5年生存率でも54.5%まで下がる。
前立腺がんは治療の選択肢が多いこともあり、他の臓器や骨への転移が深刻ではない限り「手を替え、品を替え」余命を引き延ばすことが可能だ。言い換えれば「転移」を抑える長期戦に耐える覚悟が必要だということ。
一方、肺がんの5年生存率は、全病期を通じて39.5%。1期は77.9%と8割近いが、4期になると5.6%と衝撃的な数値が出てくる。しかも病期が進むほど治療開始1、2年目の生存率ががくっと落ちる。早期発見の重要性は言うまでもないが、短期決戦で濃厚な治療を覚悟すべきだろう。
逆に女性の乳がんは10年生存率でも8割以上と高いが、ジワジワと低下し続けるのが特徴。一般に治癒の目安といわれる5年を過ぎても再発・転移の可能性があり、10年、20年はがんと付き合う心構えと経済計画が必要だ。
なにせ、2人に1人ががんにかかる時代。このデータはいたずらに余命に怯えるのではなく、がん発症を織り込んだ生活設計を立てる際の参考にしたい。
(取材・構成/医学ライター・井手ゆきえ)
[DIAMOND男の健康]
Posted by nob : 2016年03月02日 10:38
言わずもがな、、、しかし自らが信じることを信じるように実践する他はない。。。Vol.2/如何なるメソッドも諸刃の剣、バランスこそがすべてだと思います。。。
■やっぱり危ない!?
「糖質制限ダイエット」第一人者が急死した
真っ二つに分かれる評価
炭水化物さえ食べなければ、何を食べてもいい。簡単でしかもすぐに痩せられて糖尿病も治る。だが、甘い謳い文句ばかりを信じると、思わぬ落とし穴が待ち受けているかもしれない。本当に大丈夫か。
あんなに元気だったのに
「『糖質制限ダイエット』で急激に痩せられた頃は、心配したんです。打ち合わせをしていても、痩せる前に比べてぼーっとしてるかなと思うこともありました。やはり糖が足りてないのかなと。でも見た目は元気そうだったので、まさかこんなことになるなんて……」
桐山氏と10年来の付き合いのある担当編集者は、こう言って肩を落とした。
2月6日未明、ノンフィクションライターの桐山秀樹氏が逝去した。享年61。関係者によれば、宿泊先のホテルの部屋で亡くなっていたという。
「今度一緒に飲む約束もしていたのに、あまりに突然のことで言葉もありません。死因は、はっきりとは分かっていませんが、心臓系の疾患だと伺っています」(知人)
桐山氏は、1954年愛知県生まれ。学習院大学を卒業後、ホテルジャーナリストとして活躍。旅行、リゾート、レストランのサービスについて多くの批評と著書を執筆してきた。ホテル業界でその名を知らぬ者はいないほど、業界に精通した人物だった。
数年前からは妻と二人で軽井沢に拠点を移し、執筆活動に勤しんでいた。
ホテルジャーナリストとして活躍する一方で、近年、桐山氏が一躍注目を浴びたのが、炭水化物を一切取らない「糖質制限ダイエット」である。
桐山氏がダイエットを始めたのは'10年、56歳の時。当時は、身長167・5㎝で、体重は87kg。ウエストは100㎝超もあった。痩せることを決意したきっかけを、桐山氏は、かつて本誌にこう語っている。
「咳が出るので、最初は風邪だと思っていたんです。だが症状は次第に重くなる。呼吸も苦しくなり、食べたものを咳とともに吐くようになった。
医師から告げられた病名は「糖尿病」—。やはり来たかと、頭をガーンと叩かれたような衝撃を受けた。さらに心臓肥大という診断まで出た。糖尿病による動脈硬化で、心臓にまで影響を及ぼしていたという。異常なまでの息苦しさはそれが原因だった」
飲食のルポを書くことも多く、深夜の執筆中に揚げ物やパスタなど高カロリーなものを食べ続けていた。糖尿病は、長年の「不摂生」な生活の結果だった。睡眠不足、運動不足も明らかだった。
糖尿病と診断された時の検査結果は、血糖値が215(正常値は109以下。カッコ内以下同)。糖尿病の指標である過去2ヵ月の血糖平均値、HbA1c(へモグロビンエーワンシー)は9・4(5・8以下)と非常に高い数字が出た。
血圧は上が200以上、下が100近くあり、いつ倒れても不思議ではない状況だったという。
「このままの状態で放っておくと生死に関わる」
と医師から忠告され、桐山氏が実践したのが、前述の「糖質制限ダイエット」だった。
3ヵ月で15kg痩せた
その日以来、あれほど食べていたご飯や蕎麦、パスタなどの炭水化物を一切食べないようにした。代わりに主食として食べるのは、豆腐やチーズ、肉、魚。酒は焼酎、ウィスキーはOKで、赤ワインも少量なら問題ない。そして日々の散歩も欠かさないように努めた。
「結果はすぐに出た。なんと1週間で5kg痩せ、3ヵ月後には血糖値は93に半減、体重は15kgも減った。数値の上では糖尿病を脱したことになる。おかずを満腹食べて酒を飲んで、しかも痩せられる。糖尿病は良くならないと諦めている人には、短期間でここまで改善することは『奇跡的』と感じられるはずだ」(桐山氏)
糖質ダイエットをする際、桐山氏が参考にしたのが、京都の高雄病院理事長の江部康二医師の著書『主食を抜けば糖尿病は良くなる!』だ。
「糖質制限ダイエット」の提唱者である江部医師は、そのメリットをこう強調する。
「ご飯やパンなどの糖質を抜けば、あとは満足するまで何を食べてもいいので、他のダイエットに比べて、圧倒的に楽に誰でも簡単に始められるのです。
糖質摂取を減らすと主な栄養素は脂肪とたんぱく質になり、食後の血糖値は上昇しません。この場合、肝臓でアミノ酸や乳酸などからブドウ糖を作るので低血糖にはなりませんし、その際一定のエネルギーが消費されるので寝ている間に痩せていくのです。
さらに脂肪が分解され、脳や体のエネルギー源となるケトン体の血中濃度が、非常に高くなる。つまり糖質を摂らなくとも脳はちゃんと働き、体重はどんどん減少するのです」
その後、桐山氏は同じく肥満で糖尿病を患う中年男性たちと「おやじダイエット部」を結成。皆で集まり楽しく食事をしながら、我慢せず痩せるダイエットを実践してきた。その活動を綴った『おやじダイエット部の奇跡』はシリーズ化され、テレビでも取り上げられた。
糖尿病も改善され、体も軽くなったはずだった……。にもかかわらず、なぜ今回のような事態が起こったのだろうか。
「桐山さんは亡くなるまで、糖質制限をずっと続けていました。リバウンドもなく、体重をキープされていましたね。痩せて健康になったはずなのに、なぜ急に亡くなってしまったのか分かりません」(前出の知人)
糖質制限ダイエットの旗手であった桐山氏が亡くなったことで、誰もがこの食事療法に「不安」を覚えてしまうのは、当然のことだろう。
真っ二つに分かれる評価
現在、糖質制限ダイエットについては、専門家の間でも肯定派と否定派、真っ二つに意見が分かれている。
京都大学大学院の森谷敏夫人間・環境学研究科教授はこう警鐘を鳴らす。
「糖質は摂らないほうが良いと言う医者がいますが、これは大きな間違い。そもそも医学部には栄養学を学ぶ機会がないので、食生活に関する知識が不足している医者が多いんです。ラットの実験では糖質を摂らなくても問題ない事が証明されているので、多くの医者は人間の体にも当てはまると言うのですが、それは無理がある。ラットと人間では脳の大きさが全然違うんですから。
言っておきたいのは、脳を動かすエネルギーは100%、『糖』だということです。炭水化物を食べずに、脳を正常に保つためには、一日に大量のたんぱく質や脂質を摂らなければなりません。数kgもの肉を食べ続けることは現実的じゃない」
とはいえ、痩せれば血糖値も下がり、健康になるのではないか。
「痩せたのは脂肪が落ちたからではなく、体内の水分が無くなっただけなんです。糖エネルギーが不足すると、それを補うために、筋肉を分解してアミノ酸に変えて脳に送ります。その時に水分を使用するので、体重が落ちるんです。でも脂肪は減っていない。
糖質制限ダイエットをしている人は、慢性的な眠気を抱えており、すぐ眠ってしまうのが特徴です。これは脳が極力エネルギーを使わないように指示を出すためなんです。動かないのが一番エネルギーを使いませんからね。
一方で筋肉量はどんどん落ちるので、骨がスカスカになり骨粗しょう症になる危険性もある」(森谷氏)
さらに愛し野内科クリニック院長で、糖尿病を専門に診ている岡本卓医師は、「糖質制限ダイエットは死を招く恐れまである」と忠告する。
「'06年に『ランセット』『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』という世界の二大医学誌に、糖質制限ダイエットを厳格に実行すると、体内に老廃物が溜まり、体が酸化し非常に危険な状態に陥るケースが報告されました。
スウェーデンの医師は、たんぱく質ばかりを摂ることで、悪玉コレステロールが溜まり、動脈硬化を招き、心筋梗塞や脳梗塞が増えたという結果を発表しています。
短期的にみれば体重も減るからいい数値が出る可能性がありますが、一年以上の長期にわたって実行する場合は、悪影響が出る可能性が高い」
実際に体の不調が表れた医師もいる。医療法人再生未来Rサイエンスクリニック広尾院長の日比野佐和子医師だ。
「私が糖質ダイエットをしたのは36歳の時でした。あっという間に15kgも痩せたので喜んでいたのですが、しだいに頭がぼーっとする状態が続くようになりました。
そしてある朝、目覚めると右半身が麻痺してまったく動かなくなったのです。しばらくしてなんとか動けるようになったので、病院に行きMRIを撮った結果、脳梗塞の一歩手前の一過性脳虚血発作を発症していることが分かりました」
検査の結果、たんぱく質や油分を摂りすぎることで、脂肪飽和になり、一時的に脳の微小血管が詰まったことが原因だと判明した。
「炭水化物以外なら、なんでも好きなだけ食べていいという言葉に踊らされるのは危険です。大切なのは糖質制限のやり方なんです。たとえばサラダから食べて、最後にご飯を食べるように、食べる順番を変えるだけで食後の血糖値の上昇を抑えることができる。
日本で認識されている糖質制限ダイエットは、とにかくご飯を含む炭水化物を一切食べないという間違った認識が独り歩きしている気がします」(日比野氏)
「特に高齢者の場合は、太っているからといって無理に痩せる必要はない」と語るのは、食物学学術博士の佐藤秀美氏だ。
「高齢者のほうが、消化吸収能力が落ちているため、若い人より内臓組織の原料となるたんぱく質を多く摂る必要があるのです。ですから炭水化物を摂らず、たんぱく質を糖質に変えていては、本来摂取されるべきたんぱく質が吸収されず、他の臓器に負担が出てくる。
それでも健康のために痩せる必要がある人は、いきなり糖質をまったく摂らないようにするのではなく、お菓子や甘い物などの間食を減らせばいいのです。数値に惑わされず、何のためにダイエットするのかをもう一度、考えてください。痩せることより、長生きすることのほうが重要なのです」
もし痩せていなければ……
このように糖質制限ダイエットのデメリットを指摘する声は多い。だが仮に、桐山氏が体重を減らさず、血糖値を下げていなければ、糖尿病はさらに悪化していただろう。もしかしたら、より死期を早めたかもしれない。
桐山氏の良き相談相手で、糖質制限ダイエットを推奨してきた前出の江部医師は、今回の死因をこう推測する。
「桐山さんが亡くなられたのは本当に残念ですが、直接的な原因は、糖質制限ダイエットではないと考えます。
桐山さんの場合、もともと心臓が苦しくなり、医者に駆け込んだところ糖尿病が発見されましたが、そうなるまでに何年間、高血糖の期間があったかが問題です。
『高血糖の記憶』と言うのですが、いくら血糖が正常になっても、過去に一旦発症した血管の狭窄は、簡単にはなくならないのです。痩せて安心する人も多いのですが、定期的に検査をしないと、心筋梗塞などを起こす可能性があるのです」
即効性があり、楽に痩せられる糖質制限ダイエットには、もちろんリスクも生じる。かといって、そのまま肥満を放置していれば、病気を悪化させるばかりだ。
桐山氏の葬儀は、遺族の意向により密葬で執り行われた。桐山氏と親交のあったホテル関係者が語る。
「桐山さんの取材スタイルはとにかく『現場主義』。年間100泊ほどホテルに泊まり、実際に自分で体験し、そのホテルの問題点を鋭く突っ込んでくれました。
一方でユーモアのある方で、よくコンシェルジュの女の子たちに駄洒落を言って笑わせていました。あと、とにかく博識で歴史からスポーツまで詳しかったですね。神経が細かすぎるくらい、いろいろと気配りをする人でした」
何のために痩せるのか、健康のために優先すべきは何なのか。桐山氏の死は、それをもう一度考える機会を、私たちに与えている。
[現代ビジネス]
Posted by nob : 2016年02月24日 16:48
言わずもがな、、、しかし自らが信じることを信じるように実践する他はない。。。
■桐山秀樹さんの急死で波紋 「糖質制限ダイエット」専門家はリスク指摘
ご飯やパンなど炭水化物を控える「糖質制限ダイエット」の第一人者として知られたノンフィクション作家、桐山秀樹氏が今月6日、心不全のため61歳で急死したことで波紋が広がっている。桐山氏の関係者は死因と糖質制限との関係を否定しているが、専門家からは、極端な糖質制限を長期に行うリスクを指摘する声も上がっている。
糖質制限とは、ご飯やパン、麺類、ジャガイモなど炭水化物(糖質)の多い食品を食べない糖尿病患者のための食事療法。糖質だけを控えれば肉や魚は制限なく食べてもよく、カロリー計算のいらない手軽さから糖尿病患者だけでなく、ダイエットをしたい人にも人気となっている。
桐山氏は糖質制限食の実践者として、中高年向けのダイエット本を多数出版。夕刊フジでもその効果について「医者いらずで糖尿病を克服し、メタボからも脱出できた」などと語っていた。
一方、糖質制限食をめぐっては、日本糖尿病学会が「総エネルギー摂取量を制限せずに炭水化物のみを極端に制限して減量を図ることは、長期的な食事療法として安全性などの重要な点についてこれを担保するエビデンス(科学的根拠)が不足している」などと指摘。「現時点では勧められない」とする提言を公表している。
これに対し、桐山氏は2013年4月の夕刊フジへの寄稿で反論した。糖尿病治療にはこれまで、カロリー制限食と薬物療法が用いられてきたものの、糖尿病腎症で透析などに陥る患者が後を絶たないなどと主張。「なぜ、肥満解消を含め効果の出ている糖質制限のみを否定するのか」「私は断固支持し実践し続ける」と結んでいた。
糖質制限食の効果を宣伝してきた“生き証人”の突然の訃報は、衝撃を持って迎えられている。
桐山氏の公私にわたるパートナーで文芸評論家の吉村祐美氏によると、桐山氏は今月5日朝に仕事場がある神戸市のマンションを出発。6日朝に東京都内のホテルの室内で発見されたという。死因は心不全。吉村氏は夕刊フジの取材に、糖質制限と死因との因果関係について「関係ないと聞いている」と否定した。
こうした中、専門家からは糖質制限が及ぼすリスクを指摘する声も上がる。
山野医療専門学校副校長で医学博士の中原英臣氏は「脳の活動を維持する栄養素となっているのがブドウ糖で、私たちは砂糖などを通じて摂取している。それを取らないということが『体にいい』とはいえない。さらに、長期的に摂取しないともなれば、個人差はあっても、体にいろいろな影響が出ても不思議はない」と話す。「健康的にやせるには、バランスの取れた食事をし、運動でカロリーを消費するということが基本だ」と中原氏は強調している。
[ZAKZAK]
■糖質制限ダイエットと「突然死」の因果関係は
『おやじダイエット部の奇跡』などの著書があり、“糖質制限ダイエットの伝道師”として知られるノンフィクション作家の桐山秀樹氏が急死していたことが分かった(享年62)。死因は心不全で、滞在中のホテルのベッドで倒れていたという。
桐山氏は2010年に糖尿病と診断されたことをきっかけに、ご飯やパン、麺類、ジャガイモのような糖質(炭水化物)を多く含む食品を食べない糖質制限を実践。3週間で20kgのダイエットに成功した体験を広く紹介し、人気のダイエット法として定着させた。
ネット上では、今回の悲報を伝えるワイドショーなどに批判が集中した。
〈まるで糖質制限ダイエットのせいだと言わんばかりの内容〉
〈ダイエットと死因の因果関係ははっきりしてないはず〉
〈心臓発作などの急死の原因に糖質制限ダイエットを加えようとしている〉
糖質制限自体はもともと糖尿病を治療する食事法として一般的に行われているものだが、桐山氏の死去と過度な糖質制限ダイエットへの警告を結びつける報道に違和感を抱く視聴者が多かったのだ。
では、糖質制限ダイエットは安全なのか危険なのか――。この議論はこれまでも度々繰り返されてきたが、じつは糖尿病の専門医でも「推進派」と「反対派」が拮抗しているのが現状だ。2014年5月に開かれた糖尿病学会の学術集会で糖質制限食の是非が話し合われた際も、意見は完全に割れた。
推進派の医師は、糖質制限によって短期間で体重を減らすことができるメリットのほか、血糖や血圧、脂質の値がすべて改善し、糖尿病のさまざまな合併症予防も期待できると主張した。
一方、反対派の医師からは、糖質を抑える代わりにタンパク質や脂質の摂取量が増えれば、腎機能や骨密度の低下、悪玉コレステロールの増加による動脈硬化や心筋梗塞のリスクが高まる、と真っ向から対立。糖尿病学会としては、〈長期的な食事療法としての遵守性や安全性などを担保するエビデンスが不足しており、現時点では薦められない〉(2013年に出した提言)と慎重な立場を崩していない。
栄養学の観点から見た場合はどうか。栄養学博士の白鳥早奈英氏がいう。
「人間が考えたり動いたり、体全体の機能に指令を送っているのが脳で、その重要なエネルギー源になっているのが、糖質から作られるブドウ糖です。炭水化物の理想的な摂取比率は50~60%で、残りを脂質とタンパク質でバランス良く取ることが大切です。
このバランスを極端に崩してしまうと、さまざまな体の異常をきたす原因となります。米やパンなどの主食を減らせば脳の働きが鈍くなりますし、その分、肉など脂質を多く取ると脂肪が増えてダイエットには逆効果となります。また、タンパク質の取り過ぎはプリン体を生んで尿酸値を高めたり、カルシウム不足になったりする弊害を招きます」
白鳥氏によれば、「糖質も上手に取ればダイエット効果がある」と指摘する。
「たとえば、ご飯を食べる前に食物繊維を多く含んだ野菜を取る習慣をつけると、糖質の吸収や血糖値の上昇をおだやかにして、太りにくい体質をつくることができます。うどんなどの麺類を食べる場合も、食物繊維の豊富な海藻や山菜と一緒に食べれば心配ありません」
さらに、白鳥氏は著書などで1日1回の『冷やごはんダイエット』を推奨している。
「ご飯やジャガイモが冷めると、でんぷんの一部が『レジスタントスターチ』という食物繊維に似た成分に変わるため、ダイエット効果が出てきます。
そのため、コンビニでお弁当を買ってもレジで温めないほうがいいですし、うどんも冷やしうどん、ジャガイモも温かく煮たものよりポテトサラダのような冷たいメニューを選んだほうが太りにくいといえます」
どんなダイエットでも「やり過ぎ」は禁物。糖質制限ダイエットも安全性の“お墨付き”がない以上、成功者のケースをそっくり鵜呑みにするのではなく、人それぞれ体調に合わせて工夫することも必要だろう。
[ガジェット通信]
Posted by nob : 2016年02月17日 19:44
白湯、私もお薦めします、、、私は保温力の高いサーモス山専ボトルを使用しています。。。
■ぼくが試している白湯の美味しい淹れ方や飲み方
先日yaottiさんがドリップコーヒー環境2015というエントリを書いていたのが記憶にあたらしいが、コーヒーはエンジニアだけでなく一服を必要とするすべての人にとってよく飲まれている嗜好品であろう。
ぼくもコーヒーは好きだし一服時によく飲んでいたのだけれど、最近はそれよりももっと飲んでいるものがある。
それは白湯だ。僕はいま猛烈に白湯にハマっている。今は冷たい飲み物はほぼ飲まず、白湯を2リットル/日のペースで飲んでいる。
この生活をはじめてからまだ腹痛に悩まされていないので一定の効果はあるらしい。
ところで、コーヒーには淹れ方や飲み方があるようだが、白湯にもまた淹れ方や飲み方があるはず。なので今回はぼくが現在試している淹れ方や飲み方について紹介したいと思う。
■ティファール
白湯を飲む上で欠かせないのは飲みたいと思った時にサッと白湯が飲めること。ティファールなら500mlを沸かすのに1~2分だ。快適な白湯ライフを送るためにはティファールは欠かせない。
■マグカップ
白湯は熱いので取っ手がないと飲みづらいためマグカップが良い。また、300ccくらいの大きさがちょうど良い。これより大きいと注いだ白湯が後半冷めた状態になるし、小さすぎると何度も注ぐのがめんどくさい。300ccくらいのマグカップに2~3回注いだらティファール内の白湯が空になるといったペースがよい。
■白湯+冷水
白湯はだいたい熱湯だからとても熱い。なにも考えずに飲むとやけどする。だからやけどが怖い場合は大抵水を足す。白湯8:冷水2くらいの割り方でちょうど良い。
■白湯+氷
白湯に氷を入れるという割り方もある。これは氷が溶けていく様をみていると落ち着いて良い。
■ゆっくり何度も飲む
喉をぎりぎりまで乾かせて、一気に飲むとビールなどは気持ち良いのだけどそれは体に良くない。いきなり冷たいものが胃に流し込まれると内蔵に脂肪がつきやすいという話もあるし一気飲みはやめたほうがよい。だからおすすめしたいのはずっと胃に白湯がはいっていてぽかぽかしている状態にすること。そのためにはゆっくりと何度もすこしずつ飲みつづけること。そうするとトイレにいく回数は増えるんだけど別に困ることはない。
■白湯毒出し健康法
白湯毒出し健康法というのがあって、アーユルヴェーダにもとづいて白湯を飲むと幸せになれるとか、慣れると甘く感じるとかかなりとんでもないことが書いてある。「正当な白湯」とか「水にヴェータを入れる」とか聞きなれない言い回しが多いのでコンテンツとして白湯のツマミに読むと良い。
■最後に
ここまでマグカップがいいとかティファールがいいとか色々書いたんだけども、結局のところ白湯の最も良い点は手軽ということなので何も考えず好きに飲むのが一番良い。白湯原理主義みたいなめんどくさい人にはならないためにもこだわりながらも適当につづけていけたらなと思う。
[All About News Dig]
Posted by nob : 2016年02月17日 19:37
万能の良薬、、、それはプラセボ(≒思い込み)。。。
■「ゴジラ」を想像したら胃がんが消えた?
「病は気から」ウソみたいな本当の話
作家・高橋三千綱さんインタビュー
病気って「ありがたい」!?
―糖尿病、肝硬変、さらに食道がんに胃がんという大病相手の闘病をつづった、自伝的小説です。病気と闘う過程は、やはり人生を見つめなおす機会になったのですか。
いや、そんな大仰なものじゃないんです。僕はもともと特別な人生観は持ち合わせていないんです。思い出を作ることが人生だと思ってきたから、若いころからやりたいことをいろいろやってきた。馬で40日もロッキー山脈を旅したり、映画を作ったり、ゴルフにのめり込んだり。
医者から「余命4ヵ月」と宣告されて死を意識するようになると、頭に浮かんでくるのはそういう昔の思い出ばかりなんです。この作品はその思い出を書いてみたわけですが、「なんだ、俺の人生って大したことないな。なんとなく愉快に過ごしてきただけじゃないか」と。
でも、昔の思い出に浸るのもなかなかいいものです。そういう意味じゃあ、一度大病を患ってみるのもいい。若い頃の思い出が自然によみがえってきますからね。だからこの本は、健康な人に「一度、病気に罹ってみたいな」と思わせるための本なんです(笑)。
―大の酒好きだった主人公が、糖尿病になって医者から止められている酒をなかなか断ち切れず、肝硬変になって苦しめられる様が描かれています。
フィクションの部分はほとんどないんですよ。実際、酒はなかなか止められませんでした。
闘病もそれなりに大変でした。一番まいったのは食道がんの手術の2ヵ月後、胃の中にあった静脈瘤の処置のため再入院した頃でした。手術を受けようとしていたのに、医師から「血糖値が高くて手術できない」と言われて、自宅に帰された。そうしたらその3日後、肝性脳症になってしまった。肝機能が低下しており、処理されるはずのアンモニアが脳に回って、意識障害を起こしてしまったんです。
夜中に下着のまま庭を歩き回ったり、お腹に激痛が走るのでトイレに行ったら脂汗が一升くらい流れ出たり。結局その時は救急車に乗って緊急入院する羽目になりました。
こんなに家族に迷惑をかけるのなら、こっそり毒キノコでも準備しておいて、いっそ自分で死んでしまえばよかった、と本気で思いました。
―終盤では、保険適用されていない再生医療の一種、幹細胞療法も試したことが書かれていますが、その先は描かれていません。現在、体調が安定されているのはその治療効果のお陰ですか。
結論から言えば、期待したような効果は上がりませんでした。本来、自分の皮下脂肪から抽出した幹細胞を培養してまた体に戻すというやり方なのですが、私の場合は幹細胞自体が弱っていたので、他人の幹細胞を使ってやったのです。
そのせいもあるのかもしれませんが、私の場合、どうやら功は奏さなかったようです。いま体調をなんとか維持しているのは、「大丈夫だ」と自分で自分に暗示をかけているからです。あとは何もしていません。
胃にがんが二つあったんですが、その一つは毒蛇のような形をしていたので、「これをやっつけるにはゴジラだ」とひらめいた。頭の中で、ゴジラに放射熱線を浴びせられた毒蛇が溶けていくシーンを何度も何度も想像していたんです。で、1ヵ月後に検査をしたら、がんが消えていた。
嘘みたいな話ですが、本当なんです。医者が、腫瘍マーカーの値を見て「おかしい、おかしい」と言うほど。内視鏡検査をしきりに勧められていますが、病気で血液中の血小板が少なくなっているので、もしも検査の時に出血したら大事になる。だから内視鏡検査も断っています。
―ラストは、主人公が家族宛てに「リビングウィル(生前の意思)」を書く場面で終わっています。「痛み止めを打ってもまだオレに意識があるようだったら、そっと一本燗酒をつけてくれ」という一文が胸に迫りました。
どこかは言えませんが、僕は自分の死に場所をすでに決めているんです。そこで大好きな日本酒を飲んで逝くのが理想の死に方なんです。
そのときのために、とっておきの徳利からぐい飲みまで全部用意してあります。友人の陶芸家にいろいろ作ってもらったけどなかなかしっくりこない。尾道の古道具屋でたまたま見つけた江戸時代のぐい飲みがとても良かった。5000円くらいのものですが、これで最後に燗酒を飲んで死のうと決めているんです。
―お酒への愛が深いのですね。
酒は僕の親友だったんですが、病気で飲めなくなってその親友を失ってしまった。
そうなると時間を持て余しちゃってしょうがない。だったら仕事をしようか、と思い至ったんです。僕はそれまで長い間小説を書いていなかったから、世の中からは忘れ去られたような作家でした。
その僕が入院してからは3冊も出しましたからね。「ありがとう肝硬変」というのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、病気のお陰で執筆のエネルギーが増大したのは間違いありません。
この作品は確かに闘病記なのですが、病気の人ではなく、むしろ健康も仕事も人生のピークにあると自覚しているような人に読んでもらいたい。人は誰しも絶頂期には傲岸になりやすい。そういうときには気づきにくい、人間を重層的に見る視点を今作では描いたつもりです。読めばきっと、他人への接し方が柔らかくなると思います。
(取材・文/阿部崇)
[現代ビジネス]
Posted by nob : 2016年02月15日 19:21
共感支持します、、、君たちは正しい。。。
■戦争行かない、行かせない 安保法抗議 高校生2・21一斉デモ
安全保障関連法に反対する高校生らのグループ「T−ns SOWL(ティーンズ・ソウル)」のメンバーが二十一日、東京都内で記者会見し、東京・渋谷や東北、大阪などで二月二十一日に安保法に抗議する高校生の一斉デモを実施すると発表した。三万人の参加を目指す。
メンバーは「安保法で戦争に行ったりして当事者になるのは私たち。今の政治に将来をゆだねられない」と訴えた。
選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられる今夏の参院選に向け、都内の高校に通う十五〜十八歳の五人が会見。都立高三年、福田龍紀(りゅうき)さん(18)は「違憲の安保法は百時間審議しても認められない。高校生だろうと、大人だろうと、国民が団結して法を止める。デモで声を上げた先に参院選があると思う」と語った。
デモのほか、模擬投票などのイベントも予定している。高校二年のあいねさん(16)は「十八歳選挙権も、同世代が呼び掛けた方が伝わると思う。どんな政治や暮らしがいいのか、無関心な大人も含め一人一人に考えてほしい」と訴えた。
ティーンズ・ソウルは昨年七月に発足。六十五人のメンバーは、無料通信アプリ「LINE(ライン)」などで連絡を取り合い、都内でのデモや勉強会開催などの活動を続けている。関西を拠点にしているメンバーもいる。
[東京新聞]
■国民も野党もメディアも「とりまユナイト」で——安保反対の高校生が「団結」呼びかけ
安保関連法制に反対する高校生グループ「T-nsSOWL(ティーンズソウル)」が1月21日、東京・永田町の参議院議員会館で記者会見を開き、今夏の参議院選挙に向けて、国民と野党・政治家とマスメディアが団結するよう呼びかけた。キャッチフレーズは「とりまユナイト(とりあえず、まあ、団結)」だ。
ティーンズソウルは昨年7月、安保法制の廃案や安倍政権の退陣を求めて、東京都内の高校生のメンバーを中心に結成されたグループ。国会前などでおこなわれた安保法制反対デモに参加して、「とりま廃案(とりあえず、まあ、廃案)」などと訴えて、メディアの注目を集めた。メンバーは全国に60人ほどいるという。
●「2016年になって、違憲なものが合憲になったわけではない」
メンバーのたくやさん(高校2年生・男性)は会見で「安保法制は、自分たちや自分たちの子どもが当事者として関わる問題だと考えている。安保法制は立憲主義に反している。いけないことはいけないと言わないといけない」と話した。
メンバーのりゅうきさん(高校3年・男性)は「安保法制のニュースも減り、過去のことになりつつある。だけど、2016年になって、違憲なものが合憲になったわけではない」と強調した。そのうえで、「国民と野党の政治家とメディアの団結がないと、安保法制はとまらない」と訴えた。
グループの呼びかけ人のあいねさん(高校2年生・女性)は「政治を考えるのは、難しいことでも、かっこ悪いことでもない。家族や友だちを守るために政治を考えることが大事だ。同世代には同世代の声が一番響く。もっと多くの人に訴えかけていきたい」と話した。
ティーンズソウルは、全国にある他の高校生グループに呼びかけて、今年2月下旬に「全国一斉高校生デモ」を計画している。また、今年から「18歳選挙権」が始まることから、今後もデモや勉強会を通じて、高校生が政治について考える機会を作っていくとした。
[弁護士ドットコム]
Posted by nob : 2016年01月22日 11:45
結局は自己免疫力の問題、、、生活習慣と食生活からの体質改善により、もうまったく発症しません。。。
■冬の肌に起こりやすい謎のブツブツ…。それって「寒冷じんましん」かも!
入浴後や自宅から外に出たときに起こる謎のじんましん…。「かきむしって赤くなってしまった」など「ぶつぶつとした小さな発疹がなくならない」と困っている人もいるでしょう。冬だけでなく、冷たい金属や水に触れたときなどにじんましんなどの症状を引き起こすことを「寒冷じんましん」といいます。
◆冬場に発症しやすい「寒冷じんましん」とは
寒冷じんましんは、体温よりも低い温度の冷気や水、氷、金属などを接触した際に発症する、非免疫系のアレルギーです。気温の低い冬場に発症しやすいですが、エアコンの冷風が原因で起こることもあります。
皮膚が赤くなり、鳥肌に似た小さな腫れとかゆみが起こるのが特徴です。温かい場所から寒い場所へと移動したり、お風呂からあがったりするときにかゆみが発症する人は、寒冷じんましんの可能性が高いです。
◆どうして「寒冷じんましん」が起こるの?
寒冷じんましんは、急激な温度の低下により、皮膚の下の血管周辺にある肥満細胞が刺激されることが原因で起こります。肥満細胞が刺激を受けると、免疫機能が働きヒスタミンという化学物質を放出します。ヒスタミンはかゆみを引き起こすと同時に、皮膚の血管を拡張させます。これにより、血液中の液体成分が外にもれだし、皮膚を赤くふくらませ、じんましんとなって現われるのです。
手足だけでなく、首やお腹、顔などにも出ることがあり、はじめはピリピリとした痛みやかゆみを感じます。かいてしまうと、じんましんが広がることもあるので注意しましょう。
◆「寒冷じんましん」を防ぐにはどうすればいい?
寒冷じんましんは放っておくと症状が悪化することもあれば、悪化せずにたまに出る程度で留まることもあります。何度も起こる場合は、ヒスタミンを抑える抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬を病院で処方してもらいましょう。また、寒冷じんましんを起こさないために予防することも大切です。
□冬は冷たい地面に裸足で歩くことがないようスリッパを履いたり絨毯を敷いたりする
□暖房がきいているところでは薄着で過ごす
□寒い外に出るときは温かい格好をして急激な温度差を感じないようにする
□気温の低い外に出るときはマフラーや手袋を使用し、露出する面積を少なくする
□室内で汗をかいた直後に寒い外には出ない
体調が悪いと刺激に対しても敏感になるため、日頃からストレスをためず、万全な体調でいることも大事です。辛いかゆみやブツブツを脱することができるよう、冬は特に気温の変化に気を付けたいですね。
監修:岡本良平(医師)
[Mocosuku Woman]
Posted by nob : 2016年01月14日 16:27
これからの主流。。。
■【あの有名人から学ぶ!がん治療】愛川欽也さん たくさんの器具に繋がれた最期ではない
2014年12月に末期の肺がんが発見された愛川欽也さんは2015年の年明けより在宅医療を受けられました。3月に、自宅に介護ベッドや点滴器具が入るのが目撃され「重病説」流れました。このあたりから、愛川さんのがん闘病が世間に知られることになりました。
しかし、在宅療養の場合は、家に出入りする人は限られています。愛川さんのように介護者(奥様のうつみ宮土理さん)がおられる場合は、主治医と1〜2名の訪問看護師くらいなので、終末期を静かに過ごしたい人や、有名人の愛川さんのようにプライバシーを大切にしたい場合には在宅療養は適しています。
しかし、未だに、「在宅療養だとがんの痛みが心配だ」と危惧される人がおられます。私はそれは杞憂にすぎません、と申し上げたい。今や、病院やホスピスと全く同じ質の緩和ケアが自宅でも受けられる時代なのです。モルヒネに代表される医療用麻薬も、自宅でも病院と同じように使えますし、夜間などに急に痛みが強くなった時にいつでも使えるように、在宅医は予め頓服薬(レスキュー)を用意しています。
そして、在宅医療の場合は、自然の経過にまかせて徐々に枯れていく最期、つまり“平穏死”になります。肺がんの末期と聞くと、酸素吸入や痰の吸引器など、たくさんの器具に繋がれた最期を想像する方がいるかもしれませんが、在宅医療の場合、それらの管とはほぼ無縁です。こうした事実は、2014年の日本肺癌学会において、私は肺がんの専門医の方達にも講演しましたが、病院の専門医の方でも、私の話に首を傾げる人がいましたから、市民にはあまり知られていない真実かもしれません。
愛川さんは自宅に介護ベッドが搬入されてから1ケ月程度で旅立たれています。これは自費でなく介護保険を使えばその日のうちに搬入できます。自己負担は1ケ月、2000円程度。市役所に介護認定の申し込みをすれば末期がんの場合は、すぐに認定結果が出ますし、出る前(つまり申し込んだ当日)から介護保険が使えることもあまり知られていないことです。肺がんに限らず、末期がんの平均在宅療養期間は1〜1.5ケ月です。認知症の場合は、介護のために仕事を辞める介護離職が社会問題になっていますが、がんの場合は介護休暇で済むことが大半です。私の診療所では、年間約90名の人を在宅でお看とりしていますが、半数が末期がんで、半数はがん以外の病気、つまり老衰などです。しかも末期がんの場合、在宅看取り率は9割以上なので、ほとんどの方が最期まで在宅で過ごされているのが実態です。愛川さんがなぜ病院でなくて在宅で亡くなられたのか? 疑問を呈する週刊誌の記事もいくつか見かけましたが、こうしたケースは珍しいことではありません。芸能人や有名人ならば尚の事です。愛川さんが亡くなられた後、妻のうつみさんが記者会見を開きました。
■ご家族の言葉と大病院の医師の言葉から考えよう!
<うつみさん記者会見から(2015年5月10日)>
− 私は病院へ行く、入院させるという考えは、頭にちらとも浮かびませんでした。自宅で、私の横で、私も頑張ってなんとか元気にさせたいと思いました。病院に、なんていう2文字は浮かんだことがありません。病院へ行ったら治るものですか? それよりも、愛川が家が好きだということを知っているし、私の横にいるのが好きなことを知ってるので、うちに来てくれるお医者様と一緒に頑張りました。手を握っていました。ずーっと。手を握って、ずーっと。
「病院に行けばもっと長生きできたのでは?」という記者の質問を受けて、うつみさんは、「病院へ行ったら治るものですか?」と返しました。この言葉に、うつみさんが在宅療養という選択肢になんの後悔も持っていないことが伺えます。私も日々、愛川さんご夫婦と同じようなケースの患者さんを診ていますが、皆さん迷いがありません。迷いが生じるのは、遠くに住んでいる長男や長女が「今すぐ大病院へ行こう」と突然介入し、夫婦の決断を壊すときです。そういうときは、在宅医も彼らとの話し合いに多くの時間を費やすことになります。
さて、もう一つご紹介しましょう。愛川さんの死を受けて、民放の某人気情報番組で大病院の肺がん専門医の方がお話されたことです。
<某人気報道番組でのキャスターと大病院の専門医のやりとり>
キャスター:60%以上の方がご自宅で療養したいって言われていますが、現実にはなかなかないというのは、どこが原因ですか?
大病院の専門医:まずひとつは介護する人がいないということです。実際にいないのではなく、やりたいんだけど体力的にはなかなかできない。精神的にもつらい。急に何が起こるかわからないので怖いと。そういう状況があります。
キャスター:家族の承諾もいると。
大病院の専門医:ただまあ、その状況でなかなか踏み切れないんですよね。お金もかかる。しかも、一番困るのは突然、急変した時にどうしていいかわからない。
キャスター:病院よりも(医療費が)安くなるっていうことはあるんですか?
大病院の専門医:国が払うお金は安くなります。しかし、保険のカバーされている中では、なかなか十分な介護ができないという現実もありますね。
キャスター:お医者様に定期的に来てくださいって言ったら、来てくださるんですかね?
大病院の専門医:それは来てくれるのですけど、抗がん剤に対応できる在宅医が周りにいるかという問題もあります。我々が行くわけにいきませんので。対応してくれる在宅医がいる場合は、僕らはもう任せています。対応できない場合は必ず我々のところ(大病院)に戻ってきていただいて、相談させていただく。
キャスター:やっぱり病院に相談するのが一番ですか? 自宅でやりたい場合は。
大病院の専門医:ただ、全部できる在宅医もおられますので……なかなか医者(在宅医)のスキルと言いますか、一様ではないので。
この病院の専門医はおそらく在宅医療の現場を一度も見たことがないのでしょう。“肺がん”はよく知っていても“肺がんの在宅療養”に関してはご存知ないようです。こうしたネガティブなコメントをテレビで披露されてしまうと、在宅での希望が萎える患者さんも出てくるはずで、在宅医の私としては非常に残念です。 「何かあれば病院に戻って来てもらう」ということですが、私の場合はそのような指示をすることはありません。患者さんや家族がそれを希望された時のみ病院に戻ることが稀にあります。
一方、「在宅医のスキルが一様でない」という指摘はその通りかもしれません。医療用麻薬は在宅でも普通に使えますが、現実には医師のスキルに差があるので啓発や再教育が急がれているところです。私は、今回の出来事で、笑顔で満足して在宅療養を楽しんでおられる患者さんの様子を、病院の医師にもっとフィードバックしなければいけないと改めて思いました。
愛川さんは、肺がんでも大切な最期の時間を大切な人と住み慣れた自宅で生活できることを多くの国民に教えてくれたように思えてなりません。愛川欽也さん、ありがとうございます。ご冥福をお祈り申し上げます。
■ 長尾和宏(ながお・かずひろ) 長尾クリニック院長。1958年香川県出身。1984年に東京医科大学卒業、大阪大学第二内科入局。阪神大震災をきっかけに、兵庫県尼崎市で長尾クリニック開業。現在クリニックでは計7人の医師が365日24時間態勢で外来診療と在宅医療に取り組んでいる。趣味はゴルフと音楽。著書は「長尾先生、「近藤誠理論」のどこが間違っているのですか?」(ブックマン社)、「『平穏死』10の条件」(同)、「抗がん剤10の『やめどき』」(同)。
[夕刊フジ]
Posted by nob : 2016年01月07日 22:10
なるほどね。。。
■1回だけも数十秒もダメ! 正しい体温の測り方って?
36度以下の平熱が続いている状態を「低体温」といいますが、そのままにしておくと心身のトラブルも! そこで自分が低体温かどうかをチェックするには、なにはともあれ体温を測ってみること。
といっても、体温は一日のうちで結構大きく変動する。一般的には深夜に最も低くなって夕方から夜にかけて最も高くなる。その差はおよそ1度。つまり、いつどんなタイミングで測るかによって数値にバラつきがあるので、たまに体温を測ってもその数値が必ずしも自分の平熱とはいいきれない。「クリニック真健庵」院長の吉村尚美先生に直撃!
「正確な体温を計測するには、昔ながらの水銀柱の体温計がおすすめです。皮膚の中でも温度が高い腋の中心に正しく体温計を挟んで、10分間測ります。朝、昼、晩と3回測り、平均値を出しましょう。その数値が平熱となります」
現在では数十秒で測れる予測式体温計が主流。予測式による数値は10分後の実測値を予測したもの。このタイプの体温計には10分間の実測検温ができるものもあるので、一度は時間をかけてしっかり実測してみましょう。
※『anan』2016年1月13日号より。取材、文・石飛カノ
[ananNEWS]
Posted by nob : 2016年01月07日 12:26
前回いつかかったのか記憶がないほど久しぶりに風邪をクリスマスプレゼントに、ここぞ体内清掃とばかりに医薬品なしで静養中の雑炊で極度の発汗、人生4度目の失神してしまいました。
■失神
失神(気絶)は、突然起こる短時間の意識の消失です。
*失神は脳の機能が障害を受けると起こります。
*めまいやふらつきが一般的ですが、失神の原因によっては他の症状が出ることもあります。
*失神の原因を突き止めるために、チルト試験や心機能の検査が行われます。
*通常、横になることで意識は戻りますが、基礎疾患の治療が必要になるかもしれません。
失神は、脳に十分な酸素や他の栄養素が供給されないために起こる症状で、普通は一時的な血流量の減少によって生じます。体が血圧の低下を急速に回復できない限り、脳への血流は減少します。
原因
脳の機能が全体的に障害されない限り、意識を失うことはありません。このような障害は、通常は脳への血流量の減少によります。脳への血流量の減少は心疾患が原因で発生することもありますが、より一般的には何らかの原因により心臓に戻る正常な血流が妨げられ、それによって脳(および体の他の部分)への血流が減少することで起こります。まれに、脳底部の血管の疾患によって脳への血流量が減少することがあります。脳疾患であるてんかんによっても意識は失われますが、これは失神とはみなされません。慎重に検査しなければ、患者も医師も失神とてんかんを区別できないことがあります。
心機能の障害: 血圧を正常に保つのに十分な量の血液を心臓が送り出せなくなると、失神することがあります。たとえば、不整脈や心臓弁障害は心臓の機能を損ないます。このような障害がある人は、安静時には問題を感じません。しかし、運動時には失神しそうになったり、実際に失神したりします。これは運動によって体の酸素需要量が増え、それに見合うだけの血液を心臓が送り出せないためです。こうした失神は労作性失神と呼ばれます。このような障害がある人は、運動後に失神することもあります。運動中は心拍数が増えるため、心臓は血圧を適切に維持するのに十分な血液をなんとか送り出すことができますが、運動をやめると心拍数と心拍出量が減り始めます。しかし、運動中に多量の血液を筋肉とやりとりするために拡張していた筋肉内の血管は広がったままです(具体的には、筋肉内の細動脈は筋肉組織へ酸素と栄養素を供給するために拡張したままであり、静脈は運動中に生じた老廃物を取り除くために拡張したままです)。心拍出量の減少と細動脈や静脈の拡張が同時に起こると、血圧が低下して失神します。
肥大型心筋症(心筋症: 肥大型心筋症を参照)と呼ばれる心臓の異常も、運動中に起こる失神の原因となります。大動脈弁の重度の狭窄も同様の影響を及ぼします。これらの疾患は高齢者にも若年者にもみられますが、とりわけ高血圧の人に多くみられます。治療しないと死に至る可能性があります。
血流量の低下: 血液量が減りすぎると失神が起こる場合があります。血液量が低下する主な原因は出血です。その他に、下痢、多量の発汗、水分の摂取不足、多量の排尿(無治療の糖尿病[糖尿病(DM): 糖尿病を参照]やアジソン病[副腎の病気: アジソン病を参照]でみられる一般的な症状)などによる脱水症も原因となります。高齢者では、特に暑い季節や病気のため十分に水分を摂ることが難しい場合などに利尿薬を使用すると、脱水症を起こすことがよくあります(利尿薬は腎臓からの塩分と水分の排出を促し、尿量を増やして体内の体液量を減らします)。
加齢による影響
低血圧は、心臓に影響を及ぼす多くの疾患によって起こります。心疾患の多くは高齢者に一般的にみられるため、高齢者は低血圧になりやすい傾向があります。
心臓発作で心筋が衰えると、送り出すことができる血液の量が減り、低血圧につながります。感染症や心臓弁障害、心臓にダメージを与える薬の使用によっても、心機能は低下することがあります。また、心膜炎では、心臓を包む心膜(心嚢)の中にたまった体液が心臓を圧迫するため、血液を送り出す能力が低下します。
異常に遅い、または異常に速い心拍によって低血圧が起きることもあります。心拍が遅い場合(徐脈)、心臓は十分な量の血液を体に送り出すことができません。また、心房細動などにより心拍が速くなると、拍動の間隔が短くなり心室は血液で満たされず、十分な血液を体に送り出すことができません。
心疾患の治療に用いるカルシウム拮抗薬やアンジオテンシン変換酵素阻害薬、利尿薬、パーキンソン病治療薬などの薬の中にも、血圧を下げるものがあります。
起立性低血圧は、高血圧の治療薬を服用している高齢者に特に多く見られます。高齢者では、排尿時(排尿失神)や食事の後(食後低血圧)に低血圧や意識の消失がみられる傾向もあります。
体は低血圧を予防する多くの機構を持っていますが、高齢者ではこの機構がうまく働かなくなります。
迷走神経への刺激: 首、胸、腸へとつながる迷走神経が刺激されると失神が起こることがあります。迷走神経が刺激されると心拍が遅くなります。またこの刺激により、吐き気、皮膚が冷たく湿っぽくなるなどの症状がみられます。このような失神は、血管迷走神経性(血管運動性)失神と呼ばれます。迷走神経は、痛み、恐怖、血を見たことなどによる不快感、嘔吐、多量の排便、排尿などによって刺激されます。排尿中または排尿直後の失神は、排尿失神と呼ばれます。まれに、食べものを勢いよく飲みこむことで迷走神経が刺激されて失神することもあります。
血流量の減少: 緊張によって、心臓に戻る血液の量が減少した場合にも失神することがあります。せきによる失神(咳嗽失神)は通常、そのような緊張によって起こります。排尿後や排便後の失神の一部は、緊張と迷走神経の刺激が原因です。前立腺肥大のある高齢の男性が、排尿時に膀胱を空にするためにいきむ必要がある場合、この種の失神を起こしやすくなります。重いものを持ち上げたときに起こる失神(重量挙げ失神)は、運動中に十分な呼吸をせずに重いものを持ち上げたり押したりしようとするときの緊張が原因です。
血圧の問題: 急に座ったり立ち上がったりしたときに起こる失神は起立性失神といいます。特に高齢者に多くみられます。起立性失神は起立性低血圧が原因です(低血圧: 起立性低血圧を参照)。起立性低血圧とは、立ち上がったときに重力により脚の静脈に血液がたまって生じる低血圧を、血管の収縮や心拍数の増加などの代償機序によって十分に回復できない状態です。これと似た失神に閲兵場失神があります。閲兵場失神は、暑い日に長時間立ったままでいるために起こります。脚の筋肉を使わないでいると、心臓に血液を戻せなくなります。その結果、脚の静脈内に血液がたまって血圧が低下します。
高齢者では、食後に血圧が下がりすぎる食後低血圧(低血圧: 食後低血圧を参照)によって失神することがあります。
その他の問題: 不安などによって非常に呼吸が速くなる過呼吸あるいは過換気によっても失神が起こることがあります。この失神は過換気性失神と呼ばれます。過呼吸では、体から大量の二酸化炭素が吐き出されます。二酸化炭素の血中濃度が低下すると、脳内の血管が収縮し、気が遠くなったり失神したりします。
まれに、脳の一部(底部)への血流が突然減少する軽度の脳卒中によって失神が生じます。脳卒中による失神は高齢者でより多くみられます。赤血球の不足(貧血)、肺疾患、血糖値の低下(低血糖)、糖尿病など、他の多くの疾患によって、特に代償機序も損傷した場合には失神が生じます。
特定の薬も失神の原因となります。そのような薬の中には高血圧、狭心症、心不全の治療に使われる薬が多数含まれています。これらの薬を使用する場合は、血圧を下げすぎないように慎重に投与量を調整する必要があります。
症状
特に立っているときには、失神する前にめまいがしたり、ふらついたりします。失神して倒れた後は血圧が上昇しますが、その理由の1つは、横になることで血液が重力に逆らわず脳へと流れるようになり、失神の原因が取り除かれるということです。しかし、あまり急に起き上がると再び失神します。
不整脈による失神は通常、突然始まって突然回復します。場合によっては、失神する直前に動悸を感じることもあります。
血管迷走神経性失神は座っているときや立っているときに起こります。失神する前には、吐き気、脱力感、あくび、視力障害、発汗などがよくみられます。皮膚は冷たく湿っぽくなり、顔色は非常に青白くなり、脈拍が非常に遅くなって失神します。
前兆症状とともに徐々に始まり、同じようにゆっくりと回復していく失神は、血液中の変化、たとえば糖濃度の低下(低血糖)や二酸化炭素濃度の低下(低炭酸ガス血症)などが原因で発生します。低炭酸ガス血症が起こる前にはたいてい、指先や唇の周りにしびれてチクチクするような感覚があります。
診断
失神を起こす原因の中には重大なものも含まれるため、医師は原因の特定を試みます。不整脈や大動脈弁狭窄症などの心疾患は命にかかわります。その他の原因であれば、それほど心配する必要はありません。
症状の特徴から原因が示唆されることもあります。その場に居合わせた人の話も役立ちます。深刻な疾患が懸念されるのは、前兆症状なしに(特に運動時に)発生する失神、息切れや胸痛などを伴う失神、けがにつながる失神、失神した患者に心臓や神経系の検査で異常な所見が認められた場合です。また、何らかの疾患を有するかどうか、処方薬や市販薬を服用しているかどうかも確認する必要があります。
ストレスの多い状況で起こった失神や、吐き気、発汗、冷たく湿っぽい皮膚、蒼白など、血管迷走神経性失神の症状がみられた後で起こる失神は重症ではないことが多く、診断のための検査や治療が必要になることはまれです。
心臓の電気的活動を記録する心電図検査(ECG)により、原因となっている心疾患を検出できることがあります。失神の原因を決定するには連続的な心電図検査が必要となる場合があります。この検査では、電池式の小型の装置(ホルター心電計)を装着します。ホルター心電計は、普通に日常生活を送っているときの心臓の電気的活動を24時間以上記録します(ホルター心電計による心電図の連続記録イラストを参照)。もし、失神と一致して不整脈がみられる場合は、必ずとはいえませんが、不整脈が失神の原因と考えられます。
超音波により心臓の画像を映す心臓超音波検査(心エコー検査—心血管系の病気の診断: 心臓超音波検査(心エコー)とその他の超音波検査を参照)など、その他の検査では、心臓に構造的または機能的な異常があるかどうかを検出できます。血液検査では、低血糖症や貧血の有無がわかります。
てんかんによる意識消失(けいれん性疾患を参照)は、失神とは原因も治療法も異なるため識別が必要です。これら2つを識別するために、脳の電気的活動を記録する脳波検査(EEG)を行うことがあります(脳、脊髄、神経の病気の診断: 脳波検査を参照)。また、てんかんの後は意識消失から回復するのが遅く、意識がもうろうとした状態が少なくとも10分は続きます。
失神の原因であると考えられる障害を特定するため、医師は安全な条件の下で失神発作を再現してみることがあります。たとえば、患者に速く深く呼吸してもらう場合や、心電図検査で心拍を監視しながら頸動脈洞(血圧を監視するセンサーがある内頸動脈の一部)の上を静かに圧迫する場合があります。この圧迫で頸動脈洞内の血圧が一時的に上昇するため、体は全身の血圧が上昇したと思いこみます。頸動脈洞は血圧を下げるように脳へ信号を送り、その結果、意識が遠のいたり失神したりします。
チルト試験(心血管系の病気の診断: チルト試験を参照)は、失神の原因を突き止めるために一般的に行われます。モーターのついた検査台の上に患者をベルトで固定し、その後、検査台をほぼ立っている状態まで傾けます。この位置で最大45分間静止し、血圧と心拍数を連続して監視します。血圧が下がらない場合は、心臓を刺激するイソプロテレノールを投与し、検査を繰り返します。この薬を投与すると検査に反応しやすくなります。
治療
多くの場合、体を水平に寝かせておくことで意識は回復します。脚の位置を高くすると、心臓と脳への血流が増して回復が早くなります。急に起き上がったり、何かに寄りかかったり、直立の姿勢で運ばれたりすると、再び失神する可能性があります。したがって、失神した人は完全に回復するまで寝かせておくべきです。
心拍があまりにも遅い場合は、心拍動を刺激する電子装置、ペースメーカを植え込む手術を行って心拍を適切に調節します(正常な拍動を保つ人工ペースメーカについてイラストを参照)。心拍があまりにも速い場合は、アテノロール、メトプロロールなどのベータ遮断薬(ベータ・ブロッカー)などの薬で心拍を遅くします。心拍が不規則な場合は、正常な律動を回復させるために除細動器を植え込むことがあります(不整脈: 正常な律動の回復を参照)。低血糖や貧血など、その他の原因による失神も治療できます。血液量が非常に少ない場合は点滴で輸液を補給し、心臓弁障害の場合には手術を考慮します。
[メルクマニュアル医学百科]
Posted by nob : 2015年12月28日 12:53
自ら学び、考え、(治療方法を)決める、、、自らの生を救えるのは自分自身のみ。。。
■“がん治療”偏った考え方に陥らないようにするには?
今年9月、肝内胆管がんで亡くなった女優の川島なお美さんは、2013年8月に健康診断で腫瘍が見つかり、翌年1月に手術を受けたものの、その後は外科手術や抗がん剤治療を拒否。高濃度ビタミンC濃縮点滴や温熱療法といった代替医療や、金の棒を患部にあててさする「ごしんじょう療法」といった民間療法に取り組んでいたという。
しかし、代替医療や民間療法は効果を科学的に証明する「エビデンス」が十分ではなく、その治療を選択することに対して懐疑的な意見も飛び交っている。
書店の「家庭の医学」の棚にいくと、さまざまな人がさまざまな立場から書かれた本が並んでおり、何が一体正しく、何が一体正しくないのか悩ましく感じることもある。
医師といっても、その専門領域は様々だ。
例えば、アスコムの『医者は自分や家族ががんになったとき、どんな治療をするのか』は、西洋医療と代替医療を組み合わせた“統合医療”の実践を進める川嶋朗氏が執筆しており、「どんな治療法であっても、それによって健康を損なうリスクがなく、また経済的に余裕があるなら、どんどん試してみてよいのではないか」という私見を表明している。
川嶋氏は東洋医学や自然医療を専門としている医者であり、その視点に基づいて本が書かれている。そのため、代替医療についての記述は深く、本書では「手を出してはいけない代替医療」についても触れられている。
がん治療専門医の大場大氏は『東大病院を辞めたから言える「がん」の話』(PHP研究所/刊)の中で、「標準治療」を最善の治療とした上で、「先端医療」や「先進医療」が持つ「ハイグレードな治療」なイメージに対して警鐘を鳴らす。
がん治療における「標準治療」とは「抗がん剤治療」「放射能治療」「外科手術」のことで、どの先進国であっても通用する推奨レベルの最も高い治療を指す。ところがそうした「標準治療」を否定する主張をする人たちもいる。
大場氏は、特に“がんもどき理論”を提唱する近藤誠氏の「がん放置療法」に対して厳しい批判を加えながら、メディアを通して「がん治療」が歪んだ形で一般大衆に広まっていることを指摘する。
「がんの治療」は生命にそのまま直結することであり、どうしても情報はセンセーショナルに広まってしまいがちだ。そこに医療不信が覆いかぶさり、世間はネガティブな情報に敏感になってしまう。
長尾和宏氏は『抗がん剤が効く人、効かない人』(PHP研究所)の中で、かつて抗がん剤が大嫌いだったが、ここ数年いい薬が開発され、「もしもがんになって、抗がん剤が効くタイプであれば受けてみよう」と思うようになったと述べている。つまり、自分が触れている情報が一体いつのものなのかという視点も必要になってくるのだ。
「がん治療」にまつわる様々な情報は、私たちの生活の至るところに転がっている。しかし、それぞれ主張することが違うため、どの医師の言うことを信じればいいのか分からず、詐欺まがいの治療法をすすめる人につけこまれる可能性もある。
しかし、いかなる情報をあさっても「確実」「絶対」はない。メディアが使う「効く」という言葉も、必ずしもそれはイコールとして「治る」ではないだろう。では、そういった不確定な情報ばかりの中でどう判断すればいいのか?
重要なことは、自分の治療法について医師からじっくり説明を受けた上で、納得のいく決断をすることではないだろうか。セカンドオピニオンを仰ぎつつ、自分にとって適切な方法を選ぶ。戦うのは患者本人なのだから。
人間はセンセーショナルな言葉に弱い。それに負けないようになるためには、がんについての正しいリテラシーを持つことが大事だろう。さまざまな主張や情報を目に通しながら、納得のいく結論を導き出すことが必要だ。
(新刊JP編集部)
[新刊JPニュース]
Posted by nob : 2015年12月16日 19:07
解りやすい。。。
■知っておこう!がんの基礎知識
がんを治すなら早期発見
がんは、正常な細胞のブレーキが壊れ、増殖し続けるようになったものです。私たちはもともとがんになりやすい遺伝子と、がん抑制遺伝子を持っています。生活習慣の改善で、ある程度、がん遺伝子を活性化させないようにできることがわかっています。
◆ 悪性腫瘍は脳、内臓、皮膚、骨、筋肉、血液など、からだのあらゆるところに発生します。医学的には、悪性腫瘍のうち「がん」は内臓の粘膜や皮膚などの上皮細胞というところに発生するものを指します。一方、「肉腫」と呼ばれるものもあり、骨や筋肉など、上皮細胞ではないところに発生し、非上皮性悪性腫瘍とも呼ばれます。骨肉腫や軟部肉腫、また白血病なども含まれます。ここでは、悪性腫瘍全体を指して、「がん」といいます。
◆ 私たちの細胞は必要に応じて増殖し、必要数に到達したら増殖をやめるようにプログラミングされています。しかし、なんらかの誘因でこのプログラムが障害され、細胞の増殖が止まらなくなってしまうのががんです。がん細胞は遺伝子の変異を続け、性質を変化させ、さらに広がって増殖を加速させるようになります。
◆正常な遺伝子ががん遺伝子になる可能性のあるものを「がん原遺伝子」と呼びます。一方、細胞の増殖を抑制し、遺伝子に生じた傷を修復する、いわばがん化を防ぐものもあり、これは「がん抑制遺伝子」と呼ばれます。
◆ がん原遺伝子ががん遺伝子になってがんを発生させるには、進行の速いがんを除いて、5年以上、10年単位の時間が必要です。がん遺伝子が発生しても、がん抑制遺伝子や自己免疫の働きで、がん遺伝子を消滅させて増殖を食い止めることも可能です。体内では目に見えない攻防が日々繰り広げられているといってもいいでしょう。
◆がんの発生・進行にかかわるリスク要因は、
①喫煙(ほぼすべてのがん)
②肥満(食道がん、結腸がん、乳がん、腎臓がんなど)
③過度の飲酒(口腔がん、咽頭・喉頭がん、食道がん、肝がんなど)
④運動不足(結腸がん)
などです。また、紫外線が皮膚がんの原因になり、放射線や化学物質などもさまざまながんの発生に関与しています。
◆ 一般的に早期発見のがんほうが標準治療が確立され、治療法の選択肢も多いので、仕事や家庭など、事情に合わせた治療法を選ぶこともできます。もっとも進行の速いがんの場合、健診と健診の間にがんが発生して大きくなっているようなケースもありますが、統計的な頻度としてはそれほど多くないといえるでしょう。
◆がん発生機序の解明や抗がん剤をはじめ治療法の開発は日進月歩です。治療だけでなく、予防という観点でも調査・研究が進んでいます。医療を受ける側からも、2人に1人の発症リスクをしっかりと受け止めて、がんを予防するヘルスケアに努めたいものです。
(監修:東京医科大学病院 総合診療科准教授 原田芳巳)
[ケータイ家庭の医学SP]
Posted by nob : 2015年12月10日 13:00
なるほど、、、でも私は炊きたてごはんを美味しくいただきます。。。
■カロリーを60%カット!ココナッツオイルごはんがスゴイ!
最近、巷でブームを巻き起こしている「冷やごはんダイエット」。
お米に含まれるでんぷん質は、冷やすことでレジスタント(消化されない)スターチ(でんぷん)に変わります。これは、その特性をいかしたダイエット方法です。
温かいままだと吸収されやすいお米も、レジスタントスターチに変わった冷えたお米を食べることで、小腸で吸収を抑えて、大腸まで届かせることができます。
つまり、お米を我慢することなく、血糖値の上昇を抑制し、摂取カロリーを制限することができるというわけですね。おまけに、便秘の改善効果も大!
ですが……
「寒い季節に冷えたごはんなんて食べたくない!」
「そもそも、まずい!」
なーんて声がチラホラ……。
女性は“冷え”の悩みを抱えた人も多いので、「冷やごはんダイエット」は、どちらかというと筋肉質の男性におすすめのダイエット法といえるみたいです。
そこで今回、筆者が女性に強くおすすめしたいのが「ほかほか☆ココナッツオイルごはんダイエット」なんです!
■冷えごはんと同等の効果がある「ココナッツオイルごはん」
これまで、レジスタントスターチの効果は、冷えたお米でないと発揮されないといわれていました。
ですが、アメリカ化学会で行われたスリランカのコロンボ大学のサットヘア・ジェームズ氏の最新の研究発表によると、ココナッツオイルを使用して炊いたお米は、再加熱しても同等の効果が得られることがわかったとのこと。
さらに、ココナッツオイルを入れたお米は、通常よりも、レジスタントスターチが10倍増加。これ、カロリーに換算すると50〜60%ものカットになるんだそうです!
というわけで、さっそくココナッツオイルごはんを作ってみましょう!
【ココナッツオイルごはんのつくり方】
【材料】
米……1カップ
熱した湯……200ml
エクストラバージンココナッツオイル……小さじ2
1 鍋もしくは炊飯器に米と湯を入れる
2 ココナッツオイルをくわえてよく混ぜる
3 炊飯する
4 冷蔵庫で12時間冷やす
食べる際は、電子レンジで加熱すればOK!
ココナッツオイルごはんは、ほんのりとココナッツの香りがするので、カレーなどにもよくあいそう……。ごはん好きにはたまりません〜。ココナッツオイルの香りが苦手という人は、香りカットのココナッツオイルを使ってくださいね。
塗ってよし、食べてよしの万能のココナッツオイルを使ったごはんで、空腹知らずに美ボディGET!みなさんも是非、試してみてはいかがでしょうか。
YUE
YUEビューティ&ライフコラムニスト
渋谷生まれ渋谷育ち。モデル、アパレル会社、編集プロダクション勤務を経てライターに。10キロの体重増減を繰り返した体験によりダイエット、美容に対する探求心が旺盛。美容ニュースやムック本等で執筆中。
[GODMake]
Posted by nob : 2015年12月07日 10:53
どこからのどんな情報を良しとして選択するか、、、自らの生を救うための第一歩。。。
■減塩する必要はなくコレステロール制限も無意味と近藤誠医師
「女性は医療産業のターゲットになりやすいので、気をつけたほうがいいですよ」と語るのは、『先生、医者代減らすと寿命が延びるって本当ですか?』を上梓した、医師の近藤誠先生だ。
「女性は体の変化の波が大きい。生理による毎月の変動に妊娠、出産。閉経を迎えても、やれホルモン補充療法だ、骨粗鬆症だと常にゴールがなく、人生のさまざまな局面で商売の的にされやすい。だからこそ、本当に正しい健康知識で身を守ってほしいんです」(近藤先生、以下「」内同)
そんな近藤先生に、巷で信じられている健康法に関し、意見を聞いてみた。
“塩分控えめが体にいい”というイメージが定着しているが、近藤先生は否定する。
「昨年、17か国の約10万2000人を対象に塩分摂取量と死亡率の関係を調べたデータで、1日の塩分摂取量を「10g以下にすると寿命が短くなる」と判明しました。総死亡率がもっとも低かったのは、1日の塩分摂取量が10~15gの人たち。それに比べ、7.6g未満の人たちは27%増しという結果となっています」
日本高血圧学会は、1日の塩分摂取量6gの減塩生活を推奨している。塩分の摂りすぎが高血圧の原因となり、脳出血や脳梗塞、心疾患、慢性腎臓病を招くという理由からだ。しかし、近藤先生は「高血圧が脳出血の原因とする点がまず疑わしい」ときっぱり言う。
「その昔、東北地方の人々はしょっぱい漬物や干物をたくさん食べるために高血圧となり、脳出血になると考えられていましたが、実際には低栄養のため血管がもろくなって破れていたようです。
「女性は医療産業のターゲットになりやすいので、気をつけたほうがいいですよ」と語るのは、『先生、医者代減らすと寿命が延びるって本当ですか?』を上梓した、医師の近藤誠先生だ。
「女性は体の変化の波が大きい。生理による毎月の変動に妊娠、出産。閉経を迎えても、やれホルモン補充療法だ、骨粗鬆症だと常にゴールがなく、人生のさまざまな局面で商売の的にされやすい。だからこそ、本当に正しい健康知識で身を守ってほしいんです」(近藤先生、以下「」内同)
そんな近藤先生に、巷で信じられている健康法に関し、意見を聞いてみた。
“塩分控えめが体にいい”というイメージが定着しているが、近藤先生は否定する。
「昨年、17か国の約10万2000人を対象に塩分摂取量と死亡率の関係を調べたデータで、1日の塩分摂取量を「10g以下にすると寿命が短くなる」と判明しました。総死亡率がもっとも低かったのは、1日の塩分摂取量が10~15gの人たち。それに比べ、7.6g未満の人たちは27%増しという結果となっています」
日本高血圧学会は、1日の塩分摂取量6gの減塩生活を推奨している。塩分の摂りすぎが高血圧の原因となり、脳出血や脳梗塞、心疾患、慢性腎臓病を招くという理由からだ。しかし、近藤先生は「高血圧が脳出血の原因とする点がまず疑わしい」ときっぱり言う。
「その昔、東北地方の人々はしょっぱい漬物や干物をたくさん食べるために高血圧となり、脳出血になると考えられていましたが、実際には低栄養のため血管がもろくなって破れていたようです。
実のところ、塩分摂取量と血圧の関係は解明されていないんです。相関関係はあっても、因果関係があるとはいいがたい。少なくとも、健康な人が1日6g以下に減塩する必要はありません。根拠もなく、むしろ危険。減塩のしすぎは、逆に寿命を縮める可能性があります」
卵のコレステロールや乳脂肪分を気にしている人も多いが…。
「コレステロールは細胞膜やホルモンの原料となり、生命に欠かせない重要な成分。閉経すると卵巣からのホルモン分泌が止まりますが、副腎や脂肪細胞で女性ホルモンは作られ続ける。
コレステロールが少ないということは体内の細胞がもろくなることも意味し、低コレステロールの人はがん死亡率が高いというデータもあります」
1976年から、“長寿地域”として有名だった東京都小金井市の70才の人の食事を追跡した調査がある。10年後に80才を迎えた人の「1日の総摂取エネルギーに対する脂肪の比率」をみると、男性は10年間で23.7%から26%へ、女性は22.5%から26%に増えていたという。
「年をとって、むしろ、こってり系をよく食べ始めた人が長生きしているんです。食事でコレステロールを制限するのは無意味・有害です。肉、魚、卵や牛乳など、脂肪とたんぱく質を毎日しっかり摂ることが、健康に長生きする秘訣ですよ」
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2015年11月30日 17:03
言わずもがな、、、でしょっ。。。
■タバコ級にヤバい!毎日飲むと「4.6歳も細胞が老化」する飲み物とは
疲れたときにプシュッと開けて飲む、いいですよね~。 えっ? ビールの話ではありません。炭酸飲料水の話です!
全国清涼飲料工業会がまとめた“清涼飲料水品目別生産量推移”を見ると、他の清涼飲料水を押さえて近年は炭酸飲料が群を抜いて生産されていると分かります。
ただ、この炭酸飲料、飲み過ぎると実は細胞の老化原因になるとご存じでしたか? そこで今回は米カリフォルニア大学サンフランシスコ校の情報を基に、飲み過ぎに要注意の炭酸飲料とその量をまとめます。
■1:砂糖入りの炭酸飲料が細胞を老化させる
炭酸飲料と言っても色々な種類が売られていますが、老化の原因になると指摘される炭酸飲料は砂糖の入ったタイプ。
米カリフォルニア大学サンフランシスコ校によると、この手の炭酸飲料は細胞の老化を早める原因になるのだとか。
そもそも細胞とは学校で習った通り、人間の体そのものです。人体は60兆個の細胞が積み上がってできているのですね。
そうした細胞は全て、分裂を繰り返して死んでいく“寿命”があります。この寿命は細胞によって違い、1日半で死んでしまう細胞もあれば、神経細胞や心筋細胞のように100年以上生き続ける細胞もあります。
■2:老化の悪影響はタバコ級
しかも同大学の調べによると、500mlペットボトルの砂糖入り炭酸水を1日1本程度のペースで摂取するだけで、4.6年分も細胞の寿命が短くなってしまうと分かったとか。
言い換えれば細胞が4.6歳も老け込んでしまうのですね。この悪影響はなんと喫煙と同程度……。
まだ同調査には課題が多いと研究者たち自身も認めていますが、これから炭酸飲料水を飲む際には成分表をチェックし、炭水化物(糖質+食物繊維)の量を確かめてください。
炭酸飲料水には基本的に食物繊維は含まれていないと考えられますので、ほぼ炭水化物=糖質の量なのです!
■3:細胞の寿命のメカ二ズム
前述の通り、細胞は分裂を繰り返しながら寿命をむかえます。この細胞分裂と寿命の鍵を握る物質が“テロメア”と呼ばれるもの。
細胞の核の中には遺伝子がギュッとまとまった、普段はこけしのような形をした染色体があります。この染色体の両端に被さっているニット帽のような存在がテロメアです。
テロメアは長さが重要で、細胞分裂のたびに短くなってしまいます。長~いニット帽が巻き上がってどんどん短くなってしまうイメージ。
そして一定のサイズをテロメアが下回ってしまうと、その染色体(&テロメア)を抱え込んだ細胞は分裂できずに死んでしまいます。
実は砂糖の大量に入った炭酸水の日常的な摂取は、正確な仕組みは分かっていないそうですが、このテロメアを短くしてしまうと指摘されているのですね。
いかがでしたか? 今は清涼飲料水のメーカー各社も消費者の健康を考えて、さまざまな商品を出してくれています。できるだけ炭水化物(糖質)が少ない炭酸飲料をチョイスする習慣を作りたいですね。
(ライター 坂本正敬 )
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2015年11月30日 16:42
私がバニック障害を発症したのも爆弾低気圧の日でした。。。
■そのうつ、実は天気のせいかも…本当は怖い「天気痛」
「雨が降る前は片頭痛が悪化する」「低気圧が来ると、昔ケガをしたところが痛む」など、これらは気象の変化によって持病が悪化することを指すもの。昔から天気と人の体調には相関関係があるが、近年、大型台風の増加などの異常気象により、天気痛を訴える人が増えているとう。
しかも実は、「天気痛」という言葉の名付け親でもあり、愛知医科大学病院で「天気痛外来」を開設している医師の佐藤純氏によると、頭痛や関節痛だけでなく、うつや不安症、不眠症といった心の病気も、天気の変化に左右されるのだそうだ。
そのうつ、実は天気のせいかも!? 本当は怖い天気痛「気圧が上がったり下がったりすると、自律神経が乱れ、不調が生じるのが天気痛のメカニズムですが、『心の不調』といわれる諸症状も、気圧の変化に大きく左右されます。例えば、最近増えている新型うつ。また、心の中にもやもやとした感情を抱えている不安症、人と話をするのが得意ではない、過去の出来事にショックを受けて引きずっている、パニック発作など、広範囲に及びます。重症患者さんじゃなくても、天気の変化が激しい春、梅雨、秋などは、『何故か気持ちが落ち込む』『だるくて起き上がれない』となる方は多いです」(佐藤氏)
10年以上も悩まされていたうつが、ある日突然……
これを裏付けるような、実際の診療例がある。原因不明のうつが、実は気圧由来だったというケースだ。
佐藤氏の診療室の門をたたいた50代のある男性は、10年以上も原因不明のだるさやうつ的な症状に悩まされていた。その男性は理科系の研究開発をしており、仕事の内容は緻密さを要求される厳しいもの。産業医からの診察を受けて休職したものの、復職してもしばらくするとまた心身の不調が起こり、10年のうちに5~6回休職と復職を繰り返したという。
「そのうち、自分の症状が『天気にも左右されているのではないか』と思うようになったのだそうです。というのも天気が悪い日は、あからさまに起き上がれなくなってしまう。産業医や精神科の先生にそう訴えたものの『まあ、天気も関係あるんだろうが、今のところは天気にはなすすべがない』と言って、睡眠薬や精神に作用する薬、内科的な症状に合わせた薬を処方してもらうしかなかったそうです。そして薬を服用していても、特に劇的な改善がないまま月日だけが過ぎていきました」(佐藤氏)
そんなある日のこと。テレビで佐藤氏が天気痛について解説しているのを見た男性は、「自分の症状はこれなんじゃないか!?」と思い当たった。
「私がテレビで紹介した『天気痛には、内耳の働きをおさえる酔い止め薬が効く』という方法をとりあえず試してみようと、これから具合が悪くなりそうだなと思ったときに、市販の酔い止め薬を飲んだそうです。すると、モヤモヤ・うつうつとしていた頭が、みるみるうちにパーッと明瞭になって、驚かれたそうです」(佐藤氏)
この経験によって、男性は「自分のうつは、内耳に関わる天気依存の症状に間違いない」と確信。その後、医師の紹介で佐藤氏の外来を受診したが、その時点でうつはかなりラクになっており、「復職できます」と笑顔を見せていたという。
「私の外来に来るのは女性のほうが多いですが、男性も潜在的な患者さんがいると思います。特に働き盛りの男性は、具合が悪くても我慢する傾向にあります。原因不明の体調不良に悩まされるようになったら、『自分は天気痛かも』と疑ってみることが大切です」(佐藤氏)
【佐藤純氏】
愛知医科大学病院で「天気痛外来」を開設。著書に『天気痛を治せば、頭痛、めまい、ストレスがなくなる!』などがある。
[日刊SPA]
Posted by nob : 2015年11月30日 16:36
食事法おさらい/コンビニスローカロリーセレクション
■「食べる順番」食事法、1品で実践する技がある
外せないキーワードは「スローカロリー」
丸田 みわ子
美養食研究家/シニア野菜ソムリエ(野菜ソムリエの最高峰)
自身の体調不良により、健康でスリムで美肌になる 野菜や果物の効果をもっと追究したいと、野菜ソムリエの最高峰であるシニア野菜ソムリエを取得する。
「真の“美”体質」をテーマに、 カラダの中から"美"を養う料理を発信。
「美養食研究家」として、料理教室やセミナー、レシピ開発、 商品プロデュースなどを手掛けている。これまでに考えたレシピは400点、スムージーレシピ100点以上。
「食べる順番」食事法を、コンビニアイテムで実践するには?
今年4月に施行された「機能性表示食品」制度。半年が経過し、届け出件数は300件、受理商品は100件を超える規模になりました。これにより「食事のあり方」が国をあげて見直されているわけですが、忙しいビジネスパーソンの食事にも変化が見られています。
なかでも「糖質オフ」や「食べる順番(最初に野菜類を食べ、その次に肉や魚、最後にご飯やパン、麺類を食べる、というもの)」の考え方は、ただのブームにとどまらない食事法として根付いた感があります。
「スローカロリー」な食べ方とは
また、機能性表示食品制度の開始をにらみ、食品メーカーや医療関係者のグループが研究を進めてきたのが、「スローカロリー」という分野。これもやはり、生活習慣病予防をはじめとする、健康的で規則正しい食生活を推奨するためのものです。
「スローカロリー」は、ゆっくりと消化吸収される糖質の摂り方をしましょうという考え方。具体的には、血糖値が急に上がったり下がったりしない甘味料、糖質が含まれていても食物繊維が多く血糖値が上がりにくい食品(果物、玄米、全粒粉、シリアルなど)を推奨しています。
糖尿病や高血圧、メタボなどの生活習慣病を予防するには、糖質制限が最重要。ただ、たとえばスポーツをする場合などを考えると、糖質はなくてはならないエネルギー源でもあります。どうしても一方に偏りがちですが、そこを「二兎とも追う」ことのできる食事法こそが、スローカロリーな食べ方なのです。
では早速、気をつけるべき点を具体的に見ていきましょう。
基本は「食べる順番」でお馴染みになりましたが、まず野菜料理を最初に食べること。これにより食物繊維がお腹にたまるので、次に食べる物の消化吸収をゆっくりと行い、血糖値の急上昇を防いでくれます。
次に摂るべきは、肉や魚、大豆製品などのタンパク質。お肉については脂質の摂りすぎにならないよう気をつけなければいけませんが、食物繊維が先にお腹に入っていると、高脂肪のリスクがいくらか軽減されます。
タンパク質はスポーツをする人だけでなく、人が生活をする上で必要な筋力をつけてくれる大事な栄養源。そして最後に摂るご飯やパン(糖質)は脳のエネルギーになるので、成長期のお子さんやスポーツ選手に必須の栄養源になります。
また、スローカロリーの考え方では糖質の「質」を上げるために、白米を玄米や雑穀入りご飯に、白いパンを全粒粉やライ麦入りパンに、甘味料は白砂糖ではなくオリゴ糖(てんさい糖)、パラチノース、ラ・カントなどの天然成分でできた甘味料を摂ることを推奨しています。
コンビニで探せる「スローカロリー」な食品
コンビニや食品メーカー各社は日々、この食べ方にあった製品を開発、商品化していますので、チェックしてみてください。
おかずが複数入ったお弁当なら、「食べる順番」でスローカロリーな食べ方を実践できますし、一品で済ませたいなど、食べる順番を無視せざるを得ないときのための「スローカロリー食品」もありますよ。
〈みわ子流、「スローカロリー」の助けになるコンビニアイテム!〉
・バータイプの菓子類
ソイバーやシリアルバーは、忙しくて昼食が取れない時やおやつにピッタリ。大豆やシリアル、雑穀、ナッツ、ドライフルーツには食物繊維が含まれています。
その上大豆はタンパク質、ドライフルーツや雑穀には糖質も含まれるので、スローカロリーな食品と言えるでしょう。
・おむすび類
忙しい時のデスクでのランチに食べやすいおむすびは、玄米のものや、雑穀入りのもの、大麦ご飯のものなど、単品でも食物繊維がとれるものも登場しています。
白米のおむすびでも、五目御飯や豆ごはんなら野菜がたくさん炊き込まれているので、いくらかスローカロリーなおむすびと言えるでしょう。
・ゆで卵
おむすび中心のランチの際、一品加えるといいのがコレ。複数あるアミノ酸(タンパク質)がすべて揃っているうえ、1個あたり約75キロカロリーと安心できる範囲です。高血圧予防のためにも、塩はつけすぎないようにしましょう。
・ドライフルーツ、冷凍フルーツ
糖度はやや高めですが、食物繊維が豊富なので、消化吸収が緩やかで血糖値の上昇も緩やかに抑えられます。おまけにビタミンやミネラルも摂取できます。お菓子を我慢したいけど甘いものが欲しいときに重宝する健康おやつです。
また冷凍フルーツコーナーでは、もともと糖度が低いイチゴ、ブルーベリー、アサイーなども見つかります。
・買い置きの砂糖類
オフィスで飲むコーヒー・紅茶に砂糖を入れる習慣がある方は、白砂糖系(スティックのグラニュー糖、角砂糖など)ではなく、オリゴ糖(てんさい糖)、ラ・カント、スローカロリーシュガー(パラチノース)にチェンジしてみましょう。
11月も後半に入り、来週からはいよいよ師走。忘年会シーズンは暴飲暴食をしがち。冬太りは生活習慣病リスクを高めるので、食べ方を少し工夫して、体の負担が少ない食生活を身につけておきましょう。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2015年11月27日 20:11
酵素 VS ファイトケミカル、、、すべては諸刃の剣、バランスが何より肝要です。。。
■がん予防 野菜は皮ごと煮込み汁ごと食べるのが効果的と医師
がん予防に効果的な栄養素、“ファイトケミカル”とは、植物が作り出す天然の機能性成分。毎日意識してしっかり摂ることで、がんを作り出す原因は撃退できる。
「健康な人でも、体内では毎日5000~6000個の“がん細胞の芽”が生まれています」(麻布医院院長 高橋弘さん・以下同)。
つまり、誰もががんのリスクを持っているというのだ。1つのがん細胞が成長して、がんになるには、平均9年かかる。いち早くその芽を摘み取り、成長を食い止めれば、がんを防ぐことができる。
がんによる死は、約35%が食事、約30%が禁煙、約10%がウイルス感染の予防で防ぐことができるといわれる。中でも重要なのが食事で摂る野菜の量だ。野菜の消費量とがんの発症率は密接な関係があると高橋さんは指摘している。
「野菜の色や香り、辛みなどの成分をファイトケミカルといいますが、この成分がすごいのは、活性酸素を除去する抗酸化作用、免疫力を高める作用、がん細胞の増殖を抑える作用、そのいずれもが非常に優れている点です。がんを防ぐには、このファイトケミカルを含んだ野菜を毎日350~400g摂ることが必要です」
ファイトケミカルは、硬い細胞壁で覆われた細胞の中にあるため、野菜を生食したのでは、体内には吸収されにくい。
「加熱すれば、成分が細胞の外に溶け出てきます。特に豊富なのは皮や芯ですから、できるだけ皮ごと煮込み、汁ごと食べるのがおすすめです」
逆に控えたいのが、鉄の多い肉類や魚介類。鉄は体内に酸素を取り込むのに欠かせないミネラルだが、取り込んだ酸素の約1%は活性酸素になるため、鉄が多すぎると、活性酸素が増えてしまう。しかも、鉄を介してできる活性酸素は毒性が強い。
「女性は閉経後、がんの発症率が上がります。それは、生理によって鉄が排泄されなくなるのも一因。特に閉経後は、鉄分の摂りすぎに注意。また、がん細胞の成長を進める高GI値(糖質が多い)の食品も控えめにしましょう」
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2015年11月25日 10:38
各人の個々の考えに拠けばいいだけのこと、、、私は、選択可能な限りは心と身体に良くないものは摂りません。。。
■発がん性認定のソーセージやハム、怖がる人は交通事故防止に外出を一切やめるべき
今回は「極端君」に登場してもらいます。極端君は「今日から加工肉は一切食べない」と宣言しています。彼の意見は先日、世界保健機関(WHO)が出した報告に機敏に対応したものです。WHOは国際連合の一機関です。そんな権威ある組織が、「ハムやベーコン、ソーセージなどの加工肉は、人に対して発がん性がある」と正式に認定したのです。たとえば、毎日50グラムの加工肉、つまりホットドッグ1本、ベーコンスライス2枚を食べると大腸がんのリスクが18%上昇するというのです。
22人の専門家が800件近い研究結果を分析し、そして「The LANCET Oncology」という一流英文誌に発表されたものです。権威ある機関が、権威ある雑誌に、そして統計的な明らかな有意差をもって出された結論です。テレビのバラエティ番組などで取り上げられる「○○は××に良い」といった根拠のない話とは雲泥の差があります。
極端君は、このWHOの発表を受けて、今日から加工肉は一切口にしないそうです。私はそんな選択肢もOKだと思います。バラエティ番組を見て、特別な医学的根拠や統計的有意差などまったくないのに、「○○が××にいい」と放映されると次の日にその食品が欠品するような国に私たちは住んでいるのですから。
極端君のような人はどこにでもいるので、「確かにそんな意見もある」ということで納得するとして、では一般的な人はどうすればいいのでしょうか。
まず、発がんの「%」ですが、「18%」という点が大切です。たった18%しか上昇しないのです。これが、「2〜4倍」などとなるのであれば、当然に食することはやめたほうがいいと思います。ホットドッグ1本で18%ということは、毎日ホットドッグを5本食べてやっと2倍のリスクになります。毎日ベーコンを10スライス食べて、2倍のリスクになるのです。それほど食べる日本人は一般的ではありません。
そして国立がん研究センターも、私の直感と同じ以下のコメントを先日出しました。
「日本人の平均的な摂取の範囲であれば影響はないか、あっても小さい」
●バランスよく考える
さて、極端君の意見を無視するのではありませんが、ひとつ極端君に質問があります。
「交通事故で毎年何人が亡くなっているか知っていますか?」
答えは、「最近は毎年4000人強」です。4000人も毎年亡くなっているのです。もしも年間4000人以上が亡くなっている交通事故に遭いたくなければ、外出を一切控えればよいのです。しかし、私たちはそんなリスクは承知の上で、必要だから、楽しいから、ただなんとなく、当たり前のように外出します。
バランスよく考えるとはそういうことです。極端を通すのであれば、危険を避けることを徹底するのであれば、極端君は今日から外出をやめて家に閉じこもっていたほうが、加工肉の摂取をやめるよりもはるかに効果的です。
つまり、私たちはある程度の危険は承知で生きているのです。今回の報道もWHOが世界に向けたものであって、加工肉の摂取が比較的少ない日本では、あまり心配する必要がないと思います。
(文=新見正則/医学博士、医師)
[Business Journal]
Posted by nob : 2015年11月09日 11:28
コンビニ飯でもここまでできる、、、何をどう摂る以前に、まずは悪いものを摂らないことから。。。
■最新がん予防策、「ハーバード式スープ」とは
コンビニ飯なら「条件を絞って」選んでみよう
丸田 みわ子 :シニア野菜ソムリエ
日本人の2人に1人が「がん」になると言われている現代。そしてがんの原因の35%が食事にあると言われています。その原因というのは主に、体内にある食べ物の残留物。老廃物とも言いますが、それらが酸化することで、様々な疾患を生み出してしまうのです。
そんな老廃物を掃除してくれるのが、野菜や穀物の食物繊維。これ自体はよく聞く話ですが、その摂取方法を工夫することでより抗酸化作用が高まり、生活習慣病の罹患リスクが減るということがわかってきました。
毒素から体を守る救世主、どう摂取する?
ハーバード大学では、がん研究と共に「免疫栄養学」という学問を打ち立て、日本人医師の高橋弘先生も交え野菜に含まれる「ファイトケミカル」の研究を行っています。その結果、老廃物から発生する「活性酸素」を撃退できるのはファイトケミカルだけだという結論に達したそうです。
ファイトケミカルはタンパク質や炭水化物(糖質)、脂質、ビタミン、ミネラルの五大栄養素の中には含まれず、体の筋肉や骨の生成、糖質や脂質の代謝などの働きはありません。しかし、抗酸化作用、抗がん作用、免疫力強化という3つの作用があり、体内の毒素から体を守ってくれます。
このファイトケミカル、動物性食品にはほとんど含まれないので、野菜や穀類から摂取するのが効果的。さらに病気予防や治療食として活用するには、年中手に入りやすいキャベツ、タマネギ、ニンジン、カボチャを「野菜スープ」にしていただくのがいちばんのようです。
これら4つの野菜で作る野菜スープを毎日・毎食いただくと、生活習慣病の罹患リスクが確実に減り、血圧や肝機能値の適正化、体重の減少まで望めるそうです。そのうえ、病気がちで薬を手放せない人の「減薬」にもつながるとのこと。
「スープ」という調理法を推すのには理由があります。水から加熱調理すると野菜の切断面からファイトケミカルが溶け出すので、汁まで飲むスープであればムダなく摂取することができます。そして具として野菜を食べることで、食物繊維もしっかりいただけるのです。
キャベツ、タマネギ、ニンジン、カボチャの4つが選ばれた理由は、様々な野菜の組み合わせを試した結果いちばん食味がよかったことと、年間を通して手に入りやすいこと。ただ、ほかの野菜にもファイトケミカルは入っているので、好みや補いたい栄養素に応じて、皆さんでアレンジしてみてください。
風邪予防に効果的なビタミンCは、葉もの野菜なら(多少の含有量の差こそあれ)ほぼ含まれています。キャベツやタマネギの代用としては、レタス、チンゲン菜、サツマイモ、ジャガイモなどがいいでしょう。
粘膜の健康維持、夜間の視力維持などの助けになるビタミンA(野菜ではβカロテン)は、ニンジン、カボチャに含まれます。ほかの野菜なら、トマト、パプリカ、緑黄色野菜で代用できるでしょう。
体内の脂質の酸化を防ぎ体を守るビタミンEは、ニンジン、カボチャなどに含まれています。これらの代役としては、パプリカ、赤ピーマン、ほうれん草あたりが適切です。
コンビニで探すなら、条件を絞ろう
キャベツ、タマネギ、ニンジン、カボチャが必須!と考えてしまうと、見つけるのが難しくなってしまいますので、「野菜をカットして加熱調理してあること」「ファイトケミカルとビタミンA・C・Eが溶け出ていること」の最低条件に絞って探してみましょう。
〈みわ子流、ファイトケミカルを摂れるコンビニ飯!〉
●クラムチャウダー
摂れる野菜はニンジン、タマネギ、ジャガイモ。アサリやミルクも含まれるので、一緒にタンパク質と鉄分、亜鉛も摂取でき、冷え予防にもなるでしょう。
●野菜が摂れる餃子スープ
摂れる野菜はニンジン、ほうれん草、タマネギ。餃子や卵もいただけるので、タンパク質補給はもちろん、満腹感も得られるでしょう。
●豚汁
摂れる野菜はネギ、ニンジン、サツマイモ、もやしなど。豚肉からビタミンB群が摂れるので、疲れやすい体の回復にいいでしょう。
●フォー
摂れる野菜はパクチー、ニンジン、タマネギ、もやしなど。鶏肉でタンパク質、米麺で炭水化物も摂取。一皿で五大栄養素が摂れ、栄養バランス抜群です。
●スンドゥブ
摂れる野菜はほうれん草、ニンジン、タマネギなど。卵や海老も入っていて具だくさん。生姜、ニンニク、唐辛子といった香辛料はエネルギーを燃やしてくれるので、新陳代謝もよくなるでしょう。
●カボチャスープ
摂れる野菜はカボチャ、タマネギ、パセリ。カボチャは加熱すると炭水化物化するので満腹感も得られ、体が温まるでしょう。
「ハーバード式野菜スープ」は確かに健康的ですが、が毎日続くと飽きてしまいそうですよね。そんなときにこそ、機能成分はそのままに外出先でも理想に近いスープをいただけるよう、上のメニューを参考にしてみてください。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2015年11月03日 18:17
すべては偏った結果論、、、結局は患者本人の決断こそが唯一無二の正しい選択。。。
■川島なお美さん 手術遅かったとの指摘は間違いと近藤誠医師
「もっと早く手術していれば…」の指摘は正しいのか
9月24日、川島なお美さんが胆管がんで54歳にして亡くなった。川島さんが胆管がんと診断されたのは昨年8月のことだが、その翌月に近藤誠医師のセカンドオピニオン外来を訪れていたことがわかった。
近藤誠医師といえば、手術も抗がん剤も患者にとって有害だとする「がん放置療法」で知られる。他臓器に転移しないがんを「がんもどき」と名づけ、治療せずに放っておいた方が長生きできるというのだ。
そんな近藤医師から川島さんはどんなセカンドオピニオンを受けたのだろうか。取材にあたり、近藤医師は患者のプライバシーに関わること、亡くなった人に対する守秘義務は生じないことを説明した上で、「話しておかなくてはならないことがある」と取材に応じてくれた。
「テレビの報道を見ていると、もっと早く手術していればとか、抗がん剤治療を受けていれば助かったのに、という趣旨のコメントが目立ちます。これでは視聴者が誤った認識に誘導されてしまうと危惧を抱いています。川島さんのケースから明らかなことは、手術が遅かったことではなく、手術をしても救えなかったという事実です。なぜそこを誰も突っ込まないのでしょうか」
川島さんは一昨年の8月半ばに人間ドックのPET-CTで胆管がんを発見された。近藤医師のセカンドオピニオン外来にはCT画像などの検査データを持参していた。近藤医師のセカンドオピニオンはいかなるものだったのか。
「その時点で症状は出ていなかったのですが、確かにがんだとわかりました。胆管がんは肝臓、膵臓などと並んで予後の悪いがんのひとつです。症状がなくても、いずれ転移が出てくる可能性が高い。
考えられる治療法は4つ。1、手術。2、ラジオ波焼灼術。3、放射線治療。4、様子を見る、です。川島さんはミュージカルの舞台を優先したいこと、そのためには今手術は受けられないこと、抗がん剤治療は体を傷めるので受けたくないことなど、はっきりした意志をお持ちでした。
ぼくは『ラジオ波なら手術をしないで済むし、1ショットで100%焼ける。体への負担も小さい。そのあと様子を見たらどうですか?』と提案しました。『手術しても十中八九、転移しますよ』ともお伝えしました。むしろ手術することで転移を早めてしまう可能性もあるからです」
セカンドオピニオンを受けて約4か月後の今年1月、川島さんは手術を受けた。しかし半年後の7月に再発。抗がん剤治療を拒否し、舞台に立ち続けた。そして9月、激やせした姿で記者会見を行った。川島さんの再発がどのようなものだったのか、施術した病院や医師からの発表はないが、近藤医師は再発の理由をこう分析する。
「手術後わずか半年で再発したのは、やはり手術が原因だったのではないでしょうか。手術することでがん細胞が暴れ出し、再発が早まることはよくあります。また、転移先のがんの増殖を抑える物質が初発巣(初めにがんができた部位)から出ている可能性についても近年わかってきました。テレビに出てくる医者には、川島さんはもっと早く手術するべきだったと言う人がいますが、もっと早く手術していたら、もっと早く再発し、死期を早めていた可能性もあります」
もう1点、他の医師たちから疑問の声が上がった川島さんの“抗がん剤拒否”については、「賢明な選択だった」と近藤医師は言う。
「医者からはかなり強く勧められたようですね。でも、もし手術後におきまりの抗がん剤治療を受けていたら、あのように舞台に立ち続けることはできなかった。抗がん剤を受けなかったからこそ、彼女は死の1週間前まで舞台に立ち、毅然とした態度で記者会見を行うことができたのです。実にあっぱれな生き方だったと思います」
最後に、川島さんも毎年受けていたという有名ブランド病院の人間ドックについて。「これだけは言っておきたい」と、近藤医師は警告する。
「高級な人間ドックに行くと、最先端の検査機器がたくさんありますから、胆管がんのような見つけにくいがんも発見されます。川島さんの胆管がんも、ご本人がおっしゃっていたように早期発見でした。それでも治らないのですから、早期発見しても意味がない。早期発見するほど手術も早まるから、人間ドックでがんを見つけられると早死にすることもあるわけです。川島さんのケースも残念ながら、人間ドックの被害者と言えるかもしれません」
◆近藤誠(こんどう・まこと):1948年生まれ。慶應義塾大学医学部放射線科講師を2014年3月に定年退職。「乳房温存療法」のパイオニアとして知られ、安易な手術、抗がん剤治療を批判。現在「近藤誠がん研究所・セカンドオピニオン外来」を運営。著書に『がんより怖いがん治療』、近著に倉田真由美氏との共著『先生、医者代減らすと寿命が延びるって本当ですか?』など。
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2015年11月03日 18:04
健康はあらゆる創造の源。。。
■健康的なライフスタイルを送ることが仕事にも良い影響を与える理由
Dumb Little Man:どんな仕事でも、体だけでなく精神的にも感情的にも健康であることが求められます。しかし残念ながら、健全なライフスタイルを送っている人ばかりではないでしょう。また、私たちは仕事以外のほかの義務や責任も果たしていく必要があるので、それらがストレスにもなってしまいます。しかも、私たちはそのような状況のせいで、健全なライフスタイルを持つことの重要性を認識できないのです。
このような状況は、大きな影響をキャリアに及ぼします。ですから、健全でポジティブなライフスタイルを送ることは、確実にキャリアに良い影響を与えるのです。
体力がつき、仕事の生産性・効率が上がる
取り組んでいる作業を、これ以上続ける体力が足りないと感じたことがありますか? 認めるかどうかは別として、体力の有無は仕事のパフォーマンスに影響しています。運動を定期的にしない人は、1日がんばり通す体力が足りないので、たびたび停滞感を感じることになるでしょう。私たちは、体を鍛えないと疲れやすくなるのです。
仕事の生産性と効率を高めたいなら、健康に気を遣いましょう。まずは、興味が持てるエクササイズなどで、運動する時間を定期的に取りましょう。しっかりと運動していると、1日中がんばれる体力がついてきます。健康的な体で体力が満ちあふれていると、倦怠感を感じないので仕事に身が入ります。
病気になるリスクを減らす
デスクワークばかりの生活だったり、不健康な食事を好む人は、病気になるリスクが高くなります。仕事で多忙なときは、健康な状態である必要があります。いつも具合が悪かったり、何らかの病気を抱えたりすると、どうなるでしょうか? 医者に診察してもらうにも、会社を休まなければなりません。また、もっと最悪なケースは、キャリアを諦めなければならないかもしれません。そのようなことは、絶対に起こって欲しくないはずです。健康的なライフスタイルを送ることで、健康を害するリスクを回避したり、軽減することができます。
ストレスに簡単には負けないくらいポジティブになれる
どんな仕事でも、たまに燃え尽き感とストレスを感じるときがあります。これはどんな職場にもあることです。ストレスは誰も避けることができないものですが、軽減する方法はたくさんあります。健康的なライフスタイルの人は、そうでない人に比べてストレスの感じ方が弱いことを示す研究がたくさんあります。エクササイズをしたり体を使う活動をしているとき、体は幸せホルモンと呼ばれる「エンドルフィン」を分泌します。このことは、エクササイズを定期的にする人が、ストレスに強い理由を示しています。
ストレス耐性が強いと、どんな作業においても、エネルギーを集中して使うことができます。私たちはストレスを感じると、気分屋になりがちで集中力に欠けることさえあります。ですから、仮に、私たちがストレスを低くする効果的な方法を知っていると、重要なことに集中するのがずっと楽になります。
物の見方が良い方向に変わる
健全な精神は健全な肉体に宿ります。ポジティブな生活を送っていると、自己満足が高くなり、自信がわいてきます。このような一連の流れで、人生における物の見方もさらにポジティブになります。また、仕事だけでなくプライベートなことでも、頓挫してしまいそうなとき、ポジティブな物の見方ができると随分と役に立ちます。
目標を達成したり、挑戦したりしたいと思うどんなことでも、ポジティブになることで成功するのが楽になります。自信があって物事のポジティブな面を見ると、はるかにはっきりした意見が持てるようになります。仕事の効率と生産性が高まるのです。
健康的なライフスタイルを持つ秘訣
健康は、さまざまな実践と良い習慣の組み合わせによってもたらされます。健康になるためにはまずは、エクササイズをする時間を取ることをオススメします。興味のあるスポーツだろうと定期的なワークアウトだろうと、いつもエクササイズをする時間をとりましょう。
そして、定期的なエクササイズに加え、摂取する食べ物にも気を付けなければなりません。食事は良かれ悪かれ健康に影響を与えます。ぜひ、油っぽい食べ物や加工食品を食べるのは避けましょう。その代わりに、心身の健康に良いビタミン、ミネラル、そのほかの栄養素が含まれている食品を食べてください。
健康であることは、いろいろな形でキャリアに確実なメリットをもたらします。仕事がはかどるだけでなく、プライベートにまでポジティブな影響を与えてくれます。
How a Healthy Lifestyle Affects Your Career|dumblittleman.com
Kiara Halligan(訳:春野ユリ)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2015年10月28日 12:04
つい洗ってしまいがちですが(オリーブオイル石鹸もしくはハーブパウダーにて)、なるべく実践しています。。。
■シャンプーを使わないことで髪質改善!?海外セレブ発の「ノー・プー」は試す価値あり!?
「余計な刺激物を取り除くことでキレイを手に入れる。」
あの佐伯チズさんも提唱した肌断食は、スキンケアをやめることで肌を休め、美肌を目指すという、それまでの常識を覆すものでした。
この全く新しい考え方、実は肌ケアだけではなくヘアケアにまで広がっているのをご存知ですか。
ノーシャンプーの略でノー・プー。シャンプーを使わずにお湯だけでシャンプー(湯シャン)するというノー・プーは、果たして本当に髪に良いのでしょうか。
ノー・プーについてよく知らないのがみんなの本音!?
そもそも、ノー・プーを取り入れたいと思っている人はどの程度いるのでしょうか。世の女性たちの本音とは・・・?
肌断食ならぬ髪断食「ノー・プー」やってみたいと思いますか?
Yes:44人
No:56人
Noが半数以上と、取り入れたくないという人が圧倒的という結果に。
“よく分からないので、やりたいと思いません。良いものならやりたいと思います。”(30代女性・パート)
“どんな内容か良く分からないので、あえてやってみたいとは思いません。”(30代女性・会社員)
取り入れたくない方の意見を見てみると、「あら?実はよく知らないだけ?」というコメントが。
「シャンプーをしない」とだけ聞けば良い印象はなかなか持てないですよね。それでは、ノー・プーがなぜ髪に良いのかについて紹介します。
コツもテクニックも必要なし!ノー・プーについて知ろう!
●ノー・プーのやり方・流れ
1.髪をブラッシング
2.先髪前に軽く頭皮マッサージ
3.ぬるま湯で丁寧に洗髪(もちろんシャンプーやトリートメントは使いません)
4.念入りにタオルドライ
5.ドライヤーで乾かす
やり方はとても簡単で、通常の洗髪の流れでシャンプーを使わないだけ。
実は普段の洗髪でも、シャンプーを付ける前にお湯で丁寧に髪を洗えば、7〜8割の汚れが落ちると言われています。
普段「髪のために」と思って使っているシャンプーですが、硫酸塩や鉱物油、アルコールなどを含むものが多く、これらが髪を乾燥させる原因となっているんだそう。
また、シリコン入りのシャンプーは髪をコーティングすることで、水分が髪に吸収されるのを妨げてしまうため、髪が乾燥してしまうと言われています。
美髪のために使っているシャンプーにはマイナスな面も多く存在しているんですね。
それなら、マイナス面を取り除くノー・プーは髪に良い気がします。
早速今日からノー・プーを始めよう…?ちょっと待った!向き不向きがあるんです!
“1年ほど前からあまりにも髪がパサつくので、シャンプーを2日に1回にしていますが、以前より明らかにパサつきが改善されました。”(40代女性・専業主婦)
“1日もしくは2日おきに、シャンプーせずに湯シャンのみにしています。ベタつきや臭いが気になりましたが、家族や友人からは反応はありません。以前よりも頭皮の痒みや毛髪のきしみが解消されました。美容院でも髪をほめられます。”(50代女性・専業主婦)
既に湯シャンの効果を感じている方も!
コメントから分かるように、髪のパサつきやきしみが気になる方には効果があるようですね。
そうなんです!ノー・プーに適しているのは頭皮や髪が乾燥している人!
乾燥に悩んでいる人は、シャンプーなどに含まれる成分によって、余計に乾燥を引き起こしている可能性が高いので、使わないことによって改善する効果が期待できます。
反対に油脂性の人は、湯シャンだけでは十分に油脂を取りきれない可能性が高いので、ノー・プーをすることでトラブルを引き起こす可能性があります。
準備物不要で手軽なノー・プー!とにかく一度やってみては?
これまでの海外セレブ発のブームといえば、ジュースクレンズやココナッツオイル、スムージーなど、お金が掛かるものや準備が面倒なものばかり。
「セレブだからできるのであって、庶民の私には結局向かない。」
そんな風にあきらめてきませんでしたか?
ノー・プーは今使っている余計なケアをやめるだけ。あなたの日常にとっても取り入れやすい庶民派ブームなんです。
夏には「湯シャンだけでは臭うのでは?」「汗をちゃんと取りきれるのか」なんて心配もあったでしょうが、これからの涼しい気候なら試しやすいのでは?
本当に効果があるのか、あなた自身の髪で確かめてみてくださいね。
文/暮らしニスタ編集部 日高
[暮らしニスタ]
Posted by nob : 2015年10月28日 09:58
言わずもがな。。。Vol.2/加工肉食品業界のダメージは大きい。。。
■ハムなどの発がん性指摘 「適切ではない」
WHO=世界保健機関の専門機関が肉の加工食品などに発がん性があると指摘したことについて、国の食品安全委員会は、「この結果だけでリスクが高いと捉えるのは適切ではない」とする見解を発表しました。
WHOの専門機関、「国際がん研究機関」は26日、食肉とがんに関する調査結果を発表し、ハムやソーセージなどの肉の加工食品について、「発がん性がある」としたほか、牛や豚などの哺乳類の肉についても「おそらく発がん性がある」などと指摘しました。
これを受けて国の食品安全委員会は27日、インターネットのフェイスブック上で見解を発表しました。
それによりますと、調査の詳細な結果が公表されていないため、引き続き検討が必要としたうえで、今回の発表は主に、肉の加工品などに含まれる物質に発がん性があるかどうかを解析したもので、発がん性の強さや、日常生活で肉を食べるだけでもリスクがあるかどうかなどについてはあまり考慮されていないと指摘しました。
そして、この結果から「食肉や加工肉はリスクが高いと捉えることは適切ではない」として、食品としてのリスクについて専門の機関で食べる量などのデータに基づいて、改めて評価する必要があるとしました。
食品安全委員会では、健康な食生活のためには「多くの種類の食品をバランスよく食べることが大切です」と呼びかけています。
[NHK NEWSWEB]
Posted by nob : 2015年10月28日 09:41
言わずもがな。。。
■加工肉摂取に「がんリスク」=毎日50グラムで18%増―WHO
【ベルリン時事】世界保健機関(WHO)の専門組織である国際がん研究機関(本部フランス・リヨン)は26日、ハムやソーセージなどの加工肉を食べると、がん発症リスクが高まるという「十分な証拠」があると発表した。
加工肉を毎日50グラム食べた場合、直腸や結腸のがんになる可能性が18%増すという。個人にとってのリスクは「小さい」ものの、摂取量が増えれば高まると指摘した。また、牛や豚など赤身の肉にもがんを誘発する恐れがあると言及した。
国際がん研究機関は、赤身の肉は栄養価が高いとした上で、リスクとのバランスを踏まえながら当局が「食事に関する最良の勧告を行う」必要性を訴えた。同機関は800以上の研究結果を分析し、見解をまとめた。
[時事通信]
Posted by nob : 2015年10月27日 17:23
体感的にはごく自然に納得できます。。。Vol.2
■がん糖尿病急増の「本当の原因」とは?水をこまめに飲んで血液サラサラのウソ?
日本人の死因の2位(心筋梗塞)と4位(脳梗塞)が「血栓症」なので、血液をサラサラにするために「水分をこまめに補給するべし」「1日2リットル以上飲むべし」などという指導がなされている。20年くらい前からこうした「水を飲め」という指導がなされているが、この間、心筋梗塞、脳梗塞による患者数と死者数は増加し続けている。
筆者が少年時代、サッカーや草野球をする時、炎天下にもかからず練習途中で水を飲むと、監督から「力が出なくなるので水は飲むな」と一喝されたものだ。筆者はサウナが大好きで週2〜3回は東京・両国や錦糸町のサウナ風呂に行くが、みんな滝のような汗をかいているが脳梗塞や心筋梗塞で倒れる人など見たことはない。
血栓症は、血液中のコレステロール、中性脂肪、赤血球、フィブリン(タンパク質)を血小板(血球の一種)が硬めることによってつくられる。よって、水分をたくさん摂って血液中の水分を多くして血液をサラサラにするというのが、「西洋医学」の論理のようだ。
たくさん水分を摂ると、胃腸から血液に吸収され、一時的に血液中の水分は多くなる。しかし、体には「恒常性」があり、1日中、1年中血液中の水分量は一定に保たれている。よって、血液中の水分が多くなると、水分はすぐ腎臓から膀胱を経由して尿として排泄される。
その時、血液の病因物質のコレステロール、中性脂肪、赤血球、フィブリン等々は、尿と一緒に排泄されるわけではない。コレステロール尿、中性脂肪尿などというのは聞いたことがないし、赤血球やフィブリンが尿として出ていくと、「血尿」「タンパク尿」ということになり、それは「病気」ということになる。
つまり、水分をいくら多く摂っても血液はサラサラにならないし、血栓症は防げないわけだ。冒頭でも述べたように、「水分を多く摂れ」との指導が始まってから約20年間、脳梗塞や心筋梗塞をはじめとする血栓症は、むしろ増え続けている。
●体温と病気の関係
では、血栓症の原因は何か?
もちろん1960年以降、日本人の食生活が西洋化し、肉、卵、牛乳、バター、マヨネーズに代表される高脂肪食物の摂取が急増し、高脂(高コレステロール、高中性脂肪)血症の人が増えたことが大きな要因だ。ラードやバターも加熱すると液状になる。逆に水を冷やすと氷になる。食物を冷蔵庫に入れると硬くなる。つまり、一応36.5℃前後が平均体温とされている人体の中で、「血液が固まる」ということは、「体の温度」が大いに影響している、ということになる。
日本人の脇の下の平均体温は、約50年前は36.9℃プラスマイナス0.34℃とされていた。しかし、今では35.8℃前後と、約1℃低下している。この「低体温」こそが血栓症の大きな要因といってよい。
よって、血栓症が1年のうち、寒い時期である12月、1月、2月に最も多く発症しやすいことは、これにより首肯である。しかし、7月、8月の暑い時期にも多発する。その理由について西洋医学は、「夏は暑いから、発汗が多くなり、血液中の水分が少なくなるため」と説明している。
しかし、クーラーがなかった40年前までの日本では、夏は一日中大量の汗をかいたものだが、脳梗塞や心筋梗塞はほとんど存在しなかった。
7月、8月に血栓症が増加するのは、「冷房による体の冷やしすぎ」といってよいだろう。
いずれにしても、日本人の体温がこの50年で約1℃低下したことが、代謝を低下させ、免疫力を落とし、高脂血症、高血糖(糖尿病)、ガン、うつ、アレルギー等々、ありとあらゆる病気の要因になっている。
最後に整理すると、日本人の低体温化の要因としては以下の点が挙げられる。
(1)交通の発達、家電製品の普及による肉体労働、ウォーキングの不足
体温の40%は筋肉で生産されるので。
(2)塩分の制限のしすぎ
東北地方の人々は寒いがゆえに体を温める塩分を多量に摂っていた。
(3)水分の摂りすぎ
雨に濡れると体が冷えるように、水分の摂りすぎは体を冷やす。
(4)体を冷やすの食物の摂りすぎ
外観が青白緑の食物は体を冷やし、赤黒橙の食物は体を温める。
(文=石原結實/イシハラクリニック院長、医学博士)
Posted by nob : 2015年10月20日 13:31
逝き方は生き方の完結、、、自らがどう思うかだけでなく、〈看取る〉周りにどう思われる生き方をしてきたのかが問われる。。。
■在宅死、病院死。幸せな「最期」を迎えるにはどちらがいい?
~究極の難問。答えを出した人たちに聞いた
新藤兼人監督の場合
どんな家族も、大切な人を見送る時には、悩み苦しむ。一秒でも長く生きてもらいたいが、治療で苦しむ姿を見るのも辛い。簡単には答えは出ない問題。だからこそ、家族を見送った人たちの言葉から、改めて、家族の、そしてあなたの幸せな結末を考えてみて欲しい。
「亡くなる直前まで仕事を続け、自宅で孫娘に見守られながら、スーッと息を引き取った。息子である私も憧れるくらい、パーフェクトな最期だったと思います」
日本を代表する映画監督・新藤兼人氏の次男で、近代映画協会社長の新藤次郎氏はこう語る。
新藤監督は、'12年5月29日、先立った妻で女優の乙羽信子さんと共に暮らした都内のマンションで、静かに亡くなった。
そのひと月前の4月22日には、柄本明や大竹しのぶといった縁の深かった俳優や映画関係者を集めた、100歳の誕生パーティを行ったばかりだった。次郎氏が続ける。
「父は94歳のとき、映画の撮影の準備中に肺炎を起こして入院したんです。そこで検査してみると、血糖値の異常や胆石が見つかりました。
入院前から、独り暮らしの父のマンションにはお手伝いさんが通い、食事の準備をしていました。退院後には要介護3と認定され、糖尿病のためのインスリン注射が必要だったり面倒も増えるので、私の住む家で一緒に暮らそうと持ちかけました」
しかし、「息子の世話にはならない」と監督は断った。そこで、次郎さんの娘で同じく映画監督の風さんが、監督のマンションで付き添うようになった。
「父は孫娘とは気が合い、風は下の世話からいろいろ面倒を見てくれました。車椅子生活を余儀なくされながらも、98歳で『一枚のハガキ』をクランクイン。その現場にも娘がつきっきりでした。
ただ、すべてを娘がやっていては根を詰めてしまうので、食事はヘルパーさん4人でシフトを組み、面倒をみてもらいました。
父には老人ホームなどの施設の資料を見せたこともありますが、見ず知らずの人と一緒に生活できる性格ではなかった。正直言えば、施設に入るよりカネはかかったと思います」(次郎氏)
次第にベッドに横たわる時間は長くなったが、映画の構想のため常に頭を働かせていたという。
「食は細っていきましたが、最期まで自分で食べていました。死の前日の晩も、映画を撮影する夢を見ていたようで、『ここは英語と日本語で2回撮るよ』と寝言で言っていたそうです。
最期は定期的に診てくれていた訪問医が看取り、老衰と死亡診断書も書いてくれました」
次郎氏は、そう穏やかに語った。「父の最期に憂いがないのは、しっかり送ってあげられたという思いがあるからです」
約束は守りたい、でも…
ただし、すべての人が、新藤監督やその家族のように、納得できる看取りや、最期を迎えられるわけではない。看取る側、看取られる側が共に在宅死を望みながら、叶わなかったケースもある。千葉県在住の主婦・杉森栄子さん(66歳・仮名)が言う。
「独り暮らしをしていた母は、83歳で大腸がんを患って手術しました。お医者様からは、余命は半年と言われました。最期は住み慣れた我が家で死にたい。ことあるごとに母は私にそう言っていたので、在宅で介護を続けることにしたんです」
杉森さんの母親は、ヘルパーや訪問診療、訪問看護を利用しながら、半年どころか3年間を我が家で過ごすことができた。
「でも、母が少し風邪をこじらせて入院したところ、心身ともに一気に弱ってしまったようで、病院で『家に帰る自信がない』と言い出したんです。
大丈夫よ、家でみんなで交替で看るから、と何度も説得しました。でも、母はうんとは言わず……。
いま考えると、やっぱり私たち家族に遠慮していたんだと思います。結局その後すぐ、病室のベッドの上で眠るように亡くなりました」
それは、本当に母にとって幸せな最期だったのか。亡くなって4年が経ついまでも、杉森さんの頭からは苦悩が離れない。
「もしあの時、無理にでも連れ戻していたら、本人の『最期は家で』という願いを叶えてあげられたのではないか。そうふと考えてしまうんです。ずっと相談に乗っていただいた訪問看護の方は、『あなたは間違ってなかった』と言ってくれました。でも、どこかで違った道があったんじゃないかって」
都内の家電メーカーで部長まで勤め上げた北川豊さん(67歳・仮名)は、90歳で他界した母親の「死に方」について、逡巡を重ねた。
「元気なうちから母とは何度も話し合い、『延命治療はいらない。病院には入らない』と決めていました。母は80代の後半に入ってから認知症が悪化し、私とヘルパーさんとの区別もつかなくなり、ほとんど寝たきりになってしまいました」
動きまわったり、暴れたりしない分、介護はしやすくなった。北川さんはそうプラスに考えるようにもなった。覚悟はできているつもりだった。
「そんな中、娘が妊娠したんです。私にとっては初孫、母にとっては初めてのひ孫です。どうしてもひと目、顔を見せてあげたい、なんとか持ってくれと願っていましたが、母の調子は目に見えて悪くなっていった。
出産予定日まであと3ヵ月という時、母は誤嚥性肺炎を起こした。事前の約束など忘れて、病院に駆け込みました」(北川さん)
容態を持ち直した北川さんの母親は、経口で食事はできるものの、摂取できる量が明らかに減った。点滴や、胃瘻(腹部に管を通して直接栄養を送る)に頼れば、活力を取り戻せるかもしれない。このまま入院させれば、初ひ孫の顔も見せてやれる—そう北川さんは考えた。
「でも、前々からのかかりつけ医に『本当にそれでいいの?』と言われたんです。胃瘻をすれば、味わう力が落ちて、考える力もなくなる。点滴をして、元通りに食事ができるようになる人もいるけれど、心臓に負担がかかって寿命を縮めるケースもある、と」
結局、散々悩んだのち、北川さんはいちばん最初の約束どおり、母親を入院させず、自宅で自然に任せることを選んだ。
「母はひ孫が2歳になるまで、生きてくれました。結果としてですが、老衰で死んでいく母を傍らで看取ることもでき、納得しています」(北川さん)
もちろん、入院・治療を選択して命を長らえ、救われる家族もいる。長尾クリニック院長の長尾和宏氏がこう言う。
「私自身は高齢者や老衰では『在宅での自然な最期』がお勧めです。しかし胃瘻については否定しません。胃瘻のおかげで最悪期を乗り越えられた方もいるし、人それぞれの綺麗事ではすまない状況、考え方があるので、ご家族とはしっかりと話し合うことが大切。
ただ、胃瘻のメリット・デメリットを説明しても『私は手を汚したくありません。先生が決めて下さい』という家族も多い。最愛の家族の人生に責任を持とうとしない家族には、正面から向き合って欲しいと願います」
在宅死か病院死か—。どちらが正解ということはないが、医療法人社団悠翔会理事長の佐々木淳氏によれば、在宅で看取ったことを後悔する人が少ないのは事実だという。
「看取ったご家族のお宅にお焼香に伺ったり、四十九日を過ぎてから挨拶に伺うと、『大変だったけれど、家で看取ってよかった』という方がほとんどです。当社団が行ったアンケートでも、96%の人が、『家で看取るという選択をして良かった』と答えています」
「在宅」にこだわりすぎない
「最期は家で」と家族で話し合っていても、現実の介護という問題にぶち当たったとき、老人ホームなどの施設を頼らざるを得ないことも多い。特別養護老人ホーム・芦花ホーム常勤医の石飛幸三氏は言う。
「私たちのようなホームに入居する人の多くは、家族での在宅介護が難しくなって飛び込んでくる人たちです。
いまは核家族化が進んでいるので、家族での介護も夫婦の老老介護や、親子でも一対一の関係が多い。すると、精神的にもどんどん疲弊していく。家族だからこそ長年積もり積もった感情がある。そこから、DV紛いのことが起きているのが実態です。そんな経験を経てホームに入居された人やその家族は、それはホッとした表情をされます」
施設の役割をそう強調しながら、「ただし」と石飛氏が続ける。
「在宅死を望むのは自然な感情です。このホームの方も、入居後しばらくは夕方になると『お家に帰りたい』と口々に言い出す。私は『夕方症候群』と呼んでいます」
老人ホームでは本格的な医療行為はできない。
「入居者の方には、病院に移らず、『自宅は無理でも、ホームで自然な最期を』と望まれる人は多い。
しかし、ホーム入居を決断したご家族ではなく、離れて暮らしていた親族が、『なぜ病院に入れないんだ!』と無理に連れだしてしまうケースもあります。そうしてチューブだらけになった親の姿を見て、心を痛める人も多いんです」(石飛氏)
どんな家族も、大切な人を見送る時には、悩み苦しむ。家族としては、「本人の希望」はもちろん叶えたい。一秒でも長く生きてもらいたいが、治療で苦しむ姿を見るのも辛い。そして、そんな考えすべてが、親への思いではなく、自己満足なのかもしれない……。
簡単には答えは出ない問題。だからこそ、家族を見送った人たちの言葉から、改めて、家族の、そしてあなたの幸せな結末を考えてみて欲しい。
[現代ビジネス]
Posted by nob : 2015年10月20日 13:20
体感的にはごく自然に納得できます。。。
■「早起き」すると寿命が縮む!オックスフォード大学の研究で判明
~心筋梗塞、脳卒中、糖尿病のリスクが倍増賢者の知恵
早起きは健康である—誰もが信じきっていた通説を覆す研究発表が全世界で話題だ。そこに示されていたのは早起きによって起こる病気の数々。一流学者が本誌に語った、驚くべき「睡眠の新常識」。
体にも心にも悪い
「『早起き』が健康に良いものだと思っているのならば、それは大きな間違いです。朝6時に起きて、日課のジョギングを1時間ほどこなしてから、余裕をもって会社に向かい、9時から仕事に取りかかる。誰もが理想的だと考えるそんな生活が、重大な病気を引き起こし、命取りになることもあるのです」
朝早く起きることは、人体にとって「拷問」に等しい—そんな衝撃的な研究結果を発表したのは、英オックスフォード大学の睡眠・概日リズム神経科学研究所の名誉研究員、ポール・ケリー博士である。
同博士が、イギリスで行われた科学イベントで発表したレポートが英ガーディアン紙などで報じられ、いま世界中で話題となっている。
この記事の注目すべき点は、一般的な会社員にとっては当たり前のものとして受け入れられている「9時5時」という就業時間が、実は人間の体内時計と全くかみ合っていないということだ。
さらにそれが原因となって、さまざまな病気を引き起こす恐れがあるほどに、精神にも肉体にも悪影響を与えるという。
ケリー博士は言う。
「世界中のあらゆる人たちの睡眠パターンを分析して、年齢層ごとの推奨すべき起床時間と起床後の活動開始時間をはじき出すことに成功しました。それによれば、個人差はあるものの、起床時間は青年期(15~30歳)であれば朝9時、壮年期・中年期(31~64歳)なら8時、高年期(65歳以上)だと7時となっている。
また起床後の活動開始時間は青年期11時、壮年期・中年期10時、高年期は9時が最適だと分かっています。この数値を見れば明らかなように、すべての年齢層の人に言えることは、6時よりも前に起床することは人間として本来あってはならないということです」
人間、年を重ねていくほど眠れなくなって、朝が早くなりがちだが、こうした習慣が身体に重大な影響を及ぼすというのである。
これまでの研究から、早起きすることで起こりうる病気の数々についてケリー博士はこう続ける。
「わたしのいるオックスフォード大学だけでなく、米国のハーバード大学やネバダ大学などの研究機関で、早起きが病気のリスクを高めることに関する実証研究がすすめられています。
現時点でもすでにメタボリック・シンドロームや糖尿病、高血圧、より重篤な病気であれば、心筋梗塞や脳卒中、心不全などの循環器疾患やHPA(視床下部-脳下垂体-副腎皮質)機能不全によるうつ病などが判明しています」
集中力も落ちる
早起きのせいで、病気にかかりやすくなる—なぜこんなことがわたしたちの身体で起こりうるのだろうか。ケリー博士によれば、その原因は「人間の体内時計の『ズレ』」にあるという。
体内時計とは、「概日リズム」とも呼ばれる、生物に生まれながらにして備わった生命活動のサイクルである。これがあるおかげで、人はもちろん、あらゆる生物は意識しなくても活動状態と休息状態を一定のリズムで繰り返すことができる。
ケリー博士はこの体内時計の周期と人間の実生活における行動周期とにズレが生じることが、人の身体に悪影響を及ぼすものだと考えている。そして早起きこそが、このズレを生むのだという。
「体内時計は身体のあらゆる部位に存在します。例えば脳の視交叉上核という場所に体内時計が備わっていますが、早起きすることによってこれがズレてしまうと、著しく脳の機能が低下します。すると集中力や記憶力、コミュニケーション能力などが著しく減退してしまうのです」
ハーバード大学医学部において、朝から夕方までの勤務シフトで働く医者と、昼から夜までの勤務シフトで働く医者の仕事ぶりを比較する実験をケリー博士らが行った。すると、前者の医者は後者に比べて集中力の欠如が見られ、医療ミスが36%も増加したという。
博士らの研究の正しさは、ビジネスエリートたちも証明している。
世界最大のIT企業、グーグルはとりわけ社員の能力と睡眠の関係性を重要視している企業の一つだ。フレックスタイムを導入しているグーグルは、社員が自由に出社時間と退社時間を決められるようにしている。
そのため、午前中のオフィスは人もまばらで、昼過ぎになってようやく社員たちが姿を見せ始めるという。
「脳に加えて、心臓や肺などのあらゆる臓器にも体内時計は備わっています。ただでさえ早起きをすることによってこれらの体内時計にズレが生じる上に、そのズレは年齢を重ねるごとに自然と大きくなります。
そうなると、必要以上に臓器を酷使してしまうことになり、病気を誘発するリスクがさらに高まるのです」(ケリー博士)
実際に65歳以上の高齢者で平常時の起床時間と病気の発生リスクの関係を調査したケリー博士の研究結果がある。
博士が先に述べた高齢者の理想的な起床時間である7時以降にいつも起きている人と比べて、それよりも早い6時以前に起きている人は、心筋梗塞や脳卒中などの循環器疾患の発症リスクが最大で約4割、糖尿病やうつ病といったその他の病気に関しても2~3割高くなり、またその多くが重篤化しやすいという驚きの結果が出た。
早起きが習慣化してしまったばかりに、脳や心臓に負担をかけ、その寿命を縮めてしまうのだ。
高齢者は「遅寝遅起き」を
今回のケリー博士の研究発表と同じく、日本の睡眠医療の専門家である遠藤拓郎・スリープクリニック調布院長も、早起きが病気を引き起こす恐れがあると指摘する。
「人間のパフォーマンスというのは体温に依存します。体温が低い時は身体中の機能が著しく低下します。人間の一日のなかでの最低体温というのは、個人差もありますが朝の4時から6時。一方で最高体温となるのが夕方4時から6時。したがって、ケリー博士の言う通り、朝早くから活動をするのは年齢に関係なく危険なのです」
とはいえ年齢を重ねれば、自分の意思とは関係なく、つい朝早くに目が覚めてしまうものだ。遠藤氏は続ける。
「高齢の方が朝早く起きてしまいやすくなるのは、メラトニンという眠気を誘発するホルモンが加齢によって減少してしまうからです。また体力の低下が、そのまま寝る力も奪ってしまっています。
むしろ高齢の方は早寝早起きよりも『遅寝遅起き』のほうがずっと健康にいいんですよ」
遠藤氏によれば、早起きすることなく深い眠りを実現する一番の方法は、昼間から夜にかけて、時間を忘れるくらい趣味に没頭することだそうだ。
ウトウトしながらテレビを眺めているのは最悪で、例えばプラモデル作りなどの集中力を要する趣味に時間をかけると、朝まで深く長く眠ることができるという。
ケリー博士は特に日本社会に対して危機感を抱いている。
「統計的にも、日本人は世界中で突出して睡眠時間が短い。加えて早く起きる人の割合も多い。しかも学校や政府、企業がそれを主導しているように思えます。『早起きは三文の徳』ということわざが日本にはあるようですが、とくに高齢の方には、それは科学的に間違いだということを十分理解してもらいたいです」
健康に長生きするため早寝早起きを心がけよう—その思い込みが、実は、あなたの命を脅かしている。
[現代ビジネス]
Posted by nob : 2015年10月19日 00:36
がん難民68万人!?(驚)、、、他者への依存が迷いの元、すべては不完全ながらも有効な選択肢、他の何ものでもない自分自身の決断こそがいつも正しい。。。
■なぜ「がん難民」は生まれる? 医師が指摘する2つの理由
がんの治療法が確立したとされる日本でも、よりよい治療を求め、医療界をさまよう「がん難民」が生まれている。それはなぜなのか。がん研有明病院放射線治療科副医長の加藤大基医師、さぬき診療所院長の讃岐邦太郎医師、日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授の勝俣範之医師、さらにがん体験者の大久保淳一さんが集まり、意見を交わした。
──「治療方針に悩んだり、よりよい治療をしてくれる医師や病院を探し求めたりして、途方に暮れながらさまよう」。民間シンクタンク「日本医療政策機構」の調査(2006年)によれば、そうした「がん難民」は推計約68万人いるといいます。科学的根拠に基づいた標準治療が確立している日本で、「途方に暮れる」がん難民が生まれるのはなぜでしょう。
加藤:がんを発症するのは人生の一大事です。ですから、ベストの方向を見つけ出す
というのは当然、必要な過程だと思います。ただ問題は、そこから先。途方に暮れる患者さんが出るのは、端的に言うと、医師と患者さんのコミュニケーション能力が問われているからだと感じます。
勝俣:私は理由が二つあると思います。一つは、加藤先生がおっしゃったコミュニケーションの問題。近年、医師と患者さんとの間のコミュニケーションはどんどん希薄になってきています。なぜかといえば、医師が忙し過ぎるからです。私は一日20人弱のがん患者を診ていますが、他の医師と比べて少ないと思います。患者さんと納得いくまでとことん話し合うためです。
それでも、私は腫瘍内科なので時間に少し余裕がありますが、外科医になると一日100人近いがん患者を診る医師はざらにいます。そのような状況で患者とコミュニケーションをとるのは難しい。そのため、医師と患者さんとの間にギャップが生まれ、話を聞いてくれないとか、見放されてしまったと感じてしまう場合があると思います。
もう一つは、情報の問題。治療に関する正しい情報ががんの患者さんにきちんと届いているかといえば、必ずしもそうではありません。ともすると、「がんは放置したほうがいい」などという間違った危険な情報も少なくありません。そうしたものが野放しにされている結果、患者さんは惑わされてしまうのだと思います。
──それは、標準治療をやり尽くした後の話でしょうか。
勝俣:標準治療を手術、抗がん剤、放射線の3大治療だけに限って考えると問題があります。「緩和ケア」も標準治療の一つです。緩和ケアと聞くと、もう積極的な治療法がなくなった末期の患者向けと誤解されがちですが、緩和ケアをしっかりやることで患者のQOL(生活の質)も上がり、生存期間を延ばすことができる、つまり治療効果がある、というエビデンスが最近出てきて、アメリカの臨床腫瘍学会は声明まで出しています。
讃岐:私は1年半前に地域のホームドクターとして、東京の町田市に診療所を開業しました。それまでは、慈恵医大附属病院をはじめ大病院で勤務してきましたが、開業して思うのは、がん患者さんにとって重要なのは、専門的な話より生活のことまで相談に乗ってくれる医師が近くにいてくれることです。その意味では、身近に相談できるホームドクターがいれば、がん難民になる可能性は低くなってくると思います。
大久保:私は07年、42歳の時に睾丸がんを発症しました。しかし、幸い「がん難民」にはならず、標準治療を受け社会に戻ることができました。私個人の経験と、多くのがん患者さんから聞いた情報を交えて話をさせていただくと、がん難民が生まれる背景には二つあると思います。まず、患者にとって、医療が「非日常」だということ。そのため、知識も情報もない中で最善の選択をするには相当な壁があります。もう一つは、親戚や友人たちが「あの治療のほうがいいんじゃない?」などと、親切心からお節介を焼くことです。そうすると、自分の選択は正しいのかと迷いがちになります。
[AERA]
Posted by nob : 2015年09月26日 14:01
まずは減らしていくだけでも効果は出ますが、、、私は主体的には摂取ゼロにしたところ、もはや心も身体もそれらを求めなくなりました。。。
■40男の敵は小麦!? 話題の「グルテンフリー」ダイエット
朝トースト、昼はサンドイッチというように、多忙な40男はその手軽さから、つい「パン食」が多くなりがち。しかし、パンには主原料の小麦粉のほかに、砂糖やバターが含まれ、少ない量でも高カロリーなものが多いためダイエットの大敵なのだという。そこで注目したいのが、小麦製品をカットすることでダイエット効果を狙う「グルテンフリーダイエット」だ。ダイエットコーチのEICOさんに詳しく話を聞いた。
今回のアドバイザー
ダイエットコーチEICOさん
1年で20kgのダイエットに成功した後、準ミス日本を受賞。現在は日本初のダイエットコーチとして活動し、ダイエットサロン桜梅桃李を主宰。
小麦製品の“粘り”がグルテンの正体
EICOさん「グルテンフリーダイエットとは、パンやうどんなどの小麦製品を食べないダイエット法です。グルテンとは、小麦や大麦、ライ麦に含まれるタンパク質の一種。小麦をこねて発酵させると出る粘りがグルテンの正体で、うどんの“コシ”もグルテンによるものです。このグルテンには、小腸の消化吸収を妨げる、という特徴があります。
また、小麦加工食品の多くは砂糖やバター、塩分や油も多く含んでいるものがほとんど。それらをセーブするだけでも、摂取カロリーや塩分は大幅に削減できるので、減量にもつながります。製造過程で大量の塩と小麦粉を使ううどんも、グルテンフリーダイエットでは避けたほうがいいでしょう。グルテンと同時に塩分をカットすることができます。高血圧が気になる人にもぴったりなダイエット法です」
食事選びが重要なポイント
EICOさん「小麦製品の摂取を控えるうえで重要なのが、食べ物の選び方です。パン食はもってのほかですが、男性が忘れがちなのが揚げ物類でしょう。唐揚げやなんこつ揚げは、小麦粉で打ち粉をするし、天ぷらやとんかつにはつなぎにパン粉を使います。どれも居酒屋の定番メニューなので、外食の際は避けてください。また、パスタやラーメンの麺にも小麦粉が使われているので、注意しましょう。
グルテンフリーダイエットの主食としてベストなのは、グルテンが含まれていないお米です。また、肉や野菜、魚も揚げ物以外ならば問題ありません。より摂取カロリーを低く抑えたい場合は、お刺身がおすすめ。米や魚など、グルテンフリーの食生活は日本食と親和性が高く、和食好きな方ならシンプルに実行できるはずです」
最後にアドバイザーからひと言
「どんなダイエットもそうですが、短期間に無理をして実践するのは危険です。長くつづけられる、自分に合った方法を見つけてください」
[エディトゥール]
Posted by nob : 2015年09月21日 07:12
ほぼ毎日いただいています。。。
■1か月に1回ナッツを食べるだけ 死亡率、がん死亡率が下がっていた
イタリア国立神経学研究所の研究者らは、少量のナッツを月に1〜2回食べるだけでも全死亡率(あらゆる死因を含めた死亡率)とがん死亡率が低下すると発表した。
研究者らはイタリア在住の成人1万9368人を対象に、地中海食と肥満や疾患の関係を調査している「Moli-sani Study」を利用し、4年間にわたってナッツの摂取量とがんや心血管疾患、脳卒中などによる死亡率の関係を分析した。
その結果、ナッツをまったく食べない人と、1か月に2回以下は少量でもナッツを食べている人を比較した場合、食べている人は全死亡率が32%低下しており、がん死亡率が36%低下していた。また、月に8回以上食べている人では全死亡率が47%低下していたという。
研究発表は2015年8月27日、英国栄養学会誌「British Journal of Nutrition」オンライン版に掲載された。
参考論文
Nut consumption is inversely associated with both cancer and total mortality in a Mediterranean population: prospective results from the Moli-sani study.
DOI:10.1017/S0007114515002378 PMID:26313936
[Aging Style]
Posted by nob : 2015年09月20日 23:35
朝・夕食後には、普段珈琲と他くるみ・黒無花果・ダークチョコレートといっしょにいただいていますが、、、アーモンドだけ朝食前に変えてみようかしら。。。
■善玉、悪玉コレステロールを改善するには 朝食前に「アーモンド」
朝食前に10グラム(およそ9〜10粒)のアーモンドを食べ続けると、HDL(善玉)コレステロールが増加し、LDL(悪玉)コレステロールが減少すると、パキスタンのアーガー・ハーン大学の研究者らが発表した。
心臓に血液を送る冠動脈で血液の流れが悪くなり、心臓に障害が起こる「冠動脈疾患」の発症リスクは、LDLコレステロールが高い人や、HDLコレステロールが低い人で高いといわれている。
研究者らはアーモンドを食べることでHDLコレステロール値を高めることができるか検証するため、冠動脈疾患を発症したことがあり、LDLコレステロール値が100 ミリグラム/デシリットル以下、HDLコレステロール値が男性で40ミリグラム/デシリットル以下、女性で50ミリグラム/デシリットル以下の成人150人を3つのグループに分類。それぞれ毎日朝食前に10グラムのパキスタン産のアーモンドを食べる、米国産のアーモンドを食べる、アーモンドを食べない生活を12週間送ってもらい、6週目、12週目の時点でのコレステロール値を計測した。その結果、アーモンドを食べていた2グループは6週目、12週目いずれの時点でもHDLコレステロール値が12〜16%上昇し、LDLコレステロール値は減少していた。アーモンドの原産国による効果の違いはなかったという。
研究結果は米栄養学会誌「The Journal of Nutrition」オンライン版に2015年7月22日掲載された。
参考論文
Dietary Almonds Increase Serum HDL Cholesterol in Coronary Artery Disease Patients in a Randomized Controlled Trial.
DOI:10.3945/jn.114.207944 PMID:26269239
[Aging Style]
Posted by nob : 2015年09月13日 05:41
分煙の徹底あるのみ。。。
■受動喫煙の男性は喫煙者と同程度、歯周病の危険
他人のたばこの煙を吸う受動喫煙をしている男性は、喫煙者と同程度、歯周病になる危険が高まるとする研究結果を国立がん研究センターと東京医科歯科大のグループがまとめた。
同グループは2005年~06年に歯科検診を受けた1164人を対象に受動喫煙と喫煙、歯周病の関連を調べた。受動喫煙は「家庭で10年以上喫煙者と同居」「職場などで1日1時間以上喫煙者とほとんど毎日接する」などとした。
分析の結果、重度の歯周病になる危険は、受動喫煙をしていない男性に比べ、家庭で受動喫煙をしていると約3・1倍、家庭とそれ以外の場所で受動喫煙をしていると約3・6倍高かった。喫煙者が歯周病になる危険は約3・3倍でほぼ同じだった。女性における受動喫煙と歯周病との関連はみられなかった。
[読売新聞]
Posted by nob : 2015年09月01日 17:26
自らの主治医はあくまで自分自身、、、医療の活用と依存との間には天地の開きがある。。。Vol.2
■「1滴」でがん、うつ病、アルツハイマーまでわかる 血液検査は驚くべき進化を遂げていた【ドクター注目記事】
将来の疾患リスクがすべてわかる日も近い?
健康診断でおなじみの採血。今日では、血糖値や血中コレステロール値などを調べるにとどまらない。
日本や海外の研究機関では、1滴の血液からがんやアルツハイマー、うつ病、さらにこれまでのウイルス感染歴までわかるほど「進化」を遂げている。
206種類のウイルス判別で早期治療可能に
米ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学の共同研究チームは科学誌「サイエンス」2015年6月号で、1滴に満たない血液から、過去に感染したすべてのウイルスが判明する血液検査「VirScan」を開発したと発表した。ウイルスに侵入された際に免疫系が出した抗体の有無を調べる。これまで、同様の分析方法では数種類が判別できる程度だったが、VirScanでは人が感染する206種類のウイルスを判別できる。感染歴がわかると、後天性免疫不全症候群(エイズ)やC型肝炎のような感染から発症までの潜伏期間が長い疾患の早期発見や、各ウイルスに対応する抗体の有無で今後の感染や発症のリスクがわかり、早期治療も可能になる。
血液検査の技術や精度向上によってわかるのは、ほかにもある。がんもそのひとつだ。 一般的に、大腸がんなら便潜血検査、胃がんなら内視鏡や胃X線検査、乳がんならマンモグラフィーと、がんの部位によって必要な検査は異なる。しかしここ数年、血液1滴から主要ながんを判定できる血液検査が、千葉大学や神戸大学、昭和大学、国立がんセンターから次々と発表、実用化されており、全国の医療機関で受診できるようになっている。アミノ酸の濃度やがん細胞が出す特定の物質の有無など、分析方法は異なるものの、どれも3〜7日と早い期間で判定できるのが特長だ。がんの有無だけでなく、発症リスクや従来の検査では見落としていたかなり早期のがんも発見できる可能性がある。
血液検査に加えて従来のがん検診も受診すれば、さらに精度が上がるという。
誤診による誤った投薬や治療の防止に
10年後の脳梗塞、心筋梗塞の発症リスクが高い精度でわかる血液検査も実用化されており、疾患予防のためにも欠かせない検査になりつつある。
血液検査の可能性はさらに広がる。例えば「うつ病」のように、進行しなければ診断できないとされてきた疾患も、正確かつ早期発見できるかもしれない。
うつ病は問診による診断が基本だが、うつ状態や躁うつ病と誤診して誤った投薬や治療法を続け、いつまでも改善がみられない場合もある。より正確な診断のための検査方法として、世界中で血液検査の研究が進められている。日本では臨床研究段階ではあるが、血液中のエタノールアミンリン酸という物質の濃度から診断する検査法が一部の病院で受診できる。
現在は治療法がなく、症状がかなり進行しなければ診断できないアルツハイマーも、健康な人が3年以内に発症するリスクを、90%以上の精度で判定できる初の血液検査法が2015年3月に米国で発表された。早期から発症を予測できれば、進行を阻止、症状を改善する方法も発見できるのではないかと期待されている。[監修:山田秀和 近畿大学医学部 奈良病院皮膚科教授、近畿大学アンチエイジングセンター 副センター長]
参考論文
Viral immunology. Comprehensive serological profiling of human populations using a synthetic human virome.
DOI: 10.1126/science.aaa0698. PMID: 26045439
[Aging Style]
■がん細胞を直に集中攻撃 極小カプセル「ナノマシン」の威力
今年6月、がん治療の現場に朗報が舞い込んだ。切らずに治療できる「ナノマシン」の開発が発表されたのだ。このナノマシン、未来の医療に大変革を起こす可能性を秘めている。
直径わずか50 nm(1nmは100万分の1mm)の「ナノマシン」が医療に革命を起こしている。
ナノマシンとは、抗がん剤など様々な機能を詰め込んだ高分子の極小カプセルのこと。東京大学大学院工学系研究科/医学系研究科の片岡一則教授を中心とする研究チームがナノテクノロジーを駆使して開発している。
その最大の特徴は、体内に取り込まれると自動的にがん細胞を検出し、抗がん剤を用いて「狙い撃ち」することだ。
臨床ではまず、静脈注射や点滴でナノマシンを人体に注入する。通常、体内に入りこんだ異物は除去されるが、ナノマシンは生体適合性が高く、除去されない仕組みになっており、血管内をスイスイと泳ぐ。
がん細胞の周辺には、高分子物質が集まる性質(EPR効果)がある。高分子の集合体であるナノマシンはこのEPR効果を利用して、血管の隙間からがん細胞内に侵入する。
「がん細胞の周囲は血管の目が粗く透過性が高い。ナノマシンは血管の目が細かい正常な細胞には届かないが、目が粗いがん細胞には届く絶妙な大きさになっています。そしてがん細胞の核に近づき、集中的に攻撃します」(片岡教授)
がん細胞は正常の細胞とは違い、やや酸性だ。ナノマシンはpH値の絶妙な違いを感知し、抗がん剤を放出する。
「魔法の弾丸」と呼ばれるナノマシンは、ターゲットとなる組織や細胞に薬を効果的に到達させる「ドラッグデリバリーシステム(DDS)」を高度に発展させたもの。がん細胞のみを標的とするため、健康な細胞への副作用が少ないことが最大のメリットだ。通常の抗がん剤治療や放射線治療の難点を克服できる。
さらにナノマシンと放射線を組み合わせた治療法も開発中だ。体外から中性子線を当てると反応してがん細胞を壊す放射線を出す物質をナノマシンに載せ、がん組織に集めるのだ。そのうえで患部に中性子線を当てれば、がん細胞だけが破壊される仕組みである。片岡教授らは、マウスでそれを実証した。この成果は今年6月に公表されたばかり。
「この治療法はMRIでナノマシンががん細胞に集まっていることを確認しながら中性子線を照射して、ピンポイントの放射線治療ができるのでより精度が高い。通常、がんの開腹手術は1か月近くの入院期間で費用もかさみますが、ナノマシンを利用した“切らない手術”が普及すれば、患者の負担を心身とも大幅に軽減できる。将来的にはがんの日帰り手術も期待できます」(片岡教授)
すでに現在、ナノマシンを利用した5つの抗がん剤臨床試験が進んでおり、乳がん用のナノマシンは今年中にも厚労省に承認申請される予定だ。長寿命にとって大きな壁となるがんを克服する日は一歩一歩近付いている。今後はアルツハイマー病や再生医療への展開も考案中という。
[NEWSポストセブン/SAPIO]
Posted by nob : 2015年08月23日 13:04
何歳からでも、どんな健康状態からでも、まずは始めて、そして続けていくことのすべてが、やがて自らに還ってくる。。。
■暑さに負けずトレーニングをしたほうがいい理由
汗だくでぐったりな状態が好きな人なんていません。太陽にじりじりと焼かれるような日は、エアコンの効いたジムでワークアウトしたくなるのも当然です。けれども、暑さを耐え抜けば、トレーニングが楽になるだけでなく、気温が下がった時の持久力もアップします。
暑い中でのトレーニングは危険をともないます。気温が高い時に走る場合の常識的な注意事項はおわかりですよね。なかでももっとも大事なのは、十分な水分補給です(飲みすぎるくらいでも良いのです)。また、吐き気やめまい、だるさなどの熱中症の症状を感じ始めたら、すぐにトレーニングをやめて助けを求めることです。暑い環境でも走れる体力をつけるのは素晴らしいとはいえ、ムリは禁物です。
また、我慢できないほど気温が高い時は外に出ないでください。また、都会に住んでいる人は光化学スモッグやオゾン濃度に注意しましょう(気温が上がると悪化します)。
暑い日の運動がつらいのはなぜか
ランニングも暑さも両方身体に堪えるものです。さらに、暑い日のランニングはなおさら辛いですよね。でも問題はそれだけではありません。暑い日の運動は、必要以上にきつく感じられるのです。
暑い日に頑張ると、脳は通常とは異なる受け取り方をするので、オーバーヒートする前でもだるさを感じます。学術誌『European Journal of Physiology』で発表されたある研究によれば、被験者のサイクリストたちは摂氏35度の研究室でトレーニングをした時のほうが、摂氏15度で同じトレーニングをした時よりスピードが落ちました。これに関しては納得できます。でも、不思議なのは、オーバーヒートしたためにスピードが落ちたわけではなく、始めから動きが鈍かった点です。脳が暑さを感知し、エネルギーを節約しようとしたのです。この作用により、身体の動きをあえて鈍らせたわけです。
トレーニングを続けると、身体は熱を帯びてきます。別の研究にて、被験者たちに疲れ果てるまで自転車を漕いでもらいました。すると、スタート時の気温に関係なく、被験者たちが完全に体力を消耗したのは、深部体温が摂氏40度に達した時でした。学術誌『Journal of Applied Physiology』に掲載されたこの研究で、深部体温が40度に達するまでにもっとも時間がかかったのは、水分に反応するクーリングウェアを着ていたアスリートでした。運動する時に、キンキンに冷えた飲み物を飲み、頭から水をかぶると、これと同じ効果が得られます。体温を低く保てば保つほど、つらいトレーニングを長く続けられるのです。
とはいえ、ただ身体を冷やせば良いというわけではありません。コップ1杯の冷たい水を頭やお腹にかけたところで、涼しいのはほんの一瞬ですし、クーリングウェアは、生理学の研究室から一歩外に出れば実用的とは言えません。では、実際の状況で何が起きるのかを見ていきましょう。
身体は、汗をかくことで体温を下げようとします。皮膚の表面から汗が蒸発する際に、熱も一緒に奪っていくからです。しかし、蒸し暑い日は空気中がすでに水蒸気でいっぱいなので、汗はなかなか蒸発しません。ですから、「暑さ」といっても、実際は「暑さという感覚」であって、熱と湿気が結びついた状態を指しています。下の暑さ指数チャートを見るとその関係がわかります。
高温多湿の環境下では、走るスピードが落ちます。こちらのようなチャートを見れば、どのくらいスピードが落ちるのかを正確に予測することも可能ですが、実際は、暑さに対する慣れと、身体のサイズで変わってきます。
落ちるスピードは、どれだけ鍛えているかではなく、身体のサイズによって変わるのです。体格の良い人は筋肉や脂肪、またはその両方が多くなります。筋肉は熱を生み出し、脂肪は断熱材の役割を果たします。一方、身体の小さい人は熱の発生量は少なく、熱を発散させる皮膚面は増えます。古くから知られている、体表面積と熱発散の関係を示すアレンの規則のことですね。暑い日のレースでは、小柄なランナーのほうが速く走れます。
鍛えたほうが暑さに強くなると考える人もいますが、その反対もまた然り。鍛えれば鍛えるほど、激しい運動が得意になり、身体が発する熱も増えていくからです。
体型を変えずに暑さに耐えて運動できるようになるにはどうしたら良いでしょうか。その答えは簡単。暑い中でトレーニングを積めばいいのです。
暑さに慣れる方法
暑い時にトレーニングを積めば、暑さに負けず走れるようになり、ひいてはもっと速く走れるようになります。
仮に、自分が今年の夏中、すべてのトレーニングを屋外でこなすと想定します。一方、自分の双子の片割れは、エアコンの効いたジムでまったく同じ内容のトレーニングをします。そして、真夏の真っ盛りに5 マラソンに出場した場合、どちらが勝つと思いますか? 勝つのは、涼しい室内でトレーニングした双子の片割れではなく、自分です。
万が一、マラソン当日、季節外れの涼しさだったとしても、暑さの中でヒート・トレーニングを積んでいますから、勝つのは自分です。ヒート・トレーニングには、血管の血流量を増やすという魔法の効果があります(身体を冷やすためには皮膚の血流を促したほうがいいのですが、筋肉にエネルギーを運ぶための血流も十分にあるわけです)。その効果は言わば、合法的な血液ドーピングといった感じです。
とはいえ、良いことばかりではありません。暑さに慣れるには努力を要します。夏中ずっとエアコンの効いた室内にいて、たまに思い切って外に出て運動するだけでは不十分です。ウェブサイト「European Journal of Applied Physiology」に掲載されたある研究によれば、暑さの中での運動に取り組まなかった人は、暑さに対する耐性が春と秋で変化しないことがわかっています。ヒート・トレーニングで効果を得たいなら、そのための努力が必要です。
アメリカ陸軍が開発した、「暑さに順応するトレーニング計画案」は、暑さに慣れたい人にとっての良い手引きです。この計画案によると、毎日最低でも2時間は外で活動し、その一環として、心血管運動(ランニングやサイクリングなど、心拍数が上がるエクササイズなら何でも)を行わなければなりません。
2週間ほど経てば、暑さに慣れてくるでしょう。ただし、トレーニングの効果は始めてから数日で実感できるかもしれません。
始めからトレーニングをすべてこなせるわけではありません。トレーニング初期の脳は、まだ暑さを察知し、身体が疲労しているからスピードを緩めようと、指令を出してきます。労働者向けセーフティーガイドラインで、トレーニングが現実的であるかどうかチェックしてください。労働安全衛生管理局(OSHA)は、ヒート・トレーニング初日は通常の作業負荷の20%のみに抑え、1週間かけて徐々に100%に持っていくよう推奨しています。
また、暑さへの耐性をキープするためには、引き続き暑い環境下でトレーニングを積まなければなりません。数日なら休んでも構いませんが、1週間サボったら、暑さに耐える驚異的なスーパーパワーが失われ始めます。陸軍の推算では、3週間サボるとスーパーパワーの75%が失われてしまうそうです。
涼しい季節でもヒート・トレーニングを続けたいなら、長そでとタイツを着用しましょう。これは、2007年世界陸上競技選手権大会の開催地である蒸し暑い大阪でのレースに備えて、一流ランナーのKara Goucherが取り入れた方法です(1万m走では、アメリカ人初の銅メダルを獲得しました)。Goucherはさらに、レース前の数週間を大阪で過ごしています。熱心なランナーで、有給休暇が余っている方は、ぜひこの方法を参考にしてみてください。
また、以前、米ライフハッカーの記事「身体を涼しく保つ方法」を紹介していますが、それと正反対のやりかたを試してみてもいいでしょう。1日でもっとも暑い時間帯に、日の当たるアスファルトの道路を走ってみてはどうですか? いずれにせよ、ムリをせずに、新たに獲得したスーパーパワーを楽しんでください。
Beth Skwarecki(原文/訳:遠藤康子/ガリレオ)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2015年08月23日 12:40
自らの主治医はあくまで自分自身、、、医療の活用と依存との間には天地の開きがある。。。
■がん検診を受けると早死にする?放射線検査と「過剰な医療」が寿命を縮める
「胃がん検診を受けたら、偶然、早期のがんが見つかって命拾いした」などと言っている人が、身近に結構いたりしませんか? 乳がんの撲滅をうたったピンクリボン運動をご存じと思いますが、その宣伝塔を務めるタレントも同じようなことを言っていますね。「だから、乳がん検診を受けましょう」って。
今から30年ほど前のことです。米国ミネソタ州にある有名な総合病院「メイヨー・クリニック」が中心になって行った、大規模な追跡調査のデータが世界に衝撃を与えました。この調査は、肺がん検診の効果を確かめるため、タバコを吸っている9211人の男性ボランティアを対象に行われたものでした。
調査では、まずボランティアたちが公平に2つのグループに分けられました。年齢や性別、タバコを吸っている本数などが両グループで揃えられ、人数も同じになるよう調整されたのです。次に、一方のグループに年4回の胸部レントゲン検査を受けてもらうように約束をしました。このグループを「検診群」と呼ぶことにします。もうひとつのグループには、地域で行われている年1回の一般的な健康診断だけを受けるように依頼しました。こちらは「対照群」としましょう。
6年後、「肺がんで死亡した人数」を調べたところ、検診群で122人、対照群で115人となっていることがわかりました。一生懸命に肺がん検診を受け続けた人たちのほうが死亡率は高かった、という驚きの結果だったのです。
●過剰な診断
このようなデータを見せられた時、考えるべきことがいくつかあります。
ひとつは、偶然そうなっただけかもしれないということです。もうひとつは、データにねつ造や隠ぺいがあったかもしれないということです。昨年のSTAP細胞論文問題では、論文に掲載された写真に不自然な点があったことから一連の不祥事が暴露されましたが、数値データが中心の追跡調査の論文では、ねつ造などを見抜くのは至難の業です。
幸い、ほとんど時を同じくして、同じ目的の調査が英国、米国、それに旧チェコスロバキアの3カ所で独自に行われていて、結果もまったく同じだったのです。「肺がん検診を受けると、死ぬリスクが高まる」のは、間違いのない事実と考えてよさそうです。
理由もほぼ明らかにされていて、検査で使われるレントゲン線が放射線の一種であるため、発がんリスクを高めてしまうからです。
もうひとつあります。ひとたび「がん」と診断されてしまうと、精密検査、手術、抗がん剤治療、放射線治療など、ありとあらゆる医療が施されますが、中には放置しても構わない腫瘍が相当数あったと思われます。だとすれば、過剰な医療が命を縮めてしまったのではないでしょうか。欧米の専門家は、これを「overdiagnosis(過剰な診断)」と呼び、深刻な事態だとしています。しかし、日本ではまったく話題にされず、この言葉の訳語すらありません。
●「肺がん検診を毎年受けると、死亡率が半分に」は正しいのか?
その日本では、40歳以上のすべての人に毎年、肺がん検診を受けるよう勧奨が行われています。厚生労働省のホームページには、次のように書かれています。
「きちんとした科学的データをもとに検討が行われ、その結果を踏まえて市町村で実施されているものです」
科学的データとは、厚労省研究班という名のもとに宮城、群馬、新潟、岡山の4県で一斉に行われた、ある調査の結果を指しているようなので、その概要をまとめておきましょう。
4つの地域では、コンピューターを使えば「肺がんで死亡した人」を簡単に抽出することができ、かつ過去3年間に肺がん検診を受けていたかどうかがわかるようになっていました。そこで、不幸にして肺がんで亡くなった人たち(1035人)が、どれくらい検診を受けていたのかが調べられたのです。ただし比べる相手がいないと評価ができませんから、「現在のところまったく健康」という6713人を同じコンピューターで選び出し、同じ要領で検診歴をカウントしました(対照群)。
その結果、肺がんで死亡した人たちは、前年に検診を受けていた割合が、対照群に比べ半分くらいだったことがわかったというのです(2年前と3年前の検診歴には差がなかった)。当時、この話は全国ニュースとなり、新聞各紙の1面に「肺がん検診を毎年受けると死亡率が半分に!」という見出しが躍っていました。
さて、メイヨー・クリニック調査との違いがどこにあるか、考えてみてください。
その答えは、本連載のタイトル『歪められた現代医療のエビデンス』にも通ずるものですが、簡単ではないため、回を重ねながら明らかにしていきたいと思っています。
(文=岡田正彦/新潟大学名誉教授)
[Business Journal]
Posted by nob : 2015年08月23日 12:23
心身に良いことづくめのウォーキング。。。
■頭脳にはウォーキングが必要だ
99u:私たち現代人の仕事を、常にクリエイティブにしてくれたり支えたりしてくれる万能薬は存在しません。しかし、それに近い効用を持つ方法があります。ウォーキングです。
神経科学者のAndrew Tate氏はCanvaのブログ記事で、長距離ウォーキングがもたらす効用について以下のように述べています。
クリエイティブになる
米国スタンフォード大学の2014年の研究において、人はじっと座っているときより、歩き回っているときの方が、はるかにクリエイティブであることが示されています。Marily Oppezzo氏とDaniel Schwartz氏によると、トレッドミルでも屋外でも、人は歩いているときの方が座っているときよりも60%もクリエイティブだそうです。
素晴らしいコミュニケーション法になる
スティーブ・ジョブズやマーク・ザッカーバーグ氏は、二人とも最初のミーティングを動きながら行うことを好みます。これは、歩きながら会話することで、他の形式の会議よりもはるかに自然で気が散らないからです。血流が良くなることで、クリエイティブなアイデアや問題の解決策が浮かぶだけでなく、より上手にそういったアイデアを表現することができ、同僚とのコミュニケーションにも役立ちます。
偉人たちと同じ道を辿ることができる
ベートーベンはウォーキング愛好家で、午後の間はずっとウィーンを歩き回っていたようです。いつも紙と鉛筆を持ち歩き、ひらめいたことをすべて書き留めていました。他にも、ウォーキング愛好家で有名な人物は小説家のチャールズ・ディケンズです。ロンドンや故郷のケント州の自宅では、いつも長い散歩を好んでいました。ディケンズは1日に30マイル(約48km)も歩きます。彼の作品で最も素晴らしいキャラクターの何人かは、ウォーキングの際に思いついたものです。
さらに、進化論を唱えたチャールズ・ダーウィンは、考え事をするための散歩道として自宅にレーストラックならぬ砂利道を設けていました。彼はウォーキング開始時に石を積み、1周するごとに1個ずつ崩し、問題の困難度を石3つ分、4つ分、5つ分と言い表していたようです。Twitter の共同設立者で、現在デジタルファイナンス企業Squareを率いているジャック・ドーシー氏は、入社した新入社員を「ガンジーウォーク」に連れて行きます。これはサンフランシスコの通りからSquareオフィスまでの壮大なウォーキングで、Squareの指導原則として彼が信奉していることなのです。
つまり、将来のプロジェクトに関するものであろうと、既存の問題に対する革新的な解決策であろうと、アイデアは動き回っているときにひらめくものなのです。また、動いているとそういったアイデアを自分自身や一緒に歩いている人に、より明瞭に伝えられます。
ウォーキングには、また別の大きな効用も存在します。頭を働かせすぎて生理的にもう何も考えられない場合は、一人で歩いて頭脳をクリアにするしか方法はありません。携帯電話もヘッドフォンも、(何かを見つけて衝動的に買ってしまわないように)財布も持っていってはいけません。長距離ウォーキングは頭脳のパワーアップだけでなく、頭をフル充電させることができる健康ツールなのです。ですから、頭をすっきりさせてリセットした後は、以前よりはるかにクリエイティブになれるのです。
あなたが最後に一人でウォーキングしたのはいつですか? 目的地を考えず、その身にガジェットなど持たず、何も思いを巡らさずに。あなたが今必要としているのは、これだけのことかもしれません。
The Power of the Long Walk|99u
Allison Stadd (訳:コニャック)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2015年08月04日 11:47
健康増進維持管理は、最もクリエイティブかつバリュアブルなライフワーク。。。
■健康を長続きさせるのに最適な5つのモチベーション
健康に対するモチベーションは不意にやってきて、すっと消えてしまいます。もしも皆さんのモチベーションが目標に達するまで続かないのだとしたら、他の人たちはどうやっているのでしょう?
まず初めに、人生のあらゆることと同様に健康な体作りとは学習である、ということを理解してください。次に、自分のモチベーションが何処にあるのかをはっきりさせることで、必要なときにモチベーションを得られるようになります。ブログ・Zen HabitsのLeo Babauta氏は、新たなスキルを習得するのに最善のモチベーションとして5つの指標を挙げています。これを少しアレンジして、健康増進に当てはめてみました。こちらです。
好奇心:
皆さんの中には、純粋に、より健康で強い体を作るための方法を知りたいという気持ちがあるはずです。大切なのは、何をすれば快適で、活動しやすく、快食・快眠ができ、そしてより良く生きることができるのかを問いながらこの好奇心に付き合うことです。たとえば、新しい方法やコツを学ぶとき、それをいきなり鵜呑みにするのは避けたいと思ったり、自分のライフスタイルや好みに合うかどうか試してみるだけにしたいと思ってもよいのです。
新しいものへの探究心:
Leo氏は、これは好奇心と関係があると述べています。楽しく視野を広げることで、エクササイズや行動そのものの中に楽しみを見つけ、うんざりするようなルーチンをいきいきと活気づかせることができます。「文句はやってみてから言うもんだ!」とはこのことです。
誰かと一緒にやってみる:
仲良く競争しましょう。もっと重要なのは、仲間に対して責任感をもつことです。Leo氏はこう付け加えています。「...自分自身のために何かをすることもすばらしい目標ではありますが、誰かのためにするというのはまた、大きなモチベーションになるのです。」
健康について深く考える:
たいていの人が気にしているのは、おそらく全体的な健康を向上させることでしょう。それは良いモチベーションですが、長続きしにくいものです。より健康的になるために、なぜそうなりたいのか、繰り返し自分自身に問いかけて、本当の理由にたどりつくまで掘り下げてみましょう。たとえば、「体重を5キロ落としたい」と言う代わりに、なぜ5キロ落としたいのかと問いかけるのです。きっと、容姿を良くしたいからでしょう。それなら、なぜ容姿を良くしたいのか問いかけ、いちばん大きな「理由」にたどりつくまで質問を繰り返していきます。
難しいことにも取り組める自分であることを証明する:
難しい課題には心が折れるものです。Leo氏はこう述べています。
長年、私は学ぶことが難しくなると、諦めてしまいました。しかし、難しくなってからが、真に学べるものなのです――難しいことをやり通そうとするとき、そして、失敗してもうやめたいと思っているようなとき。私たちはやっかいな場所に身を置くことで学ぶのです。
もし、毎回諦めてしまっていたら、決してものごとを深くまで学ぶことはできないでしょう。したがって、最近の私にとって最善のモチベーションは、自分が難しい学びにも粘り強く挑戦できると自分に証明することです。今のところ、私は正しいようです。
The Best & Less-than-Best Motivations for Learning | Zen Habits
Stephanie Lee(原文/訳:コニャック)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2015年07月29日 11:27
幸せの公式
直感力+想像力=愛する力
愛する力<愛せる力
愛せる力=幸せ力
Posted by nob : 2015年07月28日 18:18
健康管理キホンのキ、、、何かする前に、身体に良くないことをしないことから。。。
■ああっ…それは食べちゃダメ!栄養士が「全力で避ける」体に悪い食品4つ
あなたは毎日どのような基準を持って、食品を購入して料理を作ったり、外食したりしていますか?
「家族の大好物だからいつもコレ」「特売で安かったから今日は●●にする」という方は多いと思います。でも、食品に入っている成分や材料、製造過程まで厳密に調べている方は、少ないのではないでしょうか?
しかし、食と栄養のプロは、食品を選ぶときに別の基準を持っているようです。そこで今回は、海外の女性誌『Glamour』ウェブ版などの記事を参考に、栄養士が「体によくないから」と避ける食品をご紹介しましょう。
■1:“低カロリー”食品
ダイエットをしている人が多いためか、市場にはヨーグルトや清涼飲料水、アイスクリームなど、さまざまな“低カロリー”を謳った商品が出回っています。
しかし栄養士に言わせると、「ひと口食べただけで人工甘味料とわかる甘みで、後味もよくない」とのこと。手を加えられたカロリー控えめ食品よりも、カロリーが多少高くてもより自然に近い食品を食べたほうがいいそうです!
■2:冷凍食品
「あ~、今日はごはん作るの面倒だな……」という時便利なのが、チンするだけで食べられる冷凍食品。
しかし、「冷凍食品には塩分、糖分、脂肪分が高く、さまざまな保存料などが入っています」とは栄養士の弁。これではお腹が膨れても、食べた後にいい気分にはなれそうもありません。
やはり、食事はできたて新鮮なものに限るのです!
■3:パッケージ入りのチーズ
スーパーで購入する便利なパッケージ入りチーズ。でも、一体いつどんな材料を使って作られたのやら……!?
「加工されているからいかにも人工的な味で、保存料もいっぱいだから食べない」と栄養士は証言。多少値は張っても、チーズを作る牧場などから直接買うのはいいアイデアですね。
■4:市販のサラダドレッシング
「健康のために……」とさまざまな野菜を入れて作ったサラダ。でもそこに市販のドレッシングをドバドバ……なんてかけていませんか?
最近ではオーガニック製品も出ていますが、一般のサラダドレッシングのラベルを見ると、なんだかよくわからない材料がたくさん入っています。中には糖分・脂肪分が高いものや、不健康なオイル、人工甘味料、着色料などが入ったものも!
ドレッシングはオリーブオイルやバルサミコ酢などからも簡単に作れます。自作したほうが健康にも経済的にもいいですね!
以上、栄養士が避けている食品をご紹介しましたが、いかがでしたか?
健康と美容に大事なのは、加工された食品は避け、なるべく自然に近い食品を食べること。次回食品を購入する際は、カゴに入れる前にラベルをよく読んでみてくださいね!
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2015年07月28日 17:51
10年でなかったことに。。。
■喫煙による糖尿病リスク、禁煙10年で解消 5万人調査
たばこを吸っていると、糖尿病にかかるリスクが高まる一方、禁煙を10年以上続ければリスクは吸わない人と変わらなくなる――。国立国際医療研究センターなどのグループが、そんな報告をまとめ、22日付の米科学誌で報告した。禁煙による糖尿病の予防効果を大規模調査で確認したのは珍しいという。
関東などに本社のある八つの企業に勤める男女約5万4千人について、喫煙状況を含む健診データを提供してもらい、その後を4年間ほど追跡した。この間に約2400人が、生活習慣も原因とされる2型糖尿病を発症していた。
肥満の度合いといった、糖尿病の発症にかかわるほかの要因が影響しないようにして解析したところ、たばこを吸う人では吸わない人に比べ、1日に11〜20本の人で36%、21本以上の人では50%、2型糖尿病にかかるリスクが高かった。
[朝日新聞]
Posted by nob : 2015年07月23日 18:45
自己責任による選択の問題
■安いなら「ジェネリック医薬品で…」
その選択があなたの寿命を決めている?
クスリを処方されるときに、ジェネリック医薬品を勧められたことはありませんか? 中には「同じ成分で値段が安いなら……」と勧められるがままに、ジェネリック医薬品を選んでいる人も多いのではないでしょうか? 果たしてジェネリック医薬品は本当に安全なのか……。『「先生が患者ならどうします?」医師が自分のために選ぶクスリ・治療法』の著者であり医学博士の岡田正彦氏にジェネリック医薬品の安全性について伺いました。
安いなら……と安易に
ジェネリック医薬品を選んでいませんか?
今、ジェネリック医薬品の品質を懸念する声が高まっています。なぜなら、新薬のように厳格な臨床試験を行う必要がなく、成分が同じだからという理由で簡単に発売が認可されているからです。
成分が同じなら、わざわざ臨床試験をする必要はないのでは?というのが、大方の意見かと思います。ジェネリック医薬品とは、特許の切れたクスリを模したものです。製造・販売しているのは専業メーカー、大手製薬企業など合わせて約20社。一番の特徴は値段が安いことです。
しかし、クスリを製品化するには、薬用成分の化学構造だけでなく、ほかにも大切な技術が必要となります。たとえば服用したあと、さっと効くクスリもあれば、徐々に吸収して一日中、ゆっくり効果を発揮するクスリもあります。胃では溶けずに腸から吸収するようにしたクスリもあるなど、高度なノウハウが結集されていて、それらは別途、特許が申請されています。その製法特許が切れていなければ、それまでのクスリをそっくりまねをすることができません。
つまり、ジェネリック医薬品は、新薬と同じもの、ということは言えないのです。
ジェネリック医薬品の効果を
追跡調査した結果……
ジェネリック医薬品は、「後発医薬品」とも呼ばれますが、その発売後、新薬のほうも少し高い薬価で発売は続けられ、呼び方も「先発医薬品」と変わります。米国では、ジェネリック医薬品の製造・販売の認可を受ける際、次の諸点を証明しなければならないことになっています。
・先発医薬品と剤形、分量、服用方法、品質、効能、適応疾患が同じこと
・服用後の血中濃度変化を24~36人の健康人で調べ、先発医薬品と80~125%の範囲で一致していること
日本でも、これに準じた基準があるようです。
しかし、これだけの条件で先発医薬品とジェネリック医薬品が同等であるとは、とても言えません。長期間、服用を続けるとどうなのか、健康でない人が飲んでも同じなのか、などの疑問がいろいろ思い浮かびます。
幸い、高血圧症の患者を2グループにわけ、それぞれ先発医薬品とジェネリック医薬品を服用してもらった追跡調査が多数行われています。それらの論文を集めて検証したレポートによれば、先発医薬品とジェネリック医薬品との間に、「血圧を下げる効果」と「心臓病、脳卒中を予防する効果」において、有意差はないと結論される、とのことでした。
本当にジェネリック医薬品は
先発医薬品と同じ効果をもたらすのか?
しかし、これらのレポートには問題がいくつかあります。血圧のクスリについて行われた調査の多くが、数週間~数ヵ月しか追跡が行われていなかったことと、対象者数が数十人程度でしかなかったことです。
血圧のクスリのように、長期間にわたって服用するとコレステロール値や中性脂肪値が上昇する人がごくわずかに増える、など微妙な副作用のせいで「総死亡率が改善しない」という事実がありますから、もっと大規模に、もっと時間をかけて調査を行ってほしいものです。高血圧のクスリ以外では、このような調査さえ行われていないのが実情で、ジェネリック医薬品についてはわからないことだらけです。
したがって安心して服用できるのは、新薬でもジェネリック医薬品でもなく、(発売後かなり時間が経っている)先発医薬品ということになります。
もし私が患者さんに「ジェネリック医薬品は安全ですか?」と問われたら、「今のところ、不明です」とお答えするでしょうし、私自身、安いからという理由で、安易にジェネリック医薬品を選ぶことは決してしません。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2015年07月23日 15:33
医療は外傷や急性疾患時の緊急避難手段として、、、慢性疾患には生活習慣の見直しと食養生、自らつくりだした疾患は自ら解消できる。。。Vol.4
■がんを克服するための感情マネジメント
全米ベストセラ―『がんが自然に治る生き方』(3)
ケリー・ターナー=文
治癒不能といわれたガンが自然治癒する現象が、実際の医療現場で話題になることはまずない。 しかし筆者が目を通した1000本以上の医学論文において、ガンが自然に治癒した事例を報告していた。医師は治すのが仕事なのでこうした事例を追跡研究することはなく、「たまたま」治ったという話は「偽りの希望」を与えるだけだとして積極的に口外することもなかったために、自然治癒事例は事実上放置されてきたのである。全く科学的にメスを入れられていないこのテーマを解明するために、「劇的な寛解」事例を報告した医学論文をくまなく分析し、日本を含む世界10カ国で寛解者と治療者のインタビューを行った結果、ガンの自然治癒を体験した人々には、「9つの共通する実践事項」があった。それらは、がんの治癒のみならず、予防としても役に立つものである。発売と同時に米アマゾン1位“がん部門”にランクイン、ニューヨーク・タイムズ・ベストセラーとなった話題の書『がんが自然に治る生き方』。
デカルトの心身二元論はもう古い――心と身体を別ものとして考える時代は完全に終わりました。過去50年のあいだ、科学者たちは心と身体が単に結びついているだけではなく、密接に絡み合っていることを明らかにしました。
心身二元論に最終的に決着をつけたのは、心、脳、免疫システムの相互作用を研究する精神免疫神経学(PNI)から得られた知見でした。1991年にニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに掲載された初期のPNI研究で、研究者たちは大規模なグループを対象に質問用紙に記入させ、その後一般的な風邪のウイルスか塩水の入った点鼻薬スプレーを渡しました(被験者は自分がどちらかのスプレーをもらうことを了解していました)。その結果、ストレスの大きい人は風邪を発症し、ストレスの少ない人は風邪ウイルスを撃退しました。そしてこの結果には年齢、体重、食生活など他の多くの要素にはまったく関係なかったのです。
なぜストレスが病気を引き起こすのか
それから15年後、研究者たちはなぜストレスが身体の病気を引き起こすのかを突き止めました。PNIの研究は、恐れや怒りなどストレスをもたらす感情は脳下垂体にコルチゾール、アドレナリン、エピネフリンなどのホルモンを放出するようシグナルを送ります。これらのホルモンは、敵と戦ったり、敵から逃げたりするような緊急事態であると身体に伝えます。 休息したり回復したりしている場合ではないというわけです。その結果、わたしたちの体は食べ物を消化吸収したり、体内の病原菌と戦ったりすることをいったんやめて、目の前の猛獣から逃げるために血圧を高めようとするのです。
私たちは猛獣に追いかけられるような生活をもはやしていませんが、終わりなき「TO-DOリスト」に追われています。そして何かに失敗するのではないか、誰かに嫌われるのではないかと常に怯えています。そしてやっと休暇を取って「戦うか逃げるか」というモードを休暇モードに切り替えたときに何が起こるでしょう。そう、病気になるのです。なぜなら「TO-DOリスト」から過去何カ月も逃げているあいだに、あなたの身体はあえてウイルスの侵入やバクテリアへの感染を「時間ができるまで」放置していたからです。休暇になってほっとした途端、病気になるのはそのためです。
なぜ幸福な人は健康なのか
どうすればよいでしょうか。脳下垂体は私たちがストレスや不安を感じるたびに免疫を抑制するホルモンを出しますが、私たちが幸せや安らぎを感じているときには免疫を増進するホルモンを出します。これらの「自家製ドラッグ」にはセロトニン、ドーパミン、リラキシン、オキシトシンなどがあります。これらの強力なホルモンが血液中に放出されると、より多くの免疫細胞をつくるように指令を出します。たとえば1日5分間笑ったり、嬉しいと感じたりするだけでも白血球やナチュラルキラー細胞の数は大幅に増えるのです。
がんを克服するための感情マネジメント
PNIの研究からわかった感情と免疫系の関係を考えれば、私が研究しているがんの劇的寛解者たちが回復の途上で自分の感情にとりわけ関心を寄せたのは当然のことだといえるでしょう。過去10年間、私は非常に厳しい状況からがんを自力で克服した何千人という人たちの事例を研究しています。拙著『がんが自然に治る生き方』では、彼らに共通する9つの実践事項を抽出しましたが、そのうち3つは感情と直接的な関係がありました。
●抑圧された感情を解き放つ
●より前向きに生きる
●周囲の人の支えを受け入れる
運動をしたり、ユーチューブを見たり、ペットのネコと遊んだり、方法はさまざまですが、がんの劇的寛解者たちは毎日ストレスから自らを開放して深い呼吸をすることを毎日魚油のサプリメントや処方された薬を飲むのと同じくらい重要であると考えていました。 がんと闘うには免疫力を強めておくのはなによりの戦略です。がんの劇的寛解者たちはあらゆる方法でそれを試みています。そしてRNIの研究が明らかにしたように、感情をうまくコントロールするのは免疫力を高めるのに非常に有効です。
そしてがんの患者だけでなく、健やかに生きたいすべての人にとって、免疫力を高めることは理にかなっています。だから今日1日、5分だけでも自分を甘やかしてあげてください。
※この原稿はケリー・ターナー博士のオフィシャルブログ http://www.drkellyturner.com/blog/ を翻訳したものです
■最善のがん治療は「直感」が教えてくれる
全米ベストセラ―『がんが自然に治る生き方』(4)
ケリー・ターナー=文 長田美穂=訳
治癒不能といわれたガンが自然治癒する現象が、実際の医療現場で話題になることはまずない。 しかし筆者が目を通した1000本以上の医学論文において、ガンが自然に治癒した事例を報告していた。医師は治すのが仕事なのでこうした事例を追跡研究することはなく、「たまたま」治ったという話は「偽りの希望」を与えるだけだとして積極的に口外することもなかったために、自然治癒事例は事実上放置されてきたのである。全く科学的にメスを入れられていないこのテーマを解明するために、「劇的な寛解」事例を報告した医学論文をくまなく分析し、日本を含む世界10カ国で寛解者と治療者のインタビューを行った結果、ガンの自然治癒を体験した人々には、「9つの共通する実践事項」があった。それらは、がんの治癒のみならず、予防としても役に立つものである。発売と同時に米アマゾン1位“がん部門”にランクイン、ニューヨーク・タイムズ・ベストセラーとなった話題の書『がんが自然に治る生き方』から抜粋してお届けする。
私は、医師に「あらゆる手を尽くしたがこれ以上はなすすべがない」と言われながらも自分で生活を変えたり代替治療法を実践したりしてがんを克服した人たちについて研究をしています。彼らのほとんど全員が、回復過程で自らの直感に従って決断を下していました。直感や第六感といったものの研究から、彼らがなぜそのような行動をとったかが見えてきます。
直感は危険を察知する
科学者たちは人間の脳は2つの運転システムを備えていることを発見しました。第1のシステムは、高速稼働し、直感的で、無意識的に働きます。第1システムを支配するのは、右脳と、脳の中でも太古から存在する「大脳辺縁系」と「間脳」です。第2システムは、ゆっくり稼働し、分析に力を発揮し、意識的に動くものです。左脳と、有史以降に発達した新しい部分「前頭葉」がこのシステムを支配しています。
直感は第1システムから生じるということが、科学的に明らかになっています。直感の訪れが唐突で、合理的なものに思えないことが多いのはそのためです。要は直感的な判断とは、慎重に状況判断をして下すものではなく、本能的に沸き上がってくるものなのです。
けれども腹で感じる直感が「信頼に足る」という根拠はあるのでしょうか。脳の第1システムが「答え」を出す速度は、実は第2システムよりずっと速かったということを報告した研究があります。「勝てば賭け金がほぼ全額手に入る」というルールのカードゲームを使った実験がありました。
実はこの実験には、被験者には知らされていない仕かけがほどこされていました。カードの山は2つ。片方の山は、勝てば大きいが負ければ大損をする山です。もう片方は、勝っても儲けは少ないが、損はほとんど出ない山です。被験者は、50回ほどカードをめくったあたりで安全な山はどちらかを勘づきはじめ、80回目には2つの山の違いを説明できるようになりました。興味深いことに、10回目の時点で、被験者の手のひらの汗腺は、危ない山のカードを触るたびに少しだけ開いていました。
また被験者は10回目あたりから、なんとなく安全なカードの山の方を好むようになっていました。つまり被験者の分析的な脳が状況を認識するずっと前に、被験者の身体は危険を感じ取り、自然と安全なほうへと向かっていたのです。
人間は本能で2、3秒後に起きることを予測している
類似の実験を、コンピューターでおこなったものもあります。モニターを見て、被験者は2枚のカーテン画像のどちらの背後に絵が隠れているかを当てます。カードの実験と同じように、研究者は被験者の身体反応を調べました。
驚いたことに、被験者の手の汗腺は、コンピューターがどちらのカーテンに絵を隠すか決める2、3秒も前に、答えを正しく予測していたのです。もっとも手の汗腺の開きをみるかぎり被験者はほぼ正解を予測していたのに、自分の手のひらの反応に気づくことができず、誤答していました。人間には、2、3秒後の未来の予測能力があったのです。カードゲームをするギャンブラーにとっては、貴重な教訓でしょう。自分の手のひらの汗腺の動きがわかるほど身体の声に耳を澄ませば、次に来るカードを予知できるようになる、というのですから。
直感に従って決断した人の満足度は高い
直感は信頼に値すると示す実験を、さらに紹介しましょう。ある実験によると、どの家を買うか、誰と結婚するかといった人生における大きな決断では、頭で論理的に考えた末の選択よりも直感で決めた方がよい結果をもたらすことがわかりました。車の購入時、情報収集をして熟考の末に決めた人のうち、買ったあともその車に満足していた人は、わずか25パーセントでした。それに対して直感で即決した人は、60パーセントが満足していたのです。
似たような実験に、複雑な問題に対してじっくり考える時間を与えられた被験者群と、急に答えを出すよう求められた被験者群では、直感で即座に答えた後者のほうが概して正解率が高かった、とするものがありました。
この研究に取り組んでいるあいだ、わたし自身も、さまざまな直感を得たおかげで、ずいぶん作業がはかどりました。そのときは不思議な感じがしましたが、研究するうちに、わかってきました。直感とは、わたしたちが頭で答えを出す前に、どうするのがいちばんいいかを教えてくれるものなのです。直感を司る脳の部位は、人間が藪に潜む猛獣を避けながら暮らしていたような太古の時代に発達しました。差し迫った危険を感知したり、安全な場所を見きわめたりする能力を備える部位です。
幸いにして、現代のわたしたちの日常は、格段に安全になりました。脳のこの部分を稼働させる必要はほとんどなくなったので、いざというときにも、わたしたちには使い方がわかりません。脳からのメッセージにも気づきません。けれども、わたしたちは直感力を失ったわけではありません。実際、劇的な寛解を遂げた人々は、直感力をうまくつかって生命の危機を克服した人々なのです。
※この原稿は、『がんが自然に治る生き方』からの抜粋です。
[いずれもPRESIDENT online]
Posted by nob : 2015年07月20日 00:05
医療は外傷や急性疾患時の緊急避難手段として、、、慢性疾患には生活習慣の見直しと食養生、自らつくりだした疾患は自ら解消できる。。。Vol.3
■余命宣告から「自然治癒」に至った事例が放置されてきた理由
全米ベストセラ―『がんが自然に治る生き方』(1)
ケリー・ターナー=文 長田美穂=訳
治癒不能といわれたガンが自然治癒する現象が、実際の医療現場で話題になることはまずない。 しかし筆者が目を通した1000本以上の医学論文において、ガンが自然に治癒した事例を報告していた。医師は治すのが仕事なのでこうした事例を追跡研究することはなく、「たまたま」治ったという話は「偽りの希望」を与えるだけだとして積極的に口外することもなかったために、自然治癒事例は事実上放置されてきたのである。全く科学的にメスを入れられていないこのテーマを解明するために、「劇的な寛解」事例を報告した医学論文をくまなく分析し、日本を含む世界10カ国で寛解者と治療者のインタビューを行った結果、ガンの自然治癒を体験した人々には、「9つの共通する実践事項」があった。それらは、がんの治癒のみならず、予防としても役に立つものである。発売と同時に米アマゾン1位“がん部門”にランクイン、ニューヨーク・タイムズ・ベストセラーとなった話題の書『がんが自然に治る生き方』から抜粋してお届けする(全2回)。
「逸脱した事例」がわたしたちに教えること
がんと診断されたことのあるすべての人に
そして愛する人のがん治癒を支える人に
こんな話を聞いたことはありませんか。
進行がんと診断されて、手術や抗がん剤といった病院での治療はすべて試したけれども効果はなく、自宅にもどされた。ところが5年後に医者を訪ねたその元患者は、がんから解放されてすっかり元気になっていた。
わたしが初めてこうした事例に遭遇したのは、サンフランシスコのがん専門病院で患者のカウンセラーをしていたころでした。昼休みにわたしはアンドルー・ワイル博士の『癒す心、治る力――自発的治癒とはなにか』(角川文庫ソフィア、1998年)を読んでいました。そこには、医学的には手遅れだったはずのがん患者が、見事に回復を果たす事例が載っていたのです。わたしはのちにこうした事象を「がんの劇的寛解」(Radical Remission)と名付けました。
驚きのあまり、凍りつきました。こんなことがありうるの? 進行がんを現代医療を使わずに克服した? もしそうなら新聞の一面に載るような話じゃない? たとえ極端な事例だったとしても、画期的な出来事です。
その事例の当事者は、たまたま何かの方法に出合って、治癒に至ったのです。いったい、この人は何をしたのか。自分が担当しているがん患者の方々のためにも、なんとしてもこの現象について知りたいと思ったわたしは、劇的な寛解の症例を探し始めました。
そして衝撃的な事実を発見しました。
なんと、これまでに1000件以上の症例報告が、実際に医学雑誌には掲載されていたのです。けれどもわたしはそんな話を聞いたことがありませんでした。わたしの勤めていたのは有名ながんの研究機関ですが、こうした現象はまったく話題になっていませんでした。
調べれば調べるほど、いらだちが募っていきました。実際、医師たちはこういった症例について調べることもなく、追跡さえしていなかったのです。
わたしは少しずつ、がんから劇的に寛解した人々を探して、直接話を聞きはじめました。彼らは言いました。主治医はよろこんではくれたけれど、どうやって回復したかについては一切関心を示しませんでした。それどころか、「ほかの患者には話さないでください」と主治医に頼まれた人さえいたのです。その理由は、「あらぬ希望を与えたくないから」。
もちろん医師が特殊な事例から得た情報で患者をミスリードしたくないと考えるのはもっともなことです。けれどもだからといって、現実に起きた回復の症例を黙殺すべきではないはずです。
「治るためなら、何でもしたい」という最後の望み
がんが治った人たちから直接話を聞きはじめてしばらくしてからのことでした。抗がん剤治療を受けつつわたしのカウンセリングにやってきた女性がいました。31歳、双子の赤ちゃんがいながら、悪性度の高いステージ3(全4段階)の乳がんと診断されたばかりでした。わたしの目の前で、彼女は泣き出しました。
「治るためなら、何でもしたいの。子どもたちには母親が必要なんです」
彼女は疲労困憊し、最後の望みを求めてわたしに思いをぶつけてきたのです。泣きじゃくる彼女を前に、わたしの脳裏に浮かんだのは、医師たちから見向きもされずに放置されていた1000件以上の劇的な生還の症例のことでした。わたしは一息つき、彼女を見つめて言いました。
「確かなことは言えない。でも、何か方法があるか探してみるわ」
がんの劇的寛解の研究のために、大学院博士課程に進み、人生を捧げると決意した瞬間でした。がんから劇的に生還した人々の症例を探し、分析し、この現象について語っていこう。そう決めたのです。
「がんとの闘い」に勝利するために、すでに勝利した人の体験談を聞く。もっともなことですよね。がんからの生還という驚異的な体験の裏には、どんな秘訣があったのか。それを解き明かすため、思いつくかぎりの質問をぶつけて、科学的な検証をしてみるべきでしょう。説明がつかないからといってその事実を黙殺したり、口封じしようとするのではなく、事実に向き合うのです。
「逸脱」した現象に目を向けた科学者といえば、アレクサンダー・フレミングを思い出します。1928年、フレミングがバカンスを終えて実験室にもどると、菌の培養皿の多くにカビが生えていました。長期休暇の後にはよくあることです。フレミングは皿を消毒して、実験をやり直そうとしました。けれども、ここが運命の分かれ道でした。ちょっと待てよと、彼はカビの生えた皿を注視しました。するとなかに一つだけ、皿の中の培養菌がすべて死んでいた皿があったのです。フレミングは、「たまたまだ」とその皿を放置したりはしませんでした。それが抗生物質の先駆け、ペニシリンの発見につながったのです。
本書では、わたしが手がけているがんからの劇的な寛解についての研究成果を、みなさんにお伝えします。アレクサンダー・フレミングに倣って、わたしは標準から逸脱した事象を無視することなく、より詳細に検討していきます。
本題に入る前に、まずは自己紹介をさせてください。わたしが何によって導かれ、このテーマに人生を捧げることになったのかお話しします。
小児病棟でのボランティアで決意したこと
「がん」との最初の出合いは、3歳のときでした。叔父が白血病だと診断されたのです。叔父の闘病は5年におよびました。親族が集まるたびに、わたしたち子どもは「がん」という恐ろしい病について聞かされ、震え上がりました。わたしが8歳の時、叔父は亡くなり、いとこは父親を失いました。大人の男の人たちは、「がん」で死ぬかもしれない、とわたしは思いました。
14歳のとき、学年末の終業式の直後に、仲のよかった男の子が胃がんと診断されました。ウィスコンシン州の小さな町には衝撃が走りました。募金集めのためにパンケーキ朝食会を何度も開き、彼のお見舞いに行きました。大丈夫だよと言う友だちもいましたが、わたしには「あのときと同じことになるかもしれない」という、いやな予感がありました。男の子は副作用に2年も苦しんで、17歳で亡くなりました。町中が悲しみに暮れました。その後何年間か、わたしは友だちと彼のお墓に花を供えに行きました。彼の死によってわたしは、がんは年齢に関係なく誰をも死に追いやる病なのだと悟ったのでした。
ハーバード大学の学生だったとき、わたしは代替医療やヨガ、瞑想と出合いました。それは初めて体験する不思議な世界でした。それまでのわたしは、心の世界と身体の状態とは別のものだとして、2つを切り離して考えていました。けれどもしだいにそうした考え方に違和感を覚えるようになりました。
ハーバードでの4年間はすばらしいものでした。卒業後の最初の仕事として、わたしは地球温暖化をテーマにした本を共同執筆する予定でした。ところが気がつくと、学生時代に謳歌していた人的なつながりを一切失い、ただコンピューターに向かうだけの生活をしていました。あるとき、その孤立感を友人に話したところ、彼女は、ボランティアをしたらとすすめてくれました。それで、がん患者の役に立つためのボランティアをしようと思い立ったのです。
ニューヨークにあるメモリアル・スローン・ケタリングがんセンター小児病棟で、最初にボランティアをした日のことは、いまもはっきりとおぼえています。わたしの仕事は、静脈注射による抗がん剤治療を受けている子どもたちと、ボードゲームのモノポリーで遊ぶ、というものでした。たったそれだけです。けれどもその数時間のあいだ、子どもたちは、病気のことをすっかり忘れて夢中になっていました。わたしにとっては、人生を変えるほどの意義のある出来事でした。これが天職だと感じました。数週間のボランティアを通じて、わたしはカリフォルニア大学修士課程に進むことを決めました。腫瘍社会福祉学、なかでもがん患者へのカウンセリングを専門に学ぶことにしました。
大学院で学ぶうちに、わたしは改めて代替医療に関心を持ちました。多くの本を読み、ヨガのインストラクターの資格も取りました。日中はがん患者のカウンセリング、夜は勉強とヨガの時間に充てました。当時、わたしの夫は鍼(はり)や漢方など中国伝統医学の学位をとるため勉強をしつつ、身体エネルギーを活用した難解な治療法を学んでいました。代替医療の学習材料には事欠かない環境でした。
人生の転機となったアンドルー・ワイル博士の本に出合ったのはこの時期のことです。ワイル博士の説く「自発的治癒」という現象に興味を持ち、このテーマを追求するため博士課程へ進むことにしました。医学的には不可能だとみられた状態からがんを克服した人々は、いったい何をしていたのか。その探求に人生を捧げる決意をしたのです。
がんの「劇的な寛解」とは何か
がんの劇的な寛解とは何を意味するのか。これを考えるにあたって、まずは「標準的な」寛解、あるいは「劇的ではない」寛解とは何なのかを考えてみましょう。
医師ならこう考えるでしょう。初期に発見された、治療しやすいタイプのがんなら、寛解は期待できる、と。たとえばステージ1の乳がんで、手術、抗がん剤と放射線という標準的な治療を受けた女性の場合、統計的にいえば、その後5年間はまず再発しないだろうという予測が成り立ちます。でも、もし同じ女性が膵臓がんのステージ1だと診断されたら、同じく標準治療を受けたとしても、5年生存率はわずか14パーセントにすぎません。なぜなら現代医学には、ステージ1の乳がんほどの治療効果を上げる膵臓がんの治療法は、存在しないからです。
わたしは「がんからの劇的な寛解」の定義を、次のように定めました。
・がんの種類は問わず、「寛解」が統計的に極めて稀であること
・その統計とは、がんのタイプ、ステージ、受けた治療によって異なるものとする
さらに具体的に記しましょう。
「がんの劇的な寛解」とは、次のいずれかの事態が起きた状態を指します。
1 医学の標準治療(手術、抗がん剤、放射線)を一切用いずに、がんが検知できなくなった場合
2 標準治療を受けたががんは寛解せず、代替医療に切り替えてから寛解に至った場合
3 統計的にみて余命が極めて短い(5年生存率で25パーセント未満)がん患者が、現代医療と代替医療を併用したところ、統計を上回って生存している場合
統計的予測を覆してがんが寛解するのは、たしかに稀ではありますが、体験者は数多く存在します。
わたしは腫瘍内科医に会うたびに、「がんを劇的に寛解させた患者を診たことがありますか」と聞いています。これまでのところ、全員の答えが「イエス」でした。そこで「ではその症例について医学雑誌で報告しましたか」と聞くと、全員が「ノー」と言いました。
思ったとおりです。劇的な寛解の症例を追跡するシステムでもつくらないかぎり、こうした現象が実際にどのくらいの頻度で起きているのか、わたしたちには知る由もないのです。
この目標を実現するため、本書のウェブサイト(RadicalRemission.com)では、がんを克服した人、医師、治療者、読者の皆さんが手軽に劇的寛解の症例を投稿できるようにしました。データベースは無料で一般公開しています。データは研究者も自由に使えます。またがん患者やその家族にとっては、ほかの人がどうやって劇的な寛解を遂げたか、調べることができます。
■末期がんから自力で生還した人たちが実践している9つのこと
全米ベストセラー『がんが自然に治る生き方』(2)
ケリー・ターナー=文 長田美穂=訳
「治った」人の1000件以上の医学論文
寛解症例の研究に着手してまず驚いたのは、1000件超の医学論文において、2種類の人々がほぼ黙殺されていたことでした。
一つは、劇的に寛解した患者本人の一群です。大多数の論文では、患者自身が劇的な寛解の原因をどう考えているかについて一切言及していませんでした。劇的な寛解を遂げた患者の身体の生化学的変化については、何本もの医学論文が詳細に記していました。しかし、患者に「あなたは自分がなぜ治癒したと思うか」と聞き、その答えを記したものは皆無だったのです。患者たちは、意識的だったかどうかはともかく、がんを治すため何かに取り組んでいたはずです。医師はなぜそれに興味を持たなかったのでしょうか。
そこでわたしは劇的な寛解を遂げた20人にインタビューし、「あなたはなぜ自分が治癒したと思うか」を聞くことにしました。
医学論文で黙殺されていたもう一群は、代替療法の治療者たちです。がんからの劇的な寛解は、当然のことながらほとんどの場合、現代医療では打つ手がなくなった患者に起きています。それなのに、西洋医学外の治療者や代替療法の治療者たちががん治療にどう取り組んできたのかを誰も調べてきませんでした。この事実にわたしは驚きました。
わたしが会った劇的寛解の経験者は、世界の隅々まで、それこそ血眼になって治療者を探し出していました。そこでわたしも世界中を旅して回り、非西洋医学の治療者、代替療法の治療者50人にインタビューをしました。10カ月かけて10カ国(アメリカ“ハワイ”、中国、日本、ニュージーランド、タイ、インド、英国、ザンビア、ジンバブエ、ブラジル)を回りました。ジャングルや山の中、そして都市を旅し、治療者と話をしました。各地のすばらしい治療者がわたしに話してくれた経験を、読者のみなさんにご紹介します。
がん治癒を目指して実行していた9項目
劇的な寛解について記した医学論文は1000本以上分析しました。博士論文の研究を終えてからもさらにインタビューを続け、その対象者は100人を超えました。
わたしは、質的分析の手法で、これらの症例を何度も詳細に分析しました。その結果、劇的な寛解において重要な役割を果たしたと推測される要素(身体、感情、内面的な事柄)が75項目、浮かび上がりました。
しかし、全項目を表にして出現頻度を調べると、75のうちの上位9項目は、ほぼすべてのインタビューに登場していることに気づきました。
たとえば登場回数が73番目に多かった「サメ軟骨のサプリを摂取する」。これは調査対象中の、ごくわずかな人が話してくれただけでした。かたや語られる頻度のもっとも高かった9つの要素については、ほぼ全員が、「がん治癒を目指して実行した」と言及していたのです。
その9項目とは次のとおりです。
・抜本的に食事を変える
・治療法は自分で決める
・直感に従う
・ハーブとサプリメントの力を借りる
・抑圧された感情を解き放つ
・より前向きに生きる
・周囲の人の支えを受け入れる
・自分の魂と深くつながる
・「どうしても生きたい理由」を持つ
この9項目に順位はありません。人によって重点の置き方が異なるものの、インタビューで言及される頻度は、どれも同じ程度でした。わたしが話を聞いた劇的寛解の経験者はほぼ全員が、程度の差はあれ9項目ほぼすべてを実践していたのです。
そこで本書は9章に章立てし、1章で1項目ずつ説明していきます。
各章では、まずその章のテーマについての解説と、それを裏付ける最新の研究報告を紹介します。次に、劇的な寛解を遂げた人の実話を記します。章末には「実践のステップ」と題して、その章のテーマを実践しやすいかたちにして、いくつかの方法をご紹介します。
偽りの希望と真の希望とは
9項目の詳細に入る前に、はっきりさせておきたいことがあります。
まず、わたしは手術、抗がん剤、放射線の「三大療法」を否定する者ではないということです。
たとえ話をしましょう。ふつう、フルマラソンを走るとき、人は靴を履いて走ります。けれどもごく稀に、自分なりのこだわりがあって裸足で走る人がいます。なかには裸足のまま元気に完走してしまう人もいます。
同じように、がんにかかった人は、普通は現代医療に頼るものです。けれどもときおり、ほかの方法を試そうとする人が存在します。わたしは後者に関心を持ちました。何を実践して、彼らは医師の予想を覆す偉業を達成したのか。それを突き止めることがわたしの仕事です。
二つ目に、わたしは本書によって、患者の方々に偽りの希望を与えるつもりは一切ありません。
劇的な寛解をした患者のほとんどが、医師から「ほかの患者には黙っていてほしい」と言われたと告白しています。ひどい話ではありますが、その医師の立場になって考えれば、わからなくもありません。来る日も来る日も、生存の見込みの乏しい患者を診察するのは、想像するだにつらい仕事です。
けれども劇的に寛解する人が現にいるという事実を黙殺するのは、偽りの希望を患者に抱かせるよりも、ずっと罪深いことではないでしょうか。
カリフォルニア大学で、研究方法についての授業の初回に、教授はこう言いました。
仮説から逸脱した事例に遭遇したとき、研究者にはそれを吟味する科学的責務がある。そしてその逸脱事例を吟味してから、研究者がとるべき道は2つ。
一つ目は、なぜ仮説に合わない事例が生じたのかを公に説明すること。二つ目は、その事例を説明できる新しい仮説を考え出すこと。
要するに、仮説に合わない事例は無視してよい、という選択肢は存在しないのです。
がんの克服は人類共通の目標です。現代医療なしで治癒した症例を黙殺することは、科学的に無責任な態度なのです。
次に、「偽りの希望」について検討します。「偽りの希望を人に与える」とは、事実かどうかわからないことや、明らかな虚偽を人に伝えて、希望を抱かせるということです。がんからの劇的な寛解が起きる理由は、いまのところ説明不能ですが、それを体験した人が存在するのは事実です。現代の医学では説明のつかない方法で、彼らは自分のがんを治したのです。
9つの仮説から私たちは何を学べるか
この違いを理解したうえで、わたしたちは、「偽りの希望を抱くことになりそうで怖い」と考えるのではなく、がん治癒の鍵となるかもしれない症例を、科学的に検証していこうではありませんか。
9つの要素は、がんからの劇的寛解が起きた理由についての仮説であり、まだ科学的に十分裏付けされた理論ではありません。この9項目によってがん患者の生存率が上がると断定するには、データの量的分析や無作為な臨床試験が必要で、残念ながらあと何十年もかかるでしょう。
それでもわたしはこの仮説は重要だと考えています。これを読者と共有するのに、あと何十年も待とうとは思いません。それよりも、質的分析を使ったわたしの研究結果を公表し、がんからの劇的寛解を遂げた症例はなぜ黙殺されてきたのか、わたしたちはこの症例から何を学べるのかという、より重要な議論へとつなげていきたいのです。
もしもわたしが、「この9項目を実践したらあなたのがんは確実に治ります」と言ったなら、それは人に偽りの希望を抱かせる行為です。わたしはそうは言いません。わたしに言えるのは、「がんの劇的寛解の起因になったと考えられる9つの仮説を検出しました」ということだけです。
次に、わたしが本書の執筆によって何を期待しているかをお話しします。
まず、研究者たちの手で、がんからの劇的な寛解についてのわたしの仮説が、少しでも早く検証されること。それからがん患者本人、そして大切な人ががんを患ってしまった人々が、治癒を遂げた人々の真実の体験談から勇気を得てほしいと思います。
わたし自身、初めてがんの劇的寛解の症例に出合ったとき、その事実の持つ力に大いに勇気づけられました。医学的常識に反してがんを克服する人が、本当に存在するのですから。
がんの予防や健康全般に関心のある人にも、本書は役立つはずです。そして現在病院で治療中の方々、そして打つ手がなく別の方法を探している患者のみなさんにとって、本書が励みになることを願っています。さらに本書がきっかけとなって劇的な寛解をめぐる議論がはじまり、人々が黙殺をやめてこれらの症例から学ぼうとすることを心から願っています。
症例を見ていて不思議に思うことがあります。なぜ、ある人に効く方法がほかの人には効かないことがあるのか。いまのわたしたちには、その理由はわかりません。けれども説明不能を理由に劇的寛解の現象から目を背けるのではなく、真摯に研究していけば、少なくとも人間の自然治癒力について何らかの知見を得ることができるでしょう。うまくいけば、がん根治の治療法の発見につながるかもしれません。いずれにせよ、黙殺からはどんな知見も得ることはできません。
もしアレクサンダー・フレミングがカビの生えた培養皿を捨ててしまっていたら、社会はいま、どうなっていたでしょう。彼の逸脱事例の研究が時間の無駄ではなかったことは、歴史が証明しています。
あまたの歴史的発見は、逸脱事例の研究からはじまりました。逸脱した事例には、真の希望が宿っている可能性があるのです。
Dr. Kelly A. Turner ケリー・ターナー博士
腫瘍内科学領域の研究者。学士号を取得したハーバード大学時代に統合医療に関心を持ち、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号取得。博士論文研究では奇跡的な回復を遂げた1000件以上の症例報告論文を分析し、1年間かけて世界10カ国へ出かけ、奇跡的な生還を遂げたガン患者と代替治療者を対象に、治癒に至る過程についてのインタビューを行った。本書はそこから得られた知見を患者や家族、そして健やかに生きたいすべての人のためにわかりやすくまとめた著者初の書籍。
[いずれもPRESIDENT online]
Posted by nob : 2015年07月19日 23:54
医療は外傷や急性疾患時の緊急避難手段として、、、慢性疾患には生活習慣の見直しと食養生、自らつくりだした疾患は自ら解消できる。。。Vol.2
■「がんからの生還者」から学ぶ「治る人」の共通点
医師、医学博士 岡本裕氏
がんというのは、特殊な病気です。
ほかの病気と決定的に違う点は、「治し方」が患者さん一人ひとりによって異なることです。もちろん、ガイドラインに沿った標準治療は存在します。しかしそれ以上に「患者さんが心に抱えている問題」にまで踏み込む必要があることが多いのです。平たく言うと、心の持ちようで、治るペースが遅くも早くもなります。
『がんが自然に治る生き方』(ケリー・ターナー著/プレジデント社)には、医学的・科学的には説明のつきにくい劇的な寛解の事例が「逸脱した事例」と総称して、数多く登場しています。
私自身も、本書に挙げられていたような「逸脱した事例」を目にしたことは多々あります。今まで、のべ約4000名のがん患者さんの医療相談に応えてきましたが、体感では年間4〜5例、逸脱した事例に接したと記憶しています。
■「知らない間にがんが消えた」という人も
私が実際に患者さんに接した例は、大きく2つのグループに分けられます。
まずは、ある老人福祉施設に入所中のがん患者さんの場合です。
年齢を重ねている患者さんの場合、おなかにメスを入れるだけで、相当な負担となることがあります。
そのため、手術が可能な範囲であっても、本人やご家族と話し合い、積極的な手術には挑戦せず、あえて見守ることもあります。
「手術に挑まず、経過を見守る」という選択に、ご本人もホッとされる部分もあるのでしょうか。そういう方の中には「なぜかがんが見当たらなくなっていた」、もしくは「進行しないがんと数年間共存して、老衰で亡くなった」ということがよくあります。
もっとも、その老人福祉施設は「食養生」や運動を実践しています。それらの努力が、がん細胞の消滅や、肥大抑止に、功を奏しているのかもしれません。
一方で、この本の「9つの実践項目」に相当するような事柄に留意をせず、切除手術もしていないのに「がんが知らない間に消えた」という人たちにもお目にかかります。これらも「逸脱した事例」です。
私はこれらの「逸脱した事例」には、共通した理由が、必ずと言ってよいほど存在していると感じています。
■3大治療は「時間稼ぎ」にすぎない
私たちは、「e−クリニック」というウェブサイト上で、日々個別の相談を受け付けています。そのため、一度相談に乗ったことのある方が「サバイバー」(がんからの生還者)となり、連絡をくださることも少なくありません。実は、サバイバーの方こそ、がんとうまく付き合うコツを知っています。
私は彼らと接しながら、このような問いかけをよく繰り返しています。
「がんが治る人と治らない人との決定的な違いは?」と。
やはり「考え方を変えた」「食事を変えた」という違いが、よく挙げられます。つまり、「今までのままでは駄目」ということなのです。今までの自分がストレスを増長させ、病気になったわけなのですから、積極的に患者さんが「自分自身」を変える必要があるのです。
まずは食生活を変えることから始め、趣味や旅行、働き方、人とのお付き合いの仕方まで。具体的なことを変えると、「考え方」は大きく変化し、それまでに負荷としてかかっていたストレスを減らすことにもつながるのです。そして、どうしても「時間稼ぎ」が必要な場合には、がんの3大治療(西洋医学)も上手に利用すればよいのです。
そもそも、3大治療とは万能なものではなく、「時間稼ぎ」にすぎないことを理解しておく必要があります。3大治療は、ほとんどが対症治療です。がんには対症治療だけでなく根本治療が不可欠です。
がんの根本治療とは、すなわち自身の自己治癒力を高めて、がんの病勢に打ち勝つこと。そのためには3大治療とは別にどうしても自己治癒力を高める手段が不可欠となります。今までの生き方や過度なストレスが、自己治癒力を低下させ、がんを発生させたのですから、今までの生き方や考え方を変えることが大切です。
私たちは自己治癒力を有意に高めるため、がん患者さんに中医学(気功、中医薬)などの補完代替療法を奨めています。もちろん、3大治療を頭ごなしに否定するわけではありません。上手に活用すれば非常に有用です。
しかしながら、主治医の言いなりに3大治療を受けるのではなく、必ず次に述べる2点をしっかりと押さえて欲しいのです。
1点目は、「やろうとする治療法の目的」「メリットとリスク」「治療の根拠」「代替案の有無」を担当医に訊いておくことです。
また目指すところが「根治」か「微々たる延命治療」か、はたまた「機能回復」「緩和治療」か、「形ばかりのアリバイ治療」かも、確かめておきましょう。
2点目は、「匙加減が可能かどうか」を確認しておくことです。今や欧米では標準治療を基準にしながらも、抗がん剤の投与量を微調整するなど、個人に合った治療を行っています。そのような小まめな配慮をしてくれるかどうかも最初に訊いておきたいところです。
■医師と患者で異なる「治る」の意味合い
そして患者さんは「治る」ということに関して、正しく認識してほしいと思います。
実は「治る」という言葉は、医師サイドと患者サイドで、大きな差があるのです。
多くの患者さんにとって「治る」は「元気で長生きする」ことであるはずです。
しかし、たとえば抗がん剤を手がける医師から見た場合、抗がん剤によってがんが50%以上縮小した期間が最低4週間あれば、「効果あり」と認められます。
極端なことを言えば、患者さんのがんが50%以上小さくなって、抗がん剤治療の4週間後に亡くなったとしても。医師からすると、そのケースは「抗がん剤は効いた」、そして「抗がん剤によってがんが治った」ということになるのです。これは、患者さんにとっての「効く」とは、かなりかけ離れたイメージではないでしょうか。
医療の現場においては、患者さんと医師の認識の間に、このような乖離がしばしばあります。
そして突き詰めて考えると、優秀な医師が最先端の医療を活用しても、「治す」ことができない病も少なからずあります。
私自身、若い頃は脳外科の道を選んで脳外科のスペシャリストを目指しました。ところがどれだけ技を尽くしても、治したい人を思うようには治せないのです。脳外科医だった当時、「医療とは何のためにあるか?」という根本的な問いに自分自身が答えられなくなり、医療の最前線から「降りる」ことにしました。そして、患者さんの患部に限らず、人格をも含めた全体を捉える方向へと考え方をシフトしました。すると、違った風景が見えてきたのです。サバイバーを目の当たりにしたとき、私は彼らから多いに学ぶべきだと気付いたのです。
一般的な医療の現場では、標準治療以外で治った患者さん(「逸脱した事例」)は「例外」とされ、「なぜ治ったのか」という点に関してはまったく関心を持たれなくなります。それは非常にもったいないことです。
本質的なことを言えば、たとえ「例外」でも治ればいいはずです。「例外」というレッテルを貼るのなら、その「例外」の事例を増やせばよいのです。どうしたら「例外」が増えるか、どのようなことで「例外」が増えるか、本書のように共通項を探して、広く一般に広めればよいのです。
「例外」となる確率が上がることには、本書にあったようなヨガや呼吸法、食生活の改善など、さまざまな要素があります。
私たちは、ときにサバイバーを含むがんの患者会の皆さんと共に活動しています。結局のところ、本書にあるような「治っている人がいる」という事実こそ、がん患者さんの直接的な励みとなるからです。
サバイバーが気軽に情報を発信したり、誰もがアクセスできるウェブ上のシステムや、リアルなコミュニティーが各地にできれば、がんに対するイメージも変わってくると思います。
※本稿で紹介している『がんが自然に治る生き方』原作(ケリー・ターナー著)のウェブサイト(http://www.radicalremission.com/)では、劇的な寛解(がんが自然に寛解したり進行しない例)について、誰でも投稿・公開できるようになっています。
----------
岡本裕(おかもと・ゆたか)
医師、医学博士。1957年生まれ、大阪大学医学部、同大学院医学部卒業。麻酔科、ICUの研修を経て脳外科専門医になり、悪性脳腫瘍の治療に取り組む。細胞工学センターでがんの免疫療法、遺伝子治療の研究を行う。その後、現在の医療・医学に疑問を持ち、仲間の医師たちと「21世紀の医療・医学を考える会」を設立。 2001年から、本音で応える医療相談ウェブサイト「e−クリニック」(http://www.e-clinic21.or.jp/)を運営する。
----------
(岡本裕 構成=山守麻衣)
[PRESIDENT online]
■「がんが消える」患者は決してゼロではない
『がんが自然に治る生き方』を医師として読んで(1)
著者=川崎市立井田病院・かわさき総合ケアセンター医師 西 智弘
構成=山守麻衣
「アメリカでベストセラーとなり、日本でも版を重ねている」と聞いたのが、『がんが自然に治る生き方』(ケリー・ターナー著/プレジデント社)を手にとるきっかけでした。医師として、その人気の理由を知りたいと思いました。精読したあと、多くの方と本書の発するメッセージと、本書を読む際の注意点を共有したくて、患者さんや医療関係者を対象とした読書会で取り上げるに至りました。
本書では、著者が調査・取材した「劇的な寛解」の100余りの事例から導き出された9つの共通点が仮説として示されています。世界中に、厳しい余命宣告を受けながらも、そこから劇的な快復を見せ、がんが消えたり長期生存したりする方たちがいるのです。
また、著者が出会った腫瘍内科医たちは皆「がんを劇的に寛解させた患者」を診たことがある、と回答したそうです。
かくいう私も、ここ10年ほどでがんが自然に寛解したり進行しない例については何件も目の当たりにしてきました。
たとえば悪性リンパ腫と宣告され、抗がん剤治療をすすめられていたAさんという男性の患者さんがいます。Aさんは抗がん剤治療を頑なに拒み、途中からぱったりと病院に現れなくなりました。そして「具合が悪くなっては受診し、抗がん剤治療をすすめられると、姿を消す……」ということを繰り返していました。
まるで“いたちごっこ”のような日々の末、ようやく抗がん剤治療に踏み切ろうとしたAさんの患部のCTを撮ったところ、進行しているに違いない……と思っていた病巣が見当たらなくなっていたのです。当時の私は主治医ではなく担当医として関わっていたのですが、「そもそも最初の診断が誤診だったのではないか?」と問うAさんの怒りの表情は、今も瞼に焼き付いています。
※注:きちんと組織検査はしていましたしAさんは数年後、同じところにがんが再燃したため、誤診ではありませんでした。
緩和ケア病棟から退院する人も
また、次のような例もあります。ホスピスに入所してきたBさんという女性の「末期がん」と他院で宣告された患者さんのケースです。
彼女は、余命約3カ月と宣告されていて、緩和ケア病棟に入るために自宅を売り払い、身辺整理を済ませてきました。しかし、入院後に何度検査をしても、がんの影は小さいまま。3カ月で亡くなるどころか1年以上たってもがんは大きくならず、日常生活にも支障はないので、ご自身の人生のためにも退院することをおすすめしたところ「資産も戻る家も処分してしまって帰る場所も無いのに」と、困惑していらっしゃいました。
最終的にBさんは緩和ケア病棟から退院となり介護施設に移りましたが、その後もしばらく、がんは全く進行せず数年間長生きすることができました。
もちろん、これらは一般的なことではなく極めてレアなケースです。しかしこのような自然な寛解だったり「進行しないがん」の可能性がゼロではない、という事実は、もっと知られてもよいと感じます。それに、抗がん剤治療をすることで寛解にいたる例も、固形がんであったとしても決してゼロではありません。
しかも、AさんもBさんも、本書に挙げられている「9つの実践項目」、たとえば「抜本的に食事を変える」などの取り組みを、意識的に実践してはいなかったはずです。
このように、がんとはある意味不思議な病気で、統計的な予測を覆す側面を少なからずはらんでいます。それにもかかわらず、本書では最初に「これは仮説です」と前置きしていながら、読んでいると「明日から実践しましょう」と書かれているところ、そして「これが『がんが自然に治る生き方』です」とタイトルに示しているところが、注意して読むべき本と思った理由です。
「治療の手引き」として読むべきではない
本書に挙げられていた「劇的な寛解」のある事例についても指摘すべき点があります。
ドンナさんという58歳の女性のケースです。
彼女はステージ3の進行性結腸がんと診断され、腸の切除手術を経て、人工肛門を形成するに至ります。そして術後数週間後から、再発を抑えるための抗がん剤治療に挑みます。しかし白血球減少などの副作用で集中治療室に入院することになってしまった彼女は医師から、今後の抗がん剤治療の中断と帰宅をすすめられることになります。
そこでドンナさんが選択したのは、カナダの「クーガーマウンテンセラピー・センター」で行われる、鍼とハーブによる集中治療のプログラムです。それは「抗がん剤を身体から出しきったほうがよい」という瞑想サークルの友人の助言によるものでした。
プログラムの期間中、ドンナさんは健康的な野菜と魚の料理を楽しみ、磁器パルサー発生装置による治療を受け、さらには参加者との交流で過去の感情を発散させていたそうです。
当初は、「歩くのもままならない」という状態で到着した彼女でしたが、10日間のプログラムが終了したときには何キロも歩けるようになっていたといいます。
それから彼女は通常の生活に戻り、愛する孫の成長を見守り、肉や小麦、砂糖、乳製品を控えた食事療法、ビタミン剤の摂取や瞑想を続けます。そして退院から2年目、人工肛門を外せるまでに快復を遂げます。さらにそれから6年以上経っても、ドンナさんは小康状態を保ち、孫の子守りやボランティア活動に励んでいるのだそうです。
この描写から、「クーガーマウンテンセラピー・センターのプログラムに参加した結果、元気になった」というメッセージを一般的には読み取るかもしれません。しかし、こういったケースを「劇的な寛解」と取り上げていることも、本書を注意して読んだ方がいい理由のひとつです。
もちろん、このプログラムがドンナさんのメンタル面を強化してくれたということはあるかもしれません。しかし厳密に言えば、彼女がこのプログラムに参加をしていなくても、快方へと向かっていた可能性は高いのです。
なぜなら一般的に、抗がん剤治療の副作用で体調が悪かったのであれば、それを中止するだけでも、体調の快復が得られることは珍しくはないからです。そして、ステージ3で手術をしたのであれば、その後抗がん剤をしなくても再発しない、という可能性も少なくはなく、つまりはこのプログラムで治った、というよりはがんの手術でがんが治った、という可能性の方が高いのです。
この9つの実践で万人が治るわけではない「仮説」である以上、この本をそういった「治療の手引き」としてとらえるならそれはやはり注意した方がよいと言わざるを得ません。でも、その点に注意したうえで、前向きに生きるためのヒント、がんを持ちながら生きるためのヒントを得るための本としては、読む価値があるかもしれません。
我々医療者は、科学者として伝えるべきことはきちんと伝えるべきだし、危険な治療法や詐欺に患者さんが向かおうとしているのなら、それは止めるべきと思っています。しかし一方で、患者さん達がいかに前向きに人生を生ききることができるかを常に考え続けないとならないとも思っています。この本を読んだことをきっかけに、患者さんが前向きな希望を持てた、というのであれば、この本はひとつの役割を果たしたと言えると思いますし、その「希望」自体を私が否定するものではありません。それならば私は、人間としてその希望を支えつつ、医学の科学者としてアドバイスをしつつ、患者さんの生きる道に寄り添って行きたいと思います。
西 智弘(にし・ともひろ)
川崎市立井田病院・かわさき総合ケアセンター医師。2005年、北海道大学医学部卒。家庭医療を志した後、緩和ケアに魅了され、緩和ケア・腫瘍内科医として研修を受ける。2012年から現職。緩和ケアチームの業務を中心として、腫瘍内科、在宅医療にも関わる。日本内科学会認定内科医、がん治療認定医、がん薬物療法専門医。http://tonishi0610.blogspot.jp/
[PRESIDENT online]
Posted by nob : 2015年07月19日 23:15
まずは食生活改善と適度な運動から、、、ドローイン、私もお勧めします。さらに捻りを加えれば完璧です。。。
■産後のお腹のたるみを解消!家事をしながらキュッと引き締める方法
大野えりか
コスメ薬事法管理者/美容ライター
引き締まったウエストと腰にかけて美しい曲線を描くくびれは女性らしさの象徴といっても過言ではありません。しかし、産後を期に体型が崩れてしまってからというもの「ぽっこりお腹」に悩まされている女性は多いのではないでしょうか。かくいう私も、産後のぽっこりお腹に悩まされた一人です。
そこで今回は女性らしい曲線美を叶えるべく、家事や買い物の最中でもできるお腹の引き締めテク「ドローイン」を紹介いたします。
「ドローイン」ってご存知ですか?
ドローインはお腹をへこませた状態で行う腹式呼吸のことで、へこませた状態を数十秒間キープすることでインナーマッスルを鍛え、お腹がへこむ癖をつけることができることで知られています。また、呼吸の仕方に工夫を加えるだけなので、時間や場所も選ばず気軽に始めることができるのも魅力のひとつ。
「ドローイン」の効果
息を吸ってお腹をへこませるとお腹の一番深層にある腹横筋を鍛えることができます。この腹横筋は「ウエスト」をつくる筋肉のため、ドローインを行うことでお腹まわりのサイズダウンが期待できるのです。
また、腹横筋が鍛えられてくるとカラダの軸となる「体幹」も自然と安定し、背中や腰の痛みを改善できるほか、基礎代謝が上がり1日の消費カロリーもアップすると言われています。
「ドローイン」の呼吸法
ドローインには様々な呼吸法がありますが、ここでは基本をベースに、私が実際に行い効果のあった方法を紹介いたします。
1:姿勢を正し、胸を張る。そして、お腹をへこませた状態でゆっくり、たくさんの息を吸い込む
2:息を吐きながらさらにお腹をへこませる。このとき、お腹を背中側に引き寄せるようなイメージで
3:息を吐ききりお腹もへこませきったら、お腹の状態をキープしたままゆっくりと息を吸う
4:息を吐きながらさらにお腹をへこませる。息を吐くときはおへそから5〜8センチほど下を意識する
5:お腹をへこませた状態をキープしながら10〜20秒ほど軽く呼吸を続ける。慣れてきたら30秒、40秒とへこませる時間を徐々に伸ばしていく
これをお皿を洗っている時、テレビを見ている時、街中を歩いている時など、ふと思い出した時に行います。
また、基本とされるドローインには3と4の動きはないのですが、さらに引き締めを強めたいときに行うとお腹がプルプル震える感覚があり、腹横筋の強化を実感することができますよ。
「ドローイン」の注意点とコツ
いつでもどこでもできると紹介したドローインですが、食後のお腹がいっぱいの状態ではへこませにくく、苦しさを感じてしまうため避けた方がよいでしょう。
また、ドローインを行うとどうしても呼吸が深くなってしまうため、電車の中など人が多いところでは人目が気になり恥ずかしさを感じることもあるでしょう。その場合はドローインではなく、「ただお腹をぐっとへこませる」だけでもお腹に意識を向けることが習慣化できるためオススメです。
女性は「ながら作業」が得意といわれていますから、慣れてきたら意識せずとも続けることができるはず。みなさんも、ドローインで引き締まったウエストとくびれを手に入れてみませんか?
[暮らしニスタ]
Posted by nob : 2015年07月01日 18:49
私も、出先で白米を出されない限りは、もうすっかり玄米と雑穀米を食べ分けています。。。
■若返り、デトックス、顔やせ……最も効果が高いのはどれ? 白米VS玄米・雑穀米
柴田真希
管理栄養士・雑穀料理家
日本人にとって毎日の食生活で欠かせないのが、お米。一口にお米といっても、白米・玄米・雑穀米など、様々な種類があります。でも、どうせ毎日食べるなら、身体にも美肌にも良いものを選びたいですよね!
そこで、「白米VS玄米・雑穀米」をテーマに、美肌に良い食べ方をご紹介します。今回は、管理栄養士で雑穀料理家の柴田真希さんにお話を伺いました。
■白米は逆から書くと「米白」→「粕」
一般的に、最も多くの方が食べているのが白米ではないでしょうか? でも実は、白米は文字通り「粕」の状態。玄米に含まれている豊富な栄養素(ビタミンB群やEなど)が取り除かれてしまっているのです。
もちろん、エネルギー源である炭水化物は含まれていますが、食べやすさを追求した結果、身体にとってはとても勿体ない状態になってしまっているのが白米なのです。
■玄米のメリット・デメリットとは?
そうなると、「栄養価が失われていない玄米を選べばいい!」と考えがちですが、玄米には加工されていないが故のデメリットもあるそう。
「玄米は栄養価は高い一方、白米に比べて調理時間が長いのが難点。また、よく噛まないと栄養価が吸収できないため、お子さん・お年寄り・胃腸の弱い方にとっては食べにくい上に栄養が摂取できていないことも考えられます」。
そんな不便さを伴うことから、玄米を摂り続けることに抵抗感を示す人も少なくありません。
しかし、玄米も栄養価が優れていますので、しっかり浸水した後に十分に炊きあげて、よく噛んで食べて玄米の栄養をきちんと消化・吸収するようにしましょう。白米にも玄米にも、良いところと悪いところがあるのですね。そこで、良いとこどりなのが「雑穀」というわけです。
■白米に雑穀をプラスして栄養価アップ!
雑穀は特別な品種のお米というわけではなく、白米の一部です。そのため、雑穀を加えてもカロリーは変わらず、ビタミン・ミネラル・食物繊維などの栄養価がグンとアップするのが特徴!
また、通常通りご飯に混ぜて炊くだけなので余分な手間もありません。さらに、どんな食事にも合わせられ、毎日・毎食取り入れることが可能なので、続けやすく・効果を感じやすいのが魅力です。
■旬の野菜との組み合わせて「美肌ビタミン」を網羅
「美肌ビタミン」と呼ばれている、ビタミンA・C・E。しかし、これらをバランスよく摂るのは意外と難しいもの。雑穀(穀類全般)にはビタミンA・Cは含まれていませんが、逆に野菜類に少ない、代謝アップのビタミンB群や、「若返りビタミン」と呼ばれるビタミンが雑穀には豊富に含まれています。
ビタミンAやビタミンCを豊富に含んだ、旬の野菜や緑黄色野菜を雑穀と合わせて摂れば、美容に良いビタミン類をくまなく摂ることが可能に。野菜だけ・お米だけといった偏った食事では成し得ない、美肌効果をもたらしてくれるのです。
■雑穀で全身デトックス!
雑穀の嬉しい効果はそれだけではありません。ほかにもカルシウムや鉄分などのミネラルが豊富なことから、ストレス軽減、貧血防止などにも役立ちます。また、食物繊維も豊富なので、多くの女性が悩んでいる便秘解消に繋がるというメリットも。
どんなに高価な美容サプリを摂っても、余分なものを出さなければ美肌にはなれません! そんなデトックス効果も担ってくれるのが、雑穀なのです。
■雑穀の色には栄養の秘密がいっぱい!
雑穀には黒米・赤米・あわ・きび・はと麦など、たくさんの種類があります。色とりどりの美しさも雑穀の魅力ですが、これらは単に見て楽しむだけでなく、それぞれに栄養素を含んでいるもの。サプリメントのように、その時々によって摂りたい成分で選んでみるのも良いかもしれません。
□色の保つ成分「フィトケミカル」
・黒米の紫色……瞳の健康維持に効果的なアントシアニン
・赤米のピンク色……ビタミンEの5倍の抗酸化力! プロアントシアニジン
・あわやきびに含まれる黄色……エイジングケアに有効なポリフェノール
■雑穀で顔やせも!?
雑穀ごはんをたべていると、白米に比べて自然と良く噛むようになります。そのため、満腹中枢を刺激するためダイエットにも効果的。噛む回数が増えるとあごのシェイプアップにも繋がります。
ちなみに柴田さんによれば、パン食、麺食はよく噛むことが難しいので、アゴ周りに締まりがない人が多いのだそう。思い当たることがあった方は、雑穀ごはんに挑戦してみてください。
このように、毎日食べている白米に雑穀をプラスして炊くだけで、美肌のために良いことがたくさん! また、雑穀ごはんを並べるだけで、食卓の彩りもよくなり、楽しい食卓になること間違いなしです。
白米派だった皆さんも是非今晩から、美容と健康のためにも「雑穀食ライフ」を始めてみてはいかがでしょうか?
[AllAbout]
Posted by nob : 2015年06月27日 10:56
何者でもない、何者にもなりうる自らを全面的に肯定する絶対的価値基準が、他者による客体的価値基準という根源的要因を霧散させる。。。
■当てはまる人は要注意! 「働き過ぎ」のサイン5つ
MakeUseOf:ワーカホリックは深刻な問題です。心疾患や偏頭痛などの症状のほか、どちらかがワーカホリックの夫婦は、その半数以上が離婚に至っているというデータがあります(ワーカホリックの夫婦の離婚率は、そうでない夫婦の3倍)。あなたも同じ運命をたどりたいですか?
米国人の平均就労時間は、1970年代以降増え続けています。仕事を終えるために長く働かざるをえないだけでなく、キャリアのトーテムポールを登りつめるには、他を犠牲にしてでも働く必要がある時代なのです。
仕事中毒の根幹にあるのは、仕事への没頭です。では、ワーカホリックとハードワーカーの違いは何でしょう。ワーカホリックは、スキー場にいても仕事を夢見ている人で、ハードワーカーは、仕事をしながらスキーに行くことを夢見ている人です。
WebMDより
実は、これを書いている筆者は、ワーカホリックです。では、読んでいるあなたはどうでしょう? 以下の5つのサインが1つでも当てはまったら、ワーカホリックかもしれません。私が克服した方法も書いておきますので、当てはまる人は参考にしてください。
非生産性の恐怖
問題点
ふつうの労働者は、できれば仕事から逃げたいと思っているものです。帰宅と同時にテレビにかじりつき、ぼーっとしながら心と体を休めたり、友人と街を歩いて時間を忘れたり。買い物に行くのに、「時間をムダにしている」なんて思うことはありません。
ワーカホリックの場合、そのようなことはほとんどありません。仕事以外に費やす時間はすべて、「非生産的」だと感じてしまうのです。
リラックスしようとすると、病気になってしまう人がいます。2002年にオランダで行われた調査によると、人口の約3%が、この「休暇病」になるそうです。休暇病になると、疲労、筋肉痛、吐き気、それからインフルエンザのような症状が現れます。
また、偏頭痛の3分の1、緊張性の6分の1が、「週末頭痛」だと言われています。
The Wall Street Journalより
仕事をしなかった時間を、仕事に充てることができたかもしれない。ワーカホリックは、その感覚を恐れます。非生産性の恐怖が頭をもたげ、仕事をしていないと不安になってしまうのです。休暇のような楽しいはずの時間でさえ、非生産的でムダな時間だと思えてきます。
解決策
非生産性の恐怖は、どこに行っても何をしていても付きまといます。そこでたとえば、毎日3時間、仕事をしない時間を作るという方法があります。しかし、それだけでは不安が募るばかりでしょう。
そんなときは、マインドフルネスがオススメです。これは、「今この瞬間」に意識を集中させる、瞑想のようなテクニック。「忍耐強さ」「信頼」「頑張らない」のほか、全部で7つの要素があります。
とはいえ、自由な時間を確保して、意識的に仕事から離れることが重要です。「生産性がすべてではない」と受け入れるためには、非生産的な状態に慣れる必要があるのです。
「故意の非生産性」を実践するには、オンラインのリラクゼーションツールや、休憩向けのウェブサイトがオススメです。それに少しのヨガを組み合わせれば、不安は消えずとも、ある程度は解消されるでしょう。
でも、何よりも大切なのが、「自分はリラックスする権利がある」と自分に言い聞かせ、信じること。成功する起業家は、それを知っています。目標を達成したければ、100%の力で休みなく動き続けることはできません。休みがなければ、いつか壊れてしまうのは目に見えているのです。
テクノロジー中毒
家族や友人と一緒にディナーを食べたのはいつですか? レストランでも自宅でもいいので、食卓を囲み、積極的な会話を交わした時間のことです。ほとんどの人は問題ないと思いますが、きっと数人は、iPhoneを見ながら食べたという人がいるはず。
自分でそれに気づいていますか? そうでなければ、あなたはスマホ中毒かもしれません。そのスマホは、あなたの人生をむしばんでいるのです。
ワーカホリックは、テクノロジー中毒に陥りやすいことで有名です。常にメールをチェックしないと気が済まない癖は、プッシュ通知やアクセスの容易化により、このところ増加傾向にあります。テクノロジーのおかげで、上司や同僚、クライアントとのメッセージのやり取りに追われている人がたくさんいるのです。
でも、このような方法での生産性の追求は、健全とはいえません。いえ、生産性を目指すことそのものは健全なのですが、余すことなく生産性を絞り出そうとするのは不健全だと言いたいのです。
解決策
あらゆる中毒に共通することですが、まずは自分が中毒でだと気づくことが必要です。以下の質問が当てはまるなら、スマホ中毒の可能性があるので要注意。
起きてから1時間以内にスマホをチェックしますか?寝る前の1時間以内にスマホをチェックしますか?メールが来た瞬間にチェックする必要はありますか?人と面と向かって話しているときに、スマホを使うことはありますか?1週間スマホを手放せと言われたら、手放すことができると思いますか?
中毒であることがわかったなら、次はスマホの奴隷状態から抜け出しましょう。そのためには、ちょっとした我慢と、家族や友人のサポートが必要です。それさえあれば、すぐに依存症を退治できるはずですから。
テクノロジー中毒のもうひとつの症状が、最新ガジェットがほしくてたまらなくってしまうこと。そんなあなたは、アーリーアダプターだと言えるでしょう。趣味であればいいのですが、そうでない場合、アーリーアダプションは生産性への没頭を意味します。
生産性を目指しすぎると、限度がありません。終わりのない追求を続けているうちに、燃え尽きてしまうのです。制御不能になる前に、生産性への没頭から抜け出しましょう。
新しいプロジェクトを追いかける
問題点
非生産性の恐怖は、さまざまな形で現れます。その中でもいちばんわかりやすいのが、いつでも心の中で計画やリサーチをしていること。フリーランサーであり起業家である私は、常に新しいプロジェクトを求めている状態です。
私がもっとも仕事中毒だったころ、MakeUseOfでの責任と小説執筆、ビデオゲームのコーディング、デジカメアートの勉強を、毎日やりくりしていました。しかも、それだけでは事足りず、もっとたくさんのプロジェクトをやりたくて、アイデアを追い求めていました。
正直に言うと、それらのプロジェクトはすべて、失敗に終わりました(MakeUseOfでのポジションは残りましたが)。時間が足りないばかりか、睡眠不足で効率どころではなかったのです。
でも、こんな事例は世の中にあふれています。ワーカホリックは世界中のあちこちに存在しており、多くの人が、自分の限界を超える仕事を請け負っているにもかかわらず、さらなる仕事を探しています。
解決策
人生を整理することです。これ、言うのは簡単ですが、なかなか実行は難しいものです。
多くの研究で明らかになっているように、効率と生産性の面で、マルチタスクは有害です。注意力が散漫になり、すべてが中途半端になるだけ。また、ストレス、罪悪感、不安のもとにもなります。あなたの脳は、それほどの処理能力を持っていません。
あわただしさの最大の罪は、時間を奪うこと。その時間は返ってきませんし、ダメージは永遠に続くこともあります。
ワーカホリックのエネルギーをもっとうまく使うには、ミニマリズムを身につけましょう。時間とお金の節約になるだけでなく、ストレス解消にもなるはずです。
健康や衛生を無視してしまう
問題点
いろいろなことが面倒になり、健康をおろそかにしてしまうことがあります。運動をせず、食べもせず、眠りもしない人もいます。毎朝カフェインに頼らなければ目を醒ませない人も多いでしょう。
とにかく、座っているのは健康によくありません。さまざまな疾病のもとになるだけでなく、姿勢が悪くなり、コンピューター病も引き起こします。
食生活も重要です。ワーカホリックの多くが、仕事を中断しないために、デスクでランチを食べています。時間も短く、たいてい20分以内に食べ終えます。それどころか、米国人労働者の29%は昼食抜きであるという調査結果も出ています。
さらに、仕事に心を奪われるあまり、不眠症になることもあるのです。
解決策
健康のための時間を、毎日少しは確保しましょう。ハードワークのせいで早死にしてしまったら、たとえその先に成功が待っていたとしても、そこまで到達できませんよ。
何よりも、料理を学びましょう。最初は手間取るかもしれませんが、コツを身につければ、ヘルシーな食事を手早く作れるようになるはずです。ディナーを多めに作って、残りをお弁当にするのがオススメです。
職場では、ランチを抜かないこと。食べる時間を確保しましょう。昼休み中は、仕事のことを考えないように。
睡眠は、毎日決まった時間に取るようにしましょう。それは思ったよりも簡単です。Windows、Linux、iOSの場合は「F.lux」を、 Androidの場合は「Twilight」をインストールして、睡眠を妨げるスクリーンライトを減らします。ホワイトノイズアプリも便利です。毎朝のリフレッシュのための習慣も、最大限に活用しましょう。
最後に、運動は絶対に必要です。最初はシンプルでかまいません。デスクでのエクササイズや簡単な筋トレから始めましょう。調子がよくなってきたら、YouTubeの筋トレチャンネルを見るのもいいでしょう。
仕事に満足できない
問題点
ワーカホリックが仕事をし過ぎてしまうのは、自分の成果に満足できないから。完ぺきの追求にこだわってしまうのです。それ自体は褒められるべきことかもしれませんが、それが人生に悪影響を及ぼし始めたら、褒められることではなくなります。
私がまさにこの状態です。どんなものを生み出しても、たとえそれが1回目の挑戦でも1000回目の挑戦でも、満足できません。そのせいで、いつか誇れるものを生み出すために、日々努力、練習、仕事を続けてしまいます。
もちろん、高い基準を自分に課しながら、ワーカホリックにならないことも可能です。そこに到達するにはどうしたらいいでしょう? その高い水準を保つために学ぶのか、挑戦をやめてしまうのか。前者の方が望ましいでしょう。
解決策
具体的な目標を立てることから始めましょう。長期的に達成したいことは何ですか? そこにたどり着くために、短期的にはどのようなステップを踏めばいいのでしょう? 毎晩、翌日すべきことを考えましょう。その日のタスクを終了したら、それ以上手を出さないこと。目標を達成したのだから、あとは休むことを考えてください。
そのためには、Todoistなどのようなシンプルなタスクアプリや、Googleタスクのようなタスクマネジャーを使うといいでしょう。
ここで大事なのが、結果ではなく、努力に注目すること。結果は質的です。うまく行くこともあれば、行かない日もあるでしょう。一方、努力はやったかやらないかのどちらかです。「やった」と言えるのであれば、それを祝福しましょう。
当然、質の高い結果を出す努力は続けるべきですが、両者の間の微妙な違いは、どこにプライドをかけるかです。インプット(努力)か、アウトプット(結果)か。
診断やいかに?
どうでしたか? あなたはワーカホリックだったでしょうか? 上記の解決策がうまく行かない場合、もっとちゃんとしたセラピーを受けた方がよさそうです。長期的な健康を望むのであれば、仕事中毒とは別れを告げるべきなのです。
たとえ完全なワーカホリックじゃなくとも、モチベーションの焦げ付きや、生産性が原因のストレスにさいなまれることはあるはずです。それらが大きくなる前に、芽のうちに摘んでしまいましょう。
5 Signs That You're Working Too Hard (And How to Fix Them) | makeuseof
Joel Lee(訳:堀込泰三)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2015年06月13日 16:01
不健康な制汗対策はもう止め、吸湿即乾下着はもちろん、頭部バンダナや帽子、首にはスカーフなど、発汗前提の迎える対策に切り替え、今日も元気に汗をかいています。。。
■【あなたはどっち?】質のよい汗・悪い汗の違いを知ろう!
まだ6月なのに蒸し暑い日が続いています。暑い日に汗をかくのは仕方がないことですが、同じ汗でも“質”があるって知っていますか?
汗っかきの人ほど汗の質がいい
私たちの汗は、実は血液から作られています。体が“暑い”と感じると、体温を下げるために、血液中の水分とミネラルが汗腺へと運ばれ、汗腺から水分が吹き出ます。この吹き出た水分が、いわゆる「汗」です。このとき大切なミネラルを血液に戻し、水分だけが表面に出るのが理想的です。
汗の質が悪いと汗ジミや体臭の原因になることも…
質のいい汗は、たっぷりの水分とちょっぴりの塩分でできているので感触はサラサラ。ところが汗腺の働きが低下していると、本来血液に戻るはずのミネラルが汗と一緒に外に出てしまい、いわゆる質の悪い汗となります。そのため、質の悪い汗は、濃厚でベタッとしているのが特徴です。
なかなか落ちない汗ジミができる、鉄っぽい体臭がする、サウナに入ってもなかなか汗が出ない、暑い日でも少ししか汗をかかない…という人は、汗の質が悪いのかもしれません。
1日1回はしっかり汗をかく習慣をつけよう!
いい汗をかくには、“汗腺”の働きを活性化することが大切。汗をかけばかくほど汗腺は活性化し、質のよい汗をかくことができます。夏は冷房の利いた部屋で過ごしがちですが、スポーツや半身浴などで1日1回は汗をドッとかいて、汗の質をあげましょう!(TEXT:中島祐美)
[クックパッドニュース]
Posted by nob : 2015年06月13日 15:41
以前は終日何杯となく、今は朝夕1日2回に、さらにこれまでの半量の豆で淹れることで1回カップ1杯に、、、満足度は落とさずに快調です。。。
■カフェイン断捨離のすすめ
目を覚ますためについつい、起き掛けにコーヒーを飲んだりしませんか?最新の研究で、朝9時前にコーヒーを飲むとカフェイン耐性ができることがわかりました。コーヒーを美味しく飲んで、上手く日常生活に取り入れるにはどうすれば良いでしょうか。
◆コーヒーでリラックス…と思いきやストレス増!!
朝8時から9時は、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールの分泌量がピークになります。このピーク時にコーヒーを摂取すると、コルチゾールの分泌量が50%も増加し、カフェイン耐性を作りやすくしまうことが、最新の研究でわかりました。(脳神経科学博士課程Steven Miller氏より)
目覚まし代わりに朝コーヒーを飲む人は多いと思いますが、カフェイン耐性ができてしまっては、意味がなくなってしまいます。なおかつ、ストレスホルモンまで増えてしまうとは、リラックス効果があったと思っていたのに、体内では真逆の現象が起きていました。
また、午後には仕事に気合を入れるために、ランチの後にコーヒーを毎日飲んでいるビジネスマンも多いのではないでしょうか。
◆カフェインを断捨離して効果を最大活用
コーヒーに含まれるカフェインの量は、カップ1杯でおおよそ、インスタントで50〜60mg、ドリップで140〜160mg含まれているそうです。成人の1日のカフェイン摂取量は200〜300mgが理想です。
しかし、カフェイン効果が体内から消滅するまでに8〜12時間、完全に体内からカフェインが消滅するには数日かかります。
これでは毎日コーヒーを飲んでいたら、カフェインの効果が感じられなくなってしまいます。
カフェインの効果を有効的に活用するには、まずは週末だけでもカフェイン断ちをしてみると良いかもしれません。
◆コーヒーなしで目覚められるカラダに
朝は気持ちよく爽やかに起きるのが理想ですが、忙しいビジネスマンや主婦に平日の朝からそんな悠長なことはなかなかできません。爽やかな朝を迎えたい時間帯にストレスホルモンのコルチゾールの分泌量が多いのは、なぜでしょうか。
生物は寝ている間も心臓を動かしたり、細胞内の活性を維持するために血液中にブドウ糖が必要です。コルチゾールは、寝ていて食事からエネルギーが摂取できない間も、血糖値を維持する役割を果たしているのです。
朝3時頃からコルチゾールが分泌しはじめ、体温が徐々に上昇して目が覚めます。そしてコルチゾールの分泌量がピークになるのが、朝8時から9時なのです。つまりカラダは、自然と目覚めるような仕組みになっているのです。
寝る前にカフェインが体内に残っていると、自律神経が高ぶってなかなか寝付けなくなり、コルチゾールの分泌する時間もずれてきます。
コルチゾールは食事によっても分泌量が変動します。朝8時〜9時以外にも食前後1時間は同様に、コーヒーを飲むとコルチゾールの分泌量が50%増える可能性があります。
カフェイン摂取量と摂取時間を上手く調整して、カフェインの効果を上手く享受してみませんか。
参考
https://www.jstage.jst.go.jp/article/shokueishi1960/30/3/30_3_254/_pdf
監修:山本 ともよ(管理栄養士)
[Mocosuku Woman]
Posted by nob : 2015年06月13日 15:22
また旅立つ君へVol.98/人は自分自身に還るために旅に出る。。。
■シンプルな人生を送る為に、捨てるべき「7つの習慣」
shingoogawa
人生をシンプルに過ごすって
どういうことだろう?
一口にシンプルな生活、ミニマルな生活と言ってもいろんな捉える方がある。でも減らすことの利点に関して確実に言えるのは、「余裕」ができるということだ。街も、部屋も、生活も、スペースには限界がある。
身の回りをシンプルにして、空白のある人生を感じること。物やイベントや小道具やアクセサリー。そして周りにいる人々に深入りし過ぎないでいることができると、ずっとキモチは軽くなる。
シンプルでいることは、自分の周りにある小さな存在をきちんと味わいながら楽しみ、今起こっていることに積極的に自分から関わっていける余裕と機会をあたえてくれる。
1
やりたくないこと
自分が楽しいと思うことをするのはいいことだよね?でもやりたいことをやれと言われると、ちょっと面倒くさくなる。そんなときに簡単にできることは、「やりたくないことをやらない」というコト。無理矢理頑張る必要なんてない。「いいえ」の一言が大事なのだ。
人生に起こる最高のことは
いつも予想していなかったときに起きる
期待していなかったからこそ、最高なのだ
エリ・カマロフ
義務や約束を減らして、最高の出来事が起きた時に反応できる余裕を持っておこう。
2
期待しすぎること
自分が持ってるものによく注意して目を向けてみると、十分だってことに気づく。持っていないものばかりに集中してしまったら、ただただ自分を惨めな気分にしてしまうだけだ。目の前にあるものを噛み締めよう。
3
余分なモノを持つこと
空間とは、ものをひとつにまとめられる場所だし、ものをおいておけるところだ。空間がないといろんなものがそれぞれの上に重なり合ってしまう。自分の環境から取り除けるものを少し取り除いて、人生にも少しスペースをつくろう。きっと、そうしてよかったと後で思うはず。
4
答えのでない悩みごと
悩むことと、考えることは違う。時間が経っても答えがでずに、行き詰まってしまう悩みごとに追われると、目の前のことに集中できる様になる。どんな結果が出るのかは、結果が出るまで分からない。わからないことを悩んでも意味がないし、わかっていることを悩んでも意味がない。目の前のことに本気になれれば、もっともっと好奇心旺盛で想像力豊かな人生になる。
人生は偶発的、突発的な変化の連続だ
抵抗するな
抵抗は悲しみしか生まない
現実は現実のままにしておきなさい
そしてそれがどんな道であれ
物事が自然に前へと流れるようにしなさい
荘子
5
綿密過ぎる計画
考えた通りに物事が運ぶ計画なんてない。自分の願い通りにいくことは絶対にない(本当だ。何度も何度も何度も試した経験から言っている)。未来はだれにも予測できない。計画を減らせば、もしなにかが実際に自分の思い通りに行ったとき、それが大きな喜びになるし、まるでプレゼントみたいに感じることができる。
上手な旅人はなんの計画もせず
どこに辿りつこうとも思っていない
荘子
6
嘘の常習犯
嘘をつくと、いつまでも真実を胸に秘めて置かなければならなくなる。本当のことを話せばそんな余計な悩みがなくなる。ずっと覚えておかなきゃいけないことが減るだけでなく、自分が本当に思うことをはなすことで、自分のありのままの姿を受け入れられるようになる。難しいのは、嘘が言葉だけではないというところ。
嘘をつくことの本質は
その言葉ではなく感覚にある
ジョン・ラスキン
7
受け売りの自分
「ありのままでいよう」と聞くと、大抵の人は自分のことをアイデンティティや、個人が信じている自分像を思い浮かべる。でも大抵の場合、私たちは自分を間違って認識していて、それを自分のアイデンティティと混ぜ合わせている。がんばって「なろう」としているのだ。
でも、いつかは「そうである」ということに気づく。なにかになる必要はなくて、そこにいるだけで十分だ。本当のあなたらしさは、あなたじゃないものになろうとしていない時、なんの努力の必要もなしに際立ってくるものだ。
所有することで、反対に所有されてしまう。シンプルになるというアイデアに自分が慣れてくれば慣れてくるほど、ありとあらゆる物事に対する無駄な執着心が無くなっていく。
私たちの幸せは、一定の結果や状況、所有物や物事に頼らなくても、そこにあるものだ。何かに左右されるのではなく、何もないことに満足できてこそ、幸せを実感することが出来る。
やらなきゃいけないことばかり追い求めがちだけど、その分やらなくて良いことも見つけなければ、どんなスペースもパンクしてしまうのだから・・・
[TABILABO]
Posted by nob : 2015年06月05日 17:05
また旅立つ君へVol.97/今ここに貴方が、そして私もいる、これこそがすべて、、、明日そこに貴方が、そして私も、それが未来。。。
■明日できることは、今日やらないほうがいい理由
「過去はもう仕方がないけれど、せめて未来はなんとかしなくちゃ。」そんな努力はポジティブにも思えるけれど、未来の計画に振り回されて、ちょっと疲れてしまうこともあります。
未来がまだない今を遊ぶ
『荘子』のなかには「不測に立ちて無有に遊ぶ」という言葉がでてきます。それを踏まえ、僧侶にして芥川賞作家である玄侑宗久さんはこういいます。
「無有に遊ぶ」に込められた意味は、未来はここにはないのだから、「ないという今を遊ぶ」ということです。
(「『荘子』2015年5月 (100分 de 名著)」P51より引用)
いくら頭のなかで計画をたてても、それは所詮頭の中での話。未来は今ではないのに、そのことに頭を悩ませていても意味がないということでしょうか。
とくに悪い方へ考えてしまって、今は最悪のケースでもないのに未来の想像だけで胃を痛めるようなことのないようにしたいですね。
明日できることは今日やらない
また玄侑さんはつづけてこんなことも書かれています。
多くの人は、今日やるべきことが終わると、明日やるということをつい引き寄せてしまいます。「明日できることは今日やらない」という強い信念がないと、人間は休めない。
(「『荘子』2015年5月 (100分 de 名著)」P51より引用)
たしかに不思議とひとつのことが終わればまた、明日でもいいはずの次やることが目に入ってくるものです。でも、やるべきことに集中するためには、しっかり休む時間も必要。
次のやるべきことが目に入った瞬間に「はぁっ」とため息がでてしまったときは、「明日できることは今日やらない」という言葉を思い出し、「荘子に書かれているんだから」と言い聞かせながら、しっかり休みたいと思います。
[MY LOHAS]
Posted by nob : 2015年06月05日 16:49
また旅立つ君へVol.96/まずは自分自身による完全な束縛が初めの一歩、、、そしていずれその自分自身という呪縛から解き放たれる時こそが。。。
■「人生は耐えるものでなく、楽しむもの」。幸せのために、いますぐ捨てるべき「15の習慣」
鴨下ゆかり
「人生は耐えるものではない、楽しむためのものだ」
――Gordon B. Hinckley
30,000日(82歳まで生きたと仮定して)の人生を幸せなものにするか、ただツライものにするかはあなた次第だ。でもそのためには、どうしたら良いのか?
ここでは、marcandangelの記事を参考に、TABI LABOの視点を交えつつ「幸せで成功している人が捨てている、15のコト」を紹介していこう。輝いてみえるあの人は、こんな考えや習慣を捨てているだけかもしれない。
01.
自分以外はどうでもいい
無関心
無知よりも怖いのは、無関心かもしれない。夢を持つこともない、人に優しくできない、世界の問題に目を向けることもない。そんな人間が増えてしまったらこの地球はどうなってしまうだろう。無関心を捨てることで、人生はより楽しく興味深いものとなる。いろいろなことに関心を持ちわくわくすることが、私たちを前に進めてくれる原動力になるのだ。
02.
1日2時間!?
SNSにしばられる時間
SNSを1日に10回以上眺めたり、投稿したりしている場合、軽く1日1~2時間は費やしていることになるだろう。その少しの時間でも運動や勉強、趣味に当てられたらどんなに毎日が豊かになるか。
世界の成功者はいち早くSNSの危険性に気づき、使用時間を決めたり、週末デジタルデトックスを行うなどの対処を始めているようだ。
03.
自分の意志がない
人の意見に左右されること
人の意見を聞くのは大切なこと。しかしそれですべてを決めてはいけない。あなたはあなたの直感にしたがうことで初めて、 真の成功を掴むことができるのだから。
04.
今すぐ結果が欲しい!
焦る気持ち
高い山を登るには、頂上が見えなくても都度小さなゴールを目指しながら進むしかない。人生はそう簡単に進展しないものだから、焦ってはいけない。仕事もダイエットも恋愛もすべて、努力を続けることで成果があらわれる。「急がば回れ」ということを忘れずに・・・。
05.
人生は仕事だけ・・・
無意味なハードワーク
夜遅くまで働くことが偉いわけではない。時間をきっかり決めて、いかに効率良く進められるかを考え、あとはリフレッシュや家族との時間に当てた方がずっと良いだろう。自分の時間を持てば、より良いアイデアが浮かぶことだってある。人生を振り返った時に、働きすぎたと後悔をしないように。
06.
なにごとも、一番がいい・・・
完璧主義
人生はマラソンのようなもの。常に完璧を求めていては、いつか疲れてしまうときがくる。時には休んだり、苦手なことは人に頼んでみてもいい。成功者がすべて完璧だったわけではない。完璧主義になりすぎると、準備が整わないと挑戦できなくなる傾向にある。その結果、何もできなくなってしまうので注意が必要。
07.
ストレスがどんどんたまる
ネガティブな心
人生には良い日も悪い日もある。幸せな人はそれを分かっているから、小さなことはいちいち気にしない。何だか良くない日は美味しいご飯を食べて、ぐっすり寝てしまえばいい。
平凡な日々もたくさん笑うようにすればいい。世界と接する際にもしネガティブな気持ちで接していたらすべてが悪く見えてしまう。反対に、良いところを見るようにすると世界はバラ色に変わる。毎日を幸せに生きるとはそういうことだ。
08.
あの頃は良かった・・・
過去の栄光
「今」を生き「未来」を輝かせたいなら、過去の栄光に浸っていてはいけない。素晴らしい人ほど、自ら過去の自慢話は口にしないものだ。一つの成功で終わらないのが、真の成功者である。
09.
不安で前に進めない
根拠のない恐怖
成功をイメージできない人に、成功は訪れない。悪い想像ばかりして恐怖に怯えている人は、リスクをとって挑戦することができず、当然何も成し遂げられないのだ。ポジティブな未来予想をすることで、自然と幸運を引きせせられるようになる。根拠のない恐怖を持つのではなく、根拠のない自信を持とう!
10.
今も忘れられない
恨みや怒り
人間は恨みや怒りといった負の感情に支配されやすい。そうなれば世界は歪んで見え、小さな幸せにも気づけないようになってしまう。許すことは相手のためではない。自分自身を自由にし、希望を持って生きていくために必要なことなのだ。
11.
自分も他人も信じられない
疑いの心
自分自信を信じ、仲間を信じ、挑戦をした人だけが成功をおさめることができる。私なんかにできるのか?あの人に任せていいのか?と疑っていたら前には進めない。人に信頼して仕事を任せられないようでは、一向に成長できない。
12.
差別や思い込みで決める
固定概念
差別や固定概念は、あなたの可能性に限りをつけてしまうだろう。選択肢を狭め、経験できたかもしれないことや新たな出会い、世界や知恵を自ら拒んでしまうことになる。既存概念に縛られていれば、ある種の安心感があるのは分かる。でももっと柔軟になることで、あなたの人生はより開けるはずだ。見たことや、やったことのないことに挑戦していこう。
13.
この通りに進めなきゃ
年密な計画を立てること
多くの成功者も始めは計画を持ち1歩ずつ足を進めるが、やがて人生はほとんど思い通りにならないということを悟る。ある程度の計画はあってもいいだろう。ただ安全策をたくさん用意する必要はないし、計画通りじゃないからと焦って絶望することもない。柔軟に対応し、挑戦を辞めないことが大切だ。
14.
人の心も傷つける
ネガティブな言葉
ネガティブな言葉は口にだした瞬間、人を傷つけたり不快にしたりする凶器となる。あなたの印象を下げることになることにもなるだろう。疲れた、あの人嫌い、気に入らない、美味しくない、楽しくない、そんなネガティブな言葉を口に出すのはもうやめよう。それを意識するだけで、あなた自身も明るく前向きになれるはずだ。
15.
空気を読みすぎ
遠慮しすぎてしまうこと
自分がやりたい仕事があるなら、積極的に手を上げよう。意見があるなら、相手が誰でもきちんと伝えよう。恋愛だってそうだ。好きな人には、好きと言おう。もっと自分の気持ちに素直になることで、人生はより素敵なものになるだろう。
[TABILABO]
Posted by nob : 2015年06月05日 16:36
手段は人それぞれ、、、最期まで自力で歩けてこそのすへての人々の幸福。。。
■「認知症1000万人時代」に備えよ!最後まで自分の足で歩く10の鉄則
結局、これができるかどうかが分かれ目です
高さ40cmほどの椅子に腰かけ、手を使わずに片足だけで立ち上がれるだろうか。できなかったら、近い将来、車椅子が必要になるかもしれない。そうなれば、認知症のリスクも急上昇。今から対策を。
95歳で杖も一切必要なし
「私の生活習慣なんて、メチャクチャ。これ以上ないくらい不規則なんですよ。夜2時まで起きていたり、朝ごはんがお昼になったり……ってね。
2週間に1度、仲間で集まって麻雀をやっています。それが朝10時から夜中の0時になっちゃうこともあってねぇ。一緒に住んでいる娘から『もう少し早く帰ってきて』と言われるんだけど、そうはいきません(笑)。
それから、気功、デッサン、絵手紙、ワインの勉強会も、それぞれ月に1度、仲間と一緒にやっています。スポーツ観戦も大好き。阪神ファンですから野球も必ず観ますし、サッカー、ラグビー、テニス……なんでも観ますよ。ルールも全部知っていることは、自慢できるわね。
もう、毎日忙しくって死んでる暇なんてないわ、っていつも言っているんです(笑)。1日38時間、1ヵ月が50日欲しいくらい。長生きするためには、早寝早起きで三食きちんと食べないと、なんて言うでしょう。私の場合、それにはまったく当てはまらないですね」
こう話すのは、滋賀県大津市に住む伊東綾子さん。今年で95歳になるというのだが、背筋はシャンと伸び、早口でてきぱきと話す姿は、実年齢より20歳は若く見える。
「昔よりは体力は衰えてきましたけれど、杖なんて一切使いません。元気で長生きする秘訣?みんなに聞かれますけどね、気をつけていろいろとやっているわけではないんですよ。でも、ちゃんと自分の足で歩いていることがいいんでしょうねぇ」
平均寿命が延びているとはいえ、伊東さんのような「スーパーおばあちゃん」はごく一握り。現実は深刻だ。
いま、認知症の患者が急増している。厚労省の発表によれば、'12年の時点で65歳以上の認知症患者は推計462万人。「認知症予備軍」と言われる軽度認知障害を含めると800万人を超えている。このままいけば、10年後には1000万人を超えるとみられており、「認知症1000万人時代」が間もなく到来するのだ。
たとえ長生きできたとしても、ボケてしまっては元も子もない。だが、自分の足で歩き続けることができれば、死ぬまでボケずに人生を全うできる可能性は広がる。じつは、歩くことこそが認知症の予防につながっているのだ。認知症専門医で、おくむらクリニック院長の奥村歩医師が言う。
「そもそも、人間の脳が発達して頭が良くなったのは、二足歩行によるところが大きいと言われています。認知機能に重要な前頭葉の働きは、歩くことと深く関係している。逆に言えば、自力で歩けなくなると、前頭葉の働きが著しく低下するということです。馬は歩けなくなると死んでしまいますが、人間も寝たきりになるとボケてしまうので、人間的な生活が送れなくなる。それくらい、自分の足で歩くことは大切なのです」
今回本誌は、90歳を過ぎて、ボケることなく杖も車椅子も使わずに生活している全国の高齢者たちを取材した。すると、ある「共通点」が浮かび上がってきた。彼らの生活習慣から、「最後まで自分の足で歩くための10の鉄則」を探っていこう。
筋肉が1週間で20%低下
冒頭の伊東さんの場合、〈1〉毎日のように外出する趣味を持っていることが、一つの大きなポイントとなる。順天堂大学大学院医学研究科・加齢制御医学講座教授の白澤卓二医師が解説する。
「何事にも好奇心を持ち、趣味が多い人は、高齢になっても元気な方が多いんです。日常生活の活動と肉体機能には関連性があるので、とくに人に会ったり、外に出かける趣味は、最後まで自分の足で歩くためにはいい。健康な人でも、1日中じっとしていると、下肢の筋肉が1週間で20%、3週目には60%も低下するというデータがあります。さらには、体中の関節がスムーズに動かなくなり、歩くことができなくなっていくのです」
取材した日、伊東さんは身に着けた青い洋服に合わせて、ブルーがかった銀色のマニキュアを塗っていた。
「出かけるときはもちろんお化粧もします。赤い口紅をひいてね。マニキュアは洋服や指輪の色なんかに合わせて、変えていますよ。麻雀をするときにも爪は目立つでしょう。この歳になっても女ですから(笑)」
女性であれ男性であれ、身なりに気を遣うことで、人に会うのも楽しみになり、行動範囲は広くなる。〈2〉おしゃれをすることで、自然と活動量は増えていくのだ。
「自分で洋服を選び、女性ならお化粧をすることで、気持ちも若々しく保てます。身なりに気を遣わなくなると、人に会うのもおっくうになり、外出も少なくなっていく。おしゃれをして社会性を保つことが、認知機能を維持し生活の質を高めることに役立ちます」(前出・白澤医師)
転ぶのを防ぐために
90歳を過ぎても自分の足で歩ける元気な高齢者たちは、毎日の生活の中で自然と体を動かす習慣を持っていた。たとえば、茨城県水戸市に住む黒川幸二さん(仮名)は、90歳になった今も、自宅の2階に寝室があるという。
「転んだら危ないので、娘に『1階で寝てよ』と言われるんですが、もう40年以上の習慣ですし、変えられません。昔に比べたら時間がかかりますけど、上がれないわけではありませんからね」
紺色のジャケットを羽織り、取材現場に颯爽と現れた黒川さんだったが、背筋も伸び、〈3〉歩くのが速いことに驚いた。それを伝えると、こんな答えが返ってきた。
「私は昔から車を運転しないんです。自宅から最寄りの駅が遠くて、出かけるときは徒歩で片道20分はかかりますし、近場であればどこへ行くのも歩いていきます。それに、せっかちな性格なので速足なのかな」
NTT東日本関東病院の整形外科主任医長の大江隆史医師は、この「速足」がポイントだと話す。
「米国で発表された研究ですが、65歳以上の男女を対象に歩行速度と寿命の相関関係を調べたところ、速く歩く人ほど5年生存率、10年生存率が高く、元気で長生きできるということがわかったのです」
死ぬまで自分の足で歩き続けるには、足腰の筋力を維持することがもっとも重要になるが、速く歩けるということは、筋力が衰えていないということ。自分で歩く速度を測るのは難しいが、それに代わるこんなチェック方法がある。「2ステップテスト」というものだ。
まず、できるだけ大股で2歩歩き、距離を測る。その値を身長で割ったものが「1・3を下回るようなら要注意」(大江医師)。たとえば身長160cmの人なら、2歩の距離が208cm未満なら、筋力が低下していると言える。
前出の伊東さんは「何もやってない」と言いながらも、話を聞いていると、じつは毎日、気功を続けているということがわかった。
「15年ほど前からやっているかしら。朝に20分、夜に20分、講習会で先生に習った気功をしていますが、気持ちいいんですよ。たしかに、これは私の健康法ね」
東京都調布市に住む松原洋二郎さん(89歳・仮名)は、仕事を辞めてから30年近く、毎朝のラジオ体操を欠かさない。
「朝は6時に起きて、ラジオ体操をして目を覚まします。気候がよくなってきたから、最近は外でやりますよ。旅行先でも欠かさないので、ラジオはどこにでも持っていくんです」
こうした〈4〉ゆったりした運動を続ける習慣は、中高年にとって転倒を予防するためにお勧めだ。
「車椅子や杖に頼らずにいるには、まず、転ばないことが大切です。高齢になるほど筋力の衰えと共にバランス感覚が失われるので、転倒の危険性が高くなります。気功やラジオ体操、太極拳といった体全体を使ったゆったりした運動も高齢者では効果があるでしょう」(桜美林大学大学院老年学研究科教授・新野直明医師)
転ばないために、体操のほかに簡単に始められる習慣がある。今回話を聞いた一人、東京都杉並区に住む笠井正美さん(91歳・仮名)の「こだわり」がそれだ。
「私は、出かけるときは〈5〉いつもスニーカーを履くんです。だって、歩きやすいでしょう。とくに運動はしていませんが、息子夫婦と孫夫婦、保育園に通うひ孫と暮らしていて、食事作りは私の仕事。ほぼ毎日、6人分の食材を買いにスーパーに行きますが、いつもスニーカーで歩いて行っていますよ」
この日も、春らしい花柄のシャツに細身のズボンをはき、足元は白いスニーカー。ショートカットの白髪にはパーマがかかっており、ピンク色の口紅と頬紅をつけた顔は、とても90代には見えない。
前出の新野医師が言う。
「転倒防止のために、スニーカーなどかかとが入る靴は非常にいい。サンダルや草履などは、脱げやすく転びやすいですし、脚を上げずに歩く癖がつくので、筋力も弱まって転倒しやすくなってしまいます。家の中でスリッパを履くのも、高齢者の方にはお勧めしません」
痩せすぎはよくない
食事については、これまでの「常識」と反対のことがわかってきた。まず、高齢になったら「粗食はNG」。歳をとったら消費カロリーが減るので、昔ながらの粗食がいいと思われがちだが、そうではない。取材したお年寄りたちには、〈6〉肉をよく食べる人が多かった。
「筋肉量を維持するためには、たんぱく質を継続的に摂取しなければいけません。また、体を支えている骨は、半分がカルシウム、半分がたんぱく質でできています。メタボを気にして肉は控えるという方が多いですが、高齢の方が粗食をすると、筋肉や骨を作るたんぱく質が不足してしまうのです」(前出・大江医師)
では、実際にはどれほどの量を摂らなければならないのか。厚労省が提示しているたんぱく質の食事摂取基準の推奨量('15年)は、20代でも70代でも変わらず、男性で一日60g、女性は50gが必要とされている。
「たとえば赤身の牛肉の場合、たんぱく質の含有量は20%程度なので、60gのたんぱく質を摂ろうと思ったら、300gのステーキを食べる必要があります。こ れほどの肉を食べるのは難しいですが、たとえば豆腐は一丁20gほど。魚のたんぱく質含有量は15%程度なので、組み合わせて摂取するようにしましょう」 (大江医師)
前出の黒川さんは、60歳で奥さんに先立たれてからずっと一人暮らしをしているというが、毎日自炊をしており、「手の込んだ料理はしませんが、魚と肉を毎日交互に食べています」と話す。
また、あまりに太っていたら腰や膝に負担がかかってしまうが、自分の足で歩き続けるためには、高齢になったら少し太めくらいがいい。とくに、〈7〉60代以降は、痩せすぎないことが重要だ。
「肥満度を示すBMI(体重〈kg〉÷身長〈m〉÷身長〈m〉)の値が19未満の人は、骨粗鬆症になりやすいことがわかっています。そうなると、骨折して自分 の足で歩けなくなります。太りすぎはいけませんが、BMI25以下であれば、体重を減らさないほうがいいでしょう」(前出・大江医師)
食品では肉のほかに、牛乳やヨーグルトなどの〈8〉乳製品を積極的に摂ることもいい。前出の伊東さんは、毎朝フルーツに牛乳をかけて食べており、松原さんはヨーグルトを欠かさないという。前出の白澤医師が言う。
「私が以前所属していた東京都老人総合研究所の調査では、乳製品を習慣的に摂る人は、摂らない人に比べて寝たきりなどの介護状態になりにくいという結果が出て います。良質のたんぱく質や骨を作るカルシウムなどを多く含み、最後まで自分の足で歩くためにはパーフェクトな栄養食品です」
楽しみながら腹筋強化
埼玉県川越市に住む野上和夫さん(90歳・仮名)は、60代から市民農園の
趣味を始めた。
「昔から趣味がなくて、仕事を辞めてから暇を持て余していたんです。娘から勧められて始めたんですが、だんだん面白くなってきた。枝豆やトマトから始めて、大根、白菜、と徐々に種類が増えていった。毎日欠かさず畑仕事をしていますね。このおかげか、脚も丈夫だし食欲もある。畑仲間と、たまに青空の下で飲むビー ルも最高ですよ」
60代から始めた趣味が、野上さんの健康にいい影響を与えている。それは、歩くための筋力を保つということだけではない。〈9〉毎日、日光に当たるということが秘訣だ。
「骨粗鬆症を防いで最後まで自力で歩くには、紫外線が重要な役割を持っています。骨の生成には、カルシウムだけでなく、カルシウムを体に取り込むためのビタミ ンDが不可欠。干しシイタケなどにも含まれますが、皮膚が紫外線に当たることで、人間はビタミンDを体内で生成できる。紫外線は悪とされていますが、日光に当たることは大切なのです」(前出・大江医師)
国立環境研究所が行った調査によれば、必要なビタミンDを生成するには、7月の昼間だと6分、12月の昼間だと41分の日光を毎日浴びないといけない(関東圏・つくばでのデータ)。もちろん日焼け止めはつけない状態で、だ。食事やサプリで摂取するのも手だが、毎日30分以上の畑仕事をしている野上さんは、自然に必要なビタミンDが生成されているようだ。
最後まで自分の足で歩くためには、こんな意外な要素もある。昭和大学藤が丘病院副院長の佐々木春明医師が話す。「男性ホルモンのテストステロンに、筋肉や骨の老化を防ぐ効 果があることがわかってきています。自分の足で歩き続けるためには、男性ホルモンの低下を防ぐことが重要です。そのためには、まずストレスを溜めない生活を送ること。ストレスが脳に作用して、男性ホルモンの分泌を妨げてしまうのです」
千葉県流山市の村本泰三さん(89歳・仮名)は、趣味のカラオケでいつもストレスを発散している。
「カラオケボックスに行くことも多いけど、月に1度はレッスンを受けに行っている。歌うのは、やっぱり演歌だね。女性の先生に褒めてもらうために、みんな必死で歌うんだよ(笑)。気持ちもいいし、こんな安上がりな楽しみはないでしょう」
ちなみにカラオケには、こんな利点もあるので、歩き続けるために一層効果を発揮する。「〈10〉お腹の底から大きな声を出して歌うことで、脳下垂体を刺激し て自律神経が整うだけでなく、自然に腹式呼吸になるので心肺機能も高まります。力一杯歌うと、1曲で100mのジョギングをするのと同じくらいの有酸素運 動になるんです」(前出・白澤医師)
歌うのが嫌いな人が無理にやっても効果はないというから、やはり、楽しんでやるというのが一番の秘訣のようだ。
ボケずに幸せな人生を全うするためには、最後まで自分の足で歩くことが不可欠。そのためにも、いま挙げた10の鉄則を実践してみるところから始めてみてはどうだろうか。
[現代ビジネス]
Posted by nob : 2015年06月03日 16:56
また旅立つ君へVol.95/自分だけが出逢える「本当の自分」
■「本当の自分」を見つけ、自分らしく生きるには
自分らしく生きることがどういうことかは、自明のように思えます。起きたいときに起きて、やりたいことをやる。誰にも流されず、他人の目なんか気にしない。でも、世界はそれを許してくれません。誰もが気づかぬうちに、本当の自分を隠して生きているのです。そのため、クリエイティビティ、創意工夫、自意識が抑圧されてしまいます。
親といる時、クライアントといる時、恋人といる時など、きっとあなたも、シチュエーションによってさまざまな自分を使い分けているでしょう。このような「自分のでっち上げ」は普通のことであり、誰でもある程度はやっているものです。
しかし、これに慣れてしまうと、本当の自分がわからなくなります。特に、SNSで自分をポジティブに見せることが「自分らしい」とされることが多い現代では、その傾向が強いようです。さらに悪いことに、最近のメディアは「自分らしく生きる」ことを、ほら吹き、道から外れた若者の代表、ヒステリー嗜好で変わった身なりのアウトサイダーのような取り上げ方をしています。
でも、それは本当の自分などではありません。自分らしく生きることとは、ところかまわず自分の意見を発言することではなくて、自分の意見に対する確固たる自信を持っていることなのです。
このように「自分らしさ」が流行るずっと前から、数々の哲学者が、その答えを求めてきました。ルソー、カミュ、サルトル、キェルケゴール、マズロー、メイ、バジェンタルなど、そうそうたるメンバーです。「Philosophy Now」では、これについて以下のように総括しています。
自分らしくあることは、各個人のミッションである。なぜなら、それぞれが人間らしくあるための自分なりの方法を持っており、自分らしさとは個々によって違うからだ。
さらに、自分らしさというものは、文脈によって大きく変わるもの。社会的、政治的、宗教的、文化的な特徴によるところも大きい。しかし、各個人の個性は、当人の中にではなく、当人がなる者の中に見つけることができる。
自分らしく生きることとは、1回のイベントなどではなく、継続的なプロセスなのだ。そのためには、自分を知るだけでなく、他者を知り、個人間の相互的な影響を認識することが必要だ。
本当の自分を求める目的が自己実現だけだとしたら、それは個人主義的なエゴである。しかし、そこに他者や広い世界への認知が伴うのであれば、それは価値ある目標になる。
要するに、本当の自分を見つけるには、自分に正直になるだけでなく、自意識を高め、謙虚になり、他者からのフィードバックを受け入れる覚悟が必要なのです。それは厳しく、終わりのないプロセス。なぜならあなたのアイデンティティは常に進化しているから。でも、それによって得られるのは、よりハッピーで、よりクリエイティブな自分です。心理学者によると、自分らしさを持つことで、優れた対処戦略、自己肯定感、自信、最後までやり抜く力が身につくそうです。
自分の経歴を振り返る
「自分のことぐらい知ってるよ!」と思うかもしれませんが、過去の自分をじっくり振り返ったことはありますか? 今のあなたを作っているのは、過去のさまざまな出来事であり、価値観であり、経験なのです。
「The Harvard Business Review」は、自分を定義するために、過去の経歴を詳しく振り返ることを勧めています。これまでの人生、どんなふうに育てられましたか? 新しい状況にはどのように対処してきましたか? コンフォートゾーンから飛び出したことはありますか? 自分の価値観をじっくり見つめなおしたことはありますか?
これを実施するには、心のエクササイズや日記を書くなどの方法がありますが、大事なのは、自分の過去をできるだけ客観的に見つめること。時間をかけて自分の過去の判断を批判し、そのような選択を下した理由を分析します。友人や同僚からもらったフィードバックについても考えましょう。
でも、いちばん大切なことは、過去の失敗を詳細に振り返ることです。自分がどれだけ自己中心的で無礼だったか。なぜそんな振る舞いをしてしまったのか。最終目標は、自分についてもっと知ること。だから、できるだけたくさんのことを振り返ってください。きっと、自分についてあまりにも知らなかったことに驚くと思います。
クリティカルシンキングの癖をつける
哲学者セーレン・キェルケゴールは、複数の本において、自分らしさ(authenticity=主体性と訳される)を、人が現実に向き合い、決断を下し、それにコミットし、責任を持つための目的であると述べています。つまり、キェルケゴールの言う自分らしさとは、現実に向き合い、自分の意見を形成することなのです。
クリティカルシンキングを身につけることが、自分らしさを見つけるうえで決定的な要素になります。批判的思考とは、細部に注意を払い、適切な質問をすることで、言われたことを鵜呑みにするのではなく、独自の意見を持つことを意味します。世界に対する自分なりの意見を持つことができれば、人任せではなく、自力で現実を読み解くことができるのです。そうすることで、自分の世界観を定義している先入観を知ることができるため、自意識を高めることができます。
クリティカルシンキングは、非常に骨の折れる作業です。現実と先入観の両方について考え始めると、対処しなければならない不一致があまりにもたくさんあることに気づくでしょう。たとえば、30歳までには家族を持つものと考えていたにもかかわらず、自分の気持ちと向き合ってみると、そうしたいと思えない。それは、子どものころから刷り込まれた先入観なのです。
いま自分が持っている世界観と同時に、自分の中で大切にしている原則にも注目しましょう。誰もが、何かしらの信念のもとに育てられてきました。でも、その多くは、今の自分の考えとは一致しないはず。たとえば、仕事のときはスカートをはきなさいと両親に教えられ、それに従っていたら、自分がスカート嫌いだという事実に気がつかなかったなんて話も耳にします。
これは暢気な例ですが、人種、宗教、セクシャリティなど、もっと重大な問題を抱えている人もたくさんいます。このように、小さなころから続けている習慣や世界観を、少し疑ってみましょう。昔ながの信念を見つめなおすチャンスはめったにありませんが、詳しく振り返ることで、自分のことがもっとわかるようになるはずです。
目標を定義しなおす
今の自分が大切なのは確かですが、どんな人間になりたいかという目標も、同じくらい大切です。恐れずに自分らしく生きるには、目指す先を知っておく必要があるのです。かねてから、なりたい自分が、今の自分を示す最良の指標だと言われてきました。Joshua Knobe准教授は、「New York Times」への寄稿で、こう述べています。
哲学的な伝統を見れば、この質問には比較的わかりやすい答えを見つけることができます。多くの哲学者が支持するその答えでは、人間の最も特徴的かつ根本的な性質として、合理的な内省ができる能力を挙げています。
人は、衝動や気まぐれなど、つかの間の感情をたくさん抱えています。しかしこれは、その人の最も根本的な部分ではありません。本当の自分を知りたければ、立ち止まり、自分の中の最も深い部分にある価値観について考えることです。
ヘロイン中毒に苦しむ人を例にとりましょう。その人は、誘惑に負けてまた注射に手を伸ばしてしまいます。これを「あの人らしい」とか「人となりを表している」と言うのは、いささかばかげています。その人は、自分をだまして、大切にしていることをあきらめているのです。
やりたいことを見つけるのは簡単ではありません。でも、自分が将来ほしいものを知ることで、本当の自分が見えやすくなります。ここでは、自分の目標と価値観を知りましょう。
いつか引退したい? 結婚したい? 無人島に暮らしたい? お金持ちになりたい? こんな風に、自分の目標について時間をかけて考えたのはいつですか? 今の目標は、5年前と同じでしょうか? きっと違うでしょう。価値観や目標は、時とともに変わるもの。行動は、それについてくるのです。
目標ややりたいことがわからないなら、やりたいことを見つける方法について書いた過去記事をご覧ください。
その中でも、私は個人的マニフェストをオススメします。個人的マニフェストを書くには、机の前に座り、自分なりの価値観を定義したいトピックをいくつか選びます。他人に定義してもらわずに、とにかく深掘りしてください。倫理、性格、その他あなたが重要だと思うものであれば、何でも構いません。
トピックを選んだら、自分の信念、モチベーション、意図を書き出します。自明のようでいて、いざ書き出してみると、自分の予想とは違う内容に驚くこともあるでしょう。
リアルワールドで行動に移す
自分について詳しくなっても、引き続きこの世界を航海しなければなりません。それは多くの人にとって、今の仕事を甘んじて続けることを意味します。一見、それは難しいことのように思えます。少なくともある研究において、自分の社会的アイデンティティを隠して働くことは、仕事に対する不満の原因になりやすいという結果が出ています。
自分らしくあることは、自分の心を何から何まで包み隠さず話すことではありません。誠実であることは大切ですが、私たちは常に攻撃しあっているわけではありません。職場でも同じです。声に出して言いたいことを言う必要がありますが、相手が誰かをいつも考えてください。
たとえば、銀行の役員室で初めて会った人に、昨夜行ったストリップクラブについて話すのはやめた方が無難です。これは、社会的なアイデンティティを隠しているのではなく、相手によって情報開示の方法に気をつけることを意味します。
友人関係や恋人との関係でも同じことが言えます。正直で誠実、かつ自分らしくあること。そして、どんなに奇抜なアイデアでも、自分の考えを話すこと。自分が心を開くと、相手も開いてくれることに驚くでしょう。そして、そのプロセスで、自分についてもっと詳しく知ることができるようになるのです。
Thorin Klosowski(原文/訳:堀込泰三)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2015年05月28日 16:20
暫し休酒してみれば実感できます。。。
■薄毛・肌荒れ・口臭…アルコールによる10のデメリットって?
「酒は百薬の長」という言葉もありますが、適度なお酒ならリラックスや人とのコミュニケーションというメリットがあるかもしれません。でも、行きすぎてしまうとデメリットが大きくなってしまいます。お酒を飲みすぎることによる10のデメリットを紹介します。
【1】薄毛、肌荒れになりやすい
アルコールを体内で処理するには、ビタミンB群を中心に多くのビタミンを消費します。ビタミンが消費され不足してしまうと、健康な肌や毛髪を作ることができなくなってきます。
【2】疲れやすくなる
アルコールの処理で消費されるビタミンB群は、エネルギーを作るのに欠かせない栄養素です。また、神経が正常な状態を保つのにも重要な働きをしています。アルコールを飲むことでビタミンB群が不足すると、体が重く感じたり、心身ともに疲れを感じやすくなります。
【3】口が臭くなりやすい
アルコールの持つ利尿作用で体の水分が失われると、唾液の量が減り、口臭の原因になることもあります。もちろん、しっかり水分補給(アルコール以外の利尿作用がない飲料)することや、唾液が出やすくなるガムをかむことで予防できます。
【4】取り返しのつかない失敗をする……かもしれない
お酒を飲むことで気が大きくなる人や、記憶を無くしてしまう人は、大きく後悔するようなことをしてしまうかもしれません。
【5】生活習慣病になりやすい
脂肪肝や高コレステロール血症、高血圧などの生活習慣病の原因になります。また、アルコールの刺激は、食道や胃などの消化器官を荒らします。頻繁に荒らしてしまうと消化器系のガンなどがおこりやすくなります。また、糖尿病や痛風なども起こりやすくなります。
【6】脳の病気になりやすい
少量のお酒は脳をリラックスさせてくれますが、量が増えるとダメージの方が大きくなってしまい、脳の委縮が起こります。アルコールによる脳の委縮は、認知症との関係が報告されています。
【7】妊娠、赤ちゃんの健康に影響する
妊婦の飲酒は、胎児性アルコール症候群(アルコールの影響で胎児に脳の発達障害等が起こる疾患)や発育障害を引き起こします。授乳中も、血中アルコールは母乳に出てしまいます。また女性だけでなく、男性のEDの原因になったりもします。
【8】睡眠の質が低下する
お酒を飲むとよく眠れるような気がするかもしれませんが、それは眠りの入り口だけ。睡眠の質という面では、アルコールによって眠りが浅くなることがわかっています。
【9】翌日の効率が下がる
お酒が残っている感覚はなくても、睡眠の質が落ちたり体が軽い脱水状態になることで、普段より思考力や集中力が低下してしまいます。
【10】中毒性と依存性がある
一時的に体の処理能力以上のアルコールを摂ることで起こるのが急性アルコール中毒です。アルコール処理能力には遺伝的な差もあるので、深酒をする前に自分のタイプを調べておくことも大切です。
依存によって飲酒のコントロールができなくなった状態がアルコール依存症です。飲酒量が増えれば依存症になるリスクも増えます。また、同じ量の飲酒の場合、女性の方がアルコールの処理能力が低く、依存症になりやすいこともわかっています。
「お酒は飲んでも飲まれるな」と言われるように、お酒とは「お金と時間と健康を失わない程度のお付き合い」にしたいですね。
(文/健康食品アナリスト 小浦ゆきえ)
[マイナビスチューデント]
Posted by nob : 2015年05月11日 20:31
いつでもどこでもできるストレッチVol.2/身体は隅々まで繋がり合っている。。。
■一石二鳥! 運転中の眠気対策になるエクササイズ
イビキも減らす口の体操
欠伸
あくびをするなら、思いっきりしましょう
単調な運転が続くと眠くなって、アクビが出ます。アクビが出ると、さらに眠気が強くなると感じる人もいますが、実はアクビには眠気を覚ます効果があります。
アクビをするときは、口を大きく開けます。口の周りの筋肉が引き伸ばされると、神経を伝って脳に電気刺激が届きます。この刺激によって、脳が目覚めようとするのです。
この原理をうまく使って、体の筋肉を伸ばしたり縮めたりすると、脳に刺激が伝わって目が覚めてきます。運転中に手足を動かすと危険ですが、顔の運動ならあまり問題にはなりません。顔の運動にはいろいろなありますが、なかでも「あいうべ体操」がお勧めです。
「あいうべ体操」は、福岡にある「みらいクリニック」の今井一彰院長が考案した、口の体操です。口呼吸をしていた人が「あいうべ体操」を行うと、鼻呼吸をしやすくなります。イビキをかく人の大半が口呼吸をしていますが、鼻呼吸に変わるとイビキが減ります。ですから、「あいうべ体操」を習慣化すると、眠気覚ましになるだけでなく、イビキが減って夜の睡眠の質も高まるのです。
あいうべ体操のやり方
アゴが悪い人は、「い」と「う」だけでも効果があります
「あいうべ体操」のうち、「あいう」は口の周りの筋肉の、「べ」は舌を突き出す筋肉のトレーニングです。
まず、口を楕円形にして、のどの奥が見えるまで大きく開き、「あ~」といいます。つぎに、前歯をむき出しにして、首の筋が浮き出るくらい口をグッと横に開いて、「い~」といいます。
「う」は口を閉じる筋肉の体操で、唇を尖らせて前に突き出して、「う~」といいます。最後の「べ」では、舌の付け根が引っ張られるくらい、思い切り舌を前に突き出して、「べ~」といいましょう。
「あ・い・う・べ」それぞれに、おおむね5秒間くらいずつかけて行います。体操を習慣化するなら、「あいうべ」の4つの動作を1セットとして、1日30 セットを目安に行います。慣れるまでは、30セットを2~3回に分けて行ってもかまいません。もっと回数を増やしたいときには、1回30セットを朝晩や朝昼晩に行うとよいでしょう。
ダイエットにも役立つエクササイズ
ウエスト・腹横筋
メタボ対策にも、有効な運動です
下腹がポッコリ出ているのを何とかしたいと思って、いわゆる腹筋運動(クランチやシットアップなど)をしても、なかなかお腹はへこみません。下腹部を効率的にへこますには、お腹を縦に走る腹直筋だけでなく、横に走る「腹横筋」も鍛えなくてはいけません。
腹横筋のトレーニングを行うときには、体を大きく動かす必要はありません。また、手足を動かす必要もありません。ですから、自動車の座席などに座った状態でも、十分にトレーニングができます。
運動の前に、「横へならえ」をするように、手をウエストに当ててみてください。このとき、人差し指から薬指が当たる部分の、お腹の柔らかさを確認します。おなかに力を入れていなければ、柔らかいですよね。
ここから、エクササイズです。まず、お腹をへこまします。特に下腹を意識的にへこませ、お腹のラインが地面と垂直になるようにします。この状態で、トイレで踏ん張るように、下腹部に力を入れます。思いっきりいきみますが、呼吸は止めずにゆっくり続けてください。
指をあてた部分のお腹は、硬くなりましたか? ここが十分に硬くなるよう、頑張っていきんでください。この状態を10秒間ほど続け、短い休憩をはさんで2~3回行うと、眠気も減ってきます。
運転中にエクササイズを行うときは、安全のため、しっかりハンドルを握った状態で行ってください。
[All About]
Posted by nob : 2015年05月11日 20:13
眼精疲労、首や肩の凝り、頭痛、ストレスなどの解消にも効果があります。。。
■頭皮の血行促進方法
頭皮の血行促進方法1:頭皮マッサージ
血行不良の頭皮は、髪や毛根に栄養が行き渡らず髪の成長を妨げてしまいます。太くてコシのある毛髪を育てるために、頭皮マッサージやツボ押しで血行を促進させましょう。
頭皮マッサージをするとき、まず耳を包み込むように親指以外の4本の指をあて、親指は後頭部で固定させます。そのまま親指を固定した状態で、頭皮全体を動かすように、円を描いてマッサージしていきます。それから少しずつ指をずらして頭全体をまんべんなく押していきます。
マッサージのやりすぎは頭皮に負担となり逆効果ですので、1日5分程度を目安にしましょう。最近では頭皮マッサージ専門のブラシもあるので、それらを試してみてもいいかもしれません。
頭皮の血行促進方法2:ツボ押し
・百会(ひゃくえ)
血行促進でもっとも重要なツボです。多くの気が集まる場所にあり、自律神経を整えるツボとして広く知られています。両耳の延長線と眉間の中心から伸びたラインが交わる頭頂部にあります。
・角孫(かくそん)
頭皮の血行促進や抜け毛予防のほか、目や耳、歯の病気にも効くといわれています。耳の穴をおおい隠すように耳全体を折り曲げたとき、耳の先端があたる、耳の上の髪の生え際辺りにあります。
・玉枕(ぎょくちん)
血行を促進し頭頂部の薄毛に効果的なツボで、緊張性頭痛や眼精疲労にも効果があるとされています。玉枕は、後頭部に2か所あります。仰向けに寝たときに、枕に頭があたる位置にあります。
ツボは、正式には「経穴(けいけつ)」といい、穴という字が入っていることからわかるように基本的にくぼんでいます。ツボを押すときは、そのくぼみを最初浅めに、次第に深く5秒間前後かけてゆっくり押していきましょう。健康な頭皮であれば、弾力があり気持よく感じます。硬かったり、痛みを感じたりする場合は、1日のうち複数回行いましょう。
頭皮の血行促進方法3:育毛剤
育毛を促進するには、毛母細胞やその周辺を活性化させることが重要です。毛母細胞などの分裂を促進する方法は、育毛剤に配合されている有効成分によって変わってきます。たとえば、血行促進効果のある成分として「センブリエキス」や「ナイアシンアミド(ニコチン酸アミド)」が入った育毛剤を試してみてもいいでしょう。
シャンプー後の頭皮が湿った状態で使うと、浸透しやすくなります。一日1〜2回の塗布を目安にしてください。
[メンズスキンケア大学]
Posted by nob : 2015年05月11日 20:03
股関節を緩める、、、日々のストレッチに是非とも加えたい。。。
■股関節ストレッチでリラクゼーション効果と美脚を手に入れる!
美脚のためのストレッチやマッサージなどケアの方法は色々ありますが、股関節の柔らかさが美脚にとても重要な役割を持っていることを知っていますか?
股関節が硬いと足の動きが少なくなり、そのため足の筋肉が衰え脂肪がつきやすくなります。筋肉が衰えていると血行が悪くなって老廃物が流れにくくなることで、太ももにびっしりとセルライトがつき、ヒップラインまで影響が出てしまいます。
その結果、下半身ばかりが太くなってしまうことに…。股関節を柔らかくするストレッチで下半身太りを解消させて、誰もが羨むような美しいレッグラインを作ってしまいましょう。
手軽にできる股関節ストレッチ
テレビを見ながらできる、ながらストレッチをするならこの方法がおすすめです。
・両足を開いて床に座ります(リラックスしながら)。
・膝を曲げ、力を抜きながら両方の足の裏を合わせます。
・両膝を床に押し付けるようにゆっくり上下させます。
上下させる時はゆっくりと、股関節が伸びているのを意識しながらストレッチしましょう。股関節が硬く、足の裏を合わせるのが辛い人はあぐらをかいた姿勢から始めてください。
バレリーナストレッチ
バレエのように足を高く上げてやるストレッチです。ちょうどいい手すりやバーがなければ、机や棚など安定性のある丈夫なもので代用してみてください。
・腰の高さくらいの手すりやバーなどに片方の足をかけます。
・もう片方の膝を曲げて腰を落とします。
・股関節が伸びているのを意識しながら30秒そのままの体勢を維持します。
・終わったらもう片方の足で同じアクションを行います。
股関節が硬い人は少し難しいかもしれません。低めの場所から練習してみましょう。
開脚前屈ストレッチ
足を広げて身体を前に倒すストレッチです。少し負荷がかかる方法ですので無理なくできる範囲で行いましょう。
・無理のない範囲で足を開いて床に座ります。
・足首を上に向けて、膝が曲がらないように股関節を意識しながら上半身を前に倒します。
身体を前に倒す時は、首からでなく胸から倒すようにしましょう。
股関節の前面を伸ばすストレッチ
背中側だけでなく前部分を伸ばすストレッチです。
・床に仰向けに寝ます(リラックスしてください)。
・片方の足を抱え込むようにお腹に近づけ30秒維持し、ゆっくりとしたスピードで足を戻していきます。
・反対側も同様のアクションを行います。
床につけたほうの足が浮いてしまわないよう気をつけましょう。
ももの内側を伸ばすストレッチ
太ももの内側を伸ばすストレッチです。
・両足を外側に開いて立ちます。
・お尻をゆっくりと下ろしていき、無理のないところで30秒維持します。
・その後、ゆっくり元の体勢に戻します。
ももの内側もしっかりとストレッチすることで、股関節の柔軟性がアップします。さらにストレッチを習慣にすることで脳からα派が放出されやすくなるので副交感神経が活発になり、リラクゼーション効果が期待できます。毎日少しのストレッチで、美脚を手に入れましょう!
[かみまど]
Posted by nob : 2015年05月11日 19:50
姿勢と呼吸、、、キホンのキ。。。Vol.2
■口臭の原因!? 口呼吸をしている人は今すぐ鼻呼吸に!
無意識のうちに口が開いていたり、やたらと口の中が乾いたり…。こんな症状に思い当たる方は、鼻呼吸ではなく口呼吸になっているのかもしれません。
身体にさまざまな影響を及ぼす口呼吸の原因と対処法、鼻呼吸のメリットについて詳しくご紹介します。
口呼吸は免疫力の低下や口臭などを引き起こす
人は呼吸をする時、普通は鼻で空気を吸ったり吐いたりして鼻呼吸をしています。
鼻毛や鼻の奥にある繊毛は、ホコリや花粉を取り込まないようフィルターの役目を果たしており、吸い込んだ空気を加温・加湿することで喉や気管を守っています。
しかし、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎など鼻に慢性的な疾患があると、鼻ではなく口で呼吸をしてしまうことがあります。これがいわゆる口呼吸です。では、口呼吸になると身体にどんな影響が現われるのでしょうか?
1.口から空気を吸うことで、ウイルスや菌が入りやすくなり、扁桃腺(リンパ組織)がダメージを受けて免疫力が低下。風邪をひきやすくなる。
2.口が乾くことで雑菌が繁殖して口腔内のバランスが乱れ、虫歯や口臭が発生しやすくなる。
3.いびきをかきやすくなったり、舌が喉のほうに下がることで気道が塞がれ、睡眠時無呼吸症候群を引き起こす可能性も。
口呼吸の主な原因と対処法
口呼吸を治すためには、口呼吸の原因を見直すことが必要です。口呼吸の主な原因と、その対処法をご紹介します。
1.鼻疾患の治療をする
子どもの頃から慢性的な鼻疾患がある場合、口呼吸が習慣化していることがあります。自分では口呼吸に気付きにくいため、鼻水や鼻づまりなどの症状が気になる場合は、早めに耳鼻科を受診して治療を。
鼻でしっかりと空気を吸うことができるようになると、自然に鼻呼吸ができるようになります。
2.歯列矯正をする
前歯が出ていたり、上下の歯の噛み合わせが浅かったりと歯並びが悪いことで、口呼吸になってしまうことがあります。この場合、歯科を受診して歯列矯正をすると、口呼吸の改善につながります。
鼻呼吸をすることでダイエット効果も
鼻からきちんと息を吸うことは、実はダイエットにも効果的。鼻呼吸をすることで、横隔膜や腹横筋などの呼吸筋を刺激することができ、自然と体幹トレーニングになるのだとか。
また鼻からゆっくりと息を吸い、おなかをへこませながら口から息を吐くドローイン・ダイエットも、おなかやせ効果大。
口呼吸には多くのデメリットがあり、身体への影響も大きいと言われています。口呼吸を治して正しい鼻呼吸を身につけ、健康的な生活を送っていきましょう。
[かみまど]
Posted by nob : 2015年04月28日 22:14
いつでもどこでもできるストレッチ/姿勢と呼吸、、、キホンのキ。。。
■腹凹の最終手段【吐いてひねる】。 これでダメならあきらめて!
残念ながら、食事節制だけではお腹は凹みません。ダイエットしたいけど、腹筋なんて面倒、というワガママさんの為に、どこでも出来て、みるみる引き締まる体操をご紹介します。
ジュディ
「筋トレしなくても、ただ常に凹ませてればいいの。」
私の通っているヨガのスクールに、縦割れのラインが入った腹筋が特に美しい先生がいました。
彼女に、どんな筋トレをしたらそんなお腹になるのか聞いたことがあります。
その時に返ってきた言葉が上の一言。
ぽかーん、としてしまった私。
彼女は確かにヨガインストラクターなのでお腹が見苦しくたるんでいる筈はないのですが、普段筋トレの代わりにあることをしているというのです。
「常にお腹を凹ませた状態をキープする。」
意識して、「お腹を凹ませた状態」をイメージ出来ますか?
力を入れておへそを背中の方に引っ込めた状態です。
歩いている時も、座っている時も、電車に乗っている時も、常にこの「お腹を凹ませた状態」をキープし続けているんだとか。
え?それだけ? と思いますよね。
でもこれ、案外大変なんです。そもそも腹筋が弱い人は、自力で十分にお腹を凹ませることが出来ないことも。
皆さんはぎゅっとお腹を凹ませられますか?
「凹ませて、ひねると効果倍増。」
常に腹筋を凹ませて生活するだけでも、お腹は確実に凹みます。
しかもこれは、床に横になってする腹筋運動より遥かに身体に負担が掛からないだけでなく、同時に背筋も使うので、バランス良くインナーマッスルを鍛えられるから、美しいS字ラインのボディになれるんです。
そして、これに更に効果をプラスするのが「ひねる」運動。
「吐き切って、ひねる。」これも言葉にすると、それだけですが、効果絶大。
オフィスなどで疲れた時や、同じ姿勢を続けて体が凝った時のストレッチにもなるから試してみて。
やり方は簡単。4ステップ
Step1:まずは足を肩幅に開いてまっすぐに立ちます。手は軽く腰に当てましょう。
Step2:そのままお腹を凹ませながら、「ふぅー」と言うつもりで、とにかく息を吐き出します。
Step3:限界の手前まで吐き出したら、上体を左右どちらかにひねります。
※この時、腰は正面に向けておいてください。腰から上だけをひねるつもりで。
Step4:ひねった状態で、残した息を思い切り吐き出します。
※ステップ4の段階で腹筋にマックスの負荷が掛かるので、ぐぐっとこらえましょう!
これを左右何回でも繰り返します。
1日に何回やってもOK。
インナーマッスルが十分に刺激され、腸も動くので、便秘の方にも効果的です。
夏までひたすら絞ってぺたんこなお腹を目指しましょう!
[美BEAUTE]
Posted by nob : 2015年04月28日 22:09
また旅立つ君へVol.91/代わり映えのしない退屈な毎日なんてどこにもない
日常のすべては一期一会
二度と戻らぬかけがえのない
奇跡の一瞬の連続
Posted by nob : 2015年04月22日 23:04
また旅立つ君へVol.90/人の在り様になど囚われることなく、、、自らの在り様を楽しみ尽くすことに粉骨砕身していきたい。。。
人の己を知らざることを患えず
己の人を知らざることを患う
これを知る者は
これを好む者に如かず
これを好む者は
これを楽しむ者に如かず
[いずれも「孔子/論語」より]
Posted by nob : 2015年04月22日 22:54
また旅立つ君へVol.89/限られた時間、、、無駄な事柄に費やす余裕はない。。。
好きでもない相手との付き合いなんかに
余計な時間や手間をかけてばかりいると
本当に好きな人にそれだけ出逢えなくなってしまいます
Posted by nob : 2015年04月22日 22:39
1以外は私も実践確認済みです。。。
■必要なのは5分だけ。すぐにストレスを減らす5つの行動
皆さんがストレスを感じている理由の1つは「1日の時間が足りないと思っているから」です。そのため、安易にストレス解消をしようと思っても、それをするのに時間がかかるので、さらにストレスを感じてしまう可能性が大いにあります。
少ししかない時間でどうすればストレスを軽減することができるのでしょうか? 燃え尽き症候群予防の専門家になった元弁護士、Paula Davis-Laack氏が最近ハフィントンポストに寄稿した素晴らしい記事には10の対処法が紹介されています。
1. パスワードを変更してみる
離婚後にクリエイティブなパスワードを使って心の傷を癒やした男性の話があります。Davis-Laack氏は、ストレスにさらされている社会人でも同様のテクニックを使ってちょっと違う結果をもたらすことができると提案しています。"Forgive@h3r(彼女を許す)"のようなものではなく、皆さんを元気づけてくれる、あるいはストレス レベルを下げるよう注意してくれる、クリエイティブなパスワードを選びましょう。「一日のうち、何度パスワードを入力するかを考えてみてください。皆さんが求める環境を作り出すのに役立つようなパスワードを考えてください」とDavis-Laack氏は書いています。
2. 抱きしめてみる
このアイデアは、抱きしめることのできる誰かが側にいるかどうかにかかっているため、皆さんの同僚との関係によっては、夜になるまで待たなくてはならないかもしれませんが、この記事によると、安心して寄り添えられる人を見つけられたら、簡単なハグだけでもストレス退治効果を大いに発揮するということです。
「誰かを抱きしめると、リラクゼーション、信頼感、そして思いやりの一因となる、社交的な行動を促すホルモン、オキシトシンが分泌されます。Paul Zak博士の人気のTEDトークでによると、人との強い関係を維持するためには、1日8回以上ハグすることが必要です」とDavis-Laack氏は説明します。
3. 書き出してみる
書くことを試すのも良い方法です。たったの5分間、考えを全て書き出すだけでいいのです。「非生産的な思考や感情は、日中に蓄積します」と、記事は主張します。「最悪のシナリオに思考がとらわれた状態は、頭からそれらを全部出してしまうまでは好転しません。問題を紙に書き出してみると、いかに違って見えるかに驚かされます」。
4. 「4-7-8 呼吸法」
瞑想するだけの時間がないと思っていませんか? もしそうなら、この方法は集中するのに役立つ代替策です。「背筋を伸ばした状態で椅子に座るか、床に座ります。4つ数えながら息を吸い込み、7つ数えながら息を止め、8つ数えながら息を吐き出します。この呼吸法を5分間繰り返します」とDavis-Laack氏が呼吸法を伝授してくれましたが、このテクニックのコツをつかむには少し時間がかかる場合があるとしています。
5. 何かを味わってみる
「何かを味わうということは、ポジティブな出来事やポジティブな感情を高める効果のある考えや行動に注意深く集中することに関わっています」Davis-Laack氏によると、このアイデアは将来的な出来事を予測することにも、その瞬間を最大限に活用すること、または、過去の幸福な記憶からより多くの喜びを引き出すことにさえ役立てられるということです。時間をとってランチがいかにおいしいかということに気づいたり、最近行った素敵なバケーションを思い出したり、と、人生に幸福をもたらすものを単に味わうことも即効性のある簡単なストレス軽減法になるのです。
お気に入りの即座にストレスを解消できる方法は何ですか?
5 Ways to Bust Your Stress in Less Than 5 Minutes|Inc.
Jessica Stillman(訳:コニャック)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2015年04月22日 22:13
これはホントです、、、私も実践中。。。Vol.2
■【HEALTH HACKS】飲むだけで得られる「白湯」の効果とは?
白湯(さゆ)というと、赤ちゃんや体の弱っている人が飲むものというイメージがあるのではないだろうか。実際、インドの伝承医学アーユルヴェーダにおいても、白湯は内臓の機能や血液循環を高めるものとして考えられている。そんな白湯だが、有名女優やモデルたちをはじめとし、取り入れる人が増えてきている。何の変哲もない、ぬるいお湯=白湯だが、これを飲むことで内臓が温まり代謝がアップ、血液循環を良くする、老廃物が排出されやすくなるデトックス効果、冷え性改善、便秘解消、むくみ解消、ダイエットなど様々な嬉しい効果があると言われている。ダイエット食品『マイクロダイエット』を展開するサニーヘルス株式会社は、同社が運営するダイエット情報発信サイト「microdiet.net」で「女優やモデルも「白湯」の虜に!飲むだけで得られるその効果とは?」と題し、情報を公開している。その一部を紹介したい。
■効果的な飲み方とは?
まず50度前後の白湯を用意しよう。わざわざ温度計で測る必要はない。飲んでみて、少しぬるいながらも温かいと感じる程度が目安。10分間沸騰させて冷ましたものが推奨されているが、自分が続けやすい方法で作ればOK。やかんで軽く沸かす程度でも良いですし、電子レンジで加熱してもかまわない。ポットで保温したものでも、もちろんOK。使用する水は、水道水でもミネラルウォーターでも可。浄水器の付いていない水道水の場合は、5分ほど沸騰させ、冷ますこと。カルキ臭が抜けて飲みやすくなる。飲むタイミングは以下の通り。特に起床時に白湯を飲むと、効果を実感する人が多いようだ。
◎起床時
朝起きてすぐに1杯、100〜150ccほどの量をゆっくりと飲む。睡眠中に失った水分の補給と、体を内側から温め代謝を上げる効果、腸を刺激してぜん動運動を促し便通を良くする効果もある。
◎食事中
食事中の飲み物として白湯を飲む。量は100〜150cc程度。食べた物の消化吸収を助ける作用がある。
◎就寝前
眠る前にも白湯をゆっくりと体に染み込ませよう。量はやはり100〜150cc程度。副交感神経が優位になりリラックスできるので、質の良い眠りが得られる。
[@DIME]
Posted by nob : 2015年04月22日 22:08
同感です、、、がんに至るまての様々な病の元かと。。。
■体内時計を無視するから、日本人はがんになる
「時計遺伝子」の力を知っていますか
藤田 紘一郎 :東京医科歯科大学名誉教授
今、日本ではがんになる人が増えています。一生のうち2人にひとりはがんになり、3人にひとりはがんで亡くなっています。
理由はいろいろ考えられますが、私は日本人が生体のリズムを無視した生活をしていることが、がん発生の一因になっていると思っています。近年の研究により、体内時計を無視した生活が発がんを促していることが明らかにされてきたからです。
私たちの体は、約60兆個の細胞によって構成されています。一つひとつの細胞核のなかには「生物の設計図」と言われる膨大な数の遺伝子が詰め込まれています。その一部には、「時計遺伝子」と呼ばれる十数個の遺伝子が含まれています。がん細胞は、時計遺伝子に異常が起こると発生することがわかってきたのです。
人間の体を構成する60兆個の細胞は、細胞分裂によって日々、新しいものへと入れ替わり、働きを維持しています。これを新陳代謝といいます。1日に新旧が入れ替わる細胞は全体の約2%です。つまり、1.2兆個もの細胞が細胞分裂によって毎日生まれていることになります。
体内時計が狂うとがんになる
これほど膨大な数の細胞が、周期的に正しく分裂を行えるのは、時計遺伝子がすべての細胞に組み込まれ、正常に働いているためです。しかし、時計遺伝子に異常が生じると、細胞が分裂するまでの周期に狂いが生じます。これが、がん細胞が発生する大きな要因のひとつだろうと考えられるようになってきたのです。
京都府立医科大学の八木田和弘教授のチームは、時計遺伝子が細胞分裂と密接にかかわっていることを研究しています。細胞内に存在する「ピリオド」という時計遺伝子は、マウスの正常な皮膚細胞では周期的に増減して、約24時間のリズムを刻んでいました。ところが、体内時計を持っていないES細胞(胚性幹細胞)では、「ピリオド」が体内時計を作ることはできませんでした。この研究によって、がん発生と体内時計の関係性についての研究がますます進むことが期待されています。
私たち人類は、体内時計を持つことができたからこそ進化をとげることができた唯一の生物種です。しかし、大半の現代人は、体内リズムには目もくれず、昼夜関係なく好き勝手な生活を送っています。大勢の人々が次々にがんで亡くなってゆく背景のひとつに、体内時計を無視した生活環境があるのは間違いないと思います。
過去の生物の歴史を見ると、体内時計を獲得できなかった生物は地球上から淘汰されています。体内時計のリズムに素直に従わない日本人が次々とがんという難病に侵されています。これは自然の営みを無視し続けている日本人に対する、地球からの警告であると私には思えてならないのです。
私たち人類は、太古の昔は時間に単位という明確な物差しを持っていませんでした。ただ、宇宙のリズムを全身で体感しながら生きてきただけだったのです。やがて人類は、文明を創造するなかで、時間の単位を構築し、単位によって時の流れを計算するようになりました。その単位を上手に使って生活を心豊かに彩りつつも、一方では、自然現象から宇宙のリズムを感じながら生きてきました。
私たちの体は、宇宙のリズムに呼応して動いています。この規則性を「サーカディアンリズム」といいます。「サーカ」とは「おおむね」、「ディアン」は「1日」という意味です。この生体リズムをコントロールしているのが、「体内時計」です。
つまり、「時間」とは、宇宙のリズムがもたらす現象であり、人が身勝手に制御できるものではないのです。だからこそ、私たちは宇宙のリズムとサーカディアンリズムに調和をもたらしてくれる体内時計に、もっと謙虚な気持ちで向き合うべきだと思うのです。
時計は、1日24時間ときっちり計算します。しかし、私たちの体内に埋め込まれたサーカディアンリズムはそうではありません。サーカディアンリズムは、「おおむね1日のリズム」で、きっちり24時間ではないのです。その理由は、地球の自転周期がだんだん延びていることにある、とされています。
地球が誕生したのは、約46億年前と考えられています。そのとき、地球の自転周期はなんと5時間だったそうです。10億年前は約 20時間、5億年前は約21時間という周期で、1日が徐々に長くなってきました。人間の祖先である霊長類が生まれた約3500万年前は、約23.5時間だったとされています。そして今は、おおむね24時間の周期で1日が繰り返されています。
このように地球の自転周期は、ほんのわずかずつですが、日々、伸びています。こうしたズレに未来永劫に対応できるように「だいたい1日」という、伸びしろの大きいサーカディアンリズムが組み込まれたと考えられます。私たち人間は、24時間11分というサーカディアンリズムを持っているのです。
光を浴びて、サーカディアンリズムをリセットする
地球上で、私たちが生きていくには地球の自転周期とサーカディアンリズムのズレを、毎日リセットしなければなりません。そのリセットの役目を果たしているのが、起床時の太陽の光です。
「早起きは三文の得」と昔から言われていました。「規則正しい生活が大事」とは、当たり前すぎるほど健康の常識ですし、早寝早起きが体調をよくすることも私たちは体験的に知っています。
しかし、なぜ早寝早起きが体によいのか考えたことがあったでしょうか。朝、太陽の光を浴びて体内時計をリズミカルに始動させることこそが、体内時計の老化を防ぐからです。体内時計が若々しくあれば、時計遺伝子は正常に働き、リズムよく活動することができるのです。
もうひとつ、サーカディアンリズムのズレをリセットする方法があります。それは、1日3度の食事を決まった時間に取ることです。
電気を獲得した現代生活では、光刺激に依存する体内時計は、どうしても崩れやすくなっています。常に強力な光を目に受けてしまう生活では、体内時計のリズムの振幅が小さくなり、活動と休息の時間のメリハリがなくなってしまうからです。しかし、3度の食事によって「腹時計」をしっかり動かすことで、たとえ体内時計が乱れてきても、食事のたびにズレをリセットできるのです。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2015年04月22日 18:00
他人(医師)に訊いても判らない腰痛の原因、、、自分の身体に訊き続ける他はない。。。
■慢性的にツライ…"腰痛"に効く5つのツボ
執筆者画像鍼灸マッサージ指圧師:青木 秀人
腰痛の原因は…?
腰痛には、
・原因を特定できる特異的なもの
・原因を特定できない非特異的なもの
の2種類があります。
特異的なものには、
・腰椎椎間板ヘルニア
・腰部脊柱管狭窄症
・腰椎分離すべり症
などがあげられます。
ぎっくり腰は「腰椎捻挫」と診断されますが、どの組織がケガしているのか医師がみても特定できないため、非特異的腰痛に分類されます。
実は「腰が痛い」という場合の約85%、つまりほとんどがこの非特異的腰痛に分類されると言われているのです。[※1]
特異的腰痛は原因が分かっているため、どこをどのように治療すればよいのか分かりますが、非特異的腰痛は決定的な原因が分からないため、治療法が確立されていません。
ただし、体幹を鍛えたり、鍼やマッサージ、ストレッチすることで腰痛の軽減、または予防することは可能です。
今回は腰痛にはこのポイントが効果的!というツボをお伝えしたいと思います。
腰痛に効く5つのツボ
腰痛に効く5つのツボを教えます!
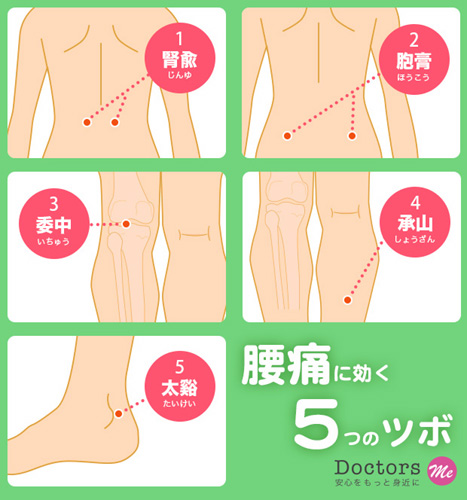
1:腎兪(じんゆ)【膀胱経】
第2腰椎棘突起の下から約指2本分外。生殖器疾患にも有効。
2:胞膏(ほうこう)【膀胱経】
第2仙椎棘突起下から指4本分外。子宮をつかさどるツボとして婦人科疾患にも有効。
3:委中(いちゅう)【膀胱経】
膝関節の裏側。横ジワ中央。腰痛の代表的なツボ。
4:承山(しょうざん)【膀胱経】
膝裏とかかとのほぼ中央。アキレス腱から指を上に滑らせとまるところ。むくみにも有効。
5:太谿(たいけい)【腎経】
内くるぶしとアキレス腱の間、動脈拍動部。水分代謝に重要なツボ。
ツボ以外で腰痛に効果的なことは?
私もひどい腰痛持ちだったのですが、必要な体幹トレーニング、ストレッチ、メンテナンスをすることで今はもうほとんど腰が痛く感じることはありません。
体を局部でみるのではなく、トータルでみることが大切かと思います。
これは「肩こり」でも述べた根本的な部分にアプローチする、ということです。
私は来院される方の体をみて、マッサージが必要なのか、トレーニングが必要なのかを判断し、様々な方法を組み合わせて治療することにしています。
何か1つだけやっても、なかなか良くならないからです。
例えば、腰痛がある人は「腹筋運動をすると良い」ということをよく聞くかと思います。
なぜ腹筋運動が腰痛に効果的なのか?
簡単に言うと、腹筋が弱まると腹圧が下がり、お腹が前に出て反り腰になり、腰に負担がかかるためです。
腹筋運動は確かに効果的な方法の1つですが、なぜ腹筋運動をすると良いのか理解する必要があります。
また、おしりや脚の筋肉が弱くても腰痛になりやすいです。ゆえに、上にあげた5つのツボのうち1つはおしり、3つは脚です。
これら例のように、腰痛は腰以外の部分も重要であり、トータルでバランスを取る必要があります。
1度きちんとした治療院で見てもらって、アドバイスをもらうのもいいかもしれませんね。
[Doctors me]
Posted by nob : 2015年04月22日 17:39
美味しいものは糖と脂肪でできているVol.2/人工甘味料のさらなる恐怖
■ゼロカロリーに潜む罠 がん、脳腫瘍、白血病の危険 砂糖より肥満リスク高い果糖ブドウ糖液糖
文=南清貴/フードプロデューサー、一般社団法人日本オーガニックレストラン協会代表理事
4月3日付当サイト記事『命を蝕む砂糖、がんや糖尿病の原因に…栄養素なく高カロリー、コカインと同様の依存性』では、缶コーヒーやペットボトルのジュースに入っている砂糖の問題についてお伝えしましたが、「砂糖が入っていないゼロカロリーの飲み物を飲んでいるから大丈夫」などと言っている人は要注意です。
ゼロカロリーの飲み物は、実は砂糖を摂取するよりもリスクが高いかもしれないからです。アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムカリウムなどの合成甘味料が、ゼロカロリーの飲み物には使われています。
アスパルテームの構成成分の一つにメタノールがあります。このメタノールは劇物に指定されており、体内でアスパルテームから分離されて吸収されますが、摂取量によっては死に至ることもあります。実際に戦後の食糧難だった時には、酒類にメタノールを混ぜて売っていたそうですが、飲んだ人が命を落としたり、失明するということが頻繁に起きたようです。
アスパルテーム入りの缶コーヒーやジュースを飲んだからといって、すぐに重大な疾患につながるわけではありませんが、そういった事実を知っておいたほうがいいでしょう。また、アスパルテームはがん、脳腫瘍や白血病との関連も強く疑われています。
スクラロースとアセスルファムカリウムは、自然界には存在しない完全な化学合成物質で、私たちの体内では分解することができません。したがって、そのまま吸収されて異物として体内をめぐり、肝臓や腎臓に多大なダメージを与え、免疫力を低下させてしまいます。
スクラロースもアセスルファムカリウムも、強い甘みがありますが、分解されて糖分が吸収されるわけではないので、カロリーとしては計算できません。これが「ゼロカロリー」の意味なのです。「カロリーがないので、体によさそう」と思う人もいるかもしれませんが、決してそうではないということを肝に銘じておきましょう。
恐ろしい高果糖コーンシロップ
さらに、私たちが日常的に口にする甘味料で注意しなければならないのが、高果糖コーンシロップです。これは異性化糖、果糖ブドウ糖液糖、あるいはブドウ糖果糖液糖などとも呼ばれます。呼び名によって、ブドウ糖や果糖の含有量などに多少の違いはありますが、ほぼ同じと考えていいでしょう。
高果糖コーンシロップは、飲み物だけでなく、スイーツ、惣菜や冷凍食品などの加工食品にも幅広く使われています。アイスコーヒーやアイスティーなどに入れるガムシロップも、この高果糖コーンシロップです。原材料はコーン、つまりとうもろこしですが、そのとうもろこしは遺伝子組み換えによって作られたものです。
高果糖コーンシロップは、実は砂糖よりも激しく血糖値を上昇させるといわれています。しかし、コストが安いため、あらゆる食品に甘みをつけるために使われているのです。血糖値の問題だけではなく、その延長線上にある肥満や糖尿病などの原因になることもあり、アメリカでは使用禁止の運動も展開されています。
ただし、果物などに含まれている果糖と、高果糖コーンシロップの甘みの主体である果糖は違うものなので、果物は安心して食べてください。果物などに含まれる果糖は、食物繊維などの働きもあり、体内にゆっくり吸収されていきます。果物には、私たちの体に必要なビタミンやミネラル、植物栄養素などが豊富に含まれており、健康的な食べ物といえます。
一方、高果糖コーンシロップは私たちの体に多大な負担をかけるので、飲み物や加工食品などを通じた取りすぎに注意したいところです。高果糖コーンシロップは低温で甘みが増すという特徴があるため、アイスクリームや清涼飲料水、冷たい菓子類などにもよく使われており、知らない間にたくさん摂取してしまう危険性もあります。
高果糖コーンシロップの日本での市場規模は、年間約800~1000億円といわれていますが、日本スターチ・糖化工業会に加盟している十数社で約 9割のシェアという寡占状態にあります。砂糖と同様に利権がからんでいるため、この問題がマスメディアで取り上げられることはほぼありません。だからこそ、私たちは自主的に高果糖コーンシロップを遠ざけなければならないのです。特に、子供たちには摂取させないような配慮が必要です。
国際糖尿病連合(IDF)の報告によると、世界の糖尿病人口は爆発的に増え続けており、2014年現在で糖尿病有病者数は3億8670万人、世界人口の8.3%が罹患しています。また、このまま有効な対策を施さないと、その数は35年までに5億9190万人に増加すると予測しています。
糖尿病の増加率は先進国で20%、発展途上国では69%にも上るといわれています。厚生労働省の発表によると、日本人の5人に1人は糖尿病およびその予備軍です。糖尿病は決して対岸の火事ではありません。糖尿病との縁を断ち切るために、まずは高果糖コーンシロップ入りの飲み物を手に取らないことから始めましょう。
[Business Journal]
Posted by nob : 2015年04月15日 15:26
美味しいものは糖と脂肪でできている/世間に蔓延する糖の恐怖
■命を蝕む砂糖、がんや糖尿病の原因に…栄養素なく高カロリー、コカインと同様の依存性
文=南清貴/フードプロデューサー、一般社団法人日本オーガニックレストラン協会代表理事
オフィスで集中して仕事をした後や、営業の外回りから戻ってきた時、退屈で長い会議が終わった時に、ホッと一息つきたくて、缶コーヒーやペットボトルのジュースを一気に飲み干した――こんな経験を持っている人も多いと思います。
しかし、その缶コーヒーやジュースにはどれくらいの砂糖が入っていて、その砂糖がどんな影響をもたらすか、というところまではあまり考えたことがないでしょう。例えば、一般的な缶コーヒーには角砂糖約3個分、「コーラ」のような清涼飲料水には同じく約10個分の糖分が入っています。
では、スポーツドリンクのほうがいいのかというと、そうでもありません。一般的なスポーツドリンクにも、角砂糖6~7個分の糖分が入っています。さらにいえば、ファーストフード店などで販売しているシェイク状のドリンクには、角砂糖20個分以上は入っているといわれています。
「砂糖の取りすぎは体によくない」という事実は知られていますが、世界保健機関(WHO)のガイドラインによると、成人および子供の1日当たりの糖類(炭水化物とは別)の摂取量は、全カロリー中の5%未満にすべきとされています。一般的な成人の1日の摂取カロリーは、1800~2200キロカロリーといわれています。仮に2000キロカロリーとした場合、その5%となると100キロカロリーで、缶コーヒー1~2本分に当たります。
計算上、缶コーヒーを2本も飲めば、その日はもう糖類を摂取できないことになってしまいます。ただし、実際にはそれで済むわけはないので、摂取カロリーに占める糖分の割合はどんどん増えてしまいます。そして、それが結果的に体に大きなダメージを与えてしまうのです。
砂糖にはカロリーはありますが、私たちの体に必要な栄養素はほとんど含まれていません。そういった食品のことを「空のカロリー」といいます。アルコール、白米や白く精製された小麦粉なども空のカロリーの一種です。一部で「空のカロリーは体内に残らないので太らない」などと考えている人もいますが、これは大きな間違いです。
必要な栄養素を含まない空のカロリーは、体内に摂り込むと大きな負担になってしまいます。カロリーがあるということは、体のエネルギー源になるということであり、なんらかの経路でブドウ糖に変化するということです。ブドウ糖がエネルギー源になるには、体内のさまざまな機能や物質を使う必要があります。
その一つが、クロムという必須ミネラルの一種です。このクロムが、細胞膜にあるブドウ糖を受け入れるドアを開ける鍵の役割をすることで、ブドウ糖を細胞の内側に取り込むことができます。砂糖(アルコールも同じ)には、クロムはまったく含まれていないので、砂糖に含まれるブドウ糖をエネルギー化するためには、他の食品から摂取したクロムを使うことになります。
つまり、砂糖はクロムを体内にもたらさないどころか、他から摂取したクロムを浪費してしまうのです。その上、エネルギー化のために必要なもうひとつの栄養素であるビタミンB1も含まれていないので、体には多くの負担がかかります。
砂糖の過剰摂取で脳機能にも変化
アメリカの保健指標評価研究所が2010年に発表した「世界疾病負荷調査報告書」によれば、糖分を含む飲み物の過剰摂取が原因とされる死亡例のうち、糖尿病は13万3000人、心血管疾患は4万4000人、がんは6000人となっています。注目すべきは、その78%が低~中所得国で発生しているということです。今、日本では貧困率の悪化が問題になっていますが、この仲間入りだけは避けたいところです。
また、アメリカのプリンストン大学で行われた、ラットを用いた実験では、砂糖を過剰摂取することによって明らかに依存性が認められた上、一度砂糖の投与をやめて再び与えた際には、以前よりも摂取量が増加したそうです。さらに、砂糖の供給を絶たれたラットはアルコールの摂取量が増え、脳機能に変化が起きていることがわかったといいます。空腹時に多量の砂糖を摂取するラットの脳内では、コカイン、モルヒネ、ニコチンなどの依存性薬物による変化と同様の神経化学的な変化が起こっていることもわかっています。
ラットの実験がそのまま人間に当てはまるわけではありませんが、まったく無視するというわけにもいかないでしょう。そもそも、無視するぐらいなら最初から実験をする意味がありません。こういったことを鑑みると、仕事の合間や息抜きに砂糖たっぷりの缶コーヒーなどを飲み干す習慣は、やめたほうがいいのではないでしょうか。
[Business Journal]
Posted by nob : 2015年04月15日 15:15
幸せとは、心の中に自ら種を蒔き大切に育んでゆくもの、、、幸せを願うも、種蒔きを始めず、不幸せに留まり続けんとする自らに気付くことから。。。
■自分にとっての幸せを見つけるヒントになる質問
99U:多くの人が「幸せを見つけることが難しい」と感じるのは、自分が幸せになるために何が必要かということについて、時間を取って真剣に考えられていないからです。
仕事で行き詰まったり、失敗してイライラしたりすると、多くの人は、その怒りの気持ちや絶望感に浸っているだけで、具体的に何を変える必要があるのか? と自分に問いかけることをしません。
ですから、幸せになるために必要なものは何かを考える時間を取ってください。そうすることで、生きるのが楽になるだけではなく、幸せであることで生産性は高まり、熱心に仕事に取り組むことができ、創造力も豊かになります。
「Thought Catalog」でKo Im氏は、自分が幸せを感じるパターンを多く見つけるのに役立つ質問を提示しています。いくつかお気に入りを紹介します。
・自分の身に起きた1番良い出来事は?
これに答えることで、幸福な記憶を思い出すだけではなく、自然に感謝の気持ちが生まれます。また、皆さんの視野の広さもわかります。その出来事は、特定の出来事ですか? それとも「生まれてきて良かった!」というような全体的なことですか?
・自分の好きな所ベスト5は?
そうです、自分で自分のことをほめちぎりましょう。
・他の人が3つの形容詞であなたを言い表すとしたら?
皆さんを表す形容詞には、良いものもイマイチなものもあるでしょう。主観的な認識と現実は相反します。大切なのは、自分を知った上で自信を持つことです。
・次の文章を完成させてください。「私の夢は○○です」
怖がらずに書いて声に出して言ってみてください。なんだったら屋根の上から叫んでください! もし、自分以外に誰も読まないし見ても聞いてもいないとしたら、空欄に何を入れますか?
何をすれば楽しくなり、心が満たされ、刺激を受けるか? といった自由回答式の問いについて考えることで、あなたが感じる幸せの尺度が明らかになります。
しかし、幸せの本当の意味とは一体何なのでしょうか? 満足感や充実感、情熱や喜び、それとも、その組み合わせでしょうか?
皆さんにとって意味のあることこそが幸せなのは1つの真理です。幸せにたどりつくためには、自分が幸せを感じ、幸せな状態を生み出してくれる物や行動が何であるかに気づくことです。まずは、上に紹介したような質問を使いながら幸せについてじっくり考える時間を作ることから始めましょう。
How To Find What Makes You Happy|99U
Allison Stadd(原文/訳:コニャック)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2015年04月11日 09:41
何もせずとも、何にもならずとも、何も持たずとも、、、明るく楽しく生きられることを知ること。。。
「自分」というものが、自分の自由にならない
これが依存している状態です
すべてがぼんやりとしており
自分が何をしてよいのか
何をしたいのかわからない
あるいは、わかっているとしても、それができない
自由に生きているという人も
ただ自分の欲に突き動かされて行動しているだけで
真に自由な心を手に入れているわけではない場合がたくさんあります
[吉田松陰]
Posted by nob : 2015年04月07日 12:32
私は何時も何事もただ成り行きに心身を委ねています。。。
■「眠れなくてもベッドに入ってたほうが良い」は嘘!眠れない時にすべき唯一のこと
睡眠コンサルタントの友野なおです。
世の中には“睡眠神話”なるものがいくつも存在していますが、そのひとつが、「眠れなくてもベッドに入っていたほうが良い」という話。皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
確かにベッドに横になっていれば体は楽ですし、さらに目を閉じていれば視覚からの情報をシャットアウトすることができるので、脳を多少なりとも休ませることが可能です。しかしそれ以上に、この行為は不眠を助長させてしまう恐れがあるので、おすすめはできません。
長時間眠れずにベッドに横になっていることで、どんどん「眠れない」ことを意識するようになり、交感神経が優位になってベッドが「リラックスモードの場所」から「戦闘モードの場所」に切り替わってしまうことも…。
こうなると、その日の晩だけでなく、翌日からも「また眠れないのでは?」という不安に襲われ、快眠を得ることが難しくなってしまうのです。
■羊を数えても眠れません
雄大な草原でのんびり暮らす羊を思い浮かべながら数を数えると入眠がサポートされそうですが、羊の数が増えれば増えるほど眠れていないことを実感してしまい、かえって焦りから入眠が妨げられることも!
そもそも、羊は英語で「シープ(sheep)」と発音するときに深く呼吸を吐くので副交感神経が優位になるとか、「シープ」と「スリープ」の発音が似ているから数えている間に眠りの暗示を自分にかけられる、などといったようなことがこの話の由来だといわれています。よって、残念ながら日本語で数えても意味はないのです。
■なかなか眠れないときの対処法
では、なかなか寝付けないときにはいったいどうすれば良いのでしょうか?
答えはとてもシンプル! ベッドに入ってから30分以上眠れない場合は、一度ベッドから出ることがベストです。ベッドから出たあとは、自然と眠気が訪れるまで本を読んだり、洗濯物をたたんだり、アイロンや靴磨きなどの単調な作業を行うのが理想的。
間違っても、眠れないからとスマホをいじったり、テレビを観たりしないように注意してくださいね。そして、少しでも眠気を感じたら速やかにベッドに戻りましょう。
「眠れない」背景にはストレスが大きく関係しているケースが多いので、日々ストレスを溜め込まぬよう、上手に発散することを心がけてください。
(文/睡眠コンサルタント・友野なお)
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2015年04月07日 12:08
語りかければ応えてくれる、、、自らの心身との対話力は日々高めてゆける。。。
■「午後の睡魔」に打ち克つには、これをしよう
ガムを噛んだりしなくても、これなら簡単
安達 純子
医療ジャーナリスト
ガムや飲み物がないとき、午後の眠気をどう振り払う?
新年度が始まった。電車に乗るとわかるが、いろいろな行事で何かと多忙なのか、お疲れ気味の人が少なくない。加えて、春のポカポカ陽気で、特に午後になると強い眠気に襲われることがある。
頭の回転はスローになり、まぶたも下がり気味。飲物があれば、ひと口飲んで眠気を吹き飛ばすことも可能だが、そういうときに限って飲み物がない。しかも、ガムや清涼菓子を気軽に口に入れられる雰囲気ではなく、こっそり手の甲をつねっても、痛みよりも眠気が勝る。さて、こんな「午後の睡魔」に対し、道具を使わずに打ち勝つ方法があるのだろうか。
日本ブレインヘルス協会理事長でもある、古賀良彦・杏林大学医学部教授(精神神経科学教室)がアドバイスする。
「生体リズムには、眠くなる時間帯が昼も夜も2時~4時で、これを睡眠圧力といいます。午後の2時~4時の会議では、眠くなりやすいのです。このとき、自律神経のひとつ交感神経を優位にすると、眠気を覚ますことは可能です。一般的に、リラックスするため副交感神経を優位にする自律訓練法は、よく聞かれるでしょう。それを逆にすると交感神経を優位にすることができます」。
古賀教授が伝授する眠気を吹き飛ばす方法は次のとおり。①心の中で「額が温かくなる~」と、自分に言い聞かせる。②次に、「お腹が冷える~」と思う。たったこれだけ。
「交感神経が優位になると、額は温かく、内臓は冷える傾向にあるのです。それを意識して心の中で自分に言い聞かせると、緊張感も高まり、眠くなりにくくなるといえます。もうひとつ、たくさん息を吸い込むことでも、交感神経を高めることは可能です。ただし、息を吸い込み過ぎると、特に若い女性は、過呼吸になりやすいので、あまりお勧めはできません」(古賀教授)。
昼休みに「目覚めの条件づけ」をする
とはいえ、「額を温かく、内臓を冷やす」、と自己暗示をかけても、簡単に眠気を吹き飛ばせない人もいるだろう。そんなときには、昼休みを活用するのが一考だ。
「人間の身体は、『条件づけ』をすることで、眠ったり、覚醒したりすることができます。朝起きたときに、歯を磨き、コーヒーを飲みながら朝食をとり、スマホなどをチェックする。これを繰り返すと、条件的に脳の覚醒が促されるようになるのです。それを昼休みにも応用すると良いでしょう」(古賀教授)。
たとえば、昼食後にコーヒーを飲み、ハミガキをして、スマホやパソコンを見る。スマホやパソコンのブルーライトには、睡眠を妨げる作用もある。その作用を最大限に活かすには、朝起きてスマホを見るときに、天気予報、通勤電車状況、ニュースなど、順番を決めておく。そのサイトを昼休みにも見るのがコツ。「朝のスマホの目覚めの儀式」を昼休みに繰り返すことで、睡眠圧力を退けることも可能になるそうだ。
「お昼休みに5分程度スマホのゲームをするのも良いでしょう。職場でスマホをチェックしづらいのであれば、ストレッチなどで身体を動かすのも効果的です。コミュニケーションと運動は、目を覚ますのに役立ちます。それでも眠気が強い場合は、20分以内の『ショートナップ』を活用しましょう。昼食を食べると、副交感神経が優位になって眠気が強くなる傾向があります。ちょっとだけ睡眠をとることで、午後の眠気を防ぐことができるのです。ただし、20分以上寝てしまうと、夜の睡眠に影響を及ぼすので注意が必要です」(古賀教授)。
昼間の睡魔をつくっている原因は何だろうか。例えば夜にスマホのSNSやゲームを行うと、前出のように睡眠を妨げる作用があり、目はギラギラ。深夜2時の睡眠圧力によって眠りにつくものの、早朝6時台の起床時間では頭がボーッとしてしまう。このような睡眠不足の状態では、昼間の眠気も強くなりがちだ。
夜しっかり眠るための条件とは?
「日本人の平均睡眠時間は6時間台と報告されています。米国の疫学調査で、7時間の睡眠時間は死亡率が低いとの結果もあるだけに、日本人は睡眠時間が短いといえます。20代~50代の睡眠障害の人も多い。しっかり目覚めるには、まずは夜の睡眠を7時間とることをお勧めします」(同)。
夜ぐっすり寝るためには、昼間の目覚めるための方法を逆にするだけだ。夕食をとり、歯を磨き、スマホは見ずに翌日の準備を整え、本を読み、音楽を聞くなどして、副交感神経を優位に導き、リラックスする。そして、布団の中で「額が涼しくなる~」「お腹が温かくなる~」と、昼間とは逆のことを繰り返すと、寝つきが良くなりやすいそうだ。
「睡眠不足の状態が続くと、食欲を増進させるホルモンの一種グレリンが分泌されやすくなり、体重が増えるだけでなく、生活習慣病などに結びつきます。不眠による糖尿病や高血圧の発症リスクは、そうでない人と比べて2倍以上といわれているのです。昼間しっかり起きるためだけでなく、健康のために毎日7時間の睡眠時間を確保するようにしましょう。また、うつ病の人の自覚症状として、不眠や食欲不振なども特徴的です。夜眠れないだけでなく、早朝覚醒といって夜中に目が覚めてしまうのです。眠りたいのに眠れないときには、一度、専門医に相談してみると良いと思います」と古賀教授はアドバイスする。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2015年04月07日 11:54
すべては幻想。。。
窓の外を見たり、なにかほかのものを見るとき、自分がなにを見てるかわかるかい?
自分自身を見てるんだ。
ものごとが、美しいとか、ロマンチックだとか、印象的とかに見えるのは、自分自身の中に、美しさや、ロマンスや、感激があるときに限るのだ。
目で見てるのは、じつは自分の頭の中を見ているのだ。
[フレデリック・ブラウン『シカゴ・ブルース』/青田勝訳]
Posted by nob : 2015年04月04日 14:51
「栄養のバランス&糖と脂肪のコントロール」が食生活の根幹。。。
■“内臓脂肪”と“代謝の低下”が原因だった?
年を取ると腹まわりから太る理由
内臓脂肪とは、文字通り内臓の周囲に分布する脂肪のこと。つまり内臓がたくさん詰まったお腹まわりは、加齢によって代謝が低下することで、いっそう脂肪がつきやすくなる部位なのだ。突き出たお腹は実年齢以上におっさん臭く見えるのでご注意!
日々の乱れた食生活や運動不足がたたり、ちょっと油断すると途端にお腹まわりがキツくなるお年頃。
それにしても、年齢を重ねるごとにお腹まわりにばかりぜい肉がつきやすくなるのは気のせいか。それとも、お腹の脂肪は実感しやすいだけで、全身まんべんなく脂肪が増えているのだろうか?
「気のせいではありません。加齢とともに腹部にばかりぜい肉がつきやすくなるのはれっきとした事実です。これは皮下脂肪の影響も当然あるのですが、どちらかといえば“内臓脂肪”が増えていることによって起こる現象なんです」
そう語るのは、新宿ライフクリニックの須田隆興先生だ。一体どういうこと?
「皮下脂肪とは別に、内臓脂肪というものがあるのはよく知られていますが、これは文字通り、腸や肝臓など内臓の周囲に分布する脂肪のこと。皮下脂肪と同じ白色脂肪(中性脂肪を溜め込む組織)で、内臓が偏在する腹部につきやすく、他の部位よりも相対的に胴まわりが肥えているケースでは、この内臓脂肪の比重が無視できません」
つまり、お腹は内臓が詰まっている場所だから、内臓脂肪もそこに溜まるという理屈だ。
「この内臓脂肪がつく要因としては、糖分の過剰摂取や運動不足などと並び、加齢が大きく影響します。代謝特性を比較した場合、内臓脂肪は皮下脂肪よりも代謝によって分解されやすい性質があるため、加齢とともに代謝そのものが低下することで、腹部の肥満につながりやすくなるわけです」
結論として、年を取るとお腹まわりから太るというのは、医学的にも根拠のある現象だった。…だからといって、「しょうがないか」とあきらめてはいけない。食生活の見直し、運動の習慣付けなど、できるかぎりの努力をしよう。
(友清 哲=取材・文)
■北嶋佳奈のビジネスマン栄養学
糖質過多で肥満や骨の老化が加速
糖質は重要なエネルギー源 肥満などをもたらすが、不足も問題 本間昭文=イラスト糖質は重要なエネルギー源 肥満などをもたらすが、不足も問題 本間昭文=イラスト
でんぷんや果物などに多く含まれる糖質は、たんぱく質、脂質と並ぶ三大栄養素のひとつで、エネルギー源として欠かせないものです。糖質を大幅に制限することには賛否がありますが、いずれにせよ摂りすぎは肥満以外にも、体に様々な悪い影響を及ぼします。
糖質はブドウ糖に変化してエネルギーになります。しかし摂りすぎると血中の中性脂肪が増えたり高血糖状態が続き、血流が悪化して肩こりなどを招きます。また、過剰な糖質と体内のタンパク質が結合することを「糖化」といい、骨の老化などが加速するといわれています。
一方、極端な糖質制限もおすすめできません。脳のエネルギーとなる糖質が不足すると、頭がぼーっとするなどの可能性があります。
1日に摂るべき糖質摂取量は、男性(18~49歳)の場合だいたい350gほどが目安といえますが、ごはん1杯(150g)だけでも55gもの糖質が含まれているので、摂りすぎに注意した食事を心がけましょう。
富永玲奈(アート・サプライ)=取材・文
■身体にまつわる都市伝説 第218回
米を食べ過ぎても糖尿病になるの?
米もうどんも、要はバランスが大切。炭水化物だけを過剰摂取することは、生活習慣病の原因になる。
米は日本人の主食。炊きたての美味しい白米にありついた時、「日本人でよかった!」としみじみ感じ入る人は少なくないはず。
しかし、炭水化物の摂り過ぎはダイエットの大敵といわれ、昨今はごはんやパン類・麺類を控えめにする人も増えてきた。うどんの消費量No.1を誇る香川県が、人口当たりの糖尿病患者数で全国ワーストなんて話を聞くと、炭水化物の摂り過ぎを心配する気持ちもわからなくはない。ただ、大好きな米を控えなければいけないのはちょっと寂しいが…。
実際のところ、炭水化物にはどのくらいのリスクがあるのだろう? 新宿ライフクリニックの須田隆興先生に聞いてみた。
「炭水化物というのは糖質ですから、過剰に摂取すれば、糖尿病をはじめとする生活習慣病の原因になるのは事実です。それは米やうどんにかぎらず、パンやソーメンなども同様。また、炭水化物を摂り過ぎて肥満化するとインスリンというホルモンの動きが悪化し、それが糖尿病の発症リスクを高めることにもなります。体調がすぐれない時など、“今日は軽めに素うどんですませよう”という人もいますが、これは生活習慣病の予防を目的とした場合、ほぼ糖質だけを摂取しているのに近いので逆効果ともいえます」
もちろん、人が活動するうえで炭水化物は重要な栄養分だが、過ぎたるは及ばざるがごとし、ということだ。
「食事において重要なのは栄養バランス。生活習慣病を予防するためには、脂質・タンパク質・炭水化物・食物繊維をバランスよく摂取し、かつ、全体のカロリー量を控えめにすることが大切なんです。その意味では、汁物やサラダ、その他のおかずとセットアップしやすいお米は、バランスさえとれていれば決して健康に悪いものではありません。また、食べる時間帯にも気をつけたいですね。朝食で摂取する炭水化物は、消費されやすく体内に蓄積されにくいですから、白米が大好物だという人は、朝の米食を習慣にしてはいかがでしょうか」
末永く美味しい食事を満喫するためにも、今のうちから肝に銘じておいた方が良さそうだ。
(友清 哲)
■食欲を抑え、メタボや肥満を予防する!
ナッツ類はダイエットの味方?
メタボの診断基準は日本とアメリカでは腹囲の基準が異なるだけで、ほかは同じ基準が用いられているメタボの診断基準は日本とアメリカでは腹囲の基準が異なるだけで、ほかは同じ基準が用いられている
「アーモンドやくるみなど、ナッツ類は美しく痩せるために摂取するといい」と、よく耳にします。どちらかというと、油分が多くてカロリーが高いイメージのナッツ類ですが、その噂は本当? 医学博士の白澤卓二先生に聞きました。
「アーモンドを食間のおやつに食べると、血糖値の上昇度合いを抑えられることが、オーストラリアとアメリカの大学の共同研究から判明しています。午前と午後のおやつに43gのアーモンドを食べたグループと食べていないグループとを比較したところ、食べたグループは血糖値の上昇度合いが抑えられていたのです」
血糖値とは、血液内に含まれるブドウ糖の値のこと。ごはんやパスタ、スイーツなどから糖質を摂取すると、体内で分解されてブドウ糖になります。ブドウ糖は生活に必要なエネルギー源ですが、糖質を摂取しすぎると血糖値が急上昇! 血糖値を下げるために、体内でインスリンが大量に分泌され、血中のブドウ糖が中性脂肪として溜めこまれてしまうそう。食間にアーモンドを食べることで血糖値の上昇を抑えられるとは、嬉しい事実です!
「ほかにも、ナッツを多く食べている人(1日平均16g)は、ほとんど食べていない人(1日平均5g)に比べ、メタボリックシンドロームの発症率が低いことが、アメリカの大学の研究からわかっています。前者は後者に比べ、メタボ発症率が32%も低かったのです」
白澤先生によると、この結果には「ナッツの食欲を抑える効果も関係している」のだとか。ナッツを食べることで、血糖値の上昇が抑えられて脂肪を溜めこまないだけでなく、そもそもの食欲を抑えるから過食を防ぐという、ダブルの効果が得られるということ!
「また、ナッツに含まれる成分も要注目です。ナッツに含まれる栄養素、オメガ3脂肪酸が動脈硬化や心臓病の予防に効果的とされるほか、健康維持に有効なファイトケミカルも豊富に含まれています」
ナッツは種類により異なる栄養成分を含んでいて、アーモンドは活性酸素を取り除くビタミンEが豊富。ピスタチオは塩分によるむくみを改善するカリウム、マカダミアナッツは糖尿病を予防するパルミトレイン酸、カシューナッツにはアンモニアなどの毒素を排出してミネラルを運ぶアスパラギン酸、ヘーゼルナッツにはイライラ解消に役立つビタミンB1が豊富。また、くるみはオメガ3脂肪酸の含有量がナッツのなかで断トツだとか。
「ナッツは1日50gほどの摂取が理想的。たくさん食べる予定があるときは、その前に食べておくといいでしょう。ひと口に15回を目安によく噛んで食べると、少量でも満腹感がありますよ」と白澤先生。ダイエットどころか、健康に長生きするためにも、ナッツを取り入れた生活は効果がありそう。小腹がすいたときは、ナッツを食べてみましょう!
(富永明子)
[いずれもwebR25]
Posted by nob : 2015年04月04日 14:35
常に体内では良性と悪性細胞増殖の鬩ぎ合いが、、、そもそも癌は病ではありません。。。
■ゲッ…拍子抜け!がん患者が増えているのは単に「日本人が●●」だから
いまや“3人に1人”がかかり、昭和56年から日本人の死因第1位になっているがん。1/3の確率ですから、誰でもなる可能性があり、もはやひとごとではありません。
ところで、なぜ日本人にがんが増え続けているのか、疑問に感じませんか?
そこで今回は、国立がんセンターがん予防・検診研究センター・センター長の津金昌一郎さんの著書『がんになる人 ならない人 科学的根拠に基づくがん予防』などを参考に、日本人にがんが増え続けている理由とそれに伴う予防法をご紹介します!
■“がんによる死亡が増え続けている”理由は?
“がんによる死亡が増え続けている”原因というと、日本人の体質変化、環境汚染、がんの悪性度が増していることなどが理由ではないか、と考える方もいらっしゃることでしょう。同著によれば、上記はいずれも科学的な根拠はなく、がんが増えている単純な理由は、“日本人が長寿になった”からとのこと。
<(略)日本でがんになる人やがんで死亡する人が多くなったのは、寿命が伸び、人口構成が高齢化していること、すなわち、がんになる確率の高い年齢層の国民が増えていることを反映しているのです。>
健康長寿はたいへん喜ばしいことですが、上記のとおり、長生きによるがんなどの病気のリスクは、今から念頭に入れておく必要がありそうです。
■日本人が80歳までにがんになる確率は?
また、同著によると、日本人が80歳までにがんになる確率は、男性で3人に1人、女性で5人に1人になるとか。
<さらに、85歳までとなると男性では2人に1人、女性では4人に1人とがんのリスクは一段と増大します。>
最新のデータを見ると、2012年の日本人の男女合わせた平均寿命は84歳で、世界長寿になっています。上記の確率を見ると、風邪を引くのと同じか、もしくはそれ以上にありふれた病なんだということがわかりますね。
■日本人のためのがん予防法!
これまでのなかで、がんは誰にでもなりうる病だということがわかりましたが、私たちが予防のためにできることって具体的に何があるのでしょうか? 国立がん研究センターがん予防・検診研究センターのHPを参考に、“日本人のためのがん予防法”をご紹介します。
(1)たばこは吸わない。他人のたばこの煙をできるだけ避ける
(2)節度のある飲酒(日本酒なら1日1合、ワインならボトル1/3程度)
(3)食塩の摂取は最小限に、野菜や果物をよく摂り、バランスの良い食生活を
(4)1日60分を目安に適度な運動を行う
(5)中高年期男性のBMI値は21~27、女性は21~25の範囲内を目指して体重管理
(6)一度は肝炎ウイルスの検査を受けること。機会があればピロリ菌の検査も
なんといっても、がん予防の最も大きな効果が期待できるのは、(1)の禁煙なんだそうですよ。たばこを吸っている人は健康のことを考え、できるだけ吸わないように心がけたいですね。
以上、日本人にがんが増え続けている理由と予防法をご紹介しましたが、いかがでしたか?
がんは老化現象により起こるものとも考えられているので、誰しも年をとれば、がんになる可能性があることになります。ですから、がんになるリスクを極力下げるためには、日ごろの地道な取り組みが重要といっても過言ではないでしょう。ご参考にしてみてくださいね。
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2015年04月04日 14:18
最強の執着は「私」/Vol.2
捨てるためには、自我が実在しなければなりません。
ですから、「自我が錯覚であることを発見しなさい」と言います。
言い換えれば、「解脱に達しなさい」という意味になります。
自我は錯覚であると発見した時点で、自我に対する執着も消えるのです。
自分を捨てる必要も、自我を捨てる必要もありません。
自我は錯覚なので、捨てられるものではありません。
しかし、「自分」という気持ちは実感なのです。
この実感は、感覚から生まれるものです。
物ごとを感じることが感覚なのです。
その感覚は、瞬間、瞬間に変わってゆくものです。
私たちは、感覚に対して「私」という言葉を使っています。
楽しい、悲しい、寂しい、羨ましい、などの言葉も、感覚を表しています。
ありのままに見る人々は、感覚は瞬間瞬間生まれては消えるものだと、原因によって感覚が現れるのだと、感覚をありのままに見ないから自我という錯覚が起こるのだと、発見するのです。
[執着の捨て方・「私」を手放して自由になる/アルボムッレ・スマナサーラ]
Posted by nob : 2015年04月04日 10:46
最強の執着は「私」
みんな誰でも「私」がいると思い込んでいますが、「私」は存在しません。
自我があるとは、科学的に証明されていません。
脳の中を調べても、自我がどこに存在しているかわかりません。
「私」というのは幻覚なのです。
身体は常に変化し続け、感情も変化し続けています。
さっきの私の身体と、今私の身体は別ものです。
さっきの心と今の心も別ものです。
身体も心も実体がありません。
だから、「私」と思い込んでいるものは、じつはすべて無常で変化し続けているもので、実体がないのです。
誰でも、こうした自分に執着しています。
実体がない錯覚とはいっても、自分に対する愛着(=執着)は捨てられませんし、捨てたくありません。
だから、強烈で最強です。
しかし、こうした「自分はいる」という「我論」があるために、そのほかのすべての執着が生まれ、すべての苦しみをつくるのです。
[執着の捨て方・「私」を手放して自由になる/アルボムッレ・スマナサーラ]
Posted by nob : 2015年04月04日 10:16
流れを変えるのは自分の行動
幸運とか不運というものは
天から無差別に降ってくるものではなく
すべて自分の方から求めているものなのです
そのことを思い出すことができれば
他人のせいにしたり
組織のあり方に腹を立てたりすることなく
「自分の行動を変えよう」
という発想に行き着くことができるはずです
[吉田松陰]
Posted by nob : 2015年04月03日 10:04
健康で暮らせてこその老人天国。。。
■都内の高齢者 10年後は「4人に1人が介護必要」 現役世代の負担激増
団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる平成37年には、東京都内の高齢者の4人に1人に介護が必要となり保険費負担が増加する。そんな推計が27日、都が公表した「都高齢者保健福祉計画」で示された。支えるためには現役世代(15~64歳)の35人に1人が介護職に従事しなければならない。だが、全国平均に比べれば、高齢化率はまだ低い水準という。
同計画は、都が平成27年度から3年間の福祉政策の指標とするために策定。今回は団塊の世代が75歳を迎える10年後の「2025年問題」に焦点を当てた。これによると、後期高齢者は5年後の32年に171万人となり、65~74歳の前期高齢者(153万人)を超過。37年には約198万人に及び、都内の人口の15%を占めるようになる。
さらに要介護認定者は27年の約57万人から20万人増の約77万人に。これは65歳以上の高齢者の24.5%にあたる数字という。
また、これに伴い、各種サービスにかかる介護保険給付費も27年度の8363億円から1兆2107億円に増加。65歳以上の都民が支払う介護保険料の平均月額は現在の4992円から、10年後には8436円に上昇する見通しという。
要介護者の増加に対応するため、都は37年までに特別養護老人ホーム1万8千人分▽介護老人保健施設9700人分▽認知症高齢者グループホーム1万600人分-を新たに整備し、10年後には17万4374人に上るとされる施設・居住系サービス利用者を受け入れる計画を示した。
一方、それを支えるためには32年度の介護人材が、同年度の生産年齢人口(15~64歳)854万人の約3%にあたる計24万7786人必要といい、学生や主婦も含めた現役世代の35人に1人がヘルパーなどの介護職に就くことが求められるという。
だが、これでも37年の都内の高齢化率は25.2%で、全国平均の30.3%よりは低い。都は「介護職員の昇級を促すキャリアパス制度などを活用し、これまでの増加率に加え、さらに年間3千人の介護従事者を確保すればいい。実現可能な数字だ」としている。
[産経ニュース]
Posted by nob : 2015年04月03日 09:58
私も普段から舌で免疫力を簡単チェックしています。。。
■「舌苔」がんリスクか 原因化合物、口中で高濃度 岡山大など発表
舌の表面にできる白い汚れ「舌苔」が多い人は、口や喉(のど)のがんの原因になるとされる化合物「アセトアルデヒド」の口中濃度が高いことを岡山大と北海道大のチームが突き止め、発表した。舌苔を取り除くと、濃度が下がることも確認しており、舌をきれいにすることが、がん予防につながる可能性があるとしている。
チームによると、舌苔は食べかすや口の中からはがれ落ちた粘膜細胞、細菌がたまったことによる汚れ。口の中が乾燥しやすいと付着しやすく、口臭の原因ともされる。
研究は健康な男女65人を対象に実施。その結果、舌苔が舌全体の3分の2以上付着した人の呼気中のアセトアルデヒド濃度は、付着が3分の1以下の人の約3倍に達していた。口の中のアセトアルデヒドは喫煙や飲酒などで発生するとされるが、チームは舌苔に含まれる細菌もアセトアルデヒドを作り出しているとみている。
チームの岡山大病院歯科医師、横井彩さんは「舌苔と発がんとの詳しい関連性や、どんな細菌が関与しているのかさらに調べたい」と話した。研究成果は海外の科学誌電子版に掲載された。
[産経ニユース]
Posted by nob : 2015年04月03日 09:48
変えるためには、まずは現状を受け容れることから、、、否定から生まれるものは新たな否定のみ。。。
■性格は、自身の個性に合ったものに変えよう 『性格は捨てられる』
「昔からの怒りっぽい性格が抜けない……」と、つい嘆いてしまうことはありませんか?
性格リフォーム心理カウンセラーの心屋仁之助氏によれば、昔は必要だった性格が必要ない今も残ってしまっていることがあるそうです。心屋氏もかつては「怒りっぽい」性格のために、周囲の多くの人を傷つけ苦しんでいたと言います。
今回は、そんな心屋氏の著書『性格は捨てられる』の中身を、「必要のない性格を変える」をテーマにして一部お伝えしていきます。
変えられる「性格」、変わらない「個性」
著書によれば、変えられないのが「個性」で、変えられるのが「性格」。そのことを著者は、料理を例にして伝えています。
例えばカレーを作るとき、まずは「今ある材料」を確認します。そして、肉・玉ねぎ・人参を鍋の中に入れて煮込みはじめます。このときの、肉・玉ねぎ・人参が「個性」です。どんな料理を作るとしても、肉が魚に、また人参がキャベツになることはありえません。
反対に、どんどん変えていけるのが味つけです。辛さや濃さなどは、教わった人やリクエストの発生などで変わっていきます。このような「料理の味つけ」が「性格」。そして料理は、素材を生かしたものが一番美味しいと話しています。
たとえ他の人の口には合わなくとも、自分の「個性」に合った自分だけの「性格」こそが、最高の味つけであると言えるのではないでしょうか?
性格を変える手段の一つ、「自分の感情に向きあう」
他人によって作られた性格を変えるには、異なる価値観や自身の弱さなどを受け入れる必要があります。そのための手段の一つが「自分の感情に向きあう」こと。ここでは、著者が薦める、ネガティブな感情の「使い方」をご紹介します。
怒り・悲しみ・嫉妬などが湧いたときは、抑えようとせず「あぁ、いま私は怒っているんだ」と収まるまで感じてみます。それでも鎮まらないときは、「くやし―!」「うらやましい―!」と、スッキリするまで大声で叫んでみましょう。
もし叫ぶ場所がないときは、抱いている感情を込めて「ふ―ーーっ!」と大きく息を何度も吐いてみてください。喜怒哀楽のエネルギーは、内に溜めすぎることで溢れたり鬱になったりしてしまいますので、こまめに出すことが大切です。
[U-NOTE]
Posted by nob : 2015年03月20日 16:20
私もこの数年実践中、、、少量の塩歯磨きペーストも使用しますが。。。
■1日1回でOK!? 「虫歯知らずの歯みがき」5つの鉄則
松尾典明
最近、こんな記事が話題になってます。
「歯磨きは1日3回」ひと昔前の常識はウソ 1回でも時間をかけることが大切–Peachy–ライブドアニュース
みなさんの歯みがきスタイルはどんな感じですか?
わが家では、今回ご紹介する歯みがきスタイルになって3年。結果的には歯の状態はとても良好で、虫歯知らずです。昨年、虫歯チェックに歯医者さんへ行った時にも「虫歯ありませんね。歯も良く磨けています」と夫婦でほめられました。
■3年前の日経の記事を読んで、スタイル変更
ちょうど今から3年前、2012年上旬に下記の2つの記事を読みました。
フッ素には一杯くわされました。| I歯科医院の高楊枝通信。–楽天ブログ
これに加えて、今までの歯医者さんに言われたことや、ちょうどその時期に参加したパパママ学級で聞いた話から、歯みがきのポイントを自分なりに出してみました。
(1)1日1回でいいから、睡眠前に汚れを徹底的に落とすことが大切
(2)歯みがきは食後、30分以上あけてから
(3)歯みがき粉はいらない
(4)強い力はいらない
(5)歯ブラシの毛は「硬い」必要まったくなし。「やわらかい」で十分に汚れは落ちる
それでは、実際にどんな感じか具体的にご紹介します。
■歯みがきは1日に1回、寝る前に時間をかけてしっかりみがく
きっかけは、先ほどの日経の記事です。
口の中が酸性になっても、唾液の力で中和されて溶けたエナメル質も復活する。ただし、30分ほど時間がかかる。食後すぐに歯をゴシゴシと磨くと軟らかくなったエナメル質を削り落としかねない。とはいえ、自分が食べた食事が酸性かどうか見分けるのは難しい。そこで「食後は歯磨きまで30分ほど置くのが安全策」(北迫助教)。
(中略)
歯を磨くタイミングだけではなく、回数についても常識は変わりつつある。よく「毎食後すぐに3分間」といわれたが、「なんとなく3回磨くよりも1日1回、特に寝る前に口の中から徹底的に汚れを出すことが大事」と鶴見大学の桃井保子教授は強調する。
「なるほど。1日1回なら(ちゃんと集中して)しっかり磨けそう」と、このスタイルでやってみようということになりました。
歯を磨く時間に関しても、「夕飯→片付け→お風呂→(歯みがき)→就寝」の流れにして、夕飯から歯磨きまで1時間以上あけています。
ただ例外的に、1日に2回以上磨くときもあります。心身が極度に疲労した時や、高熱などの体調不良の時です。
冒頭でご紹介した記事を読むとよくわかりますが、口の中を正常に保つのに欠かせないのが「唾液」です。経験則ですが、心身の不調は唾液の分泌にも影響しています。そのため、極度の疲労時や不調時など、特に昼寝する必要がある時には、その前に歯を磨きます。
■歯みがき粉はいらない
「歯みがき粉は特に必要な物ではない。むしろ、その清涼感で歯を磨いた気になって、しっかりと歯を磨けないのならいらない」
これは、歯医者さんでの歯みがき指導やパパママ学級で聞いた内容です。
そして、よく聞く「フッ素」についても、冒頭でご紹介した歯医者さんの下記記事を読んで、「必要なさそうかな」と思いました。
フッ素には一杯くわされました。| I歯科医院の高楊枝通信。–楽天ブログ
歯みがき粉を選んで買う手間やお金がかかりませんし、無駄に水を汚さなくてすむので、いいことばかりです。
■歯みがきに力はいらないし、硬い毛もいらない
これも、あらゆる情報源がそう言ってますし、磨いていてもそう感じます。子供の仕上げ磨きをやっていると特に感じます。
歯みがき粉の時もそうですが、「磨いてる感(達成感)」のようなものは、硬い毛で力を入れてゴシゴシッとしているほうが感じるかもしれませんが、歯にも歯茎にもあんまりいいことはありませんよね。
■「食のスタイル」
重要な関連項目として「食のスタイル」があげられると思います。今回取り上げた日経の記事のとおり、「酸性に偏りがちな飲食」は歯への影響がとても大きいようです。
わが家で、酸性の強い飲み物で注意するものといえば、暑い季節に大人たちがビールを飲むくらいです。さらには、食事のスタイルが「ほぼほぼベジタリアン」なのも影響しているかもしれません。
■おわり
ということで、わが家の歯みがきスタイルをご紹介しました。結果的に良い歯の状態がキープできていて、ラクちんで、お金もかからないので気に入ってます。
みなさんの歯みがきスタイルの参考になれば、嬉しいかぎりです。
[AllAbout/newsdig]
Posted by nob : 2015年03月06日 17:18
適量には個人差が、、、私の場合は、カカオ分85〜99%のチョコレート20〜25g程度を、ほぼ欠かさず毎日摂取しています。。。
■友チョコや自分用に!ビューティー志向なチョコレートの選び方
チョコレートの美容効果が注目されていますね。冷え取りやむくみの改善など、気になる効果もありますが、チョコレートのチョイスを間違えると、効果が感じられないことも……。友チョコや自分用におすすめできる、ビューティーなチョコレートの選び方をご紹介します。
■チョコレートのビューティー成分2つ
(1)エピカテキン
チョコレートの原料であるカカオ豆に含まれるポリフェノール「エピカテキン」には、血管の収縮を担う血管内皮細胞を活性化させ、血管を拡張させる効果があることが、世界各国の大学の研究で判っています。血管が拡張して血液の流れがよくなることで、冷えやむくみ、クマやくすみの改善が期待できます。
(2)テオブロミン
チョコレートの苦み成分の一つ「テオブロミン」にも、冷え取り効果があります。テオブロミンは、血管を拡張させて血流を改善して、体温を上昇させる働きがあります。また、リラックスホルモン「セロトニン」に働きかけてリラックスした状態を作る効果もあり、筋肉がリラックスした状態になることで血流がスムーズに。
■ビューティーなチョコレートの選び方3つ
(1)カカオ85%以上をチョイス
チョコレートの血流改善作用の主な成分はカカオ豆によるものですから、カカオ85%以上のチョコレートをチョイスしましょう。ローマ大学で行われた実験によれば、カカオ30%未満のミルクチョコレートでは血流の改善効果が認められなかったそうですから、カカオ含有量の高いチョコレートをチョイスして!
(2)ホワイトチョコレートはNG
ホワイトチョコレートには、カカオが含まれていません。
(3)ナッツ入りをチョイス
アーモンドに含まれるビタミンEには血管の収縮を抑えて毛細血管を広げる働きが、クルミに含まれるαリノレン酸には、血管を柔らかく保ち血流をスムーズにする働きがありますから、カカオポリフェノールとダブルで血流の改善に期待大!
カカオポリフェノールは、水溶性のため体内に蓄積されませんから、こまめに食べることが大切。ただし、カカオにはカフェインも含まれるため食べ過ぎはNG。1日50gを目安にちょこちょこ食べて、チョコレートのビューティーパワーを実感したいですね。
(岩田麻奈未)
[LIFE & BEAUTY REPORT]
Posted by nob : 2015年02月16日 09:36
自然で身体に良い食材
本当に美味しいものは
普段から食べつけていないとなかなか解らない
Posted by nob : 2015年02月12日 11:28
天然はちみつは質の高い糖質、、、トリプトファンがセロトニンに変わる点は高ポイント。。。
■1杯のハチミツが睡眠の質を上げる!
あるテレビ番組で、体重100kg以上の女性がダイエットを行っていたときのことです。その女性は、1年間順調に体重が落ちていましたが、ある時から全然減らなくなったそうです。それには、何と睡眠の質の低下に問題があることが分かったのです。ダイエット停滞期中の方は必見です!
睡眠の質を上げてダイエットも成功する就寝前の大さじ1杯のハチミツ
田井メディカルクリニックの田井祐爾(タイユウジ)院長によると、寝る前に適量のハチミツを摂取すると、質の良い睡眠が取れるそうです。ハチミツには「トリプトファン」が豊富に含まれており、摂取すると体内で「セロトニン」に変化します。
「セロトニン」は睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を促進するため、ハチミツは熟睡を助ける働きがあると考えられています。
過度の糖質制限食は禁物
ここ数年、糖質摂取を抑えるダイエットが流行っていますが、限度を超えた糖質制限食を続行していると、脳の機能を保つための糖質が不足しやすくなります。
糖質が不足すると、成長ホルモンの分泌がスムーズでなくなり、睡眠中の身体の修復作業が効率良く行われなくなる可能性があります。そのため、就寝前に適量の糖質を摂ることは奨励できますし、ハチミツは理想的です。
ハチミツ摂取の前に注意することは?
少しでも栄養のことを考えるのであれば、「天然ハチミツ」を選びましょう。なぜなら、ハチミツは減菌のための加熱処理をされると、酵素や栄養素が破壊されてしまいます。「純粋」「天然」との表記がありますが、「天然ハチミツ」なら自然の恵みをたっぷり享受できますよ。
ただし、糖尿病を患っている方は注意が必要です。「2009年 Int J Food Sci Nutr」によると、2型糖尿病患者が糖質制限を無視して食事に天然ハチミツを加えてしまうと、糖尿病は悪化してしまうのです。ですから糖尿病患者のダイエットにハチミツは厳禁なのです。
当然ながら口にするものには身体に合う、合わないはあるものです。最初は少量から続けてみてくださいね。
[ネムジム]
Posted by nob : 2015年02月12日 10:22
自分自身の生を救えるのは自分自身だけ。。。
■他人にどう思われるかを気にしないようにする4つの方法
昨年、私は人生の中でしたいことが何なのか、ぼんやりとしていました。明確ではなかったため、言い切るだけの自信はなく、また周囲の人たちに自分の陰口をたたく理由を与えるのは、正直なところ、我慢なりませんでした。
私は、人に刺激を与えたいと思っていました。世界を旅したいと思っていました。そして、今度こそジムに入会しようと思っていました。
しかし、私の目標のほとんどが、身の回りの人たちがしていることとは非常にかけ離れているように見えました。たとえ私が異なる道に進もうと試みても、彼らは耳を傾けてくれなかったでしょう。そのような時に変化が訪れました。2014年の初めに突然ひらめいたのです。周りの人がどう思うかをずっと気にして、人生を送ることなんてできないと気付いたのです。
他の人の意見を恐れないようにして、もっと自立するために変えなければならなかったことがいくつかありました。ですので、このアドバイスは、何かしたいことがあるのに他の人の意見を気にして実行に移すことができない読者の役に立つものです。
1)同じような志を持った新しい人と会う
大抵の場合、人は最も付き合いの深い5人のようになると言われています。この説では、不安が重要な要素になります。というのも、あなたと似た人と付き合うことで、本当にしたいことがずっと簡単にできるようになるからです。
ブログを始めたいと最初に思った時、ブログをしている他の人のことをまったく知りませんでした。私の当時の友人にブログをやっている人がいなかったのは確かです。ブログを始めて2、3ヶ月でこの状況は変わりました。私と非常に似通ったことを探求しているブログを運営している人たちとつながりを持ち始めたからです。そのような人たちとつながれたことと、また彼らがいつもサポートし、助言をし、同じ志を持って会話をしてくれることで、より簡単に物事を進めることができるようになりました。
これまでの友人を忘れたという訳ではありません。これまでの友人が素晴らしい友人であり、いつもそばにいてくれたのに、他の友人ができたからといって彼らをなおざりにしようなどとどうして思うでしょうか。ただ、自分と同じ波長の新しい人と会うことで、友人の視点から必要とするサポートをしてくれたり、方向性を示してくれたりしてもらえるということを心に留めておくことには価値があるというだけです。
2)身の周りから否定的な要素を取り除く
私の体験談に出てくる古くからの友人の多くは、人生に対して否定的な見方をしていたり、人のやりたいことに対してどちらかと言えば否定的な態度をとったりしていました。そのような彼らにとって、人の意見を否定することは、ごく簡単なことでした。
たとえば、ジムに入会するつもりだと初めて言った時、数人の人から胸が痛むほど笑われ、その体験を乗り越えて振り払うのには苦労しました。その後、筋骨隆々になり多くの人を驚かせましたが、彼らのもたらした否定的なイメージを人生から取り除かなければ実現できなかったでしょう。
私は自分に疑いや感情的な葛藤をもたらす人と関係を絶つことで、グループの中で簡単に自分を出せるようにし、他の人と目標を共有して気持ちよく過ごせるようにしました。
そのようにすることで、ここ数年間、非常に助かり、これまでよりずっと多くのことができるようになりました。否定的でしみったれた友人と縁を切ることは、周りの人たちの間でより自信を持ち、他の人の意見を恐れないようにする上で重要な一歩になります。
3)信頼できる友人を重視する
あなたには、おそらく異なるタイプの友人が多くいるでしょうが、特に信頼している友人は誰でもごくわずかでしょう。いつもそばにいてくれて、どんなことがあろうとあなたをサポートしてくれる人です。誰かと話したいときは、そのような信頼できる友人の所に行くべきです。彼らなら理解を示してくれて、非常に頼りになるからです。
初めて自分の考えを話し、1人の人間として自信を持ちたいと思っていた時を振り返ると、2、3人の友達1人1人と個別に話をしたものです。私は自分の目標や新しい考え、物事に対する意見などを共有し、友人は話に耳を傾けてくれて、実際に会話が盛り上がったものです。
これらの会話によって私は自信を強めました。私が話していることを理解し、異論を唱えない人もいることがわかったからです。そして私は、徐々にグループ内の他の友だちにも心を開くようになっていきました。事態が変わっていくのに時間はかかりませんでした。より快適に暮らせるようになり、私の目標が現実になり始めたのです。
まずは信頼のおける友人から始めて、徐々に他の人にも心を開くようにしていってください。初めから多くの人と会って不安を克服しようとしても無駄になります。少しずつ自信をつけてください。
4)人生を進めていくのは誰かを忘れずに
最後に覚えておいて欲しいことがあります。ほかのことより、メンタル面での課題になることですが、自分の人生を進めていくのはあなた自身だということを忘れないでください。何を選び、何をしようとも、あなたの自由です。友人はやって来ては去って行きますし、多くの人に毎日会いますが、そのほとんどとはもう会わないでしょう。
ですから、外に出て自信をつけてください。あなたの人生のあらゆる瞬間を体験するのはあなた以外の何者でもありませんし、あなたの自己評価を高く保つことは、幸せで平和な生活を送る上で常に最も重要な一歩なのですから。
このひらめきが、2014年の私にとって何よりも衝撃的なことでした。私は、上記すべてのことを実践できますし、サポートしてくれる素晴らしい友人の集まりを手に入れられます。しかし、自分の人生をコントロールするのは自分自身しかいないということを理解していなかったら、私たちは常に疑念や不安の底に囚われ、埋められているように息苦しく感じることになるでしょう。
人生において、他人の意見を気にし続ける状況を受け入れることで、やりたいことのほとんどを最終的に実行に移していないことに気付くと衝撃を覚えます。私たちは、新しい人に話しかけて拒絶されることを恐れ、自分の考えに従って動いてはダメだと言われることを恐れます。
私たち全員がこの恐怖を克服し、やりたいことをやったら、どんなに幸せになれるか考えてください。
自信を持って、幸せになり、決して他人にけなされないようにしましょう。
4 Ways To Stop Caring What Other People Think | PICK THE BRAIN
Dan Western(原文/訳:Conyac)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2015年02月09日 18:01
過ぎたるは及ばざるが如し、、、時としてすべてを失うに等しい。。。
■働き過ぎだと感じたら...休憩を取るべき5つの重要な理由
Inc:私の新年の抱負の1つが、愛する人々ともっと時間を過ごすこと、いくつかの趣味を追求する時間をもっと持つことです。というのは、8年前の起業以来、趣味をしっかり楽しむ時間が無くなってしまったからです。もう1つの抱負は、パソコンの前に座る時間を減らし、もっと動くことです。もっとも、私はワーカホリックなので、この抱負を実現し続けるのは難しいでしょうが...。
自分で事業を行っている(もしくは単に自分の仕事が大好きである)場合、おそらく年がら年中仕事をしていることでしょう。しかし、仕事以外に趣味や夢中になるものを持つのは大切なことです。会社から外へ出て、何か別のことをするのは健康的なことです。本当です、私自身、休憩を取って他のことをする 時間を作ったところ、仕事がもっとうまくいくようになったのですから。
仕事以外に趣味や夢中になるものを見つけることが必要な理由をまとめると、次のようなことが挙げられます。
1. 遅くまでずっと仕事をしていると、友人や家族と一緒にいるチャンスを失ってしまいます。彼らは関心を持たれていないと感づき、そのうち一緒に過ごして欲しいと頼むことを止めます。しまいには、皆さんが彼らと一緒に過ごそうと思った頃には、もはや必要とされなくなっているのです。
2.遅くまで仕事をしているとき、何を食べているでしょうか? テイクアウトやファストフードの類でしょう。もっと家で食事をするようにしましょう、そうすればもっと健康的な食生活が出来るようになります。
3. 遅くまで仕事をしている人は運動量が少ない傾向があります。とりわけ座って仕事をする人にとっては、運動は重要な生活の一部です。1日中コンピューターの前に座っていないで、立ち上がって動かなければなりません。時間を見つけて、必ず1日の中に何か運動を組み込みましょう。昼食の休憩時間に散歩をするだけでもかまいません。体を動かすことなら何でも意味があります。
4.趣味や夢中になれるものは良いストレス解消になります。数時間(もしくは 1日でも)仕事から離れると、ずっとリフレッシュした状態で仕事に戻れますし、困難な課題を成し遂げられる気分にもなっています。時に、物事に行き詰まったときなどは休憩するしかありません。そうすることで目の前にある答えが見つかるということもあるでしょう。
5.休憩を取らずに仕事をする人に、バーンアウト(過労やストレスによる心身の疲労)はよく起こります。そうでなくても、ひたすら働いた結果、かつては大好きだった仕事にうんざりするようになるでしょう。仕事が退屈になり、もうこれ以上やりたくないと思うようになるのです。
つまりは、ワーカホリックはもうやめにしましょう。1日20時間も働くのは体に良くありません。食事は不健康になり、座り過ぎ、さらには家族や友人との時間を失う結果となるのです。運動もせず、ビジネスに対する情熱すら失いかねません。ですから、一息ついて犬の散歩に出かけたり、子どもとキャッチボールをしたりしましょう。そうすれば、集中力が高まった状態で仕事に戻れるはずです。実際、私も息子と連れだって、数分間サーフィンレッスンを受けていますよ。
5 Important Reasons Why You Need to Take a Break|Inc
Rhett Power(訳:コニャック)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2015年01月28日 15:24
サスティナブルな運動の蓄積、、、心も身体も必ず応えてくれます。。。
■痩せるだけじゃない!運動することで得られる6つのメリット
林田玲子
「アナタは何か運動をしていますか?」という質問をすると、半数以上の方が「いいえ」と答えます。中には、「私、身体を動かすことが嫌いなのです。運動なんてもっての他です!」なんていう方もいます。
今、この記事を読まれている「アナタ」はどうでしょうか?
【運動するメリット】
運動嫌いの方の心が動く「メリット」をお話しします。
1 プロポーションの維持。
2 体脂肪が減る。
3 老化が止まる。
4 肌が綺麗になる。
5 頭が良くなる。
6 ストレス解消 等。
逆に考えれば、運動していない人は、運動している人と比較して、これらの全てが低下していく、ということです。
この中で、1、2、6は納得できても、3、4、5はあまりピンとこないかもしれませんね。
一つ一つ説明していきましょう。
【プロポーションを維持し、脂肪燃焼に有効な運動】
私は体重を落とすことよりも、綺麗になるための指導をします。体重変化よりも、綺麗になったかどうかが重要なのです。
美しい女性の裸体を想像してください。筋骨隆々で腹筋が割れている女性よりも、しなやかで適度に筋肉と脂肪がついた裸体の方に美しさを感じませんか?
つまり、マシントレーニングをするよりも、ヨガ・ルーシーダットン等の軽度でかつ、ストレッチを重視した運動をすることで「綺麗」になれます。
もちろん有酸素運動ですから、脂肪も燃焼します。スキマ時間エクササイズ=「スキマビクス」をプラスして、週1~2回これらの運動をすることで、綺麗に痩せていくことができます。
【老化が止まる運動】
老化するかどうかの鍵を握るホルモンは「成長ホルモン」です。
成長ホルモン分泌のタイミングは、運動後と睡眠時。
ですから、きちんと運動して快眠できれば老化防止できるのですね。
成長ホルモンは、無酸素運動(軽い筋トレ・スロースクワット等)で筋肉細胞を壊すことによって、分泌のスイッチが入ります。成長ホルモンには脂肪燃焼効果があり、ダイエットにもとっても重要なホルモンです。
つまり運動をすると、ダイエットしながら若さを維持できるのです。
【肌が綺麗になる理由】
運動すると汗がでますね。汗には角質をふやかして剥がしやすくするピーリング効果があります。汗と共に老廃物も排出されて、デトックス効果もあります。
さらに、運動している人はしていない人よりもコラーゲンの生成が多いと言われています。血行が促進されて、栄養や酸素が肌細胞に運ばれて美しい肌に生まれ変わっていきます。
【頭が良くなる】
運動すると、脳内で大きな変化がおこり、注意力、判断力、決断力、記憶力が向上します。さらに問題解決能力、創造性、人とコミュニケーションをとりながらものごとを実現する能力までもが向上することが、近年の研究で明らかになっています。(「ランニングで頭が良くなる」京都大学 久保田 競氏)
【ストレス解消】
運動によって、ノルアドレナリンやドーパミンなどの脳の神経伝達物質の働きがよくなり、精神的にもリフレッシュすることができます。やけ食いする理由の第一がストレスです。運動でストレスが解消されると、「やけ食い肥満」も防げそうですね。
【最後に】
運動嫌いで、ダイエットは「食事制限のみ」とお考えの方も、少しだけ運動しようかな?と思われたのではないでしょうか?
私はいつも皆さんに問いかけます。
「痩せたいの?」それとも「綺麗になりたいの?」
アナタの答えはどちらでしょうか?
(林田玲子/ハウコレ)
[ハウコレ]
Posted by nob : 2015年01月19日 10:05
同感、、、私の隠遁生活もはやもう十五年余。。。
■つながらなくたっていい、寂しいくらいでちょうどいいのだ。
森博嗣氏と言えば、昨年ドラマ化された「すべてがFになる」や、「スカイ・クロラ」などの小説を思い浮かべる方が多いのではないだろうか。本書は、その森氏が「孤独」について分析、孤独の価値を論理的に説明し、提示する本。「まえがき」によると、森氏は現在「隠れて」生活しているのだと言う。
五年ほどまえになるが、遠くへ引越をして、どこに住んでいるのかも明かさないようにした。編集者にも会わないようになった。(中略)大勢の人が集まる場所へはもともと出ていかない、一人が好きな人間だったが、それでも世間の柵(しがらみ)があり、仕事でしかたなくつき合うことも少なくなかった。そういった義理と不可抗力を一切絶ってしまったのが、今の生活の始まりである。(以上、引用)
20~40代まで猛烈に働いた末に、現在の「隠遁生活」を手に入れたという森氏。本書では「孤独は酷いものなのか」と問題提起する。それというのも「今の若者、あるいは子供たちの中には、孤独に悩み、それに押し潰されそうになっている人がいるからだ」。
「何故孤独は寂しいのか」と題された第1章では、人間は群れを成す動物である点や、幼いころから「みんなと歩調を合わせる」ことを「良い子」の条件として教え込まれる点などを指摘。孤独は寂しい、そして寂しいことはいけないこと、という通念が世間に浸透している背景を読み解く。
そして第2章「何故寂しいといけないのか」を経て、第3章の「人間には孤独が必要である」という結論に突入していく。「現代人は『絆の肥満』になっている」とも記し、最終的には、「孤独を受け入れる方法」のひとつとして、詩を作ってみることを提案している。
孤独を絶対駄目な状態だと思い込んでいるのは損というものである。それは大きな間違いだ。そんなに悪くない。むしろ、ありがたがっても良いくらい価値のあるものかもしれない、と思い直してほしい。(「あとがき」より)
全く同感だ。「つながる」などという言葉が氾濫する世の中は、薄気味が悪い。
時々耳にする言い回しを拝借するなら「人間は、寂しいぐらいがちょうどいい」のである。
(評者・スタッフN)
[honto]
Posted by nob : 2015年01月19日 09:57
相対的視点からは、、、
本質的価値は生まれない。。。
Posted by nob : 2015年01月09日 13:51
急激に血糖値をあげないようにGI値に気を配りながら多くを種類の食材をバランス良く、、、ダイエットのみならず健康食生活の基本。。。
■おやつは2回が正解!?「冬太り」解消のための新常識3つ
佐久間健一
ボディメイクトレーナー
おやつは2回が正解!?「冬太り」解消のための新常識3つ
いよいよ2015年始動! でも、お正月に食べ過ぎて少し「ふっくら」としちゃった人も多いのでは?「今すぐダイエット!」といきたいところですが、年始は仕事も忙しく、ダイエットに専念できないのが現実。そこで今回は、忙しい人でもできる、痩せやすい生活習慣を、ボディメイクトレーナーの佐久間 健一さんに伺いました。冬太りを解消したい人は必見ですよ~!
Q)冬に入ってから、すでに体重がプラス2.5kg...。ダイエットを試みるも、一度つまずくと続けられなくて...。こんな私でもどうにか痩せられる方法を教えて下さい!
A)実は、冬こそ一年のうちでもっとも痩せやすい時期! 食事のタイミングを意識するだけで「痩せ体質」に近づけることができますよ。
冬に「太りやすい」と感じる2つの理由
1.水分を摂る回数が減る
冬は水分を摂る頻度がグッと減りますよね。じつは、人間は水を飲むときに脂肪を分解するホルモンが分泌されると言われています。水分を摂らなくなると、脂肪を分解するホルモンが分泌されなくなるので、脂肪を身体に溜め込みがちに...。1日の水分は体重1kgあたり50cc(体重50kgの人なら、 1日2.5L)を摂るのが理想的です。
2.寒さで、動作が小さくなる
身体の熱は、血液を通して全身に伝わると言われているため、寒さで動作が小さくなると、どうしても身体に熱がまわりにくくなります。そうすると自然と身体も暖まりにくくなるので、脂肪が燃焼しにくい体質になってしまいます。
冬太り解消には、こまめな水分補給と運動が一番ですが、忙しい人にはなかなか難しいもの。そんな人のための、簡単に痩せ体質をつくれる習慣をご紹介したいと思います。
新習慣1:おやつを2回食べて痩せる!
甘いものが好きな女性は多いですよね。でも、ダラダラと食べたり、一度にたくさん食べるのはNG! おやつを食べるなら2回食べましょう。15時におやつを食べている場合、14時と16時に分けて食べることをオススメします。
(例)おやつにドーナツを食べる場合
14時...ナッツ類やヨーグルトなど、血糖値をゆるやかに上昇させるものを食べる
16時...ドーナツを食べる
一般的に、体内の血糖値が急激に上がると、インスリンがたくさん分泌され、身体に脂肪を貯めやすくなると言われています。食べ過ぎて、トータルのカロリーが上がってしまったら元も子もないですが、甘いおやつを食べる前にワンクッション置く事で、血糖値の上昇をゆるやかにすることができます。
新習慣2:飲み過ぎ&食べ過ぎの翌日こそ、しっかり食べる!
飲み過ぎた翌日は、お水をたっぷり飲むという方が多いのではないでしょうか? これは大正解! まずは体内のアルコールを薄めてあげることが大切なのです。さらにやって欲しいのが、朝ご飯に必ず糖質をとること。アルコールを分解するのはすべて肝臓の仕事。アルコールが体内に入ると、身体はそれを「毒」と認識します。当然、解毒作用が働きますが、その解毒に効果的なのが「糖質」。糖質を手早く摂るには、みかんやグレープフルーツなどの柑橘系がオススメ。
また「食べ過ぎた日の翌朝は、何も食べない」なんてことはありませんか? じつはそれはとっても危険な行動! 長時間食べないと、次に食事をしたときに血糖値が一気に上がって脂肪がつきやすくなってしまいます。ゆで卵など、たんぱく質を少量でも良いので食べておきましょう。
新習慣3:仕事中にもできる! 1分できる代謝アップストレッチ
最後に、忙しい人でも仕事中にできる、代謝アップストレッチをお伝えします。
1. 手を後ろでつなぎ、そのまま腕を下に伸ばす
2. 1の姿勢のまま、姿勢をピンと正して10秒キープ
3. 1と2を1分間繰り返す
オフィスでは、パソコンに向かうことが多く、つい前かがみの姿勢になりがちですよね。そうすると、使う筋肉が限られてしまい、代謝が落ちてきてしまいます。このストレッチをするだけでも、前のめりの姿勢で使わなかった部分が一気に動かされるので、血液の巡りも良くなり代謝もアップ。デスクでできる簡単なストレッチなので、気分転換にやってみてください。
ダイエットまでいかなくても、日常生活のちょっとした心掛けで、痩せ体質になることができるんです! ぜひいつものライフスタイルに取り入れてみて下さいね♪
[Beauty & Co.]
Posted by nob : 2015年01月09日 13:42
進むべき道を誤ったあなたには、引き返すもしくは放棄逃避する勇気が、、、
進むべき道を往くあなたには、眼前の1個の事象にこだわるのではなく、何か自分は別の価値を求めているんだ、という思考法が必要、、、
人はいつからでもどこからでもやりなおせる。。。
■早死したくないなら「仕事に本気にならない」ことだ
養老孟司×隈研吾 日本人はどう死ぬべきか? 第5回
清野 由美
ジャーナリスト
日本社会において血縁共同体の代わりを担った「サラリーマン共同体」。だがそれには、「死」に対しては無責任であるという欠点があった。「定年=死」という生き方を回避するための秘訣は「仕事に本気にならないこと」と養老先生は説く。「日本人はどう死ぬべきか?」最終回です!
今回の対談は、私たちにとって切実な未来である「死ぬこと」について語っていただいています。養老先生、隈さんの共通したご意見は「死ぬことを考えるのは無駄」ということでした。
そこまで達観できればいいのですが、「日経ビジネス オンライン」の読者の方々には、40代から60代男性の自殺率の増加などは、身につまされることも多いのではないかと思います。
養老:自殺は、それぞれの国によって特徴があるんですよ。
隈:そうなんですか。
養老:自殺の原因には世界的、人類的な傾向というものがあるんです。だいたい、一人当たりGDP(国内総生産)の増加と比例して自殺が増える。日本では働き盛りの中年男性の自殺が多いけれども、中国では若い女性の既婚者の自殺が多いんです。
隈:死を選ぶ理由は何なんですか。
養老:抗議の自殺ですね。嫁さんがだんなの家族に抗議して死ぬんだ。
儒教的な考え方の中で、嫁が人間扱いされないということでしょうか。
養老:詳しいことは分からないんだけど、中国では、男の子を大事にするけど、女の子は相当下に見られているでしょう。
死の恐怖から救ってくれない「サラリーマン共同体」
日本の働き盛りの男性の自殺は、1999年から一気に増加しました。養老先生はどう見ていますか。
養老:日本の世間って結構うっとうしくて、そこに丸々付き合ったらたまったものじゃないよね。でも、丸々付き合ってしまって、にっちもさっちもいかなくなるんでしょう。そういう背景があると思いますよ。
不況をバックに、中小企業経営者の自殺が増えましたが、同時に定年前後の会社員も多いと言われています。
隈:サラリーマン人生って、勝ち残りの競争の中で、すごくクリティカルな、重大な分岐点がいくつもあるじゃないですか。判断ひとつで後戻りもできないし、先にも行けないというような。あれ、みんな、よく平気だなと思いますよ。
確かに。エリートになればなるほど、過酷をきわめる。
隈:それで定年間際には、そのストレスと、自分の体力的な転換点が重なるわけだから、おかしくなってしまうのは、よく分かるな。
この連載が本になりました。『日本人はどう死ぬべきか?』2014年12月11日発売。解剖学者と建築家の師弟コンビが、ニッポン人の大問題に切り込みます。
戦後の日本では、かつての血縁共同体がサラリーマン社会に置き換えられたわけじゃないですか。前世紀のサラリーマン社会も、ここにきて変貌が激しいし、それとどう付き合うかなんて、人類として未体験ゾーンですよね。
第4回の、隈さんのお父さまのお話とつながりますね(前回参照)。隈さんは、本能的にその事態を避けた。
隈:そうですね。うちのおやじから教訓を得て、サラリーマン人生を回避した。
でも、お父さまは定年を超えて、長生きされたわけですよね。
隈:85歳まで生きました。息子である僕や、家族にいろいろ八つ当たりしたから、長生きしたと思うんですよね。毒を周りに吐き散らかしながら(笑)。
養老:医学の方から言うと、中年男性の自殺は、初老期うつ病ということはあると思いますね。これは今に始まったことではなく、昔からあるんですよ。
それは男性特有なんですか。
養老:特有ではないけれど、女性の場合はその前段階で更年期障害があるから。初老期うつ病よりも更年期障害の方が認知度が高いでしょう。その分、自覚もしやすいし、対処のしようがまだあるんだと思いますよ。
隈:日本で一番死に近いのが、僕と同年代のサラリーマンだというのは、身につまされますね。確かに僕の仕事先の会社でも、そういう例を聞きます。「え、あの、先週ご一緒した〇〇さんが?」と、驚くことがある。
いい人ほど耐え切れなくなる、ということはありますか。
養老:それは個別には分からないね。ただ、イヤなやつは死なないんだ。池井戸潤の銀行小説に出てくるような野郎どもとかはね(笑)。
思い詰めてしまっている人に向けて、何かアドバイスはありますか。
養老:言ったって無駄でしょう、その年で。
隈:ラオスに虫捕りに行きなさい、とか。
養老:そういう忠告が効く段階としては、40代後半から50代って、もう遅いんだよ。
30代から考える、老後の生き方
いつだったら間に合いますか。
養老:やっぱり30代ぐらいで考えなきゃいけないことじゃないですかね。日本の場合は、大学を出て22歳でしょう。そこで社会に入ったとして、28〜29歳で社会的適応がほぼ完成する。そこから10年たったら、40歳近く。その辺で考えなきゃいけないんじゃないですか。でも、仕事に追われて、一番考えない時期ですよね。
今、アラフォーの読者の方々は、ぜひご傾聴ください。
養老:そうね。この後、どうするんだよ、ということは一応考えていた方がいい。
当の養老先生は考えておられましたか?
養老:まあ、考えるといったって、何か行動を起こす、というわけでもないよね。僕はだいたい40代で、「55歳になったら職場は辞めよう」とは思っていたかな。
養老先生の40代は、高度成長の世の中でしたよね。
養老:そんなのは全然関係なかった、と言ってもいいですね。
みんなが仕事にまい進している時期に、養老先生が辞め時を考えることができたのは、なぜだったのですか。
養老:なぜでしょうね。やっぱり仕事にあんまり本気でなかったんだろうね。
さらっと(笑)。
養老:実は、そういう態度が大事なんじゃないかと思っている。『アンナ・カレーニナ』に、官僚だったアンナの兄貴の話が出てくるけど、彼は官僚の仕事が好きじゃなくて、本気でやってなかったから官僚として成功した、と書いてある。実際に官僚組織に勤めないと分からないけれど、確かにあれは本気で肩入れしちゃいけない仕事だと思いますよ。
日本ではメディアをあげて「仕事しろ、仕事しろ、有能であれ、有能であれ」と、日々、強迫観念を押しつけてきます。
養老:人って、あんまり働くと周りに迷惑が掛かるよ。仕事というものに対しては、適度な距離がなきゃいけない。一番いい仕事をするのは、本来は仕事に関心がない人なんです。
建築家はどうですか。
養老:建築家は違うよ、全然。組織の仕組みの中にいる人と、何かを作らなきゃいけない人は違う。
隈:ただ建築家も、一個一個の建物で傑作を作ろうとすると、ストレスで破綻すると思います。
養老:それはそうですよね。
目の前の仕事を完璧にしようとすると破綻する
隈:クライアントがいて、予算があって、法律があってと、とにかくいろいろな制約があるでしょう。その中でいちいち完璧を目指そうと思ったら、破綻します。だからある種、超越した無関心さはいるかもしれません。
超越した無関心?
隈:目の前にある1個の建物にこだわるのではなくて、何か自分は別の価値を求めているんだ、という思考法。いちいちすべてが解決するとは思わない。そういった超越性のことですね。
17世紀のイタリアに、パッラーディオという建築家がいて、当時最高の建築家と謳われていたんです。パッラーディオは、ベネツィアの郊外に邸宅の傑作をいろいろ作っていて、それが後のヨーロッパのあらゆる住宅建築のモデルになったと言われています。
でも、あれだけの建築家でも、自分は本当はこうやりたかったけど、施主の都合でできなかった、というのがほとんどなわけです。だから「建築四書」という一種の作品集を自分でまとめた時は、全部自分がやりたかったように直したの(笑)。
養老:写真がない時代だからできたんだ。
隈:20世紀最大の建築家と言われたコルビュジエはもっとひどくて、自分の作品を撮った白黒写真で、白い壁の構成がうまくなかったと思うと、周りの影にスプレーをかけて、美しくなるように修正しました。彼の作品集の写真をよく見ると、影が不自然なものが多いんです。
「フォトショップ」(写真加工など画像編集ソフト)の先駆けですね。
隈:そうそう。自分の手で行うフォトショップで写真を全部直した。建築家って、そのぐらいのずうずうしさがないと、やっていけないんです(笑)。
養老:でも、クライアントには違う言葉で接していたはずですよね。
隈:パッラーディオが設計していたのはベネツィアのお金持ちたちの農園だから、お金持ちに絶大な信頼があったわけだけど、たぶんクライアントには全然違うことをしていたはずです(笑)。
養老:あの「半沢直樹」の作者の池井戸潤さんって、銀行に勤めていたのかな。
1963年生まれで、慶應義塾大学を卒業してから、三菱銀行(現・三菱東京UFJ銀行)に勤めています。銀行を退職されたのは95年。バブルの最中から崩壊後までの時代ですね。
養老:彼も銀行の生活を、ああやって自分なりのフォトショップで書き直したんでしょうね。
隈:なるほど。
養老:銀行という組織内部のえげつない権力闘争の中で、こうあったらいい、というのが「半沢直樹」ですよね。
隈:現実では絶対にあり得ない、銀行内の下克上ですよね。
養老:あの小説とテレビドラマは、サラリーマンの健康法だよね。銀行のディテールを分かった上でのファンタジーだから、みんなに効いたんですよ。
隈:それは、さきほど養老先生がアンナ・カレーニナの兄のところでおっしゃったように、作者に「本気じゃない距離感」があったから描けたわけですよね。
養老:そう、距離があったわけですよ。銀行組織という、あの内部に丸ごと入っちゃうと、年を取ってから、もうどうしようもなくなっちゃう。
あんまり真剣になり過ぎないように、というのが養老先生のアドバイスですね。
養老:好きなことが何か1つでもあればいいんですよ。それがない人が、自分の仕事に真剣になっちゃう。でも、しょせん仕事なんて、誰かが代われるものなんだしさ。そういうことに真剣になりすぎるって、使い物にならないという、そのことだからね。
定年目前から死ぬまでにある「30年」
日本のサラリーマンは、定年を目前にして、「好きなものがない」と気が付くパターンも多いとか。
養老:そうなんですよね。ゴルフといったって、実は会社のやつとしか行ってない。しかも会計も会社持ちだったとしたら、趣味とか楽しみとかじゃなくて、業務の一環だよね。
50代で気づいても、もう遅いですか。
養老:いや、そこは断言できない。そこは知りませんよ。だって、今、みんな長生きになりましたからね。
厚生労働省が今年発表した2013年の平均寿命は、男性が80.21歳、女性が86.61歳で、男性もついに80歳を超えました。
養老:50歳から80歳まで、30年あるんだよ。モーツァルトは、35年の生涯の中で、600以上も作曲したわけだし、高杉晋作だって死んだのは28歳ぐらいだよね。
体力の問題は置いといて、革命の志士にもなれてしまう時間が目の前にある時代になりました。
隈:なんか、生きる意欲というより、もうどうなってもいいや、って思っちゃいますけどね(笑)。
養老:ともあれ、自殺は絶対にお勧めしません。死んでも当人は困りません、ということをこの対談でもさんざん言ってきましたが、周囲の人は困りますからね。自分がいなくなって悲しむ人は必ずいる。それは常に思っておいた方がいい。それと、無理心中も困りますよ。
殉死という概念に惹かれたりはしますか。
養老:典型は乃木大将でしょうけど。あれは、奥さんと一緒に自刃したんだよね。当時もいろいろ論議はあったんですけどね。息子たちが2人とも先に戦死していて、生きていてもしょうがないと思ったのか。田原坂で軍旗を取られたから、その時に死んだつもりで、というのが乃木さんの言い分だったんだけど、それを明治天皇が止めて、だったら明治天皇が生きている限りは、生きていようと。
その心境はご理解できますか?
養老:分かりませんね。
あっさり、分からない、と。隈さんはいかがですか。
隈:分からないですねえ(笑)。
あと、太宰治のように女性を道連れにして自殺未遂を繰り返すというのは、どう思われますか。
養老:あれは特別だよね。太宰は鎌倉の鶴岡八幡宮の裏山でも一度、首を吊っているんだよ。当然、失敗していますけど(笑)。
渡辺淳一じゃありませんが、心中あるいは殉死ということに、ある種あこがれるというのが、日本人の中にはあるんじゃないですか。
養老:知らない。
知らない、と。
薄くなった共同体の関係性をどう埋めるか
養老:自殺にあこがれるって、俺はよく分からないんだよね。
隈:僕も理解不能。
養老:理屈で言えば、別に本人は困らないからいいんだけど。それを生かしているのは、周りの知り合い、つまり共同体ですよね。その中に悲しむ人がいるんだから、自殺はやめてほしい。
ただ逆に言うと、共同体の関係性が薄くなってしまえば、生きる理由も薄まって、「もう死ぬよ」と言いやすくなってしまう。それは今の日本の社会に起きていることだと思います。
人間関係が薄くなれば、死ぬのは勝手でしょう、となりやすい。
養老:俺が死んでも俺は困らないし、だったら周りも困らない、という理屈が立ってしまう。しかも現代人には、命は自分のものだ、という意識があるから、ますますそうなっていくでしょう。昨今の無差別殺人の動機なんかはそれですよね。
でも、それは本当に困る。そこについては、誤解してほしくない。日本の世間は窮屈だと、僕はことあるごとに言ってきましたが、だから勝手に死んでもいい、ということではありません。「二人称の死」が持つ意味こそ、もう一度考えるべきでしょう。
養老孟司(ようろう・たけし)
1937年、鎌倉市生まれ。1962年、東京大学医学部卒業後、解剖学教室へ。1995年より同大名誉教授。著書に『からだの見方』(サントリー学芸賞)『人間科学』『唯脳論』『バカの壁』(毎日出版文化賞)『死の壁』『養老孟司の大言論』『身体巡礼』など、隈研吾との共著に『日本人はどう住まうべきか?』がある。
隈研吾(くま・けんご)
1954 年、横浜市生まれ。1979年、東京大学工学部建築学科大学院修了。米コロンビア大学客員研究員を経て、隈研吾建築都市設計事務所主宰。2009年より東京大学教授。1997年「森舞台/登米町伝統芸能伝承館」で日本建築学会賞受賞。同年「水/ガラス」でアメリカ建築家協会ベネディクタス賞受賞。2010 年「根津美術館」で毎日芸術賞受賞。2011年「梼原・木橋ミュージアム」で芸術選奨文部科学大臣賞受賞。著書に『負ける建築』『つなぐ建築』『建築家、走る』『僕の場所』、清野由美との共著に『新・都市論TOKYO』『新・ムラ論TOKYO』などがある。
[日経ビジネス]
Posted by nob : 2015年01月09日 12:22
似て非なるもの Vol.46
健康であることと
病気ではないということ
Posted by nob : 2015年01月07日 09:48
似て非なるもの Vol.45
三浦雄一郎さん、、、
肉を食べるから健康なのではなく
健康だから肉が食べられるのです。。。
Posted by nob : 2015年01月07日 09:45
人はいつからでもどこからでもやり直せる、、、直感と想像力からはじまり革新へと繋がっていく。。。
■【三浦雄一郎】「人間は150歳まで生きられる」
最高齢エベレスト登頂者が挑む“攻めの健康”
日野 なおみ
最近は、登山に挑戦したり、山岳部に属して山に挑んだりする絶対数が少なくなっています。確かに登山は、ある意味じゃあ非常に危険なきついスポーツですからね。そういう意味ではある種のチャレンジ精神が薄れている世代になりつつあるんじゃないかな。
ただ、そんな世の中でも山に挑む若い連中を見ていると、みんなテクニックや技術は素晴らしいよね。トップクラスの登山家は、今も昔と全然変わらないどころか、もっとすごい。
例えば、2013年に僕と一緒にエベレストに登った平出(和也)くんは、登山家の金メダルと言われるゴールデンピッケル賞をもらっていますし、冒険山岳カメラマンとしても一流。
僕が必死にエベレストにしがみついているところを、自分の庭みたいに跳び回っている(笑)。そういう意味では、新しい世代が次々に生まれているんでしょうね。
登山家だけじゃありません。国際的な評価を見ても、オリンピックのメダリストやノーベル賞の受賞者、国際的な学術関係のトップクラスの受賞者たちは、僕らの年代と比べてケタ違いに増えています。
僕らの時代はノーベル賞なんて、遠くて遠くて。日本人が一生取れるものじゃありませんでした。湯川秀樹さん以外、自分が生きているうちに取れる人はいないんじゃないかと思っていたら、みなさんどんどん受賞していますよね。
もちろん、単にノーベル賞を取ればいいというものじゃないでしょう。けれど科学のほかに、スポーツでも世界のトップを争うようになってきている。うれしいですね。
僕のこれまでの挑戦を振り返っても、日本人というのは、戦後の日本の復活とともに成長してきたのではないかと思います。
「松下幸之助さんが興奮した」
僕が世界で初めて、エベレストのサウスコル8000m地点からスキー滑降したのは1970年のことです。当時の僕のやっていたことというのは少し変な表現だけれど、時代のニーズといいますかね、そういうものがあったように思います。ちょうど日本が世界にチャレンジして、どんどんトップに迫りつつあった時代でしたから。
その頃、スポンサー探しでソニーの盛田(昭夫)さんや松下幸之助さん、本田宗一郎さん、サントリーの佐治(敬三)さんに会いました。みなさん、当時ちょうど世界に挑戦しようとしていた第一線の経営者たちです。
お会いしてみると、みなさん、それぞれに素晴らしい独特の個性と非常に強い好奇心を持ち、チャレンジ精神も旺盛でした。例えば松下幸之助さんというのは、非常にまじめで実直な印象をお持ちの方が多いでしょう。だけど一緒に食事をして、僕が世界で初めてエベレストをスキーで滑るんだと言ったら、松下幸之助さんは興奮して「いや、これはすごいですよ」と応援してくれた。
僕はゼロからスタートして、まったく未知の世界に飛び込んでいった。そういうフロンティア精神やチャレンジ精神に共鳴してくださったのでしょう。本田さんにお会いしても、盛田さんにお会いしても、みなさん一緒でした。佐治さんなんかはそれこそ、「おもろい、やってみなはれ」という感じで(笑)、一も二もなく応援してくれました。
全身全霊の挑戦なしには成し遂げられない命がけの目標。こういうものが、世界に挑戦して成功した起業家の人たちと同じだったのでしょう。人間、切羽詰まったり、命懸けになったりすると、いろいろな知恵が生まれますよね。それが製品にどんどん反映されて、日本企業は世界をリードできた。
応援してくれたのは経営者だけではありません。エベレストをスキー滑降した時には、石原慎太郎さんに頼んで、石原プロを総動員して映像を撮ってもらいました。ちょうど、石原裕次郎さんが「黒部の太陽」や「富士山頂」を撮っていた頃です。このフィルムが英語版になって、1976年のパリの映画祭で長編記録映画のアカデミー賞をもらったんです。
今でも僕の挑戦を応援してくれる企業は多いですね。一番の理解者であり応援者なのは、やはりサントリーの佐治さんの息子さん、信忠さんです。ほかにも、東芝さんやトヨタグループの皆さんだとか、世界を舞台に活躍する日本企業の幹部の人たちは、みなさん応援してくれています。個人的にサポートしてくれる方も大勢いらっしゃる。非常にありがたい話ですし、挑戦者を応援する文化は日本に根付いていますね。
「え、氷河がまたこんなに溶けたの」
1969年から今までエベレストを行ったり来たりしていて、今、とても気になっているのがエネルギー問題です。中でも地球の温暖化には特に胸を痛めています。
地球の温暖化が進み、海面の上昇が進行すれば、日本の土地がおよそ半分なくなるだろうというくらい、非常に危機的な状況を迎えているんです。モルディブだとかが、どんどん海底に沈んでしまう。今から防止しても間に合わないかもしれないけれども、これを止めなきゃいけないし、そのためにはクリーンエネルギーを進めていかないといけない。
僕はもう50年近くエベレストを見ていますが、登頂するたびに、温暖化の脅威を感じるんです。恐ろしいくらい氷河が後退していて。ヒマラヤの周辺には、インドも中国もあるでしょう。これらの国々はヒマラヤの水で生活をしているわけです。それなのに、氷河の水がどんどん少なくなっているんですね。僕はちょうど5年おきぐらいにエベレストに行っていますから、登るたびに「え、またこんなに溶けたの」と感じるんです。この氷河の崩壊が、いずれアジアやインド大陸の水資源の枯渇につながっていくかもしれない。
加えてアジアのいろいろな国が、ものすごい排気ガスをクルマや工場からばらまいています。ネパールでは、病院を訪れる患者の8割が呼吸器系の疾病だと聞きました。それでも病院に入れる人はいいんですけど、入れない人もたくさんいる。化石燃料に変わる新しい資源を生み出し、こうした問題を解決しないといけないんです。
「攻め」の健康があってもいい
環境問題のほかに、課題だと思っているのが、急速な高齢化社会です。日本はせっかく世界で一番の最先端高齢化社会になっているんだから、この高齢者たちにこれから、どうやって元気で活力を持って生きてもらうか。
高齢者が増えても、寝たきりだったり、介護が必要だったり、あるいは栄養補給や酸素補給に頼ったりして生きている状態なら、単に寿命が延びただけでしょう。そうじゃなくて、もう一段アクティブな「健康寿命」が大事なんじゃないかな。
守りの健康がある一方で、攻めの健康があってもいい。守るだけじゃ、どんどん年を取って年齢に負けていきますから。年を取っても富士山に登ってみようだとか、マラソンを始めてみようだとか、何かアクティブに運動する、行動する。
その点、僕の挑戦は同世代には分かりやすいと思います。
僕自身も病気をしたり、けがをしたりして、それを抱えて動いているから。だけどみなさん、病気をしたり、けがをしたりすると諦めちゃうんですよね。「ああ、もう年だし、無理だ」って。けれど、高齢者だってまだまだ挑戦できるんです。
エベレストの山頂にたどり着くと、実年齢が20歳の登山家が、90歳くらいになったように感じると言われているんです。酸素は地上の3分の1くらいしかありませんから、どうしてもパフォーマンスが出ないんですね。20歳の若者が70歳加齢されるんだから、僕が80歳でエベレストに登ると、体感年齢は150歳くらいということでしょう。実際には20歳の登山家よりもっと歳を取っていますから、本当は200歳くらいなのかもしれない(笑)。
ということは、逆に言うと、人間は150歳くらいまで生きられるのかなと思うんです。
90歳で4度目のエベレスト登頂に挑戦する
高齢化が進む日本にとって、100歳の「センチュリアン」が1つの節目になっていく。あと10年もすれば、60歳の還暦を2回祝う、120歳の「大還暦」がテーマになる時代が来ると思うんです。100歳になってもまだまだこれからだ、と。
高齢者はみんなそう思わなきゃいけないし、そうなれば、今度は個人も社会も、どうしなきゃいけないかが分かってくる。
つまり80歳というのは、人間がどんどん衰退する状態ではなく、100歳に向かってまだまだ挑戦していく年齢になる。
僕の当面の目標は、85歳でチョーユーというヒマラヤの8200m地点からスキー滑降をすることです。それを達成したら、次は90歳でエベレストに4度目のトライをしたい。
僕の一番の欠点は心臓の不整脈なんです。スポーツをやっているうちは心臓が肥大して、これが高齢になると心臓が変形しちゃう。ただ、ノーベル賞を受賞した山中伸弥さんのiPS細胞とか、再生医療も随分進歩していますよね。心臓も今、実験中だそうです。
うまく技術を生かして、若返る心臓を作れる可能性が見えています。まだ、これから10年近くありますから、他力本願だけれど、再生医療の進化を期待しながら、90歳でエベレストに登頂できる可能性があるんじゃないかと思っています。
今もまだ休んでいますが、足にはそれぞれ1.4kgのウエイトを付けていますよ。
今晩(取材時の2014年11月18日)は、これから小泉(純一郎)さんや豊田章一郎さん、御手洗(富士夫)さんを含めた財界人のパーティーが夜にあるんです。いつも通り、これにも重りを付けて参加します。いつも、そうやってうろうろしているとみんなが寄ってきて、「今日は何キロ?」なんて聞かれたりして(笑)。
「63歳で余命3年と宣言された」
実は一旦、50代後半でもうリタイアだと思っていたんですね。仲間がみんな死んでいきましたから。植村直己や加藤保男、山田昇、長谷川恒男…。僕より若い、世界に誇る登山家や冒険家が、次から次へと死んでいった。
僕は運が良かっただけだとは思うけれど、よく今まで助かったものだと感じて、60歳にリタイアしようと考えていた。
でもね、リタイアした途端に、典型的な怠け者になったんです。飲み過ぎや食べ過ぎで運動不足になってしまった。
すると63歳くらいの時に、寝ていて、気持ち悪いなと思った途端、心臓が何かにつかまれるように痛くなったんです。狭心症の発作でした。本当に危ない状態になって、病院で検査を受けたら「余命3年どころか、明日だって危ない」と言われたくらいです。
狭心症の発作以外に糖尿病も患っていたし、血圧も高くて190ぐらい。人工透析も、もうすぐというぐらいで、本当に「余命3年」と宣言されてしまった。
それで、思い切って足に重りを付けて、背中にザックを背負うようになったんですね。
1年目はそれぞれ1kgずつ、2年目から3kgずつ、3年たって5kgずつ。最後には10kgずつ、合計で30kgを背負って歩くようになりました。こうしたらメタボが完全に治って、膝の半月板損傷や腰の痛みも全部治っちゃった。
エベレストに登ってみたいという目標を立てた時、僕は走れなかったんです。だから苦し紛れに足に重りを付けてゆっくり歩き始めた。
例えば新幹線で大阪に行く場合は、(東京の)北参道にある事務所から東京駅までの約9kmの道のりを、片足5kgずつ、背中に25kgの重りを背負って歩いて行きます。ちょうど富士山に登ったのと同じくらいの運動量で、やっとの思いでふらふらしながら新幹線によじ登る。それで、トイレでびっしょり汗をかいた洋服を全部着替えていくんです。
どん底の健康状態を克服してエベレストへ
実はこのトレーニングで大失敗したことがありました。
心臓の手術を受けた2週間後にこのトレーニングをやったら、うっかり風邪をひいて熱が出て、心臓手術の前よりももっとひどくなってしまった。
とうとう病院に担ぎ込まれて、全身麻酔で電気ショックをかけられて、ぎりぎりの手術をしたんです。
それがエベレストに向けて出発するちょうど1カ月くらい前でした。リハビリにはもう失敗できないし、ベースキャンプまで行くのに時間もない。だから「今までのヒマラヤに登る常識を全部変えてやってみよう」と、1カ月かけてゆっくりと体調を整えていきました。
普段通りの健康な80歳の体でエベレストに登るのはうんと楽だったんでしょうが、そういうわけではなかったんですね。
70歳の時には狭心症発作を起こしていたし、75歳の時にはひどい不整脈を抱えていた。そして80歳の時には、やっと心臓が良くなりかけたと思ったら、直前にまた手術を受けることになった。
そのうえ76歳の時には大腿骨と骨盤を骨折しました。この時は、治っても車いすで生活できればいいだろうと言われて、さすがに再起不能だと思いました。
もうエベレストに登るなという思いや色々な迷いはあったけれど、結局は怪我を治して、ようやく本番という時に、半年前にヒマラヤへ入って虫歯がひどくなって、それが引き金になって心臓の不整脈が悪化した。
手術して不整脈が良くなりかけてきたのに、さきほど説明した東京駅で風邪をひいて、また再起不能かという状況になってしまった。1月15日に手術をして、3月に出発でしたから。
つまりどんな挑戦でも、「そういうこれがなかったらいいのに」というどん底の状況に追い込まれながらやってきたわけです。僕自身は、こちらのほうが、意味があると思っています。
「いくつになっても諦めるな」
要するに、病気であっても、けがをしても、いくつになっても諦めるなということです。可能性はいくつも開けるんだ、と。
みんな80歳を過ぎると、病気をしたりけがをしたりすると、すぐ「あ、俺はもうだめだ」って諦めるんです。
僕だって再起不能だと言われる困難に直面したことは何度もあったけど、エベレストに登ろうという目標があったから頑張れた。
国家でも企業でもそうなんですよね。夢や目標があるとチャレンジし続けます。人間だって同じでしょう。目標があれば、病気やけがも乗り越えられる。
やっぱり人間、一番大事なのはイマジネーションです。想像力というか、1つの創造性。自分はこうありたいと思うこと。
「エベレストの山頂に立ちたい、立ったらすごいだろうな」と強く思う。そうすると、その過程で何をしなきゃいけないかが見えてくるわけです。けがしたら治さなきゃいけないし、心臓がだめだったら手術してリハビリをする。あるいは、登り方を、今までと全然違う方法に変えてみるとか、それなりの工夫をする。
不可能を可能にする「3つの想像力」
つまり、あらゆるものの中に、3つの想像力があるわけです。イマジネーションとインスピレーション、それとイノベーション。
健康法の中にも当然、今までなかった方法があるだろうし、病気を治す方法にしても、病院の先生がこうだという方法だけじゃない手段もいっぱいあるんです。
僕は今だって心臓の冠動脈の65%が詰まっているんです。専門医の先生は「手術しなきゃ心臓が詰まって死ぬから、絶対にエベレスト登頂は許可しない」と言っていました。
でも65%が詰まっているということは、35%が通っているんだから、それでいこうと考えたんですね。そのうえで、血液をさらさらにする薬を処方してもらいました。
つまり、できる方法を探ればあるわけです。
僕の挑戦は、いろいろな人が喜んでくれているし、珍しがられてもいます。だからこれからも、挑戦を続けていきたいと思いますね。まずは85歳でヒマラヤをスキー滑降すること。これに向けて挑戦していきたいですね。
[日経ビジネス]
Posted by nob : 2015年01月06日 10:25
自らの身体との対話力、、、日々重ねていけば着実に向上していきます。。。
■いい睡眠は頭をほぐすことから! 自分でできる頭のマッサージ
冬も本番。寒さで、頭も身体もガチガチになっていませんか? あったかいお風呂にゆっくりつかれば、いくらか体はほぐれますよね。でも、頭をほぐすにはどうすればいいのでしょうか? いい睡眠には欠かせない頭のリラックス。こんな方法もありますよ!
不眠症の人の頭はカチカチ!?
ガチガチになった身体をほぐすには、マッサージやお風呂といった方法がすぐに思い浮かびますが、頭をほぐすってなかなか難しいですよね。
不眠に悩む人ならなおのこと、頭をリラックスさせるのは大変だと感じておられるかもしれません。
では、こんな方法を試してみるのはいかがでしょう? それは文字通り頭をほぐすこと。カイロプラクティックの先生が触ると、不眠症や自律神経失調症の人の頭皮は、すごく硬いそう。また、頭自体の温度が高く、血液や脳脊髄液の拍動が強く感じられるのだそうです。
「頭なんかカチカチなのに、どうやってほぐすの? それに、それで何が変わるの?」と思われるでしょう。実は、こうやってほぐすことができるそうなんです。
頭がい骨に覆われている脳は、触ってほぐすなんてできませんよね。でも、頭皮をほぐすことで緊張した脳もほぐすことができるそう。脳の活動状態は頭皮にも反映されるので、逆に頭皮をほぐすことで脳もほぐせるということなのです。
つまり、美容院でシャンプーしてもらうときに「あ~、気持ちいい~」と感じますよね。あれと同様の効果を作り出すということです。
頭皮マッサージでいい睡眠を!
道具はなにもいりません。入浴を済ませ、髪をしっかり乾かし、後は寝るだけの状態にしてから始めましょう。回数や強度はあくまでも自分で気持ちいいと感じる程度が目安。がんばりすぎると逆効果になります。
1.指もしくは手のひらをおでこに当て、皮膚の表面をこすらないように手を上下させる。
2.まゆ毛をしっかりつかみ、左右に動かす
3.生え際から頭頂部までを指先や手のひらを使って小刻みに上下させる
4.側面とこめかみ、耳の上を3と同様に行う
5.後頭部、首との境目も3と同様に行う
6.耳全体を、人差し指と親指ではさみほぐす
7.最後に耳を引っ張る
カチカチの頭、ほぐれましたか? アロマや音楽など、いろいろなものを組み合わせてみるのもおすすめ。リラックスタイムを充実させて、いい睡眠をとりましょう!
[ネムジム]
Posted by nob : 2015年01月05日 16:31
言わずもがな、、、“適時適量をバランス良く”に尽きます。。。
■肉を好きなだけ食べてやせる糖質制限ダイエットで死亡率上昇
ダイエット効果があると一大ブームを巻き起こしたのが「糖質制限食」だ。「炭水化物を食べなかったら1か月で8kg痩せた」、「肉と野菜をお腹いっぱい食べているのに服のサイズが13号から9号になった!」と、ダイエット成功者からは歓喜の声があがっている。しかし、この食事制限には大きなリスクがあった。
愛し野内科クリニックの岡本卓院長はそのリスクを次のように話す。
「2008年、アメリカ国立衛生研究所が発表した試験結果があります。1万人を対象にしたその試験によると、厳格な糖質コントロールを行って血糖値を下げたグループは、標準レベルの血糖コントロールを行ったグループに比べて21%も死亡率が高かったのです。
日本では、2013年に発表された聖路加国際病院内科医の能登洋先生による研究があります。約27万人のデータを分析した結果、糖質制限で糖質を1日の総摂取エネルギーの30%以下にした場合、60~70%にした場合に比べて死亡率が31%上がることがわかりました」
糖質制限によるリスクはそれだけではない。糖質だけを制限することができないことにより病気になる可能性があるという。
「糖質制限では炭水化物を控えるよう指南していますが、炭水化物を含む食べ物には糖質だけでなく食物繊維やミネラル、カルシウムなど体に必須の栄養素が含まれます。炭水化物を食べなくなることでそれらの摂取量が不足する。
また、炭水化物以外なら何を食べてもいいので、お腹を満たすために自然と肉を食べる量が増えます。ハーバード大学のデコニング博士らが4万人超を20年間追跡調査した結果、高動物性たんぱく質の食事をすると糖尿病の危険性が高くなるという論文を発表しています」(岡本院長)
また、『その「健康法」では早死にする』(扶桑社刊)著者で高須クリニック院長の高須克弥さんは、低糖質により精神状態が不安定になると指摘する。
「オーストラリアの研究チームによる報告が興味深い。24~64才の肥満の人106人を2つのグループに分け体重や精神状態の変化を1年間にわたって追跡したものです。片方は『肉、乳製品などたんぱく質や脂質を中心に摂取し、炭水化物を控える』グループ。もう片方は『炭水化物を多く食べる』グループです。食事以外は同じ減量プログラムを受けた結果、体重減少はどちらのグループも平均13.7kg。しかし精神状態については、炭水化物を控えたグループに気分の落ち込みや不安が見られたというのです」
※女性セブン2015年1月8・15日号
[Social News Network]
Posted by nob : 2015年01月03日 10:14
自らを受け容れることから始まり、、、自らを受け容れることで終わらずにまた新たに始まる。。。
■最高の人生を送るために「捨てる」べき15のコトと、「獲得したい」コト
石田陽子
ダイエットに関する情報が次々に更新されていくように、幸せな人生を送るためにもいろいろな方法が紹介されています。欧米で多くの人が共感して、話題になっているのが『最高の人生を送るために「捨てる」べき15のコト』です。
最高の人生を送るために「捨てる」べき15のコト
少し前に日本でも「断捨離」という言葉が流行りました。断捨離とは、不要なモノなどの数を減らし、生活や人生に調和をもたらそうとする生活術や処世術のこと。モノへの執着から解放され、身軽で快適な人生を手に入れようという考え方、生き方を導くものです。
『最高の人生を送るために「捨てる」べき15のコト』にある15項目を挙げてみます。
(1)「間違った人」との時間
(2)困難から逃げること
(3)自分への嘘
(4)願望を後回しにすること
(5)自分ではない誰かになろうとすること
(6)過去にしがみつくこと
(7)失敗を恐れること
(8)自分を責めること
(9)幸せを買おうとすること
(10)他人に依存すること
(11)立ち止まること
(12)無理だ、と思うこと
(13)間違った男女関係
(14)新しい恋を拒むこと
(15)他人と競うこと
つまり、自分らしく前向きに生きるためには過去や誰かにしがみつくのではなく、失敗を恐れずに自分らしく新しいことに挑戦していこう!ということです。
私は恋愛ガイドなので、数多くの恋愛の悩みを直接聞いたり、コメントを読んだり、自分でも考えたりしてきました。そして、恋愛で悩んでいる人の多くは1つのこと、一人の人にとらわれてしまっているために視野が狭くなっていることを感じてきました。あることにとらわれて、不安でいっぱいな気持ちを安定させてくれるもの、自分を安心させてくれる人を求めて狭い世界から抜け出せず、悩みがより深刻になっていくこともあります。
自分を安心させてくれるものだけを頼りに同じ場所にとどまりたいという気持ち。つらいときに無理に自分らしくない行動をとっても、傷が深くなるだけだと感じるかもしれません。
でも、私はある映像を見て、そうじゃないんだなと思いました。アフリカゾウがライオンの群れに襲われて「もうダメかも」と誰もが諦めそうな場面。きっと、ゾウも「あぁ、これホントにもうダメだ」と思う瞬間があったに違いない絶望的なピンチを迎えたとき。ゾウは最後の力をふりしぼって、鼻でライオンを追い払うように抵抗して、傷つきながらもその場から立ち去っていったのです。
生きるために何が大事かって、最後まで生き抜こうとする意志なんじゃないかと思ったんです。他人と競うためにではなく、自分が生きるために闘うこと。成人した人間は、選択肢が多いか少ないかの差はあるものの、生活する場所も付き合う相手も自分で選べます。昔は居心地が良かったけれど、今は最悪…… そのうち良くなるかもしれないと我慢して同じ生活を続けるのは自分の選択の結果です。
獲得したいのは、強く自分らしく生きるための希望を失わない心。その心を曇らせたり、間違った方向に進ませるような雑音や邪念、執着は早いうちに捨ててしまったほうがいい。捨てれば幸せになれる……という単純なことではなく、生きる希望を失わせるものを捨て、自分にとって必要なものを自分の力で獲得していくのが人生らしい……そう思いませんか?
[AllAbout newsdig]
Posted by nob : 2014年12月30日 10:39
依然続く珈琲とチョコの健康効果、、、いずれも適時適量が優◎かと。。。
■医学博士 大西睦子のそれって本当? 食・医療・健康のナゾ
チョコレートは罪な快楽?それとも健康食品?
食、医療など“健康”にまつわる情報は日々更新され、あふれています。この連載では、現在米国ボストン在住の大西睦子氏が、ハーバード大学における食事や遺伝子と病気に関する基礎研究の経験、論文や米国での状況などを交えながら、健康や医療に関するさまざまな疑問や話題を、グローバルな視点で解説していきます。
冬になると新製品が続々登場し、つい手が伸びるチョコレート。虫歯や肥満のもとなどと問題視される一方で、健康に良いという話も耳にします。実際のところはどうなのでしょうか?
ダークチョコレートやココアは、とても魅力的ですね。最近ではそのおいしさだけでなく、高血圧や心血管疾患、認知症などの予防に良い効果があるなどといった、健康面からの注目が高まっていますが、実際はどうなのでしょうか?
米国ミシシッピー大学医学部の研究者らが、2003年から2013年に発表された研究をまとめました。その報告内容をご紹介しましょう。
ポリフェノールのフラバノール?
■参考文献
US National Library of Medicine National Institutes of Health「Chocolate--guilty pleasure or healthy supplement?」
日本では高ポリフェノールをうたうさまざまなチョコレート菓子が人気になっていますが、ではポリフェノールとは何か、ご存じでしょうか?
ポリフェノールは、植物性食品の色素や香り、苦味、辛味などの化学成分である「フィトケミカル」の一種です。ポリフェノールは、すでに明らかになっているだけでも、約8000もの物質の総称です。そのなかで、化学構造に応じて、さまざまなグループに分類されています。例えば植物エストロゲンともいわれるイソフラボンやスチルベン(特に心血管疾患発症のリスクを減らし、寿命を延ばすなどと話題のレスベラトロール)、フラバノール(認知症のリスク軽減への関連などが話題)などが代表です。
このうちフラバノールが、チョコレートやココアの主原料となるカカオ豆には豊富に含まれているわけです。
カカオ豆の学名はテオブロマ・カカオ(Theobroma cacao)で、ギリシャ語の「テオ(神)」+「ブロマ(食べ物)」を合わせた言葉です。つまり「神の食べ物」という意味を持つことになります。人類がココアを消費するようになったのは紀元前1600年と言われています。16世紀にはメキシコ中央高原の国家、アステカの皇帝モンテスマが「疲れと戦う神の食べ物」だと、熱心なココア崇拝者になっていたようです。それだけ古くから愛されてきたとなると、やはりその効果には期待してしまうでしょう。
以下の表(出典:Circulation. 2009;119:1433-1441)は、主な食べ物とフラバノールの含有量です。
フラバノール含有量
(出典:Circulation. 2009;119:1433-1441)
食品 フラボノール含有量(mg/kg あるいは mg/L)
チョコレート 460-610
豆 350-550
アプリコット 100-250
チェリー 50-220
桃 50-140
ブラックベリー 130
りんご 20-120
緑茶 100-800
紅茶 60-500
赤ワイン 80-300
ではフラバノールが豊富なチョコレートやココアを摂取すると、心血管系の病気の予防になるのでしょうか?「快楽は罪ではない!」と喜んでいいのでしょうか? 残念ながら、結論を出すには少し早すぎるようなのです。もう少し深く考えてみましょう。
心血管系疾患に対する、ココア、チョコレートの影響
そもそもこの関心は、パナマ共和国のサンブラス諸島に住むクナインディアン(Kuna Indians)と呼ばれる人々の観察研究から始まりました。
クナインディアンは、加齢に伴う高血圧や動脈硬化に悩むことがありません。ただし、パナマ市とその近郊に移住したクナインディアンは、加齢とともに血圧が上昇し、高血圧の有病率は西洋人に匹敵します。実はこの差がクナインディアンの遺伝よりも、食生活、特にココアの摂取にあると、ハーバード大学医学部ノーマン·ホレンバーグ医師らが報告しました。
■参考文献
US National Library of Medicine National Institutes of Health「Hypertension, the Kuna, and the epidemiology of flavanols.」
US National Library of Medicine National Institutes of Health「Vascular action of cocoa flavanols in humans: the roots of the story.」
サンブラス諸島に住むクナインディアンは、平均して1日5杯、移住組クナインディアンの10倍の量、成分未調整のココア飲料を摂取しています。また島に住むクナインディアンは、移住したインディアンと比較すると、塩分の消費量は同等、あるいはそれ以上で、BMI(Body Mass Index:体格指数)に有意差はありませんでした。
このことから、クナインディアンがココアを摂取するという生活習慣が、彼らの健康に影響していると考えられたわけです。
フラボノールの含有量
ココアの心血管系疾患に対する予防効果は、ココアに含まれるフラバノールが、血管内皮の機能を高めるからだと考えられています。
ただしフラバノールの含有量は作物の品種タイプ、収穫後の処理、および加工技術に依存するため、同じココアでも製品によってフラバノールの比率がかなり異なるのです。
■参考文献
US National Library of Medicine National Institutes of Health「Flavanol and flavonol contents of cocoa powder products: influence of the manufacturing process.」
新鮮なカカオ豆や、醗酵したカカオ豆には、約10%のフラバノールが含まれています。
カカオ豆を加工したココアパウダーには約3.6%のフラバノールが含まれ、クナインディアンが消費しているのはこのピュアなココアパウダーです。
一方、市場にはフラバノールは苦いため西洋人の口に合わないからと、風味が調整されたものが出回っています。例えば、120℃までの高熱とアルカリ化による「ダッチング」という処理で溶けやすく味をマイルドにしたり、嗜好性を向上させるために砂糖、牛乳、バニラ、および乳化剤などを加えた、成分調整ココアが売れているのです。こうした成分調整ココアをたっぷり使ったダークチョコレートのフラバノール含有率は、わずか約0.5%です。ミルクチョコレートやホワイトチョコレートには、フラバノールは低いか含まれていません。
フラバノールが含まれていないとなれば、当然、本来のココアが持つ心血管疾患や高血圧への利点も残っていないのです。
成分調整ココアに比較すると、チョコレート菓子やココア飲料におけるココアの割合からしても、製品中のフラバノール含有量を保証するものではないと分かります。ココア70%のチョコレートバーが、製品によって全く異なるフラバノール含有量になり得るわけです。
フラバノールの作用
では、実際にチョコレートやココアを摂取すると、どのような影響があるのでしょうか? チョコレートやココアに含まれたフラバノールは、身体に良い影響を与えているのでしょうか?
[1]血圧、心血管疾患
生体内で合成され、さまざまな機能を持つ窒素酸化物の1種である一酸化窒素は、血管内皮細胞から作られます。この一酸化窒素が、血管の健康状態を維持する血管内皮機能を調節しています。フラバノール含有量の高いココアを摂取すると、一酸化窒素が増え、血管拡張(血圧低下)、血小板凝集抑制(抗動脈硬化)などにつながります。
いくつかの研究により、心血管疾患のリスク因子を有する患者さんが、フラバノール含有量の高いココアドリンク(176-185mg)を摂取すると、一酸化窒素の循環レベルが急速に、ココアドリンクを飲む前の3分の1以上、増加したと報告されています。また、ココアのフラバノールには活性酸素の発生やその働きを抑制する抗酸化効果もあり、市販のダークチョコレート(74%ココア)40g摂取の2時間後に、血液中の抗酸化状態の大幅な改善が報告されています。
また、いくつかの比較試験で、ダークチョコレートが高血圧患者の血圧に与える影響が調査されており、2003年、2005年の報告では、対象者を2群に分けて調査。ダークチョコレート100gを食べるグループと、90gのフラバノールを含まないホワイトチョコレートを食べるグループに分けた結果、ダークチョコレートを摂取したグループは、2003年時は収縮期血圧5.1+/-2.4mmHg、拡張期血圧1.8+/-2.0mmHg、2005年時は、収縮期血圧11.9+/-7.7mmHg、拡張期血圧8.5+/-5.0mmHgと、数値の低下が報告されました。ホワイトチョコレートを食べたグループは血圧が下がりませんでした。
ところが一方で、効果が認められなかったという研究も報告されてきています。
そこで2012年に、それまでの20の研究のメタ分析(複数の研究結果、研究データを計算してまとめる手法)が行われ、その結果、平均、収縮期血圧2.77mmHg、拡張期血圧2.20mmHgの低下が認められました。
一般的に、収縮期血圧3mmHgの低下で8%の脳卒中の死亡率、5%の冠動脈疾患の死亡率、4%の全死因の死亡率のリスクが低減すると推定されています。
[2]インスリン抵抗性、認知症
フラボノールは、インスリン抵抗性を減らすことが期待されています。
フラバノールが豊富なココア100gを含む食事を15日間続けた高血圧患者の調査では、インスリン抵抗性が低下したことが報告されています。インスリンは脳機能の調節に重要な役割があり、認知機能障害の一因として考えられています。
フラバノールを少なくとも520mg、毎日摂取している高齢者は、認知能力の大幅な改善を示し、インスリン抵抗性の減少との関連が分かりました。つまり、フラバノールの摂取は、心血管の健康と認知機能を改善する可能性があるのです。
[3]注意事項
ほとんどの市販のカカオ製品は、たくさん摂取すると、飽和脂肪酸や糖分により、カロリー(500kcal/100 g)の摂り過ぎになります。そして、カカオのプラスの効果を打ち消すほどの、体重増加や血糖の上昇を招きます。
[4]副作用
チョコレートは胃腸の症状、片頭痛やイライラ感を引き起こすと報告されていますが、これらの副作用は、臨床試験で実証されていません。また、チョコレートはカフェインが含まれているため、頻脈性不整脈、睡眠障害のリスクを高める可能性がありますが、普通の量を単独に摂取してもカフェインの量は問題になりません。
以上から、チョコレートは健康食品ですが、市販のチョコレートの食べ過ぎは、カロリーの過剰摂取となり、メリットがなくなります。特に肥満の方にとって、チョコレートは罪な快楽として懸念されています。
一方、バランスの取れた食事に、ヘルシーなダークチョコレートを組み合わせることは、おいしい健康食品として、おすすめですよ。
[NIKKEI TRENDY NET]
Posted by nob : 2014年12月27日 12:37
不安を怖れず受け止めんとする心が安息に繋がっていく。。。
■夜中に目が覚めて不安になった時の対処法
不安感に襲われて夜中に目が覚めてしまうのは、困ったものですね。パニックになってイライラや不安が募るし、どうにかまた寝つけたとしても、ぐっすり眠るのは難しいでしょう。でも、一睡もできないまま朝を迎えるのは、もうおしまいにしましょう。この記事では、不安感によって睡眠が妨げられるメカニズムと、その対処法を紹介します。
不安感が脳におよぼす影響とその対処法については、以前にも米Lifehackerで取り上げています。それから、全般的に睡眠の質を向上させる方法についても。今回紹介する「DNews」の動画はもう少しニッチな話で、不安を感じた瞬間の脳の反応や、そもそもの不安の引き金になるもの、睡眠中に不安が襲ってきた場合に何が起こるかについて、詳しく説明しています。
簡単にまとめると、あの急な不安感の引き金になっていたのは、生体のストレス反応でした。この反応は、いつでも予兆なしに起こりうるものです。起きてテレビを見ている時でも、夜眠っている時でもお構いなし。問題のおおもとは、私たちの無意識です。大きなプロジェクトの締切が気になっていたり、明朝に旅行に出発する予定だったりして、起きている間にストレスを感じていると、そうした直接のストレス源から解放された後でも、脳がそのパターンと似た状況に陥ることがあります。そうなると私たちの体は、ストレスのかかったパニック状態になります。その結果、せっかく何とかリラックスして眠っていたのに、夜中に目が覚めて、仕事のストレスや「飛行機に乗り遅れないようにしなきゃ」という不安に苛まれることになるのです。
こうしたストレス反応が夜中に起きると、不安感は何倍にも自己増殖します。つまり、何かのことが気になって目が覚めてしまうと、今度は「十分に眠れていないこと」自体が心配の種になって、ますます不安が募り、そのループが一晩中続いて、心身が休まらないのです。
ではどうしたら良いのでしょうか。これまでの記事で取り上げたものも含め、いくつかヒントを紹介しましょう。
* 諦めてベッドから出る:以前にも記事にしたことがありますが、ベッドにいて良いのは、寝るつもりの時か、今にも寝てしまいそうだという自覚のある時だけです。脳がベッドと睡眠欲をセットで記憶するように仕向けましょう。他のものと関連を持たせるのは好ましくありません。ですから、眠れなくてつらい時は、いっそ起き上がって、椅子に座るなり部屋を移るなりしたほうが良いのです。
* 気を紛らわす:気楽な読み物とか(明かりはほどほどに)、ホットミルクを1杯とか、軽い夜食とか(胃にたまるものや、アルコールを含むものはもちろんダメですよ)、窓の外を行き過ぎる車のライトを眺めるとか。自分にとって効果のある方法なら何でも良いのです。突発的なパニックから生まれるネガティブ思考や負の感情から、うまく気をそらしましょう。以前の記事にも書きましたが、身のまわりのものに注目して、細かく描写してみると、瞑想のような効果が得られ、心が落ち着きます。どうぞお試しあれ。
* リラックスを心がけ、リラックスした状態を保つ:口で言うほど簡単でないのは承知の上。それでも、また眠りにつくための鍵を握るのは、リラックスを心がけ、不安やパニックが少しずつ遠のくようにして、心と体をだいたい平常通りに戻すことです。この目的で瞑想をする人もいますね。汎用性のある良い方法ですが、お好みでない人は、意識的にリラックスできる自分なりの方法を探しても良いでしょう。
* 時計を見るのは我慢する:時間は確認したほうが良いと思うかもしれませんが、しないようにしましょう。時計を見るのは完全に逆効果になります。時間がどんどん過ぎていくのに、いつまでたっても眠れないと考えてしまい、ますますストレスがたまるのです。暗い中で1人、目を覚ましてしまった場合はなおさらです。
具体的にどんな方法をとるにしても、夜中の突発的な不安に対処する方法は、たいてい上記のどれかにあてはまるのではないでしょうか。
お決まりの注意書きになりますが、一晩中眠れない深刻な状態が続いたり、夜中に頻繁に目を覚ましたりするようなら、医師に相談するなどして、睡眠をチェックしてもらいましょう。何か別の要因があるかもしれませんから。その場合は、きちんと治療をすれば、もっとよく眠れるようになるでしょう。
[lifehacker]
Posted by nob : 2014年12月22日 20:58
ほおぅっ、、、そう言われてみれば確かに。。。
■一流アスリートが「朝食を食べない」理由。
実践したら、なぜかわかった
岡田真理
朝はフルーツなどを少しで十分!?
スポーツ業界で働くようになって12年。これまでいろんな選手たちの食生活を覗いてきたが、最近になってひとつ気づいたことがある。
それは、私のまわりには「朝ごはんをしっかり食べないアスリート」が多いということだ。しかも、名前は出せないが、誰でも知っているようなトップアスリートばかりだ。彼らの朝食は、思わず「そんなんでパワー出ます?」と聞きたくなるようなメニューなのだ。
朝は“排泄のための時間”らしい
多くの人は、親や学校の先生に「朝ごはんはしっかり食べなさい」と言われて育ってきたかと思う。
私自身も、「朝ごはんをしっかり食べないと力が出ないし、脳もちゃんと働かなくなって授業に集中できないよ」と教えられた記憶がある。ところが、だ。
体が資本のプロアスリートたるもの、当然しっかり朝食をとっているのだろう…と思いきや、いざ聞いてみると「青汁だけ」「ヨーグルトとフルーツだけ」「野菜ジュースだけ」「水だけ飲んで食べない」といった驚きの回答が。つまり、ほとんど食べていないのだ。(もちろん、昼と夜はその競技の特性を踏まえた栄養バランスの食事をきちんと摂っている。)
ある30代後半のベテランアスリートは「朝は体にとって排泄のための時間だから、消化器の負担を少なくするためにあまり食べないほうがいいと専属の栄養士に指導された」と言っていた。
また、別のアスリートは「試合後(夜)にたくさん食べるので朝は内臓を休ませる」ために朝はほとんど食べないのだという。
集中力アップ&体重キープでいいこと尽くめ
朝ごはんはしっかり食べるべき。朝食べないと力も出ないし頭も回らない。そう信じてきたのだが、トップアスリートたちがここまで朝ごはんを食べないので、私も試しに実践してみることにした。
今までは、朝は白いごはん一杯、お味噌汁一杯、簡単なおかずを一、二品とごく一般的な和朝食をとっていたが、それを「お水とリンゴ酢のみ」「ヨーグルトのみ」「青汁+豆乳を一杯」「フルーツのみ」などに替えてみた。
それによって何が起こったかというと、まず驚くことに、体調がすこぶるいいのである。朝ごはんを食べないと頭が回らないと思い込んでいたが、朝ごはんを軽めにしたほうが集中力もアップして原稿の進み具合がいい。
そして、以前は夜の食事会が続くとそれにともなって体重が徐々に増えていったが、朝ごはんを食べなければ前の晩に食べ過ぎてもだいたい一日で食べ過ぎ分をリセットできる(ような気がする)。そのおかげで、無理しなくても体重をキープできているのだ。
さらに、「朝は排泄の時間」と聞いていたように、朝食を食べないことで内臓の動きを排泄器官だけに集中させてあげることができるせいか、お通じも非常によい。ついでに、食費を多少カットできるというメリットもあったりする。
これらはあくまで私の個人的な実感だが、アスリートたちが朝食をあまり食べない理由を自分なりに理解することができたように思う。ただし、何事も人によるため、すべての人におすすめするわけではない。
「三食ちゃんと食べなくてはいけない」「朝ごはんはしっかり食べたほうがいい」「おなかいっぱい食べると元気が出る」というのは、もしかしたら体の本来の声とは違うのかもしれない。今回の体当たり実験を通してそんなことを感じている。
[現代ビジネス]
■チョコレートを食べて美脚!?脚の冷えとむくみを予防する食べ方
岩田 麻奈未
冬のお悩みナンバーワンと言っても過言ではない足の冷えとむくみ。足先はキンキンに冷えているのに、ふくらはぎはむくみでブーツがキツイ…… なんて経験は、どなたにでもあるのではないでしょうか? 血液の流れが滞ることで、冷えとむくみが同時に起こる場合があるのですが、なんと! 「チョコレート」を食べて脚の血流を改善できるそうですよ。
■冷えとむくみの関係
冬は外気の寒さから身体を守るように、末端の血管を収縮させて熱を逃がさないようにするため、手や足など末端部が冷えやすくなってしまいます。血液の流れが滞ると老廃物や余分な水分がスムーズに排出されず、むくみを引き起こします。水分が溜まることで、さらに冷えやすくなってしまうという悪循環に陥らないためにも、末端の血流UPが、冬の冷えとむくみを解消するポイント!
■チョコレートで脚の血流UP!?
ローマ大学で行われた実験によれば、ダークチョコレートを食べることで脚の血流が改善された、とのこと。チョコレートの原料となるカカオには、抗酸化力の強いポリフェノールが含まれており、ポリフェノールの影響で血管を拡張させて血流を促す効果のあるNO(一酸化窒素)の濃度が高まり、脚の血流が改善したのではないか、と考えられるそうです。またチョコレートに含まれるポリフェノールの一種「エピカテキン」には、血液中に存在する活性酸素を除去して血管の健康を守る効果があることが判っています。
■脚の血流をUPするチョコレートの食べ方・選び方
(1)カカオ85%以上のダークチョコレートをチョイス
先述の実験では、カカオ85%のチョコレートを40g使用しています。積極的に脚の血流を改善したい方は、カカオ85%以上のチョコレートを選びましょう。
ダークチョコレートと書かれていても、カカオ含有量の表示のないものは避けた方が無難です。
(2)ちょこちょこ食べる
ポリフェノールは水溶性のものが多く、ある程度の即効性が期待できます。ただ、持続性がないため、一度にたくさん食べるのではなく、こまめに、そして日常的に食べる習慣をつけましょう。
美味しいチョコレートで脚の血流が改善できるなんて嬉しいですよね。ブーツの多くなるこれからの季節、チョコレートを食べて冷え知らず、むくみ知らずで過ごしたいですね。
(岩田麻奈未)
[LIFE & BEAUTY REPORT]
■医師が説明する耳の正しい手入れ方法
1日のうちのかなりの時間聴覚を使って暮らしているのに、耳の正しい手入れの仕方はほとんど知りません。耳の正しい手入れと耳あかの扱いに関しては随分と誤解が多いようですから、このあたりで正しておきたいと思います。
プライマリー・ケア医のDan Weiswasser博士に、耳あかの正しい手入れの仕方をじっくりと伺いました。
綿棒を使うのをやめる
まず初めに、耳あかは外耳を感染や外傷から保護する重要な役割をしています。ある程度耳の中にある方が健康的なのです。
耳を掃除するのに綿棒を使うと、耳あかを耳道の奥へと押し込んでしまいます。悪くすると、外耳道を傷つけるか、脆い鼓膜を破裂させてしまうかもしれません。
「たいていの人は耳掃除を日常的にする必要はありません」とWeiswasser博士は言います。「私の経験では、耳あかを取れば取るほど、体は耳あかを作ってしまいます。そしてこれは悪循環につながります」耳をきれいにしないのは初めは変な感じがするかもしれませんが、耳あかを取るのをやめると、体が慣れてきて次第に耳あかができにくくなります。
一般に、あごの動きが耳あかを耳道から押し出しています。耳あかの役割は、埃と汚染菌が耳の奥に入る前に止めることですから、耳あかを取ることは害があることになります。「耳の中には肘より小さいものを入れるな」という古い諺がありますが、まさに真実かもしれません。
万が一耳に水が入っても、綿棒を使って乾かそうとしてはいけません。その代わり、ヘアードライヤーの冷風を吹き付けるか、消毒用アルコールを数滴落として、乾かすのがいいでしょう。
毎日の入浴で、耳の外側の耳あかの手入れはしています。本気で耳の外側の手入れをしたいなら、コットンボールのような短い長さのものを使いましょう。耳道の中には入れないようにしてください。
スプレーは避けて、ミネラルオイルを試してみる
過去に鼓膜を悪くしたことがないなら、頑固な耳あかを取るのには常温のミネラルオイルを使うのが一般に安全です。Weiswasser博士の説明は次の通りです。
私は一般的にミネラルオイルを使うように助言しています。ベビーオイルはミネラルオイルとほとんど同じですが、香料が入っていることが多いのです。それだと、刺激があるので、避けた方が良いです。処方箋なしで買える耳あか取りの製品もありますが、私が知る限り、有効性も安全性も証明されていません。過酸化水素は使わないように、いかなる製品も数日以上にわたっての使用はしないようにと助言しています。どちらも刺激が強すぎるからです。
耳あかで耳が詰まっていると思ったら、ミネラルオイルに浸したコットンボールを1週間に10分から20分間、耳道に入れてみてください。横に頭を傾けてコットンボールが詰まった方の耳を空に向けましょう。
医師の手による耳あかの除去か耳道の洗浄
大抵の人の場合、1カ月かそこらで耳あかの量がぐっと少なくなります。ミネラルオイルを時々使ってみた後でも、まだ耳が詰まっているような気がしたら、医師のところに行ってください。医師は専用の道具を使って耳あかを手で取り除けます。
そうでなければ、医師は針の付いていない注射器を使って水で耳道を洗浄することもできます。Weiswasser博士の経験によれば、耳の洗浄は耳道への刺激が少ないけれど、強くやり過ぎると鼓膜が破裂する危険性があるそうです。
自宅では手で耳あかを取ることも洗浄もやめてください。どちらも医師に任せてください。
刺激を受けた耳ほど耳あかができやすい
耳を触らないでおいても、まだ耳あかがたくさんあると思うなら、何か別の物が耳を刺激しているのかもしれません。たとえば、耳栓の使い過ぎではありませんか? もしくは、湿疹などの肌の状態が耳道に影響を与えているのかもしれません。
ときどきミネラルオイルを使っても、1カ月以上耳あかが極端に多い状態が続くなら、医師に相談してください。
耳が感謝してくれます
なかなか信じがたいことかもしれませんが、耳に少し耳あかがあった方が耳の健康を保てるのです。綿棒のような物で耳の中をかき回すのは止めましょう。耳あかは放っておいても大丈夫なのです。耳あかを取りたいなら、ミネラルオイルを使うか、医師に相談して手で取り除いてもらうか、洗浄をしてもらいましょう。それでもまだ、極端に耳あかがあるなら、耳の中に入れて中に触れている物がないか考えるか、別の問題がないか医師に相談しましょう。
Herbert Lui(原文/訳:春野ユリ)
[lifehacker]
Posted by nob : 2014年12月22日 20:44
私も淡々と準備を進めています。。。
■自分が死んだ後、個人情報を管理するための3つのアイデア
自分が死んだあとの情報をどうするか? あらゆる情報をデジタル化するようになった今、死後の情報管理は多くの人の関心対象です。
Q&Aサイト「Stack Exchange」では、死後の情報管理について以下のような質問が投げかけられました。
「自分の死後、銀行口座の暗証番号といった重要な情報をしかるべき人が見れるようにしたいです。生きている間は情報を秘密にしつつ、死後にのみ特定の人に情報を公開するにはどうすればよいでしょうか?」と投稿された質問に対して、寄せられた回答から3つの良いアイデアを紹介します。
1.重要な情報を記録したビデオを作り、ビデオとパスワードを人に託す
以下、Adnanさんの回答。
1年以上前、自分の人生に対する不安が膨らんでいたときに、僕は次のような行動をとりました。
1. 周囲の人々に知ってほしい情報の全てを記録したビデオを作る
2. そのビデオを「TrueCrypt」上に保存
3. ビデオを2つ複製し、最も信頼している2人の友人に渡す
4. そのビデオを開くためのパスワードを、父親と当時のガールフレンドに伝える
父親とガールフレンドには、パスワードを他人に教えないようお願いし、友人2人には、僕が死んだあと、もしくは合理的に考えて死んだと思われるときに、父親とガールフレンドにビデオを渡すように伝えました。
この手段は、身近な人々との間に、何年もかけて築いた信頼があるからこそ可能です。僕は完全に自動化されたシステムを信頼していません。たとえば、音信不通になると任意の受信者に用意したメッセージを送れるサービス「Dead Man's Switch」を使ったことがあります。ですが、死んでいないにも拘わらず何週間、あるいは何カ月か姿を消すことだってありえるのに、Dead Man's Switchではその間に起動してしまうのです。
弁護士を雇うというアイデアもあります。遺言を書き、パスワードを渡し、死亡したときにのみ公開するように伝えるのです。こうすれば、パスワードは法的に守られることになります。
2.Googleの「Inactive Account Manager」を利用する
次は、davidwebster48さんの回答より。
Googleは「Inactive Account Manager」というサービスを開始しています。これを使えば、一定期間アカウントの使用がなかった際に、特定の信頼のおける人々があなたのアカウントにアクセスできるように設定できます。未使用期間は3〜18カ月の範囲内で設定できます。
3.銀行の貸金庫を利用する
最後はpetiepoooさんの回答。
銀行の貸金庫を利用してみてはどうでしょうか。同時に、小さなカードにパスワード類とそのパスワードを使うための情報を書いておきます。カードを折り畳んでパスワードを隠し、受取人の名前とプライバシーに関する注意事項を外側に書きます。最後に、その折り畳んだカードをラミネートにかけます。
次に遺言執行人(裁判所の命令のもと、貸金庫を開けることができる人)が誰であるかを特定した遺言状を書き、そこにパスワードを書いた紙の取り扱い方についても記載しておきます。
死後の情報受取人に対しては、重要ファイルを渡しておくか、情報の入手方法について伝えておきます。もしくは、それらの情報を遺言状かパスワードを書いたカードに記しておくのもよいでしょう。
ちなみに、私は物理メディアを信頼していません。CD-ROMなどは数年経つとデータが読み取れなくなるからです。USBドライブでさえも、いつかはデータが壊れてしまいます。定期的にファイルの状態を確かめる気力があるのなら、貸金庫にUSBドライブを保管するのも良いかもしれません。または、今後継続的にに安心して使えるサービスだと感じるのであれば、オンライン上にファイルを保管することも1つの手でしょう。
とにかく、受取人が情報を入手できなくなるほどプロセスを複雑にしすぎないことが大事です。PGPのような公開鍵暗号もオススメしません。とはいっても、WinZipのようなソフトの使用を避けたいのであれば、PGPやGnuPGを使うのもありでしょう。7- Zipを使うのも良いかもしれません。無料のオープンソースですし、簡単に利用可能です。
How can I share certain information only after my death? | StackExchange
Tessa Miller(原文/訳:佐藤ゆき)
[lifehacker]
Posted by nob : 2014年12月16日 18:02
また旅立つ君へVol.83/必要なのは経験にすがる自信ではなく、自らの直感を信じる勇気。。。
■勇気と活力が湧く「心の科学」
Alubomulle Sumanasara
アルボムッレ・スマナサーラ
スリランカ上座仏教長老
人生はトラブルや苦悩、悲しみや不安に満ちています。勤務先の業績悪化、リストラの危機、愛する家族との別離、夫が鬱に、妻がガンに、子供がニートになった等々。これらの深刻な問題が、いつ自分の身にふりかかってくるかもしれません。
ブッダは生命とは何なのかと調べた結果、「苦」だという答えを出しました。私たちは幸せを求めて生きていると思っていますが、じつは「命は苦でできている」のです。なぜご飯を食べるかと言えば空腹感が苦しいから。呼吸するのも呼吸しなければ苦しいからです。すべての欲望の裏には苦があって、それが原動力となって命は動かされているのです。
あらゆる生命にとっての「苦」は、「生老病死」の4つです。すべての生命は、生まれ、老い、病み、死にます。人間には乗り越えがたい苦しみですが、それは同時に、生きることそのものでもあるのです。
人が生きるうえで、苦について徹底的に考え抜いたブッダは、こう語っています。「諸行はまさに無常である」(生じて滅びる性質を持つ。諸行はまさに無常である)。この世のすべてのものは変化する。生じて滅びるということです。変わらないものは何1つありません。
この真理を発見したブッダは、「では、我々はどうしたらいいのか?」ということについて、次のように説いています。
「生じて滅びるそれらから こころを静めるのが安楽である」。つまり、自然も会社も人も変わり続けるという真理を認め、どんな変化も当然のこととして受け容れられるようになれば、苦しみは乗り越えられ、心が安らぐというのです。
「無常」というと、暗い話を思い浮かべる人がいますが、実はそうではありません。変わり続けることは、いい悪いではなく、そういう法則だという、ただそれだけのことです。人は、子供が成長するという変化は喜ぶのに、なぜそれ以外の変化には怒るのでしょうか。社会や経済が変わるのも、病み衰え死ぬのも、雨が降り、地球が自転をするのと同じ、当たり前のことなのです。
苦しみは、無常という真理を認めようとしない心が生みだしています。たとえば、人は自分の都合のいいように、勝手に「安定」を期待します。好調な業績は今後も続くだろうと考え、結婚で得た幸せはゴールであり永遠に変わらないと思いたがり、子供がいい学校に入ったら「もう大丈夫」と安心します。しかし本当は安定などありえないのです。
ダラダラ生きていると、取り返しがつかなくなる
安定を求める私たちは、毎日の生き方において、安易に「安心感」に陥りがちです。世の中はすべてがずっと刻一刻変わり続けているのですから、私たちは毎日を注意深く生きなければなりません。今日も精一杯頑張れただろうか、何か問題は生まれていないかと十分注意を払う必要があります。仕事で業績を維持するには毎日さまざまな手を打たなければなりませんし、結婚後に家族がずっと幸せで仲良くいるためにも、毎日死ぬ瞬間まで努力し続けなければならないのです。
そのことに気づかずに、長年、毎日をダラダラと生きていると、小さな「ゴミ」が積み重なり、気づいたときには取り返しのつかない状態になっているのです。
しかし、すべては無常であり、あらゆるものは変わるのだと知れば、慢心せずに、毎日を大切に生きなければならないと気づきます。
「過去に惹かれるなかれ、未来に期待するなかれ」と、ブッダは説いています。人は往々にして現実から離れ、「夢の中」で生活しようとします。実在しない世界、つまり過去と未来に思いを馳せるのです。過去や未来のことを考えるのは妄想の中で生きるのと同じです。
ブッダはこれについて次のような意味のことを語っています。
「過去は過ぎ去ったものであり、もう存在しない。未来はまだ現れていないのだからわからない。過去の栄光を追ったり失敗を悔いたりしても意味がない、未来について心配しても仕方ないし、何かを願っても期待どおりにはならない。
過去や未来に囚われず、いま何が起こっているかを正しく観察し、動じることなく、怠らず、いまこの瞬間に行うべきことを実践しなさい。そうすれば心を煩わされることなく、解放された心で生きていられます」
これが「日々是好日」です。
この言葉は「今日はよい日だなあ」というような曖昧なものではなく、前述のようなきちんとした実践を伴った言葉なのです。「いま、ここ」に集中し、自分の力で「今日はよい日でした」と言えるような生き方をしなさいという意味なのです。
私は来日して30年になりますが、とくに昨今は「景気が悪くて大変だ。昔はよかった」と嘆く人が目立ちます。しかし、その人たちが「景気がよかった」というバブル期はどうだったでしょうか。みんな儲けるために汲々(きゅうきゅう)とし、非常に神経質で、ヒステリックな時代でした。
ふり返って「よかった」という時代も、その時代はその時代なりに大変だったのです。つまり、生きることは常に大変なのです。
人生というのはいつも緊急事態です。毎日毎日、その場でその場で、判断し対応するよう努めなければなりません。
仕事や家事をしていても、いつもイライラ焦ってしまうと悩んでいる人がいます。それは、先のことをアレコレ考えてしまうからです。あるいは、過去にできなかったことを思い悩んだりしているからです。「やらなければならない」ことを妄想していては、キリがありません。
また、私たちは希望をもちたがります。将来のことはどうなるかわからないのに、あれこれ未来を想像し、専門家にも予測を求めます。予測することで安心したいのです。しかし実際は予測どおりになるわけはなく、予測が外れた、希望が裏切られたといって怒り、落ち込むのです。
私たちは、現実的には「いま」の瞬間だけを生きています。何をするにしても、いまこの瞬間にすべきこと以外はできません。何をすべきか、どの課題に集中すべきかということは、「いま、ここ」のことならはっきりわかるはず。過去を悔やんだり、未来の心配をしなければ、解決方法を発見し、それを実行することも容易にできるのです。
常に、いまやるべきことに取り組めば焦りは生まれません。仕事や家事なら、たとえば十分刻みで、そのとき必要なことを順々にこなしていけばいいのです。いまの10分より先の10分は存在せず、過ぎてしまった過去の10分も存在しないのです。現実に存在する、いまこの10分で、やるべきことを精一杯やるしかないのです。やり遂げればその度に喜びが生まれます。その小さなユニットを繋げることを人生とすればいいのです。
人は「生きる意味は何か」と問いたがりますが、意味はありません。問う必要もないのです。とにかく生きる。ただ、その瞬間をしっかり生きるだけです。
流れに逆らわず、適切に身を守る
すべてのものが変化する、無常の世の中。そこで生きるのは、たとえてみれば私たちはみな川に流されているということです。では、その激流を、どう渡ればいいのでしょうか。
問われたブッダはこう答えています。
「私は、立ち止まることなしに、あがくことなしに、激流を渡ったのです」
何もせずに立ち止まっていたら沈んでしまいますし、激流に逆らって泳ごうと暴れれば溺れてしまいます。波に合わせて流してもらうことで、うまく渡ればいいのです。岩にぶつかりそうになったときは、ちゃんと手を打って身を守る。流れの緩い場所になったら泳いでなるべく岸に近づく。また流れが激しくなったら、泳ぐのを止めて流される。そのように人生を調整し、操縦しながら進めていけばいいと語っています。
「立ち止まりもせず、あがきもせず」という微妙な調整です。川の流れに応じてその場でテキパキと的確に判断しなければなりません。そのためにも、先に述べたように、過去や未来に囚われず、つまり頭の中に余計な妄想を描いていないで、「いま、ここ」をしっかり生きることが大切なのです。
私にとってブッダの言葉はすべて大切ですが、その中でも多くの人に知ってほしいと思っているのは次の言葉です。「本当の宝物は知恵である」。
知恵をもっている人は、世界を偏見なしに、軽々と面白がってとらえます。ところが、この知恵を妨げるのが「感情の毒」なのです。怒りや見栄、エゴ、嫉妬など感情のウイルスに汚染されると、脳がうまく活動しません。あれやこれやとややこしく考えてしまうのは、感情のために脳の活動がストップしてしまっている証拠です。
知恵をもっている人は、性格も謙虚になり、物事をシンプルに思考します。たとえば仕事で自分の提案がうまく採用されなかったり、あるいは仕事でミスをしてしまった場合。どうしても自分の面子や感情が入ってしまうかもしれません。しかし「まずいッ」という悔いや焦りが入り込むと、問題はかえってこじれ、うまくいかなくなる可能性が大きくなるのです。
妄想をするな、感情で生きたら負ける
大切なのは、自我やこだわりは捨てて、問題そのものだけをシンプルに取り出し、考えることです。それができれば、自分の提案に対して指摘された欠陥部分をすばやく修正できますし、迅速な対策も立てられます。ミスを素直に認められる謙虚な姿勢をもつ人ほど、さらなる知恵を獲得することにもなるでしょう。余計なことを考えずに「ああ、そうですね。やり直しましょう」と実行するのが一番早いのです。
他人と議論したり、口論、喧嘩を仲裁する場合も同様です。互いの気持ちの部分、自己主張の部分には囚われず、問題のポイントだけをシンプルにまな板に載せれば、おのずと互いの心が整理され、解決の道筋が見えてきます。
私たち出家した人間がとりわけ大切にするのは、ブッダの次の言葉です。
「真理に従って生きる人は真理が守ってくれる」
これは、淡々と真理に従って生きる人は真理によって守られる、妄想ではなく真理に従え、という戒めです。感情で生きたら負けますよということ。
ブッダは人間の苦しみは普遍的なものであり、それは無常という真理を認めようとしない心の問題にあることを発見しました。そして、その心が真理を認める勇気をもつように修行することが知恵を開発することにつながり、苦しみから脱出することができる、と発見したのです。ブッダはこの方法でみずからがその苦しみから脱出してから、つまり解脱してから人々に伝えました。
ブッダが説かれたものは「宗教」や「信仰」ではありません。ブッダはけっして「神を信じろ」とか「私を信じろ」とは言いません。奇跡とか神秘体験やマインドコントロール、風水などといったこととも、いっさい関係がありません。何かにすがり依存しろとも言っていません。ただただ、この世の真理に従えばいいというのです。
仏教は心の科学です。ブッダが説いているのは、ブッダが発見した世の中の「真理」です。世の中について、生命について、人の心について、宇宙について考え抜いて知ったもの、つまり普遍的な法則、真理を伝えているのが、ブッダの言葉なのです。世の中にあることをそのまま、少しもねじ曲げることなく、こうなっていますと説明することは科学です。いわゆる物理・科学が物質を対象とするのに対して、ブッダの場合は心を研究し、生きるということをテーマとした科学なのです。生きることはなぜ苦なのかを突き詰めた科学なのです。
テーラワーダ仏教(上座仏教)はブッダの教えに最も忠実なものです。仏教が世界各地に伝播し、それぞれの開祖によって各種の発展を遂げる以前の、最も初期の仏教。ブッダが実際に説法に用いたパーリ語(古代インドの俗語)のオリジナル経典に基づいた仏教です。阿弥陀仏など諸仏の存在は認めず、菩薩への信仰もありません。極楽浄土があるとも言いません。
ブッダが辿り着いた「悟り」の境地に近づくために、私たちは瞑想を行っています。たとえばその1つはヴィパッサナーと呼ばれる瞑想法で、その瞬間に起こっていることをありのまま見つめることによって、洞察力を養うもの(深呼吸後、下腹部が受動的に動くのに合わせ、その感覚を「膨らみ」「縮み」と心の中で淡々と実況中継する等)です。
変化に合わせて「自分」を変えていく
私たちが生きることの本質は「苦」であることを認め、安定はない、すべては変わるのだ、と知った人には大きな勇気が生まれます。「すべては変わる」ということは、「すべては変えられる」ということです。変化に合わせて、自分も変わればいいのです。どんどん挑戦すればいいのです。変わることを恐れているうちは、不安から解放されず、自由と安らぎも得られません。経済が悪い、国が悪い、環境が悪いと嘆くのではなく、みずからを変える勇気をもってください。諸行は無常です。自分が生きる世界は、自分で築くことができるのです。
[PRESIDENT Online]
Posted by nob : 2014年12月16日 17:44
人はいつでもどこからでも変われる、、、思い込みを棄て覚悟さえすれば。。。
■誘惑を断ち切れる体質になるには「できない」ではなく「しない」と言うべき:研究結果
きっぱり「ノー」と言うスキルは、ぜひとも身につけるべきです。特に、生産的で健康な生活を送るうえでとても役に立ちます。する必要のない仕事にノーと言えれば、疲れを癒やすための時間が手に入ります。日々の気晴らしをうまく断れれば、大切なことに集中する余裕もできます。
逆に、きちんとノーと言えないと大きな失敗につながります。成功を収めている起業家たちも、それを大きな過ちとして挙げています。「ノーと言うなんてかなり難しい挑戦だ...」と考えるかもしれませんが、実はほんのちょっとした工夫次第です。科学的研究によって明らかになった「うまくノーと言うための心がけ」を紹介します。
きっぱり「ノー」と言うには...科学が明かす最善の方法
米学術誌『Journal of Consumer Research』で、120人の学生を2つのグループに分けて行われた実験結果が発表されました。
実験は、それぞれのグループで「誘惑に直面した際、自分に言い聞かせる言葉」を変えるというもの。片方のグループは「~できない」、もう一方は「~しない」です。例を挙げると、「アイスクリームを食べられない」なのか、「アイスクリームを食べない」なのかの違いです。
「〜できない」、「〜しない」のフレーズを何度も繰り返したあと、学生たちは研究とは関係のない一連の質問に答えて、解答用紙を提出しました。学生たちは「これで研究は終わり」と思っていましたが、実はここからが本番。学生が部屋を出る際に、1人ずつご褒美を渡します。ご褒美は、チョコレートバーか、ヘルシーなグラノーラバー(穀物、ナッツ、フルーツなどをミックスしたもの)のどちらか好きなほうを選ばせます。どの学生がどちらを選択したのかを、研究者は解答用紙に書き込みました。
その結果、こんなことが起きました。
「〜を食べられない」と自分に言い聞かせていた学生の61%が、チョコレートバーを選びました。一方、「〜を食べない」と言い聞かせていた学生のうち、チョコレートバーを選んだのはわずか36%でした。言葉をほんの少し変えただけで、ヘルシーな食べものを選択する確率が大幅に向上したのです。
研究でわかったのは、それだけではありません。次のセクションでは、その内容を紹介しましょう。
「正しい言葉」を使えば、誘惑を退けるのが楽になる
私たちのほとんどは、一度だけならチョコレートバーを断れても、いつかは誘惑に負けてしまいます。仕事にしても同じです。時間に追われていれば集中できるかもしれませんが、日々変わらず非生産的な行動を避けるためには、いったいどうしたらいいのでしょうか。この疑問に答えるべく、この研究チームが実施した別の結果を取り上げます。
研究では、仕事を持つ女性30人を対象に「健康に関するセミナー」を開催しました。セミナーでは、まず参加者全員に「自分にとって重要な健康上の長期目標」を考えてもらい、次に参加者を10人ずつの3グループに分けました。そして、誘惑に駆られた瞬間に自分に言い聞かせる言葉を変えてもらうのです。
グループ1には、目標達成を妨げそうな誘惑に駆られたら、単純に「だめ」とだけ言うように指示しました。
グループ2は「〜できない」です。たとえば、「今日のエクササイズをさぼることはできない」という具合です。
グループ3は「〜しない」です。「エクササイズをさぼらない」となります。
その後、10日にわたって次のようなEメールを参加者に送り、進捗状況の報告を求めました。「10日間、あなたにメールを送信します。このメールはあなたへの指示を確認し、効果の有無を報告するのを忘れないようにするためのものです。効果がなかった場合、その旨を連絡すれば、メールの返信をやめてしまって構いません」。そして10日後、以下のような結果が得られました。
グループ1(だめ)では、10日目まで目標を守り続けられたのは10人中3人。
グループ2(できない)では、10日目まで目標を守り続けられたのは10人中1人。
グループ3(しない)では、10日目まで目標を守り続けられたのは10人中なんと8人にのぼりました。
つまり、正しい言葉を使えば、個々の場面で良い選択ができるだけでなく、長期的な目標を守るうえでもプラスの効果が得られるというわけです。
「できない」よりも「しない」が効果的な理由
使う言葉によっては、自信や支配の感覚を生む効果があります。さらに、脳にフィードバックのための回路を作り出し、その後の行動にも影響を与えます。
たとえば、胸の内で「できない」と言うたびに、脳では「自分の限界を思い出させる」フィードバック回路が作られていきます。この言葉は、自分の欲求とは逆のことを無理やりしようとしている状況を表すものです。それに対して、「しない」と言う時には、「その状況における支配力や決定権を自分が握っていることを思い出させる」フィードバック回路が構築されます。これぞまさに、悪い習慣を打ち破り、良い習慣を身につける方向へ自らを導くフレーズなのです。
コロンビア大学のモチベーション科学センター長を務めるヘイジ・グラント・ハルボーソン(Heidi Grant Halvorson)博士は、「しない」と「できない」の違いについて、次のように説明しています。
「しない」という言葉は「選択」として体験するため、自分が決定権を持っているように感じられます。これは、自分の判断力と意志力を肯定する言葉だといえます。対して、「できない」は選択ではなく「制約」であり、あなたに課されるものです。「できない」と考えると、意志力や主体性の感覚が弱まってしまうのです。
つまり、同じ「ノー」を意味するフレーズでも、「できない」は心理的な力を弱め、「しない」は心理的な力を強める言い方なのです。
日々の生活に応用するには
何かに「ノー」と言わなければならない状況は、毎日のようにやってきます。エクササイズをサボりたくなった時、メールやツイートに気を散らしてしまう時...ひとつひとつを見れば、どのような対応をしても状況にそれほど違いはありません。私たちが「できない」という言い方で片付けてしまっても、たいしたことではないような気がするのはそのためです。
けれども、あなたをもっと力づける言葉を常に使うようにした場合、積もり積もってどれほどの効果が出るのか想像してみてください。
「できない」と「しない」は同じような言葉ですが、私たちはたいてい、この2つを特に使い分けてはいません。しかし、実際は異なる心理的フィードバックを生み出し、最終的には行動をも変える力があります。単なる「言葉」や「フレーズ」ではなく、あなたの信条や行動の理由を裏打ちし、目標を思い出させるものなのです。
誘惑に打ち勝ち、きっぱり「ノー」というスキルは、身体的な健康だけでなく、日々の生産性や精神的な健康を守るうえでも欠かせません。
つまりはこういうことです ── 自分の言葉の犠牲になるか、それとも自らの力で言葉を操るか。あなたなら、どちらを選びますか?
A scientific guide to saying "no": How to avoid temptation and distraction | Buffer
James Clear(原文/訳:梅田智世/ガリレオ)
■「コーヒー抜きの1カ月」で学んだこと:思い込みを捨てれば、人生のあらゆることは変えられる
「Zen Habits」のライターであるLeo Babautaさんは、7月に入ってから、「○○抜きの1年」というチャレンジを始めました。これから1年の間、毎月何かひとつ、特定のものや習慣を抜いた生活を送り、その月の終わりに、そこから学んだことを記事にするというのです。
今後は砂糖やアルコール、新しいものの購入、インターネットなどを断つつもりだそうですが、記念すべき最初のターゲットに選ばれたのは「コーヒー」でした。では、この1カ月の様子を報告してもらいましょう。
「○○抜きの1年」の最初の月となった7月、私はコーヒーを断ちました。そもそも大好きな飲みものですし、今まで何度もコーヒー断ちに挑戦しては無様に失敗しているので、そう簡単にはいかないだろうと思っていました。でも今回は、コーヒーなしの生活がすっかり気に入ってしまったのです。われながらとても驚きました。初日も、最初の1週間も、まったくつらいとは感じず、何の問題もなくコーヒーとお別れできました。
成功のカギは、代わりになる良い習慣を見つけ、それがとても気に入ったことです。飲めなくなったコーヒーについてくよくよと考えるのはやめて、毎朝おいしいお茶を飲もうと決めたのです。おいしいお茶を飲める喜びのおかげで、コーヒーのことなどすっかり忘れてしまいました。というわけで、「○○抜きの1年」の最初の1カ月はそれほど苦労もなく終わったのですが、その中でいくつかわかったことがありますので、以下でご紹介しましょう。
コーヒーを断ってみて気づいたこと
コーヒーのない生活について、気づいた点をまとめました。
* どうもシャキッとしないとか、頭痛がするとかいった禁断症状が出るのは覚悟していました。でも、そうした症状はまったく出ませんでした。代わりに飲んでいたお茶に、多少カフェインが含まれていたおかげかもしれません(ただし、薄めのお茶だったので、それほど大量ではなかったはずです)。早朝の時間帯でもきちんと目覚めていましたし、集中力もキープできました。
* また、自分以外の人がコーヒーを飲んでいるのを見ると我慢できなくなるのでは、という心配もありましたが、こちらも全くつらく感じませんでした。
* 唯一、「ああ、コーヒーが欲しい!」という衝動を感じたのは、香りを嗅いだ時でした。あの匂いって、本当に驚くほど魅力的ですよね。あんな香りはめったにありません。(妻の)Evaがいれたコーヒーの香りにはたまらないものがありました(もちろん、豆も上質のものを使っていましたから)。でも衝動は、それほど強烈ではありませんでした。
* この1カ月で一番コーヒーを飲みたいと思ったのは、ちょっと油っ気のある、ピリ辛の料理(オリーブオイルで炒め、チリパウダーで味をつけたもの)を食べた時でした。しかも目の前にはEvaが飲むコーヒーがあって、良い香りが鼻をつきます。どうやら私の場合、スパイスと油、コーヒーの強い香りという組み合わせが、強力なトリガーになっているようです。衝動はしばらく続きましたが、水を飲んで口の中からスパイスと油の後味を流し去り、コーヒーの匂いがしないところへ移動してやり過ごしました。
* 7月中にポートランドへ出かけたのですが、その時にも面白い体験をしました。同行した妻のEva、友人のJesse JacobsとJosh Jacobsが、「この街の素敵なコーヒーショップめぐりをしたい」と言い出したのです。私は車のハンドルを握って3人をお店に連れて行き、さまざまな名店で一級品のコーヒーの香りを楽しみましたが、一滴も口にすることはありませんでした。この1カ月で一番自分の決心が試されるシチュエーションだと思っていたのですが、それほどつらくはありませんでした。すばらしい香りだけで十分だったのです。
* Evaのために「Blue Bottle Coffee」へ立ち寄った時も、豆乳を使ったジブラルタル(ショットグラスよりちょっと大きめのグラスで供されるミルクたっぷりのコーヒー)を飲みたくなってもおかしくなかったはずです。でも、そうはならずに、無事にやり過ごせました。
この1カ月で学んだこと「思い込みを捨てれば変われる」
「○○抜きの1年」は、自分自身をより深く知るための実験です。自分の衝動や欲求を把握し、生きていくのに欠かせないと自分では思っている習慣を変えることに、どれだけ抵抗感を覚えるのかを確かめたくて始めました。
「これがなければ生きていけない」というものをとりあげられそうになったら、誰だって抵抗します。でも実際には、「生きていけない」なんてことはないはずです。生きていくために欠かせないものは、思っているほど多くありません。そうした思い込みを捨てれば、人生のあらゆることを変えられるはずです。
では、この1カ月で私は何を学んだのでしょうか? いくつかわかったことがあります。
* コーヒーがとても恋しくなると思っていたのですが、それほどでもありませんでした。事前にあれこれ悩んでいても、いざやってみるとそれほど大変ではなかった、というありがちなパターンです。コーヒー以前にも、何度もそういう経験をしています。チーズのない生活なんて無理だろうと思っていました。自家用車を手放した時も、肉を断った時も、しょっちゅう食べていたジャンクフードやファストフードをやめた時も同じです。毎回、実に簡単に縁を切ることができて、そのたびに驚かされたものです。
* 代わりになる良い習慣を身につけると、何かを断つのは本当に楽になります。やめたもののことばかり考えていると、つらくなるだけです。でも、代わりに始めた良い習慣について考えるようにすれば、気分も明るくなります。
* 禁を破りたいという衝動は、どんなに強烈なものでもそれほど長くは続きません。それに、ほとんどの衝動は軽いものでした。人はとかく衝動に屈しやすいものですが、今回はやすやすと抑え込むことができました。一番強烈な衝動でも、しばらくは続きましたが、そのうちにどこかに行ってしまいました。そうした衝動と向き合い、じっくりと感じ、不安に身を委ねてみたら、実はそれほどつらいものではないことがわかりました。不安を受け止め、それに身を委ねるのは、とてもためになる体験でした。
* あらかじめ限度を決めておくことは、衝動に対抗する有効な手段になります。人が衝動に屈してしまうのは、多くの場合、歯止めがないからです。「ピザ1切れ、あるいはクッキー1枚だけなら、別に良いのでは?」と思ってしまうわけです。でも、自分にルールを科し、限度を決めておけば、衝動に抵抗しやすくなります。これもコツの1つですね。
* また、目標を公言しておくのも役立ちます。あらゆる人に(この記事を読んでくださっているみなさんも含めて)、「コーヒーを飲まない」と宣言しておいたおかげで、決心が揺らぐリスクはかなり下がったはずです。
お茶の良さを知ったからコーヒー断ちできた
人間の衝動について学んだことのほかには、これが1カ月のコーヒー断ちで得た一番のメリットでした。旅行中も含め、お茶を毎日飲む習慣がつきました。今後もぜひ続けたいと思っています。お茶の習慣についてわかったことを、ここに記しておきましょう。
* 起き抜けのお茶は格別です(今回のチャレンジ以前は、お茶を飲むのは午後がほとんどでした)。身体に負担がかからず、必要以上に目が冴えることもありません。また、集中しながらゆっくり飲むと、豊かな香りに気づかされ、意識を高めるきっかけにもなります。
* 加えて、お茶を飲むようになって、前よりも健康になった気がします。コーヒーの健康上のメリットについては疑わしい点もあります(賛否両論があり、私にも何とも言えません)が、お茶の効果にはほぼ疑問の余地はないでしょう。お茶には癒やしと覚醒、両方の効果があると思います。
* お気に入りの朝のお茶は、サンフランシスコのティーショップ「Samovar」で購入した「Bai Mudan white tea」で、これを薄めにいれるのが好みです。朝の早い時間には本当にぴったりですよ。「Monkey Picked Iron Goddess of Mercy oolong」や、「Breakfast Blend Black Tea」もおいしいのですが、朝のすきっ腹には、最初に挙げた薄めの白茶が一番です。
* 旅先には、この携帯型ストレーナーを持っていきました。とてもシンプルで持ち運びやすいところが気に入っています。
* 友人でSamovarの創業者であるJesse Jacobsから、この自動式ティーメーカーをもらいました。絶対に必要な品ではありませんが、これはまさに逸品です。ちょっと贅沢をしたい人や、お茶好きの友人を気の利いた贈りもので喜ばせたい人にとっては、最高のティーメーカーだと断言できます。
* Jesseのおすすめに従い、茶葉を多めに使って抽出時間を短めにするようにしました。少なめの茶葉で抽出時間を長くする人も多いのですが、それよりもずっとおいしくなります。
* おおまかに言うと、私の好きなお茶は烏龍茶や緑茶ですが、白茶やプーアル茶でも、質の良いものであればおいしいと思います。
これからもコーヒー断ちを続ける?
ゴールの7月31日を過ぎてもコーヒーを断ち続けるか、それともまた飲み始めるか。この問題は1カ月間ずっと、私につきまとっていました。正直に打ち明けると、最高のコーヒーを出してくれるお店を訪れた数回以外は、コーヒーを本気で恋しく思うことはありませんでした。朝のお茶を心から楽しんできたのも事実です。とはいえ、コーヒーを飲むと自殺のリスクが下がるという記事を読んで、迷いが出てきました。多少であれば、気分に応じて飲んだほうが良いのではないか、と。
というわけで、今後についてはこう決めました。朝はコーヒーではなく、今まで通りお茶を飲み続けます。ただし、最高のコーヒーショップが淹れてくれる極上のコーヒーであれば、1~3口(限度はカップ半分)くらいは飲んでも良いことにしました。これくらいがちょうど良いバランスだと、今は思っています。
A Month Without Coffee | Zen Habits
Leo Babauta(原文/訳:長谷 睦/ガリレオ)
[いずれもlifehacker]
Posted by nob : 2014年12月16日 17:33
散歩、ひいてはウォーキング、さらにトレッキングは、心も身体も救う。。。
■散歩の達人は「解決の達人」でもある:ぶらぶら歩くことは創造力を高める
多くの文豪が、頭の整理のためにあてもなく歩いたといわれています。心をストレスから解き放つことが、新しいアイデアを生み出すきっかけになったのでしょう。
ディケンズに倣って、私も歩いてみた
イギリスの小説家で『オリバー・ツイスト』『クリスマス・キャロル』などを書いたチャールズ・ディケンズは、1日に20マイルも歩いたそうです。
ディケンズにとって、歩くことは2つの意味がありました。1つは、その鋭い目を使って、賑わう街のさまを記録するという事実調査の意味合い。街の様子を記述することが、彼にとっての商売道具だったのです。
(中略)ところがディケンズの人生にとっては、もう1つの意味が重要でした。彼にとって歩くことは、自己防衛の手段でもあったのです。
(中略)ディケンズは、書くことがつらく苦しい作業であることを知っていました。デスクで時間を過ごすと、途方もないほどのイライラが募ります。歩くことは安全弁のような役割を果たしたのです。
『Frisky as the Dickens』より
私もやってみることにしました。この2週間毎日、頭が働かないときはデスクを離れて外に出ることにしたのです。近所を闊歩したり、公園を散策したり...これが正解でした! 私の頭は再び回り始めたのです。次の一歩につながるような、完璧な外出になりました。
どういうわけか、デスクを離れて外に出ると、抱えていた問題でも筋道を立てて考えられるようになるのです。なぜ、そんなことが起こるのでしょうか。
草木の存在が創造力を高める
デスクを離れて外を歩くと、必ず木々を目にします。たまに長い散歩をすると、草原にたどり着くこともあるでしょう。自然の緑は穏やかで、心を落ち着かせてくれます。それだけではなく、創造力も刺激するのです。
ドイツとアメリカの研究者が、豊かな緑を見ることが創造力に与える影響を調査したことがあります。被験者は、緑、白、赤、灰色、青のうち1つの色を見せられます。短い間、その色を見た後で、クリエイティブなタスクが与えられます。たとえば、「空き缶のクリエイティブな使い方」や「丸いもの」を思いつく限りに挙げるといったことです。
その結果、見せた色とデータに強い相関がみられました。緑を見せられた被験者は、空き缶の面白い使い方を思いついたり、あきれるほどに丸いものを挙げられたりと、創造力のパフォーマンスが高かったのです。緑を見ることでクリエイティブな解決策に至った、型にはまらない考え方ができるようになったのです。
同じように、詩人や作家は、歩きながら色を「取り込む」ことによって創造力を高められたのでしょう。
歩くときには流れるようなリズムで
散歩に出ると、手と足が自由になります。ディケンズは「気ままな歩き方」(swinging gait)をしていたそうです。クリエイティブ思考やクリエイティブ知能の理論では、「創造性とは流れに乗るものだ」考えます。
スタンフォード大学とタフツ大学の研究者が、「体の動かし方によって創造力は高まるか」という実験をしました。被験者を2つのグループに分け、1つは腕を流れるように動かし、もう1つはこわばったように動かします。その運動後にいくつかの質問が行います。たとえば、新聞の使い道や、思いつく限りの乗り物を挙げるなどです。その結果、流れるように腕を動かしたグループは創造力が高まりました。乗り物に「ラクダ」を挙げた人もいたのです。
ぶらぶら歩くときは、腕だけでなく流れるようなリズムで全身を動かしましょう。この動きが、創造力を高めてくれるのです。
暇な時間がひらめきを生む
当てもなく歩く時、目的地はありません。達成すべきことも、買わなければならないものもないのです。ぶらぶら歩くと、暇な時間が生まれます。エッセイストであり漫画家でもあるティム・クレイダー氏はこう書いています。
暇がもたらす空間や静寂は、人生から一歩離れて全体を見渡すために必要な条件です。それによって、予期せぬつながりが生まれたり、真夏の落雷のようなひらめきを待ったりできるのです。逆説的ですが、それこそ仕事を進めるために欠かせないことなのです。
『The Busy Trap』
暇な時間は、ひらめきを得るための機会になります。怠けることを恐れずとも大丈夫。ノーベル文学賞受賞者であり、ジャーナリスト兼哲学者であるアルベール・カミュは、こんなに心強いことを言っています。
暇というものは凡庸な人びとにとってのみ致命的なことであった。
『幸福な死』(高畠正明訳、新潮文庫)
何もしない喜びを存分に味わってください。無意味なことにも力は宿るのです。ぶらりと散歩に出れば、クリエイティブなひらめきが生まれるかもしれません。
Go wander: how meandering in the outdoors can enhance creativity | ooomf
Divya Pahwa(訳:堀込泰三)
[lifehacker]
Posted by nob : 2014年12月16日 17:19
言い得て妙。。。Vol.26/幸せ、、、気付きさえすればいつもそこにあるもの。。。Vol.2
■小池龍之介「追い求めると逃げていく。“幸せは副産物”の理由」【2】
小池 龍之介
月読寺住職兼正現寺住職
人類の歴史上、普通の人々がバーチャルな幸福感に浸れるようになったのは、長く見てもこの100年くらいのことです。
それ以前は、身を粉にして働かなければならない日々の中で、快感のスイッチが入る機会は稀にしかありませんでした。収穫祭やたまのお祭りといったハレのとき。あるいは1日の労働を終えて「ああ、ご飯だ」というときに快感が走ったりしたのかもしれませんが、その頻度は現代人に比べてはるかに少なかった。
脳内の快感物質は麻薬のようなものです。快感を連続して入力するということは、麻薬を絶えず脳内に分泌している状態なので、中毒化します。言ってみれば慣れが生じて、同じ分量の快感物質では同じ気持ちよさを感じられなくなる。同じ気持ちよさを感じるためには、より多量の快感物質を必要とします。それができないと、現状維持をしているだけで“前より状況が悪くなってはいないのに”、「自分は不幸だ」と感じるようになる。
ときどき快感が走る程度の生活なら、中毒になることはありません。ましてや畑で鍬を振り下ろす、薪で火を起こすというような反復運動に集中していると、快感物質が抜けて心が落ち着いてきます。昔の人々の生活は快感をどこまでも追い求めるのではなく、自然に絶えずリセットする習慣になっていた。快感に身を委ねて暮らしていられたのは王様や貴族などひと握りで、そうした人々はドーパミン中毒になって心の病に陥りやすかったのですが、一般庶民は幸いにして日々を穏やかに過ごしやすかったはずです。
翻って現代では、年収200万円で負け組と言われている人でさえ、その多くは困窮しないで、昔の王様並みの生活ができます。ちょっとお金の使い方のバランスを変えれば、豪華な食事もできる。デジタルツールで瞬時に他人とつながることもできます。
お金を出せばいくらでも自分の欲を満たせて脳内麻薬を生み出せる。歴史上、大半はそういう状況にない中で人間は自己形成されてきました。快感スイッチを連続入力するような現代の生活は、人間の生き物としての仕組みを壊してしまう気がします。
たとえばしょっちゅう携帯電話のメールチェックをしないと気がすまない人は、誰かとつながっていることを確認して快感を覚える、ある種の快感中毒といえます。携帯電話やパソコンで頻繁に情報にアクセスするのは、ドーパミンを連射しているようなもの。依存症やうつ病など精神的な疾患が増えているのは、そのあたりにも関連がありそうです。
快感を得ることがすべてダメと言うつもりは毛頭ありません。快感とのつき合い方を考えるべきであり、快感を入力しない時間が必要だと思うのです。一時の快感で偽の幸福感を得て脳をいわば“ドーパミン漬け”にしてきた現代人の支払うツケは、ドーパミンの効果が薄れて気持ちがそわそわしたり、イライラしたり。実は、苦しみのもとでしかない。仏教の言葉で壊れる苦しみのことを「壊苦(えく)」と言いますが、快感はまさに壊苦そのものです。
本当の幸福とは何か。ブッダは「褒められても心が浮つくことなく、非難されても決して落ち込むことなく、心が平静でいられるのが幸せである」と言っています。心が波打つ苦しみから解放されて、穏やかに安らいでいる状態。それが万人に共通しうる最高の幸せだと言います。
「心が安らいでいる」と言うと何もしないでボーッとしているイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。むしろ意識がシャキッと目覚めて、背筋が伸びているような感じ。緊張したり余計なことを考えたりしないで、目の前のことに集中できている心の状態を「安らいでいる」と言います。
脳内物質の働きでいえば、抗重力筋(腹筋や背筋など重力と反対方向に働く筋肉)を管理するセロトニンの神経回路が活性化して、暑さや寒さ、痛さなどに対する耐性が高まり、外界からの刺激に影響を受けにくくなった状態です。この神経回路を活性化させるコツは、快感を入力せず、いわば麻薬抜きをする時間をつくることです。起き抜けに携帯電話をチェックする生活は、朝から快感物質を発射するようなもので、1日中、心が快感や不快感にゆらぎやすくなります。せめて起床後の30分や1時間は、心の平静に努めたい。
セロトニンの神経回路を活性化するもう1つのコツは、目的意識を持たないことです。目標を立ててそれに向かって突き進むと、「ああまだ達成できていない……」という苦しみが、達成したときに緩和されて快感物質が発射される。これを避けるには、ゴールに向かって走るという意識を捨てて、いま目の前で行っていることに意識を振り向けることが大切です。慣れていない人は、短い単位で同じことを反復する行為に集中することから始めましょう。
たとえば手を動かして掃除をしてみる。皿を洗う。前述のように農作業に没頭するのもいい。歩くのでも、部屋の端から端へ行ったり来たりするなんて無目的の極みです。最初は「何やっているんだろう」と思うかもしれませんが、それを無視してひたすら歩く。すると体の感覚に意識が集中し、リラックスしているのに冴えているような感覚になってきます。
心安らかな状態が継続的に維持できれば、「何々があるから幸福」ということではなく、何をやっていても幸福でいられると思います。しかし、穏やかな気持ちを保つのはそう簡単なことではありません。たとえば今回の震災のように、ふいに訪れる不幸な出来事や悲しみに感情が揺さぶられることもあります。
些細なことですが、私は自転車を盗まれることがよくあって、昔はそのたびにイライラしていました。「あそこに置かなければよかった」「また新しい自転車を買わなきゃいけない」と後悔や落胆の念をしばらく引きずってストレスを抱えていたのです。
それがあるときから、気にならなくなりました。これは平素から「現実」と「頭の中で起きる反応」を仕分けるトレーニングをしてきた成果で、自転車が盗まれたという現実と、自分の心の中に湧き起こる悲しいという感情が交じり合わなくなったのです。
何か不幸な出来事、悲しい出来事が起きたときに、それが1本目の矢として心に突き刺さります。しかし多くの人は降りかかった現実を元にそれを脳内で編集し、後悔や不安を交えながら不幸や悲しみを増幅させてしまう。いわば自分で自分の心に第2の矢を突き立てて、いつまでも気に病むのです。
第1の矢と第2の矢を区別して、「あ、いま、自分の頭の中で編集している」と気づくと、気持ちは鎮まってくる。誤解を恐れずに言えば、震災で全財産を失ったり、家族を亡くしたときでさえ、ある程度の訓練を積めば同じことが可能です。
無論、これができない人は大勢います。できない人に対しては、比較的できている人、心が落ち着いた状態にある人が寄り添ってあげましょう。反対に心が落ち着かない人に寄り添われるとイライラが増します。「被災した人はかわいそう」「自分が役立たなくては」と気負ったり、涙ぐんでボランティアに参加されても迷惑なだけです。
仏教で言う「慈悲」とは他者の苦しみに共感するということです。感情的に自分も涙するというのではなく、心を鎮めて相手の苦しみ、痛みにそっと手を当て、「苦しいんだね」と理解し、受容する。
自分の苦しみに自分で寄り添うこともできます。私の道場では「慈悲の瞑想」という指導もしています。まずは不安や恐怖を洗い出し、「そうか、苦しいんだね」と目を閉じて心の中で唱えて自分の苦しみを慈悲の温情で抱きとめる。すると、とても心が柔らかくなり、苦難に立ち向かう勇気も湧いてきます。
[PRESIDENT Online]
Posted by nob : 2014年12月15日 20:38
言い得て妙。。。Vol.25/幸せ、、、気付きさえすればいつもそこにあるもの。。。
■小池龍之介「追い求めると逃げていく。“幸せは副産物”の理由」
小池 龍之介
月読寺住職兼正現寺住職
幸せの感じ方は人それぞれです。お金が手に入れば幸せという人もいるし、人から愛されることが幸せだと思う人もいる。仕事で評価されることに幸せを感じる人もいるでしょう。
しかし、こうした心が満たされたような感覚はどれも、脳内でドーパミンが発射されて生じた刺激によりつくり出される、バーチャルなものにすぎません。満たされたように感じるのは、それ以前には満たされていない状態にあったからです。人は何かほしいものがあって、それが手に入らないとき、つまり満たされていないときには「苦しい」と感じます。そして、満たされなかったものが満たされた瞬間にいままでの苦しみがすっと消えて、「もう苦しくない。ああ気持ちいい」と感じる。これが快感の正体です。
「一切皆苦」という仏教の根本原理があります。人間が心と体を通じて知覚できる刺激は、「苦」という感覚だけ。「苦」の量が増減するだけという考え方です。その「苦」が減じた状態を脳が勝手に情報処理して、「快」と錯覚させる脳内物質を分泌します。欲望が満たされたり、目標が達成されたりすると、脳の神経回路が刺激され、快感物質のドーパミンが大量に発射される。それで「気持ちいい」と感じますが、神経には負担がかかっていますので、“現実的”には「苦」なのだと申せるでしょう。
しかしドーパミンはずっと放出され続けるわけではありません。快感物質を放出する神経回路が刺激されるのは、欲望が満たされたり、目標が達成されたりしたほんの一瞬だけ。そのときの快感は記憶に残って、「あのときは気持ちよかった」と思い出すたびに多少のドーパミンは出ますが、それは時間の経過とともに少なくなってきます。そしてそれは、神経レベルでは不快な信号として認知されるようになっていて、ドーパミンが出た後には必然的に物足りなくなってそわそわと落ち着かなかったり、満たされなくなってイライラしたりしてくるのです。
もっとお金がほしい。もっと愛されたい。もっと仕事で認められたい。もっとおいしいものが食べたい。満たされない苦しさから脱出するために、新たな目標を設定するようになります。しかも、より大きな快感を求めてより高い目標を課すようになる。目標が高くなれば達成が困難になってより苦しくなるうえに、失敗することも多くなります。
目標が達成できそうにないと感じたとき、別の欲望を満たすことで快楽を得ようとする人もいます。たとえば仕事がうまくいかないときにお酒でストレスを発散する。一時的な快楽で苦痛を忘れることはできますが、もとの苦しさが減るわけではありません。苦しさから逃れるための代替行為がエスカレートして、お酒やギャンブルに溺れる人もいます。
頑張るバイタリティのある人なら、より高い目標もクリアできるでしょう。そのときもドーパミンが放出されて気持ちよくなる。しかし、いずれ慣れてしまうので、さらなる快感を求めてもっと高い目標を設定して……という繰り返しです。
満たされないことに比べれば、満たされたほうが幸せに決まっています。しかし、満たされたことで感じる「快感」も「苦」の情報を脳が書き換えて、快感スイッチを入れることで感じるバーチャルな感覚にすぎない。多くの人はそれを幸福感と錯覚しているのです。
[PRESIDENT Online]
Posted by nob : 2014年12月15日 20:23
また旅立つ君へVol.82/居るべき場所、進むべき道、考えることではなく自ずと感じること、、、何処で何をするかではなく、置かれた今にどう取り組むのかということ。。。
■天職は何か、考えてはいけない
迷っているなら「どっちもやってみたら?」
仲 暁子 :ウォンテッドリー株式会社代表取締役CEO
「世の中を変えたい」そんな熱い思いを持ってスタートアップに踏み切る人たちはどんなマインドセットを持っているのだろうか、どんなキャリアを積んできたのだろうか。そんな思いで、有名スタートアッパー達と対談を続けてきました。
ですが、「仲暁子」という個人について語ったことはありませんでした。今回は自分の歩んできたキャリアについて語らせてください。
どうすれば「ココロオドル」仕事を見つけることができるのかことができるのか。幸運なことに『ココロオドル仕事を見つける方法』という本を出す機会もいただきました。自分のキャリアに迷っているビジネスマンの皆様の一助になれば幸いです。
「やりたいことがわからない」
学生にも社会人にも、よく、こんな相談をされます。
そんなときにはいつも、こう答えます。
「わからなくて普通。将来の夢なんて、なくて普通」と。
その質問をされるたびに、思い出すことがあります。
それは、「3歳児に『好きな食べ物はなに?』と聞いたら、『カレーの王子さま』と答える。なぜならその子は、食べたことのないフカヒレやフォアグラのおいしさを想像することができないから」というものです。
3歳の子どもは、「自分が食べたことのある中でいちばんおいしい、カレーの王子さま」を、「好きな食べ物」だと思ってしまうというのです。
「やりたいことがわからない」という質問への答えも、それと同じだと思います。
人間は、体験したことのないもの、接したことのないものは、そもそも選択肢として選べません。3歳の子どもが食べたことのないフカヒレやフォアグラを選べないように、やったことのないこと、触れたことのないことを「これが絶対にやりたいことだ!」とは、なかなか言い切れないものです。
だから、今から、X年後にどうなっていたいか、なんて自分で考え続けても意味はありません。
「何になりたいか」「何のために、これをやるか」なんていう夢は捨てて、「無目的」でいること。目の前のことに、ひたすら真剣に、愚直に向き合うこと。
そうやっていれば、振り返ったときに、過去の自分が想像できたところよりも、はるか先まで来ていることに、気づいたりします。
では、天職を見つけるために、私たちは何をすればいいのでしょうか?
未来の可能性を潰すことから始めよう
わたしたちの未来にはさまざまな道が広がっています。大企業に就職して安定した会社員になるという道、資格を取って手に職をつけるという道、小説家になるという道――。たくさんの道、計り知れない可能性、そして夢は、みなさんの前に並べられた、数えきれないほどたくさんの「選択肢」です。
この「選択肢」が多ければ多いほど、豊かな人生を送れるに違いない──。
あるときまで、そんなふうに思い込んでいました。
でも本当はそうではありません。
自分の未来について悩んでいるとき、よく考えてみると、すべての悩みの大もとは「選択肢を捨てきれないこと」にあると思います。
前回、書いたように、私が、マンガ家になりたかったにもかかわらず、周りの目を気にしてゴールドマン・サックスに就職して悩んでいたことも同じです。
「やっぱり、マンガ家になりたい」
「もしかしたら、なれるかもしれない」そんなふうに考えて、「マンガ家」という人生の選択肢を捨てきれないからこそ、悩んでいたのです。
そして、私が「マンガ家」という選択肢を捨てることができたのは、「やってみた」からでした。
「あれだけやってダメだったんだから、もういい」心の底からそう思えたのです。
天職を見つける人の共通点はなんだろう?
だからこそ今、目の前の「ウォンテッドリー」に集中できている自分がいます。
「もしマンガ家になっていたら、大成功していたかもしれないなぁ……」
漫画家になるためにあがいた8カ月がなかったら、今もそんな夢を捨てきれず、週末のたびにマンガを描き、仕事に全力投球できない人生を送っていたかもしれません。
人生には限りがある。自分が人生でチャレンジできることやチャレンジできる時間にも限りがあります。
マンガもやりたい、仕事も成功させたい、何かあったときのために、こんな資格も取っておきたい……。それが全部うまくできるならば話は別ですが、1日は24時間しかないし、1年は365日しかありません。
アップルを大成功させたスティーブ・ジョブズはこう言っています。
「“集中する”というのは、集中すべきものに『イエス』と言うことだと誰もが思っている。だが本当はまったく違う。それは、それ以外のたくさんの優れたアイデアに『ノー』と言うことだ」と。
「何をやったらいいのだろう、何が自分にいちばん合っているんだろう」多すぎる選択肢を前に、そんなふうに悩んでしまったときに、まずできることは、「選択肢を潰していくこと」だと思います。
目の前にある選択肢を潰すためには、まずはチャレンジしてみる。思いきりぶつかっていく。そして、ひとつずつ見切りをつけていく──。
もちろん、ぶつかったものがうまくいったら、それに全力を注げばいい。
逆に、うまくいかずに、自分には向いていないことがわかるときは、「いつのまにか」次の選択肢に興味が移ってしまっているものだと思います。
まだ、ほかに興味が移らないうちは、ひとつのことをやり続ければいい。
いつのまにかほかのことを始めてしまっていたら、それが「選択肢を潰した」証拠です。「これは自分には向いてない」と思えたら、それはあなたの人生が定まっていっている証拠です。
「どちらか」で悩まなくていい
では、もしあなたにはどうしてもやりたいことが2つあって、どちらを選択すべきか決められないとしたら、どうするか。
たとえば、気象予報士になるために、つなぎで始めたはずの塾のアルバイトが面白くて、「先生にもなりたい」と思ってしまったら?
仕事はとても面白いけれど、子どもを産んで育児もしたい……と、どっちにするかで悩んでいたら?
私の答えは簡単です。
「どっちもやってみよう!」
どちらにするか迷ったときには「同時に2つともやってみる」。
社長になってからというもの、この大切さをますます実感するようになりました。
みなさんにも、こんな経験はありませんか?たとえば、ウェブサイトのデザインを決めるとします。チームの仲間が集まって、いくつかのアイデアを検討した結果、最後に残った2つのデザインがどちらも甲乙つけがたくて、いくらみんなで話し合っても判断がつかない……。
そんなときわたしは「同時に2つともやってみる」ことにしています。
このやり方は、フェイスブックにいたときに学びました。「答えはユーザーに聞いてみる」──これがフェイスブックの哲学です。
フェイスブックは、現場で実際にサービスを作っているエンジニアの裁量が非常に大きい会社でした。
普通の会社なら、多くの部署の人たちがたくさん案を出して、それをひとつずつ会議で議論して承認を受けてからでなければ、新しいサービスは発表できません。
しかし、フェイスブックは違います。「現場の職人」であるエンジニアの判断で、「これがいい」と思ったものは、どんどんユーザーに使ってもらうのです。そして、うまくいったものは残して改良を重ね、ダメだったものは潔く消してしまう。
そうやってつねに行動していくから、「いいか、悪いか」を考える手間が省けて効率がいい。「考える前に、作る」。フェイスブックの成長スピードが速い秘訣は、ここにあるのです。
「いつのまにか」が見つかるまで続けよう
そして、このやり方は人生にも応用が利きます。
「どっちもやりたいけれど、どっちを選べばいいかわからない」と迷うくらいなら、両方やってみればいいのです。
やってみて、周りの反応や、自分の行動や、気持ちの変化を見ていれば、どっちを選ぶべきなのかはいずれわかってくるもの。
現実が明らかにして、教えてくれるものです。
自分は何に一生をかけるべきか、
何を仕事にするべきか……。
そう悩んでいる人は、ぜひ、「可能性を潰す」ことから始めてみてください。
続けていればそのうち、「いつのまにか見つかる」もの。
それが見つかるまでは、悩まなくていい。ただ、やってみればいい。
そうすることで、あなたの「ココロオドル仕事」が手に入るものなのです。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2014年12月15日 19:50
言い得て妙。。。Vol.24/長所か短所か、、、まずは受け容れてみて初めて判断できること。。。
■最大の欠点は最大の長所かもしれない。完璧主義から脱する方法
今は完璧主義者の時代です。テクノロジーは少しでも進化するべく常に必死で、労働者は下がり続ける経済と目に見えない海外との競争を恐れ、より効率よく、より生産性を上げなければ、という終わりのないプレッシャーに苦しめられています。
このように前進することや向上することばかりを重視していると、完璧にならなければという気持ちになりやすいです。失敗することを深刻に恐れ、恥だと思うようになります。そして、自分の欠点に対して、攻撃的な怒りを向けてしまうこともあるでしょう。何の前触れもなく、ゴールポストが動いたかのように、Facebookで友だちのすてきな生活(南国のビーチ! 仕事での成功! 完璧な家族写真!)を目の当たりにして、自分は何も達成していないし全然完璧じゃない、とかなり落ち込んで嫌な気分になります。
誰でも一度は経験があると思いますが、このような気分を味わっている人は、フリーランス組合のブログでライターのKate Hamill氏が書いているメッセージを読んで、今すぐやめましょう!
最大の欠点は最大の長所でもある
完璧な人間になろうとするのをやめた方がいい理由はいくらでもあります。なにか行動を起こそうとするときの妨げやリスクになったり、自分を惨めに感じたりするだけではありません。それは、到底不可能なことだからです。人間は誰もが欠点がある複雑な生き物だから、というだけではありません。最大の欠点は、最大の長所でもあります。このことを心に留めておくことで、Hamill氏はかなり前向きになれました。
本当に気が狂いそうになるほど嫌だった最大の欠点でさえ、自分の本当に好きな長所と同じように前向きにとらえることができました。私は短気でどうしようもなく、熱い人間ですぐに感情的になってしまっていたので、怒りと闘っていました。それに、先延ばししてしまう欠点もありました。しかし、先延ばしにするのは、自分の心をクリエイティブにさまよわせるのと同じように、最高の仕事をしたいという深い欲求が根底にあったからです。
反省するのはいいけれど
反省したり、自己研鑽したりしなくていい、と言っている訳ではありません。Hamill氏の話は、欠点を認めるのをやめるのではなく、自分の一番良くないところを見て自己嫌悪したりせず、自分に対してもう少し理解と思いやりを持ちましょうということです。
これは、役に立たない習慣や自己崩壊するようなパターンに、いちいち囚われる必要はないという意味です。欠点を、まるで未知の生物のように、完全に撲滅しなければならないもののように考えるのをやめましょう。そうではなく、欠点は自分の良い(すばらしい)部分が極端に表れたものだと思いましょう。完璧な自分になろうとするのではなく、行動を調整することを意識します。欠点や自分自身を嫌いになる必要はありません。
あなたの最大の欠点は何ですか? それは最大の長所の裏返しかもしれません。
How to Learn to Love Your Weaknesses|Inc.
Jessica Stillman(訳:的野裕子)
[lifehacker]
Posted by nob : 2014年12月15日 19:28
気持ちいい。。。
■魔法の簡単マッサージで、瞬時に足が細くなる!!
こんにちは、仁香です。今回の「女はやっぱりヤセぷよ♡」では、私が毎日おこなっている、簡単足マッサージを教えちゃいます。
講座でも毎回レクチャーしますが、驚かない人がいないくらい、すぐに効果が出るんですよ。
正しい基本ウォーキングをするにも、1日の疲れやむくみを溜めないためにも、とても重要になってくるマッサージ。
足全体の筋肉を動かしやすくするためにも常にほぐしておく必要があります。
ただ難しいと人は嫌になり続きません。簡単に効果がでる、これに尽きるでしょう。では早速実践してみてくださいね!
ふくらはぎが激変するマッサージ法
では早速、瞬時に足が細くなるマッサージ開始です。片足が終わったら、マッサージしていない足と比べてみてくださいね。違いが一目瞭然です!
<マッサージの手順>

1.足指を縦横に順番に開きます。まずは横に3セット。次に縦に3セット。

2.足裏のアーチに沿って3か所、折り紙を折るように押しながら折ります(×3セット)。親指と人差し指のあいだ、中指と薬指のあいだ、薬指と小指のあいだの3か所。痛気持ちいい程度。

3.かかとを親指で押していきます。基本ウォーキングはかかと着地するため、常にかかとをほぐす。かかと周りは女性系のツボもあるので、刺激すると◎。

4.足首をまわします。足の指と手の指を恋人つなぎして、ギュッと奥まで入れる。きっちりつかみながら大きく足首をまわしましょう(内回し外回しを10回ずつ)。
足首は固まりやすいので、柔らかくしてあげることが大切。柔らかくないとトラブルに繋がる恐れも。

5.足の甲の骨と骨のあいだを押します(×3セット)。夕方になると骨が見えなくなるくらいにむくむ場所。痛い人はむくんでいますよ!

6.ふくらはぎに親指、スネに残りの指4本を乗せて、下から上にギュッギュッと押していきます(×3セット)。膝裏まできたらリンパがあるので、親指で刺激。
ふくらはぎは、下がった血流と老廃物を下から上に流してくれる重要な役割。しっかりほぐしましょう。

7.太ももの内側の筋肉を大きくつかんで、パッとはなす(×3セット)。太もものつけ根までくり返します。
1日の終わりにテレビを見ながらでも、マッサージをしてみてください。その日のむくみはその日のうちに取る! これが太くならないコツです。
血流をよくして、毎日老廃物やむくみを取ってあげると、こんなにも違うんです。ちょっとした手間ひまが、あなたの足を変えていきますよ♡
by 仁香
[glitty]
Posted by nob : 2014年12月11日 10:25
牛乳以外は私も実践中、、、日々効果を実感しています。。。
■「ストレス緩和フード」はクルミ、牛乳、チョコレート、アボガド
カフェグローブより転載:いよいよ師走。気候も厳しく、心も身体も何かとストレスフルな日が続きます。
そこで、取り入れたいのが、思わずほっとする、ストレスを緩和してくれる食べ物。海外サイト「YouBeauty」で、そんな食材を見つけました。身近なものをいくつかピックアップしたいと思います。
気分の浮き沈みを防ぐクルミ
オメガ3脂肪酸でも欠く事のできないリノレン酸を多く含み、血圧を下げて、ストレスの波を和らげ、気分の浮き沈みを防いでくれます。
(中略)
ナッツをバリバリと食べるだけでもストレスの発散になります。
「YouBeauty」より引用翻訳
ダイエットにも効くと話題のナッツ類。確かに、思い切り噛み砕いて食べるのって気持ちいいかもしれません。さっそく試してみようと思います。
カルシウム豊富な牛乳
牛乳には抗酸化作用があり、ビタミンB12、プロテイン、カルシウムがストレスによって発生した活性酸素に働きかけます。
(中略)
またプロテインが血圧を抑え、カリウムは筋肉を和らげ、こむら返りを防いでくれます。
「YouBeauty」より翻訳引用
「寝る前に牛乳を温めて飲むとよく眠れる」、と祖母に教えてもらった記憶がありますが、理にかなっていたんだと妙に納得しました。
リラックスにはダークチョコレートを
チョコレートには抗酸化作用があり、血圧を抑え、身体がリラックスして落ち着いた状態へと導いてくれます。
(中略)
注意するのはダークチョコレートを選ぶ事だけです。
「YouBeauty」より翻訳引用
気分が落ち込んだり、疲れているとチョコレートが食べたくなるときがあるのは自然な事だったと知り、少し安心したのは私だけではないはずです。
メンタルの安定にも優秀なアボガド
ストレスによる酸化ダメージの元となる脂肪の吸収を防いでくれるグルタオチンが豊富であるうえ、ベーターカロチン、ビタミンE、そして葉酸を多く含み、精神を安定させる効果があります。
「YouBeauty」より翻訳引用
栄養が豊富なだけでなくストレスにも効くなんて、さすがスーパーベジの代表! アボカドが好きでよかったと思うほど。
以上、意外と身近にあったストレス対策に効果的な食材でした。どれもすぐに取り入れられる食材ばかりですので、これからの時期、溜まりがちなストレスの解消のためにも意識して摂取して行きたいと思います。
(石井真代)
[lifehacker]
Posted by nob : 2014年12月11日 10:18
まさに効果てきめん、、、特に作業を終えるまで携帯の電源は切っておきましょう。。。
■集中力を高めるために簡単に実行できる5つの方法
忙しく、ペースの速い現代社会。時間とエネルギーを日常的にやりくりしなければいけないため、多くの人々は気がつくと集中力を高めようとしてコーヒーや栄養ドリンクを何杯も飲んでしまっています。
もしみなさんが私のようなタイプなら、その方法で注意を怠らず、集中力を維持させるのはどんどん難しくなってくると思います。もし集中がどうしても途切れてしまう自分に気がついたら、エナジードリンクに手を伸ばす代わりに、これから紹介する方法を試してみてはいかがでしょうか。
1. 周りの雑音をシャットアウトする
背景に雑音があると、どうしても気が散ってしまいます。テレビやラジオの電源をオフにすることは、目の前にある課題に集中して取り組むにはかなり効果的です。脳が周りの音に気を取られると、ボーっとしやすくなります。雑音を消すことができない場合は、ヘッドフォンをつけて、気分を落ち着かせ、集中力を高めてくれる音楽を聴くと良いでしょう。
2. 仕事場の環境を整える
作業スペースを整えると、混乱なく仕事に取り組むことが可能です。照明を置いたり、飾りを付けて魅力的なスペースにするのも良いでしょう。仕事場を快適にすることは、自分でできる重要な方法です。なぜなら、みなさんには快適に仕事をする権利があるからです。
3. マルチタスクを極力避ける
複数の作業を同時にこなすのは、できる限り避けてください。1つずつ仕事を行うようにしてください。
4. 散歩をする
ときどき、休憩をして運動しましょう。5分間の散歩だけでも、張りつめた心を和らげる効果をもたらします。このように定期的に休憩をとれば、頭の中のモヤモヤ感をスッキリさせられます。
5. 携帯電話の電源を切る
全神経を集中する必要のある仕事に取り組む時は、携帯電話の電源を切るようにしましょう。突然鳴る着信音は私たちを驚かせ、神経質にさせます。電源を切ることでストレスを減らし、落ち着いた心を保てます。
不十分なエネルギー源に頼るかわりに上記の方法を実践することで、忙しい日でも1日中頭が冴えた状態で働けますように。
Improve Your Concentration and Focus In 5 Easy Steps|Inc.
Rhett Power(訳:Conyac)
[lifehacker]
Posted by nob : 2014年12月11日 10:08
自らの在り様と境遇を受け容れて、完全な満足という夢を追いつつその時々の納得を重ねる現実の日々を、私は過ごしていきたい。。。
■生まれ変わってもまた自分になりたい人は33.4%! 20代だけ低い理由は?
今度生まれてくる時は、とびっきりお金持ちがいいなぁ、彫の深い美人になってもてはやされたいなぁ、有名人の子供として生まれたいなぁ、など、誰しも一度は、生まれ変わったら自分以外になりたいという願望を持ったことはあるでしょう。
とはいえ、どんなお金持ちや美人であれ、表面上は幸せそうに見えても、心の底で幸せだと感じているかどうかは本人にしか分からないものでしょう。
そこで、しらべぇ編集部では、アンケートサイト「マインドソナー」を使って、『生まれ変わってもまた自分に生まれたいと思いますか?』と問いかけてみました。その結果は、人生の奥深さを物語っている結果となりました。
■生まれ変わってもまた自分に生まれたいと思いますか?
・はい:33.3%
・いいえ:66.6%
3人に1人が『また自分に生まれたい』」と回答しました。おそらく現状の自分に100%満足しているという人は、ほぼいないのでは?と思いますが、この3 人に1人という数字、意外と多いと感じませんか?この数字を年代別に分けてみたら、その答えがなんとなく見えてきました。
・20代:24%
・30代:33%
・40代:37%
・50代:35%
20代の若者世代の少なさがまず目につきます。そして、30、40、50代は、大きく変わらず僅差でした。そもそも『生まれ変わっても、また自分に生まれたい』と思う理由とは、どんなことでしょうか?考えられる理由をあげてみましょう。
①今までの自分の人生に満足しているから
②今の自分や環境が好きだと思えるから
③これからの未来が幸せなものになると思っているから
(幸せな人生を歩もうと思っているとも言えますね)
わかりやすく言うと、①=過去、②=現在、③=未来と分類できると思います。どれか一つでも当てはまれば、『また自分に生まれたい』と思う理由になり得るのでは?
■今はNOでも、そう思う時が来るのかも
20代の数字が低かったのは、若さゆえ、まだ人生や自分自身さえも模索中である人が多く、現在・過去・未来に幸せを見いだせていないからなのかもしれません。反対に、40代・50代と歳を重ねると、それだけ長く自分自身と向き合っていることになり、自分そして周りの環境も愛せるようになるということなのでしょう。
恋愛では、たくさん会えば会うほどその相手を好きになりやすいという統計結果も出ていますが、自分自身においても同じことが言えるのかもしれませんね。
残念ながら、生まれ変わっても自分になりたいというのは、現実的には叶わぬ夢。寿命を終え生まれ変わったとしても、現在の自分の姿ではなくなってしまうからです。誰しも今世は一度きり!それならば『生まれ変わっても、また自分になりたい』と心から思えるような人生を送りたいと思いませんか?
(文/しらべぇ編集部・小林香織)
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2014年12月09日 12:08
これはホントです、、、私も実践中。。。
■ 押切もえも実践!「白湯」飲むとキレイになれるってほんと!?~その効果編~
撮影現場でモデルさんが水分補給するとき、コーヒーや紅茶よりも常温のお水やお湯を飲んでいるのが前から気になっていたのですが、現在発売中の『美的』1月号で気になる記事を発見!
それによると、何も混ぜない飲料のお湯=「白湯」にはキレイになれる効果があるらしいのです。
もえちゃんも実践してます
そんな白湯のスゴい効果とは、主に以下の4つ。
1 胃腸を温める
胃腸を温めると、全身の代謝がよくなったり、消化力が向上したり、冷えから体を守ってくれたりと、女子的にはうれしいことばかり!
2 代謝が上がる
体温が上がることによって代謝がアップすると、不必要な脂肪が燃えて、ダイエット効果が期待できるそう。
3 デトックス効果がある
白湯を飲むと、胃腸の壁など、体内にたまった未消化物や、それが原因でできた毒素を排出してくれます。便秘が解消したり、むくみにも効果的!
4 心と体のバランスが整う
精神的にリラックスできることによってストレスに強くなり、風邪なども引きにくくなるそう。適度に体が温まることで、眠りの質も向上します。
担当の美的編集部・黒一点先輩によると、「昔からあった健康法ではあるのですが、ここ数年タレントやモデルさんが実践していたり、美的編集部スタッフも日常的に白湯を飲んでいたりしているのが気になっていたんです。調べるとやはり奥が深くて、美容の視点的にもいいことづくめでした」とのこと。
押切もえさんも実践しているという「白湯」習慣、起き抜けの一杯に、寝る前に……おすすめです!(五十嵐ミワ)
[Woman Insite]
Posted by nob : 2014年12月08日 06:25
私も休煙中、、、きっぱり止めようと考えずにしばらく休むつもりで気楽に取り組めば止められ、いや休み続けられます。。。
■医師が伝える禁煙法とは!?
その1 喫煙の体への影響は!?
喫煙は全身のあらゆる臓器の機能低下や癌化に大きな関連があると証明されています。
中でも最も影響をうける臓器は肺です。
喫煙により肺組織への悪影響で肺活量がおちたり、将来癌にかかる可能性が高くなることは証明されています。
ただ個人差が非常に大きいので、一概に喫煙数だけで議論ができるものでもありません。非常に大量の喫煙をされている方でも、大きな問題なく経過される方もおられえば、少しの喫煙でも先程述べたような大きな影響を 引き起こす可能性もあります。
また、喫煙と体力低下の関連についてですが、やはり個人差が多いのが事実です。同じ喫煙量でも影響を強く受ける方と、あまり受けない方がおられます。しかし先ほど述べたように、肺はもっとも影響をうける臓器です 。喫煙によって肺組織への悪影響で肺活量が低下したり、将来の癌化に大きな影響を及ぼすことは証明されています。ただ先ほども述べましたように個人差があるので、一慨に線引きできないのが事実です。
一般的に一日の喫煙本数×喫煙年数で計算される数値をBrinkman指数(ブリンクマン指数)と呼びます。この値が400を越えると、癌の発生リスクが高くなるとされ医療現場で一つの目安として使われていますので参 考にしてきてください。
※Brinkman指数…喫煙量と喫煙年数を掛けた数値。1日の喫煙本数×喫煙年数で表される。この数値が400を超えると癌(がん)が発生する危険性が高くなるとされる指数。
その2 禁煙法伝授!!
①喫煙と結びついている今までの生活行動パターンを変える!
たとえば、洗顔、歯磨き、朝食など、朝一番の行動順序を変える。食後早めに席を立つ。コーヒーやアルコールをひかえる。食べ過ぎない。過労をさける。夜ふかしをしない。喫煙のきっかけとなる環境を改善するなどが挙げられます。
②喫煙のきっかけとなる環境を改善する!
たとえば、タバコ、ライター、灰皿などの身近な喫煙具をすべて処分する。 タバコが吸いたくなる場所をさける。(喫茶店、パチンコ、飲み屋など) 喫煙者の周囲に近づかない。自分が禁煙していることを周囲の人に告げる。等が挙げられる。
③喫煙の代わりに他の行動を実行する!
たとえば、深呼吸をする。 水やお茶を飲む。 散歩や体操などの軽い運動をする。糖分の少ないガムや仁丹、干昆布をかむ。 歯を磨く。机の引き出しなどの整理をする。 プラモデルの制作や庭仕事をする。 音楽を聴く。 時計を見て、吸いたい衝動がおさまるまで秒数を数える。等が挙げられます。
その3 禁煙外来の存在!
呼吸器内科で禁煙外来をしているところがあるかと思います。 禁煙に良いお薬治療もございますので、そちらでご相談頂くのが一番有効かと思います。
また自宅で可能な手段として、薬局でニコチンパッチなどが売っていますので、それで試してみられるのも一つかもしれません。
ただ効果は不透明な部分も多いので、一番の近道は病院の禁煙外来に通われるのが一番であると考えます。
[Doctors Me]
Posted by nob : 2014年12月02日 17:51
また旅立つ君へVol.80/久方ぶりのhikaruからの便り、、、かのような親しい心象、、、hikaruの旅は終わらない。。。
■旅は楽しいものじゃない。それでも「なぜ旅に出るのか」?
世界中の美しい空、海、山、遺跡、田園、街、人。今、それらは様々なメディアを通してすぐに見ることができます。写真や動画を通じて、わたしが今いる場所から遠く離れた世界の、切り取られたものを見るのは簡単です。
ですが、それらは決して「すべて」ではありません。この世界のどこかにある、ごくごく一部です。
今日は、わたしが大学を休学して8ヶ月間「好きなところに好きなだけ滞在し、その土地の日常を見る」とだけ決めて一人で放浪していた時の話を交えながら、「旅」とはそもそも何なのか考えたいと思います。
「旅」は絶望から始まる
「旅」と呼ばれるもののほとんどを定義づけているのは、「移動」ではないかとわたしは思います。
なにせ、食事をしたりお喋りをしている時間よりも、バスや電車、歩いたり飛行機に乗って移動している時間の方が圧倒的に多いのです。もし仮に移動をやめると「生活」が生まれます。よくバックパッカーの間で、居心地がよすぎて一箇所に長期間滞在することを「沈没する」と言いますが、この「沈没している状態」は、厳密に言えば旅をしている、とは言えないかもしれません。
つまり、旅というのは常に「移動し続ける」ことであるということです。ほかにもたくさん考え方があるかと思いますが、今回は、この定義に則りたいと思います。
さて、移動し続けていると分かるのですが、旅をしている間にふと気づきます、「あれ、わたしってどこまで行ってもよそ者だわ」と。例え行く先々で仲良しの友人や大好きな人ができたとしても、「わたしは根っからここの生活文化に浸ることはできないし、会得することはできない」と感じてしまいました。
わたしは、旅の滞在方法として「カウチサーフィン」を使っていましたが、あらゆる日常には、積み重ねてきた時間、歴史があり、わたしはこの国のことを何も知らず、目の前にいる友人たちが今生きているその土台を積み上げてきたものを何も共有していないという事実に、しばしば打ちのめされました。
それを決定的に感じたのは、8ヶ月の旅の前半でドイツで出会ったアナと、わたしの帰国前にイスラエルを一緒に5日ほど周った時でした。
エルサレムにあるイスラエル博物館に二人で行ったのですが、年代別にイスラエルの、主に戦争の歴史について展示物が並んでいて、入館するや自然と二手に分かれて、思い思いに館内を回りました。そして、ちょうどアウシュヴィッツ強制収容所など、第二次世界大戦中のエリアに来たとき、ふと顔を上げると目の前にアナがいて、わたしも彼女も涙を流しているのに気づきました。
目があっても、わたしもアナも何も言わなかったけれどお互いなんとなく何を考えているかわかりました。そして同時に、過去の歴史を知る同世代の立場では在れるけれど、彼女の涙の本質は、ドイツと日本という違う「背景」がある限り、根底からは共有し得ないのだということにショックを受けました。
永遠によそ者であると自覚することは、大変勇気がいります。なぜなら、圧倒的な孤独を受け入れることになるからです。ですから、わたしの旅はほとんど絶望から始まりました。なんてわたしは無知で無力なのか、という絶望と、どこへ行ってもよそ者で有り続けるという、旅の最中における必然的な孤独に対する、絶望でした。
どこへ行けども居るのは「人」
旅の最中に、本当にわくわくして心躍ることなんて、まさにわたしたちがネットで飽きるほど見ている絶景写真なんかと一緒で、ごく一部でしかありません。
もっと日常的な話をすれば、実際は、お風呂に毎日入れるわけでもないし、食事だって美味しくないものもあるし、街ゆく人に話しかけても誰も助けてくれなかったり、洗濯も満足に出来ず何日も同じ服を着ていることなんてザラです。(もちろん、目的などによってスタイルは変わりますが、言ってしまえばお金さえあればいくらでも快適さを買うことはできると思います。)
先ほど、わたしは「あらゆる日常には、積み重ねてきた時間、歴史があり、わたしはこの国のことを何も知らず、目の前にいる友人たちが今生きているその土台を積み上げてきたものを何も共有していない」と書きました。
けれど、それは日本であろうとどの国であろうと同じなのではないか、と思うのです。生まれてこの方まったく同じ環境で育った人間なんで誰ひとりとしていないのだということです。当たり前です、当たり前ですが、わたしたちは普段「日本人だから」「女だから」「男だから」となんとなくわかりやすいカテゴリーによってイメージを固定化しているように思います。
ですが、そのイメージから大きく逸れることだって十分有り得ますし、生活や文化の土壌が違うから分かり合えない、というのは異国であろうと日本であろうと発生する現象なのです。だから「ああ、これは解決できるできないの問題ではなく、揺るがない事実で、だから優劣とかそもそも無いんだ」と分かり、すっと憑物が落ちたようでした。
また、三大欲求や衣食住といった、人間を人間たらしめる要素は、国の違い云々は全く関係ありません。結局、行けども行けども、人は人がいるところへ旅をしようとするのだと思います。移動する先、旅の先には、かならず「人」がいました。
理由や目的はどうでもいい。まずはやってみる
冒頭の問いに戻りましょう。「旅」とはなにか?
これに答える前に、わたしがよく聞かれる質問について、さいごに少しだけ。
8ヶ月の一人旅に行っていたと言うと、「どうして旅へ行ったの?」とよく聴かれます。ですが、一度として納得のいく答えを返せたことがありません。なんとなく、目的や理由というのはいくらでも後付けできると思います。ただ、「移動」することによって得た気づきは、同じ場所で延々生活し続けていただけでは決して得られないものでした。
旅に出ようか迷っているひとに、「まあまずは行ってみなよ」と言うのは簡単です。やってみないと、自分が何を求めていたのか分からないこともあります。まずは、行動に移せないのか移さないのかを明らかにすること、そしてそれが解消できることであれば、ひとつずつ潰していくしかありません。そこから、「旅」を通した自分との対峙が始まっていると思います。
ですから、まとめると、旅とは「移動」であり、よそ者であるわたしが、自分と周りの世界の孤独と向き合うための手段だと思います。
さいごに、付け加えておきたいのは、これらはすべてわたしの「感覚」の話で、「教養」の話ではないということです。そしてもちろん、すべての人に当てはまる話でもありません。あなたもわたしも永遠によそ者、でも分かり合おうと近づけば、なにか共鳴するものが見つかるかもしれません、あなたもわたしも「人」であることは同じですから。
Misaki Tachibana
富士山の麓で生まれ、今は日本文学を勉強中。好きな作家は川上未映子と堀田善衛。おばあちゃんになったら、国内外問わず、山の中で書道の先生をやるのが小さい頃からの夢です。
[TRiPORT]
Posted by nob : 2014年11月26日 08:14
受け容れるためには、、、まずは受け止めることから。。。
■平凡がいちばん!? 幸福学者が「幸せ」を語る
ドイツにおける幸福研究の第一人者、ヘルベルト・ラスツィオ氏の子女、ソニアさんは、一風変わった幸福論で有名です。彼女の幸福感とはいったいどんなものなのでしょうか。
幸せになる秘訣は「受けいれること」
著書「幸福なんてクソくらえ(現題:Fuck Happiness)」をとおして時の人となった彼女。「ヨーロッパにおける幸福研究所」の研究員としても働いています。そのソニアさんによると、幸福を感じるうえでいちばん大切なものは、「受けいれること」であるといいます。
1、自分の力ではどうしようもないことを受けいれる
現実を見て、ときには事務的になることができる人間の方が、人生の満足度が高いといいます。仕事にしろ、家族にしろ、友人・恋人に至るまで、私たちは「こうあるべき」という思いに縛られてしまいがち。しかし、そういったいき過ぎた期待感を強くもつほど、かなわなかったときにの失望は大きいのです。
2、人を幸せにしようとすると自分にもどってくる
人が不幸を感じる原因は、他人から何かがもらえることを常に期待しているから。つねに他人に期待してばかりではいけません。自分を幸せにしてくれるのはなにか、だれかを幸せにしてあげられるものはなにかを考えましょう。そうすると、おのずと信用や信頼という、人と自分を幸せにしてくれるものが見えきます。
「Sonia Lazlo」より引用
ソニアさんは幸福が人間にとってどのように働いているのか面白い例を挙げています。
サルにリンゴを1個与えます。するとサルは喜びます。つぎに、こんどはレーズンを与えます。すると、リンゴをもらったときよりももっとサルは大喜びします。少したってから、そのレーズンを取りあげます。その結果、目の前のレーズンがなくなったことにサルは深く落ちこむと言います。
日々を受けとめるのが大切
人間もおなじように「もっともっと」と欲を出すことで幸せになろうとします。けれど、この「幸福感」は長くは続きません。本来のありがたみ(最初にもらったりんご)をすぐに忘れてしまうからです。だから普通でいること、いまの状況に満足して平凡でもいいからそのままの日々を受けとめる。そのことで、すこしいいことがあったときに幸福を感じられるようになるのだと思います。
そして、幸せを長続きさせたいのなら、日々のちいさな満足を感じとれるようにするのが大切です。幸福とはすでにあなたの手のなかにあるのですから。
[Sonia Lazlo/MY LOHAS]
Posted by nob : 2014年11月26日 08:07
いずれにせよ私は朝晩ゆったり美味しくいただく毎日です。。。
■コーヒーは結局、カラダに良い? 悪い?
食、医療など“健康”にまつわる情報は日々更新され、あふれています。この連載では、現在米国ボストン在住の大西睦子氏が、ハーバード大学における食事や遺伝子と病気に関する基礎研究の経験、論文や米国での状況などを交えながら、健康や医療に関するさまざまな疑問や話題を、グローバルな視点で解説していきます。
全日本コーヒー協会が発表したデータ(出所:ICO統計/2014年7月)によれば、日本のコーヒー消費量は世界でも第3位に入るほど、コーヒー愛好国になっています。
一方で、気になるのがコーヒーが健康に与えるという“うわさ”の数々。はたして真相はどうなっているのでしょうか?
コーヒー愛好家のみなさんの中には、“悪いうわさ”──不眠になる、情緒不安定になる、発がん性があるなど──から、「控えている」という人も多いかもしれません。でも、真相はどうなっているのでしょう?
ハーバード公衆衛生大学院は、科学的根拠に基づいたダイエット&栄養の情報を、臨床医など医療従事者、メディアや一般の人向けに提供しています。その中で、「コーヒーと健康」に関するいくつかの疑問に、同大学栄養学科のロブ・ヴァン・ダム教授が、自身の研究から答えているものがあります。さっそく、見ていきましょう。
■参考文献
Harvard School of Public Health「Ask the Expert: Coffee and Health」
[1]ダム教授の研究結果による、コーヒー愛好家の良いニュースとは?
ダム教授らハーバード大学の研究者は、約13万人の健康な男性と女性のボランティアを対象に、コーヒーの摂取と死亡率の関係を調査しました。
研究開始当時、対象者は40〜50代で、その後18〜24年間の追跡調査を行いました。期間中に、コーヒーの消費量を含め、対象者の食生活やライフスタイルの習慣を追跡し、さらに死亡した人を記録。コーヒーが、がんや心血管疾患などあらゆる原因による死亡のリスクには関係がないという結果が出ました。
さらに、1日にコーヒー6杯まで飲んだ人でも、死亡のリスクは増加しませんでした。つまり、一般の人にとってはコーヒーが、深刻で有害な健康への影響がないことを示しています。
■参考文献
American College of Physicians.「The Relationship of Coffee Consumption with Mortality」
[2]コーヒーが有害ではないことが、どうして重要な研究結果?
コーヒーは、喫煙や飲酒などと同じように、不健康な習慣というイメージがあります。そのため、コーヒーが好きなのに、飲む回数を減らしたり、やめるための努力をしている人も多いでしょう。ですから、コーヒーが有害ではないという結果が重要なのです。
[3]毎日飲む、コーヒーの量の上限は?
もしコーヒーを飲んで、振せん(意思とは無関係に起きる、細かいふるえ)、不眠、ストレスや不快を感じているなら、明らかに飲み過ぎです。ダム教授らの研究によれば、コーヒーを1日6杯まで飲んでも、死亡率やその他の健康への負の影響は、特にありませんでした。
ただし、注意が必要なのは、ほとんどの研究のコーヒー1杯の定義は、カフェイン100mgを含む、8オンス(=約240ml)のカップで行われていること。例えば、ティーカップであれば150ml程度、マグカップだと250〜300ml程度のものが一般的なので、マグカップで6杯だと、多くなってしまう可能性が高いですね。
もう一つ、これらの研究で飲まれるコーヒーは、ブラックか、入れても砂糖やクリームを少量だということも、注意が必要です。コーヒーにポイップクリームを浮かべたウインナーコーヒーや甘いカフェオレを飲み過ぎれば、肥満や糖尿病の原因になりますので、ご注意ください。
[4]それでは、コーヒーの利点を示す研究はありますか?
ここ数年の研究で、コーヒーの摂取で、2型糖尿病、パーキンソン病、肝臓がんや肝硬変が予防されるのではないかとの発表がされてきています。また、ダム教授らの研究では、めったにコーヒーを飲まない人に比べて、定期的にコーヒーを飲む人は、心血管疾患による死亡のリスクがやや低くなりました。
ただし、この分野の研究は、議論が非常に活発で、まだまだ賛否両論。今の段階では、コーヒーが好きではない人に対して、健康に良いからと無理にコーヒーを飲むことを薦められません。
ただし一般的に、妊娠中や、血糖や血圧のコントロールに悩む方以外は、コーヒーは、ヘルシーな飲み物の1つと言えます(もちろんブラックや砂糖、ミルクが少量のコーヒーに関してです)。
[5]どうして科学者たちの間で意見が対立するのですか?
多くの人は、「コーヒー=単なるカフェイン入りの飲み物」と考えています。ところが実際には、非常に多くの異なる成分を含む、とても複雑な飲料です。ですから、コーヒーを飲むと、健康に多様な影響をおよぼします。でもそもそも、どんな食品もさまざまな成分を含むわけで、コーヒーに限らず、単純な食品はほとんどありません。
そんななか、現在、コーヒーが健康に与える影響に関して、具体的な研究が行われています。例えば、コーヒーが糖尿病のリスクになるかなどですね。一方で、ダム教授らの研究は、長期間にわたるコーヒー摂取と死亡率を見て、全体的な健康への影響を調査したものでした。
もともとコーヒーの研究は、ほかの食品よりも少し複雑でした。背景にはコーヒーを飲む人の中に喫煙者、運動不足の人、栄養のバランスが欠けている人が多く、特に初期段階の研究では、それらのライフスタイルの因子を除外することが難しかったことが影響しています。結果、数十年にわたり、実際には、ほかの因子が関係している可能性があるにもかかわらず、コーヒーがある種のがんや心臓病のリスクを増加させると報告されていました。
ダム教授らの調査のように、すべてのライフスタイル要因についての多くの情報を含む大規模な研究では、それらのリスクは見つかりませんでした。
[6]妊娠中のコーヒーやカフェインのリスクに関する最新の研究結果は?
妊娠中の女性のコーヒーやカフェインの大量摂取が、流産のリスクを高める可能性についての論争があります。まだ結論はついていません。ただし、カフェインは胎盤を通過し、胎児に到達し、胎児はカフェインに非常に敏感です。ですから、妊娠中の女性は1日1杯程度に控えるべきだと考えられます。
[7]高血圧や糖尿病の人は、コーヒーやカフェインの摂取量を減らすべき?
カフェインをまったく摂取していない人がカフェインを摂取すると血圧が上昇しますが、摂取後1週間以内に、血圧の上昇は顕著に表れなくなります。
ただし、数週間、継続的にカフェインを摂取した場合、血圧の上昇が少し残る場合があります。
もともと高血圧でなければ、カフェインは血圧に影響しません。ただ、高血圧の人で、血圧のコントロールに悩んでいる場合は、カフェインなしのコーヒーを試して、血圧に良い影響があるかどうか確認してみると良いでしょう。
糖尿病に関しては、パラドックス(逆説的)といえます。多くの研究で、カフェイン入り、カフェインなし、どちらのコーヒーを多く飲む人も、2型糖尿病のリスクが低いと報告されています。ところが急性期(症状が比較的激しい時期)は、カフェイン入り/なし、どちらかのコーヒーを飲んだあとにブドウ糖を多く含む食品を摂取すると、インスリンの感受性(インスリンの効き具合)が下がり、血糖が予想以上に上がります。
これまでに、コーヒーの摂取と、血糖のコントロールに関する長期経過を観察したデータはありません。ただし、糖尿病の人で、血糖のコントロールに悩んでいる場合、カフェインなしのコーヒーを試してみて、血糖によい影響があるか確認してみてください。カフェインあり/なしの両方を同時に止めるより、カフェインありからなしにスイッチしてみてください。カフェインなしのコーヒーが血糖の反応を抑えたという報告もありますから。
[8]コーヒーでパラドックスが起きる理由は?
カフェインそのものが健康に与える影響と、カフェイン入りコーヒーとが同様に語られるケースが多いことも要因でしょう。カフェイン入りのコーヒーでも、一般的にはカフェイン含有量に基づいて健康への影響が予想されていることが多いわけです。
例えば、運動のパフォーマンスを上げる点から考えると、カフェイン摂取はある程度有益と考えられています。ただし、この場合のカフェインは、カフェイン入りのコーヒーを想定していません。
またカフェインと、カフェイン入りコーヒーの効果を比較した場合、カフェイン入りコーヒーは血圧の上昇を引き起こしますが、含まれているカフェインの量から想定されるよりは、弱いものです。食後のコーヒーとカフェインが、血糖値に与える影響についても同様のことが言えます。
コーヒーには、カフェインの効果を打ち消す化合物が含まれている可能性があるのです。今後、より多くの研究が必要なポイントです。
[9]ペーパーフィルターでコーヒーを淹れるとヘルシー?
コーヒーはLDL(悪玉)コレステロール値をあげるカフェストールと呼ばれる物質が含まれています。カフェストールはコーヒーの油性成分(油性画分)に含まれます。
ペーパーフィルターでコーヒーを淹れると、カフェストールは、フィルターに残ります。一般的に、フレンチプレスコーヒー、トルココーヒーなど未ろ過のコーヒーは、カフェストールの量がはるかに高くなります。コレステロール値が高いなどで気になる人は、ペーパーフィルターで淹れたコーヒーやインスタントコーヒーを選んだほうが良いでしょう。
エスプレッソは、フレンチプレスコーヒー、トルココーヒーなどよりも、カフェストールが少なく、ペーパーフィルターで淹れたコーヒーよりも高くなります。
ということで、全般的に見れば、コーヒーはヘルシーな飲み物といえますね。愛好家の人も、安心して、コーヒーを楽しんでください。また、妊娠中の女性、血圧や血糖のコンロトールに悩んでいる人は、コーヒーを控える、カフェインなしのコーヒーに切り替えることを検討してください。
これからも、コーヒーのさまざまな成分の解析が進むのが楽しみですね。
大西睦子(おおにし・むつこ)
医学博士。東京女子医科大学卒業後、同血液内科入局。国立がんセンター、東京大学医学部附属病院血液・腫瘍内科にて、造血幹細胞移植の臨床研究に従事。2007年4月より、ボストンのダナ・ファーバー癌研究所に留学し、ライフスタイルや食生活と病気の発生を疫学的に研究。2008年4月より、ハーバード大学にて、食事や遺伝子と病気に関する基礎研究に従事。著書に『カロリーゼロにだまされるな——本当は怖い人工甘味料の裏側』(ダイヤモンド社)。
[日経トレンディネット]
Posted by nob : 2014年11月22日 23:25
長年精油を愛用してきましたが、飲用したことはありませんでしたので、早速試してみようかと思います。。。
■胃腸の荒れとニキビに効く!?天然の殺菌エキス「ハッカ油」の威力とは?
丸田みわ子
秋冬は、外も室内も空気が乾燥して、のどがイガイガしやすい季節。そんな時、美容にも良さそうな「ハッカキャンディー」で、のど予防をする女子も多いことでしょう。このハッカ、のどの殺菌だけでなく、飲み会シーズンで疲れた胃腸の改善、ニキビ予防と女子の悩み改善に適しているようです。詳細を見てみましょう。
■「ハッカ油」とは?
ハッカはミントの和名のこと。アロマショップでミントの精油を買うと高価ですが、ドラックストアに「日本薬局方」準拠の「ハッカ油」があり、数百円で購入できます。「日本薬局方」準拠のものなら、ハッカ油は「薬」のように内服することもできるのです! ハッカにはメントールという殺菌作用のある成分が含まれており、口に入れた途端、スーッと鼻の通りが良くなって、気分がさわやかになるのも特徴ですね。
■風邪予防!ニキビ予防に効果あり!?
のどをはじめ、体内の各器官の粘膜を殺菌したり、胃腸の消化不良を改善する効果も望めるので、飲み会シーズンの“飲みすぎ”、“食べすぎ”で弱った胃腸の改善にも役立つでしょう。またリラックス効果も期待できるので、イライラ予防にも! そして外用としての美容アイテムとしても活躍。皮膚の殺菌作用が期待できるので、水で濡らしたコットンに数滴たらして顔を拭けばお肌が殺菌でき、ニキビ予防や外気で汚れたお肌のクレンジングにもなりますよ。
■「ハッカ油」の取り入れ方
スーパーのハーブコーナーで買えるミントだと1パック全てを使い切るには大変ですよね。そこで「ミント油」を大いに内外美容として取り入れて、秋冬の美容悩みを改善しちゃいましょう!
・ミネラルウォーターに1~2滴入れて飲めば、のどのイガイガや風邪予防になりますし、のどの痛みがひどい場合は“うがい薬”の代わりにしても良いでしょう。
・ミネラルウォーターや精製水をスプレー式の空容器に入れて、ハッカ油を数滴たらしたものを持ち歩けば、ニキビがひどい時の殺菌や、手の殺菌、食後の口臭対策としてマウスウォッシュなどにも使えます!
・熱湯に数滴たらして飲めば、話題の「お白湯ビューティー」にも!
・バニラアイスやアップルパイ、カットフルーツに数滴たらして頂くと、スイーツを食べてしまった罪悪感も減り(?)、気軽にビューティーおやつとして摂取できます。
・サラダのドレッシングやマリネ、お刺身、お肉の素焼きなど味付けのシンプルなお料理にプラス。
秋冬は空気が乾燥してウイルスも蔓延しやすい季節。殺菌効果が望め、ドラックストアで見つかる「ハッカ油」を日常生活に取り入れて、体の内側からも外側からも、健康と美肌を守りましょう!
[Life & Beauty Report]
Posted by nob : 2014年11月17日 16:29
病院と医師の選択、治療方針の決定、ライフスタイルの転換、、、自らを救うのは自分自身。。。
■がんに負けやすい人の特徴は?
健康に気をつけていても、病気になるときはなる。最終的に明暗を分けるのは、病気と適切に向き合うことができるかどうか。だが、よくも悪くも情報が溢れている世の中だ。「世間には、患者の不安に付け込むニセ医学も蔓延している」と警鐘を鳴らすのは、現役の内科医であるブロガーのNATROM氏。「例えば、流行りの『がんは治療するな』という言説。論拠となっているのは『がんによる死の80%は三大治療(手術・抗がん剤・放射線療法)によるものである』『アンケートで271人の医師に“あなた自身に抗がん剤を打つか”と質問したところ270人が“断固NO”と回答した』といった情報ですが、いずれも出典が明らかではなく、現代の医療事情に則してもいない、明らかなデマです」
とりわけ、大きな誤解を受けているのが「抗がん剤治療」だ。
「多くの場合、固形がんに対する抗がん剤治療は延命治療にすぎず、その意味ではいずれ亡くなってしまいますが、副作用を考慮してでも長生きしたい患者さんにとっては検討に値する選択です。また、白血病などの血液性がんには抗がん剤がよく効く。これらの事実を無視して『抗がん剤は毒だ』という単純な主張を鵜呑みにすると、いたずらに寿命を縮めかねません」
厄介なのは「自分は抗がん剤など使わなくても治った」などの経験談を持ち出し、善意で患者にアドバイスをする身内や知人の存在。
「がん治療はケースバイケースなので、体験談に振り回されるべきではない。食事療法の類いも、少しなら心の安寧になりますが、やりすぎると闘病時に何よりも大切な“体力”を奪います」
専門家の意見をやみくもに求めるのも危険行為だという。
「主治医の紹介状を持って別の医師の意見を聞く『セカンドオピニオン』と、紹介状を持たない『ドクターショッピング』は別物。後者の場合、患者さんの説明だけでは病状も主治医の治療方針も正確にはわからず、ツラい検査をやり直したりするハメに。主治医に黙って診てもらっているため、異なる結論が出たときにどちらを取るか悶々としてしまう患者さんもいますね。なんにせよ、余計な消耗を強いられるだけです」
◆TEST 当てはまる項目にチェック!
□ 100万部売れている医療本の内容は信用していいと思う。
□ 実際に病気を経験した人の体験談に勝る情報はないと思う。
□ 病院の治療だけでは不安なので、食事療法にもこだわりたい。
□ 体調がいいときは、ムリに薬を飲まなくてもいいと思う。
□ 主治医以外の意見も聞きたいので、とりあえずいろんな病院を回りたい。
3つ以上は赤信号だ。11/17発売の週刊SPA!では「早死にする人検定」を行っている。ほかにもチェック項目があるのでぜひ試してほしい。 <取材・文/週刊SPA!編集部>
[日刊SPA!]
Posted by nob : 2014年11月17日 16:21
また旅立つ君へVol.79/遠回りばかりしてきたからこそ、、、
自分自身が満足するという原点に辿り着くことができた。。。
Posted by nob : 2014年11月15日 19:55
ツボ、、、侮れません。。。Vol.2
■肩に3つ、背中に2つ、おへその周囲に2つ、手に2つ、そして足に4つ、万能のツボと呼ばれている計13のツボ。これだけ覚えておけば、まずほとんどの症状がカバーできるというツボを紹介します。
肩のツボ
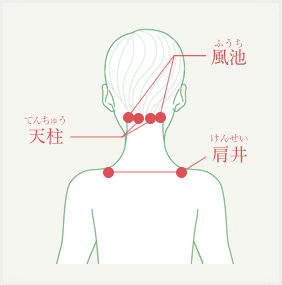
風池【ふうち】
熱っぽい、セキが出るなどの風邪の症状にピッタリ。
そのほか目、耳、鼻、頭痛にも効果があります。
頭を支える太い2本の筋肉のはえぎわのところ、天柱のツボのさらに1㎝くらい外側、風邪のツボともいわれる。
髪に注意。
肩井【けんせい】
首や肩のコリ、寝違え、目、耳、歯痛、頭痛など。全身の血行がよくなるので冷え症にも効果があります。
首のつけ根と肩の先のちょうど中間で押すと重い痛みのあるところ。
天柱【てんちゅう】
目、耳、鼻など頭に関するツボ、頭痛にもピッタリ。慢性的な、なんとなく頭が重いときにも効果があります。
頭のうしろのはえぎわ、頭を支える2本の太い筋肉の間のくぼみから両側に親指1本分外側にあるツボ。
髪に注意。
背中とおなかのツボ
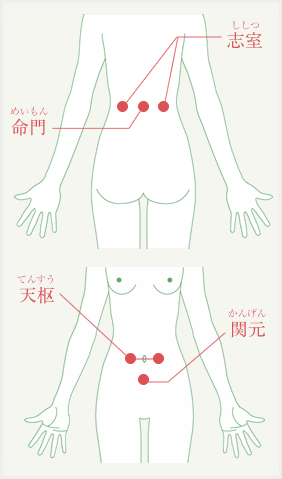
命門【めいもん】
つかれをとり体調をととのえるツボ。腰痛、冷え症、下痢などひろくカバーします。
おへそのちょうど真裏の背骨と背骨の間にあるツボ。
志室【ししつ】
元気がでない、腰痛、冷え症など、つかれたとき思わず腰に手がいく、あの場所にあるツボです。
おへその真裏にある命門から指4本分両外側にあるツボ。
天枢【てんすう】
消化不良、慢性的な下痢、便秘にきくツボ。さらにヒザや腰痛にもきくとされています。
おへその両側、指3本外側のツボ。
関元【かんげん】
胃腸障害をはじめ、冷え症、生理痛など女性特有の症状にも効果があります。
おへそから下に指4本さがったところ丹田とも呼ばれるところ。
手のツボ
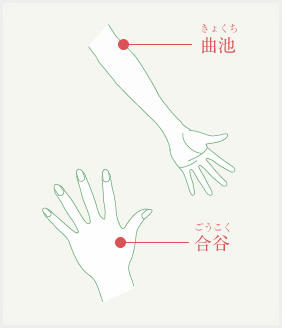
合谷【ごうこく】
風邪のひきはじめや目、鼻、歯の痛みなど首から上の症状に効果的。ほかにも肩こり、ストレスなど万能のツボともいわれています。お灸体験にはまず、この合谷でためしてみることをおすすめします。
手のこうを上にして親指と人さし指の間のくぼみを押え、痛みのあるところ、気持ちのいいところ。
曲池【きょくち】
ヒジの痛み、肩こり、テニスエルボー、パソコンつかれ、歯痛や胃腸をととのえる役割もあります。
右の曲池は右手を曲げ、左手の親指で右のヒジの曲がり角を押さえ、痛みのあるところ、気持ちのいいところ。
足のツボ
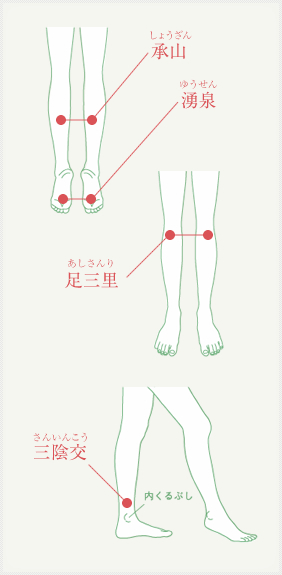
承山【しょうざん】
足のつかれ、むくみなど足の症状にきくツボ、こむらかえり、ギックリ腰にも効果があるとされています。
かかとからアキレス腱に沿って指を上にすべらせてきて、ふくらはぎの筋肉の境目にあたるところ。
湧泉【ゆうせん】
首のコリをほぐし、頭の血行をよくする。体のだるさ、つかれを取る。腰や膝痛、不眠にも効果があるとされています。
足の裏、土ふまずの前のほうにある。足の指をギュッと曲げたときにくぼむところ。
足三里【あしさんり】
病気予防、体力増強以外にも足のつかれ、むくみ、胃腸の症状にも万能養生のツボ。
ヒザのお皿の下のくぼみから指4本分下にさがった向うずねの外側にあります。
三陰交【さんいんこう】
消化器、肝臓、腎臓などの働きを助けると共に女性特有の症状には欠かせないツボです。
足の内側のくるぶしから指4本くらい上の、スネの骨の内側のくぼみにあるツボ。
[せんねん灸]
Posted by nob : 2014年11月15日 19:43
ツボ、、、侮れません。。。
■ツボ押しで美肌をゲット!お部屋で簡単セルフマッサージ
忙しくてゆっくりとマッサージに通う暇もない、色々化粧品を試したけど改善しないという時には、時間も手間もあまりかかからず、そのうえ効果を実感しやすい美肌のためのツボを押して、セルフマッサージで美肌をゲットしましょう!
■基本のつぼの押し方
押すとぽこっと指が入る場所、また押して気持ちが良い所がツボなので、下で説明する各ツボの場所を参考に、そのまわりを押して探してみてください。見つかったら息を吐きながら押します。3秒くらいしたらゆっくりと離します。これを5回から10回繰り返します。この時あまりにぎゅうぎゅう押すと、ハリカエシといって筋肉痛のようになったり、周辺を痛めてしまったりしますので、イタ気持ち良いくらいの強さで押してください。
■胃腸の調子を整え、便秘に効くツボ
胃腸の調子が悪いと、きちんと食物が消化・吸収されないため、お肌に行くはずの栄養が少なくなってしまいます。ストレス気味で胃が重い……という人でイマイチお肌に元気がないと感じる人は、まず下記の“足三里(あしさんり)”というツボを押してみてください。また、要らないものを腸に溜めておく便秘は、便の中にある毒素を腸から吸収することになり、血流に乗って皮膚に毒素を運んでしまいます。そうするとお肌に悪影響を及ぼすことがあります。そのため、一刻も早く出すことが必要ですが、“足三里”は便秘にもよいとされていますので、便秘の人も押してみるといいかもしれません。
・ツボの場所
“足三里”は、膝のお皿の下から指4本分くらいの所にあり、スネの骨と側面の骨が交わる所の際の近くにあります。その辺りを押して、ぽこっと指が入る所がツボになります。

■血行改善に繋がるツボ
お肌の栄養は血が運んでいきますが、冷えなどで血行が悪くなるとお肌への栄養が足りなくなり、活き活きしたお肌になりません。そこで、血行を改善するツボ“三陰交(さんいんこう)”を押して血行を改善しましょう。デスクワークで下半身を動かすことが少なく血行が悪くなっている人や、立ち仕事で足が冷え気味という人にもよいツボです。“三陰交”は冷えからくる生理痛にも効くツボなので、毎月ツライ!という人にもオススメ。ただし妊娠中は注意が必要なツボなので、妊娠の可能性がある方や、妊婦さんはよく調べてからおこなってください。
・ツボの場所
足の内側のくるぶしの上から指4本くらい上の骨の際にあります。

■皮脂分泌を調節するツボ
毛穴から分泌された皮脂は、汗と混ざり皮脂膜になります。こうしてできた皮脂膜は体内の水分の蒸発を防いだり、細胞間脂質・NMFと一緒になり、お肌を守る役割を持っています。そのため皮脂が少ないとバリア機能が弱くなり、お肌が乾燥してしまうのです。しかしこの皮脂が多すぎるとベタベタとして、不快になりますよね。そこで皮脂分泌を整え、程よくしっとり肌を目指すべく皮脂分泌を調整しストレスにも効くツボ“合谷(ごうこく)”を押しましょう。
ツボの場所
親指と人差し指の骨の交わる所の際にあります。押して気持ちがよい場所を探してみてください。
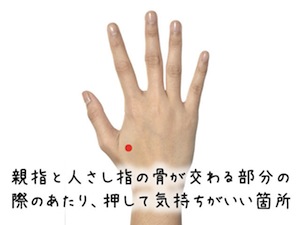
今回は、自分でできる簡単なツボ押しをご紹介しましたが、あまり熱くないアロマの香りのお灸や、ツボ押しグッズなどもたくさんあるので、そういうのを活用してもよいかもしれません。ぜひセルフマッサージで美肌をゲットしてくださいね。
[Life & Beauty Report]
Posted by nob : 2014年11月15日 19:32
休酒、休煙、玄米と雑穀白米&菜食中心の体質改善生活もはや10ヶ月、、、私の心と身体は劇的に変貌しました。。。
■中性脂肪が高くなる原因とは
さやか美容クリニック・町田 院長/皆木靖紀
健康診断で引っかかったことで、初めて中性脂肪値が高かったことに気づく人も多いと言います。そのなかの多くは、普通に生活しているだけなのになぜ?と疑問を持つのだとか。そこで、中性脂肪値が高くなる原因について解説します。
中性脂肪値を高める原因とは?
遺伝や肥満、未診断の糖尿病など、中性脂肪値を高める原因はさまざまですが、もっとも影響が強いのは暴飲暴食です。
精製された炭水化物である白パンや白米、麺類、清涼飲料、お菓子やアルコールの過剰摂取は、中性脂肪値を高める大きな原因となります。精製された炭水化物はインスリンの急激な上昇を招き、インスリンを作るすい臓に負担をかけます。
インスリンは炭水化物の消化に欠かせませんが、炭水化物を過剰に摂取するとその働きに不具合が生じ、消化しきれなかった炭水化物が中性脂肪の材料となってしまうのです。また、アルコールも中性脂肪を分解する酵素の働きを低下させるため、中性脂肪値を高める原因となります。
肥満が中性脂肪を倍増させる
暴飲暴食などが原因で体内に蓄積された中性脂肪は、肥満を招きます。そして、その肥満がさらに中性脂肪を高めるという悪循環になるのです。
肥満になると体内に脂肪が溜まりますが、太ももやお尻につく皮下脂肪や主にお腹まわりにつく内臓脂肪以外は、ほとんど全てが中性脂肪です。
肥満になると動かなくなり、エネルギーの消費が低下します。しかし、食欲は変わらないため、食事量はいつもと変わりません。そうすると、余分な糖質や脂質が溜まってしまうため中性脂肪も増え、さらに太り、さらに中性脂肪も増える…という悪循環が起きてしまうわけです。
タバコも中性脂肪の原因に
タバコに含まれるニコチンには交感神経を刺激させる作用があるため、血圧を上げ心拍数を高めるなど、心臓に負担をかけますが、ほかにも次のような問題を引き起こします。
・中性脂肪の原料となる血液中の遊離脂肪酸を増やす
・善玉コレステロールの濃度が低くなる
・血液中のコレステロールが酸化し、粥状動脈硬化が進行する
これらは、いずれも動脈硬化を促進してしまう原因となります。
[メンズスキンケア大学]
Posted by nob : 2014年11月12日 23:13
たそがれていく心地好さ
留まることない時の流れに身を委ね
風のように過ぎ去っていく日々の
二度とは戻らぬ何気ない瞬間を愛おしみ
淡々と歳を慈しみ重ねていく
今日よりも素敵な明日へ
Posted by nob : 2014年11月03日 07:10
何者にもならず、何処にも属さず、何も遺さない、、、近しいスタイル私の自然発生的漂流生活もはや二十有余年。。。Vol.3
■堀江貴文氏が語る、「生きるのに必要なこと」
僕が「家もプライドも要らない」と思うワケ
吉川明日香
東洋経済オンライン編集部
9月に瀬戸内寂聴との共著『死ぬってどういうことですか? 今を生きるための9の対論』を上梓した。死ぬこと、生きることって何なのか。堀江貴文氏へのインタビューを前編、後編に分けてお届けする。
堀江貴文氏が考える「生きること」とは
先を考えることに意味ってあるの?
――瀬戸内寂聴さんとの共著本の中で印象的だったのが、「死にたいと思ったことがない」とおっしゃっている箇所でした。たとえば仕事に命やプライドを懸けている人は、それが思いどおりにならないと強烈にへこむことがある。場合によっては死を選ぶことがあると思うのですけど、堀江さんには無縁の発想だと感じました。
何でへこむんでしょうね。よくわからないです。
――自分の基盤が危うくなったと感じ、未来がかすんでくるからじゃないでしょうか。
そもそも、僕は未来なんか見てないですね。今を一生懸命生きるっていうスタンスです。逆に、先を考えることに意味があるのかわからないのです。何かメリットがあるのかというと、別にない気がする。未来のことを人に聞かれたら「先のことを考えたら何かいいことあるんですか?」っていつも聞くんですけど、ないでしょう? なんかあります?
――たとえば30歳で結婚して、40歳で家を買って、50歳で子供が成人して……と長期的視点で人生を思い描くことで、計画的に物事を進められたり、安心感が生まれたり。
それは何なんでしょうね。何かいいことあります? それで。
――堀江さんは計画的な人生はお好きではないですね…。
はい。割と行き当たりばったりで生きています。それが面白いじゃないですか。明日何があるのかわからないから面白いんであって、明日がわかっていたらつまらないでしょう。
世の中は、農耕からシェアへ
――確かに、それには反論はしにくいです。
だから、(未来を見ることは)意外と別に何の意味もない。何でかと言うと、たぶん、そういうのって、道徳とか倫理とか常識にとらわれているからじゃないでしょうか。なんでそうなったのかなって考えたら、たぶん、農耕に縛られていたからかなと思いますね。
――農耕民族の農耕ですか。
そうです。いわゆる長期的視点うんぬんっていうのは、そこが起源なのかなという気はしますけどね。農耕は予定も立てなきゃいけないし、先のことを考えないとできないでしょう。そういうふうにして初めて作物がちゃんと育っていくので。生きていくために必要だったのだと思いますよ。決して楽しいことではないんだけど、生きていくために必要だからやっていた。そのためにいろんな、たとえば一夫一妻制の結婚制度や家っていう概念、家族っていう概念もたぶん必要だった。
最後にオフバランス化したいのは、洋服
――本の中でも「家を所有しなきゃいけない理由はない」とおっしゃっていましたね。
そう。僕は、賃貸もやめました。家を契約して借りる意味もよくわからないから。今はホテルに住んでいますね。
――たとえ期間限定の家であっても、所有することが謎だと。
謎っていうか、なんかいいことあるのかなって思う。それはもう、僕自身が楽しく生きるために全体を最適化していく中で、当然、出てくる解で。人生のクオリティ・オブ・ライフを上げていくうえで非常に大事なことですね。ちなみに僕にとっては最後、いちばんネックになっているのは服ですね。
――えっ、服、ですか?
今は所有からシェアへという流れがあるわけじゃないですか。僕は服も含めて、いろんなものをシェアするのでいいと思っているんです。
僕、今は本当に何も持っていないですよ。持ち物は、スーツケース2、3個分ぐらいしかなくて。でも、そのほとんどを服が占めているのです。服をもっとオフバランス化(編集部註:資産から外すことで、リスクや負担を軽減する)したいというか。
――具体的に、どうやってオフバランス化できるでしょうか。
考えたのは「WEAR」というファッションコーディネートアプリがあるんですけど、たとえば「WEAR」で僕のお気に入りコーディネートを20人ぐらい選んでおくと、そこから推測して8割ぐらい僕の好みの服が送られてくるとか。
ほかには、僕のGoogleカレンダーの予定を自動でさらっていってもらって、結婚式の出席が予定に入っていたらフォーマルなタキシードを送ってきてくれたり、海に行く予定なら海パンなんかを送ってきてくれたりとか。さらに2割ぐらいは“ノイズ”を入れてくれるとうれしい。「こんなのどう? 最近はやっているけど」みたいなオススメのもの。
――自分の想像もしなかったコーディネートが入っているというのは、楽しいですね。
「あ、これいいな」みたいな。そうやってブラッシュアップしていって、送ってくる前にリストを出してくれて、「これはいるけど、これはいらないな」とか自分で選べるサービスだといいですね。
しかも、それがインテリアにうまくハマるようなオシャレなダンボール箱で送られてきて、回収にも来てくれるわけですよ、しかも洗濯しないでいい。着たらダンボール箱にばんばん入れていくだけ。そういうサービスあったら使いたいなと思っていて。
――TSUTAYAのネット宅配レンタルみたいなイメージでしょうか。
あ、そうですね。着ても着なくても定額でいくらって決まっていて、松竹梅みたいなコースがある。タキシードを手配したときはエクストラチャージがかかります、みたいな。
――所有欲というのはもともと少なかったんですか。それともだんだん減ってきたんですか。
だんだん減ってきたというか、これまでは所有せざるをえなかったわけでしょう。そういう状況だったということですかね。もちろん最初は考えたこともなかったですよ。
――シェアの意識が芽生えたのは出所後ですか?
いえいえ、全然、関係ないです。シェアに対して、バチッとここからですというのもないですよ。大学生のときはルームシェアしていましたし。たとえば友達2人で借りると、より広くて環境のいい部屋を安く借りられるじゃないですか。当たり前のことだと思ってたのですけど、意外とそういうことをやっている人はいなかったですね。
――今はあまり一般的でない服のシェアも、そのうち当たり前になってくるんでしょうか。
でしょうね、たぶん。実際、僕がいちばん最後に困っているのはそれなので。実現すると後はカバン1個になっちゃいますよね。誰か(服のシェア事業を)やってほしいですねぇ。
プライドって……それおいしいの?
――本の中では、プライドの話も出てきますね。「プライドなんか持つ必要はない、自分が自分を信じればいい」とおっしゃっています。堀江さんから見て一般的な人、特に男性のプライドが気になるときってありますか?
日本はプライド高い人が多いですよね。なんでだろうなあ。
――最初の話にも関連しますが、プライドの問題で会社を辞めたり、自殺したり……。
そうですねえ、意味がわからないですねえ。そんな大事なの? 何それおいしいの? みたいな(笑)。
――プライドを原動力に生きている人もたくさんいる気がしますが、プライドに代わりうる力ってどういったものがあると思いますか?
うーん、恋愛とか。
――恋愛ですか……。
恋愛ダメですか? あと食欲とか、「面白さ」じゃないですか。
――面白さを求めるのは自然のことだと思うんですが、日本人的には言いにくいですよね。
面白さは大事ですよね。そういう意味では昔から、僕はあんまり仕事している感じはないのです。そもそも、嫌なことはやりたくないんですよね。それで厳しい顔するやつとかいたら、罵倒してしまいますね。若い頃からそうで、けっこうぶつかっていましたね。今よりも、もっとぶつかっていました。
――一般人は、立場を考えて、ぶつかることを自粛しています。家でも会社でも。
僕には、立場ってのはもともとないですよ。その立場ってのは何ですかっていう話じゃないですか。ハブられるとかそういうことですか。
――集団の中で干されるとか、会社として不利益な結果を招くとか。
まあでも、会社からはハブられましたけどね、壮大に。まあでも、全員に好かれるってことはまず無理ですよ。それに自分の考えは折れたくないじゃないですか。
大事なのは自分の考え方であって、ぶつかってもいいんじゃないかと思うんすね。もちろん、それはその人の判断ですけど。
――堀江さんのお話を聞いていると、日頃、われわれが生きていくうえで大事だと思っているものが、そうでもないと思えてきますね。
※記事後編に続く
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2014年11月03日 07:01
もはや五十にして初めて立つ、、、他人の瞳に映る幻想の自身との別離から。。。
■<サラリーマン>「こころの定年」どう克服?
若いころにがむしゃらに働いたサラリーマンが40歳前後で先が見え始め、組織で働くことの意味に悩み始める。現役サラリーマンで評論家の楠木新さん(60)は、そんな状態を「こころの定年」と名づけ、会社人間だけではない、もう一つの自分を持つことを勧めている。
10月中旬。大阪市中央区のビジネス街にあるビルの一室で、楠木さん主催の「こころの定年研究会」が開かれた。仕事帰りの男女ら約10人が参加した。
「こころの定年」とは、サラリーマン人生の前半戦と後半戦の境目にあたる40歳前後で、働く意味を見失っているような状態を指す。研究会はこれを理解し、克服する方法を考えようとスタートし、今回で52回目。座学もあればグループワークもあり、何度も参加する人も多い。
この日の参加者は、3グループに分かれ「5年後、10年後のイキイキした自分の姿」を書き出した。
「副業を成功させる」「子供たちを教える場を作る」「趣味のブログを多くの読者に読んでもらう」。参加者はそれぞれ、仕事の時とは違う、もう一つの自分の姿を語った。さらに「自分が何をすべきか、分かっておく」「年齢を否定せず動き出すべきだ」など、もう一つの自分になるための方策も次々と挙がった。
大阪市東住吉区の会社員(60)は、出向先でこれまでのやり方が通用しなくなり、こころの定年の状態になったという。「研究会でいろんな価値観に接して刺激され、仕事とは別の自分の立場で、組織の姿を見直した。すると、これまでと違った景色がみえるようになった」と振り返る。
●自らの体験もとに
楠木さんは生命保険会社で人事労務関係の課長を務めるなど、順調なサラリーマン生活を送っていた。しかし、出身地の神戸で阪神大震災に遭遇したことをきっかけに、会社だけで働く意味に疑問を持ち始めた。
仕事は続けていたが、47歳の時の転勤を契機に「もっと出世したい」という気持ちと「誰のために働いているのか分からない」との感情に引き裂かれ、出社できなくなり、うつ状態と診断された。
職場に復帰したものの平社員に降格。何をしていいのか分からない状態の中で、仕事を辞めて別の道を歩んでいる人たちに興味を持ち、片っ端から話を聞きに行った。
通信会社の社員からちょうちん職人、市役所職員から耳かき職人−−など、中年になってからこれまでと全く違った職に転身する人たち。収入は下がったものの、皆いきいきとしていた。
しかし、だれもが転身して成功するわけではない。楠木さん自身も「会社を辞める、辞めないの二者択一では精神的に追い込まれる。平社員をしながら、もう一つの自分の仕事をする第三の道もある」と、会社は辞めずに空き時間を使って、働き方についての執筆活動を始めた。
●二つの自分を持つ
楠木さんは、外でいきいきと活動することで、会社での仕事にも打ち込めるようになったという。「二つの自分を持てば、これまでと違った視点で会社が見え、負の側面ばかりでなく、良いところが分かってくる。サラリーマンをやっていると無形の情報を取り入れられる。複数の道を持てば、働き続けられることを伝えたい」と話す。
9月には東京都内で楠木さんのセミナーが開かれ、40人ほどの会場は満員に。参加者からは「励まされた」「もう一度話を聞きたい」という感想が多く挙がったという。中高年の先行きが見えない時代だけに、もう一人の自分をもつ必要性を訴える主張に共感が広がっている。
厚生労働省の2011年の患者調査によると、40〜50代のうつ病患者は男性が約16万1000人、女性が約18万人に上る。自殺者は中高年の男性に多い。
中高年のうつに詳しい新潟青陵大学の碓井真史教授(社会心理学)は「かつて中高年の男性は職場や家庭内で尊敬される存在だった。しかし近年、終身雇用や年功序列は崩れ、コンピューター操作の能力は若手のほうが上。これまでの経験がいかせないなど、職場でストレスがたまることも多い。家庭でもないがしろにされ、父親としての権威も失っているケースもある」と指摘する。その上で「職場や家庭以外の場所にやりがいをみつけることは、相対的に苦しみが減るので、ストレス解消に効果的な方法の一つといえるだろう」と話している。【柴沼均】
[毎日新聞]
Posted by nob : 2014年11月03日 06:26
おさらい。。。
■美と健康を叶える食の話
腸内環境をよくする秘策
ホリスティック栄養コンサルタント、食育アドバイザー
北川みゆき
腸内環境を善玉菌優位にすることが美肌、健康へつながる
大腸内には約100兆個の細菌が住みついており、その細菌の種類は100種類以上あるといわれています。その性質によって、大きく分けて善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3つにグループ分けすることができます。
理想的な腸内細菌バランスは、善玉菌(ビフィズス菌や乳酸菌など)が3割、悪玉菌(ウェルシュ菌、ブドウ球菌、大腸菌など)が2割、日和見菌(善玉菌と悪玉菌のどちらか優勢な方の見方をする)が5割といわれています。
善玉菌が優位だと日和見菌が見方をしてくれるので、腸内の環境を善玉菌が多い状態にしておくことがとても重要になってきます。
悪玉菌が優位になる要因には、肉食中心の食生活や野菜不足、善玉菌のエサとなるオリゴ糖や水溶性食物繊維、乳酸菌(納豆、みそ、ぬか漬け、甘酒、キムチなど)が足りない場合が考えられます。
食物繊維(不溶性も水溶性も)と乳酸菌、オリゴ糖を意識して摂ることにより、善玉菌が優位となり、腸内の環境は安定し、美肌の実現や免疫力が高まり健康へとつながります。
腸内環境を整える要となる食物繊維って?
食物繊維とは「人の消化酵素で消化されない食物中の難消化性成分の総体」と定義されていますが、実は食物繊維は、腸内細菌の善玉菌によって発酵されると分解され短鎖脂肪酸に代謝され、体内でのエネルギー源として利用されます。
食物繊維には水溶性(水に溶けるタイプ)と不溶性(水に溶けないタイプ)があります。水溶性食物繊維は海藻類(アルギン酸)、熟した果物(ペクチン)、こんにゃく(グルコマンナン)、ごぼう・きく芋・ゆり根(イヌリン)などに含まれています。
血中のコレステロール値を下げたり、糖質の吸収を抑える作用があるため急激な血糖値の上昇を抑制する働きがあります。また、腸内の善玉菌のエサとなるため善玉菌の働きを活性化し腸内環境をよくする働きがあります。
一方、不溶性食物繊維は、野菜や穀類(セルロース)、野菜やココア(リグニン)、寒天(アガロース・アガロペクチン)などに含まれています。腸内では便のカサを増して排便を促し、便の腸内通過時間を短縮するため、便秘予防や発がんの抑制につながります。
老年期に入ると腸内の善玉菌は減り、悪玉菌が増える
生後間もない赤ちゃんの便が黄色っぽく臭くないのは、母乳しか飲んでいないため母乳の乳糖やガラクトオリゴ糖を主体とした栄養源からビフィズス菌が増殖し、善玉菌のビフィズス菌優位の環境になっているためです。大人では、ビフィズス菌は10~20%の割合で腸内に存在しています。
老年期に差し掛かると、悪玉菌のウェルシュ菌の量が顕著に増え、同じく悪玉菌の大腸菌や腸球菌も徐々に増え、善玉菌のビフィズス菌の量が減ってきます。
このことからも、老年期には、積極的に乳酸菌や善玉菌のエサとなる水溶性の食物繊維やオリゴ糖を摂ることが大切になってきます。
ストレスは腸内環境を悪くする
腸内における善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れる要因は、食生活のほかに実はストレスも関係していることをご存じでしょうか。
強いストレスを受けると自律神経のバランスが崩れ、消化に関わる胃酸や腸液の分泌を低下させ消化不良を起こしたり、大腸の蠕動運動が鈍くなり悪玉菌が活性化しやすい環境になります。
自分の心と体の声に耳を傾けて、あまり無理をしないことが大切です。ストレスを感じていることを早めに認識し、疲れていると感じたらゆっくり休養をとるようにしましょう。
健康の源は大腸にあるともいわれています。食生活とメンタル面の両方を整えて腸内環境をよくして美肌と健康を実現させましょう。
[スキンケア大学・美ログ]
Posted by nob : 2014年11月03日 05:53
こわっ!?(゜〇゜;)Vol.2
■【細菌の温床】トイレの三角折り、マニキュア・・・良かれと思ってする行為が実は不潔!?
世界的には「エボラ出血熱」の拡大が大きなニュースになっていますが、これから日本もインフルエンザやノロウイルスが流行する季節。そこで今回は、大学で医学を勉強中の筆者が、意外と身近に潜んだ感染症の危険性について、ご紹介しましょう。
■トイレ「三角折り」の恐ろしい可能性
以前、しらべぇ編集部では、「トイレットペーパーの三角折り」についての調査を行いました。結果、実に62.9%もの人が「嬉しくない」と回答。理由の中には、「用を足した後明らかに手を洗っていないのに、トイレットペーパーを触るのは不潔だし、逆にマナー違反だと思う」など、清潔面を気にするものが目立ちました。
用を足し終わってトイレを出て手を洗い、ふたたび個室にわざわざ入って、次の人のためにトイレットペーパーを三角に折っている人は少ないでしょう。自分が用を足し、トイレットペーパーで拭いた後に、三角折りを実行しているとしたら、手に付着した自分の排泄物由来の細菌を次の人にプレゼントしているのは間違いありません。次の人に気持ち良くトイレを使って欲しい気持ちが裏目に・・・。
■マニキュアの剥がれかけは注意
女性だけでなく、最近はファッションに敏感な男性がマニキュアしているのを見かけます。しかし、このマニキュア、剥がれかけてくると、ばい菌が増えてくる可能性があると言われているのです。手洗いをしても、洗い残ししやすくなるからでしょう。
ちなみに、つけ爪は剥がれる前からばい菌増加の要因になっている、との報告があります。とはいえ、マニキュア・つけ爪フリークの人にとって、裸の爪なんて考えられませんよね。おしゃれをとるか、清潔な手指をとるか、悩むところです。
■トイレで手洗いの後、水分を髪になじませる
男性からすると衝撃的な事実かもしれませんが、手洗いをした後に「髪をセットするていで手を拭く女性」を、筆者も何度か見たことがあります。しらべぇ編集部がアンケートサイト「マインドソナー」を使った調査によると、女性150人中なんと105人が「髪で拭いた」経験アリ!
ワンピースやスカートなどといった女性の服には、ポケットがついていない場合が多いため、ハンカチを持ち歩けない女性の気持ちも分かりますが、人間の髪の毛は細菌の宝庫!
デートだからとデザイン性を重視したポケットのないワンピースを着たために、手洗いの水分を髪になじませ、その手で彼と手をつないでるなんて・・・きっとその彼氏は知る由もなく、彼女からの愛情たっぷりの細菌を受け取るのですね。彼氏のためにも、ハンカチを持ち歩きましょう。
意外なところに潜む細菌やウイルスに気をつけて、健康的な秋冬をお過ごしくださいね。
(文/しらべぇ編集部・こなりかほ)
[しらべぇ]
■ゲゲッ!口に触れるアノ部分が「トイレより10倍もバイ菌まみれ」と判明
並木まき
美意識の高い女性ほど日々の生活の衛生面にも高い意識を持っていらっしゃることと思いますが、みなさんはご自分のカラダの“ある部分”が、トイレの便座より5倍も10倍もバイ菌まみれだという事実をご存じでしたでしょうか……。
そんな恐ろしいことが判明したカラダの部分とはなんと、私たちが毎日使っている手のひらや指先だというのです!
アルコール消毒液を販売する健栄製薬が行った、汚れに関する衛生検査の調査結果をもとに、早速その内容をご紹介していきましょう。
■手のひらはトイレの5倍も汚い!?
“ATPふき取り検査”といわれる、微生物や食物の細胞に存在するATPを計測する検査によれば、なんと調査結果の平均数値として、手のひらは一般的なトイレの便座の汚れに比べて5倍以上の数値が測定されたとのこと!
ちなみにトイレの便座の測定値は179RLUという数値で、エレベーターのボタンは123RLU、不特定多数の人が触る階段の手すりは485RLUという測定値ですから、手のひらは階段の手すりよりも汚れが潜んでいるという衝撃の事実が判明しています。
■爪の長い人からはさらなる量の汚れが!
次に爪の間、つまり指先についての測定値を見てみると、こちらはなんとトイレの便座の10倍以上もの汚れが潜んでいると判明したのです!
指先の汚れに関しては爪の長さも影響していて、2mmを基準にそれぞれを計測したところ、爪の長い人は短い人に対して、約1.9倍もの汚れが潜むことも判明しています。
以上、衝撃の調査結果についてお伝えしましたが、みなさんは自分の“手”の衛生についてどのくらい意識をしていますか。
手は食事やメイクのときに頻繁に使う部分ですから、ここに多くのバイ菌が付着していると感染症や病気、肌荒れの原因にもなりかねません。同発表によれば手を清潔に保つためには、アルコール消毒液による手指消毒と、爪の長さを6.35mm未満にすることが推奨されているようです。
手のひらや指先が見た目には汚れていないようでも、美容や健康のために常に清潔を保てるように積極的に意識したほうがよいといえるのではないでしょうか。
[WooRis]
Posted by nob : 2014年11月03日 05:43
何がベストかは人それぞれ、、、一食で栄養のトータルバランスをコントロールできる人ならば悪くはないと思います。。。
■話題の「1日1食健康法」 体に良いのか、悪いのか
1日に1食しか取らない健康法が話題になっている。「栄養不足にならないの?」と疑問もわくが、ダイエットや若返りなどに効果があるといい、書店には多くの関連書籍が並んでいる。だが、子供のころから教わってきた「規則正しく3食しっかり食べる」という生活習慣が健康にいいと考えている人も多いはず。いったい、1日何食が体にいいのだろうか。流行の1日1食健康法をちょっとだけ試しながら、専門家たちの話を聞いてみた。(今仲信博)
■若返り遺伝子に長寿ホルモン…1日1食のメリット
多くの関連書籍などが推奨している1日1食の健康法は、朝と昼は取らずに夕食だけを取るという方法。ただ、「朝食は1日の元気の源」と言われているが、朝ご飯を食べないで本当に大丈夫なのだろうか。
「朝目覚めたときは前日のアルコールが残っていたり、胃がもたれたりしていて、胃の粘膜を回復させる必要がある。朝は胃を休めることが大切」と語るのは、1日1食の健康法の火付け役となった医師の南雲吉則さん(59)。
30代のころに仕事上のストレスから暴飲暴食に走り、体重が15キロ増加して77キロになったという南雲さんは、45歳から1日1食に切り替えて減量に成功。現在は62キロの体重を維持し、人間ドックでは血管年齢が20代といわれるまでになったという。
「最初は、おなかが『グーッ』と鳴ったら食事を取る。そのうち、夕方になっても鳴らなくなる。人間は危機的な環境になると生命力がわく。空腹でおなかが鳴っているときは若返り遺伝子が増量し、長寿ホルモンが分泌され、肌つやも良くなる」と説明する。
また、「『1日3食取らないと力が出ない』というが、現在は過食で病気になる人が増えている」と指摘し、「1日1食なら何を好きなだけ食べてもかまわない。人間の体は慣れていくので、だんだんと食べる量も減ってくる」。
ただ、この健康法は男性は30歳以上、女性は50歳以上のメタボリックシンドロームの人に推奨しているとし、「育ち盛りの子供や病人、閉経前の女性で血糖値の下がりやすいタイプの人は対象ではない。そういう人たちは1日3食取ることが大事」と話した。
「一日一食 40歳を過ぎたら、食べなくていい」の著者で、医師の石原結(ゆう)實(み)さん(66)は20年以上、1日1食を実践。石原さんは「メタボリックシンドロームや高脂血症などになる人の多くが栄養過剰者。おなかいっぱい食べられるようになったのは最近で、人類の歴史は飢餓の歴史でもあり、空腹の方が体に向いている」と語る。
ウエートトレーニングが趣味の石原さんはベンチプレスで100キロ以上挙げるといい、「1食の人はみんな元気。これから始める人はまず朝食を抜いて2食にし、だんだんと回数を減らして1食を目指すのが理想」と話した。
■臓器の能力に合わせた食事を…反対派は警鐘
健康面や美容の面からも効き目があると推進派の人たちが説明する1日1食の健康法。一方で、回数を分けた食事を推奨する人たちの見解はどうだろうか。
日本の食文化を紹介してる「日本食物史」(江原絢子・石川尚子・東四柳祥子著、吉川弘文館)によると、身分や地域、職業によって一様ではないが、日本で3度食が一般的になったのは安土桃山時代という説や、江戸時代という説など諸説あるという。そんな日本人の生活に定着した1日3食のスタイルは、厚生労働省のホームページでも「食事をする時間や食べ方などにも注意し、1日3食規則正しく食べましょう」と呼びかけている。
大正13年設立の「佐伯栄養専門学校」(東京)の専任講師で、管理栄養士の星屋英治さん(55)は「現在の成人男性に必要な1日のエネルギー量は2300〜2600キロカロリー。それを1度に摂取するのは難しく、3分の1ずつに分けて取るのが理想」と説明する。その上で、1日1食の健康法について「その人の生活習慣もあるが、1食だけだと量を多く取ってしまうため、消化吸収の面でも悪いのではないか」と疑問を呈した。
精神科医の和田秀樹さん(54)は、朝と昼にタンパク質や脂肪、午後3、4時に糖質を取り、夜は軽めの食事で済ます1日4食の食事法を推奨している。「肝臓は午前中、膵(すい)臓(ぞう)は午後3、4時ごろが代謝能力が良い。臓器の元気な時間に合った栄養を取ることが大事。臓器の能力などを考えないで食事を取ると、うまく栄養が利用できない」と強調した。
また、「太りたくないという気持ちは分かるが、栄養不足は臓器の老化を進める」と警鐘を鳴らし、「若いうちは良いだろうが、中高年の1日1食は危険だと感じている。年を取った人は、ちょっと太っている方が血色が良かったりする。必要な栄養をきちんと摂取することが、長生きにつながる」と話した。
■1日1食、ちょっとだけ体験…空腹との戦い
反対派の意見も理解した上で、流行の健康法をちょっとだけ体験してみることにした。現在33歳の記者(今仲)は、新聞記者になってからの不摂生が影響し、入社してから一時は体重が30キロ近く増加。1年半ほど前にいつもはこっそり破棄していた健康診断の結果が妻に見つかり、野菜中心で1日3食取る生活に切り替えてからはこれまでに20キロ近くやせた経験がある。それでも、体重は100キロ超えが続いている。
現在は朝を軽めに食べ、昼食は外食、夜は自宅か外食で済ますという生活スタイル。1日1食を実践した初日は昼食を取らずに水分だけで本社で勤務したが、日頃から必要以上に摂取してきた体内に残る栄養たちが頑張ってくれたのか、夕方まで特に空腹が気になることはなかった。
しかし、口さみしさだけは我慢できず、夕方以降はガムをかみ続けた。午後7時以降になるとさすがにおなかも鳴りだしたため、食事を取ろうと思ったが、この時間帯は締め切りなどで多忙な時間。1日1食を推奨する書籍では「空腹を楽しんで」と書かれているが、ビギナーの私は何をどう楽しんでいいのか分からず、結局この日の勤務が終わるまで「グーッ」と鳴るおなかと戦っていた。
勤務も終わり、「早く何かおなかに入れよう」とコンビニで弁当を買おうか迷ったが、「せっかく我慢したのにそれでいいのか」という思いにかられ、何も食べずに帰宅。この日は妻が用意してくれたペペロンチーノとサラダを食べたが、食事のありがたみを改めて感じさせられた。
翌日もおなかが鳴ったときには食事に行ける状態ではなく、夜に再び空腹と対戦。前日の反省を踏まえ、何かしらの軽食を用意しておけばよかったと、おなかが鳴ってから後悔した。
2日間試してみて、体重は2キロほど減っていたが、私にとってその程度の変動は誤差の範囲。すぐに効果が出たとは言い切れない。ただ、軽食を用意するなどの対策をしっかり取っておけば、きっと私でも継続できるだろうと思った。
2日だけ試したと南雲さんに伝えたところ、「続けてみてください」と勧めてくれた。しかし、食べることが楽しみな私にとって、1日に3回ある楽しみが1回に減ってしまうことは死活問題。健康と美容のために続けたいが、朝の卵かけご飯や昼のラーメンも捨て難い。続けるか否か−。もう少し悩んでから決めたいと思う。
[産経新聞]
Posted by nob : 2014年10月29日 09:04
こわっ!?(゜〇゜;)
■超危険「3次喫煙」とは?受動喫煙の数倍から数十倍の影響あり
米国カリフォルニア大学から最新報告
受動喫煙と比較して、「3次喫煙」と呼ばれるものが、ニコチン、ニトロソアミン化合物といった毒性のある物質からの影響が数倍から数十倍になると判明。極めて危険であると分かった。
米国カリフォルニア大学リバーサイド校を中心として研究グループが、プロスワン(Plos ONE)誌で2014年10月6日に報告したものだ。
「コットン」は「ポリエステル」より危険に
この3次喫煙とは、室内の表面に付着または環境中に停滞している副流煙成分から化学物質を吸い込むものを指している。
研究グループは、3次喫煙の成分の被害の可能性を検討。
コットンのクロス、ポリエステルのフリースをたばこの煙にさらす実験を実施。一定時間を置いてからそれぞれの素材に含まれる化学物質を抽出して、この化学品にさらされた場合の影響を推定した。
たばこの煙にさらされてから16カ月後、1時間にわたって水で抽出したところ、コットンのクロスから出てきた化学品は、ポリエステルと比べて、ニコチンは約41倍、ニトロソアミンは約78倍になった。
クロスからの赤ちゃんや子ども、成人がどれくらいの化学品の影響を受けるかを推定したところ、受動喫煙と比較して、3次喫煙で受けるニコチンは赤ちゃんでや子どもで6.8倍以上、成人であれば24倍以上になると見られた。
ニトロソアミンについては赤ちゃんや子どもは16倍以上、成人で56倍以上と分かった。
たばこの煙にさらされた部屋の中では、化学品がただよい、受動喫煙以上の影響があり得るわけだ。
日本でも今後、注目されそうだ。
[Medエッジ]
Posted by nob : 2014年10月29日 08:56
若干スタイルが異なりますが、私も肩甲骨ストレッチを日々実践しています。。。
■肩甲骨をほぐして痩せ体質に
湯上りすっきりストレッチ
愛星(まなせ)ゆうな
骨盤のゆがみも解消
「肩甲骨は体の中でもすごく大事な部分です。肩甲骨周りを柔らかくして、スムーズに閉じたり開いたりすることによって代謝が良くなり、ダイエット効果も高まります」
また、肩甲骨は骨盤と連動しており、肩甲骨のストレッチをすることで骨盤にも良い影響を与えるのだという。
「これはバレエで教わったことなんですが、肩甲骨を動かすと骨盤もいっしょに動きます。肩甲骨のストレッチをすることで骨盤のゆがみも取れますし、位置も矯正されて姿勢も正しくなるんです」
「肩」ではなく「肩甲骨」をしっかり動かすこと
では、さっそく実践していきましょう!

【写真1】肩甲骨をグーッと開きましょう

【写真2】次に胸を開いて肩甲骨を閉じます
【写真1】のような体勢で肩甲骨を開き、胸を閉じる。次に【写真2】のように肩甲骨を閉じて、胸を開いてください。ゆっくり息を吐きながら、それぞれ5秒〜10秒を目安に行ってください。

【写真3】肩甲骨を開く、というのは後ろから見るとこのような感じ

【写真4】今度は肩甲骨を閉じて、胸をグッと開く
後ろから見ると、【写真3】【写真4】のようになります。

【写真5】肩甲骨から前へ回すように

【写真6】今度は後ろへ回すように
これが終わったら、【写真5】【写真6】のように肩甲骨を前から後ろ、後ろから前にグルグルと回してください。ここで注意したいのは、肩を回すのではなく、肩甲骨をしっかり動かして回すことです。
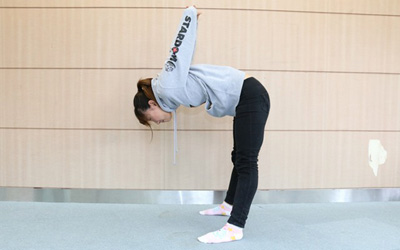
【写真7】この体勢のストレッチも効果的です
また、【写真7】の体勢になるストレッチも有効です。
生理痛にも効果的
「特に女性にとって骨盤はすごく大事なんです。骨盤のゆがみを直すことで生理痛が軽減されるので、ぜひ肩甲骨のストレッチを試してみてください」
肩甲骨と骨盤の密接な関係、みなさんご存知でしたか? しっかりと肩甲骨を動かせば、ダイエットに、骨盤矯正にと良いこと尽くめ。愛星選手が言うように、特に女性のみなさんには肩甲骨ストレッチの実践をお薦めしたいです!
[スポーツナビDo]
Posted by nob : 2014年10月27日 22:54
ほおっ(感嘆)。。。
■いいことだらけ!緑茶をもっと飲んだほうが良い7つの理由
ODACHIN
緑茶が健康に良いことなんて、誰もが知っている常識。きっとあなたも知っているでしょう。では、そんな緑茶には一体どれだけの効果があるか知っていましたか?今回はそんな緑茶のもつ驚くべき体への効果7つをご紹介します。
その1) 脳の働きもよくする?!カテキンのすごさ
『カテキン』という言葉はよくダイエット情報などでよく耳にしますが、実は脳の働きにも影響するスーパー成分だったようです。
スイスの研究機関が明らかにした情報によると、液体か抽出物であるかに関わらず、カテキンを摂取した人は脳の作業と記憶に関わる部分の動きが摂取していない人に比べ14%も向上し、勉強や仕事の効率もアップしたそう。
これはカテキンに含まれる酸化防止効果が影響した結果であり、情報処理のスピードを上げたことによります。
その2) 骨にもイイ!カテキンパワー
緑茶に含まれるカテキンに、エピガロカテキン(別名EGCブースト)という種の酸化防止成分があるそうで、このカテキンが骨の成長に最大79%も影響しているそうです。
またEGCブーストは骨量減少の原因となる細胞のブロックもするそうで、骨の保護と骨粗しょう症のリスクも下げることを香港からの研究が明らかにしています。
その3) 癌予防にも?!恐るべしカテキン
カリフォルニア大学からの研究によると、緑茶に含まれる抗酸化物質のは、通常、体の中のがん細胞の増加を抑える効果もあるのだそうです。
そしてその効果と同じことが、1日2杯以上お緑茶を飲む人の80%以上が皮膚がんのリスクを大幅に減らしていることも判明した、とウィスコンシン大学の研究が明らかにしています。
その4) 風邪にも効果アリ!
緑茶のもつその他の効果として、風邪予防があります。風邪のウイルスが人体に及ぼす影響の最初のプロセスに影響するそうで、ひきはじめなどに飲むと良いそうです。
その5) アルツハイマーの症状も遅らせる緑茶のパワー
一般的にアルツハイマー病は完治のできない病として知られていますが、緑茶に含まれる没食子酸エピガロカテキンという物質が、アミロイドと呼ばれる脳を詰まらせるたんぱく質を破壊する効果もあることがミシガン大学の研究によって明らかになったそうです。
このことが、アルツハイマー病を止める、あるいは症状を遅らせる能力でもあるそうです。
その6) うつ病防止にも!テアニンのちから
現代人に多い病、うつ病。アメリカの臨床研究によると、1日に4杯以上の緑茶を飲んでいた高齢者グループのうち44%が大幅なうつ病の発症を削減できたそう。
このメカニズムには、緑茶に含まれるL-テアニンというアミノ酸が深く関わっているそうで、L-テアニンはまた、ドーパミンおよびセロトニンといった良い気分のホルモンの生産を増加させる効果があるそうで、これはつまり、緑茶には気分を向上させる効果が期待できるということです。素晴らしい!
その7) 目にもイイぞ!抗酸化作用
緑茶に含まれる抗酸化作用には、消化器官を通って目にも作用する能力があるそうで、緑内障のような眼病の予防にも繋がる可能性は十分にあると、アメリカの科学誌『the Journal of Agricultural and Food Chemistry』は発表しています。
暫定的な研究結果ではあるものの、研究者ならびに著者らは、これらの物質が目および体全体に起きた酸化ストレスをブロックするのだそう。
いかがでしたか?緑茶のもつ効果にはダイエットだけでなくこんなにも多くの知られざる効能があったようです。近年は海外でもそのヘルシーさが受け愛飲者が多いという緑茶。今すぐにでも始められる簡単な健康法といえます。
[GEAR for MEN]
Posted by nob : 2014年10月27日 22:45
ビターチョコ、、、私もお勧めします。。。
■止まらない食欲をおさえる方法、管理栄養士の目線で考えてみた。
こんにちは、クックパッド ダイエットの管理栄養士です。ダイエット中だと思うほどに襲ってくる、食欲。今回は食欲がわくメカニズムと、食欲が抑えられない時や間食したくなった時の乗り越え方についてご紹介します。
「食べたくなる」体のメカニズムとは
お腹がすいたと感じる栄養素とは
食べ物には色々な栄養素が含まれています。その中でも「炭水化物」「タンパク質」「脂質」は三大栄養素と呼ばれて、人が生きていくために欠かせないエネルギー源です。これらの栄養素は食事をすると消化されて血液の中に吸収されていきます。その中でも「おなかがすいた」と感じる栄養素は血液の中に溶けた炭水化物と脂質です。
食べたくなるサインとは
食べたご飯やパンや麺類やお砂糖などの炭水化物は、体の中で消化されます。そしてグルコースという、砂糖よりもずっと小さい分子に分解されて、血液に入ります。食後しばらくは血液の中のグルコースの量が増えていきますが、時間がたつにつれ、グルコースの量は減少していきます。すると脳では「エネルギーを補給して〜!」と、摂食中枢とよばれる神経細胞に指令を出しはじめます。これが「食べたくなる」サイン。
さらに時間が経過して空腹状態が続くと、カラダは先ほど食べた炭水化物や脂質、タンパク質をエネルギーとして使い果たします。食事から得たエネルギー源を使い果たした後、今度は今まで溜めこんでいた皮下脂肪(中性脂肪)を肝臓で分解してエネルギーを作り始めます。肝臓でエネルギーが作り出された後、中性脂肪の部品であった脂肪酸だけが肝臓に残ります。この残った脂肪酸が血液に流れてまた脳では「早く食べ物をちょうだ〜い」と摂食中枢の神経細胞に指令を出すのです。
空腹を感じた時こそダイエットチャンス!
つまり、空腹を感じた時こそ余分な皮下脂肪が燃えているというサインです。脂肪が分解されている時間を長く持たせるためには、食事と食事の間は6時間はあけましょう。
食欲や間食の誘惑に負けそうになったら、ビターチョコ1カケ。
食事をしてから6時間あけることで、しっかり脂肪を燃焼させるのが理想です。しかし、実際はそう上手く行かないときもありますよね。小腹が空いたり、甘いものが食べたくなったり、そんな時はチョコレートを1カケだけ食べましょう。おすすめはチョコレートの中でも糖分が比較的少ないビターチョコレートです。
チョコレート1カケがオススメな理由
チョコレートには含まれるポリフェノールは食事前に食べると脂肪の消化や吸収を抑える働きがあります。チョコレートに含まれるテオブロミンという物質は脳を興奮させて、食欲を抑える働きもあります。またチョコレートに含まれる甘さが幸せ気分を運んでくれます。 1カケですよ、1カケ。温かいお茶と供に、リラックスタイムとして楽しんでみてはいかがでしょうか。
ダイエットは頑張りすぎないで!!
ダイエットは頑張りすぎると心を苦しめてしまう時もあります。食欲のメカニズムを知って、時には自分の食欲すらも客観的に見つめること。食欲や欲求うまくコントロールして、心がほっこりできるようなダイエットを楽しみましょう。
クックパッド ダイエット
水谷俊江
[クックパッドニュース]
Posted by nob : 2014年10月27日 22:37
笑えますが、、、確かに効果は期待できるかと。。。
■最新の科学が証明!コツコツ脂肪を燃やしてガッツリ痩せる17の裏ワザ
近年の肥満研究によれば、極端なカロリー制限やハードな運動を行うよりも、小さな良い習慣を積み重ねていくほうが、実は手っ取り早く脂肪を燃やすことができるとのこと。ここでは、最新の科学が証明したダイエットの裏ワザを紹介しましょう。
1.外食前に軽食をとる
レストランで外食する前に、15グラムのタンパク質をふくむ200Kcalの軽食(ゆでたまご2個など)をとっておきましょう。あらかじめ胃の中をタンパク質で満たしておくことで、食欲を減らすホルモンが分泌され、結果的には食べ過ぎずにすみます。
2.お腹のなかにガスメーターを想像する
あらかじめ、お腹のなかにガスメーターを思い描いておき、外食のときは、そのメーターを4分の3まで満たすようなイメージで食事をしましょう。他愛のない方法に思えるかもしれませんが、レトロフィットなどのダイエット企業が採用している、非常に効果のあるイメージトレーニングです。
3.口に入れたものは40回噛む
中国で行われた研究によれば、毎食ごとに40回噛んだ人は、15回の人にくらべて12%も体重が減る傾向があったとのこと。40回を目標にすると、満腹ホルモンが分泌されて、食べ過ぎをふせぐことができます。
4.食事を実況中継してみる
イギリスで行われた調査によれば、自分の食事を心のなかで実況中継してみると、食べ過ぎが一気に減るとのこと。具体的には、「この牧草牛は噛むほどジューシーな肉汁がしみ出すなあ」や「キュウリは食感がサクサクしているなぁ」といった感じです。
5.食事前に健康に関する記事を読む
オランダの研究者いわく、食事の前にダイエットや健康に関する記事を読んでおくと、レストランに入ってもデザートを頼む量が減ったそうです。事前に健康的な食事を意識することで、無意識にもブレーキがかかるようになるわけですね。
6.空腹でスーパーに行かない
有名栄養士のアニータ・ミルシャンダニによれば、空腹のままスーパーに行くと、普段よりも高カロリーの食品を買う確率が高くなるとのこと。最適な買い物時間は、週末の朝食を食べたあとだそうです。
7.エクササイズの内容を変える
いつも同じようなエクササイズをしているなら、少し内容に変化を加ええてみましょう。ランニングが好きなら筋トレを、普段は筋トレがメインなら有酸素運動に切り替えてみます。新しい動きにより心拍数があがり、最大で1時間につき120Kcalも脂肪が燃えるようになります。
8.不安定な場所を走る
あるスポーツ誌の調査では、砂場のように足が不安定な場所を走ると、30%も脂肪燃焼の効果がアップします。アスファルトの上だけでなく、できるだけ自然の中を走るようにしましょう。
9.筋トレは短い休憩を入れる
筋トレで脂肪を燃やすには、1セットごとに30〜60秒の休憩を入れましょう。ぶっ続けで筋肉をいじめるよりも、かなり代謝がアップします。
10.朝食前に筋トレする
2013年にイギリスで行われた調査では、朝食前の空腹状態で筋トレをすると、ため込んだ脂肪が素早く燃えるようになるとのこと。
11.有酸素運動は全身を使う
どうせ有酸素運動をするなら、単に走るだけではなく、ボート漕ぎ運動のような全身を使うエクササイズをしましょう。より多くの筋肉を使うほどカロリーは消費されるため、ランニングなどにくらべて、30分で135Kcalも余分に脂肪を燃やすことができます。
12.日常生活の消費カロリーを増やす
イギリスで行われた研究によれば、実は定期的にジムに行くよりも、日常的な家事などで消費カロリーを増やすほうがダイエット効果は高いとのこと。具体的には、庭仕事、床の掃除、ベッドメイク、ギターの練習などでも、10分で平均40Kcalを消費できます。
13.最低でも1日1.5キロは歩く
予防医学の専門誌が行った統計データによれば、買い物や通勤などで最低1日1.5キロほど歩くだけで、大幅に体重を減らせることがわかっています。
14.ダイエット仲間を探す
ミシガン州立大の研究者によれば、目標を同じくするダイエット仲間を見つけるだけで、減量のモチベーションが一気に高まり、成功率が格段にアップするそうです。
15.エクササイズ中は好きな曲を聞く
カリフォルニア大の調査によれば、エクササイズ中に好きな曲を聞くのは、非常に効果的なダイエット法とのこと。その際には、自分によって思い出の曲を選ぶのがコツだそうです。
16.失敗したら友人に金を払う
米メイヨークリニックの調査によれば、「ダイエットに失敗したら友人に2,000円を払う」と約束した人は、何もしなかった人にくらべて1年で4キロも多く体重が減ったとか。
17.食事日記をつける
ピッツバーグ大学の研究によれば、スマホのカロリー記録アプリなどで、こまめに食事の内容を記録しつづけた人は、自然に食べ過ぎが減っていき、多くがダイエットに成功したとのこと。
[GEAR for MEN]
Posted by nob : 2014年10月22日 13:06
右を向くか左を向くか、、、表を見るか裏を返すか。。。
悟りと迷いは
隣り合わせ
表裏一体
Posted by nob : 2014年10月14日 09:21
言い得て妙。。。Vol.22/“事実はひとつ、考え方はふたつ”で世界が変わる。。。
■過去や他者のせいにしても何一つ解決しない!
「今、自分にできること」にスポットを当てよ
和田裕美×岸見一郎 対談【前編】
49万部のベストセラーとなった『嫌われる勇気』は、フロイト、ユングと並んで「心理学の三大巨頭」と称されるアドラーの思想を哲人と青年の対話形式で紹介し、“アドラーブーム”とも呼べる現象を巻き起こしています。
そのアドラー心理学に共感し、自身でも「陽転思考」という生き方の転換を唱えているのが作家・経営コンサルタントの和田裕美氏。その和田さんと、『嫌われる勇気』の著者・岸見一郎氏が行った公開対談の内容をダイジェストで2回に分けてお届けします。前編では、4年前に出会っていたというお二人に、アドラー心理学を巡って、その特徴や、「陽転思考」との共通点などを縦横に語り合っていただきました。(構成:宮崎智之)
専門家による独占を拒否した
アドラー心理学
和田裕美(以下、和田) 本日はよろしくお願いします。
岸見一郎(以下、岸見) こちらこそ。
和田 私がアドラー心理学と出会ったのは4年前。石田衣良さん原作のドラマ『美丘』(2010年放送)を観たときでした。ドラマは滅多に観ない私が、その1話だけ偶然観ていたんですが、大学の先生役をしていた志賀廣太郎さんが「アドラー心理学」に関する台詞を一瞬言ったんですね。それが素晴らしくて、思わずそばにあったティッシュの箱にメモしたくらいです。
私は「陽転思考」という考え方を皆さんにお伝えしていますが、それは“事実はひとつ、考え方はふたつ”で世界が変わるという思考法なんです。それまではこの考え方を裏付ける心理学は知る限りありませんでした。マズローなどにしても過去に原因を求めるので、変わることができないんですよね。でも、アドラー心理学なら、私の考えの裏付けになるかもしれないってその瞬間に思ったんです。
岸見 それで、私にご連絡くださったんですね。
和田 はい。それも大阪で開催された自分の講演会にお呼びして、講演まで聞かせて(笑)。
岸見 そうでしたね(笑)。
和田 その後、初対面であるにもかかわらず、3時間くらい一緒にいろいろなお話をしました。今日はご著書に書かれていない話も含め、聞かせていただければと思っています。
岸見 僕は友人から『美丘』でアドラー心理学が取り上げられていることを教えてもらいました。その後、amazonで検索してみたら関連書籍の順位が急上昇していました。しかし、それでも当時は今ほど知られていなかったのですが……。
和田 まさか4年後にアドラーがここまで注目されるとは思いませんでしたよね。アドラー心理学は長い間、メジャーになれない憂き目をみていて、研究者も少ないと聞きました。なぜなのですか?
岸見 一つは、大学で学べないということが大きな要因だと思います。大学で心理学を専攻した人でも「名前は聞いたことがあるけど……」という程度です。さらに、もともとアドラー心理学が専門家のみを対象としたものではないことも関係しているでしょう。アドラーがアメリカに活動の拠点を移したときに、精神医学の技法としてアドラー心理学を採用したいとニューヨークの医師会が申し出たことがありました。その際の条件は「われわれ医師会にだけアドラー心理学を使わせてほしい」というものです。しかし、アドラーはその申し出を断わったのです。
和田 どうしてですか?
岸見 「私の心理学は、みんなの心理学である」というわけです。しかし、そのような考え方を専門家はあまり好みません。専門家だけの専売特許にしたいからです。
和田 アドラー自身も他者からの評価を求めなかったということですね?
岸見 アドラーは「自分の学派が存在していたことを皆が忘れてしまってもかまわない」と言っています。それだけ、皆の生き方に浸透したという証拠です。アドラーが他の心理学よりメジャーでないのは、アドラー自らが望んだことだとも言えそうです。
和田 たしかに名前は知らなくても、考え方はいろいろなところに浸透していますよね。私の「陽転思考」もその一つだと思います。
岸見 実はアドラーが源流となっている考え方が色々とあることは間違いないと思います。
人は隠れた「目的」のために
「原因」を作り出す
和田 『嫌われる勇気』では、とてもわかりやすい実例がいくつも提示されています。たとえば赤面症で悩む女の子の話が出てきます。彼女は赤面症を治して好きな男性に告白したいと言うわけですが……。
岸見 赤面症に限らず神経症の人が、「この症状を治してほしい」と言ってカウンセリングに来ることはよくあります。赤面症の彼女も「治してほしい」と言葉では言うのですが、実は治ってしまうと困るのです。なぜなら、治ってしまうと人とのかかわりが始まるからです。今は「赤面症だから、男の人とお付き合いができない」と言い訳ができても、赤面症が治ったら好きな男性にアプローチしなければならない。それで振り向いてもらえなかったら、ひどく傷つきますよね。それが怖いから赤面症という原因を作っている可能性がある。「男性にアプローチしたくない」という目的を果たすために。だから、症状をどうこうしようという話はカウンセリングではしません。
和田 何の話をするんですか?
岸見 人は一人では生きていけません。人と交わることで傷つくこともあるし、裏切られることもある。しかし、そういう経験をしなければ、他者と深い関係に入ることができない。深い関係にならなければ、生きる喜びも得られません。だからあえて対人関係の中に入り、そこでいろいろなことを経験して生きる喜びを感じてほしいといった話をします。
和田 私が岸見先生にお聞きしたカウンセリングのなかで一番印象的だと思ったのが、先生が相談を受けるときに使う三角柱の話です。三つの側面のうち、二つの面には「かわいそうな私」「悪いあなた」と書いてあり、相談者が話している内容に沿って三角柱を回転させながらどちらかを提示していくという。
岸見 ほとんどの話が、この二面のうちのどちらかなんですよ。
和田 私も相談者とお話しするとき、「つらい、つらい」とばかり訴える人とときどき出会います。「私はこんなにつらくて、こんなに大変で」と。これは「かわいそうな私」ですね。一方、「夫は帰りが遅くて、お酒ばかり飲んでいて、私の話を聞いてくれない」と「悪いあなた」ばかり話す人もいる。でも、この三角柱を見せられながら話すのは、結構キツいですよね(笑)。
岸見 今、自分がどういうことを話しているか意識してほしいのです。しかし、二つの側面の話に終始していてはカウンセリングになりません。そこで、患者さんに見せていなかった三角柱のもう一つの側面を提示します。そこには、「私には何ができるのか」と書いてあります。過去のことを聞くことがまったく意味がないとまでは思いませんが、あまり意味がない。今は過去ではありませんから。解決策を一緒に考えていきましょうというスタンスで話を進める必要があります。だから「私には何ができるのか」を示すのです。
和田 誰かの責任にしているあいだは、何も解決しないですよね。
岸見 そうですね。
和田 日本の犯罪報道を見ていると、犯人は過去に親に捨てられただとか、虐待を受けただとか昔のことを調べて、そうしたトラウマが原因で悪人になったと報じる傾向があります。
岸見 虐待を受けたことが、まったく影響を与えなかったとは言いません。しかし、二つのことを指摘したい。一つは同じ境遇に育った人が皆、同じような大人になるとは限らないということ。同じような境遇に育った全員が犯罪に走るわけではない。もう一つは、過去に原因があって今があるというのが正しいとしても、タイムマシンがない限り過去には戻れないということです。だから、「私には何ができるのか」が大切になるのです。
過去ではなく、
自分で変えられる「今」にフォーカスする
和田 でも、悩み事を抱えている方は、自分のことをわかってほしくて仕方ないんですよね。過去のつらい出来事を吐き出して、「大変だったね」と言ってもらいたい。悩んでいる人にそのように接するのは悪いことですか?
岸見 アドラーは「患者を無責任と依存の地位に置いてはいけない」と言っています。つまり相手に対して、「あなたのせいではない」という言い方をしてはいけない、と。責任を他者に転嫁するお手伝いをするのではなく、「すべてが自分から始まっている」ことを理解してもらう必要があります。
和田 なるほど。一方では、虐待された子どもが、親になったときに虐待を繰り返すという話もありますね?
岸見 これはかなり複雑な背景があると思います。というのも、どんなに親から大変な目に遭っていても、カウンセラーが「それは酷い親ですね」と相談に来た方に言うと怒られてしまうことがあります。なぜなら、どんな子どもでも例外なく親を愛しているからです。では、なぜ自分が親になったときに子どもを虐待するのかというと、「私が子どもを虐待して、なおかつこの子を愛せるなら、私の親も私を愛していたのだ」と思いたいからなのです。
和田 かなりこじれていますね。
岸見 私は、相談に来られた方が考えもしなかったことを伝えるのがカウンセリングだと思っています。これまでの考え方を強化するようなカウンセリングをしても意味がありません。
和田 なるほど。
岸見 カウンセリングをした後に、その人の人生が変わらないようなカウンセリングはしてはいけないと思います。どうにかして「なんとかできそうだ」という希望を抱いて帰っていただきたい。過去の話をしても絶望するしかありませんよね。たとえば子どもが不登校になったと相談しにきた人に、「あなたの育て方がよくなかったからだ」と話しても救いがありません。「今後、適切な関わり方をしていけば子どもとの関係は変わります。そのことによって子どもが変わるかどうかは子ども自身の『課題』なのでわからないけれど、少なくとも変わる可能性は出てきます」といった話をする必要があると思います。
和田 今、自分が変えられることにフォーカスするということですね?
岸見 そうです。「私には何ができるのか」ということに思いを向けてもらうのです。
和田 過去ではなく「今」にスポットを当てるのは、アドラー心理学の素晴らしいところですね。でも、たとえば「死にたい」と言われたらどうしたらいいのでしょうか。「よりよく生きたい」とか「人とつながりたい」といった根っこの欲求があれば話は別ですが、そうではない場合にどう対応したらよいかわからなくなってしまうのです。
岸見 そうした人に私は「ご両親は健在ですか?」と聞いたことがあります。「もし、親御さんが亡くなっていれば、死んだら天国で会えるかもしれない。でも、ご存命なら会えませんよ」と。おかしな説得の方法だと思うかもしれませんが、カウンセリングに来る人は、総じて深刻な人が多い。生きる以上、真剣でなければいけないとは思いますが、深刻である必要はないのです。ですから、深刻さをやわらげるために、風向きを変えるような拍子抜けする話もしてみる。生死の問題は単純ではないのでリスクはあるかもしれませんが、あまり思い詰めなくてもいいということを伝えたいのです。
和田裕美(わだ ひろみ)
京都府生まれ。作家、営業コンサルタント。人材育成会社「和田裕美事務所」代表。
岸見一郎(きしみ いちろう)
哲学者。
(後編に続く)
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年10月11日 16:05
頭と足の身体の両端から、、、私もおすすめです。。。
■美髪を作る!頭皮&足裏マッサージ
健やかな頭皮を保つための美髪マッサージ&リフレクソロジー
マミ レヴィ
アロママッサージサロン「マミーズタッチ」主宰、IFA認定アロマセラピスト。
女性の髪の悩みも多いもの
シャンプー後の排水溝、ブラッシング後のヘアブラシや、ドライヤーの後のドレッサーの下を見て、「こんなに髪が抜けて大丈夫かしら?」と、びっくりすることはありませんか?
四季の中でも春秋は抜け毛が多い季節です。しかし、ダイエットによる栄養不足や、頭皮の日焼け、また疲れやストレスによって頭皮が硬くなり、血液循環が悪くなることが原因になって抜け毛が起こることもあります。髪に栄養を与える頭皮の血行は、美しい髪の毛の成長に大きく関わります。
頭から遠い足のリフレクソロジーを取り入れることは意外なようですが、
頭皮が硬くなっている時には、足の指に老廃物が溜まっていることが多いのです。全身の血行不良をセルフケアで素早く解消させるには、頭皮と足のダブルアプローチをお勧めします。
頭皮の健康を保つ簡単な解消法としては、硬く凝った頭の筋肉をヘッドマッサージでやわらかくして、血行を促進させることです。同時に足のマッサージを行う事で、流れやすくなり、頭の軽さが出やすくなります。
頭皮の血行やリンパの流れが良くなることで、抜け毛防止につながるだけでなく、自律神経のバランスを整えたり、眼精疲労や肩凝り、頭痛の解消にもつながります。
頭のコリをほぐす頭皮マッサージ
頭は凝ると表面が硬くなり、少し押しただけで痛みを感じることもあります。
頭頂部だけではなく、耳の周りの側頭部、首の付け根の後頭部も、痛気持ち良いと感じる程度の力で、丁寧に揉みほぐしていきましょう。

指の関節を使ってマッサージ
1 指の関節を使って頭全体をマッサージ
指先に上手く力が入らずに刺激が足りない時には、指を曲げて第一関節で刺激するといいでしょう。少しの力でしっかり刺激されますよ。

前頭部をさする
2 前頭部をさする
両手の四指を眉の上にあて、頭頂部までしっかり押しあげます。4~5回。

側頭部を押し回す
3 側頭部を押し回す
両手の四指で耳を囲むようにして、小さい円を描きながら押し回す。4~5回。

後頭部をもむ
4 後頭部をもむ
首と頭の付け根のあたりに両親指を当て、5指全部を後頭部に当てて、らせんを描くように刺激します。4~5回。

耳に指をかけて側頭部を押す
5 指間接で側頭部を押す
耳に指をかけて、指の関節で側頭部を押ていく。
仕事中や、リラックスタイムなど、いつでもどこでも簡単にできるヘッドマッサージですが、私のお気に入りは、入浴中バスタブに浸かりながらのマッサージ。代謝がアップし易くなって汗の出がグーンと良くなりますよ。
美髪をはぐくむ頭部をケアするリフレクソロジー
足のリフレクソロジーでは、頭の反射区がある親指をメインに、足指全体をよく揉みほぐしましょう。
寝不足、ストレス、頭や目を酷使したり、首が凝りすぎていると、頭皮が硬くなりますが、そうなると足の親指がパンパンに膨らんでいて、押しても揉んでも何も感じないということがあります。痛みがないから何も問題がないというより、老廃物が溜まりすぎて、刺激が届かないということが多いので、足指がむくんでいたり膨らんでいるときには、柔らかくなるまでしっかり揉みましょう。

頭の反射区を刺激。つまむように
1 頭の反射区を刺激。つまむように。
足指全体を手の親指、もしくは人差し指の第一関節を使って刺激します。
足の親指は刺激が届きにくいので、少ししっかりめにじっくりと行いましょう。他の指は各3~4回づつ。

甲状腺の反射区を刺激。しごくように。
2 甲状腺の反射区を刺激。しごくように。
手の親指を使い、母指球の周りを円を描くように刺激します。3~4回。
食事ではタンパク質、ビタミンC、亜鉛を積極摂取!
マッサージの他に、食事ではタンパク質(肉、魚、豆、卵など)ビタミンC、亜鉛(納豆、ひじき、海藻類)を含むものを積極的に摂ることをお勧めします。これらの食品は頭皮の血液循環や髪の毛の質に影響してきます。
だんだん気温が下がり、肩や首がこわばりが気になる季節、頭皮のマッサージは髪のためだけでなく、体の凝り予防にも効果的。ぜひお試し下さい!!
[ALLA]
Posted by nob : 2014年10月07日 10:43
果物や野菜は美味しく直接頂きましょ♪
■「野菜ジュース」の成分は“満足感”だけ!
「1本で1日に必要な野菜」「濃縮還元」は詐欺!?
上田 真緒 :東洋経済オンライン編集部
野菜ジュースの「健康神話」は本当?
<編集部より追記(10月1日)> 本記事は、安部司氏の見解をもとに構成しています。多面的な議論を紹介したものではありません。その点をご留意ください。
B郞(40代)はこの秋の昇格人事で部長になった。働かない上司のA男(50代)に気配りしつつ、激務をこなしているのだから当然だ。それなのに妻のC美(30代)には「もう少し家庭に目を向けてよ」と不満をぶつけられる。戦う男は体調とメンタルをつねに万全にしておかねばならない。そこで「1日に必要な野菜が取れる」野菜ジュースを飲むようになった。息抜きのコーヒーは、ブラックだと胃に悪い気がするので必ずコーヒーフレッシュを入れる……。
消費者はもうちょっと疑問を持って!
野菜ジュース1本で、本当に「1日に必要な野菜」が取れるのか。コーヒーフレッシュはなぜカフェにタダで山盛りに置いてあるのか。「消費者は疑問を持ってほしい」と安部司さんは忠告する。
かつて食品添加物の専門商社に勤務し、多種多様の食品添加物を加工食品業者に販売していた安部さんは、消費者が知らない加工食品の現場を見て、食の安全性に危機感を抱くようになった。現在は無添加食品の開発を推進。その経緯を著書『食品の裏側』にまとめ、消費者に警鐘を鳴らしている。
まず「1日に必要な野菜が取れる」という表示はトリックだと指摘する。厚生労働省が、健康を維持するには成人1日当たり350g以上の野菜を取ることを推奨しているのだが、「その数字を基に、1日に必要な野菜350g分を計算上、入れたということであって、野菜350gを取った場合の栄養素が入っているわけではない」。
やや古いデータだが、名古屋市消費生活センターが2007年に市販の野菜ジュース35銘柄の栄養成分を分析している。野菜350gを取った場合、ビタミンCを45mg、カルシウムを114mg、カロテンを8.6g取れると換算して比較。「ビタミンCやカルシウムなどの摂取はあまり期待できない(35銘柄中、水準に達したのは2銘柄)」「カロチンは十分なものがいくつかあるが、ほとんど含まないものもあった(35銘柄中、水準に達したのは8銘柄)」。
栄養素がない野菜ジュースを飲んでも気休めにしかならない。そこにあるのは飲んだ人の“満足感”だけである。安部さんは「特に『濃縮還元』タイプのものは、栄養素がほとんどない」と教える。その製法はこうだ。
まず野菜は世界各国から輸入される。野菜の原産地を見られるQRコードがパッケージに記載されている商品や、メーカーのホームページで公開している商品もある。
「基本的に、メーカーは値段が安ければ世界中どこからでも集めてきます。だいたい15カ国ぐらいだが、中国産もある。となると気になるのは残留農薬のリスク。今のところ、輸入時の検査で違反はないが、何か問題が起きたときに、どの国のどの野菜が原因だったのか追跡できるのか不安が残る」
それらの野菜を加熱して6分の1の体積に濃縮。ケチャップのようなどろどろの“濃縮ペースト”を冷凍して、日本に輸入する。体積が6分の1だから、運賃も6分の1になるというわけだ。
この“濃縮ペースト”に水を加えて元に戻したものを「濃縮還元」と呼ぶ。国内で戻せば「国内製造品」と表示していい。
野菜ジュースのパッケージに「濃縮還元」「国内製造品」と書いてあったら、消費者は「安心、安全。体にもよさそう」と思うだろう。
だが、「この方法だと、香りはもちろん、ほとんどの栄養素が失われてしまう。食物繊維は飲みにくくなるので、あらかじめ取り除いている。メーカーによっては香料やビタミンC、ミネラル、カルシウムなどの食品添加物で補っています」。
安全性に疑問のある香料も、一括表示!
この香料がくせものだ。化学的に合成された香料は3200以上あり、それらを組み合わせて作る。たとえば、イチゴの香料なら、酪酸エチル、乳酸エチルアルデヒド、リナロール、アセトフィノン、アルデヒドなど20種類以上を混ぜて、天然に近い香りを作る。「フルーツ飲料系のみならず、野菜ジュース、缶コーヒー、お茶に至るまで、さまざまなドリンクに香料は使われている。作れない香りはない」と、“食品添加物の神様”と呼ばれた安部さんは断言する。
問題は、メーカーがどんな香料をどれだけ使っているのか、消費者に知る術がないことだ。何百種類使っても「原材料名」には「香料」の一括表示でOKなのである。
これがもし上記のような合成香料の名前がずらずら表示されていたら、消費者は買うのをためらうのではないだろうか。中には安全性に問題のある香料もあるが、一括表示では避けようがない。
したがって、「香料」の表示があるドリンクはすべて買うべきでないということになる。しかし、多くのドリンクに香料が使われているからやっかいだ。
一括表示が許されているものは、ほかに「調味料」「乳化剤」「pH調整剤」「酸味料」「苦味料」など14種類ある。「それを隠れみのにして、メーカーが何をどれだけ入れていることか。メーカーにとっては非常に便利な表示です」と明かす。
では、ビタミンCの添加物はどうか。これはアスコルビン酸である。「アスコルビン酸、クエン酸、りんご酸、フマル酸は、ほとんどが中国産。日本の公定基準に合わせて作っているでしょうか」と疑問を投げかける。
野菜で貧血を起こす!
こうした添加物以上に安部さんが問題視するのは、野菜ジュースに含まれている硝酸態窒素だ。野菜に取り込まれる硝酸態窒素が国際的に問題になっているという。
「硝酸態窒素を大量に摂取すると、体内で亜硝酸窒素になります。これは血液中のヘモグロビンが酸素が取り込む前に酸素を取ってしまうので、貧血を起こす。アメリカでは、ほうれん草の裏ごしスープを離乳食として赤ちゃんに与えたところ、酸欠状態になり、全身が青くなった。そこから『ブルーベビー病』と呼ばれています」
硝酸態窒素が野菜に取り込まれる原因は、窒素系(アンモニア態)の肥料を大量に与えすぎること。これが土壌の中で硝酸態窒素に変化し、それを野菜が取り込む。本来、野菜が成長する過程で硝酸態窒素はアミノ酸、たんぱく質に変わっていくのだが、野菜を早取りすると硝酸態窒素のまま残ってしまう。
「EUの基準では硝酸態窒素は野菜100g当たり0.2~0.3gですが、日本には基準がなく、現段階で規制もされていない。日本の水道水の基準は1リットル当たり10mgだが、その2~18倍の量が市販の野菜ジュースから検出されたという民間の分析報告もある。メーカーはきちんと硝酸態窒素の含有量を公開してほしい」
野菜ジュースの“健康神話”を根底から疑ってみる必要があるだろう。
コーヒーフレッシュは「ミルク」ではない
コーヒーフレッシュは何でできている?
さて、コーヒーフレッシュである。安部さんは食品メーカーと一緒に、まさに開発していた。
「コーヒーフレッシュは何からできているでしょうか」と講演で質問すると、ほとんどの人が「ミルク」や「生クリーム」と答える。「そんなものは入っていない。植物油と水と食品添加物からできています」と、作り方を教えると一様に驚くという。
まず植物油と水を混ぜる。水と油は分離するので乳化剤を入れる。すると混ざって白く濁る。さらに、とろみをつけるために増粘多糖類(一括表示)を入れて、カラメル色素で薄く茶色にすると、いかにもクリームのようになる。そこにミルクの香料(一括表示)を入れて、日持ちをさせるためにpH調整剤(一括表示)を入れて出来上がり。
カフェのコーヒーフレッシュ
「普通のミルクや生クリームをコーヒーに入れると、ほわっと上がってくるでしょう。あの上がり方を再現するのが難しかったなあ。1年かかったよ。でも簡単に元は取れた。原価が安いし、外食系企業がぼんぼん買ってくれたからね」
コーヒーフレッシュの正体は添加物だらけの“ミルク風油”だった。「ミルクがなぜ常温で置きっ放しでも腐らないのか、ちょっと考えたらおかしいと思うはずだけどね」と安部さん。おかしいと思わない消費者の感覚こそが、おかしいのかもしれない。
このように、裏側を知るとギョッとするような「原材料」はまだまだある。たとえば、合成着色料は石油。「タール系色素」とも呼ばれる。少量でムラなく色が出るのが利点だ。
現在、日本で食品添加物として認可されている合成着色料は12種類(赤色2号、赤色3号、赤色40号、赤色102号、赤色104号、赤色105号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、緑色3号、青色1号、青色2号)。
イギリスの食品基準庁では、合成着色料を摂取した子どもに多動性行動が見られたという研究報告を受けて、「子どもの活動や注意力に悪影響を与える可能性があります」という表示を義務化した。義務化されたうちの赤色40号、赤色102号、黄色4号、黄色5号は、日本で使われている。国によって取り扱いが異なるから不安である。
「石油」に「虫」――着色料は何でもアリ?
だが、天然着色料も安心できない。コチニール色素はオレンジや赤の着色に使われるが、原材料はなんと虫(サボテンに寄生するカイガラムシ科エンジムシ)。ドリンクのほか、ハムやお菓子など広く使われている。
このコチニール色素によるアレルギー症状の発症例が報告され、2012年5月に消費者庁が注意を呼びかけた。
「虫の内臓から色素を取るから、内臓のたんぱく質に反応してアレルギーを起こすのです。日本でも1990年代からコチニール色素によるアレルギーの臨床報告が大阪などであったのに、国はずっと無視してきた。しかも、2012年5月以降もアレルギー表示を義務化する動きはない」と安部さんは首をかしげる。
食物繊維が入っている“ファイバードリンク”としておなじみ「ファイブミニ」のオレンジ色も、コチニール色素が使われている。製造・販売している大塚製薬の広報に確認してみた。
「現在も引き続き、コチニール色素を使用しております。1988年に発売してから25年以上経ちますが、アレルギーを発症したという報告はございません。健康被害の申し出も今のところないという状況です。アレルゲンたんぱく量を十分確認したうえで、2001年からは低アレルゲン化したものを原材料として仕入れて使用しております」
──なぜわざわざ虫を使うのかが不思議です。ほかのもので代用できないのでしょうか。
「コチニール色素はいろいろな食材に使われていることもありまして、商品設計の中で最適なものを使用しております」
米国のスターバックスでは「ストロベリー・フラペチーノ」の赤色にコチニール色素を使っていることが判明し、2012年3月に「段階的にコチニール色素をやめて、トマトから抽出されるリコピンに切り替える」と発表している。ベジタリアンが「動物由来のものは使わないで」と批判したのがきっかけらしい。……論点はそこ!?
▼ニューズウィーク日本版「スタバ究極の無添加フラペチーノは昆虫風味」
では、日本のスターバックスでは現在、赤色にどんな着色料を使っているのか。市販のドリンクと違って、飲食店のドリンクは「原材料名」をすぐ確かめることができない。こういう時のために「お客様相談室」があるのかもしれない。スターバックス コーヒージャパンのお客様相談室に問い合わせてみた。
「今はコチニール色素を使用しておりません。『ストロベリー・フラペチーノ』は期間限定でお作りしているもので、そのときどきで使用する着色料が異なることもございますが、直近で発売された今年7月の『ストロベリー・ディライト フラペチーノ』は、ストロベリースライスに紅こうじ色素、ストロベリーソースに赤色40号、ストロベリーシロップにクチナシと紅花の色素を使用しておりました」
──赤色40号は安全なのですか。
「今、申し上げました色素はすべて食品衛生法上で許可されている安全なものです」
赤色40号は前述のとおり、イギリスで『子どもの活動や注意力に悪影響を与える可能性があります』と表示義務があるもの。日本では表示義務がないから、実際にこうして使われるのだろう。
国の認可が取り消されることも
「天然由来だからといって盲信はいけない」と安部さん。植物のアカネから抽出したアカネ色素は、発がん性があるとして2004年に禁止された。
「アカネ色素はそれまで20年ぐらい使われていました。2003年度版までの食品添加物の本には、安全性は確立されていると書いてあったが、2004年度版からはそのページが飛んでいる。これまでに60品目の食品添加物が厚生労働省に認可を削除をされた」。つまり、国が「安全」と言っていても、いつ禁止になるかわからないのだ。
そもそも、“意外な”原材料の着色料がドリンクや食品に使用されるのは、もともと着色料が衣料の染色から始まったからだという。そして、消費者も「きれいな色」のドリンクを好み、味をイメージする重要な要素となっている。
味覚に与える影響は、香りより色のほうが大きい
安部さんは講演で香料と着色料を使ったこんな実験をしている。
片方にメロンの香料、片方にレモンの香料を入れて、色をつけない透明な液体を聴衆に飲ませて、何のドリンクか当てさせる。すると、ほとんどの人は当てられない。
次に、レモンの香料のほうを緑に着色すると、「メロン」と答えるという。つまり、透明だと何のドリンクか判断できず、香りより色が大事なのだ。「試しに、『ファンタオレンジ』を誰かに目をつむって飲ませて、何味か当てさせてみるといい」。
「きれいな色」だけでなく、「自然な色」に見せるためにも、わざわざ着色料が使われる。前述のカラメル色素だ。
「赤っぽい茶色から真っ黒まで、いろんなカラメル色があり、私も売り歩いていた。日本の着色料の80%はカラメル色素。醤油やみその文化だから、茶色は自然な色に見えて安心するのです」
ただし、カラメル色素には製法によって4種類あり、発がん性が疑われるものもある(詳細は明日の記事で説明)。なぜメーカーはその製法で作るのか。
「昔ながらの砂糖を煮詰める方法ではカラメル色が安定しないからです。特にクエン酸が入った酸味の中だと色があせていく。数年経っても色が変わらないように化学処理をする」
消費者は、そうまでして「きれいな色」や「自然な色」のドリンクを飲みたいわけではなく、安全性が何より重要なはずだ。しかし、その判断をするためにも、メーカーの情報開示と、消費者の知る意欲が不可欠である。
安部 司(あべ・つかさ)
1951年福岡県生まれ。山口大学文理学部化学科卒。総合商社食品課に勤務後、無添加食品の開発・推進、伝統食品や有機農産物の販売促進などに携わり、現在に至る。熊本県有機農業研究会JAS判定員。経済産業省水質第1種公害防止管理者。工業所有権 食品製造特許4件取得。食品添加物の現状、食生活の危機を訴えた『食品の裏側』は60万部を突破するベストセラーとなる。そのほか、『食品の裏側2 実態編』『なにを食べたらいいの?』などの著書がある。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2014年10月06日 05:46
また旅立つ君へVol.78
続けていく先に答えがある
Posted by nob : 2014年09月30日 14:27
理にかなっています。。。
■アンチエイジングには
食後1時間の運動が効果あり!
久保 明
[東海大学医学部 抗加齢ドック教授/慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授]
アンチエイジングにとって、食事や睡眠とともに大事なのが運動です。いや、運動を抜きにしたアンチエイジングなどありえないと言っていいくらいです。といってもただやみくもに身体を動かせばいいのではありません。効果的なタイミング、適切な運動というものがあるのです。
まずは何度も紹介した老化の大敵「糖化」と運動です。過剰な糖が体内で蛋白質と結び付き、発生したAGE(最終糖化産物)が血管や内臓、皮膚などに沈着して機能低下を引き起こす、これが糖化です。糖化を予防するには、食べる順序を工夫する(第3回の懐石食べ)やGI値の低い食品を摂る(第4回)などがありますが、食後1時間に軽く運動するのも大変効果があります。
食後の運動、最適なのは?
食事をして血糖値が上昇し始めるのは血管の中にブドウ糖が入ってからです。食べた食事は胃、小腸に入ってでんぷんなど糖質がブドウ糖に分解されます。それから血管の中に入っていくわけですが、15~20分で血糖値が上昇し始め、1~1時間半程度でピークに達し、2時間位で下がり始めます。このピークの時にブドウ糖をエネルギー源として使う運動を行うと、糖化が抑えられるのです。ただし、激しい運動をしては消化を妨げることになりますので、軽い運動がお勧めです。
具体的には15分ウォークとハーフスクワット20回程度をすればいいでしょう。歩くことで有酸素運動、ハーフスクワットで筋肉を使う。この組み合わせが糖化を抑制するのです。ハーフスクワットは腰を軽く落とすくらい、膝も90度曲げれば十分です。
ハーフスクワットの代わりに階段の上り降りでもかまいません。15分ウォークは昼食を外に食べに行って歩いてもいいし、食後に散歩をして7~8分くらいの距離を往復してもOKです。朝なら朝食後、通勤で駅まで歩いたり、また駅の階段を上り降りすれば、糖化防止に役立ちます。
一番手軽な運動と考えられているのが歩くこと、ウォーキングです。皆さんの中にもポケットや鞄の中に万歩計を入れたり、スマホで歩数をカウントしている人もいらっしゃるのではないでしょうか。歩くことは大変いいことです。有酸素運動であるウォーキングは生活習慣病の予防や心肺機能アップ、ストレス解消にも役立ちます。
ただし、最近は「歩く」ことが多少、過大評価されているきらいがあります。毎日歩いてさえいれば、健康長寿につながる、と考える人が結構います。でも、だらだら漫然と歩いていても駄目。
アンチエイジングには歩行スピードが重要なのです。「歩行スピードが速い人は、遅い人に比べ、寿命が長い」というデータがあります。アメリカのピッツバーグ大学などのグループが行った調査で、65歳以上の高齢者約3万人を対象に歩行スピードと生存率の関係を調べたところ、ある範囲では歩行速度が毎秒10cm速くなるごとに死亡リスクが12%低下することが判明したのです。
やってみると分かりますが、歩行スピードを上げて歩くのはなかなか大変です。心肺機能はもちろん、足腰に筋肉がついていないと歩行スピードが上がりません。ウォーキングでは足腰に筋肉がつかないので、別に日常生活で筋力をつけるための体操や動作、トレーニングを取り入れて、足腰を鍛えながら歩行スピードを上げていくべきなのです。
足腰を鍛える代表的な運動がスクワットです。スクワットとは、直立したまま膝関節の屈曲、伸展を繰り返す運動です。プロレスの鍛錬などでおなじみですよね。プロレスラーは目一杯腰を落としたスクワットを1000回以上もやるという話も聞きますが、アンチエイジングでは膝を90度ほど曲げるハーフスクワットを20回~30回やるくらいでOKです。これでも足腰の衰えを防ぐには十分効果があるはずです。
認知症と運動の深い関係
運動は認知症予防にも効果があります。脳の視床下部のBDNF(脳由来神経栄養因子)には、脳の細胞を増やし認知症やアルツハイマーの予防作用があることが分かっています。このBDNFを増加させるのが軽い有酸素運動です。1日3.2km歩けばいいとされています。1日0.4kmしか歩かない人は、3.2km歩いた人に比べて1.8倍認知症のリスクが増すというデータもあります。
握力が弱くなると、認知症になるリスクが増えます。第1回でもお伝えしましたが、老化の度合いを測るバロメーターの一つが握力なのです。握力には全身の筋肉の衰えが顕著に表れてきます。筋肉の活動が衰えると、脳の活動も衰えるのです。厚生労働省の調査では、握力の強い人は脳卒中になりにくいという結果も出ています。最近、瓶の蓋やペットボトルの蓋を開けるのに苦労するようになったという人は要注意です。
WHO(世界保健機関)は健康長寿のためには、以下の4つを鍛えるべしという勧告案を出しています。(1)筋力、(2)持久力、(3)関節の柔軟性、(4)バランス力です。
筋力は、筋肉に力を込めるトレーニングで強くなりますし、持久力は有酸素運動のウォーキング、関節の柔軟性には各種ストレッチ、バランス力には閉眼片足立ちなどの動作が有効です。
ただし、運動をするにはそれなりの準備が必要です。狭い障害物のある場所で発作的に閉眼片足立ちなどはしないこと。鍛えるにも徐々に自分のペースでやることがお勧めです。また、駅の階段があればエスカレーターを使わずに上ったり、家で風呂の掃除を買って出たり、日常生活の中でこまめに身体を動かすように、「生活の活動度」を上げていくのもアンチエイジング的にはポイントが高くなります。
筋肉を保つための食事法
食事の点では、筋肉を保つためには蛋白質が必要です。高齢になり、筋肉量の低下が気になったら、肉を食べた方がいいのです。年を取ると、肉はよくないのではと思っているとしたら、むしろそれは逆。年を重ねると、筋肉量は加速度的に減っていきますので、運動とともに蛋白質の摂取が欠かせません。
肉の蛋白質には体内で合成されないアミノ酸が含まれています。肉を食べれば体に必要なほとんどのアミノ酸が摂れると言っていいほどです。中高年の蛋白質摂取の目安は体重1kgにつき1g、60kgの体重なら60gになります。肉のほかにも魚や大豆、豆類、卵などからバランスよく摂ってください。
今回のメディカル・トピックスは、「身体の機能評価と予後」の関係です。
(1)握力、(2)歩行スピード、(3)椅子からの立ち上がり、(4)片足立ちバランスは、将来の骨折リスク、認知機能低下とどう関係するか、という調査(2011年)です。握力、歩行スピード、椅子からの立ち上がり能力、片足立ちバランス、それぞれの低下と骨折リスクは関係していました。
一方、認知機能低下と握力低下は最も関係があり、歩行スピードの低下とも大きく関係があり、片足立ちバランスとは若干相関が認められる一方、椅子から立ち上がるとはほぼ無関係という結果が出ています。中年のうちからこれらの能力の低下には注意した方がいいでしょう。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年09月30日 14:19
変わることで生まれる「不安」と、変わらないことでつきまとう「不満」、、、どちらを選ぶかは自明のことと思いますが。。。
■もしもあなたが職場で「嫌われる勇気」を持てたら
嫌われて出世する人、ダメになる人の違いを大調査
宮崎智之 [フリーライター]
「嫌われる勇気を持ってこそ、人生を自由に生きられる」と説く、アドラー心理学に改めて注目が集まっている。その火付け役となった書籍『嫌われる勇気』はベストセラーを記録。ヒットの理由として、嫌われることに萎縮し、本来の自分を出せずに悶々としている人が世の中に溢れていることが推察される。我々が人目を最も気にするビジネスの現場を見ると、周囲に嫌われていても尊敬される人、出世する人がいる一方、嫌われて自らの立場を危うくしている人もいる。この差はいったい何なのか。ビジネスパーソンへのアンケート調査を基に、職場で嫌われることのメリットとデメリットを考察しよう。(取材・文/フリーライター・宮崎智之、編集協力/プレスラボ)
みんな、人目を気にせずに生きたい
でも「嫌われる勇気」を持てない現実
あなたは自由な人生を送るために、嫌われる勇気を持つことができるか――。
書籍『嫌われる勇気~自己啓発の源流「アドラー」の教え』(岸見一郎、古賀史健著/ダイヤモンド社)が、話題となっている。同著は、オーストリア出身でフロイト、ユングと並ぶ心理学三大巨匠の1人、アルフレッド・アドラー(1870~1937年)の思想を、哲人と青年の対話形式でまとめたものだ。
「人間の悩みは全て対人関係の悩み」「嫌われる勇気を持ってこそ、人生を自由に生きられる」という旨を説くアドラーの教えは、多くの日本人に深く刺さった。同著は、昨年末の発行以来大きな話題となり、40万部を超えるベストセラーとなっている。
これほどまでに同著が受け容れられた背景には、嫌われることを恐れる人が世に溢れているという現実がうかがえる。誰もが人の目を気にせず自由に生きたいと思うものだが、実際には嫌われることに萎縮して、本来の自分を出せずに悶々としている人が大勢いる。
それも無理はない。世の中の景気は上向いてきたとはいえ、多くの日本企業を取り巻く事業環境は依然として厳しい。一時は「追い出し部屋」などという言葉が流行り、成果主義的評価制度の定着も相まって、多くのビジネスパーソンは「なるべく失敗をしないように」「上司や同僚に嫌われないように」と、周囲の顔色をうかがいながら仕事をしている。
プライベートでも気が抜けない。特に最近ではSNSの普及もあり、自由な発言の場が増える一方、投稿によって人間関係のトラブルに発展するケースが相次いでいる。「ツイートの内容を、いつ誰にチェックされているかわからない」と、警戒心を抱くユーザーが増えている。こうして見ると、現代はかつてなく人の目を気にする機会が多い時代だと言える。
嫌われても出世する人と
嫌われてダメになる人の違いを大調査
しかし、このへんでちょっと考えてみたい。他人に嫌われないように気を配り続けることが、本当に全て自分のためになっているのだろうか、と。
我々が人目を最も気にするであろうビジネスの現場を例にとると、職場には「嫌われても尊敬されている人」「嫌われても出世している人」が、少なからずいるのではないだろうか。彼らのなかには、「嫌われないように」と八方美人に徹しているあなたよりも、よほど周囲からの評価が高い人もいるはずだ。もし、あなたの周囲にもそうした人がいるとすれば、それは自分なりの「嫌われる勇気」を実践して、成功している例なのかもしれない。
もちろん一方で、周囲に嫌われて自らの立場を危うくしている人も、数多く目につくだろう。この「差」はいったい何なのだろうか。嫌われることはリスクが大きいが、単に嫌われないことだけでもダメだとしたら、我々はいったいどうやって世渡りをすればいいのか。これは、私たちが考えるべき処世術としては、最も高度な判断力を要する課題の1つと言えるだろう。
そこで今回は、リサーチ会社「リビジェン」の協力を得て、全国の男女200人に対してアンケートを実施し、「職場における嫌われる勇気」に対する意見を聞いた(対象は20~50代/経営者・役員、会社員、公務員、自営業)。その結果を基に、職場で嫌われることのメリットとデメリットを考察しよう。
まず世間の人々は、ビジネスの現場で「嫌われる」ことに対して、どんな感想を持っているのか。「あなたは、職場で嫌われることが怖いですか?」という質問には、68.5%が「はい」と回答した。男女別で見ると、男性が64.1%、女性が73.4%となっており、女性のほうが嫌われることを恐れる傾向があるようだ。
さらに「嫌われることが怖い」と回答した人を年代別で見ると、20代が79.3%で1位となり、30代の65.2%、40代の61.5%、50代以上の33.3%と続く。年齢を重ねると人目が気にならないこともあるのか、はたまた自分の実力に自信を持てるようになるからなのか、いずれにせよ年齢を重ねるにつれ、嫌われることへの恐怖が薄れる人が増えていくことは確かなようだ。
「仕事が円滑に進まなくなる」
7割の人は嫌われる勇気を持てない
嫌われるのが嫌な理由としては、以下のような声が上がった。
「嫌われると、仕事が円滑に進まなくなる」(37歳・男性/営業職)
「職場に1人、絶対的な存在の人がいて、その人に目を付けられたくない」(24歳・女性/事務系)
「精神的に弱いので人から嫌われるのは怖い」(35歳・女性/事務系)
「会社に居づらくなってしまう」(25歳・男性/営業職)
「必要なときに助けてもらえない可能性がある」(29歳・男性/事務系)
「皆に好かれたい」(29歳・男性/技術系)
「嫌われると、契約を切られるのではと心配になる」(30歳・女性/事務系)
「1日のうちで職場にいる時間は長いので、周りとうまくやっていきたい」(29歳・女性/事務系)
このように全体を俯瞰すると、おおよそ7割近い人が「嫌われる勇気」を持てずにおり、またその理由は「嫌われること」に対する潜在的な恐怖心に端を発していると言える。
もちろん、ただ単に「嫌われる勇気」を持てばいいというものではない。そもそも嫌われることは諸刃の剣である。「嫌われる勇気」を実践するなら、嫌われることを気にせずに自分の流儀を貫いてもなお、尊敬される人物になることが理想であるはずだ。アンケート結果を見ると、意外なことに、全体の46.5%が「周囲にそのような人物がいる」と回答している。
明暗を分ける2つのキーワード
一貫性のある人は結局尊敬される
では実際に、「嫌われても成功する人」と「嫌われて失敗する人」との違いとは、何なのだろうか。アンケート結果からは、その明暗を分ける2つのキーワードが浮かび上がった。
1つ目のキーワードは「一貫性」だ。まずはこのキーワードにあてはまる、「嫌われても成功する人」の人物像や理由を見てみよう。事務系の女性(44歳)は、アンケートに対してこんなコメントを寄せている。
「意志が強く、他人の意見でふらふら振り回されず、正しいことを正しいと、上司・部下に関係なく発言する人がいます。始めは疎んでいた周りの人も『その人の言うことなら間違いない』と、その人を規範とするようにさえなっていきました。結果的には、我が社で最年少の役員へと上り詰めていきました」
さらに事務系の女性(27歳)からは、こんな意見も。
「たまに厳しすぎるときもあって、敬遠されがちの上司。でも、いつも他人を思いやり、決して他人の悪口を言わず、必ず会社が良くなるために行動していて一貫性がある」
他にもこんな声があった。
「甘えを見極めて、厳しく人を育てる先輩を尊敬しています。『甘えでできない』と『一生懸命やっているができない』とでは全然違います。『本当の一生懸命は人に伝わる』ということを教えてくれた方でした。いつも皆を平等に見てくれていました」(30歳・男性/自営業)
「嫌われてもしっかり筋の通ることを貫いて、信用を得ている人がいる」(27歳・女性/事務系)
つまり、どれだけ自分の意見を押し通そうが、厳しく振る舞おうが、その根底に「一貫性」があり、それが周囲のためになっていると認識されている人は、尊敬され、出世するということなのだろう。
逆に、「嫌われるだけ」のタイプについては、こんな意見が寄せられた。
「有言実行じゃない人、言葉に行動が伴ってない人、矛盾している人」(24歳・女性/事務系)
「活躍している人にはゴマをすり、努力しているけれど芽が出ない人には冷たい態度を取っていた同僚が、そのことが原因で仕事がなくなった」(28歳・男性/自営業)
「人に言うだけで、自分が実践できてない人」(36歳・男性/自営業)
人には厳しいのに自分には甘い、人によって態度が変わるなど、一貫性のない言動は嫌われる原因になるようである。
どんなに嫌われていようとも
業績さえ上げれば文句を言われない
2つ目のキーワードは「成績」だ。少し身も蓋もない話になってしまうが、利益を上げることが至上命題の会社組織では、どんなに嫌われようと業績さえ上げていれば文句を言われないという側面もある。
「営業成績がズバ抜けて良かったので、周りから嫌われていても部の中では大事な存在になっていた」(34歳・男性/技術系)
「ハッキリとものを言うから同僚からは非難されているが、営業成績がトップのため出世した人がいる」(33歳・女性/自営業)
「意見についていけない人であっても、仕事ができれば尊敬されると思う」(38歳・男性/技術系)
逆に、ただ単に嫌われるだけのパターンは次のようなものだ。
「仕事ができないのに、下の人に対してかなりの上から目線!」(28歳・女性/技術系)
「性格が悪い上、仕事ができない人がいます。特に実績がないのに態度がデカく、人に注意することを自分のほうがちゃんとできていないので、みんなに嫌われています」(29歳・女性/営業系)
実力主義の会社では成績を残している限り、「あの人はできる」と一目置かれるということだろう。しかし、このタイプはひとたび成績が下がれば一気に嫌われ者となってしまう可能性があるので、注意が必要だ。
嫌われる勇気を持つ以前に
ただ嫌われるだけのタイプは要注意
これら2つのポイントをよく研究し、地雷を踏まないように注意すれば、「嫌われる勇気」を実践しつつも、順風満帆な会社員人生を送れる可能性は高そうだ。
ちなみに、嫌われる勇気を持つ、持たないという問題以前に、「ただただ周囲から嫌われるだけ」というタイプも参考までに紹介しておこう。
「責任逃れをするタイプ」(45歳・男性/技術系)
「自分の非を認めない、他人の批判ばかりする、約束を守らない、口先だけで行動しない、という人が嫌われています。尻ぬぐいをするのは周りなので」(34歳・女性/事務系)
「嘘をつく人はダメです。最初は騙される人も多いのですが、最後はどこかでその嘘がばれ、辻褄が合わなくなり、結果、周りにも多大な被害をもたらすことになって、降格、解雇といった処分を受けた人が数人います。本人もそのことによりウツになり、会社に出て来られなくなったりしたこともありました」(44歳・女性/事務系)
「責任逃れ」「約束を守らない」「批判ばかり」「陰口」「嘘」などは、ここで紹介したコメント以外にも多く見られるキーワードだった。決して、そういうイメージを周囲に与えてはいけない。心当たりのある人は、すぐに改善したほうがいいだろう。
変わることで生まれる不安と
変わらないことでつきまとう不満
最後に、書籍『嫌われる勇気』からこんな文言を引用したい。
「あなたはご自分のことを、不幸な人間だとおっしゃる。いますぐ変わりたいとおっしゃる。別人に生まれ変わりたいとさえ、訴えている。にもかかわらず変われないでいるのは、なぜなのか?
それはあなたがご自分のライフスタイルを変えないでおこうと、不断の決心をしているからなのです。(中略)新しいライフスタイルを選んでしまったら、新しい自分になにが起きるかもわからないし、目の前の出来事にどう対処すればいいかもわかりません。未来が見通しづらくなるし、不安だらけの人生を送ることになる。(中略)
つまり人は、いろいろと不満はあったとしても、『このままのわたし』でいることほうが楽であり、安心なのです。(中略)ライフスタイルを変えようとするとき、我々は大きな“勇気”を試されます。変わることで生まれる『不安』と、変わらないことでつきまとう『不満』。きっとあなたは後者を選択されたのでしょう」
嫌われるリスクを背負ってまで、職場で自分の意見や流儀を貫き通すことには勇気がいる。しかし、「自由な人生」を送るためには、一歩踏み出さなければならないこともある。前述の引用に従うなら、「嫌われても評価される人物」になりたくてもなれないでいるビジネスパーソンは、自ら「『嫌われても評価される人物』にならないでおこう」と決心していると言えそうだ。
変わることで生まれる「不安」と、変わらないことでつきまとう「不満」。どちらを選ぶことが正しいかは、人それぞれ価値観の違いがあるので、一概に答えを出すことは難しい。
1つだけ言えるのは、成功や失敗の可能性から逆算して「嫌われる勇気」を持つか否かを考えるのではなく、自分が正しいと思う信念に基づいて「嫌われる勇気」を持てる人こそが、結果的に周囲から尊敬される人になれるのではないか、ということである。このことを、よく肝に銘じておきたい。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年09月29日 08:39
自然環境破壊、ウイルスの蔓延、放射能の拡散などと同様に、過度な情報という害悪から心身を護るのは、現代社会を生き抜く基本的な力。。。
■ドラえもんで描かれた道具を手にしつつある社会にもたらされた光と影。デジタルの恩恵は私達を幸せにするのか?
第1章 デジタル社会の光と影【前編】
僕は、デジタルは人間に恩恵を与えるものだと信じている。だから今日も、僕はデジタルの領域で活動する。(中略)その一方で、僕は不思議な違和感を覚えるようになっている。はじめは小さかったこの違和感は、デジタルが世を覆い尽くすにつれ大きくなっている。(中略)人間はもちろん人間のためにデジタルを駆使し、進化させようとしているはずだ。……にもかかわらず存在する違和感。その違和感の正体を突き止め、真摯に対峙しなければ、訪れる未来は必ずしも明るいものにはならないだろう。このような予感が、本書を執筆する原動力になっている。――小川和也・著『デジタルは人間を奪うのか』「はじめに」より
* * *
ドラえもんのひみつ道具が次々と実現
世界の総人口は70億人を超えた。
2050年には96億人、2100年までに100億人を上回る見通しだ。世界の人口が増すにつれ、デジタルの存在感、それが及ぼす影響力も増す一方だろう。
デジタルは、人類の歴史の中でもとりわけ大きな変革を起こそうとしている。あらゆるものの効率化を促し、これまでの不可能を可能にする。人間の脳や身体を補完し、労働を肩代わりする。漫画の中のつくり話を、どんどん現実のものとする。
実は、ドラえもんがポケットから出したひみつ道具の多くがもはや夢ではなくなっている。たとえば、糸電話の紙コップを模した道具である「糸なし糸電話」。離れたところで話ができるこの道具はまさしく携帯電話として世の中に普及している。
鉛筆状の筆記用具に六角形をしたコンピュータらしきものがついている「コンピューターペンシル」。これを使えば、量の多い仕事や勉強でもあっという間にすらすらと終わらせられる。これはまさに、いまのパソコンに置き換えられる。ディスプレイの世界地図から描きたい地点を指定し、そこの風景などを描くことができる「いつでもどこでもスケッチセット」は、グーグルのストリートビューに近い。紙の上に物を載せるとその物と同様の立体的な複製が紙から出てくる「立体コピー紙」などはまさに3Dプリンターだ。
「こんなこといいな できたらいいな」というアニメの『ドラえもん』の主題歌にノスタルジーを感じるほど、かつての空想の話もいまや現実の話になりつつある。近い未来には、さらに多くのひみつ道具が実現されることになるだろう。
これらの空想を現実のものとしているのは、まさにデジタルだ。
デジタルの恩恵を味わえば味わうほど、もはやデジタルのない世界へさかのぼることは難しくなる。デジタルはこれからますます社会を覆い尽くし、人間が100億人を超えているであろう2100年の世界では、デジタルの影響はいまの比ではないものとなっている。降りることのできないデジタルの船はいまよりずっと先に進み、その時にはその中で暮らす人が100億人を超える。そういう日が、やがて訪れることになる。
デジタルが発展途上国の50億人に光をもたらす
フェイスブックは「internet.org」をテクノロジー企業6社(Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, Qualcomm, Samsung)と共同設立、主に次の3つの課題にフォーカスし、発展途上国のネット利用の実現を進めている。(参照元:フェイスブックによるプレスリリース http://newsroom.fb.com/News/690/Technology-Leaders-Launch-Partnership-to-Make-Internet-Access-Available-to-All)
(1) データ伝送の効率化によるインターネットアクセス料金の減額
(2) アプリの効率化による使用データ量の低減
(3) インターネット普及の新モデル構築
フェイスブックのCEO(最高経営責任者)であるマーク・ザッカーバーグ(Mark Zuckerberg)氏は、これに関して次のように発言している。
「不公正な経済の現実とは、すでにフェイスブックにいる人々は、それ以外の世界すべてを合わせたよりも多くのお金を有しているということだ。我々が今後非常に長い期間にわたってインターネットの恩恵に浴していない数十億人の人々に仕え続けることは、可能であったとしても、利益にはつながらないかもしれない。それでも我々は、誰もがネットに接続できるようにすべきだと信じている」
彼らは既にそのための素案を公開し、その改良意見を世に求め始めている。
現在のインターネットユーザーは27億人で、世界の総人口のおよそ3分の1にあたる。
しかしその増加率は毎年9%以下で、インターネットが成長過程の初期段階にあることを鑑みれば、低い成長率だということを彼らは危惧している。(参照元:“Is Connectivity A Human Right?”)
この視点を持つのはフェイスブックだけではない。
2012年11月8日、米グーグルは発展途上国の利用者を対象としたGoogle Free Zone(グーグルフリーゾーン)というサービスを発表している。その1つ目のパイロットプログラムとしてフィリピンの通信キャリアであるGlobe Telecomと提携し、同国での提供を開始している。
このフリーゾーンは、インターネット接続機能を持つ携帯端末のユーザーが、検索、Gmail、Google+等のグーグル主要プロダクトを無料(データ通信契約も不要)で利用できるサービスだ。検索結果に表示されたリンク先のページにも無料でアクセスできる。
フィリピンのモバイルマーケットは既に飽和状態にあり、97%のユーザーがSMS(ショートメッセージサービス)を利用しているものの、モバイルインターネットの利用はわずか9・8%だ(2011年度World Bankデータ)。フリーゾーンを通じてフィリピンでモバイルインターネットの利用を普及させる取り組みは、より高性能な端末への買い替えとグーグルの利用を促す狙いはあるが、これもフェイスブックと同じく大義によるものだといえるだろう。
「デジタル・ディバイド」という言葉がある。
これは、インターネットを中心とした情報通信技術を利用できる人とできない人の間に生じる経済格差を指す言葉として使われている。
米国では1996年、当時の大統領であったビル・クリントン(Bill Clinton)氏と副大統領のアル・ゴア(Al Gore)氏がこの言葉を公式に使用し、クリントン政権ではすべてのアメリカ国民がコンピュータとインターネットを利用できるようにすることを国家的な目標とした。そしてここ日本においては、2000年前後からこの言葉が使われ始めている。
僕は数年にわたり、スリランカの児童養護施設の支援に携わらせていただいているが、その子供たちが将来活躍するための武器として、デジタルスキルが重要な意味を持つことを目の当たりにしている。
ちなみにスリランカのインターネット普及率は15・0%だ。さらに普及率が低い国では、バングラディッシュ5・0%、カンボジア4・4%、ミャンマーになると1・0%というのが実情(参照元:Internet World Stats / Internet Users 30-June-2012)であり、そのような国々でデジタル・ディバイドの解消がなされる意義は大きい。
たとえば、電子メールの送受信や様々なデータベースの利用、商品の購入や音楽の受信配信、金融取引などが可能になることで、生活やビジネスの利便性が上がる。さらには新しい産業も生まれて育つ。これらにより、経済的には労働生産性の向上、文化的には相互理解が深まることにつながる。
また、国民が等しく国際情勢を把握できれば、政治的には民主化の推進を促すと考えられる。
デジタルが、発展途上国の50億人に光をもたらし、成長を促す。もちろんそこで必要なのはデジタルだけではないが、デジタルが放つ光の力は計り知れない。発展途上国におけるデジタルの普及がその国や人々の姿を大きく変え、さらにそれが世界全体の発展にも寄与する。僕はそう考えている。
18歳女子高生の大発明
スマートフォンなどの携帯型デジタル機器を四六時中利用するようになったことで逆に不便を感じるようになったことがある。それはその稼働電力だ。小さなデジタル機器の中には、長い期間それを稼働できるようなバッテリーは入れられない。だからいまはまだ、そのバッテリーをこまめに充電する必要がある。しかし一定量の充電をするには概ね数十分から数時間を要し、そのためのコンセントがある場所も限られる。これはデジタルの利便性と表裏一体の不便さであるが、そこにもちゃんとデジタルテクノロジーが解決にあたってくれようとしている。
たとえばそのひとつが、2013年に開発された非常に小さなスペースに大量のエネルギーを保持できるテクノロジーだ。開発したのはなんと当時18歳の米国の女子高生で、インテル国際学生科学技術フェアの準優秀賞を獲得した。この技術を応用すれば、様々な電子機器などを短時間で効率よく充電することが可能になるという。
また、街の中を飛び交うWi-Fiに含まれているエネルギー波を電流に変換するテクノロジーが米国の学生によって開発されている。太陽電池パネルに相当する実用性が得られるとのことだが、天候に左右されない安定した電力で、どこからでも給電できるようになるのも時間の問題だろう。
このようなデジタルテクノロジーが毎日のように生み出されては進化をし、われわれが不便に感じるところには、すかさず新しい光が射す。それにより、われわれの生活の中にある不便という穴はどんどん埋められていくだろう。
光が射す一方で、つくられる影
デジタルがもたらす光、その力と功については、もう既に目の前にあるものだけでも充分過ぎるほど理解できるだろう。
しかし一方で、その光に伴ってつくられる、影のようなものの存在を感じることがある。その影は、さりげない日常生活の中にも見え隠れしている。
朝起きたらすぐにベッドの中で、おはようの挨拶の前にスマートフォンを手にとる。朝の散歩でもスマートフォンをチェックする。気づいたら散歩道の景色の記憶が薄い。友達との食事中も頻繁にスマートフォンのチェックをし合っている。デートの時も、旅先でも、ゴルフのプレイ中も、誕生会でも、そこにはスマートフォンに関心を奪われる自分やみんながいる。
誰かといるのに、みんなといるのに、すぐそばにいるのに、とても遠く感じる。そのような感覚の中にこそ、この影が潜んでいる。
デジタルが光をもたらす一方で、つくられる影。この影は光を遮り、われわれの社会に歪みを与えようとしているのだろうか。
毎日ムダな情報と出会っている?
われわれはいま、溢れんばかりの情報の中で生きている。
その中から縁あって出会い、毎日触れている情報は、あなたにとって本当に有益なものなのだろうか。もしかしたら、不必要な情報の陰で本当は必要な情報が埋没してしまっているかもしれない。
米EMCが調査会社の米IDCに委託して実施したデジタルユニバースに関する調査結果(http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf)はインパクトがあるものだった。
2020年にはデジタルユニバースの規模は40ゼタバイトに達し、世界の全人口1人あたりではおよそ5247ギガバイトのデータを保有する量に相当するという。「ゼタバイト(Zettabyte)」といわれても、ピンとこない人が大半だろう。これはデジタルデータの容量の単位で、単位の小さい順に並べてみると、「バイト→キロバイト→メガバイト→ギガバイト→テラバイト→ペタバイト→エクサバイト→ゼタバイト→ヨタバイト」となり、単位が1つ上がるごとに1024倍(2の10乗)という仕組みだ。
ゼタバイト、とてつもなく大容量であることくらいはすぐに想像がつく。累乗で表すと2の70乗、約11垓8059京と聞くと、また想像からはみ出てしまう数字になる。これはDVDで2500億枚に相当し、少し馴染みのあるギガバイトをコーヒーカップ1杯分とすれば、ゼタバイトは万里の長城の体積に匹敵する。
2006年時点では0・161ゼタバイトであったが、その増大スピードは加速の一途、デジタルユニバースは2年ごとに倍増するペースの中にある。
一方、その膨大なデータを活用しきれずにいる状態にあり、2012年時点のデジタルユニバースの23%(643エクサバイト)はビッグデータとして活用可能であるものの、タグ付けされているデータはそのうち3%、さらに分析まで行われているデータの割合は1%未満だといわれている。
この膨大な情報の源として成長を続けているのがソーシャルメディアだ。
ソーシャルメディアが実生活とウェブをつなぐインターフェイスとなり、世界中のユーザーが日常の細かな出来事をそこへ集積するようになった。検索がウェブ上の情報を収集してインデックス化する速度を、世界中のユーザーがソーシャルメディア経由でウェブに情報をアップロードする速度が凌駕してしまった。
その中でもフェイスブックのニュースフィードは、毎日7億人以上が見る情報フィルターになった。それにもかかわらず、このニュースフィードに表示される投稿がどのような仕組みで選択されるかというアルゴリズムはあまり明らかにされていない。自分がつながっている友達の投稿が全てそこに表示されている訳ではないし、むしろ目に触れられる機会すらないまま、多くの投稿が流れ去っている現実がある。
いずれにせよ、われわれが膨大な情報の中で生活するようになったことで、それらを捌いて必要な情報を目の前に運んでくれる何らかのフィルターが不可欠になった。
しかし、どんなフィルターであっても、それがあらゆる情報から一部を抽出するフィルターである限り、自分が必要とする情報に100%出会えることは保証されない。いまの社会において、情報との出会いはセレンディピティ(役に立ったり必要なものを、偶然の出会いから発見すること)次第なのだ。
残念ながら、情報量と接触する情報の質は比例しない。どれだけ情報が増えても、その増えた分だけあなたにとって必要な情報と出会える確率が高まるとは限らない。われわれはこれから、爆発的に増えていく情報の価値を、本当に享受しきれるのか試され続けることになる。
〝嘘の戦争〟にも気づかないまま
もはやインターネット上の事典として、世界中で使われるようになったウィキペディア。英語版からスタートしたが、その後多くの言語に展開され、いまや270言語以上に及ぶ。
調べごとにこれを使う人が増えたことで、市販の事典の売れ行きが減少しているという話も聞く。ネット利用がアクティブになるにつれ、〝調べごとはウィキペディア〟という人が増えるのは当然の流れだろう。
誰もが新規記事の執筆や既存記事の編集に参加できることが特徴で、主立った用語はかなり網羅されるようになった。公的なニュースや書籍などでも、ウィキペディアから引用されることも多くなり、情報の信頼性や信憑性は増している。
しかし過去には、このような出来事があったことを思い出す。ウィキペディアで〝嘘の戦争〟がつくり上げられ、しばらく気づかれずに放置されていたのだ。
「ビコリム戦争(Bicholim conflict)」という2007年に作成されたページがそれだ。
1640年から41年にかけ、植民地支配を目指したポルトガルと当時インドの大部分を支配していたマラータ王国との間で起きたのがビコリム戦争であると説明されていた。戦争の名前の由来から、最後は平和条約を締結したという結末まで記述されており、5年間ほどこの〝嘘の戦争〟が閲覧されていた。
米国のユーザーの一人がこの情報に疑問を持ち調査を行ったことから、このビコリム戦争自体が一切なかったことが判明、申し立てを受けたウィキペディアがページを削除した。
まさに、誰かのいたずらでつくられた〝嘘の戦争〟が事典の中に収められ、長いこと閲覧されていたのだ。編集への参加は実名を明かさなくても可能であり、このようないたずらの書き込みへの対処は実際難しい。
ソーシャルメディアが普及し、自身をより魅力的に見えるように着飾って投稿をしたことがある人は、実に2人に1人はいるという調査などもある。もしもその脚色が度を超えてしまっていた場合、真実とは異なる情報を受け取ってしまうこともあり得るということだ。
豊富で便利な情報の背後にある信憑性のリスク。
もちろん多くの項目において役に立つ情報が記述されているし、思いがけず面白い情報に出会えたりもする。しかし一方で、そこには一切の保証がないことも理解しておいた方がよいだろう。
つまり、あなた自身が最終的に正しい情報のフィルターを持たなければ、嘘の情報に飲み込まれかねないということだ。
<以下、【後編】に続く>
■つながり依存、脳腫瘍発生の危険性、経済損失・・・デジタルの影の部分にも明るい領域をつくらなければならない
第1章 デジタル社会の光と影【後編】
SNSが生む経済損失
手元のスマートフォンのアラートに頻繁に喚起され、それに手を伸ばしてはチェックを繰り返す。たとえ仕事の打ち合わせ中でも、である。そのアラートは、フェイスブック上で更新が生じたことやメッセージ受信のお知らせだ。また、仕事でパソコンに向かうことが多い職業だと、画面上でフェイスブックやツイッターに常につながったままの状態の人も少なくない。
ワシントン・ポスト紙の元スタッフ・ライター、ウィリアム・パワーズ(William Powers)氏は、自著の中で次のことを指摘している。
「心理学の知見によると、頭を使う仕事をやめて横から入ってきた用事に対応すると、感情や知覚はたちどころに肝心な仕事から離れはじめ、別件に長いあいだ気を取られていると、元に戻るのに要する時間も長くなるという。いくつかの推定によると、集中力を回復するのにかかる時間は中断時間の10~20倍にもおよぶこともある」(引用元:『つながらない生活 「ネット世間」との距離のとり方』有賀裕子訳)
あらためて言われてみると、身に覚えがある人も少なくないだろう。
パソコンに向かって上司への報告書を作成している。すると同じパソコン画面上で接続しているフェイスブックのニュースフィードにちょっと目をやると、友達の投稿がどんどん流れてくる。ちょっと一瞬のつもりでフェイスブックの投稿を眺める。いくつかの投稿を眺めてコメントをしたりで滞在5分。たった5分の寄り道だ。しかしどうだろう。作成中の上司への報告書に戻ったものの先ほどの投稿が頭にちらつく。「ああ、投稿にあったイタリアンレストランはよさそうだな。今度行ってみよう」。そんなことを頭の中でもやっと思いながら、作業を進める。そう、実は集中力という観点では、5分の寄り道では済まなくなっている。先のデータを基にすれば、集中力を回復するのに、下手したら中断時間である5分の10〜20倍の時間を要することだってあるのだ。物理的にはたった5分でも、作業効率という観点ではなかなかのダメージだ。
この〝なかなかのダメージ〟についてはこんなデータもある。
BaseX(http://basex.org/)が2008年に行った推計では、情報過多により年間9000億ドルもの経済損失が生じているという。以降、ソーシャルメディアの利用者数と利用時間が飛躍的に伸びていることを考えると、現時点ではもっと多くの経済損失の源になっている可能性がある。みんなの「ちょっと一瞬」が積もりに積もると、経済損失という観点ではとんでもない数字に膨れ上がるという試算だ。これはもう、〝なかなか〟と言える次元ではない。
「新しい病」を生むデジタル
「友人からのSNSへのコメントやメールにすぐに返答しなくては、と思うとなかなか寝つけないんです」
SNSでのやりとりに没頭し、やめられなくなる「ネット依存」の悩みを抱えて医療機関にかかる人が増えている。スマートフォンやソーシャルメディアの普及がネットから片時も離れられないという「新しい病」を生み出しているというのだ。
厚生労働省の科学研究費で行われた成人対象抽出調査(2008年)で、インターネット依存の恐れがあるとされたのは全国で推計271万人、子供の数を加えると500万人を超えていた。この調査以降、フェイスブックやツイッターなどのソーシャルメディアの利用者が急増し、2012年の段階では5000万人を突破、加えてスマートフォンの普及も一気に進み、LINEのような新しいコミュニケーション手段も増えた。それにより、ネット依存症を訴える人の数や症状はより深刻になっている。
その多くがソーシャルメディア上のコミュニケーションにのめり込み過ぎて生活や仕事に支障をきたす〝つながり依存〟だと言われている。日本でもフェイスブックが普及し始めていた2011年6月、フェイスブックに夢中になった滋賀県の主婦が、高熱を出していた1歳の息子を放置して死なせるという事件が起きて大きな議論を呼んだ。逮捕されたこの母親は調べに対し、「インターネットのチャットに熱中し、昼夜逆転の生活をしていた」と供述している。このような状況を受け、国立久里浜医療センターでは薬物と同様の依存性に着目し、専門の外来を開設し治療法の開発に着手している。
インターネット依存は、「自分の意思でインターネットの利用(時間)をコントロールできない」「常にそれに気を奪われる」「人にやめるように言われてもやめられない」「現実から逃避したい心理状況などにより、過度に利用してしまう」などの症状があり、日常生活に支障を及ぼす。これはまさに、薬物やアルコール依存にも近く、だいぶ深刻だ。
程度の差こそあれ、自分もこの「新しい病」に罹患しているのではないか? と思われた方もいるだろう。
さらにこの依存性は、人間の精神面だけではなくその肉体にも影響を与え始めている。
長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用が原因で、腱鞘炎に悩む人が増加している。マウスのクリックやキーボードのタイピングなど、決まった動作を何度も繰り返すことで手指の腱に炎症を引き起こす〝反復運動過多損傷(RSI)〟を主な原因とする、「キーボード腱鞘炎」「マウス腱鞘炎」といわれる症状がそれだ。最近はスマートフォンの操作により親指を使い過ぎる人が多い。その結果、手首の親指側にある腱鞘が炎症を起こし、親指を伸ばすと痛みを感じるドケルバン病という症状に悩む人も続出している。
ビジネスマンが一日にキーボードを叩く回数を試算してみよう。ローマ字入力の場合で1文字あたり2回キーを叩くとする。一日に10通、メール1通あたりの平均文字数を200文字とすれば、400回×10通=4000回。メール以外にも、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアに投稿したり、コメントを寄せたりする機会も増えているし、ビジネスマンであれば書類作成などで毎日万回単位でキーボードを叩いているはずだ。それに、スマートフォンでのフリック入力という新しい動作も加わっている。
かくいう自分に置き換えてみるとぞっとする。僕はパソコンとスマートフォン、それにタブレット端末を併用し、優に100通を超えるメールを毎日のようにやり取りしている。メール以外にも、大量の書類作成や原稿執筆を常態的に行っている。こまかいメッセージのやり取りは、スマートフォンでのフリック入力で対応する。これでは、「キーボード腱鞘炎」「マウス腱鞘炎」にいつなってもおかしくないという状態だ。フリック入力を大量に行うことで、親指の付け根の違和感も頻繁に感じているから他人事ではない。
デジタルは、大きな利便性を提供していると同時に、人間の心身に新たな病巣をもたらしてもいる。これも現実だ。
携帯電話で脳腫瘍が増加する
携帯電話で一日30分以上の通話を5年間継続すると、脳腫瘍が発生する危険性が2〜3倍に増えるとの調査結果をフランスの研究者がまとめたことを、AFP通信等の仏メディアが報じて(2014年5月13日付)話題になった。
2004〜2006年に、仏ボルドーの公共衛生研究所(ISPED)が脳腫瘍の一種であるグリオーマや髄膜腫を患った約450人を調査したところ、他の健常者と比較し、携帯電話の利用が少ない人ほど脳腫瘍の発生が少ない傾向が認められたのだという。
調査をした同研究所のイザベル・バルディ(Isabelle Baldi)博士は、脳腫瘍の発生率上昇が携帯電話を最も頻繁に利用する人だけに確認されたことを強調し、電話を耳から離して通話するハンズフリー機器の使用を勧めている。
人間の活動の利便性向上に大きく寄与している携帯電話が、人間の脳に病巣をつくる道具にもなっているのだとすれば、なんと皮肉な話なのだろう。
評判を求め過ぎる子供たち
メディア、特にソーシャルメディアを多く使う子供たちは、評判を重要視する傾向が強いという調査結果がある。
米国の団体「Children’s Digital Media Center in Los Angeles」(子供のデジタルメディア・センター)が全米の9歳から15歳までの子供に対して行った調査(2013年4月19日、米国発達心理学会会議にて発表)によると、13歳未満の子供たちの約4分の1がソーシャルメディアを使っており、それが子供たちの価値観に大きな影響を与えているという。
子供たちがソーシャルメディアを使うようになったことで(フェイスブックなどはアカウント開設時に13歳以上であることを条件としているのだが)、友達の反応(いいね! やコメント等)を求める習慣がつく。その結果、子供たちが「評判を求める行動」へと傾倒している。
日本の内閣府が2010年に行った「国民生活選好度調査」によると、幸福度を判断する場合に重視した事項について、15〜29歳の60・4%が友人関係と回答している。
日本においても、若者が友達からの評価を気にし、そこに承認欲求を求めている実態がうかがえるが、ソーシャルメディアの利用がそれに拍車をかけている。
友達の評判を気にすること、友達からの承認を求めること、それ自体はある種の本能ともいえる。しかし、その度が超えてしまった場合、自分の価値評価を他者による評価に委ね過ぎ、ストレスの要因となってしまう。
社会のデジタル化が進む中で、子供の頃から、自分ありきではなく他者ありきで自分が成立する傾向が強まるとすれば、本当の自分らしさというものを見失いかねない。自分の価値は、もっと「自分による自分のもの」であってもいい。
デジタル写真を撮影するほど記憶が薄れる
日常生活、旅先、様々なイベントでデジタルカメラを手にし、思い出に残そうと撮影に勤しむ。
多くの人が心当たりのある行為ではないだろうか。
しかしこれが、イベントなどへの参加度を減らし、記憶を薄れさせることにつながるという研究結果がある。
2013年12月、米フェアフィールド大学の心理学者であるリンダ・ヘンケル(Linda Henkel)氏が米心理学専門誌「Psychological Science」(サイコロジカル・サイエンス)で発表した研究によると、博物館でのガイドツアー中、展示品を見学しているだけの人よりも、撮影していた人の方が詳細を覚えていなかったという。
同大学内にある博物館のツアーに学生を参加させ、写真を撮影するか、見学だけをするかの2通りに分けた。そして、いくつかの展示品を覚えておくよう指示を与えた。翌日、指定した展示品に関する記憶を調査すると、見学だけしていた学生と比べ、写真を撮影していた学生の方の対象物に関する認識が正確さを欠いていた。
同氏はこれを「写真撮影減殺効果」と称し、「物事を覚えておくために技術の力に頼り、その出来事をカメラに記録することで、自分自身で積極的に参加しようとする必要がなくなってしまい、経験したことをしっかり覚えておこうとしてもマイナス効果を与えかねない」と説明している。
さらに、写真を撮影した学生のうち、被写体の特定部分をズームアップして撮影した学生は、拡大した部分だけではなく、写真のフレームに収まらない部分の記憶も良く残っているようだとしている。
同氏は「この結果は〝心の眼〟と〝カメラの眼〟が同じではないことを示している」とし、写真は何かを記憶する助けにはなるものの、それは時間をじっくりかけて鑑賞したり見直した場合に限り、過剰に写真撮影をすると鑑賞が疎かになる可能性を指摘している。加えて、「思い出を残すためにデジタル写真を撮影しても、量が多過ぎ、整理もしなければ、多くの人が写真を見直したり思い出す気もなくなることを調査結果が示している。記憶にとどめるためには、写真を撮りためるよりも、撮った写真を眼にする機会を持つ必要がある」と述べている。
デジタルカメラの時代になり、一枚一枚が消化されるフィルムよりも、気軽にパシャパシャと撮影するようになった。スマートフォンのようなモバイル端末にカメラが内蔵されていることで、その気軽さは加速している。条件反射のように何も考えず、カメラのシャッターを切り、ソーシャルメディアで写真を共有する。
無闇にシャッターを切り記録を残そうとする前に、ちょっと立ち止まって顧みる必要があるのかもしれない。「目の前のもの、目の前で起きていることは、自分の脳裏にちゃんと焼き付けられているのだろうか」と。
ソーシャルメディアが失言を誘発する
「最近、政治家や著名人の失言や暴言が波紋を呼ぶことが増えている」と感じる人は多いだろう。
もちろん、失言や暴言自体はいまに始まった話ではなく、これまでの歴史の中で政治家や影響力のある人々が公の場にて数々の失言や暴言を重ねてきた。
その昔、ひとつの失言が大きな金融恐慌を引き起こした。
1927年3月から発生した昭和金融恐慌は、同年3月14日の衆議院予算委員会の際の片岡直温蔵相の失言をきっかけに金融不安が表面化し、中小銀行を中心に取り付け騒ぎが起こったことに端を発している。東京渡辺銀行が破綻したという事実とは異なる発言により、預金者の不安が一気に広がり、中小銀行に殺到し預金が引き出された。たった一つの失言が大きな恐慌を生み出すきっかけになったのだから、もはや、「すみません、失言でした」と言い訳のできる次元ではない。
1953年2月28日の衆議院予算委員会において、当時の吉田茂首相と右派社会党の西村榮一議員の質疑応答中、吉田首相が西村議員に対して「バカヤロー」と暴言を吐いたことをきっかけに衆議院が解散されるまでに至ったこともある。このバカヤロー事件(解散)なども、うっかりではすまない失言だ。
ちなみにこのバカヤロー事件、吉田首相が大声で叫んだ訳ではない。吉田首相が席に着いた際にとても小さな声で「ばかやろう」と〝つぶやいた〟だけだった。そのつぶやきを偶然マイクが拾い、気づいた西村議員がそれをとがめたことで騒ぎに発展したのだ。
このマイクの機能を、ツイッターなどのソーシャルメディアが担うようになったのがいまの社会だ。さりげないつぶやきを拾い、そして拡散する力は、吉田首相のつぶやきを拾ったマイクの性能よりも格段に上だ。
「王様の耳はロバの耳」という有名な寓話がある。
王様はロバの耳をしていて、それをひた隠しにしていた。その王様の髪を刈っていた理髪師は、王様はロバの耳であることを知っていたが口止めされていた。しかし理髪師はどうしても黙っていることができずに、井戸の奥に向かって「王様の耳はロバの耳」と大声を出して叫んでしまう。その声が伝わって、井戸という井戸から「王様の耳はロバの耳」と聞こえ、皆に王様の耳はロバの耳であることが知られてしまうという話だ(ささやいた言葉が風に乗って広まってしまうというストーリーなども存在する)。
この井戸も、いまとなってはまさにソーシャルメディアがその代役を果たしている。井戸から井戸へ伝搬するくだりなどは、やがてソーシャルメディアのような拡声器が生まれることを予見していたようにすら感じる。
人間は、失言につながりかねないことを、腹の中で思っていることがままある。多くの場合、それを腹の中だけでコントロールし、公言しない。
しかし時として、感情というせき止めのきかない〝魔物〟によって理知を超え、口から失言を吐き出してしまうことがあるのもこれまた人間だ。
それが参加者の限られた会議室、井戸端の世間話であればまだ救いようがある。しかしソーシャルメディアの中での失言はそうもいかない。発言は記録化され、その記録はソーシャルネットワークをとめどなく駆け巡る。しかも記録は完全に消すことができず、残り続ける運命にある。
そしていまの社会には、ソーシャルメディアの中で生まれた失言をマスメディアが取り上げることで、「王様の耳はロバの耳」という失言を井戸の外へ持ち出し、街中へ強烈に拡散するという構造がある。
厄介なことに、ソーシャルメディア、さらにその拡散力を補強するマスメディアが失言を伝搬する中で、その失言自体に様々な尾ひれはひれ、バイアスが加わることがある。失言は、それが口から吐かれたものとは違った形でより負の方向へ肥大化していく場合もある。
ソーシャルメディアは、〝失言を誘い出す魔性〟のようなものを持っているのかもしれないと思うことがある。
人はソーシャルメディアを前に、腹の中にはあるけれど本当は口に出すべきではないことをいとも簡単に吐き出してしまうようになった。言わない方が無難であることくらい、たいていの場合は判断がついているはずだ。しかし、目の前のスマートフォンの中から「今どんな気持ち?」とささやかれて、その判断力は思わずなし崩しにされてしまうようだ。
サイバー攻撃で死者が出る
サイバー攻撃。
これはデジタル社会が生んだ新たな脅威である。
インターネットやコンピュータが普及しその重要度が増すにつれ、コンピュータウイルスのばらまきやデータの書き換えや破損、通信やサーバーをダウンさせるような破壊活動が相次ぐようになった。人や社会に大きな危害や打撃を与えるような深刻なもの、政治的な示威行為として行われるものもある。大きな企業や組織に対し、または不特定多数を無差別に狙った高度なサイバー攻撃は増加の一途で、世界中でそれらに対する不安と警戒が強まっている。米McAfeeと米シンクタンクの戦略国際問題研究所(CSIS)が2014年6月9日に発表した推計によると、サイバー犯罪がもたらす経済損失が世界で年間最大5750億ドル、少なく見積もっても3750億ドルに上るという。サイバー攻撃による犯罪が世界経済に与える悪影響は極めて大きい。
そして遅かれ早かれ、「サイバー攻撃で死者が出る」可能性を示唆している専門家も多い。それは、軍事兵器、電力や通信設備、医療機器、車のナビゲーションなどの安全装置を対象とした攻撃が大規模でなされた時に起こるとされている。
もはや国家安全保障のレベルで対応せざるを得なくなった「サイバー攻撃」は、まぎれもなくデジタルがつくる影のひとつである。
インターネット墓地を受け入れられるか
お墓参りはインターネットで─。
インターネット上に仮想のお墓を設け、スマートフォンやパソコンの画面上には、戒名や生前の写真が現れ、そこでお墓参りを行う。デジタルにより、そのような新しいお墓参りの形態が生まれ、存在する。
少子高齢化やお墓が遠方でなかなか行けない、実際のお墓だと管理が難しい、そのような背景の中で、この「インターネット墓地」のニーズがあるようだ。海外では日本以上に広まっているところもあるという。
一方、これに対しては批判もある。
サーバーの不具合等でデータが消滅してしまったらどうするのか、お墓は実際に行って拝むべきもの、というような類いだ。遺体や遺骨を葬り、故人を弔う場所としてのお墓は古代からの慣習であり、「インターネット墓地」のような新しいアプローチに関して賛否両論が巻き起こるのは当然のことであろう。
いまのところ、この「インターネット墓地」はあくまでも従来通りのお墓の付随物としての位置づけだが、果たして未来の人間は、このインターネット墓地というものをもっと受け入れ、主たるお墓の形態に据えてしまうだろうか。それとも拒絶し、消滅させてしまうだろうか。インターネット墓地の未来は、まだ未知の段階だ。
忘れられる権利
一度インターネット上に露出した写真や文書を完全になかったことにするのは難しい。露出した途端に画面をコピーされたり、写真を保存できてしまう。
皆がソーシャルメディアを使うようになってからは、それらを人から人へ一気に拡散する環境が整い、いざ引っ込めたい情報を完全に封印することは困難になった。その不可逆性に苛まれるようになった人間は、インターネット上の情報を消し去ることの権利を「忘れられる権利」と称し、その権利を求めるようになった。
しかし、「忘れられる権利」は、なかなか正式な権利として認められないまま時が経過してきた。そんな中、個人情報やプライバシーに敏感なヨーロッパではこの権利の必要性の議論が活発に行われ続け、2014年5月13日、ついに司法が重要な判断を下した。EU(ヨーロッパ連合)司法裁判所は、グーグルに対し、自分の情報へのリンクを検索結果から削除するよう求めたスペイン人男性の請求を認める判決を言い渡したのだ。
判決は「忘れられる権利」を認め、情報が不適切、既に関連性がない、過度である場合には削除を求められるとした。この判決は、「忘れられる権利」が公のものとなっていくきっかけになることだろう。
とはいえこれは、検索結果にヒットしないようにする対応に過ぎず、一度出た情報を過去にさかのぼって取り消すこと自体がかなえられた訳ではない。
「忘れられる権利」は、デジタルの船が前に進むほど、人間にとってますます尊いものとなるだろう。デジタルは、光としてみんなで共有する優れた方法を提供し、一方で忘れられたいのに忘れられない苦しみの影をつくっている。
デジタルは、こうして光と影を同時につくっている。そもそも光と影は表裏一体、光があれば必ず影があるものだ。われわれは、デジタルがもたらす光と影の両方の影響を同時に受けなければならない。だからこそ重要なのは、その影の存在に気づき、向かい合うことだ。それにより、影を暗闇にせず、影の中に少しでも明るい領域をつくれるはずだ。いや、つくらなければならない。
<第1章 了>
小川和也(おがわ・かずや)
アントレプレナー、デジタルマーケティングディレクター、著述家。
[いずれも現代ビジネス]
Posted by nob : 2014年09月29日 08:30
へえ〜っ(驚)
■「顔ダニ」は美容の味方だった!?
僕たちの体には、目に見えない様々な微生物が共生している。そのなかには、健やかに生きていくために必要なものもいれば、害をもたらすものもいる。
そうした肉眼では確認できない微生物の1つに、人の顔の皮膚などに棲息するという「顔ダニ」がある。テレビやネットでその拡大写真を見ると、いかにも虫っぽい容貌にゾッとさせられるのだが…。この顔ダニ、健康や美容の面でどのような影響をもたらすものなのだろうか? 用賀ヒルサイドクリニックの鈴木稚子先生に聞いてみた。
「あらためてビジュアルで確認すると気持ち悪いかもしれませんが、顔ダニは誰もが持っているもの。人の顔を厳密にチェックすれば、顔ダニの死骸や糞がたくさん存在しているはずですが、基本的には無害なのであまり気にする必要はありません。ただし、増えすぎるとニキビなどの肌荒れの原因になるので要注意です」
顔ダニは別名を「ニキビダニ」と呼び、ニキビダニ科ニキビダニ属に属する生物。主に毛根に寄生するものや、皮脂腺に棲みついているものなど、複数のタイプがあり、顔ダニとはその総称なのだ。
「顔ダニは必ずしも悪いものではなく、その存在によって皮膚が弱酸性の状態に保たれ、美容に貢献している一面もあります。ただ、ストレスなど何らかの理由で免疫力が低下したり、極端に皮脂が多い状態のままでいると、顔ダニが大量発生してしまい、バランスが崩れて肌荒れを起こすことがあるんです。美容のためには、こまめな洗顔をお勧めしたいですね」
なお、洗顔によって洗い落とすことができるのは、棲みついている顔ダニのせいぜい2〜3割程度だそうだが、普通に毎日洗顔していれば、顔ダニの棲息数を適量に保つことができると鈴木先生は語る。
ダニという名称に拒絶反応を起こしがちだが、顔ダニと上手に付き合うことが美容の秘訣でもあるのだ。
(友清 哲)
[R25]
Posted by nob : 2014年09月24日 05:32
私のブレンド/自家製乳酸菌溶液に、ミント・ヒバ・ユーカリアロマを適宜加える。。。
■デング熱から身を守る蚊よけアロマ
とにかく蚊を排除する!
ワクチンのないデング熱は対症療法のみと言われています。蚊を除けることが第一ですよね。
エッセンシャルオイルのなかには蚊が嫌う成分を含む種類があります。これを使えば、殺虫はできなくても、蚊を寄せ付けない効果は期待できます。例えば、蚊取り線香には、除虫菊というキク科の植物から作られているものが今も販売されています。これと同じように、植物の忌避効果を活用して蚊を追い払います。
市販の虫よけ剤に含まれている薬剤はもっと作用が強烈。同じような効果は望めませんが、古くから「自然のものは、自然のもので対処する」というスタイルのひとつとして、市販のものと使い分けてみてください。 蚊がものすごく多い場所(山、公園など)に行く場合は市販の虫よけ剤を。普段の生活(通勤やお買いものなど)ではアロマスプレーを使う、といった具合です。
蚊よけに良いアロマでアロマ蚊よけスプレー
家に置いておくのは100mlサイズ持ち運びは20mlサイズなど使い分けていつも携帯しましょう
では用意したいアロマをご紹介します。
* シトロネラ
* レモングラス
この2つはハーブとレモンもミックスしたような爽やかな香り。含まれるシトラールという成分が蚊よけに役立ちます。同じくレモンのような香りをもつユーカリの1種もあります。
* ユーカリキトリオドラ
いずれもきつい香りではありませんが、虫が嫌う香りのような印象を受けます。そのためもう少し「良い香り」に仕上げたい場合はゼラニウムをブレンドするといいでしょう。
これでお肌につけることのできる、アンチ・モスキート―のスプレーを作りましょう。
■作り方(100mlサイズ)
* 前述のエッセンシャルオイル(1種でも全てでも)…合計20~30滴
* 無水エタノール…5~10ml
* ミネラルウォーターまたは精製水…約90ml
無水エタノールにエッセンシャルオイルを加えて、最後に水を入れれば完成。
霧吹きやスプレー容器に移します。外出時に使う場合は小さな容器に入れ替えます。
エッセンシャルオイルは天然100%の素材です。揮発しやすいため数時間置きにスプレーした方がいいでしょう。
■使い方と留意点
* よく振ってからスプレーします。肌の弱い方、傷のある方、子どもなどは気を付けて使ってください。肌に合わない場合は使用を中止してください。髪の毛もOKです。
* 衣類やかばん、ベビーカーなどにつける場合、ほとんどのエッセンシャルオイルは色がついています。事前に了承の上、使いましょう。
* 赤ちゃんの肌にはつけないでください。
* 目、口のなかに入らないように気を付けましょう。
ベランダの蚊よけ対策
見た目もかわいい素焼きストーンにアロマを垂らして
私は蚊に刺されやすいようです。なので、洗濯ものを干したり、植木に水やりをしてる間も対策を講じています。
ベランダやテラスには素焼きストーンに先ほどのアロマをしみこませて置いています。蚊取り線香のように煙に乗って広がるわけではないので、何か所かに置いておくのは無駄ではないと思います。
避けたいアロマ
花の香りに誘われて虫が寄ってきます
蚊にも種類がありますが、花の香りを好むものもいるとか。フローラル系のアロマ香水は蚊の多い場所では控えた方がよさそうですね!
からだの抵抗力をアップさせて重症化を防ぎましょう!
ディフューザーやアロマライトを使って
さて、デング熱は、デングウイルスが感染しておこる急性の熱性感染症で、発熱、頭痛、筋肉痛や皮膚の発疹などが主な症状です。インフルエンザや風邪と同じで、重症化するかしないかは体の抵抗力にも関係すると思います。
普段から、体の免疫力を高めると言われるアロマを使っておくことで予防しましょう!
■おすすめのエッセンシャルオイル
ティートゥリーのエッセンシャルオイルは体の免疫力を高めると言われます。ベッドサイドでディフューザーで香りを広げてゆっくりと休みましょう。
レモンのエッセンシャルオイルは感染症の予防に使われることがあるといいます。リビングなどに香りを広げて家族全員の健康を守りましょう。上述のティートゥリーとブレンドしてもOKです!
ハーブティも活用できます
コーヒー3杯のうち1杯をハーブティに変えてみませんか
キク科のエキナセアは乾燥したものがハーブティ用として売られています。風邪の予防などにまずチョイスされる有名なお茶です。毎日欠かさず、というわけではなく、1週間ほど飲んで、また少し休んで飲む、といった感じで飲みましょう。
エキナセア小さじ1杯に熱湯120~150ccほどを入れて、紅茶を出すように3~5分蒸らして濾して飲みます。
デング熱と地球温暖化
子どもたちの未来のために
地球温暖化が進むことで、日本ではあまり見られなかった感染症が増えることが懸念されるます。今回のデング熱やマラリアなど、蚊が媒体となって感染する熱帯性の病気は、地球温暖化も関係してるのではないでしょうか。今後、このような感染症による被害が拡大しないためにも、地球環境を真剣に考えなさいというメッセージのように思われます。
アロマはナチュラルなもので、環境にも負荷が少ないはずです。人にも地球にも優しいアロマがお役に立てるといいですね。
[All About]
Posted by nob : 2014年09月16日 19:04
情報の取捨選択と整理、、、現代を生き抜く必携の力の一つ。。。
■自分の心とつながるために。スイッチオフの習慣
どこにいくにもスマートフォンが手放せない、そんなあなたはもしかして「フォーモ・シンドローム」かも。これは英語でFOMO(Fear Of Missing Out)といい、つねに世の中から取り残されてしまうのではないかという不安に苛まれ、食事中だろうと入浴中だろうと、スマートフォンをチェックしている人たちのことを指します。
そんな人に、スマートフォンからちょっとだけ離れることの効果をご紹介したいと思います。
スイッチを切ることでつながる絆
大事なニュースが世界中どこにいてもすぐに入手できる便利さ、災害時につながるネットワークなどを考えると、スマートフォンは確かにとても便利で、世界中がポジティブに変化していることは事実です。
スマホは「使い方次第である」という意見もありますが、まさにその通り。つけっぱなしではなく、毎日決まった時間に、自分の時間を作るために「スイッチを切る」という、シンプルなルールを自分で設けてみてはどうでしょうか。
一緒に誰かとカフェに行き、相手が横に座っているにもかかわらず、新聞や雑誌を広げたり、スマートフォンに夢中になったりするのはマナー違反です。
食事の時間は、食事をゆっくり楽しむ。外に出て散歩をして新鮮な空気を吸う。静かに本を読む時間を設ける。あるいは子どもと一緒に台所に立って学校での出来事を話す。「ながら」のない、ひとつのことに集中する時間を持ち、人と、空間と、時間と、そして自分との対話してはどうでしょうか?
これは、昔の人たちは当たり前のこととしてしてきたこと。人の表情を見ることに集中したり、相手との会話の内容を掘りさげたりすることの方がはるかに大切です。
情報を得ること=しあわせ、ではない
絶え間なく入ってくる情報は、自分にとってどれほど役に立ったのだろうか、と考えたことがありますか? びっくりするほどその内容を思い出せなかったり、じつは情報をプライオリティーにそって振りわけて処理することの方が面倒くさいと感じることがしばしばあります。
心理学からの側面で考えると、「自分のいま」という時間を大事に使うことを真剣に考える人は、遠くの将来について不安を抱えることが少なく、総じて幸せである、という調査結果が出ています。つまりは"Carpe Diem"、ラテン語で「君の今を生きろ」のコンセプトです。さらに、幸せ度の高い人というのは、いわゆる「バランスの取れた時間へのとらえ方」を持っている人のことをいうのだそう。
これはつまり、過去・現在・未来という時間の明確な区切れがないために、緩やかに時が流れているということ。過去の失敗を思い出しては、これからの自分のために活かすことをしたり、未来のいつかに成し遂げたいことを逆算して、今からできる努力を重ねていくこと、等。
(Boniwell and Zimbardo 2004 より抜粋)
どうしてもスマートフォンを「いま、いじらなくてはいけない必要性」にとらわれないために、いつも肩の力が抜けている感覚を持っていることが大切なのです。
スイッチを切ることで、他人との絆だけでなく、もう一度自分が何をしたいのか、自分とは何か?を見直す。いつも何かをしなくてはならない必要性からちょっと抜けだす。そうすることで自分のこころとつながることができるのです。
[Positive Psychology UK/MY LOHAS]
Posted by nob : 2014年09月13日 21:07
今さらながら、、、水について。。。Vol.2/おまけにレモン
■「水の飲みすぎでむくむ」は嘘!? 水分補給のホントのところとは
継田理恵
9月がスタートしましたが、まだ日中は暑い日も多いですよね。あなたは、しっかり水分を補給していますか?
美と健康のためには、1日に2リットルもの水を飲むべきだという説がありますが、飲みすぎはむくみや水太りの原因になるともいわれます。
水をたくさん飲むべきか控えるべきか、一体どちらが正解なのでしょうか。今回は水分不足にならず、むくまない水の飲み方をご紹介します。
■1日に飲むべき量と正しい飲み方
1日に飲むべき水分量は、”体重÷30”で算出できます。体重が50kgなら、50÷30=1.6666……約1.7リットルを目安に水を飲むのがベストということです。
食べ物からも水分を摂ることができるので、算出した数字よりやや少なめでもよいのですが、思っているよりも多くの水を飲まなくてはなりません。
カフェインを含む飲み物やアルコールは、水分補給にはならないので要注意。水分を摂った気になってしまうので、1杯のコーヒーやお酒につき1杯の水を飲むようにしましょう。また、スポーツドリンクは砂糖や甘味料などの添加物がたっぷり。太る原因になるので気をつけてくださいね。
水では飽きてしまうという方には、ココナッツウォーターがおすすめ。ココナッツウォーターに含まれる成分は、人間の血漿に非常に似ているといわれているので、運動後の水分補給にも最適です。
また、ココナッツには優れた抗酸化作用があるので、年齢が気になりだした方にもぴったり。中鎖脂肪酸やビタミン・ミネラルも豊富なので、美肌やダイエットにも。いいことづくしです!
■むくんでしまう理由は腸にあり
水分をしっかり摂るとむくんでしまうという方は、腸のはたらきが弱くなっていることが考えられます。腸のはたらきを整えることから始めましょう。
(1)起き抜けに一杯の水を飲む
眠っている腸を目覚めさせましょう。
(2)朝バナナを食べる
食物繊維やカリウムが豊富なバナナで、朝のスッキリを促しましょう。
(3)ココナッツウォーターを飲む
食物繊維を含むココナッツは整腸作用も期待できます。
(4)適度な運動
運動不足でも腸のはたらきは鈍ります。30分のウォーキングや腹筋など、続けられる運動を毎日行いましょう。
1日に飲むべき水の量は意外と多いです。むくみが気になる方は、腸のはたらきを整えることも意識して行ってみてくださいね。
■甘く見ちゃダメ!酸っぱい「朝レモン水」の美容効果はスゴすぎる
佐藤まきこ
ストレッチにヨガ、グリーンスムージー……。誰もが惹かれるような美人は必ずといっていいほど、何か朝に習慣として行っていることがあります。
そんな中でも、明日の朝からすぐに始められそうで、しかも女性にとってうれしい美容効果がたくさんあるのが、”レモン水”です。
驚くべきレモン効果を知ったら、必ずレモンを常備したくなるはずですよ。
■1:腸の働きがよくなる
朝起きたときに水を飲むと刺激となって、腸も目覚めて活動を始めます。ビタミンCには腸の運動を活発にさせる働きがあるため、レモンを絞ったレモン水ならばその効果がアップするというわけ。しつこい便秘解消にも効果が期待できます。
■2:デトックス効果
ビタミンCは抗酸化作用があることでも知られ、不要な老廃物を排出してくれます。さらにレモンには利尿作用もあるため、朝のレモン水が前日や寝ている間に溜まってしまった老廃物を、排出するよう促してくれます。
■3:疲労回復効果
レモンに含まれるクエン酸は疲労の原因となる乳酸の生成を抑え、エネルギーを効率よく作れるよう促してくれます。そのため、疲れが溜まってツライ朝や休み明けの朝などに飲むと、疲れが軽減しているように感じられるでしょう。
■4:爽やかな目覚めになる
これまで述べてきたとおり、レモンにはさまざまな効果がありますが、やっぱり口にするときに一番強い印象を残すのは、あの酸っぱさと独特の香り。
そんなレモンの香りをかぎ、心地良い酸っぱさを感じると、爽やかな目覚めをもたらしてくれるでしょう。コーヒーを多飲している方には特に、コーヒーの代用としておすすめします。
レモン水の作り方は、水にレモン一切れ分を絞るだけ。冷たすぎる水は体を冷やしてしまうので、白湯を用意していればなおベターです。また寒い季節なら、温かいお湯にレモンを絞ってホットレモンにしてもOKです。
このほか、『美レンジャー』の過去記事「あなたはいくつ知ってる?レモンの超おいしい飲み方5つ」でもご紹介していますが、レモンには体内時計のリセットやダイエット、体臭を抑える効果などもあります。朝起きたときだけでなく、レモンはヘルシー美人にとってぜひ活用したいアイテムですね。
[いずれも美レンジャー]
Posted by nob : 2014年09月13日 21:04
今さらながら、、、水について。。。
■水の飲み方次第では老化も!?正しい水分摂取のポイント3つ
前田紀至子
美肌や健康に対する意識が高い人なら、当たり前のように飲んでいるミネラルウォーター。ですが、飲み方次第で老化の原因にもなり得ることをご存知ですか? 健康のためのつもりがマイナスに……なんてことになってしまわないよう、正しい水分摂取のポイントを押さえておきましょう。
■加齢と共に減って行く体内の水分量
人間の身体の60%は水分でできていると言われています。それだけではなく、実は骨の3分の1も、水でできています。体内の水分量は新生児で 80%、幼児は70%と、成長とともに減ってゆき、成人すると男性は60%、女性は55%まで減少します。さらに60歳以上になると50%くらいになってしまいます。
■水分量の摂り方を間違えると意味が無い!
水は血液として身体をめぐり、栄養素を運び、老廃物を排泄するという大きな役割があります。水が不足していると、血はドロドロになってしまい、血の巡りが悪くなったり、便秘がちになったり、疲れやすくなってしまいます。だからと言って、水を大量に一気飲みしても、意味がありません。人の身体は、水を一気に吸収することができず、単に身体に負担をかけることにしかなりません。
大切なことは身体にとって必要な水分量を知り、こまめに飲むこと。汗や尿として排出する水分を含めて考えると、1日に補填したい水分量は2.5Lですが、水だけではなく、お茶や食事からも水分を摂取するので、ミネラルウォーターで摂取したい水分量は1日に1L~1.5Lが目安であると覚えておきましょう。
■美肌のためにも覚えておきたい水飲みポイント3つ
1:カフェインを摂取する時はお水も忘れず!
カフェインは胃腸に負担がかかる他、利尿作用があり、体内の水分を排出してしまいますので、コーヒーやお茶を1杯飲んだら、水を2杯飲むというように、カフェインを含んだ飲み物を飲む場合は、水もセットにして飲むようにしましょう。
2:500mlペットボトル3本を朝昼夜に分けて飲む
水を一気に飲んでも意味が無く、大切なのは少しずつこまめに飲むこと、とは言っても、習慣にするまではなかなか難しいもの。リズムをつかむためにも、1日に500mlを3本飲みきることを意識し、デスクの上に置いたり、鞄の中に入れたりして、のどが渇いたときはもちろん、小腹がすいたときに間食の代わりに飲むなど、水を身近な存在にするのがおすすめです。
3:常温の水で肌のコンディションを整える
常温の水は身体に吸収されやすく、代謝を上げる作用も期待できるため、疲れが気になる時や、肌のコンディションが優れない時、ダイエット中などは、常温の水を飲むようにしましょう。
健康と美肌のお供として欠かせないミネラルウォーター。正しい飲み方で頼りになる相棒になって欲しいものですね。
[Life & Beauty Report]
Posted by nob : 2014年09月13日 20:47
また旅立つ君へVol.77/常識は、、、
だれかの都合。。。
Posted by nob : 2014年09月01日 15:15
そもそも至極当然のこと。。。
■自分の命を人に預けない
石崎 公子
広島をはじめ、多くの地域の土砂災害被害は大変なものになっている。テレビ画面に映るあり得ないような惨状に、言葉もない。朝になったら、家の状況や周りの状況が一変しているというのは、どれだけ大きなショックだろう。この蒸し暑い中で、土砂と格闘されるのは想像するだけで気が遠くなる。
被害に遭われた方には、心よりお見舞い申し上げます。
この状況を見て、私たちはいったい何を学べるのだろう。このような災害による被害をどう防いだらいいのか、どのような対策ができるのか、どうしたらいいのか……?
それに対して、NHKの防災担当記者がテレビで言っていたのが、「自分の命を人に預けない」ということだった。
今や、自然災害の大きさは、想定範囲を大きく超える。大雨も洪水も、地震も津波も、竜巻も台風も。少し前ではありえないような異常気象が頻発している。
「自分の命を人に預けない」とは、「自分の命を自分で守る」ということだ。
何が起きるかわからないから、いろいろなことを想定しながら、自分はどうすればいいかを自発的に自律的に考えること。自ら情報を取りに行き、自ら想像力を働かせて、自ら何をしたらいいかを考える。そういうことだ。
これを聞いて思った。これは、防災だけではない。人生も、仕事も、何もかも。そういう時代になったのだな、とつくづく思うのだ。
会社だって、仕事だって、明日はどうなるかわからない。今日安泰なことが、明日安泰であるかどうか、どんどんわからない時代になってきたと思う。しかも、何をすれば安心、という「100%」が、今の時代にはないのだ。
自分で自分をどう守るかなど、かつてはそうそう考える必要などなかったのではないか。それはきっと、会社が、ご近所が、家族が、支えてくれていたのかもしれない。そこまで急激に変化するようなことが多くなかったこともあるだろうが、変化に対して、周りが守ってくれたことも大きかったし、会社や地域の人が考えてくれたり、専門家の人が考えてくれたりしていたのだと思う。
今は、かつてよりも情報はたくさんある。情報源も増えた。危険を予知する方法だって以前よりも増えているかもしれない。
しかし、情報がたくさんあったとしても、どの情報を取りに行くかを決めるのは自分。選ぶのも自分だし、情報を取りに行くのも自分。さらに、その情報を元にどう考えるかも自分だ。
医療だって、お医者さんにお任せだったのが、今ではどのお医者さんに診てもらうか、どこで診てもらうかを自分で探し、選ぶことで、より良い医療が受けられるし、治療法だって選ぶ時代だ。
どれを選ぶかを一緒に考える人や教えてもらう人との関係性まで、以前よりも自発的に作ることが求められつつあるように思う。
そういうことを自由自在にできる人はいい。誰もがそういう人ではない。そうはできない。何をどうしたらいいか迷う人、わからない人には、とても厳しい時代になったと言わざるを得ない。でも多くの人がそうなのではないだろうか。
命も人生もすべて、人任せにするな。自分が自分で決める、考える、そうしなくてはいけない時代。自己責任という言葉が話題になってからずいぶん経つが、もはやそれは当たり前で話題にすらならないのかもしれない。わかるけれど、厳しい。
人生を人に預けない。
防災を考えることで厳しい時代を再確認し、自分自身の人生についてもしっかり自分で考えることが、今、求められているのだと改めて思う。
[newsdig]
Posted by nob : 2014年09月01日 15:09
また旅立つ君へVol.76/想像する力が、創造する力を生む。
思いやる事も、夢見る事も、自分を変える事も、
すべては想像から始まり、そこから創りあげていくもの。
[首都医校CMコビー]
Posted by nob : 2014年08月31日 07:05
利も害も併せ持つ何事も何物もバランス感覚。。。
■せっかくのUV対策がムダに!? 「日焼けを加速させちゃう食べ物」3つ
by 町山町子
涼しい日も増えてきましたが、まだまだ気になる紫外線。美意識が高い女性にとって、夏の紫外線対策は毎日戦いのようなものですよね。もちろん過度に紫外線に当たる行為は肌にとってよくありませんが、実はその日食べた物によって、日焼けしやすい体質になってしまうことがあるんです!
そこで今回は、ハーブなどのセラピストである筆者が、『日本メディカルハーブ協会認定 メディカルハーブセラピスト 公式テキスト』を参考に、“日焼けを加速させる食べ物”をご紹介します。
■1:キュウリ
夏場にはよく食べられているキュウリですが、じつは日焼けを促進してしまうといいます。何故なのでしょうか? それは“ソラレン”という成分が含まれているからです。
ソラレンは感光物質と呼ばれており、紫外線に当たるとシミの原因になります。そのため、キュウリは日焼けを加速させる食べ物だと考えられているのです。
■2:柑橘系のフルーツ
たとえば、レモンはビタミンCが豊富に含まれているので、日焼け対策によさそうですが、これもまたソラレンが含まれているので、出かける前や日中は摂取を避けたほうがよいそうです。夜に食べる分には問題ありません。ポイントは、日中紫外線に当たる前に食べるのがNGだということです。
そのほかに、グレープフルーツやオレンジ、キウイなども、ソラレンが含まれています。
■3:蕎麦やアルコール
暑い夏は、ざる蕎麦などを食べる機会が増えますが、朝食や昼食に食べるのは要注意です! なぜなら、蕎麦にもソラレンが含まれているから。紫外線は日焼けだけでなく、シミやシワの原因にもなりますので、ソラレンを豊富に含む食べ物は肌老化を加速させる原因になります。
また、アルコールの大量摂取も日焼けを加速させるので飲み過ぎには気をつけましょう。
以上、“日焼けを加速させる食べ物”をご紹介しましたが、いかがでしたか?
柑橘系のフルーツや蕎麦、アルコールは夏の楽しみのようなものですよね。肌を老化させないためにも日焼け止めは必須ですが、食生活にも気を配れるといいですよね。
■紫外線だけが原因じゃない!女性の敵「シミ」に対抗する栄養素3つ
by 町山町子
肌の悩みで、シミができるのは紫外線が原因というのはご存知だと思いますが、主な原因はそれだけじゃないんです!
女性はホルモンバランスによって、肌の状態が変化します。この女性ホルモンには2種類あり、バランスが崩れると肌の力が衰えてダメージを受けやすくなります。とくに生理中や妊娠中、ピルを服用しているときはプロゲステロンの作用で日焼けしやすくなり、シミの原因になります。日焼け止めはもちろん、UVカット仕様のアイテムでいつも以上の対策を心がけたいものです。
そこで今回は、“内側からキレイを強化する3つの栄養素”を、美容皮膚科銀座よしえクリニックの廣瀬よしえ先生の著書、『「若いね」といわれる美肌づくり』をもとにご紹介したいと思います。
■1:イソフラボン
植物由来のエストロゲンともいわれており、抗酸化力を上げてくれるポリフェノールの一種。イソフラボンは女性ホルモンと似た働きをするので、肌の保湿力アップや美白に役立ちます。主に大豆に多く含まれており、1日の摂取量の目安は、たとえば豆腐なら1パック、豆乳なら1カップ程度です。毎日摂取して女性ホルモンを上手に補いましょう。
■2:ビタミンC
紫外線に対する抵抗を高める抗酸化パワーのある栄養素です。サプリメントより、緑黄色野菜や淡黄色野菜から摂取するほうが吸収率は高くなります。ビタミンCは、シミやそばかすなどの色素増加を抑える効果や、メラニンを還元して退色させる働きがあります。日焼けのあとの肌荒れを治す働きもあります。
■3:ビタミンE、ビタミンA(ベータカロテン)
主にゴマ油、オリーブ油、大豆、落花生、アーモンドに多く含まれています。オレンジやトマト、ニンジンなどに多いビタミンAも、体の内側から抗酸化力をアップしてくれます。肉食中心の生活は体が酸化しやすいため、野菜中心の食生活に変え、抗酸化作用のあるサプリメントなども上手に取り入れて活性酸素を抑えましょう。
女性ホルモンのバランスは、過度なダイエットや不規則な生活などでもすぐに崩れます。ここに上げた3つの栄養素は、ひとつだけを強化してとるのではなく、すべての栄養をバランス良くとることが美肌づくりの近道です。バランスのとれた食事と十分な睡眠を確保して規則正しい生活を心がけてください。
[いずれもWooRis]
Posted by nob : 2014年08月31日 06:55
呼吸は鼻だけでいい。。。Vol.2/長年の口呼吸からの完全脱却はなかなかに難しい。。。
■無意識に口開いてない?老け顔の原因にもなる「口呼吸」の対策法
by 望月理恵子
緊張がとまったり、ボーっとしたりすると、気づいたら口が開いているなんて方も多くいるようです。この状態になってしまうのは、口で呼吸をしているせいかもしれません。あなたも、まわりの友人などからよく「口が開いているよ」なんて言われたことはありませんか?
最近増えてきていると言われる“口呼吸”。でも、この呼吸法が身体にデメリットをもたらしているということを知っていましたか?
今回は、リラックスのために呼吸法を大切にする“ヨガ”のインストラクターである筆者が、意外と知らない“2つの呼吸”についてご紹介します。
■あなたは口呼吸or鼻呼吸?
呼吸法については口呼吸と鼻呼吸の2つがあります。自分がどの呼吸法をしているのかわかりますか? おそらく呼吸は無意識に行っているものなので、意識的にどちらの呼吸法をしているかというのはわかりにくいと思います。
“無意識に口が半開きになっている”、“唇が渇きやすい”、“朝起きると、喉がヒリヒリ痛い”、“歯並びが悪い”これら1つでも当てはまると思ったものがある場合は口呼吸を行っている可能性があるのです。
■口呼吸があなたの身体に悪影響を与えている
口呼吸は身体に様々な影響を及ぼしてしまいます。口呼吸をしている、つまり口がずっと開いている状態でいると、通常口の中は唾液で潤っているはずの口の中が乾燥してしまうのです。
唾液には殺菌作用があります。そのため口の中が乾燥してしまうと、細菌が繁殖しやすい状態になり、口臭や炎症また虫歯をつくりやすくなってしまいます。
さらに口が常に開いているということは口周りの筋肉を使えていないということであり、お肌がたるみやすくなってしまうという美容面のデメリットもあります。
■なぜ口呼吸をしてしまうの?
慢性的な鼻炎を持っている方や、普段うつ伏せで寝る習慣がついてしまっていると、口呼吸しやすくなります。また、固いものを食べる習慣が減少傾向にあり、口周りの筋肉を使う機会が減ってしまったことも口呼吸が多くなっている原因の1つ。
筋肉は使わないと衰えてしまいます。知らないうちに口周りの筋肉が衰え、口が開きやすい状態になってしまうことで口呼吸をしてしまっているのかもしれません。
■鼻呼吸に切り替えるには舌を意識してみよう!
鼻呼吸が良いのはなぜでしょうか? まず鼻にはウイルスやホコリなどが身体に入るのを防ぐために鼻毛や粘膜などのフィルターがあります。また吸った空気を浄化してくれる働きもあります。口呼吸をしてしまう方は、舌の位置を意識すると鼻呼吸に切り替えやすくなります。
舌を上あごにつけることを意識すると自然と口を閉じることができるので、鼻呼吸をしやすくなります。しっかりと鼻から息を吸い込むことで、今までの不調が改善されるかもしれません。試してみてください。
以上、老け顔の原因にもなる“口呼吸”の対策法についてお伝えしましたが、いかがでしょうか?
ちなみにヨガは腹式呼吸、ピラティスは胸式呼吸という方法で、呼吸法を大切にした運動です。どちらも基本は鼻からの呼吸となります。リラックスしたいときは副交感神経を刺激する腹式呼吸で、体と頭をスッキリさせたいときは交換神経を刺激する胸式呼吸をして、呼吸から健康を手に入れたいですね。
[WooRis]
Posted by nob : 2014年08月29日 09:42
酵素に関するおさらい
■美と健康を叶える食の話
“酵素”が注目されるわけ
ホリスティック栄養コンサルタント、食育アドバイザー
北川みゆき
酵素は生命維持に欠かせない栄養素
私たちの体内では、24時間絶えまなく行われる化学反応によって生命活動を維持し続けています。食べたものを消化しそれを吸収できる形にする。エネルギーを作る。できたエネルギーを保存できる形にする。古くなった組織を壊し、新しい組織を作る。身体に不要なものを排泄できる形にする…。
これらすべての化学反応には必ず“酵素”が関わっています。酵素は化学反応のスピードをアップさせるために必要不可欠なものなのです。
酵素には「消化酵素」と「代謝酵素」と「食物酵素」がある
酵素には大きく分けて「消化酵素」と「代謝酵素」と「食物酵素」の3つがあります。
“消化酵素”と“代謝酵素”は体内で作られるので「体内酵素(潜在酵素)」、“食物酵素”は食物に含まれていて食事から摂るものなので「体外酵素」ともよばれています。
“消化酵素”は消化・吸収に働き、“代謝酵素”は生命維持活動に働きます。一方、“食物酵素”は生の食品(生の魚、肉、野菜、果物)や発酵食品に多く含まれており、消化を助けてくれるため、体内で生成される“消化酵素”の無駄遣いを防いでくれます。
体内には1万以上の異なった酵素が存在し、消化酵素だけでも9,000以上、代謝酵素は3,000以上存在あるといわれています。また、食物酵素はほとんどが48度以上で失括するため(中には60度や70度まで持つものもある)、加熱をしないで生の状態で食べると食物酵素が摂れることになります。
体内で作られる酵素には限りがある
体内酵素は体の中で作られるもので、酵素の生産量は1日一定量しかなく、人はその一定量を消耗して生きています。また、加齢とともに作られる量が減ってくるため積極的に食事から“食物酵素”を取り込む必要があります。
体内で生産できる消化酵素と代謝酵素は共に限りがあるため、いかに消化に関わる酵素を減らし、代謝に関わる酵素に回せるかにかかっています。代謝酵素の量が多くなると、お肌の新陳代謝もよくなるなど、アンチエイジングにもつながります。
生の食べ物から酵素を摂り入れて酵素ジュースや酵素サプリメントなどは、消化酵素の無駄遣いを防ぐために摂り入れて、結果代謝酵素の量が増えることを目的に摂取をしているのですね。
消化・吸収・排泄が大切
私たち人間が、一生涯で消化しなければならない食物の量はどれくらいになるかご存知ですか。なんと、平均10トン=50mプール1杯分にもなるそうです。果たしてそれらの食物を日常で、正しく完全に消化・吸収されていると思いますか?答えはノーです。
その顕著な症状として、胃もたれ、膨満感、便秘、下痢、臭いおならなどがあります。これらの症状を、日常で抱えている方も多いのではないでしょうか。
食物は消化・吸収してこそはじめて体の栄養になります。消化・吸収された栄養は小腸から肝臓を介して血液に入り、60兆個の細胞一つ一つへ運ばれるのです。消化がきちんとされない状態、つまり未消化の食物が大腸に届くと、腐敗や発酵を起こし腸内の悪い微生物(悪玉菌)の栄養素となってしまいます。
そうならないためにも、腸内の環境を整えることと、ストレスを上手に解消しながら心の状態を平穏に保つことが、よりよい消化吸収排泄への近道となります。
酵素を活性しながら、腸内の環境を整えるには“HOPE”が大切といわれています。
H:High Fiber 高食物繊維
O:Oils-Essential Fatty Acids, Flax, Fish and Borage 質のよい油・必須脂肪酸
P:Probiotics-Good Bacteria 乳酸菌やビフィズス菌
E:Enzymes-Taken With Meals 酵素
つまり、野菜・果物を多めにとり、質のよい油、善玉菌の乳酸菌とビフィズス菌の摂取、食物酵素の摂取が健康の要となるということです。
酵素の働きを、ざっくりとでもつかんでいただけたでしょうか。
さあ明日から酵素を意識した食生活を心掛けて美と健康を手に入れましょう!次回は、体内で酵素をより効率よく活性化するための条件について記したいと思います。
[スキンケア大学・美ログ]
Posted by nob : 2014年08月25日 11:04
また旅立つ君へVol.75/夢を求め続ける勇気さえあればいい。。。
■アナタはいくつ当てはまる? 幼い頃に現れる「成功者のサイン10」
Michael Anthony Yoshioka
オレはビッグになれる!!大器晩成型だ!
子どもの時に、そう思っていた人はぜひ見て欲しい。
海外で話題になっている、いわゆる「成功者」になる子どもに現れる特徴を10つ、まとめてみた。
※成功者=社会に大きなインパクトを与えることができる人、沢山の人を夢中にさせる人のコト
アナタの幼少期はどうだっただろうか?また、自分の子ども、まわりの子どもはどうだろうか。これから紹介する「成功者のサイン10」は、子どもだけでなくもちろん成人にも当てはまる。アナタにいくつあてはまるか、ぜひ見てほしい。大切なことが見つかるかもしれない。
1. 自分を理解している、自己分析が出来る。
自分のことを自分で、分析できる。或る意味、自分を俯瞰して、客観的にとらえることができるのだ。
2. 飽くなき向上心がある。
驕ることなく自分を高めることなら、いかなる努力も惜しまない。そして何より負けず嫌いだ。
3. 常に変化を求めている。
既存のモノにとらわれず、常に新しいものを見い出すため追求し続ける。それによって新しいチャンスを掴むキッカケになるのだ。
4. 他に惑わされず、自分を持っている。
周りに流されることなく、自分からアクションを起こしている。何事も自分の声に耳を傾ける。
5. 楽観的で希望を持って進める!
物事どうにもならないことに直面することだってある。そんな時でも悲観せず、前をみて歩く。
6. 常に、知識を深めている。
やはり知識を増やすことは成功への重要なステップ。博識ある人との会話や本を読むことでインスピレーションをもらう。先人たちから学ぶことは多いのだ。
7. 黄金の心(優しさ)を持っている。
相手にも優しく出来ないようでは、まわりが認めてくれないし、また協力を得ることができない。
8. 最優先すべきところは富、地位、幸福ではない。
一個一個、確実に正しい選択をすれば、それらは自ずと後からしっかりついてくるものだ。本当に大切なものはそれぞれ。自分の大切なものを持っている。
9. クレイジーになる!
周りの人たちと一緒ではいけないこともある。世界を驚かしてきた人々は、自分の持つ個性を最大限に引き出してきたのだ。
そして最後はもちろん、、、
10. デッカい夢をもっている!
これがなければまず始まらない。自分の思い描く夢に向かって、努力を尽くし、挫折を味わい、最終的には夢をかなえるのだ。
ミッキー・マウスの生みの親である実業家のWalt Disney (ウォルト・ディズニー)もこういっている。
夢を求め続ける勇気さえあれば、すべての夢は必ず実現できる。いつだって忘れないでほしい。すべて一匹のねずみから始まったということを。ーWalt Disney
アナタはいくつあてはまっただろうか?
[T A B I L A B O]
Posted by nob : 2014年08月25日 10:38
また旅立つ君へVol.74/どんな仕事をするかではなく、、、どのように仕事に取り組むのかということ。。。
■「今の仕事では満たされない」と感じた時に。転職すべきか否かを決める3つのサイン
転職するべきか、否か。
ほとんど全ての熱心な社員はそのキャリアの中で、いつかはこの問いと対峙することになります。名目上はとてもいい仕事に就いています。でも、それら全てを投げうって、何か全く違ったことをしたいという欲求も捨てがたいでしょう。どんな時、今の仕事を続けるべきで、どんな時、その内なる声に耳を傾けるべきなのでしょうか。
こういう場合には、両方の側の意見を考え抜く必要があります。多くの人の仕事の満たされなさは、部分的には、その人の態度の問題にあります。そして、多くの人は見方を変えるだけで、画期的にその仕事を楽しめるようになります。一方で、自分に合わない仕事に就いている人は、仕事を替えるべき時期は、とっくに過ぎているのです。
しかし、それらの難しい問いに対してもひとつだけ、出口を探し始めるべきサインがあります。それはその仕事があなたにとって挑戦ではなくなった時です。
Human Workplace on LinkedIn のCEOであるLiz Ryan氏は、最近、次のようにすすめています。
賢くなる上で最も確かな方法のひとつは、自分より知的な人たちに囲まれるようにすることです。それによって、自分の居心地の良い領域(コンフォートゾーン)から常に外にストレッチをするように、はみ出すようにと保つことができます。現在の仕事があなたにとって役不足なのだとすれば、この現象は起きようがありません。
仕事にたくさん貢献したいと思っているのなら、あらゆる筋肉を使うべきでしょう。脳をフルに使っていたいとも思うことでしょう。自分と周りの賢い人と一緒に問題解決を図ろうとします。オウムとウサギは固いものを噛んでいる必要があります。私たちにとってもそれは同じです。
ではどうやったら、その仕事が、ただ気が休まらないだけなのか、それとも時間をかけて他の高い要求の仕事を探すべきかわかるのでしょうか。Ryan氏はいくつかの指標を示しています。
1.問題。え、何が問題?
「同じことを何回も正確に同じやり方でやり直しても、そこから何も学ぶことはできません。同僚が、歩きなれた道を踏み固めることにしか興味がないなら、あなたのスキルを伸ばす余地はそこにはないのです」とRyan氏は言います。「同僚たちは地球上で最もいい人たちかもしれません。でも、彼らが、あなたがいつもと枠組みの違うアイディアをだしても、その考えについて会話することもなく、いつもと同じことをするだけならば、あなたは間違った場所にいます」。
2.尊敬する人がいない
大事なことなのでもう一度言います。自分より頭のいい人たちと一緒にいると、より賢くなれます。もし、現在の職場を見まわして、誰からも学ぼうと思えないのであれば、それはレッドカード状態です。自分自身に問いましょう。「誰と議論できるか。仕事場で精神的な刺激を与えてくれるのは誰か。誰かを尊敬していてその人から学びたいものがあるか」。もし、これらの問いに対して答えが「...誰もいない」ならば、脱出の計画を立て始める時期です。
3. トップがビジョンを持っていない
何に向かって仕事をしているかわからなければ、自分自身を進展させることも難しいです。あなたが組織のトップに立っているのでない限り、そのチーム、部署、会社に対するビジョンはトップから来るべきです。ビジョンを提示する代わりに、組織がどこへ向かおうとしているかについて、彼らが沈黙を守っているだけであれば、意味のある貢献の余地はとても限られてしまいます。「もし、あなたがビジョンが何だかわからなかったり、どうやって手に入れるかわかってない人の下で働いているのであれば、自分自身の枠組みを育てることができません。それらは上司から学ぶべきなのです」とRyan氏は忠告しています。
3 Signs You're Too Smart for Your Job|Inc.
Jessica Stillman(訳:Conyac)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2014年08月25日 10:31
眠りに関する考察/まとめとおさらい
■睡眠を科学的にとらえて、健康な生活をデザインしよう
1日に8時間眠る人の場合、人生の約3分の1は寝ていることになります。わざわざそれだけの時間を費やして残りの3分の2を生きているのですから、睡眠は間違いなく大切です。しかし、眠ることに関する研究は今も発展途上で、未知の領域だらけです。
今年の3月末、11年ぶりに厚生労働省から、「健康づくりのための睡眠指針」が出されました。データに基づいて睡眠12箇条も作られています。これまで巷で言われていたことの中には、間違った説もあったようです。間違えて覚えていたことがないか、ぜひサイトをご覧になってみてください。
■経験則がほとんど
さて、保健の教科書で睡眠が最初に登場するのは、「健康とは?」「健康には何が関係しているのか?」という小学4年生の単元で、食事(栄養)、運動と共に取り上げられています。皆さんは、睡眠が大切な理由を、どのように教わりましたか?
以前とある会合で質問してみたところ、寝ている間に成長ホルモンが出るから寝なければならない、ぐっすり寝て休養しないと次の日に集中できない、体内時計があるので夜に寝ないとリズムが狂う、寝不足になると運動中にケガしやすくなる、などといった答えが次々と出てきました。
でも、これらが、どのような科学的データに基づいて言われていることなのか、ほとんど学習しなかったと思います。日常経験則に基づいた内容が多く、自分の経験と照らし合わせて、確かにそうだなと納得しながら重要性を学習していたのではないでしょうか。それもそのはず、睡眠が科学的に解明されていなかったからです。そもそも、なぜ眠らないといけないのか、その究極の解すらまだ見つかっていません。
■脳との関係で考える
保健では、睡眠は休養という言葉と一緒に並べられています。休養の意味を「体を休める」と捉える人もいれば、「脳を休める」と考える人もいます。どちらも正しいのですが、そもそも脳について理科で学習するのは中学2年生からです。脳を休めると言われても、脳のどのような機能を休めるのか、起きている時とどう違うのかといった内容は高校レベルになってしまいます。
しかし、睡眠は成長過程でとても重要です。高校生になるまで学習を待っていられません。また、睡眠に限らず、体と脳の関係は健康を考える上で重要です。そのため、保健では理科よりも早い段階で脳が登場します。脳から出される「ホルモン」といった用語も、理科では高校生物の範疇ですが、小学校の保健で出てきています。
とはいえ、まだまだ脳に関する記述は、ほんの少しです。記憶や学習といったことと脳の仕組みについては保健でも理科でもほとんど学習しません。完全に科学で解明されたわけではなく仮説の部分が多々あるので、教科書的に記載できないこともあるのでしょう。ですが、私たちは大人です。解明されていることだけでなく、解明されつつある内容も含めて学習し、そこから物事の本質を捉えて健康に活かすように心がければよいのです。
例えば、脳は、新しく得た知識や感情を睡眠中に整理し、これまでの情報と関連づけながら脳内に記憶保存させていくと言われており、その整理過程で夢を見ているのではないかと考えられています。このことは、科学的に完全に確かめられているわけではありませんが、「脳は、睡眠中にしかできない、やるべき仕事を持っている」と捉えることは、間違いにならないでしょう。
つまり、私たちが眠らない限り、脳はやるべき仕事をできないのです。そう考えれば、私たちは一日の終わりに、脳が仕事をできるように必ず睡眠をとるべきであり、どのような時間シフトを組めば、脳に十分な作業時間を与えることができるのか、といったことを意識するようになります。
小さな健康情報を一つひとつ覚えて、その都度実践していくことは大変ですが、このように、まずは大きな概念で捉えて必要なことを理解していくと、健康のために知識を活かしやすくなります。
結局、脳は一人ひとり異なっているのですから、脳に必要な睡眠のとり方も一人ひとり微妙に違ってくるはずです。だからこそ、睡眠を単なる休養と考えず、脳の機能と密接に関係があるものとして捉えてみてはいかがでしょう。そして、事例や統計データをヒントにしながら、人生設計を立てるように自分の睡眠生活をデザインしていくとよいのではないかと思います。
●吉田のりまき
薬剤師。科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」主宰
[newsdig]
■睡眠時間が短い人の脳は老化が早い:研究結果
TEXT BY SANAE AKIYAMA
睡眠時間が少ない人ほど脳の老化が早まり、認知力が低下しやすくなるという研究結果が発表された。はたして、健康的な人生を送るためにわたしたちは何時間寝るのがいいのだろうか。
社会の高齢化や平均寿命が長くなるにつれて、看過することのできない社会問題がある。加齢にともなう認知力の低下や、パーキンソン病やアルツハイマーなどの神経変性疾患だ。しかし、お年寄りの全員がこれらの病気に悩まされるわけではない。今回デュークNUSシンガポール校が行った研究によると、睡眠時間が少ない人ほど脳の老化が早まり、認知力が低下しやすくなるのだという。
脳の老化が早まるには、もって生まれた遺伝子に加え、おそらくいくつかの環境要因があると思われる。なかでも、ジャーナル誌「Sleep」で発表された研究が注目したのは、「平均的な睡眠時間」と「認知機能」の関連性だ。
デュークNUSシンガポール校では、55歳以上の中国人被験者66人を対象に、睡眠の長さと質について尋ねた。研究者らは、炎症の度合いを調べるための血液検査や、認知力を試す神経心理学的検査を行い、加えて、脳の容積もMRIで測定。睡眠時間が脳にどう影響するかを調べるために、同調査を2年ごとに行った。
「睡眠時間は脳の老化のマーカーとして使えます」と話すのは、研究を率いたジューン・ロー博士だ。
彼らの結果によると、被験者の一部は年齢を重ねたにもかかわらず、神経心理学的検査に練習効果とみられるスコアの上昇があった。しかしほかは、睡眠時間が少なかった人ほど脳室の拡大が早く、認知能力にも低下がみられた。年齢、性別、学歴やBMIを考慮した後も、睡眠時間の影響は統計的に有意なままだったという。また今回の調査では、睡眠時間と炎症反応には関連がみられなかった。
睡眠は、食事や適度な運動と同様に気を配る必要があるということだ。
今回の結果を受け、デュークNUS認知神経科学のディレクターであるマイケル・チー教授は次のように述べている。
「神経心理学的検査の大規模な研究結果をみると、大人には7時間の睡眠が最適であることがわかります。これからは何が心血管の代謝に良いのかを調査し、脳の長期的健康を保つ方法を模索していきたいですね」
[WIRED]
■意外な新事実!最も適切な「黄金の睡眠時間」は●時間と判明
by 相馬佳
あなたは1日に何時間睡眠をとっていますか?「そりゃ、普通は8時間とるべきでしょう」という人もいれば、「忙しすぎて、6時間くらいしか寝る時間がない」という人もいるでしょう。
一般常識的には、昔から「睡眠時間は8時間とったほうがいい」と言われてきました。しかし、研究によると、実は8時間寝る必要はないばかりか、8時間よりもっと適切な睡眠時間が判明したというのです!
アメリカの英字新聞『Wall Street Journal』英語版の記事を参考に、睡眠についての新事実を探ってみましょう。
■黄金の睡眠時間とは?
睡眠についての研究によると、体と健康に一番いい睡眠時間は“7時間”だそうです。一説によると、それよりも20分少なくても、また多すぎても、記憶力や健康状態に悪影響が出てくるとか。
カリフォルニア大学の研究者が、110万人に対し6年間にわたって行った大規模な調査によると、成人の睡眠時間の中で一番死亡率が低かったのは、6.5時間から7.4時間の間だったそうです。それを平均すると、約7時間ということになりますね。
新生児や乳幼児が長い睡眠時間を必要とするのはよく知られた事実ですが、どうやら睡眠時間は、年齢が高くなるにつれて少なくなっていくようです。
同じ研究者がシニア女性に対し、10年間にわたって行った調査では、睡眠時間が5時間以下、または6.5時間以上だった女性の死亡率が、5時間~6.5時間だった女性よりも高かったそうです。
■“寝すぎ”で起こる健康的弊害とは
睡眠不足で起こる疲労や記憶力の低下、肥満の危険性などの健康的弊害はよく知られていますが、驚いたことに、“寝すぎ”の場合も多くの害があるようなのです。
研究によると、成人が睡眠時間を必要以上にとりすぎる生活を続けると、糖尿病や肥満、心臓疾患などにかかりやすくなるとか。しかも、睡眠時間が多すぎる人は、7時間睡眠をとっている人よりも、死亡率が高いそうです!
確かに、睡眠をとりすぎて起きた翌朝は、頭がぼーっとして体もかえって重くなり、体がうまく機能しないこともありますよね。良質な睡眠をとるには、普段から自分の生活習慣に気をつけ、適当な運動と健康的な食生活をし、時間に余裕を持って就寝しなければならないようです。
以上、適切な睡眠時間に関する新事実をお伝えしましたが、いかがでしたか? 統計的な平均で見ると、1日7時間の睡眠がもっとも健康的な生活を送るのに適しているようです。しかし、睡眠時間の必要性は、個人個人の体調や習慣で違う可能性も考えられます。
自分の頭や体が「この睡眠時間ならもっとも活発で健康的に感じる」という数字を知り、就寝や起床時間を調整して、なるべく毎日一定の睡眠時間をとるようにしましょう。
[WooRis]
■夜勤の睡眠時間2~3時間がもたらす影響とは?
現在、夜勤の多い状況下で働く看護師のうち、新人の5割はその年のうちに辞めていくといわれています。また、看護師の入れ替えも多い中で、その心身の健康への影響ははかりしれないものだといいます。看護師の、夜勤の現場の睡眠事情とその影響に迫ります。
夜9時頃まで残業して、深夜0時からまた勤務!
今の看護師さんは、日勤、夜勤とさまざまなシフト体制で働いていることは知られていますが、中でも「日勤―深夜」というシフトがあるのには驚きます。これは、日中普通に働き、夜9時まで残業、そしてその数時間後の深夜0時からまた深夜勤務が始まるというシフトです。
また、夜勤そのものも、月10回を下回るような看護師はそういないともいわれています。こうした状態が続くと、体だけでなく心にも変化が起きてくるといいます。
例えば、睡眠時間2~3時間の日が続いたというある看護師は、夜勤の最中、食事をする暇もない状況に。だんだん人と話すのもおっくうになってしまったのだそうです。しかし、このような激務は決して珍しいことではないようです。
夜勤の短い睡眠時間がもたらす健康リスク
日本医療労働組合連合会による2013年の「看護職員の労働実態調査」によれば、慢性疲労を訴える看護師は7割を超えており、6割の人は健康に不安があると答えているそうです。
このような状態で、睡眠時間が削られることについて、その影響はいかなるものなのかというデータがあります。
短い睡眠の繰り返しが、睡眠中の心拍数にどのように影響するのかを調べた実験によれば、睡眠短縮によって徐波睡眠が増え、それがレム睡眠中の心拍数を増加させていることが判明したのだそうです。
これは、長時間の夜勤による不十分な睡眠は、睡眠中の循環器系機能に負担をかけ、健康リスクが高まることの証明だといえるでしょう。
不眠・睡眠不足による事故リスク
不眠による疲労と作業効率についてのデータもあります。特に不眠状態が続くと、真夜中から明け方にかけての時間帯に、人間の作業能力は極端に落ち、なんと酒気帯び状態での同作業よりも劣るほどだというのです。
夜勤中に無意識の眠りに落ちたという人も多い中、仕事中の事故についてはますます不安の声が高まっています。
そもそも長時間の日勤と夜勤は労働安全上、事故リスクが相対的に高くなることがあります。一回の勤務時間が長ければ長いほどリスクが高まり、さらに日勤よりも夜勤でリスクが高まることもわかっています。
しかし、今の日本では、2交代制勤務、16時間夜勤が大半を占めています。
こうした現状からして、事故リスクははかりしれないといわれています。
[ネムジム]
■免疫力を高める睡眠方法とは? カギは成長ホルモンにあり!
残暑がまだまだ厳しいですが、夏風邪などをひいていませんか? 暑さの厳しい夏を乗り越えるためのキーワードの1つが免疫力です。どうしたら免疫力を高めることができるのか、徹底解明します!
免疫力は睡眠の質が影響していた?
たとえば、あなたが仕事などで大きなストレスを日常的に感じているとします。ストレスは睡眠の質を低下させ、成長ホルモンの分泌量の減少につながってしまうと考えられています。
その結果、免疫力が下がり、風邪をひきやすくなったり、ウイルスに感染しやすくなってしまうのだそうです。この免疫力には睡眠が大きく関わっていることがわかっています。
免疫力を高め、強い身体をつくるためにはどのような睡眠をとればよいのでしょうか?
注目すべきは、「睡眠の質」です。
免疫力を高めるには?
免疫力を高めるためには、睡眠時に成長ホルモンをしっかりと分泌させることがカギを握っています。それでは、どうしたら成長ホルモンがたくさん分泌されるようになるのでしょうか?
これもすでに科学的に解明されていて、成長ホルモンというものは、寝ついて最初の3時間でたくさん分泌されて、それ以降は分泌されにくい物質なのだそうです。この3時間にいかに深く、質の高い睡眠を得られるかが勝負の分かれ目、というわけですね。
そうは言っても、なかなか寝つけない日やぐっすり眠れていない時ってありますよね? そんなときはどうしたらよいのでしょうか。
睡眠の質を高める2つの方法
1つは、就寝1時間前に入浴をして、身体の芯から温めること。ただし、熱すぎるお風呂は交感神経を優位にして身体が起きてしまうので、38~40度の少しぬるめのお風呂に10~20分入るとよいそうです。そうすることで副交感神経が優位になってリラックスできるので、就寝時間までにはちょうど体温が下がって、眠りやすくなります。
もう1つが就寝30分前に首元を温めること。ここを温めると、身体の深部温度が逆に下がるので、就寝しやすくなると考えられています。
この2つを意識して、眠りはじめの3時間を深く、質の高い眠りにして免疫力を高めましょう!
[ネムジム]
■自分の時間をもちたいなら「分割睡眠法」がおすすめ!?
睡眠は、ほとんどの人が一様に夜から朝までまとめて寝ているものですよね。でも、分割睡眠を活用して、効率的に生活している人たちがいるということをご存知でしたか?
誰もが平等に与えられている1日24時間を分割する!?
誰しもが平等に与えられている1日24時間。しかし、時間の使い方は人によって驚くほど違うものです。睡眠のとり方もその1つで、1日に10時間以上寝る人もいれば、たった3時間しか寝ないという人もいますよね。
そんなさまざまな睡眠のとり方がありますが、最近注目を集めている方法に「分割睡眠」というものがあります。みなさんはこの言葉、ご存じでしたか?
これは簡単に説明すれば、まとめて睡眠をとるのではなく、1日2、3回にわけて睡眠をとるという方法。
では、分割睡眠にはどのような効果があるのでしょうか?
環境によっては特殊ではない分割睡眠
そもそも、西欧では大昔から「第1の睡眠」、「第2の睡眠」と呼び、何回かに分けて睡眠をとることが普通だったと言われています。近年では、ナイジェリアのある部族が分割睡眠をとっていたことがわかっています。
また、ニューヨーク・タイムズ紙は、照明のない環境で暮らすと分割睡眠をとる傾向にあるという実験結果も報告しています。つまり、特別なことではなく、環境次第では日常的に起こるものだということですね。
では、照明がどこにでも存在する環境に暮らす私たち日本人が分割睡眠をとるメリットはあるのでしょうか。調べてみたところ、ある書籍によると、仕事や勉強の効率が上がり、さらに好きなことをするための時間がとれるようになるのだそうです。
では、具体的な方法をご紹介しましょう。
分割睡眠で自分の時間を確保できる!?
これはあくまで方法の1つですが、夜10時ごろに就寝し、深夜2時ごろに起床、そこから数時間を「好きなことをするための時間」として活用するというもの。
たとえば、深夜2時から4時までの2時間を読書にあてて、4時から朝まで再度しっかり寝れば、翌日の仕事や勉強に影響はないといいます。もちろん、これは個人差があるものなので、自分に合った分割睡眠を模索することも大事でしょう。
確かに、仕事で疲れた状態のまま本を読んでも、なかなか頭に文章が入ってこないものですよね。一度、寝ることで頭もスッキリして大好きな読書を楽しめるというのは有意義なことかもしれません。
みなさんも一度、試してみてはいかがでしょうか?
[ネムジム]
■寝る前にやったらダメ!「知らずに睡眠の質を下げている」NG習慣3つ
by 望月理恵子
昼間だけでなく、夜も気温が高い日が続いていますね。そうすると、なんだか寝つきが悪いと感じることもあります。扇風機や冷房を使用して対策をしているという人も多いのではないでしょうか。
それでも寝つきが悪いと感じる方、それはもしかしたら気温が高いことだけでなく、寝る前のNG習慣が大きく関わっているのかもしれませんよ。そこで今回は、管理栄養士である筆者が、“睡眠の質を下げてしまうNG習慣”についてご紹介します。
■1:お風呂のお湯は42℃以上はNG
「ダイエットのため」と言って、半身浴をしている方もいるはず。半身浴は血液の流れを良くしますし、汗をかくためデトックス効果もあると言われています。半身浴だけでなく、湯船につかることはなんだかほっとした気持ちになれリラックスもできます。
しかし、その入浴方法で気を付けたいのが温度。高め(42℃以上)の温度のお湯につかると交感神経が刺激を受け、身体が興奮した状態になります。そのことで睡眠が浅くなってしまい、熟睡しにくくなってしまうのです。
■2:夜のコンビニはNG
寝る前に強い光を浴びてしまうと、これもまた交換神経が刺激され寝つきが悪くなってしまいます。
パソコンやテレビ、スマートフォンなどの電子機器を寝る直前に使用すると、私たちを睡眠に導く“睡眠ホルモン”とも呼ばれている、“メラトニン”の分泌を妨げてしまいます。さらに要注意なのが夜のコンビニ。コンビニの照明は一般の家庭で使用されている照明よりも明るいものを使用しているのです。
もちろん、遅くまで営業しているスーパーや雑貨屋さん、電気屋さんも同様です。お店はお客さんの購買意欲を高めるために明るくしていますが、メラトニンの分泌を抑制して、睡眠の質を下げてしまいます。
■3:寝る直前のアルコール摂取はNG
寝ている間にも水分は失われてしまうので、寝る前の水分摂取を避けるのはあまり良いことではありません。
ですが、水分摂取といっても、その時に何を飲むかということにも注意が必要です。基本的には常温の水が理想的です。あまり冷たいものを飲んでしまうと内臓に刺激を与えてしまいます。
また寝酒をするという方もいますが、アルコールが分解されると刺激されるのは交換神経。そのため寝る直前のアルコール摂取も、睡眠の質を下げる原因になります。アルコールを飲む場合は、就寝時間の3時間くらい前には切り上げるようにすると良いですね。
いかがでしたか? 他にもハーブティーを飲んでみること、軽いストレッチを取り入れることなどが、質の良い睡眠に効果的です。ハーブティーの良い香りや温かさには身体をリラックスさせる効果があると言われており、またストレッチも血液の流れを良くしてくれるので、質の良い睡眠をとりやすくなると考えられています。
寝る前の習慣を見直して快適な睡眠を手に入れ、疲れをしっかりと取り除いて次の日を迎えられると良いですね。
[WooRis]
Posted by nob : 2014年08月25日 10:02
また旅立つ君へVol.73/ひとと違う、だからこそ新しい何かが生まれる。。。
ひとと違う、という価値。
[クラレCMコピー]
Posted by nob : 2014年08月24日 11:17
また旅立つ君へVol.72/私も生涯大人げない大人であり続けたい。。。
引用1
どういうわけか日本では、我慢を美徳として考える傾向がある。
そして、強い自制心を持つことが大人の証明になるとされる。
しかし、私の周囲の成功者とされる人に、我慢強い人物は見当たらない。
逆に、やりたいことがまったく我慢できない、子どものような人ばかりだ。
そういう人は、好きでやっているのだから、時間を忘れていくらでもがんばるし、新しいアイデアも出てくる。
我慢をして嫌々ながらやっている人が、こういう人達に勝てるはずがないではないか。
引用2
私のスタイルの説明は単純である。
自分より偉い人や強い人の意見をいったんはすべて否定していくのだ。
もし、こうした人たちが自分と同じ考えを持っていたとしても、おとなしくしているのは気に入らないから、自分の考えを真逆に変えてしまう。偉い人がいうことは全部悪い冗談だ、そんなことあるわけがない、と自らを思い込ませ反対意見に回っていく。
なぜこのようにするのかといえば、権力を持った人の考えは、完璧な独裁者でもない限り、民主主義の論理に沿って部分最適に向うからである。
乱暴に言えば、自らの地位を守るために自然と大衆に迎合していくのだ。
そして、すべての意見を公平に扱おうとすれば必ずどこかで無理がでてくる。
常々、平均から逸脱することが得だと考えている私としては、こうした論理に飲み込まれることは、耐えられないのである。
[いずれも『大人げない大人になれ!』成毛眞]
Posted by nob : 2014年08月22日 18:20
また旅立つ君へVol.71/受け入れるだけの「学び」は、もういらない。。。Vol.2
学ぶことの最大の障害は答えを教えることではないか?
それは、自分で答えを見つける機会を永久に奪ってしまうからである。
自分で論理的に考えて、答えを見つけ出すのが、人が学ぶための唯一の方法だと私は信じている。
[エリヤフ・ゴールドラット]
Posted by nob : 2014年08月22日 18:07
今後の実用化に期待。。。
■がん:採血で診断、開発へ 来年度、乳がんで先行実施
国立がん研究センターなどは18日、乳がんなど13種類のがんを1回の採血で発見できる診断システム開発に着手したと発表した。血液中の物質「マイクロRNA」が、がんになると量が増減することに着目した方法で、身体的、経済的な負担の少ない新たな早期がん発見方法として確立を目指す。このうち解析データが多い乳がんの検査は、来年度にも東京都内の検診機関と提携して先行実施を目指す。
血液などに含まれるマイクロRNAは2578種あり、特定のがんの「腫瘍マーカー」(がんの進行具合を示す指標)になることが分かっている。だが、がんの有無や部位発見には分析が不十分だった。同センターや東レなどの開発チームは、同センターが保有するがん患者約6万5000人分の血液データを解析する。がんの種類ごとにマイクロRNAの種類とその量のパターンを調べ、どの部位のがんにどのマイクロRNAが多いのかなどを探り、がんの有無と部位の特定を目指す。
従来の腫瘍マーカーは、がんの早期から高い数値を示すケースは少なく、腫瘍がある程度、大きくならないと検出できなかった。
がん検査を巡っては、乳がんはマンモグラフィー(乳房X線検査)、肺がんや胃がんはX線検査などと、各がんに対応する検査があり、大型検査装置が必要なことが多い。また、初期のがんを見落としたり、良性腫瘍を悪性と判断したりすることもある。今回の検査が実現すれば、初期に陽性と判明する割合がわずか2%程度とされる乳がんで、早期発見率が大幅に上昇することが見込まれている。
来年度の先行実施を目指す乳がん検査は、がんと分かっていない人が希望すれば受けられるようにする予定。受診料は未定だが、従来の装置による検査より大幅に低くなる見込みだ。
また、診断システムを認知症の診断にも応用する研究を進める。【鈴木敦子】
[毎日新聞]
Posted by nob : 2014年08月22日 17:54
何物も諸刃の剣、、、何事にもバランスが肝要。。。
■悪影響ばかりじゃない!知っておきたい紫外線の「プラスのパワー」
カズ シュライバー
紫外線の強い季節になりました。みなさん、日焼け止めを塗る、帽子をかぶるなど、紫外線対策はしていますか?
確かに浴びすぎると、シミやシワ、肌の老化、ひどい場合には皮膚がんになる可能性もあるわけですから、避けたくなるのは当然です。でも、紫外線には、私たちにとってプラスになる面もあることをご存じですか?
そこで今回は、英語圏の情報サイト『OPRAH』『BenefitOf.net』を参考に、知られざる“紫外線のパワー”をご紹介しますね。
■1日にどれくらいなら日に当たってもいいの?
いくら、体に良いことがあるとはいえ、あまり長く日に当たってしまうと、日焼けやシミ、そばかすが増えてしまいます。1日に15〜20分程度が目安です。日焼け止めは、SPF30以上のものをお使いくださいね。
ちなみに、日焼け止めを毎日つけている人は、時々つける人と比べると、なんと24%もシワ、シミが少ないそうです!
■血圧を下げる
紫外線と血圧……一見、何の関係もないように見えますが、2014年の調査によると、1日20分ほど日の光に当たるだけで、なんと血圧が下がるということが分かってきています。日の光が肌に当たると、一酸化窒素が生産されて、血管をリラックスさせ、血液の流れを良くするからだそうです。
■乳ガンのリスクを下げる
6,000人の女性を対象にして、日に当たった組と、当たらなかった組とを分けて行った実験では、当たった組の方が、はるかに乳がんのリスクが低かったことが分かりました。これはどうやら、日に当たることで、ビタミンDが大量に生産されたからだという見解が一般的です。
何と、ビタミンDは特定の乳がんのリスクを下げることが分かっているといいます。
■認知症やうつ予防にも
最近の調査によると、45歳以上の人で、日常的に日の光を浴びている人と、そうでない人とでは、将来認知症になるリスクに差が出るということがわかっているそうです。
日の光を浴びると、ビタミンDが生産され、体内時計が正しく働きます。さらに、日の光は記憶に関係するセロトニンを生産して、脳の海馬で記憶細胞が作られるのを助けるそうですよ。
セロトニンが減ってしまうと、うつ状態につながるようですから、やはり日の光に当たることは、大切なんですね。
■関節炎予防にも
ハーバード大学の調査によると、日常的に紫外線に当たっている人は、そうでない人と比べて、将来関節炎になるリスクが、約21%も低いということが分かりました。どうやら、これも日の光に当たることによってビタミンDが作られることと関係があるようです。
ビタミンDは、体の免疫機能を向上させるので、関節炎の予防になるそうですよ。
いかがでしたか? この他にも、日の光は体内時計を整え、新陳代謝を上げるので、ダイエット効果があることも分かっています。ただ、何事もいいことばかりではありません。やはり、日の光に当たりすぎると、いろいろな弊害も起こりますから、ほどほどを心がけてくださいね。
[WooRis]
Posted by nob : 2014年08月22日 17:46
また旅立つ君へVol.70/受け入れるだけの「学び」は、もういらない。。。
学ぶことを止めたとき
人は初めて考え始める
そして創造することへ移行していく
Posted by nob : 2014年08月22日 17:34
また旅立つ君へVol.69/表現の道に生きていく覚悟、、、
それは
迷いと悩みと苦しみを享受し続けていくこと。。。
Posted by nob : 2014年08月21日 23:51
また旅立つ君へVol.68/迷い悩みもがき続けるからこそ。。。
いつも探し求め続けていればこそ
然るべき人にもモノにも出逢える
Posted by nob : 2014年08月17日 16:48
また旅立つ君へVol.67/後悔先に立たず、、、自らの納得こそがすべて。。。
■歳を取ってから気付いた、人生で失敗した24のコト
人生は短い。この書物を読めば、あの書物は読めないのである。
by ジョンラスキン イギリスの思想家
後でやればいい?歳を取ってからでは、遅くなってしまうことが余りにも多い・・・人生の先輩が歳を取ってから気付いた、「人生で失敗したこと」を紹介しよう。「今」やるべき事がたくさんある。「今」しか出来ないことがたくさんある。
さあ、これを読んだらあなたは動き出さずにいられない。
1.余裕があるときに旅行しなかったコト
時間と体力がある若いときの方が、自由に旅行が出来る。そして何より、若い時の方が、新しいモノをみた時の感動が大きい。沢山の世界に触れよう。
2.嫌いな仕事を辞めなかったコト
「嫌な仕事でもとりあえず3年続けなさい」という言葉があるが、3年後社会がどのようになっているかなど誰にも分からない。そう考えると、「今」を我慢に費やすのはもったいない。
3.自分の夢を諦めたコト
やらなかったことを後悔するより、やって後悔する方が何倍も良い。やって失敗したことは、後に笑い話になるが、やらないで後悔したことは、ネタにすらならない・・・
4.先延ばしばかりしたコト
明日から頑張ろうではなく、「今日だけ頑張ろう」という発想をいつも持つこと。
5.学校できちんと勉強しなかったコト
勉強する苦しみは一瞬、勉強しなかった後悔は一生残る。今日のヨダレは、将来の涙・・・
6.家族とあまり時間を過ごさなかったコト
家族と過ごす時間はこの世のいかなる成功よりも大切なもの。どんなに忙しくても、 家族との時間を作ろう。
7.人を恨んでしまったコト
人を恨むことは自分自身を苦しめる。誰にでも1つくらい良いところがある。恨む前にまずそれを探そう。
8.働きすぎたコト
人生は楽しい事がたくさんある。仕事だけにあなたの時間を費やすのはもったいない。まわりを見渡そう。大切なモノがたくさんある筈。
9.学べる時に学ぼうとしなかったコト
学びたくても学べない人はたくさんいる。学べる環境にいるだけでもあなたは恵まれているのだ。その事を心に留めておこう。
10.冒険しなかったコト
人生は冒険だ。常にチャレンジし続けよう。やるかやらないかを迷ったら、進もう。アイデアに価値はない、実行することに価値はあるのだ。
11.ジェンダーロール(例:女性らしくとか男性らしくとか)に縛り付けられてしまったコト
女性らしさや男性らしさはいらない。必要なのは「あなたらしさ」。
12.親のアドバイスを聞かなかったコト
親はあなたよりも長く生きている。その分社会にも詳しい。最も身近な社会の先輩であり、あなたの一番の理解者でもある親は、最高のアドバイザーだ。
13.悪い恋人から離れなかったコト
出会える人数は限られている・・・あなたを苦しめる恋愛からは早く卒業しよう。相手のことを考えると心がワクワクするような恋愛をしよう。
14.料理の腕を上達させようとしなかったコト
人間にとって「食べる」という行為は非常に大切。故に料理は人間が身につけておかなくてはならない生きる術なのだ。
15.周囲の目ばかり気にしていたコト
周囲の目を気にしてしまうのは当たり前の事。しかし、あなたが思っているほど人はあなたの事を気にしていない。
16.社会的、文化的規範を気にして我慢してしまったコト
ルールを気にしてばかりの人生はつまらない。自分で新しいルールを作ろうとする位が丁度いい。
17.1度始めた事を最後までやり切らなかったコト
1度始めたことを最後までやり切るのは容易ではない。しかし、やり切った後の達成感を若い時に味わっておこう。それから先の物事への取り組み方が変わるはずだ。
18.様々なことについて心配しすぎたコト
悩み、考える事は生きる上で必要な事。しかし、過度の心配は食欲不振や睡眠障害など、健康に悪影響を及ぼす恐れがあるので注意しよう。
19.運動をさぼっていたコト・・・
気がついたら、元気のないカラダになってしまっていた・・・
20.強い嫉妬心を持ってしまったコト
嫉妬している時は自分のことばかり考えている時。嫉妬のし過ぎを防ぐためには、1度相手の立場に立って考えると良い。
21.人脈を広げようとしなかったコト
広い人間関係を築くことは、視野が広がるとともに、自分にチャンスを呼び込む事にも繋がる。
22.親友を傷つけてしまったコト
親密な相手との喧嘩は堪え難いもの。時間が経つにつれて関係を修復するのは難しくなるので、時間をあけずに謝罪する事をおススメする。
23.新しいことを学ばなかったコト
人生は一生が学習。つねに学ぶこと忘れないで。
24.感謝しなかったコト
「ありがとう」をたくさん言おう。その言葉で皆を幸せな気持ちになる。
人生はあなたが思っているよりも短い。だからこそ、今を精一杯生きようではないか。
■最高の人生を送るために「捨てる」べき15のコト
幸せになるためには、不要なことがいくつかある
幸せのかたちは人それぞれ。絶対の法則なんてない。しかし、最低限「幸福を求めるなら、これは要らないよね」ということはある。
ここに挙げたリストは、今欧米で多くの人が共感している「人生で捨てるべきこと15」だ。
1、「間違った人」との時間
人生は短い。あなたを不幸にする人と過ごしている暇はない。真の友人とは、最高の状態の時に一緒にいてくれる人ではなく、最悪の時に一緒にいてくれる人だ。そういう人と一緒に過ごそう!
2、困難から逃げること
何か問題があれば真正面から向かい合おう! もちろん簡単じゃない。誰もが、悲しみ、傷つき、挫折をする。しかし、学習し、適応し、解決することもできる。プロセスを通して、人間は進化してきた。
3、自分への嘘
世界中に嘘をつくことができたとしても、自分自身に嘘をつくことはできないはずだ。人生においては、与えられたチャンスをものにすることが大切だ。そのためには、常に自分に正直でいる必要がある。
4、願望を後回しにすること
他人を助けることは大事ですが、なによりもあなた自身が救われなければ意味がありません。追求したい夢や情熱、関心事があるなら、誰かを気遣ったり、誰かの目を気にする必要はない。今すぐに実行しよう!
5、自分ではない誰かになろうとすること
多くの場合、周囲はあなたが「みんなと同じ」人になることを求める。しかし、本当は同じ人なんて誰一人としていない。誰かの方が誰かより可愛く、誰かは誰かよりカッコいいし、誰かは誰かより若い。そんなことを気にして、周りの人から好かれるために変わるのは間違っている。自分自身でいることで、本当にふさわしい人があなたを愛してくれるようになる。
6、過去にしがみつくこと
過去にしがみついている間は、何も新しい事は起きない。それは本の同じところを何度も読んでいるようなもの、同じ映画のシーンを何度も観るようなもの。いつまで経っても次へは進めない。
7、失敗を恐れること
何かに挑戦して、失敗するのは恐ろしいかもしれない。しかし、何もしないことはもっと恐ろしい。すべての成功は、積み重ねてきた失敗の上にある。失敗したことよりも、何もしなかったことの方が最終的には後悔する。
8、自分を責めること
失敗をする事は誰にでもある。しかし、失敗したことで、自分にとって何が正しく、自分にとって正しい人とは誰なのかを知ることができる。失敗して、後悔することだってあるだろう。しかし、それは過去のこと。現在のあなたは、未来を変える力を持っている。だから、失敗した自分を責める必要はない。
9、幸せを買おうとすること
幸せのために、人生のために、本当に必要なのはお金ではない。愛、笑顔、そして情熱を持って働くことだ。
10、他人に依存すること
自分自身に満足していなければ、誰かと幸せになることはできない。誰かを求める前に、まずは自分自身が精神的に安定する必要ことが大切だ。
11、立ち止まること
立ち止まって考えるのは悪くない。しかし、考えすぎてはいけない。考えすぎると、そもそもなかったはずの問題を自分自身で作り上げてしまう。それよりも、状況を判断して、行動を起こすべきだ。一塁ベースに足を置いたままでは、いつまでも二塁ベースに進めない。
12、無理だ、と思うこと
チャンスが訪れた時に、100%完璧な準備ができている人はいない。だから千載一遇のチャンスが来れば、それが難しくてもチャレンジをするべきだ。無理だ、なんて考える必要はない。
13、間違った男女関係
男女関係は慎重に選ぶべきだ。間違った相手といるくらいなら、一人でいるほうがマシ。急ぐ必要なんてない。運命の人とはふさわしいタイミングで出会う。寂しいからではなく、あなたがふさわしいと思う人と恋をしよう!
14、新しい恋を拒むこと
人生で出会う人すべてには、出会う理由がある。あなたを試す人もいれば、あなたを利用する人もいるし、あなたに教訓を残してくれる人もいる。たとえ以前の恋愛が悪かったとしても、新しい恋愛は違うかもしれない。最も大切なのは、あなたの最高の部分を引き出してくれる人だ。
15、他人と競うこと
あなたより優秀な人を気にしてはいけない。自分自身と向き合い、自分をアップデートしていけば何も問題はない。幸せを掴むための戦いは、あなたとあなた自身によるものでしかないのだ。
これはマルクとエンジェルという男女のライターが書いている「人生を楽に生きるコツ」というブログから厳選されたものだ。
恋愛や仕事に具体的に当てはめてみると「なるほど!」と思えるはずだ。
Never Stop Exploring… 人生を最高に旅しよう
[いずれもT A B I L A B O]
Posted by nob : 2014年08月15日 17:25
また旅立つ君へVol.66/本当の自分自身に出逢うために君は旅に出る。。。
■「すべての旅人が共感!」一人旅があなたを成長させてくれる15の理由
インターネットの発達による情報収集が容易になり、LCCが登場した現代。一昔前よりも、世界を旅することのハードルは低くなった。しかし、やはり異国の地に足を踏み入れる事は、とても勇気がいる。一人旅なら尚更だ。 今回は全ての旅好きに捧ぐ、一人旅が素晴らしい15の理由を紹介しよう!
01. すべて自分で決めることができる
命令される関係でなくても、一緒にいれば他の人に影響されてしまう部分がある。それが家族や友人やパートナーであっても、だ。しかし、一人ならすべては自分次第となる。何をし、何をを食べ、どこへ行くか。誰にも気遣う必要はないのだ。
02. 新しい文化を学ぶチャンスが多い
文化は人がつくるもの。ゆえに、全く違う文化でも順応は可能だ。食べ物や住居、ライフスタイル全般。一人だからこそ自分のペースで新しい文化に触れることができる。
03. 新しい友達ができる
一人での旅は孤独だ。しかし、これは逆にチャンスでもある。一人だからこそ出会いも多い。思いがけもしないところで、まったく違った価値観の人や旅人と友達になるかもしれないのだ。
04. とにかく自由!
一人で旅をしている最大の魅力と言えるだろう。自分の気が向いたところに行き、好きなだけ時間をかけ、誰かに気を使うこともない・・・。本当に生きていると実感できるはずだ。
05. 自分の本当の気持ちを知ることができる
普段は思っていても、人に流されたり世間体を気にして自分に正直になれないときがあるかもしれない。しかし、一人で旅をしていると、自分への問いかけができる。
06. 裸の自分になれる
一人旅で接する人は、誰もあなたのことなど知らない。ある意味、あなたは裸だ。
07. メイクをする必要はない
これは女性限定かもしれない。異国の地では(特定の場所を除いて)メイクをしたり、着飾る必要はない。メイクに割く時間は、別のことにあてられる。多くの発見や出会いがあるはずだ。
08. 1人の時間を有効に使える
興味のあることや自分の趣味にいくら時間を使っても構わない。他人から見れば、無駄な時間も、あなたにとっては有効なこともある。
09. 「経験」ができる
経験や思い出を他の人と共有することは、話す側も聞く側も楽しい。しかし、やはり実際に行って感じた経験と記憶そのものには適わない。それは何物にも代え難い貴重な財産だ。
10. 自分を信じられる
いつも人からのアドバイスに頼ってないだろうか?繰り返しになるが、一人旅で頼れるのは自分しかいない。自分を信じて道を切り開いていくしかない。その過程で、「自分を信じる力」がついていく。
11. 孤独に打ち勝てるように!
すべてのことを自分一人でこなしていくと、一人でいることに慣れ、孤独に打ち勝つことができる。それは日常では意外と鍛えることができないものだ。
12. 忍耐強さが手に入る
一人旅ではハプニングがつきものだ。しかもそれは避けることはできない。ゆえに、我慢強さや忍耐力が身に付く。
13. 恋人や家族との絆が深まる
愛する人や家族としばしの時間会えないというのは辛いものだ。しかし、この愛する人を募う想いが、それぞれの距離をさらに縮め、強い絆を生む事ができる・
14. 感謝の気持ちを持てる
偶然は必然。一人旅をしていれば、必ず、あなたを助けてくれる人や素晴らしい機会に巡り合うことがある。そういったすべての出来事に感謝するだろう。
15. フィジカルへの意識が高まる
一人旅では、変化する環境に合わせ、より一層に健康に気を使うようになるはずだ。
さあ、一人旅の準備はできましたか?
思い立ったら、最初の一歩を踏み出そう!
旅ラボ海外ライター Michael Anthony Yoshioka
生まれも育ちもほぼニッポン。外人感全くゼロのハーフがコンプレックス。
東京の高校卒業後すぐにカリフォルニアへ留学し現在3年目。社会学を専攻。暖かい気候と陽気な天気のもとサーフィンとウクレレにどっぷりはまり、おかげでさらに自由人に。将来の夢は”世界を旅しながら運営する旅カフェ”を作る。
[T A B I L A B O]
Posted by nob : 2014年08月15日 17:11
できてしまえば驚くほど簡単なほんの些細な思考と言動の積み重ね。。。
■本当に幸せになるためにやめなければいけない8つのこと(と、その代わりにすべきこと)【LHベストヒッツ】
Dumb Little Man:幸せになるためにやめるべき8つのことと、その代わりにすべきことを紹介します。
行動を変えるには努力が必要になります。ただ、真剣に取り組めさえすればこれまでの自分から抜け出して幸せになれるでしょう。取り組む準備はいいですか?
1.マイナスのオーラを放つ人に気持ちを削がれないようにしよう
人は周りに影響を受けがちです。そんな中、ネガティブなことばかり言う人といつも行動するとどうなるでしょう? 両親、兄弟姉妹、親友、配偶者や同僚...。彼らはいい人たちかもしれませんが、あなたに否定的な態度を取っているのかもしれません。
そんなときには逆にポジティブな態度を取るようにしましょう。あなたが肯定的に振る舞うと、どんなにネガティブな人でもあなたには明るく接したり、あなたがそばにいるときだけは良い雰囲気を保ったりするようになるでしょう。
2.自分の決断を批判しない
どのチーズを買うかといった些細なことからキャリアチェンジなどの重大事項に至るまで、選択を行う瞬間は自分の内なる声が聞こえてきます。
「この選択は間違っているかも」
こんな悪魔のささやきからどうすれば逃れられるのでしょう?
これが最後の決断かもしれないなどと臆するのではなく、すべては人生学習であると考えましょう。どんなチーズでもいいから買ってみましょう。おいしくないなら次からは違うチーズを選べばいいのです。今の仕事を辞めて新しいことを始めてみてもいいでしょう。うまくいかなかったときに金銭的には苦しくなるかもしれませんが、自信がつき経験が増えます。失敗もあるでしょうが、すべての決断を学習の機会とみなすことで、そこから学びを得て自己成長できるでしょう。決断したあとで自分を批判する必要はありません。
3.自分には価値がないなどと思わない
いいチャンスが舞い降りてきても、自分はそれに値しないと思うことがあるでしょう。「あんなに美しい人が、自分なんかに振り向くはずがない」などと。ときに自分の人生をとても辛く感じ「なぜ自分だけがこんな目に...」と思うこともあるでしょう。自分が感じていることが正しいと信じていると、平穏で楽しい日々を送れるはずがありません。そんな時は自分のことであっても、そうではないかのように考えましょう。
4.起きたことにとらわれない
両親、教師、友達、元カレ/元カノなどに嫌な思いをさせられましたか? あまりにも気持ちが滅入って、客観的に物事を考えられる心的状態にないときは、その人たちを許すことも忘れることもできないでしょう。それゆえに幸せも感じられないはずです。
すぐにその人たちを許せなくても、忘れられなくても構いません。前に進むことだけを考えましょう。いつか許せるときが来るでしょう。まずは、起きたことにとらわれず今日を良い日にすることだけを考えてください。いつの日か、過去はそんなに大事ではないこと、許したり忘れたりすることが簡単にできること、あるいはそのようにする必要がないことがわかります。
5.起きてもいないことを心配しない
あなたは、将来に不安を抱いていませんか? 準備や計画をしているとき、起きもしていないことを心配して精神的に弱くなっていることがあるでしょう。
将来のことをあれこれ考えて不安に駆られるのは避けましょう。毎日数分、悪いことが起きたときのことを考えて、どう対処するかに考える時間を取っておけばいいのです。他の時間では、心配事は「あとで解決できること」として心の脇に置いておきましょう。日記などに「後で取り組むこと」として書き留めるのもいいでしょう。
6.自分の幸せを後回しにしない
今やらなければならないことがありすぎて、休む暇もないという状態が続いたらどうでしょう。ToDoリストにたくさんやるべきことがあると、自分の時間や身体を回復させる時間を確保できなくなります。
スケジュール帳に休みやリラックスタイムを書き込んでおきましょう。忙しく働いている人なら、毎年同じ時期に休暇を取って、どんなことがあっても子どもと釣り(でなくてもいいですが)に出かける予定を立てましょう。最初は上司や同僚からひんしゅくを買うかもしれませんが、毎年恒例として行っていると、彼らはスケジュールを調整してくれるでしょう。
7.他人を傷つけることを恐れない
「本気で世界を変えたい」「人と違うことをしたい」と考えていて、友人や家族がどう反応するかわからないとき。もしかしたら、批判されるかもしませんし、誰かのことを傷つけることになるかもしれません。
そんなときは「絶対傷つけないようにする人」を1人決め、ほかの人のことは忘れましょう。親でもいいし、配偶者、自分の子どもやあなたの価値観に合った想像上の人物でも構いません。
一度にすべての人の期待に応えることはできません。先に決めた人を傷つけさえしなければ、まずはほかの人のことを気にしないでください。これであなたは正しい道を歩めるし、周りもあなたのことを尊重してくれるでしょう。
8.できもしないことを約束しない
責任感を持たずに「やります」と約束して、それを守れないこともあるでしょう。勢いだけで返事をすると、うしろめたさや不安を感じることになります。頼んだ人の気を害せず、かつあなたが時間と労力をかけすぎないためにはどうすればよいでしょう?
そんなときは「なるほど、一度考えてみましょう」と答えてみてください。こんな簡単な返答で、相手はあなたの思いやりを感じるでしょうし、よく考えて後で回答するという約束は簡単に守れます。回答を考えるとき、あなたが時間をさけるなら「やります」と答えられます。できないときは相手を傷つけることなく「できない」と伝えるときを模索しましょう。
さて、いよいよ行動を起こすときです。筆者が示した8つのことは「初めの一歩」です。このリストに追加できることは他にもたくさんあるでしょう。
幸せのためにやめるべき行動は何ですか? そしてその代わりに何をしますか?
8 Things You Should Stop Doing To Yourself to Really Be Happy (And What to Do Instead) | Dumb Little Man
Sumitha Bhandarkar(訳:駒場咲)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2014年08月15日 17:05
(眼が)疲れた時、人指し・中・薬指の腹を揃えて、ほんの10秒そっと目を閉じた瞼の上に置いてみる/自らの身体は些細な刺激に鋭敏に応えてくれるのがよくわかります
■むくみ・角栓を撃退!小顔と美肌を手に入れる魔法のオイルマッサージ
肌にも髪にもボディにも、オイル美容ブームは止まらない!
けれど、オイルについての正しい知識を知らないと、ベタつきがちな夏は「さらにベタつきそう……」なオイルを避けてしまう人も。
でも実は夏こそオイルの出番なんです! 紫外線やエアコンでゴワついたお肌をふっくらやわらかくしてくれたり、使い続けることでつるんとなめらかにしてくれたり……。
オイルを使ってゴワつく夏の肌を柔らかくするマッサージ法を『AneCan』9月号よりご紹介します♪
AneCan2014年9月号P213

【1】まずはオイルをあたためます。
マッサージをするときは、オイルは500円玉大くらいをたっぷりと使いましょう。てのひらにオイルを取って、両てのひらを合わせてオイルをあたためます。あたためると、オイルの成分が肌に浸透しやすくなります!
【2】マッサージの鉄則は下から上へ!
【1】であたためたオイルをてのひら全体にのばし、顔全体になじませていきます。人差し指、中指、薬指の3本の指の腹を使って、あご、頬、目の周り、おでこの順に、下から上に軽く持ちあげるようにマッサージ。オイルには肌をやわらかくする効果があるので、まずは全体をマッサージして固くなった肌をゆるめましょう。
【3】小鼻とあごのザラつきをオフ。
小鼻やあごなど、皮脂が詰まりやすい部分は、指の先を使ってくるくると円を描くように小刻みに動かしてマッサージしましょう。オイルを使って毎日マッサージすることで、ニキビや毛穴の黒ずみの原因となる角栓が出やすくなります。
【4】ツボを押してむくみを撃退!
目頭の眉下あたりとこめかみは指の腹を使ってじんわりプッシュ。頬骨の下あたりのくぼんだところは、人差し指の第2関節でコリをほぐすようにやや強めに押しましょう。
ツボを刺激すると、リンパの流れがよくなって、たまった老廃物や滞っていた血流がスムーズに流れます。さらに皮膚の温度も上がり、顔色もよくなるといいことずくめ!
【5】老廃物をリンパに流す。
最後に老廃物を流します。小指の側面を使って、耳の後ろあたりから首筋を通り、鎖骨のくぼみ部分にある老廃物の出口に向かって、やや強めに押し流しましょう。リンパの流れを良くすることで、顔のむくみが取れるのはもちろん、フェイスラインがすっきり見えて小顔に!
【6】仕上げ
マッサージ後は、顔に吸収しきれない余分なオイルが顔に浮いているような感覚に。余分なオイルを残しておくとメイクくずれの原因になるので、化粧水をひたしたコットンでふきとります。ちなみに、夜はオイルマッサージ後に蒸しタオルを30秒のせると、オイルがより浸透してやわらかい肌に。
この後にメイクをすると、メイクのりは抜群!
オイルマッサージをするとすぐに肌の違いを感じるかと思いますが、継続するとさらにつるんともっちりやわらかに。美肌&小顔を目指している方は、是非この魔法のマッサージを継続してみてくださいね♪(後藤香織)
[Woman Insight]
Posted by nob : 2014年08月15日 16:54
また旅立つ君へVol.65/それでも私は真実が知りたい。。。Vol.3
現実離れして映るのは、、、
ありのままの現実を捉えているから。。。
Posted by nob : 2014年08月12日 18:16
また旅立つ君へVol.64/それでも私は真実が知りたい。。。Vol.2
自ずと伝えられ
簡単に理解できる答えなど
それらは伝えてくる相手にとっての都合ばかり
まったくたいしたものではない
真実とは
自ら迷い悩みもがいて
そしてさらに運にも恵まれて
ようやく手にすることができるもの
Posted by nob : 2014年08月12日 09:41
また旅立つ君へVol.63/それでも私は真実が知りたい。。。
everything happens for reasons...
すべてに理由があるのだから
どんな疑問にも必ず答えはある
私は
だからこそすべてを知ったうえで
いつも自らの進むべき道を決めていきたい
Posted by nob : 2014年08月09日 10:09
また旅立つ君へVol.62/本物は希有。。。
腐ったものばかりに囲まれていると
本当のものがあっても気付かなくなってしまう
[「普通の女の子」として存在したくないあなたへ/村上龍]
Posted by nob : 2014年08月09日 10:02
また旅立つ君へVol.61/想像力とは、、、希望を見いだす力。。。
知識や技術の集積
日々の努力
そうした誰でもできることは当然のこととして
大切なのは
そこから未知への一歩を踏み出すプラスαの力
Posted by nob : 2014年08月09日 09:50
最も美しい景色、、、それはあなたと見る何気ない日々の景色。。。
君は空を見てるか
風の音を聞いてるか
もう二度とこゝへは戻れない
でもそれを哀しいとは
決して思わないで
いちばん大切なことは
特別なことではなく
ありふれた日々のなかで君を
今の気持ちのままでみつめていること
忘れないで
どんな時も
きっとそばにいるから
そのために僕らはこの場所で
同じ風に吹かれて
同じ時を生きてるんだ
[たしかなこと/小田和正]
Posted by nob : 2014年08月09日 09:30
また旅立つ君へVol.60/根拠のない自信が、、、Vol.2
「依存」は
この世の中の最大の悪である
他人やモノや薬物や酒に依存することは
それだけで人生を放棄することなのだ
主体性は
人間全員にペタッと最初から貼り付いてあるものではない
何かの瞬間に私たちに発生するのだ
主体性が発生するためには
まず依存をなくすことが第一の条件となる
[「普通の女の子」として存在したくないあなたへ/村上龍]
Posted by nob : 2014年08月08日 21:02
また旅立つ君へVol.59/根拠のない自信が、、、
あらゆる葛藤の根源であり
様々尽きない迷いや悩みを生み出し続ける。。。
それが
創造者や開拓者としての逃れえぬ宿命であり
そして戦い続けうる腹心の武器でもある。。。
Posted by nob : 2014年08月08日 20:35
また旅立つ君へVol.58/説教をする人も説教そのものも決して信じてはいけない。。。Vol.2
依存しないで「生きのびていく」のはとても難しい
この国のすべての人々は
システムというか共同体の奴隷となって
「生きのびていく」などという言葉とはまったく無関係に年をとり死んでしまう
説教が大好きなのはそういう人々である
[「普通の女の子」として存在したくないあなたへ/村上龍]
Posted by nob : 2014年08月08日 18:28
また旅立つ君へVol.57/説教をする人も説教そのものも決して信じてはいけない。。。
今この国に
生きのびる指針となるような価値観を持っている年上の人間なんかどこにもいない
どう生きればいいかわかってる人なんか誰もいない
[「普通の女の子」として存在したくないあなたへ/村上龍]
Posted by nob : 2014年08月08日 18:22
ストレスとは付かず離れず仲良く付き合っていきましょう♪
■手遅れになる前に。今日からできる簡単な7つのストレス撃退法
ストレスというのは、誰もが抱えているものですが、放っておくと大変なことになります。ストレスに参ってしまう人もいれば、ストレス源をシャットアウトする人もいます。逆に、やる気を出したり、より向上するために、ストレスを利用する人もいます。ただ、ストレスは正しく管理をしないと、すぐに忍び寄り襲いかかってくるのです。
とは言え、ストレスは早いうちに解消するのが一番なので、今回は簡単な7つのストレス撃退法をご紹介しましょう。
1. 客観的に全体を見る
締め切りが近付くと、段々焦ってきて嫌な気分になるかもしれませんが、それは奥さんや子どものせいでもなければ、おそらく同僚や上司のせいでもありません。何か良くないことがあった時に、他人を責めたり、身近な人に八つ当たりするのはやめましょう。自分の人生においてもっとも大事なことを思い出すのがとても重要です。時には、ストレスが溜まり過ぎて、感情が爆発することもあるかもしれませんが、そんなことをしたら、もっと面倒なことになって、さらにストレスになるだけです。何事も常に適切に扱おうと努力すれば、日々ストレスレベルが下がっていくはずです。
2. 運動をする
動くことで、体や脳が健康になります。ストレスを感じたら、職場を離れ、外に出て少し休憩したり、歩いたりしましょう。このちょっとした息抜きで、心身共にリフレッシュでき、ストレスをすぐに解消できます。それに、体を動かして脳内でエンドルフィンが放出されると、気分が良くなり落ち着きます。
3. 体に良いものを食べる
シュガークラッシュと呼ばれる低血糖は本当に起こります。砂糖はほとんどの加工食品に入り込んでいるので、食べるものにはかなり気をつけた方がいいです。まずは、卵や野菜たっぷりの健康的な朝ご飯を食べるところから始めましょう。それから、どんなに忙しくてもお昼休憩はきちんと取り、ランチを食べること。体と脳が健康的な食事で満たされると、ストレスが溜まりにくくなります。
4. 仕事の進捗を把握する
どれくらい仕事が終わったのかを書き出すようにします。仕事の進捗を見ながら、いつ頃までに終わりそうなのかを確認しましょう。このように進捗を追うことで、実際に今どの程度仕事が終わっているのかが分かり、仕事がどれくらい終わっているのか分からない不安から、精神的に参ってしまうことがなくなり、現実的な計画を立てられます。
5. 常に整理しておく
どんなものでも散らかった状態というのは、脳にとってストレスです。仕事も、環境も、行動も、自分がいちばん心地良く感じる状態に管理しておきましょう。散らかった部屋にいると、脳は目の前の仕事に集中することができません。整理整頓されている環境にいれば、意識はしていなくても心地良く感じられるものです。部屋の中でも、仕事でも、スケジュールでも、整理されていなくて落ち着かないと感じたら、10分でいいので、整理するための時間を使ってみましょう。
6. いつもポジティブでいる
ネガティブな考えに捕らわれていると、やらなければならないことが終わりません。時間通りに終わる、終わらせることができると自分に言い聞かせ、頭を整理して、健全でいるように心がけましょう。目標を決めたら、紙に書き出し、自分に責任を課してください。
7. 楽しむ時間をつくる
昔から「よく働き、よく遊べ」と言われていますが、仕事ばかりして、遊びの時間がなくなると、すぐにストレスが溜まり、燃え尽きてしまいます。いつも幸せを感じられるようにし、その幸せを周りにも広めましょう。仕事仲間や同僚と、誰もが参加できる楽しい課外活動を計画し、仕事抜きで会社以外の場所で遊びましょう。
7 Simple Steps to Banish Stress From Your Life Forever|Inc.
Peter Economy(訳:的野裕子)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2014年08月08日 15:02
私はご飯[雑穀白米・(発酵)玄米]でしっかり朝食派です、、、自ずと身体が不要なものを欲しなくなりました。。。
■お肌は内臓の鏡
あなたは朝食を食べる派、それとも食べない派?
ビューティーアドバイザー
平井里枝
あなたは朝食を食べる派、それとも食べない派?
「朝は何も食べない」「スムージーだけ」、「太るから炭水化物を摂らない」、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?上記に関する本もたくさん出版されていますね。皆さんご存知だと思いますが、朝起き抜けの体温は日中よりも低いのです。
ですから、どんなにミネラルやビタミン類が豊富に含まれ栄養価に富んだ野菜や果物、スムージも、生の物は体を冷やす作用がありますので、朝の体温を上げるのには向いていません。
体を冷やす物は体内酵素の働きを50%低下させます。栄養の消化だけでなく、エネルギー生産力も低下します。体内酵素が一番活発に活動する温度が、36.5℃といわれています。ですので、私たちの基礎体温は酵素が一番活発に活動する体温になっています。
一日を元気に過ごすには、生野菜やスムージではなく、体温を上げる朝食を取りたいですね。日本古来の和食(ご飯、お味噌汁、漬け物等)は、体を温める作用があります。
朝食で体内時計をリセット!
体内時計って、耳にしたことがありますね。朝を迎えると目が覚めて、夜になると眠くなる、これが体内時計です。体内時計は25時間周期で動いています。これを24時間にリセットするのにも朝ご飯が関係しています。朝起きてから2時間以内に朝食を食べることで24時間にリセットされます。
ですので、1日の始まりを自分では認識できていても、朝食を抜くと体内時計は25時間周期で動いているため時差ボケのような状態を生み、体の不調にもつながってきます。
また、朝食の中身と量も大切です。
炭水化物とタンパク質を中心に、一日の食事量の1/4以上取る必要があります。一日を活動的にするためにも、朝食抜きや、パン食、スムージーだけでなく、しっかり朝ご飯を食べたいですね。
ご飯によって供給されるブトウ糖は、私たちのエネルギー源として、欠かせない栄養源です。ご飯が不足すると、スタミナ切れを起こし、疲れやすくなります。特に脳へのブトウ糖の供給が不足するとイライラします。
また、ご飯を食べる量が少ないと、甘い物が欲しくなります。ご存じだったでしょうか?
[スキンケア大学・美ログ]
Posted by nob : 2014年08月08日 14:59
健康な身体は不純な食品を求めなくなる。。。
■あなたを太らせる「塩、砂糖、脂肪」のワナ
味蕾の地雷、『フードトラップ』を読む
鰐部 祥平 :HONZ
18歳以上のアメリカ国民の33パーセントが、BMI30以上の肥満体だという。本書によれば、陸軍幹部が公式発表で首都ワシントンの18歳以上の男女が太り過ぎで採用できないと表明。また、カリフォルニア州ロサンゼルスでは、太り過ぎのため帝王切開が困難になり死亡する産婦が増えているという。また痛風患者は全米で800万人にも達するという。
なぜアメリカはかくも肥満大国になってしまったのか。本書はアメリカの加工食品産業の問題点について、原材料である塩、砂糖、脂肪という三点を軸にしながら追及する。
塩、砂糖、脂肪の罪
この三つの材料は加工食品になくてはならない物である。なぜなら、製造工程において、苦味、金属味や渋味などの付着がおきてしまうのが通常だが、この三つの材料を加える事により、それらの不純な味を隠すことができるのだ。
糖分への渇望は人間が本能的に持っているものだ。生後間もない赤ちゃんに砂糖水を与えると微笑むという。また、糖分には「至福ポイント」と呼ばれるものがある。至福ポイントとは食べ物や飲み物に糖分を加えた際、最も美味しいと感じる最大点の事だ。この至福ポイントを的確に狙う事で、より依存度の高い商品を開発できる。だが、驚くことに脂肪分には至福ポイントが存在しない。多く投入すればするほど、脳は快楽を得て恍惚感に浸るのだ。
実は糖分や脂肪分を摂取したときに使用される脳の神経回路は麻薬などを摂取したときに使われる神経回路と同じである事が最近になって判明している。
このような消費者の糖分、塩分、脂肪分への渇望を食品会社は熟知している。各社は膨大な予算と大量の科学者を抱え、科学的に人々を依存へと導く商品の開発にまい進しているのだ。例えば、社内で「ビリオネア・ブランド」と呼ばれる29種類のブランド商品を持つネスレはローザンヌ、東京、北京、サンティアゴ、ミズーリ州セントルイスなどの施設に化学者350人を含む700人のスタッフを抱えている。彼らは毎年70件以上の臨床実験を行い、200本の学術論文を発表し、80件もの特許を出願している。
ネスレは悪の帝国?
ネスレのビリオネア・ブランドのひとつ「ホット・ポケット」と呼ばれる冷凍食品は重さ約230グラムの中に飽和脂肪酸10グラム、ナトリウム1500ミリグラムが入っている。これ一つで成人男性が健康的に暮らすために推奨されている一日分の摂取量の上限近くだ。先ほども書いたが、糖、脂質、塩分は麻薬と非常に似た働きを脳内で示す。これらの成分が大量に含まれた商品は食べても、食べても、また食べたくなるという特徴がある。
食べ過ぎを誘う大量の依存物質が入った商品を販売するネスレは、一方で過食に苦しむ人々向けの医療栄養食品を扱う企業を2007年に買収し、その分野にも進出しているという。人々に過食を促し、太らす商品を販売する一方で、太り過ぎの人々を治療する食品も販売している。
このような話を聞くと、ネスレが悪の帝国のように思えてくる。だが、ネスレは摂取し過ぎると健康を害する原材料の使用量を抑えるために様々な努力をしているのだ。しかし、塩、砂糖、脂肪を減らした商品は目に見えて売り上げが落ちる。たとえ、ネスレが一社が努力しても、売り上げが落ちればスーパーの陳列棚を競合他社が占領していくだけである。企業としてそれは看過できる事態ではない。
本書では様々な食品会社がいかにスーパーの陳列棚の占拠を巡り、激しい競争を繰り返しているかが綿密に取材されている。アメリカの子供たちの朝食を巡り、ケロッグなどが激しいシリアル市場の攻防戦を繰り返し、ペプシコとコカ・コーラは「コーラ戦争」を戦う。商品の砂糖含有量はみるみる跳ね上がり、成分の70パーセントが砂糖というシリアルまで販売されている。もはや、それを朝食と呼ぶことができるのであろうか。
著者は加工食品の売り上げにおいてマーケティングがいかに重要かに気づきマーケティングの専門家にも多数インタビューを行っている。コカ・コーラ社はユーザーの新規開発と同じくらい重要なものとして、以前からコーラを愛飲しているヘビーユーザーの重要性にいち早く気づいた企業だ。ヘビーユーザーにもっとたくさんのコーラを飲ませる。そして、思い出に残る楽しい場面にコーラが常に存在するように、という点に多くの力を注ぎながら日夜マーケティング戦略を練っている。
食品業界の一部の人々も、高まる健康志向と自己の良心の呵責の末に、塩分、糖分、脂肪分の減少を模索する。しかし、彼ら良心派は常に亜流に止まる。熾烈な競争の中で、いかに利益を上げるかという重圧は業界の人々に常に圧し掛かる。著者の目は次第に彼らの出資者が集まるウォール街へと向いていく。
味蕾を刺激する地雷
本書は食品業界が流通させる、加工食品がいかに健康を害するかを論じた本である。一方で企業の歴史やマーケティング戦略といったビジネスに関する面を、内部資料の分析や業界人へのインタビューで非常に丹念に追っている。そのような視点で読めば、優れたビジネス書として読むこともできる。また、自由主義市場が求める利益が加工食品メーカーの良心を圧殺しているという視点を鋭く指摘している点も見逃せないと思う。
加工食品メーカーは出資者の求める成果を出すために科学者、心理学者、技師、マーケティングの専門家、デザイナーなどがあらゆる能力を駆使し、綿密に計算された商品を「設計」しているのだ。
これは肥満という現代の社会問題が個人の意思のみで解決しうるものでないことを如実に表している。我々はまさに味蕾を刺激する地雷に囲まれた日常を生きている。本書を読むことで、真実と情報を手に入れ、賢く懸命に振る舞える消費者になることが、自己と家族の健康を守る唯一の武器になるのではないか。そう思わせる一冊だ。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2014年08月08日 14:55
口臭も体臭もまずは清潔を心がけることからですが、、、体内の清潔維持も大切です。。。
■いつでも空腹な人、胃腸が弱い人は口が臭い!?
原因別!食べるだけで口臭を消す魔法食材
池田陽子 [薬膳アテンダント/食文化ジャーナリスト]
こんにちは。薬膳アテンダントの池田陽子です。
前回、前々回は、「水分過剰タイプ」「熱タイプ」「血行不良タイプ」という3タイプ別の体臭撃退法を薬膳の考え方を取り入れながらご紹介してきました。今回は、ニオイといえば体臭と同じくらい気になる、「口臭」の対策法をお話しします。
“上下悪臭男”になってない?
いつでも「腹ぺこ」の胃熱口臭タイプ
気になる口臭も、薬膳で改善を図りましょう。中医学では、口臭の原因は胃の状態が反映されていると考えられています。体臭同様、口臭もタイプ別の対策が必要。大きく2つに分かれるので、それぞれに合った食養生を心掛けることが大切です。
まず、「胃熱タイプ」について説明します。下記のチェックリストで自分が「胃熱タイプ」かどうか、確認してみましょう。
【胃熱タイプ】
□ 過食気味
□ アルコール摂取量が多い
□ 食べてもすぐ、お腹がすく
□ 口が粘る
□ のどが乾きやすい
□ 便がかなり臭う
□ 口内炎
□ 歯槽膿漏、歯肉炎
□ 歯茎から出血がある
□ 胸やけしがち
もしチェックリストの半数以上に当てはまるならば、あなたは胃に余分な熱がたまることで、口臭を引き起こすタイプです。暴飲暴食気味で、脂っこいものや辛いものも大好きな人が多く、その結果、胃に火がついて熱が発生します。また、過剰なストレスも身体に熱を生むため、胃熱の原因になることがあります。
胃にこもった熱は身体の外へ排泄されるべく、上は口に向かって昇り、腐ったニオイを放って女子に逃げられ、下は便といっしょに過剰なニオイを放ち「お父さんの入った後のトイレに入りたくない!」と娘にまで嫌がられてしまう「上下悪臭男」になりがちです。
胃から口の中に進入した熱のせいで、口が渇いてねばついたり、歯茎が赤く腫れて出血したり、歯槽膿漏といったトラブルも引き起こしがち。口内炎になりやすい傾向もあります。
また、胃が熱を持つとお腹がすきやすくなります。食欲過剰になり、さらに胃が熱を蓄え、どんどん必要以上に食べられるという「魔のメタボ胃袋」になり、立派な「口臭デブ」化するという恐ろしい事態になりがちです。
このタイプは放っておくと胃潰瘍になる危険性もあるので要注意。
胃の「火消しフード」で口臭をシャットアウト
胃熱タイプの口臭対策は、とにかく胃にこもった熱を冷ますことが大切。胃に集中的に働きかけて、一気に火消しする食材を取り入れて、口臭をシャットアウトしましょう。
【おすすめの食材】
■トマト
身体の余分な熱を冷ますとともに、胃熱を鎮めてくれるパワー絶大。胃熱口臭対策には欠かせない食材。また、食欲過剰気味のときには朝イチでトマトを摂取しておくと、一日中食欲が落ちつくので、お試しを。暑気払いにもよく、夏バテにもおすすめ。二日酔いにも役立ちます。
【コンビニ/外食】グリーンサラダ、トマトジュース
【居酒屋】冷やしトマト
■大根
身体にこもった熱を下げるとともに、胃をクールダウンし消化を促進して、スッキリさせる効果があります。吐き気、胸やけ、口内炎にもよい食材。のどの痛みや炎症など、気管支系トラブルにもおすすめ。かいわれ大根も使えます。
【コンビニ/外食】大根サラダ、おでんの大根
【居酒屋】しらすおろし、ふろふき大根
■ほうれんそう
胃熱を鎮めるとともに、腹部膨満感にもよく、腸に潤いを与えるため便秘にも効果があります。血を補う効果が高く、血の不足が引き起こすとされる動悸、疲れ目や脳疲労時にも取り入れたい食材。高血圧による頭痛にもおすすめ。
【コンビニ/外食】ほうれんそう入りのカップみそ汁、ほうれんそうの胡麻和え
【居酒屋】ほうれんそうのおひたし
■そば
寒涼性食材で、胃もたれ、消化不良に効果的。ストレスを解消して、リラックスさせてくれる効能もあります。高血圧にもおすすめ。ランチタイムは激辛ラーメンでさらに口臭を炸裂させるようなことは慎み、迷わず「おろしそば」が正解。
■ゆず
過剰な胃の熱を消し、食べ過ぎによる胃痛、胃もたれも解消してくれます。咳や痰のからみにもよい食材。またさわやかな香りが、気持ちをリラックスさせてくれる効果もあります。二日酔いのときにもおすすめです。
【コンビニ/外食】ゆずジュース
【居酒屋】ゆずサワー
もちろん、このタイプはふだんの暴飲暴食を改め、胃に熱を持たせる辛いもの、脂っこいものは控えることも大切です。
胃腸が弱い人も口が臭い!?
口臭ヘロヘロ男になっていないか
次に「胃腸虚弱タイプ」の口臭対策を紹介します。早速、下記のチェックリストで確認してみましょう。
【胃腸虚弱タイプ】
□ 胃痛がある
□ 胃がつかえた感じがする
□ 食欲不振
□ よく吐き気がする
□ 胃がもたれやすい
□ げっぷが多い
□ 下痢をしがち
□ 胃下垂
□ 脱肛
□ お腹がごろごろとなる
いくつ当てはまりましたか?半数以上当てはまった方は、中医学で消化機能をつかさどる「脾」とよばれる臓器と、胃の機能が弱いことが原因で、口臭を引き起こすタイプ。中医学では「脾胃不和」とよばれる状態です。
脾と胃は協力して、消化吸収を行います。脾は取り入れた栄養を身体全体に運ぶ作用があり、胃でできた栄養物を身体の上部に運ぶ作用があります。一方、胃は消化して不要となった残り物を腸へと下部に運んでいます。ところが、脾と胃が弱るとその働きが逆転し、不要なものが上へと昇ってしまい、口臭の原因となるのです。要は、生ゴミが匂うのと同じこと!
ふだんから胃の調子が悪く、食欲不振になったり、胃もたれしがちで、慢性胃炎と診断されている人も。また、下に降ろすという本来の胃の機能が働かなくなっているので、げっぷや吐き気といった上向きの症状があるのも特徴です。
胃が弱ったままでは体内に栄養をしっかり取りこむことができず、人間にとって重要なエネルギー源である「気」を生み出せずに、疲労はじめ全身のさまざまな不調につながります。「口臭ヘロヘロ男」化しないためにも食養生を。
「胃ヂカラ」をつける食材で口内消臭
このタイプの口臭対策は、胃のパワーをアップさせる食材を取り入れて、その働きを活発にすることが大切。胃を立て直して、根本からのマウスケアに努めましょう。
【おすすめの食材】
■ナガイモ
胃を丈夫にするとともに食欲不振、下痢にも効果的。ナガイモは中国では「山薬」とよばれ、気を補うための代表的な生薬としても使われているほど、滋養強壮にすぐれています。疲労回復、アンチエイジング、糖尿病、精力増強にもおすすめのパワフル食材。
【コンビニ/外食】とろろそば、麦とろごはん、お好み焼き
【居酒屋】ナガイモ千切り、山かけ
■キャベツ
胃のパワーをアップするとともに、胃痛、胃もたれに高い効果があります。胃潰瘍や十二指腸潰瘍にもよく、胃のトラブルには欠かせない野菜。虚弱体質や疲れやすい人にもおすすめです。つけあわせのキャベツは胃薬だと思ってしっかり食べること。
【コンビニ/外食】コールスロー、ロールキャベツ
【居酒屋】塩キャベツ
■かぼちゃ
胃の働きを整え、消化を助ける効果があります。また、気を補うとともに身体の末端の血流に作用して、全身、とくにお腹を温めて体力をつけるパワーもある食材。便秘にもおすすめです。また、顔や、全身のたるみ改善にも役立ちます。
【コンビニ/外食】かぼちゃのサラダ、緑黄色野菜のサラダ
【居酒屋】かぼちゃの煮物
■きのこ類(しいたけ、まいたけ、しめじ、マッシュルーム、エリンギ、なめこなど)
胃の働きの低下によく、消化力を高め、食欲不振にもよい食材。気を補って全身にエネルギーを満たし、滋養強壮、疲労回復にもおすすめです。免疫力をアップする効果が高く、花粉症対策にも役立ちます。
【コンビニ/外食】きのこパスタ、なめこのカップ味噌汁
【居酒屋】しいたけ串焼き、きのこソテー
■りんご
胃腸虚弱を解消し、消化を促進します。食後の腹部膨満感や下痢にもよいフルーツ。二日酔いにも効果的です。
【コンビニ】りんごジュース
胃腸虚弱タイプはふだんから、胃に負担をかけない食事を心掛けることも大切。冷たいもの、生ものの過剰摂取、スパイスが過剰に効いた刺激の強いものは控えめにしましょう。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年08月08日 14:51
また旅立つ君へVol.56/自己肯定よりも大切な 「自分を受け入れる勇気」Vol.2
■ホリエモンもほれた
閉塞した社会を切り開くアドラーの教え
堀江貴文×岸見一郎×古賀史健 鼎談【後編】
アドラー心理学の核心を凝縮した『嫌われる勇気』。フロイトやユングと比べると日本では知名度の低かった状況を覆して37万部の大ベストセラーとなり、空前の“アドラーブーム”を巻き起こしています。
そんなアドラーの思想を体現しているのが、ホリエモンこと堀江貴文氏です。堀江氏の著書『ゼロ』は、『嫌われる勇気』の実践編だと捉えることもできます。鼎談の後編は、堀江氏が幼少の頃から抱いていたあるコンプレックスにまで話が及び、アドラーの思想をさらに深掘りする内容になりました。(構成:宮崎智之)
誰かの期待を満たすために
生きてはならない
古賀史健(以下、古賀) 僕が制作チームの一員として『ゼロ』を作っているとき思ったのが、堀江さんは経営者というより、思想家なんだなということです。人間心理だったり、世界に対する真理だったりするようなものを、不器用だけど一つ一つ自分の手で掴みながら前に進んでいるという印象を受けました。
堀江貴文(以下、堀江) すべてのことに正面から向かって行くタイプだから、そう見えたのかもしれません。僕は幼稚園の頃から、周りに対して気を遣って言いたいことも言わないでストレスを溜めるより、言いたいことを言ってぶつかって、その後に仲良くなればいいという思いで生きてきました。そんな生き方をしていたから、批判され続けてきたわけですけど。
岸見一郎(以下、岸見) 仲良くなれるってわかっていればぶつかりますが、普通はそうは思えないです。
堀江 僕の場合、なぜかはじめからそう思ってしまった。自分は過ぎたことを引きずらないから、他人に対しても正直に接したほうが結果として関係がよくなると思ったんです。たとえば、『嫌われる勇気』には、「承認欲求を否定する」という話が出てきますよね。
古賀 「誰かの期待を満たすために生きるのは、他人の人生を生きることである」ということですね。
堀江 はい。当然、僕にも承認欲求はあるんですけど、子どもの頃から承認されない人生を歩んできたので、途中から「承認されることはない」という前提で生きることにした経緯があります。『ゼロ』にも詳しく書きましたが、僕の親はテストで100点を取っても褒めてくれませんでした。それが当たり前だと考えていたんですね。だから次第に両親に褒められなくても、自分が満足してればそれでいいと思うようになりました。だからこそ、「他人も、自分(僕)の期待を満たすために生きてはいないだろう」ということにも気付くことができた。
古賀 それは経営をしているときに気がついたんですか?
堀江 いやいや、それも小学校くらいの頃だったと思いますよ。なんでこいつら自分の思った通りに動いてくれないんだろうと。それに対する対処法があるわけではなく、もんもんとしていたけど、とりあえずは諦めることにしたんです。自分だって自分の満足のためだけに生きているのに、他人が僕の期待を満たすために動くはずがないだろうと。
岸見 それがわかっていると大きいですよね。
堀江 僕は大学生のとき、先輩に「人の気持ちを少しは考えろ!」と言われ、「人の気持ちなんかわかるはずがない!」と反論したことがあります。結局はそういうことだと思うんですよね。他人の期待や自らの過去に縛られて動けなくなっている人が世の中にはたくさんいます。しかし、そういったことは考えても仕方ないことなんです。自分ではどうにもならないんだから、自分は今の自分の人生を全力で生きるしかない。『嫌われる勇気』を読んではっきりとそのことを再認識しました。
ホリエモンが長年抱えていた
あるコンプレックス
堀江 一方で、なかなか過去のとらわれから抜け出せなかったのが恋愛です。『嫌われる勇気』では、「お前の顔を気にしているのはお前だけ」というエピソードが出てきますよね。それはわかっているんだけど、自意識を引きずってなかなかそうは思えなかった(笑)。
岸見 「愛のタスク」は、人生において一番難しい課題なんですよ。
堀江 そう、一番厄介なんですよね。というのも、小学校のときに喧嘩して、「お前みたいな不細工と俺は違うんだ」と言われたことがありました。たった一言だったのにもかかわらず、それ以来、「そうか俺は不細工なのか」と20年間くらい思い続けていたんです。
岸見 それは、心理学的には「属性付与」と呼びます。「お前は○○だ」と断定された側が、それを事実上の命令ととらえてしまい、ずっと縛られてしまうんです。
古賀 いわゆるレッテル貼りですよね。
岸見 そうです。子どもが母親に、「お母さんなんて大嫌い」と言ったとします。でも、母親が「お母さんは、あなたが本当は私のことを好きだと知っているよ」と返したとする。すると、言われた子どもは、「お母さんのことを好きになりなさい」と命令されたような気がしてしまう。そういうものに、人間はずっと縛られてしまう習性があります。
堀江 属性付与された属性を自ら取り消すにはどうすればいいんですか?
岸見 「その属性は一つの考え方、見方でしかない」というふうに思うしかないです。
堀江 そうですよね。僕もそう思ったんですよ。あれは単なる喧嘩したときの捨て台詞だったのかもしれない、本気でそう思ってなかったのかもしれない。そう思うことでなんとか脱却できました。でも、自分は不細工という思い込みは強烈なものでした。女の子に、「そんなモテない感じじゃないよ」と言われても信用できませんでしたから(笑)。
岸見 そう言ってくれる人がいても、「例外的な存在」だと思ってしまうんですよね。
堀江 そうそう。
岸見 どんな人だって、モテない証拠を探せばいくらでも見つかりますから。
堀江 まさに僕がやっていたことですよね。自分に対しても他人に対しても、悪いところを見つけるなんて簡単です。
岸見 子育てに関するカウンセリングをしていても、子どもの短所や、欠点、問題行動などを挙げ続ける母親がとても多い。止めなかったら1時間くらい話す人もいます。カウンセリングではその内容を聞くのはあまり重要ではなく、母親が子どものよくないところばかり見ているという一つの事実さえわかればいい。
堀江 なるほど。
岸見 それを変えていくのがカウンセリングの目的なのですが、「子どもの長所を教えてください」と聞いても、ほとんどの人がすぐに言葉に詰まってしまいます。
堀江 とても面白いエピソードですね。だから僕はポジティブリストを出して、人の長所を見つける生き方をしたいと思っているんです。刑務所に入ってその思いは、より強くなりましたね。刑務所に入っている人なんて、悪いところを見つけようと思えば簡単なんです。でも、いいところもたくさんあって、そこをちゃんと伸ばしてあげれば、犯罪をするような人にはならなかったんじゃないかという思いを抱くようになりました。
岸見 悪い部分ではなく、良い部分にスポットライトを当てるべきだということですね。さらに言えば、悪い部分も含めて自分のことを認めることが必要です。そのためには前編でも言いましたが、できもしないのにできると暗示をかけるような「自己肯定」ではなく、できないことも含めて自分を受容する「自己受容」が大切。そして、自分が他者に貢献できていると思えたとき、「自分は価値がある存在なんだ」とはじめて思える。
堀江 『嫌われる勇気』は刑務所で読まれるといいかもしれませんね。
自分のことを不細工だと
思っていた本当の理由
岸見 でも難しいのは、ある目的を達成するために、あえて自分のいいところを見つけようとしない人もいるということなんです。モテないと思っている限りは女の子に声を掛けなくてもいいですよね。でも、自分にはいいところがあると思っているなら、女の子に声を掛けなければいけない。そうすると断られるかもしれないですよ。傷つくリスクがある。そういうリスクを冒さないために自分はモテないと思い込むわけです。
堀江 なるほど。それは耳が痛い指摘です。まさに、僕がそうでした。
岸見 アドラー心理学では、そうした「原因論」を否定しています。あくまで原因は現在の目的を達成するために、後から作ってしまっているに過ぎない。つまり、堀江さんの場合、「自分は不細工だから」という原因を意図的に作って、女の子に振られるリスクを回避していた可能性がある。
堀江 はい。女の子に対して、積極的にならない理由を求めていたという側面はありましたので、すごくよくわかります。だから、恋愛の問題で最後までとらわれていたのでしょう。やっぱりアドラー心理学は面白いですよね。面白いですけど、とらわれている人からすれば、受け入れ難い思想でもあります。でも、これだけベストセラーになれば、拒否反応を示すタイプの人の手にも届く可能性が出てきますよね。
岸見 そうなってほしいですね。そういう方の役に少しでも立てればうれしいです。
古賀 両方の著書に関わらせていただいた経験で言うと、『嫌われる勇気』が理論編、『ゼロ』が実践編という分け方ができると思いました。
堀江 そうそう。僕も講演会でそういう話をしているんですよ。本の帯コピーを変えて売り出しますか?(笑)
古賀 いいですね(笑)。でも、本当にセットで読んでほしくて。『嫌われる勇気』だけで足りない人は、『ゼロ』を読めば堀江さんの人生を通してリアルに納得できるだろうし、『ゼロ』だけを読んで「堀江さんだからできたんじゃないの?」と思った人は、『嫌われる勇気』を読むと理屈がわかり、自分自身でも実践できる生き方だとわかってくる。
堀江 『嫌われる勇気』は僕の読者に本当に評判がいいです。
古賀 実際に執筆しながら、堀江さんのことを思い浮かべたことが何度もありました。
堀江 そうなんですか。光栄ですね。この二つの書籍が深いところで結びついていて、しかも両方とも古賀さんが関わっているということに、運命を感じますよね。
古賀 『ゼロ』の制作を進めながら、「堀江さんって現代のアドラーじゃん」って、スタッフ同士で話していたので、偶然というより、必然的な運命だったのかもしれません。
堀江 『嫌われる勇気』がこの時期の、この日本でヒットしたのにも運命を感じます。
岸見 四半世紀ほど研究していますが、アドラーがこんなに注目されたのは初めてです。
古賀 これまでアドラーが日本で受け入れられなかったのは、その思想が厳しすぎたせいだと思います。フロイトが提唱するトラウマという考え方は、「今こんな酷い状態なのは過去のトラウマのせいで、あなたは悪くない」と慰めてくれるけど、アドラーはそれを否定しますからね。アドラーにとってトラウマは、現在の目的を果たすためのものに過ぎない。つまり、「過去の原因のせいにして、今の自分を許そう」という目的をアドラーは暴いてしまいます。厳しい現実を突きつけられると、どうしても拒絶したくなってしまう。
岸見 しかし「過去のせいにしていても駄目だ」ということに、だんだんと多くの人が気づき始めたのかもしれません。原因論だと一歩も前に進むことができない。そんな局面に社会が差し掛かっているからこそ、今やっとアドラーが受け入れられるようになったのでしょう。
堀江 いずれにしても、自信を持ってお勧めできる本なので、もっともっと読まれてほしいです。僕の『ゼロ』とセットで100万部を目指しましょう(笑)!
古賀 いいですね(笑)。ほんとうに今日は、ありがとうございました。
岸見 私も、堀江さんとお話しできて楽しかったです。
堀江 ありがとうございました。
(終わり)
堀江貴文(ほりえ・たかふみ)
1972年福岡県八女市生まれ。実業家。元・株式会社ライブドア代表取締役CEO。民間でのロケット開発を行うSNS株式会社ファウンダー。東京大学在学中の1996年、23歳のときに有限会社オン・ザ・エッヂ(後のライブドア)を起業。2000年、東証マザーズ上場。2004年から05年にかけて、近鉄バファローズやニッポン放送の買収、衆議院総選挙への立候補などといった世間を賑わせる行動で一気に時代の寵児となる。しかし2006年1月、証券取引法違反で東京地検特捜部に逮捕され懲役2年6ヵ月の実刑判決を下される。2013年11月、刑期を終了したのを機に著書『ゼロ』を刊行し新たなスタートを切った。
岸見一郎(きしみ・いちろう)
哲学者。1956年京都生まれ、京都在住。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。専門の哲学(西洋古代哲学、特にプラトン哲学)と並行して、 1989年からアドラー心理学を研究。精力的にアドラー心理学や古代哲学の執筆・講演活動、そして精神科医院などで多くの「青年」のカウンセリングを行う。日本アドラー心理学会認定カウンセラー・顧問。訳書にアルフレッド・アドラーの『個人心理学講義』『人はなぜ神経症になるのか』、著書に『アドラー心理学入門』など多数。古賀史健氏との共著『嫌われる勇気』では原案を担当。
古賀史健(こが・ふみたけ)
ライター/編集者。1973年福岡生まれ。1998年出版社勤務を経てフリーに。これまでに80冊以上の書籍で構成・ライティングを担当し、数多くのベストセラーを手掛ける。臨場感とリズム感あふれるインタビュー原稿にも定評があり、インタビュー集『16歳の教科書』シリーズは累計70万部を突破。20代の終わりに『アドラー心理学入門』(岸見一郎著)に大きな感銘を受け、10年越しで『嫌われる勇気』の企画を実現。単著に『20歳の自分に受けさせたい文章講義』がある。堀江氏の『ゼロ』でも構成を担当。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年08月06日 13:41
また旅立つ君へVol.55/自分を許せない時期は辛いが、、、 その果てにしか素敵な笑顔はないのだ。。。
自分の周りが何だか馬鹿らしく感じるけれど
とりあえず今のこの場所にいるしかないのも自分でわかっている
何とかしたくとも
何をすればいいのかわからない
他人を羨んだりもするけど
そういう自分は嫌い
自分を縛るそんなもやもやから脱却して
自由に、楽しく、素敵に生きたいといつも願っている
[「普通の女の子」として存在したくないあなたへ/村上龍]
Posted by nob : 2014年08月04日 17:50
普通であることにこそ大きな勇気が必要。。。
■アドラー流 お悩み相談室
岸見一郎
もう、いい加減にして!
「自慢話」の多い攻撃的な友人をどう回避する?
フロイトやユングと並ぶ心理学の巨人・アドラーは、現代を生きる私たちに人生観が変わるほどの気づきを与えてくれます。その教えをわかりやすく説いた『嫌われる勇気』は今や37万部のベストセラー。本連載では『嫌われる勇気』の著者・岸見一郎氏が、職場や日常生活で起こりうる皆さんのお悩みを「アドラー流」に解決いたします。
今回のお悩みは、27歳の男性によるもの。アドラー流の解決策はどのようなものでしょうか?
【今回のお悩み】
「自慢話が多く、攻撃的な友だち。
聞き流そうと努力するものの、やはり傷つきます。」(27歳・男性)
やたらと自慢話が多い上から目線の男友だち。笑っちゃうくらい高学歴アピールの話を挟んでくるので、普段は「そうかー、そうかー」と聞き流しています。しかし「お前、やばくね?」と上から目線で攻撃してくることがあり、聞き流そう……と思っても上手くいかず、傷ついて落ち込んでしまいます。どうしたら傷つかないようになれるでしょうか?
【アドラー流回答】
わざわざ言葉にして自慢する人の、「目的」を考えてみましょう。
傷つかないようになるためには、その友だちの「目的」を考えるといいでしょう。
なぜその友だちは、自慢話ばかりするのか。やたら他人に対して上から目線なのか。答えはきわめてシンプルです。
じつは彼は、強烈な「劣等感」を抱いているのです。アドラー心理学では、この種の劣等感のことを「優越コンプレックス」と呼びます。
つまり、「ありのままの自分」を受け入れられず、他人より優れていることを誇示するという安直な手段によってしか自分の存在を認められない……。
彼はまだ「普通であることの勇気」を持てていないのです。
よく覚えておいてください。わざわざ言葉にして自慢するような人は、ほんとうのところは自分に自信がないのです。
自らが優れていることを誇示しなければ、周囲の誰一人として「こんな自分」を認めてくれないと、恐れているのです。
このように相手の振る舞いの「目的」さえわかってしまえば、それに対して怒りが湧いたり傷ついたりするようなことも、減っていくでしょう。
もうひと言いえば、あなたはなぜ、そんな友だちとつき合い続けているのですか?
つき合いたくない人と無理につき合う必要などありません。
友だちは一生友だちである必要などないのです。
対人関係のカードは相手ではなく、常にあなたが握っています。関係を断ち切りたくなったら、断ち切るのはあなたの自由なのです。
今回のアドラー流ポイント:優越コンプレックス
アドラー心理学は「劣等感」を忌避すべきものだとは捉えていません。成長や努力の促進剤ともなる、あたりまえの心理状況だと考えます。ただし同時に、人はずっと劣等感を抱き続けることには耐えられないと考え、それをどう克服しようとするかを重視します。健全な努力をもって克服を目指せればいいのですが、多くの人は何の努力もせずに、自らの劣等感を「言い訳」として使いはじめます。それが、アドラー心理学が「劣等コンプレックス」と呼ぶ心理状態です。
たとえば、「私は学歴が低いから成功できない」などと考える。もしくは「(自分は学歴が低いが)もしも学歴さえ高ければ、自分は容易に成功できるのだ!」と、自らの有能さを暗示する方法を取る人間もいます。さらには、それが「優越コンプレックス」と呼ばれる心理状態に発展することもあります。あたかも自分が優れているかのように振る舞い、偽りの優越感に浸るのです。過度の学歴自慢やブランド信仰といった「権威付け」はその身近な例です。
劣等感は健全な努力をもってしか克服できません。いくら「劣等コンプレックス」や「優越コンプレックス」を抱いて言い訳をしたところで、状況は何ひとつ変わらないのです。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年08月04日 17:40
また旅立つ君へVol.54/自己肯定よりも大切な 「自分を受け入れる勇気」
■ホリエモンが共感した
アドラー心理学が教える現代サバイブ術
堀江貴文×岸見一郎×古賀史健 鼎談【前編】
フロイト、ユングと並んで「心理学の三大巨頭」と称されるアドラーの思想を哲人と青年の対話形式で紹介した『嫌われる勇気』。発売と同時に大きな反響を呼び、7月時点で37万部の大ヒットを記録しています。
そのアドラー思想に共鳴し、「自分の考えそのもの」と絶賛するのが、同じくベストセラーとなった『ゼロ』の著者である、“ホリエモン”こと堀江貴文氏です。既存の社会システムに異議を唱え、ことあるごとに改革の必要性を訴えてきた堀江氏は『嫌われる勇気』をどう読み、なにを感じたのか。著者である岸見氏、古賀氏との鼎談を、2回に分けてお届けします。(構成:宮崎智之)
“ホリエイズム”を体系化した
『嫌われる勇気』の衝撃
古賀史健(以下、古賀) 本日はお忙しいなか、ありがとうございます。
堀江貴文(以下、堀江) こちらこそ。
岸見一郎(以下、岸見) 今日の対談を楽しみにしていました。
堀江 おふたりが執筆された『嫌われる勇気』は、僕の『ゼロ』の担当編集者・柿内芳文さんから「堀江さんの思想にそっくりだから、とにかく読んでみて」と何度も勧められていたんですよ。先日ようやく読む時間が取れて読んでみたら、もうほんとうに滅茶苦茶ビックリしました。自分が言いたかったことがすべて書かれているといっても過言ではないくらい似ていて……。
古賀 僕もそう感じました。
堀江 本を書いたり、講演をしたりするのって、要は自分の考え方がどうしてこうなったのかということを整理して説明する作業ですよね。それを何回も繰り返すことによって、自分の考えが体系化されていく。でも、『嫌われる勇気』を読んだら、僕の考えていたことは、僕が生まれるずっと前にアドラーが体系化していたことがわかった。本当に驚きですよ。最近、講演会で「『嫌われる勇気』を読めば僕の言いたいことが書いてある」と言っているんです。僕が長々と話すより、そのほうがわかりやすいかもしれません(笑)。
古賀 特にどのようなところに共感しましたか?
堀江 いろいろあり過ぎて一つには絞れませんが、「他者の課題を切り捨てよ」という発想は本当にそのとおりだなと思いました。たとえ相手が自分のことを嫌っていたとしても、それは他者の課題であって、自分とは関係ないことであるという考え方ですね。あと、「人生とは連続する刹那である」という言葉にも感動しました。
古賀 まさに、「今に全力を尽くす」堀江さんの生き方そのものですよね。読者からは、「目から鱗が落ちた」や「人生観が180度変わった」という感想が寄せられたのですが、堀江さんにとっては、「そうなんだよ!」って感じだったということでしょうか。
堀江 よくぞ言ってくれた!という感じでした。僕が本を書くと、ある種の色眼鏡で見られてしまうことがあると思うんです。「お前だからできるんだろう」とか、「普通はそんな生き方はできないよ」とか。でも、アドラーはそういう考え方をきちんと理論立てて体系化している。僕の生き方が特殊ではないということを証明してくれているんです。
古賀 『嫌われる勇気』は哲人と青年の対話という構成を取っていますが、堀江さんは普段は相談を受ける側、どちらかというと哲人の側ですよね。
堀江 そうそう。哲人ほど悟ってないですけど、僕のところには青年のような若者がたくさん来ますよ。彼らは本当に青年とそっくり。僕の言うことに対して「なるほど」と納得するのですが、「でも〜」と付け加えて実行できない理由を並び立てようとする。
岸見 カウンセリングでは、その「でも〜」を少なくするのが目標になるんです。堀江さんのおっしゃるとおり、どんなに具体的なアドバイスをしても、「でも〜」と言っている限りは絶対に実行はしません。しかし、「わかりました」を引き出すためには、「でも〜」を繰り返す過程が必要でもあります。堀江さんのように「でも〜」なしにアドラー心理学を受け入れる人もいるかもしれませんが、ほとんどの場合は抵抗しながら徐々に納得して受け入れていくというパターンが多いです。
世の中の起業家は
ほとんどがバカ?
古賀 堀江さんにも、青年みたいな時期ってあったんですか。
堀江 それがあんまりないんですよ。振り返ってみても、子どもの頃からアドラーの思想を無意識に実行していたような気がします。そのせいで、いろいろ軋轢を生み苦労しましたけど(笑)。
古賀 堀江さんはしばしば「拝金主義」という表現のされ方をしますよね。でも、堀江さんはお金をある種の「自信」をつけるための手段であるととらえている節があると思うのですが。
堀江 自信をつけるためには、「成功体験」が必要になります。でも、「成功」って明確な基準がないじゃないですか。その点、お金は「数字」になって出てくるのでわかりやすく、ビジネスであれば「多く稼いだほうがいい」というシンプルな基準もある。つまり、ルールが明確で、誰でも参加できる平等なものなんです。
岸見 なるほど。
堀江 たとえ頭が悪くても、他に秀でている部分があれば商売では勝つことができますからね。「お金を稼いだ」という、誰にでもわかりやすい成功の形が作れるんです。だからこそ、僕は『稼ぐが勝ち』という本であえてお金を稼ぐことを勧めていたのですが、変な誤解をされてしまって「拝金主義」のレッテルを貼られてしまいました。
古賀 そうですよね。
堀江 こんなことを言ったらあれなんですけど、成功した起業家の大半はバカなんですよ。大バカですね。でも、逆に頭のネジが抜けているからこそ、上手くいくという側面もあると思う。『嫌われる勇気』で書かれているようなことを、天然で実行してしまっているんです。そして、クオリティ・オブ・ライフが高く、いきいきしている人が多いということも特徴です。でも、サラリーマンには、目が死んでいる人が多いですよね。毎日満員電車で通勤して、仕事が嫌だ嫌だと言いながら生きている。僕はそういう人たちは、小利口だから駄目だと思っています。下手に利口だから未来のリスクばかり考えてしまう。この前、年金の心配をしている20代の女の子に会いました。どうかしていますよ!
岸見 自分の人生にうすらぼんやりした光を当てて、先が見えるような気がしてしまうんでしょうね。
「『嫌われる勇気』には自分が言いたかったことがすべて書かれている」と堀江さん。
堀江 なにが起こるかわからない現状を、「なにが起こるかわからないからワクワクする」と感じるのか、「なにが起こるかわからないから怖い」と感じるのか。この違いは大きいと思います。『嫌われる勇気』の言葉を借りれば、「連続する刹那を生きる」ということになるでしょうか。わかりもしない未来に怯えていることが、いかに人生にとって無駄なのかということを伝えたくて、僕はよくバカな経営者の話を人前でするようにしています。
岸見 たとえば、どんな方がいらっしゃるんですか?
堀江 札幌に飲食店などを経営している友達がいるんですけど、先日、LINEで未公開株詐欺の典型的な文章を送ってきて、「堀江さんこれどう思います?」って聞いてくるんですよ。いや……これ典型的な詐欺でしょって(笑)。それを僕に聞いている時点で、半分くらい信じていると思うんですよね。それだけバカだということですよ。そんな男が何社も経営している、世間的に言えば「成功者」なんだから、恐ろしいことですよね。
古賀 でも、そういうものに食らいついてしまうほど後先を考えないところがあるからこそ、成功を掴むことができる側面があるということですね。
堀江 そうそう。あと、カナダのバンクーバーで大成功しているジャパニーズレストランの社長もバカなんですよ。日本で寿司屋チェーンを経営していた親父が病気になってしまい、急遽20代で会社を継ぐことになったんですが、魚の仕入れ方法もわからず、はじめはスーパーで寿司ネタを買って握っていたそうです。そんな素人が、なぜかバンクーバーに出店しようと言い出して、よくわからないまま、とにかく成功してしまった。
古賀 リスクを考えないからこそ、成功したということでしょう。たしかに世間的に言ったら「バカ」ですが、「バカ」でなければ成し遂げられないものもあるのだと思います。
自己肯定よりも大切な
「自分を受け入れる勇気」
岸見 アドラーは「誰でもなんでも成し遂げることができる」ということを言っているんですよ。多くの人は無理だとはじめから思ってしまうから、成し遂げることができないだけで。でも、たとえ失敗したとしても、やらないよりやったほうがベターですね。
堀江 失敗自体が経験になりますからね。失敗したら次にやるときは仕組みがわかっているので、何度も失敗して成功のスパイラルに入る人もいる。ブックオフの創業者・坂本孝さんも成功するまでは、いろんな事業を失敗しているんです。結局ブックオフも内紛のような形で追われて、今は「俺のフレンチ」「俺のイタリアン」でまた成功しています。
岸見 アドラーは「失敗することの勇気」という言い方をしているんですけど、もう一つ、「失敗したことが人前で明らかになることを恐れない勇気」があると言うんです。
堀江 他人にとっての自分なんて実は取るに足らない存在で、家族や恋人ですらも大して自分(僕)のことを考えていないものということは、経験上、理解できるようになりました。
古賀 『嫌われる勇気』でも、「過剰な自意識が、自分にブレーキをかける」と指摘されています。
堀江 僕は潰れた会社のブランドを買って、それを再生するということをよくやるんです。一番有名なのは「ライブドア」。ライブドアって、一度は潰れた会社なんですよ。それを自分たちの会社の名前にするという、かなりトリッキーなことをした。普通は自分の会社名に愛着を持って、それを大事にするでしょう。それを潰れた会社を買ってそっちの名前に変えたもんだから、こいつはなんなんだと話題になりました。でも、僕は会社が潰れたという事実を誰がどれだけ覚えているんだとも思うんです。
古賀 なるほど。
堀江 たとえばJALは一度倒産しましたが、JALがそうなったことを覚えている人がどれだけいるのか。質問すれば「そういえば」ってことになるかもしれないけど、せいぜいそんなもんですよね、人の記憶なんて。だから、「君が失敗したことなんて、誰も覚えていない」と僕は言いたい。
古賀 本当にその通りですね。
堀江 「失敗したことが人前で明らかになることを恐れない勇気」ということでいうと、僕は20代の後半から、「小学1年生のときに教室の後ろでウンコを漏らした」というネタを人前で言うようになりました。大学生の頃は、そんなこととても言えませんでしたけど、カミングアウトすることでネタになり、失敗がプラスに作用することもある。
岸見 誰も覚えていないですしね。堀江さんが漏らしたことなんて。
堀江 もちろんそうです。僕がウンコを漏らしたことなんて誰も覚えていない。過去にとらわれることなく、それをネタに変えていくくらいのポジティブさが必要なんです。だからトラウマを否定し、「現在」しか存在しないというアドラーの思想に強く共感する。
岸見 つまり、自己肯定ではなく、自己受容が大切だということです。無理に自分を肯定するのではなく、過去も含めてありのままの自分を受け入れる。堀江さんが『ゼロ』でおっしゃっていた、「なにもない自分に小さなイチを足していく」という考え方は、アドラーの言う自己受容に近い考え方だと思いました。
(続く)
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年08月02日 22:00
また旅立つ君へVol.53/You are good enough now!
■アドラー心理学が教える
幸せに生きるための3つのヒントとは?
宮台真司×神保哲生×岸見一郎 鼎談第2弾(後編)
私たちが信じていた常識を次々とくつがえすアドラー心理学。『嫌われる勇気』はその理論をわかりやすく解説して37万部のベストセラーに! 同書の著者・岸見一郎氏が、宮台真司氏、神保哲生氏とインターネット放送番組「マル激トーク・オン・ディマンド」で繰り広げたトークセッションの後編をお送りする。「共同体感覚」とは何か? そしてアドラー心理学が教える「幸せに生きるための3つのヒント」とは?
共同体感覚を
身につけるための3条件
神保哲生(以下、神保) 第13回でも取り上げたアドラー心理学の重要なキーワード「共同体感覚」を身につけるにはどうすればよいのか。『嫌われる勇気』には3つの条件が書かれています。「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」の3つですね。岸見先生、これについてご説明いただけますか。
岸見一郎(以下、岸見) どのようなときに自分を受け入れられるかといえば、自分が役立たずではなく、誰かの役に立てている、つまり貢献できていると思えるときです。そして、誰かに貢献したいと思うなら、その相手は「敵」ではないでしょう。「仲間」として信頼できるからこそ、その人に貢献したいと思う。ということで「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」の3つはワンセットなんです。
共同体感覚を身につけるための「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」は3つでワンセットだと岸見氏。
神保 最初の「自己受容」というのはどういう感覚ですか。今のままの自分でいいということでしょうか。
岸見 先ほどの言葉で言えば「自分に価値がある」と感じられるということです。今のままでいいというより、「この私しかいないのだから、とりあえずそこから始めよう」ということですね。
神保 この私しかいないから……。
岸見 「自分に価値があると思えるときに人は勇気を持てる」とアドラーは言います。どのような勇気かというと、対人関係に取り組む勇気です。しかし自分に価値があると思えない人は他者の中に入っていこうとしない。
神保 自分に価値があるとなかなか思えない人はどうすればよいのでしょう。
岸見 難しいですね。自分に価値があると思ってはいけないと決心している人さえいますから。
神保 どういうことですか。
岸見 自分に価値があると思えば人との関係のなかに入っていかなければなりません。それが恐い人は、自分に価値があると思うと都合が悪いわけです。たとえば、好きな異性ができたとします。でも、その異性に自分の気持ちを打ち明けたからといって、相手も好きだと言ってくれる保証はありません。そこでフラれる経験をするくらいなら初めから人と関わらずにおこう、そのためには自分に価値があってはいけないと思うわけです。これはけっこう厄介です。
神保 なるほど。
岸見 そういう人たちに自分を好きになってもらうためには、「他者貢献」という部分でアプローチします。アドラーは先の言葉に続けて、「共同体に貢献していると感じられるときに、自分に価値があると思える」と言っています。つまり、自分は役に立っている、貢献していると感じられることで、自分に価値があると思えるように援助するのです。
神保 他者貢献っていうのは具体的にどんなイメージですか。どんなことをすると他者貢献ができていると感じられ、それが自己受容につながるのでしょう。
岸見 行為のレベルだとよくわかります。誰かに役に立つことをすればいい。
神保 いわゆる人助けみたいなことでいいですか。
岸見 そうしたことも含め、自分が何かをしたら喜んでもらえたという経験です。ただ、もう一つあって、存在のレベルで貢献するということもあります。
無条件で自分はOKだと
思えることの重要さ
神保 存在のレベル、ですか?
岸見 たとえば僕は病気をしたのでよくわかるのですが、まったく身動きがとれない寝たきりの状態でも、なお人の役に立てていると思うことは可能です。誰でもそうした存在のレベルで他者貢献できることを感じて欲しいのです。ただ、これにはかなり勇気が必要です。何かをして他者の役に立てたと感じることは容易ですが、何もできない状態でそれを感じるわけですから。
神保 いるだけで?
岸見 はい。ですが、そう思えない人は他者に対しても行為レベルでしか価値判断をしないことが多い。「あの人は役立たずだ。生産性に何ら貢献していない」と切り捨ててしまいがちです。
神保 行為のレベルで価値を判断するのは必ずしもよくないと?
岸見 それだけで判断するのはよくないでしょう。
宮台真司(以下、宮台) E・H・エリクソンという心理学者が提唱した「基本的信頼(basic trust)」という概念があります。これが岸見先生がおっしゃったことに重なるんですね。「basic trust」は、何かをしたからではなく、つまり条件付き承認とは無関係に、無条件で自分はOKだと思えるということです。
「basic trust」を持たない人は、それを埋め合わせるために過剰同調が生じがちです。つまり、他者に迎合して──つまり他者の課題を自己の課題とすることで ──承認されよう、嫌われないようにしようと思う。その意味で、自立にとっての基本条件は、無条件に「自分はOK」だと思えること。つまり存在そのものの肯定です。
「何かをしたから承認される」という条件つき承認の意識を持つ人は、ギブ&テイク的に見返りを求めます。つまり損得勘定が動機付けになります。こうした「ほめて欲しくて何かをする人」は、ほめてもらえないと相手を恨みます。このように他人を恨む人は、自分を条件付きでしか承認できない人ですが、他者をも条件付きでしか承認できません。
神保 行為なくして自分が受け入れられる状況をつくるのに苦労している人は多いと思います。他者に何かしてあげることで仲間になることはあっても、単に存在するだけでいいというのはなかなか難しいでしょう。そうなればいいなと思いつつも、うまくなれていない人が多いのでは?
宮台 近現代社会がそうした方向にシフトしてきた事実を、社会学者タルコット・パーソンズは「業績本位の社会にシフトした」と言います。能力を発揮することが承認の条件となるメリトクラシー社会になったということ。社会思想家ユルゲン・ハーバーマスはそれを社会領域の問題だとします。業績が承認の条件となる〈システム〉と、そうではない〈生活世界〉です。
ハーバーマスによれば、近代化とは、〈生活世界〉が〈システム〉と置き換わる過程です。昭和34年生まれの僕が幼少の時分、まだ昔ながらの共同体=〈生活世界〉があって、ちょっと頭が変な人や傍若無人のヤクザもいました。学級にヤクザの子もいたのでそうした人と繋がる機会もあり、父親よりもヤクザのほうが格好いいと思ったりした。
あるとき、僕がいつも満票で学級委員に選ばれるのは、ヤクザの子たちが僕のために周囲を脅していたからだと分かりました。上海で生まれ育ったバタ臭い僕の母が、しばしば彼らを家に呼んで晩飯を食べさせたり、高い玩具で遊ばせたりしていたからです。父の仕事で転校だらけだった僕のために、母が考えたことでした。
そんなこんなで、本当はヤクザの子みたいに喧嘩が強いガキ大将になりたいと思ったものです。ダイバーシティ(diversity)という言葉があって「多様性」と訳しますが、僕は嫌いで、「何でもあり」と訳します。たとえば、他者一般への基本的信頼があれば、細かいことは気にせず「何でもあり」に耐えられる。基本的信頼こそダイバーシティへの鍵です。
逆に言えば、「何でもあり」を邪魔するのは、細かいことを気にするヘタレ。そうしたヘタレはたいてい条件付き承認しか経験してきておらず、承認されたいがゆえの損得勘定で右往左往する作法を大人になっても継続しがちです。こうしたヘタレが多いと多様性フォビアが蔓延しがちで、社会はダイバーシティ=「何でもあり」から遠ざかります。
岸見 存在の次元で認めることができれば、あとは何でもプラスなのです。とにかく生きている状態がOKだと思えれば、子どもが学校へ行かなくてもOKです。ベッドの中で冷たくなられているわけじゃない。何でも引き算してしまえば多くの人はマイナスでしか採点されません。そういう社会が健全だとは僕は思わない。そう考えるとアドラー心理学は強者の心理学とはいえませんよね。
宮台 全然違いますよね。関連しますが、性愛系ワークショップをやっていて気になるのは、相手にイエスと言わせようと細かいことを気にして、ビビる人が多いこと。僕は「気に入られようとしてビビッてる人が君の目の前にいたらどう思う?」と問うことにしています。間違いなく嫌な感じがするはず。ハッピーに感じる人は一人もいない。
基本的信頼の不足ゆえに、損得勘定で右往左往する「細かい輩」は、人の好意を買おうと一喜一憂します。これは他者の内面を慮っていると見えて、実は違う。実際には目の前の相手を嫌な気持ちにさせるので全くモテないし、マクロに考えれば、こうしたモテない輩で溢れる社会は、既得権益を動かせない「原発をやめられない社会」になります。
前回「立派か卑怯か」の二項図式が廃れた話をしました。「立派な人」は細かいことを気にしない。僕は昔から、日本初の右翼団体「玄洋社」創設者の頭山満という人物を持ち出します。彼は「右か左かはどうでもいい、お前の心意気に打たれた」「イデオロギーは知らないが、意気に感じた」と、世直しを志す若い衆を食客にします。そこにヒントがあります。
岸見 課題をきっちり分けられれば、細かいことにはこだわらなくて済みます。極端な例ですが、僕の友だちの息子さんが高校生のとき「2年生になった」と親に言ったそうです。すると父親が「そうか、どこの中学だったかな」と(笑)。無関心と言われそうですが、子どもの課題と自分の課題を分けられれば、細かいことにはこだわらなくてよい。そして、もっと大事なことに関心があるという信頼があれば、親子関係は大丈夫なはずです。課題の分離ができない親は、基本的に子どもを信頼していません。「私が言わなければ、この子は永遠に勉強しない」と思っている。そんなことはあり得ないのです。
普通であることの勇気
神保 続いては『嫌われる勇気』に出てくる3つのキーワードに沿って、アドラー心理学として「幸せに生きるためのヒント」を頂ければと思います。その3つとは「普通であることの勇気」「人生の嘘」「今この瞬間を生きる」です。まずは最初の「普通であることの勇気」ですが、これはアドラー的にはどのような意味になるんでしょうか?
岸見 まず、人というのは特別に良くなろうとしがちな存在です。それに失敗すると逆に特別に悪くなろうとする。そのどちらでもなくていいということです。
この言葉を聞くと思い出すのは、私が初めてアドラー心理学の講演を聴いたときのことです。1989年にアドラーの孫弟子であるオスカー・クリステンセンの講演を聴いたのです。そのとき私は通訳で呼ばれていたのに、いっこうに出番がないまま講演会が終わってしまいました。そこで質疑応答になったとき、なぜか英語で質問をしようと思ったのです。クリステンセンは英語で答えてくれたのですが、そのあと自分の学生時代の話をしました。
アドラーの弟子であるルドルフ・ドライカースからレポートの課題を出されたときの話です。課題は「フロイト心理学とアドラー心理学の違いについて2ページで論じなさい」というもの。クリステンセンは懸命に20ページも書いて提出したところ、ドライカースに呼び出されたそうです。「あなたは、なぜこのレポートを書いたのですか?」と。クリステンセンが「アドラー心理学に非常に関心があったから」と答えたところ、「いや違う。あなたはただ私に impress(印象づけ)しようとしたのだ」と。たしかに普通ならそんなに書かないですよね。ドライカースは「君は特別良く見られたいと思い、他の学生と違うことを教師である私に印象づけようとしたのだ」と言ったそうです。そして「そんなことをしなくても、君は今のままの君でいいのです」と。
神保 「You are good enough now」と言われたんですね。
岸見 この話は、僕に向けられたものだったと思います。「あなたは別に英語がそれほど得意じゃないのだから、他の人と同じように日本語で質問すればいいのです。なぜわざわざ英語で質問したのですか?」という意味でしょう。そのとき僕は、それまでの人生でずいぶん背伸びして自分を良く見せようと思って生きてきたことに気づきました。「そうか、自分は特別であろうとしていたんだ」とわかり、それまでこだわっていたことがまったく消えてしまった。アドラーの教えのなかでも私が本当にすぐ納得できたのは、この「普通であればいい」ということです。
神保 ですが「普通」は「平凡」という意味に聞こえてしまって、それが嫌な人も多そうですね。
岸見 たとえば自己紹介を求められたとき、肩書きから始める人がいますね。ああいう人たちは「普通である勇気」がないのだと思います。すごい経歴がないと自分を認めてもらえないと思っている人というのは勇気をくじかれているのです。
神保 日本人は「何をやっているんですか?」と聞かれると会社名を言うことが多いですね。会社で経理部にいれば「経理の仕事をやっています」と言えばよいのに。宮台さん、この「普通であることの勇気」についてはいかがですか?
宮台 誤解されやすいのは、「ありのままでいい」というのとは少し違うってことですね。
神保 たしかにアドラー心理学は「人は変われる」という話でした。
宮台 細かいことを気にする人たちは、要するに「もっと大事なことがある」ということが分かっていない。もちろん人から良く見られたいというのは誰にでもあります。嫌われるよりは好かれたい。尊敬されないよりは尊敬されたい。しかしやはり優先順位が大事なので、人に良く見られたいというのが優先順位の筆頭にくるのはおかしいわけです。
神保 自分の人生を生きていないと。
宮台 一つ例を出しましょう。少し前にロシア抜きのG7がありました。その際、安倍首相はテレビカメラが回った各国首脳との懇談で同時通訳を付けず、これを新聞社のデスククラスが嘲笑の的にしていました。宮澤喜一元首相があれだけ英語ができても必ず通訳を入れたのは、通訳が喋る間にじっくり考えられるからです。実に合理的な熟慮です。
安倍首相の英語力は巷の噂どおり。それで僕はあれを見て、痛々しくて哀しくなりました。問題は、安倍本人を含めて、痛々しいと思わない人たちが大勢いるということ。あれを格好いいと感じる輩や、自分も同じように振る舞いたいと思う輩が、大勢いるということ。そうした次元で政治家の行為を評価する〈感情の劣化〉がポピュリズムを駆動します。
どうすれば承認欲求を
克服できるのか
神保 たしかに、自意識過剰、劣等感、優越感、承認欲求といったものを克服できない人は多いと思います。では「普通であることの勇気」を手に入れ、承認欲求を克服するためにはどうしたらいいのでしょう。
岸見 同時通訳を付けないようなことをアドラーは「虚栄心」と言います。そういう人たちは、じつは「優越コンプレックス」を持っている。優越コンプレックスは劣等コンプレックスの裏返しなので自分を良くは見せないし、本当に優れている人は自分が優れていることを誇示しない──まずはそのあたりの気づきから始めるべきでしょう。「こんなことは少しも格好よくない」とわかれば、やがてそういうことから離れていけると思います。
神保 ただ、実際にはそうした虚栄心をすごいと思ってくれる人がいるわけですよね。
宮台 そうした虚栄心に満ちた輩を賞賛する〈感情の劣化〉を被った人だらけなのが昨今です。だから子どもが成長する環境としては問題が多い。前回も話したけれど、「立派か卑怯か」という語彙が死滅したコミュニケーション環境に育つのは、大きなハンディです。放っておいたらダメで、別のもので補わない限り、勇気ある存在になれません。
岸見先生には釈迦に説法ですが、初期ギリシアは〈依存〉を嫌って〈自立〉を推奨します。全能の神からの罰を恐れてちゃんとするというのはダメ。罰がなければちゃんとしないからです。そういう損得勘定と関係なく、自らちゃんとしようと思える人間が善い。そういう人間を育てるにはどうすればいいか。つまり初期ギリシアの教育観とは何か。
前回紹介したジョージ・ハーバート・ミードはプラグマティストです。プラグマティストとは「内なる光」を灯すことを使命と心得る者です。「内なる光」とは損得勘定を超えて湧き上がる力です。僕の言葉では〈自発性〉ならぬ〈内発性〉です。この観念の由来は、「内なる光」という言葉を使ったラルフ・ウォルドー・エマソンのようにキリスト教を経由するにせよ、初期ギリシアです。
ミードの「I/Me」論も初期ギリシアの教育観を引き継ぎます。即ち「立派か卑怯か」「立派か浅ましいか」という二項図式を使った「賞賛と揶揄」です。初期ギリシアの最大価値は「死を恐れずポリスに貢献する勇気ある兵士」という名誉です。「賞賛と揶揄」も賞罰ですが、賞罰を気にしない者を賞賛し、気にする者を揶揄する。特殊な賞罰です。
かかる特殊な賞罰の目的は明らかです。賞罰の如き損得勘定を気にせず、理不尽や不条理にそのまま体と心を開いて立ち向かう、〈自立〉した英雄を育てること。つまり、子ども時代には「卑怯なヤツと思われたくない」という損得勘定から出発させ、やがて人にどう思われるかに関係なく「自分は立派でありたい」と願う大人へと仕立て上げます。
そうした立派な在り方が人間本来の姿なのに、ゴミやヨゴレがついてダメな大人になる。だから、ゴミやヨゴレに抗って人間本来の姿(可能態)を引き出すのが、初期ギリシアの教育です。だから、英語のエデュケーションにせよ、ドイツ語のエアツーウンクにせよ、教育という言葉は、ギリシア由来の「引き出す」という観念を保っているわけです。
「人生の嘘」とは何か
神保 アドラー心理学における「幸せに生きるためのヒント」の2つめは「人生の嘘」というものですが、これはどのようなことでしょう。
岸見 さまざまな口実を設けて人生の課題から逃れようとすることです。先ほどの話にもあったように、自然に任せておけば人は誰でも自分を良く見せたくなるものです。それゆえ、できないことがあると、できない理由を山ほど言います。アドラーはそれを「人生の嘘」という非常に厳しい言葉で断罪しているわけです。
神保 これはどう克服すればよいのでしょう。
岸見 理由など要らないからできないことを認め、そのうえで挑戦するしかないでしょう。
神保 できない理由を挙げることで、挑戦することから逃げられるわけですね。
岸見 結局、神経症的なライフスタイルというのは、オール・オア・ナッシングなのです。できなければしない。100%できないとしない。しかし、それはやらないための口実にすぎません。50や60でもやらないよりやったほうがましだとの発想に立たない人が多いのです。
神保 なるほど。100点にならない理由を見つければ、やらなくて済むわけだ。
宮台 この問題も本当にいろいろなことに関係します。たとえば、日本の社会運動を見ていて感じるんですが、やはり「ゼロか100か」になりがち。運動をやらない人だけでなく、やる人にも見られます。やらない人は、100から遠いことを以て「どうせ無駄でしょ」と決め込みますが、やる人も100を求める完璧主義なので、現実を変えられません。
下北沢再開発問題などもそう。「100を貫徹するために頑張るぞ」という自己鼓舞は分かりますが、100じゃないと満足しないのはどうか。原子力ムラだけでなく左翼ムラを含めた全てのムラに見られる閉鎖的で陣営帰属的な自己満足です。妥協策を提案すると「貴様、本当は敵側じゃないのか?」みたいな批判を浴び、それを恐れて100を言い続けます。
既に古くからの開発計画がある場合「ゼロか100か」はまず通らない。であれば、三軒茶屋の再開発みたいに開発エリアと保全エリアを分けることを飲ませる条件闘争をすればいい。しかし、それを言うと、知り合いの運動リーダーの一人は「宮台、お前の言うことは分かるが、それじゃ元気が出ないんだよ」と言うわけです。
神保 それは矛盾だよね。
宮台 そう。「元気が出ない気持ちも分かるが、あなたを元気づけるためじゃなく、実を取るための運動だ。獲得結果の最大化につながるなら、あらゆる妥協をするつもりでやらなきゃ」と僕は言います。あと、過激なことを言い募るほどポジションが取れるという「内集団の論理」もあります。これも「あなたのポジションなどどうでもいい」で終了。
神保 自分のためにやっているんだね。
宮台 そう(笑)。
神保 いろいろ理由をつけて「だからやらない」という人と、玉砕主義的なやり方をする人という両極になっていますよね。前者は、あえてやらない理由を見つけ人生の嘘をついていると。では後者はどう考えればいいでしょう。100点じゃなければ意味がない、妥協して 60点の成果をあげるくらいなら玉砕したほうがいいといった人は。
岸見 アドラーは、そういう事例についても触れています。負けることがわかっているのにあえて攻撃をやめないで、「玉砕」させてしまうような指揮官の例を、共同体感覚のない人の例として挙げているのです。
神保 何度も話に出てくる共同体感覚ですね。
岸見 要するに自分のことしか考えていないのです。自分の名誉ばかり考えている。そのために兵士が亡くなろうが関係ない。それって愛国的でさえないですよね。このような考えをアドラーは「セルフ・インタレスト」(self interest)と呼びました。そして他者に関心を持つことを「ソーシャル・インタレスト」(social interest)と呼ぶわけです。この「ソーシャル・インタレスト」が、実は共同体感覚の英語訳なのです。
神保 なるほど。
宮台 「どうせムダ」も「玉砕覚悟で」も結局は「自分可愛い」だけ。「ゼロか100か」は「自分可愛い」人のワザ。そうした自己中心的な幼児性を示す「Me」に対し、立派な共同体成員なら誰もが示すはずの反応を示せる「I」を獲得することが、大人になること。それが共同体感覚のミード的言い換えです。「ゼロか100か」は恥ずべき幼児性です。
「今この瞬間を生きる」ことの
本当の意味
神保 アドラー心理学の「幸せに生きるためのヒント」の3つめは、「今この瞬間を生きる」となるわけですが、これも解説をお願いできますか。
岸見 人は過去のことを考えて後悔し、未来のことを考えて不安になります。けれど実はどちらもなくて、人は今ここにしか生きられないのです。
神保 実際には、その瞬間瞬間しかないと。
岸見 そうです。
宮台 関連しますが、以前、京都大学霊長類研究所の松沢哲郎教授に興味深い話を伺いました。500万年前に分かれたチンパンジーと人間の基本的違いについてです。チンパンジーは今そこにあるものを認識・記憶する能力は人間よりはるかに優れています。人間は代わりにそこに存在しないものについてまで認識する能力に優れています。
たとえば、嫉妬。チンパンジーは目の前で行為が行われると嫉妬しますが、見えない場所での行為や過去になされた行為については一切問わない。人間は逆で、見えない場所でなされた過去の裏切りを、永久にぐじぐじと問い続けるわけです。これは「もし、あのとき、お前がああ振る舞いさえしなければ、俺は……」という反実仮想です。
神保 松沢氏の話では、チンパンジーは寝たきり状態になった場合も、むしろ飼育員が優しくなるので陽気に振る舞うということでしたね。しかし人間は、寝たきりにならなければ自分はもっと幸せな人生を送れたはずと考えて悲観してしまう。
宮台 「もし、あのとき~だったら、今の俺は……」という不在のものについてのリグレット(後悔)が、前方に投射されると、「もし、今~をしたら、未来の俺は……」というプラニングを生み、それが人間社会を猿社会と異なるものに進化させたのではないか、というお話でした。つまり、今を生きないことが、人間社会における社会性をなしていると。
神保 今を生きないから人間は猿と違う社会をつくれたと。
宮台 逆の言い方をすると、人間社会への社会的適応だけを考えていると、自動的に今を生きなくなる。「しくじった」と絶えず過去のリグレットをし、それゆえに、「未来にリグレットしないように今こうしよう」という指令に従い続けます。「過ぎ去ったことなのに、暗い過去をいつまでも覚えているから、明るい未来を構想する」という逆説です。
今に集中して幸せに生きることと、明るい未来のデザインを含めて社会的に生きることとはバッティングしがち。しかし、未来のデザインのために今を犠牲にすれば、未来になって「しまった」とリグレットを抱きがちだし、犠牲を取り返すぞという具合に損得の亡者にもなりがち。つまり、人間はチンパンジーよりも明らかに幸せじゃないんです。
神保 でも、それが人間の脳がここまで大きくなった理由でもあるそうです。チンパンジーの脳のほとんどが瞬間を把握するのに費やされているのは、ジャングルで生きていくためには一瞬の判断を求められるからだと。人間はその必要がなくて、代わりに脳を未来の心配に向けるということでした。これってアドラー心理学的には何か思われるところありますか。
岸見 今の話に引きつけられるかどうかわかりませんが、逆に今この瞬間を生きない人がいるというのはどういうことでしょう。薄らぼんやりとした光を今の瞬間に当ててしまうと、本当はそうじゃないけれど何となく先が見えるような気がするのではないでしょうか。しかし強烈なスポットライトを今ここに当てると、もう向こうは見えない。そういう生き方のほうが本来的かなと私は考えています。
神保 ただ「今この瞬間を生きる」というのは、一歩間違うと計画的に勉強して資格を取ったりすることを否定しているようにも聞こえます。そのあたりはどう考えたらいいですか。
岸見 計画は立てられないだろうと思いますが、「目標を持たなくていい」と言っているわけではありません。『嫌われる勇気』の最後に出てきますが、アドラーは「導きの星」ということを言っています。瞬間を丁寧に生きていくなかで、どんな状態であれ究極の「導きの星」を我々が目にしていればOKなのだと。
神保 目標は持っていいと。
岸見 その目標は「他者貢献」なんですね。自分のしていることが最終的にそこに向かっていることさえわかっていれば、あまり思い煩ったり迷ったりすることはないのです。
神保 たとえば「良い学校に入りたいから勉強する」というだけでは不十分で、良い学校に入ったうえでどうするのかが重要だと。勉強することで他者貢献への道を開くところまで考えて、いま一生懸命勉強すればよいわけですね。
岸見 有名大学に入るためだけに勉強している人は、人生を先延ばしにしていると思います。今この瞬間を大事にせず準備期間だとしか思っていない。そういう人は大学に入ったら、何も目標がなくなってしまうでしょう。
宮台 それで「親に騙された」と恨むわけですね(笑)。
岸見 そうですね。
神保 さらに言えば、東大に入ったことを高く買ってくれるような選択をするしかなくなりますね。選択肢がむしろ狭まる可能性もあり得ると。
岸見 今この瞬間を丁寧に生きて、結果的に振り返るとずいぶん遠くまで来たなということはあるはずです。天才たちは誰もがそうですよね。数学の問題を考えていたら時間が経つのも忘れたとかね。そういうことを積み重ねていけば、立派な業績を打ち立てられるかもしれないし、そうでないかもしれない。それはわからないけれど、とりあえずやることが楽しければいいと思います。そして、そういう勉強や研究が共同体に貢献することがわかっていれば、努力し続けられるのではないでしょうか。
宮台 社会学には「期待するから期待外れに打ちのめされる」というテーゼがあります。「未来のために現在を犠牲にしたのに、望んだ未来が到来しないのでバックラッシュして……」というのはよくある話。そうならないために……と人間的に頭を使い、「チンパンジーのように現在を生きつつ、人間的に未来を志向する」というのがアドラーの推奨でしょう。
本当の共同体に
関心をもつことの大切さ
神保 色々とありがとうございました。ここまでアドラー心理学および『嫌われる勇気』について話してきたわけですが、何か重要な点で抜け落ちていることはありませんか。
岸見 大丈夫です。ただ、これだけアドラーの名前が知られてきたことを単なるブームで終わらせたくないとの思いは強いです。アドラーが医師になることを選んだのは私腹を肥やすためではなく、「この世界を変えるためだ」と言っています。そういう彼の本来の精神が引き継がれることを望みます。個人の利害、自分自身への関心ではなく、本当の意味での共同体に関心を持てる人が増えて欲しいと思います。
本当の意味での共同体というのは、現実の共同体ではないわけです。国家でもありません。もっと大きな共同体の利害を考える必要がある。けれど最近の政治を見ているとそうでもないようです。そうした問題に『嫌われる勇気』を読んだ人が関心を持って欲しいですね。何もしないのは、結局、現状を肯定してしまうことですから。「世の中でいま行われていることはおかしい」といった怒りは、けっして感情的ではなく理性的な怒りなのです。
神保 個人的な怒りではなく、世の不条理に対する怒りはいいわけですね。
岸見 そうですね、世の不条理に対してはやはり声を上げないといけない。その一方で、足元もちゃんと見ていく必要があります。「人生の調和」という言い方をアドラーはしていますが、生きていく上でいろいろな調和が取れていなければならない。仕事が忙しいからといって、他のことが目に留まらないような生き方は問題なのです。
神保 宮台さんも何かありますか。
宮台 昨今ではアドラー心理学がビジネス分野で興味を持たれるようになりました。繰り返しになるけど大事な問題を申し上げます。自己啓発やコーチングやカウンセリングの本でしばしば「プライミング」の概念が使われます。目標を強く思念することで、それに引きずられて現在の優先順位が変わることです。アドラー心理学にも似た図式はあります。
では、強く思念すべき目標として何を選ぶべきか。この目標を他人に握られるとマインドコントロールされます。経営者の目標を自分の目標だと思い込まされるのが典型です。これは今日の主題である「課題の分離」にも抵触するおかしな話です。そういうタイプの自己啓発書とアドラーでは読後感が全く違うので、敏感に違いを嗅ぎ分けて欲しい。
神保 なるほど。僕が座右の銘に近い扱いをしている言葉に「I am the captain of my soul(私は自分の魂の指揮官である)」というのがあります。『インビクタス』という映画のテーマになった言葉です。ともするとすごく気負った感じに聞こえますが、アドラーの話と引きつけると非常によくわかります。つまり「AだからBできない」という原因論では、個人がAに支配されてしまっている。アドラーは「Bできない理由として、私がAを利用しているだけだ」と考えるわけですね。自分で「できない(cannot)」と思っているのが、じつは「やろうとしていない(will not)」だけだと言われたのはかなり身に染みました。
岸見 厳しいですよね。
神保 基本的に厳しいです。アドラー先生は。
岸見 『嫌われる勇気』を読んですごくよかったと言って下さる方は多いのですが、「本当かな」とちょっと思うときはあります。本当にわかると「これは辛いな」「聞かなければよかった」と率直に思う人もいるだろうなとは思います。
神保 いずれにせよ是非読んでみてください。いろいろと思うところがあると思います。人生を幸せにするためのヒントが得られるかもしれません。
宮台 岸見先生は『嫌われる勇気』『アドラー心理学入門』の2冊だけではなく、アドラーの翻訳もたくさん出しておられます。今はそれらもすべて手に入りますから是非読んで欲しいですね。アドラーの本はけっして難しくない。フロイトの本との違いです。
神保 それがアドラーの非常に大事にしたところのようですね。それでは長い時間ありがとうございました。
宮台 ありがとうございました。
岸見 こちらこそ、ありがとうございました。
(終わり)
岸見一郎(きしみ・いちろう)
哲学者。1956年京都生まれ、京都在住。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。専門の哲学(西洋古代哲学、特にプラトン哲学)と並行して、 1989年からアドラー心理学を研究。精力的にアドラー心理学や古代哲学の執筆・講演活動、そして精神科医院などで多くの「青年」のカウンセリングを行う。日本アドラー心理学会認定カウンセラー・顧問。訳書にアルフレッド・アドラーの『個人心理学講義』『人はなぜ神経症になるのか』、著書に『アドラー心理学入門』など多数。古賀史健氏との共著『嫌われる勇気』では原案を担当。
神保哲生(じんぼう・てつお)
ビデオジャーナリスト/ビデオニュース・ドットコム代表。1961年東京生まれ。コロンビア大学ジャーナリズム大学院修士課程修了。AP通信記者を経て93年に独立。99年11月、日本初のニュース専門インターネット放送局ビデオニュース・ドットコムを設立。著書に『民主党が約束する99の政策で日本はどう変わるか?』『ビデオジャーナリズム―カメラを持って世界に飛び出そう』『ツバル-地球温暖化に沈む国』『地雷リポート』、訳書に『食の終焉』などがある。ビデオジャーナリスト神保哲生のブログ
宮台真司(みやだい・しんじ)
首都大学東京教授/社会学者。1959年仙台生まれ。東京大学大学院博士課程修了。東京都立大学助教授、首都大学東京准教授を経て現職。専門は社会システム論。博士論文は『権力の予期理論』。権力論、国家論、宗教論、性愛論、犯罪論、教育論、外交論、文化論などの分野で著書多数。主な著作に『制服少女たちの選択』『終わりなき日常を生きろ』『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』『14歳からの社会学』『日本の難点』『「絶望の時代」の希望の恋愛学』などがある。宮台真司オフィシャルブログ
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年08月01日 21:30
まったく同感です、、、問われれば応えながら見護りつつ、自分力を自ら育む手助けをしていくこと。。。
■「ほめて育てよ」は間違い。
ほめることはその人を見下すことである
宮台真司×神保哲生×岸見一郎 鼎談第2弾(前編)
37万部のベストセラー『嫌われる勇気』の影響で一気に日本における知名度が高まったアドラー心理学。同書の著者・岸見一郎氏と、社会学者の宮台真司氏、ジャーナリストの神保哲生氏がインターネット放送番組「マル激トーク・オン・ディマンド」で繰り広げたトークセッションを2回に分けて掲載。
前編では現代日本の親子問題、恋愛問題、教育問題などをテーマに、「課題の分離」が不得意な日本人の特徴から、「ほめて育てよ」の嘘までをアドラー心理学を用いて語り尽くす!
すべての悩みは
対人関係の悩みである
神保哲生(以下、神保) 本日は、哲学者・岸見一郎先生をお招きしての「アドラー心理学」第2弾ということになります(第1弾は本連載の第9回、第10回をご覧下さい)。
宮台真司(以下、宮台) 第1弾は、「過去よりも未来」あるいは「トラウマよりも最終目的」という、わりと時間軸に沿った話をしましたが、今回は時間軸というよりも、むしろ人間関係のような空間性が主題になります。それゆえ第2弾が必要だということですね。
神保 人間関係ということでいうと、『嫌われる勇気』によれば「すべての悩みは対人関係である」と書かれています。しかし、自分が抱えている悩みには、対人関係じゃないものもあると感じる方もいるかもしれません。それでもアドラーは、すべては対人関係の悩みだと言い切る。岸見先生これはどういうことでしょうか。
岸見一郎(以下、岸見) 話をすると皆さんわかってくださるのですが、逆に言えば対人関係の問題だととらえないと、少しも問題が解決されないことのほうが多いはずです。対人関係の問題だとわかってしまえば、解決の糸口が見えてくることが多いのです。
神保 ほとんどの自分の悩みは、じつは対人関係の文脈に落とし込めるということですか。
岸見 そうです。
神保 自分だけでただ悩んでいるようなもの、たとえば自分のキャリアのこととか、体型のこととか、そうしたこともやはり対人関係だと。
岸見 体型なんて、人との関係がなければ問題にならないでしょう。
神保 たしかに、一人で生きていればね。
宮台 誰も見ていませんからね。
岸見 性格もそうです。性格は対人関係のなかで決まるものです。もし一人で誰とも接することなく生きているのであれば、性格は問題になりませんし、体型だって誰も気にしない。痩せようとも太ろうとも思わないはずです。
宮台 「共同体感覚」など今回扱う重要な問題と関係するので、裏側から言っておきます。僕は1980年前後に自己啓発セミナー──アメリカで言うアウェアネス・トレーニング──を体験しました。当初は受講者もスーパーエリートが多く、ファシリテイターが、体験の組織化と、理屈の説明を、織り交ぜながら進行するものでした。
最も重要なものの一つが「過去、一番自分が楽しかったことを、ありありと思い描く」というリマインディング・プログラム。これをやる前にダイアド(二人一組)のセッション等を通じて受講者は変性意識状態に入ります。その後、時間をかけて頭の中の鍵を外し、過去を思い出す。すると、皆がブワーッと声をあげて泣き始めるんです。
その後、皆で体験をシェアするのですが、それを通じて僕は、最も楽しかったことや幸せだったことも、すべて対人関係に由来することを学びました。どんなに辛い家族関係を生きてきた人も、むしろだからこそ、この上なく幸せだったことや希望を抱いたことを覚えている。それらはすべて対人関係に関わる幸せや希望なのです。
いつも厳しくて暴力を振るうお父さんが、珍しくこんなことをしてくれた。仲が悪かった両親がたった一度子どもたちを連れて海に行ってくれた。すべての悩みは対人関係の悩みですが、だからこそ、いちばん幸せな記憶もすべて対人関係の幸せです。それがアドラーのいう最終目的に関係するのですね。
前回、岸見先生が説明してくださったけど、アドラーは、究極の最終目的を思い描き、それによるプライミング(先行の学習や記憶が後続の事柄に影響を与えること)で現在の優先順位を変えるよう推奨します。この場合のリスクは、最終目的を他の人に操縦されること。たとえば、アドラーを持ち出す経営者は、従業員の最終目的を操縦しようとします。
最終目的を他人に操縦されないためには、過去の幸せがもっぱら対人関係に由来していることをわきまえ、自分が過去にいちばん幸せだと感じたことに矛盾しないように最終目的を設定するのが安全です。繰り返すと、悩みや苦しみにおいても、希望や勇気においても、対人関係が最も重要なファクターになります。
「課題の分離」とは何か
神保 対人関係に関連して、アドラー心理学の非常に重要なキーワードに「課題の分離」というのがあります。これについて触れていきたいと思います。
宮台 社会学者として言うと、「課題の分離」は日本の社会にありがちな弱点に関係します。親が、子どもの課題と自分の課題の区別がつかなくなり、それによって子どもも、親の課題と自分の課題の区別がつかなくなる、というのが、最終目的を他人に握られるケースの典型です。
神保 その「課題の分離」について、できれば具体的な事例で、岸見先生は実際にカウンセリングをやられているので、その実例を引きながらご説明いただけますか。
岸見 アドラーは、「あること」の結末が最終的に誰に降りかかるか、あるいは「あること」の最終的な責任を誰が引き受けなければならないかを考えたとき、その「あること」が誰の課題であるかがわかる、という言い方をします。具体例をいうと、私は「勉強することは誰の課題か」と、実際にカウンセリングの場面で親に尋ねます。自分の子どもが勉強しないからと相談に来られる親御さんは非常に多い。そこで、勉強しないことの結末は最終的に誰に降りかかるか、あるいは最終的な責任は誰が引き受けなければならないかを考えてもらい、「勉強をするかしないかは、誰の課題でしょう」と質問するのです。
すぐに「それは子どもの課題です」と答える人は実はあまり多くない。「まぁ理屈としては子どもの課題ですよね」って首をかしげながら答える人が圧倒的に多いわけです。でも実際のところ、勉強しなければ困るのは子どもであって、別に親の頭が悪くなるわけではない。高校入試などで志望校の選択範囲がうんと狭くなるなど、責任は子どもが取らなければなりません。だから勉強は子どもの課題なのです。このことを親が認めれば、それまで無邪気にあるいは無意識に言ってきた「勉強しなさい」という言葉は、言ってはいけないし、そもそも言えないことになります。およそあらゆる対人関係のトラブルは、人の課題に土足で踏み込むこと、あるいは踏み込まれることから起こるとアドラー心理学では考えます。
神保 では、勉強しない子どもに「勉強しろ」と言ってはいけないというところから始まるんですね。そもそも、自分の課題じゃないんだからと。
岸見 あるいは、言わなくてもいいということですね。
宮台 日本にも昔からそういう言い方はありましたよね。「困るとすれば自分だから、好きにすればいい」と。僕もいつもそればかり言っています。
神保 でも、そう言われても「はい、そうですか」と言えない親は多いですよね。やはり勉強してもらわなきゃ困る、いい学校に入ってもらわなきゃ困ると。それが子どもの将来のためだと。
岸見 そこがポイントです。要するに「あなたのため」というところが胡散臭い。自分のためなのです、率直に言うと。
神保 親が自分のために言っている。
岸見 でも、そうは言えないというか、言いたくないので、「あなたのためを思って言っているのよ」などと言葉を補足しながら、「勉強しなさい」と親は言うわけです。
宮台 ここは重大なトラブルに結びつくポイントです。僕は性愛ワークショップで〈親への恨み〉をキーワードにします。実際それが障害になっているケースが大半です。親の言う通り、つまり親の課題と自分の課題の分離に失敗したまま、一生懸命勉強する。「勉強して東大に入れば、あとは何でもできる」と言われてきたとします。
で、実際、東大に入ったけど、モテないし親友もできない。人間関係を自由にハンドリングして青春を謳歌する周囲を見て、妬み嫉みなど浅ましき感情に駆られた挙げ句、「ママの言う通りにしてきたのに、話が違うじゃないか!」となる。これは依存的暴力としての家庭内暴力につながります。〈親への恨み〉の背後に「課題分離の失敗」があるんです。
神保 では、勉強しなさいと言ってはいけないとして、それで終わりですか? その次のアドバイスはないんですか、親に対して。
岸見 その次はあるのですが、あまり言いたくはないです。カウンセリングだと「勉強しなさいと言ってはいけない」でとりあえず終わります。で、どうなったかを次回に報告してもらう。
神保 なるほど。
岸見 とりあえず1週間経ってからもう一度お聞きすると、「やはり勉強しません」と言われる。「でも子どもが勉強しないからといってあなたは困らない。勉強しない人生も美しい人生ですよ」と、僕は断言します。いずれにせよ、親が子どもの人生を生きるわけではないので、「とりあえず、勉強について話すのをやめませんか」と、さらに言います。
実際はその次がないわけではありません。つまり、本来は子どもの課題であるものを、親と子どもの共同の課題にするのです。それは不可能ではない。ただ、それを言ってしまうと、親は何でもかんでも共同の課題になると勘違いして平気で子どもの課題に介入するので、あまり言いたくはありません。
先ほど言いましたが、人の課題に土足で踏み込むこと、踏み込まれることから、対人関係のトラブルは起こります。土足で踏み込まなければ、対人関係がこじれるリスクはある程度避けられます。だから土足で踏み込まず、共同の課題にする手続きを踏めばいいわけです。具体的に言うと「最近のあなたの様子を見ていると、あまり勉強しているようには見えません。そのことについて一度話し合いをしたいのですが、いいですか」と伝えるのです。
神保 子どもに?
岸見 はい。多くの場合「嫌だ」と言われますよね。そうしたら、「事態はあなたが思っているほど楽観できる状況だとは思わないけれど、またいつでも相談したいことがあれば言ってください」と、それで終わらせるしかないですね。
「共同の課題」が
生みやすい勘違い
神保 「共同の課題」ですが、あまり早くそこにいってしまうと、何でもかんでも共同の課題にして、結局は相手の課題に踏み込むだけになりかねないですよね。これはどうしたらいいんでしょうか。まずは人の課題と自分の課題をはっきり識別できるようにして、そのうえで共同の課題を話し合って決めるというプロセスに入るということですか?
岸見 というか、協力関係に入るのです。
神保 協力関係?
宮台 一足跳びに「共同の課題」に行くと勘違いが生じると岸見さんがおっしゃったことがポイントです。自分が日頃何をやっているかをモニターできるようになることが、まずは大事です。それができないと大きな勘違いにハマる。「共同の課題」の御題目で「課題分離の失敗」が正当化されるからです。
神保 頼まれもしないのに相手は助けを必要としていると勝手に判断することが問題ということですか?
岸見 それはありますね。私の息子が小学生のときにこんなことを言いました。私が「甘やかしってどういうことかわかる?」と聞いたら、少し考えて「頼まれもしないことをすること」だと。正解ですね。多くの親はそういうことを平気でやっている。
神保 先生はご著書のなかで、友人のお嬢さんが泣きながら帰ってきたとき、「何かできることはある?」と親が聞いたら、「leave me alone」と言ったという話を引いていますね。
宮台 「課題の分離」に成功した親が「できること」とは、「放っておくこと」だという話です。ここに、若い人の性愛状況が関係します。「ソクバッキー問題」として知られるように、恋愛相手を束縛するヘタレたちが増えています。なぜ相手を縛ろうとするのか。そこにもやはり「課題分離の失敗」があります。
近代の性愛は、二人で同じものを同じように体験したい、つまり一体化したいという目標と関係します。ところがソクバッキーはその目標を間違って解釈するのです。「なぜ君と僕で意見が違うんだ、なぜ僕に従わないんだ」などと。たとえば「その髪型は君に似合わないって言ってるじゃないか」と。「課題の共有」どころか「相手の操縦」です。
神保 自分の好みを押しつけているだけだよね。
宮台 昨今の若い人を見るとそうした貧しい性愛コミュニケーションをする輩が大半です。だから僕は「ナンパをして成功するところまでは前半部分にすぎない」と言います。実際ソクバッキーのナンパ師が珍しくない。ちなみに僕は「後半部分は、相手の幸せに寄り添うべき相手にダイブできるようになること」と言います。アドラーの言う「協力」です。
「共同の課題」にすべきこと、
すべきでないこと
神保 課題の分離は簡単にできるものでしょうか?
岸見 よく考えればすぐ理解はできるはずです。でも、あまり理解したくない人が多いのかもしれないですね。先ほど言いましたが、課題の分離について説明すると、多くの親はそれを認めつつも首をかしげるわけです。
神保 そうでしたね。
岸見 言われればわかるのです。言葉ではわかる。けれど認めたくないという人が多い。
宮台 それは認知的整合化のなせるワザです。そうした親の場合、子どもの課題と自分の課題を混同することで自分の人生目標が与えられ、それによるプライミングで今の優先順位が決まっている。だから、子どもと自分の課題が別だと認めた瞬間、「あれ、私は今日からどうやって生きていけばいいんだろう」となる。だから認めたくないんです。
神保 自分の人生を生きていなかったわけですね。
宮台 そのとおりです。
神保 とはいえ岸見先生、「自分からはあまり勉強しないタイプだったけれど、親からうるさく言われたので仕方なく勉強した。そのお蔭で今はそこそこの状況にある」と思っている人はけっこういると思うんです。僕なんかも親に言われなきゃ全く勉強しなかった気がする。それはどう考えたらいいですか。
岸見 それは「お蔭で」と言えるような意味で成功したり何かを達成ができたからそのように言うわけであって、逆のケースのほうが圧倒的に多いかもしれません。結局、自分の人生なのに自分で責任を取らず親任せにしている。たまたま結果が世間的にいう成功だっただけですよね。
神保 「お蔭で」っていうのは、逆のケースだと「せいで」になるわけですね。
岸見 そうです。
宮台 神保さんだって、言われなくても高校2年生から突如勉強し始めることもあり得たでしょう。
神保 ああ、当然そうでしょうね。
宮台 親に言われて勉強した結果、そうなったと思っているけど、実際には他のルートを通ってもそうなったかもしれない。あるいは、もっとよくなったかもしれないわけです。
神保 たしかに、親に言われたからこの程度しか勉強しなかったのかもしれないしね。
宮台 「〜のお蔭で」は、問題を過去に帰属させたり他者に帰属させたりする外部帰属化です。子どもにとっては責任逃れで、親にとっては自分の手柄にする夜郎自大化です。
神保 しかし、「これは共同の課題にすべきこと、これは私の課題、これはあなたの課題」といった判断は難しいですね。
岸見 カウンセリングに来られる方を見ると、一方で本来はすべて自分の力でやるべきことまで他者に依存してしまうタイプの人がいます。他方で本当は援助が必要なのに援助を求めない人も多い。
神保 つまり助けを求めない?
岸見 人間は一人では生きていけないことを大前提にすれば、できることとできないことの見極めをきっちりとつけるのが大事です。できないことまでできるという人も困りものです。だからこそ課題を分けていく作業は絶対に必要なのです。
神保 まずは、自分にできないこととできることを見極めて、できないことだった場合は、共同の課題にして欲しいと意思表示するんですか?
岸見 そうです。だから、そういう意思表示を子どもからしてきたときは、共同の課題にしていいと思います。それは比較的安全なのですが、親が子どもの課題を共同の課題にしようとするケースは非常に危険です。親は子どもに対して「何かできることはないですか」と常に言っておけば十分です。そして、子どもが何も言ってこなければ何もしないほうがいいのです。
横の関係/縦の関係と
共同体感覚
神保 アドラー心理学では、縦の関係と横の関係ということもすごく言われます。たとえば、親が「子どもによかれと思って」というようなのは縦の関係で、それでは問題は解決しないと。とはいえ、親からすれば子どもとの関係は縦が当たり前だと思っているところがあるでしょうし、人生経験も親のほうが豊富なわけです。それでも、「いや、そうではなく、横の関係つまり対等であるべきだ」という。その点を説明していただけますか。
岸見 親と子どもが同じだと言っているわけではありません。知識も経験もたまたま先に生まれたので、子どもよりは親のほうが多少はあるでしょう。そういう意味では同じではない。また、取れる責任の量が違います。たとえば、ある家庭に門限があるとします。小学校1年生の子の門限が夜10時ということはあり得ない。責任が取れませんから。けれど、もしその家庭に門限というものがあるのならば、子どもだけでなく父親にも門限がないと対等とは言えないということです。
神保 父親は遅い時間でもいいけど、門限はやっぱりなきゃいけないと。
岸見 そうです。親と子は違うけれど、人間としては対等だと言いたいのです。
宮台 アドラー心理学のキーワードは、岸見さんの『嫌われる勇気』のタイトルにある「勇気」に加えて、「責任」です。前回の話にも出たように、過去ならぬ未来の引力に自分が引っ張られる場合に「勇気」が出るわけです。これに対し、課題の分離は「責任」の問題に深く関わります。
やはり恋愛がわかりやすい。プラグマティストが重要視するような、利害損得の〈自発性〉を超えた、内から湧く力である〈内発性〉──利他性や貢献性── の本質は、アダム・スミスが言うシンパシー(同感)に当たります。「相手が喜ぶことが自分の喜びになり、相手が悲しむことが自分の悲しみになる」という感情の働きです。
この同感可能性にとって、親子や先輩後輩や上司部下のような縦の関係は、雑音になります。なぜなら、「何かしなければ」という義務倫理的なものが入り込むからです。ちなみに哲学では、義務倫理と徳倫理を分けます。義務倫理学は、カントの無条件命令が典型ですが、「〜しなければならない」という義務的命令を重視します。
これに対し、内から湧く力である「内発性=ヴィルトゥス(徳)」を重視する徳倫理学は「〜しなければならない」でなく「〜したくてたまらない」という感情を重視します。上下関係や、横関係でもルールで縛られた関係だと、感情の次元が義務に乗っ取られます。むろん僕らは義務を引き受けて社会生活を送りますが、問題はその引き受け方です。
〈内発性〉に発する喜びゆえに引き受けるか。義務の観念に縛られて引き受けるか。フロイトなら「超自我」という形でやはり義務の次元を重視します。超自我は心の中で抑圧を担います。フロイトには強迫的な「義務」からの解放という主題が出てきますが、引き受ける「責任」の話がない。「責任」を引き受けるには〈内発性〉が必要です。
神保 『嫌われる勇気』では縦と横の関係に関連して、「共同体感覚」という話が出てきます。縦の関係では共同体感覚が実現できないと。そこのところ説明していただけますか。一般的に言われているコミュニティ的な意味での共同体と同じなのかも含めて。
岸見 共同体感覚(Gemeinschaftsgefühl)という概念は、この言葉だけではそれが何を意味するかわかりません。アドラーは、これを「ミットメンシュリッヒカイト」(Mitmenschlichkeit)とも言い換えています。「人と人」(Menschen)が「共にある」とか「結びついている」(mit)という意味です。そういう関係を考えたとき、それは縦ではあり得ない。横でしかミットはできないと私は理解しています。
宮台 「課題の分離」と関係づけます。社会システム理論では、融合(フュージョン)と、分離されたものの統合を、区別します。レヴィ・ブリュールによれば、未開社会にも共同体がありますが、そこではフュージョンがポイントになります。「自分と他者」の融合や、「人と物」の融合です。
近代社会では「自己と他者」も「人と物」もいったん分離されたので、上からあるいは外からの統合要求は、抑圧を生みます。そうではなく、「課題の分離」を達成した人たちが、〈内発性〉ゆえに相手と同じことを喜ぶのが、良い。相手の喜びが自分の喜びになる相互的な関係を軸としたとき、初めて「課題の分離」と矛盾しない共同体が見えてきます。
神保さんが言った「共同体」は、「課題の分離」と矛盾する抑圧的なものです。日本にはそれが目立つのです。たとえば学校では「君はなぜ自分の目標ばかり言うんだ」「皆で同じ目標を達成しようと頑張ってきたじゃないか」と体育会的です。それも共同体と呼ばれますが、「課題の分離」が貫徹したアドラーの言う共同体の、反対物です。
ほめることは
相手を見下した行為
神保 僕は意外だったんですが、アドラー心理学では「ほめるのはダメ」なんですね。ほめるのは縦の関係だと。
岸見 はい。そのことを知らないと、「叱らずにほめて育てよ」と皆が言うので、多くの親は子どもをほめて育てます。ところが、それではうまくいきません。子どもをほめるとはどういうことかをまず考える必要があります。たとえばカウンセリングに母親が3歳の子どもを同行してきたとしましょう。カウンセリングはだいたい1時間ぐらいなのですが、その間子どもは母親の隣で待たないといけない。子どもは自分が置かれている状況の意味を確実に把握できると僕は信頼していますから、1時間おとなしくしていたからといって驚きはしません。ですが親はひどく驚いて、カウンセリングが終わったときに「えらかったね」「よく待てたね」とほめる。では同じような状況で、夫のカウンセリングをしているときに妻が待っていたとしましょう。1 時間経って終わったとき夫は妻になんと言うでしょうか。
神保 「お待たせ」かな。
岸見 どうして「えらかったね」と言わないんですか。
神保 ああ、そうですね。子どもだったら言うのに。
岸見 そこがポイントなのです。「子どもは待てない」と思っているわけです。それなのに思いがけず待てたから「えらいね」とか「よく待てたね」という言葉を発する。でも大人同士でそんなことを言ったら失礼じゃないですか。だから「ほめる」というのは、能力のある人が能力のない人に下す評価の言葉なのです。
神保 「ほめる」というのは、上から下だと。
岸見 縦関係が前提ですね。横の関係だと絶対にほめはしない。
神保 しかし「勉強しなさい」と言ってはならず、自分で勉強しているのを見て「えらいね」と言ってもいけない。どうしたらいいんでしょうか。
岸見 たとえば今の場面だと、大人同士ならなんて言うでしょうか。もちろん「お待たせ」でもいいですが。子どもも言われて嫌ではない言葉がけはなんでしょう。
宮台 僕だと「ありがとう」かな。
岸見 そうですね。「ありがとう」がすぐに出てくる人は少ないです。「ありがとう」というのはほめているのではなく、子どもの貢献に注目した言葉です。1時間おとなしくして親に貢献したということを子どもに伝えているわけです。貢献を伝えられた子どもは、自分に価値があると思えます。「ああ、自分は人の役に立ててよかったな」と自分の価値を認められるようになる。ところが、ほめられた子どもは自分に価値があるとは思わない。どこか馬鹿にされたような気がする。なぜかは子どもにはわからないでしょうが。
神保 では、ほめれば喜ぶだろうと思うのは間違いですか。
岸見 間違いです。小さな子どもさんを観察すればすぐわかることですが、ほめられた子どもはすごく嫌な顔をしています。それを知らないから親は観察しませんが。われわれ大人がもし「えらいね」と言われて嫌であれば、子どもも嫌なのです。それなのに大人と子どもは違うというのは、差別の論理だと私は思います。
神保 逆に、ほめられると喜ぶような子どもだと要注意ですか。
岸見 要注意です。
宮台 普通に敏感なら、「よくできたね」って言われたら、「できないと思っていたんだな」と感じます。大人に言わないのは、それが伝わっちゃうことを知ってるからです。ならば、なぜ子どもには伝わらないと思っているのか。子どもはほめるものという思考停止があるからでしょう。こういう思考停止は性愛コミュニケーションにもよくあります。
神保 ほめられると喜ぶ子どもは、できないと思われていることをなんとも思わず、縦関係に満足しているのだと。
岸見 そうですね。だからそういう子どもは、上司にお世辞を言って気に入られたがるような大人になるかもしれない。
神保 うーん、なるほど。
岸見 そうした子どもは、「ほめて、ほめて」と言います。親が意識的に「ありがとう」や「助かった」というような子どもの貢献に注目する言い方をし始めても「どうしてほめてくれないの」と。そういう子どもには「私はあなたをほめない。なぜなら、ほめることはあなたを家来や子分にすることだから。私はあなたを家来にも子分にもしたくない」とはっきり言うべきだと思います。
「見る神」が
いない社会の課題
神保 岸見先生は、縦の人間関係が精神的な健康を損なう最大要因であるとも書かれています。
岸見 そう思いませんか。縦の関係では、絶えず上の人の顔色を窺わないといけない。自分の言うことが気に入られるかどうかを気にするのはかなりしんどいですよね。
宮台 人間は、人が見ているとちゃんとするけど、見ていないとズルをする動物です。実験でも確かめられてきました。だから、この性向を利用した制度があります。国家機密をアメリカなら25年、ヨーロッパの多くの国なら30年で情報公開するルールがありますが、いずれ情報公開されると知っていれば、私利私欲の暴走が抑制されるからです。
社会システム理論の視座から言えば、「見る人」がいないとちゃんとできない成員が大半である社会は、一定以上は複雑になれません。絶えず対面制御が要求されるので、コミュニケーションの文脈が制約され、取引コストが上がるからです。コミュニケーションを文脈自由にするために必要な信頼を調達できないということです。
部族段階(原初的社会)から文明段階(高文化社会)へと複雑化した社会は、大半が「見る神」の表象を持ちます。代表的なのは、ユダヤ教の神やキリスト教の神やユダヤ教の神です。これら3つは同一神ですが、この唯一絶対神に限られません。日本で「お天道様が見ている」とか「ご先祖様が見ている」という場合も、「見る神」を持ち出している。
前ローマ教皇ベネディクト16世が、キリスト教の唯一絶対神──「主」ないし「神の中の神」──の本質は「見る神」で、罰や報償を与える神ではないと述べています。罰や報償に関係なく、「見る人」を前にすれば、人はシャンとするのです。あるいは「見る人」がいなくても「見る神」がいればシャンとします。
神を持たない社会、あるいは神が死んだ社会ではどうなるか。それを課題としたのが、プラグマティズムの社会心理学者ジョージ・ハーバート・ミードです。ミードについてよく知られているのが、「I」と「Me」の対立概念です。その含意を日本では社会学者でさえ理解していないので、ここで紹介します。
ミードは、「Me」とは「自分が見た自分」で、「I」とは「自分が見た自分に対する反応」だと言います。たとえば、「自分が見た自分」が浅ましく見えたことへの反応として「浅ましいことはやめよう」という意欲が湧いたりするのが、そうです。こうして、「見る神」が存在しなくても、「見る自分」の存在によって、自分がシャンとすると考えたのです。
では、「Me」の浅ましさに対して適切に反応する〈内発性〉としての「I」は、どう形成されるか。ミードは、ロールテイキング(役割取得)をもたらすロールプレイ(ごっこ遊び)が重要だとします。たとえば、僕らが子ども時代のアニメでは「卑怯者!」がキーワードでしたし、子ども同士のごっこ遊びに「卑怯だぞ!」という物言いが頻繁にありました。
そうした罵声自体がネガティブなサンクションになって、子どもらは、「一般に人はこういう振る舞いを卑怯だと思うこと」や「そう言われると誰だって嫌だと思うこと」を学びます。これをミードは「一般的他者の役割を取得すること」と表現します。そうやって子どもらは立派な大人になっていく。ところが今は「卑怯」という言葉は死語です。
神保 ほんと、聞かないね。
宮台 そう。「立派」と「卑怯」という対立概念が消えて、「うまくやるヤツ」と「やれないヤツ」の対立だけになりました。そこに、ロールプレイが貧弱だという「ロールテイキングの貧しさ」ゆえの、コミュニケーションの貧しさが見出せます。それが貧しいのは、「Me」に対する適切な反応としての、共同体感覚に満ちた「I」が不在だからです。
ミードは、ごっこ遊びのロールプレイを通じて「一般的他者の役割」つまり共同体感覚に満ちた「I」を習得する過程で近接する他者たちとの関係性が不可欠だと考えましたが、最終的には近接する他者たちが必要なくなる、つまり周りに人がいてもいなくても大概の人がそう見るように自分を見て反応できるようになる、としています。
岸見 縦の関係が前提の「ほめる、ほめられる」について補足しますと、ほめられて育った子どもは、ほめる人がいないと適切な行動をしなくなります。ゴミが落ちていれば普通拾いますよね。でも、そうした子どもはまず周りを見ます。そして目撃している人がいれば拾ってゴミ箱に捨てる。それは精神的にあまり健全だとは思えないですよね。誰も見ていなくてもちゃんとゴミを拾う子どもになって欲しい。だからほめることは望ましくないとアドラー心理学では考えます。
宮台 ある程度複雑化した社会には、他人に見られない振る舞いがいっぱいあります。もし人が見ていなければ何でもアリになるようであれば、複雑な社会は到底存続できません。「見る人」がいなくても、「見る神」ないし「見る自分」の存在ゆえにきちんと振る舞えることが重要になります。
その場合も、「見る神」や「見る自分」が、「損得勘定」を超えた「内から湧き上がる力」をもたらすのが良い。つまり〈自発性〉ならぬ〈内発性〉をもたらすのが良い。初期ギリシアが「見る神」を否定して「見る自分」を鍛えようとしたのは、「見る神」が「罰する/褒美をくれる神」になると、損得勘定が優位になりがちだからです。
ベネディクト16世ことヨーゼフ・ラッツィンガーが、主なる神は「見る神」であっても「罰する/褒美をくれる神」ではないと強調するのも、ルカによる福音書10章25節以降の「善きサマリア人の喩」などを通じて、こうしたギリシア的思考を意識するからです。ちなみに全てコイネーギリシア語で書かれた福音書にはギリシア的思考の影響があります。
いずれにせよ、人が見ているからちゃんとするのと、人が見ていないときに内から湧き上がる力でちゃんとするのとでは、動機づけの文脈依存性が違います。後者は社会的文脈をオープンにし、社会の進化を支えます。ミードによれば〈内発性〉の不在は、子どもの成長過程における故障です。岸見先生が「健全ではない」とおっしゃることに重なります。
(続く)
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年07月28日 06:20
また旅立つ君へVol.51/かつての途に迷う旅から、、、Vol.2
予期せぬ出会いと出来事は
今日までの自身との別離と
明日の新たな自身との出会い
Posted by nob : 2014年07月27日 19:02
また旅立つ君へVol.50/旅立ちの時はいつも唐突に自ずと訪れる。。。
やりたいことが見つからない時には
その時々目の前の与えられた事柄に鋭意専心することから、、、
そして本当にやりたいことを見つけたのなら
先送りせずにすぐに着手一意専心していくこと。。。
Posted by nob : 2014年07月20日 21:55
まずは毎朝のウォーキングと舞夜就寝前のストレッチから、、、身体と生活にリズムが生まれてきます。。。
■「眠れない、食べられないのに夏太り」に注意
ぐっすり眠れないと、「脂肪分解力」が7割も減少!
安達 純子 :医療ジャーナリスト
「ちょっと体調が悪くて……」「なんか最近体が……」こんな悩みを抱えているビジネスマンは多いはずだ。だが忙しい企業戦士のみなさんのこと、気軽に休暇を取得して病院で1日じっくり検査、というわけにはいかないだろう。大抵、「寝れば治る」で、放っておいてしまう人が多い。
だが、ちょっと待ってほしい。その病気になる直前の“病気もどき”こそ体のSOS信号なのだ。この連載では看過することのできない”病気もどき”について、医療ジャーナリストの安達純子氏が解説する。
ぐっすり眠れないと、脂肪分解力が7割減に!
熱帯夜では、布団に入っても、「暑くて眠れない」といったことになりがち。エアコンを低めに設定し、ウトウトとしたものの、寒過ぎて夜中に目が覚める。再びエアコン調節をして寝ても、しばらくすると暑くて再び起きてしまう。当然のことながら寝不足。こんな状態を繰り返していると、翌日の仕事のパフォーマンスに悪影響を及ぼすだけでなく、ふと気がつくと、お腹周りに脂肪がプヨプヨ。夏太りにまで結びつくという。寝不足で体力低下のはずが、脂肪だけはしっかりと体内に蓄積されていく。その原因とはなにか。
「ダイエット外来の寝るだけダイエット」(経済界刊)の著者で、日本肥満学会会員、佐藤桂子ヘルスプロモーション研究所所長が説明する。
「寝ている間に分泌されている成長ホルモンは、一晩で約300キロカロリーの脂肪を分解します。ところが、ぐっすり眠れないと、成長ホルモンの分泌は「通常の3割」に減り、90キロカロリー程度まで脂肪を分解する能力が落ちてしまうのです。一方、真夏の外気によるストレスや寝不足は、自律神経の働きを乱します。本来、肥満細胞から分泌される『レプチン』は、交感神経の興奮と連動して、食欲の抑制や脂肪燃焼に関係していますが、自律神経が乱れると分泌量が減ってしまうのです。
逆に、胃から分泌されて食欲に関与する『グレリン』という物質は増加します。眠れなくて成長ホルモンが減り、脂肪燃焼がしくにくだけでなく、自律神経の乱れで、脂肪燃焼は制御されて食欲は増すといったことが、真夏には起こりやすいのです」
「そうめん&アイスだけ」は、やってはいけない
自律神経が乱れてグレリンの分泌量が増えると、食欲は増す。しかし、灼熱の太陽が照りつける中、夏バテで食欲は減退しがちという人もいるだろう。そんなときに食事で選びやすいのが、そうめんやアイスなど、のど越しの良い食材。ガッツリとした丼物よりも、カロリーは低いように見えるのだが、夏太りに拍車をかけることがあるそうだ。
「夏場は、汗と一緒にビタミンB群が失われやすいのです。ビタミンB群は、脂肪燃焼に欠かせないのですが、汗で失われると同時に、そうめんやアイスといったのど越しのよい食材からは、体内に補給することができません。ビタミンB群不足で脂肪が燃焼されにくくなることが、夏太りを後押しするのです」(佐藤所長)。
そうめんやアイスばかり食べていると、糖質ばかりを体内に入れることになる。糖質は、本来、エネルギー源となるが、夏場は基礎代謝も落ちやすい。基礎代謝というのは、安静の状態でも消費されるカロリーのこと。
「真夏は、外気の影響を受けて基礎代謝が落ちます。冬場はエネルギーで体温を高める必要がありますが、夏場は体温調節のための代謝は、外気温が高いゆえに冬場と比べて必要ありません。基礎代謝が落ちるため、冬場と同じ食事量でも、夏場は太りやすいのです」(同)。
人間の身体は、体温を一定に保つ仕組みになっている。外気が10度以下の冬場は、体温を36度前後に保つため、脂肪を燃焼してエネルギーに変える。ところが、夏場の外気35度以上では、体温を自然に上がるため、脂肪を燃焼する必要がなくなるというわけだ。
基礎代謝が落ちていると、エネルギーとして使われる量が少ないゆえに、そうめんやアイスなどでとった糖質は体内で脂肪となって蓄積されやすい。ビタミンB群不足で燃焼もされず、寝不足では成長ホルモンによる分解も期待できない。食欲を増すグレリン分泌量が増えていると、糖質への食欲も増す一方。結果として、夏太りへの一途をたどることになる。
効果的な「夏太り予防法」と「解消法」とは?
佐藤所長によれば、夏太りの予防と解消法は次のとおり。
① 寝つきをよくするために、寝る2~3時間前にウォーキングやラジオ体操などで身体を軽く動かす。運動習慣のない人が、ジムなどでハードトレーニングを行うと身体に悪影響を及ぼし、逆効果になるため、軽い運動にとどめる。
② ビタミンB群の補給のため、レバニラ炒めや豚肉の生姜焼きなど、ビタミンB群の豊富な食材を積極的に食べる。ただし、副菜は肉類に偏ることなく、肉や魚とバリエーションに富んだメニューが良い。
③冷たい飲食は身体の基礎代謝を落とすため、なるべく温かいものを食べるようにする。食事は、ご飯、みそ汁、おかずが基本。
④ 野菜も温野菜がベター。発酵食品のみそ汁の中に、野菜類をたっぷり入れると、腸内環境を整えて自律神経の乱れも解消しやすい。
⑤食生活の改善が難しいときには、食欲調整ホルモンへの作用が期待されるサプリメントを活用するのも一考だ。
「仕事などでストレスがあると、脳内物質のセロトニンを増やそうとして、脳が甘いものへの食欲を増幅させます。寝る前にアイスなどを食べるとホッとするという人はいるでしょう。しかし、寝る前に身体を冷やすと寝つきが悪く、基礎代謝も落ちるなど、短時間で体重が増やすことに結びつきます」。
「ストレス解消のアイスを食べるなら、昼間にしましょう。そして、バランスの良い1日3回の食事と十分な睡眠時間を確保することで、夏太りから身を守っていただきたいと思います」と佐藤所長は話す。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2014年07月19日 21:40
また旅立つ君へVol.49/持たざる豊かさ、、、彼には及びませんが私も実践中です。。。
■【特集:移動】「15個の持ち物」だけで暮らす新しいライフスタイル
移動をするには、捨てる覚悟をもつこと。15のグッズしか持たないで暮らす男。
シンプルにコンパクトに、暮らす。
大量生産に大量消費。ありふれたモノ、かかるコスト。
その中で暮らすことが、果たして幸せなのだろうか。
本当に必要な「モノ」というのは実は少ないかもしれない。その過程をもとに生活実験をした男がいた。
その人物は、米ニューヨークにいた。
彼は、たった15個の必要最低限の物しか持っていない。家を持たずに、ホテルを転々と移動して暮らしている。
彼が特に有名なのは、パンツと靴下を除いて15個の物しか所有していない点だ。彼が所持している品は次の通り。
バックパック
シャツ
レインジャケット
ランニング用ショートパンツ
Tシャツ
タオル
ウールジャケット
洗面用具
サングラス
財布
MacBook Air
iPhone 3GS(2011年5月当時)
ドレスシャツ
ジーンズ
ランニングシューズ (パンツ・靴下を除く)
ある時に、「ミニマル主義」に興味を持った彼は、持ちモノを100個に集約した。その時にほとんどのモノが必要ないことに気付き片っ端から捨てていった。
そして、今の15個にたどり着いたのだ。
シャツは2枚しか持っておらず、交互に着るようにすれば、ファッションに悩むことはなくなり、考える時間を省けるそうだ。
不確実性が支配するこれからの時代に、周りをモノで囲まれて動きにくい生活はリスクになる。
ここでいうモノとは、物質的なものでもあり、また本当はそこまで大切ではな いにも関わらず手放せないでいるプライドや偏見、 新しいことへの不安などだ。
本当に必要なものは実は限りなく少なく 、リュックサック1つにおさめることができる。
私たちは移動する生き物だ。そし て間違いなくこれから、大規模な移動がライフスタ イルの中に入ってくる。その際に、本当に大切なものだけを見極めて、それ以外は大切ではないという
「捨てる覚悟」を持っておく必要がある。
あなたにとって、
暮らしをしていく上で本当に必要なモノとは何だろうか。
まわりにあるモノを見渡して、是非考えて頂きたい。
[TABI LAVO]
Posted by nob : 2014年07月14日 21:19
また旅立つ君へVol.48/旅に出る、、、未知との出会い、、、自らへの気付き。。。
■【特集:移動】あなたは、間違いなく外へ飛び出したくなる!世界の格言10選
移動が加速化していく時代。その加速する流れについていくのか、置いていかれるのか。それとも敢えて乗らないのか・・・
移動する。そのアクション自体は簡単だが、時にはほんの少しの勇気が必要になってくることも。ここに集めた言葉たちが、あなたの背中を押してくれるはずだ。
さあ、今いる場所から、移動しよう!
まだ見ぬ、新しい世界に足を踏み出そう!
人生の冒険をはじめよう!
001
「世界は一冊の本のようであり、旅をしない者は本の最初のページだけを読んで閉じてしまうようなものである」
by アウグスティヌス
今、あなたのいる場所は、あなたの可能性を狭めているかもしれない。移動することで、道は開けてくるかもしれない。そう考えると、ページをめくらずにはいられないはずだ。
002
「人が旅をするのは目的地につくためではなく、旅をするためである」
by ゲーテ
どこへ行くかも大事だが、どのように行くかも重要だ。求めるべきは、結果ではなく過程。そこで得られる見聞こそが、あなた自身を形成していく。
003
「旅人よ、道はない。 歩くことで道は出来る」
by アントニオ・マチャド
どこかへ移動する際、前例を求めるなんて馬鹿らしい。自分で決めて、自分で動くことで、得られるものは大きいはずだ。
004
「あちこち旅をしてまわっても、自分から逃げることはできない」
by ヘミングウェイ
移動することは、決して逃げることではない。問題を解決するのは、移動した先の環境ではなく、自分自身だ。
005
「旅の過程にこそ、価値がある」
by スティーブ・ジョブズ
もちろん、その“価値ある過程”は、一歩踏み出した者だけが享受できる。
006
「希望に満ちて旅行することは、目的地にたどり着くことより良いことである」
byスティーブンソン
希望を持って動き出した。その時点で、あなたはもう何かを手に入れている。もしも行きたい場所へ行けなくても、だ。
007
「旅行するおかげで我々は確かめることが出来る。たとえ各民族に国境があろうとも、人間の愚行には国境がないと」
byアンドレ=プレヴォ
残念だが、世界中どこへ行っても、愚者はいる。ただし、同じ数だけの賢者がいることも付け加えておきたい。
008
「1000マイルの道のりのある旅路でも、最初の1歩から始めるべきである」
by Lao Tzu
とにかくスタートすることだ。そこで躊躇していては、何も始まらない。何も変わらない。
009
「旅に出て、もしも自分よりもすぐれた者か、または自分にひとしい者に出会わなかったら、むしろきっぱりと独りで行け。愚かな者を道連れにしてはならぬ」
by 仏陀
馴れ合いは何も生み出さない。 一歩踏み出す時には、孤独な決断が必要となる。
010
「長い旅行に必要なのは大きなカバンではなく、口ずさめる一つの歌さ」
by スナフキン
「歌=気持ち」と置き換えてもいいだろう。物理的なものが役立つ場所は限られるが、崇高な精神は、世界中どこへいこうとも普遍的な武器となる。
[TABI LAVO]
Posted by nob : 2014年07月14日 06:13
普通であること、、、それは普遍であること。。。
普通の人は
普通に生きているのが
いちばん幸せです
しかし
何事もなく
普通に生きいくのが
いちばん難しい
[天台宗/光前寺]
Posted by nob : 2014年07月09日 23:15
若者の未来を守ることは大人が最後まで果たすべき義務、同感です、、、死に様は生き様の完結、常日頃から考え備えることから。。。
■長生きすることは、本当に良いことなのか?
親の介護で未来を奪われる若者たち
竹井善昭
[ソーシャルビジネス・プランナー&CSRコンサルタント/株式会社ソーシャルプランニング代表]
社会保障が日本最大の社会問題になっていることは常識だと思われているが、十分に理解されているとは言い難い。先日も、とあるスーパーマーケットの前で、ある国会議員が辻説法を行なっていたのだが、盛んに公共事業の無駄をなくそうと訴えていた。
たしかに、クルマが通らない道路や、客が入らないどころか、そもそもイベント自体が行われないようなホールを作るのは無駄だ。そして、税金の無駄遣いをなくすことは重要な政治課題だ。しかし、日本の公共事業費は約6兆円。それに対して社会保障費は約110兆円である。日本の財政赤字問題解決のためには、公共事業よりも社会保障のほうがはるかに重要な問題なのである。しかも、社会保障費は削減が難しい。道路や建物の建設に反対することはできても、高齢者の福祉を削減しろとは誰もが言い出せない。しかし、そのことを真剣に議論すべきときが来ているように思える。それは、財政的な問題だけなく、わが国の若者たちの未来のためでもあるからだ。
介護で未来を閉ざされる
若者たち
最近、メディアが取り上げ始めた問題。それが、「若者による介護の問題」だ。つまり、親の介護のために、未来を奪われている若者たちがいる。この、これまで注目もされず、社会から見えなかった問題に光が当てられ始められている。たとえば、今年6月17日に放送されたNHK『クローズアップ現代』では、「介護で閉ざされる未来 ~若者たちをどう支える」と題して、タイトル通り、親の介護で未来を閉ざされた若者を紹介した。
番組に登場した25歳の女性の場合は、父親が病気により脳に障害を受け、身体が動かなくなった。食事も自分ではできず、寝返りも打てない状態に。当初は母親が介護していたが、その母親もガンを患う。父親の介護は娘であるこの女性の役目となる。彼女は当時、大学3年生。将来は福祉関係の仕事をしたいと国家資格取得のために勉強に励んでいたが、金銭的な負担も大きく、介護と学業の両立を諦めざるを得なかった。父親の病気がどのように進行するかまったく分からないため、将来の見通しも自分の未来もまったく見えないという。
また、番組では26歳の男性も紹介された。この男性は、母親が若年性痴呆症となり、4年前から徘徊も始まった。当時、この男性は就職したばかりだったが、介護と仕事の負担により体調を崩してしまう。そして、父親と相談した結果、会社を辞めて母親の介護に専念することにした。父親のほうが、収入が多かったためだ。
また、日経新聞でも、まさにクローズアップ現代と同日の6月17日に、「親の介護で未来を奪われる若者 ある20代の場合」と題した記事を掲載している。こちらで紹介されているのは29歳の男性。大学生時代に父親が若年性認知症を発症。当初は母親が介護していたが、父親の病状が進行。さらに同居していた祖母も認知症となり、介護の負担はさらに増えた。ちょうど就活の時期を迎えていたのだが、「システムエンジニアになりたかったが、諦めるしかなかった」という。
人はいかにして生き、死ぬべきか
このような、20代というキャリア形成の重要な時期に、親の介護のために「未来を閉ざされた若者」がどれほど多くいるのか。『クローズアップ現代』では、「去年、国の調査で、家族の介護を担っている15歳~29歳の若年介護者が、17万人以上に上ることが明らかになった」と紹介している。この 17万人という数字をどう考えるかは意見が分かれるかもしれない。しかし、この若年介護者の存在は、数字以上に若者の未来と人間の尊厳という問題を、日本国民に深く突きつける問題だ。人はいかにして生きるべきか、そして死ぬべきかという、哲学の問題である。
社会保障が単に財政的な問題だけであれば、解決策はあるかもしれない。もちろん、そう簡単ではないことは分かっているが、それでもお金の問題はお金で解決できる。しかし、若者の未来はお金だけの問題ではない。そして、高齢者の命とか尊厳の問題は、まさにお金では解決できない問題だ。若年介護者の問題。これは、誤解を恐れずに言えば、「若者の未来を、死にゆく者が奪うことの正当性」を問う問題である。
日本は高齢者に対して、非常に優しい国である。「過剰に優しい」と言ってもよい。そう言うと、反論したくなる人も多いことはよく分かる。老人福祉はまだまだ足りていないと主張したい人もいるだろう。もちろん、僕も日本の老人福祉が完璧だと言いたいわけではない。論じたいのはその「思想」だ。日本は、ある意味で過剰に人を生きさせようとする。そのことが、はたして高齢者にとっても若者にとってもよいことなのか、それで人は幸福になるのか、ということだ。
あまり知られていないようだが、欧米にはいわゆる寝たきり老人はいない。なぜなら、寝たきりになるような老人は延命処置をしない、つまり「殺してしまう」からだ。たとえば、イギリスでは、自力で食事できなくなった老人は治療しないという。福祉大国のイメージが強いスウェーデンやデンマークも同様だという。
また、これは聞いた話なので数字が不確かなのだが、ニュージーランドではある年齢(75歳だったかと記憶している)を超えると、病気になっても治療しないという。モルヒネを打つなどの緩和処置はやるが、それ以上はやらないということだ。実際に、スウェーデンの高齢者医療の現場を視察してきた医師のブログには、下記のように紹介されている。
日本のように、高齢で口から食べられなくなったからといって胃ろうは作りませんし、点滴もしません。肺炎を起こしても抗生剤の注射もしません。内服投与のみです。したがって両手を拘束する必要もありません。つまり、多くの患者さんは、寝たきりになる前に亡くなっていました。寝たきり老人がいないのは当然でした。
(読売新聞の医療サイトyomi Dr.「今こそ考えよう高齢者の終末期医療」より)
日本の病院で同じことをやれば、確実に「人殺し」扱いされて、マスメディアでもネットでも大炎上必至である。しかし、欧米ではこのような考え方がスタンダードなのだ。この差は一体何かと言うと、人の尊厳に対する考え方の違いだ。つまり、何が何でも生かしておくことが正義なのか、人の尊厳を守ることが正義なのか、という考え方の違いである。
人の尊厳をどう考えるかは、安楽死、つまり「死ぬ権利」を巡る議論の根幹となる問題だ。安楽死は基本的に自らの意志で死を選ぶことだが、認知症など、自分の意志では死を選べない場合もある。そのような場合は「殺される権利」というものも考える必要があるだろう。人は自分の尊厳を守るために、死ぬことを選んだり、殺されることを選ぶ権利があるのかもしれない。
病気になって初めて考えた
自分の死に様
もちろん、そんなことは死に直面していない人間が安易に考えたり、結論を出していい問題ではないし、出せるものでもない。僕自身、いざとなったときに潔く死を選べるかどうかは分からない。死を選びたいと思ってはいるが、いざとなったら怖気づくこともありえるわけだ。正直に言って、これだけは本当に死に直面してみなければ分からないと思う。
ただ、そこまでの重大な局面ではないが、最近、少しばかり死を意識するような状況に追い込まれてしまい、それなりのリアリティを持って自分の死に様を考える機会を得た。病気である。実は、昨年秋に心不全と判断され、しばらく経過観察で病院に通っていたのだが、3月から急激に悪化。たった50メートルの距離も歩けなくなり、4月に3週間、入院した。
通常、このような場合はカテーテル検査をするのが原因究明に最も手っ取り早くて確実なのだが、入院したところ、心臓と同時に腎臓の機能も悪化していることが分かった。しかしながら、心臓と腎臓はどうも相反関係にあるようで、簡単に言えば、心臓に良いことは腎臓に悪く、腎臓に良いことは心臓に悪い。だから治療が難しい。絶妙のバランスが必要とされる。心臓のカテーテル検査は腎臓に悪影響を与えることがあり、最悪の場合は検査が引き金となって人工透析が必要になるというリスクもあるという。
そのリスクを冒してカテーテル検査を行なうかどうか僕は決断を迫られていたが、正直、なるべくならそんな検査はしたくなかった。入院のおかげで体調はだいぶ良くなったこともあり、いったん退院して、外来で腎臓に負担をかけない検査を続けていた。しかし、GW明けにまた体調が悪化。もう待ったなしの状態となったため、透析のリスクを覚悟のうえでカテーテル検査を行なうことを決断。6月に再入院した。
普通なら3日で退院できるようなケースだが、僕の場合、透析のリスクを減らすために循環器内科の専門医が2人も担当。腎臓内科と連携しながら、点滴、酸素吸入のほかに、検査のために毎日のように血液採取しながら同時に輸血も行なうという、ちょっと矛盾を感じる処置などを慎重に行いながらカテーテル検査に挑んだ。そのため結局、2週間の入院となった。幸い、担当医の細心の処置のおかげで、腎臓への負担は最小限にとどまり、人工透析に至らずに済んだ。
ちなみに、カテーテル検査の結果、冠動脈閉塞などの重大な欠陥は見つからず、「心不全の原因は何か」という問題は残った。しかしながら、外科手術がすぐに必要な状態ではないことは分かった。というわけで、緊急事態が避けられたのはラッキーだったのが、約2ヵ月の間、腎臓と心臓のどちらを選ぶのかという選択を僕は迫られていたわけだ。
この間考えていたのは、人工透析が必要となった場合、自分はどうするか、ということだ。人工透析は週に3日ほど通院して毎回5時間ほどかかる。その時間的負担も大変だが、治療費が毎月40万円ほどかかる。ただし、この費用は公費で賄うことができ、自分で負担する必要はないという。しかし、透析が必要となった腎臓は、機能が回復することはない。つまり、治る見込みのない病気のために年間500万円ほどの公費を使うわけだ。
若い人ならともかく、自分の場合は娘もすでに社会人となっているし、自分が生き長らえるためだけに多額の公費を使うことに何の意味があるだろうか、とずっと考えていた。念のために言っておくが、僕は高齢者の人工透析を辞めろと主張したいわけではない。ただ、治る可能性のない病気の治療のために多額の公費を使うことの意味を考えることは、大人としての義務ではないかと思うのだ。
死を「決断」することへの恐怖
もちろん、それも実際に透析が必要になってないから言えることかもしれない。作家の団鬼六さんも慢性腎不全を患いながら「人工透析は断固、拒否」と言っていたが、結局は透析を受けていたようで、最後はガンで亡くなった。僕も、もし透析が必要となったとき、本当に拒否できるかどうかは本音を言えば自信がない。現実に、僕は人工透析のリスクを冒してでも、少しでも生きながらえるために心臓カテーテル検査を行なったわけだし。ただ、わりと真剣に透析のこと、心臓のこと、死ぬことを考えてみて分かったこともある。
それは、死ぬことが怖いのではない。死を決断することが怖い――ということだ。
言葉を変えれば、人が死を決断するには、自分の死を超えた何か、たとえば思想・信条とか職務とか、あるいは家族などの個人的な関係性でもいいが、そのような「守るべき何か」のためでなければ、死を決断することはやはり難しいということだ。当たり前の結論と言えるが、やはり頭で考えるよりも、多少なりとも死のリスクに直面したほうが、リアリティをより強く感じるし、確信も強いものがある。
だからこそ思う。若者の未来を奪うくらいなら、僕は死んだほうがマシだと。そして、日本の社会もまた、このデリケートでやっかいな問題に、勇気を持って議論をすべき時が来ていると。その議論の結果は、高齢者には過酷なものとなるかもしれない。ただ、ひとつだけ確実に言えることは、若者の未来を守るために死を選ぶことは、結局は自分自身の尊厳を守ることなのだ。
僕自身もまた、自分の尊厳を守れるような死に方をしたいと思う。若者の未来を守ることは、大人が最後まで果たすべき義務だと思うから。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年07月08日 09:50
いや、誰もが生き直すことができる、、、いつからでも、どこからでも。。。
私は生き直すことができない
しかし
私らは生き直すことができる
[大江健三郎/晩年様式集(kenzaburo oe In Late Style)より]
Posted by nob : 2014年07月07日 22:04
変わるということ、、、それはそれまでの自らを一旦あるがままに受け容れることから。。。
■あなたの「性格」は、何歳で決まった?
転職先で生まれ変わろうとする
26歳男性の悩みとは?
岸見一郎(きしみ・いちろう)
哲学者
フロイトやユングと並ぶ心理学の巨人・アドラーは、現代を生きる私たちに人生観が変わるほどの気づきを与えてくれます。その教えをわかりやすく説いた『嫌われる勇気』は今や35万部のベストセラー。本連載では『嫌われる勇気』の著者・岸見一郎氏が、職場や日常生活で起こりうる皆さんのお悩みを「アドラー流」に解決いたします。
今回のお悩みは、26歳の男性によるもの。アドラー流の解決策はどのようなものでしょうか?
【今回のお悩み】
「性格が暗く上手くなじめません。
転職先で明るいノリに生まれ変わりたいです」(26歳・男性)
私は子供の頃から性格が暗く、引っ込み思案であまり他人とうまくコミュニケーションがとれません。そのためか、最初は親しくしてくれていた友人もやがて離れていってしまいます。社会人になって表面上は多少うまくやれるようになってきましたが、飲み会とかは苦痛で仕方ありません。これから何十年もこうした生活を続けないといけないかと思うと、絶望的な気分になります。もうすぐ転職します。どうすれば、このダメな性格を変えられるでしょうか?
【アドラー流回答】
その「性格」は、あなたが望んで選んだものです。
まず、性格は生まれつきのものでもないし、変えられないものでもありません。
「性格(キャラクター)」という言葉が持つ、「変えられないもの」というニュアンスにとらわれないように、アドラーは「ライフスタイル」という言葉を使います。
ライフスタイルとは、なにか問題を解決するときのパターン(癖)や、自分のことや他の人のこと、またこの世界をどんなふうに見ているか、を指します。
たとえば同じ親から生まれ、ほぼ同じ環境で育ったきょうだいでも、性格はまるで違いますよね。このように性格とは、遺伝や環境によって決定されるものではないのです。
われわれは幼児期の出来事を、大きなトピックであれば覚えています。怪我をしたとか、病気をしたとか、引越したというようなことです。ところが、それがいつのことだったかを時系列に思い出すことは、なかなかできません。
しかし、これが10歳を越えるくらいになると、はっきりしてきます。当時の担任の先生の名前を覚えているでしょうし、友達のこともよく覚えているでしょう。
アドラー心理学では、10歳前後の年齢で「このライフスタイル(性格)で生きていこう」と決心したのだと考えます。
そのころの自分と今の自分は、見た目こそ変わっているものの、ライフスタイル(性格)はあまり変わっていません。
たとえ自分のライフスタイル(性格)を不自由で不便だと思っていても、それとは違うライフスタイルを選んでしまったら、たちまち何が起こるかを予想できなくなる。
その変化が怖かったから、変えられないのです。
あなたは、自分の性格が暗く、引っ込み思案なので、他者とのコミュニケーションがうまく取れないといわれますが、そうではありません。
ほんとうは、他者とコミュニケーションを取らずにすむように、「自分の性格は暗い」と思い、「私は引っ込み思案だ」と思っているのです。
親しかった友人が離れていったとき(これは誰にでもあることです)にも、そのことを自分の性格のせいにしたいのです。
これからも同じ生活が続くかどうかは、あなたが決めることです。
ある日、突然、「明るい性格」になれば、そこからなにが起こるか予想がつきません。「暗い性格」のままなら、誰かがあなたから離れていったときにも「やっぱりそうだった」と思え、安心できるでしょう。
もしも同じ生活を続けたくないのであれば、いまとは違うライフスタイルを選べばいいのですし、選ぶことはできます。
ところで、私はあなたの性格が「ダメ」だとは思いません。
自分のことを「暗い」と思ってこられたかもしれませんが、ご自分に対して違った側面から光を当てて見ることができます。
たとえば、あなたは周囲の人を傷つけることがないように、あれこれと心を配ってきたのではないでしょうか。もしもそのことに思い当たるのであれば、あなたは「暗い」のではなく、「やさしい」といっていいのです。
自分を暗いと見てしまえば、自分を好きになれず、他者と積極的に関わることもむずかしいでしょう。
でも、やさしいと見ることができれば、そんな自分が好きになれ、他者との関係においても、一歩前進することができるはずです。
今回のアドラー流ポイント: ライフスタイル(性格)
アドラー心理学では、性格や気質のことを「ライフスタイル」と呼び、人生における思考や行動の傾向としてとらえます。そしてそのライフスタイルは、先天的に与えられたものでは決してなく、自分で選び選びなおすことも可能だとアドラーは説きます。しかしながら、新しいライフスタイルを選ぶと、新しい自分になにが起きるかわからず、目の前の出来事にどう対処すればいいかわからなくなります。すると「このままのわたし」でいるほうが楽であり安心だと感じ、人は自らに対して「変わらない」という決心を下してしまう傾向にあります。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年07月07日 17:12
また旅立つ君へVol.47/些末な打算を棄てて、、、自らの直感と想像力を指針に。。。
かつての根拠のない自信が
これまで自ら経験を重ねてきた分だけの確信に
しかし
思い起こしてみても
その自信と確信の間に差違などほとんどありはしなかった
Posted by nob : 2014年07月04日 15:58
脳腫瘍以前に、日々の眼精疲労・頭痛・ハリやコリetc.の蓄積慢性化が、予期せぬ重篤な疾患に繋がっていく。。。
■使いすぎ注意!スマホによる「脳腫瘍リスク」回避のポイント8つ
ケータイやスマホがすでに体の一部のようになってはいませんか? 外出時に、お財布は忘れても、ケータイは忘れないという人が多いようです。
このように、ケータイにどっぷりと依存している私たちですが、本当に安全なのでしょうか? 以前からケータイ使用の危険性は伝えられてはいますが、実際のところはどうなのでしょう?
そこで今回は、英語圏の情報サイト『BERNSTEIN LIEBHARD/CONSUMER INJURY LAWYERS』の記事を参考にして、ケータイ利用の危険性と、脳腫瘍のリスクを下げるヒントをお伝えいたしますね。
■電磁波による脳へのダメージ
みなさん、ケータイが電磁波を発していることはご存じですよね? ごくわずかですが、その程度の電磁波でも、人間の血液を変化させ、脳に影響を与えるということがわかっています。
とくに子どもの脳は成長段階にあるため、長時間の使用は望ましくありません。
■WHOの調査
ケータイで通話する際に人体に吸収される電波の平均エネルギー量の許容値は決まっていますが(アメリカではSAR/比吸収率が1.6W/kgまで)、それでもWHO(世界保健機関)の調査によると、ガンとの関係は否定できないとか。
とくに、長時間使用する人ほど、脳腫瘍、神経膠腫、聴神経腫瘍、髄膜炎などにかかるリスクが高くなるそうです。
また、アメリカのMayo総合病院の調査では、1日に30分以上の使用で、神経膠腫にかかる率が2倍に跳ね上がるといっています。
■ケータイ使用の注意事項
では、どうしたらこういった脳腫瘍のリスクを防げるのでしょうか?
(1)できれば、1日に30分以上は使用しない。
(2)頭から、できるだけ離して使う。
(3)使っていない時は、電源をオフにする。
(4)ヘッドセット、またはスピーカーにして使う。
(5)おしゃべりよりも、メールにする。
(6)ケータイの電波が届きにくいところでは、使用しない。
(7)できるだけ、子どもには使わせない。
(8)ケータイを買う時に、SAR(比吸収率)がどれくらいなのか確認して、できるだけ低いものを買う。
いかがでしたか? 以上がケータイの使用で脳腫瘍になるリスクと、それを回避する8つの方法でした。
ケータイは、今では生活必需品ともいえるものです。ですが、使用し過ぎは、脳腫瘍といった恐ろしい結果を招きかねません。とくにお子さんには、十分気をつけてあげてくださいね。
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2014年07月01日 21:29
また旅立つ君へVol.46/かつての途に迷う旅から、、、
昨今はもうあてすらもない旅へ、、、
予期せぬ出会いと出来事がまた楽しい。。。
Posted by nob : 2014年06月27日 21:03
また旅立つ君へVol.45/希望は自身で創り出すもの、、、いつでもどこででも。。。
この国には何でもある
ただ
希望だけがない
[希望の国のエクソダス/村上龍]
Posted by nob : 2014年06月27日 20:58
毎日ドバドバ出してます。。。
■汗はデトックスにならず!? 便をドバドバ出すことが一番理想的だった
私たちは普通に生活をしているだけで、大気汚染や食品添加物などから、たくさんの有害物質を体内に取り込んでしまっています。
これらの有害物質を体外に排出することをデトックスというのは、ご存知の方が多いのでは? 特に美容や健康のために、ランニングやウォーキングで汗をかき、デトックスしている方は非常に多いようです。
しかし、実は汗からは、たった3%の毒素しか排出されていないとされています。毒素の75%は便、20%は尿、3%は汗、2%は毛髪から排出されるので、毎日便を出すことが理想のデトックスだといえます。
そこで今回は、スムーズに便を出すための3つのコツをご紹介します。
■1:主食を”米”に変える
米には、難消化性でんぷんという成分が含まれています。この難消化性でんぷんは、胃や小腸で消化、吸収されることなく大腸まで届き、食物繊維と同様に便の量を増やして排便を促す作用があるので、便秘を改善するのにも効果的。
パンや麺類が好きな方も、デトックスのために米を食べる回数を増やしてみては?
■2:朝、水を飲む
大腸は、1日のうちに3~4回大きく動きます。特に、朝が一番大きく動くので、コップ一杯の水を飲んで、体の内側から胃腸を刺激し、蠕動運動を活発にしてあげることをオススメします。
朝のうちに排便があれば、スッキリした気分で一日を過ごすことができますよね。毎日の習慣にしましょう。
■3:”腸のゴールデンタイム”はリラックスして過ごす
肌と同じように、腸にもゴールデンタイムが存在します。気になるその時間とは、副交感神経の働きがピークを迎え、腸の働きが活発になる24時以降。蠕動運動を促すためにも、この時間には眠っていることが理想的なのです。
ただし、夕食後すぐに寝るのは、食べたものが消化されないのでNG。夕食は、21時までに済ませて、24時には寝るようにしたいものです。
スムーズに便を出し、体の不要なものをデトックスしちゃいましょう。美しい肌と健康をキープするためにも、毒素は毎日しっかりと出すように3つの習慣を心がけてくださいね。
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2014年06月20日 20:00
心と身体に優しいこまめな無理のない運動の継続。。。
■物忘れと認知症の違いは? 認知症の基礎知識
認知症で行方不明になる人が全国で問題になる中、認知症の予防、地域で安心して暮らせるコミュニティーづくりが急ピッチで行われている。そもそも認知症とはどんな病気なのか。群馬大学大学院保健学研究科教授の山口晴保氏に聞いた。
Q1 認知症とはどのような病気ですか。
認知症は大脳がつかさどる認知機能が低下する病気です。認知機能とは、「見る・聞く・嗅ぐ・味わう・触る」などの五感を通して脳に入る情報から、自分の置かれている状況を認識したり、言葉を自由に操ったり、計算するなど知的機能を総称する概念です。この認知機能が低下して、人の手助けなしでは生活できないレベルにまで、生活力が失われる状態になることを「認知症」と言います。
Q2 自然な「物忘れ」と認知症の「物忘れ」はどこが違いますか。
認知症の症状の一つに「物忘れ」がありますが、誰でも加齢に伴い記憶力は少しずつ悪くなります。「具体的な内容を忘れる」のは、自然な物忘れ、「出来事そのものを忘れる」のは、アルツハイマー型認知症による記憶障害という違いで比較できます。例えば、冷蔵庫を開けて消費期限が切れたお肉が出てきたら、「1 週間前に買っておいたのを忘れた」と気がつくのは自然な物忘れ。「誰が買ったのか」と、自分が買ったことを忘れていたらアルツハイマー型認知症の疑いがあります。
Q3 認知症と間違いやすい病気はありますか。
認知症と「うつ」は深い関係にあります。レビー小体型、脳血管性の認知症は、うつ的な症状が目立ちます。また、認知症の初期の段階、軽度認知障害(MCI)の段階で「うつ」の状態になると、アルツハイマー型は 1.65倍、脳血管性認知症は2.52倍の確率でなりやすいことがわかっています。「うつ」状態では、脳の中にセロトニンという神経伝達物質が不足しているので、ジョギング、水泳、早歩きのようなリズミカルな運動を毎日30分ぐらい続けると、3カ月で脳内のセロトニンが増えてくるという調査結果もあります。
Q4 認知症になりやすい生活習慣、または遺伝はありますか。
アルツハイマー型認知症の多くは、70歳を超えて発症しますが、中には40〜50歳代と比較的若い段階で発症する方もいて、遺伝的な素因を持っている傾向があります。遺伝的なアルツハイマー病は「家族性アルツハイマー型認知症」と呼ばれています。しかし、遺伝性のアルツハイマー型はごく一部。65歳以下で発症する認知症は全体の1%です。また、認知症になりやすい生活習慣は、運動不足が挙げられます。内臓脂肪型肥満に、高血圧、高血糖、脂質異常症のうち、二つ以上を合併した状態を「メタボリック症候群」と言います。このメタボになると、アルツハイマー型の発症リスクが2倍以上に高まるという調査結果も出ています。メタボを防ぐには運動が最も効果的です。こまめに体を動かしましょう。
[週刊朝日]
Posted by nob : 2014年06月20日 19:53
ごく当たり前のことばかり、、、幸せはいつもすぐ近くに。。。
■何個欠けてる?今すぐチェック「本当にハッピー」になるための8つの条件
あなたは、今“ハッピー”だと感じていますか? 「感じていない」という場合、そんな気持ちがどこからきているのでしょうか。もしかしたらそれさえわからず、イライラ、ウツウツして毎日を過ごしているのかもしれません。
アメリカで絶大な人気を誇るTVパーソナリティ、オプラ・ウィンフリーのウェブサイト『Oprah.com』の記事によると、自分の人生を“幸せ” と感じるためには、いくつかの鍵があるそうです。今回は同サイトを参考に、“ハッピー”になるための8つの条件をご紹介します。
人生が充実していない、幸せを感じられない……という方は是非チェックしてみて下さい。今自分に何が欠けているのかわかれば、幸せを手にするための改善策がとれます!
■1:自分自身を知る
生まれたばかりの赤ちゃんは“素”の存在。しかし、育つうちに一定の価値観や常識を学び、だんだんとその素の部分が見えなくなってしまいます。
幸せになるための第一歩は“素の自分を知ること”。素敵な彼氏や可愛い子どもがいる他人の幸せをうらやんでも、人は人、自分は自分です。あなたの幸せの答えは、すべて自分の中にあるのです。
まずは携帯やPCの電源を切り、自分自身と向き合ってみてはいかがでしょうか。
■2:人間関係を充実させる
幸せな気持ちは、他の人々とのいい関係から生まれてくる部分が大きい、といいます。恋愛や家族、友人関係がうまくいっていると、心からウキウキして幸せを感じますよね。
仕事に趣味に没頭しすぎて、あなたを幸せな気分にしてくれる大切な人々をおろそかにしていませんか?
■3:やりがいのある仕事に就く
自分の仕事にやりがいを感じていますか? あなたにとって“成功”とは何でしょう。もし、現状は“生きていくためにお金を稼いでいるだけ”だったとしても、将来的に自分の好きな仕事をできるように努力することだってできます。
好きな仕事に就きたいならば、そこへ至る道を調べて、少しずつでも進んでいきましょう。
■4:ポジティブな姿勢で物事に向き合う
トラブルがあっても、「これは私が学ぶために必要なことだ」と思える人と、「どうして私ばっかり」とふてくされる人では、基本的な姿勢が違います。
どんなことからも学べることはあるはずです。幸せになりたければ、まずは「幸せになる!」という姿勢を選択し、不平を言う代わりに、ポジティブな面を探してみましょう。
■5:感謝する心をもつ
どんなシチュエーションでも、感謝すべきことはたくさんあります。健康や友情、子どもや夫の存在、無償の愛を捧げてくれるペット、青い空や美しい花……。その1つ1つに感謝することで、毎日の幸福度は変わってきます。
■6:楽しいことをする
お金持ちだからといってそれだけで幸せというわけではありません。幸せな人は、自分が何をすれば楽しいかを知っていて、それを実行する努力をしています。
毎日の生活に追われて、“楽しむこと”を忘れていませんか? 好きなTV番組を観て大笑いするだけだっていいんです。生活の中で、「楽しい」と思う気持ちと笑顔をお忘れなく!
■7:健康でいる
女性の多くは夫や子どもの世話を優先し、自分自身の心身の健康をおろそかにしがちです。最近、体や心に変調はありませんか? ハッピーな生活は、自分自身の健康があってこそです。
自分が枯渇しては、他人に何かを与えることはできません。まずは、自分自身をケアすることから始めましょう。
■8:心の拠りどころを作る
信条や信仰を持つ人は幸福度がより高いそうです。宗教で幸せになれるというわけではありませんが、表面的な存在よりももっと深いもの、自分のエゴよりももっと大きな存在に気づくことで、心の拠りどころができます。
心がざわざわと落ち着かないときは、精神世界に関する本を読んだり、瞑想をしたり、自分の気持ちに耳を傾けたり、お寺巡りをしたりするのもいいかもしれません。
以上、ハッピーになるための8つの条件をご紹介しましたが、いかがでしたか?
「幸せじゃない……」と感じている方、今の自分に欠けているものは、このリストから見つかったでしょうか? 人それぞれに、幸せの形があります。自分自身の幸せがなんであるのか立ち止まって考え、それに近づく努力をしてみてくださいね!
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2014年06月17日 21:34
確かに、、、塵も積もれば山に、可能な限り控えたい(すでに実践中)。。。
■白砂糖、乳製品の恐ろしい実態
白砂糖が身体に及ぼす害
前回お伝えしました、白砂糖や乳製品がなぜ身体に悪影響なのか?オブラートに包まずお伝えしたいと思います。
白砂糖はそもそも自然物ではありません。それどころか「白い麻薬」とさえ言われる存在なのを皆様ご存じでしょうか?白砂糖はとても消化吸収が早いため、体内に入ると直ぐにブドウ糖に変わり血糖値を急上昇させます。
血液中に入った糖分は酸性となるために、これを中和しようとアルカリ性であるカルシウムが動員されます。砂糖がカルシウム泥棒と呼ばれるのはこのためです。カルシウムが大量に消費されることで骨や歯がもろくなり、骨粗鬆症や虫歯を引き起こします。そして、キレやすくもなります。
白砂糖をとると血糖値が急激に上昇するので、それに対応するためにインスリンが過剰に分泌され、次は逆に血糖値が急低下します。血糖値の上下を繰り返すと低血糖症を招く原因になります。
そして血糖値を上昇させる時、イライラしていると出てくるホルモン(アドレナリン)が出ます。別名は攻撃ホルモンとも呼ばれます。
アドレナリンが分解されるとアドレナクロムというものが出るのですが、これは麻薬成分に含まれる物質です。体内に多量に存在すると正常な判断ができなくなってしまうんです。その結果、ホルモンを調整する機能が麻痺し自律神経やホルモンバランスが崩れ、うつ、精神不安定や異常行動などに繋がってくるというわけです。
皆さんが毎日当たり前のように摂っている白砂糖。こんなに危険な毒物だと知っていましたか?
若くして刑務所行きになってしまった青年達の摂取物を調べると、白砂糖やスナック類が大半というデータも出ています。物事の判断が鈍ってキレやすくなると、どうなるか…分かりますよね。
白砂糖のとり過ぎには絶対に注意して下さい!
乳製品が身体に及ぼす害
乳製品は牛乳から加工され、ヨーグルトやチーズ、生クリームなどができます。牛乳は人間が飲むものではなく、牛の赤ちゃんが飲むものです。犬や猫の母乳を飲むことと同じなのです。
牛乳は見た目は白色ですが、元の色は赤色です。乳首を通過する時に白色に変わるだけです。牛乳は牛の血液です。牛の血液を飲むことができるでしょうか?他人の血液をも飲むことができないと思います。
現在、血液による輸血感染が多数あります。動物の血液を飲むことにかなりのリスクがあるのではないでしょうか?給食に必ず牛乳が出るようになり、その世代に育った子供やその世代の人々が生んだ子供にたくさんのアトピーや、他の今までになかった病気が増えるようになりました。ガンが増えたのも戦後です。
他の食べ物も関係しますが身体に良いと思って飲食している物が、実は身体に良くないことが多いのです。
牛乳は栄養バランスが良い…。カルシウムが摂れるその前に考えてみてください。牛の血液を飲むことと牛乳を飲むことは同じことです。
身体を守るために
ただ乳製品の場合、高温で煮沸や加熱することで害となる菌が死滅するので大丈夫です。
例えばピザやグラタンのチーズ、ホワイトソースなど。どうしても牛乳が飲みたい人は、1分以上沸騰してから飲んで下さい。
白砂糖は加熱しても何をしても、その毒素は抜けませんので、きび砂糖か黒砂糖にかえて下さい。
■ミネラルウォーター、有機作物…本当に安全?
精製塩は白い麻薬!?
前回は白砂糖や乳製品についてお伝えしましたが、それに並んで「白い麻薬」と呼ばれているのが精製塩です。
インターネット上には精製塩が良いとか自然塩が良い、自然塩に含まれているニガリが健康を害するなど、色んな記事が書かれ何が本当に良いのか分からなくなりますね。
塩は海水から作られますが、海水に含まれているミネラルは赤ちゃんがお母さんのお腹の中で育つ羊水とほぼ同じミネラルが含まれています。これは、生物が誕生した源が海から発生したことに関係があるのではないでしょうか?
精製塩は、とことん生成された99.9%の塩化ナトリウムです。これは、自然界に存在しない食品添加物です。
自然塩でも一番良いとされている天日のみで1年位かけて作る完全天日塩は、精製塩と違い口にすると甘く感じられ、おにぎりにつけて食べると格別に美味しいですよ。
塩分は身体に必ず必要であるからこそ、健康を害する可能性のあるものは避けられた方が良いと思います。
有機農産物について
「有機農産物=無農薬」と思っている方は、多くおられるのではないでしょうか?
有機農産物というのは農薬も化学肥料も使用してはいけないという前提がありますが、農林水産省では有機でも21種類の化学合成の農薬・化学肥料・土壌改良資材を条件付きで認めています。しかも農薬を使用した場合でも、残留農薬を調べることも必要ありません。
実際に、これらの農薬や化学肥料を使用して作られた有機農産物が少なくありません。つまり有機農産物には有機無農薬と有機低農薬の2種類があるのですが、表示義務がないため、消費者には見分けがつきません。農薬を使用しているかどうかは、生産者に聞くしか方法がありません。
有機農産物は安全と思っておられる方は多くおられますが、有機だからと言って無農薬とは限らないのです。安全を求めて購入される場合、有機ではなく無農薬と表示しているものを選んで購入されることをオススメします。
本当に身体に良い水とは?
最近テレビやニュースではあまり報道されなくなりましたが、酸性雨は人間の健康に与える影響が大きいです。
長年に渡り水の研究もしてきましたが、現在の日本でとれる湧水は昔とは違い酸性雨の影響で人体にも影響を及ぼしかねません。酸性雨で汚染された飲料水を使って料理をしたり、直接その飲料水を飲んでいるのが現状です。水道水も塩素で消毒され、人体に良いとは言えません。
ご家庭で使用されている浄水器にしても、一般に販売されている浄水器では塩素は取り除けますが、逆浸透膜浄水器を使用しない限り硝酸(しょうさん)性窒素などの化学物質は取り除けません。硝酸性窒素はほとんどの水道水で検出されるのが現状です。
またコンビニなどでペットボトルに入った水が販売されていますが、本州でとれる湧水は酸性雨の影響で飲料水にするには問題があると思います。
健康食品や健康飲料にやたらとお金をかける方がいらっしゃいますが、その前に…腸内環境を整え毒を体内に取り込まないことの方が大切ではないでしょうか?そのためには人体に必要な水や塩、毎日とる食材などをより安全性の高い物を選ぶことが健康体へ導き、病気やアトピーの改善にも繋がります。
いずれの記事も
メディカルビューティー&ヘルスアドバイザー・山岡豊恵/スキンケア大学・美ログより]
Posted by nob : 2014年06月17日 21:20
美脳づくり、、、脳のプラセボ効果の大きさは侮れません。。。
■本能のままに「食べて寝る」のが最大の美容法!
オーガニックコスメアドバイザー、ホリスティック美容家
林田七恵
ダイエットが成功しない理由、きちんとわかっていますか?
みなさま、こんにちは。ホリスティックビューティ担当の林田です。
さて、夏に向けてダイエットをしなくてはと思っている方も多いのではないでしょうか。本能のままに食べて寝るのがいい!なんてタイトルに挙げましたが、「そんなことしたら太っちゃう」と思いますよね。ダイエットが成功しない理由と共に、この謎をお話していきたいと思います。
私たちの身体をコントロールしているのは、脳です。寝る、食べるなどの本能的な欲求も、心臓を動かすのも、細胞を修復するのも、全部脳が指令をしています。具体的には脳の視床下部というところなのですが、この脳の働きがきちんと機能していれば、本来は必要以上に食べることはなく太ることもありません。また冷え性になったり、代謝が悪くなってくすんだり、シミが居座ったりということも起こるはずがないのです。
では、なぜ現実は食べ過ぎて脂肪になり、働きすぎて体調を壊し、代謝が悪くなってシミやくすみに悩むなんてことが起こるのでしょうか。
美容を妨げる最大の敵!?脳のプチ機能障害。
それが、脳の「プチ機能障害」。機能障害なんていうととても怖いですが、生命にすぐに危機があるようなものではなく、ちょっとずつチューニングが狂っていくような感じといえばわかるでしょうか。
色んな化学物質によって微細な機能障害があちこちに起こり、それが視床下部のコントロールを狂わせていると言われています。近年ではずっと問題になっているキレやすい子供、というお話しも同じ。拒食症、過食症も同じ。また、そこまで過度なものでないにせよ私たちの多くは何かしらの慢性中毒症状、依存症を抱えていると言われています。
この脳に染みついた「本来の働きとは違うクセ」が私たちの美容の最大の敵と言ってもいいかもしれません。
カフェインの場合、1日にカフェイン100mg、濃いめのコーヒー1杯を毎日飲むだけでも中毒性が見られると言われています。コーヒー、コーラ、緑茶、栄養ドリンクなどにもカフェインは多く含まれており、休憩の度にこれらを手にしたいと思う人は注意かもしれません。
例えば夕食の後にコーヒーを飲むことが習慣になっていたら。カフェインは脳を興奮状態に導く働きがありますから、本来は興奮を鎮め、副交感神経を優位にしていきたい夕方、夜には飲まない方が良いですよね。でもそれがわかっていても、やめられない。コーヒーを飲むから、結局熟睡できない。熟睡できないから昼間もなんとなく眠い。眠いからまたコーヒーを飲む。
これでは本来、昼夜メリハリをつけて身体を健康に美しく保っている機能もどんどんどんどん鈍ってしまいます。
他にもアルコール、タバコ、最近では炭水化物や甘いものを必要以上に欲しがる糖質中毒も話題になっています。糖質中毒もお菓子や炭水化物が脳に必要以上に快楽を与えるために、中毒になり、より多くの量を摂らないと気が済まなくなるというものです。
私は2歳半の子供がいるので、このことが身をもってわかります。普段は合成甘味料の多いお菓子や脳への刺激の強いチョコレートなどは一切あげないのですが、たまに周りの方から頂いて食べたりすると、もう大変。まっさらな脳に急に強い刺激が与えられ、息子は中毒のように「チョコレート、チョコレート、チョコレート!!と言い続けます。
そしてそれを与えないと、普段には見せないほどの激しさで泣きわめき要求するのです。でも2、3日与えずに、その刺激が薄らいでいくと途端にそこまでわめき散らさなくなります。「チョコレートっておいしいよね~。また食べれたらいいね~。」などと可愛いことを言ったりはしますが(苦笑)
私たちはこのくらい、口から入れる物質によって脳が左右されているのです。つまり食欲が抑えられなくてダイエットに失敗してしまう、という人は無理やり食欲を抑えようとする前に、どうしたら正常な脳に戻せるかを考えることが大切、ということです。
脳のチューニングを戻すには、ファスティングがオススメ!
さて、チューニングが狂った脳をどうすれば元に戻せるのか。一番良い方法は、ファスティング=断食です。
しっかりとした知識と管理下で行うことが大切ですが、生命維持に必要な水とわずかな栄養だけを液体で摂り、腸を休ませます。この時、脳を刺激する余分な物質も入ってこなくなりますので脳のデトックスにもなるのです。
3日間でもファスティングをすると、とても味覚や嗅覚が敏感になるのがわかります。そしてその時に本当に美味しい、と思うものだけを食べるのです。習慣になっていたコーヒーは、香りがきつすぎる、苦すぎる、と思うかもしれません。
こうして自分の脳の状態を本来の状態に戻せればあとは正常な脳の欲求のままに、食べたいとその時思うものを、食べたい量食べれば一番健康な状態になることができます。
全ての食事を抜くのが難しい場合は糖質だけを1週間抜いてみる、いつも習慣になっているコーヒーやお酒などを1週間抜いてみる。そんな方法もとても効果的です。
脳が正常に機能するようになると、睡眠障害も起こりにくくなります。眠くなったら寝る。寝たいだけ眠る。身体の声に従うだけで、どんどん身体は元気に美しくなっていきます。
ぜひこの夏、思い切って糖質や習慣的に摂ってしまっているものをストップして、美脳作りにトライしてみてくださいね!
[スキンケア大学・美ログ]
Posted by nob : 2014年06月17日 21:12
私も効果を実感、、、おすすめします。。。
■腰を揉んでも意味ない!「腰痛の時ほぐすべき」なのはこの3カ所
山下ゆり
ぎっくり腰、ヘルニア、坐骨神経痛など腰のトラブルを抱える方は多数いらっしゃいます。腰が痛いと、動くのがおっくうになったり、体のふしぶしまで痛くなってきたりして厄介ですよね。そんな時、みなさんはどう対処されますか?
腰を伸ばしたり、マッサージへ行ったりする人が多いと思いますが、腰が痛いからといって腰だけを揉んでもらうのはNGです。それでは意味がないのです。
そこで今回は、エステティシャン歴8年、東洋医学にも精通している筆者が、腰痛の時ほぐすべきポイント3箇所をコッソリ教えちゃいます。
■1:梨状筋をほぐすべし
梨状筋(りじょうきん)は、お尻の奥にある筋肉です。骨盤の出口付近にあるので、坐骨神経痛やぎっくり腰の人はココがとても張りやすいのです。また、デスクワークや運転などで普段座りっぱなしの人は、上半身の重さがすべてお尻にかかっているので、実はお尻がとてもこっているんですよ。
お尻を伸ばすようにストレッチしたり、整体などでお尻までしっかり揉んでもらうと腰痛が改善される可能性があるので、ぜひお願いしてみて下さい。
■2:お腹周りをほぐすべし
腰痛には腹筋トレーニングが効果的だということをご存知ですか? 人間は重い頭をまず背骨で支え、さらにその上半身の重さを腰でカバーしています。そして骨盤周りを支えているのはお腹の外側にある“外腹斜筋”と、その奥にある“内腹斜筋”です。
この2カ所が固まってしまっていると、骨盤周りの動きがスムーズにいかなくなり、腰が重くなってきます。ひねりを加えたエクササイズなどでしっかりほぐしておきましょう。
■3:膝裏をほぐすべし
腰痛がある人の中には、膝の裏まで痛くなる人がいらっしゃいます。腰が痛い人は座ったり立ったりするときに腰をかばい、膝に体重をのせてしまう方が多いからだといわれています。
また、膝裏は“委中”と呼ばれるツボがあり、腰痛や坐骨神経痛の方はここが硬くなっています。ゴルフボールを挟むなどして膝の裏をやわらかくすると、腰への負担が軽減されます。
以上、腰痛の時ほぐすべきポイント3ヶ所をご紹介しましたが、いかがでしたか?
腰が痛くてクイックマッサージや整体で腰を揉んでもらったのに、よくなったのは一瞬ですぐに元に戻ってしまったという経験をお持ちの方は、上記ポイントをおさえてほぐしてみましょう。
[ウーリス]
Posted by nob : 2014年06月16日 21:58
発症後の治療としての効用は高いと私も実感、、、いずれにせよ食べ過ぎは万病のもと。。。
■断食の効用:免疫系を再生させる科学的確証
断食することにより、免疫系が回復するという研究結果が発表された。高齢者やガンの化学療法を受けている患者にとってとりわけ有益な発見だ。
わたしには、毎年数日間断食をする友人が2人いる。彼らは、最初は疲労して空腹を感じるけれど、その後すぐに、より力強く、集中して、活動的で、エネルギーがあふれているように感じるのだと証言する。私はこうしたことに常に魅力を感じてきた。しかし、完全に納得したことはなかった。ほかでもなく、怠慢のためだったが。
しかし今、南カリフォルニア大学長寿研究所のヴァルテル・ロンゴの行った研究が、科学的確証をもたらしている。3日間の断食は、免疫系全体を再生させる。これは、高齢者においてもだ。
これまで断食は確かに「流行」したが、栄養学者たちの見解は反対だった。しかし、研究によれば、短期間食事をしないことで細胞は刺激を受け、新しい白血球を生み出すことになる、というわけだ。白血球は、感染に打ち勝ち、病気を遠ざけることで、免疫系を回復させる。
ロンゴはこう説明する。「断食の間に、体は、損傷し老化して不要となった細胞から解放されます。おそらくは、エネルギーを節約しようとするからでしょう。高齢者や、化学療法を受けている人の体のことを考えるなら、私たちはこの効果の重要性をよく理解することができます。断食は、文字どおり新しい免疫系を作り出すのです」
実験の間、被験者たちは、6カ月ごとに2〜4日間、食事を避けなければならなかった。分析からは、断食が、老化や腫瘍の成長のリスクと関係する酵素、PKA(プロテインキナーゼA)を減少させることに貢献したことがわかった。
化学療法を受けている患者においては、食事を控えることで、副作用が最小限になることが観察された。「わたしたちは、断食が幹細胞を活性化させられることを発見しました。幹細胞は、免疫細胞を再生し、化学療法によって起きる免疫抑制の防止が可能になるようです。さらにマウスにおいては、免疫系を若返らせられるようになります」
もし確証が得られれば、この発見は、研究者たちが実験を行い始めた腫瘍患者たちにとって、この上なく有利なものになるだろう。断食は、ジェノヴァのガズリーニ病院でロンゴが行った先行研究ですでに示されたとおり、化学療法の効果を最大20倍強化することができるだろう。
断食は、完全に健康な体にとっても、体調を改善するのに役立つとも言えるようだ。「数日間食事を控えることが人体に害を与えるという証拠は何もありません。その一方で、特筆すべき恩恵をもたらすという強力な確証が存在します」と、ロンゴは語った。
[ワイヤード]
Posted by nob : 2014年06月16日 21:46
最も怖いのは自分自身。。。
■アドラー流 お悩み相談室
岸見一郎
自分自身にダマされる!?
16歳の女子高生が気づいていない
LINE「ウツ」の本当の正体とは?
フロイトやユングと並ぶ心理学の巨人・アドラーは、現代を生きる私たちに人生観が変わるほどの気づきを与えてくれます。その教えをわかりやすく説いた『嫌われる勇気』は今や30万部のベストセラー。本連載では『嫌われる勇気』の著者・岸見一郎氏が、職場や日常生活で起こりうる皆さんのお悩みを「アドラー流」に解決いたします。
今回のお悩みは、16歳の女子高生によるもの。アドラー流の解決策はどのようなものでしょうか?
【今回のお悩み】
「LINEで返信がないと、不安で不安で……。
頭がおかしくなりそうです。」16歳女子高生
LINEが気になって、やめられません。
自分の送ったメッセージが「既読」になったのに返信がないと、何か悪いことを言ったのか、私のいないところでみんなが私の話をしているんじゃないか、とかいろいろ気になってずっとLINEばかり見てしまいます。自分が嫌われているんじゃないかってすごくこわくなります。
ときどきもう嫌になるけど、やっぱりLINEはやめられません。
【「アドラー流」回答】
その不安という感情は、ある「目的」のために
「捏造」している可能性はありませんか?
自分がいないところで、他の人は何を話しているのか。
ひょっとしたら自分の悪口をいっているのではないか。LINEにかぎらず、大いに気になることでしょう。
しかし、四六時中みんなのメッセージをチェックすることはできませんし、他の人があなたのことをどう見るかはわかりません。「既読」のまま返信してこなくても、それがあなたのことを嫌っている証拠とはいえません。ずぼらなだけであったり、忙しくて返信してこなかった可能性もあるでしょう。
そして、仮にあなたのいないところで、誰かがあなたの悪口をいっていたとしても、それはあなたが止められる問題ではありません。
あなたを悪く言わないようにできるのは、あなたではなく、その人だけなのです。
あなたができるのは、自分の生きたいように生きているのなら、少しくらい嫌われてもよいと思う勇気を持つことです。
ただ、ひとつ気になったことがあります。それは、ほんとうの問題は別のところにあるかもしれない、ということです。
みんなが自分のことをどう思っているのか気にならなくなったとしても、あなたはLINEをやめられないかもしれません。
それは、なぜでしょうか?
ちょっと考えてみて下さい。LINEをするようになって、できなくなってしまったことはありませんか?
たとえば、あなたが「LINEが気になって、勉強できなくなった」と感じているとしましょう。勉強しようと机に向かっても、すぐにLINEを見てしまう。矢継ぎ早にメッセージが届いて、とても勉強なんかできる状態ではない、と。
これはLINEのせいで勉強できなくなったのではありません。「勉強なんかしたくない」という目的をかなえるために、「ずっとLINEばかり見てしまう」という状況を自分自身でつくり出しているのです。
もしもそうだとしたら、あなたはLINEが気になっているのではない。
あなたの望む「目的(勉強したくない)」をかなえるために、ずっとLINEをやっているのかもしれないのです。
【今回のアドラー流ポイント 「原因論」と「目的論」】
アドラー心理学では、人は過去の「原因」によって規定されるのではなく、いまの「目的」に沿って生きていると考えます。
たとえば、「子どものころに虐待を受けたから、社会でうまくやっていけない」と考えるのがフロイト的な原因論であるのに対し、アドラー的な目的論では「社会に出て他者と関係を築くのが不安だから、子どものころに虐待を受けた記憶を持ち出す」と説きます。
人はある目的を達成する手段として、不安や恐怖といった「感情」をこしらえる場合があるのです。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年06月16日 21:25
今年に入って以来の体質改善プログラムの一環として、禁酒ではなく休酒してみて、それまでの呑み過ぎを初めて深く実感、、、只今絶好調、あと半年継続してみます。。。
■老化を防ぐ、お酒の飲み方とは?
久保 明 [東海大学医学部 抗加齢ドック教授/慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授]
ビールや日本酒、ワインは
何杯も飲めばあっという間にご飯数杯分の糖質摂取に
今回はお酒をテーマにアンチエイジングを考えてみましょう。
働き盛りの大人であれば、お酒を飲む機会がかなりありますよね。接待や友人との飲み会、仕事を通じての「ノミニュケーション」等々。お酒が好きで、お酒と食事の組み合わせも大好きで、ストレス解消や気分転換にも欠かせないという人も多いのではないでしょうか。
まず糖化(参考:第2回「老化のスピードを早めてしまう糖化とは?」)とお酒の関係をみてみましょう。
焼酎、ウィスキー、ブランデーなどの蒸留酒には糖質が含まれていません。ただし、水やウーロン茶などで割るのでなく、コーラやサワー類などで割ればその分の糖質がかなり加わります。
一方、ビールや日本酒、ワインなどには糖質が含まれていますので、何杯も飲めばあっという間にご飯数杯分の糖質を摂取してしまいます。甘いカクテル類にも相当の糖質が含まれますのでご注意を。
糖質を含まない蒸留酒を飲むなら問題ないかといえば、そうでもありません。肝臓の問題があります。
老化を防ぐ、
アルコールの適量とは
お酒を飲んでいるとき、肝臓はほかの作業を後回しにして、アルコールを分解するため、糖を血液に放出する働きが抑制されます。これにより、一時低血糖になることもあり、身体にとって大きな負担になってしまいます。飲み過ぎはさらに肝臓を疲れさせ、大きな負荷をかけますので、慎みたいものです。
お酒の健康的な適量というのは案外少ないものです。
健康を保つため、厚生労働省が推奨しているアルコールの適量は、1日純アルコールで20gほど。ビールなら中瓶1本、日本酒なら1合、ワインならグラス2杯、ウィスキーならダブル1杯、焼酎グラス1杯くらいに相当します。お酒を飲む人にとっては物足りない量ですよね。
しかし、どんなに多くても、40gを適量の限度にすべきと言われています。お酒の飲み過ぎは身体に毒です。もちろんアンチエイジングの大敵でもあるのです。
お酒は飲み方によっても身体への影響が違います。
一人飲みは、
飲まない人に比べ、リスクが倍にも!
面白いことに「一人で飲むより、みんなで楽しく飲む」と老化や病気になるリスクが少なくなるのです。お酒の場合、飲むときのメンタル面が大きな要素になるのです。ストレスを抱えて一人で鬱々とのむと悪酔いするとよく言われますが、実際、そうなのです。
週に300g未満であれば、「みんなで楽しく飲んだ」人は全く飲まない人より、脳梗塞や脳出血など脳血管疾患の発症リスクが低いというデータもあるほどです。週に300gなら、結構お酒が楽しめますよね。週、300g~449gでも、「みんなで楽しく」飲むなら発症リスクは飲まない人と同じくらいです。
ところが、一人飲みの人は、週300g~449gで脳血管疾患の発症リスクが飲まない人の倍くらいになるのです。
また別の調査では、ほぼ毎日お酒を飲んでいても、健康的な適量(純アルコールで20g)なら、全く飲まない人に比べて、高齢になっても生活機能レベルが落ちていないことが報告されています。ただし、日本人はお酒に弱い体質の人も多いですから、無理に飲むことはありません。くれぐれも飲みすぎには注意しましょう。
お酒でもうひとつ気をつけたいのは、お酒を飲むと食欲が増進し、ついおつまみや食事を食べすぎてしまうことです。
唐揚げやコロッケ、焼き肉、チーズがたっぷりのったピザ等々、高カロリーや糖化につながる高GI(GI値=グリセミック・インデックス値。食後の血糖値の上昇を数値化したもの)食品は、不思議とお酒には合いますよね。ただし、ビールや日本酒、ワインなどと一緒にたくさん口に入れれば、糖化への道まっしぐらです。おつまみのメニューやお酒の組み合わせ方を上手に選んでみましょう。
また、「懐石食べ」のように、サラダやおひたし、和え物など食物繊維の多いものや豆腐など大豆製品をはじめに食べ、その後にお刺身や肉などを取るという作戦もありますね。知恵を使って、お酒をより楽しい場にすることがお勧めです。
50歳以上の
正しいたんぱく質の摂り方
今回のメディカル・トピックスは、たんぱく質の摂り方です。
今年、2014年に発表された研究では、たんぱく質の摂取が少ない高齢者(66歳以上)では死亡リスクやがんの罹患リスクを上げ、中年(50歳~65歳)では低たんぱく質摂取が死亡リスクやがんの罹患リスク、糖尿病の罹患リスクを下げることが分かりました。
中年では肉や魚、乳製品などたんぱく質の摂りすぎに注意、高齢者は反対に肉や魚、乳製品などの摂らなさ過ぎに注意するということです。
アンチエイジングは年齢によって気をつけることが違うのです。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年06月10日 08:40
生きとし生けるものは、、、
みな宇宙を抱いている。。。
Posted by nob : 2014年06月07日 17:02
発症していない人の数値範囲に過ぎず、、、明日は判らない。。。
■治療も薬もやめたい…「血圧147正常」で混乱する医療現場
日本人間ドック学会などが発表した「血圧147」が波紋を呼んでいる。この騒動の内容から疑問の解決まで、現役の高血圧治療医らへ取材した。
* * *
「『自分は上が147以下だから治療をやめたい』と言う高血圧の患者さんが今日も診察に来ました。高血圧に伴う脳梗塞もある方です。あなたは治療しないと危ないと言ってどうにか納得してもらいましたが、数値が独り歩きしていて、非常に危ない状況です」
高血圧治療を専門にするある医師はこう嘆く。いま、医療現場では高血圧の数値をめぐって大きな混乱が起きている。
きっかけは、4月4日に日本人間ドック学会と健康保険組合連合会が発表した「新たな健診の基本検査の基準範囲」だ。過去に人間ドックを受診した約150万人のなかから、肥満や持病がなく、たばこを吸わないなどの条件を満たした「スーパーノーマル(超健康)」な人、約1万〜1万5千人を抽出。血圧、血糖値、コレステロール値など計27項目を調べたものだ。
その結果、血圧については、基準範囲の上限が、147/94(初めの数値が上の血圧、次の数値が下の血圧、単位はmmHg、以下同)。「高血圧治療ガイドライン2014」では、140/90以上が高血圧の診断基準なので、上の血圧はそれより7mmHg高いことになる。さらに血圧以外の項目でも、これまで「治療の必要がある」とされてきた診断基準の数値と比べ、総じて“ゆるい”数値が示されたのだ。
人間ドック学会の数値が報道されると、「正常の範囲が広がった」と受け止められた。「自分は高血圧ではない」と考え治療をやめたいと言いだす患者や、薬を勝手にやめてしまう患者も出てきた。
人間ドック学会には医師からの問い合わせが殺到した。その後、「今すぐ学会判定基準を変更するものではない」「『健康』とされる範囲を緩和した新基準を発表したかのような一部報道は事実誤認」とホームページで表明するなど、騒動の火消しに追われた。
診療側の学会も相次いで声明を出した。日本高血圧学会は、「人間ドック学会の『正常』の一部には、『要再検査、要治療』が含まれていると理解するのが正解」と指摘。同学会学術委員長で大阪大学大学院老年・腎臓内科学教授の楽木宏実医師は、「血圧を下げるべき人への生活習慣修正の指導もされなくなってしまい、血圧のさらなる上昇と将来の心血管病発症の危険が増加する可能性がある」と心配する。
ついに5月21日には、日本医師会が「多くの国民に誤解を与え、医療現場の混乱を招いている実態に鑑みても、『拙速』と言わざるを得ない」と、人間ドック学会の対応を厳しく批判する事態にまで発展した。
「147」という数値をどう理解したらいいのか。臨床研究適正評価教育機構の理事長で、東京都健康長寿医療センター顧問の桑島巌医師は、「正常範囲が広がったと理解するのは正解ではない」と指摘し、人間ドック学会、高血圧学会の数値の違いをこう解説する。
「人間ドック学会の数値は、現時点で健康と考えられている人の血圧の分布範囲。つまり将来、脳卒中や心筋梗塞を発症する可能性には言及していません。一方、高血圧学会の基準値は、脳卒中や心筋梗塞を予防するうえで、どのレベル以上だと危険かということを示した数値なのです」
高血圧の恐ろしさは、放置すると動脈硬化が進み、脳卒中や心筋梗塞といった命にかかわる病気を引き起こすことにある。高血圧学会の数値は、将来これらの病気が起こる危険性を考慮している、というわけだ。
[週刊朝日]
Posted by nob : 2014年06月06日 09:02
また旅立つ君へVol.44/ずっと昔の歌だけれど、、、時代を超えて。。。
http://www.youtube.com/watch?v=JwYX52BP2Sk
原曲♪
Ticking away the moments that make up a dull day
You fritter and waste the hours in an off-hand way
Kicking around on a piece of ground in your home town
Waiting for someone or something to show you the way
Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain
You are young and life is long and there is time to kill today
And then the one day you find ten years have got behind you
No one told you when to run, you missed the starting gun
And you run and you run to catch up with the sun, but it's sinking
And racing around to come up behind you again
The sun is the same in the relative way, but you're older
And shorter of breath and one day closer to death
Every year is getting shorter, never seem to find the time
Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines
Hanging on in quiet desparation is the English way
The time is gone the song is over, thought I'd something more to say
訳詩♪
倦怠にまみれた一日を刻む時計の音
お前はただ無駄に時間を浪費していく
小さな部屋を怠惰に寝そべったままで
「導いてくれる何か」をひたすら待っている
妄想と自慰に飽きて
尚も家の中から外の雨を眺め続ける日々
若いお前にとって人生は長い
一日を無駄にしても時間は有り余る
ある日、10年が過ぎ去っている事に気付く
いつ走り出せばいいのかなんて
誰も教えてはくれなかった
お前はスタートの合図を聞き逃していたのだ
太陽に追いつこうとひたすら走る
地平線の向こうへ沈んだかと思った太陽は
お前の背後から再び姿を現わす
相対的に太陽の位置は一切変わっていない
お前だけが年老いていく
やがて息は切れ 刻々と死に近づいていく
「もっと言いたい事があったはずなのに・・・」
毎年毎年、一年が短くなる
契機など一向に見つかりそうにない
お前の人生計画はすべて失敗に終わり
予定表はページ半分になぐり書きされた線と化す
お前は英国紳士らしく静かな絶望に身を任せるだろう
こうして時間は過ぎ、この曲も終わりを迎える
「もっと言いたい事があったはずなのに・・・」
Posted by nob : 2014年06月03日 18:11
私はこの半年生活習慣を根本から見直して体質改善中、、、一年で全身すべての細胞は生まれ変わる、あと半年頑張るつもりです。。。
■体が若返ることってあり得るの?
男女を問わず、いかに若々しさを維持するかというのは切実な問題。細胞の生産サイクルを高めて、見た目も中身もアンチエイジングを!男女を問わず、いかに若々しさを維持するかというのは切実な問題。細胞の生産サイクルを高めて、見た目も中身もアンチエイジングを!
残業続きで疲労困憊(こんぱい)の帰り道。ふと、電車の車窓に映る自分の姿を見て、「老けたなあ」「くたびれているなあ」なんて感じてしまったこと、ないだろうか?
まだまだ仕事も恋愛も頑張らなければならないお年頃としては、このまま老けこんでしまうわけにはいかない。幸いにして世はアンチエイジングブーム真っ只中で、男女向けに様々なアイテムが売られている。
…でも、老化を少しでも遅らせようというのであればともかく、一度老化してしまった部位が再び若返るという現象は、本当にあり得るのだろうか? 用賀ヒルサイドクリニックの鈴木稚子先生に聞いてみた。
「それはあり得ますよ。人間の体というのは皮膚も髪の毛もすべて細胞が集まって形成されており、常に新しい細胞と入れ替わっています。若いうちは細胞がダメになるペースよりも作られるペースが上回り、細胞の総量が増えていくため体が成長するわけですが、加齢とともにこのペースが逆転することで、老化が始まります。何らかの治療や対策によって、部分的に細胞がダメになるスピードを抑え、新たに作られるペースを上回らせることができれば、その部位は若返るといっていいと思います」
つまりは差し引きで細胞の量が増えれば、その部位は若返ると鈴木先生は解説する。そうするためには、細胞が失われるスピードを抑える努力をすることが重要だという。
「不摂生な生活をあらため、規則正しいサイクルと栄養バランスのいい食生活に切り替えるだけでも、細胞が損なわれる速度を抑えることができ、アンチエイジング効果はありますよ」
これは何も見た目だけにかぎった話ではない。鈴木先生によれば、そうした生活改善によって内臓のアンチエイジング効果も生まれ、結果として各臓器の機能アップにもつながるという。
最近ではエステやレーザー治療などアンチエイジングのための様々な方法があるけれど、まずは規則正しい生活を心がけることから始めてみては?
(友清 哲)
※この記事は2013年6月に取材・掲載した記事です
[webR25]
Posted by nob : 2014年06月03日 17:59
簡単即効、、、おすすめです。。。
■イラっとしたら…すぐ!即効性のあるストレス解消法
「ストレス解消したいのに、今できない。でも、どうしても今したい」そう思ったことはありませんか?上司の発言にイラっ!何かこぼしてイラっ!といった些細なことでストレスを感じるあなたに、最適なストレス解消法があります。それは、反射です。この記事では、人の本能が持つ反射を利用して、その場のストレスを軽減させる方法をご紹介します。
■ 反射の力で速効ストレス解消!
◎ 反射とは?
猫だましされたら目を瞑る・ビックリしたら息を吸う・熱いものに触った時にとっさに手をひっこめるなど「こうしよう!」と思う前に、無意識に脳が筋肉を動かすことを反射といいます。学校で習いましたね!実は、この反射を利用して心拍数を下げ、リラックスを促す方法があるのです。これをストレス解消に利用しましょう。
■ まずは試しに、「呼吸反射」
「落ち着いて、ハイ!深呼吸して〜」と、よく聞きますよね。これはとても理にかなった方法です。人間は、息を吸うと心拍数が上昇します。逆に、息を吐くと心拍数が減少するようにできています。これを利用して、呼吸反射を体験してみましょう。
◎ 呼吸反射でストレス解消する方法
5秒間息を吸ったら、吐けるところまでゆっくりじっくりと息を吐いてみましょう。すると…どんどん心拍数が落ち着き、リラックスしていきます。どうですか?これが初歩的な反射を利用したリラックス方法です。
■ これからが本番、「アシュネル反射」(眼球心臓反射)
アシュネル反射という言葉を聞いたことがありますか?これは、眼球心臓反射とも呼ばれます。アシュネル反射は感覚反射の一種で、激痛を感じると心拍数が上昇したりするのと同様の反射です。言葉は難しいですが、やり方は簡単です。
◎ アシュネル反射でストレス解消する方法
まず、両目を閉じ、まぶたの上に触るか触らないかくらいの位置に指先を添えます。そして、ゆっくり静かに眼球を圧迫しましょう。怖い人は手のひらでも大丈夫です。あくまで優しくを心がけてくださいね。決して強く圧迫しないでください。ソフトに触れる程度でOKです。どうですか?イラっとした気持ちが落ち着いたでしょうか?眼球の後ろにある神経を眼球の圧迫により興奮させることで、副交感神経の迷走神経が刺激され、緊張が緩和されます。これにより、血圧と心拍数がさがるのです。アシュネル反射を利用して、効果的にストレスを解消してみましょう!緊張症の人や、イザという時にもぜひやってみてくださいね。
■ 速効でストレスケアするために本能に頼ろう!
狭いところが落ち着く、人に見られていない方が落ち着くという本能は、様々な反射が複雑に組み合わさったものです。利用しない手はありません。「呼吸反射」と「アシュネル反射」を組み合わせて、吐くことを意識しながら眼球圧迫すると効果は倍増です。イラっとしたときに即効でストレス解消をして、ためないストレスケアをしてみてはいかがでしょうか。
[著:nanapiユーザー・ いおり 編集:nanapi編集部]
Posted by nob : 2014年06月03日 17:51
私も日々留意実践しています。。。
■いいことづくしの酵素を「効率よく摂取する」とっておきの方法7つ
高橋果内子
いいことづくしの酵素を「効率よく摂取する」とっておきの方法7つ] 食物繊維を摂るなど、食事に気をつけているのに便秘症でなかなか体重が落ちない……。こんな悩みをよく聞きます。便秘は、お肌トラブルの原因にもなりますし、ダイエットの大敵でもあるもの。
そこで今回は、酵素を増やして、美肌と便秘知らずの身体を手に入れるための方法を紹介したいと思います。
■腸美人はスリムな体型でいられる!
私たちが食べているものは腸で吸収され、それが血液を通じて、全身の細胞へ運ばれてエネルギーになります。腸の働きが低下してくると、いくら栄養バランスの取れた食事をしていても、栄養を腸で吸収できずに全身へ届けることができません。
食べたものが腸で速やかに吸収される、すなわち、腸の状態が良好になれば、エネルギー代謝も促進されて体重の悩みからも解放されるでしょう。
■腸の状態には”酵素”が重要な役割を担う
酵素とは、生命に存在するたんぱく質です。体内に豊富にあれば、エネルギーも免疫力も高まります。でも、インスタントやレトルトなど、酵素の少ない食べ物ばかり食べたり、アルコールやタバコは、摂取したことによるストレスを解毒するため、大量の酵素が使われてしまいます。
酵素を増やし、腸の働きを活性化させることが、便秘解消への一番の近道。ちなみに、酵素には生きていくために必要な”代謝酵素”、食べたものを分解し吸収しやすい物質に変換する”消化酵素”、生の食物に含まれる”食物酵素”の3つの種類があります。
”食物酵素”だけが、外部から摂取することができるので積極的に摂取しましょう。
■酵素を効率よく摂取する方法7つ
では、どうしたら酵素を増やすことができるのでしょうか? ここでは具体的にお伝えしていきます。
(1)死んだ食品を摂らない
死んだ食品とは、化学調味料や食品添加物、精製された砂糖や人工甘味料のこと。これらには食物酵素が含まれず、逆に添加物に含まれた化学物質を解毒するために酵素を使ってしまいます。
(2)ローフードを食べる
酵素は熱に弱く、48℃で破壊が始まり75℃でほぼ全滅してしまいます。そこでお勧めなのはローフード。果物や発酵食品、生野菜、海藻、刺身など加熱せずに食べられる食べ物には、たくさんの酵素が含まれていますので、積極的に食べると良いです。
(3)植物性食品と動物性食品の割合は85:15に
ローフードとともに気をつけたいのが、動物性食品の摂り過ぎ。肉類は腸内で消化する時に、大量の消化酵素を消耗します。また、食物繊維を含まないので腸内に溜まりやすく、便秘にもなりやすくなります。食事の15%以上が動物性食品になりそうな時は、次の食事で豆類や野菜、海藻などを食べるように心がけましょう。
(4)加熱していない生物から先に食べる
せっかくローフードを食べるなら、順番は一番最初がベスト。量のある生の野菜や果物から食べることで、胃の中を満たす効果も期待でき、ビタミンや食物繊維などの栄養素と酵素を先に身体へ届けることができます。同時にお水を飲むと、約20分ほどで細胞のすみずみにまで酵素が運ばれ、脂肪燃焼の手助けをしてくれるので、ぜひ食事中の水分補給を習慣にしてみてください。
(5)1日1.5リットルの常温のお水を飲む
食事中の水分補給は、栄養を身体のすみずみに届けるため、また老廃物を流すためにとても大切ですが、冷水では腸の温度を冷やし腸の働きを弱めてしまいます。効率よく酵素を摂取するためにも食事の際は、常温のお水を飲むようにしましょう。毎食事の際、約500ミリリットルずつ飲むと、ちょうど良いです。
(6)良質な調味料を摂る
化学調味料は、避けた方が良いとお伝えしましたが、それなら逆に調味料にこだわってみるのはいかがでしょうか。昔ながらの製法で作られた天然ものの調味料は、ミネラルが豊富です。上質な調味料に含まれる栄養素が、腸本来の働きを高め、栄養の吸収も高めてくれます。
(7)一口30~40回は咀嚼する
消化するのに酵素が使われてしまわないように、楽に消化ができるようにすることが大切。早食いや大食いは、消化に負担がかかるのでNG。噛むことで胃の消化が楽になり、唾液の分泌も活発になります。また、その唾液がさらに消化を助けてくれます。噛むことで満腹中枢が刺激されて、食べ過ぎを防ぐこともできるので一石二鳥です。
腸内環境を整えると、良いことばかりですね。便秘に悩んでいる方もそうでない方も、ぜひ7つの方法を取り入れて、”美腸”を目指してくださいね。
[美レンジャー]
Posted by nob : 2014年06月03日 17:37
また旅立つ君へVol.43/言い得て妙。。。Vol.19
■もっと自信が持てるようになる13のアドバイス
Inc.com:「自分に自信がありますか?」と聞かれて「はい」と答える人はほとんどいないでしょう。しかし、作家であり、元フォーチュン 500の役員でもあるBecky Blalockさんは、誰でももっと自信が持てるようになると言っています。自信というのは、身に付けることができるスキルなのです。
まずは、「自信やリーダーシップがあり、人前で話すことができる」のは、生まれつきの資質によるものだという先入観を捨てることから始めましょう。実際に研究では「恥ずかしがり屋で控えめ」という性質こそ、人間が持って生まれたものだと証明されています。Blalockさんは、「私たちの祖先が遺伝子を残すために生き残るには、慎重でなければならなかったからです。しかし、心配をしなければならなかったことが、現在では心配をする必要がなくなっています」と言っています。
では、もっと自信が持てるようになるにはどうすればいいのでしょうか? Blalockさんの13のアドバイスを紹介しましょう。
1.考えはあくまでも考えだと知る
平均的に人間は毎日65000のことを考えています。そして、そのうちの85~90%は、心配したり恐れたりしているネガティブなことを考えています。これは竪穴式住居に住んでいた時代の名残で、自分に対する警告なのでしょう。
たとえば、火に手を突っ込んだら、そんなことは二度としないように脳が確認をしようとするでしょうから、もっともな話です。しかし、生き残るためのメカニズムが、希望や夢よりも恐怖に意識を向けさせてしまっています。
大事なのは、脳がこのような仕組みで動いているということを知ること。そして、ネガティブな出来事に過剰反応しないようにすることです。考えはあくまでも考えなのだと認識しなければなりません。頭で考えたことが、必ずしも客観的な事実とは限りません。
2.目的地を知る
「やりたいことは何ですか?」「どんな人になりたいですか?」とたくさんの人に聞いてきましたが、「わかりません」という人がたくさんいます。自分が何をしたいのかを知ることが重要です。自分のやっていることが、自分の行きたいところ(なりたいもの)へとつながっています。
3.感謝の気持ちを持つ
何に感謝しなければならないか。それを考えることから一日を始めましょう。この世にいる70億人のうち、ほとんどの人には、あなたの「やっていること」をするチャンスがありません。そのような視点で考えると、残りの一日をどんな気持ちで過ごすかが決まってきます。
4.安全地帯から毎日一歩踏み出す
安全地帯というのは面白いものです。安全地帯から定期的に踏み出していると拡大するのに、ずっと留まっていると縮小するからです。安全地帯が縮小しないようにするには、そこにはない、やったことがないことをやるのです。
誰もが怖い経験をしたことがあるはずですが、それはそんなに悪いことではないと気付きます。Blalockさんの場合、軍の基地へ行った時に、パラシュート訓練をするタワーの一番上から飛び降りる体験をしました。もちろん命綱できちんとつながれていたのですが、「ごめんなさい、できません。小さな子どもが家で待っているんです」と言って、止めさせてもらおうとしました。しかし、誰かが背中を押してタワーから飛び降りてしまいました。でも、「そんなに悪くないな」と思ったのです。
常に、安全地帯から蹴りだしてくれる人がそばにいるわけではありませんから、自分でそうしなければなりません。「とにかく動け!」というのがアドバイスです。
5.停まっている車を犬は追いかけない
反対意見や疑問、心配などが頭に浮かんでいる時は、それが思い浮かぶだけの理由があるのでしょう。そのような警告のサインを無視しろというわけではありませんが、そのようなネガティブな視点からは離れましょう。変化や現状を変えようとしているから、そのことに相反するものが生まれているのです。
6.失敗に備える
自信を喪失させるのは失敗ではなく、失敗に備えていなかったことです。備えがあれば、失敗から学び、もう一度チャレンジできます。ホームランの記録を持っている野球選手は、三振の記録も持っていることが多いのです。三振を恐れてバットを振らなければ、ホームランは打てません。
7.お手本となる人を見つける
何かをやりたいことがあるなら、それを実現したことがある人を見つけましょう。ためになるアドバイスをもらったり、ロールモデルとして参考にさせてもらったりして、できる限りのものを吸収するのです。
8.仲間は賢く選ぶ
ネガティブかポジティブかなど、自分の物の見方というのは、自分がよく一緒に過ごしている5人の平均になります。ですから、一緒に過ごす人は慎重に選びましょう。自分を励まして、気分を高めてくれるような人としっかり一緒に過ごすようにしましょう。
Blalockさんが本を書くために経営幹部職を辞めた時、愕然として「誰もそんな本を読まないよ」と言う人もいれば、反対にがんばれと励ましてくれる人もいました。そのおかげで、自分がそばにいるべき、励ましてくれる友だちを見つけるのに、時間はかからなかったそうです。
9.準備をする
ほとんどの場合、きちんと準備ができていれば自信を持てます。スピーチをしなければならないなら、原稿を書き、何度か練習し、録音して聞きましょう。初めての相手と会議をする場合は、相手の会社のウェブサイトで事前に情報を入れたり、相手のソーシャルメディアの情報をチェックしたりしましょう。インターネットを使えば準備をするのが楽です。
10.十分な休息と運動をする
十分な睡眠と運動と栄養を取っていれば、気分と生産性に良い影響があることは、あらゆる研究によって証明済みです。週3回、中程度の運動を20分ほどするだけで、海馬にとっては十分で、アルツハイマー病やうつ病を回避するには何よりも効果的です。しかし、運動は優先順位が下がることが多いです。誰かに任せられることはたくさんありますが、運動は他の人に代わりにやってもらえません。
11.呼吸をする
とても簡単なことです。深呼吸をすると、脳に酸素が行き渡り、意識がより明晰になります。緊張するような状況では、自分の体をコントロールできると認識することはとても重要です。あまり呼吸を活用していない人は、すぐに取り入れてみてください。
12.うまくできると信じる
やったことの無いことや、資格を持っていないことを、知ったかぶりするということではありません。しかし、必要なスキルを大体持っていて、足りないものがわかっている場合は、尻込みはしないでください。
ある会社が、男性よりも女性の方が昇進する人が少ないのかを調査しました。自信に対する考え方にかなりの違いがあるのが問題でした。男性の場合は、ある役職や仕事に対する能力の半分を満たしていれば、それに値すると考える傾向にある。しかし、女性の場合は、ほとんどを満たしていないと値しないと考えることが多かったのです。仕事や何かをやる前に、それに対する豊富な経験が必要だと思い込んで、躊躇しないでください。
13.助けを求めるのを忘れない
自分がやりたいことを誰もが知っていると思い込まないように。自分でやりたいことがわかったら、それを周りの人にも伝えましょう。あなたのやりたいことが相手に伝わったら、助けてくれるように頼みましょう。予想以上に助けてもらえることに驚くかもしれません。
人は、アドバイスや助けを求められるのを、本当にうれしく思うものです。断られた場合は、別の人に頼みましょう。しかし、Blalockさんの経験によると、ほとんどの人は断らないのだとか。
Minda Zetlin(原文/訳:的野裕子)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2014年06月01日 08:45
また旅立つ君へVol.42/やりたい人はやれば、やめたい人はやめれば、その時々の納得の基準を自他どちらに求めるかだけの差、、、自らの内なる心の声に従えばいいだけのこと。。。Vol.3
■夢は9割叶わない。
弘兼憲史
“仕事を選ぶ新人は、絶対成功しない”
「やりたくない仕事」が持つ大きな意味
上司から仕事を振られて、「こんな仕事やりたくないな」「やる気が出ないよ」と思ったことはありませんか?誰だって嫌な仕事はあるものです。しかし、こうした「やりたくない仕事」との向き合い方次第で、あなたの人生は大きく変わってきます。
新人のうちは、
「仕事」を選んではいけない。
新人のうちは「とにかく何でもやる」という意識が大切です。
経験や実績がないうちから「これはやるけど、これはやりたくありません」「この仕事に社会的な意味はあるのでしょうか」などと言ってしまうと、上司には嫌われ、会社からも見放されてしまいます。
社会に出れば、やりたいこともあれば、やりたくないこともあります。「正しい」と思うこともあれば、「これは間違っている」と感じることもあるでしょう。
でも、新人のうちから「何でもやる」というスタンスを持っていれば、必ず人生の幅は広がっていきます。
例えば漫画の世界で、名もない新人漫画家が「これはやります」「これはやりたくありません」なんて言っていたら、まったく仕事はなくなります。僕も駆け出しのころは、頼まれた仕事は全部引き受け、片っ端からやっていました。だから忙しいときには、1日18時間以上働いていましたし、徹夜をすることもしょっちゅうでした。
そもそも、新人とはそういうものだと僕は思っています。
「新人は、相手の言うことを聞くもの」。
その理由とは?
そして、新人のうちは「とにかく、相手の言うことを聞く」というのも大事なスタンスです。
僕の経験から言っても、出会う編集者のすべてが優秀で、漫画のセンスに溢れ、的確なアドバイスをするわけではありません。
正直に言えば、「えっ、そんなふうに描くの?」「こんな修正をしたら、まったく面白くなくなるよ」という指示を出す編集者もいました。それでも、若いころはとにかく編集者の言うことを聞いて、目の前の第一読者(編集者)を喜ばせることに意識を集中しました。
理由は、大きく分けて2つあります。
1つ目は、そもそも実績のない新人漫画家が何を言ったところで、聞く耳など持ってくれるはずがないということです。ペーペーが偉そうな意見を言っても「代わりはいくらでもいるからな」と言われて終わりです。
仮に僕の言うことが正しかったとしても、結果としてチャンスを失い、その後の可能性を潰してしまうとしたら、これは本末転倒です。
「偉そうなことを言う前に、
俺を喜ばせてみろよ」
そしてもう1つの理由は、「どんな仕事でも、目の前の人を喜ばせることができなければ、その先はない」と常々思っているからです。
目の前の第一読者である編集者を喜ばせられないのに、その先の何万、何十万の人を喜ばせられるわけがない。長年漫画家をやっていれば例外があることも重々理解していますが、特に若い人は、そう思っておいたほうがいいでしょう。
僕が編集者の立場なら「そんな偉そうなことを言う前に、まずは俺を喜ばせてみろよ」と言いたくなりますし、その思いはきっとみんな同じはず。だから、僕は新人のころ、編集者のどんな要望にも応えようと必死でやってきました。
当時の作品を今になって読み返してみたとき、「ああ、やっぱり編集者の言う通りにしたのは失敗だったなぁ……」と作品的には思うこともありますが、自分がキャリアを積み重ねていく上では決して間違った選択ではなかったと思います。新人のころはそれが当たり前なのです。
これは何も漫画の世界だけの話ではなく、一般企業でも同じではないでしょうか。
「まず上司を喜ばせる」。
すべてはそこから
上司が理不尽なことを言って、自分としては納得できないケースも当然あります。
しかし、何の経験もない新人が「それは理不尽です」「そのやり方は間違ってます」なんて言っても、聞いてもらえるはずがありません。「正しい」とか「間違っている」という以前に、残念ながら、新人にはそんな発言権がないのです。
だからこそ、まずは上司の言うことを聞き、上司を喜ばせるしかない。すべてはここからスタートです。
上司を喜ばせることができれば、その次の機会には「○○さん、この点について、ちょっと提案があるんですけど」と発言する機会が得られるかもしれません。また、上司の信頼を得ていれば、向こうのほうから「君はどう思う?」と聞いてくれるようになるかもしれません。このように、新人はちょっとずつ自分の立場を構築し、発言力をつけていくしかないのです。
目の前の上司、あるいは第一読者を喜ばせられないうちから「これをやりたい、これはやりたくない」「これは正しい、これは間違っている」などの主張をするのは、あきらかに順番が違います。
上司が言うことを聞いてくれないと思うなら、何よりもまず、その上司を喜ばせること。そこからしか突破口は開けないと、僕は思います。
■夢は9割叶わない。
弘兼憲史
“会社に入ったら、3年は辞めないほうがいい理由”
自分の「強み」と「弱み」を知ることの大切さ
「会社を辞めたい」「自分はこの仕事に向いてない」「仕事がつまらない」。社会人であれば、一度は思ったことがあるかと思います。本日のテーマは、「社会人としての修業期間」です。自分の「強み」と「弱み」を知ることの大切さについて、お話しいたします。
「仕事の向き不向き」は、
自分で勝手に決めつけているもの
「会社に入ったら3年は辞めないほうがいい」、これが僕の考えです。その理由を述べていきます。
入社してすぐに会社を辞める人の多くは「こんなはずじゃなかった」「想像していたのと違う」などの思いを持つと思います。
でも、まず考えて欲しいのは、会社側だって「あなたに何が向いているのか」を正確に把握できるわけじゃない、という点です。
とりあえず何かをやらせてみて、その過程で能力、向き不向きを判断していくのは当たり前ではないでしょうか。会社とて、あなただけを見ているわけではありません。それなのに、あまり早い段階から「自分の向いている仕事をやらせてもらえない」と言って会社を辞めていくのは、とてももったいない気がします。
それと理由をもう1つ。
「仕事の向き不向き」というのは「自分が勝手に思っているに過ぎない」のです。
自分と他人を比べて、
能力と才能を見極める
あなた自身は「企画が向いている」と思っているのに、会社や上司が営業の仕事を与えてくれば、当然不満を感じるでしょう。その気持ちはよくわかります。
しかし、「企画が向いていて、営業は向いていない」と感じているのは自分だけで、上司や会社側は「こいつには営業が向いている」と判断しているのかもしれません。
営業職へのインタビューの中でよく聞くこととしては「営業だけは向いていないと思っていたが、やってみたら天職だった」という意見です。やってみて、はじめてわかることは多いものです。自分だけの判断で、まして若いうちから「これは向いている、向いていない」と早々に決めつけ、会社を辞めてしまうのは得策とは言えません。
だから、せめて3年くらいは会社から与えられた仕事を懸命にやってみて、「自分には何ができるのか」「自分ができないことは何か」をじっくり考えつつ、情報収集と検証をしたほうがいいと僕は思います。
3年くらい働けば、自分と他人の能力差、資質の違いなども少しは見えてくるでしょうから、その上で今後の身の振り方を考えても決して遅くはありません。
「900人が採用され、
100人が辞めた」と言われる研修
ちなみに、僕が就職した松下電器のような大きな会社では、希望する部署に配属されないのは当たり前でした。今はどうかわかりませんが、当時は大卒、高卒、高専卒などを合わせて約900人が毎年採用され、そのうち100人くらいが研修中に辞めたなんて話も聞いたことがあります(あくまでも噂ですが……)。
当時の研修は、文系も理系も関係なく、とりあえずいろんなことをさせてみる、という感じの内容でした。入社直後の3ヵ月は会社全体のことを学びます。「松下の世界の工場ではどんなことをやっているのか」などを徹底的に学ぶ時間。
それが終わると、次の3ヵ月では系列販売店での実習が始まります。当時、販売店にはお客さまから「テレビが故障したので見に来て欲しい」などの連絡が入り、僕らのような新人が派遣されるわけです。
その頃のテレビは真空管を使っていたので、テスターという機械を使って、どこが断線しているかを調べ、修理をします。その現場では文系、理系は関係なく、大学院でものすごく高度な研究をしてきた人でも、同じように販売店の仕事をしていました。
専門的なことを学んできた理系の人たちにしてみれば「こんな単純なことしてられるか!」と不満を持っていた人も多かったに違いありません。そして、販売店実習が終わると、次の3ヵ月は工場実習です。
どこに配属されるかは、
完璧に運の世界。
新入社員全員はそれぞれどこかの工場に配属されて、工員として仕事をします。配属先の希望なんて受け入れてもらえるはずはなく、「どこの工場へ行くか」によって処遇が大きく変わってきます。これは完璧に運の世界でした。
当時、人気が高かったのが録音事業部という、オーディオなどを作る部署。この部署には若い女の子がたくさんいて、1日中いい感じの音楽が流れ、まさに「楽しくおしゃべりしながら働く」という感じでした。少なくとも他の工場勤務の連中はみんなそう思っていました。まさに当たり部署というわけです。
しかし、僕が配属されたのは、電気事業部という外れ部署。鉄板を打ち抜く音が1日中ガンガン鳴り響いている工場内で仕事をするので、働く人は全員が耳栓をしていました。身振り手振りをしなければ、ロクに会話もできません。
また、「打ち抜いた合板をアルミで固める」という作業をする関係上、夏でもクーラーは一切なし。室温が下がると作業効率が下がるので、仕方がない措置とは言え、まさに地獄のような部署でした。
ちなみに、僕らは毎朝、栄養補給の錠剤を飲んでから工場実習に入っていました。それだけでも、いかに過酷な環境かわかってもらえるでしょう(もちろん、当時と今では研修内容も、職場環境もまるっきり違うと思います)。
何もできない人間が一人前になるには、
相応の修業期間が必要
それだけの研修を経て、11月に配属が決まります。すでに述べたように、研修中に約1割が辞めていくし、研修を終えたからと言って、自分の希望の部署に配属されるわけではありません。
でも、僕は社会とは、そもそもそういうものだと思っています。何もできない人間が、一人前になるためには、やはり相応の修業期間が必要なのです。
だから、せめて最初の3年くらいは、好きな仕事だろうが、嫌いな仕事だろうが、向いていようが、向いていなかろうが、上司の言うことに納得できようが、できなかろうが、とにかく文句を言わずにやってみることが一番大事だと、僕は考えます。
懸命にやってみて「自分は何ができるのか」「何ができないのか」をきちんと知る。これこそ社会人としての第一歩ではないでしょうか。
根気良く、懸命にやりもせずに「これは自分に向いていない」「こんな仕事に興味が持てない」「上司の言うことは間違っている」なんて言うタイプは、結局は何をやっても結果は出せません。そして、その言い訳として「自分に向いている業務ならば、もっと成果を上げられる」と言い出す人も見かけます。
しかし、社会はそんな甘えた言い訳に耳を貸してはくれません。自分の好きな分野、向いている仕事に就きたいと思うなら、まずは、「社会人として一人前になるべく、目の前の仕事を懸命にやってみる」というスタンスが必要なのではないでしょうか。
■夢は9割叶わない。
弘兼憲史
“世界の9割は、理不尽でできている”
たくましく生きるための「たった1つのコツ」
「こんなの理不尽だ」「世の中おかしい」。こんな思いをしたことはありませんか?そうです。社会は理不尽で、「正義」や「ルール」が通用しないことが多々あります。さて本日は、そんな現実社会の中でたくましく生きるための考え方をご紹介します。
「世の中は理不尽だらけ」。
まず、現実を知る
若い人が社会に出て、まず何を学ぶべきかと言えば、それは「世の中の理不尽さ」かもしれません。実際、世の中とは理不尽なことばかりです。
上司は勝手なことを言うし、その上司の言う通りにしていたら、今度は別の上司から「何をやっているんだ!」と叱られる。あるいは、教えてもらってもいない仕事を押しつけられて、いろいろ手間取っていたら「いつまでチンタラやってるんだ!」と怒られる。
そんな上司に対して不満があっても、昇給やボーナスの査定、さらには昇進も上司の評価に左右される以上、基本的には我慢するしかありません。サラリーマンとして生きるのであれば、いつかこの壁にぶつかると思います。
こんな理不尽な話はないと思いますが、これが現実なのです。
最近は、学校の先生に体罰を受けることもほとんどなくなり、地域のガキ大将に理由もなく殴られることもなくなりました。その分、陰湿なイジメが横行しているのかもしれませんが、概して最近の子どもや若い人たちは「理不尽さ」に慣れていないように感じます。理不尽さへの耐性が低い。これは大きな問題だと思います。
誰も助けてくれない。
それが現実
ちなみに、僕は大学生のころ寮暮らしをしていて、実家からは毎月2万円の仕送りをもらっていました。貧乏学生のなけなしの生活費です。
ところが、この仕送りが届くころになると、決まって先輩から電話がかかってきて「おまえ、仕送り届いたか?」と聞かれました。それで「はい、2万円届きました」なんて正直に言ってしまうと、「じゃあ、それ持って出てこいよ」と無理矢理呼び出され、新宿や下北沢へ飲みに行くわけです。
ときには、キャバレーのようなところへ連れて行かれ、店の女の子と一緒に飲んで、騒ぐこともありました。ひとしきり騒いだ後、お会計はもちろん僕の仕送りから払うことになります。当然ながら、後日返してもらえるなんてこともありません。
たまたま寮には朝食と夕食がついていたので、昼食さえ我慢すれば何とか生活はしていけました。でも考えてみれば、こんな理不尽な話はないでしょう。
しかし、文句を言っても仕方がないのです。それが現実なのですから。自分で何とかするしかありません。
世の中から「理不尽」は消えない。
たくましく生きるには?
誰も助けてくれないわけですから、こっちも頭を使うようになるわけです。
毎月、仕送りの2万をまるまるふんだくられてはたまらないので、「今月は5000円しかありません」などと適当な嘘をついて、何とか手元のお金を確保するなど、さまざまな工夫をしていました。
社会に出て理不尽な思いをしたとき、「パワハラだ!」と正当性を主張したり、騒ぎ立てたりする人が多いと聞きます。
しかし、そもそも世の中は理不尽なのですから、「世の中とは、そんなものなんだ」と開き直ったほうが”楽”ではないでしょうか。
何を言ったって、世の中から「理不尽さ」はなくなりません。だから、その「理不尽さ」を学び、「理不尽さ」の中でたくましく生きていく術を身につけるほうが、はるかに現実的な対処法だと思うのです。
[いずれもDIAMOND online]
Posted by nob : 2014年05月31日 09:57
食生活、運動に加えて、心と身体の健康管理の根幹、、、当たり前過ぎて意外に難しい。。。
■人生の3分の1を占める睡眠を見直す「快眠」を呼ぶ7つの方法
今日も眠れない。せっかく寝たのに、夜中に目が覚める−−。安眠グッズを買ったり、寝酒と称して就寝前に酒を飲んでみたがダメ。こんな体験をお持ちの方は多いはずだ。熟睡できない原因は何なのか。原因がわかれば、熟睡できる方法も見えてくる。
「ただ寝付けないだけでなく、せっかく眠れても夜中に目が覚めてしまう。人に勧められて安眠グッズなどの商品を試したが効果がない」
こう嘆くのは、都内に住む会社員Kさん(50)。とくに最近はひどく、布団に入ったのに何時間も寝付けない。眠れないので考え事をしてしまい、かえって目がさえてしまう。
「結局、会社に行っても集中力が出ない。昼食を取れば眠くてどうしようもなくなるんです。仕事に支障が出るし、体調もすっきりしない日々が続きました」(同)
精神的にも不安定になったため、Kさんは思い切って医療機関で治療を受けることにした。
「先生との問診を繰り返すうち、体のどこかが悪いとか、肉体的に欠陥があるわけではなく、生活習慣を改善することで良質な睡眠が取れるようになることがわかったんです。指導に従って意識改革して努力をしたら、徐々に熟睡ができるようになり、気持ちも落ち着きました」(同)
誰もが子供の頃はぐっすり眠れていたのに、大人になると不眠に悩む人が増える。そんな人が、'96年に約43万人だったのが、'08年には何と104万人以上(厚労省調べ)と、2倍以上に膨れ上がってしまったのだ。
厚生労働省が今年3月に公表した「健康づくりのための睡眠指針2014」によると、一晩の睡眠時間は人それぞれだが、成人後の一晩の睡眠時間は20年ごとに30分程度減少し、早寝早起きの傾向が強まっているという。
同指針では「日中の眠気で困らない程度の自然な睡眠が一番」とし、午後の早い時間帯に30分以内の短い昼寝をすることが作業能率の改善に効果的だと明記している。
指針の検討委員会座長を務めた日本大学の内山真・主任教授(精神医学)は「体を横たえずに、椅子にもたれて目をつぶるだけでもリフレッシュする」としているが、注意も必要で、「30分以上眠ると起きてから頭が働き始めるまで時間が掛かり、かえってよくない」とも話している。
また、仕事に支障を来たすほどの眠気は睡眠不足のサインで、「慢性的な睡眠不足は昼寝では補えない。毎日十分な睡眠を取り、体調を整えることが基本」と強調している。
「人生の3分の1に当たる睡眠時間は大変貴重です。もし睡眠不足に陥ったり悩んでいるなら、1日でも早く是正し、快適な日常生活が取り戻せるようにしないといけません」
と、“脱ダメ睡眠法”を説くのは、東京社会医療研究所の片岡幸誠主任だ。
「私たち人間は、朝起きてから寝るまでは“活動”であり、夜寝ているときは“休息”です。健康的な人生を送るには、活動と休息のバランスがとれていなくてはいけません。日中、過度、あるいは過少な活動、加えて就寝前に間違った活動をすれば、眠りは自ずとダメになる。そもそも眠りは、休息のためにあるのではなく、活動のためにあるもの。いい眠りは有益で効果的な活動に結びつくし、健康的で人生を豊かにすると思います」(同)
良い睡眠のための七箇条
そこで、片岡氏など専門家の意見を参考に、悪い睡眠、ダメ睡眠からの脱出法として次の点をまとめてみた。
(1)入浴にひと工夫
寝る前の入浴は就寝3時間前に済ませる。ややぬるめ湯で短く。湯温は42℃を超える熱いお風呂だと交感神経が刺激され、睡眠が浅くなる。ぬるめは逆に交感神経の緊張を和らげる効果がある。リラックス・バスタイムにはエッセンシャルオイル、アロマバスなどがお勧め。
(2)夕食の取り方にもひと工夫
全てを実行する必要はないが、食事は落ち着いた所、落ち着いた環境で、毎日ほぼ同じ時間に取るようにしたい。就寝直前に食べてはいけない。食事中は仕事、読書、テレビを見るのを避ける。昼食はしっかりと食べ、夕食は量、質ともに軽くすべき。
(3)夜遅くの買い物を避ける
一般的なリビングの明るさは300〜500ルクス程度だが、スーパーなどの照明は1000〜1500ルクスもある。交感神経を活発にし、「睡眠ホルモン」のメラトニンという物質の分泌を妨げることになり、夜遅くなっても眠気が訪れず、睡眠質の低下を招く。早目に用事を済ませたい。
(4)コーヒーなどカフェイン飲料は夕方以降の飲み過ぎに注意
カフェインは寝つきのよし悪しだけでなく、睡眠の深さにも影響する。睡眠の研究者によると、250mgのカフェインを摂ると中途覚醒が頻繁に起こることがわかっている。カフェインの覚醒作用は約4時間続き、体質によっては10時間以上も続くといわれている。夕方以降、とくに就寝近い時間帯にはノンカフェインの飲料に切り替えるのがベター。コーラー、栄養ドリンク、ココア、玉露、紅茶などはカフェイン入りだ。
(5)寝酒は入眠を助けるが、睡眠は浅い
就寝前の“寝酒”は日中の緊張を解放しリラックスさせ寝つきはよくなる。しかし、アルコールが分解されていくにつれて交感神経が優位に立ち、全体的に眠りが浅く、人によっては夜中に目が覚めやすくなる。翌朝早く目が覚めるのは、眠りが浅く、十分な睡眠が取れていない証だ。
(6)運動は適度なものに限る
運動は睡眠にとってよい影響がある。種類によるが、基本的にはセレトニンの分泌を増やすことになり、睡眠ホルモン・メラトニンの分泌量が増えて快眠につながる。だが、体力の半分を超えて行う運動は、逆に体に疲労が残ってしまう。口で息が始まる(ハアハア、ゼイゼイ)・汗をダラダラかき始めてきた・1時間休んでも疲れが残っている…などの状態になる場合、逆効果になる。
(7)就寝前の考え事はやめよう
精神的なストレスがあると、ベッドに入ってからも、いろいろ考え事をしてしまう。これは交感神経を刺激する要因にもなる。精神科医によれば「寝る前にネガティブなことを考えていると悪夢を見る確率が高くなる」という。就寝前はできるだけ、リラックスできる環境を整えることが、熟睡の大事な要素なのだ。
[週刊実話]
■不調の原因はコレかも?知られざる「pHバランスの乱れ」症状と対策
皆さん、“pH(ペーハー)バランス”という言葉を聞いたことはありますか? 実はこのpHバランスが崩れている人が急増しているというのです。
体内のpHバランスが崩れると、疲労、不眠、イライラなど、心身に悪影響を及ぼし、肌もボロボロになるという、まさに美容と健康の敵です。
また、さらに恐ろしいことに、pHバランスの崩れは、自分で気付かない限り、見つけにくい症状なのです。病院に行っても体調の悪さが改善されず、精神科に行く方もいるといいます。
そこで今回は、pHバランスの乱れの兆候と対策について、アメリカの健康サイト『LIVESTRONG』の記事を参考にご紹介します。当てはまっていないかどうか、一緒にチェックしていきましょう。
■pHバランスとはいったい何?
そもそもpHとは、水素イオンの濃度のことで、酸性とアルカリ性の度合いをpH0〜14の数字で表し、pH7を中性として、それより小さいと酸性、大きいとアルカリ性となります。そして、体内のpHバランスについて一般的に理想とされているのが、弱アルカリ性と言われるpH7.3~7.4です。
しかし、食生活や喫煙、アルコール摂取、ストレス等の原因で、酸性へ傾いている人が増加しているそうです。
■pHバランスが酸性に傾くとどうなる?
体内のpHバランスが酸性に傾くと、心身に悪影響を及ぼすといいます。症状としては、不眠、頭痛、低血圧、疲労感、エネルギー不足、低体温、免疫力の低下、乾燥肌、歯の過敏性、爪のもろさ、あくび、便秘、頭痛、下痢や精神的なイライラなどが特徴とのこと。
実は、“なんか体調が悪い”という方は、このpHのバランスが酸性に傾いていることが多いということです。
■pHバランスがアルカリ性に傾くとどうなる?
逆に体内のpHがアルカリ性に傾くとどうなるのでしょうか? この場合は、筋肉のけいれんなどが主な症状として現れますが、全く症状がでない場合もあります。また、過呼吸などで、二酸化炭素が体内に不足した際にも、この症状になるとのことです。
■pHバランスを元に戻すには?
簡単に言うと、酸性に傾いた身体をアルカリ性に戻すには、アルカリ性の食べ物を食べればよいのです。アルカリ性の食べ物とは、アボカド、イチジク、蜂蜜、レーズン、ココナッツ、果物、野菜、大豆製品などです。
それとは逆に、アルカリ性に傾いた場合は、酸性の食品を摂取するようにしましょう。アスパラガスや、コーヒー、アルコール、肉、卵、お茶やお酢などです。また、酸性の食品だけ摂取していてもかたよりすぎて良くないので、電解質ドリンク等を飲むこともお勧めです。
以上、pHバランスの乱れとその対策についてご紹介しましたが、いかがでしたか? 体内のpHバランスを自分ではかれるキット等もあるので、気になる方は試してみてください。
体調が悪く、上記の症状が当てはまるようでしたら、pHバランスが崩れている可能性が高いので、食生活や生活習慣を見直してくださいね。慢性疲労の原因がpHバランスの崩れだった、ということもあるかもしれませんよ。
[週刊ポストセブン]
Posted by nob : 2014年05月31日 07:40
また旅立つ君へVol.41/やりたい人はやれば、やめたい人はやめれば、その時々の納得の基準を自他どちらに求めるかだけの差、、、自らの内なる心の声に従えばいいだけのこと。。。Vol.2
■自分のために生きる勇気~人生の舵をとるために考えたいこと
成功に不可欠なのは
「人材の借り物競争」!?
―――白木夏子×南壮一郎対談後編
金融の世界から体ひとつでスポーツビジネスへ転身し、そして最近ではインターネットの世界で起業した株式会社ビズリーチの南壮一郎氏と、ジュエリー業界の経験ゼロからブランドを立ち上げたHASUNAの白木夏子さん。人生に迷いがある人に絶対に読んでほしい、『自分のために生きる勇気』刊行記念対談後編。
何もないから、頑張れる
南 前回、「持たない生活」のお話を白木さんがされていて、僕もそういえばいつも捨ててきたな、とふと思い出しました。
白木 捨ててきた、というと?
南 僕は小さいころからずっとマイノリティでした。幼稚園で突然父親の転勤でカナダに移住して、唯一のアジア人になった。中学・高校は田舎の町の帰国子女。大学ではまたアメリカに行き、体育会サッカー部に入るも、体育会では珍しいアジア人。金融の世界に入ったと思ったら、今度はスポーツビジネスに飛び込む。そして気づいたら今はインターネットの世界へ。――いつも、「お前は何者だ」と言われてきたわけです(笑)。常に積み上げたものを捨ててきて。
白木 長い時間をかけて構築したコミュニティや文化を持ったことがなかったのですね。でも、お父様の転勤は致し方ないとして、ビジネスの世界に入ってからは、あえてご自分で捨てているように見えます。それは意図的なのですか?
南 うーん、結局、リセットした方が頑張れるんですよ。自分がゼロからのスタートだと、何かひとつ知識を得るごとに急激なカーブを描いて成長できる。でも、しばらく経つとその成長度合いは急激にゆるやかになっていきます。経済学的に言うと「限界効用逓減の法則」に近いのかな。
白木 みるみる成長していくから、初心者って楽しいですものね。
南 だから、ゼロの状態からイチをつくっていく、何かを得ていく、というプロセスにものすごく歓びを見出すようになって。
白木 なるほど。
南 20代は、自分が人生でいちばん楽しいと思える瞬間ってよくわかっていなかった。けれど、30代になって、僕は「何もない状態」が楽しめるとわかってきました。頑張っているとき、つまり夢中になっているときが楽しくて。だから、自分でそういう場を選んだりつくったりしています。
「できる理由」から始める
南 ビズリーチをアジアに展開させようと決めたとき、僕、日本のオフィスにある自分の席もなくして飛び込んでいったんです(笑)。
白木 ええっ。周りの方、困られなかったですか?
南 僕がいないなら、他の人がやるしかありません。僕、もともと父親の影響で駐在員になる夢も持っていたのですが、起業したときにこの夢はあきらめていて。でも、途中で気づいたんです。「自分で辞令出せばいいじゃないか!」って。
白木 あはは、社長ですものね。
南 「社長がいないと会社が回りません」とさんざん言われましたが、そんなはずはない。僕ができないなら、誰かがやればいいだけの話ですから。
白木 自分じゃなくてもいい、できる人がやればいい、と。
南 僕は「できる理由から始めよう」を大切にしています。みんな、できない理由ばっかり並べるんですよ。できる理由から始めて、課題を解決していけばいいはずなのに。
白木 その方が面白いことが起こりそうですね。
南 そうです。人生も仕事も、課題が多い方が頑張れるじゃないですか。人間なんてだいたいフェアにできているので、環境や課題を与えられれば、みんなわくわくして頑張ると思います。でも、そういう環境に飛び込まないと課題にはぶつかれない。「課題解決を楽しんでやる!」と思ってあえて壁にぶつかりに行けばいいのではないでしょうか。
白木 そうですね。実は、私も将来、東京のほかにどこか2ヵ国を拠点にして、一年の3分の1ずつをそれぞれの国で過ごしたいな、と考えていて。それが直近の目標です。
南 おお、いいですね。
白木 将来的にHASUNAの海外展開も視野に入れていて、それなら、その場所に住めばいい、自分の手で展開していけばHASUNAのビジネスも個人の夢も両立するじゃないか、と気づいたのです。
南 なるほど。
白木 新しい土地に住んだり挑戦したりすると、新しい自分やぜんぜん知らなかった才能に気づいたりしますよね。きっと南さんもそうじゃないかと思うのですが。そういう、常に刺激がある人生を送っていきたいと思っています。
南 白木さんは本当に人生に前向きですよね。今まで、後悔するようなことはなかったのではないですか?
白木 いえ、とんでもないです! 後悔なんて数え切れないくらい、いっぱいありますよ(笑)。
南 へえ、それは意外です。たとえばどのような後悔ですか?
白木 そうですね。いちばん大きいのは、バックパッカーで旅していたとはいえ、もっと世界中を自分の目で見ておけばよかったということでしょうか。これは心から後悔しています。
南 どうしてできなかったのですか? お金がなかったから? 時間がなかったから?
白木 後回しにしていたのです。世界一周旅行は大学院に行く前の春休みにまとめて行こうと思っていて。でも、途中で「貧困を救うのは援助ではなくビジネスだ」と思い立って、結局大学院に行かずに日本に帰ってきたので、その機会を逸してしまいました。
南 そうだったんですね。
白木 だから、そのときの後悔を今のビジネスで実現しているのです。学生時代のときにお金もスキルも知識もなくて達成できなかったことを、今ならできる。時間をかけてでも「できる」になっている。そういうことが嬉しいですね。
いろいろな人の力を「借り物競争」する
白木 私、南さんの二冊目の本『ともに戦える仲間のつくり方』がとても好きで、「一歩を踏み出したいすべての人が読むべき」と、いろいろな方に薦めています。
南 ありがとうございます。
白木 特に、「自分より優秀な人を巻き込む」というところが印象的で。何かを始めようというとき、「自分で全部やらないといけない」「自分の言うことを聞いてくれる人を集めなきゃ」と思ってしまいがちですから。
南 そうですね。ただ、僕がラッキーだったのは、いざ立ち上げようとしていたインターネット事業について、僕がいちばん詳しくなかったということ(笑)。つまり、みんな自分より優秀だったんです。普通、事業を始める人って「自分ができること」で始めるじゃないですか。
白木 そうですね。興味がある、詳しい、実績がある。たいてい、そういうところから選びますよね。
南 そうすると、自分の発想を表現しがちになるんです。もし僕が金融業界で会社を立ち上げていたら、経験もあるし土地勘もあるから、もっと口を出してしまっていたと思います。あえて知らないことを始めるというのは、ひとりよがりな自分を抑えるコツです。なぜかと言うと、誰かにやってもらわないと絶対にできないから。
白木 力を借り続けなければできないですよね。
南 多くのIT企業の創業者はITエンジニアではないですよね。頼らざるを得ないからこそ、自分も会社の中でひとつの役割分担になる。その方が絶対うまくいくと思います。
白木 私も最初のころは自分ひとりで会社を回していたので、まったくわからないことばかりでした。経営はどうするのか? 百貨店のバイヤーと出会うにはどうすればいいのか? PRやマーケティングはどうすればいいのか? ――そういう、自分にできないことをその道のプロフェッショナルに助けていただくしかなくて。人材の借り物競争、という感じでした。
南 ああ、「借り物競争」。まさにそういう感じですよね。
白木 「白木さんだからできたんじゃないか」と言われることもたくさんありますが、とんでもないです。私の右腕になってくれているデザイナーがいなければあんな素敵なジュエリーはつくれないし、ジュエリー業界歴十年以上のプロフェッショナルがいるから全店舗を統括できるし、数字を見てくれる役員がいるから安心して経営できます。みんなの力を少しずつ借りているだけなのです。
南 僕もそうです。「なぜ挑戦できたんですか?」「南さんだからできたんじゃないですか?」って聞かれることがとても多くて。白木さんと同じで、ぜんぜんそんなことないんですけどね。
あ、そういえば僕、社員に「南さんの口癖は『わからないから教えてください』だ」と言われるんですよ。
白木 それは、社員の方に対しても外部の方に対しても、ですか?
南 そうです。新入社員にも子どもにも、わからないことがあったらどんどん聞いてしまいます。何よりも「知ること」が楽しくて。自分が知ってることなんて、本当に少ししかないから。でも、たぶん人より不真面目だからすぐに聞いちゃう。
白木 不真面目?
南 本を読むより二十人の専門家に聞いた方が早いと思っていて。みんなが読んだり経験したりして解釈してくれたものを吸収できるじゃないですか。
白木 確かに(笑)。
南 誰しも、知識を伝えたいという本能があると思うんですよ。だから、知識の共有って、聞く側も聞かれた側もみんなハッピーになれると。もちろん、利用しているわけではないのですが。
白木 ええ、わかります。
振り返ったときに映画みたいな人生を送りたい
南 「優秀な人を巻き込む」という話をしましたが、僕はいつもいろいろな人に「とにかく巻き込み、巻き込まれよう!」と言っていて。
白木 巻き込むだけでなく、「巻き込み、巻き込まれる」?
南 そう。新しいことを始めることが偉いわけではありません。面白いことをやっている人を見たら、すかさず巻き込まれにいくことがとても大切で。
白木 ええ。
南 飲み会もイベントも面白そうだと思ったら無償で手伝えばいい。面白いチームの中にいれば、自然と「次は自分がやってみたい」と思うようになりますから。僕は楽天イーグルスの立ち上げに参画しましたが、言いだしっぺだったわけでも、トップだったわけでもありません。それでも、本当に楽しかったですよ。だからこそ、次は自分が、と思えた。
白木 やりたい仕事があったら、プロボノでもいいから職場体験をした方がいい、とは私もよく言います。何かを一生懸命にゼロから創り出そうとする姿を見るのはとても大切だから、と。
南 そういう人の近くにいると、トライすることへのハードルが下がりますよね。僕にとって、楽天イーグルスの立ち上げはある意味で練習試合だったのです。
白木 その感覚、とてもよくわかります。私がかつて勤めていた不動産投資会社はベンチャー企業だったのですが、創業社長の近くで仕事ができたことはとても大きな経験でした。私にとっては、あれが練習試合だったような気がします。
南 今ビズリーチにいる社員が将来、「僕にとってビズリーチは練習試合だった」と言って飛び出してくれれば、とてもうれしいですね。最大の学びは自分でやってみることですから。
白木 南さんは、10年後どうなっていたい、といったプランはありますか?
南 そうですね……そもそも、30歳のとき、「40歳になったら自由になっていたい」ということを目標にしていて。
白木 自由?
南 いつでも、どこでも、誰とでも、自分がやりたい仕事に就き、どんな状況やお客様に対してでも、付加価値をちゃんと創り出せるようなビジネスマンになりたいと。それが僕にとっての自由です。それが実現できるような力をこの10年でつけたい。そう30歳のときにひとつの目標にしたのです。
白木 なるほど。素敵ですね。
南 僕は「一生をかけてこれがしたい」というものが絶対的にあるわけでもなく、さまざまなステージで、その都度やりたいことが変わってきました。だからこそ、やりたいと思ったことはすぐやってみて、一つ一つの場面を思い出しながら「楽しかった!」と笑えるような人生にしたいのです。
白木 やっぱり南さんは「ネタになる」と同じく、「振り返ったとき」ですね。
南 そう、まったく未来志向ではなくて(笑)。今は、映画の1シーンをせっせとつくっているイメージです。将来子どもや孫に「映画みたいな人生だね!」と言われるような人生を歩みたいと思っているからこそ、リスクを楽しめているのかもしれません。
白木 私も勇気がわいてきました。今日は本当にありがとうございました!
■夢は9割叶わない。
弘兼憲史
“まあいいか、それがどうした、人それぞれ”
人生を心から楽しむための3つの言葉。
悩みを抱える。問題に直面する。人がうらやましくなる。人生は、自分の思い描いた通りにはなかなかいかないものです。そんなとき、あなたの心の支えとなってくれる「3つの言葉」をご紹介します。
苦しいときこそ、
この3つの言葉を思い出していた。
生きていく上で、僕は3つのキーワードをいつも大事にしています。
それは「まあいいか、それがどうした、人それぞれ」です。
この3つの言葉を思い描いていれば、たいていのことはやり過ごすことができます。
最初の「まあいいか」は、いい意味での諦めを指します。
松下電器時代、上司に怒られることはたくさんありました。漫画家になってからも、常に順風満帆で、最高の作品を連続して描けたわけではありません。周囲の人とちょっとしたトラブルになることもあれば、「良かれ」と思ってやったことが、かえって反感を買ったこともあります。
そんなとき、とにかく僕は「まあいいか」と思うようにしています。
たいがい人は「どうにもならないこと」をくよくよ悩んでいるものです。「過ぎてしまったこと」「起こってしまったこと」にいつまでも怒っている、というケースも多いのではないでしょうか。
でもそれは精神衛生上良くないし、そもそも時間と労力の無駄遣いではないでしょうか。
「それがどうした」。
思い切って、開き直ってみる
だから僕は、すぐに「まあいいか」と諦めてしまいます。そうやって気持ちを切り替え、すぐ次のことを始めたほうがいいからです。
その次の「それがどうした」は、言ってみれば開き直りです。
この本を読んでいる多くの人も「些細なこと」できっと悩んでいるはずです。職場で上司とうまくいかない。営業成績が上がらない。友人とケンカをしてしまったなど、いろんな悩みがあるでしょう。
でも、それはよくよく考えてみれば、どれもたいしたことではないはずです。「何かあったって、自分は今生きているじゃないか」、そう思えば、たいていのことはどうでもよくなります。
何らかの策を講じることで問題や悩みが解決するなら、すぐに動き出せばいいし、どうしようもないことなら「まあいいか、それがどうした」とやり過ごしてしまったほうがいい。そうは思いませんか。
「人それぞれ」。
自分と他人を比較しても、つらいだけ
最後の「人それぞれ」は、人と比較しないための言葉です。
人間は、自分と他人を比べることで、どんどん自分を追い込んでしまいます。
例えば、あなたが主任に昇進して大喜びしていても「同僚が課長になった」と聞けば一気に気持ちが暗くなる。
「なんで俺が主任で、あいつは課長なんだよ」といった卑屈な思いもわき起こってくるでしょう。
収入や生活レベルにしたって同じ。別に生活に窮しているわけでもなく、それなりに楽しく、満足した暮らしができているのに、「あいつは自分より給料が多い」なんて話を聞くと、どんどんストレスがたまってくるものです。
僕も松下電器を辞めるときには「おまえ、収入が下がるぞ」「みんなが高給をもらっている中、自分だけひもじい生活になってもいいのか?」とよく言われました。
「自分が楽しければ、
それでいいじゃないか」
実際は、収入が落ちるようなことはなかったのですが、もしあのときに、
「同期の連中に比べて、俺だけひもじい暮らしをするのは嫌だな」
「そんなの恥ずかしいな」
「プライドが傷つけられる」
などと思っていたら、大企業を辞めて漫画家を目指すことなど絶対にできなかったでしょう。
「自分が楽しければ、それでいいじゃないか」という発想があったからこそ、僕は僕なりの道を歩き始めることができたのです。
自分と他人を比べることに、ほとんど意味はありません。それどころか、自分自身を苦しめ、どんどんストレスをためるだけです。
だから人生は「まあいいか、それがどうした、人それぞれ」の精神で生きていったほうがずっと楽しいし、自分らしくやっていけます。悩みを抱えたり、問題に直面したり、人がうらやましくなったときには、ぜひこの言葉を思い出して下さい。少しは気持ちが軽くなるはずです。
[いずれもDIAMOND online]
Posted by nob : 2014年05月27日 18:25
また旅立つ君へVol.40/やりたい人はやれば、やめたい人はやめれば、その時々の納得の基準を自他どちらに求めるかだけの差、、、自らの内なる心の声に従えばいいだけのこと。。。
■自分のために生きる勇気~人生の舵をとるために考えたいこと
究極のリスクは死ぬことだから、
「何かが起こる方」に賭けるしかない。
―――白木夏子×南壮一郎対談
金融の世界から体ひとつでスポーツビジネスへ転身し、そして最近ではインターネットの世界で起業したビズリーチの南壮一郎氏と、ジュエリー業界での経験ゼロからブランドを立ち上げたHASUNA白木夏子さん。異色の経験を持つ二人が語ったのは、リスクについてでした。人生に迷っている人、必読です!(構成・田中裕子)
特別な人間なのではなく、自分のリスクを把握できただけ
白木 今日は、ずっと尊敬していた株式会社ビズリーチの南壮一郎さんとの対談が実現して、とても嬉しいです。
南 G1サミット(*編集部注・日本、世界を担っていくリーダー達が学び、交流する「日本版ダボス会議」を目指して創設されたプラットフォーム)などでご一緒はしているけれど、なかなかちゃんとお話する機会はなかったんですよね。今日はよろしくお願いします。
白木 よろしくお願いします!
南 早速ですが、今日、せっかくだから聞きたいと思っていたことがあるんです。僕、講演会でよく「自分は南さんみたいに元気ではないし……」と言われるんですが……。
白木 元気(笑)。
南 でも、確かに世の中には挑戦する人としない人がいるな、と思って。じゃあ「挑戦した人」である白木さんの元気の源って何なんだろう? ということを聞きたくて。
白木 元気の源、ですか?
南 たとえば、挑戦するときの「怖い」という感情とどう向き合ってきましたか? 一歩を踏み出すとき、少なからずありますよね、そういう感情。
白木 そうですね……。いろいろな思考法はこの本に書いたのですが、いちばんは「人生を棒に振ることが最大のリスク」と考えることでしょうか。
南 なるほど、人生を棒に振ること。白木さんの「棒に振る」はどういう定義でしょうか。
白木 やりたいこともできず、毎日を鬱々と過ごすこと、です。このまま晴れない心を持ちながらなんとなくおばあちゃんになってしまうんだろうか、「やりたいことができなかったなあ」と思いながら死んでしまうんだろうかって考えると、「それは嫌だ!」って。
南 白木さんにとって時間こそが宝なんですね。いや、本当に共感します。何もしないでだらだら過ごすことは最大のリスクですよね。
白木 そうなんです。南さんはいかがですか? 多くの方は「失敗するかも」という恐れから足がすくんでしまうのだと思いますが、そういう気持ちとどうやって折り合いをつけていらっしゃいますか?
南 失敗に怖気づくと、現状維持に逃げてしまいそうになりますよね。そういうときは、自分に言い聞かせてるんです。「失敗したらどうする? ネタにすればいいじゃないか!」と(笑)。
「失敗したら、ネタにしよう」とは?
白木 あはは、ネタにする。
南 そう。だって、ネタって、ひとと違うことをしないと生まれないじゃないですか。居酒屋で、「昨日は電車に乗って出社して、エクセルで表をつくって、ランチを食べて、資料をまとめて退社しました」というストーリーを話されたら、どうですか?
白木 うーん、いまいち盛り上がらないかもしれませんね。
南 そう。ネタって人と違うことをすること、つまりは挑戦することからしか生まれないんです。それって、エピソードとして客観的に見たらものすごく興味深いじゃないですか。聞いていて面白いし。
白木 確かに。
南 だから、怖気づきそうになったら、3ヵ月後のとある飲み会にワープした姿を想像するんです。「南、お前、面白いことしたんだって?」「そうそう、実はあのとき……」って盛り上がっているはずだって。
白木 そう思えるのも南さんの心が強いからだと思いますが(笑)。
南 ちがうちがう。僕だって普通の人間だから、失敗したくないし、悪口も言われたくないし、人に迷惑だってかけたくないと思ってるんですよ。だから、これは「おまじない」なんです。怖気づいたときに心理的なバリアを取り除くための。
白木 「おまじない」ですか。なるほど。
南 そういう「おまじない」を自分にかけつつ、小さいことを積み重ねて、一歩を踏み出し続けているだけなんです。
白木 でも、南さんがされていることは決して小さいことではないですよね。金融業界からスポーツビジネスに転進して楽天イーグルスの立ち上げを行ったり、ネットベンチャーを起業されてわずか5年で400人規模の組織に成長させたり。
南 自分の中ではそう考えているんです。あまり高尚に考えすぎると、気張ってしまって失敗するリスクが逆に大きくなってしまうんですよ。だから、僕は人と違うチャレンジをするときは「自分の人生をくすぐる」くらいの軽いイメージを持っています。小さい話じゃないか、と。でも、そういう小さい一歩一歩を積み重ねていかなければ、大きなことはできないと思っています。
リスクは、社会が勝手につくったルールでしかない
白木 南さんの最初の大きな挑戦は、やはり金融業界からスポーツビジネスに転身しようと決められたときですか?
南 そうですね。そのとき、人生で初めて「リスク」という言葉を意識したかもしれません。
白木 確かに、人生のリスクって学生時代にはなかなか実感しませんものね。
南 同じ会社に居続けることを想定すると、サラリーもキャリアも、なんとなく未来の想像がつくじゃないですか。ロールモデルもいるし、5年後、10年後、20年後の姿が「見える」というか。初めてそのレールを踏み外すという選択を考えたとき、何も見えなくなってしまったわけです。ものすごく怖くなりましたね。
白木 その恐怖をどうやって乗り越えたんですか?
南 そのときは、やればできる、と思ってがむしゃらに(笑)。でも、実際挑戦してみて思うのは、普通のことを一生懸命やれば意外とできてしまう、ということ。とにかく、世の中にはがむしゃらにやる人が圧倒的に少ないだけ。リスクという言葉は、社会が勝手につくったルールでしかないんです。
白木 なるほど、やらない人にとってはそう見えるというだけなんですね。では、当時はとりあえず目をつむって恐怖を乗り越え、スポーツビジネスの世界に飛び込まれた、と。
南 最初はビジネスの世界に飛び込んだというより、あまりにもツテもアテもないので、ひたすら自分を営業していましたね。そうそう、営業と言えば、26歳のとき単身アメリカに渡りました。映画『マネーボール』のモデルにもなったメジャーリーグの球団、オークランド・アスレチックスのGMに会いに。
白木 スポーツビジネス経験ゼロ、しかも26歳の日本人がいきなりGMを狙うなんてすごいですよね。会って、どうされようとしていたんですか?
南 もちろん、「仕事をください」と直談判しようと思って。でも、当然アポなしだから、受付の女性に門前払いされてしまったんです。「お約束がございませんから」と取り付く島もなくて。こんなとき、白木さんならどうされますか?
白木 うーん……。アポイントを入れていないわけですから、帰るかもしれません。
南 いや、普通、帰りますよね。でも、僕は居座ったんです。受付の前で3時間以上。
白木 3時間以上も、ですか!
何かを得たいのであれば、「恥ずかしい」を乗り越えなければならない
南 そう。だって、「言われるがままホテルに帰って、日本に戻って、何か得るものはあるか?」って考えたら、何もなかったから。もちろん、受付の前に日本人が長時間居座っていると目立つし、変な目で見られるし、決して歓迎されていないのはわかるから、ものすごい心理的な負担は大きかった。でも、何か起こるか起こらないかとしたら、少しでも起こる方に賭けたくなったんですよ。
白木 やるかやめるか、どちらかしかないですものね。
南 やめるのって本当に楽で簡単です。むしろ、やめることが常識。やることは非常識。でも、あとあと人に話して面白がられるのは、非常識な行動をとった話じゃないですか。だから、待てるだけ待とう、と。
白木 やっぱり「ネタになるかどうか」は重要なんですね(笑)。
南 それに、待って自分が失うものって何もないなと思って。それどころか、もし、結局会えなかったとしても、あとあと日本で「お前、どれくらい待ったんだよ」と聞かれたとき、「いやー、3時間粘ったんだけど」という話題になるでしょう? その方が面白いな、と(笑)。それに、何かビジネスチャンスがあるときにこの話をしたら、熱意も伝わるじゃないですか。
白木 そうですね。結局、GMにはお会いできたんですか?
南 そう、それがラッキーなことに、3時間経ったころ、受付のお姉さんが不憫に思ったのかGMの右腕の方に会わせてくれたんです。
白木 すごいですね!
南 そこから直接ビジネスにつながることはなかったけれど、確実に人生の積み重ねになりましたね。今もこうしてお話できているわけですし。
白木 私も、悩んだ末に起業していろいろな壁を乗り越えて学んだのは、何かを得たいと思うのであれば「恥ずかしい」を乗り越えないといけない、ということでした。恥ずかしいのは人と違うことをするからこそ生まれる感情です。でも、その違いにこそ価値があるんですよね。
南 そのとおりだと思います。リスクっていろいろ頭をよぎってしまうんですけど、結局、究極のリスクって死ぬことなんですよ。
白木 ああ、そうですね。本当、そのとおりです。
南 人生うまくいった、いかなかった、なんてプライドの問題でしかない。究極のリスクではないわけです。だから、「これが失敗しても、死なないし」という言葉も僕のおまじないのひとつです。「もし事業がつぶれてしまっても、死なないから」と。そのときはまた頑張ればいいんですよね。
白木 そうですよね。私も、かつてバックパッカーとして世界中を旅してから、「大丈夫、死なないから」という気持ちは強く持つようになりました。人間、劣悪な環境でも生きていけるんだって。それに、バックパッカーは最小限の荷物、最低限のお金を持って旅をしていくのですが、その経験から「持たない生活」もできるんだ、ということが分かったんです。
南 なるほど、「持たない生活」ですか。
白木 今の日本は豊かですから、ついつい持ちすぎてしまうんですよね。でも、そういう旅を経験していると、「自分は持たない生活にも適応できる」という確信を持てる。モノを持たないことを怖れなくなったんです。
南 だからこそ、一回いろいろなものを失ってしまってもまた復活しようって思えるのですね。
■夢は9割叶わない。
弘兼憲史
“夢を諦めず、がんばり続けるのは正しいのか?”
人生をより良くするには「やめる決断」が必要。
「努力すれば、夢は叶う」「がんばることは素晴らしい」。学校や社会の中で、この価値観を教えられてきた人が多いかと思います。しかし現実問題として、本当にこの考え方は正しいのでしょうか。人生を充実させることができるのでしょうか。
「夢を諦めずにがんばり続ける」のは、
本当に正しいのか?
夢を持つのはすばらしいことです。でも、夢には期限をつけるべきだと僕は思っています。
前回の記事でも述べましたが、僕の知人に、芸大合格を目指して5年、10年と挑戦し続けている人がいました。そんな人に対して「夢を諦めずにがんばっているなんて、すごい!」と評価する人も大勢いますが、僕は懐疑的です。
もちろん、がんばること自体を否定するつもりはありません。
しかし、「芸大合格を目指していたら、30歳になっていた」ら、その人の人生は本当にそれでいいのだろうかと思ってしまいます。
仮に芸大に合格しても、それで画家になれるわけでも、イラストレーターになれるわけでもありません。飯が食える保証など、どこにもないわけです。
こんなことを言うと、「世の中には何十年も不遇の時代、下積みを経験した後に成功する人もいるじゃないか」と反論する人が出てきます。テレビや雑誌は、そんな「不遇の成功者」をとり上げ、美談に仕立て上げるのが大好きです。
1人の成功者の陰には、
何十万の「夢破れた人たち」がいる
しかし、その「成功者」がほんのひと握りであることは、あまり強調されません。
1人の成功者の陰には、何千、何万、何十万の「夢破れた人たち」がいます。人生を台無しにしてしまった人もいるでしょう。
厳しい現実に蓋をして「がんばり続ければ夢は叶う」「諦めなければ、失敗はない」という聞こえのいいメッセージだけを発し続けるのは、やっぱり僕は違うと思います。現実は現実として、シビアに向き合うべきなのではないでしょうか。
しかし、「夢を持つな」と言いたいわけではありません。僕がここで言いたいのは「夢に期限をつけること」。
スポーツ選手や芸能人、漫画家、芸術家、会社社長、弁護士、会計士などいろんな夢を持つのはいいでしょう。
でも、その夢を無計画に、一生(あるいは何十年も)追い続けるのはあまり得策ではないと思います。
「30歳までがんばってダメだったら、
きっぱり諦めよう」
例えば僕の場合、大卒で入った会社の松下電器産業(現在のパナソニック)を3年で辞めて、漫画家の道を目指しました。
漫画家になれる人なんて、万に1人、十万人に1人、いえ、百万人に1人の世界でしょう。そんな世界を夢見て、せっかく入った大企業を辞めるなんて、それこそとんでもない決断です。普通に考えれば、無謀な選択以外の何物でもないでしょう。
しかし、僕だって若いなりに夢に期限をつけていました。会社を辞めたのが25歳だったので、「30歳までに自分の作品が印刷され、出版されなければきっぱりやめよう」とはっきり決めていたのです。
たまたま、最初に応募した作品『風薫る』が入選して、『ビックコミック』に掲載されることになりました。今から40年前の、1974年のことです。包み隠さずに言えば、才能があったのかもしれないし、運も相当良かったのでしょう。
だから結果として「夢の期限」が訪れる前に、1つの夢を叶えてしまったわけです。とはいえ、夢に期限をつけることはとても大事だと、今でも思っています。
人生をより良くするには、
「やめる決断」が必要
なぜなら、「何かをやめる」というのは、本当に難しいからです。
結婚より離婚のほうが難しいとよく言われます。確かにその通りで、たいていの物事は始めるよりも、やめるほうがはるかに困難です。自分が長い間がんばり続けていることなら、なおさら大変だと思います。
自分の能力に見切りをつけるのはさらに難しいでしょうし、「これまで費やした時間と労力が無駄になるのでは?」と考え始めたら、どんどん先延ばしにしたくもなります。株で損をしている人が「もうちょっとしたら、再び値が上がるんじゃないか」と思うのと似たような心境です。
しかし、人生をより良く生きるには、「やめる決断」が必要なのです。そんな決断を後押ししてくれるという意味でも、あらかじめ「夢に期限をつけること」が大切なのではないでしょうか。
期限をつけたら、そこまでは迷うことなく、必死でがんばる。でも、期限までに夢(あるいは、それに向かう段階)を達成できなかったのなら、潔く諦める。
そんな戦略と見極めが、人生には必要だと思います。
[いずれもDIAMOND online]
Posted by nob : 2014年05月26日 20:10
食生活と生活習慣を変えれば心と身体は変わる、、、一年続ければすべての細胞ごとまったく新しい身体に生まれ変わる。。。
■医学博士 大西睦子のそれって本当? 食・医療・健康のナゾ
痩せない理由は腸内にあり? 腸内細菌叢を整える
食、医療など“健康”にまつわる情報は日々更新され、あふれています。この連載では、現在米国ボストン在住の大西睦子氏が、ハーバード大学における食事や遺伝子と病気に関する基礎研究の経験、論文や米国での状況などを交えながら、健康や医療に関するさまざまな疑問や話題を、グローバルな視点で解説していきます。
今回は腸内で健康を守っている「腸内フローラ」こと「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」と肥満の関係について。
いろいろダイエットをしているのに、なかなか痩せないと悩んでいる方。もしかしたら腸内細菌叢に問題があるかもしれませんよ。
2013年、米国セントルイスにあるワシントン大学のジェフリー・ゴードン博士らのチームが、「腸内細菌叢が肥満に影響する」という新たな研究成果を科学雑誌「Science」に報告しました。
■参考文献
Science「Gut Microbiota from Twins Discordant for Obesity Modulate Metabolism in Mice」
腸内細菌叢=腸内に生息する9000兆個以上の微生物群が作る生態系
そもそも、腸内細菌叢って、何でしょうか?
私たちの腸内には、重さにして約1〜1.5kg、少なくとも1000種類、9000兆個以上の微生物が生息しています。数だけで言えば地球上の全人口の100万倍以上というすさまじい数です。これらの微生物群が織りなす生態系を、腸内細菌叢あるいは「腸内フローラ」と言います。
腸内細菌叢は、アレルギーや皮膚疾患、脳、神経系疾患など、さまざまな疾患に大きな影響があることが明らかになってきましたが、何と言っても、肥満との関係が注目されています。
ゴードン博士らは2006年に、腸内細菌叢が肥満のリスクに影響することを報告。その後、栄養失調にも、腸内細菌叢が関与することを報告しました。
博士らのチームは、腸内細菌叢と肥満に直接関係があるかどうかを評価するため、1人が肥満で、もう1人は痩せているという、双子のペアを募集しました。これは双子であれば食生活や遺伝子が似ていて、肥満の原因が腸内細菌叢である可能性を絞り込みやすいという理由からで、最終的に、4組の女性の双子が選ばれました。
■参考文献
ロバルト・ヘルス「肥満も栄養失調も、原因は腸内細菌?」
肥満の人の腸内細菌を移植されたマウスはより多く脂肪が蓄積
研究者らは、それぞれの双子から腸内細菌を集めて、無菌のマウスの腸に移植。肥満の人からの腸内細菌を移植したマウス群と、痩せた人の腸内細菌を移植したマウス群を用意します。この両群のマウスは、標準的なエサ(同内容・同量)を摂取するようにします。その結果、肥満の人から腸内細菌を移植された無菌マウスは、痩せた人の腸から細菌を与えられた無菌マウスに比べて体重が増加し、より多くの脂肪が蓄積しました。
エサの条件が同じであるということは、この相違が、体内に入ってきた栄養素の代謝を変化させる、腸内細菌によって引き起こされているはずということになります。
細菌叢の戦いに勝つのは、痩せた人の腸内細菌
研究者らはさらに、2つのグループのマウスを一緒のケージに収容しました。マウスは糞を食べるのですが、そうなるとこれら2つのグループのマウスは、意図せずお互いの微生物によって、影響を受け合います。ゴードン博士は、これを“細菌叢の戦い”と呼んでいますが、この戦いの結果、肥満の人から腸内細菌を移植された無菌マウスは、痩せた人の腸から細菌を与えられた無菌マウスの細菌叢の影響で、体重が減りました。ところが、痩せた人から腸内細菌を移植された無菌マウスは、肥満の人からの腸内細菌の影響を受けませんでした。
なぜでしょうか? 肥満の人は細菌叢の多様性が少なく、特定の菌種に偏るという報告があります。これに対し、痩せた人の細菌叢は多様性に富むため、肥満の人の細菌叢を一方的に侵略できることが要因と推測されます。
腸内細菌を交換しても、食事を変えなければ減量に効果なし
ではなぜ、一般には、伝染病のようにマウスの痩せは広がらないのでしょうか?
重要なのは、この研究が「食事に左右されるもの」だったことです。
2つのグループのマウスを一緒のケージに収容させた際も、与えた食べ物によって結果に違いが出ました。食物繊維が多く飽和脂肪酸の少ない、健康的な食事を与えたときは、痩せた人の腸から移した細菌の影響をうけた肥満マウスは、体重が減少しました。
ところが、食物繊維が少なく飽和脂肪酸を多く含む、典型的な西洋食を与えたときには、 痩せマウスと肥満マウスは互いの腸内細菌の影響を受けないように見えたのです。要するに、腸内細菌を交換しても、食事を変えなければ減量に効果はないと考えられます。
■参考文献
Nature「Richness of human gut microbiome correlates with metabolic markers」
食事で腸内細菌叢を変えるには、どのくらい時間がかかる?
ここで、「よし、健康的な食生活に変えて腸内細菌叢を変えよう!」と思われた方、どのくらいで効果がでるか気になりますよね。
先日、ハーバード大学のターンバウ博士らが、食事を「完全な動物性食品(肉、卵やチーズなど)」から、「完全な植物性食品(穀物、レンズ豆、野菜や果物など)」に、あるいはその逆に変えると、腸内細菌叢は、なんと1日足らずで変化すると報告しました。
例えば、動物性食品の食事を摂ると、胆汁に耐性のある細菌、ビロフィラ・ワーズワーシア(Bilophila wadsworthia)が増えていました。ビロフィラ・ワーズワーシアは、炎症性の腸疾患との関係が示唆されている細菌で、この変化が私たちの健康にどのような影響を与えるかは、次回の研究成果が期待されますが、食物繊維の多い、バランスのとれた食事が、私たちの腸内細菌叢のよいエサになることは明らかです。
ちなみに、タンパク質や脂質の多い、低炭水化物ダイエットも、腸内細菌叢には良い影響を与えないようですね。
■参考文献
■Harvard Gazette「Your gut’s what you eat, too」
■Nature「Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome」
腸内細菌叢を利用した「痩せ薬」も出てくる!?
ところで、腸内細菌叢を利用した「痩せ薬」って可能なのでしょうか?
最近、大手の製薬会社が、腸内細菌叢を利用した治療薬の開発を進めています。
2014年5月2日、米国セカンドゲノム社は、製薬メーカーであるファイザー社と提携し、大規模な観察研究によって、腸内細菌叢と肥満や代謝疾患の関係についての研究を行うことを発表しました。さらにこの研究により、腸内細菌叢が、肥満などの治療薬のターゲットになる可能性があります。科学の進歩の速さには本当に驚かされますが、とはいえ研究はこれからといったところ。すぐに夢のような「痩せ薬」ができることはなさそうですね。
つまり私たちが、今すぐ今年の夏に向けてできるとこは、食生活を改善し、健康的な腸内細菌叢で、肥満やメタボリックシンドロームの予防することですね!
■参考文献
■Second Genome「Second Genome Enters Into Agreement with Pfizer Inc. on Microbiome Research Initiative in Obesity」
[NIKKEI TRENDY NET]
Posted by nob : 2014年05月23日 16:59
私の雑穀白米は雑穀と白米の比率がほぼ同じ(笑)、、、最近では酵素玄米5・玄米1・雑穀白米1くらいの割合です。。。Vol.2
■不健康・不規則な食生活から抜け出せない人に!
想像以上に栄養価が高い「雑穀」活用のすすめ
雑穀ごはん、雑穀クッキーなど、最近耳にする機会が多くなった「雑穀」。ランチのときに定食屋やレストランなどで、「雑穀米にしますか?それとも白米にしますか?」と聞かれた経験のあるビジネスマンも多いのではないだろうか。しかし、いざ「雑穀って何?」「どのような栄養が含まれているのか」と聞かれると、よく知らないという人がほとんどでは? じつは筆者もその一人なのだが、そんな“雑穀初心者”にぴったりなセミナーを見つけた。
大阪・梅田にあるアサヒグループのコミュニケーションスペース「アサヒ ラボ・ガーデン」で開催された『“キレイ”にうれしい雑穀パワー』だ。
聞けば雑穀には、食物繊維のほか、ビタミン、ミネラル、ポリフェノールなど、人が若々しく健康であり続けるための栄養素がたっぷり含まれているという。「不規則で不健康な食生活を続けてしまっているが、仕事が忙しくてなかなか改善できない」、「最近太ってきたけどダイエットに取り組む時間がない」といった人にはピッタリの食材なのだ。
ブームになりつつある雑穀
4月18日に開かれたセミナーの講師は、雑穀クリエイターの梶川愛さん。日本で初めて雑穀クリエイターの資格を取得し、10年以上も前から雑穀の魅力を広める活動を続けてきた女性だ。
まずは「雑穀」の定義から。
雑穀とは「日本人が主食以外に使用している穀物の総称」である。思い浮かべやすいのはキビ、アワ、ヒエ、大麦などだが、そば、豆類、ゴマ、黒米、赤米、玄米、キノア、アマランサスなども雑穀として扱われる。
これらの雑穀を食べている人は10年前にはかなり少数だったが、ここ5、6年の間に認知度は急上昇、美容や生活習慣病を気に掛ける人を中心に静かなブームになりつつあるそうだ。
雑穀ごとに特徴があるのだが、まずは雑穀すべてに共通する魅力を梶川さんが挙げていった。それが「よく噛むようになる」「エネルギー代謝が良くなる」「錆びにくい身体になる」の3点である。
雑穀の力(1)「噛むことで健康になる」
雑穀の魅力として最初に挙げられたのは「よく噛むようになる」。噛むことでどんな良いことがあるのか?
「ものを噛むと唾液が出ますね。この唾液には抗菌作用のあるラクトフェリンやリゾチウムが含まれており、免疫力をアップさせます。また若返りホルモンと言われているパロチンや、EGFと呼ばれる美容成分も唾液には含まれているんですよ」と梶川さん。

キビ、アワ、玄米を始め豆類、ゴマなども「雑穀」
また、噛むという行為そのものが血流を良くし、学習能力の向上や認知症の予防にもつながるほか、満腹中枢を刺激することによって食べ過ぎの抑制効果もあるという。
「ところが現代ではよく噛んで食べることが少なくなりました。戦前には1回の食事で約1400回咀嚼していたのが、今では約600回に。食事時間も 22分から11分に短縮されました。噛み応えがあり、自然に咀嚼の回数を増やしてくれる雑穀は、唾液の出やすい身体をつくる上で非常に有効なんです」
雑穀の力(2)「代謝の良い身体をつくる」
次に挙げてくれた雑穀の魅力は「不足しがちなビタミンやミネラルを補い、エネルギー代謝しやすい身体をつくる」だ。
体内の生理機能や代謝などの生命活動を維持する上で、欠かすことのできないビタミンやミネラル。ミネラルはすべて、ビタミンも多くのものは体内で作ることができないため、意識して摂取する必要があるのだが、雑穀にはそれらが豊富に含まれている。
「野菜や果物もビタミンやミネラルが多い食材ですが、昔に比べてその量は減ってきています。その原因の一つとして、旬を無視した栽培や品種改良などが考えられます。その分を雑穀で補っていただければと思います」
また雑穀には糖尿病、心筋梗塞、高血圧、痔、便秘、大腸の病気などを予防する効果があるとされる食物繊維も多い。
厚生労働省によると、食物繊維の摂取量は成人で20~25gとすることが望ましいとされているが、欧米型に変化した現在の食生活では不足しがち。そこを雑穀でカバーしてほしいと梶川さんは話す。
「食べずに痩せようとするのは絶対にダメ。お肌はボロボロになり、頬はこけ、きれいに痩せられません。それよりもエネルギー燃焼しやすい身体をつくることが大切。雑穀にはビタミンCやAが不足しているので、それらの食材とうまく組み合わせるとさらにバランスのとれた食事になります。バランスの良い食生活を心がけてください」
雑穀の力(3)「錆びにくい身体になる」
「雑穀を見て、白米との違いがわかりますか」と梶川さん。すぐに気づくのは、それぞれに特徴のある色がついているということだ。「その色はすべてポリフェノールです」。
ポリフェノールといえば、赤ワインなどに多く含まれ、抗酸化作用のある成分として有名だ。
「過剰になると身体に害を為す活性酸素を、ポリフェノールが安定した無害な物質に変えてくれます。ポリフェノールは摂ってから2~3時間しか効果が持続しないので、毎食はもちろん間食でも摂ってほしいのですが、毎回赤ワインを飲むのも難しいので、雑穀入りのご飯やおかず、お菓子などであれば摂りやすいでしょう」
咀嚼力を高めて免疫力を向上させる、代謝を良くする、抗酸化作用で生活習慣病を予防する……、雑穀には想像以上にすごい力が備わっていることがよくわかった。
受講者が熱心に聴き入る中、話題はそれぞれの雑穀の特徴と、食事で手軽に美味しく摂るためのレシピ紹介に進んだ。
雑穀は「おいしい」
セミナーの冒頭から各テーブルに回されていた様々な雑穀。それらを実際に使った料理と効能が紹介された。

もちきびとアボガドのテリーヌ
「キビは抗酸化作用に優れ、必須アミノ酸のメチオニンが豊富で肝臓内の毒素や老廃物を排除してくれます。きれいな黄色なので緑のアボガドと合わせてテリーヌにしてみました」

ひえと根菜のクリームコロッケ
「ヒエはアワとともに日本最古の穀物です。ミネラルが全体的にバランスよく含まれています。クリームコロッケにすると、男性にもとても喜ばれます」
「モロコシ(たかきび)も抗酸化作用に優れた雑穀の一つです。別名ミート・ミレットとも呼ばれ、ひき肉の代用素材としてよく使われます。マーボー茄子にすると本物のひき肉を使うのと遜色ない味わいです」
へえ、こんなに様々な料理法があるのかと驚いた。参加者からも、「ごはんに混ぜる以外にこんなに使い道があるとは」という声や、「雑穀ごはんが苦手な夫も、こんなレシピなら食べてくれるかも」などという声が聞かれた。
美味しそうなレシピに食欲をそそられたところに香ばしい匂いが…。
アサヒグループが研究開発し、現在、アサヒグループの通信販売専用商品としてオンラインショップ「アサヒの健康生活」で販売している「黄金の発芽大麦」を炊き込んだごはんの試食会だ。ひと口頬張ると甘く香ばしい風味がいっぱいに広がった。プチプチした食感も面白く、噛めば噛むほど旨味が増す。
大麦はこれまで、固い表皮の部分を削って押麦などに加工されてきたが、それを発芽させることで粒全体を柔らかくし、β-グルカンやビタミン、ミネラルなどが豊富に含まれている表皮ごと食べられるようにしたのだとか。
この発芽大麦、じつは偶然の産物で、焼酎の原料として麦を研究していたアサヒビールの研究員が、余ったサンプルをごはんに炊き込み試食したのがきっかけだったという。
日本で流通する雑穀は90%が輸入
最近では雑穀のすばらしさが見直され、国内での栽培面積、生産量ともに少しずつ増加しているそうだ。しかし輸入量も増え続け、現在日本で流通している雑穀の90%以上は輸入。食料自給率を向上させ、日本人の食環境の改善や日本農業の活性化のためには、国内での雑穀生産量を増やしていくことが重要な課題と言えそうだ。
アサヒグループホールディングス・イノベーション研究所 主任で、日本雑穀協会が認定する“雑穀エキスパート”の肩書を持つ淡嶋恭子さんによると、「昨今のブームで、もち麦を含む雑穀の需要は確実に増えています」とのこと。「ただ雑穀によっては食べやすくするために、加工の段階で栄養価に富んだ部分まで削ってしまうことも多いんです。そこをもうひと工夫することによって、自然の恵みをそのまま、しかもおいしくいただけるような提案をしていくことが、私たちのような研究機関の務めだと思っています」。
身体に良いばかりではなくおいしいとなれば、普及の速度も増すに違いない。「私たちは食材そのものをおいしくする努力をし、梶川さんのような先生方にはバリエーション豊かなレシピの開発をお願いしています」(淡嶋さん)
健康が気になるビジネスマンも、ランチなどで雑穀米が選べるときは、積極的にオーダーしてみることから始めるのもいいかもしれない。
(取材・文/林慶子 撮影/入交佐妃)
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年05月23日 16:40
私の雑穀白米は雑穀と白米の比率がほぼ同じ(笑)、、、最近では酵素玄米5・玄米1・雑穀白米1くらいの割合です。。。
■美肌を作る 雑穀ごはんと旬おかず
白いごはんなのに白米より栄養価をアップさせる方法
柴田真希
管理栄養士・雑穀料理家
美味しい「白いごはん」
「炊きたての白いごはんがあったら何杯でも食べられそう」
「白いごはんに合いそうなおかずだね」
なんて言葉をよく耳にします。やはり日本人にとって「白いごはん=美味しい」というイメージが強いのですよね。
健康や美容を気にする方なら白いごはんよりも雑穀ごはんや玄米ごはんなど精製度の低いごはんが、身体のためにもお肌のためにも良いことはご存知のはず。
しかし一緒に食べるご家族が白米愛好家な方や、栄養価が高いことは分かっているけれどやはり雑穀ごはんを受け入れられないという方に朗報の白米そっくりの雑穀ごはんの炊き方をご紹介します。
小粒の雑穀、白い雑穀
オススメの雑穀がコチラです。

これはきび、あわ、ひえと言った小粒の雑穀。米粒よりも小さくて、色もあまりつかないのでごはんと一緒に炊いても入っている存在に気が付かない人も。

さらに、大麦やはと麦のような白い雑穀も見た目に分かりにくいです。食べてみると噛み応えがあるので「いつもより食感があるなー」と思うかもしれませんが、モチモチしていてむしろ美味しくなります。
雑穀ごはん?白いごはん?
実際にごはんに混ぜて炊いてみると…

一見、雑穀ごはんに見えませんが、よーく見てみると…

黄色や白のプチプチが見えたでしょうか?
「雑穀ごはんが嫌い」
「美味しくないから食べない」
と言う人に何も言わずにこのごはんを出すと、だいぶごはんを食べてから「…これって雑穀ごはんだったの?」と気がつくということがよくあります。最初から気が付いても、「むしろ美味しい」と言って平らげてくださいます。
紫色に炊き上がる雑穀ごはんが苦手!という方も、色付くごはんだけが雑穀ごはんではありません!
「雑穀」と一言で言っても種類は様々。白いごはんと比べてエネルギー(カロリー)が変わらないのにビタミンやミネラル、食物繊維がUPする美肌ごはんに変えてくれるのが雑穀。是非ご自身が好きな雑穀をみつけてくださいね。
[スキンケア大学・美ログ]
Posted by nob : 2014年05月23日 02:05
頭皮の保湿とブラッシングも効果大です。。。
■なるほど!意外と知らない「白髪が生える場所とその理由」とは
高木沙織
30歳を過ぎると、髪を黒くするメラニン色素を作る”メラノサイト”の活動が弱まり、白髪がチラホラと現れるようになります。お風呂上がりにドライヤーをかけているときや、髪をセットしているときに、キラッと光る白髪を見つけてドキッとしたことがある方も多いのではないでしょうか。
そこで多くの方は、「白髪がはえてきた……」という思いにばかり気を取られてしまうのですが、”どうしてその場所に白髪がはえたのか”ということは、あまり考えないかもしれません。
しかし、白髪がはえる場所には、理由があると言われています。今回は、白髪がはえる場所とその理由についてお話していきたいと思います。
■1:頭頂部(分け目)の白髪
髪の分け目部分にはえる白髪は、無防備に浴び続けた紫外線が影響しています。紫外線を浴びると活性酸素が発生し、それが白髪の原因になります。特に分け目部分には、紫外線が直接あたるため注意が必要!
外出時は、髪用の日焼け止めスプレーや日傘を使って、紫外線から守りましょう。
■2:こめかみの白髪
こめかみのあたりには、神経細胞が通っています。パソコン作業や細かい作業のような頭を使う仕事をしている方は、神経細胞が活発になりその部分に活性酸素が発生。それが周囲の細胞にも影響を与えることで、白髪になると言われています。
帰宅後は、心身ともにリラックスできる時間を作ることを心がけましょう。また、携帯電話を長時間使用するのも、神経細胞を疲れさせることになるので、注意してください。
■3:後頭部の白髪
後頭部には、生殖器系のツボがあります。後頭部に白髪を見つけたら、生理不順などホルモンバランスが乱れていないかを疑ってみてください。
■4:特定の場所にはえる白髪
いつも同じ場所に白髪がはえるという方は、日常生活での癖を改善する必要があります。例えば、いつも同じところで髪を結んでいる、シャンプーをするときに一部だけ強く洗ってしまう、頭をかく癖があるなどの行為は、頭皮への刺激となり、活性酸素を発生させます。
頭皮に刺激を与え続けないように、日常生活での習慣を見直しましょう。
今回は、白髪がはえる場所と理由についてお伝えしました。近頃、白髪が気になっているという方は、上記の項目を参考にしてみてくださいね。
[美レンジャー]
Posted by nob : 2014年05月23日 01:58
何と言っても食生活の改善こそが根幹、、、私は生活習慣改善9か条すべてクリアできています。。。
■【デキる人の健康学】中性脂肪を下げる生活習慣とは
■中性脂肪はライフスタイルのバイオマーカー
年に一度の健康診断でコレステロールは正常値なのに中性脂肪が異常値でチェックされている中高年男性も多いと思う。コレステロール値が低くても中性脂肪が単独で高いだけで心筋梗塞のリスクになることが最近明らかとなり、中性脂肪はメタボリック症候群の診断基準の1つに取り入れられた。
中性脂肪が多いと善玉コレステロールが減って悪玉コレステロールが増えやすくなるため動脈硬化を間接的に促進することもなる。中性脂肪と聞くと食事での油の摂り過ぎと考えがちだが、お酒を飲む機会の多い人や間食でケーキや甘いもの、果物をよく食べる人は中性脂肪が増えやすい傾向にある。
アルコールや清涼飲料水に含まれている果糖や精製された糖質を摂取すればするほど、肝臓で合成される中性脂肪が多くなるためだ。コレステロール値は生活習慣を改善してもなかなか下がらないのに対して、中性脂肪値は生活習慣の改善により値を下げることができる。だから、ある意味では中性脂肪はライフスタイルのバイオマーカーと考えられる。
■中性脂肪を下げる生活習慣改善9か条
最近、米国心臓協会が「中性脂肪と心臓病に関する報告」をまとめたが、その声明のなかでも「生活習慣の改善の重要性と有効性」が強調されている。報告書をまとめた米国心臓協会理事で米国ボルチモア市メリーランド大学のマイケル・ミラー教授によると以下の9項目のライフスタイルを改善することにより、中性脂肪の値を20〜50パーセント下げることができると提言している。
その9項目とは、(1)5〜10パーセントの体重の減少で中性脂肪の値が20パーセント低下する。(2)食品や飲料に添加されている砂糖の一日摂取量を総カロリーの5〜10パーセント未満(女性で約100kcal/日、男性で約150kcal/日)に抑える。(3)清涼飲料水や加工食品、果物に含まれる果糖の一日摂取量を100グラム未満におさえること。(4)摂取カロリー1000kcalあたり食物繊維を10グラム/日以上摂取すること。更に摂取カロリー1000kcalあたり食物繊維を20グラム/日以上摂取すると中性脂肪の値が8パーセント低下する。(5)低グリセミック・インデックス(低GI)食品の摂取により中性脂肪の値が6パーセント低下する。(6)総カロリーにしめる脂質の割合を中等度に抑える(カロリー比32.5〜50パーセントの中脂肪食)。中脂肪食は低脂肪食(カロリー比18〜30パーセント)に比べて、中性脂肪の値が9.4mg/dL低下する。また、飽和脂肪酸の摂取量を総カロリーの7%未満、トランス脂肪酸の摂取量を1%未満に抑える。(7)オメガ?3脂肪酸の摂取。オメガ?3脂肪酸(EPA/DHA)1グラム/日の摂取あたり中性脂肪が5〜10パーセント低下する。(8)アルコールの摂取制限。アルコール非摂取群に比べて1オンス/日のアルコール摂取あたり中性脂肪が5〜10パーセント増加する。(9)定期的な運動。中性脂肪の値が150mg/dL以上の人で、中等度の有酸素運動で中性脂肪が15〜20パーセント減少するが、もともと中性脂肪の低い人では有酸素運動による中性脂肪の低下は認められない。
■ライフスタイルの改善により中性脂肪は50%以上下がる
ミラー教授は体重を5〜10パーセント減量するだけで中性脂肪の値を20パーセント下げることができるので、まず肥満傾向で中性脂肪の高い人は減量が大切であることを強調する。次に食事での砂糖と果糖、飽和脂肪酸を減らして不飽和脂肪酸を増やすことにより中性脂肪の値を更に10〜20パーセント下げることが可能であると考察している。
トランス脂肪酸や飽和脂肪酸の制限、オメガ?3脂肪酸の摂取と定期的な有酸素運動を組み合わせることにより最終的にはライフスタイルの改善により中性脂肪の値を50パーセント以上下げることが可能であるとしている。中性脂肪は我々の体に取っては重要なエネルギー源で欠かせない脂質成分であるが、生活習慣が乱れて必要以上に血液中に存在すると寿命を縮めてしまう可能性がある。
白澤卓二
順天堂大学大学院医学研究科加齢制御医学講座教授
[産経新聞]
Posted by nob : 2014年05月23日 01:51
どれもみな理にかなっているかと、、、早速実践してみます。。。
■さらば肩こり、腰痛。お腹も凹む「通勤エクササイズ」
フィジカルトレーナー 清水 忍 構成=遠藤 成
フィジカルトレーナー・清水 忍が、毎日の通勤時間を上手に使った、始業時からフルスロットルで働ける頭と体のつくり方を紹介する。
交感神経を上手に目覚めさせよう
東京・神奈川・埼玉・千葉在住で東京都内に勤め、妻と同居しているサラリーマンを対象にした調査では、通勤時間の平均は60分。往復2時間と考えると、多くのビジネスマンが、かなりまとまった時間を電車の中で過ごしている。そんな満員電車での通勤がしんどくて、会社に着いたときには、すでに疲れきってしまっているということはないだろうか。
「仕事ができる人かできない人かは午前中の仕事ぶりでわかる」とはよく言われる。体がいい状態になければ、アイデアも閃かないし、頭も回転しないことは、みなさんも経験済みのはず。通勤でクタクタになっていては、いい仕事は望めない。
そこで朝の通勤を上手に使って、始業時からフルスロットルで働ける頭と体にセッティングしようではないか。指導はフィジカルトレーナーの清水忍さん。
「眠りから覚めると、体はリラックス系の副交感神経優位から活動的な交感神経優位に切り替わります。できるなら、ゆとりを持って起きて窓を開け、朝の光を浴びて新鮮な空気を吸いながら、軽く体操してリセットするのがベストですが、みなさん朝は忙しいですからね。
今回、紹介するエクササイズは筋トレや有酸素運動ではありません。悪い姿勢の矯正と、普段使っていない部位に刺激を入れることで、頭と体を目覚めさせるものです。どれも簡単なエクササイズですが、効果てきめんなので、ぜひ通勤時の習慣にしてください」
では、まずは立つ姿勢、体幹の安定から。たくさんの人が悩みを抱える腰痛の多くの原因は姿勢にあると清水トレーナーは見ている。
「腰痛を引き起こす原因のひとつが反り腰姿勢です。立ったときに腰を反らせてお腹を突き出す姿勢になっていませんか? 自分では気がつかないのですが、立ち姿を横から写真に撮ってもらってみてください。ベルトがバックル側を下に斜めになっていたら、それは骨盤前傾、つまり反り腰の状態です。これは正しく腹筋が働いていない姿勢なのですが、この骨盤前傾状態の人がとても多いのです」
反り腰はよい姿勢と勘違いされがちだが、脊柱起立筋が緊張しっぱなしで、腰痛を招きやすい悪い姿勢だと清水トレーナーは指摘する。
正しい骨盤の位置は前傾状態でも極端な後傾状態でもないニュートラルの状態なのだが、骨盤の位置を意識したことがない人にはわかりにくい。
「後傾させるのは恥骨を引き上げる感覚。結果的にお尻の穴がきゅっと締まる。ベルトが地面に対し平行になるのが目安です」
骨盤を後傾に固定するコルセットの役割が腹横筋。腹横筋は骨と連動していないので意識するのが難しいが、腹を凹ませれば自然と働く。呼吸は腹を凹ませたまま胸式呼吸で行う。この腹部の緊張を維持したまま、駅から会社まで歩いてみよう。
「正しい姿勢を覚えると、腰痛が起こりにくいだけでなく、重いものが持ち上げられる、速く動けるなど、パフォーマンスがアップします」
正しい姿勢をとるだけで腹は凹む
正しい姿勢になれば動きも軽やかになり、疲れにくい。アクティブに仕事に打ち込めるはず。効果はそれだけではない。骨盤の位置が変わり、ダラ~ンと緩んでいた腹横筋が緊張収縮するために、体重が減ったわけでもないのにウエストがグンと細くなるのだ。
(1)のエクササイズで腰まわりの体幹を安定させたところで、次に矯正するのが肩の位置。(2)のエクササイズ。
「たいがいの人はどちらかの肩が上がっていてアンバランスですが、最も悪いのが両肩とも上がっている人。パソコンに向かう時間が長い人ほど首から肩にかけての筋肉(僧帽筋)が緊張収縮状態になり肩をすくめたようになっています。肩が上がっていていいことは何もありません。血行も悪くなり、肩こりの原因にもなります。オフィスでも疲れたなと思ったらこのエクササイズをしてみてください。首を上に長く伸ばす感覚です」
(1)腹凹&アナル締め(ターゲット:腹横筋、腹直筋)
電車内で立った姿勢で、息を吐き最大限にお腹を引っ込める。そのまま骨盤をできるだけ後傾させる。この姿勢を10秒キープして10秒インターバルを開ける。これを降車駅のひと駅前からひと区間続ける(約3分目安)。電車から降りてもこの腹部の緊張を意識して会社まで歩く。
⇒体幹の安定が高まり、腰痛が発生しにくくなる。骨盤の位置が変わり腹横筋が緊張収縮することでお腹が凹む。
(2)胸を張って肩を落とす(ターゲット:僧帽筋下部)
信号待ち、駅のホームなどで、立ったまま両手でカバンを後ろ手に持つ。そのまま最大限に胸を張り、カバンを押し下げるように肩を落とす。この姿勢を10秒キープして10秒インターバルを開ける。これを数セット繰り返す。
⇒肩こりが予防できるだけでなく、胸式呼吸が交感神経刺激となり、積極的な感覚が高まる。
今回紹介したエクササイズでぜひ実践してほしいのが、この(1)と(2)。体がきっと楽になるはずだ。
正しい姿勢を覚えたら(3)以下も試してみよう。
「(3)はゲーム感覚で人と競うものではありません。眠っている体は反応がニブい。素早く体が反応するかどうかが大事で、どうすればより速く動けるか、いろいろ試してみましょう。余計な力が入ると体は動きません。仕事も同じですね。力を抜いてリラックスした状態のほうが、脳の指令に素早く反応できることに気づくはずです」
(3)最速はじめの一歩(ターゲット:敏捷性)
赤信号で止まっているときに、できるだけ脱力し、全身から余計な緊張を取り除き、軽く膝を曲げてつま先にほんの少し体重をかけて待機。青信号に変わった瞬間に最速の反応で一歩目を踏み出す。
⇒注意力が高まり、力むよりも余計な力を抜いたほうが速く動ける感覚をセットできる。
(4)は膝と腰をうまく使って電車の揺れを吸収する運動。
「加齢に伴い肉体が衰えるのは自然ですが、なかでも急速に失われがちなのは筋力よりもバランス感覚などの神経系の働き。普段意識しない足の裏の感度など全身の神経と脳の連動性をアップさせます」
(4)電車サーフィン(ターゲット:重心調整)
電車内でつり革につかまらずに立つ。足幅は比較的狭く、膝は突っぱらずに軽く曲げて立つ。腰と膝をクッションにして電車の揺れを吸収するようにバランスをとる。踏ん張らず、揺れを逃がすのがポイント。頭の位置はできるだけ変えない。
⇒重心の変化に素早く対応することで、全身の神経が活性化し、空間認知能力の高まりが期待できる。
(5)は上手に使っていない人が多いお尻の筋肉(大臀筋)を意識するエクササイズ。
「多くの人は階段を前傾姿勢でつま先から着地し、大腿四頭筋を使って足で地面を押しながら、体を押し上げるように上っています。かかと着地にすると、自然と大臀筋を使って体を引き上げる動きになります。同じ階段を上る行為でも、使っている筋肉がまるで違います。大臀筋は普段使っていないので、意識しないとなかなか動かせませんが、大臀筋が使えるようになると、だらしなく垂れていた尻がきゅっと締まって後ろ姿がかっこよくなります」
(5)かかと重心階段上り(ターゲット:大臀筋)
駅などの階段を上がるときに、かかとに全体重をかけ、体を前傾させずに力強く上る。
⇒大臀筋に刺激が入ることでよりダイナミックに股関節が活動し、エネルギッシュに動けるようになる。
(6)と(7)は眼球の筋肉を使う運動。視覚情報は脳への刺激も大きい。朝、脳を活性化させるにはもってこいの運動だ。これで頭も体もスイッチオン!
(6)あっちこっち見てホイ(ターゲット:遠近視力調整)
電車の中にある中づり広告を、近くのものと遠くのものとを、ひとフレーズごと交互に読む。
⇒パソコン仕事で衰えがちな眼球を動かす筋肉のトレーニング。自動的に脳への刺激も高まる。
(7)気分はイチロー(ターゲット:動体視力調整)
通過する駅のホームにあるポスターや窓外の電柱の看板などを瞬時に読みとる。顔を動かしてもかまわない。
⇒動体視力の向上とともに、相当な集中力も要求されるので、眠っていた脳が活性化される。
[PRESIDENT Online]
Posted by nob : 2014年05月21日 07:31
また旅立つ君へVol.39/人は、何時からでも何処からでもやり直し、また新たに始められる。。。
■嫌われる勇気──自己啓発の源流「アドラー」の教え
トラウマを否定するアドラー心理学が
今なぜ多くの人に求められているのか
鼎談(前編)
宮台真司[首都大学東京教授/社会学者]
神保哲生[ビデオジャーナリスト/ビデオニュース・ドットコム代表]
岸見一郎[哲学者]
社会学者の宮台真司氏とジャーナリスト神保哲生氏が司会を務めるインターネット放送番組「マル激トーク・オン・ディマンド」に、『嫌われる勇気』の著者・岸見一郎氏がゲスト出演した。いまなぜ、日本でアドラー心理学がこれほどまで注目されているのか、その原因をさまざまな角度から徹底的に議論した放送内容を、特別ダイジェスト版として2回に分けてお送りする。前編ではアドラー心理学とは何か、そしてなぜ日本ではこれまで無名だったのかを深く掘り下げる。
ソーシャルメディアの台頭と
嫌われたくない若者の増加
神保 本日はアドラー心理学の日本の第一人者であり、いま『嫌われる勇気』という本が27万部のベストセラーになっている哲学者の岸見一郎さんをゲストに招いています。まず宮台さん、この本がこれだけ売れているのはソーシャルメディアとも関係あるのではということなのですが、それはなぜでしょうか?
宮台 ソーシャルメディアについては、僕が「脳内ダダ漏れ現象」と申し上げているように、本来なら人に見せないような心の内を、無防備なまま書くという傾向が一般に強く、それで人間関係が壊れることも頻繁にあります。
そうしたものがある一方、最近「既読プレッシャー」と呼ばれますが、「相手方に既読マークが見えているのに返事を書かないのはまずい」「すぐに返事を書かなきゃ」といったオブセッション(強迫)があります。
LINEの利用率が半数近くになる昨今、もともと日本人のコミュニケーションにありがちな過剰同調が、ソーシャルメディアの存在ゆえに増幅されています。そうした状況でどんな波及的な事態が起こるかが大きな問題なんです。
「KY(空気が読めない)」という言葉に象徴されることですが、KYだと思われないように絶えず意識しながらポジションを取ることが、以前にも増して重要になっているんです。そのご褒美が、Facebookなら「いいね」。
要は、KYだと思われることなく、承認してもらいたい、というわけです。実際はそんなもの承認でも何でもないけれど、昨今の若い人たちはいったい何を勘違いしているのかという問題があります。
ソーシャルメディアの普及を背景に、KYフォビア(恐怖症)や承認オブセッション(強迫)が異様に高まり、不自由が蔓延しているのが昨今です。そのことへの気づきがようやく拡がって、この本が売れるようになったんでしょう。
神保 「SNS疲れ」なる言葉もあるそうだし、今の時期は「5月病」的なものも出るシーズンでもあるということで、それらも想定して今日のゲストをお招きしたわけですが。
宮台 この2年間、僕は性愛系のワークショップをしています。彼女・彼氏のステディがいる割合が今世紀に入る頃からどんどん下がっているからです。こうした傾向が目立つようになってから、すでに15年ほど経ちます。
いろんなリサーチが示すところによれば、昨今の20歳代独身男性は7割が「将来結婚できない」「将来結婚したくない」と答えます。独身女性もこの傾向を追いかけています。対人関係が構造的に変動しているんです。
特に女子の場合、この5年ほど、つまり2010年代に入って顕著になったのは、「ビッチ」というキーワードです。友だち関係よりも性愛関係を重視する女性を、同性間でビッチ呼ばわりし、それが性愛からの退却を増幅しています。
神保 ビッチって言葉が日本でも普通に出回っているんだ。
宮台 そう。昔は恋人ができれば同性の友だちとは疎遠になるのが普通で、そのことに友だちも寛容でしたが、今世紀に入る頃から違ってきました。友だち間のポジションを失いたくないし、この5年ほどはビッチ呼ばわりを恐れます。
かくして性愛から退却気味になるだけじゃありません。同性の友だちから、「いいね」と言ってもらえない相手(男)を彼氏に選べないんです。自分としてどう思うのか、という感情の発露が閉ざされた状態です。
そういうことも岸見先生との話ではテーマにしたいですね。
日本でアドラー心理学の
知名度が低い理由
神保 なるほど。僕は今日のテーマはとても重要だと思っています。「人は変われる」とか、もっと大きく言えば「幸せとは何か」「自由とは何か」といったテーマです。『嫌われる勇気』という本は、腹にズシンと響くような内容でした。タイトルや帯の「自由とは他者から嫌われることである」というコピーが印象的です。いずれにせよ、アドラーブーム的なものが来そうな予感がしなくもありません。
宮台 今でいうコーチングのルーツは、1970年代半ば過ぎにアメリカで始まったアウェアネス・トレーニング(日本でいう自己啓発セミナー)です。こうした流れのすべてにおいて、アドラー心理学の絶大な影響があります。
ところが、この日本に限っては、アドラー心理学自体の知名度が低すぎるので、コーチングをファシリテイション(推進・実践)する人たちでさえ、ほとんどが、自分たちがアドラーの掌の上にある事実を、ご存じないんですね。
神保 それは驚きです。岸見先生なぜなんでしょうか?
岸見 ひとつは、日本のアカデミズムでアドラーが取り上げられることが皆無と言っていい状態だからです。学校で心理学を専攻するとフロイト、ユングについての講義は受けるのですが、アドラーについては名前と若干の思想を教授が話し、学生は記憶の片隅に置くくらいの扱いですね。まずはそれが大きな原因かと思います。
神保 では、日本のアカデミズムでフロイトとかユングが認知を受けているのに対し、アドラーがあまり普及しなかったのはどのあたりに原因があるとお考えですか?
岸見 アメリカでもやや似たような状況があります。アドラーはウィーンの精神科医ですが、ナチスの台頭に伴って活動の拠点を晩年にはニューヨークに移しました。あるとき、ニューヨークの医師会から講演を依頼されたことがあります。それは精神科の医療にアドラー心理学の考え方だけを採り入れたいという話でした。そこで我々だけにアドラー心理学を教えて欲しいと医師会がアドラーに申し入れたのです。すると「いやそれはできない。私の心理学はみんなの心理学だから」とアドラーは言ったそうです。アドラーの心理学は「個人心理学」と言うのですが、専門家の心理学ではなく、みんなの心理学であるということですね。
同じようなことが日本に紹介された頃にも起こったようです。専門家たちの間で自分たちが優先的にアドラー心理学を学びたいという動きがありました。ところが、日本アドラー心理学会という学会があるのですが、そこは普通の人々、つまり非専門家の集まりだったのです。そうした非専門家と一緒にやりたくないという医療関係者やカウンセラーが初期の頃かなりいたという状況があり、それが最初のつまずきになったのではないかと考えています。
神保 なるほど。僕は心理学とか精神医学の門外漢なのですが、今回『嫌われる勇気』を読ませて頂いて、自分にとって大袈裟に言えば人生の書のように思っているヴィクトール・E・フランクルの『夜と霧』にものすごく多くの共通点を感じたんです。フランクルも心理学者ですが、これは何か接点があったんでしょうか?
岸見 フランクルはアドラーの弟子ではないのですが、のれん分けをしてもらったような感じでしょうか。活動を共にしていた時期があるので、当然、影響を受けているはずです。『夜と霧』はアドラーの考えに近いと私も感じますし、それは偶然ではなく歴史的に見て二人に接点はあったわけです。
神保 やはりそうですか。それで、フランクルの本から多く引用しているのがスティーブン・コヴィーの『7つの習慣』なんですが、やはりそうした人たちもアドラーに通ずるところがあるんですね。
宮台 フロイトもマルクスも19世紀の人です。アドラーもそう。しかしアドラーは19世紀の思想家としては異色です。19世紀は、フランス革命以降の〈反啓蒙の思考〉の時代です。人間は理性的でも合理的でもなく、感情的で非合理的な存在だとします。
そして非合理の理解について〈潜在性の思考〉を展開します。人も社会も、「見えるもの」が「見えないもの」に規定されているとする理解。典型的なものがマルクスとフロイトで、マルクスは、大衆文化から政治思想まで含めた上部構造が、生産関係すなわち所有関係からなる下部構造に規定されるとします。
他方フロイトは、我々の意識は無意識によって規定されるとする。つまり、アドラーが敵視したフロイトは「我々は規定されているがゆえに非合理的だ」とする19世紀的思考の典型です。フロイトを含めた19世紀的な〈潜在性の思考〉は、20世紀、正確には戦間期に入ると、知的先端から否定されます。
具体的には、ヴィトゲンシュタインの言語ゲーム論が典型です。従来、数多ある数学を、論理学(が明らかにする論理)が規定するとされてきました。彼はそれを否定。いろんな数学がまずあり、それを観察するゲームとして論理学がある。論理学が数学を根拠づけるなどあり得ないとしました。
数学という言語ゲームがあり、それとは無関係に、数学を観察する論理学という言語ゲームがある。要は「根拠がある」のでなく「根拠付けのゲームがある」だけ。事物に根拠などなく、さまざまな言語ゲームが存在するという事実性だけがある。根拠なるものは、観察する言語ゲームの内部表現に過ぎないと。
アドラーは20世紀的な〈自己言及の思考〉を先取りします。「見えるもの」が「見えないもの」に規定されるのでなく、規定されているという理解があるだけ。現在が過去に規定されているのでなく、規定されているという理解があるだけ。そんな理解がある種のゲームを可能にしているだけだとします。
知的先端を別にすると、大衆的には19世紀的な〈潜在性の思考〉が残ります。自分が不自由なのは、見えないものに規定されているからだ。見えないものとは、過去のトラウマだ。階級的な所有構造だ。そう言われると、ある種の帰属処理ゲームが始まって、気づきが生じたと錯覚。カタルシスが起こります。
「騙されていたんだ」「規定されていたんだ」と。規定されていた事実への気づきで自由になったと感じますが、実際は、苦痛が説明されて安堵し、敵が見つかり溜飲が下がっただけ。僕も中学時代にフロイトを読み、思春期の苦痛が、トラウマによって構造化された無意識に由来すると「気づき」、安堵しました。
そこでは「見えないもの」を「見る」のが精神科医で、フロイトを学んだ専門家だけが一般の人には「見えないもの」が「見える」。かくして、一般人に解を提供してくれる専門家たる精神科医のアカデミーが、権威を維持できます。ところがアドラーはこうした言語ゲームの全体を見通していたんですね。
アドラーは、19世紀的な〈反啓蒙の思考〉とは異なり、また18世紀的な〈啓蒙の思考〉とも異なる。啓蒙か反啓蒙かというのはメタ万物学(形而上学)、つまり近代哲学の問題設定ですが、岸見先生の本にもあるように、アドラーは、むしろ初期ギリシアの万物学、つまり現代哲学の問題設定なんです。
フロイト 対 アドラーは、〈潜在性の思考〉対〈自己言及の思考〉であり、メタ万物学(近代哲学)対 万物学(現代哲学)であり、ユダヤ的思考 対 ギリシア的思考。ユダヤ教徒フロイトは過去の引力(無意識による規定)を重視しますが、ギリシア哲学を出発点とするアドラーは未来の引力を重視します。
神保 なるほど。しかしこれだけ『7つの習慣』やデール・カーネギーに使われているのに、あまりアドラーの名前が表に出されていないのは何か理由があるんでしょうか?
岸見 アドラーから引いたということをあまり言いたくないんじゃないでしょうか? かなり印象的な考えですから、自分の独創だと言いたくなる人が多いのかもしれません。アドラーの思想のことを喩えて「共同採石場」と呼ぶことがあります。つまり皆がそこからいいところを取っていく、と。
神保 いいとこ取りということですね。アドラーもそれは構わないと考えていたんですか?
岸見 本人は極めておおらかで、アドラー派という学派が存在したことすら忘れられてもいいというような人だったそうです。しかし、それもあって多くの人がアドラーの思想のいいとこ取りをして、しかもその名前を冠しなかったという現実があります。ただ、僕はそれでもまだたくさん原石が残っていると思っています。彼らが持ち去らなかったものがある。まとまりもなく磨かれてもいないけれど、原石のまま光り輝くものがあるので、それをこれから見ていかないといけないと思っています。逆に言えば、そこを持っていかないとアドラーの本当のところが伝わらないと思うのです。表面的にはアドラーの考えに似ているようで、フタを開けると全然違うというような印象を受けることもありますので。
トラウマの存在を認めない心理学
神保 それでは、まずは大枠の入門的なところだけでも、アドラー心理学とは何かということの説明を岸見先生お願いします。
岸見 ひとことで言うと「過去を振り返らない心理学」ということになります。たとえば、カウンセリングに来られる方の過去のことをどれだけ言っても、何ら今の悩みの解決にはならないでしょう。ただ、ある種の安心にはなるかもしれません。自分のせいではなかったのだ、と。たしかに「あなたのせいではなかったんですよ」とか「他の人に責任を押しつけてもいいんですよ」と言われれば安心はするでしょう。けれど、それではカウンセリングの前と後で、その人の人生は少しも変わらないでしょう。現状維持どころかもっと悪くなるかもしれない。過去に何らかの原因があって、いま何かの症状が出ているということが仮に明らかになったとしても、過去にタイムマシンを使って戻れない限り問題は解決しないのです。
たとえば、子どもが学校に行かないというケースでお母さんがカウンセリングに来られたとします。そこで「あなたの育て方が悪かった」と言われても絶望して帰るしかないじゃないですか。それはもう過ぎたことだから、とりあえず問題にせずにおこう、というのがアドラー心理学の立場です。
またトラウマに関して言うと、トラウマによって今の自分が規定されていると考えるのはある意味では楽です。しかし問題の解決がまったく違う方向に向かってしまいかねない。たとえば、ある治療者が大阪の附属池田小学校で無差別殺傷事件が起きたときこういうことを言っていました。自分は怪我などをしていなくても友達が殺されるのを見てしまった子どもたちには、人生の大事な段階において必ず何らかの問題が起こる、と。これはひどいと思います。治療者として絶対に言ってはいけないことでしょう。あのときの子どもたちはそろそろ成人しているはずです。彼や彼女がいたり、結婚したりする年齢です。たとえば付き合っている人とうまくいかないとき、その原因を事件にまで遡るかもしれない。けれど実際には、今目の前のその人との関係が悪いだけであり、それを改善すれば何とかなるはずです。なぜ過去に遡る必要があるのか。過去に遡りトラウマと言い出せば自分の責任が曖昧になります。ある意味都合が良いのかもしれないけれど、そういうことをアドラーは言わないわけです。
神保 過去に原因があるならどうしようもないよね、となりますからね。そのほうが楽ということなのかな。
宮台 「自分は変われない」という人に「それはなぜですか?」と問うと、「私は過去にこういうトラウマを負っているんです。あなたと違って私が変われるわけがないじゃないですか」と自己を免責するんですね。風俗嬢の取材を通じて無数に目撃してきました。
岸見 過去に大きな出来事に遭遇した場合、その影響がまったくないとは言い切れません。もちろんあるでしょう。東日本大震災でも阪神淡路大震災でもかなり悲惨なことがありましたから、影響がなかったとは言いません。ただ、同じ出来事を経験したかたらといって、皆が同じようになるわけではない。そういう決定論から脱している点がアドラー心理学の特徴なのです。
神保 PTSD(心的外傷後ストレス障害)のような症状はアドラー的にはどのように考えるんですか?
岸見 一緒です。トラウマを否定するので、PTSDも否定します。
神保 では、本当にすごいものを見てしまったので、後からそれがトラウマになっていると思っていても、実はそうではないということですか?
岸見 アドラーは「見かけの因果律」という言葉を使います。AというできごととBという現象のあいだには本来因果関係はない、それにもかかわらず、両者に因果関係があるとみなしたがる人はいます。その際、過去のことや過去に心に傷を受けたことを持ち出すのです。
神保 それは『嫌われる勇気』にも書いてありますが、過去がどうだったかではなく、自分がそれにどのような意味を与えるかが問題だということですね。
宮台 たとえPTSDと言われる症状があるとしても、人は基本的にそうしたものから自由になりたい以上、自由になるために必要な枠組みは、「トラウマゆえにそれが起こった云々」ではまったく足りません。アドラーによれば、トラウマへの意識が、自分がこれからどうするかという志向を、束縛するんです。
神保 「だからどうした」ということですね。
岸見 アドラーは「患者を無責任と依存の地位に置いてはいけない」と言っています。しかし「あなたのせいじゃない」と言えば、患者さんを無責任という地位に置いてしまうのです。
神保 一見楽になるように見えるけれど、問題の解決には寄与しないということですね。
岸見 そうです。しかも、過去の出来事を持ち出してこれが今の悩みの原因ですよという治療者に、患者さんは依存してしまいます。患者さん自身は何も言えないのです。治療者から一方的にこうなんだと言われると、依存関係になってしまう。アドラーはそうしたことも明確に否定しています。
アドラー心理学の目標とは?
神保 続けて「アドラー心理学の目標」について教えて下さい。『嫌われる勇気』によれば、まず行動面での目標は「自立すること」「社会と調和して暮らせること」だそうですが、こちらについてはフロイトに代表されるような他の心理学と違いはあるんでしょうか?
岸見 そこについては特に違いはありませんね。
神保 では、次に心理面での目標は「私には能力がある、という意識」「人々は私の仲間である、という意識」を持つことだそうですが、これはいかがでしょう?
岸見 まず「私には能力がある、という意識」ですが、アドラー心理学では、自分が直面する「人生のタスク」というものを考えます。仕事のタスク、交友のタスク、愛のタスクという、避けては通れない課題(タスク)があると考えるのです。そのタスクに立ち向かっていく能力がないと思い込んでいる人に対して、いやそうではない、あなたはタスクを前にして逃げる必要はないし、勇敢に立ち向かっていけるはずだと、それを知ってほしいということです。
もう一方の「人々は私の仲間である、という意識」ですが、世の中には周りの人は私の敵だと考えている人が多くいます。うかうかしていると私を陥れかねない怖い人ばかりだと。しかしそうではなく、周りの人は私が求めれば援助をしてくれる、味方をしてくれる仲間なのだ、と思って欲しいのです。なぜなら、そうでないと他の人の役に立とうとする人になれないからです。誰も敵の役に立とうとは思わないでしょう。他の人の役に立てているという貢献感はアドラー心理学において極めて重要なのです。
宮台 初期ギリシアの思考は[自立/依存]の二項対立です。200年経った紀元前3世紀のストア派になると、マケドニア帝国の支配下で都市国家が単なる都市へと頽落したのを背景に、自立よりも自律、つまりセルフガバナンスやセルフオートノミー、つまり自己決定へと理念が縮退しますが、それとは別物。
自立は、セルフガバナンスでなくインディペンデンス。ディペンド(依存)しないこと。初期ギリシアでは、超越の神に依存するのも、普遍の真理に依存するのも、よくないと考えました。なぜなら、アレをすれば罰ないし損を被るが、コレをすれば賞ないし得が得られる、と損得勘定を駆動させるからです。
そうではなく、自分の内側から理由なく湧く力(ヴィルトゥ)こそが大切だと見做されました。これはアドラーの「私には能力があるという意識」に関係し、現在ならば「自己効力感」と呼ぶところですが、いずれにせよ、損得勘定の自発性よりも、内から湧く力である内発性が大切だと見做されました。
繰り返すと、それが真理だからとか、神が命じたからとかいう理由で、漸くやる気が起こるのは、真理への依存・神への依存です。真理や神に反すればネガティブな報いを受ける。つまり呪いを受ける。呪いから逃れるために何かをする。そんな動機は、初期ギリシアの考え方に従えば、名誉に反します。
知識社会学的には、損得勘定に依存した行動原則では、常時ポリス間戦争がある状況でポリスが生き残れないから、損得勘定の自発性を超えた理不尽な力である内発性が愛でられました。とりわけ重装歩兵らのファランクス(集団密集戦)では内発性が決め手。岸見先生のお話はそんな古い智恵と響き合います。
岸見 アドラーによれば、人が自立するためには2つのポイントがあります。一つは「叱らない」ということです。叱られて育つ子どもは自立しません。何かをする・しないというときに自分で決められず、親や大人に叱られるからやる・やらないということでは自立しているとは言えません。これが一つです。
もう一つは、「甘やかさない」ということ。甘やかされた子どもは自立しません。これはアドラーが何度も繰り返し問題にしている点です。今日では愛情不足の子どもなどあまりいません。親側から言えば愛情過多、子ども側から言えば愛情飢餓の状態です。愛されているのにもっともっと愛して欲しい、と。これは穴の空いた花瓶に水を注ぐようなもので徒労です。私は、井上陽水の「感謝知らずの女」という曲をよく引き合いに出すのですが、彼女にダイヤの指輪を贈ったところもっと大きいのが欲しいと言われた、という歌詞です。今そういうタイプの人が非常に多い。甘やかされた子どもは自立できず、当然自分で考えられない、そういう問題をアドラーは具体的に述べています。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年05月20日 17:35
また旅立つ君へVol.38/人は、何時からでも何処からでもやり直し、また新たに始められる。。。Vol.2
■「自分は変わりたい」と言う人が、
実は「変わらない」と決心をしているのはなぜか
鼎談(後編)
宮台真司[首都大学東京教授/社会学者]
神保哲生[ビデオジャーナリスト/ビデオニュース・ドットコム代表]
岸見一郎[哲学者]
人はなぜ変わりたいのに変われないのか? その背景には、実は変わりたくないという自らの決意があるとアドラー心理学は喝破する。それはなぜなのか。昨今の若者に増えている「本当の自分・仮の自分」という意識の分析も交え、社会学者・宮台真司氏、ジャーナリスト・神保哲生氏、『嫌われる勇気』の著者・岸見一郎氏が熱く語り合う! インターネット放送番組「マル激トーク・オン・ディマンド」特別ダイジェスト版の後編を大公開!
人はなぜ不幸であることを
自ら選ぶのか?
神保 『嫌われる勇気』は哲人と青年の対話という形を取っていますが、その最初のほうで「人は変われる」のだと哲人が断言するところがあります。それに対して青年が、変わりたくても変われない人がたくさんいると言う。すると哲人が、「変われないでいるのは、自らに対して『変わらない』という決心を下しているから」だと言うんですね。一生懸命変わらないと決心しているから変われないんだ、と。これはどういうことか教えて頂けますか。
岸見 今とは違う自分になってしまうと何が起こるか予測できなくて怖いのです。だから変わりたいと言っている人は実は変わりたくない。変わってしまったら次の瞬間何が起こるかわからないので、不断に「私は変わらないでおこう」という決心をしているんです。もし変わりたいのであれば、変わらないでおこうという決心を解除する必要がある。そしてそれは非常に勇気がいることです。
神保 その変わらない決心というのは自覚的ではないのですか? 自分としては変わりたいなぁと思っているわけですから。
岸見 自覚的ではないでしょうね。そういうことを言われて生まれて初めて気づくかもしれない。「あなたは変わりたくないんですね?」と言われて、「あ、そうなんだ」と気づく人は気づきます。それでも気づかない人、あるいは気づきたくない人はいるかもしれません。
宮台 前回トラウマはあるのかという話になり、トラウマのせいで自分にはできないのだと免罪をする癖を問題にしました。トラウマを持ち出す人は、そのことによって「自分が本当の自分だと思っているもの」を擁護し、「自分は変わりたくない」と宣言しているのだ、と。
僕は札幌を中心に久しぶりに風俗の取材を進めていますが、インテリ系の風俗嬢に目立つのは、第一に「トラウマの意識」、第二に「真の自分と仮の自分」です。そこには「トラウマを被った真の自分は、とても傷つきやすく人前に出せないから、私は仮面で人に接する」という意識があります。
「仮面なら、真の自分を隠せるから、自由になれて、できなかったことができる。それが風俗労働だ」という理解が典型です。僕は介入的だから、「それって変。真の自分とかトラウマって何? そうやって『真の自分』とやらを温存したら、永久に変われないし、トラウマも消えない」と言います。
実際、放っておくと変われません。そうやって25歳になり30歳になり35歳になるのは傍目に悲惨です。過去の引力ではなく、未来の引力に身を委ねればいい。未来に実現したい最終目的は、自分でどうとでも定められるから、それ次第で「自分は思っていたような自分じゃなかった」となれます。
「自分は思っていたような自分じゃなかった」という気づきを何度か経験すれば、岸見先生のおっしゃる「変わらない決意」を、「あれは何だったんだろう」という具合に過去のものにできます。そんなふうに過去は横に置き、最終目的に由来する未来の引力に開かれればいい。
僕がよくする言い方は、「君はトラウマを持ち出して自分を変えないことで、利益を得ている。それはわかる。でも、君が本当にありたい自分になるという大きな目的に照らして、有限な時間をそんな小さな利益のために使っていいのか」というものです。
トラウマの多くは「親への恨み」つまり「親が別の振る舞いを選択してたら自分はこうならなかった」という思いと結合します。そこで親と対決して「別の選択ができなかったのか」とぶちまければ、たいてい親の反応は期待外れだから、「親に別の選択肢なんてなかった、親はこんなにも小さかった」となります。
実際、1980年頃のアウェアネス・トレーニング(日本でいう自己啓発セミナー)は、前半にフロイト的なトラウマ概念を用いた「過去を赦す」セッションがあり、後半にアドラー的な大きな目的概念に照らして「今を感じる」セッションがありました。そんなふうに、過去の引力と未来の引力を関係づける仕方もあるのですね。
神保 やはりトラウマがあると思っていることが根っこにあるんですか? トラウマがあるから今自分はこうなっているというのは、アドラーが最も否定するところですよね。そこが大きな分かれ目になってしまう?
岸見 カウンセリングでは必ずしもトラウマという言葉は出てこないです。ある種の人たちはそう言うかもしれませんが、普通の人の話題には出てこないですね。ただ、本当の自分とか仮の自分という言い方は、病気とか心の傷の文脈を離れてもあります。たとえば「ついカッとして」というのは、本当の自分はついカッとするような人間じゃないんだと言いたいわけです。
アドラー心理学のことを本来は個人心理学と言いますが、個人というのは英語で言うとインディヴィジュアルです。これは「分けることができない」という意味です。何が分けられないかというと、意識と無意識、感情と理性、身体と精神など、そういったあらゆる二元論にアドラーは反対するわけです。つまり、分割できない全体としての人間を扱う心理学ということです。その流れで今の宮台さんの話を見れば、本当の自分と仮の自分なんてあり得るわけがないことになりますね。「この私」しかないということです。
神保 その延長になると思うんですが、「あなたの不幸はあなたが選んでいるものだ」ということが『嫌われる勇気』には書いてあります。しかし、わざわざ自分で選んで不幸になるわけがないじゃないかと青年も怒っていましたが、これはどういうことでしょうか?
岸見 こういう言い方をしていいかわからないですが、不幸であることが自分にとって有利だと考える人は不幸であることを選ぶ、ということです。不幸にはいろいろな意味がありますが、たとえば病気であれば周りの人は腫れ物に触るように付き合わなければいけないわけです。本当は病気から解放されて元気になりたいのだけれど、病気で弱っているときのほうが皆が良くしてくれる。であればどちらを選ぶかというと、不幸のままのほうを選ぶ人もいるというようなことですね。
神保 うーん。それはあらゆる場合にそうなんでしょうか? 明らかに恵まれない境遇に生まれ育つ人もいますよね。であれば、いくら何でも自分の場合は不幸を選んだなんて言われたくない人もいるのでは?
岸見 いや、境遇の問題ではないのです。どんな貧しくて一般的には不幸な境遇に生まれたからといって皆が不幸になるわけではありません。
神保 たしかに心の問題ですよね。
岸見 逆に裕福な家庭に生まれても不幸な人は不幸じゃないですか。ここでギリシア哲学の話をしますと「ソクラテスのパラドクス」として知られる、「人は誰もが悪を欲しない」ということがあります。でも、悪を欲しないと言っても、世の中には不正を犯す人だっていっぱいいるじゃないかと思いますよね。政治家なんて皆そうじゃないかという人もいます。しかしギリシアの、もっと言うとプラトンなのですが、プラトンが悪とか善という場合、そこには道徳的な意味は全然なくて、悪は「ためにならない」ということなのです。で、善は「ためになる」ということです。
そういう意味として「人は誰もが悪を欲しない」という言葉を振り返ってみると、誰も自分のためにならないことは欲しないということになります。考えてみれば当たり前のことです。ただ、何が自分にとってためになるかならないかという判断を人間は誤ることがあるのです。私は不幸が自分のためになるとは思わないですしアドラーも否定するでしょうが、不幸であるほうが自分にとってためになる・善であると判断した人は不幸であり続けるのです。そういう意味では自分で選んでいるとしか言いようがありません。
過去に対する意味付けが
我々を縛る
神保 あなたの不幸はあなた自身が選んだとすれば、それを変えるにはどうすればいいかですが、『嫌われる勇気』では「交換ではなく更新」ということが書いてあります。これはどういう意味でしょう? 不幸の問題とどう関わってくるんですか?
岸見 人は全く突如として別人格にはなれません。たとえば、消極的な人が一夜にして脳天気な積極的な人になるのは難しいでしょう。ウィンドウズを使っていた人が今すぐMacに変えるのも難しいわけですが、OSのバージョンアップならできますよね。そういう変化ならあり得ます。私が全くこれまでの私でなくなるわけじゃないけれど、中身を変えてしまうというか、自分についての意味付けを変える、あるいは世界に対する意味付けを変えることはできます。私は私なんだけれど、それまでとは異なる世界に住み、全く違う自分を見つけ出す、更新とはそういう意味です。
神保 要するに、過去に起きたことは実際には今の自分と関係ないんだけど、それに自分がどういう意味を与えるかで縛られている、と。本によれば、原因論と目的論という言葉が関係しているようですが、そのあたりも説明をお願いします。
宮台 これはアリストテレス的な話ですね。
岸見 ではアリストテレスで説明しましょうか。アリストテレスは事物が生成するためにはいくつかの原因が必要だと説いています。たとえば彫像をつくることを考えてみましょう。まず大理石とか粘土などの素材がなければ彫像はできません。これを「素材因(質量因)」と言います。次に彫刻を彫る彫刻家がいないといけません。これは「作用因」と言います。さらに、彫刻家の頭のなかにどんな像を彫ろうかというイメージが必要です。これは「形相因」と言います。ではその3つがあれば彫刻はできるかというとそれだけでは無理です。何のためにこの彫刻をつくるのかという「目的因」がなければなりません。像をつくって飾り物にするとか、売ってお金儲けをするとか、そうした目的がなければ絶対に彫刻はできないのです。
プラトンも師のソクラテスに関して似たことを言っています。ソクラテスはご存知のとおり死刑になります。あれもひどい話ですよね。若者を扇動して害悪を与えたということで処刑されるのです。で、彼は獄中にずっと留まっているのですが、当時の慣習ではお金さえ出せばいくらでも脱獄できました。でも彼は頑としてそれを拒否したのです。私が今ここに座っていることの原因は、たとえば筋肉や腱の仕組みから説明できるけれど、私がここに留まっていることを善しとしている(先ほどの善の話です)から、ここに留まるのだ、と。もし脱獄することが自分にとってためになる、つまり善であると判断するならたちどころに外国に逃げているだろう、と。この後者の原因をアドラーは目的と呼びます。目的があればこそ人は動き出すのだ、と。だから周りの原因だけをいくら詳細に論じても人間の行動の意味を理解することはできないというわけです。
神保 これは過去のことも含めての原因ということですね。過去がどうこうではなく、それに我々がどのような意味を与えているのかが我々を縛っていると。何となくわかる感じもするんですが、もうちょっと説明が欲しいかなと。
岸見 過去だって変わるんですよ。実際には。昔のことだから変わらないと皆さん思っているのですが、過去の意味付けさえ変えれば過去は変わります。たとえばカウンセリングで、できるだけ生まれて間もない頃の記憶を思い出してもらうことがあります。「早期回想」と言って、治療の場面でよく使います。昔のことを話して下さいと言うとほとんどの人はそれほど警戒せずに喋ってくれます。どんな短い断片的な思い出でもいいから話して下さいと言うと話してくれるんですね。
で、ある男性が小さいときのことを話してくれたんです。彼の幼少時はまだ街に野良犬がいるような時代で、彼のお母さんが「犬はあなたが逃げたら追いかけてくるから、出会ったらじっとしていなさい」と言ったと。そしてあるとき友達と連れ立って歩いていたら向こうから大きな犬が来たそうです。で、友達はパッと逃げたけれど、自分は母の言うことを守ってそこに留まっていたと。何が起こったかというと、その犬に足をガブリと噛まれたそうです。
回想はそこで終わっているのですが、少し考えればわかるように、実際はそこで話が終わるわけがないですよね。次のストーリーがあるはずです。あるのだけれど、彼はその時点では思い出せない。なぜかというと、今現在の彼が「この世界は危険なところだ」と思っているからなのです。あるいは周りの人はすごく怖い人でうかうかと信用してはいけないと考えている。だからその先のストーリーが思い出せなかったんですね。
けれど、カウンセリングが回を重ねるなかで、「人々は私の仲間である」と思い始めた彼は、あるカウンセリングのときに「あの次のストーリーを思い出しました」と話し始めました。過去自体は変わりません。だから噛まれたところまでは同じです。けれど、そのときにたまたま自転車に乗ったオジサンがやってきて荷台に載せて病院まで連れて行ってくれました、と。これだと全く違うストーリーになりますよね。彼の過去は、犬に噛まれた点は変わらないとしても、意味付けは全く変わるんです。すっかり違うものになるでしょう。意味付けというのは、そのように理解するとわかりやすいと思います。
宮台 経験に与える意味に関して、アリストテレスに照らせば、フロイトのトラウマ概念が作用因、アドラーの目的概念が目的因に当たるという話が出ました。それを理解するために僕の経験を話します。僕は本を書く際、読者にミメーシス(感染的摸倣)を与え、内発性を呼び覚ますことを意図します。
すると、多くの読者は「僕のようになろう」と目標を立てます。でも人はそれぞれリソースが違うから、必ずしも僕ができたことができません。すると、自罰的なるか、他罰的になって僕を恨みます。これは間違った展開で、「僕のようになろう」という設定に目標混乱があるんです。
目標混乱はまずい。「僕のようになろう」と思う理由を考えることで、本当の目標つまりアリストテレスの最終目的──第一原因(究極原因)の対概念──に気づけます。最終目的に照らせば、「僕のようになる」ことは手段に過ぎず、「僕のようになる」ことが効果がなければ別の手段に取り替えなければならない。
岸見先生のおっしゃる「経験に与える意味は目的との関連で決まる」とはそういうことです。「僕のようになろう」としてうまくいかず僕を恨む人は、「僕のようになろう」としたのが「最終目的のための手段」に過ぎず、取り替えが効く事実に気づけば、僕を恨むという「宮台からの呪い」から自由になります。
トラウマに象徴される「過去からの呪い」と、人への恨みに象徴される「他者からの呪い」から自由になるには、アリストテレス的な意味での最終目標をイメージする力が重要です。それが岸見先生のおっしゃることのポイントです。最終目標を設定して「経験に意味を与える」のは、僕たち本人です。
人は自分にとって
都合が良い過去をつくる
神保 過去の経験のなかには、明らかに客観的な事実というのがありますよね。たとえば犬に噛まれた事実というのは変わりようがない。しかしそのことの意味をどう与えるかで、すべてが変わるということなのでしょうか?
岸見 同じように噛まれたからといって、皆が同じようにはならないし同じような解釈はしないですよね。痛いことに変わりはないかもしれない。けれど今から過去を思い出したって、痛みは今はないじゃないですか。過去の痛みは今の痛みじゃないのです。でも痛かったと思いたい人と、そんなに痛くなかったと思いたい人は出てくるかもしれない。ただ、より大事なことは、私を助けてくれた人がいたということです。それを思い出したというのは、もはや過去が変わったと言ってもいいくらいだと私は思います。
神保 やはり過去の経験に与える意味によって、過去自体が変わってしまうと。
岸見 そうなんです。ただ私は最近、本当は客観的事実なんてないのではないかとちょっと思っていまして(笑)。私の父が認知症になって長く介護をしたのですが、二人で話しているなかで、私が過去にこんなことがあったと言うと、父はそんなことはなかったと言うわけです。この場合、その出来事が本当にあったかどうか証明できるかというと、すごく微妙な問題だと思います。複数の人が証言していればいいですが、二人しか知らないことで片方がそんなことはなかったと言えばわからないですよね。父に殴られたという話を『嫌われる勇気』にも書きましたが、それさえ本当かどうか今となってはわかりません。
神保 そのように先生が勝手に思い込んでいるのかもしれないと。
岸見 そうです。父との関係が悪くなって、看病していたときも悪くて、だから父との過去の記憶は無数にあるはずなのに、関係が悪かった事例を引っ張り出しているだけではないかと。
神保 そういうのは実際の記憶にも影響してしまうんですか? 先ほどの犬に噛まれた後のことを思い出せなかった例もそうですが、世界観が変わったことで記憶の中身自体も変わるということですか?
岸見 そうですね。何を思い出すか、何を忘れるかということは、まったく無原則ではないはずです。それは大脳の説明だけでは済まないことでしょう。私の認知症の父を見てもわかるのですが、意味があることは覚えているけれど、思い出したくないことは忘れるのです。
宮台 社会心理学には「認知的整合性理論」と呼ばれる理論系列があり、ハイダーの認知的バランス理論やフェスティンガーの認知的不協和理論が有名です。これは、人はなぜピアプレッシャー(仲間からの圧力)に負けるのかを説明する際にも使えますが、何を記憶として思い出せるのかというときにも使えます。
例えば、父親が東電の社員であるような息子や娘は、原発災害による放射能被害を小さく見積もりたがります。つまり、複数の認知的要素が価値的に整合するように、認知を歪めたり、記憶から外す傾向が、人間にはあります。その結果、現在の認知的フレームに整合しないものは、思い出しにくくなります。
神保 思い出しにくいってことは、なんか引き出しの順番みたいなものがあるってことですかね?
岸見 いや、もっと唐突なものですね。
神保 でも忘れてしまうわけではないんですよね。
宮台 心のどこかにはあります。岸見先生の犬の話は、中国の言い方では「人間万事塞翁が馬」、日本の言い方では「終わりよければすべてよし」に関係します。ところが「どこが終わりなのか」を主観が決めています。噛まれた話で終わったらバッドエンド、おじさんが助けてくれた話で終わったらハッピーエンド。
でも、これは脳がどこまで思い出すかをランダムに決めているのではありません。自分がどんな現在的リアリティを生きているかによって、思い出のストーリーの終わりをどこに設定するのかが変わるのです。変わる理由は、脳に認知的整合化を行う機能があるからです。脳の機能に注目する必要があります。
神保 それは先ほどの話にもあったように、そのほうが自分にとって都合が良いから、そのようにつくっているということなんですね。
人生の自由を獲得するための
代償とは?
神保 いろいろ話をお聞きしてきましたが、この『嫌われる勇気』というタイトルと、本の帯にある「自由」というのはどのようにつながってくるんでしょうか。そのあたり最後にお聞かせ頂けますか。
岸見 人に合わせていると誰も自分を嫌わないんですよ。八方美人になっているということです。でもそういう人の生き方は非常に不自由だとアドラーは考えます。自分の周りに自分を嫌う人が一人もいない人は、不自由な生き方をしている。逆に、自分のことを嫌う人がいるとすれば、その人は自由な生き方をしている。もっと言えば、それは自由に生きていることの証ですし、自由に生きるためにはそれくらいは払わなければならない代償だと考えます。
神保 でも、自分を嫌う人がいるというのはストレスになりますね。
岸見 うーん、なりますかね? 私はそうは言わないです。
神保 そのようになってみないとわからないということですか?
岸見 そのように思えない人たちはすぐには変身しないでしょう。Facebookですぐに「いいね」を押さないと嫌われると思うわけでしょう。そんなことやってみないとわからない。でも、一度もしたことがないことはできないんですよ。
神保 それも勇気がいるということですね。
岸見 ただ、生きるか死ぬかという話ではないわけですから、さしあたり1週間Facebookを休んでみるくらいのことはできるかもしれない。1週間が無理なら2日だっていいんです。それでどんなことが起こったかを見るようなお試し期間を設けることならできるでしょう。
神保 でもそれで実際に友達の輪から外されたりする人も出てくるかもしれないですね。そういう相談があったらどうされますか?
岸見 カウンセリングなら、それは良かったじゃないかと言いますね。何が良かったんですかと聞かれたら一緒に考えますよ。悪いことばかりじゃないはずです。朝から晩まで、お風呂に入るときまでSNSを見ているわけでしょ、若い人って。でもそんな生活から自由になれたならすごく楽になったと思わないですかと、僕はそんなことを言うと思います。
神保 なるほど、スマホ症候群ってやつですね。
宮台 ちなみに、僕はカウンセラーではないので、相談事を持ち込む学生や取材などで会った人にアドラー的なメッセージを語って、けっこう嫌われます(笑)。「カウンセラーは『君が悪いんじゃない』と言うだろうが、自分で選んでいるんだから君が悪い」と言うと、「もうお前とは話さない」みたいになる。
神保 冷たいよね、とかね。まぁ仕方ないよって言ってあげたほうが相手は喜びますよね。
宮台 僕は「仕方ないよ」とは絶対言いません。何だってやりようはありますから。最近も若い人に「未来に実現したい幸せをイメージして、それを目的にすれば、いろんなことができるよ」と言ったら、「それは恵まれた人が言うことで、自分みたいにトラウマを抱えた人間には無理です」と言われました。
神保 しかもトラウマなんてないっていう話ですからね。それを、自分でトラウマを絶対的なものだと思っている人に言うわけだからね。
宮台 その際「それは言い訳だ。変わりたくない人はトラウマを持ち出す。新しい目的に沿って新しいことをしてみれば『自分は思っていたような自分じゃなかった』となって、ますます新しいことができる」と言って、また嫌われる。僕は短時間の1回しかコミュニケーションできない場合、嫌われても言います。
岸見 そういう場合、カウンセリングだと戻ってくる人もいるんですよ。何年か掛けてね。
神保 やはり先生の言うとおりでしたみたいな感じですか?
岸見 そうですね、ただそういうのは本人に任せるしかないので、こちらからまたおいでとは言わないです。
神保 先生はアドラー心理学のカウンセリングとしてそのようにやってらっしゃると思うんですが、他の流派だとどうなんでしょうか?
岸見 それはわからないですね。もしかするともっと熱いかもしれません。私は自分が冷たいとは思いません。自分では「涼しい」と言っていますが(笑)。ただ、それくらい距離がないと問題は解決しません。カウンセラーも同じように悩んで巻き込まれてしまっては、カウンセラーと患者さんが共依存になってしまいます。だから、カウンセラーも患者さんに嫌われる勇気を持たないと無理だと思います。
実際の私は、かなり悩むほうですよ。すごく患者さんのことを心配するし関わりたいとは思うけれど、でもやはり距離を置かないとしんどいです。別にその人を切り捨てるつもりは全くないですし、なんとか力になりたいと思っているのが基本なんですが。
なぜ自己のホメオスタシスを
崩す勇気が持てないのか
神保 宮台さん、ここまでのところでもっと深掘りしておきたいこととかありますか?
宮台 僕にとって10年以上前に岸見先生にお会いしたことが重大な転機になっています。岸見先生の『アドラー心理学入門』を読み、僕自身も若い頃にアドラーの強い影響下にある自己啓発セミナーのトレーニングを受けていたことがあって、それが何だったのかをアドラーの枠組みで位置づけ直しました。
その上で、僕が本や講演で使ってきた概念やフレーズにどう対応するのか考えました。そのプロセス抜きでは僕が今やっている性愛ワークショップも政治ワークショップも成り立たない。だって、いろんな理由を持ち出して「できない」と悩む人が来るんだから。「あなたは悪くない」じゃ話になりません(笑)。
神保 なるほど、やりたいけどできないって言う人に「実は君はやりたくないんだよ」って言うんですね。
宮台 これは優先順位の問題です。本人はやりたいと言うし実際やりたいのだろうが、実はそんなに優先順位が高くない。代わりに「モテたいのにモテるための努力ができない理由は、そういうことだったのか」と納得することのほうが高い優先順位だったりする。その意味では「さしてやりたくない」んです。
神保 やりたいと言っているのにね。岸見先生、なぜ人はそれに気づかないんですか? 実はモテたいとかは二番目か三番目の優先順位のことなのに、主観的にはそれが一番したいことなんだと思ってしまう。実はもっとしたいことがあるのに自分はそれに気づかない。なぜそんなことが起きるんでしょうか?
岸見 それはわからないですね。単純明快なことだと思うんですが。
神保 不思議ですね。それは今に始まったことではなく、ギリシアの時代からそうなんですよね。
宮台 僕がサブカルチャー分析で使うキーワードは「自己のホメオスタシス(恒常性維持)Homeostasis of the Self」です。認知的整合性理論とも関連しますが、「自分はこんな人でこういう生き方をする」というフレームやスクリプトを何だかんだと維持しようとする傾向です。アニメや音楽もそのために使われます。
こうしたフレームが維持され、自己のホメオスタシスが貫徹できれば、人はいろんなものを免除されます。チャレンジの努力も免除されるし、選択できない自分を責める営みも免除される。「トラウマだからできない」とか「自分は然々の性格だからできない」とか。かくして同一フレームに留まることで楽をする。
本人がどんなに「辛い」と言っていても、自己のホメオスタシスによって免除されることがすごくたくさんあるので、それら免除の利得を手放してまで今の「辛い」状態から逃れたいと思っているかどうか、「辛い」という科白だけじゃわからない。その意味で「辛い」という科白を真に受けちゃいけません。
神保 いま宮台さんがホメオスタシスという言い方で表現したある種のバランスというか、それを崩すことが人間にとってはものすごく勇気がいることだったり、苦しいことだったりするのが背後にあるんですかね。そのことにあまり自分は気づいていない。少なくとも主観的には気づいていないと。
宮台 ただ、ゲシュタルト(全体性)を維持することでさまざまなものを免除される状態を変えたくないと望んでいる事実は、人から言われないと意識できません。なぜなら「あなたのすべての振る舞いは、ゲシュタルト維持という同一の機能に、意図せずして貢献している」という、潜在機能の問題だからです。
とはいえ、僕のような下手な人が言うと、意識させることは一瞬できるかもしれませんが、「何だこの野郎!」と反発されて、僕自身が自己防衛の対象──いわば敵──になりがちです(笑)。そうなると、僕の言葉は相手に入っていかなくなります。
神保 そこは岸見先生のように色々と技術的に接することが大切なんですね。
岸見 もう一つは、どう変わるかというイメージがはっきりしていないと変われないですね。変わらないでおこうと決心していることまではわかったとしても、じゃあどう変わればよいかがはっきりしていないとどうしようもない。そこは積極的に私も教えます。「カウンセリングは再教育である」とアドラーは言っていますが、これまで知らなかったことを学んでもらう必要があるわけで、ほとんどの人がそれまで実践したことがないようなことばかりです。だから、まずはそれをやってみましょうよと。まぁいろいろ考えはあるかもしれないけれど、まずこれをしてみたらどうですかと提案する。やってみたらうっかり変われるかもしれないわけです。
神保 となると、1週間くらいとりあえずやってみようというのは一つの結論ですかね。いきなり全部変われと言われても勇気が持てないかもしれないので。
岸見 別に元に戻ってもいいんだよと言っておかないと変われないですね。
神保 なるほど。今日は色々と伺いましたが、まだお聞きできていないことも多いのでもう一度おいでいただくようお願いします。最後に宮台さん何かありますか?
宮台 この『嫌われる勇気』がベストセラーになっているわけですが、アドラー心理学の本が日本でこれだけ売れるというのはまったく初めてのことなので、本当に素晴らしいことだと思います。そのことが「あなたは悪くない」と語るカウンセラーを減らすことにつながれば、もっといい。
神保 この本が20数万部も売れているという背景を宮台さんはどう見ますか?
宮台 やはりニーズはあったということだと思います。多くの人たちは「あなたは悪くない」じゃ済まないことだらけという事実を理解するだけの力を持っていて、自分がどんな責任を負うのかを明確にしたいと思っていたということでしょう。
神保 逆に言うと、それだけ嫌われることにビクビクしている人たちがたくさんいたということなんでしょうか?
宮台 そう思います。「その場の切り抜け」と「最終目標の現実化」を切り分けて優先順位が付けられず、右往左往しがちです。ただし、そうした人じゃなくても、この本は読む価値があります。「変わりたいけれど変われない」とこぼすすべての人に意味がある本だと思うので、ぜひ読んでいただきたいです。
神保 では、今日はありがとうございました。次回またよろしくお願いします。
岸見 こちらこそありがとうございました。
岸見一郎(きしみ・いちろう)
哲学者。1956年京都生まれ、京都在住。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。専門の哲学(西洋古代哲学、特にプラトン哲学)と並行して、1989年からアドラー心理学を研究。精力的にアドラー心理学や古代哲学の執筆・講演活動、そして精神科医院などで多くの「青年」のカウンセリングを行う。日本アドラー心理学会認定カウンセラー・顧問。訳書にアルフレッド・アドラーの『個人心理学講義』『人はなぜ神経症になるのか』、著書に『アドラー心理学入門』など多数。古賀史健氏との共著『嫌われる勇気』では原案を担当。
宮台真司(みやだい・しんじ)
首都大学東京教授/社会学者。1959年仙台生まれ。東京大学大学院博士課程修了。東京都立大学助教授、首都大学東京准教授を経て現職。専門は社会システム論。博士論文は『権力の予期理論』。権力論、国家論、宗教論、性愛論、犯罪論、教育論、外交論、文化論などの分野で著書多数。主な著作に『制服少女たちの選択』『終わりなき日常を生きろ』『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』『14歳からの社会学』『日本の難点』『「絶望の時代」の希望の恋愛学』などがある。宮台真司オフィシャルブログ
神保哲生(じんぼう・てつお)
ビデオジャーナリスト/ビデオニュース・ドットコム代表。1961年東京生まれ。コロンビア大学ジャーナリズム大学院修士課程修了。AP通信記者を経て93年に独立。99年11月、日本初のニュース専門インターネット放送局ビデオニュース・ドットコムを設立。著書に『民主党が約束する99の政策で日本はどう変わるか?』『ビデオジャーナリズム―カメラを持って世界に飛び出そう』『ツバル-地球温暖化に沈む国』『地雷リポート』、訳書に『食の終焉』などがある。ビデオジャーナリスト神保哲生のブログ
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年05月20日 17:25
食生活の改善維持は、健やかで美しい心身づくりの根幹です。。。
■早く凹む!ボディワーカーが教える「タイプ別ポッコリお腹」解消法
磯部 奈央
夏前に、「脂肪を何とか落としたい!」と意気込んでいる方も多いのでは? 特に、女性でもポッコリお腹に悩んでいる方は多いことでしょう。
『美レンジャー』の過去記事「プロが警告!”腹筋運動だけでお腹は凹まない”衝撃の事実が判明」にもご登場いただいた、ボディワーカーの森拓郎先生によると、ポッコリしているお腹を凹ますためには、タイプに合わせたダイエットが必要とのこと。
今回は、森先生に伺ったタイプ別のポッコリお腹解消法をお伝えします。
■1:“内臓脂肪タイプ”の解消法
森先生によると、「内臓脂肪がついたポッコリお腹に、最も短期的に効果が出るのは食事改善です。食事に気をつけないと、むしろ運動しても効果は少ない上に、頑張ってもやめた途端にリバウンドが待っています」と話していました。
「まず、ツライ腹筋運動などはやる必要なく、炭水化物の量を減らすことだけに集中します。ただ、今まで摂り過ぎていた人が全て炭水化物を抜いてしまうと、結局我慢ができなくなり、リバウンドにつながります。炭水化物をたくさん摂らないようにするところから始めましょう」
さらに、「飲み物は水かお茶にしてください。炭水化物を減らすというと、ご飯やパンを想像しがちですが、最も摂取制限の優先順位が高いのは飲み物なのです。
甘い清涼飲料水はもちろん、100%ジュースや健康飲料、ゼロカロリー系のものもダメです。手軽に摂取できてしまう“甘いもの”を何となく飲む、という習慣を控えることが重要です」と教えていただきました。
アルコールでは、ビールよりも糖質のない焼酎やブランデー、ウォッカなどの蒸留酒を選ぶと内臓脂肪にはなりにくいそうです。
一方、お菓子は、やはり食べないのが一番よいとのこと。どうしても我慢できない場合は、食べる時間を定めましょう。仕事をしながら、テレビを観ながらなどの惰性で食べる習慣を改めれば、摂取量を減らせるはずです。
いきなり全てを断つのではなく、適量を楽しむようにするだけでも、効果がきっと感じられるでしょう。
■2:“内臓下垂タイプ”の解消法
森先生曰く、「内臓下垂でお悩みの方は、インナーマッスルの強化が必要です。インナーマッスルというと難しそうなイメージがありますが、ご自分でお腹をスッと引き上げて、ウエストを細くしてみましょう。ちょうど、オードリーの春日さんのような感じです」とのこと。
さらに、森先生は、「実はこれがインナーマッスルを使っている状態なのです。”ドローイン”ともいわれる方法ですが、身体を動かしているときには、絶対に筋肉が必要。自分でお腹を凹ませる力がインナーマッスルの力であり、これが弱ると内臓が落ちてくるというわけです」と話していました。
お腹を割るという目的であれば、腹筋運動をする必要がありますが、お腹を凹ませるというだけであれば、お腹をスッと引き上げるドローインで十分なのだそうです。
いかがでしたか? 自分がどのタイプのポッコリお腹なのか、しっかり理解した上で、適切なダイエットを行うことが何よりの近道です。どちらのタイプも体力を使いすぎたり、時間がかかりすぎるような大変なものではないので、毎日の習慣にしてスッキリお腹を手に入れましょう!
[美レンジャー]
Posted by nob : 2014年05月19日 16:53
代謝が上がるだけでなく、セロトニンをつくり出すなど、様々な効果を期待できます。。。
■午前中に「太陽光を20~30分浴びる」だけで痩せ体質になると判明
佐藤まきこ
[午前中に「太陽光を20~30分浴びる」だけで痩せ体質になると判明] 細かい桁までカロリーを気にしたり、甘いものを食べたくてもグッとこらえるなど、体重コントロールにかける女性の努力は、涙ぐましいものがあります。
でも、ツラい運動も食事制限もなく、朝8時から12時までにあることをすると、BMIの値を低くキープできるという、驚愕の実験結果が明らかになりました。
■”午前中に最低20分”がカギ
ノースウェスタン大学の研究員が人の肥満度を図る指標BMIの値に、太陽光がどのように影響しているか調査を行いました。実験では平均年齢30歳の男女54名を対象に、太陽光を浴びた時間と、睡眠時間、食事で摂ったカロリーなどについて調査しました。
すると、午前中に太陽の光を浴びている人は、もっと遅い時間に太陽光を浴びた人に比べて、BMIの値が低い傾向にあることがわかったのです。
太陽の光を浴びる理想的な時間は午前8時から12時までで、BMI値が上がらないようによい方向へ影響をもたらすためには、20〜30分で十分であることもわかりました。
光の単位を使って表すと、BMI値に影響を与えるのに必要な光の量は500ルクス。しかし現代では窓のない職場や地下で働く人も多く、そのような環境にいる人は、わずか200〜300ルクス程度しか浴びていないと言います。
曇りの日でさえ屋外にいれば1,000ルクスは浴びるため、いかに屋内ではなく屋外に出ることが大切かがわかります。
■自然光を浴びると代謝がアップする
人が太陽の光を浴びると体内時計が調整され、それによって身体の代謝が上がります。そのため光を浴びるとスリムな体型を保てるのです。
これまで研究者たちは、BMIに太陽光を浴びることはもちろん、その浴びる時間帯やどのくらい長い時間が必要かなど調べてきましたが、これらの要因単体ではBMIには何も影響を与えず、すべてが組み合わさった時に初めてBMIに影響をもたらすとわかったのです。
もしも午前中のこの時間帯に外に出ることができない環境にいる人は、休憩時間などを使って少しでも屋外に出るようにしましょう。
わずかな体重変化のために、さまざまな努力をして一喜一憂している私たちにとって、午前中にたった20〜30分外に出るだけで代謝が上がって、健康かつスリムになれるなら、こんな嬉しい話はないですね。
[美レンジャー]
Posted by nob : 2014年05月19日 16:45
私も実践中、、、おすすめです。。。
■毎日10秒続けるだけで「透明感と小顔」が手に入る
美肌や小顔にとってマッサージは効果的だって言うけど、時間と手間がかかるのが難点。
それならば、マッサージよりも簡単にできる「顔ツボ10点プッシュ」がおすすめ。わずか10秒で、くすみやむくみに効果を発揮してくれるんです!
顔ツボ10点を覚えよう
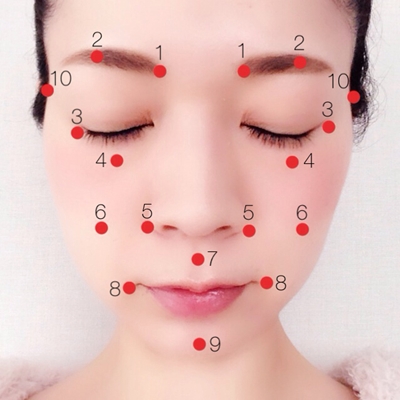
画像の赤い点がツボの場所になります。眉頭・眉山・目尻・黒目の下・小鼻ワキ・頬骨下・鼻下・口角ワキ・アゴ・こめかみと、番号順に人差し指や中指でツボ を押していくだけです。
私は8年ほど前からスキンケアの最後にこの10点プッシュを行っていますが、いまでは自然と手が動いてしまうほどあたりまえになっています。
仕事中の目の疲れにも効果的
それぞれのツボによって効果は違いますが、10点すべてを押すことでむくみ・たるみ・血行不良などの改善が見込め、小顔に導いてくれます。
とくに目のまわりのツボは眼精疲労などにも効きますので、仕事で疲れたときにプッシュするのもいいですよ。
忙しくてスキンケアにさける時間がないという人でも、これなら気負いなくできそうですよね。クセにしてしまうことが毎日続けるポイントです。
イトウウミ
ビューティーリサーチャー
モデル/知念沙也樺
[glitty]
Posted by nob : 2014年05月16日 15:58
筋肉を育むために運動は必須なのだから。。。
■今日から取り入れるべき習慣がここにある! エクササイズせずに体の代謝をあげる15の方法
田端あんじ
痩せたい。でも……運動はしたくないの! 絶対ッ!
お嬢さん、その気持ち、痛いほどわかります。本日は、そんなあなたにピッタリのとっておき情報をお届けしちゃいますよぉ!
ご紹介するのは、海外サイト「Daily Makeover」が報じている、エクササイズせずに代謝をあげる15の方法。
もちろん運動するに越したことはないけれど、日々の生活に取り入れるだけで代謝アップ、ひいては体重減少に繋がり得る「習慣」は、他にもたっくさんあるのです。それでは早速、その気になる全貌を、一緒にみていくことにいたしましょう。
1 起床後すぐコップ2杯の冷水を飲む
代謝アップにおいて、「水を飲むこ」とは欠かせない要素。冷たい水が内臓に入ることによって、体はスリープモードから一気に活動モードへ切り替わります。ドイツの研究者曰く、「1日6カップの冷水を飲むことで、体を温めようとする動きが活性化、その結果代謝があがる。これは1日につき0.05キロカロリー、静止した状態の代謝量が上がることを意味します」とのことです。
2 1日1~2時間は立つ
デスクワークに従事している方は、特に取り入れてほしい習慣がコレ。座りっぱなしでは、筋肉を使う機会を得ることができません。強制的に1日1~2時間立つべく、立ったまま仕事ができる「スタンディング用デスク」を導入してみるのもテ。
3 温水と水を交互に浴びるコントラストシャワーに挑戦
2~3分温水を浴びた後、30~45秒ほど水を浴びる。これを行うことによって血の巡りが良くなり、循環系が改善、代謝がアップします。また体の緊張を緩めるため、よく眠れるようにもなるのだとか。
4 十分な睡眠をとる
十分な睡眠は、代謝アップにおいて不可欠。体を機械とすると、それが再起動するためには、効果的な休みがどうしても必要になってくるのです。
5 断食をする
断食といっても、「1日中なにも食べてはいけない」といった事例ばかりではありません。たとえば夕方18時までに食事を終え、それ以降口にして良いのは冷水のみ。朝食も冷水だけ、昼食に食事を再開する。まずはこの程度の断食から始めてみましょう。
6 香辛料の効いた物を食べる
代謝アップに欠かせない食べ物が、香辛料。特に唐辛子は、消化・血液循環・エネルギー増加に効果大。またコショウは、消化を促し満足感を得るのに、非常に適した食品です。日々の食事において、効果的に摂り入れてみて。
7 セロリを食べる
カロリーをより多く消費するのに効果を発揮してくれる食べ物が、セロリ。たとえば6カロリーのセロリを消費するのに、体は7カロリーの熱量を使用しなければならないのだそう!
8 料理に使用するなら断然ココナッツオイル
ココナッツオイルはより早く消化される上、エネルギー消費において優先的に使用されるのだとか。そのため脂肪になりにくく、中性脂肪を減少させる効果も。
9 シナモンを摂り入れる
代謝アップスパイスの代表格として、シナモンも欠かせません。血糖値の低下や、中性脂肪やコレステロールの低下が期待できるのだそう。
10 ニンニクを食べる
脂肪を燃やし代謝を上げるのに効果を発揮、血糖値をも正常に保ってくれるのが、ニンニクです。免疫系も上げ、高血圧をも防ぎ、さらには抗酸化作用もある、パーフェクトな食材、それがニンニク!
11 グレープフルーツを食べる
代謝を上げるうえで抜群の効果を発揮してくれるグレープフルーツは、ビタミンCやAも豊富なので、美肌にも必須。脂肪を燃やす酵素を含み、タンパク質の分解をも助けてくれるため、積極的に摂り入れたい食品です。おススメの調理法は、シナモンとナツメグをかけていただく、「焼きグレープフルーツ」。
12 繊維質を多く含んだ食品を摂取
全粒粉パスタや豆類など、繊維質を多く含んだ食品は、消化に多くのエネルギーを必要とします。つまり、高繊維質食品は、カロリー消費に一役買ってくれるというわけ。
13 緑茶を飲む
緑茶に含まれる緑茶カテキンが代謝を上げ、体重減少に効果を発揮することは、巷にある商品のおかげで、みなさんもご存知なのではないでしょうか。特に朝、2杯のアイス緑茶を飲むようにすると、カテキンとカフェインがより効果的に働いてくれるのだそう。
14 ギリシャヨーグルトを食べる
代謝を上げるために必須なタンパク質が通常のヨーグルトの倍、さらにはカルシウムも豊富に含まれている同品は、プレーンの状態で食べるのがベスト。アレンジを加えるのであれば、パイナップルとステビアを混ぜて食べる方法がおススメなのだとか。
15 サーモンを食べる
代謝を上げてくれるサーモンは、タンパク質、オメガ3脂肪酸が豊富。オメガ3脂肪酸は、心臓病のリスクを下げるなど、健康面でも効果を発揮してくれます。
いかがでしたか? 代謝を上げてくれる習慣、そして食物を積極的に摂り入れて、夏までにスリムボディーを手に入れるべくがんばりましょうね~!
参考元:Daily Makeover
[Pouch]
Posted by nob : 2014年05月14日 07:14
なおざりな私、、、明日から留意したいと思います。。。
■男の紫外線対策
野々下一美
メンズコスメアドバイザー
紫外線対策の必要性
初夏の装いを意識するようになると、注意しなければならないのが「紫外線対策」。「真夏じゃないのにもう紫外線対策するの?」と言う声が聞こえてきそうですが、紫外線対策は真夏では遅いのです
一年を通して、もっとも紫外線の強い時期は5月~8月と言われています。特に6月以降8月までの午前10時から午後2時くらいの紫外線は、1月の5倍以上に達すると言われています。曇り空でも、晴れているときの50~80%の紫外線は発生していると言われているので、この時期は要注意です。
そもそも、紫外線対策は何のためにするの?ということで言えば、単に色が黒くなってその結果シミになってしまうから…。そう単純なことでもないのです。誰でも望むことですが、「いつまでも若々しくいたい」という思いとは裏腹に、シミがあるだけで、ない人と比べ5~6歳ほど老けて見えると言われています。
若いうちから紫外線対策をしている方は、いつまでも若々しく美しい肌を保つことができます。特に男性は紫外線対策を意識していない方が多くいらっしゃいますので、今年からは早速始めていただきたいと思います。
紫外線の恐怖
紫外線のメカニズムを説明すると、たった2分間太陽を浴びているだけで紫外線は確実に真皮にまで到達し、瑞々しい肌の要素であるコラーゲンを破壊し、肌のハリや弾力を奪い取ってしまうと言われています。
かたやシミの元になるメラニン色素は、肌の真皮下において紫外線を異物として認識して、紫外線が侵入してこないように防御の意味で発生します。
メラ二ン色素は、新陳代謝が活発な若いときははがれ落ちていきますが、加齢と共に新陳代謝が鈍くなるといつまでも表皮にとどまり、頑固なシミとして皮膚に沈着してしまいます。日に焼けたブロンズ色の肌がカッコイイと思う時は人生のうちでもわずかな時間です。
熟年になってからシミ・シワ・たるみだらけで実年齢より歳老いたボロボロの肌で暮らさなければならなくなります。そして、何より恐ろしいのは皮膚がんの原因にもなってしまうことが分かっています。
紫外線対策
まずは、外出時には必ず日焼け止めクリームを塗りましょう。その際には、サングラスや帽子も忘れずに。
うっかり日に焼けてしまったら、早めにケアを開始してください。紫外線は、コラーゲンを破壊するだけでなく必要以上に肌の水分を奪い取ります。肌の乾燥は、角質がめくれあがって細胞間の脂質を不足させ、カサカサの状態を作ってしまいます。
丁寧な洗顔の後、たっぷりと化粧水をつけてください。一度にたくさんの量を付けずに、何回かに分けて付けると良いでしょう。最後にきちんと乳液かクリームで水分蒸発を防ぐためにバリアを作ってください。
また肌の新陳代謝を活発にして、できてしまったシミをなるべく早めになくすようにパックやマッサージするのもオススメです。
加齢による老化は避けて通ることはできませんが、紫外線による光老化はある程度対策が可能です。せめて、光老化による対策は気づいた時点で始めましょう。
[スキンケア大学・美ログ]
Posted by nob : 2014年05月12日 21:59
また旅立つ君へVol.37/失敗は次なる成功への一過程に過ぎない。。。
■人はなぜ失敗を恐れるのか。
失敗の正体と、その正しい生かし方
菊池龍之
失敗は人を成長させる、といいます。しかし、できるだけ失敗したくないと思うのもまた事実です。本能的にも失敗を回避する心理は働きますが、後天的な経験を通じて、さらに失敗を恐れるようになるといいます。
ロシアの心理学者ツァイガルニクの研究によると、人間はうまくいったことよりうまくいかなかったことを強く記憶する傾向があるようです。何かを達成しなくてはいけないという課題場面において、人は緊張状態にあります。達成するとこの緊張から解放されるために、課題自体を忘れがちになるといいます。テスト前の一夜漬けの勉強内容を、試験が終わるとキレイさっぱり忘れてしまうのは、同様の理由です。逆に、課題解決がうまくいかないと、緊張状態が長く続くため、記憶にも定着します。その失敗した苦い記憶が、トラウマとなったり、挑戦すること自体を恐れてしまう要因になります。
もうひとつ、私たちが失敗を恐れる理由を示す実験があります。
スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエックは、クローディア・ミューラー氏とともに、ニューヨーク市内の12の学校である実験を行いました。研究では、5年生400人あまりに、言語を用いない比較的やさしいパズルを課題として与えました。テスト終了後、研究者たちは生徒たちに点数を伝え、簡潔な言葉で褒めました。半分の生徒には「あなたは頭がいいんだね」と彼らの知性を褒め、残りの半分には「一生懸命やったね」と彼らの努力を褒めました。
そして次に、先ほどの生徒たちにまた別のテストを2種類与え、生徒たち自身にどちらか好きな方を選ばせました。ひとつは最初のものより難しいパズルですが、やればとても勉強になると説明されたものです。もうひとつは、最初のものと同様の簡単なテストです。
すると、努力を褒められた子どもたちは、90%近くが難しい方のパズルを選択し、一方知性を褒められた子どもたちは、ほとんどが簡単な方のテストを選んだのです。大変興味深い選択です。ドゥエック氏によると、知性を褒められた子どもは、自分を賢く「見せる」ことに気持ちを向けるようになり、間違いを犯すリスクをとれなくなるのだと説明しています。
つまり、いい結果を出したことを評価され続けた人にとっては、いい結果が出せなくなるかもしれない選択(新たな課題に取り組むこと)は避けたいという心理が働くのです。
しかしこうした理由があっても、現場を引っ張るリーダーである皆さんは、正解のないビジネスにおいて失敗を恐れず果敢に挑戦しなければなりません。孔子の言葉「過って改めざる、これを過ちという」にあるように、失敗を失敗のまま終わらせてしまうことが本当の失敗です。「失敗」にきちんと向き合い、その失敗を生かしていくことが大事です。
心理学ジャーナリストの佐々木正悟氏は、失敗を生かすためのコツとして、「失敗からむやみに教訓を引き出そうとしないこと」を挙げます。「失敗を次につなげる」「失敗を生かす」という表現は使っているころには時間が経ち過ぎているので、失敗を生かす方法はすでに忘却されているものだと指摘します。
そこで、彼の提唱する失敗を生かす最善の方法は、失敗しているまっただ中で
* やるべきだったのにやらなかったこと
* やるべきでなかったのにやってしまったこと
の2点を箇条書きにして、できるだけ即座に行動を起こすことです。
侍ハードラーと呼ばれた為末大氏は自身のTwitterを通じて、新たな挑戦に勇気を与えるメッセージを送っています。
チャレンジはある一定の失敗の確率を含む。失敗の確率が低いものはチャレンジではなくただの実行。チャレンジし続けるということは失敗するリスクを取り続けるということ。
チャレンジは自分に限界を超えさせて、成長を促す。そのチャレンジが不足するということは長く見ると成長が滞り、結局結果が出なくなっていく。
やるからには結果を出さないと、という価値観が強過ぎる人は、いずれやらなくなる。やらないから経験がなく、すべて頭で考えた世界で生きる。プライドが肥大化し、そして現実とどんどん剥離する。
思いっきり挑戦して、失敗すれば笑う人もばかにする人もいると思う。そういうときは自分も一緒に思いっきり笑えばいい。そして気が済んだらまた挑戦する。結果は運だけれど、挑戦は選択。勇気を持って選択し続ければ本当に勇気がある人間になれる。
何を失敗と呼ぶのか。失敗の定義は、あなた自身の考え方次第で、その姿を変えていくのです。
[DODA]
Posted by nob : 2014年05月12日 21:49
言い得ています、、、食生活とは「食べてイキイキ(生き活き)」大切にしたい。。。Vol.2
■心が満足してないと過食する!「食べ過ぎを防ぐ」簡単な心得9つ
庄司真紀
美レンジャーカロリーや栄養素だけで食事を捉えるのはナンセンスです。質素でも満たされる食事もあれば、お腹が空いていないのに、食べ過ぎてしまう時もあります。
食事は身体と心を作り、人生に影響するもの。ホリスティック栄養学では、身体に必要な物質としての栄養だけのみでなく、心も養う食を大切に考えています。
今回は、この栄養学で参考になるシンプルなルールを、ホリスティックヘルスコーチの二宮香里さんに教えていただきました。
■9つのシンプルルール
(1) 未精製 > 精製
(2) 全体 > 部分、抽出
(3) 手作り > 加工食品
(4) 粒 > 粉
(5) 地産、旬 > 輸入、一年中
(6) 豆 > 魚 > 肉
(7) 同じ釡の飯 > 個食、孤食
(8) 温 > 冷
(9) 腹八分 > 満腹
「新鮮なもの、なるべく熟してから摘み取ったものの方が、当然美味しく栄養価も高くなります。そして近場で採れたものが理想的で、フードマイレージも低くなります。
また手作りすることは、真心を込めること。添加物を控えることにもなり、自分の身体が本当に求めているものが得られることにより心も満たされるのです。さらに大切な人と時間や空間をともにすると、深い満足感が得られます」と二宮さんは、語ります。
毎日、9つのルールのうち1つでもよいので、意識して食事をしてみましょう。
■どうしてもファストフードが食べたい時には
加工品やファストフード、お菓子を欲してしまう場合はどうしたらよいでしょうか。
二宮さんは、「砂糖、小麦、ポテトチップスなどの揚げ物、塩味のもの、タバコ、アルコール、カフェインを含むものなどの中毒性のあるものは、一時的な快楽をもたらしますが、心や身体を本当の意味で満たすわけではありません」と話します。
さらに、「これらは、精製され抽出されたもので、”生きた”食べ物ではありません。生きたものでないと、身体は満たされないので、もっと必要な栄養素を欲することになります。また、マーケティングを駆使した中毒性のあるものに抗うことは、意思の強さとは関係ありません。自分の意思の弱さを責めなくても大丈夫です」とのこと。
満たされていないと、さらに他の食べ物を欲してしまうという悪循環に陥ってしまうのですね。
アルコールやカフェインも同様で、1週間摂らずに過ごして身体がどう感じるか様子を見てみましょう。心を満たすことができない食事は、食べ過ぎにつながるリスクが潜んでいることを感じていただけましたか?
[美レンジャー]
Posted by nob : 2014年05月12日 21:44
言い得ています、、、食生活とは「食べてイキイキ(生き活き)」大切にしたい。。。
■プロが断言!ダイエット成功の秘訣は「3倍高い食べ物を買う」こと
庄司真紀
「普通に美味しいと思うものを何も考えずに好きなだけ食べていれば、誰でも簡単に糖尿病になる環境にある」とフィットネストレーナーでダイエット指導者でもある森拓郎さんは言います。それだけ飽食の世界では、健康リスクが高いということ。
もちろん、みなさんお分かりのように太らない食べ物としては、脂肪分が少ない食べ物や野菜、果物などの酵素たっぷりの食べ物などがあります。しかし、もともと高カロリーなパンやお菓子、お弁当など加工品を選ぶ時には、何を基準にすればよいのか? それにはもっと簡単なルールがあるのです。
太らずに健康でいられるために、森拓郎さんの著書『運動指導者が断言!ダイエットは運動1割、食事9割』からお伝えします。
■安価で手に入る食べ物を摂取しない
森さん曰く、「太る食べ物と太らない食べ物を見極めましょう。まず太りやすい食べ物は、不自然な食べ物であることが多いのです。太らない食品を選ぶ基準は、どれだけ精製されているか、どれだけ化学合成されたものが入っているかが、判断の目安になります」とのこと。
コンビニで売っているスナック菓子や菓子パン、チョコレート、シュークリームといったスイーツなどは、大量に精製された砂糖やトランス脂肪酸が入っており、さらに香料、保存料も大量に使われています。お菓子だけに限らず、コンビニのお弁当や清涼飲料水もそうです。
つまり、すぐに安価に手に入る食べ物は控えるということが大事なのですね。ちなみに、森さんがコンビニで買う食べ物は、ミネラルウォーターとバナナ、ほし芋、無塩ミックスナッツくらいだそうです。
■3倍高い食べ物を買うこと
「お菓子を食べるな!」とは言いませんが、どうせ食べるのであれば、できるだけ上質なお菓子を食べましょう。
「上質であれば太らないということではありませんが、上質なお菓子は素材もよいものを使っていることが多いので、その分価格が高い。必然的に量も少なく価格が高いので、たくさん買わなくて済みます。私は毎日のチョコやケーキを止められないという方には、3倍高い食べ物を買いなさいとお伝えしています」と話していました。
価格が高いと頻度を減らさざるを得ないため、結果としてカロリーは3分の1で、味わいの満足度は3倍になるそうです。
「血糖値が下がって集中力が低下したり、イライラするのは普段の食生活が原因」と森さんは指摘します。血糖値が下がり過ぎるのは、血糖値が急上昇するような食べ物を食べ過ぎていたり、血糖値のコントロールをする栄養素が摂れていなかったりすることが原因として考えられます。
食生活を改善し、血糖値のコントロールを自分でできるようにしましょう。
いかがでしたか? 上記のことができれば、多少お腹が空いても、集中力の低下やイライラもなくなっていきます。一石二鳥ということですね。
[美レンジャー]
Posted by nob : 2014年05月12日 21:15
ミネラルウォーター以外はすべて嗜好品、、、チェイサーを脇に美味しくいただきましょう。。。
■何でも飲み過ぎは体に毒?
笠井奈津子
栄養士、食事カウンセラー
コーヒー、トクホ飲料好きな人の飲み方のルール
「いやー、なんか、痙攣が止まらなかったんですよ。で、めまいもひどいし。ネットで症状を調べていたら、コーヒーの飲み過ぎだってことがわかって!やめたら本当にすっかり良くなりましたよ」
先日、知人が笑いながらこんな話をしてくれた。
この文脈だけを見るとなんだかコーヒーが悪者みたいに見えるかもしれないが、「毎日2リットル近く水代わりに飲んでいた」と聞いておもわず、「そりゃそうだ!」と突っ込んでしまった。でも同時に、「胃がすごく丈夫なんですね!」と感心もしてしまった。
食事をする、ということに対して「お腹を満たせれば良い」という人は少なくない。時間がない、という理由もあるだろうし、仕方がない部分もあるかもしれない。でも、水分補給に関してまで、「咽と乾きを潤せれば何でもよい」となったらそれはまずい。
飲み物は、同じような価格帯の中で、同じお店で手にするものをチェンジすれば、体への影響が改善できるなど、食べ物に比べてとてもお手軽である。そこで今回は、これから水分摂取が増えていく季節を前に、今一度飲み物について考えてみたい。
体の水分が20%失われれば生命の危機に!
生きるために欠かせない飲み物
どんな飲み物を口にするかは、その人の健康をも左右する。なぜならば、体内にもっとも多く含まれ、かつ、酸素とともに生命維持のために必要不可欠なものは、間違いなく水だからだ。だからこそ、汗を多くかけば尿量が減ったり、水分を多く摂れば尿量が増加したりと、常に一定に保たれるように調整されている。
コーヒーやビールなどの利尿作用が高い飲料を日常的に“大量に”口にするようになると、当然尿量は増えるが、そもそも、正常とされる1日の排尿回数は4回~8回程度とされている。1日に10回以上トイレに行くような場合は、水分のとりすぎや利尿作用の働く飲み物の飲み過ぎが考えられる(もしもその心当たりがない場合には、腎臓系の疾患や糖尿病など、病気の可能性もある)。また、運動量が多く、排尿回数が少ない、というのであれば、もう少し水分補給を積極的にする必要がある。
すごく当たり前のことすぎてピンとこないかもしれないが、意識してほしいのは、出納のバランスが崩れれば、その調整のために体に余計な負担をかけることになる、ということだ。ただでさえハードな毎日、ただでさえ乱れた食生活…なのであれば、それ以上の負担はかけないに越したことはない。
たとえば、体重の約1%の水分が失われれば“喉が渇く”ように、体は自然と水分が不足しないように働く。もしも10%ほど失われてしまうと、筋肉の痙攣や意識の混乱が起き、腎機能は機能しなくなり、20%以上が失われようものなら、それはもうダイレクトに生命にかかわってくる。日常においてはこのような事態にまで及ばないはずだが、それくらい大切なものなのだ、ということは認識しておきたい。
なぜなら、体内の水分は、血液、細胞内液、リンパ液、皮膚、筋肉、臓器など、あらゆる部分に分布していて、栄養素など多くの物質を全身に運ぶためにも欠かせない存在だからだ。
お茶、ジュース、トクホ飲料に含まれる
水以外の成分に要注意!
そして、栄養素の代謝は体液の中で行われている、ということを忘れてはいけない。栄養素は、体の中で、水に溶けた状態で消化吸収、運搬されている。中性脂肪のように、水に溶けないものもあるよね?と思うのだが、それもまた、水と油の両方になじむ胆汁のサポートによって、結局は水に溶ける。そして、水に溶けた栄養素に消化酵素が作用することによって、栄養素は水と反応して分解される。米や芋などに含まれるでんぷんがブドウ糖などに分解されるのは、この作用、加水分解によるものなのだ。
同時に、不要になった栄養素は体液に溶けて細胞外に出て、血液によって腎臓に運ばれて排泄されている。女性の場合、エステやマッサージに関連してよく耳にしたりしているであろうリンパ液。リンパ液は古い細胞や老廃物や脂質を運搬してくれているから、「マッサージするときは、リンパの方に流してくださいね~。そうすると、体の老廃物が流れてキレイになりますよ~」なんて美容部員のお姉さんが言っているのは本当のことなのだ。
体のために良いものをインプットするにも、悪いものをアウトプットするにも、水が必要不可欠な存在であることは間違いない。
そして、そのためには、やはり、「咽を潤せれば何でも良い」という発想で飲料水を選ぶのではなく、日常的に、色がついていない、普通の水を口にすることが大事なのだと思う。
お茶やジュースに含まれる成分には、良いものもたくさんある。トクホ飲料などは魅力的な機能成分を多く含むものもある。ただ、その分、消化吸収するために手間がかかるものもあるし、刺激物となったり、メタボの素になるものが大量に入っていることだってある。どんなものでも食べ過ぎれば毒になるように、どんなものでも飲み過ぎは良くない。1日に口にする飲料水の中で、水以外のものが大半を占める、というのはできるだけ避けるべき習慣といえる。
寝る前の「コップ一杯の水」が
翌日の仕事のパフォーマンスを変える!?
ところで、睡眠前にはよく「コップ一杯の水」を勧められるが、これは、仕事のパフォーマンスを上げることにも関係する。睡眠中は体温を調節するためにコップ一杯分の汗をかいている、と言われるが、眠りにつくと発汗が始まり、明け方にはもっとも少なくなるとのであまり自覚がないだろう。でも、良質な睡眠をとるためには、こうして汗をかくことが大事なのだ。
でも、風呂上りの脱水状態のまま、水分をとらずに寝てしまうと、十分な汗をかくことができないので、睡眠の質を下げることになってしまう。そうなると、夜のうちにリカバリーできず、翌日に疲労感を持ち越してしまうことにもなりかねないのだ。
また、デスクにおいてある飲みかけのペットボトル、もしくは、仕事用鞄に入りっぱなしになっているペットボトル。それは何時間前にあけたものだろうか。男性で、ペットボトルにストローをさして飲んでいる人、というのはあまり見かけないが、15度から30度くらい、つまり、今時期の室温に、一度開封して口をつけたものをおいておくと、2時間ほどで雑菌が増え始めるらしい。しかも、スポーツドリンクよりも、保存料無添加の麦茶の方が細菌の増加が早かった、というショッキングなデータもある。
時間をかけて飲むのはどうしたってお茶類になるだろう。すぐに食中毒に結びつくようなことではないが、安いから、とビッグサイズのボトルを買って、面倒だから、とコップを出さずにぐびぐびと飲むようなことは慎んだ方が良いだろう。
ちなみに、ストローで飲むのは上品ではあるものの、衛生面から言うと、一度口と接触した飲料が再びペットボトルに逆流したり、唾液が入ってしまうこともあるので、口をつけて飲むのと大差ない、と心得ておこう。
余談だが、私たちが飲み残した飲料水は下水処理場などを通して川や海に流れる。もちろん、そのまま流していては水中で暮らす生物たちを苦しめることになるわけだが、たとえばどの程度薄めれば魚たちが住めるようなレベルになるのかを解説した冊子を見てみた。すると、ジュース1杯(180ml)で浴槽10杯分、味噌汁1杯(200ml)で浴槽4.7杯、ラーメンの汁(500ml)で浴槽3.3杯分…だという。すごい量の水の量が必要なのだ。
体のために、と思って飲み残すことは、地球のためにはなってないことは明らかである。出されたものはちゃんといただき、自ら選ぶときは、体のために飲む、ということを大切にしていきたい。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年05月12日 21:10
そもそもお腹など一部分に視点を置くことがナンセンス、、、食事・運動・生活習慣のトータルバランスが美しい心と身体を創っていく。。。
■中野ジェームズ修一が熱血指導! 『ぽっこりお腹解消メカニズム』
運動は“頑張らない”ほうが脂肪が燃える!?
中野ジェームズ修一
フィジカルトレーナー
「腹筋でお腹は凹むの?」「バランスボール、断食、サウナはダイエットに効くの?」……メタボが気になる中年男性の“ぽっこりお腹”を解消すべく、卓球の 福原愛選手など日本を代表するトップアスリートの指導も行うパーソナルトレーナーの第一人者、中野ジェームズ修一氏が熱血指導する!
暖かくなったことをきっかけに、ダイエットを目的にしたウォーキングやランニングを再開された方は多いのではないでしょうか。
調子が良いときは「ラストスパートで倒れるところまで頑張ろう」「今日はいつもよりペースを上げて追い込もう」などと思うことがあるでしょう。それ自体は決して悪いことではありませんが、「脂肪燃焼」のことを考えると、効率的とは言えないのも事実なのです。
人間は安静にしているときでもエネルギーを消費していますが、実は運動をしていない状態だとエネルギー源のおよそ8割を「脂質」から得ています。一方、これがウォーキングになると、もちろん強度にもよるのですが、脂質がエネルギーとして使われる割合は約5割程度に減少します。
ただ、ウォーキングをするより座っているだけのほうが、脂肪が多く燃焼するということではありません。
少々細かい計算をしてみます。一般的な成人男性が1日で消費するカロリーは約1800kcalとされています。そのうちの約8割が脂質でまかなわれていますので、1800×0.8=1440kcalの脂質が1日で使われていることになります。これをさらに24で割って出てくる60kcalが1時間あたりに消費される脂質のおおよその値。体脂肪は1gあたり約7.2kcalですので、60を7.2で割った「8.3(g)」が安静状態でも1時間あたりに燃焼する脂肪量となります。
では、ウォーキングの場合はどうなるのかも確認してみます。体重にもよりますし、当然のことながら個人差がありますが、一般的な数字で計算してみましょう。30代、体重65kg程度の成人男性が、時速5.4km(分速90m)ほどの速度でウォーキングをしたとします。1時間そのスピードでウォーキングをした場合、約339kcalのエネルギーを消費します。前述したようにウォーキング時に脂質が使われる割合は約50%ですので、1時間で約170kcal 分の脂肪が消費されることになります。これを先ほどと同じように7.2(体脂肪は1gあたり約7.2kcal)で割った「23.6(g)」が1時間のウォーキングによって燃焼する脂肪の量です。
1時間で燃焼する脂肪量は安静時が約8.3g、ウォーキング時が約23.6g。ウォーキングをしたほうが安静時よりも脂肪燃焼量が多いことがはっきりと分かりましたね!
脂肪を効率的に燃焼させるカギは「心拍数」
しかしどんどんスピードを上げていけばより多くの脂肪が燃焼するかというと、そういうわけではないのです。脂質をエネルギーとして消費する割合は安静時が約8割、ウォーキング時が約5割でしたが、ランニング、ダッシュになると、約3割、約2割と減っていってしまいます。消費カロリーは上昇しても脂質が使われる割合が低下し、どこかの時点で「速度を上げないほうが脂肪が燃焼するポイント」が現れるわけです。
無駄なく効率的に脂肪を燃焼させるには、脂肪燃焼に適した強度でウォーキングやランニングを行うことが重要です。脂肪燃焼に適した強度とはどのくらいか、そして強度をキープしながら運動するにはどのようにしたら良いのでしょうか。
そのカギとなるのは「心拍数」です。
220から年齢を引いた数である程度推測できるとされている「最大心拍数」から安静時の心拍数を引いて0.6〜0.8を掛け、そこに安静時の心拍数を足した数字が、最も脂肪燃焼効率が高い心拍数とされています。ダッシュなどをして心拍数を上げ過ぎると心肺機能や持久力の向上には良いのですが、脂肪燃焼効率は低下します。逆に心拍数が低過ぎる場合も、脂肪燃焼に適した状態とはいえません。現在は心拍数が計測できるタイプのランニングウォッチが数多く売られていますので、これらで心拍数を計りながらウォーキングやランニングを行うと、効率良く脂肪燃焼を目指すことができるでしょう。
心拍数を計測する機器がない場合は、「ややきつい」「息がはずむ」程度の強度を目安として下さい。「人と話ができるかできないか」くらいが脂肪燃焼効率が高い状態だといえます。肩を使ってぜいぜいと呼吸をするような強度だと心拍数を上げすぎていて、余裕でおしゃべりをしながら運動している状態は心拍数が低過ぎる状態です。
「EPOC」って何?
効率的な脂肪燃焼を目指すうえで心拍数とともに知っておいてほしいことに「EPOC(運動後過剰酸素消費量)」があります。
EPOCとはExcess Postexercise Oxygen Consumptionの略で、運動直後にカロリー消費効率が高くなる状態のことを指します。筋力トレーニングや有酸素運動をしたあとは、運動から生まれた代謝産物の処理、脂質の代謝の高進、筋肉の合成などが行われ、これが運動強度にもよりますが、約1時間半〜2時間ほど続きます。この間は普段よりも脂肪燃焼量が高い状態となります。
逆にこのEPOCのときに座ったり横になったりして休んでしまうと、脂肪燃焼量が下がってしまい、せっかくの脂肪燃焼量が高い状態が有効活用できません。運動を頑張りすぎて家に帰ったらソファやベッドですぐに横になってしまうのは、脂肪燃焼効率を考えると非常にもったいない状態なのです。
筋力アップや心肺持久力の向上が目的ではなく、あくまで脂肪燃焼を第一に考えると、動けなくなるほど追い込む必要はありません。余裕がある状態で運動を止め、EPOCの時間を有効に使ったほうが効率的ですし、追い込みすぎないほうが翌日もやろうという気持ちが続くものです。
“EPOCの有効活用”といっても、それほど難しく考える必要はありません。例えば出勤前にランニングやトレーニングをした場合、通勤電車の中で立っていれば、それだけで十分です。出社の前に30分くらい運動をする。その後シャワーを浴びて家を出て、電車の中で立っている。駅からオフィスまで歩けば、デスクワークを始めるころにはEPOCが終わっています。電車で座れないことがラッキーだと思えれば、気持ちもポジティブになるはずです。
仕事のあとにジムに行く方であれば、帰りの電車で立っていれば良いですし、ジムが家の近くなのであれば、少し遠回りをして歩いて帰るというのも良いでしょう。
休日に運動をする方なら家族が寝ている間にランニングに出掛け、帰って来てEPOCの間に掃除や洗濯などの家事をすれば、脂肪燃焼効率だけでなく奥様からの評価も上がるのではないでしょうか(笑)。
脂肪燃焼を考えた場合、頑張りすぎないで運動を継続することが大切です。運動経験者ほどついつい追い込みがちですが、張り切りすぎずに運動を楽しんでいただければと思います。
(取材/神津文人)
[日経トレンディーネット]
Posted by nob : 2014年05月11日 05:01
また旅立つ君へVol.36/己のなかにすべてがあり、、、すべてのなかに己がある。。。Vol.3/諸行は無常だからこそまたみな至上。。。
■日本一分かりやすい般若心経 「不生不滅」編
関谷 寛明
般若心経の教えに「不生不滅」というものがあります。生まれることも滅することもないという教えなのですが、これは私達の執着を戒めるための教えです。
私達は自分の物だと思ったときに執着が生まれ、それを失えば悲しみや苦しみに苛まれます。私達は自分の物と他人の物を区別して生活しています。自他の区別をすることは社会生活にとっては必要なことです。
小さな子供がスーパーに行けば、自他の区別がつかないために、欲しい物があれば買っていなくとも袋を開けようとします。自分の物、他人の物、社会の物と区別することで、我々の生活は成り立っているのです。
ところが、自他の区別をすることで、自分の物に執着してしまうのです。自分の物は大切にするのに、他人の物はぞんざいに扱うことがあります。欲しい欲しいと熱望しても、いざ自分物になるとあきてしまうこともあります。
自分が持っていてまわりが持っていなければ傲慢になり、まわりが持っていて自分が持っていなければ妬んでしまいます。こういった執着はすべて前回書いた色の見方なのです。人間は自他の区別によって苦しんでいるのです。
仏様は空の見方をしますから、すべてはありがたいいただき物だと考えます。この命も自分のものではなく、仏様から預かっている預かり物なのです。預かっているならば、いずれは返さなければなりません。それが道理なのです。
なるべく穢さないよう大切にして返さなければなりません。立場や役職もそうですし、家族も仕事も日々の生活はすべてご縁によって一時的に預かっているだけなのです。
このように考えるならば、ことさらに執着することなく楽になるのではないかと思います。自分の物だと執着するから、得た(生)とか失った(滅)と一喜一憂するのです。すべては仏様からの預かりのだと思い、いずれは返さなければならないと思うことで、ご縁のあったものを大切にできるのです。
[newsdig]
Posted by nob : 2014年05月05日 17:57
また旅立つ君へVol.35/根拠のない自信に従うことが最も信頼度の高い道標。。。
■根拠のない自信を持てる人、会社はすごい
船井総合研究所
南原繁
ピンチに立った時でも、自信を持てて、威風堂々としている人がいます。また、そのような社風の会社があります。自分はなかなかそうはなれないのでうらやましい、と思います。
そして、多くの会社にお伺いし続けてきた実感として、そうした根拠のない自信を持てる人ほど大きな成果を上げることが多い、というのが実感です。
根拠のない自信というのは、何も虚勢を張るとか、無謀な賭けをするとか、ということではありません。根底に、「成功」でははなく、「成長」を求める意識、楽しむ姿勢があるように思います。
「成功」とは、「失敗する」人がいるから存在できる、相対的なものです。得てして、他人との比較、評価、評判などと絡みます。
一方、「成長」とは、過去の自分、一年前の会社と比べての変化していること、できなかったことができることができるようになったこと、絶対的なものです。
何かの目標に果敢に挑戦して、もし仮に未達成で終わった場合、成功かどうかの物差しでは失敗になりますが、成長という物差しで言えば、絶対になにか変化、成長しています。それを大切に、それを実感、腹落ちさせている人が根拠のない自信を持てるよう思います。
根拠のない自信を持てた会社、自分たちでいた方が元気になると思います。
[newsdig]
Posted by nob : 2014年05月04日 20:54
私も気付けば。。。
■メッチャ見かける!現代女性がやりがちな「体が歪む」NG悪癖3つ
高木沙織
[メッチャ見かける!現代女性がやりがちな「体が歪む」NG悪癖3つ] 頬づえをつく、足を組む、横座りをするなど顔や体の歪みを作る原因がたくさんあるのは、みなさんもご存知のとおり。歪みは冷えや肥満、コリなど様々な不調の原因にもなるので、できることなら避けたいものですよね。
しかし、そうは思っていても、無意識のうちにやりがちなのが下記の悪癖。当てはまるものがある方は、すぐに改めないとおブスになっちゃいますよ!
■1:モデル立ち
片足を前に出して立つ、片足に体重をかけて立つ、足をクロスして立つなどのモデル立ちは、左右どちらかの筋肉に極端に負担がかかることから、骨盤の歪みの原因になります。それだけではなく、骨盤上の背骨まで歪み、腰痛を引き起こすことも……。
電車を待っている時や待ち合わせをしている時、ついモデル立ちになってしまうという方は、両足に同じように重心をかけ、お尻の穴をキュッと締めるようにして立ってみてください。
■2:バッグ片側持ち
バッグを持つ時、決まって同じ方の腕や肩にかける方は多いですよね。実は、バッグをかけた側の肩は、無意識に上がってしまっています。そのため、肩こりの原因になるのです。また、バッグを持っている側に、骨盤が傾く傾向があります。バッグは、交互に持ち変えるようにしましょう。
■3:寝ている時の足クロス
寝ている時に足を組むというのは、すでにねじれてアンバランスになっている体を、無意識に安定させようとしている証拠。足を組むことで楽な姿勢を取れるのですが、これではねじれや歪みを増長させてしまいます。
右足首を左足首に乗せている方は右に、左足首を右足首に乗せている方は左にねじれているので要注意です。寝る時は仰向けになり、足の間に毛布やクッションを挟んで、足を組めないようにするといいですよ。
体の歪みはおブスのもと。普段から、歪みを作らないように意識をして過ごしたいものですね。
[美レンジャー]
Posted by nob : 2014年05月04日 20:47
また旅立つ君へVol.34/眼前にそびえる山に登ってみて、果てしなく広がる海原に漕ぎだしてみてこそ、初めて見えるそこにしかない美しい景色がある。。。Vol.3
■幼少時代は病弱だったGACKTの心を震わせた言葉とは?
GACKTは「小さいころは病院の思い出しかない」と告白。体が弱くて長時間運動することもできなかったが、格闘技を習い、19歳のころから体質改善に取り組み、強靭(きょうじん)な肉体を手に入れたという。
そんな彼が転機を迎えたのは20歳のころ。ある人から「成功するためには物事を知り、覚え、動いてから考えることが必要」だと学ぶ。さらに「知」「覚」「動」「考」と漢字を一文字ずつ書きながら問われたのは、その中で最も大事なファクターとは何かということ。考え込んだGACKTは「答えは目の前に書いてある。とも(=知)、かく(=覚)、うご(=動)、こう(=考)」と教えられ、その言葉に心を震わせたという。
[シネマトゥデイ映画ニュース]
Posted by nob : 2014年05月02日 22:04
そもそも他人と競い合う必要などありはしない。。。。
■あくまで現時点での差
杉本 智則
実力の差を見せつけられたとき、「元が違うから」という言い訳をよく聞きます。生まれつきの家庭の貧富の差、習い事をしてきた差、スタートラインが違うから今の差がある、というのは仕方のないことです。
しかし、これはあくまでも現時点での差。これからひっくり返せばいいじゃないですか。「元が違うから」将来にわたっても勝てない、と思うのは単に自分が努力を放棄する言い訳にすぎないと思います。
「お前の家庭は生まれつき裕福だからそんな余裕があるんだよ。」というなら、もっと努力して裕福になって余裕を生み出せばよい。「あいつの親は元プロ野球選手で子どもの頃から英才教育を受けてきたから、とても勝てない」というなら、その選手以上の努力をしてプロで追いつけばいい。
自分が生まれてきた歴史、自分が今まで生きてきた歴史がある以上、スタートラインが違うのは仕方がなく、現時点で大きな差があっても仕方のないことです。問題は、その差を前にして、「覆してやる」と発奮するか、諦める言い訳にするかで、将来その差が埋まるか埋まらないか大きく分かれてきます。
差を正確に測り、差を埋める活動スケジュールを立て、ささやかでも継続的な努力をすること。人生という長い時間の中であらゆる競争は根比べなのだと思います。
全てに全力を尽くし続けることは困難ですが、これぞと思った道では絶望的な差を見せつけられた場合でも、落ち着いて長期的にその差を埋める努力を続けることが大事だと、やりたいことをやらない言い訳をしている人にははっきり言ってあげたいと思います。
[newsdig]
Posted by nob : 2014年04月30日 16:43
誰もがそれぞれ美しい。。。
■美しさは心の中からつくるもの。欠点に気をとられがちな女性に贈る動画
突然ですが、自分のことを美しいと思いますか? パーソナルケア製品のブランド「ダヴ」が行ったリサーチによると、自分のことを美しいと思っている女性は、全世界でわずか4%。実に96%もの女性が自分を美しくないと思っており、さらに80%の女性が自分の外見に不安を感じているという結果でした。
もし、自分も96%のひとりだと思ったなら――。そんな女性に「ダヴ」の動画「ダヴ:パッチ」を紹介します。
今回の動画では、心理学者であるアン・カーニー・クーク博士が、10名の女性被験者に「ビューティパッチ」という「自分の美しさに気づくきっかけを与えるパッチ」を2週間つける実験をおこないました。そして被験者は毎日、自分の気持ちの変化をビデオで撮影したのです。実験の結果、被験者の全員が自分が美しくなったと感じるようになりました。
パッチをつけたことで、前向きになっていく女性たち
「鏡をあんまり見たくないの」
「自分に自信がなくて、男性と話もできない」
実験前のカウンセリングでは、口々に自信のなさを訴えていた被験者の女性たち。動画からは「ビューティパッチ」をつけることで、徐々に前向きになっていく様子が見てとれます。実験後のカウンセリングでは、誰もがその効果を実感していました。
「本当に人生が変わったようだわ」
「わたしが変わったみたいに、みんなもこのパッチで変わってほしい」
パッチの成分は?
「パッチが商品化されたら、もちろん購入するわ」という女性たちに、博士は秘密を明かします。実はこの「ビューティパッチ」は、「何でもないただのパッチ」。真実を告げられた女性たちは、驚きを隠しきれません。パッチの効果で美しくなったと思っていた被験者のひとりは、美しさの秘密が自分の心の有り様にあったことに気がつき、涙ぐみます。
「何もなくてもこんな気持ちになれるんだ。これが本当のわたし。今までは隠れていたけど」
効果は、本人だけが感じているものではなさそうです。実験前と実験後では、明らかに彼女たちの印象が違います。自信がなかった女性たちは、実験後には髪型や服装を変え、そして、何よりも表情が明るくなっていることがわかります。
「わたしはきれい。強くて、自由で、どんな自分にもなれる」
自分の本当の美しさに気がついた被験者の言葉が、力強く響きます。「美しさは、自分の気持ち次第で変化するもの」。そんなメッセージを受け取りました。
[ダヴ:パッチ]
(文/メーテル徹子)
[cafeglobe]
Posted by nob : 2014年04月29日 18:06
整腸を制する者が健康を制する。。。
■ヨーグルトは食べるタイミングが重要だった!
今話題の「菌活ブーム」の落とし穴
笠井奈津子 [栄養士、食事カウンセラー]
就活、終活、婚活……。今やいろんな「○活」がある中で、今回取り上げたいのは“菌活”である。暑い時期には野菜ジュースや酵素ジュースを飲んでいた健康志向の人たちの中にも、なかなか気温が上がらない秋からの冬のうちに、「冷たいものはもうちょっと…」と菌活にシフトした人がちらほらいる。
菌活とは何かというと、菌、それも、もちろん良い働きをしてくれる菌を積極的に摂ることをいうようだ。それによって善玉菌が増えて腸内環境が整えば、多くの人が悩む便秘が解消されるだけでなく、免疫力も上がるし美肌にもなる。
人の消化管には100兆以上もの菌が存在しているといわれるが、そのすべてが良い働きをしてくれているわけではなく、年をとると悪玉菌が増える傾向にある。だからこそ、良い菌を補って腸内環境を整えることの価値が増すのだ。
そして、便秘の悩みなんてない、という男性も他人事と思わないでほしい。悪玉菌が減るということは、有害物質が減るため、解毒のために酷使される肝臓の負担が減る。日頃お酒の量が多かったり、加工食品や添加物が多いものをよく食べる人も、良い菌を意識して取り入れる必要があるのだ。
菌活しているのになぜ?
なかなか便秘が解消しない理由
菌活をしている、という方々の食事記録を見せていただくと……なるほど、それらしき食材がずらりと並んでいる。たとえば、こんな感じだ。
朝 パン+味噌バター、ヨーグルト
昼 きのこスープ
夜 鶏肉の塩麹グリル、ごはん、味噌汁、サラダ
でも、「便秘解消のために菌活をしているのになかなか解消されない」という。こんなに良いものをとっているのになぜ?と思うかもしれないが、あまり驚きがないのが正直なところだ。というのも、便秘に悩む女性には、ダイエットを意識して食事量が少ない方が多く見られる。
食事記録にあるような、その食事量の少なさこそが、便秘の原因にもなり、代謝の悪い、痩せにくい体を作ってしまうのだが…。せっかく菌活をしているのだから、望む結果を出せるように、その他の原因も考えてみたい。
朝ヨーグルトだけでは効果激減!?
乳酸菌にまつわる誤解
菌といえば、乳酸菌やビフィズス菌、納豆菌、麹菌は馴染みがあると思うが、菌によってその働きはさまざまだ。まずはそれぞれの菌の働きについてみていこう。
菌が含まれる食品といわれて真っ先に思い浮かび、取り入れている人が多いのは、「ヨーグルト」ではないだろうか。菌の種類によって働きが違うと前述したが、ヨーグルトといえば!の乳酸菌は、この時期気になる花粉症対策にも効果があるといわれている。
乳酸菌とは、オリゴ糖などの糖を発酵させて乳酸をつくる微生物の総称。ブルガリアヨーグルトで馴染のあるブルガリア菌、漬物や乳酸飲料などに含まれている植物性の乳酸菌、ラブレ菌など、種類は200以上あるとされている。ビフィズス菌もその乳酸菌の一種であるが、同じ乳酸菌の中でさえ、機能性が異なる。
テレビのCMでも、「14日間チャレンジ!」というフレーズをよく耳にするが、そもそも、乳酸菌を摂ったらすぐに変わるわけではない。1日、2日で意味がない、と思うのではなく、まずは2週間チャレンジをして、それでも改善の兆しすら見えない場合には、その菌との相性が良くないのかもしれない。菌活でヨーグルトを摂っているのになかなか効果が出ないな…と思っている人は、各社、いろんな商品が出ているので、違う種類の菌を試してみよう。
乳酸菌にはタンパク質や脂肪の分解を助けてくれる働きがあるので、同じ乳製品の牛乳よりも消化吸収には良い。「牛乳だとちょっとお腹を壊してしまうんだよね…」という乳糖不耐症の方も、摂りやすいかもしれない。ただ、毎日のこととなると、やはりプレーンタイプのものがベスト。オリゴ糖と組み合わせると相乗効果があるので、甘い味が好きであれば、オリゴ糖甘味料を用いると良いだろう。
そして、ヨーグルトを摂るタイミングにも注意!実は、生きた菌を腸に届けるのは結構難しい。なぜなら、乳酸菌は胃酸に強くないから。体に良いと思って、朝ヨーグルトだけ、空腹のときのごまかしにヨーグルトを、というよりも、胃酸が薄まっている食後のタイミングで摂った方が効率的といえる。
また、発酵食品だから時間が経つほどに良いのではないか…と一瞬思うが、含まれる菌によっては、時間の経過と共に菌の数が減るともいわれる。製造年月日が若いものを、できるだけ新鮮なうちにいただくのがより良いのかもしれない。
食物繊維としても欠かせないきのこ
扱いやすい菌活アイテム
そして、色々試してみてもヨーグルトだけでは便秘が改善されないというなら、食物繊維が不足していないか振り返ってみよう。食物繊維は、便のかさを増やすものとしても、善玉菌のエサとなるものとしても、欠かせない存在。となると、食物繊維が豊富な「きのこ」に注目してみたい。
今が旬ではないものの、年間を通して手に入り、価格も安定しているきのこ。きのこを漢字に変換すると、「菌」になるくらい、きのこそのものが菌である上に、腸内の善玉菌を育てるために必要な食物繊維も併せ持つ。
脂質を気にしたり、塩分を気にしたり、カロリーを気にしたり…といった必要がないのも良い。わざわざきのこスープを作らなくても、炒めものや味噌汁の具としても良いし、ほぐしたきのこをアルミホイルに包んで、トースターで加熱して、ゆず胡椒やみそ、少量であれば焼肉のタレなどで味付けして、おかずの一品にしても良い。加熱時間が短くて扱いやすいのも、菌活のアイテムとしてはなんともうれしい。
また、乳酸菌つながりでいくと、ヨーグルト以外にも、チーズやキムチ、糠漬けにも菌は含まれている。抗アレルギー作用、整腸作用がいわれているが、油ものや肉食が多くて腸内環境が乱れている人は、同じ乳酸菌の中でも、乳脂肪が多い乳製品ではなく、キムチや糠漬けを選んだ方が良いだろう。
いずれにしても、食事でとりこんだ菌は、便となって3日ほどで体外に排泄されてしまうため、日々継続して食べることが大事だ。特に、乳酸菌は体内に長くとどまることができない。気まぐれ的な摂取で終わらないようにしよう。
コンビニでも手に入る発酵食品
朝食に取り入れることから始めよう
また、日本は発酵大国ともいえるくらいに、菌の力を利用して作られる発酵食品が多くある。実はコンビニでも手に入りやすく、菌活は日常に取り入れやすい。ヨーグルトはもちろん、チーズ、納豆、キムチ、味噌……、さらに生鮮食品が充実しているところなら、きのこもお目にかかることができる。
これらの発酵食品は、組み合わせて食べることでより効率が上がる。納豆キムチはそのままでもいただけるし、味付けとしての組み合わせでは、味噌バターなんていうのもありだ。キムチは胃腸が弱い人には積極的におすすめできないが、ダイエット中の朝食にコンビニで買える「納豆」「キムチ」「ごはん」を取り入れることを徹底したクライアントは、体重が落ちた以外にも、便通が整ったり、ガスの臭いが減った、と効果を感じていた。
ただ、便秘解消に目的をおくのであれば、やはり、朝食をきちんと摂ること、できるだけ1日3度の食事のリズムをつくること、が基本となる。その上で、菌活で腸内環境をよくすることに加え、食物繊維の多い食品や水分を充分に摂ること。さらには、ダイエット中だからと極端に脂質を控えることなく、便のすべりをよくする脂質もちゃんと押さえること。……結局はバランスよく食べてください、ということになるのだが、極めようとすればキリがない。
同じコンビニでも何を選ぶのか、手間をかけたくない中で何を選ぶのか、といえば、菌活、という視点は、多忙なビジネスマンには向いているのかもしれない。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年04月29日 17:52
また旅立つ君へVol.33/失望こそが初めの一歩、、、その積み重ねこそが成長への糧。。。
■「理想の仕事」に夢破れたら―次に進むための方法は?
長年にわたって計画と準備を重ね、追加で学位や資格を取得するために学費を払い、夢にまでみた仕事を手に入れた。それなのに、その仕事が好きになれない――。
これは驚くほどよくあるジレンマだ。近頃、求職者の中には「理想の仕事」という考えが浸透している。生活のためだけでなく、刺激があり、精神的な充実感や目的意識を満たしてくれるような仕事につくことを期待する人が増えている。情熱の源としての仕事のイメージが就職アドバイザーや自己啓発本、さらにはテレビドラマの華やかな登場人物によって喧伝(けんでん)されている。しかし、仕事に関するファンタジーは現実に対する求職者の目をくもらせ、自分に最適な職業を見つける判断力を鈍らせる。
クリエイティブな才能があると言われたCaroline Kelso Winegeartさん(25)は学生時代に広告業界を目指し、大学の広告クラブでは代表を務めた。そしてニューヨークにある大手広告代理店のインターンシップに参加した。「自分がなりたいと思っていた華やかな職業につくための足がかりになる予定だった」と言う。
大学卒業後の2010年に初めてついた仕事はノースカロライナ州ダーラムにある広告代理店マッキニーのアシスタント・メディア・プランナーだった。彼女は「理想の仕事だと思った」と話す。そこで働く人たちが好きだったし、全国的にも知られ、流行に敏感でクリエイティブなイメージをもった会社に入ったことに興奮したと言う。
だが、彼女は担当することになった顧客企業2社の大きな予算を管理するのがいかに複雑か、予期していなかった。しかも媒体からは広告スペースを売り込む電話がひっきりなしにかかってきた。予想以上の仕事量と時間的制約のプレッシャーの中で、彼女は「常にストレスを感じ、参っていた」と話す。世間知らずで、「自分の役割より会社の方が重要」だと思っていたという。
打ち砕かれた「理想の仕事」への夢を「勝利」に変えるには失望を乗り越える必要がある。どこで間違えたのかしっかりと見極め、持てるスキルを最大限に生かすことだ。ジョージア州アトランタのリーダーシップ開発コンサルティング会社、パスビルダーズで代表を務めるヘレン・ロリス氏は「完全なユーターンをせずに、ここからどこへ行けるだろう」と自問するのが良い方法だと指摘する。これは現在の仕事をしながらスキルを磨き、次のステップとなるような会社とコンタクトをとることを意味するかもしれない。
Winegeartさんはソーシャルメディアを使うことが好きだったので、この分野のスキルを磨くことを仕事の目標にした。そのおかげで、別の会社でソーシャルメディア部門を構築する仕事につくことができた。さらに、2011年には広告業界を離れ、ボーイフレンドが経営するマーケティング会社で2 年間、オペレーションマネジャーとして働いた。その後、彼女はブランド構築とウェブデザインを手がけるメードビブラント・ドット・コムを設立した。
心理学専門誌「ソーシャル・サイコロジー」に発表された2011年の研究によると、予期せぬ失敗も新しい思考法を得るきっかけにすれば、有益になり得る。そこで立ち止まり、他にどんな方法があっただろうかと深く考える人は、将来の目標達成に関してより創造的になれる傾向があることが研究で分かった。
では「理想の仕事」がうまくいかなかった場合、どれだけ長くそこにとどまるべきだろうか。ハイテク業界などは他の業界よりも離職が早い。就職仲介サイト「TheMuse.com」の創業者で最高経営責任者(CEO)を務めるキャスリン・ミンシュー氏は、スキルがあるなら数週間で見切りをつけてもいいと話す。
しかし、あまり早急に予期せぬ課題から逃げ出さない方が良い。自分が安定していることを示すために、普通は1年から1年半は務めたほうがいい。ロサンゼルス在住でキャリア開発に関する著作「Skills for Success」を執筆したアデール・シェーレ氏は、理想の仕事が煙のように消えてしまった後、精神的に回復する時間が必要になる人もいると指摘する。シェール氏は「仕事Aが満足できるものでなく、しかもそれが自分の理想の仕事だった場合、ただ仕事Bに逃げることはできない。落ち込んだ気持ちをそのまま引きずってしまうかもしれない」と話す。
特定の仕事に惹かれる理由に気付くことが重要だ。アリゾナ州メサ在住で転職に関する指南書「Body of Work」の著者でもあるパメラ・スリム氏によると、よくある失敗は、例えば「文化や経営スタイル、ワークライフバランス」といった要因を検討しないで仕事を選ぶことだという。「1日20時間働くことになることを知らなくても、弁護士になることを夢見ることはできる」と話す。
中には無意識のうちに理想の仕事を夢見る人もいる。スポーツ心理学の養成コースに入ってくる人は、自分の目標が果たせなかった元アスリートの場合もある。応用スポーツ心理学の専門誌「Journal of Applied Sport Psychology」に昨年掲載された研究によると、そうした元アスリートたちは投影された栄光に浸ることを夢見るかもしれないという。その場合、選手たちが抱える問題を聞いたり、能力向上のための戦略を見つける助けをしたりといった仕事がより難しくなる。元アスリートでもある心理学者は選手の否定的な感情や問題から健全な距離を保つことができないためだ。7人の学生を対象に、半年間の日記の分析や徹底的な聞き取り調査を行った研究でそのことが分かった。
シカゴにある弁護士や専門職向けのキャリアコンサルティング会社ローターナティブスで代表を務めるシェリル・ハイズラー氏は、自身の幸福感に影響するであろう仕事のすべての特徴について、良い点と悪い点をリストアップすることを勧める。また、すでにその仕事に就いている人から話を聞くことで、意外なことや危ないことが事前にわかることもある。
ハイズラー氏は壊れた夢を次の面接では資産として生かすといいとアドバイスする。自分が身につけたもの、例えば新しいスキルや他の業界の知識などを強調しなさいと言う。「自分は新しいことを学んだ。以前の自分とは違う」というメッセージを送ることだ。
[THE WALL STREET JOURNAL]
Posted by nob : 2014年04月27日 08:21
また旅立つ君へVol.32/己のなかにすべてがあり、、、すべてのなかに己がある。。。Vol.2/因果関係によって作り出されたすべては無常。。。
■ブッダの言葉「苦しみを消すには、自分自身を変えるしかない」
花園大学教授 佐々木 閑 構成=長山清子
今、「自分の道は自分で開け」というブッダの教えに共感する人が増えているという。苦悩に満ちた現代にこそ、ブッダの言葉は力を持って我々の心に訴えかける。
「因果関係によって作り出されたすべてのものは無常である」(諸行無常)と智慧によって見るとき、人は苦しみを厭い離れる。これが、人が清らかになるための道である。
「因果関係によって
作り出されたすべての
ものは無常である」
(諸行無常)と
智慧によって見るとき、
人は苦しみを
厭い離れる。
これが、人が清らかに
なるための道である。
●ダンマパダ277
今から2500年前に仏教を開いたブッダ(釈迦)が実在の人物であったことは間違いありません。彼の残した言葉を知るには、最も古い経典の一つである『ダンマパダ』(「真理の言葉」という意味)を読むのが一番いいでしょう。現在残っているお経のほとんどは後世の人によって作られたものなので、ブッダの教えを正しく知るには、できるだけ古い経典を見る必要があるからです。今回は主にダンマパダの中から、いくつかブッダの言葉を紹介しましょう。
我々が慣れ親しんでいる日本の仏教は、ダンマパダが書かれた時代よりもずっと後にできたお経をもとにしているため、ブッダの時代の仏教(以下、「釈迦の仏教」と呼ぶ)と比べるとかなり変化しています。たとえば釈迦の仏教では「拝んで救済を願えば、死後、よい世界に生まれる」などということは一言も言っていませんし、神秘的な力で人々を救済するような絶対者の存在も認めていません。釈迦の仏教は、あくまでも自分自身が修行することで苦しみから逃れることができるという、いわば「自己鍛錬システム」。2500年前にできたとは思えないほど合理的で、現代人も受け入れやすい教えなのです。
では、その釈迦の仏教の根本的な教えは何かというと、それは「諸行無常」ということです。
私たちは病気や老い、死から逃れることができません。世の中のありとあらゆるものは放っておいても崩れていきます。だから「諸行無常」なのですが、このことをいつも念頭に置いていれば、大事なものを失っても悲しまずに済む。これが逆に「諸行は常だ」「物事は永続する」と希望を持って暮らしていると、その希望は必ず打ち砕かれて、苦しみが生まれる。だから苦しみから逃れるためには、諸行無常を前提として生活設計をしていけということです。しかしこの諸行無常という価値観を持つには、私たちの考え方を根本から変える必要がある。そのための努力が修行です。「ダンマパダ277」はそのことを表しています。智慧とは知識や教養を指すのではなく、物事を正しく捉える力のことです。「ダンマパダ62」も諸行無常について述べたものです。
愚かな人は、
「私には息子がいる」
「私には財産がある」
などといってそれで
思い悩むが、
自分自身がそもそも
自分のものではない。
ましてやどうして、
息子が自分の
ものであろうか。
財産が自分のもので
あったりしようか。
●ダンマパダ62
私たちは自分以外のものが諸行無常であるということは、なんとなく想像できます。しかし、この自分という存在だけは、少なくとも自分が生きている間は存続していると思っている。しかし、それはおそらく脳の記憶物質か何かがもたらす錯覚で、本当は自分自身さえも一瞬ごとに別のものに変わっているというのが仏教の考え方です(仏教では人間を「いろいろな要素が集まった集合体」と考えます)。自分ですら変わるのに、ましてや自分以外の息子や財産などが永続するはずがない。だから執着するなということです。
では、どうすれば執着を捨てられるのかといえば、やはり修行によってです。毎日たゆまぬ鍛錬を続け、性格や人格が変わるほどの修行をしなければならない。「ダンマパダ19」は、そのことを述べています。
聖典の言葉をいくら
たくさん語っていても、
それを実践しなければ
怠け者である。
それはたとえば
牛飼いが他人の
牛の数を勘定
しているようなものだ。
そういう者は、
修行者とはいえない。
●ダンマパダ19
修行というと私たちは肉体を痛めつけるような行為を想像します。しかし、釈迦の仏教では肉体に苦痛を与えることはなにもしません。ただひたすら精神を集中して考える。それだけです。外からは静かに座っているようにしか見えませんが、内部においては強い精神力によって自己改造のための努力が続けられているのです。
そして修行を積むと、苦や楽についての価値観が世の中の一般的な人とは逆転します。そのことを言い表したのが「スッタニパータ第三-762」です。
ほかの人たちが
「安楽だ」と言うものを、
聖者たちは
「苦しみである」と言う。
ほかの人たちが
「苦しみだ」と
言うものを、聖者たちは
「安楽である」と言う。
法は知り難いもので
あると見よ。
無知なる者たちは、
ここで迷うのである。
●スッタニパータ第三-762
私たちは愛情や成功など世俗的な価値を手に入れようと願い、それが手に入ると喜びます。しかし手に入ったとたん、今度は失うことが心配になるし、いずれは必ず失うことになる。したがって、これらを得ることは実は苦しみのもとなのです。
しかし修行に打ち込んで執着を捨てることのできた聖者は、所有物を失う心配から解放される。そして、仏道修行による自己鍛錬の道を一歩一歩上っていく、その達成感が日々の喜びになります。それは、会社で毎日がんばって昇進していく喜びにも通じるものです。
そういう修行の生活が現代に生きる私たちにも可能かといえば、十分可能です。出家は修行を効率化するための手段ですが、出家しなくても修行はできます。
たとえばアメリカでは、仕事を終えたあと、夜、暗くした部屋でスタンドの明かりだけをつけて瞑想する「ナイトスタンド・ブディスト」と呼ばれる人たちが約300万人もいると推定されています。これは日本のビジネスマンにも応用できるでしょう。たとえば会社でイヤなことがあった日。酒を飲んで忘れてもいいけれど、それでは何も変わらない。それよりも1日の終わりに静かに瞑想して、その日にあったいろいろなことを再解釈する時間を持つ。こんなことがあったけれど、別の見方をすればこんなふうにもとれるな……とその出来事をきれいに濾過していけば、少なくともストレスを翌日に持ち越すことはない。やがてそれが習慣になり、瞑想しなくても自然にそう考えられるようになれば、幸せになれるのは間違いありません。
もし悩みを抱えるビジネスマンに、仏教が何か提言できるとするならば、「今の世の中の価値観とは違う、別の価値観もあると知っておいてください」ということです。たとえば企業の価値観に沿って生活するうちに、壁にぶつかることもあるでしょう。企業のあり方や世の中の仕組みはすぐには変えられませんが、自分の価値観を変えることで、今まで苦しみだと思っていたものが苦しみでなくなる可能性はいくらでもあります。
私はよく、「仏教とは心の病院である」といいます。病院は健康な人を無理やり治療することはしません。でも具合が悪くなったら誰でも受け入れてくれる。病院の目的は患者を増やすことではなく、病気を治すことだからです。仏教もその目的は信者を増やして勢力を拡大することではなく、困っている人を救うこと。だから無理な布教をしないのです。
いざというときのために近所の病院の場所を覚えておくように、苦しみから救うために仏教があるということを、心にとめておいてほしいと思います。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年04月26日 20:34
無理なく続けられることから始めましょう、、、しただけのことは着実に自らに還ってきます。。。
■お茶や緑の葉菜類は老化を防ぐ「抗糖化作用」あり!
「食事の最初」に摂るのがポイント
久保 明
[東海大学医学部 抗加齢ドック教授/慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授]
老化を促進する加工食品とは?
もう読者の方にはおなじみになったかもしれない、糖化によって生じる強力な老化促進物質AGE(終末糖化産物)。
AGEが体内にはびこると、動脈硬化が進んだり、骨がもろくなったり、肌が荒れたり、白内障、非アルコール性脂肪肝、さらにはアルツハイマーのリスクになったりします。
AGEは糖と蛋白質が高い温度の下で結びついてできます。体内では主に食後に血糖値が上昇し、高い状態が続くと発生(糖化)しやすくなりますが、一般的な調理でも生じます。ホットケーキの焦げた部分やウナギのかば焼きの焦げたところでAGEがみられます。
また加工食品の中にも既にAGEを含むものがあります。
ベーコン、ドーナツ、アップルパイ、ポテトチップス、コーラなどがAGEを多く含みます。これらの摂りすぎは要注意です。
復習になりますが、AGEを発生させにくくするためには、食後の血糖値の上昇をなるべく緩やかにすることが肝心です。
そのための方法として、食物繊維→蛋白質→糖質と食べる順序を工夫する「懐石食べ」とGI値(食後の血糖値の上昇スピードを数値化したもの)に注目し、なるべく低GI食品を食べることがよいと紹介しました。
今回はさらに「抗糖化食品」を紹介しましょう。
「抗糖化作用」がある食品は食事の初めのほうに摂る
まずはお茶です。日本茶(緑茶)をはじめ、ウーロン茶、プ―アール茶などには、AGE抑制作用があることが実験で示唆されています。
これらはポリフェノールの一種、茶カテキンの作用と考えられます。ハーブ茶のカモミール・ティーも効果ありです。食後に飲むもいいのですが、食前に飲んでおくと抗糖化は一層期待できます。
緑色をした葉菜類の抗糖化作用もなかなか強力です。
小松菜、ホウレンソウ、キャベツ、白菜などには芋や根菜類に比べ、糖質が少なく食物繊維が多く含まれています。懐石食べとも重なりますが、これらの野菜を味方にして、食事の初めの方に食べる習慣を身につけるのがお勧めです。
また、大豆製品やヨーグルトを食前に摂ると、血糖値の上昇を抑える効果があります。大豆に含まれる水溶性ペプチドには血中の糖を吸収するレセプター(細胞の窓口)の数を増やす働きがありますし、ヨーグルトの方は腸内環境を整えるのです。
そうは言っても、優等生的な食生活を続けるのは難しいものです。
仕事での接待や食事会、会社の仲間との付き合い、男同士の飲み会、女子会、デート、合コンなどの機会があるでしょうし、また時には羽を伸ばしたいこともあるでしょう。
そうした時は高カロリー食や高GI食を避けるのが難しいかもしれません。また、えてしてこういった機会は続くものです。そんな時はどうするか?
「昼食」で調節するのがお勧めです。
夜にこってりした肉料理や飲み会が予想されたら、揚げものランチ、ラーメン、カレーなどの高GI食は避け、和定食や野菜炒め定食などの低カロリー、低GI値の食事を選ぶようにするのです。1日3食のトータル・バランスを昼食でとるという考え方です。
さらに1週間のトータル・バランスも考えましょう。高カロリー、高GI食が続いたら昼食だけでなく夕食も自宅でとる場合は、野菜を多く含むものや低GI食品にするなどして、バランスをとってみましょう。
高カロリー食や高GI食に身体が慣れてしまう前に、元に戻すことが大事なのです。アンチエイジングは長期の戦い、諦めてはいけません。
元気な状態で長生きする
「健康寿命」を延ばす食事法とは?
今回のメディカル・トピックは「食と健康寿命」です。
50代の人5350名(男性70%)を対象とした2013年の研究です。
「揚げもの、甘いもの、加工食品、赤肉、精製炭水化物、高脂肪乳製品」を避けた食事法は、心筋梗塞や狭心症などの心血管障害の予防に効果があり、心身ともに元気に過ごせる、つまり健康寿命を延ばすというものです。
若々しく元気でいるためには、「フライやカツなど揚げものやお菓子、ハムやソーセージなどの加工食品、白米やパンなどの精製炭水化物、バターやチーズなどの高脂肪乳製品」の摂りすぎに注意した方がよい、という結論です。
当たり前のように思えても日々心がけることで「健康寿命」を延ばすことにつながるのですね。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年04月25日 23:41
また旅立つ君へVol.31/己のなかにすべてがあり、、、すべてのなかに己がある。。。
すべての事象と私たち一人一人は繋がり合っているのだから
この世界に起こっているすべての事象は
巡り廻ってみな私たち一人一人の責任なのです
Posted by nob : 2014年04月21日 16:40
また旅立つ君へVol.30/眼前にそびえる山に登ってみて、果てしなく広がる海原に漕ぎだしてみてこそ、初めて見えるそこにしかない美しい景色がある。。。Vol.2
■自分のために生きる勇気~人生の舵をとるために考えたいこと
「かたくなに一本道を歩まなくてもいい」
自分のために生きる道の選び方とは?
――白木夏子×安藤美冬 特別対談【後編】
勇気を持って生きる。この課題を、生き方、働き方にどう活かしてきたのか?「ブレないこと」「ひとつのことを極めること」が正しいとされる世の中は本当に正しいのか? それぞれ若くして会社を飛び出し起業した二人が語る、「蛇行のススメ」。大反響の安藤美冬×白木夏子対談、後編。(構成・田中裕子)
かっこよく意志を貫いてきた…わけではない
安藤 この本を読んでから、私は自分のために生きてきただろうか、と人生を振り返ってみたんです。その中で、「自分で決断できなかったこと」はいつまでも強烈に覚えているなあ、と気づいて。
白木 自分で決断できなかったこと?
安藤 私、大学進学も就職も、親の反対で第一希望を諦めたんです。両方とも、チケットは手の中にあったのに。本当は、上智大学の外国語学部スペイン語学科に行って字幕や翻訳の勉強がしたかったし、映画の宣伝を扱う仕事がしたかった。
白木 あ、そこは英文学科じゃなくてスペイン語学科なんですね。
安藤 好きなスペイン映画があったことと、どうせやるなら「英語」というメインストリームから外れようかなと。今と変わらず天邪鬼だったので(笑)。まあ、今思えば「映画がやりたい」なんてものすごく漠然とした思いだったのですが。
白木 でも、親の反対で道を諦めるということは、それほど執着がなかったとも言えますよね。私も高校生のときファッションの道に進みたかったのですが、それこそファッションデザイナーをしていた母に猛反対されて。「そこまで言うなら」とあっさり断念したんです。
安藤 親に反対されて挫折。まったく同じ経験ですね。
白木 けれど、結果的にそれでよかったと思っています。短大に行ったからこそ、国際協力という人生を変える出会いを得ることができましたし。実は、「自分の思惑と違う」という意味ではもうひとつ岐路があって。
安藤 なんですか?
白木 私、本当はアメリカの大学に行こうと思っていたんです。でも、ちょうどアメリカの大学を見学しているときに、件の同時多発テロが起こって。治安が不安だということで、イギリスの大学へと方向転換しました。
安藤 でも、環境問題や人権意識、エシカル意識はヨーロッパの方がずっと高いですよね。アメリカの大学、特にMBAの評価軸は卒業生の年収で、イギリスの大学は社会起業家の排出数だと聞いたことがあります。
白木 そうなんです。だから、ラッキーですよね。こういう経験もあって、「ここは譲れない」という部分以外は流されてしまっても結果オーライだと思うようになりました。ただ、起業するときはどんな反対に遭っても自分の意志を貫きました。それが私の「ここは譲れない」だったので。
安藤 今回の本のサブタイトル、「流されない心をつくる」というのは「ここは譲れない」という部分の話ですよね。コアの部分があるから、こだわらないところでは流されることができる。
白木 ええ。あらためてこう見てみると、美冬さんも私も、決してかっこよく一本道を進んできたわけではないですよね。
安藤 もう、全然です(笑)。あのとき反対を押し切らず、親の言うことを聞いてよかった! とすら思います。だから、これからも流されてしまえって。軸さえ持っていれば、状況に応じて変化すること、流されることは決して悪いことじゃない。
白木 誰の意見も聞かず、ワンマンで人生を決めていくのもひとつの強さかもしれない。けれど、私はそうなりたくはないんです。「素晴らしい意見だな」と思えばどんどん取り入れます。やじろべえみたいに、ブレても揺れても最後には真ん中に戻っていくイメージです。一見ゆらゆらと弱いようでいて、その実、強い。かたくなな心は折れてしまいますが、柔らかく鍛えた心はすごくしなやかなんです。
安藤 ああ、すごくわかります。
自分だけが経験するような不幸なことはない
白木 前回の留学話でもそうですが、美冬さんはネガティブな要素をポジティブ思考に変換することが得意ですよね。嫌なことがあったとき、どういう捉え方をしていますか? たとえば、ネット上でつらい言葉を投げかけられたときとか。
安藤 意外と、ネット上でいろいろ言われても落ち込まないんですよ。もちろん、最初の頃は見知らぬ人から悪口を言われるなんて初めての経験にびっくりして、かなり落ち込んだこともありましたけどね。……たとえば、夏子さん、初対面の人に突然「この卑怯者!」って言われて落ち込みますか?
白木 ……落ち込まないですね。まったく。不思議です。
安藤 そうですよね。何か言われて傷つくのは、身に覚えがあるからだと思うんです。自分自身が自分のことを心のどこかで「私は卑怯者だ」と感じているから、人の言葉を真に受けてしまう。
白木 自分が自信を持って「そうじゃない」と思えれば、それでいい、と。
安藤 はい。自分が自分を「卑怯者」だなんて微塵も思っていなければ、悪口を「受け取らない」という選択ができます。それに、チャンレンジし続けている仲間や尊敬する方々に会えば、すぐに嫌な気持ちが消えて、心が凪の状態に戻ることもわかってきた。だから、なるべくそういう仲間たちと一緒にいるようにしています。
白木 一緒にいる人をはじめ、自分のいる環境を整えるということはとても大切ですよね。
安藤 夏子さんは落ち込んだとき、どうされていますか?
白木 まず、「先人に学ぶ」ということを意識します。飲み込まれてしまいそうな高い波を目の前にしたら、「みんな経験していることだ」と開き直ってしまうんです。私が悩むことなんて、誰かが経験して、そして解決しているはず、と。歴史の中で自分にだけ降り掛かる問題って、なかなか起こらないですよね。
安藤 たしかに。
白木 たとえば、稲盛和夫さんの『生き方』(サンマーク出版)という本の中に、あるとき、社員が全員辞めてしまったというショッキングな事件が記されています。私だったら、もう、卒倒してしまうと思うのですが(笑)。
安藤 うーん、想像できないですね、そんな状況。
白木 あの歴史に名を残す経営者である稲盛さんですら、こんなにとんでもない波を経験している。私が抱えている問題なんてほんの小波だ、乗り越えられないはずはない、と思って……あとは頑張ります。そう開き直れるという意味でも、ノウハウや解決策があるという意味でも、やっぱり先人の存在ってすごく偉大なんです。
安藤 たいていの問題はだれかが経験して解決しているという考え方、気持ちがラクになりますね。まったくまっさらな道って、実はなかなかないのかもしれません。
ジェネラリストはスペシャリストより劣っているか?
安藤 私、仕事にまつわる「勇気」に関して、どうしても夏子さんとお話ししたいことがあるんです。
白木 なんでしょう?
安藤 前回お話ししたとおり若い方からキャリアの相談をいただくことが多いのですが、その中でも「色々と手を出してみるものの、これだ!と思うものが見つからない」「いろいろなことに興味はあるけれど、一生をかけてやりたいことが見つからない」という悩みが目立つんです。
白木 つまり、何かひとつを極めきれない、ということですね。
安藤 私自身ずっとコンプレックスを抱いてきたので、彼らの切実な悩みが痛いほどよく分かるのですが……若い人がなかなか勇気を出せない原因のひとつに、「スペシャリスト>ジェネラリスト」という風潮があるんじゃないか、と思うんです。今の日本、そういう雰囲気があるじゃないですか。ひとつのことに全力を傾けることが正しい、というような。
白木 ええ、ありますね。突き抜けていることが素晴らしい、と。
安藤 でもね、なにかひとつに、突き抜けるほどエネルギーを注ぐことができない人はたくさんいるんです。もちろん私を含めて。
いろいろなことに興味があって、手を出す。だから、それぞれちょっとだけ知識や経験がある。けれど、プロフェッショナルにはなれない―—。今、そういう人がすごく生きづらいような気がして。
白木 よくわかります。私も、国際協力の中でも雇用促進、児童労働、環境問題……と、たくさんの「やってみたい」がありました。そのせいで進むべき道が決められなくて。専門性がないことがコンプレックスになってしまうんですよね。「器用貧乏だ」と自分を責めてしまう。
安藤 今、「何者であるか」「何ができるか」というプレッシャーに、みんながさらされている時代になっていると思うんです。「やりたいことなんて変わるものだ」という雰囲気なら、もっとラクになるはずなのに。
白木 そのとおりですね。
安藤 やりたいと思ったら反射的に手を出してしまえばいいんです。堀江貴文さんなんてまさにそうですよね。舞台に出演したり、選挙に出馬したり、ロケット開発やグルメサイトの運営……こう並べてみても、すごい幅の広さです。
漫画、詩、小説、ファッションデザイン、新聞づくり、演劇、バックパック旅行――これ、ぜんぶ私が思春期の頃に「やりたい!」と思っていたことです。我ながら、よくもまあころころと夢が変わったなあと思いますが……。ところが不思議なことに、この一見ばらばらの「やりたいこと」の多くが今の仕事とつながっているんですよね。
白木 たとえば、どんなことですか?
安藤 漫画や小説は、出版社に入社して。ファッションデザインは、カバンやステーショナリーなどの商品企画を通じて。新聞づくりは連載や書籍執筆を通じて。そして、今年はとある企業さんから依頼を受けて初の海外取材も敢行する予定ですが、「新聞づくり」と「バックパック旅行」がつながったんです。
最近では、とある劇団の作家さんからお声がけいただいて、ひょっとすると脚本の原案をやらせていただくかもしれないんですよ。
白木 それはすごいですね! でも、キャリア、ひいては人生ってそういうものですよね。たとえ一貫性ない選択のように見えても、やりたいことはやってみて、一歩を踏み出し続ける。そのプロセスを重ね続けていけば、必然的に道が拓けていく。私も今、まさにそういう人生を歩んでいます。
安藤 そうなんです。忘れたころにつながるんですよね。
白木 もちろん、「これで一生やっていこう」と思えることに出会えることにも、とても大きな価値があります。自分の本当にやりたいことを見つけることは、それだけで素晴らしいこと。ただ、「これだ」と決めたらその道に邁進すればいいし、見つからないときはいろいろやってみればいい。どちらかが正解ではない、ということですね。ただ、人生すべてが、今の仕事につながっているということはどちらにしろ同じことですね。
プロフィールは一生更新しつづけるもの
安藤 人生すべてが今につながる——ジョブズの言うところの「コネクティング・ドット」。プロセスの点をつないで線を描くイメージですね。
私、ドットをつなぐことを可視化する意味でも、プロフィールがとても大切だと思っているんです。
白木 プロフィールというと……たとえばTwitterに記載するような?
安藤 そうです。私、プロフィールは、一生かけて更新していくものだと思っていて。
白木 プロフィールを更新?どういうことですか?
安藤 自分の紹介であり、看板というべき存在だから、「プロフィールは一生未完成なものだ」と思うんです。某テーマパークと同じです(笑)。
白木 Never be completed.『永遠に未完成』ですね。
安藤 つまり、興味が変わったり、小さな成功体験を積んだり、時代が変化するごとに更新していくもの。大きい功績や賞じゃなくてもいいんです。たとえば、小さな成功体験を積んだら「あ、プロフィールが変わったな」。新しい興味が生まれたら、「あ、この分野がプロフィールに加わったな」、と。
白木 いいですね、「プロフィール更新論」。私もこれからどんどん更新していきたいな。今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました。
安藤 こちらこそ。大好きな白木さんとまたこうして対談をご一緒できて、私自身も大きな勇気をいただきました。本日は、ありがとうございました!
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年04月15日 08:15
また旅立つ君へVol.29/変われるのは自分だけ、、、自分が変われば世界も変わる。。。
■「嫌われる勇気」を持てば、幸せになれる〜対人関係に悩まない生き方〜
自己啓発の源流「アドラー」研究者の岸見一郎氏に聞く
山崎 良兵
日経ビジネス記者
職場や学校で、誰もが直面する人間関係の悩み。「周囲の人に嫌われたくない」と考えて、自分の意見を押し殺して生きる人は少なくない。他人と自分を比較して劣等感にさいなまれて、自己嫌悪に陥る。自分の性格上の問題を、過去のトラウマに原因があるとして、不幸だと嘆く。
そんな多くの人にとって気になる本が注目を集めている。哲学者の岸見一郎氏が、古賀史健氏と著した『嫌われる勇気──自己啓発の源流「アドラーの教え」』だ。20万部を超えるベストセラーになっている。「人は変われる」「トラウマは存在しない」「人生は他者との競争ではない」「人の期待を満たすために生きてはいけない」「叱ってはいけない、ほめてもいけない」といったメッセージは刺激的だ。詳しい話を岸見氏に聞いた。
(聞き手は山崎 良兵)
なぜ本のタイトルを「嫌われる勇気」にしたのでしょうか。
岸見:私はカウンセラーとして、様々な人の悩みを聞く機会が多いのですが、嫌われることを恐れる人が多いように思います。
職場では、上司の顔色をうかがったり、上司によく思われたいと考えたりして、気持ちを曲げて発言する人がいます。同僚などとの横のつながりでも、自分がどう思われるのかをいつも気にして、嫌われないようにする。なるべく目立たないようにしようとする人も少なくありません。
普及が進む「フェイスブック」などのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)でも、メッセージを書き込む際に、「いいね!」を押してほしいと思って、“受ける”メッセージを書いてしまう。押してもらえないと残念なので、迎合して、自分の真意でもないことを書く。インターネットやスマートフォンが普及して周囲とつながる機会が増える中、嫌われることを恐れる人が増えているように思います。
だからこそ、嫌われる勇気というタイトルが一番響くのではないかと考えました。「哲人と青年の新しい心理学を巡る対話」といったタイトルも候補でしたが、それでは手に取ってみようとなかなか思ってもらえなさそうです。編集者とも相談して、なるべく多くの人が読んでみたいと思うようなタイトルを選びました。
嫌われる勇気があると、人生において、どのようなメリットがあるのでしょうか。周囲と軋轢が生じることは避けられないような気がします。
岸見:もちろん自分の主張を伝えることには責任があります。主張した時には、必ず反発する人がいて、摩擦が生じるのは当然です。それを理解する必要がある。
例えば、ある若い女性が、好きな彼がいて「この人と結婚したい」と親に言ったとしましょう。例えば、この男性がフリーターで安定した収入がない場合、多くの親は反対することでしょう。この女性は、親の気持ちを傷つけたくない、悲しませたくないと、気持ちを抑えてしまって、結婚をあきらめるかもしれません。説得するには、「どうしても結婚したい」と自分の意見を言って、親が多少傷つくとしても、摩擦覚悟で議論して、同意を取り付けるしかありません。親が「あんな人と結婚するなら悔しくて死んでしまう」と言われても、ひるまないで、「残念ですが、短いお付き合いでした」と言い返せば、結婚できるかもしれない。
「摩擦を怖がってひるんで逃げる人が多い」
それが怖くて、自分の意思を曲げて、結婚をあきらめた場合、どうなるのか。誰のための人生を生きているのか。自分の人生を生きているのかということになる。それでは意味がありません。
嫌われる勇気を持っていないと、何のために生きているのか、分からなくなる。もめても、粘り強く説得して、最終的に折れることがない。そんな生き方を選んだ方が幸せを感じられるはずです。
摩擦を怖がって、ひるんで、逃げる。世代を問わず、どんな層でも、そういう人が多い。人の気持ちに目を向けないくらいにならないと、決断できません。私はカウンセリングする中で、多くの人が「決定できない」と感じています。人を傷つけたくないと思っているからです。そういう場合、私は、一時的にでも、人の気持ちをあまり考えないような援助をします。多少の事ではびくともしない。人の気持ちよりも、自分がどうしたいのかをまず考えることで、人生が変わることが多いのです。
日本の社会は和を重んじます。嫌われる勇気がある人がたくさんいて、自分の意見をどんどん言うようになると、職場や学校の和が乱れて、大変なことになったりしませんか。
岸見:太平洋戦争の頃を思い出してください。「これはおかしい」と思っても、戦時中は異を唱えられませんでした。その結果、戦争を止められずに、多くの人が命を失い、悲惨な結末を迎えました。
だから「おかしいことはおかしい」と言える人が増えた方がいい。みんながやさしくて人を傷つけない方向に行くと社会自体が大変なことになります。気が付いたら指摘するべきです。それはおかしいんじゃないかと言える社会の方がいい。
相手が年長者でも上司でも親でも、自分自身の考えを言えるように多くの人になってほしい。抵抗があってもそれは仕方がない。自分の主張に伴う責任です。みんなが主張できない世の中は危険です。
相手に合わせず、自分の意見をはっきり言うと周囲からうとんじられたり、いじめられたりするかもしれません。とりわけ逃げ場が少ない学校のような閉鎖空間では苦しい思いをしそうです。
岸見:はっきり意見を言う子供が必ずしもいじめられるわけではありません。「何でこんなことをするんだ」と抵抗できる子供はいじめられにくい。むしろなすがままになってしまう子供はいじめのターゲットになりやすい。さらに意見がない子供は、いじめる側に回らなくても、摩擦を恐れて、いじめがあっても見て見ぬふりをして、いじめる側に同調するかもしれない。そう考えると、意見を言える方がきっといい。
「叱ってはいけないし、ほめてもいけない」
岸見さんとアルフレッド・アドラーの出会いはどういうものだったのでしょうか。アドラーは、ジークムント・フロイトやカール・グスタフ・ユングと並ぶ心理学者として世界的に有名ですが、日本ではそこまで知られていません。なぜ関心を持つようになってのですか。
岸見:来日したアドラー研究者の講演会に参加したのがきっかけです。「今日この講演を聞いて、幸せになりたいと思う人はすぐに幸せになれる。自分の決心でなんとかなる。自分がどういう風に生きるのか。それを考えれば幸福になれる」といった趣旨のことを話していました。
最初はうさんくさいなあと思い、反発も覚えたのですが、よく考えるとそうかなと思える部分が多かった。さらに子供の教育を通じて、アドラーの考え方を実践する場を得たこともあります。
当時、私はギリシャ哲学が専門で、大学院の博士課程で学び、研究職を目指していました。でも大学院を卒業しても就職口はなく、非常勤の講師などをしていました。
ちょうどその頃、子育てにかかわる機会がありました。妻は小学校の教師をしており、私の方が時間を自由に使える環境にあった。そこで幼い2人の子供たちの保育園への送り迎えを、私が担当することになりました。父親が育児に参加するのは一般的ではなかった時代です。周囲のお母さんからは「なぜお父さんが送り迎えをしているのか」といった好奇の目で見られましたが、子供とかかわる以上はきちんと子育てをしたいと思いました。今でいう「イクメン」ですね。
子育ては大変で、子供はなかなか言うことを聞かないものです。そんな中で、アドラーの思想に触れた。その考え方は衝撃的でした。「大人と子供は対等だ」と言う。大人の方が知識も経験もあり、もちろん同じではありません。でも、対等な存在として認めなければならない。「叱っていけないし、ほめてもいけない」と言っている。
私にも子供が2人いますが、「ほめて育てた方がいい」という意見をよく聞きます。一方で、叱るべき時にきちんと叱らないと、子供はわがままになってしまいます。
岸見:私も最初は子供をほめていましたが、アドラーの考え方は全く違う。衝撃的ではまってしまいましたね。私と子供たちの関係は非常にいいのですが、「ほめて、叱る」という育て方ではここまで関係は良くならなかったでしょう。
私は声を荒げるようなタイプではないのですが、子供にそういう態度だけで関わっていると好き勝手になったでしょう。叱るだけなら事態は悪くなって、もっと反発されたと思います。早い時期に子供との関係を対等にしたことで、非常に良くなりました。
例えば、子供が泣いても大きな問題になりません。子供が泣くのは親の注目を得たいからです。そういうことに対して子供に注目を与え続けると、泣き続ける。かといって叱ると事態を悪くすることになる。一喝すると確かに言うことを聞くかもしれませんが、「怖いから」というだけで、副作用があまりにも大きく、関係が決定的に悪くなる。
1歳の子供でも自分が置かれている状況の意味は意外に分かるものです。私の子供は、初めて保育園に行った日が、朝7時半から夜7時までの長時間保育でした。保育士さんは心配しましたが、私はこう言いました。「娘は私が帰ったらきっと泣くと思いますが、ずっとは泣きません。必ず30秒で泣き止みます」。担当した保育士さんは、時計で測ってみたそうですが、30秒ではなく15秒で泣き止んだそうです。
これは偶然ではありません。泣いても保育士さんは時計を見ていて注目してくれない。娘がそのことを学ぶのにかかった時間が15秒だったのです。そうしたら保育士さんが抱っこしてくれた。普段からの親子の関係作りが良ければ、何も心配ありません。
「自分が大嫌いでも、置き換えることはできない」
でも、電車の中などで小さな子供が泣きやまない場合はどうしたらいいのでしょうか。周囲の人に迷惑がかかりますし、冷たい視線で見られて、さすがに叱らないといけないような気がします。
岸見:電車の中で子供が騒ぎ出したらできることは1つです。叱るのではなく、次の駅で降りる。駅のホームなら泣くことが許されます。もちろん日ごろから話し合っていい関係を築かないといけません。電車に乗るときは静かにしないといけないと、きちんと伝えておく。そのうえで騒いだ場合に、静かにしないといけないと、改めて伝える。忍耐力が求められます。
ほめずに叱らないならば、どのような言葉をかけたらいいのでしょうか。
岸見:大人でも子供でも嫌な感じがしない言葉は「ありがとう」です。相手の貢献に注目する言葉で、役に立ったという気持ちになります。そんな大人同士の言葉をかけたらいい。そういう風に思えることが、自己受容につながり、自分のことを好きになることにつながる。
むやみに怒る上司はいやだというのと同じで、叱ることは人と人との関係を近づけはしない。叱ることで関係を悪くしておきながら、援助しようとするのは難しい。人は自分が嫌だと思う人の言うことは聞かないものです。この人はちゃんと自分のことを見てくれていると思えばこそ、話を聞いてくれるものです。
上から目線で叱るのではなく、あくまで対等な立場に立ち、相手が子供でも、貢献があれば、認めて感謝する。私も子供と接する際に実践すべきなのかもしれません。
岸見:カウンセリングに来る人は自分が大嫌いな場合が多い。でも自分はほかに置き換えられない存在です。自分という道具はずっと一生使い続けないといけない。その私が嫌いなら、人は幸せになれない。だから自分をなんとかして好きになってほしい。自分が役立たずでなくて、誰かの役に立てている。そう思える。
親は子供にありがとうと声をかける。そう言われたら、子供は自分が役に立てると思えて、自分のことが好きになる。それでも、次回も同じ適切な行動をしてほしいと期待しないでほしい。下心で言うと逆効果です。貢献に注目する。もちろん、その親以外の人は「ありがとう」と言ってくれないかもしれません。でもそう言われることを期待して、適切な行動をする子供も困る。誰かが見ていたら、ほめてもらえるのでゴミを拾うが、誰も見ていないと拾わないといった考え方です。ほめられたいと思う人は、承認欲求が強く、承認されないと気が済まない。誰かが見ていなくても、自分が共同体に貢献したいという満足感を持てれば、そうはならない。
「人生は他者との競争ではない」
「人生は他者との競争ではない」とも主張されています。しかしビジネス社会では競争があります。競争心を持たないと人は成長できませんし、組織の活力も失われるような気がします。
岸見:競争は当たり前とされていますが、アドラー哲学では、それはノーマルな状態ではありません。アドラーは競争ではなく、協力を重視します。「競争に勝ち残ればいい」という考え方では、負ける人がたくさん出てくる。むしろ、そういう人の方が多いかもしれない。競争に負けた人は、心のバランスを失って、精神的な病気になる人も多い。しかし協力を学んでいる人は、必要ならば競争できますが、負けても精神のバランスを失うことはありません。競争に負けたと落ち込むとゼロサム競争の世界になり、組織や共同体のことを考えるとプラスになりません。
人に承認されなくても、貢献感を持つことが大事です。例えば、家事の1つに洗濯があります。妻がする場合が多いのですが、夫や子供が手伝わず、なぜ自分だけがやらなければならないのかと腹が立つ人がいるかもしれません。でも自分だけが洗濯を上手にできて、家族の役に立っていると考えるようにしたらどうでしょうか。こうした貢献感があれば、ほかの人が承認してくれなくても、満足感が得られます。自分が幸せにならないと、ほかの人も幸せになれません。
カウンセリングに来る方は、この世の終わりのような不幸そうな顔をしている場合が多い。子供が学校に行かなくなったという、引きこもりに悩むお母さんが相談に来た場合、私は子供の味方にならないといけないと話します。お母さんが不幸でもそのことで子供が学校に行くわけではありません。
不幸そうな態度をしている親に非があります。近所の人が同情してくれることを期待しているからです。子供は学校に行っていないので不幸だという顔をして、世間の同情を得たい。「私はちゃんと育てたのに、あの子は学校に行かなくて困っている」といった顔をする。
しかし世間に対して背を向けた方がいい。背を向けても親は子供の味方になるべきだ。子供が引きこもりでも幸せになっていいんだと思えるようになると、お母さんは元気に若々しく、美しくなります。近所の人は「あの家は子供が学校に行っていないのに、お母さんはどうなのかしら」といった風に後ろ指をさすかもしれませんが、そんなことは気にする必要はない。嫌われる勇気を持って、子供の味方をするなら、子供と仲良くなれます。
「どっちにもいい顔をしたい」といった人の出方や顔色をうかがって態度を決定する態度ではダメです。
「カーネギーやコヴィ—の思想もアドラーに通ずる」
著名な経営者や自己啓発的な本の著者もアドラーの考え方を実践しているケースが多いと聞きました。
岸見:『人を動かす』で知られるデール・カーネギーは、アドラーを引用しています。『7つの習慣』を書いたスティーブン・コヴィーも思想的にはアドラーと近い。ただあえて引用していない人の方が多いように思います。アドラーの考え方は、聞いてしまったら当たり前だからです。理解が難しいこともありません。叱らない、ほめない、課題は自分に関するものと、他者に関するものに分けて考える。
それを聞いたらほかの人にはあまり言いたくない。自分の手柄にしようと思って言わなかった人が多かったのでしょう。アドラーの思想は「共同採石場」のようなもので、みんなが自由に落ちている石を拾って持ち去った。米国にはずいぶん自己啓発の本はありますが、理論的な裏付けがない場合が多い。理屈を知らないで実践しているケースも多いように思います。
経営者の中には厳しく叱らないと社員は育たないと言う人もいます。
岸見:私は、頭ごなしに怒鳴りつけるのは有能な経営者ではないと思います。ある程度成功するかもしれないが、限界がある。若い人が、のびのび失敗を恐れず、新しい仕事に挑戦できる状況があるのかないのかは全然違う。失敗したら叱られると、自由にはふるまえません。叱って育てられた人は、盆栽のようにスケールが小さくなりがちです。
教育では大きく育てることが大事です。社会とうまくやっていけないと思われているような人が、ちょっと指導すれば大きな花を咲かせる。短所や欠点があって、ゴツゴツとしたトゲやでっぱりがあるのが人間です。でっぱりをそいで何かを強制するような教育はよくない。
実際には「これは困ったなあ」という人が最終的には伸びるケースが多い。上司の顔色を見て嫌われることを恐れ、上司が気に入ることしかしない社員は、自発性も創造性もなく、伸びない。本当に有能な経営者は、そういうことを分かっていて、社員が伸びる環境を整備しているはずです。
「勇気を持てば、人は確実に変われる」
「人は変われる」と岸見さんは著書で書いていますが、人間は40歳にもなるとなかなか変われないような気もします。
岸見:嫌われることを恐れる生き方は、不自由で不便なので、できたら変わりたい。でも「変われない」と思った方が、都合がいい。変わったら、次の瞬間に何が起きるのか分からないと思ってしまうからです。
しかし考え方次第で人間は確実に変われます。例えば、好意を持っている人が歩いてきて、ほんの数秒後にすれ違う。自分の気持ちを告白したいと思っている人だけど、相手がふいに目をそらす。そういう事態が起きたときに、自分が嫌われていて避けられたと思う人もいることでしょう。
でも全く違う考え方をしてもいい。風でコンタクトレンズにゴミが入ったのかもしれません。「嫌われた」と思うのは変わりたくない人です。もちろん若い人の方が柔軟性はあるので、変わろうという勇気を持って、決心したら短期間で変われるように思います。
家族であっても他人を変えるのは難しい。だから自分が変わるしかない。他者を操作できるというのは誤解です。子供でも自由に操ることはできません。子供は自分の期待を満たすために存在するわけではありません。
馬を水辺に連れていくことはできても、水を飲ませることはできません。変われるかどうかは本人の問題です。カウンセリングに来るだけで大きな前進ですが、多くの人は変わらないでいようと決心している。口で言っても本当は変わりたくない。
確かに嫌われる勇気を持つと、自分は幸せになれるかもしれませんが、周囲との関係はどのように変化するのでしょうか。
岸見:あなたのことを嫌う人は増えるかもしれません。でもそれは自分の課題ではなく、相手の課題です。「課題の分離」を分かっていない人が多い。他人が自分を嫌うかどうかは、私には決められません。自分が好意的に接しようとしても、相手は嫌うかもしれない。でも人に嫌われるかどうかを悩む必要はありません。通常、自分のことをあらゆる人が嫌うことはあり得ません。自分を支持してくれる人は必ずいるので、そういう人とかかわればいい。敵視する人はきっといますが、そんな人たちのために自分の人生をふいにする必要はありません。つまらないことに、日々悩む必要はないのです。
「神や仏を持ち出さない宗教」
岸見先生のお話を聞いているとアドラー心理学は宗教に似ているような印象を受けました。
岸見:神や仏を持ち出さない宗教と言えるかもしれません。神や仏を出すと受け付けない人がいます。でも神を信仰していると言っている人が、その教えを実践できているとは必ずしも言えません。だからアドラー心理学は神のない宗教と理解しています。
最近の心理学では、あらゆることを脳の機能に還元するような傾向があります。例えば、人が誰かを好きなのは脳がそうさせている。人間には自由意志があって、何かを自分で決められることを否定している。しかし脳の仕組みで説明できることには限界があります。
トラウマの話もそうです。心理学では様々なことを過去のトラウマのせいにするケースがあります。でもアドラー心理学を研究する立場からは「トラウマは存在しない」と考えます。人間が過去の経験や体験によって決まるなら、治療も教育も育児も関係なくなる。何でも過去の体験で決まっているというなら、治療のしようがない。
私はカウンセリングで過去を聞きますが、あくまで理解のためで根掘り葉掘り聞くことはありません。過去を聞いても意味がない。それで、あなたはどうしたいのか。それが重要です。何か希望を持って帰ってほしいと思って話をする。大事なのは、過去ばかりを振り返ってあれこれ考えることではありません。今、この瞬間をあなたが、いかに生きるのかです。変われるのは自分だけであり、自分が変われば、世界も変わります。
岸見一郎(きしみ・いちろう)
哲学者。1956年京都生まれ、京都在住。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。専門の哲学(西洋古代哲学、特にプラトン哲学)と並行して、1989 年からアドラー心理学を研究。精力的にアドラー心理学や古代哲学の執筆・講演活動、そして精神科医院などでカウンセリングを行う。日本アドラー心理学会認定カウンセラー・顧問。訳書にアルフレッド・アドラーの『個人心理学講義』『人はなぜ神経症になるのか』、著書に『アドラー心理学入門』など多数。 2013年12月、『嫌われる勇気──自己啓発の源流「アドラー」の教え』を古賀史健氏との共著で上梓。
[日経ビジネス]
Posted by nob : 2014年04月15日 07:41
また旅立つ君へVol.28/眼前にそびえる山に登ってみて、果てしなく広がる海原に漕ぎだしてみてこそ、初めて見えるそこにしかない美しい景色がある。。。
■自分のために生きる勇気~人生の舵をとるために考えたいこと
「足りないのはお金でも経験でもなく、勇気」
―なぜ人は一歩を踏み出すことを怖れるのか?
~白木夏子×安藤美冬 特別対談【前編】
「勇気」というキーワードをもとに彼女たちが語る、人生の選択、キャリアの分岐などの悩みを抱える人たちへのメッセージ。「足りないのはお金でも経験でもなく勇気」という言葉の意味とは?なぜ、一歩を踏み出す勇気とは?安藤美冬×白木夏子『自分のために生きる勇気』刊行記念対談前編!
なぜ一歩を踏み出す勇気を持てたのか?
安藤美冬さん(以下敬称略) 夏子さんとは先日(編集部注:3/20~3/23)沖縄で開催されたG1サミットでお会いしたばかりですね。
白木夏子さん(以下敬称略) そうですね。今日は美冬さんと対談できること、とても楽しみにしていました。
安藤 私、実はずっと夏子さんのことを追いかけていたんです。まだエシカルという言葉も日本に浸透していない、HASUNAを立ち上げられたばかりのころに雑誌に載っている夏子さんを見かけて。
白木 ええっ。そうなんですね。
安藤 「人にも地球にも優しい」というコンセプトで、しかも心から美しいと思えるデザインのジュエリーをつくられていて、「この人すごい! 気になる!」と。それからずっと夏子さんがメディアに出られるたびに注目していましたし、ジュエリーの新作もチェックしていました。
白木 うわあ、恥ずかしい。でも嬉しいです。
安藤 だから、今回『自分のために生きる勇気』という本を書かれたと聞いて、すごく楽しみだったんです。実際、読んでみると夏子さんらしい印象的な言葉が並んでいて、今の私の心にまっすぐに響く本でした。
白木 ありがとうございます。
安藤 どうして夏子さんがHASUNAを立ち上げようと決断したのか、どうやって鉱山と取引をしているのか、なぜいつも凛としているのか……今まで感じていた疑問がすっと腹に落ちたんです。
まず、タイトルに引きこまれたのですが、なぜこのタイトルにしたのですか?
白木 この本を書くにあたって自分のやってきたことを振り返って、今、何をいちばん伝えたいか? といろいろ考えたんです。伝えたいことはたくさんあったのですが、軸になっていたのは一歩を踏み出す『勇気』だと思って。
安藤 「勇気」。これって今の時代のキーワードですよね。
足りないのはお金でも経験でもなく、勇気
白木 自分の人生の舵をとるためには、選択肢が目の前に現れたとき、ひとつひとつ自分で決めていかないといけない。決断ってすごく勇気がいることですが、自分で考えて決断して前に進んだときに見えてくる景色は格別。そういうことを伝えかったんです。
安藤 自分の道を阻んでいるのは、結局自分なんですよね。自分の勇気が足りないだけ。たとえば私、毎日のように人生相談のメールをいただくんですよ。メディアで私を知ってくださった方々や本を読んでくださった方々から。この相談の中で比較的多い質問、何だと思いますか?
白木 美冬さんに聞きたいことと言えば……やはりキャリアのことでしょうか?
安藤 そうなんです。ざっくり言うと、独立にせよ転職にせよ「会社を辞めようか悩んでいます。どうすればいいと思いますか?」という質問。でも、これ、私に聞いている時点でその人の答えは決まってるんです。だって、こんな時代に30歳で集英社を辞めて独立した私が、「とりあえず、会社を辞めるなんてリスキーな選択は控えましょう」なんて言うはずがないですよね(笑)。もちろん、よほど無謀な状況であれば別ですが。
白木 たしかに(笑)。みなさん、背中を押してほしいんですね。
安藤 そうなんです。背中を押してほしいくらい心が決まっているのに、行動に移せない。じゃあ、この人たちに足りないものは何なんだろう? そう考えたとき、結局は勇気の問題なんだと気づいたんです。
白木 なるほど。
安藤 ということは、「どうしたら自分は行動する勇気が持てるのか」ということに絞って考えればいいはずですよね。この点についてどう思われますか?
白木 そうですね。ひとつ大きな要素として、「失敗してもやり直しがきく」という安心感。これは勇気を持つ助けになると思います。HASUNAに人生を賭けようと思っていた私ですら、いざ事業を始めるときは「失敗したらもう終わりだ、これはラストチャンスだ」とは考えないようにしていました。どちらかというと、「万一うまくいかなくても、なんとかなるだろう」と(笑)。
安藤 あはは、楽天的ですね(笑)。もし失敗したらどうしよう、とは考えなかったんですか?
白木 うーん、そうですね。人ってだいたい、やりたいことがいくつかありますよね。濃淡はあれど。
安藤 たしかに。
白木 だから、失敗したらその濃淡の濃いところで別のことをしよう、と思っていて。ジュエリー職人になる、再就職先を探す、世界を旅してビジネスを立ち上げる、結婚する……具体的にいろいろ考えていました。あえて、他の道があるということは意識していた気がします。「失敗は絶望じゃない」と言い聞かせて。
安藤 なるほど。たしかに、「失敗は絶望じゃない」と思えば、一歩を踏み出すハードルはぐっと低くなるのかもしれませんね。
人がいちばん怖いのは、社会的に「失敗者」と思われること
安藤 あ、そういえば、私も独立するとき、失敗したときの「他の道」は考えましたね。
白木 そうなんですね。それはどんな道ですか?
安藤 資格取得や再就職などいくつか考えていたのですが、そのうちのひとつに、コンビニエンスストアで働くことがありました。
白木 コンビニ! 意外でした。それはまたどうしてですか?
安藤 私、とにかく、コンビニが大好きなんです! 高校生のときには学校に内緒でアルバイトをしていましたし、今も毎日、必ず通っています。コンビニ好きが高じて雑誌で連載を持つことになったくらい。コンビニって、ラインナップやレイアウトで大きな差別化を図ることが難しいですよね。だからこそ、棚の見せ方や商品につけるPOP、企業や雑誌とのコラボなど、店頭でやってみたいことがいろいろあって。
白木 あぁ、なるほど。たしかにすごく楽しそうですね。
安藤 だから、独立が失敗したらアルバイトで雇ってもらって、そこで頭角を現して店長になって……なんて妄想していました(笑)。コンビニだけでなく、ほかにもやってみたいことはたくさんある。だから、失敗したとしても「人生終わった」と絶望はしないと思います。人生はワン&オンリーじゃないはずですから。
白木 美冬さんに相談される方々だって、「失敗しても、即人生が終わるわけではない」と頭ではわかっているのではないでしょうか。仕事は、世の中には本当にたくさんありますから。自分が何にこだわるか、というだけで。
安藤 つまり、勇気が出ないのは、金銭的な問題がメインではないということですよね。結局、みんな何よりも「社会的に失敗者と見なされること」が怖いんじゃないでしょうか。
白木 そうですね。「あの人は起業したけど失敗して無職だ」「この人は独立したけど仕事がないらしい」と思われることは、怖いし恥ずかしい。けれど、それは他人の目を気にせず自分で決断する勇気、つまり「自分のために生きる」勇気を持つことで解決できる問題です。
安藤 本当、そのとおりだと思います。私、ちょっと前から勇気について結構考えているんですが、その中で「勇気には2つのフェーズがある」と気づいたんです。
白木 2つのフェーズ?
安藤 1つめは、歯を食いしばって体を震わせながら、恐怖や羞恥心と戦うフェーズ。2つめは、思い切って行動に移すフェーズ。つまり、ガタガタ震えながら恐怖や羞恥心と戦うことは、「勇気へのプロセス」なんです。
白木 恐怖や羞恥心と戦うことをやめてしまうと、勇気を得るフェーズまで到達できない、ということですね。結局、全部、自分の問題なんですよね。「できる」「できない」と囁く天使と悪魔。そのどちらを選択するかは、自分しか決められないから。
迷いや羞恥心は、確信と自信に変えていける
安藤 夏子さんは、なぜ「投資ファンドの会社を辞めて起業する」という勇気を持てたんですか? もう何万回も聞かれた質問かもしれませんが(笑)、みんな気になるところだと思うんです。ごく普通に会社員として働いていた女性が、どうして起業を、しかも日本にはないビジネスモデルを立ち上げて世界中の鉱山と取引をしようなんて思ったのか。
白木 よく誤解されるのですが、最初から「よし、ジュエリーで起業しょう!」と思っていたわけではなくて。初めのころは、何をやるか、どうやるか、ブレてブレて仕方がなかったんです。
安藤 えっ、夏子さんもそういうときがあったんですね。
白木 もちろんありましたよ。「国際協力」をテーマに考えてはいたのですが、具体的にはまったく固まらなくて。マイクロファイナンス、投資会社、ファッション……本当、いろいろ考えました。その選択肢のひとつに、ジュエリーがあったんです。
安藤 そうだったんですね。
白木 最終的に自分の原点や経験に立ち返ってジュエリーを選んだのですが、「これだ!」と決めるまでは本当に苦しかったですね。自分が何がしたいのか分からないときが、人生でいちばんつらかったかもしれません。
安藤 なによりも、目標がない状態がつらかった、と。
白木 ええ。しかも、「これだ!」と決めてすぐに自信を持って進められたかというと、そうではなかった。実は……どこか「恥ずかしい」という気持ちがあって。
安藤 恥ずかしい?
白木 働きながら事業計画を起業家の方々に見ていただいたのですが、自分でもつたない計画だと分かるんです。だから、その不完全な計画書を手に相談するのは本当に恥ずかしかった。無謀だと思われないか、嘲笑されないか、勝手に心配になって。
安藤 ああ、わかります! 私も最初のころ、「独立して何をやるの?」って聞かれるのがすごく恥ずかしかったです。自信がなかったからだと思うんですが……。
白木 そうですね。羞恥心は自信のなさから生まれると思います。私の場合、日本で初めてのビジネスモデルだから、できるかどうかもわからない。頓挫してしまったら大嘘つきになってしまう。毎回、穴があったら入りたいような気持ちでした。
けれど、だんだん「私に経験がないのは仕方がない。それにきっとこの人も、私が思うほど私に期待していないはず」と思うようになって。
安藤 吹っ切れたんですね。
白木 ええ。タダで付き合っていただいてるんだし、何も失ってないはず、と(笑)。そこから開き直って、それまで以上にHASUNAの構想を話すようになりました。「これ、いいんじゃない?」「こうすればもっとよくなるよ」とフィードバックをもらうごとに確信を重ね、次第に自信を持ち始めることができたんです。
安藤 確信と、自信。いい循環ですね。
白木 ブレてブレて仕方がなかったけれど、私の場合、たくさんの方に相談して、背中を押していただくことで揺れが固まっていきました。だからこそ、最後は自分で「これだ!」と決められたんです。
安藤 なるほど。いろいろな人に背中を押してもらいつつも、やっぱり最後は自分で決断したんですね。
この本の帯に「今こそ人生の舵をとれ!」とありますが、良い航海士になるには経験を積むしかないんですよね。ずっと天気に恵まれて、航路どおりに進んで、追い風に吹かれつづける……なんて船はなかなかない。
白木 それは「一流の航海士」というわけではないですしね。たまたま運がよかっただけで。
安藤 嵐に遭遇したらそれも経験、航路を外れたらそれも経験、向かい風でぜんぜん進まなくなってもそれも経験。そう腹を決めて進み続けるしか、一流にはなれない。「もういやだ!」と思うような経験を何度も経て、ようやく自信と確信、そして勇気が持てるようになる。今、夏子さんのお話を聞いてそう思いました。
白木 荒波に揉まれて「もう転覆する!」と思っても、一晩明ければからり晴天。なんて状況は、まさに人生と同じですね。
岡本太郎、高城剛――なぜ、人生の岐路には「洋行」があるのか?
安藤 この本の中で、夏子さんがロンドンに留学したことで人の目を気にしなくなった、というエピソードがとても印象的でした。「世間体は自分がつくっているもの」という。
白木 日本にいるときは、人の目のために生きていたと言っても過言ではありませんでした。人にどう見られているか、どう評価されているかがいつも心配だったんです。それが、ロンドンというとんでもないマルチカルチュラルの環境で過ごすことで、「他人の目は自分で勝手につくりあげていたものなんだ」とはっとして。
安藤 まさに「自分のために生きる勇気」を手に入れたきっかけだったんですね。
白木 そうですね。赤面症が治ったり人前で話せるようになったりしたのも、この「勝手に囚われていた他人の目」から脱却できたからだと思います。
安藤 実は私も、夏子さんと同じくらいの時期にアムステルダムに留学していたんです。でも、夏子さんと違って、私は留学生活をあまりエンジョイできなかった。日本人は学部全体でも私ひとり。英語のレベルはクラスでもダントツに低い。もう、完全に萎縮していました。ちょうど留学中に9.11の同時多発テロが発生したのですが、学生も教授もみんな集まっては議論をするわけです。ところが、英語で議論なんて私には当然無理で、その輪に入れないばかりか、話にすらまったくついていけない。
白木 マルチカルチュラルの中で発言しないと、存在がだんだん「無」になってしまいますよね。
安藤 そうなんです。そこで、このまま鬱屈としていてもダメだ! と早々に学校生活に見切りをつけ、“課外授業”と称して自分なりに学校外でいろいろな人と交流するようになったんです。
白木 課外授業?
安藤 はい。友人のお父さんや大学の先輩など、様々なツテを辿って、現地の日本企業にオフィス見学に出向いたり、現地で活躍するアーティストと仲良くなってライブに招待されたり、バーで同性愛者の弁護士と話したり……。
白木 さすが、幅広いですね(笑)
安藤 面白かったですよ。オランダでは同性婚が認められていますから、多様な価値観を学ぶという点でもいい経験になりました。……こういう感じで、自発的におこなったフィールドワークで得られたことはたくさんあったんです。ただ、結局、大学の授業は20%くらいの満足度で終わってしまって。
白木 留学エピソードというと成功体験ばかりが耳に入りますが、とてもリアルな声だと思います。
安藤 はい。私の留学体験は、「大学生活」という面では完全に失敗でした。けれど、私みたいな人は決して少なくないと思うんです。留学が期待はずれな結果に終わり、打ちのめされてしまった人。でも、私の場合、この失敗を受けて「あぁ、私が勝負するフィールドは日本なんだ!」と逆にすっきりしたんですよね。
白木 なるほど。
安藤 「海外に出たいとずっと思っていたけれど、どうやら長期滞在は向いていないようだ。だったら私は、日本でやっていこう。どんな環境だって日本語が使えるだけでマシなはず!」と(笑)。自分に失望することなく、本当にポジティブな気持ちでそう思えた。これは留学に行かないとわからなかったことです。
白木 もし留学に行っていなかったら、今でも海外への憧れを持ちつづけていたかもしれませんね。
安藤 そうなんです。もちろん、今でも東京をベースキャンプにして、海外にあちこち出かけて仕事をすることは目標にしています。でも、あくまで「短期滞在」という話。海外で長く生活するようなライフプランは、手放しました。
白木 なるほど。私みたいに考え方が変わってブレイクスルーする人もいるし、美冬さんのように消化不良分をポジティブに変換して、行動の原動力にする人もいる。海外に行くことで、なにかしら人生の転換期を迎えるのですね。形は人それぞれですが。
安藤 そうですね。私の尊敬する岡本太郎さんも高城剛さんも、人生の岐路となるときにはやっぱり海外へ行かれています。岡本太郎さんは芸術家として一生を捧げることを誓ったときはパリに留学中でしたし、高城さんは日本でマルチクリエイターとして活躍した後、バルセロナに拠点を移して海外を飛び回っています。そんな状況について、高城さんはご自身の著書の中で「洋行せよ」とおっしゃっていて。
白木 つまり、海を渡れ、ということですね。
安藤 はい。日本にいると聞こえてくるノイズやしがらみから離れられるから、じっくりと人生を見つめ直せる。海外に行くことがひとつの人生の岐路になるのは、きっと、そうしたプロセスを経て「勇気」を手にいれるからじゃないかと思うんです。
安藤美冬(あんどうみふゆ)
起業家/コラムニスト/Japan in Depth副編集長/多摩大学経営情報学部非常勤講師 株式会社スプリー代表。1980年生まれ、東京育ち。慶応義塾大学卒業後、集英社を経て現職。ソーシャルメディアでの発信を駆使し、肩書や専門領域にとらわれずに多種多様な仕事を手がける独自のノマドワーク&ライフスタイル実践者。『自分をつくる学校』学長、講談社『ミスiD(アイドル)2014』選考委員、雑誌『DRESS』の「女の内閣」働き方担当相などを務めるほか、商品企画、コラム執筆、イベント出演など幅広く活動中。多摩大学経営情報学部「SNS社会論」非常勤講師。Japan in Depth副編集長。TBS系列『情熱大陸』、NHK Eテレ『ニッポンのジレンマ』などメディア出演多数。著書に7万部突破の『冒険に出よう』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。
公式ホームページ:http://andomifuyu.com
白木夏子(しらきなつこ)株式会社HASUNA代表取締役・チーフデザイナー。 1981年鹿児島県生まれ、愛知県育ち。短大を卒業したあと、2002年ロンドン大学キングスカレッジ進学。国連インターン、投資ファンド会社を経て、2009年HASUNA設立。人、社会、自然環境に配慮したエシカルジュエリーブランドを日本で初めて手掛け、注目を浴びる。テレビや雑誌やはじめ、あらゆるメディアに出演し、そのビジネスと生き方に絶大な支持を集めている。世界経済フォーラムGSCメンバー。
〜続く
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年04月14日 05:06
昨今ここそこに蔓延するミニマリストやダウンシフターたち、、、カネやモノに囚われず、たまたまそうなれば良しとして、ことさらに目指すことでもない、と私は思います。。。
■世界的な流れ。幸せと自由を手に入れるためのミニマル・ライフ
ジョシュア・フィールズ・ミルバーン、ライアン・ニコデマス
「断捨離」という言葉が定着したように、身の回りのものを必要最小限にしてシンプルに暮らすという考え方は、わたしたちにとっても身近なものになってきました。とはいえ、持っているものを手放すのは苦しい選択。そこで「1番持っている」暮らしから「持たない」暮らしへとシフトした2人「The Minimalists」の著書から「ミニマル・ライフ」の始め方をご紹介します。
発想をシンプルにすることこそ、ミニマル・ライフ
『minimalism 30歳からはじめるミニマル・ライフ』の著者は、人気ウェブサイト「the minimalists」を運営している2人組のユニット。
20代後半で若手企業家として成功をおさめ、物質的に豊かな暮らしを満喫していたふたりは、「ミニマリズム」という考え方に出合いました。その後、ほとんどの所有物をチャリティーに出し、そのうちひとりはテレビもなく、インターネットを解約し、時計も持っていないという生活を続けています。
本書は彼らのウェブサイトから、なぜ「ミニマル・ライフ」を実践しているのか、読者が行動を起こすにはどうしたらいいか、といったエッセイを抜粋しています。ネットを解約、時計を捨てろ、といった過激な論を展開しているわけではありません。彼らの主張はこうです。
「ミニマリズムとは、幸せと満足感と自由を見つけ出す目的で、人生において本当に大切なものだけにフォーカスするために、不必要な過剰物を取り除くためのツールである」
(本書 イントロダクションより引用)
つまり、人生で大切なものだけにフォーカスするために、物を捨てるだけでなく、発想もシンプルにしよう、といった感じでしょうか。
今という瞬間を楽しむことがミニマル・ライフの基本
ミニマル・ライフを送るヒントとして、気持ちの持ち方から実際のモノを減らす方法まで具体的に書かれていますが、特に、考え方についてはなるほど! と思うことが多かったので、気になったものを一部抜粋します。
■山に身を置くこと
山頂についたら下山のことを考えるのではなく、まず山に身を置くことを楽しむという考え方。過去にこだわったり、未来を不安がるのをやめて、今という瞬間を楽しむことが大切。
(本書22ページより一部引用)
■変化をマスト事項として扱うことがマスト事項
自分の人生を変えたいと思っても頭で理解しているだけではダメで心のレベルでの理解が必要。決断というものは、それがマスト事項となり、アクションを強いられてようやく本当の意味での決断になる。
(本書84ページより一部引用)
■感傷のこもったアイテムは実は思っているほど大切ではない
母の形見を持たなくても母の思い出を持ち続けることができること、母を思い出すのに彼女の使っていた品物なんて必要ないことに僕は気が付いた。
(本書86ページより一部引用)
■万人から好かれる必要なんかない
愛されたいのは哺乳類の習性だけれど、ありとあらゆる人間関係をまったく同じように扱うことはできないし、だからこそ万人から同じように愛されることも期待すべきではない。
(本書88ページより一部引用)
やるべきこと、溢れていくモノに押しつぶされそうになったとき、「ミニマリスト」の考え方ができるととても楽になるはず。
ところで、ネットを解約して時計なしでどう暮らしているのか気になります。彼らの場合は自宅のネットは解約し、ネットでやりたいことをメモにまとめてたまったところで、時間を決めてパブリックのWi-Fiのある場所で集中してネットを使うのだそう。ただし携帯電話のメールは使っていると聞いてちょっと安心。時計については携帯電話のアラームのみを使用し、別室に置いて管理しているとか。
つまり、山奥で仙人のように暮らしたり、人とのつながりを断ったりしなくても、ここまでミニマルに暮らせるということ。そう聞くと、自分にも何かできるかなと前向きな気持ちになってきます。
(文/ミヤモトヒロミ)
[cafeglobe]
Posted by nob : 2014年04月10日 22:26
そのとおり!!!Vol.38/その時々の揺らぎを感じてとる直感力と、相手の立場や状況を想い量る想像力の問題。。。
■生きている人はみな「揺らぐ」存在なのだ
訪問看護師のmina
生きているという事は「揺らいでいること」に他ならない。私達はある一定の恒常性を保ちながら常に振幅している存在なのである。調子の良い時もあれば、悪い時もある。それは、体も心もそうだし、自分の成せるパフォーマンスにおいても常にそうだ。
例えば私は医療者として、すべての患者さんやご家族に120%のパフォーマンスのケアを提供できるかといえば、必ずしもそうではない。正直に言うがそうではない。いくらコンディションを整え万全にして仕事に備えても大小の差こそあれ差が出る。機械のようにはいかない。
ケアを提供する側もそうだが、受ける側も人間なのでそれぞれ調子の良い時も悪い時もある。そのお互いのタイミングがうまく合わない時だってある。となると問題はいかにお互いを許し合えるか、ではないのか?
最高のパフォーマンスのケアだけを提供し続けることはできない。ケアする側だって歳もとるし、そうなれば技術だって衰える。でも、その提供できるケアの質の揺れ幅を少しでも小さくするように努力することはできる。そのために骨を折るべきだ。そしてあとはお互いに許し合える関係性を築く事が大事なのだ。
「ミスは必ずあるもの」として過誤を定義し、リスクマネジメントの研究をするのも無駄ではない。でも、私が感じるのは「人同士の関係性をいかに育むか」という点にもっと着目して考えていきたいと思う。「ミスありき」に対して予防線をいかに張るか?だけではないのだ。
人というのはもっとファジーな存在であることを、みんなどこかに置き忘れそうになっているのではないかと思う。
「〇〇でなければならないし、私達は絶対そうするべきだ」、「〇〇なんて許せない」と思う前に、本当にそうなのか今一度考えてみる必要があると思う。人が人である限り、いつも揺らぎながら生きている。その事をもっとお互いに認め合えるような関係性を築き上げていく事こそが大切なのである。「強い心」だけではなくて、そこに「深い思いやり」がお互いになくてはならないのだ。
[newsdig]
Posted by nob : 2014年04月10日 22:17
どんな不調も早め早めの対処が肝要、、、未病のうちにまずは身体を動かすことから。。。
■5人に1人がうつ病になる時代!放っておけない「心の疲れ」対処法
仕事や家事、育児など次から次へとやることに追われ、多忙な毎日を送る女性は多いと思います。ですが、頑張りすぎてキャパを超えてしまうと、心も体もバランスを崩し、気付いた時には自分1人では解決できなくなっていることもあるのです。
そこで今回は、放っておくと危険な心の疲れの対処法について、お話していきたいと思います。
■心が疲れるとどうなる?
現代社会において、ストレスがない生活を送るというのは非常に難しいこと。ストレスを溜め込むと心や体が疲れてしまい、下記のような症状が現れます。
・気分が沈む
・不安になる
・イライラする
・寝つきが悪くなる
・朝早く目が覚める
・夜中に何度も目が覚める
・食欲がない
・風邪のような症状が続く
・胃腸の具合が悪くなる
これらのサインを無視し、「ちょっと具合が悪いけど、大丈夫」と無理をしてしまう方は、要注意。近年、多くの女性を悩ませている、うつ病にかかってしまう危険性があります。その数なんと5人に1人。これはもう他人事ではないですよね……。
では、心の疲れを感じたら、どのように対処したら良いのでしょうか?
■すぐにでも取り入れたい! 心の疲れを対処する方法
(1)完璧にこなさなくてもいい
真面目で責任感が強い方というのは、すべてにおいて100%の力を発揮しようと努力をします。これでは力を抜くことができませんので、すぐに息切れの状態になってしまいますよね? 力加減を調整したり、人を頼ったりして、頑張りすぎないようにしましょう。
(2)日光にあたる
朝日を浴びると、その14~15時間後に体内時計をリセットする、メラトニンというホルモンの分泌が始まります。すると、外が暗くなるのに合わせて眠気を感じるようになるので、睡眠に関する悩みを改善することができます。また、日光にあたることで、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌が促されます。最低でも、1日に10分は日光にあたりましょう。
(3)涙を流す
涙を流すことでストレスや緊張に関係する交感神経から、副交感神経が優位に切り替わり、リラックスしやすくなります。映画を観たり、本を読んだりして涙を流す時間を設けましょう。
(4)自分に合うストレス解消法を見つける
せっかくストレスを解消しようと思っても、その方法が自分に合っていなかったら逆効果。ストレスが倍増してしまいます。まずは、「自分は何が好きなのか」を心の中で思い返してみてください。
・ワイワイするのが好き・・・家族や友人と食事をする
・1人でのんびりするのが好き・・・映画や読書を楽しむ
・体を動かすのが好き・・・スポーツやエクササイズをする
・手先を動かすのが好き・・・料理やフラワーアレンジメント、アクセサリー作りなどの創作活動をしてみる
仕事での立場や結婚、妊娠、出産などたくさんの選択肢があるなかで、悩みが増える現代女性。心や体の声に耳を傾け、健やかな毎日を送れるようにしたいものですね。
[NEWポストセブン]
■食事VS運動 どっちから改善すべき?
健康維持には適切な食事と運動が欠かせません。でも、どちらも改善の効果がすぐに目に見えるとは限らず(目に見える時は、実はやりすぎだったり不健康な方法だったりするものです)、そのためなんとなくテキトウになってしまいがちですよね。まずは、何から手をつけたら効果的かを知って、効果的なスタートを切りたいものです。
ハーバード大学リサーチフェローの大西睦子医師に、食やダイエットなど身近な健康をテーマにした最新学術論文を分かりやすく解説してもらいます。論文翻訳のサポートとリード部の執筆は、ロハス・メディカル専任編集委員の堀米香奈子が担当します。
今回は、「最近の生活、かなり不健康だなあ、よし! 明日から健康的な生活に切り替えよう!」と考えているあなたに、とっておきの情報を伝授します。
そもそも、バランスのいい食生活と適度な運動が健康にいいことは、多くの方がご存知だと思います。ただ、わかっていても実行できない点が問題なんですよね。
例えば、「ファーストフードは体によくないって知っているけど・・・、今日くらいランチはファーストフードで済ませちゃおう!」とか、「運動は健康にいいっていうけど、面倒だし・・・」(と、結局は家でテレビを見て過ごす)、なんてこと、よくありませんか? また、毎日が忙しくてストレスが貯まっているのに、健康的な食事を準備したり運動しなければいけないことで、かえってストレスを招く・・・なんてことありませんか?
実際、従来の研究では、毎日の生活習慣の小さな変化が将来の健康につながると主張する研究者もいる一方、かえって失敗に終わるという考え方もありました。ですから食事や運動をどのように変えればいいのか、明確でなかったのです。
そこで最近は、私たちのとりがちな行動や習慣に注目した研究が行われています。
第一、健康のためには一体何から改善すればいいのでしょうか? バランスのとれた食事? それとも運動? あるいは、両方でしょうか?
スタンフォード大学医科大学院の研究者たちは、運動と同時に食事を改善した場合と、運動を改善する前後に食事を変えた場合に、どのような変化が起こるか調査しました。その研究結果が、雑誌『Annals of Behavioral Medicine』に掲載されましたので、ご紹介させて頂きます。
(省略)
試験は、米国政府の内閣機関である保健社会福祉省が推奨する身体活動や食事の水準に満たない人たち200人(45歳以上)を対象に行われました。具体的には、それまでの6ヶ月間に、中等度から活発な活動を週に60分以上行っておらず、栄養状況については、果物・野菜の摂取が毎日5サービング※1以下で、カロリー総摂取量の10%以上を飽和脂肪酸※2から摂取している人たちです。研究者は参加者を次のような4つのグループにランダムに分けて、電話によるインタビューを12ヶ月間行いました。93%の参加者が12ヶ月間試験を継続できました。
グループ1:運動指導を先に開始し、4ヶ月後に栄養指導も追加
グループ2:栄養指導を先に開始し、4ヶ月後に運動指導も追加
グループ3:当初から食事指導と運動指導を同時に開始
グループ4:栄養や運動については変更せず、ストレス対策の方法を指導
それぞれのグループの参加者は、試験開始時に一度だけ指導者と会い、その後はすべて電話による指導を受けました。グループ1の参加者は、始めの4ヶ月は主に2週間ごとに10〜15分の運動指導を受け、その後は栄養指導10〜 15分と、栄養+運動指導30〜40分が、2週間おきに交互に行われました。
グループ2はそのちょうど逆で、最初の4ヶ月が栄養指導、その後は運動指導と栄養+運動指導が交互に行われました。グループ3とグループ4の参加者は、当初から30〜40分の電話指導を、最初の5回は2週間おきに、以後4週間ごとに受けました。
運動は、米国保健社会福祉省が定めるガイドラインに基づいて、少なくとも週150分の中等度から活発な身体活動を目標にしました。参加者は、運動の種類、頻度、期間などを記録し、電話で指導者に報告します。
栄養は、アメリカ心臓協会が推奨する健康的な食事を基に、量(カロリー)ではなく、質を重視しました。具体的には、毎日5~9サービングの果物・野菜を摂取し、飽和脂酸からのカロリー摂取を総摂取量の10%以下にします。参加者は食事の内容を記録し、電話で指導者に報告します。
グループ4の参加者は、グループ1~3が自宅で上記のような身体活動や食行動を励行する間、その比較対照群として、ストレス対策を実施しました。具体的には、筋肉のリラクセーション、イメージトレーニング、楽しいイベントの企画、睡眠と時間の管理といった5つのストレス対策が指導されました。
そして、研究者たちは、以下の仮説をたてました。
仮説1)運動あるいは食事のいずれか一方から改善したグループ(グループ1・2)は、両方同時に改善したグループ(グループ3)より、初期の行動の変化は大きいだろう
仮説2)運動から改善、食事から改善、両方同時に改善した3つのグループ(グループ1~3)は、12ヶ月後には、食事や運動に大きな行動変化が起こるだろう
仮説3)身体活動は、健康に関する様々な行動変化の入り口であることが報告されているため、運動から改善したグループ(グル
ープ1)と食事から改善したグループ(グループ2)では、運動から改善したグループに早く変化が起こるだろう。
12ヶ月にわたる電話による介入は、毎週評価されました。その結果は次のようになりました。
■毎日の果物や野菜の摂取
4ヵ月の時点で、食事から改善したグループ2は、運動と食事の両方を改善したグループ3と差はありませんでしたが、運動から改善したグループ1と比較対照群のグループ4と比べると、より果物や野菜を多く摂取していました。ところが、12ヶ月後には、食事から改善、運動から改善、当初から運動と食事の両方を改善した3つのグループには、毎日の果物や野菜の摂取に差はなく、いずれも比較対照群のグループ4より摂取量が増加しました。
■飽和脂肪酸の摂取量
4ヶ月の時点で、食事から改善したグループ2は、運動と食事の両方を改善したグループ3との差はなく、運動から改善したグループ1と比較対照群のグループ4に比べて、飽和脂肪酸の摂取はかなり低めでした。12ヶ月後には、食事から改善、運動から改善、当初から運動と食事の両方を改善した3グループには、飽和脂肪酸の摂取に差はなく、いずれも比較対照群のグループ4より摂取量が低下していました。
■身体活動
4ヶ月の時点で、運動から改善したグループ1は、他の3つのグループに比べて著明に身体活動は増えていました。12ヶ月後には、運動から改善したグループ1と当初から運動と食事の両方を改善したグループ3は、食事から改善したグループ2と比較対象群のグループ4に比べて、著明に身体活動は増えていました。
さて、研究者たちの仮説と結果からどんなことが考察できるでしょうか?
仮説1)食事から改善、運動から改善したグループは、両方同時に改善したグループより、初期の行動の変化は大きいだろう:
これは部分的には正でした。運動(4ヵ月の時点で、運動から改善したグループ1は、他の3つのグループに比べて、著明に身体活動は増えていた)にはあてはありましたが、食事(4ヵ月の時点で、食事から改善したグループ2は、運動と食事の両方を改善したグループ3では差はない)は異なりました。
仮説2)食事から改善、運動から改善、両方同時に改善した3つのグループは、12ヶ月後には、食事や運動という行動に大きな変化が起こるだろう:
部分的には正でした。12ヶ月後に、両方同時に改善したグループだけが、国が推奨する飽和脂肪酸と果物や野菜の摂取、そして身体活動の基準に到達しました。
仮説3)身体活動は、健康に関する様々な行動変化の入り口であることが報告されているため、運動から改善したグループ(グループ1)と食事から改善したグループ(グループ2)では、運動から改善したグループに早く変化が起こるだろう:
食事から改善したグループは、身体活動の改善は認められませんでした。食事の改善が先行すると、かえって身体活動の改善が困難になるようです。対照的に、運動から改善したグループは、食事の改善も認められました。運動の改善が野菜や果物の摂取を大幅に改善し、飽和脂肪酸の摂取もわずかながら改善しました。
多くの方が想像されたかもしれませんが、答えは「食事と運動の両方の改善」が最も有効でした。でも、もしどちらかを選ぶ必要があれば、まず運動から始めて下さい。運動を始めれば、自然に食事も改善されるようです。
私たちにとって食べる事は、毎日のスケジュールにありますから、食生活を変えると言っても、それほど余分な時間を得る必要はありませんよね。ところが、運動をはじめることは、忙しいスケジュールの中で、その時間を見つけなければなりません。
ですから、この研究の結果を生活に組み込むのは、はじめは大変かもしれません。でも、以前のコラム(ウォーキングVSランニング)を参照にして頂いて、マイペースにできることから、是非始めて見て下さい。そのうちに、行動の変化が心の変化にも影響して、毎日が生き生きと楽しく過ごせるようになりますよ!
※1・・・Serving。アメリカにおける食品のサイズで、1回分、1人分の意味合い。
※2・・・脂質の材料で、エネルギー源として大切な成分。ラードやバターなど、肉類の脂肪や乳製品の脂肪に多く含まれる。常温では固体で存在するため体の中でも固まりやすく、しかも中性脂肪やコレステロールを増加させる作用があるため、血中に増えすぎると動脈硬化の原因となる。
■大西睦子の健康論文ピックアップ39
大西睦子ハーバード大学リサーチフェロー。医学博士。東京女子医科大学卒業。国立がんセンター、東京大学を経て2007年4月からボストンにて研究に従事。
[newsdig]
Posted by nob : 2014年04月08日 18:33
そもそも実際の基準値は体質やその時々のコンディションによって千差万別、、、日頃からの自らの心身との対話力こそがすべて。。。
■健診基準値、厳しすぎる…健康な人でも上限超え
日本人間ドック学会と健康保険組合連合会は4日、極めて健康な人でも性別や年齢によって健診の検査結果は大きな幅があり、同学会が定め、実際に使われている基準値は厳しすぎるとの研究結果をまとめた。
同学会は2011年、人間ドックを受けた約150万人のうち、病気にかかっておらず、薬も飲んでいないなど、極めて健康な男女を約1万人選び、27項目の検査データを解析した。
その結果、例えば最大血圧は、解析したデータの上限は男女とも147で、学会が定めた基準値129を上回っていた。一方、中性脂肪は女性の場合、基準値(30~149)の範囲に収まっていたが、男性は上限が大幅に上回り、男女差が見られた。
また、悪玉と言われるLDLコレステロールや、糖尿病の診断に使われるヘモグロビンA1c(エーワンシー)は、男女とも上限値が基準値を上回った。いずれの項目も、男性では年齢による差はなかったが、女性は年齢が上がるにつれて数値も高くなった。
研究を行った慶応大の渡辺清明名誉教授は「今後も追跡調査を行い、健診の現場で使えるようにしたい」と話している。
[読売新聞]
Posted by nob : 2014年04月08日 18:27
ウォーキングとストレッチは健康生活のキホンのキ。。。
■美ウォーキングを続けると、理想的なダイエットができる!?
街に出て周りを見回すと、背筋を伸ばして美しく歩いている人のほとんどはスタイル抜群の人ばかり・・・。それはなぜなの?
「正しい姿勢でのウォーキングとスタイル維持はとても関係が深いのです。美しく歩いていれば、自然にむくみやゆがみが解消されてダイエットにつながります」
そう教えてくれたのはエレガントボディメイクウォーキングコーディネーターの今関純子さん。
「ダイエットにつながる歩き方のコツは、正しい位置に自分の身体軸がある姿勢。まずはお尻と肩甲骨を壁に付けて立ち、体が一直線になっていることを意識して。重心をかかとに乗せて、お腹に力を入れてお尻を閉めること。この姿勢で歩くと、自然に全身の筋肉を使うので、リンパの流れや血液の流れがよくなります。すると、わざわざジムに行ったり、ランニングをしなくても、それらと同じぐらいの運動をしていることになるのです」(同)
さらに、正しい姿勢で歩くことで、アンチエンジング効果も期待できるのだとか。
「リンパの流れがスムーズになると老廃物が排出され、デトックス効果が高まります。そのため肌がツヤツヤになったり、顔色がよくなったりもするのです。埋もれていた鎖骨がきれいに出てきたなんてケースもあるんですよ」(同)
また、さらなる美容効果が期待できる“合掌ストレッチ”というメソッドがあるのだそう!
「イスに腰を掛けているときなどに取り入れていただきたい簡単なストレッチ法です。リンパや血液の流れを促し、肩こり解消やバストアップにも効果的です。ぜひ試してみてください」(同)
合掌ストレッチのやり方は次のとおり。
(1)胸の前で両手の平を合わせて合掌のポーズ。合わせる手のひらは押し合うように力を入れる。
(2)合掌したまま頭の上に移動させる。そのまま頭の後ろ限界まで引いて10秒ほどキープ。このとき背筋が反ることを意識する。
(3)この動きを10回繰り返す。1日3回ほど行って。
正しい姿勢のウォーキング&肩甲骨を動かす“合掌ストレッチ”で理想のボディラインを叶え、この春からはモテ女子に大変身しちゃおう。
今関純子
エレガントボディメイクウォーキングコーディネーター
[OZmall]
Posted by nob : 2014年04月03日 19:51
言い得て妙。。。Vol.18/さらに40代、50を過ぎて定年間際でも、捨て去れない人のほうがはるかに多いでしょ(苦笑)。。。
■20代のうちに捨て去るべき「7つの習慣」
大久保雅城
4月から社会人歴6年目に突入したのですが、相変わらず自分のアウトプットに自信がなく、力を抜いた仕事ができずにいる28歳です。力の抜き方が上手い先輩を見ていると、羨ましく思ってしまいます。とりあえず量をこなすべし、というメンターの教えに従って、毎日アウトプットを続けています。ただ、そもそも経験が足りないですね、圧倒的に。この4月からはもろもろ動き出す予定なので、それまでは座禅でもしながら思索にふける所存です。
さて、私はあまりビジネスのハウツー本はあまり読まないのですが、ネットを見ていたら「20代が直面する課題を乗り越えるために、手放すべき7つの習慣」という記事を見つけました。『7つの習慣』と言えば、ビジネス書の名著として紹介されることの多い本。しかし、今回紹介するのは、ビジネスに役立つ 7つ習慣のほうではなく、”手放すべき7つの習慣”となっています。一体どんな習慣なのでしょうか? さっそくですが、その7つの習慣を紹介することにしましょう。
■20代が直面する課題を乗り越えるために、手放すべき7つの習慣
1. 仕事をするフリの習慣―暇なら遊べ。早く帰れ。
2. やらされ仕事をする習慣
3. パニクッたまま仕事をする習慣
4. 今の自分の力だけで乗り越えようとする習慣
5. 昨日と同じ仕事をすることで満足する習慣
6. 納得した目標なしに、だらだら仕事する習慣
7. マイナスの気持ちを引きずったまま仕事をする習慣
http://www.lifehacker.jp/2012/08/120818custompartwith.html
「1.仕事をするフリの習慣」はありますね。上司が帰らないから、とりあえず席で仕事をしているというケースは往々にしてありそうです。暇なら遊べ、とはまさにその通り。遊びの中に仕事のヒントが隠れている場合もありますし。
「2.やらされ仕事をする習慣」も然り。仕事が機械的になってくると、どうしてもやらされ感のある仕事をしがち。反省。
「3.パニクッたまま仕事をする習慣」。もともと焦りやすい性格の人は注意。仕事はあくまでも冷静にこなしたいものです。もちろん、その人自身が ADHD(注意欠如・多動性障害)などの病気を抱えている可能性もあるので、一概にその人の性格とは言い切れないところもありますが。
「4.今の自分の力だけで乗り越えようとする習慣」。どんな壁も一人で乗り越えようとするのではなく、遠回りでもいいので「今の自分では乗り越えられない課題なのだから、力をつけてから乗り越えればいい」ぐらいの気持ちでいきたいですね。
「5.昨日と同じ仕事をすることで満足する習慣」。これは耳が痛いです。職場からの帰り際、昨日とまったく同じ作業で満足している自分がいるので…。日々生産性向上を追及していきたいものです。
「6. 納得した目標なしに、だらだら仕事する習慣」。うーん、納得した目標って難しいですね。もちろんだらだら仕事をするのはNGだと思いますが、定性的な目標に納得したことがないので…。「円滑なコミュニケーション」「別の部署の仕事にコミット」などの目標って、永遠に納得せずに終わりそう…。
「7. マイナスの気持ちを引きずったまま仕事をする習慣」。これはいつも思うんですが、感情に波がある時にぶつかったマイナス感情ほど、引きずってしまうような気がしますね。好調な時のマイナス感情はすぐに消え去るのですが、不調な時のマイナス感情はけっこう重い。感情の波のある・なしは自分ではどうしようもないので、ちょっとでも「おかしいな」と思ったら、休養を取るべきなんでしょうね。…なかなか仕事を進めながらだと、難しいところがありますけれど。
以上、捨て去るべき7つの習慣をお送りしました。引用元の記事をみると、「当たり前のことを言っている」というコメントがある一方、「30代でも捨てられていない…」という意見もありました。あなたはこの7つの習慣、どう思いますか?
[newsdig]
Posted by nob : 2014年04月03日 17:38
私も日々実感しています、、、心身の健康は何はともあれ整腸から、、、今日も絶好調です。。。
■肌荒れや体調不良はヤバイ!「腸が老化し始めている」危険な兆候
近頃、「風邪をひきやすい」「体調を崩しやすい」と感じているそこのあなた。その他にも、肌荒れやイライラに悩まされていませんか?
もしかしたらそれ、腸が老化している証拠かもしれません。腸が老化すると、なぜさまざまな不調があらわれるのでしょうか?
■腸が老化すると大変なことに
腸が老化すると便秘になります。便秘で便が腸内にいつまでも残っていると腐敗がはじまり、悪玉菌が活発化します。すると、腸内細菌のバランスが崩れて、腸内で増えた有害物質が血流によって全身に運ばれます。その結果、各臓器や肌がダメージを受けることになるのです。
また、精神を安定させる働きがあるセロトニンというホルモンをはじめ、全身の免疫細胞の約6割は腸粘膜に集結しているため、腸が老化することで免疫力がダウンし、病気やアレルギーにかかりやすくなったり、イライラ、くよくよしやすくなるのだそう。
では、自分の腸が老化しているかどうかを知るためには、どのようなことを目安にすればいいのでしょうか?
■腸の老化で出るサイン
近年は、生活環境や習慣の影響から、若い女性でも腸が老化している方が増えているそうです。下記の項目に心あたりがある方は、すでに腸が老化しはじめているかもしれません。
・便秘がち
・便の量が少ない、スッキリしない
・便のニオイが強い
・風邪をひきやすい(体調を崩しやすい)
・肌が荒れやすい
・花粉症
・イライラ、くよくよしやすい
・ストレスを感じやすい
・寝つきが悪い
春は進学や就職、転勤など新しい環境への異動があるだけではなく、花粉の飛散量も増える季節です。これらのツライ症状を悪化させないように、今から腸を若返らせておきましょう。
■腸を若返らせる生活習慣
(1)朝、コップ1杯の水を飲み、便意を促す。
(2)3食バランス良く食べる。大豆、野菜、芋、果物といった植物性の食品や、納豆、ぬか漬け、味噌、醤油などの発酵食品を積極的に食べる。
(3)適度な運動をして腹筋を鍛える。
(4)自律神経のバランスが乱れると腸の働きが悪くなるため、休養をとり、ストレスを溜め込まないようにする。
腸年齢が若いほど、元気な体と美しい肌をキープすることができます。スキンケアで効果を感じにくいという方は、まずは腸のケアをしてみてはいかがでしょうか?
[NEWSポストセブン]
■食べ過ぎ予防にも。幸せホルモン「セロトニン」を増やす
いよいよ春が到来。これから薄着になっていくにつれて、いま思うことといえば......「痩せたい」。しかし、どうにもこうにも食欲が抑えられない、そんな人は「セロトニン不足」かもしれません。
幸せホルモン「セロトニン」
心の安定を保つ「セロトニン」は必須アミノ酸のひとつ、トリプトファンからつくられる脳内物質です。幸せホルモンと呼ばれることも多く、リラックスしているときなどに分泌されます。不足するとウツ症状などを引き起こすことで知られています。
すると食欲増加につながる可能性が大
このセロトニン、自律神経のバランスをコントロールしているため、睡眠、食欲、体温調整などにも影響を与えていて、食事の満腹感UPや食欲を抑制する効果もあるんです。逆をいえば、欠乏すると食欲が過剰になってしまう危険が。
また、質の良い睡眠に欠かせないメラトニンの生成にもセロトニンが必要。睡眠不足もダイエットの大敵で、代謝の低下や食欲の増加につながるので、セロトニンってやっぱり重要。健康的なダイエットには欠かせないと言っても過言ではありません。
セロトニンを増やすには?
そんなセロトニンを増やす方法がコチラ。
セロトニンを増やす方法
・食事のポイント
トリプトファンを含む、大豆製品、バナナ、赤みのお肉や魚、卵、乳製品などを摂る。さらにトリプトファンの吸収に必要なビタミンB6も一緒に摂るのが◎です。よく噛んで食べることも分泌を促すのに効果的。
・リズム運動
有酸素運動や呼吸を整えるヨガなどが効果的。理想は30分ほど。
・スキンシップ
スキンシップでセロトニンが増えることが分かっています。また、スキンシップだけでなく人と何かを共感することも良いそうです。
・複式呼吸や深呼吸をする
・日中にしっかり太陽の光を浴びる
セロトニンは一度にたくさんつくって貯めておくということはできないそうなので、毎日コツコツ続けることが大切。最近、間食が多いので、意識してみます。
若松真美
[MYLOHAS]
Posted by nob : 2014年04月03日 17:26
調理に使わない野菜のヘタや外皮など、一切を棄てずに網に入れて、さらに昆布などと一緒に煮出すと、甘い香りと様々な栄養豊かな出し汁が、味噌も少なくて済みます。。。
■みそ汁1日3杯以上で乳がん発症率40%減少などのデータも
2013年、ユネスコの無形文化遺産に“和食” が登録された。健康的で栄養バランスがよい和食は海外でも人気だが、なかでも和食の深い味わいを象徴するみそは、生命維持に不可欠な必須アミノ酸をすべて含むなど、優れた栄養バランスを誇る食品だ。独特のうま味が動物性脂肪の過剰摂取を抑える利点もある。
女子栄養大学副学長で、栄養化学研究所所長の香川靖雄さんも、「和食の礎である“ご飯とみそ汁”は、2品で必要な栄養分の多くをカバーできる理想の組み合わせです。日本人は東アジアに特有の飢餓に対する耐性を備えた遺伝子型をもっているため、肉食中心の食生活では肥満になりやすいので健康のためにも、ご飯 とみそ汁を基本とする日本古来の食生活を大切に」と解説する。
おいしいだけではなかったみその威力をじっくり覗いてみよう。
【食塩より30%もの減塩効果あり!】
共立女子大学 家政学部臨床栄養学教授の上原誉志夫さんが行ったラットによる実験で、食塩と、同じ量の食塩を含むみそを比べたところ、食塩よりみそのほうが血圧に影響しにくく、約30%もの減塩効果があることが判明。また別の研究では、みそが血圧を下げる作用も検証されており、高血圧予防が期待されている。
みそは少量でうま味のある味つけができ、前述の減塩効果もあるため、みそ料理の塩分量は決して多くない。たとえばみそ汁1杯の塩分は約1.2g。1日の塩分摂取目標量は、男性9g未満、女性7.5g未満なので、塩分のためにみそ汁を控える必要はないのだ。塩分の吸収 を防ぐほうれんそうやいも類、ごぼうなどを具にするのもおすすめだ。
【みそ汁を飲むほど胃がんによる死亡率が低減】
日本人に多い胃がんの要因のひとつに、塩分の摂りすぎが挙げられるが、みそ汁を飲む人ほど胃がんによる死亡率が低いことがわかっている。特に男性では、まったく飲まない人と毎日飲む人の差は1.5倍。また毎日、喫煙・みそ汁を摂取する人のほうが、喫煙・みそ汁ともに 摂取しない人より胃がんによる死亡率が低いという調査結果もある。
【乳がん発症率が40%減少】
現在、日本人女性でもっとも罹患率の高いがんは乳がん。厚生労働省が40~59才の女性約2万人を対象に行った 10年間に及ぶ疫学調査によると、みそ汁を1日1杯未満飲む人に比べ、2杯の人は26%、3杯以上飲む人は40%も乳がんの発症率がダウンした。1日3 食、みそ汁を飲む習慣が、乳がん予防に効果が期待できるわけだ。
[女性セブン]
Posted by nob : 2014年04月01日 23:28
その時の発症状以外の効能の分だけの、さらに重複服用にて予期せぬ重篤な副作用のリスクも。。。
■副作用のない薬はないって本当?
風邪気味だと感じたら風邪薬を。食べ過ぎてしまった翌日には胃薬を。薬は僕らにとって非常に身近なものだ。
しかし、そこで気になるのが「薬には必ず副作用がある」という噂である。そうでなくても、副作用とはなんだか得体が知れなくて恐ろしい言葉。これが事実なら、あまり薬に頼りすぎるのも考えものだが…。新宿ライフクリニックの須田隆興先生に確かめてみた。
「副作用とは簡単にいえば、“投与することによって発生する、本来の治療目的とは異なる作用”のことです。この定義に基づいていえば、取るに足らない程度の症状も含め、副作用のない薬はまず存在しません」
須田先生によれば、医薬品に含まれる有効成分の多くは、頭痛や腹痛、発熱など特定の症状にだけ効くというものではない。薬というのは僕らがイメージしている以上に、多くの作用を持っているものらしい。それらは健康上、害になり得るものもあれば、痛くもかゆくもないものまで様々だ。
「副作用の症状は、眠気や口内の渇きを覚える軽度のものや、抗癌剤のように重篤なものなど、薬によって異なります。身近なものでいえば、頭痛薬などとして使われる消炎鎮痛剤には、副作用として胃粘膜に負担をかけるタイプの薬があり、一緒に胃薬を処方されるケースもよくありますよね」
実際、薬に同梱されている添付書類には、よく読むと細かい文字で無数の副作用がびっしりと記載されている。これを精読したことのある人もあまりいないだろうが、薬そのものにアレルギー反応を起こすケースもあるそうだから、あながち軽視していいものでもなさそうだ。
「ただ、基本的には慎重に臨床試験を繰り返して商品化されているわけですから、抗がん剤など副作用が起きやすい前提のものは別として、一般的に外来で処方される薬剤を医師の指示に従って服用している分には、大きな問題が起こる可能性は低いでしょう」
薬は用法・用量を守って服用することが大切ということだ。
(友清 哲)
取材協力先
新宿ライフクリニック
須田隆興
[webR25]
Posted by nob : 2014年04月01日 23:14
人生は旅だ。。。Vol.6/また旅立つ君へVol.27
いつしか私は旅人として
異質なものよりも
同質なものを鋭く感じるようになり
その違いのなさに共感を覚えるようになっていた
地球は自分の家といっしょだなどというと
大言壮語のたぐいなのだが
共生感とともに旅をすると
落ち着いたよい旅をすることができる
旅先のその場所が
魂の休み場所になるのだ
[立松和平/旅暮らし]
Posted by nob : 2014年03月29日 11:38
また旅立つ君へVol.26
世界とは
他の誰かが変えてくれるものではなく
ただ「わたし」によってしか変わりえない
[アドラー/嫌われる勇気]
Posted by nob : 2014年03月26日 09:23
また旅立つ君へVol.25
人生はいつもシンプルであり
深刻になるようなものではない
それぞれの刹那を真剣に生きていれば
深刻になる必要などない
人生はつねに完結しているのです
たとえ「いま、ここ」で生を終えたとしても
それは不幸と呼ぶべきものではありません
20歳で終わった生も
90歳で終えた生も
いずれも完結した生であり
幸福な生なのです
[アドラー/嫌われる勇気]
Posted by nob : 2014年03月26日 08:18
また旅立つ君へVol.24
多くの人は
対人関係のカードは他者が握っていると思っています
だからこそ「あの人は自分のことをどう思っているんだろう?」と気になるし
他者の希望を満たすような生き方をしてしまう
でも
課題の分離が理解できれば
すべてのカードは自分が握っていることに気がつくでしょう
[アドラー/嫌われる勇気]
Posted by nob : 2014年03月26日 08:16
また旅立つ君へVol.23
他者の期待を満たすように生きること
そして自分の人生を他人任せにすること
これは
自分に嘘をつき
周囲の人々に対しても嘘をつき続ける生き方なのです
[アドラー/嫌われる勇気]
Posted by nob : 2014年03月26日 08:08
また旅立つ君へVol.22
他者からの承認を求め
他者からの評価ばかり気にしていると
最終的には他者の人生を生きることになります
[アドラー/嫌われる勇気]
Posted by nob : 2014年03月26日 08:06
また旅立つ君へVol.21
他者の期待など
満たす必要はない
[アドラー/嫌われる勇気]
Posted by nob : 2014年03月26日 08:05
また旅立つ君へVol.20
行動面に目標が、次の二つ。
1.自立すること
2.社会と調和して暮らせること
そして、この行動を支える心理面の目標として、次の二つ。
1.わたしには能力がある、という意識
2.人々はわたしの仲間である、という意識
[アドラー/嫌われる勇気]
Posted by nob : 2014年03月26日 08:03
また旅立つ君へVol.19
勝ちや負けを競い会う場所から身を引いたのです
自分が自分であろうとするとき
競争は必ず邪魔をしてきます
[アドラー/嫌われる勇気]
Posted by nob : 2014年03月26日 08:00
また旅立つ君へVol.18
いまの自分よりも前に進もうとすることにこそ
価値がある
[アドラー/嫌われる勇気]
Posted by nob : 2014年03月26日 07:59
また旅立つ君へVol.17
誰とも競争することなく
ただ前を向いて歩いていけばいい
健全な劣等感とは
他者との比較のなかで生まれるのではなく
「理想の自分」との比較から生まれるもの
[アドラー/嫌われる勇気]
Posted by nob : 2014年03月26日 07:53
また旅立つ君へVol.16
われわれを苦しめる劣等感は
「客観的な事実」ではなく
「主観的な解釈」
[アドラー/嫌われる勇気]
Posted by nob : 2014年03月26日 07:52
また旅立つ君へVol.15
人間の悩みは
すべて対人関係の悩みである
[アドラー/嫌われる勇気]
Posted by nob : 2014年03月26日 07:50
また旅立つ君へVol.14
これまでの人生になにがあったとしても
今後の人生をどう生きるかについてなんの影響もない
[アドラー/嫌われる勇気]
Posted by nob : 2014年03月26日 07:47
どんなところでどんなことをするかではなく、どんなことにでもどのように取り組むかということ。。。/また旅立つ君へVol.13
■「やりたいことをやる」ではなく「やりたいようにやる」。新人が憂鬱な仕事を楽しくする方法とは?
常見陽平
人材コンサルタント
「やりたいことをやる」ではなく「やりたいようにやる」。新人が憂鬱な仕事を楽しくする方法とは?
4月も間近に迫り、入社の期待に胸ふくらませる新社会人も多いだろう。しかし期待が大きいほど、現実の会社生活にショックを受ける人が多いのもまた事実。そこで人材コンサルタントとして著書多数の常見陽平さんに「新社会人の働き方」に関してお話をうかがった。
「最近の新社会人の傾向としてすごく感じるのが、自分の好きなこと、やりたいことを実現できる場として、会社に多くのことを期待しすぎる傾向があるということです。大学時代は勉強にしろ、サークルにしろ自分の好きなものや、やりたいことを選ぶことができましたよね。そして、それを突き詰めて『がんばった!』と、誇ることができました。ただ会社はそうはいかない。期待していた配属先じゃなかったり、やりたい仕事が必ずしもできるわけじゃない。自分の思ったようにならないわけです。そんなジレンマの中で成果をださなきゃならないのが仕事なんですよ。大学はお金を払う、仕事はお金をいただく。いわば立場が違う。当然のようですが、それを理解していない学生は実に多い」
社会人になるということは、これまでの世界観やルールが通用しなくなるということ。まずそれを認識し、意識のギャップを埋めなくてはならない。自己実現の前に、まずは仕事をするということの、本質を理解しなくてはならないということだ。
「基本的に新人が期待通りに仕事で『やりたいこと』ができることは稀。だから『やりたいようにやる』という意識で仕事に取り組んでみてはどうでしょうか。
実際、私自身も新人時代にあまり本意ではない営業の部署に配属されました。ただ、その中でも興味のあったレコード会社の営業に積極的にトライし、仕事をすることができました。結果としてビジネスとしても感謝されて、興味のあった音楽業界の仕組みの一端を知ることができました。そうやって与えられた仕事の中で、少しでも興味のある分野の仕事ができるように工夫してみてはどうでしょうか」
また、『やりたいようにやる』一環として、自分が楽しめる要素を取り入れることも重要だと常見さんは語る。
「学生時代『クリエイティブな仕事がしたい』なんて言ってましたから、営業の企画書一つ作るにしても「広告代理店のようなカッコいいものを作る!」と意気込んでました。で、でき上がったものに勝手に喜びを感じたりして......。もちろん仕事として機能しなければ論外ですが」
少しずつでも楽しみを見出し、自身の強みを少しでも発揮することが重要。そして、今の仕事が自分の求めるものじゃないにしても、やりたい要素を取り入れることで将来の糧として繋げる意識をもつ。そこで得る様々な経験はキャリアの中で必ず生きる。むしろ、その経験によってゼネラリストとしてスキルアップできている、くらいに考えてもよいだろう。
「この仕事は合わない、やりたくないと食わず嫌いが一番良くなくて、やってみたら意外と面白いってことはたくさんある。だから受け身で仕事をこなすよりも、自発的に楽しいと思うことを探す感覚が大切です」
実際、社会人に「新人として入社した後、すぐに希望の部署に入れましたか?」 と、アンケートしたところ「最初の配属で希望の部署に入れた」という人は「50.3%」と約半数。そして、1年目ともなれば実際仕事が始まっても思い描いたような仕事を与えられている人は数少ないはずだ。しかし「憂鬱...」と、愚痴るばかりでは意味がない。新人時代はどんなビジネスパーソンであれ、キャリアの中で1度は経験する。仕事の本質を早くつかみ、有意義に過ごすための手段を考えたい。
(大場庸佑)
[マイナビスチューデント/フレッシャーズ]
Posted by nob : 2014年03月25日 18:08
喫煙自体よりも有害という受動喫煙、、、まったく割に合いません。。。
■発癌リスクだけでない三次喫煙の懸念
Susan Brink
for National Geographic News
室内での喫煙による煙は空気中の汚染物質と結合し、発癌性が疑われる化合物を形成する。また、この物質は何十年にもわたって残存する可能性が指摘されている。
喫煙が癌(がん)や心疾患、早期死亡の原因となることが証明されるまでには何十年もかかった。その後、二次喫煙が人を死に至らしめることが立証されるまでにはさらに年数を要した。
そして今、研究者たちはタバコによるもう一つの現象を懸念している。それが三次喫煙(副流煙残留物)だ。三次喫煙は現実に、いたる所に存在している。室内喫煙者たちは、火をもみ消してから何年間も持続する有害な遺産を知らないうちに残しているのだ。
タバコの煙の残留物はオゾンや亜硝酸といった室内汚染物質と結合し、新たな化合物を形成することが研究によって明らかとなっている。ホコリと混ざり合って堆積した残留物はカーペットや家具の表面にこびりつき、羽目板や乾式壁の多孔質材に深く入り込む。喫煙者の髪の毛や皮膚、衣服、爪に留まることもあるため、子供のそばを避けて外で喫煙する母親が部屋に戻って赤ん坊を抱えた場合、その子供は三次喫煙にさらされることになる。この新たな化合物は、除去が難しいだけでなく性質が長期にわたって持続し、発癌性も疑われる。
中でも、NNAとして知られるタバコ特異的ニトロソアミンはDNAに損傷を与え、癌を引き起こす可能性がある。カリフォルニア州のローレンス・バークレー国立研究所で研究を行うボー・ハン(Bo Hang)氏は、今週この研究が発表されたアメリカ化学会(ACS)の年次総会で開かれた記者会見で、「三次喫煙はヒトの遺伝物質に有害」と述べた。「汚染物質の毒性は時間とともに強まる」。
◆20年以上
三次喫煙は比較的新しい研究分野であり、煙と環境汚染物質からなる化合物がいつまで残存するのかは誰にもわからない。カリフォルニア大学で臨床薬理学部門を率いるニール・ベノウィッツ(Neal Benowitz)氏は、「こういった化合物の残存を示す証拠は、20年前から非喫煙者しか住んでない家のホコリや壁板からも見つかっている」と話す。ベノウィッツ氏は、2010年に始まったカリフォルニア州三次喫煙コンソーシアム(California Consortium on Thirdhand Smoke)で指揮を執っている。
タバコの煙の残留物が染み込んでいるかもしれない絨毯の上をハイハイし、カーペットの上で眠りに落ち、家具をしゃぶる乳幼児や小児は、その毒性作用を最も被りやすい。
研究者たちが心配しているのは発癌リスクだけではない。三次喫煙は、ぜんそく発作やアレルギー反応を含む他の健康問題にも関与する可能性がある。
ホテルの喫煙室をほうきで掃き、掃除機をかけ、リネン類を交換し、ほこりを払う従業員は、そこに数泊する客よりも大量の三次喫煙にさらされる。健康に危険をもたらす暴露量はまだ数値化されておらず、具体的な健康リスクもはっきりとは特定されていない。しかし、バーやカジノ、レンタカー、あるいは過去に喫煙者を招いたことのある室内空間には、かなりの残留物が存在する可能性がある。
過去に喫煙者が住んでいた家やアパートに引っ越した人がさらされる危険性もある。三次喫煙には、除去が困難という側面があるのだ。カリフォルニア州のサンディエゴ州立大学で心理学科長を務めるゲオルク・マット(Georg Matt)氏は、「三次喫煙にさらされた環境で測定値がゼロになったことは今までない」と話す。「フローリングや乾式壁を取り除かない限り、この物質を除去することはまず不可能だ」。
◆除去する方法
室内環境から残留物を取り除くにあたっての重要なアドバイスには、次のようなものがある。「洗剤を使って徹底的に掃除すること。部屋の塗り替えを勧める人もいる」と話すのはハン氏。「最善の方法はカーペットを交換し、換気装置を清掃することだ。これだけでも役立つが、新世代の洗浄剤のような製品の登場を期待したい」。問題の重大性や健康リスク、化合物を除去する有効な方法については、まだ課題が山積みだ。
また、ベノウィッツ氏は「(残留物が)どの程度存在し、どの程度の量で害を及ぼすのかはまだわかっていない」と指摘する。「子供の三次喫煙を防ぎ、喫煙者が使用した部屋や車を借りないよう親にアドバイスすべき。避けられるものは、避けるに越したことはない」。
[ナショナルジオグラフィック ニュース]
Posted by nob : 2014年03月25日 18:01
「5]以外は私も実践しています、、、おすすめです。。。
■がむしゃらに働いて燃え尽きないために...。もっと効率良く働く5つのアイデア
みなさん本当にお疲れ様です。しかし、そんなにがむしゃらに働かなくても、もう少し効率良く働くこともできます。
今回は、ソーシャルメディアの投稿スケジュールや自動化、分析などを管理するツール「Buffer」のコンテンツクラフターBelle Beth Cooper氏より、もっと効率良く働くための5つのアイデアをご紹介しましょう。(Cooper氏はExist社の共同創立者でもあります)
Bufferの文化で好きなのは、一生懸命ではなく効率良く働くことを重視しているところです。私たちのチームでは、十分な睡眠と運動、それに余暇の時間をとることを大事にしているので、仕事の時間はできるだけ生産性を上げるようにしています。
一生懸命働くというのは、陥りやすい習慣でもあります。1日の終わりに仕事スイッチを切ったり、週末に仕事のことを考えずに休養するのは、難しいこともあります。自分で会社を立ち上げていても、管理するのが難しいというのが分かりました。Bufferで仕事をしていない時はExistで働いています。そうすると、効率良く働くのではなく"1日中働く"パターンに陥りやすいのです。
そんなCooper氏が、仕事人間の罠に落ちないためにやっている5つのアイデアがこちらです。
1. もっと休憩をとる
私の大好きな作家スティーブン・R・コーヴィーの『7つの習慣』に、月日が経つにつれてより多くの木を切る木こりの話がありました。木こりが木を切るのを止めてのこぎりを研げば、次は切れ味のいいのこぎりで木を切ることができ、結局は長期的に見て効率が良く、時間も節約できます。
この例え話はとても分かりやすいですが、実行するとなると難しいです。著者のCoveyさんが、普段の生活においてのこぎりを研ぐことについて、こんな風に言っています。
のこぎりを研ぐのは、誰もが持っている素晴らしい資産、つまり自分を大切にし、向上させるという意味です。自己再生をするために、「身体的」「社会的」「精神的」「霊的」という、人生における4つの領域でバランスが取れているプログラムのことを意味しています。
のこぎりを研ぐことは、人生のあらゆる面において素晴らしい習慣ですが、特に仕事の場合は、燃え尽きたり参ってしまうのを避けられるので、メリットが大きいように思います。
人間の脳が集中できる時間というのは、平均で約90分と言われています。ですから、90分仕事をしたら、少なくとも15分休憩しましょう。90分毎に休憩をとることで、心身ともにリフレッシュし、次の90分でより活発に仕事をする準備ができます。
人によっては、15〜20分の休憩をとるのが難しいかもしれませんが、1日のうちに何回か短い休憩をすることで、持続した集中力を一旦リセットし、心身共に切り替えることができます。
2. 昼寝をする
昼寝が認知機能やクリエイティブ思考、記憶力を向上させることは、調査によって分かっています。特に昼寝の効能は、記憶力が向上することにより、学習効果が上がることでしょう。
Web ライターのMax Read氏は「記憶は最初に脳の海馬に刻まれますが、その時はまだ忘れられやすい"割れ物"のような状態です。たくさんの記憶を詰め込んだ時などは特にそうです。しかし、昼寝をすることで、その記憶が脳のより恒久的な倉庫である大脳新皮質に押し出され、書き換えられにくくなります」と言います。
記憶に関するある研究で、昼寝の後の被験者は、昼寝をまったくしなかった被験者よりも、テストの結果が非常に良いということが分かっています。
昼寝によって記憶が定着するだけでなく、新しい情報をより覚えやすくもなります。また、燃え尽き症候群というのは、寝ない限りこれ以上脳に情報が入らないというシグナルだということも研究によって分かっています。昼寝は燃え尽き症候群を避けるのにも役立つのです。
3. 自然の中で過ごす
『Focus: The Hidden Power of Excellence』という本の著者Daniel Goleman氏は、自然の中で過ごすことで、持続していた緊張や集中力が一旦リセットし、リラックスすることができると言っています。
街中の通りを歩く時と、静かな公園の中を歩く時、人間はどのくらいリラックスしているかという実験がありました。その結果、騒々しい街中を歩く時は緊張のレベルが高く、脳が集中力をリセットするためのリラックスをすることができないということが分かりました。
自然環境と違い、都会の環境は著しく注意力が必要だったり、直接注意しなければならない刺激に、満ちあふれています。(例:車にひかれないようにするなど)そのため、集中力が回復しにくいのです。
ところが、自然の中で過ごすと、頭も心も十分リラックスし、緊張がほぐれ、仕事に戻った時はより長い時間集中できるようになります。さらに、ある研究では、教室の中ではなく外にいる時の方が、学生の学習に対するやる気が高くなることが分かりました。
4. 移動してまとめて仕事をする
最近、Joel Runyonさんが書いた「ワークステーション・ポップコーン」というメソッドに関するブログを読みました。
このメソッドは、カフェや職場など場所を決めて、まとめて仕事を終わらせるというものです。まず最初にToDoリストを作成し、その場所で何を終わらせるかを決めるので、そこに着いたらすぐに仕事に没入できるという訳です。
Joelさんは、場所毎にToDorリストを分け、それぞれの場所のタスクは3つまでにしていました。決められた仕事をすべて終えたら、次の場所に移動します。
自分の好きなようにToDoリストを決めていいのですが、ここで大事なのは、次の場所に移る時間ではなく、どこまでやったらその仕事が完了なのかを明確にすることです。Joelさん曰く、移動手段は自転車か徒歩がオススメだそうです。
パソコンの画面から離れる移動時間は、瞑想の練習に使いましょう。移動中はスマホや携帯はポケットにしまいます。仕事から少なくとも30分は離れて休憩しましょう。
Joelさんは、このメソッドを導入してから、いかに生産性が上がり、1日を行動的に過ごすことができ、労働時間が少なくなったかをブログに書いていました。
5. メールは1日の最初にチェックする
これは一見、逆なのではないかと思うかもしれません。基本的にメールはすぐにチェックするなと言われることの方が多いですが、私は最初にメールをチェックすることでかなり効果的に仕事ができています。1日の最初にメールをチェックすると、生産性を向上する理由がいくつかあります。
例えば、私が Bufferでやっているように、チームと離れて仕事をしているような場合は、メールをチェックすることで、自分が不在の間にチームの半分(もしくはそれ以上)の人がどのようなことをしたのか知ることができます。離れているチームと少しでも親密に仕事をしたい場合は、1日の最初にメールをチェックして、他の人と同じ情報を入れておくことが大事です。
最初にメールをチェックすることで、自分がすでに計画していた仕事をやるべきか、他の人がやっている仕事に合わせてやるべきことを変更した方がいいのか、すぐに決断することができるようになりました。
他にも、あなたが実践している効率良く働くためのアイデアがあれば、ぜひコメント欄にお願いします!
5 Scientifically Proven Ways to Work Smarter, Not Harder|Inc.com
Jeff Haden(原文/訳:的野裕子)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2014年03月25日 17:56
主体的・積極的な食養生にて明日の健康は創りだしていける。。。Vol.3/生活習慣の見直しは言わずもがな。。。Vol.2
■寒と熱、あなたはどっち? 花粉症はタイプを見極めてケア
杉本真奈美
随筆家
3月も半ばを過ぎ、ようやく温かさが増してきました。ほがらかな春の陽気に気持ちもうきうきすると言いたいところだけど、正直なところ花粉症でゆううつ......という人もきっと多いはず。
花粉症は体内の水分バランスの乱れが原因
漢方医学では、花粉症で見られる涙、目のかゆみ、鼻水、鼻づまりは「水毒証」の症状と見られています。水毒証とは、体内の水分バランスが悪い状態にあること。身体の一部分だけが水分過剰になったり、逆に水が不足している部分もあり、それが不調として現れている状態です。
さらに、水毒証は「寒」と「熱」のまったく逆の2つのタイプに分けることができるといいます。症状が次のうちどちらにより当てはまるかで判断を。
寒タイプ:鼻水がうすくサラサラしている、涙が目からあふれるほど出る
熱タイプ:鼻づまりがひどい、目のかゆみが強い、熱っぽい
寒タイプの原因は、ずばり「冷え」。漢方では、冷えたコップに水滴がつくように、冷えが水を呼ぶと考えられています。一方、熱タイプの人は、鼻づまりなどを起こすことによって熱を帯びたり、身体の中で炎症が起こっている状態。
寒タイプなら身体を温める性質のある食材を、熱タイプなら身体を冷やす性質のある食材をとるのがいいとされています。
寒タイプにおすすめの食材:たまねぎ、からし菜、さくらんぼ、舞茸、ふぐ
熱タイプにおすすめの食材:セロリ、クレソン、のり、昆布、しじみ、あさり等
また、寒タイプなら冷たい食べ物・飲み物を避ける、熱タイプの人は飲酒を控えめにするなども気をつけたいところ。
どちらも水分バランスの調整がポイント
とはいえ、どちらも水毒証であることは同じ。身体の水分バランスを整えるのには、適度な運動や半身浴が効果的です。ここでもポイントは、寒タイプなら運動後や入浴後に身体を冷やさないようにする、逆に熱タイプならのぼせないように気をつけます。
花粉症と一口に言っても、タイプによって対処法が逆効果になってしまうことも。そのときどきの症状をよく見極めてケアする姿勢が大事になりそうです。
[MY LOHAS]
■花粉症の軽減は1杯のお味噌汁がカギ!?
美肌コンサルタント
光田敦香
花粉症が増加した原因は?
4年前に私も含めて、花粉症の方が年々増え続けているので、原因を調べてみました。
私が読んだ記事では、まず原因の一つ目は、日本の杉の木の価値が低下したため、伐採されずに残っている量が昔に比べて増えたことです。そのため、花粉の飛散量が増えているそう。
二つ目は、コンクリートの道路面積が拡大したためです。地面が土だった時代は花粉が土に落ちるとそのまま土の中に吸収されるので空中に舞うことはないのですが、コンクリートでできた道路や地面では花粉はそのまま残ってしまうので、再度空中に舞ってしまい鼻や目に入り込んでしまうのです。
食事も花粉症の一つ!
また、私達の食生活も原因の一つだと思います。実際、私の食生活4年前までは、食事のバランスが良くなかったのです。その結果、血液がどろどろになりやすく、アレルギー症状や免疫力が低下し、4年前に花粉症になりました。
私が当時、免疫力を高めるために意識したことは、コンビ二のお菓子やインスタント食品やレトルト食品のような添加物の多い食品をできるだけ摂取しないようにし、手作りの和菓子、果物、スムージー、お味噌汁、スープなどをメインとした食事に変えました。
毎日のことなので、肌も美しくなり、代謝も高まりやすくなり、4年前の花粉症状から比べると、今年の方が花粉症の症状はましなのです。
お客様のカウンセリングを通じて感じることは、長年に渡り、日本の空気に合わない欧米型の食事のような高脂肪・高タンパク質の食べ物を食べつづけることで、血液がドロドロになり、体の免疫力が低下する方が増えていると思います。
湿度の高い日本では、肉の脂身をとりすぎると皮脂が過剰になり、皮膚に雑菌を繁殖させ、肌トラブルの原因につながります。
少しずつですが、日本人の身体に合った食生活を心がけることが、花粉症の症状や黄砂といった悪環境から肌を守れる体質をつくりあげることが大切だと思っています。
発酵食品である味噌を使った料理やにんにく、たまねぎ、長ネギ、しょうがなどを使った温かいお味噌汁で血液ドロドロを防いで免疫力を高めてあげてください。
更に、キノコ類(しいたけ、マイタケ、しめじ、えのき)等、刺激を受けた免疫細胞は、再び活性化し、免疫力が高まるので、かぜやインフルエンザにかかりにくくなるという効能があります。
是非、一日1杯のお味噌汁からでも免疫力を高めてあげてください。アレルギー症状に負けない、そしてトラブルができにくい肌を手に入れてください。
[スキンケア大学/美ログ]
■ホルモンバランスを整える食事で不調を改善!
栄養コンサルタント
エリカ・アンギャル
増える女性の不調の原因とは?
PMS(月経前症候群)や子宮内膜症など、婦人科系の疾患に悩まされる人が増えている背景にも食生活の変化が挙げられます。
偏った食生活が女性ホルモンのバランスを乱し、さまざまな不調を引き起こす原因になっているのです。
ホルモンバランスを崩す一番の原因は血糖値が急激にあがる食事。ホルモンは非常に緻密で繊細な仕組みで分泌されていて互いに連携をしているので、ひとつのホルモンバランスの乱れが他のホルモンにまで悪影響を与えます。
血糖値が急激にあがる食事を摂ることで、血糖値を下げるためのホルモン「インスリン」が大量に分泌されると、女性ホルモンをはじめとする他のホルモンのバランスにまでもが乱されることになるのです。
さらに若い女性たちに目立つのは食物繊維不足によるホルモンバランスの乱れ。食物繊維には過剰になった女性ホルモンのエストロゲンを吸着しホルモンバランスを整える働きがあります。
大豆イソフラボンを積極的に摂ることもとても大切。味噌や豆腐、納豆など大豆製品をよく食べていたひと昔前の日本女性たちは更年期障害の悩みとも無縁でした。
また、質のよい油を摂取することも重要なポイント。現代の女性たちは、油の摂取が偏りがちで、特に青魚に含まれるオメガ3やオリーブオイルに含まれるオメガ9などの良質な脂肪分が足りていません。避けたい油の代表選手であるトランス脂肪酸が子宮内膜症や不妊症などの原因になるとも言われています。
ホルモンバランスが、女性の人生のカギを握る
ホルモンバランスを整える食事は、妊娠・出産を控える若い女性たちにはとても大切。さらに、今の自分の食生活が子どもや孫の世代の健康にも影響を与えるということを覚えておいてください。
また、女性なら誰もが迎える更年期を快適に過ごすためにも、それ以前の食生活がしっかりとなされていることがとても重要。コツコツと心がけることが未来のあなたの美しさや健康を支えるものになるのです。
美しく楽しく年を重ねよう。エリカ流ハッピーエイジングの勧め。
海外では、女性は美しく年を重ねた女性こそ魅力的だという考え方が一般的。そのための努力に遅すぎることはありません。
私が今のような栄養の道に進んだのは、25歳のこと。会社員を経ての再出発でした。当時のクラスメイトには55歳の人もいて、その後栄養士として活躍されています。自分の心の中の小さな声に従うことが人生でもっとも大切なこと。それが、美しさや健康、全てに影響をしてくるのです。
[スキンケア大学/美ログ]
■花粉症、敏感肌。つらい症状にはまず知識を。
オーガニックコスメアドバイザー、ホリスティック美容家
林田七恵
花粉症と敏感肌、原因は同じです。
みなさまこんにちは、ホリスティックビューティー担当の林田です。大雪が降ったかと思えば急に気温20度を超えたり、春に向けて気温差の激しい時期になりました。
秋にもお伝えしましたが、気温20度を堺に上下を繰り返すと自律神経が乱れがちになり肌トラブルが増えてきます。また春は肌が敏感に傾くだけでなく、花粉症、喘息、アトピー性皮膚炎などあらゆるアレルギーが悪化しがちになる時期。
今悩んでいる人はもちろん、誰でも発症リスクのあることですから今回はその原因を考えながら、対策や予防策を見ていきましょう。
春はアレルギーが起こりやすい体内になっています。
ヒリヒリやかゆみ、鼻のぐずぐず、どれもとっても不快な症状ですよね。
すぐにどうにかしたくて、つい花粉症に効く薬は何?敏感肌には何を塗ればよい?とあれこれ薬を探してしまいがちですが、ちょっと待ってください。アレルギーは未だに原因不明の病気。実は西洋医学の得意とするところではないものです。ここは対症療法に走らずに、ホリスティックな観点から知識を身に付け、根本療法をコツコツと行うことがポイントです。
先ほど花粉症、喘息、アトピー性皮膚炎どれも春に悪化してくると書きました。花粉症は春に花粉が飛ぶことが原因だけど、他の2つはなぜ?と思いますよね。
実は花粉症も、原因は花粉だけではありません。喘息、アトピー性皮膚炎などと同様に
体そのものが春に「アレルギーを起しやすい状況」に傾くことが大きく影響しています。
その原因はやはり、自律神経の働きによるもの。私のコラムでは何度も登場する自律神経。緊張と活動を司る交感神経と、リラックスと修復・再生を司る副交感神経、この2つが交替しながら私たちの身体を動かしています。
春はリラックスと修復・再生を司る副交感神経が優位になっていく季節なのですがこの時、身体を修復をするために癌細胞やウィルスを排除してくれるリンパ球が増えることが分かってきています。リンパ球は通常であれば免疫力を高めてくれるありがたい存在なのですが、行き過ぎると過剰に異物に反応をしやすい状況を作り出してしまいます。これがアレルギー反応になります。
ですからアレルゲンとなる花粉などの物質をシャットアウトすることと共に、身体の自律神経バランスを整え、過剰反応しやすい状況を改善していくことが大切です。
春はアクティブに、身体を動かそう!
気温も暖かくなり身体もリラックス状態になって副交感神経優位になりがちな春。副交感神経はお肌の生まれ変わりも高めてくれますから、適度であれば美容にとってはうれしいことばかり。行き過ぎに注意するためには日中の過ごし方が重要になってきます。
日中は本来、交感神経優位になるべき時間帯。このメリハリがしっかりつくように日中体を動かすことを心がけていきましょう。
《改善ポイント》
1)日中室内でゴロゴロしていませんか?できる限り外に出て体を動かしましょう。また雨の日は普段よりもさらにリンパ球が増える傾向にあります。雨の日こそジムやプールなどで体を動かすようにすると効果的です。
2)食べ過ぎたり、だらだら食べをしていませんか?食事は副交感神経の働きを高めます。
しっかり時間を決めて食べ過ぎないことが大切です。
3)人参・リンゴジュースで朝食を抜くプチ断食がおすすめです。人参・リンゴジュースは体内での白血球内の免疫バランスを取ってくれることがわかっています。また朝食を抜くことで消化器に血液が集中せず全身の血流を増やして血液中の汚れも排泄されやすい状況になります。特に肌荒れで悩む人には人参のベータカロチンは皮膚や粘膜を強化する働きがあるのでお勧めです。
つらい花粉症や敏感肌でお悩みの方は、対症療法を試しながらも自律神経のバランスという観点から生活改善法をいろいろと模索していくと年々楽になっていくことと思います。
諦めずにコツコツと。体と向き合っていきましょうね!
[スキンケア大学/美ログ]
Posted by nob : 2014年03月24日 10:39
医療は外傷や急性疾患時の緊急避難手段として、、、慢性疾患には生活習慣の見直しと食養生、自らつくりだした疾患は自ら解消できる。。。
■糖尿病から各種がんまで
「頼れる最新薬」を徹底解剖
製薬業界の裏側にも迫る!
不祥事で揺れる製薬業界
頼れるクスリはどれなのか
「あなたが今飲んでいる高血圧症薬、宣伝費と販促費の塊だよ。やめちゃえば?」。50歳男性患者は主治医ではない専門医の言葉に困惑した。
最近、ニュース番組で自分が飲んでいるクスリがでかでかと映し出されている。「不正論文」「誇大広告」なる言葉が連呼され、製薬会社に家宅捜索まで入った。このクスリ、はたして飲み続けていいんだろうか──。
「国内製薬業界の信頼失墜ぶりは、かつての米国のよう」。製薬大手関係者は青ざめた表情で息をのむ。
日本において製薬業界はこれまで、薬害事件などを除けば、ネガティブなイメージはあまりなかった。むしろ給料が高く、将来性があり、人の命を救う産業としての正のイメージが強い。就職先としても人気の業界だ。
米国は正反対。イメージはすこぶる悪い。日本のように国民皆保険制度ではないという背景もあるが、ハリウッド映画ではしばしば悪役として登場し、たばこ会社、石油会社と並んで、不正に利益をむさぼる“悪の産業”としてイメージが定着している。
1990年代後半から2000年代初頭にかけて、メガファーマ(巨大製薬会社)は米国で自社製品に有利なデータを得るための大規模臨床研究を実施したり、研究や教育の名目で医者に多額の資金を提供した。都合の悪い臨床試験のデータを隠蔽したり、政治家への露骨なロビー活動も展開した。それらがメディアの報道で次々と暴かれた。
そして今、日本でも製薬業界の不祥事が次々と明るみに出た。
最たるものは、スイスのメガファーマの日本法人、ノバルティス ファーマが販売する高血圧症治療薬「ディオバン」に関する医師主導の大規模臨床研究で、データの不正操作が発覚した問題だ。
ディオバンが血圧を下げるだけでなく、脳卒中予防などにも効果があるかどうかを5大学が試験した際に、ノバルティスの社員(当時。現在は退社)が会社とは別の肩書で関与していた。
今年の3月には、国内最大手の武田薬品工業が高血圧症薬「ブロプレス」について、効き目を誇大宣伝していた疑惑が浮上した。
そもそもディオバンやブロプレスは、血圧を下げる効果自体は、1世代前のクスリであるアムロジピンに劣っている。それでもたくさん売れたのは、「降圧を超えた効果」などと煽るフレーズで、臓器保護作用など降圧以外の副次的な効果を盛んにアピールしてきたからだ。
製薬業界団体である日本製薬工業協会は、自主ガイドラインを策定し、12年度分から医療機関に提供した金額の情報開示を始めた。会員会社の総額は 5000億円規模に上った。会社別に見ると、武田薬品が1位、ノバルティスが4位。医療機関・医者と製薬会社の間で巨額の資金が流れる癒着の構図をうかがわせるものだった。
必要なのは血圧を下げること
頼れるのは古いクスリだった?
「やめちゃえば?」と言われた冒頭の男性患者は医者へ真意を尋ねた。「古いクスリのアムロジピンと、ディオバンを併用している患者にディオバンをやめさせても、きちんと血圧をコントロールできている事例をいくつも経験したから」だという。
では今まで自分はなぜ2剤も飲み続けていたのか──。男性患者は、いま一度、本当に頼れる高血圧症薬は何かと尋ねた。「血圧を下げるクスリだ。つまり古いほうのクスリ」。医者はそう答えた。
不正論文の発覚以降、「とにかく血圧を下げることが重要」という基本に立ち返った医者は多い。
クスリには、処方箋が必要な医療用医薬品と一般用医薬品があるが、製薬業界の主力は医療用医薬品であり、新規有効成分が入った新薬が中心だ。こうした新薬は治験と呼ばれる臨床試験を経て開発される。確率が著しく低いことを、しばしば「万が一」と表現するが、新薬が承認されるまでの成功率は、なんと約3万分の1だ。
例えば、開発が比較的容易な抗生物質はとっくに探し尽くされている。患者数が多くて製薬会社にとってはうまみのあった高血圧症薬や高脂血症薬なども出尽くした感がある。
がんの画期的新薬で
国内大手が“蚊帳の外”
現在の新薬開発の中心は抗がん剤など十分な治療法が確立していない分野であり、シティグループ証券マネジングディレクターの山口秀丸氏は「近年、大手製薬会社の開発の関心はますますがん領域に集中している」と言う。
抗がん剤以外で、大きな売り上げが期待されているものは、作用メカニズムが最も新しい「ファースト・イン・クラス」、あるいは同じ作用メカニズムのクスリの中で最も効き目が強い「ベスト・イン・クラス」のものが多い。
市場に出た後の競争力の面もあるが、それ以前に「安全なのは当たり前。かなりの有効性、新規性がなければ、審査当局から承認されなくなっている」(業界関係者)という事情があるからだ。
山口氏が大型化もある有望なものとしてリストアップした新薬候補もたいてい、いずれかが当てはまる。
日本のお家芸だった電機産業が著しく凋落する中、政府や産業界では、製薬産業を成長産業と位置づけて期待する声が高まっている。
しかし、欧米の製薬産業に比べると、まだまだ力不足だ。日本最大の武田薬品が世界のベスト10にも入らない。医薬品の輸出額と輸入額の差である輸入超過額は拡大する一方だ。
がんやリウマチなどを治療するバイオ医薬品が世界のヒット商品となっているが、国内製薬大手の多くは、バイオ医薬品の研究開発で出遅れてしまった。がんの研究についても、「一部のがんの先端領域では、完全に〝蚊帳の外〟となっている」と山口氏。80年代に日本の大手製薬会社の多くが、もうからないため、がん研究を中止していたことが後々まで影響しているのだ。
2000年以降の日本国内での新薬承認件数を見ても、米ファイザーや英グラクソ・スミスクラインなどの外資大手が上位を占める。32件と最も多いファイザーに比べ、国内最大手の武田薬品はわずか8件だ。
自国の創薬ベンチャー起源による主要製薬会社の開発品目数も米国334品に対し、日本はわずかに10品となんとも寂しい。
自治医科大学の間野博行教授が肺がん患者の治療に役立つ画期的な遺伝子を発見したときも、国内製薬会社ではなくファイザーが開発して「ザーコリ」という製品名で発売した。これについて、「日本のアカデミズムの成果を海外企業に持っていかれた」と嘆く業界関係者も少なくない。
がんの領域では今、「免疫チェックポイント阻害薬」という有望視されている新薬候補がある。小野薬品工業が種を持っており米企業と組んだ。その会社を買収した米製薬大手のブリストル・マイヤーズ スクイブが現在の小野薬品のパートナーとなっている。結局このタイプのクスリで日本メーカーは山口氏の言う“蚊帳の外”だ。
生みの親にも育ての親にもなれない新薬メーカーは、生き残っていけない。今ある製品にすがりついて営業やマーケティングばかりにカネを投じても、明日の種は育たない。
最新薬の解説&リストから
製薬業界のカラクリまで
頼れるクスリを知る決定版
製薬業界および周辺の不祥事が重なり、クスリへの不安を抱く患者もいるなか、『週刊ダイヤモンド』3月29日号は「頼れるクスリ」を大特集しました。
頼れるクスリとは何でしょうか。
例えば、山のようにある高血圧症治療薬のなかで頼りになるのは、安全性が高く、血圧を下げる力が強いクスリです。単に薬価が高かったり、製薬会社の売り込みが盛んなクスリが患者にとって最適とは限りません。医者が使いやすいと評価するものが頼れるクスリといえるのではないでしょうか。
また、本誌編集部では今回、開発後期段階にある新規有効成分の新薬候補、および発売まもない製品にスポットを当てました。
治験と呼ばれる新薬の開発と承認を目的とした臨床試験は、今回問題となったディオバンやブロプレスのような医師主導の臨床研究とは異なります。この臨床研究は、基本的にすでに販売されているクスリが対象であり、製薬会社のマーケティングが目的であることも。治験はもっと厳格なものです。その審査を経て市場に参入する新薬に注目しました。
糖尿病では2014年に6製品が発売されそうです。痛風、脳卒中予防、アルコール依存症では数十年ぶりに新薬が登場しました。
がんの領域では、免疫療法ともいえる新しいタイプの分子標的薬がまもなく登場しそう。乳がんでは抗がん剤を結合させた分子標的薬が発売されます。前立腺がんのホルモン薬では即効型が台頭しています。肝がんでは原因の8割を占めるC型肝炎が完全治癒の時代に入っています。
このほか緑内障、加齢黄斑変性、花粉症・ダニ、関節リウマチ、骨粗しょう症、うつ病、高血圧症、高脂血症、認知症、ワクチン、痛みなど病気別、あるいはがん種別に開発品を含むクスリの最新情報をお届けし、製品と開発品のリストも掲載しました。
クスリの表と裏を見せる総力特集
本当に頼れるクスリへ辿りつけ!
さらに製薬および関連業界についても徹底解剖しました。
「誇大広告疑惑が浮上した武田薬品工業に何が起きているのか」「臨床研究の結果を有利に見せる『スピン』手法の手口」「大型薬の特許が切れ、参入続々のジェネリック市場」「儲け過ぎた調剤薬局を襲う14年度診療報酬改定の逆風」「初任給30万円もある薬剤師 就職率92%の超売り手市場」などなど。
このほか「市販薬の徹底攻略法」「高齢者クスリ漬けの危険」「3食昼寝付きで1000万円を稼いだプロ治験者の実態」など見どころ満載。製薬会社、バイオベンチャーの各社業績一覧では、本誌編集部が独自に集計した新薬候補数を掲載。ベンチャー一覧には実力と将来性を図る目安となる提携実績も整理しました。有望銘柄探しにお役立てください。
クスリの表と裏をお見せする本特集が、頼れるクスリへ辿りつく一助になれば幸いです。
(『週刊ダイヤモンド』副編集長 臼井真粧美)
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年03月24日 10:05
水のごとく、、、そして風のごとく。。。Vol.2
The river current never stops flowing, and its water keeps changing...
The blowing wind will never be able to come back to the present same place...
[CLIPS]
Posted by nob : 2014年03月23日 14:53
主体的・積極的な食養生にて明日の健康は創りだしていける。。。Vol.2/生活習慣の見直しは言わずもがな。。。
■ある日突然、花粉症が治るは本当?
手料理を食べるようになって改善するケースもあるとのこと。マスクなどの防御策とともに、食事にも気を配りたいところだ。
花粉症の人にはつらい季節がやってきた。今年も悪戦苦闘している人が少なくない。しかし、ごく稀ながら「特に対策をしていないのに、急に花粉症が治った」という声を聞くことがある。
果たしてそんなことがあり得るのだろうか? アレルギー治療を多く行う、エミーナジョイクリニック銀座の伊東エミナ先生に伺った。
「ある年に突然、花粉症が治ることはあり得ます。一番多いのは、腸内環境の変化によるケース。たとえば美容のために乳酸菌などを摂りはじめたところ、腸内環境が改善されて、花粉症が治ったという方はいらっしゃいます」
一見、花粉症とは縁遠いように思える腸。しかし腸内環境が悪くなると、食物成分の消化が不十分となってしまい、体内の状態が悪化。少しの花粉にも防衛反応が働いて、くしゃみや鼻水などが出やすくなるようなのだ。
「花粉はあくまでアレルギー反応の引き金。根本は、体内の状態が悪化することで、花粉にも防衛反応を示すようになることです」と伊東先生。インターネットでは、会社を退職したことでストレスがなくなり、花粉症が治ったという人も見られたが、「これもストレス減少で血流が良くなり、体の状態が改善。花粉への防衛反応がなくなった形です」とのことだ。
同様に、背骨のゆがみが治ることで花粉症が改善されることもあるらしい。背骨のゆがみは血流を悪くさせ、全身の“冷え”を起こす。冷えが強いと体はその状態を治そうとするため、風邪を引いた時と似た状態に。そこへ花粉が飛びこむと、より防衛反応を示しやすくなるようだ。
そのほかではこちらも稀な例だが、妊娠・出産を経て花粉症が治ったという話も聞く。
「これは未解明なことも多いのですが、胎児は免疫学で見ると母体にとっての『異物』なんですね。その胎児を長期間にわたり体内で育てるため、母親の免疫力やホルモン状態が大きく変わることも多いんです。これにより異物へのキャパシティが広くなり、花粉症が出なくなるのかもしれません」(同)
なお、引っ越しにより花粉症が治ることもあるという。単純に花粉の少ない地域に移るケースだけでなく、前の住居のダニやホコリ、あるいは化学物質がなくなることで改善する場合もある様子。これらが多量にあると合わせ技で花粉症になりやすいため、その原因がなくなることで防衛反応が起きにくくなるようだ。
今回挙げた例は、あくまで「レアケース」。とはいえ、いろいろな原因が積み重なって花粉症になるというメカニズムを考えれば、多くの人にとって決して無縁な話ではないかもしれない。
(有井太郎)
■花粉症対策におすすめの食材は?
暖かな春が近づくにつれて、猛威をふるい始めるイヤなものといえば花粉。花粉症で、毎年くしゃみや鼻水、目のかゆみに悩まされている人も多いのではないでしょうか。食生活で花粉症対策を意識するなら、アレルギー症状の緩和と免疫力向上がポイントです。
まず、アレルギー症状緩和には乳酸菌を多く含むヨーグルトやナチュラルチーズがおすすめ。乳酸菌には体内で起こるアレルギー反応を調整する働きが期待できます。また、サバなど青魚に豊富に含まれるEPA・DHAも、アレルギー症状を引き起こす化学物質が作られるのを抑制します。それからホタテやウナギに多く含まれる亜鉛は、免疫機能に関与するT細胞の働きを高める働きがありますよ。
ドリンクには緑茶をチョイス。アレルギーのかゆみを引き起こすヒスタミンの放出を防ぐ、抗ヒスタミン作用が期待できるカテキンがたっぷりです。これらを摂取して、少しでも「あのつらさ」を和らげたいですね。
北嶋佳奈=監修
管理栄養士&フードコーディネーター
富永玲奈(アート・サプライ)=取材・文
[いずれもwebR25]
Posted by nob : 2014年03月23日 14:10
水のごとく、、、そして風のごとく。。。/また旅立つ君へVol.12
流れる水は先を争わず
いつも自然体でいようということだ
自分だけ少しでもよくなろうと思い
無理をして先へ先へと急いでいくとする
結局人を押しのけることになり
そこから争い事が生まれてくる
水のように流れていけば
この世はすべてうまくいく
流れる水は一緒に流れているだけで
まわりを押しのけているわけではない
どんなに急いでも
まことに円満にこの世の摂理の中におさまっているのである
[立松和平/いい人生]
Posted by nob : 2014年03月23日 06:03
主体的・積極的な食養生にて明日の健康は創りだしていける。。。/「色々な食べものをバランスよく」は今日の最小限。。。
■がんにならない食べ物
ロバスト・ヘルスの川口
内科医の私が診療していると、よく患者さんから訊かれることがあります。
「先生、がんにならないためにはどんな食べ物を食べればいいですか?」
がんの治療をしている患者さんから「このがんに効く食べ物はありますか?」と訊かれることもあります。
確かに、「これを食べればがんに効く!」とか「これを食べてがんが治った!」など、広告などで目にするような気がしますが、果たしてどこまでは科学的に信じられる話なのでしょうか?このコラムで考えてみたいと思います。
がんと食べ物の関係を明らかにするためには、私たちの行っているような「コホート研究」が最もいい方法です。健康な人を集めて、まず、食生活を調べます。
例えば、コーヒーとがんの関係が知りたければ、コーヒーをどれくらい飲むかあらかじめ調べておきます。それから、10年、20年後、コーヒーをたくさん飲む人と飲まない人のグループでそれぞれがんになった割合を比べます。もし、コーヒーを飲むグループの方ががんの割合が多ければ「コーヒーはがんと関係があるのかも!」ということになります。
そして、その因果関係をはっきりさせるには、研究室での細胞を使うような実験や、動物実験などの結果もあわせて結論が得られることが実際には多いです。
さて、ではどんな食べ物を食べればがんにならないのでしょうか?国立がん研究センターでは今までの研究をまとめて公表しています。それを見てみることにしましょう。
まず、野菜とがんの関係をみると食道がんでは罹患リスクが下がるという関係が「ほぼ確実」にあるようです。胃がんでは罹患リスクが下がる「可能性」があります。
しかし、一方で他のすべてのがんではデータが不十分でこれといったことが言えません。果物でみると食道がんで罹患リスクが下がるという関係が「ほぼ確実」にあるようで、胃がん、肺がんでは罹患リスクが下がる「可能性」があると言えます。
その他のがんと食事をみてみると、罹患リスクが下がる関係が「ほぼ確実」にあるのはコーヒーと肝がん、上がる関係が「ほぼ確実」にあるのが熱い飲食物と食道がん、食塩と胃がんです。
実はこれだけなんです。実はそれほど分かっていないのが実情です。それには色々な理由があると言われていますが、私はがんの発症にかなりの部分関係していると考えられる遺伝的素因、すなわち体質の関係を今までの研究では、考慮することができなかったことが大きいのではと考えています。
今後、新しい発見が山形分子疫学コホート研究から出て行くことを期待しますが、当面は当たり前といえば当たり前ですが、「色々な食べものをバランスよく」ということに尽きるでしょう。色々な食べ物を食べることにより何よりも、「リスクを分散」することができます。
例えば、ある食べ物にがんに関係するような、今まで分かっていない物質が入っていたとしても、たくさん色々な食べ物を食べることによって、多くの量を日常的に取ることを避けることができます(もちろん他にも色々な利点があります)。
現時点では、「健康に王道はなし」です。
[newsdig]
Posted by nob : 2014年03月22日 23:07
人生は旅だ。。。Vol.5/また旅立つ君へVol.11
人間には大きく分けて二つのタイプがあると思う
こつこつと努力を積み上げ
ついの棲家をつくり
それを最終の目標とする人である
世間的な名声をかち得たら
そこに安住する
守りに入るのである
もう一つのタイプは
絶対に安住しない人である
こつこつと努力を積み上げなければ一つの世界は築き上げることはできないにせよ
できた瞬間にそれを破壊してしまう
旅というのは
出発があり到着があり
人生のようなものなのだ
そして
旅とは本来無一物であり
社会の属性を捨て
身体一つを運んでいく
死と再生とを限りなくくり返すことこそ
優れた表現者である
再生すればまたそれを壊してしまうのだから
彼に安住の地はない
[立松和平/旅暮らし]
Posted by nob : 2014年03月20日 19:05
人生は旅だ。。。Vol.4/また旅立つ君へVol.10
旅は楽しい
知らなかったことを知り
どんどん豊かになっていく自分を感じることができるからである
この世の多様性を知ることが
私たちには何より必要である
他者を認める心があれば
自己主張によるいがみあいもなくなり
戦争をすることもなくなる
旅の効用ははかり知れない
[立松和平/旅暮らし]
Posted by nob : 2014年03月20日 19:02
人生は旅だ。。。Vol.3/また旅立つ君へVol.9
旅をしていると
次から次へと多様なものと出会い
これに対してどんな態度をとったらよいのか決めかねることがある
つまり拒絶してその場を去っていくこともあるのだ
それは旅をする自分が
その相手に試されているということだ
試され拒絶されたりしたのでは出会わないほうがましである
そんなことがないよう旅先では感覚を全開にしていなければならない
目の前に現れるものすべてを柔軟に取り込んでしまう
そうすれば自分はもっともっと大きくなることができる
日本全土ばかりでなく
この地球をも丸呑みにすることだってできる
[立松和平/旅暮らし]
Posted by nob : 2014年03月20日 18:59
人生は旅だ。。。Vol.2/また旅立つ君へVol.8
旅のよいところの一つは
いつも暮らしている視点
つまり日常生活の側からではなく
自分が本来持っている感性から対象を見ることができる点だ
自分の目の高さは身長の分であり
そこからものを見る感覚が知らず識らず身についている
だが地面に寝そべれば蟻の視点になり
木に登れば鳥の視点になる
水中を泳げば魚になり
カヌーでいけば水鳥になる
そのように視点の位置をどんどん変えていくことが
旅に出るということだ
[立松和平/旅暮らし]
Posted by nob : 2014年03月20日 17:03
人生は旅だ。。。/また旅立つ君へVol.7
どこでどうしていようと
私たちは旅をしている
旅は生きるということ
旅を重ね
旅に棲む
[立松和平/旅暮らし]
Posted by nob : 2014年03月20日 16:54
その時々の自分自身をあるがままに受け容れることから、、、日々の小さな納得の積み重ねが幸せへの途をつくっていく。。。
■人目が気になるとき、本当に気になっているのは「自分の心の目」
年度が替わると、新しい環境での活動や初めての仕事に取り組む機会が増えます。人前では明るく元気に振る舞うけれど、内心は「人目が気になって仕方がない」という方はいませんか?
人目が気になるメカニズム
私たちが人目を気にするのは、「悪く見られるのではないか」「批判されたらどうしよう」「きっと○○と見られちゃう。○○と思われないようにしなきゃ」という不安や緊張が自分にあるから。
たとえば、自分が太っていると気にしていると、スイーツを食べている自分をどう見られるのか人目が気になると思いませんか? 自分に彼氏がいないことを気にしていると、「彼氏がいない女」と見られているような気がして、周りの目が気になりませんか?
人目が気になるというのは、実際は「人があなたをどう見ているのか?」ではなくて、「自分が自分をどう見ているのか?」が原因となっている場合がほとんどのようです。
自分を見る目を変える
自分を「太っている」「彼氏がいない女」と見ていたのは、周囲の人ではなく「自分自身」だったとしたら...。「自分がしていること」と認めることができたら、それを続けるのか・止めるのかは「自分の意志で決められること」になるでしょう。
「太っている」「彼氏がいない」など、あなたが気にしていることは、そんなに悪いことなのでしょうか? あなたと同じ条件の人があなたの隣に居たら、軽蔑や批判をするでしょうか。
「他人なら許せるのに、自分だけは許さない!」と自分に厳しくなっていませんか。もう少し優しい目で自分を見てあげてはいかがでしょう。
[glitty]
■「将来」の幸せではなく「今の自分」を幸せにしてくれるものに目を向けるんだ
誰もが時々、「これさえあれば、満たされるのに」「こうなったら、幸せになれるはず」という罠に陥ります。将来手に入るであろう報酬やご褒美をエサにやる気を出すのは良いことですが、そのような幸せに固執するのは良くありません。
「The Simple Dollar」で、人間は将来幸せになるために自分が求めているものに、かかる時間やお金の計算に囚われることがあると指摘しています。
また、たった一つの変化にたいして期待し過ぎるきらいもあります。実際には、それだけで人生が変わるような変化はありません。ある変化によって、ずっと不幸だった人生がずっと幸せな人生に変わると本気で信じているのであれば、それは失望に変わるでしょう。新しいパソコンは人生を変えません。夢に思い描くような恋愛も人生を変えません。そのようなもので人生は変わらないのです。
そうではなく、今の人生や生活で自分を少しでも幸せにしてくれるものに目を向けましょう。先のことばかりを見ていると、今あるものの価値を落としてしまいがちです。これだけは覚えておいてください。幸せというのはあなたの心持ちのことです。どんなものを持っていようが関係なく、いつだって自分の中にあります。
"If Only I Had This Thing, I Would Be Happy" | The Simple Dollar
Walter Glenn(原文/訳:的野裕子)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2014年03月17日 20:59
歩み始めること、、、そして歩み続けること。。。
■『一勝九敗』
経営者の一冊
東横イン社長 黒田麻衣子
父でもある東横インホテル創業者・西田憲正が、いつも私に「10回失敗できる人はいないんだよ」と言っていました。
その意味は「10回失敗したら絶対に次は成功できるのに、10回失敗できる人はいない」ということです。
2006年、東横インは、容積率違反の問題で窮地に立たされていました。一旦退職してドイツにいた私が緊急に帰国し、「私が会社を守らねば」と、決意をした時期に、本書を手に取りました。題名が、父が繰り返し私に言っていたことと、ほとんど一緒だったからです。
私に10回も失敗できるのかとも思いますが、失敗するほどに勇気を持って挑戦していきたいと決意しています。
[PRESIDENT online]
Posted by nob : 2014年03月17日 20:42
今日の想像力の問題、、、巡って明日の我が身に還る。。。
■人は皆老いて、障害を持ち、そして死にゆく
訪問看護師のmina
核家族化がもたらした最大の弊害は、高齢者と一緒に暮らす体験をなくしてしまったことだ。人は目の前にお手本、すなわち自分より先を生きている人(高齢者)がどうなっていくのかを見ることができなくなった。人はビジュアル的なモノ無しにそういうのをなかなか追体験できない。今の自分の状態が永遠だと錯覚する。
だからみんな老いた時に、機能低下した自分の体や心に絶望し「こんなはずじゃあなかった」とこぼす。そして最後は何らかの形で最後に死に遂げなければならない。私達、看護師はすべての人生の段階の人々を看る経験を仕事上する。もちろん、お看取りも含めて。そして心に思う、「いえいえ、誰しも歳を経てこうなるんです」と。仕事の体験から「生老病死」をシステマティックにも感情的にも知っている。
看護師だからといって、老いについて全く考えられない人生を送ってきた人(核家族化している今の日本に生きる人達)の気持ちに添える言葉を準備できるかというと、皆がそういうわけではない。もちろんそういった訓練を受ける機会もある。しかし多くの看護師は「こんなはずじゃなかった」とつぶやく患者に対してたいがいは「自分にはわかっていたよ」と心のどこかで感じている。
しかし、核家族で老いや病気を目にする機会が減っている中で家族生活を送ってきた人には「老い、そして病い」はまさに衝撃なのだ。
若い時は「ずっと今のコンディションがスタンダードなのだ」と無意識に感じている。そして中年になれば「まあ、歳をとればこんなものだろう」とそれなりに納得はする。でも急な病に犯されたり、もっと歳をとって心も体も病むことを体験した時に衝撃を受ける。「こんなはずじゃあなかった」と。
すでに時は遅い。高齢者や障害者に対して若い頃、自分がどんなに無関心で冷たかったかをそこでやっと初めて知るのだ。
だからこそ「人はそのようにして老いていく」ことをよくわかっている看護師という職種はもっと若い人や元気な人に「あなたも必ず老いてやがては障害を持つんです、だから、そういうことになっても心配なく暮らせる社会を作りましょうよ」と啓蒙していく使命を担っていかねばならないではないだろうか。
最近よく、そんな事を思うのだ。健康な時にはわからない。テレビで、そして小説で、あらゆるメディアを通じては知っているけど「自分の事」そして「家族の事」としてすぐには受け止められず、捉えられない。
老いる事、そして障害を持つ事。それはあなた自身、またあなたの家族であるという事に気付かせてあげなくてはいけない。どういう方法が一番効果的なのかまではわからない。でも、まずは生活者である人一人一人に知らせなくてはいけない。元気なうちから教えてあげなければいけない。それが支え合う社会を築くためにできる事の一つではないだろうか?
[newsdig]
■【美しいサプライズ】友人が「がん宣告」されたらどうする? / 誰かのためにここまで出来ちゃうあんたたちって本当に最高ッ!
今年2月、グレディ・マッケンナさんの友人のひとりが、仲間たちに「写真撮影をしよう」と声をかけました。実は数か月前に、グレディさんは乳がんの宣告を受けたのです。
集まった仲間たちは11名。なにやらサプライズの気配。いったい何が起こるのでしょうか?
本日は海外サイト「Bored Panda」に掲載されたある女性たちの熱い友情のお話をご紹介いたします。
さて、集まった11名の女性たちが向かった先は、美容院。写真撮影のためのおめかしだと思いきや……全員髪の毛を全部剃ってしまいました!!! というのも、がん宣告を受けたグレディさんは既に髪を剃っていて、彼女が淋しく感じないように、この際、皆で全剃りすればいーんじゃない? ということだったのです。
11名の中にはグレディさんのお姉さん(または妹さん)もいらっしゃるようで、「彼女は素晴らしい人なの。自分にはこれくらいしかできないけれど」と話しています。また別の友人は「彼女が経験することを想像したら、このくらいへっちゃらよ」と話しています。
美容院で、ひとりずつ、髪の毛を剃っていきます。なかには涙ぐんでしまう方もいますが、みなさん全員、とっても晴れやかな表情です。剃り落した髪の毛をつかんで、ガッツポーズを決めるシーンも。
剃ってしまったあとに、友人の1人がこんなことを言ったそうです。「髪の毛はたかだか体の一部分。一番大切にするべきなのは、プライドよりも健康だってわかったわ」
そしておそろいの帽子をかぶり、スタンバイします。グラディさん本人がやってくると、全員が帽子を取って、全剃りお披露目! まさかのサプライズに涙を流しながら、1人ずつと抱き合い「あんたたちって本当に最高ッ!」と笑顔で言いました。
その後、プロの方にお化粧をしてもらい、おそろいの衣装で写真撮影を開始! ホテルのお庭にソファーを持ってきて一人ずつ撮ったり、みんなで撮ったり。おどけた仕草やおふざけも。この写真だけ見たら、少女たちのようなはしゃぎっぷりで、悲しいことなんかなんにもなさそうに見えてしまいます。それだけ、みんな生き生きした表情です。
グレディさんにぜひ教えたいのが、グレディさんの苗字は日本語にすると「負けないで!」という激励の意味になるんだよな。「負けるな、マッケンナ!」
この美しいサプライズがインターネットに公開されると、瞬く間に大反響。Facebookではすでに3500件近くのコメントが寄せられています。
「涙が止まらないわ。こんな素敵な友達がいるなんてなんて幸せなの」
「美しい心を持った美しい女性たち」
「とても美しい行動。素晴らしい写真。動画を見ている間ずっと泣いてしまった。でも良い涙だった」
などの声も。
「友達のために髪の毛剃れるってすごーい」というだけで終わらせないで。少し自分に問いかけてほしい。たかが髪の毛ではなく、自分の大切にしているものやプライドを手放せる。それほど愛はあなたのまわりにありますか?


参照元:Bored Panda
執筆=黒猫葵
[Pouch]
Posted by nob : 2014年03月17日 20:21
???
好きなのが自分自身ではなく本当にその相手なら、、、ただ静かに想い続けていればいい。。。
■好きな人に恋人がいることがわかったらどうする?「あきらめる 63.3%」
好きな人に恋人がいることがわかったらどうする?「あきらめる 63.3%」
社会人になると出会いが少ないと思われがちですが、意外と新たな出会いに恵まれることがあります。仕事を通じて知り合った人に恋してしまうこともあるでしょう。しかし、好きになった相手に恋人がいることも。そんなとき、皆さんならどうしますか? 先輩社会人に聞きました。
Q.好きな人に恋人がいることがわかった場合、どうしますか?
A.あきらめる......63.3%
別れるのを待つ......21.1%
負けずにアタックする......12.8%
そのほか......2.8%
半数以上の人があきらめてしまうとは! 消極的な人が多いのか、それとも気力がないだけなのか......。理由が気になりますね。
■もっと早く出会いたかった!
・「ドロドロにはなりたくない」(女性/28歳/人材派遣・人材教育)
・「人の幸せを奪ってまでの熱意はない」(男性/27歳/小売店)
・「こっちを向かせるほどの自信がない」(女性/30歳/情報・IT)
恋を諦めてしまう人たちは、面倒なことを避けたがるタイプかも。恋人と別れると言ってくれたとしても、実は二股をかけられていた、ということもなきにしもあらず。ご縁がなかったと思って、次の恋へ進むようですね。
■いつかは振り向いてくれるはず
・「待っている間、冷静に考える。そしてしばらく時間が経ってもまだ好きならアタックする」(男性/33歳/情報・IT)
・「いい友人でいられたらそれはそれでいい。ただ、なにかあった時には頼りにしてほしい」(男性/31歳/その他)
・「なにも行動はできないけど、諦められない」(女性/31歳/医療・福祉)
恋人と別れるまで待つタイプは、好きな気持ちを諦められないのでしょう。片思いを続けることが苦しくても、好きになってしまったものはしょうがない! いつか振り向いてくれますように。
■当たって砕けろ!?
・「後悔したくない」(男性/34歳/学校・教育関連)
・「結婚してないならまだチャンスはある」(女性/26歳/通信)
・「当たって砕けるのであれば吹っ切ることができる」(男性/34歳/学校・教育関連)
負けずにアタックする人たちは、わずかな可能性にもかけたい様子。ダメだったとしても、何もしないよりスッキリしそうですね。
■好きな気持ちは伝えたい
・「思いだけ伝える。自分がああすればよかったという後悔をしないように」(女性/26歳/団体・公益法人・官公庁)
・「別に恋人がいても気持ちを伝えればいいのでは?」(男性/32歳/情報・IT)
・「完全に諦めはしない。けれどその人のためだけにフリーの状態を続けるほどでもない。他にいい人がいないか探す間、横目で機会をうかがう程度」(男性/30歳/小売店)
叶わぬ恋でもかまわないので、気持ちだけは伝えておきたい。そう思う人も少なくありませんでした。自分の気持ちを切り替えるためにもいいかもしれません。
男女問わず、すてきな人ほどすでに恋人がいるものです。それでも、思い切って自分の気持ちを伝えてみれば、もしかしたらいい返事がもらえるかも!? 恋人がいると思われているだけで、じつはフリーの場合もあるので、アタックしてみるのも悪くなさそうです。
文・OFFICE-SANGA 藤井蒼
調査時期:2014年2月
アンケート:フレッシャーズ調べ
集計対象数:社会人580人(インターネットログイン式アンケート)
[マイナビスチューデント]
年々早くなっていい、、、それは自然なこと。。。
■年々早くなっていく時の流れを、子どもの時のようにゆっくりに戻す方法
年を取ると時間が経つのが早く感じるのは、古今東西同じようです。米紙ウォールストリートジャーナルではDan Arielyさんが、年を取ると慣れ親しんだ生活パターンに陥ることが多いので、時間が経つのが早く感じるのだと説明しています。
私たちは、時間を記憶や思い出の積み重ねとして認識しているので、新しい経験が減ると、興味深いことで記憶を埋める機会が減るように感じるのでしょう。
年を取るにつれ、より早く時が過ぎていきます(より正確に言うなら、時は過ぎていくように感じます)。人生の最初の数年間は、感じるものすべて、やることすべてが目新しく、初めて経験することがたくさんあるので、記憶にもしっかりと残っています。
しかし、年月が経つと、初めて経験することがどんどん減るようになります。それは、すでに経験したことがたくさんあるからでもあり、慣れ親しんだ日常生活に囚われるからでもあります。例えば、先週起こったことを1日ずつ思い出してみてください。おそらく特別なことが何も無い場合は、月曜と火曜の違いも思い出すのが難しいのではないでしょうか。
このような状態になったらどうすればいいのでしょうか? 新しい経験をさせてくれる新しいアプリを入れたり、今までやったことがないことを見つけたり、食べたことのない料理を食べたり、行ったことのないところに行ったりした方がいいです。
新しいアプリのような新しいことを取り入れれば、生活はより変化に富んだものになり、新しいことをやろうと思わせてくれ、時間の流れをゆっくりにして、幸福感を増してくれます。新しいアプリのようなものが見つかるまでは、少なくとも週1つは新しいことをするようにしてみましょう。
新しいことをするのはそんなに難しいことではないはずです。自分の「コンフォートゾーン」から抜け出すことや、30日間何か新しいことにチャレンジするのがいい、というのは前にもお伝えしましたし、経験に対してお金を使った方が満足感が高くなる傾向にあります。そのように少しずつ新しいことをやるようにすると、時間の流れがゆっくりになっていくでしょう。
A Trick to Help Outrace Time|The Wall Street Journal
Thorin Klosowski(原文/訳:的野裕子)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2014年03月17日 20:10
また旅立つ君へVol.6/Be free and happy!!!
■世界は広く、あなたは小さい。だからやりたいことをやり、それを嫌う人のことは考えなくていい
自分は家族や友だちから認められていないんじゃないか、みんなが自分のことを裏でどう言っているのか、と気にするあまり、攻撃的な態度を取ってしまうことがあるかもしれません。心当たりがある人は、そろそろそんなバカげたことを考えるのはやめて、自由になった方がいいです。
この手のネタはライフハッカーでも何度か紹介したことがありますが、今回のアドバイスはさらに秀逸だったので紹介することにしました。
誰でも人に好かれたい、認められたいと思うものですが、受け入れられなかった時のことを考えると怖過ぎて、人を遠ざけたり、逆に攻撃したりする人がいます。これは人として良くないことです。
作家でコンサルタントのJulien Smithさんも、そんな人たちと同じように、相手がどう思っているのかということを気にし過ぎていました。つい最近まで、人の反応にビビリ過ぎて、精神的なサンドバック状態になっていました。Smithさんは、そんな状態から抜け出す方法を教えています。相手が自分のことをどう思っているのかを気にし過ぎず、自分に自信をつける完ぺきなガイドです。
人は常にあなたのことを評価しており、そのことについてはどうすることもできません。相手に好きになってもらう必要もありません。それは相手の問題です。世界を変える人というのは、そのような孤独感や負け犬のような邪魔な感情を振り払うことができる人です(実際、他の人にあなたの世界を変えることはできません)。
Smithさんは、このことを痛烈に分かりやすく書いています。その中でも大事な言葉を引用しましょう。
インターネットが嫌いになっていく本当の理由は、みんなが自分のことを影で嫌っているんじゃないかという被害妄想が確かなものに思えるからです。
うれしいことに、それはまったくの事実無根です。まず最初の大事な真実は、ほとんどの人はあなたが生きているかどうかすら気にしていないということです。このことを受け入れると、本当の意味で自由になれます。世界は広く、あなたは小さい。だから、自分のやりたいことをやり、それを嫌う人のことは考えなくていいのです。
(中略))
今まさに、孤独や負け犬のようなみじめな気持ちになる、辛い状況に置かれているかもしれません。しかし、心配することはありません。誰もが一度はそんな気持ちを味わいます。そんなことはよくあることだと、そろそろ気付いた方がいいです。どんなに成功している人や、世界一幸せそうな人でも、そんな経験をしているはずです。しかし、彼らはそれを通り過ぎてきました。あなたもそうしましょう。
誰かに誉められれば調子に乗り、けなされると凹んでしまうような、極端に神経質な人は、このアドバイスを参考にしてみてはいかがでしょうか。
Melanie Pinola(原文/訳:的野裕子)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2014年03月13日 14:41
私のケースは、3人で2万円ずつ、資本金6万円で合同会社を設立しました。。。(笑)
■お金がない状態から起業することは可能なのか?
沖成章
目覚めのコーヒーが元気の源です。独立・起業準備コンサルタントの沖 成章です。
独立・起業をすると聞くと、資金を調達するために銀行から融資を受ける必要があったり、ベンチャーキャピタルに投資してもらう必要があったりと、何かと初期段階でお金がかかるイメージがあるかもしれません。
確かに、そのようにして資金調達をしてから起業するというケースも多くあります。そして事実として独立・起業をしたいなぁと思っている人が、実際には中々出来ないでいる理由の一つにお金の問題があります。
そのため、
元々資金を持っている人でないと起業出来ない。
誰かから支援をしてもらわないと起業出来ない。
銀行から融資を受けられるレベルの事業企画がなければ起業出来ない。
十分なお金を貯めてからでないと起業出来ない。
世間ではこのような考えが一般的になっています。実際のところはどうなのでしょうか?
■起業にお金はかからない
結論から言うと、独立・起業はほとんどお金をかけずに行うことが出来ます。もちろんお金があるに越したことはありませんが、ないからと言って出来ないというものではありません。また、「会社を作る」ということに関しては、今はほとんどお金がかかりません。
以前は株式会社を設立するのに最低でも1,000万円の資本金が必要でした。しかし、今は最低資本金制度が廃止されたため、ご存じの通り資本金1円でも株式会社の設立が可能です。
もちろん、資本金が少ないことに対するデメリットがあったりするので一概に良いとは言えませんが、コストを最小限に抑えて会社を設立して起業するということは可能です。
■起業とはなんぞや
さて、ここまで読んで、
「そんなこと、わかっとるわー!」
って思う方もいるでしょう。確かに、「会社をつくること」と「独立・起業すること」は別物です。では、「起業」とはそもそもどのようなことなのでしょうか? オフィスを借りて備品を買ってそこで事業をする、こんなイメージはありませんか? 確かに、このようなスタイルは初期投資をする必要があるのでお金がかかります。
ですが、必ずしもこのようなスタイルが「起業」というわけではありません。
例えば、
自分の手作りのアクセサリーをネット通販で売る
自宅で栽培した野菜を直売会を行って売る
料理教室を開催して自分の調理技術を売る
これらも「起業」になります。
「起業」とは、自身が提供出来る商品や知識、サービスを提供することで、その対価としてお金を得るということです。上記に紹介した例は全て私が見てきた実例であり、かつ初期費用もほとんどかかっていません。
アクセサリー販売の例は私の中学時代の友人の例なのですが、その人は元々趣味でアクセサリーを作っていて、作った作品をブログで定期的に紹介していたら反響があったので販売することにしたそうです。
自分でネット通販用のサイトを立ち上げ、販売を開始しました。元々はサラリーマンとして勤務をしていましたが、現在は退職し、アクセサリーのネット販売を中心とした事業を行っています。
この際、かかった費用と言えばアクセサリーの原価と通販用のサイトの運営費です。手作りアクセサリーの原価は高くありませんし、通販サイトもサーバー代とドメイン代がかかるくらいなので、実際にかかった費用は数千円です。ちなみに、通販サイトの作成を外注すると数万から数十万の費用が掛かります。その後のアップデートでもお金がかかります。なので、自分で作ることをおススメします。今は専門書がたくさんあるので、一冊読みながらやれば誰でも作成出来ますしね。
このように、起業と一言で言っても様々なスタイルがあります。何かを売る、何かを提供するということの対価としてお金を得れば、それはビジネスです。あとはそのビジネスを自分なりの形でブラッシュアップさせていけば、自分のビジネスとなり最終的には独立・起業に繋がります。
立派なオフィスや事業所をかまえている社長や起業家の方たちも、スタートアップの段階では同じような形で始められていることが多いです。初めからお金があったわけではなく、徐々に利益を上げてきたからこそ今の姿があるのです。
■実際にお金がかかるとき
とは言え、実際にお金のかかる場面も出てきます。私自身はブログのサーバー代、メルマガスタンド代、シェアオフィス代くらいで始めたので、かかったお金は3万円くらいでした。法人登記に関しても、株式会社を作るならば20万円以上かかりますが、合同会社ならば7万円弱で設立できます。なので、10万円以下でも全く問題なく起業出来ます。
もちろん、株式会社を設立しちゃんとしたオフィスを構えて備品も揃えて人も雇っていくのならば結構なお金がかかります。ですが起業のスタートアップの時期はお金をかける必要はありません。
初めからお金をかけることを考えるのではなく、スタートアップ時はコストを抑えて、徐々に利益を出して大きくしていきましょう。
■まとめ
起業するからといって、初めから何百万ってお金が必要になるわけではありません。確かにお金がかかる場合もありますが、お金をかけずに起業する方法もたくさんあります。お金がネックで起業出来ないのはもったいないです。まずはお金のかからない方法で起業にチャレンジしていきましょう。
[newsdig]
Posted by nob : 2014年03月13日 14:31
やりたいことがたくさんあるのなら、、、ないのなら見つかるまでぬるま湯に浸かり続けるという選択も。。。
■新しいことを始めたいという人に読んでほしい「やりたいことをやるためにやるべきこと」
まいるす・ゑびす
思い出してみてください。今年の元旦を。
今年こそはあれをしよう、これをしよう、よい年にするぞ、心を入れ替えるぞ、ダメな私とこれでサヨナラするの、と興奮のままに鼻の穴を膨らませ、もうすでに何かが変わったような気がして寒空の帰り道を意気揚々と歩いた気持ちはどこへ行ってしまったのでしょうか? そして気付けば秋の風吹き抜ける10 月の空の下、相変わらずあの日のダメな自分のまま、変わらなくちゃという気持ちだけが空回りし、肩を落としたままトボトボといつもの遊歩道なんかを歩いてはいませんか。
新しいことを始める、というのは非常に労力を必要とします。ましてそれを習慣化するとなると、それは奇跡にも近い功績です。
では、新しいことを始める際の最大の障害とはいったい何でしょうか。今回はその障害が何かを探りつつ、必要な4つのステップを書き出してみました。
1.何がやりたいのかをリストに書き出してみる
最初に、「自分はいま、一体何に挑戦してみたいと思っているのだろうか」という単純な質問を自分の心に投げかけてみてください。
英会話もフランス語もやりたい、イースター島でモアイ像が見たい、健康のためにジョギングを始めたい、友達をたくさん作りたい、バンドを組んで解散したい、出世したい、などやりたいことは誰しもたくさん思いつくことでしょう(そもそも、この記事のタイトルをクリックしてしまった時点で、何か新しいことを始めたがっている、というのは明らかです。いまさら言い逃れしようたってそうはいきません)。
リストの項目は多ければいい、というものではないですが、いくつあっても構いません。
2.リストに順位を付け、その中で一番やりたいのは何かを決める
新幹線や飛行機があり、スマートフォンひとつでどんな場所でも連絡が取れるスピーディーな世の中を生きるわれわれに慢性的に足りないもの。それは「時間」です。
時間がない状況で大切になってくるのは<プライオリティ>、つまり<優先順位>をつけることです。あれもこれもそれもどれも、全部やりたい気持ちは痛いほどよく分かりますが、残念ながら脳みそはひとつしかありません。どう頑張っても自分という人間は一人しかいないので、やりたいことをひとつずつ順番にやっていては人生が何百年あっても足りません。
リストをよく吟味し、それぞれの項目についてよく考え、そのリストの中で一番自分がやりたいと思っているのはどれなのか選んでみてください。二番目以降の順位はあってもなくても構いません。大切なのは一番がどれか、ということです。
3.一番やりたいことに毎日どれだけの時間を割り当てるのかを決める
「一番やりたいことをやるべきだ」というのが正しい選択肢だというのは、誰の目から見ても明らか。つまり、ここまでの手順で何をやるかは見事に決まったわけです。
もっとも、そこで終わるわけではありません。必要なのは、実際にやってみること。そして、その際に大切なのは、それを習慣化させることです。
物事を習慣化させるための最も簡単な方法は、毎日欠かさずやり続けることです。その際、どうしても必要なものが「時間」です。誰しも一日24時間平等に与えられています。続けていくには、その24時間からやりたいことのために割り当てるほかありません。そして、毎日やり続けるためには、欲張らずにできるだけ短い時間に設定するのが現実的です。
僕の兄はアメリカで音楽の先生という職業に就いていて、中学や高校のオーケストラを指導してます。そこで生徒には、自分の楽器の練習を「毎日5分」やってほしいと伝えているそうです。これは「なんだ、5分くらいならおれにだってできそうじゃないか」と生徒に思わせることが目的なのだといいます。実際、5分を10分に伸ばすことはさほど難しいことではないのですが、0を5分にするのはなかなかに困難です。5分だろうが10分だろうが、わざわざそのために時間をつくることが、新しいことを始めるのには何よりも大切なのです。
ですから、もしあなたが「今年こそヘブライ語の文法をマスターしたいので、毎日10分ヘブライ語を勉強する」と決めたのであれば、毎日10分必ず、ヘブライ語タイムを設けるようにします。
続けていくと、今日はどうしてもヘブライ語なんて見たくないという日もやってくるでしょう。そういう日でも10分間、いつも勉強している机に黙って座ってみてください。なんなら「自分は今日、どうしてこんなにヘブライ語を見たくないと思っているのか」「そもそもどうしてキリスト教でもユダヤ教でもない自分がヘブライ語を勉強しなくてはならないのか」について考えてみるとよいかもしれません。いずれにしても10分の時間を強制的に割くこと。これは少々乱暴なように思えますが、何かを始め、そして続ける場合にはとても効果的です。
4.それ以外のやりたいことは(取りあえず今は)やらないことを決める
さて、ここから先がとても大切です。
いろんな人がいろんな場所でいろんなことをやりたい、という声をよく耳にしますが、あれもこれもやりたいという人ほど、どれもやりません。<あれもこれもやりたい症候群>を回避するためにも、リストに書かれた<一番やりたいこと>以外のリストに書かれていることは今現在は一切やらない、ということを決意することが大切です。
やりたいことの邪魔をするのは同僚からの合コンの誘いでも、恋人からの早朝の電話でも、常連の店の人たちと深夜に食べるラーメンでも、 FacebookでもTwitterでもありません。やりたいことをやるための一番大きな障害は、<リストの二番目以降のやりたいこと>に心がすり寄ってしまうことです。
もっともやりたいと思っていたことをしばらく続けていくうちに壁にぶつかり、(気分転換のつもりかもしれませんが)他のやりたかったことに手を出してしまい、そこまでやってきたことが水の泡になる、というの本当によくあるケースです。ほとんどの人はそんなにたくさんのことを同時に始め、同時に継続するほどの能力を持っていません(なぜなら、そんなことができるくらいであればあなたは今、この記事のこんな最後の部分まで読んでいるわけがないんです!)。
やりたいことを始めるにはひとつずつ取り組んで行くのがベストなアプローチ方法です。まずは一番やりたいことを続けていくことを人生の最重要事項に設定し、そのための時間だけは石にかじりついてでも捻出する、という生活をしてみる。そうすると、新しい習慣を身につけることは意外と可能なものです。
*
とはいえ、新しいことを始めるということはつまり、今までやってきた古いことをひとつ手放すということでもあります。何をやりたいのかを実際に決める作業は、慎重にやった方がいいでしょう。
「みんな画家になりたいとか彫刻家になりたい、とか若い方おっしゃっていますけれども、一番大事なのはその気持ちをそのまま絶え間なく持ち続けることです」と草間彌生さんもこのインタビューで語ってます。複雑に考えるとややこしくなってきますが、要するにすべては「やりたいと思うこと→やること→やめないこと」のシンプルな3段階でできているのではないでしょうか。
もちろん、何が役に立つのか分からないのが人生です。あれもこれもやってみる時期があるのもとてもいいことだと思います。いずれにしても役に立つのは実際に何かをやってみた場合だけ。やりたいやりたい言ってるだけでは人は成長しません。元も子もない話をしてしまえば、本当にやりたい人は「やりたい」と誰かにいう暇があったらやっているわけです。
今回は新しいことを始めようと思っている人たちにとって、何かのきっかけになればと書きつづってみました。
「世界を変えるためにはまず自分が変わらなくてはならない」と、インドのお札にもなっているどこかのエラい人が言っていたような気もします。世界を変えるまでの責任はないにしても、新しいことを始めるのに必要なのはがむしゃらに頑張ることではなく、取りあえず時間を作って地味ながらもやってみること、そしてそれを継続してみることだということを伝えられていればいいのですが。
■ぬるま湯のようなラクな状態を長続きさせる秘訣
Walter Glenn(原文/訳:的野裕子)
ずっと働いている職場で、仕事もきちんとやっていて、経済的にも順調。何も考えなくてもほとんどのことがうまく行くので、ただその波に乗って楽しんでいる。ぬるま湯のように落ち着ける場所よ、ありがとう!
...しかし、そう思っているうちに、思わぬ問題が起こるかもしれません。
ぬるま湯に浸かっているような時は、何事もうまく行く一番楽な状態です。ぬるま湯にいて、この楽な状態がいつまでも続くだろうと思うこと自体が問題なのです。そういう時に思いもよらないことが起こると、うまく対応できないことがあります。
では、ぬるま湯状態で何をすればいい?
ただ粛々と仕事をこなしているだけでは、会社で大きな昇進をしたり、大きく飛躍できるような新しい仕事に就いたりする機会は決して得られません。これは経済的にも同じで、ただ淡々と波に乗っているだけでは、何かが起こった時にそれを利用して優位に立つ準備ができていません。
では、一体どうすればいいのでしょう。とにかく一生懸命働いてきたのです。少しくらい楽をしてもいいですよね? もちろん! やらなければならないのは、ぬるま湯に慢心しないように気をつけるということだけです。
ぬるま湯に満足しないための方法のひとつは、毎日の日課の一部を変えるようにすることです。例えば、毎日やっている仕事のひとつとして、自分の履歴書や経歴を更新するような勉強をしたり、会社で仕事に関する新しい挑戦をしたりするということです。
日々の経済的な活動としては、経済状態が前月比から良くなるようにしたり、経済状況が上向きになるような新しい方法を探したりすることです。それが当たり前の行動になるといいでしょう。
別の方法として、将来起こりうる問題を想定し、それが起こった時にどう対処するかを頭に思い描くのもおすすめです。
非常事態に備えて準備をしましょう。しかし、どのような状態でも、このようなことを心に留めて日々実行するのは、仕事をする上で一番大事なことです。
[いずれもライフハッカー]
Posted by nob : 2014年03月13日 13:46
私もデスクで捏ねくり回し尽くした後で散歩に出ます、、、おすすめです。。。
■悩んで悩んで悩み尽くしたら、一回そいつを手放してみる
北真也
システムエンジニア
悩んで悩んで悩み尽くしても全く解決しなかったあることが、考えるのを止めた途端にぽろっと解決してしまうという経験はないでしょうか?
僕の場合は、だいたい悩んでる間は全く駄目で、一晩寝て起きたら「あー、なんだこんな簡単なことだったか」と解決したり、ランニングの途中に急に閃いてみたりと、まぁ大体頭からその事がいなくなった後に解決策を思いつきます。
何かに執着している間はその事しか見えなくなってるから、ちょっと見方を変えたら見えるモノが全く目に入らない。んじゃ、最初から執着しなけりゃ見えてるかと言えばそういう訳でも無くて、その時には興味がないから目に入ってても見えていない。
だから、悩んで悩んで悩んでぎゅーーーっと寄った後に、全然関係ないことに頭を切り換えてやると、すーっと後ろに引いてって視界を広げるって工程は、多分必要なことなんだろうね。少なくとも僕にとっては。
■悩んで悩んで悩み尽くしたら、一回そいつを手放してみる
まぁ、そんなわけで、吐き気がするほどそいつについて悩んでる人は、悩んで悩んで悩み尽くしたら、一回そいつを手放してみると良いですよ。そいつに執着している間は、色んな事が見えなくなってるもんなんすよ。
ただ、手放すったって意識的に「はい切り替えた!」なんてことは、普通の人にはできない。だから、全然違うことをやってそれで頭の中を一杯にしたり、無心になれる作業に没頭したりする必要があるんです。
なので、こういう”切り替え”のアクションを自分の中でいくつか持っておくってのは凄く大事で、例えば僕の場合だと、ランニングだったり、フラフラジュースを買いに行って風景を眺めたり、手帳に向かって全く関係ない考え事を初めて見たり、タスクやスケジュールを整理してみたりと……その時々にあった”切り替え”の定番を持っていたりします。
■あらゆる欲を捨て去った時に初めて出せる「無心の一撃」
ただ、どんだけ悩んで、悩んで、切り替えて、また悩んで、切り替えても答えに到達できない事もあったりします。周りの人も巻き込んで、あーでもないこーでもないと議論を重ねても駄目な時もあります。
もうそういう時は兎に角答えにたどり着こうと思わない、たどり着きたいという事自体捨て去ってしまうというか、兎に角目の前の作業に取り組むようにします。
例えば、資料が上手くまとまらないときは、とりあえず書けるとこから書きはじめて、その時点で綺麗に仕上げる必要の無い図を一点完璧に仕上げてみたり、思いつく限りのことを脈絡なくひたすら箇条書きや文章で書き出してみたりといった具合に。
良い資料を作ろうとか、他の人をアッと言わせるアイデアを出そうとかって下心が無くなるぐらい没頭できると、思いも寄らないパフォーマンスが発揮できて、ビックリするぐらい良い資料になったり、すごく良いアイデアに仕上がったりする”ことも”あるわけです。所謂「無心の一撃」ってやつですね。
■アウトプットに悩むあなたへのアドバイス
ということで、なにがしかアウトプットを求められるお仕事をしている方へのアドバイス2点
・悩んで悩んで悩み尽くしたら、一回そいつを手放してみる
・上手くやってやろうという下心が無くなるぐらい、目の前の事に没頭してみる
ぜひ、お試しあれ
[newsdig]
Posted by nob : 2014年03月13日 13:27
また旅立つ君へVol.5/自分自身を歩き始めること、、、そして歩き続けること。。。
■「未来に向かう者にとって、今はいつも逆境」
あなたの目の前にある困難。それは、あなたが行動しているからこそ対峙できるものであり、その先には成功が待っています。だからこそ、未来を明るいものにするには、自分から困難にぶつかっていくしかありません。
そして、大切なのは「今」は常に逆境だということ。今、あなたが感じている力不足は、あなたがより成長して、未来に進もうとしているからです。次のステージに行こうとすれば、どんな人でも自分の力不足を感じるものなのです。
未来に進んでいくために、努力で力不足を補っていきましょう。
■「実力がある奴なんていない。実行した人間がいるだけ」
成功者はみんな実力があると思っている人は多いはず。でも、西田さんは彼らにあったのは実力ではなく、実行力があったといいます。
よく言われるような「実力」とは、どんな経験を蓄積したかによって生まれます。だから、早く実行して、小さな失敗や成功をできるだけたくさん経験した人が、実力者になることができるのです。一番よくないのは、何もしないこと。たくさん実行して、実力をつけていきましょう。
トップアスリートたちを指導し、勝利へと導いているだけあり、西田さんはとても本質的なことを語っています。本当の成功を手にするにはどうすればいいのか、それはもがき苦しむ今の中にヒントが隠されているのです。
もし、どうしても弱気になってしまうときは、西田さんの言葉に触れてみてください。心の底から勇気が湧いてくるはずです。
■「自信」よりも「自分」を持つ
学校でも職場でも「自信を持ちなさい」ということがよく言われますが、自分を好きになれない人に自信を持てといっても、それは無理な話でしょう。
でも、「自信」ではなく「自分」を持つことならできます。「自分を持つ」とは、「自分の行動に、自分なりの答えを持つこと」です。これなら、自分は何が好きで何が嫌いか、という自分の価値観にしたがって考えて、判断し、行動すればいいだけです。
この繰り返しが「軸がある、揺るがない自分」をつくります。それは、いつか自分への自信につながっていきます。自分を好きになれないまま生きていくのは辛いこと。
[いずれも新刊JP編集部]
Posted by nob : 2014年03月13日 13:22
歩を進めながらその都度考えよう。。。
■考えるほど悪くなる、考え過ぎの負のスパイラルからの脱出法
人間誰しも考え過ぎてしまうことはあります。良い決断をしようとして考え過ぎたり、考え過ぎて心配し過ぎるのが習慣化していると、問題が起こりやすくなります。しかし、考え過ぎないようにする方法はいくつかあります。
「Real Simple」では、考え過ぎることで起こる、本当の問題について説明していました。
最近のことや、かなり昔のことでも、辛い出来事についてくよくよと考えるのは(牛が食べ物をよく噛んで食べる時と同じように、日本語でも英語でも反芻すると言いますが)、一番良くない、破壊的な思考の癖です。このような癖があるとうつ病になりやすく、自信や問題解決能力を失いがちで、自分の人生や生活を管理することができなくなっていきます。
では、なぜ過去のことにくよくよと囚われてしまうのでしょうか? キーワードは「癖」です。記憶は感情と結びついていることが多く、ある出来事のせいで落ち込んでいる時、その感情が過去に同じような気持ちになった時のことを思い出させます。そこから負のスパイラルが始まるのです。
では、どうすれば負のスパイラルから抜け出せるのでしょうか? いくつかの方法があるのでご紹介しましょう。
* 行動を起こそう
1つの問題や出来事に囚われて、くよくよと考えていることに気付いたら、考える代わりに、何か行動に移すようにしましょう。たとえば、考えていることを書き出すというのは、一番手っ取り早い方法です。
* 思考の癖を変えよう
くよくよと考えていることは、現実的に起こっていることなのか、もしくは本当に起こりそうなことなのか、自分に問いかけてみましょう。
* 違うところに意識を向けよう
考え過ぎないように自分の意識を別のところに向ける行動を探しましょう。
* 話したくなる衝動を抑えよう
誰かと話をするのは良いことのように思えますが、それも考え過ぎを助長させる方法の1つです。
最後に、このような考え過ぎを本当にやめられる方法があります。それは、自分の抱えている問題点を把握し、それが起きた時に自分で気付くように練習することです。練習すればするほど、負のスパイラルに陥いてコントロール不能な状態に陥ることを止めることができます。
6 Steps to Stop Overthinking Your Life | Real Simple
Walter Glenn(原文/訳:的野裕子)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2014年03月12日 19:14
しなければならないことなど何もない、、、あるのはしたいことだけ。。。
■◯◯しなければならない!?
中村 毅
「節約しなければならない」とか「ダイエットをしなければならない」とか、なかなか簡単に出来ないことを『◯◯しなければならない!」と自分を追い込み、そして挫折を繰り返す……。
強迫観念にも似た『◯◯をしなければならい』と言う言葉ですが、この言葉によってものすごいストレスを掛けちゃうから、なんでも途中で嫌になる事が多いわけで、こんなことを繰り返していると、「自分はなんでも途中で諦めちゃうダメ人間なんだ…」と落ち込むばかりか、負のスパイラルから変な病気になってしまいかねません。
例えば「節約をしなければならない」のは何故なのか?「ダイエットをしなければならない」のは何故なのか? その辺をしっかりと考えると良いと思います。そして「節約をして何が変わるのか?」「ダイエットをすると何が変わるのか?」ここを想像してみると、強迫観念から開放されるかも?
しかも、節約をするにしてもダイエットをするにしても、方法はたった一つではありません。自分が楽しいと思える方法で試してみると継続できるのでしょう。
節約をしなくともダイエットをしなくとも、命まで取られるわけではないでしょう。あなたの気持ちにプレッシャーの掛からない、変なプレッシャーを掛けないように、楽しく目的達成が出来るように成功した後の姿を想像しながら頑張りましょう!
何かをするというだけで人はプレッシャーになるものです。過度のプレッシャーを掛けないためには、あなたオリジナルの方法があるはずです。人と同じ方法で何度も試していても、結果はあまり変わりません。あなたにあったプランでの目標達成! ◯◯をしなければならないと言う考え方を捨てましょう!
[newsdig]
Posted by nob : 2014年03月12日 19:05
もはや常識。。。
■やっぱり「食べる順番」は大事だった!
老化スピードを早めてしまう「糖化」を防ぐ食事術
老化の一因「AGE」の正体
久保 明
東海大学医学部 抗加齢ドック教授/慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授
老化を強力に促進する要因に「糖化」があると前回お話しました(「老化のスピードを早めてしまう『糖化』とは?」)。
糖化とは、高い温度の元で糖分が蛋白質と結び付くものです。そして、このとき出来るのがAGE(終末糖化産物)です。
このAGEですが、実は料理や食品で目にすることができます。おいしそうに焼き上がったホットケーキにはキツネ色の焦げ目ができますよね。これがAGEです。ホットケーキの中の砂糖(糖分)とミルクや卵の蛋白質が結合したものです。焼く前には発生しませんが、高い温度が加わると反応してできます。クレームブリュレの焦げ目の付いたところや、魚や肉の照り焼き、ウナギのかば焼きの焦げた部分なども実はAGEなのです。
AGEは「終末糖化産物」の略語で強力な"老化促進物質"の一つです。増えたAGEは体を構成する蛋白質にくっつき、その機能を低下させてしまいます。
前回、AGEによって皮膚のたるみやしわ、動脈硬化が促進され、骨粗鬆症や白内障、アルツハイマー型認知症の原因ともなるとお話しました。
皮膚を例に、AGEと老化促進について少し詳しくご説明しましょう。
皮膚の真皮層のコラーゲンやエラスチンにAGEが取りつくと、正常な構造が壊されます。すると、繊維のつながりがおかしな形に変えられ弾力性を失います。その結果、たるみやしわが生じて見た目が老けて見えてしまうのです。
「糖化」を防ぐには、
食後の血糖値を急速に上昇させないこと!
体内にはAGEなどの異物を食べるマクファージという白血球の一種である「貧食細胞」があるのですが、AGEが次から次へと生成されるととても処理しきれず、AGEが溜まってしまいます。
AGEを増やさないようにする、つまり、糖化を防ぐには、食後の血糖値を急速に上昇させないことが肝心です。
特に、血糖値を急速に上昇させてしまう糖質に気を付けましょう。糖質は、砂糖や果物の果糖、牛乳の乳糖などの他、米や麦、トウモロコシ、芋類などの炭水化物、ビールや日本酒、ワインなどの酒類の一部に含まれています。これらを摂り過ぎると糖化が起きやすくなるのです。
ビール、日本酒などを飲んだ後、締めにラーメンを食べたりすると妙な満足感がありますが、あまりおすすめできません。ラーメン・ライスやお好み焼きにご飯などというのも糖質が多すぎるため、糖化を招きやすい食事です。もちろん、ケーキや和菓子の食べすぎや、甘い清涼飲料水を大量に飲むことも糖化を促進させます。
「食べる順番」は大切
糖質は摂り過ぎない。これが第一なのですが、極端に糖質を排除する「超低炭水化物ダイエット」はお勧めできません。日本人は「ご飯」を中心に野菜や魚、肉類などを食べる混合食を続けてきました。このバランスを大きく崩す食生活には無理があり、"骨髄の機能低下による動脈硬化の促進"という危険も潜みます。糖質を敵視するより、適度な糖質を摂りながら血糖値の上昇をゆるやかにする工夫しましょう。
そのひとつとして「食物繊維」の活用があります。
食物繊維は野菜や芋類、豆類、海藻、キノコ類、穀物、果物などに多く含まれています。食物繊維には糖質の吸収を緩やかにする働きがあり、しかも先に食物繊維を食べておくと一層効果的なのです。ご飯と野菜サラダを食べるとき、野菜サラダを先に食べて後にご飯を食べると、先にご飯、後から野菜サラダを食べるのに比べ、血糖値の上昇が緩やかになります。
食べる順番は意外と大事なんです。日常の食事でも、「食物繊維」→「蛋白質」→「炭水化物」というような順番で食べると、血糖値の急上昇が抑えられます。
これは懐石料理の食べ方に似ています。食物繊維の多い野菜料理、海藻、キノコ類、豆などの小鉢をまず食べ、それから刺身や焼き魚などの魚や肉などに進み、最後にご飯を食べるというものです。家の食事でそこまでの贅沢な品数は必要ありませんが、まずは野菜類や豆、海藻などの食物繊維を食べてから、魚や肉などを食べて、最後にご飯という順番が理想的です。
最初にご飯でなく野菜類を口にする習慣を身につけるだけでも糖化防止には役立ちます。外食でカツライスを食べるなら、まずカツの横のキャベツを食べてから、カツ、そしてご飯という順番ですね。
2012年、ヨーロッパで行われた45万人を対象とした約13年の追跡研究では、食物繊維の摂取量は死亡率低下と相関しました。食物繊維の摂取が多い人ほど死亡率が低下したのです。死因別にみると循環器障害や消化器疾患、心血管障害、ガンと関係しない炎症性疾患の低下と特に相関していました。アンチエイジングに食物繊維は大いに効果あり、と言えるでしょう。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年03月10日 20:01
健康生活、、、何も特別なことは必要としない。。。
■ゆっくり食べると太らない!? 満腹感は食事開始から15分で得られる
健康的に体型をキープするために、エクササイズは欠かせません。でも、日頃忙しいとなかなか時間を割くのが難しいもの。そこで、毎日の習慣にちょっとした機転をきかせることで、スリムになれる方法を見つけました。
料理のデコレーションに「花びら」
フレンチレストランへ行くと、花びらが料理に添えられていて、盛りつけの美しさに感動してしまうときがあります。このように「見た目」で味わう感動を食事の度に取り入れることで、やせる工夫になるのだといいます。
フルーツやサラダをお皿に盛りつける際、パンジーやすみれなどの花びらを2、3枚散らします。そのことで、満腹感を少し得ることができるといいます。これは、脳がおいしそうなものや美しいものをキャッチすると、満腹中枢が刺激されるからです。
食べ過ぎを防ぐためには、満腹中枢に働きかける「レプチン」というホルモンを分泌させるといいのだそう。また、食べ始めてから15分後に満腹感が得られ始めるそうなので、食事は最低でも15分の時間をかけた方がよさそうです。見た目の良さを重視した食事を、ゆっくりと味わいながら食べることがポイントです。
「眠り」こそが食欲増進ホルモンを抑える
「寝不足になると太りやすくなる」という話がありますが、その原因は意外と知られていないかもしれません。疲れやストレスから余計なものまで食べてしまう、抑えられない衝動に駆られるものですが、これには一体どういう理由があるのでしょう。
睡眠不足になると、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の血中濃度が上がり、食欲や代謝の調節を行なうホルモン「レプチン」が減少してしまいます。ある統計では、「5時間睡眠の人は太り気味にある」という傾向が指摘されています。
人の身体はホルモンの影響に左右されるので、正常な食欲をキープするためにも、睡眠は欠かせないものだといえます。基本的なことではあるものの、仕組みが分かれば即実践したくなります。
ご紹介した2つなら、どんなに忙しくてもすぐに試すことができそう。運動する時間がないならば、食べ過ぎを抑えるこういった工夫から始めたいものです。
下野真緒
南仏在住ジャーナリスト/エディター
[cafeglobe]
Posted by nob : 2014年03月09日 07:58
幸せはいつも自らの内から生まれてくる。。。
■あなたが幸せを感じない4つの理由
選択しない、愛さない、感謝しない
瀬戸和信
テクノロジーマーケティング専門家
2013年の世界幸福度報告書(World Happiness Report)が発表されました。日本は43位。毎日、身を削りながら働いて、昇進して、年収とともに生活水準が上がっても、どこか幸せを感じられないときがあります。なぜ幸せを感じることができないのでしょうか?
私は30代になってから、強く幸せを意識するようになりましたが、劣等感の塊みたいな自分を嫌になるときがあります。だから、以下に幸せを感じない理由をまとめました。幸せを感じない理由がわかれば、幸せを感じる自分をいつでも取り戻せると思ったからです。
幸せを感じない理由その1:比較するから
視野が狭いとこんな感情に襲われることがあります。「彼のほうが俺より幸せな人生を送っているのではないか?」。そう、他人との比較です。
たとえば、あなたは年収が低いから幸せを感じない、ということはありません。1000万円、3000万円、5000万円稼いでいたとしても、満足できない人はいます。あなたは年収を上げたいのではなく、他人と比較して高ければそれでいいのです。生活水準が上がっても、他人も同じように上がっているなら、豊かさに関係なく幸せを感じないのです。
昔、私は中国に住んでいました。私はそこで豊かさを感じました。おカネは稼げていなかったのですが、私よりも生活に不自由な人たちの生々しい光景を見たからです。日本に帰ってきてからは、豊かさを感じなくなりました。なぜなら周りも私と同じような生活水準だからです。この感覚から学んだことは、私がいかに他人との比較によって気分を決定していたかということでした。
人は違って当たり前。他人は他人、あなたはあなた。一卵性双生児でさえ、外見や能力、考え方も違うということを忘れてはいけません。特に私みたいな劣等感の塊みたいな人間は。
幸せを感じない理由その2:選択しないから
私の友達には、やりたくもない仕事をしている人がいます。報酬がいいからです。私なんかよりはるかに高い報酬を得ているのですが、実はまったく幸せそうじゃありません。逆に私のことをすごくうらやましいと言うのです。なぜここまで心に格差があるのでしょうか? 自ら選択する機会が少ないからです。実は本人も認めています。
たとえばテクノロジーサービスの導入を決断した企業の担当者は、労力を費やした自分のプロジェクトを失敗したと思いたくありません。当然ですよね。だから無意識にこのプロジェクトは正しい選択だった、成功した、と自分に言い聞かせる心理が働きます。自ら選択し、決断したのですから、自分を正当化するおなじみの心理です。
子育ての例です。私は息子のご機嫌をとるために、彼が大好きなおもちゃを目の前にちらつかせ、無理やり遊ばせようとしたことがありました。一瞬、手に取って遊ぶのですが、すぐにおもちゃに対する興味を失ってしまいました。今度は、2つのおもちゃを目の前に置き、彼に選択権を与えました。彼は悩んだ末、片方のおもちゃを手に取ると、長い時間そのおもちゃと遊んでいました。
他人から押し付けられるのと、自ら選択して何かに取り組むとは、月と蛍のように大きく違います。
幸せを感じない理由その3:愛さないから
愛する人に認められたい気持ちは誰もが持っています。私も強く家族に認められたいと心から思っています。
仕事で成功しても人を愛していないと何か物足りず、心の能力が低下してしまいます。そして死ぬ間際にこんなせりふを言うのです「俺は成功して大金を手に入れたけど、結局、俺の人生は何だったんだ?」。最愛の人を思い、愛することは、幸せを感じるいちばんの近道だと信じてます。幸せを感じる上位10%は恋をしていたときだそうです(参照元:エド・ディーナーとマーティン・セリグマンの調査)。
幸せを感じない理由その4:今に感謝しないから
きっとあなたは“今”に感謝しないから幸せを感じることができません。こう思うのは2つの理由があります。ひとつは、『いのちをいただく』(西日本新聞社)という本があります。本のソムリエ清水克衛さんのブログから教えてもらいました。すごく文字が少ないのですが、内容はすごく深いのです。「XXのいのちを私のいのちにさせていただきます、いただきます」と食材に感謝することを端的に説いています。いのちが支え合って循環していることがわかります。いのちの大切さがわかります。そして今を生きていることに感謝せずにはいられなくなります。
2つ目は、この質問でした。あなたも真剣に考えてみてください。参照元が思い出せないので原文と少し変わっているかもしれませんが、こんな感じの質問です。
質問:悪魔がやってきてあなたに言いました。「おまえのすべてを奪ってやる! ただし、ひとつだけ残してやる、明朝までに考えておけ」
さて、あなたは何を残してほしいと思いましたか? カネですか? 愛する人ですか? それとも、いのちですか?
あなたが幸せを感じられないのなら、それはきっと“今”に感謝していないからです。
[東洋経済ONLINE]
Posted by nob : 2014年03月05日 17:03
私もこのところゆっくりじっくりと体質改善中です。。。
■35度、34度台も! がんにもなりやすい…
日本人の「低体温化」が進行中
このところ、日本人の“低体温化”が進んでいるという。冷えや低体温に関する著書の多いイシハラクリニック副院長の石原新菜先生によると、低体温とは内臓等の深部体温が下がった状態を指し、手足が冷える“冷え性”と違って、自覚できる症状がほとんどないのだとか。
「医学大辞典には、一般的な日本人の平均体温(深部体温)は36.89度プラスマイナス0.34度と出ています。しかし、近年では35度台や34度台の低体温の患者さんも珍しくありません。大きな原因は筋肉量の減少です。筋肉は体内の熱の約4割を生み出す、体温維持に欠かすことのできない器官。しかし、交通機関が発達し、便利な家電に囲まれている現代では、体を動かす機会が減っていますから、男女を問わず筋肉が少ない人が増えているのです」(石原先生)
1日の平均的な体温を示す時間は午前10時といわれており、この時間の体温が36.5度以下の場合は、低体温と考えていいのだそう。では、低体温は身体にどんな影響を与えるのだろうか。
「体温が下がると白血球の働きが低下し、1度下がるごとに人間の免疫力は約30%落ちます。このため、風邪を引きやすくなりますし、回復も遅くなる。また、血流が悪くなり、基礎代謝が低下することで、乾燥肌やむくみの原因にもなりやすい。一番怖いのはがんにかかりやすくなること。がん細胞は体温が35度台の時に増殖しやすいのです」(同)
低体温になりにくくする一番の対策は、「とにかく筋肉をつけること」だという。
「全身の筋肉の約75%は下半身に集まっていますから、ウォーキング、ランニング、スクワットなどで、太ももやおしりの筋肉を意識して鍛えるといいでしょう。また、お風呂は必ず湯船に浸かり、汗が出てくるまで温まる習慣をつけること。入浴時は一時的ではあるものの、体温が上がることで免疫力が高まります。食事は、体を温める効果があるしょうがや根菜などを摂るように。過剰な減塩は低体温を招きやすいため、適度な塩分摂取も行ってください」(同)
低体温の疑いがある人は、普段から予防の意識を持って生活することが大切のようだ。
(成田敏史/verb)
[webR25]
Posted by nob : 2014年02月26日 10:57
また旅立つ君へVol.4
君はまだ
君自身が探し求めるものが何なのかにすら気付いてはいない
気付きの先にあるその何かは
そもそもこの世界の何処にも存在してすらいないし
そしてこれから先誰も与えてくれはしないのだから
自ら創り出していくしかない
自己肯定し続ける先には何もない
自己受容(許容)できて初めて葛藤が生まれ
迷い悩み苦しんだ末の自己否定の先に
君が探し求める何か、新たな創造がある
Posted by nob : 2014年02月25日 15:01
また旅立つ君へVol.3
如何なる失敗も
あきらめない限り次に続いてくる成功も
またその成功もその次に続く失敗への
すべてはその時々限り過程の一つに過ぎない
実際の経験に優る学びはなく
失敗と成功を度重ねることこそが真の知恵と力と勇気を育むのだから
同じ過ちを繰り返すことの愚かしさだけは深く胸に刻みつつ
その時々の内なる心の声が指し示す途を淡々と歩み続けていけばいい
Posted by nob : 2014年02月25日 14:52
美しくも愛おしい、そしてかけがえのない日々が今日もまた過ぎていく。。。
■【今日の名言】「すべてが奇跡であるかのように生きる」アインシュタイン
今週もお疲れさまです。
ちょっと心が弱ったときにそっと背中を押してくれる、そんな名言をお届けします。
今週は、アルバート アインシュタイン氏のこんな言葉。
「私たちの生き方には二通りしかない。奇跡など全く起こらないかのように生きるか、すべてが奇跡であるかのように生きるかである。」
※『アインシュタインにきいてみよう 勇気をくれる150の言葉』P6より引用
今、ここにこうしていることも奇跡なのだと思うと、なぜか急にこの世界が、自分が、ありがたく大切なものだと実感できます。
一瞬一瞬が奇跡の連続であるならば、もう無駄にはできません。
知恵子
画家/ライター
[MYLOHAS]
Posted by nob : 2014年02月23日 22:28
愛した者の勝ち、、、その愛の深さだけ幸せも大きい。。。
■幸せになる恋愛をする方法~追われる恋愛編
追われる恋の方が幸せ?
今回は『追われる恋愛』についてお話します。
よく「女性は追われる恋愛の方が幸せになれる」と言いますが、本当にそうでしょうか?
『追われる恋愛』をする人は、相手が尽くしてくれることが嬉しかったり、その一生懸命さに惹かれることが多いと思います。
もちろん自分が愛されている実感があるので、浮気などの不安や心配もなく自分らしく余裕をもっていられるというのが特徴です。ところが、その関係が慣れてくるにつれて、本当にこの人で良かったのかな?もっといい人がいるのでは?と自問自答をはじめます。
ここで考えてほしいのが「あなたがパートナーと一緒にいるのはなぜか」ということです。一緒にいて楽だから、自分のことを好きでいてくれるから、余計な心配をしなくていいから…など、追われる恋愛をしている人は「いまの自分」が満たされるための恋愛をしている人が多いような気がします。
果たして、それは本当に自分の幸せと繋がっているのでしょうか?
追われる恋をする人にとって大切なこと。
『追われる恋愛』をする人に大切なことは、自分の幸せとはなにかをしっかり考えることです。いまを満たす為の恋愛ではなく、自分の幸せに繋がる恋愛を選択することが重要です。
もしかすると、それは今の恋愛ではないかもしれないし、今のパートナーだとしてももう少し相手と向き合うことが大切になってくるかもしれません。なんとなく付き合うのではなく、きちんと自分や相手と向き合う時間を作ってみてください。
もし今の恋愛が幸せに繋がっていたとしても、パートナーから尽くされ与えてもらえることに満足していませんか?
自分はどれだけ安心していても、相手はきちんと愛情表現をしてくれない限り不安や心配を募らせるのです。そして、次第にあなたへ自分が尽くした分の愛情を要求してくるようになるか、もしくはふとした瞬間に離れていく可能性もあるのです。
気持ちは言葉や行動に表さなければ伝わりません。追われる側としてあぐらをかくのではなく、きちんと相手と向き合って愛情表現をしていくことも幸せな恋愛をするためのひとつの方法です。
パートナーと上手くいく一番の秘訣は「お互いが相手を想いやり、歩み寄ること」です。バランスをとることはなかなか難しいですが、お互いが歩み寄ることで『幸せになるための恋愛』をすることが出来るようになります。
吉元夕加里
ビューティーメンタルトレーナー
[スキンケア大学・美ログ]
Posted by nob : 2014年02月23日 22:19
知り及びませんでした。。。
■ハンドは横! リップは縦! クリームを塗る法則「ランゲルライン」
なんとなく「塗りやすい方向」にクリームを塗っていませんか? たとえばハンドクリームは縦塗り...というふうに。
しかしその方向だとクリームの伸びが悪く、また皮膚が無理な方向に引っ張られて伸びてしまい、この悪習慣の繰り返しがシワやたるみの原因になる怖れも! 保湿クリームでも日焼け止めでも、塗るべき方向には法則があるんです。その決め手が「ランゲルライン」。
ランゲルラインって?
ランゲルラインとは、「真皮に存在するコラーゲン走行」のこと。たとえば首や手首に横ジワができるのは、ランゲルラインが横に走っているからです。
クリーム類はランゲルラインに沿って塗ると、クリームの伸びもよくお肌に負担がかからないため、首なら中央から横方向に、ハンドクリームは横に塗り広げたほうがいいんですよ。
ちなみに、手荒れ用塗り薬の説明書にも、横方向に塗るよう書いてありました。また、お医者さんが外科手術でメスを入れる際も、ランゲルラインに沿って入れると傷の治りが早いと言われています。
シワができる方向に塗るの法則
場所によって方向がさまざまなランゲルライン。手は横、首は横 などと丸暗記してもキリがありません。文字にすると違和感がありますが、「シワをつくりたくなければ、シワができる方向に塗る」と覚えるのがオススメ。
たとえば唇には縦ジワが入っているので、リップクリームは縦塗りが正解! 私はリップクリームを横に塗ってしまうと余計に唇荒れがひどくなると体感しているので、リップだけは縦塗りを厳守しています。
手や首、唇などシワができやすいところは、毎日のクセが何百回、何千回と積み重なることで将来のお肌が左右されそうなので、この3か所だけでも意識してみる価値ありです!
加藤ミイ
ピアノ弾き&美容ライター
[glitty]
Posted by nob : 2014年02月21日 19:32
男とてストレスに感じます。。。
■イライラの原因はこれ!あなたのストレスを激増させてる意外な事5つ
とくにこれといった原因もないのに、気分が悪く、ストレスを感じる日ってありませんか? それ、実は自分ではたいして気にかけていなかった”隠れた原因”が、意外にも大きなストレス源となっているかもしれませんよ。
ストレスは積み重なると、健康や美容の大敵となるだけではなく、自分自身がネガティブなオーラを発し、気付いた時には友人や大切な人から避けられ、会社などで嫌われ者となってしまう事があります。
そんなことにならないように、今回はアメリカの女性むけ情報サイト『Woman’s Day』の記事を参考に、女性にとって大きなストレスを生む意外な原因を5つ、ご紹介します。
■1:発言と行動が一致しない友人
遊ぶ約束には「ぜひ!」と前向きに答えるのに、ほぼ毎回、遅刻やドタキャンをする友人や同僚はいませんか?
このような、面白いんだけど約束しても会えるかどうかわからない、発言と行動が一致しない人達との交遊は、自分が嫌いな人達よりも、よりストレスになるという調査結果があります。
解決方法としては、そのような友人には、次に何かする際に、自分は遅刻やドタキャンだけは許せない等、友人の行動が自分のストレスとなり得る事を、はっきりと前もって伝えておいて下さい。
■2:他人が散らかす事
自分の領域や共同スペースを、自分以外の人に汚される事はストレスになります。とくに、男性は何かを汚しても放置してしまう人が多いですよね。
アメリカにあるダーマー心身健康センターのアリス・ダーマー博士が言うには、研究によると、男性脳は、女性より感覚が少なく、女性にとって見えていると思っていることが、男性には見えていないという事です。
解決方法としては、家族会議などを開き、決まった時間に10分でも、自分の担当を決め、掃除をしてもらうことです。
■3:電話の音声案内
テクノロジーが進み、最近では、どの企業に電話しても、お客様相談窓口が設けられ、ほぼ音声案内に従ってボタンを全て押していかなければ、自分が必要としている答えを求められません。企業にとっては、経費の節減になりますが、私達にとってはかなりのストレスとなります。
解決方法は、なるべく人と繋がる直通番号を手に入れる事です。音声案内の時は”オペレーターに繋ぎます”を迷わず選びましょう。
■4:カロリーが少なすぎる食事
痩せる為のダイエット期間中に、カロリーが少なすぎる食事を摂取する事で、身体は自然と、食べたいと熱望します。すると、イライラや頭痛、疲労感が伴なってきます。
解決方法としては、ダイエット中のカロリー計算は止めましょう。そして食べ物をフルーツ、野菜、豆、全粒粉などの、水分と食物繊維を多く含む物を中心にし、お腹が空いたと感じさせない事です。
■5:鏡に映ったイケてない自分の姿
たとえば家族をお持ちの方の場合、子供はお洒落な服を着て、旦那はジムに行って身体を鍛えているのに、自分はそんな家族の為に、ボサボサの髪でノーメイクで夕食を作っている……。そんな状態でふと鏡に映った自分を見ると、激しくストレスに感じますよね。
人間にとって、自分が外の世界で評価されていないと感じることは、大きなストレスとなります。そして自分がネガティブなオーラを発していると、周りの人もネガティブに返してきます。
解決方法としては、なんとか時間をつくって良い美容院に行き、毎日5分間でもいいのでメイクをしましょう。見た目を明るくすると、自分もポジティブな気持ちになり、ポジティブなオーラがでてきます。周囲のあなたを見る目も、自然とポジティブに変わってくるはずです。
以上、女性にとって大きなストレスを生む意外な原因を5つご紹介しましたが、いかがでしたか? 皆さんのストレスとなっているかもしれない事はありましたか?
音声案内などは、急いでいる時だと、とくにイライラしますよね。直通番号は企業情報や会社概要で調べ、控えておきましょう。
[NEWSポストセブン]
Posted by nob : 2014年02月21日 19:29
結局は人(医師)と人(患者)、、、納得できる医師に出遭えるまでいくつかのクリニックを回ってみましょう。。。
■長く付き合いたい 医師が語る“理想のかかりつけ医”とは?
医療の世界では「常識」でも、病院に慣れていない患者にとっては戸惑うことは多い。そこで、病院にかかるときの決まりごとや困ったときの対処法について、医師や専門家に聞いてみた。週刊朝日MOOK「手術数でわかる いい病院2014」の記事から紹介する。
日頃から世話になり、いざというときにしかるべき病院に送ってくれるのが、かかりつけ医だ。
「健康について困ったとき、とりあえず相談ができて、何らかの道を開いてくれる存在」。“理想のかかりつけ医像”をそう表現するのは、東京都世田谷区にあるプライマリーケア東京クリニック院長の黒須譲医師。同クリニックは初期診療に特化した医療機関だ。「広く浅く」に徹し、守備範囲はかぜや頭痛から腰痛、さらにはうつなどの心療内科的症状までを網羅する。対応できるものは対応し、その域を超えたものは速やかに専門性の高い他の医療機関に紹介する、まさに医療の窓口だ。
「日本では患者自身の判断で初めから専門性の高い医師にもかかれます。しかしそれは患者の判断を土台としており、ときに間違った診断や時間の無駄、不必要な検査の温床にもなり得る。日頃からその人の基礎的な医療情報を持つ医師によるジャッジが、効率性と安全性の高い医療につながるのです」(黒須医師)
そのためには、いいかかりつけ医を見つけておくことが前提になるだろう。では、どんな医師がかかりつけ医に向いているのか。
医師らの意見を総合すると、(1)アクセスがいい、(2)医師間のネットワークが充実している、(3)話しやすい、という3点に集約される。
まず(1)。どんな名医でも、困ったときにすぐに駆け込めないのでは、かかりつけ医の機能は発揮できない。
(2)は、手術や入院の必要が生じたとき、「この病気ならこの先生」と、疾患ごとに得意とする医師につないでもらうためだ。かかりつけ医自身が広範囲のネットワークを構築している必要があることを指している。
そして、(3)が最も重要だろう。どんなに評判がよくても、会話をするだけで苦痛になる人物に自分の健康を任せるのは無理がある。何でも話せる、相性の合う医師を選ぶべきだ。
この医師と決めたら長く付き合うこと。付き合いが長くなるほど患者のデータは蓄積され、万一の際には役立つ。「一家そろって信頼できる町のお医者さん」を見つけておきたい。
[週刊朝日]
Posted by nob : 2014年02月21日 19:22
彼も彼女もいつもいつまでも私のすぐ隣にいる。。。
■夫の死を乗り越えるには逃げる勇気が重要と心理カウンセラー
大切な人との別れは急に訪れるもの。しかし、残された者は、その現実と向き合って、しっかり前に進んでいくしかない。
自身も13年前に事故で夫を亡くした心理カウンセラーの黒田めぐみさん(46才)に、夫の死を乗り越えるための話を聞いた。
「夫の死──それはいつ終わるかわからない悲しみです。だから“頑張って、立ち直って”という気は私にはありません。でも、大きな穴を埋めようと、自分を残していった夫を恨んだり、無力感に苛まれ続けていてはつらいばかり。自分が逃げる場所も作っておいてほしいんです」
それには“逃げる勇気”を持ってほしいと話す。次のステップに進むために、悲しみに真っ向から向き合うことも大切。でも、悲しみは自分の速度でゆっくりゆっくり受けとめていけばいい。その際、自分が好きだった旅行に出かけたり、趣味のコーラスを始めるなど、少しでも気が休まり、他のことを考えられる時間を大切にしてほしいという。
「そんな場所を作ることから始めて、次は人に話を聞いてもらってください。人に話すことは、自分の気持ちを“手放すこと”。自分の中にある後悔や無力さを手放して、自分自身の頑張りをねぎらってほしい」
そうやって夫の死を乗り越えた黒田さんは、今では生前よりはるかに夫を大切に思えると話す。
「夫を亡くしたことは私にとってつらい経験でしたが、今は心から感謝もしています。私は夫の死をきっかけに劇的に変わりました。『ご飯がおいしい』『今日はこんなことがあった』という何気ない日常を、幸せな大切な時間だと思うことができる。
今の仕事だって、OLだったころとは比べものにならないぐらい好きで楽しいんです。夫は私に、人の死とは何か、生とは何か、人の心とは何かを考えるきっかけと天職に出合わせてくれました。人としての深みが増したといったらおおげさかもしれませんが、でも、私は今の自分が大好きです。
進み方は人それぞれ。ゆっくりでいい。無理に笑わなくても、泣いて過ごす日々があってもいい。でも、いつか夫の死を乗り越えて、夫にありがとうといえる、そうやって夫の死をあなたの今に生かす人生にできれば、きっとそのとき、夫はあなたの中で生き続けられると思うんです」
[女性セブン]
Posted by nob : 2014年02月19日 20:09
恋愛、、、突き詰めればプラトニック。。。
■不倫や浮気は「時間と精神をただただ消耗しただけの恋愛」だった ~その男、あなたが本当に追いつめられた時、助けてくれますか?~
「恋はするものではなく、おちるものだ」
江國香織さんの『東京タワー』という小説に出てくる一節です。
これを初めて読んだ時、私には小説の登場人物の心情や行動の意味が、まったくといっていいほど理解できませんでした。その当時はまだ恋愛観が浅かったのだと今なら思います。
ただただ、言い回しの綺麗さや雰囲気のオシャレさだけに心奪われていた感じですね。大人の女性や恋愛への憧れや、好奇心に近いような感覚だったのだと思います。あとは、岡田准一さんのファンだった(映画化された時、岡田准一さんが主役でした)。
しかし大人になって、自分もそれなりに恋愛の酸いも甘いも味わった今、読み返すと、うーん。なんか分かるなと急に物語に登場する女性が愛らしく思えたのです。旦那が居るにも関わらず若い男の子との恋愛に溺れる、世間的に見たらどうしようもない女性たちなのですが……。興味のある方は是非読んでみてくださいね。
不倫や浮気。この世が男女ふたつの性によって成り立っている以上、永遠のテーマとしてさまざまな議論が繰り返されるでしょう。もし、当事者になってしまったならば、私たちを酷く悩ませる種となります。
不倫愛や浮気心と無縁の世界に生きて来た人たちは……そういう歪んだ愛に対して「理解できない」と拒否反応をおこすかもしれないし、経験者は……何というのでしょうか。私の周りでは、「時間と精神力をただただ消耗しただけの恋愛だった」と言う人が多くいます。
ちなみに、そのように言う友人は全員、彼女や奥様から最後まで「彼」を奪えなかった切ない女たちです。しかし、これ以上ダラダラと長引けば自分がもたない! と、もうこの恋に未来などないのだと悟って自らを律し、泥沼劇場の舞台から降りた強い女たちでもあります。
浮気はダメ。不倫なんてもってのほか! そんなことは常識だし、本人達も頭では分かっているのです。それでも溺れる泥沼地獄。
恋はするものではなく、おちるもの。
果たしてどれほどの人が、「不倫してやろう」と思って、不倫をするのでしょうか。おそらくほとんどの人がそうではないと思います(浮気だったら少しのお気楽感があるかもしれないですが、不倫となったらまた別です。なんてったって家庭があるのですから)。
気付いたら、もう、好きだった。側にいたいという感情を、理性では制御できない。この人に触れたらどんなふうに感じるのだろう。この人に触れられたら、どんなにしあわせなのだろう。
そんな感情が渦巻いて、お互いの波長やタイミングの歯車が合った時に、始まってしまうのでしょう。ダメだと分かっていても始まったら最後。天国と地獄を行ったり来たりの長い長い試練が始まります。
私も、過去に一度だけ経験があります。私の場合は、不倫ではなくお付き合いをしている女性がいる年上男性との恋愛でしたが。まぁ、簡単に言うと浮気相手ですよね。
今思うと、あれは一種のファンタジーだったように思います。一緒にいる時は、この世の何とも比較できないくらいに甘たっるい時間。しかし、彼が彼女の元へとひとたび帰って行けば、罪悪感と孤独と何とも言えない虚しさが容赦なく襲ってくる。
どんなに調子のいい事を言われても、結局、私はサブなのだという現実。会えない時にたったひとりで耐える時間の辛さ……。
今思い出すだけでも苦しい恋愛でした。でも考えたら、私と会っている時は彼女はひとりで耐えていたんですよね。今なら彼女の痛みが分かるのですが。宇多田ヒカルさんの歌詞の中に「私の涙が乾く頃、あの子が泣いてるよ」とありますが、まさに! この恋愛を続けている以上「僕らの地面は乾かない」です。
現在、絶賛浮気愛・不倫愛中の読者の皆さん、私は「止めなさい」とは言いません。いい大人同士の恋愛なのだから。人に止めろと言われて止められる程度の気持ちならば、そもそもこんなリスキーな恋愛選ばない。私もどんなに周りに心配されても聞く耳さえ持てなかったひとりでした。
ただ、考えて欲しいのは、「その男、あなたが本当に追いつめられた時、助けてくれますか? 何を差し置いても駆けつけてくれますか?」ということと、「浮気をされても変わらず愛情を注ぐ事ができますか? (自分のした事は必ず自分に返って来ます。それに男の浮気癖はなかなか治らないから!)」ということです。
本来、あなたはそんなに苦しまなくても、幸せな恋愛ができるチャンスはいくらでもあるはずです。見えていないだけで。「イケナイ恋愛」のファンタジーに溺れていると、本当に色々な事が見えなくなってしまうんですよね。もったいないくらいに。
続いて、現在、相手の浮気・不倫に勘づいている皆さん。大丈夫、あなたたちは相手よりもひとつ上のステージにいるのです。
だから、相手の女性云々ではなくて、まず自分たちふたりの関係において問題は何かを考えて、解決に取り組んでみてください。そこがクリアされれば、結構あっさりと男性は戻って来るもの。ただでさえ、浮気していてもあなたと別れないんだから、あなたやあなたとの思い出に未練タラタラなんです。
みんなが同じだけ幸せとか、みんなが平等に恋愛ができるとか、そんな理想郷はどこにもありません。残念ながら。人間は欲深い。『東京タワー』の映画が完成した時のインタビューの中で主演の岡田准一さんはこう言ったそうです。
「恋には落ちてはいけないと思っています」。
恋は時に、仕事や夢の邪魔をする。逆もしかり。恋愛感情を理性的にコントロールできたらとっても生きやすいのに。
本能的に恋愛を楽しむのも、理性的に恋愛を嗜むのも、極めればおそらくどちらも本当に魅力的な女性でしょう。
でも、それって本当に難しいのです。理性的になろうとすればするほど本能がうずくし、本能が暴走し始めれば不思議と理性的な自分が状況を客観視して分析している。
正解やゴールが無い物だからこそ、私たちは悩むし、苦しむ。だけど、恋愛でしか得られない喜びがあるのも確かなこと。痛い恋愛を若気の至りと、もう笑い飛ばせない私たちは、ひとつひとつの恋愛を大切にしていきたいものですね。
全女史に幸あれ!
eNA
(ファッション評論家/コラムニスト/ファッションイラストレーター)
[ANGIE]
Posted by nob : 2014年02月17日 20:44
バランスの取れた食事と規則正しい当たり前の暮らし、、、に尽きます。。。Vol.2
■寝ても疲れがとれない原因は「冷え」だった!? “冬不眠”解消ポイント5
2014年に入り、暖かくて穏やかな日もありましたが、2月はやっぱり寒かった!
先日は、20年ぶりに関東地方でも20cm以上の積雪を記録するなど、グッと冷え込みました。
さて、みなさんは最近、しっかり眠ることができていますか?
すぐに寝付けなかったり、夜中に起きてしまったり、時間的には眠っているはずなのに眠いなどと感じていませんか?
もし、最近、特に眠れないなという人がいたら、それは「冷感ストレス」からくる「冬不眠」かもしれません!
冷感ストレスって何!?
『血めぐり研究会 supported by Kao』が首都圏在住の男女400名に調査をしたところ、『冷え』をストレスに感じる人は、約6割にのぼり、それを「冷感ストレス」と呼ぶのだそうです。そして、その中の7割が睡眠に不満を感じており、「寝ても疲れが取れない」「寝つきが悪い」という悩みを抱えてることがわかりました。
確かに、寒いと心や体も縮こまってしまい、あまりやる気が湧かない……寒さで眠れない……なんてこともあるのではないでしょうか。みなさんも、もしかしたら、知らず知らずのうちに、冷感ストレスを感じているかもしれませんね。
冷感ストレスと冬不眠のメカニズム
そもそもストレスは睡眠サイクルに影響を及ぼすものですが、特に「冷感ストレス」は睡眠障害をさらに悪化させてしまう可能性が高いのだそうです。
日常のストレスに加え、「冷感ストレス」を感じると、能の大脳皮質というところにコルチゾールというホルモンが大量に分泌され、その直下にある自律神経にも悪影響を及ぼします。
自律神経が乱れ、リラックスし身体を休ませる副交感神経よりも、日常の活動のために身体を緊張させる交感神経が優位な状況が続くと血管が収縮し、全身の血めぐりが悪くなってしまいます。全身に熱を運んでくれる血のめぐりが悪くなるということは、身体が冷えてしまうということになります。
そして、体が冷え、良質な睡眠をとることができないと、さらに自律神経が乱れてしまい、もっと冷える……という冬の不眠サイクルに陥ってしまうのだそうです。
だからこそ、自律神経を整えること、血めぐりをよくすることが良質な眠りにつながるのです!
冬不眠を脱出するために心がけたい5つのこと
人の身体は、寝る前に体温が上がり、身体の表面、特に手足からの放熱が促され、体温が下がることで眠くなります。そのためには血めぐりをよくすることが不可欠です。
それでは、冬不眠を脱出するために心がけたいことをご紹介します。
1.首元をあたためる!
首元をほんわかあたためることで、副交感神経に切り替わり、リラックススイッチがON!就寝の30分くらい前に温かいタオルや市販の温熱シートで温めると、眠りやすくなります。
2.湯船に浸かる!
湯船には浸からず、時間がないから、シャワーだけで済ましてしまう……なんて人も多いかもしれませんが、これはいけません!
38度から40度以下のぬるめのお湯にゆっくりとつかると、全身の血管が開き、「血めぐり」がよくなるので、良質な睡眠のためにはできるだけ、湯船に入る習慣を心がけましょう!
3.眠る前のテレビや携帯はやめる!
次々に切り替わる画面、音、明かりなどの刺激に集中すると、交感神経が優位になり緊張状態となってしまうため、眠れないことがあります。
眠る前、ベッドに入ってゲームやSNSをチェック……これはやめましょう!
4.夜に甘いものは食べない!
甘いものを食べると血糖値が上がります。血糖値が上がり過ぎると体に負担になってしまうため、一生懸命血糖値を下げようとする力が働きます。
血糖値が上下することで、自律神経が乱れてしまうことになってしまうのだとか。
5.リラックス状態を作る!
忙しい毎日、1日の中でどうしても交感神経が優位な時間が多くなってしまうこともあるかもしれません。だからこそ、努めて、30分でも1時間でも、リラックスできるような音楽を聴いたり、深呼吸をしたり、ゆっくりとする時間を作って、副交感神経にしっかり働いてもらうようにコントロールしましょう。
寒さにストレスを感じる「冷感ストレス」、そして、普段のついついやってしまいがちなライフスタイルが「冬不眠」を引き起こしているかもしれません。
緊張状態がずっと続いていると自律神経が乱れてしまうので、今回、ご紹介した5つのことに気をつけて、リラックスし身体を休ませる副交感神経に働いてもらえるように心がければ、きっとぐっすり眠れますよ!
[ウレぴあ総研]
Posted by nob : 2014年02月17日 17:33
バランスの取れた食事と規則正しい当たり前の暮らし、、、に尽きます。。。
■専門家が警告 大ブームの「食事は炭水化物抜き」が一番危ない 糖質制限ダイエットで「寝たきり」が続出中!
「即効性がある」とブームが続く糖質制限ダイエット。だが今、その安全性に警鐘が鳴らされ始めた。その時、体の中で何が起こるのか。手遅れになる前に知っておきたい、超人気ダイエットの真実。
体重と一緒に筋力も落ちる
「3年前に受けた人間ドックで『糖尿病予備軍』と診断されました。定年後は家にこもることが多くなって、体重も70kgから85kgまで増えた。階段の上り下りなど、ちょっと動くだけできついし、息もすぐに切れる。このままではまずいと思い、45歳の息子が『1ヵ月で4kgも痩せた』と喜んでいたダイエットを始めました」
こう語るのは渡辺吉孝さん(70歳・仮名)だ。取り組んだのは、今話題の「糖質制限ダイエット」。
書店には関連書籍がズラリと並び、メディアにも頻繁に取り上げられている。やり方はシンプルで、ご飯やパン、芋、果物などの炭水化物に含まれる糖質の摂取量を一日130g以下に抑えるというもの。炭水化物を極力減らせば、おかずはなんでも、好きなだけ食べていい。
もともとは糖尿病や重度の肥満患者に対する食事療法として考案されたものだが、いまや「手軽に痩せられるダイエット法」として、老若男女を問わず人気を集めている。人気の秘密は、糖質さえ制限していれば、あとは肉でもアルコールでも摂取OKという取り組みやすさと、目に見えて現れる効果にある。
炭水化物の糖分は体内で中性脂肪に変わり、人間のエネルギー源となる。炭水化物を絶つことで中性脂肪を減らして痩せる、いたって単純なメカニズムのダイエット法だ。
冒頭の渡辺さんも、ご飯や麺類などの主食をいっさい抜き、肉をメインとするおかずで腹を満たす食事を続けた。その結果、1年半で9kgのダイエットに成功したのだが、同時に大問題を抱え込んだ。渡辺さんが続ける。
「初めは調子が良かったんです。1ヵ月でお腹回りがスッキリしてきて、体重が5kg減りました。効果覿面だったことが嬉しくて、それから1年半、みっちり糖質制限をした結果、体重を85kgから76kgまで落とすことができました。
当然、体重が落ちれば身のこなしも軽くなるだろうと思っていました。ところが、次第に筋力が落ち、階段の上り下りが以前にまして苦しくなってしまったんです。そんなある日、庭の手入れをしていてトンと尻もちをついたら、それだけで尾てい骨が折れた。入院して検査をしたら、『骨密度が65%しかない。骨粗鬆症です。尾てい骨の圧迫骨折もそれが原因です』と診断されました」
3年前に人間ドックで測った骨密度は75%。ダイエットを経て、たった1年半で10%も落ちたことになる。
このまま長期入院すると寝たきりになるという主治医の判断で、渡辺さんは自宅療養に切り替えたが、いまだに足腰の筋力が戻らず、歩くことができないままだ。
今、このような糖質制限ダイエットによるトラブルが、あちこちで起き始めている。専門家の間でも、糖質制限ダイエットは危険だと警鐘を鳴らす声は大きくなる一方だ。
糖質制限は、なぜ危険なのか。糖尿病の世界的権威で、関西電力病院院長の清野裕医師が解説する。
「人間には一日170gの糖が必要とされています。そのうちの120~130gは脳で消費され、30gは全身に酸素などを運ぶ赤血球のエネルギー源として消費されます。糖質は、生命を維持するために欠かせない栄養素なのです。
糖質を制限してしまうと、代わりにタンパク質を構成しているアミノ酸を、肝臓が糖に作り変えるというシステムが働き始めます。タンパク質を糖に変えられるなら、肉を食べれば問題ないのではないかと思う方もいるでしょう。しかし、人体の維持に必要なエネルギーをタンパク質や脂質でまかなおうと思ったら、毎日大量の肉を食べなければなりません。数kgもの肉を毎日食べ続けることは現実的に不可能です。糖エネルギーが不足すると、それを補うために、体は自分の筋肉を分解してアミノ酸に変えていきます。結果、筋肉量がどんどん減っていってしまうのです」
認痴症まで一直線
渡辺さんの筋力が落ちた原因は、まさにこれだ。渡辺さんの場合は特に、3食とも主食を完全に抜くというハードな糖質制限を行っていたため、筋肉もどんどん失われていったのだ。なぜ、このような危険な食事制限がまかり通ってしまうのか。
「実は糖質制限ダイエットには、はっきりした科学的根拠やガイドラインがないのです。だから、評判ばかりが独り歩きして、過剰なやり方が横行する。若い人や糖尿病患者が、医師の指導のもとで一定期間やるのはいいでしょう。しかし、65歳以上の高齢者は安易に手を出すべきではない。寝たきりになる危険性が非常に高いからです。実際、私の病院でも糖質制限で筋力が低下したと来院する高齢患者が増えています」(前出・清野医師)
糖質制限ダイエットが引き起こす問題は、筋肉量の低下だけではない。実は骨にも甚大な影響を及ぼす。
「渡辺さんのケースも、糖質制限が原因でしょう。
また、要注意なのは女性。骨粗鬆症は圧倒的に女性に多く、60歳代で 2人に1人、70歳以上で10人に7人が悩んでいます。ダイエットは女性のほうが熱心だからでしょうか。糖質制限を始めて骨粗鬆症を加速させてしまったという中高年女性の患者が、すでに何人か駆け込んできています。筋力が低下したり、骨粗鬆症になってしまった高齢者は、ほんのちょっとの病気や怪我で入院すると、あっという間に寝たきりになってしまいます」(愛し野内科クリニック院長で糖尿病専門医の岡本卓医師)
忍び寄る「寝たきり」の恐怖—。自分の足で立つことができなくなった日から、一体どのような暮らしが始まるのだろうか。
一度失った体力を元に戻すのは容易ではない。多くの場合、みるみる足腰が衰え、家族やヘルパーの手を借りなければ日常生活が送れなくなる。食事、入浴など身の回りの世話はもちろん、いずれトイレも自力でできなくなってしまう。妻や子供におむつを取り替えてもらうのが、もっともつらいと明かす人も多い。
思うようにならない毎日にあなたは絶望し、もう誰とも話したくないと思い始める。そこまできたら、認知症までまっしぐら。やがて判断能力がなくなり、家族の顔も忘れ、孤独のうちに一生を終える—。
ダイエットが引き金となり、このような悲惨な終末を迎えることになってはたまったものではない。だが、これだけでは終わらない。糖質制限は、他にも寝たきりに繋がる病気を誘発すると言われている。
厚生労働省の国民生活基礎調査によると、65歳以上の高齢者が寝たきりになる直接の原因は、1位が脳卒中、2位が認知症、3位が衰弱・老衰で、4位が骨折となっている。
血液もドロドロになる
実は、寝たきりの原因1位の脳卒中も、糖質制限ダイエットと深い関わりがあるということが、最新の医療調査で明らかになった。実例を見てみよう。
荻原貞雄さん(69歳・仮名)は、現在、半身不随で療養型病院に入院している。そこに至った原因が糖質制限によるものだったのではないかと語るのは、荻原さんと長年の付き合いがあるかかりつけ医だ。
「荻原さんは中肉中背で、特に肥満が気になるわけではありませんでした。一日5kmのジョギングが日課で、運動も十分やっていた。そのままの生活を続けていても健康に問題はなかったでしょう。
ところが'08年、ブームに乗って糖質制限ダイエットを始めたのです。荻原さんは半年で6kgも痩せ、かなり細い体つきになっていました。本人もその変化に非常に満足そうでした」
だが、ダイエット開始から4年目の夏、荻原さんは突然病魔に倒れた。脳卒中だった。
「頸動脈の血管エコー検査をしたところ、ひどい高脂血症が判明。血管の壁が1・8㎜の厚さになっている部分もあった。重度の動脈硬化が引き起こした脳卒中だったのです」
荻原さんの身に、一体何が起こったのか。かかりつけ医が続ける。
「一般的に、糖質制限をするとカロリーを補うために脂質やタンパク質を大量に摂るようになります。すると、血管に悪玉コレステロールが溜まっていく。その結果、血管が傷んだり老化が進んだりして、脳梗塞や心筋梗塞を起こす可能性がどんどん高まっていくんです。
特に肉類が大好物だった荻原さんにとって、炭水化物さえ抜けば、あとは何を飲み食いしてもいいという謳い文句は非常に魅力的だったのでしょう。トンカツや焼き肉、ステーキなど、がっつりした肉料理ばかり食べていたため、コレステロールが溜まりに溜まってしまったのです。
病院に担ぎ込まれた時点で半身は完全にマヒ。まさか気軽に始めたダイエットで半身マヒになるとは、思いもよらなかったでしょう。今となっては話すことも不自由で、後遺症を克服するメドは立っていません」
筋力低下、骨粗鬆症、動脈硬化が引き起こす脳卒中—さまざまな病気との関係が指摘される糖質制限。
「今、このダイエットを実践している人は幅広い年代に広がっています。今後さらに時間がたてば、間違いなく寝たきりになる人が続出すると予測されます」(都内病院・骨粗鬆症外来担当医)
見た目と健康、どっちが大事?
寝たきりどころか、最悪の場合、死に至ると警鐘を鳴らすのは、自身が糖質制限ダイエットを実践し、その結果危険な状態に陥った経験を持つ、Rサイエンスクリニック広尾院長の日比野佐和子医師(44歳)だ。
「ご飯からお菓子まで、炭水化物は一切とらず、その代わり好きなものを好きなだけ食べているうちに、瞬く間に15kg痩せました。『効果が目に見えて出る。だから、嬉しくてどんどん続けてしまう』—実はこれが糖質制限の怖いところなのですが、当時は私も、これほど楽なダイエットはないと思っていました。
しかし、続けているうちに常に体がしんどく、眠気が抜けない状態が続くようになりました。そして36歳のある朝、目覚めると右半身がピクリとも動かなかったのです。救急車を呼ぼうと立ち上がろうとしても、右手と右足の感覚が一切ない。これは大変なことになってしまったと覚悟しましたが、幸い10分くらいで動けるようになり、自力で病院に行きました。MRIを撮った結果、微小な脳梗塞があることが分かりました。脳梗塞の前の段階、一過性脳虚血発作の症状でした。
今ならこのダイエットが腎臓や肝臓、血管など、さまざまな部位に障害を引き起こす可能性があると分かっていますが、当時は気づきませんでした。30代半ばだった私でさえ、そのような状態になったのですから、年齢が上がるほどリスクも上がる。高齢者であれば死に至ることも十分あり得るでしょう」
命の危険すら指摘され始めた糖質制限ダイエット。だが、「痩せる」という効果があることは否めない。「身体にやさしい糖質制限」という都合のいいダイエット法はないのか。食物学学術博士の佐藤秀美氏が解説する。
「高齢でも、体型がどうしても気になる、という人はたくさんいると思います。そういった人は、甘い菓子などの炭水化物の間食を辞めるだけで、大きな効果が得られるはずです。
高齢者にとって、タンパク質は何よりも重要で貴重な栄養素。糖質制限のやりすぎで、不足する糖を補うためにタンパク質を消費することは、絶対に避けるべきなのです」
筋肉だけでなく、臓器や皮膚や骨、血液に至るまで、人体のすべての細胞はタンパク質でできている。そして細胞は、1年後にはすべて新しい細胞に生まれ変わる。
「高齢者は消化吸収能力が落ちているため、男子高校生より体重1kg につき必要な1日のタンパク質の量が多い。そうでないと、体が維持できないからです。そんな高齢者が糖質制限をすれば、内臓組織の原料となるタンパク質が不足し、体はどんどん老化します。だから原則的に、糖質を減らしてはいけない。やるとしても、おやつなどの間食を抜くだけにする。高齢になったら、糖質とタンパク質、両方のバランスをよく考えて食事をすることが望ましいのです。
大事なのは、ダイエットは何のためにするのか、ということ。見た目だけが少し良くなったとしても、肝心の健康を損なったのでは何の意味もありません。ぜひこのことを念頭に置き、自分の身を守っていただきたいと思います」(佐藤氏)
特に高齢世代は、ブームだからといって「糖質制限」に飛びつくと、寝たきりのリスクが劇的に高まることを忘れてはならない。
[週刊現代]
Posted by nob : 2014年02月17日 17:26
好きな他者になら途は示すも、引きも押しもしない、、、利害という色眼鏡を棄て、一切の執着や依存心から脱却できれば、そこから愛と信頼に満ちた世界を拡げていける。。。
■第1回
人生の迷いを断ち切る
アドラーの思想とは?
欧米ではフロイト、ユングと並び「心理学界の三大巨頭」と称され、絶大な支持を誇るアルフレッド・アドラー。名著『人を動かす』のデール・カーネギーら自己啓発のメンターたちにも多大な影響を与えた彼の思想は、日本ではまだあまり知られていない。
そこで今回、日本アドラー心理学会顧問の岸見一郎氏とライターの古賀史健氏がタッグを組み、哲人と青年の対話篇形式によるまったく新しい古典『嫌われる勇気——自己啓発の源流「アドラー」の教え』を刊行した。いったいアドラーとはどんな人物で、どんな思想の持ち主なのか、共著者の古賀史健氏が解説する。
時代を100年先行した
知られざる巨匠
「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」
20世紀の初頭、そんなことを唱えはじめた心理学者がいました。欧米でいまなお絶大な支持を誇り、フロイト、ユングと並ぶ「心理学界の三大巨頭」と称されるオーストリア出身の精神科医、アルフレッド・アドラーです。
欧米におけるアドラーの受け入れられ方は、フロイトやユングとは若干違います。たとえば、世界的ベストセラーの『人を動かす』や『道は開ける』で知られるデール・カーネギーは、アドラーのことを「一生を費やして人間とその潜在能力を研究した偉大な心理学者」と紹介し、彼の著作にはアドラーの思想が色濃く反映されています。また、スティーブン・コヴィーの『7つの習慣』でもアドラーの思想に近い内容が語られています。つまりアドラー心理学は、堅苦しい学問としてではなく、人間理解の真理、または到達点として、広く受け入れられているわけです。
しかし、「時代を100年先行した」といわれる彼の思想には、まだ時代が追いつききれていません。日本における知名度も、フロイトやユングと比べたらかなり限定的なものでしょう。彼の考えは、それほど先駆的なものでした。
本書『嫌われる勇気』は、そんなアドラーの画期的な思想を、架空の「哲人」と「青年」による対話篇のかたちを採りながら解き明かしていく一冊になります。それでは具体的に、アドラーはどんな思想の持ち主なのでしょうか?
もし、彼の思想をひと言で要約するなら、次のようになるかもしれません。
「世界」を変えるのは、他の誰でもない「わたし」である。
アドラーの思想を理解し、実践することができれば、確実に「世界」が変わります。そして「世界」を変えるのは、どこかの国の大統領でもなければ一部のエリート層でもなく、ただただ「わたし」なのです。
本書の中で哲人は、こんな話をしています。
哲人 いま、あなたの目には世界が複雑怪奇な混沌として映っている。しかし、あなた自身が変われば、世界はシンプルな姿を取り戻します。問題は世界がどうであるかではなく、あなたがどうであるか、なのです。
青年 わたしがどうであるか?
哲人 そう。もしかするとあなたは、サングラス越しに世界を見ているのかもしれない。そこから見える世界が暗くなるのは当然です。だったら、暗い世界を嘆くのではなく、ただサングラスを外してしまえばいい。そこに映る世界は強烈にまぶしく、思わずまぶたを閉じてしまうかもしれません。再びサングラスがほしくなるかもしれません。それでもなお、サングラスを外すことができるか。世界を直視することができるか。あなたにその“勇気”があるか、です。
青年 勇気?
哲人 ええ、これは“勇気”の問題です。
人は誰しも客観的な世界に住んでいるのではなく、自らが意味づけをほどこした主観的な世界に住んでいる。それがアドラーの考え方です。つまり、たとえば過去のつらい出来事に対しても「なにがあったか」が問題なのではなく、「どう解釈するか」が問題なのだと考えます。ニーチェ的にいえば「客観的な事実など存在せず、主観的な解釈のみが存在している」とすることもできるでしょう。
この発想は、アドラー心理学の大きな特徴である「目的論」という考えのなかで、より鮮明になります。
たとえば、自室にずっと引きこもっている人がいたとき、フロイト的な発想では「不安だから、引きこもっている」というように考え、「両親に虐待を受け、愛情を知らないまま育った。だから他者と交わるのが怖いのだ」と結論づけるなど、その人が引きこもるに至った「原因」に注目します(原因論)。
しかしアドラー心理学では、その人が隠し持つ「目的」を考えていくのです(目的論)。再び本文から哲人と青年の対話を引きましょう。友人が引きこもりになっているという青年に対して、哲人は次のように語ります。
哲人 アドラー心理学では、過去の「原因」ではなく、いまの「目的」を考えます。
青年 いまの目的?
哲人 ご友人は「不安だから、外に出られない」のではありません。順番は逆で「外に出たくないから、不安という感情をつくり出している」と考えるのです。
青年 はっ?
哲人 つまり、ご友人には「外に出ない」という目的が先にあって、その目的を達成する手段として、不安や恐怖といった感情をこしらえているのです。アドラー心理学では、これを「目的論」と呼びます。
青年 ご冗談を! 不安や恐怖をこしらえた、ですって? じゃあ先生、あなたはわたしの友人が仮病を使っているとでもいうのですか?
哲人 仮病ではありません。ご友人がそこで感じている不安や恐怖は本物です。場合によっては割れるような頭痛に苦しめられたり、猛烈な腹痛に襲われることもあるでしょう。しかし、それらの症状もまた、「外に出ない」という目的を達成するためにつくり出されたものなのです。
青年 ありえません! そんな議論はオカルトです!
引きこもりの人は「外に出ない」という目的をかなえるために、不安や恐怖などの感情をつくりあげている。これは即座に納得できる議論ではないでしょう。作中の青年も、すぐさま反発します。
青年 そこまで強くおっしゃるのなら、しっかり説明していただきましょう。そもそも、「原因論」と「目的論」の違いとはどういうことです?
哲人 たとえば、あなたが風邪で高熱を出して医者に診てもらったとします。そして医者が「あなたが風邪をひいたのは、昨日薄着をして出かけたからです」と、風邪をひいた理由を教えてくれたとしましょう。さて、あなたはこれで満足できますか?
青年 できるはずもないでしょう。理由が薄着のせいであろうと、雨に降られたせいであろうと、そんなことはどうでもいい。問題は、いま高熱に苦しめられているという事実であり、症状です。医者であるならば、ちゃんと薬を処方するなり、注射を打つなり、なにかしらの専門的処置をとって、治療してもらわなければなりません。
哲人 ところが原因論に立脚する人々、たとえば一般的なカウンセラーや精神科医は、ただ「あなたが苦しんでいるのは、過去のここに原因がある」と指摘するだけ、また「だからあなたは悪くないのだ」と慰めるだけで終わってしまいます。いわゆるトラウマの議論などは、原因論の典型です。
青年 ちょっと待ってください! つまり先生、あなたはトラウマの存在を否定されるのですか?
哲人 断固として否定します。
青年 なんと! 先生は、いやアドラーは、心理学の大家なのでしょう!?
哲人 アドラー心理学では、トラウマを明確に否定します。ここは非常に新しく、画期的なところです。
トラウマを否定する
「目的論」とは
そう。いまや日常語になった感さえある「トラウマ」という言葉、そこから受ける影響を、アドラー心理学では明確に否定します。これがどれだけ斬新で過激な主張であるかは、おそらく心理学を専門に学んでこなかった方々(わたしもそのひとりです)にも理解していただけるでしょう。哲人はこう続けます。
哲人 たしかにフロイト的なトラウマの議論は、興味深いものでしょう。心に負った傷(トラウマ)が、現在の不幸を引き起こしていると考える。人生を大きな「物語」としてとらえたとき、その因果律のわかりやすさ、ドラマチックな展開には心をとらえて放さない魅力があります。
しかし、アドラーはトラウマの議論を否定するなかで、こう語っています。「いかなる経験も、それ自体では成功の原因でも失敗の原因でもない。われわれは自分の経験によるショック――いわゆるトラウマ――に苦しむのではなく、経験の中から目的にかなうものを見つけ出す。自分の経験によって決定されるのではなく、経験に与える意味によって自らを決定するのである」と。
青年 目的にかなうものを見つけ出す?
哲人 そのとおりです。アドラーが「経験それ自体」ではなく、「経験に与える意味」によって自らを決定する、と語っているところに注目してください。
たとえば大きな災害に見舞われたとか、幼いころに虐待を受けたといった出来事が、人格形成に及ぼす影響がゼロだとはいいません。影響は強くあります。しかし大切なのは、それによってなにかが決定されるわけではない、ということです。われわれは過去の経験に「どのような意味を与えるか」によって、自らの生を決定している。人生とは誰かに与えられるものではなく、自ら選択するものであり、自分がどう生きるかを選ぶのは自分なのです。
トラウマなどない。われわれは過去の経験に「どのような意味を与えるか」によって、自らの生を決定している。それがアドラーの主張であり、目的論です。
それでは具体的に、引きこもりの人はどんな「目的」を持って自室に引きこもっているのでしょうか。
青年 どうして外に出たくないのですか? 問題はそこでしょう!
哲人 では、あなたが親だった場合を考えてください。もしも自分の子どもが部屋に引きこもっていたら、あなたはどう思いますか?
青年 それはもちろん心配しますよ。どうすれば社会復帰してくれるのか、どうすれば元気を取り戻してくれるのか、そして自分の子育ては間違っていたのか。真剣に思い悩むだろうし、社会復帰に向けてありとあらゆる努力を試みるでしょう。
哲人 問題はそこです。
青年 どこです?
哲人 外に出ることなく、ずっと自室に引きこもっていれば、親が心配する。親の注目を一身に集めることができる。まるで腫れ物に触るように、丁重に扱ってくれる。
他方、家から一歩でも外に出てしまうと、誰からも注目されない「その他大勢」になってしまいます。見知らぬ人々に囲まれ、凡庸なるわたし、あるいは他者より見劣りしたわたしになってしまう。そして誰もわたしを大切に扱ってくれなくなる。……これなどは、引きこもりの人によくある話です。
引きこもることによって、周囲(特に家族)の注目を集め、特別な存在になろうとする。もし引きこもりをやめてしまったら、自分は誰からも注目されず、どこにでもいる「その他大勢」になってしまう。アドラー心理学の目的論は、過去の「原因」ではなく、いま現在の「目的」から人間理解を進めていくのです。
過去になにがあったかなど関係ない
引きこもりの事例だけでは納得できない方のために、もうひとつの事例を挙げておきましょう。不登校やリストカットなどの問題行動についての考察です。
哲人 親から虐げられた子どもが非行に走る。不登校になる。リストカットなどの自傷行為に走る。フロイト的な原因論では、これを「親がこんな育て方をしたから、子どもがこんなふうに育った」とシンプルな因果律で考えるでしょう。植物に水をあげなかったから、枯れてしまったというような。たしかにわかりやすい解釈です。
しかし、アドラー的な目的論は、子どもが隠し持っている目的、すなわち「親への復讐」という目的を見逃しません。自分が非行に走ったり、不登校になったり、リストカットをしたりすれば、親は困る。あわてふためき、胃に穴があくほど深刻に悩む。子どもはそれを知った上で、問題行動に出ています。過去の原因(家庭環境)に突き動かされているのではなく、いまの目的(親への復讐)をかなえるために。
青年 親を困らせるために、問題行動に出る?
哲人 そうです。たとえばリストカットをする子どもを見て「なんのためにそんなことをするんだ?」と不思議に思う人は多いでしょう。しかし、リストカットという行為によって、周囲の人――たとえば親 ――がどんな気持ちになるのかを考えてみてください。そうすれば、おのずと行為の背後にある「目的」が見えてくるはずです。
青年 ……目的は、復讐なのですね。
フロイト的な原因論を否定し、トラウマの影響を否定し、自分の行動を目的論の立場でとらえなおすことは、かなり厳しい作業だと思います。
極端な話、原因論に立てば「いまの自分がこうなのは、親のせいだ」とか「生まれ育った環境のせいだ」と、責任転嫁することができます。
一方、アドラー的な目的論は、責任転嫁を許しません。「こんな自分」を選んだのは他ならぬ自分であり、なんらかの目的――たとえば努力をしたくないとか、失敗して恥をかきたくないとか、「やればできる」という可能性を残しておきたいとか――をかなえるために「こんな自分」であり続けている、と考えるのが目的論だからです。正面から受け止めるには、かなりの時間と勇気とを必要とする議論でしょう。
しかし、こう考えてください。アドラーの目的論は「これまでの人生になにがあったとしても、今後の人生をどう生きるかについてなんの影響もない」といっているのです。過去など存在しないし、トラウマも存在しない。あなたは「いま」、ここで自分の人生を選ぶことができるのだと。
われわれはタイムマシンで過去にさかのぼることなどできません。原因論の立場に立って「あんな家庭に生まれ育ったから」とか「あんな大学しか出てないから」と考えていたら、物事は一歩も前に進まないはずです。
原因論を切り捨て、目的論を受け入れる勇気を持ちえたときにこそ、はじめて自分を変えるチャンスが出てくるのです。
前編となる今回は「目的論」の話だけで紙幅が尽きてきました。次回の後編では、冒頭に紹介した「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」という言葉を出発点に、人生の悩みを一気に解決させる具体的方策を紹介していきたいと思います。
■第2回
他者の期待を満たすために
生きてはいけない
「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」と語るアルフレッド・アドラー。われわれは対人関係から解放されれば、すべての悩みを消すことができる。けれども対人関係をゼロにするなど、絶対にできないだろう。そこでアドラーは、対人関係の悩みを一気に解決する具体策を提示する。いったいなぜ「すべて対人関係の悩み」なのか? そしてどうやって「対人関係の悩み」を断ち切るのか?
人は社会的な文脈においてのみ
「個人」になる
人は誰しも、なにかしらの悩みを抱えて生きているものです。仕事がうまくいかないとか、失恋をしてしまったとか、自分の容姿が嫌いだとか、いろんな悩みがあるでしょう。こうした現実に対して、アドラー心理学では「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」と考えます。あらゆる悩みは「対人関係の悩み」に還元される。個人だけで完結する悩み、いわゆる内面の悩みなどというものは存在しないのだと。
はじめてこの考えに触れたとき、わたしは大きな違和感を覚えました。おそらく、みなさんも同じではないでしょうか。『嫌われる勇気』に登場する青年も、驚きながら反発します。
青年 いま、なんとおっしゃいました!?
哲人 何度でもくり返しましょう。「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」。これはアドラー心理学の根底に流れる概念です。もし、この世界から対人関係がなくなってしまえば、それこそ宇宙のなかにただひとりで、他者がいなくなってしまえば、あらゆる悩みも消え去ってしまうでしょう。
青年 噓だ! そんなものは学者の詭弁にすぎません!
哲人 もちろん、対人関係を消してしまうことなどできません。人間はその本質において、他者の存在を前提としている。他者から切り離されて生きることなど、原理的にありえない。「宇宙のなかにただひとりで生きることができれば」という前提が成立しえないのはおっしゃるとおりです。
アドラー心理学では、人間は「社会的な生き物」であると考えます。
もし仮に、われわれが「宇宙のなかにただひとり」で生きていたら、孤独は感じないでしょう。孤独を感じるのは、われわれが「ひとり」だからではなく、自分を取り巻く他者、社会、共同体があり、そこから疎外されていると実感するからこそ、孤独なのです。われわれは孤独を感じるのにも、他者を必要とします。人は社会的な文脈においてのみ、「個人」になるのです。
そんな「社会的な生き物」だからこそ、人間の悩みはすべて対人関係の悩みである。アドラーはそう主張するわけです。もちろん、この考えを素直に受け入れる青年ではありません。彼は激しく噛みつきます。
青年 先生、それでもあなたは哲学者ですか! 人間には、対人関係なんかよりもっと高尚で、もっと大きな悩みが存在します! 幸福とはなにか、自由とはなにか、そして人生の意味とはなにか。これらはまさに古代ギリシア以来、哲学者たちが問い続けてきたテーマではありませんか!
それがなんですって? 対人関係がすべてだと? なんと俗っぽい答えでしょう、哲学者が聞いて呆れますよ!
哲人 なるほど、もう少し具体的に説明する必要がありそうですね。
青年 ええ、説明してください! もしも先生がご自分を哲学者だとおっしゃるのであれば、ここはしっかり説明していただかなければ困ります!
他者との比較が劣等感を生む
なぜ「すべての悩みは対人関係」なのか。そう問われた哲人は、自身がかつて思い悩んでいた、身長についての劣等感を語りはじめます。
哲人 では、わたし自身の劣等感についてお話ししましょう。あなたは最初にわたしと会ったとき、どのような印象を持ちましたか? 身体的な特徴という意味で。
青年 ええっと、まあ……。
哲人 遠慮することはありません、率直に。
青年 そうですね、想像していたよりも小柄な方だと思いました。
哲人 ありがとう。わたしの身長は155センチメートルです。アドラーもまた、これくらいの身長だったといいます。かつてわたしは——まさにあなたくらいの年齢まで——自分の身長について思い悩んでいました。
身長が高いのか低いのか。一見するとこれは対人関係とは無縁の、内面的な悩みのように思えます。しかし、そうではないというのが哲人の、つまりアドラー心理学の考えです。哲人は友人から聞かされた「お前には人をくつろがせる才能がある」という言葉をきっかけに、そのことに気づきます。
哲人 わたしが自分の身長に感じていたのは、あくまでも他者との比較――つまりは対人関係――のなかで生まれた、主観的な「劣等感」だったのです。もしも比べるべき他者が存在しなければ、わたしは自分の身長が低いなどと思いもしなかったはずですから。あなたもいま、さまざまな劣等感を抱え、苦しめられているのでしょう。しかし、それは客観的な「劣等性」ではなく、主観的な「劣等感」であることを理解してください。身長のような問題でさえも、主観に還元されるのです。
青年 つまり、われわれを苦しめる劣等感は「客観的な事実」ではなく、「主観的な解釈」なのだと?
哲人 そのとおりです。わたしは友人の「お前には人をくつろがせる才能があるんだ」という言葉に、ひとつの気づきを得ました。自分の身長も「人をくつろがせる」とか「他者を威圧しない」という観点から見ると、それなりの長所になりうるのだ、と。
もちろん、これは主観的な解釈です。もっといえば勝手な思い込みです。ところが、主観にはひとつだけいいところがあります。それは、自分の手で選択可能だということです。自分の身長について長所と見るのか、それとも短所と見るのか。いずれも主観に委ねられているからこそ、わたしはどちらを選ぶこともできます。
われわれが抱える劣等感とは、他者との比較から生まれるものであり、「対人関係の悩み」である。そして、もしもこの世界に自分以外の誰ひとりも存在しなければ、あらゆる悩みはなくなってしまう。言葉も、論理も、コモンセンスも必要なくなる。「価値」そのものが存在しなくなる。逆にいえば、人間の悩みはすべてが対人関係に端を発することになる。それがアドラーの考えです。
ちなみに、「劣等感」という言葉を現在語られているような文脈で使ったのは、アドラーが最初だとされています。
人生の悩みを吹き飛ばす
「課題の分離」とは
そして対人関係の悩みを一蹴するために登場するのが、アドラー心理学独自の「課題の分離」という発想になります。「課題の分離」がどんなものであるか、再び哲人と青年の対話を引きましょう。
哲人 わかりました。それでは、アドラー心理学の基本的なスタンスからお話ししておきます。たとえば目の前に「勉強する」という課題があったとき、アドラー心理学では「これは誰の課題なのか?」という観点から考えを進めていきます。
青年 誰の課題なのか?
哲人 子どもが勉強するのかしないのか。あるいは、友達と遊びに行くのか行かないのか。本来これは「子どもの課題」であって、親の課題ではありません。
青年 子どもがやるべきこと、ということですか?
哲人 端的にいえば、そうです。子どもの代わりに親が勉強しても意味がありませんよね?
青年 まあ、それはそうです。
哲人 勉強することは子どもの課題です。そこに対して親が「勉強しなさい」と命じるのは、他者の課題に対して、いわば土足で踏み込むような行為です。これでは衝突を避けることはできないでしょう。われわれは「これは誰の課題なのか?」という視点から、自分の課題と他者の課題とを分離していく必要があるのです。
青年 分離して、どうするのです?
哲人 他者の課題には踏み込まない。それだけです。
青年 ……それだけ、ですか?
哲人 およそあらゆる対人関係のトラブルは、他者の課題に土足で踏み込むこと――あるいは自分の課題に土足で踏み込まれること――によって引き起こされます。課題の分離ができるだけで、対人関係は激変するでしょう。
たとえばアドラー心理学のカウンセリングでは、相談者が変わるか変わらないかは、カウンセラーの課題ではないと考えます。カウンセリングを受けた結果、相談者がどのような決断を下すのか。これまでの自分を変えて、新しい一歩を踏み出すのか。それとも、このまま踏みとどまるのか。これは相談者本人の課題であり、カウンセラーはそこに介入できないのです。
もちろんカウンセラーも、精いっぱいの援助はします。ある国に「馬を水辺に連れていくことはできるが、水を呑ませることはできない」ということわざがあるそうですが、まさにアドラー心理学のカウンセリング、そして他者への援助全般もそういうスタンスだと考えてください。
課題の分離という発想に納得できない青年に対し、哲人はこんな言葉をぶつけます。
哲人 あなたは大きな勘違いをしている。いいですか、われわれは「他者の期待を満たすために生きているのではない」のです。
青年 なんですって?
哲人 あなたは他者の期待を満たすために生きているのではないし、わたしも他者の期待を満たすために生きているのではない。他者の期待など、満たす必要はないのです。
青年 い、いや、それはあまりにも身勝手な議論です! 自分のことだけを考えて独善的に生きろとおっしゃるのですか?
哲人 ユダヤ教の教えに、こんな言葉があります。「自分が自分のために自分の人生を生きていないのであれば、いったい誰が自分のために生きてくれるだろうか」と。あなたは、あなただけの人生を生きています。誰のために生きているのかといえば、無論あなたのためです。そしてもし、自分のために生きていないのだとすれば、いったい誰があなたの人生を生きてくれるのでしょうか。われわれは、究極的には「わたし」のことを考えて生きている。そう考えてはいけない理由はありません。
われわれは「他者の期待を満たすために生きているのではない」。そして同時に、他者もまた「あなたの期待を満たすために生きているのではない」。自分を曲げてまで相手の期待に合わせる必要はないし、相手が自分の思うとおりに動いてくれなくても、怒ってはいけない。それが当たり前なのだと考えるのです。哲人は一気に畳みかけます。
哲人 われわれはみな、対人関係に苦しんでいます。それはご家族との関係かもしれませんし、職場での対人関係かもしれません。そして前回、あなたはいいましたね? もっと具体的な方策がほしい、と。
わたしの提案は、こうです。まずは「これは誰の課題なのか?」を考えましょう。そして課題の分離をしましょう。どこまでが自分の課題で、どこからが他者の課題なのか、冷静に線引きするのです。
そして他者の課題には介入せず、自分の課題には誰ひとりとして介入させない。これは具体的で、なおかつ対人関係の悩みを一変させる可能性を秘めた、アドラー心理学ならではの画期的な視点になります。
自由とは他者から
嫌われることである
本書のタイトル『嫌われる勇気』が、どのような思想に基づくものか、少しずつ見えてきたでしょう。最後に、「他者から嫌われること」をめぐって交わされる対話を引用して、この記事の終わりにしたいと思います。
哲人 何度もくり返してきたように、アドラー心理学では「すべての悩みは、対人関係の悩みである」と考えます。つまりわれわれは、対人関係から解放されることを求め、対人関係からの自由を求めている。しかし、宇宙にただひとりで生きることなど、絶対にできない。ここまで考えれば、「自由とはなにか?」の結論は見えたも同然でしょう。
青年 なんですか?
哲人 すなわち、「自由とは、他者から嫌われることである」と。
青年 な、なんですって!?
哲人 あなたが誰かに嫌われているということ。それはあなたが自由を行使し、自由に生きている証であり、自らの方針に従って生きていることのしるしなのです。
(中略)
青年 ……先生はいま、自由ですか?
哲人 ええ。自由です。
青年 嫌われたくはないけど、嫌われてもかまわない?
哲人 そうですね。「嫌われたくない」と願うのはわたしの課題かもしれませんが、「わたしのことを嫌うかどうか」は他者の課題です。わたしをよく思わない人がいたとしても、そこに介入することはできません。
今回は、本書『嫌われる勇気』の中から、「目的論」と「課題の分離」にポイントを絞ってお話を進めました。もちろんアドラーの思想はこれだけにとどまるものではありません。われわれにとって仕事とはなにか、愛とはなにか、われわれはいかに生きるべきか、人生とはなんなのか、そして幸福とはなんなのか、などありとあらゆるテーマについて、哲人と青年が存分に語り尽くしています。
アドラー心理学は「勇気の心理学」です。われわれの人生を決めるのは、生まれ育った環境でもなければ、先天的な能力(才能)でもない。変わろうとする「勇気」があるか。前に進もうとする「勇気」があるか。それだけだと考えます。
もし前後編にわたってお送りしたこの記事に少しでも興味を抱かれたなら、ぜひ『嫌われる勇気』を手に取ってみてください。アドラーの厳しくも希望に満ちたメッセージは、必ずやわれわれの人生を変えてくれるものだと確信しています。
古賀史健 (こが・ふみたけ)
ライター/編集者。1973年福岡生まれ。1998年出版社勤務を経てフリーに。これまでに80冊以上の書籍で構成・ライティングを担当し、数多くのベストセラーを手掛ける。20代の終わりに『アドラー心理学入門』(岸見一郎著)に大きな感銘を受け、10 年越しで『嫌われる勇気』の企画を実現。
[いずれもDIAMOND online]
Posted by nob : 2014年02月17日 16:52
私もかつて唐突にこの真実に気付き、以来自他すべてをあるがままに受容し、自らの満足を目指す過程での日々の納得を積み重ね、好きなものだけに包まれた幸せな毎日を過ごせています♬
■【安藤美冬×岸見一郎 対談】(前編)
一度知ったら引き返せない「嫌われる勇気」の魔力
自由に生きるための武器「アドラー心理学」
「自由とは他者から嫌われることである」──フロイト、ユングと並んで「心理学の三大巨頭」と称されるアドラーの思想が、哲人と青年の対話を通して学べる書籍『嫌われる勇気』(岸見一郎・古賀史健著、ダイヤモンド社)。cakesでの同名連載をまとめた本書は、刊行からわずか1ヵ月半で8万部を突破。これほど多くの人に注目される本書の秘密は何なのでしょう。それを解き明かすため、今回は同書の著者の一人である哲学者・岸見一郎さんと、起業家・コラムニストの安藤美冬さんの対談をお届けします。
本書を「2013年に読んだ本No.1」と公言する安藤さんは、「ライフスタイルの編集」をテーマに、商品企画、企業コンサルティング、大学講師にコラム執筆など多種多様な仕事をパラレルに手がけていらっしゃいます。すでに自分らしい働き方やライフスタイルの実現という「自由」を謳歌しているように思える彼女は、アドラーの思想の何に衝撃を受けたのでしょうか?(構成:宮崎智之)
トラウマを作っているのは
現在の自分?!
安藤美冬(以下、安藤) 昨年末にニューヨークに行く用事がありまして、飛行機の中で『嫌われる勇気』を読みました。ひとことで言うと「開眼」したというか。「ただごとではないことが起こっているぞ」という直感に導かれるまま、ホテルにチェックインした後に再読し、結局1日に2回も読んでしまいました。
岸見一郎(以下、岸見) なんと、ありがとうございます。
安藤 2回目の読書を終えた直後のことです。本を閉じ、余韻を感じながらゆっくりと顔を上げると、目の前にニューヨークのホテルから見える朝焼けが広がっていました。それがもう、ものすごく綺麗で。自分の心にも光が広がっていくような、シンクロする感覚がありました。それほど影響を受けた特別な一冊だったので、先生とお話しするのを楽しみにしていました。
岸見 私も『僕たちはこうして仕事を面白くする』(NHK出版)で安藤さんを知って興味を持ち、他の著書を読み進めていたところだったので、今日をとても楽しみにしていました。安藤さんの発言はすごく面白いですね。
安藤 本当ですか! ありがとうございます。
岸見 安藤さんは、『嫌われる勇気』のどこを気に入ってくださったのでしょうか。
安藤 今はまったく違う分野を行き来していますが、本当のところ、私が子どもの頃からいちばん興味のある分野は、「心の探究」なんです。物心ついた頃から「人はどうすれば苦しみから逃れ、幸せを感じられるのか」という大きなテーマを考えずにはいられませんでした。小学校時代にいじめられたり、高校時代に親友が心の病気を発症したり、26歳で「抑うつ」と診断されて休職をしたりしたことが理由だと思います。「心」というつかみどころのないもの、それを理解しようと、たくさんの心関係の本を読んだり、何十ヵ国を旅したりしてきました。
岸見 具体的に行動を起こされるところが、安藤さんらしいですね。
安藤 そうしたなかで私がぶち当たった最大の疑問は、「トラウマはどうしたら克服できるのか」ということでした。なぜかというと、心のトラウマというものは厄介な代物で、探求すればするほど収拾がつかなくなるからです。トラウマを解決しようにも、次から次へと泉のように湧き出してきてキリがない。ひとつ癒せばまた別のトラウマが姿を現し、それをまた癒し……。それに対して、『嫌われる勇気』は明確にトラウマの存在を否定しています。その言い切りっぷりに、すごくスッキリしたんです。
岸見 とんでもないことを言っているとは思いませんでしたか?
安藤 ショックではありましたが、読み進めていくうちに「あぁ、なるほどな」と深く納得しました。というのも、これまで心やトラウマの探求をしてきたのに一向に答えが出ないのは、そもそもアプローチ自体がズレていたのではないかという、モヤモヤした気持ちを抱いていたからです。
岸見 ズレているというより、まったく違っていたのです。私がカウンセリングしている患者さんにも、過去のトラウマを持ち出して、それが、現在の状況が困難であることや生きづらさの原因だと言う人が多いですね。しかし、アドラー心理学では、トラウマの存在を否定します。そんなものは「ない」と。存在しないものを探したり、どうにかしようとしても、答えは永遠に見つかりませんよ。
安藤 『嫌われる勇気』でも、引きこもりは過去のトラウマが原因なのではない、「外に出ない(出たくない)」という「今の目的」のために不安や恐怖といった感情を作り出しているのだ、という話が紹介されていましたね。
岸見 そうです。アドラー心理学では、「過去の原因」ではなく「現在の目的」を考えていきます。そこが、過去(トラウマ)や無意識といった「原因」を重視するユングやフロイトの心理学と、大きく異なるところです。
安藤 これまで考えてもみなかった発想で、びっくりしました。なるほど、だから私はずっと悩み続けていたのか、と。
岸見 過去の経験に今の自分の原因を求めるほうが楽なのです。
安藤 今の自分に対して無責任でいられますからね。
岸見 それよりも、「過去に目を向けている自分」に目を向けてほしい。本当はもっと自由に生きられるのに、いつまでも不自由な生き方をしているということに気づいてもらいたいと思います。トラウマなど存在しないのだと言われると、人によっては抵抗する気持ちも出てくるでしょう。でも、そこを乗り切らないと、前に進むことはできません。
他人のスープに
つばを吐く厳しさ
安藤 先に申し上げたように、私は26歳で心の調子を崩し、半年ほど会社を休んだことがあります。そのことをメディアなどで公表していることもあり、勤務している大学の学生やソーシャルメディアのフォロワーさんから、個人的に心の問題を打ち明けられることが多いんです。心に悩みを抱えている人が絶えないのは、なぜなのでしょうか?
岸見 仕事に就いてみたけど、その仕事に向いていなかったなんてことは誰にでも起こり得ますよね。
安藤 そうですね。
岸見 それで、違う仕事に就くと決心したときに、ただ「自分自身が決めた」とシンプルに考えればいいのに、「心の調子や体調が悪くて続けられない」ことを、仕事を続けられないことの原因にする人がいる。そのほうが周りも納得するし、自分自身も楽なんですよ。でも、そういった行為に対してアドラーは、「人生の嘘」という、非常に厳しい言い方をしています。本当は「仕事ができないから転職して逃げる」などと他人に否定されることが耐えられなかったり、「その仕事に向いていない自分」を受け入れることができないから、嘘の理由を言って、自分自身を納得させたいだけなのです。
安藤 なるほど。
岸見 たとえば、私は自分の子どもに「学校を休むときは明るく元気に休んでいいんだよ」と言っていました。というのも、子どもは学校を休みたいときに、お腹が痛くなったり、頭が痛くなったりするんです。これは仮病でもなんでもなく、本当にそういう症状が出る。でも私は「そんな理由がなくても休むと自分で決心したなら、親である自分が学校に連絡するから」と伝えていました。そうすると、休むために腹痛を起こすことがなくなります。
安藤 言われてみれば、ありそうな話ですね。
岸見 晴れて学校に行かなくていいことが決まった瞬間に腹痛が治まったりするものなんです(笑)。
安藤 アドラー心理学はそういったかたちで日常に役立ちますし、ヨーロッパでは自己啓発の源流としてメジャーな存在だということも『嫌われる勇気』のなかで紹介されていましたね。でも、日本の社会では、フロイトとユングと並び称されるほどには、根付いていないように感じます。
岸見 日本ではアドラー心理学が受け入れられにくいようです。トラウマの話にも関係しますけど、すべてのことが最終的に自分に降り掛かってくる厳しさが関係していると思います。過去の体験に生きづらさの原因を求めるほうが楽ですし、カウンセリングでも「あなたのせいではなかったんですよ」「こういう風に育てられてきたからですよ」と言ったほうがウケはいいでしょう。でもアドラー心理学はそうは言わない。
安藤 アドラー心理学の考え方はたしかに厳しいですが、前向きなものだと、私は思います。
岸見 そのとおりです。過去にあったことを現在のあり方の原因にしてしまうと、決定論になってしまい、現状を変えることはできないことになってしまいます。これは非常にうしろ向きな考え方でしょう。
安藤 どんなに考えても過去は変わらないですからね。
岸見 アドラーは、「他人のスープにつばを吐く」というあまり美しくない比喩を使っていました。
安藤 スープにつばですか……。どういう意味ですか?
岸見 相手のつばが自分の皿に飛び込んだのを見てしまったら、そのスープを飲むことができなくなってしまいますよね。それと同じで、一度聞いてしまったら元に戻れないのがアドラー心理学なんだという意味です。もう嘘や言い訳が言えなくなる。この厳しさが日本で受け入れられにくい原因なのかもしれません。
(中編に続く)
■【安藤美冬×岸見一郎 対談】(中編)
幸せは、自己肯定を「否定」することから始まる
自由に生きるための武器「アドラー心理学」
「すべてのトラウマは“人生の嘘”だ」──自己啓発の父・アドラーの刺激的な主張が展開される書籍『嫌われる勇気』(岸見一郎・古賀史健著、ダイヤモンド社)。
著者の岸見一郎さんがアドラー心理学を研究しているのは、岸見さん自身が幸せになりたいからだといいます。トラウマや自己肯定という“言い訳”を許さないアドラー心理学は、一見厳しい考え方に思えますが、自分の心持ち次第で人生はいくらでも変えられると教えてくれる、心強い味方です。岸見さんが安藤美冬さんに明かした、日常で実践しているアドラー的発想とは?(構成:宮崎智之)
「ポジティブ教」に
ハマらないために
安藤美冬(以下、安藤) そもそも、岸見先生がアドラーを学び始めたきっかけは何だったのでしょうか?
岸見一郎(以下、岸見) きっかけは子育てです。子どもは電車の中で大きい声を出すかもしれないし、スーパーのオモチャ売場の前で泣き叫びだすかもしれない。ときに親の言うことをまったく聞かなくなる手強い存在ですね。そういうときにどう対処したらいいのだろうと悩んで、アドラー心理学を学び始めました。
安藤 子育てがきっかけだったとは、ちょっと意外です。
岸見 あと、『嫌われる勇気』のあとがきにも書きましたが、はじめて聞いたアドラー心理学の講演で登壇者が「今この瞬間から幸福になれる」と語ったんです。私は反発を感じると同時に、「これまで哲学者として幸福について考察してきたけれど、自分自身は幸福なんだろうか」ということに思い至りました。それなら、アドラー心理学を研究して、まず自分が幸せになろうと。
安藤 『嫌われる勇気』の後半では、「“いま、ここ”に強烈なスポットライトを当てよ」という力強い幸福論が語られていましたね。まさに私はそれが知りたかったんだ!ということが語られていて、すごく共感しました。これまで何度かテレビや対談で「若者の幸福論」というテーマで話をしたことがあるのですが、意見するたびに徒労感を味わっていたんです。幸福についての議論って、小難しくそれらしいことをこねくり回しても仕方がない気がするんですよね。「笑う門には福来る」の精神で、「いま、ここ」の自分が幸せだと定義すれば、周りの世界が輝いて見える。幸せは“自家発電”していくものなんじゃないかなと思うんです。
岸見 そのとおりです。だから、私自身が幸せにならなければ、カウンセリングにこられた人に対して説得力がないんですね。
安藤 アドラー心理学には「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」という三つの重要なポイントがありました。そして、自己受容と「自己肯定」を明確に分けている。これは、ものすごく腑に落ちました。
岸見 自己肯定は、できもしないことでも暗示をかけて、「自分はできる」と言い聞かせることです。一方の自己受容は、「できない自分」をも受け入れること。アドラー心理学では、自己肯定を否定して、自己受容しながら前に進むことを推奨しています。
安藤 自己肯定感を持つためにあらゆる状況を前向きにとらえるとか、あるいは自分のことを好きになるために自己肯定の言葉を唱えるとか、そういった「ポジティブ教」みたいな考え方ってありますよね。かくいう私も一時期、ポジティブ教の信者でした(笑)。でも、それって奥底の感情がついてこないから、とても辛い。
岸見 強い劣等感に苦しみながらも自分が優れているかのように振る舞い、偽りの優越感に浸っている状態ですね。
安藤 あるいは、心の奥底では迷いや不安でいっぱいなのに、その本当の感情に目をつぶってしまっている状態。燃費の悪い車に乗っている状態、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状態ですね。
岸見 本当の意味で自分のことが好きになれなければ、幸せにはなれないんですよ。なぜなら、「自分」とは、どんなことがあっても死ぬまで付き合っていかなければならないからです。パソコンや携帯電話なら、いつでも買い替えられる。でも自分は、他の自分に換えることはできません。だからなんとかして、皆に自分を好きになってもらいたい。
安藤 そこで他者信頼と他者貢献が重要になってくるんですね。
岸見 人はどんなときに自分を好きになれるのかというと、自分が誰かの役に立てていると感じたときなんです。でも、他者を自分の敵だと思っていたら、貢献したいなんて思わないですよね。だから自己受容、他者信頼、他者貢献はワンセットでどれも欠くことはできない。自分のなかで完結しようと思うから自己肯定なんて言葉が出てくるわけで、実は、自分を肯定するためには他者が必要になるんです。
安藤 自己肯定と自己受容の違いは、とても重要なポイントになりそうですね。私も含めて、その差に気付かないで苦しんでいる人たちがたくさんいそうです。
他人をほめるのは悪いこと?
安藤 『嫌われる勇気』では、「怒り」などの感情についての考察も印象に残りました。感情には必ず「目的」があり、それに気がつけばコントロールできると。
岸見 怒りの感情の裏には、自分の主張を通したいなどの目的があります。それを理解すれば、目的を果たすためによりよい方法があることがわかってくる。子どもがスーパーのオモチャ売場の前で泣き叫んだらたいていの親は叱ると思うんですけど、子どもは自分の要求をどうしたら通せるかわからないから泣いているわけですよね。
安藤 そうですね。
岸見 だから私は自分の子どもに、「そんなに泣かなくてもいいから言葉でお願いしてくれませんか」と言ったんです。そうしたら彼も泣きやんで、「あのオモチャを買ってくれたら、うれしいんだけど」と言いました。そういう経験を重ねていけば、感情という不自由な手段を使わなくても自分の気持ちを伝えられるようになります。
安藤 それって大人でもいっしょですよね。私も母親から小言を言われるとついカッとなりますし、仕事をしていても思いどおりに事が運ばなかったり、スタッフが小さなミスをするとついついイライラしてしまう。でも、年末にアドラー心理学を知ったので、2014年はまだ感情的な手段を使っていません!
岸見 それはよかった(笑)。
安藤 ですが、内に溜まった感情を発散したほうがすっきりして前に進めるという考えもありますよね。私にはその是非はわからないのですが、あるセラピーでは、患者がカウンセラーと一緒に小さな個室に入り、今まで自分が経験してきたいろいろなことを思い出して、怒りや悲しみの感情を思い切り吐き出すと聞きました。
岸見 感情は溜まるものではありませんよ。蓄積されません。
安藤 えっ? そうなんですか?
岸見 たとえば、親と子どもが大げんかしていたとします。喧嘩の最中に親が電話を受けて、相手が学校の先生だったら、深々とお辞儀して対応すると思うんです。
安藤 ああ、声色まで変えて。
岸見 そう。でも、電話が終わって子どもの顔を見たら、また腹が立ってくる。つまり感情とは瞬間に沸いてくるものであって、蓄積されるものではないので、そもそも発散することもできないということです。
安藤 花粉症のように内部に蓄積して爆発するものだと思っていました。
岸見 すべてを感情のせいにしてしまえば、自分自身には責任がなくなるので楽になれるでしょうが、それも大きな嘘です。人は、そのときどきの目的に即して、手段である感情を使い分けています。責任は、すべて使い手である自分にあるのです。
安藤 目的に応じて、感情を使い分けている……。耳が痛いですが、勉強になります。
岸見 ええ、厳しい考え方ですが、向き合わなくてはなりません。
安藤 あと、すごく参考になったのは、叱ることもほめることも同義であるという考え方です。よく「ほめて伸ばせ」なんて言われるように、ほめるという行為は安易に推奨されがち。でも、立場が上の人間が下の人間を評価し、操作しようとする意味では叱ることと同じであるという言葉に、ハッとさせられました。
岸見 対等な関係同士ならば感情で操作する必要なんてないんです。ちゃんと言葉で気持ちを伝えればいいだけ。相手が自分より下だと思っているからコントロールしようとする。そのことがより顕著になるのが「ほめる」という行為です。仕事にしろ、育児にしろ、すべての対人関係を「横の関係」にして、この人は大切な友人なんだという感覚を身につければ、日々の生活が変わってくると思いますよ。
(後編に続く)
■【安藤美冬×岸見一郎 対談】(後編)
「嫌われる」ことは、自分の人生を生きることだ
自由に生きるための武器「アドラー心理学」
アドラー心理学のエッセンスを凝縮した『嫌われる勇気』(岸見一郎・古賀史健著、ダイヤモンド社)。同書の大ファンだという安藤美冬さんと著者の一人である哲学者の岸見さんによる対談の最終回です。
「トラウマは存在しない」「自己肯定するな」などと、従来の心理学のイメージを覆す考え方が満載のアドラー心理学。本書のタイトルとなった「嫌われる」という言葉も、一見ネガティブに聞こえますが、実はとてつもなく前向きなメッセージが込められていました。(構成:宮崎智之)
安藤美冬が対人関係に悩むワケ
安藤美冬(以下、安藤) 私の悩みを少し相談させてください。実は私、すごく人見知りなんです。そう見えないとよく言われるんですけど(笑)。特に知らない人がたくさんいるパーティーに出席するのがすごく苦手で。出席するたびに寿命が縮まる思いになります。
岸見一郎(以下、岸見) なぜですか?
安藤 どうも居心地が悪いというか。「ここにいていいんだよ」という承認を誰からも貰えていないような気がして。
岸見 それは、安藤さん自身が「自分は人見知り」という感情を作り出しているんじゃないですかね。つまり、自分が初対面の人とあまり話ができないということの理由づけとして作り出している感情だと言える。緊張するのは、人見知りだからではありません。「自分は気に入られないんじゃないか」「会話が盛り上がらないのではないか」という不安が的中したときの言い訳として、「自分は人見知り」という理由が必要なのです。
安藤 なるほど。対人関係で傷つくのが怖いから、納得できる理由を作っているわけなんですね。
岸見 安全弁を残しておきたいと考えないで、対人関係に踏み出す「勇気」を持つのです。そもそも、他者との関係がうまくいかないかもしれないのは自分だけではないですよね。その場にいる全員に当てはまります。だから、自分だけにことさらに他者を怖がる理由があるわけではありません。自らがまず、いわば武装放棄する必要があるんです。
安藤 じゃあ、初対面で打ち解けやすい人とそうでない人がいるのは、なぜなんでしょうか? 初回から会話が盛り上がる人もいれば、何回会っても一向に距離が縮まらない人もいるんです。
岸見 それは、「誰と出会っても打ち解けないようにしよう」と相手が決心しているんでしょうね(笑)。その人も安藤さんと同じ不安を抱えているということです。
安藤 では、自分が自己開示する決意をしたとしても、相手が心を閉ざしていたら駄目だということですか?
岸見 相手のことは考えても仕方ありません。相手には相手の課題があって、それに介入することは基本的にできないというのがアドラー心理学の考え方です。だから、相手がどうであろうと自己開示をすると安藤さんが決心するしかない。
安藤 ああ、そうか。相手の出方を見るのではなく、あくまで自分自身の決心が大切というわけですね。
岸見 アドラー心理学では、たとえ嫌いな人がいたとしても、その人に対する負の感情は会った瞬間に作り出されたものだと考えます。むしろ、その相手との関係をよくしないでおこうと決心しているために、過去のいろいろな不愉快な出来事を今この瞬間に思い出し、「ずっと嫌いだった」という感情を作り出している。
安藤 そういうややこしいことを瞬時にしているのが人間だと。
岸見 そうです。だから、これまでのことは関係なしに、「今日はこの人に対してにこやかに接しよう」と決心すれば、対人関係はすぐに変わります。そうシンプルに考える勇気を持つことです。
安藤 さきほどから「勇気」という言葉が出てきています。アドラー心理学のなかで定義している“勇気”とはどういうものなのでしょうか?
岸見 我々には生きていくにあたって避けては通れない課題がありますよね。仕事、恋愛、結婚、子育てなどいろいろありますが、そのすべては対人関係です。それらの課題を解決する力があると思えることが、「勇気」があるということです。課題に立ち向かい対人関係を進めていくんだと思えるためには、自分に価値があると思えるようにならなければいけない。そこでアドラー心理学では、人が「自分に価値がある」と思えるように、さまざまな援助を行っていきます。
星に導かれ自由に生きる
安藤 この『嫌われる勇気』というタイトルが、今ほど刺さる時代はないですよね。SNSの普及によってつながれる人の数が増え、できることなら誰ともうまくやりたいと思う一方、意図せずに嫌われてしまうなんてことも頻繁に起こります。嫌われたくないという気持ちと裏腹に、人から嫌われていることが「見える化」してしまう時代になったんですね。
岸見 仮に、誰からも嫌われていない人がいるとしたら、その人は非常に不自由な生き方をしていると考えられます。皆に気に入られるということは、他者の期待を満たすために生きているということであり、それでは自分の人生を生きているとは言えません。人から嫌われるということは、自由に生きるために支払わなければいけない代償ですし、自分が自由に生きていることの証なんです。
安藤 他者に嫌われるということは、自分が自由に生きていることの証である……そのとおりだと思います。
岸見 そう意識しなければ、自分の不幸の原因を他人や周囲の環境、過去の生い立ちに押し付けてしまうようになる。だから、「嫌われる」という言葉にはネガティブなニュアンスがあるかもしれませんが、このタイトルはとても気に入っています。
安藤 私は、自分らしい人生を生きるということについて、覚悟を持って追求しているつもりです。ですから、この『嫌われる勇気』というタイトルと先生の言葉に勇気をもらいました。
岸見 そう言っていただいて、うれしいです。
安藤 私がこの本のなかで一番好きな表現は、「より大きな共同体の声を聞け」という言葉です。これは図らずも実践してきたこととシンクロするような気がしています。私は父が教師で母が専業主婦という平凡な家庭で生まれたんですけど、「自分らしい人生を生きるために、より広い世界に出る」ということに幼い頃から強い関心を持っていました。幼少期から海外文学を読みあさり、10代で海外に出て、その後50ヵ国近くを旅し、オランダにも留学。社会人になってからも、一度入った組織を飛び出して現在があります。知らず知らずのうちに、今いる小さな世界から外に出ていくことを意識していたように思います。
岸見 私は安藤さんと違い、若いうちは、どちらかというと親の期待や普通の人生にこだわっていました。でも、大学院を出ても就職できず、常勤の精神科に勤めるようになったのは40歳のときでした。しかも、そこもすぐ辞めてしまい……。
安藤 そうだったんですか。
岸見 でも、そういう自分でもいいじゃないか。自分の人生を生きるためなら、狭い共同体にとらわれずそこから出て行ってもいいじゃないか、と決心をしたんですね。他者に貢献し、今この瞬間に幸せになるためには、場所や状況は関係ないのだと。
安藤 一歩を踏み出す勇気があれば、人はすぐにでも幸せになれる、と。
岸見 もちろん、今いる共同体から逃げればいいというものではありません。ただ、自分がやろうとしていることが広い意味での他者貢献だという意識があれば、どこにいたって自分の居場所を持つことはできます。より他者に貢献する機会がある場を求めて新しい場に移って行くのは逃げではない。
安藤 フリーランスだから、会社員だからというのも関係ないということですね。
岸見 そうです。その決心が「導きの星」となり、それさえ見つめていれば、どこにいても迷うことはない。導きの星を基準にして生きるのが自由な人生なんだということです。病気になって働けなくなった人の人生は不幸でしょうか? 私は違うと思います。それでも自分で人生を選び取っていく勇気があれば、その瞬間に幸せになれると思うんです。ですからフリーランスだとか、会社員だとか立場や状況で自分の人生の価値を決めるのはおかしい。どんな状況でも自由に生きることができるはずです。
安藤 先生に励まされているようで、涙が出てきそうになりました。『嫌われる勇気』はアドラー心理学の一部を凝縮したものだと思うので、ぜひ、続編を読みたいです。
岸見 シンプルなのに深いのがアドラー心理学の魅力です。たとえばテニスでは、ウィンブルドンに出場できる人はごくわずかです。しかし、ラケットで打ち返すという基本動作は少し練習すれば誰にでもできるようになりますし、ウィンブルドンに出場しているのはそれを続けてきた人ばかりなのです。だから、何事でも、まずはできることから実践して続けてほしいと思っています。続編ですか……(笑)。「青年」が成長して恋愛し、子育てをするという話も面白いかもしれないですね。
安藤 読みたいです。ぜひお願いします!
岸見 わかりました(笑) 考えてみましょう。
(おわり)
安藤美冬(あんどうみふゆ)
起業家/コラムニスト/Japan in Depth副編集長/多摩大学経営情報学部非常勤講師 株式会社スプリー代表。1980年生まれ、東京育ち。慶応義塾大学卒業後、集英社を経て現職。ソーシャルメディアでの発信を駆使し、肩書や専門領域にとらわれずに多種多様な仕事を手がける独自のノマドワーク&ライフスタイル実践者。『自分をつくる学校』学長、講談社『ミスiD(アイドル)2014』選考委員、雑誌『DRESS』の「女の内閣」働き方担当相などを務めるほか、商品企画、コラム執筆、イベント出演など幅広く活動中。多摩大学経営情報学部「SNS社会論」非常勤講師。Japan in Depth副編集長。TBS系列『情熱大陸』、NHK Eテレ『ニッポンのジレンマ』などメディア出演多数。著書に7万部突破の『冒険に出よう』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。
公式ホームページ:http://andomifuyu.com
岸見一郎(きしみ・いちろう)
哲学者。1956年京都生まれ、京都在住。高校生の頃から哲学を志し、大学進学後は先生の自宅にたびたび押しかけては議論をふっかける。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。専門の哲学(西洋古代哲学、特にプラトン哲学)と並行して、1989年からアドラー心理学を研究。精力的にアドラー心理学や古代哲学の執筆・講演活動、そして精神科医院などで多くの「青年」のカウンセリングを行う。日本アドラー心理学会認定カウンセラー・顧問。訳書にアルフレッド・アドラーの『個人心理学講義』『人はなぜ神経症になるのか』、著書に『アドラー心理学入門』など多数。『嫌われる勇気』では原案を担当。
[いずれもDIAMOND online]
Posted by nob : 2014年02月17日 15:56
光を見つけるも闇に沈むも自分次第。。。
■余録:昨年亡くなった漫画家のやなせたかしさんは…
▲昨年亡くなった漫画家のやなせたかしさんはよく「一寸先は光」と言っていた。「アンパンマン」が突然ブレークしたのはやなせさんが50代も半ばを過ぎた時だった。人生、一寸先は謎だが、それを「闇」と言うことで足がすくむのが普通の人だ
▲コップに半分水が入っているのを見て、悲観主義者は「もう半分しかない」と言い、楽観主義者は「まだ半分ある」と言う。ともに間違いでない。だが、同じものを見ても、同じような境遇を生きても、その受け止め方次第で人間はその後の運命を一変させてしまう
▲「プラス思考」「ポジティブシンキング」といった自分自身のイメージやその将来に対する積極的・肯定的な考え方が、よい結果を招き寄せるとはスポーツでもよく言われる。そんな「まだ41歳」がソチ五輪のジャンプ台で世界に示して見せた「一寸先は光」だった
▲「レジェンド(伝説)」という言葉を小さな子供らにまで広めたスキージャンプ男子ラージヒルでの葛西紀明(かさいのりあき)選手の銀メダルである。むろん冬季五輪の日本人選手としては最年長のメダルとなったが、すぐさま「次は金」と語ったご当人のプラス思考にかげりはない
▲五輪も今回が7大会連続出場という葛西選手である。ここまで多くの挫折も味わいながら、不惑を超えて初めて手にした個人種目でのメダルになる。この間、レジェンドという異名の示す通り、欧州のファンにも愛されてきたその明るく前向きなキャラクターだった
▲フランスの哲学者アランの言葉に「悲観主義は気分のものであり、楽観主義は意志のものである」がある。ジャンプする意志の偉業をたたえたい。
[毎日新聞]
Posted by nob : 2014年02月17日 15:46
依存し合い支え合えるのが愛の力、、、いざという場合への覚悟だけは持ち合いながら。。。
■依存は本当にダメなこと?~“依存”と“支え合い”のはざまに揺られて~
ちょっと前までの私は、友達が「彼氏が週2回泊まりにきている」などと言おうものなら、「ちょっとあんたそれ依存しすぎてるんじゃないの~? 泊まりってことは、実質、週に4回会ってるってことになるんだよ! 週の半分以上も一緒にいるって、それ依存だよ!」と、鬼の首をとったかのように攻撃していました。
「私は月に1回、もしくは会わないときもある。でもその位がちょうどいい」なんて言って、悦に浸っていました。依存しないワタシ、カッコイイ、みたいな。
でも考えてみたのですが、依存というのは、「会う頻度」の問題ではない。
月に1回しか会っていなくても、残りの29日、30日を彼の事ばかり考えて生きていたら、それは立派な依存だし、逆にたとえ同棲なんかしていたって、お互いまったく干渉をしなければ、それは依存しているとは言えなさそう。
依存は、決して距離や時間の問題ではないみたいです。
たぶん、心持ちの問題。
ここで話は少し変わりますが、昨今、自立した女性は素晴らしい、という風潮があります。
いつまでも腰かけOLのようなことをして、グダグダと婚活に勤しんでいる女性や、ダラダラ家事をする主婦を、さもイケていない女性かのように見て「彼女たちは寄生することしか考えていない……」などと叩き、一方、自分にしかできないことを仕事にして、独身であってもすっくと胸をはって生きている女性のことを、「カッコイイ!」、「憧れちゃう」などと称賛する風潮。
だからこの『ANGIE』においても、そういう自立した女性にばかり焦点を集めて記事を書いたり、インタビューを行ったり。かくいう私もそれをやってきました。
たしかに、自立して生きる女性はかっこよく見える。
でも反対に、依存する生き方って、そんなにダメなことだったんだっけ? と思うことがあります。
依存を全く必要としなくなったとき、人は他者を介入しなくても生きていけるようになる。それを「自立できてる女性、かっこいい!」というのかもしれないけど、そうなると結婚も恋愛も意味が薄くなる。
ある男性が私にこう言いました。
「俺は彼女と別れても、悲しくはない。でも彼女がいれば、ひとりでいるより楽しいから、付き合っているんだ」と。
確かにそれは理想だけど、いなくなっても悲しくない人と付き合っていて、何か得られるものはあるのかなあとも思います。失った時の喪失感の大きさこそが、イコールあなたが得てきたものの大きさなのに、と私は思うのですが……。
人は人といる限り、少なからず相手から何かを吸収しようとする。それが好きな相手であればあるほどに。そうして自分の中に入ってきた相手の一部を受け入れ、調和して生きていく。
言い方を柔らかくしましたが、その調和こそが依存と置き換えられそう。
自分の中で受け入れ、解けていったものは、自分の一部となり、そう簡単には引きはがすことができない。だから失ったときは自分の一部がもぎとられたような気がして、苦しくて悲しくなる。
「ああ、私こんなに依存してたんだな」と思う。でもそれはきっと、悪いことではない。
依存しがちな女性を、鬼の首をとったかのように叩く風潮。依存を恐れて、言いたいことも何も言えない関係になっていませんか?
「あなたがいないと私の世界は暗くなる」と思うことは、そこまでおかしな話ではないと思うのです。
このようにして私たちは、支え合いと依存のはざまに揺られて、うまくやりくりして生きていくのです。
さとるり
(エディター/ライター/ゲームシナリオライター)
[ANGIE]
Posted by nob : 2014年02月13日 16:30
私も禁煙ではなく長らく休煙中、、、止めるのではなく休んでいるだけと考えて、思い切って残りの煙草を棄ててしまうと、意外にも簡単に止め、いえ休めます。。。
■タバコの害はこんなにあった!喫煙を今すぐやめるべき9の理由
みなさんはたばこを吸っていますか?
健康への害は数多くあるものの、依存性も手伝ってなかなかやめられないもの。
喫煙者の方には耳が痛いかもしれませんが、喫煙のリスクを9つ、もう一度おさらいしてみましょう。
1.喫煙関連三大疾患のリスクが高まる
喫煙をすることでかかりやすくなるとされる病気が3つあります。
これらは喫煙関連三大疾患と言われ、いずれも死に直結するものです。
* がん
* 狭心症・心筋梗塞
* 慢性閉塞性肺疾患
2.うつ病のリスクが高まる
喫煙者は、非喫煙者に比べてうつ病になる確率が約3倍と言われます。
たばこをやめることで、うつ病の発症率は非喫煙者と同じくらいに戻るようです。
3.寿命が縮む
喫煙者は非喫煙者に比べて、寿命が約10年短いとされています。
4.しわが増える
顔だけでなく体中のしわが増え、老化が加速します。
たばこが血液循環の働きを妨げ、細胞の再生ができなくなるためです。
5.歯が黄色くなる
たばこに含まれるタールによって、歯が黄色や茶色に着色されます。
また、タールは口臭の原因にもなります。
6.1年で約15万円損をする
1日に1箱吸う人は、1年に約15万円をたばこに費やしている計算になります。
10年続けたら150万円、20年で300万円・・・きりがありません。
7.体が重くなる
たばこは血の巡りを悪くし、肩こり、だるさを感じやすくなります。
疲労が回復しづらく、体が本来の働きをすることができません。
8.ムダ毛が増加する
男性ホルモンを増加させるたばこは、ムダ毛を増加させます。
特に鼻毛が長くなったり、太くなることが多いようです。
9.身近な人も病気にかかりやすくなる
副流煙によって、恋人、配偶者、友達、同僚など様々な人に悪影響を与え、パートナーや大切な人達の健康を脅かすことにつながります。
禁煙は自分だけでなく、身近な人を大切にする意思表示でもあるんですね。
[Gozo Ropp]
Posted by nob : 2014年02月12日 19:07
このところすっかりマイブーム、、、ハーフカットを醤油麹と納豆を合わせて美味しく玄米をいただいています。。。
■食べようアボカド!美肌にもダイエットにもイイのです
アボカドはダイエットの味方?
ダイエットしたことがない人って、そう居ませんよね。ダイエット食をあっさり食べ終わってしまった後のなんとも物足りない気持ちは多くの人が味わっていらっしゃることと思います。数時間後にはついつい間食に手が伸びてしまったりして。
さて、そんなときにアボカドがよいかもしれないという論文が発表されました。アボカドは他のどんな果物よりも糖質が少なく、食物繊維も豊富です。良質な脂質の供給源でもあり、心疾患や糖尿病のリスクを減らすことができるとされています。
カリフォルニアのJoan Sabate博士は26人の健康かつ肥満体型の成人に昼食にアボカドを2分の1ずつ摂取させました。すると、昼食後の食欲がアボカドを摂取しなかった場合と比較して3時間の間40%抑えられ、5時間の間20%ほど抑えられたとのことです。
つまりアボカド2分の1個を食事に取り入れることで食事が終わった後の間食のリスクを減らしてくれる可能性があるのです。食後の満足感も3時間の間26%増したとのこと!すごいですね。
アボカドのカロリーと栄養
でも、アボカドってカロリーが高いんじゃ…と思っている方は多いかもしれませんね。2分の1個で94カロリーです。これくらいなら取り入れやすいですね。たとえばアボカドサラダとスープ、フランスパンくらいでも十分低カロリーに抑えられるでしょう。
2001年から2008年にわたり、17567人の米国人を対象に行った研究ではアボカドを摂取している成人はアメリカの栄養ガイドラインの示す健康的な摂食状態に近く、アボカドを摂取していない人と比較して食物繊維の摂取量が36%多く、ビタミンEの摂取量は23%、マグネシウムの摂取量は 13%、ビタミンKの摂取量はなんと48%も多かったとのこと。」
また、一価不飽和脂肪酸という良質の脂質の摂取量も高いことがわかりました。結果としてアボカドを摂取している人々はBMIが低く(つまりスリム!)、ウエストが平均4cm小さく(やっぱりスリム!)、HDL(善玉コレステロール)の比率が有意に高かった(さらにヘルシー!)というからすごいですね。
また、メタボリックシンドロームのオッズ比は50%低かったとのことでした。もちろん「アボカドを食べる人」は「アボカドを食べない人」と比較してアボカド以外の食事内容もヘルシーなのかもしれませんけど…。そんなつっこみはさておいても、魅力的なデータには違いありません。
ダイエット中は肌が荒れがちですが、アボカドにはビタミンや亜鉛などのミネラルが豊富に含まれていて、美肌効果も抜群です。
[スキンケア大学/美ログ]
Posted by nob : 2014年02月12日 19:01
自らに起こるすべての事象は、自分自身が呼び寄せ、そしてつくりあげたもの。。。
■言い訳ばかりの人生を今から変えるための3つの行動
兄弟姉妹のいる家族で育った人は、罪のなすりつけ合いをしたことが、1度や2度ならずあるでしょう。親に「これやったの誰!?」と聞かれたら「僕/私じゃない!」と即座に返してきたと思いますが、実はこのようなやりとりにはもっと気をつけた方が良さそうです。
私は幼い頃、「これ誰がやったの?」と聞かれた時に、架空のキャラクターを作り出して罪を着せることがよくありました。大人になると、このような行動の代償が恐ろしく高くつくというのが、子ども時代との大きな違いです。
自分の周りの環境は自分が作っていると言いますが、それに気付いていない場合は、若い頃にやった同じ過ちを繰り返すことになります。罪のなすりつけ合いをすることの影響がいかに大きいかを説明する前に、まずはその原因と結果を見ていきましょう。
若い頃は、将来の自分を決めてしまう考え方や思考の癖を、自分で作っているなんて考えもしませんでした。ただその瞬間を生きていると思っていました。なんて愚かだったのかと思います。私たちの行動は、将来希望を実らせるために植える種のようなものです。ですから、何かが起こった時に、それが因果だとしても驚くことではありません。種は、同じようなものを再度生み出すという遺伝子プログラムを持っています。「罪をなすりつける」という種を植えたら、その後の人生で、その芽が育ち続けるだけです。
このような罪の連鎖を断ち切るのはとても大変ですが、断ち切るのに有効な行動があります。
1. 事実を受け入れる
責任を取るというのが、変化の扉を開ける第一段階です。ご存知のように、問題を抱えず、誰にも借りがなければ、何も起こりません。誰もが、自分が持つべきだったものが手に入らなかったという、涙を誘うような話や何らかの理由を持っています。しかし、すべての原因は自分にあるのです。その事実を早く受け入れられれば、それだけ早く癒しが始まります。
2. ポジティブな言葉を口にする
一度思っていることを口にすると、それが行動となって表れます。人間は、ただ行動しているのではなく、最初に心の中でそうしようと決めるのです。それから、やりたいことの方向性を口にするために、ポジティブな言葉を足していかなければなりません。頭の中でぐるぐると考えているだけでは、すべてを達成することにつながる大事なものを見失ってしまうので、これが大事なポイントです。言葉は変化を促します。
3. より良い環境を選ぶ
自分と弁解の間には、ある程度の距離をおかなければなりません。どういうことかと言うと、より良い思考、より良い環境、より良い影響を与えるところに移るということです。「類は友を呼ぶ」という言葉があります。簡単に言うと、自分の行動に良い影響を与える人と一緒にいた方がいいということです。成功者に共通しているのは、他の成功者とつながっているということで、これは明らかな事実です。
私は、一番下の息子がクレヨンで部屋に落書きをしたことについて話した日のことを、一生忘れないでしょう。その日、家の中にいた子どもは彼だけだったのです。しかし、私が「誰がやったんだ?」と聞いたら、いつものように「僕じゃない!」と叫びました。
石けんと水で消えないものではなかったので、その日の被害は最小限にとどめられました。しかし大人になると、自分にとっての被害はもっと大きくなります。ウソをついたり、罪をなすりつけたりするのをやめて、もっとシンプルにより良く生きるために、上の3つの行動を実行してみてください。
Early Jackson(原文/訳:的野裕子)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2014年02月12日 17:44
私も最近注目注視しています。。。
■老化のスピードを早めてしまう「糖化」とは?
久保 明
[東海大学医学部 抗加齢ドック教授/慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授]
「地中海料理」はアンチエイジングに有効な料理
昨年、和食がユネスコの無形文化遺産に登録されました。ヘルシーなイメージが強い和食ですが、健康・長寿を向上させるという明らかなメディカル・エビデンス(医学的根拠)は残念ながら出されていません。さらなる研究が待たれるところです。
同じく無形文化遺産に登録された地中海料理についてはさまざまな調査研究がなされ、いくつかのエビデンスが明らかになっています。
代表的なものに2013年に報告された「地中海食と血管障害発症予防」があります。約7500名を対象に4.8年の追跡期間を費やして行われたもので、エキストラバージンオイルとナッツなどの摂取により、心血管障害の発症が30%抑制されたというものです。
心血管障害というのは、心筋梗塞、狭心症などの病気のことです。これらの病気にならないということは、健康寿命が延びることになりますから、アンチエイジングという観点からみても有力なデータですね。
アンチエイジングの分野で注目されている「糖化」
老化を促進する因子として近年注目されているのが、身体の中で起きる酸化と糖化です。
酸化は細胞内での情報伝達を担うなど、部分的にはよい役割も果たします。ところが、呼吸時に取り入れた余分な酸素が活性酸素となり、体内の脂質を酸化させると全身の細胞を傷つけ、動脈硬化を促進するなど、老化の原因ともなります。
活性酸素を抑える抗酸化機能も体内にはあるのですが、タバコ、ストレス、紫外線、大量飲酒、大気汚染など様々な要因によってそのバランスが崩れてしまいます。活性酸素を抑制するには、抗酸化ビタミン(ビタミンCやビタミンEほか)やβカロテンなどを摂り入れるのが有効です。
たるみやしわにつながる「糖化」
一方、糖化というのは体内の余分な糖分が蛋白質と結びつく反応です。糖は人間にとって大事なエネルギー源であり、糖がなければ脳も身体も動きません。しかし、この糖も食べすぎや、甘い物の摂りすぎなどが続いて過剰になると、蛋白質と結びつきAGE(終末糖化産物)という強力な老化促進物質をつくります。
接待が続いたり、残業でスナック菓子ばかり食べたり、ストレスで食欲が亢進したりと、サラリーマンならば誰でも糖の過剰摂取をしてしまうことはありますよね。
このAGEが体内にたまると身体を構成する組織や血管がもろくなってきます。体のあちこちで組織が硬直化や化石化するというイメージを持つと分かりやすいでしょう。
糖化が進むと、皮膚ではたるみやしわができ、血管の弾力性は失われて動脈硬化が促進され、骨粗鬆症や白内障、アルツハイマー型認知症にもつながっていくのです。
AGEは細胞の受容体とくっついて炎症シグナルを活発化させ、細胞に炎症を引き起こします。この炎症で大きなダメージを受けるのが血管です。血管の内側で起きる炎症こそが動脈硬化の真の原因と最近の研究は警告しています。
酸化と糖化はお互いに影響しあいながら進行していくという厄介な関係にあるので、どちらかにだけ注意すればいいというものではありません。
酸化と糖化が進むと老化が急速に進行します。これらを抑えられれば、老化のスピードは緩くなるのです。元気で若々しくパワフルであるためにも酸化と糖化を防ぐことが大事です。
食後の高血糖状態には気をつけよう
糖化は食後、血液の中に余分な糖があふれている状態で発生します。ですから、できるだけ食後の血糖値を急速に上げないことが肝心。しかし自分では気づかないまま、意外とこの数値が高くなっている人がいます。
もし、食後1時間の血糖値が150を超えていたら、糖化の危険が迫っている可能性が高く、200を超えているならかなり良くない状況にあります。例えば、食後必ず眠くなる人の一部は食後血糖値が高い可能性があります。血糖値は通常空腹時の値を測りますが、頼めば食後血糖値を測ってもらえるので医師に相談してみましょう。
食後の高血糖状態は、糖を摂り過ぎないことのほかに食べ方や摂取する食品を工夫することで改善することができますので、次回はその具体的な方法をお教えしましょう。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年02月10日 12:09
確かに。。。VOl.2/私もこれまでに他者により一度自ら一度強制終了リセットの経験があります。。。
■イヤな人・もの・コトを強制消去!「人生の変え方3か条」ハッピーだけを選んで毎日ホクホクしよう
佐藤にの
(フリーライター/プランナー)
雑誌でもテレビで溢れかえる「ハッピーライフのすすめ」。と言いつつそう簡単にハッピーになれないのが現実というもの。人間関係や仕事で悩み、結婚への理想と現実にため息をつき、月曜日の朝はやる気ゼロ……。「ハッピーライフって何だったけ?」と、職場まで歩きながら問う。1日ってだいたいそんな感じで、できています。
すごく好きなこと1つだけに、めちゃめちゃ集中する
重たい気分を一新するのに効果的なのは、別のことに集中すること。凹みそうになったら、とくべつ好きなこと1つに気持ちを切り替えて、これでもか、というくらい没頭してみましょう。
悩みはさておき、仕事が好きなら、一案件をやり遂げるまでは席を立たない。料理が好きなら、時間に関係なくフルコースをつくり上げる。買い物が好きなら、欲しいものを買うまでは帰らない。ポイントは、完了するまでは問題解決を放棄すること。
いいんです、今、解決しなくても。せっかく好きなことに集中しているのに、クヨクヨしていては、もったいないからです。
つらいことは、強制的に失くす! 人生を変える最も良い方法とは
それでも心がキツかったら「イヤなことを強制的に全消去」してみてはいかが? 恋人と別れたいなら、連絡先や写真、プレゼントまで全て処分。仕事がつらいなら、えいっと転職する。人間関係が苦しいなら、友達を辞めるか、引っ越しをする。
お金に限らず、人間関係や仕事など人生を充実させるための財産は天下の回りもの。「自分から切ったぶん、次は必ず新しい縁を生かそう」と自分磨きを心がければ、必ずふたたびめぐってきます。
逆に、一度で切れそうな、しつけ糸ていどの強度の縁なら、さっさと切ってしまうのが吉。そこにかまう時間がもったいないからです。限りある時間、めんどくさいことに関わっている暇はありません!
経営コンサルタントで起業家の大前研一氏は、「人生を変える方法」として、こんなことをおっしゃっていました。
人間が変わる方法は3つしかない。
1番目は時間配分を変える。
2番目は住む場所を変える。
3番目はつきあう人を変える。
この3つの要素でしか人間は変わらない。
最も無意味なのは「決意を新たにする」ことだ。
何かを新しくするときに必要なのは、気持ちや心構えではなく、<時間><環境><人間関係>を具体的にどう変えるか、ということ。変えてください、大いに。あなただけが重たいものを背負う必要なんて、ないです!
幸せになれない鎖なんか捨てれば、好きなことだけを選べる毎日が待っています。そう、ハッピーライフは実現できるんです!
しんどい時間も、しあわせなひと時も、過ぎる時間は等しく同じ。どちらを選ぶかは、あなたの行動ひとつです。目に見えない要らないものはどんどん捨てて、あなただけのハッピーライフを満喫してください。笑顔がもっと、素敵になりますよ。
[ANGIE]
Posted by nob : 2014年02月06日 19:13
絶えぬ珈琲効能論争、、、私は朝夕に、時折午後にも、ゆっくりといただきます。。。
■コーヒーの正しい飲み方
健康に効く2大成分はカフェインとポリフェノール
朝の目覚めに、ちょっと疲れたときに……
飲むとすっきりするコーヒーは、実は美肌や脂肪燃焼など、健康パワーの固まり!
コーヒーの力をイイトコ取りする飲み方をマスターしましょう。
コーヒーというと、「健康に悪そう……」と後ろめたさを感じつつ飲んでいる人もいるのでは?でも、ご安心を。むしろコーヒーは体に良いという認識が広がっている。今年5月、最も権威のある医学雑誌の一つ、New England Journal of Medicine誌に「1日に3杯以上のコーヒーを飲む人は、飲まない人よりも死亡リスクが約10%低くなる」という大規模調査結果が報告された(※)。東京薬科大学名誉教授の岡希太郎さんは「コーヒーの健康効果を世界の医学会が認めた、画期的な研究」と評価する。
※(N Engl J Med 2012 ;366:1891-1904.)
シミを抑え、脂肪燃焼を高める2つの効果
コーヒーの健康成分の一つは、ポリフェノール。お茶の水女子大学大学院の近藤和雄教授は「コーヒーは日本人の代表的なポリフェノール摂取源」と話す。その働きの一つとして、近藤教授は1日にコーヒーを2杯以上飲む人はシミが少ないことも確認。目安は、「ポリフェノールで1日1000〜1500mg を一応提唱している。コーヒーのみでとるなら3〜5杯ほど」(近藤教授)。ポリフェノールはカフェインを除いた「デカフェ」でもとれる。
第2の成分が、カフェイン。東京慈恵会医科大学医学部の鈴木政登教授は「カフェインを摂取すると1時間後にはエネルギー代謝が高まり脂肪が燃えやすい状態になる」と話す。鈴木教授は「コーヒー1杯分のカフェインで脂肪燃焼効果は5時間ほど続く。運動の30分前に飲むといい」とアドバイスする。とりすぎには注意しよう。
健康に効くのはこの二大成分!
1. 1杯に200〜300mg
抗酸化でアンチエイジング
ポリフェノール
活性酸素に作用して紫外線によるシミを防ぐ
コーヒーの抗酸化力を支えるのが、コーヒーポリフェノール(クロロゲン酸類)などのポリフェノール。1杯(150ml)当たり300mgと豊富に含み、「飲むと30分から1時間ほどで体内の抗酸化力を高める作用を発揮する」(近藤教授)。コーヒーを飲む量と肌の状態を調べた研究では、コーヒーポリフェノール摂取が多いほどシミが少ないというデータが出た。
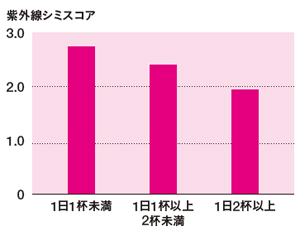
1日に2杯以上飲む人はシミが少ない
非喫煙女性131名(30〜60歳)に対して、食事調査と肌状態の解析を行った。コーヒー1日2杯以上、つまりコーヒーポリフェノールを1日150mg以上とる人は紫外線シミが少ないことがわかった。(近藤教授ら、2011年第65回日本栄養・食糧学会大会にて発表)
意外?!コーヒーは日本人の抗酸化力の源!
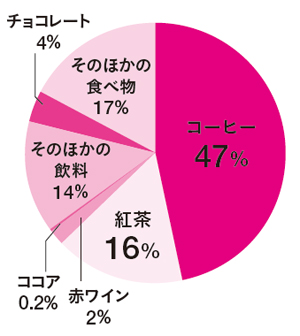
首都圏在住の主婦109人に食事、食材、飲料を一週間記録してもらい、ポリフェノールを何から摂取しているかを算出した。その結果、コーヒーからの摂取が47%と最も多く、コーヒーは日本人の最大のポリフェノール源であることがわかった。(近藤教授ら、2010年第64回日本栄養・食糧学会大会にて発表)
コーヒーポリフェノールにはこんなアンチエイジング効果も!
● インスリン抵抗性を改善し、糖尿病を予防。血圧を抑える
● 動脈硬化を予防し、心疾患リスクを下げる
2. 1杯に約100mg
エネルギー代謝を高める
カフェイン
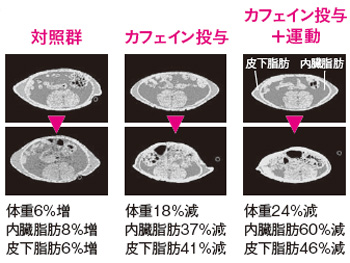
カフェインと運動で脂肪燃焼効果アップ
肥満・糖尿病モデルのラットを「安静対照群」、「運動群」、「カフェイン投与群」、「運動+カフェイン投与併用群」に分けて5週間飼育した。運動とカフェインを併用すると体重減少が顕著となり、筋肉量が増え、内臓脂肪と皮下脂肪が最も減少した。(鈴木教授の研究)
脂肪燃焼パワーを高める
カフェインをとると30分ほどで血中に到達し、脈拍が上がり交感神経が優位になる。さらに、エネルギーとして活用されやすい遊離脂肪酸が増え、脂質代謝が高まる。ラットの実験で、カフェインを投与して運動を加えるとこの働きはさらに高くなった(写真)。「ヒトを対象にした研究でも、コーヒーを飲むとエネルギー代謝が上がることを確認した」(鈴木教授)。
1杯中のカフェインはコーヒーが多い
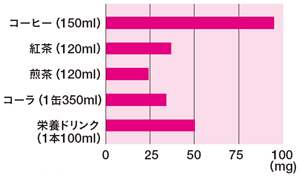
主な飲料に含まれるカフェイン量を比較すると、コーヒーの含有量が多い。コーヒーや茶葉から抽出されたカフェインは、コーラや栄養ドリンクにも使われている。(データ:五訂日本食品標準成分表、『カフェインの科学』学会出版センター)
カフェインにはこんなうれしい効果も!
● 交感神経を優位にする
● 抗炎症作用
● 肝臓など臓器の保護作用
■“コーヒーは体を冷やす”は勘違い!?
効き目大! でもとりすぎは ご用心
がぶ飲みするのはNG 妊婦は1〜2杯に
カフェインは医療にも用いられているだけあって、急激に血中濃度が高まると中枢神経系を刺激し、めまい、心拍数の増加、興奮、不安、震えなどにつながることがある(表)。「カフェインは、血中濃度40μg/mlを超えるとほとんどすべての人に不整脈やけいれんを起こす。10杯続けざまに飲む、というような過剰な飲み方をすると、何らかの副作用が生じる可能性がある」と鈴木教授。カフェインは5時間ほど体内に留まるので、頻繁に飲むのは控えたい。
妊娠中の摂取については、英国食品基準庁(FSA)が、2008年に「妊婦がカフェインをとりすぎると出生児が低体重となり、将来の健康リスクが高くなる可能性あり」とし、1日当たりのカフェイン摂取量上限を200mgと定めている。妊娠中の人は、デカフェにするか、1日当たり1〜2杯に。
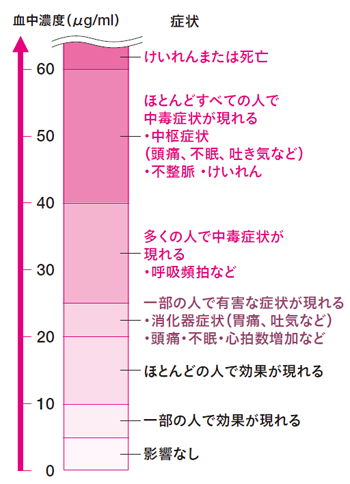
血中カフェイン濃度と症状
カフェインを治療薬として使った場合の症状と、血中カフェイン濃度との関係を示した。体重1kgあたり4mgのカフェイン投与で血中濃度は約6μg/mlになる。(表:鈴木教授)
“コーヒーは 体を冷やす”は 勘違い?!
「コーヒー摂取と冷えに相関なし」の研究結果も
福島室長は「コーヒーポリフェノール摂取と肌状態の調査の際、冷えについても調査した。夏季・冬季いずれにおいてもコーヒー摂取と冷えとの間に相関はなかった」と話す。カフェインには体熱産生作用があり、3〜4杯のコーヒーで10%程度の熱産生アップが見込めるという研究も。薬膳カウンセラーの阪口珠未さんも、「低血圧や低体温の人にとって、コーヒーを朝に飲んで体にスイッチを入れるのは賢い方法。ただし温かくして飲んで」と話す。
■コーヒーはいつ飲むのが効果的?
コーヒーは 飲むタイミングに コツがある
眠気覚ましに効果的 日中の活性酸素対策にも
こんなタイミングで元気に
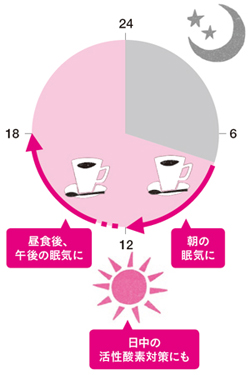
「運動や精神活動で疲れると、脳ではエネルギー代謝の残りカスとしてアデノシンという疲労物質がたまる。このときコーヒーを飲むと、脳に到達したカフェインが、アデノシンの代わりにアデノシン受容体につき、眠気を防ぐ。昼寝の直前に飲めば20〜30分後にしゃきっと目覚められる」と岡さん。「夜は睡眠中に分泌するメラトニンなどが活性酸素対策になる。日中はコーヒーポリフェノールなどの抗酸化物で対策をしたい」(近藤教授)。ただし「カフェインには胃酸分泌を高める働きがある。胃酸過多の人は、空腹時を避けて」(福島室長)。
ブラックが ダメならちょい足し ミルク砂糖
ミルクでカフェインの吸収をおだやかに
コーヒー好きな人なら苦みや酸味をおいしいと感じるけれど、ブラックの味は苦手……という人もいるはず。でも、砂糖やミルクを入れると健康効果が薄まってしまうようで心配!
ポリフェノールの吸収については「ミルクも砂糖も影響しない」と福島さん。カフェインについて「スプーン1杯、5g程度の砂糖であれば血糖値にはほとんど影響を及ぼさない。脂肪燃焼効果を下げることもない」と鈴木教授。砂糖の入れすぎはカロリーオーバーになるので気をつけて。一方、ミルクを加えると「カフェインが体内に吸収されるスピードがおだやかになる」(福島室長)。急激なカフェイン吸収は胃酸分泌増加により胃を荒らす原因にも。子どもや胃酸過多の人はミルクを加えるといい。
この人達に聞きました
岡 希太郎
東京薬科大学名誉教授/珈琲研究家
2004年にコーヒーの研究に着手。「カフェインには抗炎症作用もあり、肝臓や脳を守って肝がんやアルツハイマー病を予防する可能性も期待されている」
東京慈恵会医科大学
鈴木政登教授
体育学、応用健康科学、病態検査学が専門。「コーヒーの脂質代謝を高める効果は運動によってさらにアップする。肥満、糖尿病の予防にもコーヒーは役立つ」
お茶の水女子大学大学院
近藤和雄教授
同大学生活環境教育研究センター長。「日本人は食べ物より飲み物から多くポリフェノールをとっている。コーヒー摂取などで動脈硬化も抑制できる可能性がある」
[いずれもWOMAN Online]
Posted by nob : 2014年01月31日 09:33
私も身体の冷えの自覚がありませんでした。。。Vol.2
■『冷え』の原因となる食習慣とは?
「冷え」は女性の大敵
寒い日が続き冬真っ只中な今日この頃。
女性の一番の悩みといえば「冷え」ではないでしょうか?手足が冷たい、一日中身体の芯から冷えを感じて仕事に集中できない…などなど。
冷えはあらゆる病気の原因にもなります。色々対策はしているけど一行に改善しないという方、もしかしたら日々の習慣が原因かもしれません…
本当にお腹のため?朝ヨーグルトの習慣
お腹の調子を整えるため・美肌のため…と、朝食にヨーグルトを食べている方も多いのではないでしょうか?私自身もつい数年前まで、美容のために良いものだと思い10年間ほど毎朝ヨーグルトを食べ続けてきました。
しかし、牛乳やヨーグルト、生クリームといった流動性のある乳製品は身体を冷やす作用がとても強いとされています。また、子宮がんや乳がん、生理不順など婦人科系の病気を引き起こす原因として、この乳製品の食べすぎがあげられています。
グラタンなどクリーム系のお料理、カフェラテ、ヨーグルト、生クリームたっぷりのケーキなど…女性は乳製品を使ったお料理が大好きですよね。
元々農耕民族だった日本人が、このようなものを口にするようになったのは歴史的にみても最近のこと。牛乳を飲んでお腹がゴロゴロしてしまう方がいらっしゃるように、本来私たち日本人はそれらを多く口にしなくても大丈夫な人種だと言えます。
お腹の調子を整えたいのであれば、日本古来からあるお味噌や納豆など発酵食品を食べたほうが、同じ発酵食品でも私たちの身体には適しています。
朝スムージーの落とし穴
ダイエット、美容のために良いと言われているグリーンスムージーですが、飲み方を間違えると冷えの原因に。
胃腸へ優しく消化の負担も少ないため朝食として頂く事は悪くはないのですが、例えばそれが冷蔵庫で冷やしたものだった場合、内臓冷えの原因に。内臓を冷やしてしまうと代謝が悪くなるため、せっかくのダイエットも成功どころか逆効果に…
また、南国系のフルーツは身体の熱を下げる作用はあるためこの時期はオススメしません。
今が旬でかつ、日本でとれるフルーツで作ったほうが良いのですが、できるのであればスムージー習慣は夏だけにしておいたほうが安心です。
朝は体温を上げる習慣を!
人は日中活発に動くため、目覚めと共に体温を上げようとします。しかし、そこで上記に述べたような身体を冷やしてしまう物を食べてしまうと、1日中体温が上がりきらず過ごす事になり、冷えを感じやすくなったり集中力が欠けてしまったり…とさまざまな不調へ繋がります。
また、手軽に食べられる菓子パンも危険。菓子パンには精製されたたっぷりのお砂糖が含まれていますが、この白砂糖も体を冷やす原因食材のひとつ。
特にこの時期、朝の習慣はとっても大切!
ヨーグルトやフルーツなどで済ませている方は、温かいスープや発酵食品であるお味噌汁を頂き体の内側からしっかり温める努力をしましょう。菓子パンが習慣となっている方は、おにぎりにチェンジすることをオススメします。
いかがでしたか?冷えは長年の生活習慣の蓄積によるものです。日々の習慣を見直しできることからはじめ、冷えを解消していきましょう!
[スキンケア大学/美ログ]
Posted by nob : 2014年01月31日 09:24
私も、野菜&フルーツジュースに加えて、歳明け早々から発芽玄米&菜食中心に切り替えました。。。
■発芽玄米の登場で注目されるGABA(ギャバ)
発芽玄米の登場とともに脚光を浴びている成分、それが通称GABA(ギャバ)だ。正式名称は「ガンマ−アミノ酪酸」。文字通りアミノ酸の一種だが、たんぱく質を形作っている18種類のアミノ酸とは異なり、特に哺乳動物の脳や脊髄に存在する。
ギャバは体内で主に抑制系の神経伝達物質として脳内の血流を活発にし、酸素供給量を増やしたり、脳細胞の代謝機能を高めるはたらきがあることがわかっている。このため、脳内のギャバが不足するとイライラするのをはじめ、さまざまな体調不良を招き、ひいては大きな病気の引き金となってしまうのだ。
<GABAは睡眠中に生成される>
通常、ギャバは睡眠中、特に深い眠りに入っているときに生成されるため、睡眠不足はこのギャバ不足にもつながるとされていた。では、睡眠不足の人は、みんながギャバ不足に陥ってしまうのだろうか?
近年までは食べ物によってギャバを摂取しても、脳内へ到達することはないと言われてきた。
しかしギャバの研究が進み、最近になって、食べ物によって摂ったギャバも脳へ届くことがようやくわかってきたのだ。つまり、不足するギャバは食べ物から摂ればよいというわけだ。
期待されるGABAの効能
ギャバを摂ることによって、期待できる効果は、実に幅広く、多彩なことに驚くはず。
■血圧を下げる
ギャバには、血液中の塩分をろ過する腎臓のはたらきを活発にし、利尿作用を促すことで血圧を下げるはたらきがある。このため高血圧の予防に効果があるとされている。
■中性脂肪を抑える
ギャバが内臓のはたらきを活発にして消費エネルギー量を高める一方、血液中のコレステロールや中性脂肪をコントロールし、脂質代謝を促すことがわかっている。このため肥満の予防ばかりでなく、糖尿病などの予防にも役立つのではないかと期待されている。
■肝臓・腎臓のはたらきを高める
腎臓のはたらきを活発にして血圧を下げるばかりでなく、ギャバには肝臓のはたらきを促す効果も。このためアルコールの代謝も速くなるとされている。
■神経を鎮める
ギャバは、脳内で抑制系の神経伝達物質としてはたらく成分。このため、ギャバを摂ることでイライラなどをやわらげる効果がある。実際、パニックや不安の状態にある人の脳脊髄液を調べたところ、ギャバが著しく減っていたという実験結果も。これらのことから睡眠障害、自律神経の失調、うつ、更年期の抑うつや初老期の不眠といった症状の改善にも効果が期待されている。
さらに最近では、アルツハイマー型痴呆症の予防・改善にも期待できると話題を集めている。
発芽玄米のGABA量は白米の約10倍、玄米の約3倍!
人間の脳神経から内臓、血液のはたらきまで、さまざまな観点から効果が期待できるギャバ。これを効率よく摂取できるのが発芽玄米なのだ。ギャバの量は、白米にはわずかに1mg、胚芽米で2.5mg、玄米でも3mgなのに対し、発芽玄米は10mgと圧倒的に優れている。しかも発芽玄米なら、毎日の食事で意識しなくても摂れるのだから、便利だ。
[healthクリック]
Posted by nob : 2014年01月29日 18:16
これも呼吸法の一つ。。。
■どこでも安眠できる。ストレス知らずの丹田ヒーリング
毎日めまぐるしく動く情報の中で暮らしていると、一日が終わるころには身も心もヘトヘト。そこで、今日こそは早く寝ようと早めにベッドに入っても、神経が高ぶって眠れない......。
いくら体を休めようとしても心がついていかなければ、せっかくのリフレッシュタイムも台無しです。では、どうしたら心身ともに癒されるのでしょう?
そんなときは、ベッドに入ってからでもできる、自己ヒーリングがいいようです。おへその下、指3本分くらいのところにある「丹田」は、生命エネルギーの貯蔵庫とも言われる場所で、その丹田を温かい状態で保つと、心身共に幸福感に溢れて質の良い睡眠をとることができるのだそう。
丹田ヒーリング
1.下腹部に両手を当てます。
2.その状態で息を吸って下腹部を膨らませます。
3.次にゆっくりと息を吐きながら元にもどします。
4.これを数回繰り返します。
5.慣れてきたところで そのまま下腹部を膨らませた状態を保ちます。
6.膨らんだ下腹部の中心を意識して下さい。温かい感覚があります。この下腹部の中心が「丹田」です。
7.丹田を意識したまま、通常の呼吸に戻します。
これは、心身のほぐし&デトックスのオーダーメイドセラピー、癒やし亭 創始者である藤本明伸先生の直伝メソッド。1人で出来るので、ぜひともマスターしたいです。
丹田ヒーリングのコツを覚えると、どこにいても自分で心身を癒せるようになるので、旅先で眠れない私もやってみようと思います。これで、どこにいってもマッサージ店ばかり探す、なんてこともなくなるかもしれません。
(松田朝子)
[MYLOHAS]
Posted by nob : 2014年01月29日 14:00
結局はバランス良く、食べ過ぎ飲み過ぎに注意する、、、そんな当たり前の食生活をするということでしょう。。。Vol.2
■気がつくと「三段腹」になってしまう5つの勘違い「NG:食事が少ない」「NG:野菜しか食べない」
いかに毎日の生活を健康的に送るかが、スリム体形を維持するための大切なポイント。頑張っているのに三段腹になってしまうアナタは、勘違いしているのかも?
●勘違いその1:食事を少なめに食べる
食事を少なめに取る女性は要注意!これは「もっと食べたい」という心理的要素を煽(あお)り、ドカ食いしてしまうことを意味するのです。満足のいく量をしっかりと食べることの方がスリムへの近道!
●勘違いその2:肉類は控えめの「野菜中心」生活
脂肪が含まれる肉類は控え、野菜ばかりを食べることが健康であると信じてやまない女性は数多く存在します。しかし、そういう女性に限って三段腹が多かったりするのです。肉類に含まれる動物性タンパク質には代謝機能を高める効果があるので、脂肪も燃えやすい体質にしてくれます。お肉は適量を食べるようにして。
●勘違いその3:パンは食べない
血糖値を大幅に上げてしまう「白い」パンは食べないに越したことはないですが、全てのパンを避けてしまっているアナタは大きな損をしています。穀物がたくさん入ったパンやグラノーラ(無糖のもの)はインスリン値の上昇を遅めてくれる効果があるので、おなかに脂肪が付きにくくなるのです。1日に1回食べることで代謝に変化が見えてくるそうですよ。
●勘違いその4:「ライト」な商品を選ぶ
健康を考えて「ライト」な商品を選んでいるアナタは、身体を傷めているのをご存じでしたか?確かに糖分は少ないのかもしれませんが、その代わりに「人工甘味料」などの化学物質が大量に含まれているのです。砂糖が入っていないのに「甘い」なんて不自然にも程がありますよね。人工甘味料が脂肪を蓄えやすい身体にしているという調査結果もあるので、これは要注意。
●勘違いその5:脂肪は大敵
「脂肪=デブの要素」と思っている女性は数知れず。しかし、脂肪にもいろいろな種類があることはあまり知られていません。アボカドやオリーブオイルなどの良性脂肪は、身体に付いている脂肪を燃やしてくれる作用があるから意識的に摂(と)ることをおすすめします。脂肪が脂肪を燃やすのです。
あえて避けてきたものが実は必要なものだったなんてショックですよね!
今からだって決して遅くはないから、早速、頭を切り替えて。
※当記事は、ハイブリッド翻訳のワールドジャンパー(http://www.worldjumper.com)の協力により執筆されました。
参考:5 Habits That Give You Belly Flab
http://www.cosmopolitan.co.za/bodysoul/Diet/5-habits-that-give-you-belly-flab-pg1
[マイナビウーマン]
Posted by nob : 2014年01月29日 13:51
人は今日生きているように明日死に往くもの、、、生きるも死ぬも自らの生を救えるのは自分自身のみ。。。Vol.4
■感動ドキュメンタリー 生命は不思議なり治らないものも治ることがある 医者は見捨てた—しかし神は見捨てなかったかくて奇跡は起きた!
「余命は3ヵ月です」「もう手の施しようがありません」—突然突きつけられる医師からの宣告。死は確実に目の前に迫っていたはずなのに、それを乗り越えた患者がいる。彼らはなぜ生還できたのか。
治療もしていないのに
茨城県つくば市で在宅医療専門のホームオン・クリニックつくばを経営している平野国美医師の元に、父親が通う病院の院長から電話がかかってきたのは、2009年12月のことだ。
「お父さんが胃がんです」—院長はそう告げた。話を聞いて、平野医師は、父親の余命は3ヵ月もないだろうと判断した。
「もう次の桜を見せることはかなわないと思いました。ならば人生の最後は、せめて苦しまずに逝かせてあげたいと思い、延命治療のすべてを断り、引き取る旨を院長に伝えました」
引き取った父親のためにマンションを借り、頻繁に顔を出して買い物や食事をともにした。多少の抗がん剤は用いたが、根治療法は一切なし。それでも病状は不思議と安定し、桜の時期を乗り越える。奇跡のような日々は3年ほど続いた。
「けれど、昨年の12月から体調が急変したんです。意識が常に飛ぶようになり、何度も『オレ、大丈夫だよね?』と私に聞くようになりました。私も、心構えだけはして、葬儀の準備も進めていました」
そして今年1月、平野医師は自身が運営する看取りのできる有料老人ホームに父親を移した。プロである息子から見ても、2度目の奇跡はさすがに起きないと覚悟したのである。寝たきりの日々が続いたが、入居後10日ほど経つと、目を疑うような変化が起こり始めた。
「徐々に体調が回復し、歩けるようになったのです。『いやあ、治っちゃったよ』と本人が言うくらいで、トンカツをぺろりと平らげるくらい食欲も出てきた。今では毎朝、ホームの仲間たちと散歩をし、自転車を買いたいと言い出すまでになりました」
余命3ヵ月の見立てから、3年6ヵ月。その父・國雄さんは、友人に囲まれ、好きなものを食べ、ホームの主のような顔をして楽しく日々を過ごしている。がんの治療は、変わらず受けていない。
「がんじゃなかったんだよね、胃潰瘍だったんだよ」
國雄さんはこう笑い飛ばす。もちろん、がんという診断が誤りだったわけではないが、すでに過去のことになっているようだ。いまでは検査も受けていないので、がんがどのような状態になっているかはわからない。だが、がんが発覚したときよりも明らかに元気になった姿がそこにある。
医学的には説明できない
平野医師はこう話す。
「医学的な説明は思いつきません。『こういう人もいるんだな』としか言えない。がんと共存しているのでしょう。最初に父の世話をした医師も、父を見て思わず『お元気なんだ……』と絶句しました。何が起こっているのか、私のほうが聞きたいくらいですが、父の楽天的な性格が幸いしているのかなとは思います。病は気からと言うけれど、父はがんであること自体を否定していますから」
医者にも理解できないような奇跡的な回復—なぜこのようなことが起きるのか。誰にも説明はできない。けれど、「もう打つ手はない」と宣告された患者が生還を果たすケースは、少ないながらも存在する。
千葉県在住の加藤公子さん(70歳)も、そうした一人だ。加藤さんを襲ったのは肝臓がん。'07年の発見時にはすでに末期だった。主治医は、本人には余命までは明かさなかったが、加藤さんの娘には、「もってあと3ヵ月から半年」と宣告していた。
加藤さんが振り返る。
「娘が急に優しくなりましてね。何かおかしい、と感づいて、問い詰めました。すると涙ぐみながら、私に打ち明けたんです。言葉が出ませんでした。でも、私は20年前に乳がんもやっている。いつ死のうと仕方がないと思い、何があってもうろたえることだけはしまいと覚悟を決めました」
けれども、諦めたわけではなかった。主治医からは「治療しても効果は期待できない」と言われたが、ラジオ波焼灼術、カテーテルを入れて抗がん剤をがんに直接注入する動注化学療法など、打てる手はすべて打った。そして半年後—。
「信じられないのですが、私のがんは跡形もなく消えました。治療してくれた先生自身が、退院時に『信じられない、信じられない』と言うほどでした」
それから6年が経過。再発の兆候はまったくない。「治療が私に完璧にマッチした」、加藤さんはそう信じている。
「生存率0%」でも諦めない
青森市で弁護士として活躍する小野允雄さん(74歳)は、'02年にステージⅣの大腸がんが発覚した。がんは腹膜播種(腹膜に散らばった状態)を起こしており、手術をしても再発の可能性は非常に高かった。
「ダメなんじゃないか、と本当に不安でした。術後の抗がん剤の副作用も相当苦しかった。でも、それに耐えられたのは、とにかく生きたかったからなんです。今は死ねない、子どもたちのことをもっと見届けたいと思い続けていました」(小野さん)
だが、その思いも虚しく、3ヵ月後、肝臓にがんが見つかり、その後脾臓へと転移する。
「2度目の手術をする前、家内と一緒に医師から病状の説明を受けたのですが、『がんが腹膜に広がっている可能性が高い』と言われました。そのときは家内もひどく落胆し、二人で手を取り合って泣きました」
幸いにも腹膜への転移はなく、手術で肝臓の一部と脾臓を摘出。その後は再発の恐怖と闘いながらも、弁護士としての仕事に打ち込む日々を送った。それから10年。いまも再発はない。
「最初の手術が終わったとき、『再発して手術ができない場合は、 2~3ヵ月しか持たない』と医師から言われていたそうなのです。そして、私の病状は5年生存率が0%という状況だった。それは後から知ったのですが、もし最初からその事実を知っていたら、がんと闘う気力が失せていたでしょう。私にとっては、『知らない』ということが良かったのだと思うんです」
逆に、本当のことを全部知ったからこそ、乗り越えられることもある。悪性度の高い子宮絨毛がんの末期から生還し、がん治療のまっただ中で双子の出産まで成し遂げた長友明美さん(64歳)がその人だ。
1981年、長友さんは夫の赴任先のアフリカで第1子を死産した。その後、体調が悪化する。
「最初は産後の肥立ちが悪いのだと思っていましたが、病院に行っても一向によくならない。そこで友人のいるアメリカへ行き、病院で子宮がんが見つかりました。すでに肺にも転移しており、『余命6ヵ月』と宣告されたのです。そのときは頭の中が真っ白で意味がわからず、受け入れることもできませんでした」
抗がん剤治療が始まると、身体はどんどん衰弱していく。死の予感は日々迫ってきた。それなら母国に帰りたい。だが、死を覚悟して訪れた日本の病院で、医師からこう告げられた。
「もうがんで死ぬ時代は終わりました。やることをやれば治りますよ」—この言葉に強く打たれた。
「自分では、生きられるのはあと3~4ヵ月と思っていたんです。両親はお墓まで用意しました。でも先生は、『がんになったのはあなただから、あなたが治して帰るんですよ。私たちはそのお手伝いはできるけど、治すことはあなたじゃないとできないんです。がんと向き合ってください』とおっしゃった。びっくりしました。だって死ぬつもりだったんですから」
この医師との出会いが、諦めかけていた長友さんを死の淵から引き戻した。
「この先生に付いていって、やれるだけやってみよう。闘わずに死ぬのは悔しいと思いました」
ただ病院の治療に身を任すのではなく、長友さんはがんと闘うための猛勉強をした。抗がん剤や温熱療法といった治療に加えて、自分でできる治療法を探求して実践を重ねていった。
そんな治療の最中に、生理が止まった。「生理が止まったら再発の可能性が高い。そのときは子宮を取ります」、医師にはそう言われていた。しかしそれは、再発ではなく、妊娠だった。
「しかも、お腹に宿ったのは双子でした。自分の身体が持つかも心配でしたし、子どもへの抗がん剤の影響など不安で一杯だった。健康に生まれてこない可能性のほうが高い。ものすごく悩みました。でも、『産もう、仮に障害があったとしても、すべてを引き受けよう』と心に決めたのです」
'84年5月、双子が無事に誕生した。二人の女の子は無事に成長し、長友さんのがんは、30年以上たった今も再発していない。
厳しい病に冒された患者を見放すのも医師だが、最後まで共に闘おうとする医師もいる。
上井孝さん(39歳・仮名)は、そんな医師に巡り会い、現在、末期の大腸がんと闘っている。当初は「半年くらい」との医師の見立てだったが、それを大きく超え、がんの発覚から1年7ヵ月を迎えた。
上井さんの主治医である半蔵門病院の平岩正樹医師は、細かい病状から今後の目標まで、すべてを本人に伝え、治療法を一緒に考えているという。
「真実を告げることで患者さんは病気と向き合うことができるのです。自分でなんとかしようという気持ちが一番大事で、それがなくては医者は何もできませんから」(平岩医師)
上井さんは現在、平岩医師の診察を受けるために、自宅のある大阪から東京まで毎週1回、通っている。
「平岩先生の治療を受けたいという一心からです。先生は私がわかる言葉を選びながら、何でも答えてくれる。不安も取り除いてくれます。がんには追い込まれるイメージがありました。でも今は、広がっていくような気がします。身体は不自由になっても、失った分、得るものがある。話もできる。目も見える。ご飯がおいしいとうれしい。太陽が気持ちよいとか、風が心地よいとか、病気になる前まで見過ごしていた日常が、今は大きな喜びなのです」
一日、また一日と、上井さんは「奇跡の記録」を更新し続けている。
神様に選ばれる条件
「どんな状況になっても、明日を人生で最良の日にすることは可能なんです。そうすれば、その翌日はさらに良い日にできる。そして、そうやって大きな病に立ち向かっている姿が、他の人を救うことがたくさんあるのです」(平岩医師)
もう一人、がんとの闘いを続けている人物がいる。ドラマ『スケバン刑事』『宮本武蔵』などで活躍した俳優の中康次さんだ。公表はしていなかったが、中さんは昨年2月に直腸がんが見つかった。ステージは末期のⅣ。肝臓転移もあり、6~7cm大の腫瘍が4~5個あった。医者からは「あと6~8ヵ月」と宣告された。
「開腹手術はできない。いつ死んでもおかしくない状態でした。ただ、直腸が詰まって便が出ないので、腸閉塞対策のために人工肛門の手術だけはしてもらいました。あとは抗がん剤治療です。がんの宣告を受けても、まったく落ち込みませんでしたね。
ドラマの台本だと、ガーンと落ち込んだりするじゃないですか。僕は違った。だって、余命6ヵ月と区切られたからといっても、みんな区切られているじゃないですか。死なない人はいないんだから。『俺の人生、こういうドラマ展開できたか』と思っただけでね。自分でも『なんだ、この落ち着きは』と思ったくらいです」
そんな中さんのがんは、抗がん剤治療後、目に見えて小さくなってきた。いまは3~4週間に1度、入院して抗がん剤治療を続けている。
「余命宣告から1年3ヵ月以上たっているけど、小さくなった状態をずっとキープしています。女房があれこれ工夫して、おいしくて身体にいいものを毎日食べさせてくれるんです。おかげで毎日食事がおいしい。抗がん剤をやっているのに食欲が落ちなくて太ってしまい、減量しているくらいです。『まだ逝くはずがないな。こんだけ食事が美味しいんだから』、そう思っています」
中さんがこうして前向きでいられるのには、ひとつ理由があった。
「僕の信条は『奇跡は必ず起きる』。ただし、信じる者にしか起こらない。この考えは、病気になる前も今も同じです。またこういう取材を受けて、『中さん、本当に治っちゃいましたね』と言われるようになっていれば最高だね。そのときは、『この前言ったでしょう、奇跡は起きるんだよ』って言うからね」
宣告された余命を乗り越え、奇跡を起こすには、さまざまな要因があるだろう。だが、もし神が存在するのなら、「生きたい」と強く願い、必ず治ると信じた人にだけ、手を差し伸べるに違いない。
[現代ビジネス]
Posted by nob : 2014年01月26日 23:39
人は今日生きているように明日死に往くもの、、、生きるも死ぬも自らの生を救えるのは自分自身のみ。。。Vol.3
■結果的に幸せだった「がん宣告」それでも治療を選ばなかった人たち
がんになったら治療を受ける。いまやこれは当たり前のことではなくなってきている。治療を拒否すれば、死は確実に近づいてくる。けれど、残りの命と引き換えにしてこそ得られるものもある。
静かに眠るような最期
「僕はもう死ぬよ」
2011年2月、ドラマ『水戸黄門』『部長刑事』などで名脇役として活躍した俳優の入川保則氏(享年72)は、所属事務所社長の井内徳次氏にこう告げたという。
「がんで、もう半年も生きられないと言うのです。それまでは普通に舞台にも出演していましたから、青天の霹靂でした。今後どうしていくつもりか聞くと、治療は一切しないという。『僕はもういい。人生の幕が来たんだ。役者として死なせてほしい』と」
じつは入川氏のがんは、前年の7月に見つかっていた。直腸がんでステージはⅢ。すぐに手術を受けて腫瘍だけは切除したが、それは一時的な処置に過ぎなかった。
「確実に転移するから抗がん剤治療をしたほうがいい」と医師から言われたが、すでに入っている仕事をキャンセルするわけにはいかない。年末までの仕事をこなし、年が明けた'11年2月。精密検査をした結果、がん細胞が全身に回っていることが発覚したのだった。
「余命は6ヵ月です。あなたに来年はありません」
主治医からはそう告げられた。抗がん剤治療をすれば、命は多少長らえるかもしれない。けれど、それをやると副作用で動けなくなり、役者生命が断たれる。入川氏は治療を断り、役者として余命を使い切るという選択をしたのだった。
当時は独身で一人暮らしの身だったが、3度の結婚と離婚を経験した入川氏には5人の子供と5人の孫がいる。家族は当初、治療することを強く望んでいた。長男の鈴木正則さんが言う。
「『現役が続けられなくなったら自分の寿命はそこまでだ』と常日頃から話していたので、治療はしないという父の選択に、最終的には家族も納得しました。
父はがんを抱えたまま仕事を続けた末、'11年10月に入院しました。治療はせず、痛み止めの処置だけ行っていたんです。父を見ているうちに、似たような状況になったときには自分も同じ選択をするのではないかと思わされるようになっていました」
最初に医師から告げられた"タイムリミット"は'11年8月だったが、それよりも4ヵ月近く長く生きた。生前、自分の葬式費用を前払いし、般若心経も自らテープに吹き込んで準備万端を調える「自主葬」を実践、親しい人々との「お別れ会」も済ませていた。
「健康だったときはそんなこと口にしなかったのですが、『子供たちがいてよかった』とか『ありがとう』などと感謝の気持ちを伝えてくれたことが今でも印象に残っています。
看取ったのは12月24日。主治医の先生に『今は息をしていますが、呼吸器を外すと止まります。外してもいいですか?』とたずねられて、『いいです』と答えました。その後、父は息を引き取った。苦しみも痛みも訴えず、静かに眠るように亡くなりました」(前出・正則さん)
がんが見つかったとき、たとえ1%でも治る可能性があるのなら、少しでも命が延びるのなら、できる限りの治療を受けたいと思うのが人情だろう。
けれど中には入川氏のように「治療をしない」という選択をする人もいる。そうした人が、だんだん増えてきているという。日本尊厳死協会副理事長で埼玉社会保険病院名誉院長の鈴木裕也医師はこう話す。
「死期を延ばすだけの延命治療を拒否する患者さんは、年齢に関係なく増加しています。治る見込みがないのに抗がん剤治療などを続け、副作用を多発させて惨めで不幸な姿になっていく患者さんたちを目にしていることが大きい。
いかに生き、いかに幕引きしたらよいのか、そのことを真剣に考える人が増えてきたのだと思います」
福岡に住む胃がん患者・山口勝己さん(72歳)も、そうした一人だ。
胃がんが発見されたのは3年半前。早期だが内視鏡で取れる程度ではなく、医師からは「胃の3分の2を切除する必要がある」と言われた。治療を強く勧められたが、山口さんは手術・放射線・抗がん剤の三大がん治療をすべて断った。がんになった家族が、治療の甲斐なく亡くなっていったのを目の当たりにしていたからだ。
100%死ぬわけではない
「9年前に実兄を大腸がん、8年前に義兄を食道がんで失ったときの治療を見てきたことが、私自身のがん治療は拒否しようと決めた大きな理由です。
二人とも手術を受け、抗がん剤治療を行って退院したのですが、医師から『体力のあるうちにもう一度がんを叩いておきましょう』と言われ、2度目の抗がん剤治療をしたんです。その"念のため"の治療を始めて1ヵ月もしないうちに亡くなりました」(山口さん)
実際、抗がん剤の副作用から死に至るケースは少なからずある。こうした経験から現代医療への不信感が増し、山口さんは、断食や玄米中心の食事療法など独自の道を選択した。医師から宣告された「何もしなければ3年持たない」という余命はすでに超えたが、いまも元気に暮らしている。
がんの進行状況だけは定期的に病院でチェックしているが、発見当初の状態から進行しないまま、がんはおとなしく治まっているという。痛みなどの症状もまったく出ていない。
がん治療を拒否した患者のすべてが、山口さんのような経過をたどるわけではないが、治療を受けなくても延命している患者が多数存在するのも事実だ。
がん治療の難しさについて、「がん哲学外来」を開設し多くのがん患者との対話を続けている樋野興夫医師(順天堂大学医学部病理・腫瘍学講座教授)はこう語る。
「がん治療の問題は、われわれ医師にとってはグレーゾーンの部分があるんです。治療の効果について70%くらいは医学的に証明されていることで説明できるけれど、説明できないこともある。例えばある抗がん剤が本当にその患者さんに効くかどうかは医者にもやってみなくてはわからないことがあります。統計学的にある程度効くとは言えるが、使う患者によって副作用も違うし、ある人は使っても再発するし、ある人はそれで治ってしまう。まさにケースバイケースなのです」
グレーゾーンだからこそ、「この治療をすれば5年生存率は50%だが、やらなければ20%」といった曖昧な言い方になる。「手術をすれば100%助かるが、やらなければ0%」とは言えない。これががん治療の現実なのだ。
痛みはコントロールできる
では、実際にがん治療を受けなかった場合、患者の身体はどのように変化していくのだろうか。
進行のスピードは個人によって異なるが、がん細胞は無限に増殖を続けていく。だが、「基本的にがん自体に症状はない」という。前出の鈴木医師が解説する。
「がんはどこにできても、がんそのものから痛みや苦痛は出ません。痛みは、がんが大きくなって周辺の神経に触ったときに生じます。すい臓がんは痛みがきついことで知られていますが、これはすい臓の尻尾の部分が脊髄の太い神経に接しているため、がんが大きくなると脊髄の神経に食いこみ、激しい背中の痛みや腰痛が出るのです。
前立腺がんは骨への転移があり、進行するとやはり背中に痛みが現れます。肺がんの場合はがんが気管を圧迫し、空気が通らなくなることで苦しくなる。末期の呼吸困難はこれです。消化器系のがんでは腸閉塞になって食べ物がつかえ、苦痛とともに食欲が衰えて全身衰弱していきます」
骨への転移が進行すると、かなり脆くなりちょっとした衝撃で骨折してしまう。骨折を機に寝たきりとなり、衰弱が進むケースは多い。がんが転移して体中の臓器を蝕んでいくと、食べ物も口から受け入れられなくなってやせ衰える。結果、臓器不全となって死に至るのだ。
一方、進行したがんが原因で起こる痛みは、モルヒネなどを使った緩和ケアで「85%程度までは抑えられる」(前出・鈴木医師)。つまり、治療を拒否して症状が進んだとしても、「健やかに生き、安らかに逝く」ことは可能なのだ。
訪問看護師だった40代の加藤真弓さん(仮名)は、まさにその道を選んで逝った。
彼女を襲ったのは、胃がんの中でもとくにたちの悪いスキルス性胃がん。胃の違和感に気づいて開腹手術をしたところ、お腹の中にがんが散らばった状態で発見された。もはや手術で取りきれる段階ではなく、がんを切除できないままお腹を閉じることになった。
主治医は加藤さんに「延命措置があるのなら、やることが当然。治療しないのはあなたの罪悪だ」とまで言い、抗がん剤治療を強く勧めた。だが、加藤さんはそれをきっぱりと断った。
「がん治療で仕事ができなくなるくらいなら、何も治療せず仕事を全うしたい」—これがその理由だった。
居酒屋にも行ける
加藤さんと親しく接してきた医師で、『こうして死ねたら悔いはない』などの著書もある石飛幸三氏が思い出を語る。
「加藤さんは、仕事で終末期の方と接する中で、がんも自分の一部なのだから、一心同体のものとして受け入れていくしかないと考えていたようです。抗がん剤などでがんを叩けば、あるいは延命できるかもしれない。でもそうしたら副作用で衰えて、人の役に立つことができなくなる。
彼女にとっての"生きる意味"は看護を通して世の中の役に立つことだから、看護の仕事が続けられなくなったら、仮に延命しても、生き続ける意味がなくなってしまうと言うのです」
宣告された余命は3~4ヵ月。けれども、加藤さんは2年以上生き、できる限りの間、訪問看護の仕事を続けた。
石飛医師は、昨年加藤さんの誕生会に招かれ、そこでこんな光景を目にした。
「居酒屋で開かれた誕生会では、彼女は中心静脈栄養の管をつけていて、何も飲めず食べられない状態でした。でも友人たちに囲まれて快活に笑い、おしゃべりしており、その姿はとてもすがすがしいものでした。
残念ながら彼女はそれが最後の誕生日となり、昨年のクリスマスイブに、看護師仲間と弟さんに囲まれて亡くなりました。生前に献体を申し込んでいて、お世話になった人への手紙も書き残していた。最期まで自分の生き方を貫き、本当に立派でした」
加藤さんは、石飛医師にこう言ったという。「がんが完全に治って、元気にまた日常生活が送れるわけではない。もうあと僅かなのに自分の生き方を否定されるのはつらいんです。医者は終末期の患者に『絶対こうしなければならない』と押しつけないでほしい。これは、私の遺言です。先生、このことを世の中の医者に伝えてください」と。
治療を拒否した結果、自分の意志で穏やかな最期を迎えられる患者がいる一方、わずかな可能性にかけて治療に執着し続けた結果、逆に苦しみながら死を迎える人もいる。
進行性の肺がんと診断された会社役員の中村益三さん(仮名・享年65)が、そうだった。日の出ヶ丘病院のホスピス医・小野寺時夫医師がその様子を語る。
「最初に入院した病院で、もう手術は無理だし、このがんには抗がん剤も効かないので、治療はせず元気なうちにやりたいことをやるのが一番いいとアドバイスされたのですが、中村さんはインターネットで肺がんの名医を探し出し、そこで抗がん剤治療を始めたのです。効果が思わしくないということで抗がん剤を何度か変えて治療を続けました。
体調はどんどん悪化し、4ヵ月後には脊椎骨転移で歩けなくなり、5ヵ月目に右手がしびれ、会話ができなくなって脳転移と判明。私のところに来られたときは意識も混濁しており、2週間ほどで亡くなりました。
奥さんと約束していた南米旅行も果たせず、抗がん剤治療で苦しみ抜いた末に死を迎えたのです」
もちろん、何とか助かりたいという一念から、最後まで治療に専念した中村さんの選択を否定することは誰にもできない。とことんまで治療にこだわること自体が、その人の生きがいになっていることもある。
治療するか、しないか。それは個人個人の生き方、あるいは死に方をどう考えるかに委ねられる。前出の樋野医師は、治療を拒否してもよい最期を迎えられるかどうかを決めるのは、患者の「覚悟」だと語る。
「がん治療をしないと決めて幸せな最期を迎える人と、そうでない人の最大の違いは『覚悟』の有無です。
覚悟をもってがんを受け入れた人は後悔しません。自分はもう決めたのだから、大丈夫だと言い切れる。そういう人は、たとえ寝たきりであっても、他人を感化します。家族のため、誰かのために何かができる。勇気を与えることができる。そのときその人は、自分の社会的な地位や役割などを超越して、自分の存在自体に役割があるのだという人間観の転換ができている。そういう人は、幸せな人生を遂げられるのです」
自分が病を受け入れ、その生き様で他人に影響を与える。「人の役に立ちたい」と最期まで意思を貫いた前出の加藤さんは、まさにこれを体現していた。
家族も幸せになった
最期の最期まで積極治療をして後悔するのは、患者よりその家族のほうが多いという。樋野医師が続ける。
「死ぬまで辛い治療を受けさせ、苦しめてしまったという後悔が家族に残るからです。そうならないためには、たとえ患者が選んだ方法が間違いだと思っても、家族はそれを認めてどんなことがあっても患者に寄り添うことです」
それをかなえられた理想の形が、一昨年5月に食道がんで亡くなった作家・団鬼六氏(享年79)のケースかもしれない。長女の黒岩由起子さんが振り返る。
「医師からがんを宣告されたときは母と私も同席していたのですが、父は即座に『身体を切り刻んでまで生きたいと思わない』と手術を拒否しました。母が慌てて『ちょ、ちょっと。もう少しゆっくり考えようよ』と言ったのですが、父の意思は固かった。
もちろん私たち家族は手術を勧めました。父に生きていて欲しいという気持ちは当然ですが、団鬼六を殺してはいけないという思いもありました。でも父には、団鬼六として生きるのならば、手術を受けてヘロヘロになってまで生きながらえるべきではないという信念があったんです」
家族の願いもあり、放射線治療と抗がん剤治療を少しは受けたが、手術は最期まで拒絶し通した。胃ろうも拒み、死ぬまで口で食べることにこだわった。
だがやがて肺に転移が見つかる。咳が止まらず、苦しいと訴えるようになった。
「もうあかんってことやろ」
徐々に、身体だけでなく心も弱り、こんな言葉が口をついて出ることもあった。でも、治療を拒否した患者に対し、家族は励ますことしかできない。由起子さんは最期まで「団鬼六」として生きてもらうため、力を尽くした。
団氏は家族の支えを受け、最期まで奔放に生き抜く。医師から止められても、好きな酒は飲み続け、仲間を呼んでパーティーを開き、家族で旅行にも出かけた。そして、亡くなる5日前まで原稿に筆を走らせていた。
「最期まで手術拒否を後悔するような言葉は一切口にしませんでした。けれど、もちろん本人は生きていたかったんです。
『ただ生きながらえるのは死ぬより嫌だ』『自分の生きたいように生きさせてくれ』と言い、『ただ長生きさせることが親孝行だとは思うな』とも言っていました。この言葉は、振り返ってみると何にも代えがたい救いの言葉になっているんです。
手術を受けるにせよ、受けないにせよ、残された家族は必ずあとで『あの時ああすればよかった』と思うものです。父の言葉は、家族をそうした悔いから救ってくれました。
親の命のことなんて、どうにも決められません。だけど病院に入れば、以後は病院のレールに乗せられてしまう。家族にとってはセオリー通りに事が進むから安心なんです。『こうやっていれば大丈夫』と思えますから。そう考えると、結局、こう生きたいと考えて、それを実行に移せるのは本人しかいない。団鬼六はそうやって生き、私たち家族を救ってくれました」
がん治療を拒否する患者は、医師はもちろん、家族から見ても「わがまま」と見なされがちだ。けれども由起子さんは、こう言う。
「私も父はわがままだと思い、なんでそんなに死に急ぐのかと思いました。でも今は、父は家族のためを思って、自分の好きなように逝ってくれたのだと思えます。死んでしまうことは負けではない。父本人にとってみれば勝ちです。だって結局は死ぬんですから」
自分自身の意思を貫き、生涯を終えた後も家族の心を支えられる—それこそが、最高に幸せな生き方と言えるのではないか。
[現代ビジネス]
Posted by nob : 2014年01月26日 22:00
人は今日生きているように明日死に往くもの、、、生きるも死ぬも自らの生を救えるのは自分自身のみ。。。Vol.2
■切るべきか、切らざるべきか、あえて放置する手もある「あの『決断』が生死を分けた」医者が大病を患ったとき
人は大きな病気にかかった時、困惑し、恐怖し、どうしたらいいか途方に暮れる。それは、医者でも同じこと。だが、医者だからこそ下せた「決断」がある。彼らは、死の淵からいかにして生還したのか。
CASE1 脳卒中
命の危険を冒して早期リハビリをした
「病院で会議をしている最中、突然、何かの塊が首の左側を下から上へ、顎を通ってつむじまで、ムクムクと走り上がるのを感じました。直後、体が大きく傾いた。まるで、天地が逆さになったようでした。脳卒中でした」
琉球大学名誉教授でおきなわ健康長寿研究開発センター会長の鈴木信医師(80歳)は15年前、病に倒れた。左脳に脳梗塞を起こしたのだ。
「以前から手の震えや、コレステロール値が360まで上がるなど、今考えれば予兆といえるものもありましたが、特別気にも留めていませんでした。
ストレッチャーで運ばれている間、意識が戻ったり遠のいたりを繰り返し、やがて昏睡状態に。この間、いわゆる『走馬灯』を見ました。子供の頃に剣道教室をサボったことや、娘が生まれた時のことなど、さまざまな思い出が目まぐるしくフラッシュバックしたのです。まるで、あの世とこの世を行ったり来たりしているようでした」
目が覚めたのは9時間後。だが、残酷な現実が鈴木医師を待ち構えていた。
「目を開けると神経内科の教授がいて、『麻痺はあるか』という声が聞こえました。『ないよ』と言おうとしたのですが……『アーアー』としか声が出ない。体も動かない。完全に右半身の自由と言葉を失っていました。
周りのスタッフが話している内容はわかるのですが、言語中枢がある左脳にダメージを受けたため、失語症になってしまったのです。医師にとって、これは致命的。もうダメだ、と絶望的な気持ちになりました」
意思表示ができないので、検査や処置もされるがまま。
「体中管だらけで、まるでロボットのような状態です。必要性のわからない検査をしようとするスタッフに腹が立ったし、CTやらレントゲンを撮るため長時間寝かされ、腰がひどく痛む。『腰が痛い』『管を取ってくれ』と言いたいけど、言葉は出ません。かといって動くと、同僚医師に『我慢ができない、バカな人だ』と言われた。あの時の惨めな気持ちは忘れられません」
検査の結果、左大脳の4分の1が大きく損傷していた。鈴木医師のように頸動脈に血栓が詰まった場合、死亡率は約50%。生き残っても、3分の2の確率で寝たきりになるか、ボケてしまうという。だが、そんな窮地を脱せたのは、医師としてのある「決断」だった。
「奇跡的に命はとりとめましたが、このままでは脳細胞がどんどん死滅してしまう。当時、脳卒中になったら1ヵ月の長期にわたって安静にしてから、ようやくリハビリというのが一般的でした。たしかに、あまり早くからリハビリをすると、再発して死亡するリスクがある。だからこそ、医師は安静を求める。しかし、復帰するには一刻も早くリハビリするしかありません。私は『寝たきりやボケになるなら、死んでも本望だ』と、命を賭してリハビリすることを決断したのです。
強い意志のもと、まずは必死に口を動かすことと、発声練習をしました。
倒れてから3日目、ついに言葉が出ました。最初に出たのは『NO』。この時は感動しましたよ。そして、何とか意思疎通ができるようになったのは1週間後。でも、不思議なことに英語ばかり出てくる。これは今でも謎ですね。
その後も、新聞や本の音読、算数などで脳を刺激するほか、麻痺した顔面の体操や病院の敷地を妻に支えてもらいながら一周したりと、必死にリハビリをしました。看護師に怒られながらも、消灯後も発音訓練を続けました。
その結果、倒れて2ヵ月後に、自ら希望して病院の外来に復帰させてもらいました。当然、言葉は思うように出てきませんでしたが、日頃から通院している患者さんたちが、『私への診察をリハビリの一環にして』と言ってくれた。彼らの温情に涙が流れました。
今は、後遺症の95%は消えました。振り返ると、病気を克服できたのはあの時の『決断』と『意志の力』です。病気は医者が治すのではない。自分で治すのです。病気を経験して、改めて痛感した真実です」
CASE2 心臓弁膜症
82歳、それでも私は手術を選んだ
毎日、腕立て、腹筋、スクワットを50回、ビルの5階に入っているクリニックまでは階段を上って通勤、月に1度は20㎞の長距離ウォーキング—。
80歳を超えても、このような驚くべき生活を送ってきた虎ノ門・日比谷クリニック名誉医院長の山中秀男医師(86歳)が病魔に冒されたのは、2年前だった。
「私はそれまでまったくの病気知らず。毎日トレーニングを欠かさず、健康には絶対の自信を持っていました。ところが、82歳を過ぎた頃からでしょうか。徐々に体に異変が生じ始めました。病院への通勤途中、歩いていると息切れがひどくなるし、階段も、休み休みでないと上れなくなってしまったのです」
さすがに年が年なので単なる老化現象とも考えられるが、山中医師の様子をおかしいと感じた同院の医院長が心配して、心電図をとってくれた。
「すると、『これはダメだ。すぐに心臓の専門医に診せないと危険な状態です』と言われたのです。大病院で精密検査を行った結果は、心臓弁膜症。心臓から血液を送り出す弁が癒合し、血液の流れが妨げられる病気です。私の場合は、運動のやりすぎで、弁が固くなり弾力性がなくなってしまったらしい。
主治医からは、『このまま手術をしなければ酸欠が恒久的に続くため、腎臓・肝臓・脳といった臓器に血液が充分に送り込まれず、多臓器不全を起こすことは確実。手術をせずに薬で安静を保っても、2年しか持たないでしょう』と宣告されました」
余命2年、だが手術をすれば助かる—。
しかし、ここに大きな問題が立ちはだかる。心臓手術の場合、80歳以上になると死亡リスクが一気に高まるのだ。その確率は、6・7%。そのため、75歳以上の患者には手術しないという病院もあるほどだ。しかし、山中医師は、勇敢な「決断」を下した。
「手術を受けることを即決しました。当時、私は84歳。もともと元消化器外科医ですから、どんな手術になるのかも、もちろん承知の上でした。
死の危険を恐れて、2年の命を生きるか。即死のリスクを冒してでも、チャレンジして長生きするか……。究極の選択でしたが、私は、自分の体を信じることに決めたのです」
家族にもこの決意を伝え、山中医師はシコを踏んで気合を入れて、手術室へと向かった。
「手術は、無事に終了しました。翌朝、ICUで目が覚めた時、最初に思ったのは『ハラが減った』ということ。その日の朝食はカレーライスで、縫った傷が痛かったけど、全部平らげました(笑)。さらに翌日には一般病棟に戻り、順調に回復していきました」
自分の体を信じた「決断」は、見事にいい結果を招いた。今日も山中医師は元気に笑う。
「激しい運動のやりすぎで心臓を壊しましたが、極限に挑戦するような運動のおかげで術後の体力も保たれたと思っています。
手術3ヵ月後には、クリニックで診察を再開しました。去年からは、1日1万歩を目標に歩いています。まだまだ、現役を続けていきますよ」
「前向きな気持ちも健康の秘訣」と山中秀男医師
CASE3 腎臓がん
迷う自分を救ってくれた一言
「あのとき検査をしていなければ、私はいまこの世にいなかったでしょうね。がんを患ったあとの時間は『おつりの人生』だと思っているんです」
聖隷三方原病院(静岡県)呼吸器センター長で肺がんの名医として知られる丹羽宏医師(60歳)はこう話す。体の異変に気付いたのは、15年前、45歳のときだった。
「東京での学会が終わった夜、その解放感から飲みすぎてトイレに駆け込んだら、便器が真っ赤に染まるほどの血便が出たんです。これは大腸がんかもしれないと思って病院で検査をすると、恥ずかしながら、原因はただの切れ痔だった。でもその検査で、腎臓に腫瘍が見つかりました」
不安になった丹羽医師は、二人の泌尿器の専門医に相談に行ったという。一人目のA医師は、悩みながらこう言った。
「これは、がんかもしれないですが、お腹を切ってみなければわかりません。手術をしたほうがいいと思いますが、経過観察する方法もあります」
次に相談したB医師は、検査画像を見るなり、こう断言した。
「これは腎臓がんですね。すぐに手術をしたほうがいいです。私に任せて下さい」
この二人の言葉を聞き、丹羽医師はB医師に手術を任せるという決断をした。
「私は外科医なので、手術できるなら切ったほうが安心だろうとは思っていましたが、実際に患者の立場になると、状況を冷静に判断することができなかった。
がんでないなら手術をしなくてもいいのではないか、でもがんだったら手術しないと手遅れになるはずだ、本当に治るだろうか、自分の命はあとどれくらいだろうか……不安はつきません。自分は99%がんだと思っていましたし、『任せて下さい』と私の求めていたことを言って背中を押してくれたのが、B医師だったんです」
医者自身が治療法を迷えば、患者の不安はさらに増してしまう。どの医者に命を託すのか—それを決めるとき、医者の話を聞いて不安になるか安心するか、が一つの決め手になる。
検査で偶然見つかっただけでなく、丹羽医師のこの決断こそが生死の分かれ道となった。
へそ上から脇腹まで胴囲の4分の1周にメスを入れる大手術となったが、無事に終了。現在も再発はない。
「腎臓がんは骨に転移したり、血尿が出て初めてわかる病気なので、もしあのとき見つかっていなかったら、手遅れになっていたでしょう。それに、病気を乗り越えられたのは、あのときB医師が任せてくれと言ってくれたのが大きかった。医者は迷ってはいけない。患者の先導者であるべきなんです。そのことを患者になって改めて実感しました。その医師は、自分の疑問や不安を解消してくれるか。手術を迷っている患者さんがいるとき、自分のこの経験をお話しすることもあるんです」
CASE4 大腸がん
病気になった後も習慣は変えない
肺結核に赤痢、一過性の脳梗塞、膀胱炎、高血圧、高脂血症、肺炎、白内障、中耳炎、皮膚がん……軽いものまで含めたら、体験した病気は100以上にものぼるという。日本心臓病学会の初代理事長で半蔵門病院循環器内科の坂本二哉医師(84歳)は、まさに〝病気のデパート〟と呼ぶにふさわしい病歴を持つ。
「私はこれまでに4度ほど死にぞこないの経験をしています」と話すが、その中の一つが、大腸がんだ。
50歳のときのこと。地方へ講演に出かけた際、ベルトを締めていられないほどの腹部の膨満感を覚えた。病院へ行ってレントゲンを撮ると、進行した大腸がんが見つかる。
通常であれば、精密検査をしてから手術に臨むが、坂本医師は「即手術」を決断。4日後に手術が決行された。
「がんだとわかっているなら、早く取らないと血液に入って全身に広がってしまう可能性もある。だからすぐに手術をすることにしたんです。
じつは自分の病状は、手術当時詳しく知らなかった。術後20年経った祝いの席で、主治医の口からはじめて聞いたんです。実際は、S字結腸と直腸に合計3ヵ所のがんがあって、リンパ節にも転移していたということでした。かなり進行していたようです。そのままにしていたら、一巻の終わりだったでしょう」
当時、大腸がん手術では国内でもトップの腕を持つ医師が執刀。リンパ節へ転移したがんも丹念に切除された。腸を大きく切除したため、術後はトイレが近くなるなどの不自由は生じたが、次第に慣れていったという。
手術から20日後には、仕事にも復帰した。術後に何度か腸捻転を起こしたこともあったが、30年以上経つ現在も、再発はない。
「仕事に打ち込むことで、がんを患ったことを半分忘れていたというところもありますね」
一度手術をしたら、再発の恐怖におびえながら生活を送る人も多いが、病気を患ったことそのものを「忘れる」というのも一つの生き方だ。
さらに坂本医師は、大病を患った後も、過剰に体を労りすぎないよう、あえて生活習慣を変えないようにしたという。病になると、すぐに生活習慣を改善せよと迫る医師は多いが、ストレスを溜めずに生きることも、健康を保つ重要な要素ということだろう。
「私は大の偏食家で、野菜は食べないし、食べられないもののほうが多いくらい。けれど、がんになってからも、健康のために無理に野菜を食べようとは一切していません。食生活もまったく変わっていないですね。仕事をセーブすることもしませんでした。
私の最大の特徴は、嫌なことはすぐに忘れること。それから、諦めも早いということ。レントゲン画像を見たときはショックでしたが、医療に『100%』というものはないんです。検査の所見が間違うこともあれば、治療がうまくいかないこともある。あまりくどくど考えるほうがよくないと思っています。病気になるかならないか、いつ死ぬかということは生まれたときに決まっている。あとは運だ、とね。そういう意味では、私は神様になかなか見放されず、運がいいのでしょうね(笑)」
CASE5 前立腺がん
男性機能を失うリスクも恐れない
東京医療保健大学副学長で元NTT東日本関東病院外科部長の小西敏郎医師(66歳)は、がんを2度経験している。6年前に患った胃がんは、ごく早期だったため内視鏡治療で完治。その2年後には前立腺がんが見つかった。
「一つがんを克服したと思ったら次のがんがきた。まだほかの場所にもがんが出るのではないか、私はどのくらい生きられるのだろうか、そんな気持ちに襲われました。迷ったのは、治療法です。前立腺がんの場合、ホルモン療法、腹腔鏡手術、放射線治療、ロボット手術とさまざまな選択肢があるのですが、相談する医師が変われば勧める治療法も違いました。私の専門は消化器なので、前立腺がんでどれを選ぶのがベストなのか、まるでわからなかった」
そんな迷いが生じたとき、小西医師が相談したのが、同僚の医師だった。
「当時私が勤めていたNTT東日本関東病院の泌尿器科部長でした。長年付き合いがある飲み友達で、腕の良さも評判の医師。彼に任せよう、そう決めたんです」
その医師に勧められたのは、開腹手術だった。前立腺を摘出する手術は、術後に男性機能が失われ、排尿障害が残る可能性もある。だが、小西医師は決意を変えることはなかった。
「自分と同じ病状の患者にいつもやっている、ベストの治療をしてほしいということが私の望みでしたから。これは私の哲学です。もう孫もいましたし、男性機能が失われても逆にすっきりするのではないかと考えたんです。
手術をすれば、以前とまったく同じには戻らないことは分かっていました。でも、その後の人生に順応していけばいい、と。手術は無事に終わりましたし、後悔はありません。
医者が患者に治療法を選ばせる時代になっていますが、そんなもの決められるわけがない。何人かに相談してみて、この人なら悔いはないという医者に任せる。自分が納得できる理由があればいいと思うんです」
CASE6心筋梗塞
ちょっとした違和感で検査した
「首を寝違えたのかな……」
東京女子医科大学脳神経外科講師の林基弘医師(48歳)は、2年前の4月、首に異変を感じた。休日の夕方、自宅でテレビを観ながらうたた寝をしているときだった。
「首の左前が重たくなったんです。でも、反対向きで寝ると、じきに治った。そのままテレビを観ていたら、ふと気づくと番組が途切れてCMが映っていました。そのときは気づかなかったのですが、意識が飛んでいたんです。それから滝のように汗が噴き出してきた。おかしいなと思って、その日はすぐに眠りました」
夜中に目覚めると、症状は治まっている。だが、これは何かの兆候かもしれない—林医師は、そう予感した。
「通常、心筋梗塞の症状は胸部痛や左肩に抜ける放散痛が出るのですが、私はそれにはまったく当てはまらなかった。でも調べてみると、私のようなタイプの心筋梗塞もあるとわかりました。医者としてのプライドがあって、自宅マンションに救急車を呼ぶのもためらわれ、次の日に、循環器の専門の先生に相談することにしたんです」
翌日、心電図をとると、案の定異常が見つかった。
「林先生、すみませんがそのまま寝て下さい」
医師からそう告げられ、即、緊急治療となった。冠動脈が詰まってからすでに13時間以上が経過。心筋の壊死が進んでいた。
「治療台の上で、治療の指示を出す医師の声を聞きながら、自分の状態が良くないことがわかりました。ただ、怖いという思いはなく、『このまま目の前が真っ白になったら、あちらの世界に行ってしまうのだな』と、客観的にとらえている自分がいた。不思議な感覚でした。人生というのはテレビのスイッチを押すように、簡単に終わってしまうんだ、と思ったんです」
生死のどちらに転んでもおかしくない状況だった。だが、治療は無事に終わり、林医師は一命を取り留める。もし、あのとき首の違和感に気づかず、検査を受ける判断をしていなければ、結果は逆転していただろう。
リハビリを経て、2ヵ月後には外来に復帰。心臓の機能は正常値の70%ほどに落ちていたが、日常生活に大きな支障はない。しかし、この時点で「治った」とは思えなかったという。
「いつまた発症するだろうか。もし再発したら、自分が診ている患者さんに責任が持てなくなってしまう。それでは人間として卑怯ではないか。ある意味、欠陥品の医者になってしまったのだから、医者を辞めてまったく別の仕事をしたほうがいいのではないか……。患者さんを診ながらも、医者としての自信を失い、どうしたらいいかわからなくなってしまっていました」
一命は取り留めた。けど、自分は何のために生きるのか。目的を失って「空っぽになってしまっていた」。
そんな林医師を絶望から救ってくれたのは、外来に訪れた患者だった。
「『先生が心筋梗塞になったと聞いて気が気じゃなかった。帰ってきてくれて、本当によかった』と、僕の目の前で患者さんや家族が泣いてくれたんです。その涙を見たら、こんな自分でも頼りにしてくれている人、命を託してくれる人がいるというのは、なんとありがたいことだろう、と」
林医師はこのとき初めて、医療の本当の目的は、病気を治すことだけではなく、「元に戻すこと」なのだと気付いたと語る。
「治療によって病気を治し、『患者』から『人間』に戻れたとしても、生きる目的を持って社会と関わっていく『社会人』に戻れなければ、患者は本当に『治った』と感じられないんだということを知りました。患者さんに対しても、ただ病気を治せばいいというのではなく、『なぜ治療をしたいのか』『病気を治して何をしたいのか』ということを聞き、そのゴールに向かって一緒に努力するようになったんです」
生きる目的を見失わないこと—生死を分けるのは、こうした思いも関わってくるのかもしれない。
[現代ビジネス]
Posted by nob : 2014年01月26日 21:40
私の乾燥肌対策、、、近日公開します。。。
■今年こそ「脱、乾燥肌!!」
解消されない乾燥肌
空気の乾燥が気になるこの季節。100年前から東京では湿度が20%近く低下しているそうです。昔では「乾燥肌」などという言葉すらなかったのに、今では多くの人が悩みを持つ大きな美容テーマです。
そもそも、「お肌にとって乾燥が悪い」と言いますが、お肌が乾燥するといったい何が起こって、なぜ悪いのかをしっかり理解している方は少ないのではないでしょうか?
お肌の乾燥でカサカサして、メイクが粉を吹いたようになることを悩んでいる方もいらっしゃると思いますが、それは乾燥肌の氷山の一角にすぎません。もっと深刻な事態がたくさんあります。
また、どんなに保湿ケアをしても乾燥肌が解消されないという話しもよく聞きますが、それは正しい保湿の仕組みを理解していないからかも知れません。今回は、乾燥がお肌に悪い理由と、正しい保湿についてお伝えしたいと思います。
お肌が乾燥すると何が起こる?
お肌が乾燥すると、炎症を知らせる情報伝達物質が肌表面の角質細胞に受け渡されます。そうすると活性酸素が発生して、角質細胞が酸化してしまいます。
つまり、角質細胞が錆びてしまうのです。錆びた角質細胞は水分をキープする力が低下してさらに乾燥します。これを繰り返すことで、お肌は乾燥の悪循環にはまってしまうのです。
前回のコラムでお話ししましたが、肌表面の角質層は角質細胞が水分をたっぷり抱きかかえるスポンジのような役割をし、その細胞同士の隙間を細胞間脂質という油分が埋めつくし、それによってお肌の中の水分を外に逃がさず、なおかつ外からアレルギー物質やウィルスなどの異物が肌に入らない用にブロックするラップフィルムのようなバリア機能の役割を果たしています。
乾燥の悪循環にはまってしまうと、このバリア機能はどんどん低下し、お肌の水分は蒸発して失われ、アレルギー物質による肌荒れを起こしやすくなってしまいます。また、角質細胞が錆びると変色し肌を黄色くくすませます。さらに、バリア機能が低下して危機感を感じた肌は、バリアを強化しようと角質層を分厚くします。角質細胞は灰色をしているため分厚くなると肌は透明感を失い、感触もゴワゴワと固くなってしまいます。
保湿成分は2種類
乾燥の悪循環を断ち切るために重要になるのが保湿です。一言に保湿と言っても、2種類があることはご存知でしょうか?化粧品の成分で言えば、ヒアルロン酸も保湿成分ですし、ワセリンも保湿成分です。
ですが、その2つはまったく違う役割をします。保湿成分にはヒューメクタントとエモリエントという2種類があります。まずヒューメクタントですが、これは水分を抱きかかえる特徴を持つ保湿成分です。
先ほど「角質細胞は水分を抱きかかえるスポンジ」と言いましたが、乾燥進んだ角質細胞はその力が低下しています。この状態に化粧水で水分を補給したところで、ザルに水をかけているようなもので、すぐに蒸発してなくなってしまいます。
そのため、保湿のファーストステップはヒューメクタントで水分を抱きかかえる成分を与えます。
次にスポンジに含まれた水分が外に逃げないようにするフタの役割をするのがエモリエントです。一般的にエモリエントはお肌をしっとりさせる効果が高く即効性を感じるため、エモリエントの比率が高くヒューメクタントがおろそかになっている方が多いようです。
このヒューメクタントとエモリエントのバランスがとれて始めてきちんと保湿されたことになるのです。
●ヒューメクタントの代表成分
尿素、ヒアルロン酸、コラーゲン、PCA-Na、グリセリン
●エモリエントの代表成分
ワセリン、スクワラン、ラノリン、セラミド
※エモリエントは一般的に油分ですが、最近ではポリクオタニウム-51のような肌の表面に保湿保護膜をつくる水溶性高分子も注目されていて、油分にはない保湿効果を得られることがあります。
体全体で乾燥肌ケア
保湿ケアは大切ですが、残念ながら化粧品での保湿は万能ではありません。お肌に本来備わる保湿機能は化粧品とは比べ物にならないほど優秀なのです。実際に保湿ケアなどほとんどせずにも健やかな肌をキープしている人もたくさんいます。
保湿ケアと併せて、その本来の保湿機能を壊さずに高めることを考えて欲しいと思います。今までこのコラムでお伝えしてきたことですが、お肌を弱酸性に保ってバリア機能を高めること。食事によって細胞間脂質(エモリエント)の原料となる栄養素ととること。洗い過ぎて細胞間脂質を壊さないこと。さらに良質な汗にはヒューメクタントである尿素がふくまれますので、冬でも適度な汗をかくことを習慣にすること。
そして、できるだけストレスを溜めず、規則正しい生活を送ること。保湿ケアをしっかりしても乾燥肌がなかなか解消されない方は、体全体で乾燥肌のケアを心がけてください。
[スキンケア大学/美ログ]
Posted by nob : 2014年01月26日 21:35
人は今日生きているように明日死に往くもの、、、生きるも死ぬも自らの生を救えるのは自分自身のみ。。。
■有名人遺族が今だから明かす 思えば、あれが「死の前兆」だった(前編)森繁久彌、大鵬、三船敏郎、大島渚
感動秘話 なぜ、あのとき気付かなかったのか
ふとした瞬間の、いつもとは違う仕種や言葉。亡くなった後だからわかる。あの時、もう「死」は忍び寄っていたのだと。8人の有名人たちの遺族が、医学では説明しきれない不思議な体験を明かす。
森繁久彌 享年96 森繁建(次男)
亡くなる5日前、ギュッと孫娘の手を握った
オヤジが老衰で亡くなる1年ほど前でしょうか。家族みんなで食事をしていた時、「幸せだなぁ……。こんなに幸せな家族って、世間にどれぐらいいるんだろう」と、突然つぶやいたんです。
ずっと仕事一筋の人だったし、そもそも照れ屋でしたから、そんな言葉を聞いたのは一緒に住んでいた僕も初めてで……。今振り返ると、あれはメッセージだったような気がします。国民栄誉賞、文化勲章など、仕事では大変な評価をいただいたオヤジですが、自分にとって一番の幸せは家族との暮らしの中にあると感じていたのでしょう。
仕事は'04年の映画『死に花』とドラマ『向田邦子の恋文』が最後でした。年相応の衰えや足腰の弱りはありましたが、基本的には健康で、その後、出演依頼も何度かありました。でも、僕があえてセーブさせたんです。やはり役者であるからには、周囲に肉体の衰えを見せず、十分な演技が出来なくてはならないと考えていたからです。
仕事から離れたオヤジは、ひ孫たちととても楽しそうに遊んでいました。ご飯を食べさせっこしたり、膝に乗せて会話をしたり。子供が好きでしたから、本当に満足そうでしたね。
最後の入院は、誤嚥が原因でした。食事中、むせたかと思うと呼吸が荒くなり、顔面蒼白に。慌てて主治医を呼んだんです。
すぐに落ち着きましたが、念のため救急車で総合病院に入院しました。主治医は「2~3日で自宅に帰れますよ」と言っていたのですが、検査の結果は誤嚥性の肺炎でした。高齢ですから回復もはかばかしくなく、入院は長引き、3ヵ月。オヤジはしだいに衰えていき、とうとう自宅には戻れずじまいとなってしまいました。高齢者は入院すると、どうしても体力、気力が落ちるんですよね。
入院中、オヤジがよく口にした言葉は、「お腹が空いた、ご飯にしようか」、「お饅頭が食べたい」。また誤嚥したら怖いので我慢させていましたが、「食べたいものを、好きなだけ食べさせてあげれば良かったなぁ」と、今になって後悔することもあります。もう96歳だったのだから、最後は好きにさせてあげれば良かったのかもしれません。
日が経つにつれ、オヤジの口数はどんどん減っていきました。そして1ヵ月半が過ぎる頃には、コミュニケーションは握手が中心になった。「オヤジさん」と呼び掛けて手を握ると、「おう、おう」と答える。力は驚くほどあり、しっかりと握り返してくれました。
亡くなる1週間前からは、もう口もきけなくなって……。でも耳は聞こえていたようで、孫やひ孫たちが「じぃじ、大好きよ」と声を掛けると、微笑むんです。手もやっぱり握り返してきたし、孫たちの体を必死に触ろうとしていました。
亡くなる5日くらい前ですが、しばらく来られなかった僕の娘が面会に来て、手を握ったら……あの光景は、今も忘れられない。いつもと違い、ぎゅーっと何か言いたげに、意思を持った握り方をしたんです。言葉こそ発しませんでしたが「ありがとう、幸せだったよ」と家族に伝えたかったのかもしれませんね。今振り返れば、あのときオヤジは自分の死を覚悟したのかな、とも思うんです。
「今日がヤマです」と医師に告げられたのは亡くなる前日。病室に集まった親族の前には、心電図モニターが置かれました。僕が甥に「テレビドラマでよく見るだろう。この波線が直線になってしまうと、臨終なんだよ」と説明した途端、本当にピーという音と共に全部が直線になったんです。みんなが慌ててベッドを取り囲んだ直後、オヤジは「ふーっ」と深く息をして、一瞬目も開けた。モニター画面はその後も何度か直線になり、そのたびに周囲が「オヤジさん」、「じぃじ」と声を掛けると、息を吹き返しました。
繰り返し呼吸停止していたのは、オヤジらしく、旅立ちを前に何度もリハーサルしていたんじゃないかな。その夜一晩中僕を一睡もさせず、翌朝、オヤジは静かに息を引き取りました。
大鵬幸喜 享年72 納谷芳子(妻)
白鵬関を叱り飛ばす夫が「チューして」と私に甘えて
お父さんが亡くなったのは'13年の1月19日。心室頻拍という診断でした。
ただ、いま振り返ると、'12年12月に入院をする前から、心のどこかで死期の近さを予感していたのかもしれません。
というのも、かつて部屋にいた若い衆のことを思い出すようになったんです。「いまあの子は何してるんだろう」とか、「病気をしたらしいな。大変だろうな」なんて言葉をふと口にするのを何度か聞きました。
ほとんど使うことのなかった携帯電話で、旧友に連絡をとったりもしていましたね。用事は特にないんですよ。「おう、元気か」と声をかけて、思い出話を少しするだけでした。
ただ、一番の変化は、家族に対する接し方。心根は元から優しい人でしたが、昔は「コノヤロー」、「バカヤロー」と、怒鳴ってばかりだった。そんな人が、急に柔らかくなったんです。
思い出すと切なくなるのは、亡くなる何日か前のこと。お父さんが、「芳子、芳子」と私を呼んだ。「なに?」と聞くと、「好きだよー」という言葉に続けて、「お母さん、おまえがいたから、俺はここまで頑張ってこれた。いろいろ大変な思いをさせたな。ありがとな」と言ってくれた。冗談っぽく「おい、チューぐらいしてくれや」とも。でも恥ずかしいのと、まさかその後すぐに亡くなるとは思いもよらなかったので、私は「何言ってんのよ」と、はぐらかした。あのとき抱きついて、チュッとしてあげればよかったって……。
もともと寂しがり屋でしたが、亡くなる数ヵ月前からは何をするにも私が一緒でした。家政婦さんがいようと看護師さんがいようと、私を呼ぶ。ちょっと用事で外に出たとたん、「いいからすぐ帰ってこい」と電話がかかってくるんです。多いときは何十回も着信があり、私もくたくたになりました。それだけ必要とされたのは、妻として喜びでもありましたが。
亡くなる日も、病室から真っ先に私に連絡がきました。朝の8時くらいに、「よーしこー」とすごく調子が良さそうだった。「どうしたの?元気だね」と返事をすると「早く来てくれ」と。それが最後の言葉でした。電話を切った30分後くらいに、病院から危篤だと連絡がありました。
病室に駆けつけ、先生が手を尽くしてくれている間、「お父さん、お父さん。いつまでも寝てないで、お話しよう」と、ずっと声をかけました。意識はもうなかった。でも、お父さんの目の端から涙が流れたんです。声は届いていたんだと思います。
ただね、一つ伝えておきたいのは、お父さんが弱さを見せたのは、私の前だけということ。世間に対しては最後まで大横綱・大鵬でした。
正月前に仮退院した後、再び病院に戻る日のことです。白鵬関が「ほんの少しでもいいから、どうしてもお会いしたい」ということで、挨拶にいらっしゃった。
具合が悪く、あまり話もできない状態だから、お父さんは不安になっていました。私も「無理しなくていいよ」と言っていた。
でもね、いざ白鵬関の前に立つと、顔つきが一瞬で変わった。
「おう、俺はこれからな、病院行くけど、頑張るからな。お前はただ頑張るだけじゃだめだぞ。相撲も日常生活も、何から何まで、ちゃんと横綱らしくしないと、真の横綱ではないからな」
と熱く語ったんです。私は胸が一杯になった。本人はもう精一杯なんです。しんどくてしんどくてしょうがないんです。その証拠に、白鵬関と別れると「芳子、早く。もう病院行くぞ」と疲れきっていた。
誰よりも強くあろうとしたお父さん。そんな人だからこそ、私にだけ見せてくれた「弱さ」が忘れられないんです。
三船敏郎 享年77 三船史郎(長男)
「今日は天気がいいな」無口なオヤジがつぶやいた
'97年に全機能不全で他界したオヤジは晩年、認知症を患いました。
オヤジはそれまで約20年間、母で女優の吉峰幸子と別居し、違う女性と暮らしていたんです。ところが、認知症の症状が現れ始めた'92年、僕たちの元に戻ってきた。
一緒に暮らし始めたオヤジは、孫と楽しく遊ぶ、ごく普通のお爺ちゃんでした。
孫と過ごす以外の時間は、一人でビデオ鑑賞。約150本近く出演した自分の昔の映画を、黙って懐かしそうに鑑賞しているんです。それでいて、昔話をすることはありませんでした。若いころから口数は多くありませんでしたが、晩年は極端に無口になっていました。
今思うと、認知症を含めたオヤジの体調悪化は、'95年に母がすい臓がんで亡くなった直後から急に進んだようでした。
母の死がオヤジの精神面にどのような影響をあたえたのか、今となっては知りえません。しかし、時期がちょうど一致するのは、何か意味があったのかも……とも思えるのです。
認知症が悪化したオヤジは、担当医のすすめで、高齢者医療の専門病院に入院しました。
入院後、しばらく元気に過ごしていたオヤジでしたが、亡くなる約半年前から、床に臥せりがちになり、食事も流動食しか受け付けなくなりました。
流動食に切り替わる少し前のことです。窓の外を眺めていたオヤジが、突然「今日は天気がいいな……」と、一言つぶやきました。僕は、「そうだね」と返した。
それが、ほとんど話さなくなっていたオヤジと交わした、最後の会話でした。
これを境に、体調は急激に悪化。生きる気力も失っていったように思えました。
そして、死の約1ヵ月前になると、あらゆる内臓の機能が極度に低下し、流動食の摂取も難しくなった。最後は、点滴による栄養補給に切り替わりました。医師から「そろそろ危ない」と告げられたのは、この頃です。
そこで、若手時代からオヤジを我が子のようにかわいがってくれた、俳優の故・志村喬夫人の政子さんに連絡をとりました。
親族以外で容体を伝えたのは、身内同然の彼女だけです。「世界のミフネ」と呼ばれていただけに、認知症が発覚したときも大騒ぎになっていましたからね。オヤジの周囲を騒がせたくない一心でした。
政子さんが駆けつけたのは、亡くなる1週間前のことです。すでに、オヤジは昏睡状態に陥っていました。
政子さんはオヤジの頬をぺたぺたと叩き、耳元でこう声をかけました。
「ほら、三船ちゃん、しっかりするのよ!」
すると、驚いたことに、オヤジの目から一筋の涙が流れたのです。
1ヵ月前からコミュニケーションが一切取れない状態が続いていたため、にわかには信じられませんでした。あまりのことに、医師にも言い出せなかったほどです。
オヤジは志村喬さんと数々の映画で共演させていただき、仕事を離れても志村家とは家族ぐるみの付き合いでした。幼かった僕も、二人を「じぃじ」「ばぁば」と呼んでいたほどです。
世界を股にかけて活躍したオヤジですが、賞賛も批判も一身に背負う俳優という仕事は孤独でもあり、志村さん夫妻は心の拠り所になっていたのでしょう。
そんな政子さんが、死の淵にいる自分に声をかけてくれた。僕には医学的なことは分かりませんが、あのときのオヤジには政子さんの言葉が、たしかに聞こえたのだと思います。きっと、走馬灯のようにさまざまな思い出が胸を去来し、想いが涙となって溢れたのでしょう。
最期は、家族に見守られる中、静かにスーッと息を引き取りました。徐々に意識が消えていくように、穏やかな表情をしていました。
大島渚 享年80 小山明子(妻)
最後のお願いは「お酒が飲みたい」でした
'12年11月、大島は肺炎で救命救急センターの個室に入院しました。この時、すでに年を越せるか分からない状態でしたので、京都に住んでいる大島のいとこの俊彦さんや、入院すると大阪からいつも来て下さる古くからの知人にも連絡しました。もうほとんど声の出ない状態だったんですけど、お二人の呼びかけに、ちゃんと「はい」って返事をしていました。
亡くなる数日前には少し落ち着いていたので、1時間ほど「京都でこんなことがあったわよね」なんて昔話をしました。実際は私が一方的にしゃべっただけですが(笑)。そのとき、
「神様に最後のお願いをするとしたら何がしたい?おうちに帰りたいか、おいしいものを食べたいか、お酒を飲みたいか。一つだけ選ぶとしたらどうする?」
と聞きました。「家に帰りたい」と言うかと思ったら、大島は、
「(お酒が)飲みたい」
って。これが最後の会話です。もしかしたら自分がこれからどうなるのか分かっていたのかもしれません。お酒好きでしたし、大島らしい選択だと思いました。
先生に「さすがにお酒はダメですよね」って訊いたら、「唇につける程度なら大丈夫ですよ」とおっしゃってくれて。だから毎日、唇に少しだけ指でお酒をつけてあげたの。香りだけでも、最後の望みをかなえてあげられたのかな、と思います。
家族が見守る中、大島が静かに息を引き取ったのは'13年の1月15日。翌日から私は18年ぶりの舞台に出演することになっていて、最後の舞台稽古が19時から始まる。大島と一緒の車で家に戻り、布団に寝かせて、最後を迎えられる準備をして、劇場に向かいました。大島は私のために日を選んでくれたのかなと思っています。
あとで看護師さんから聞いたのですが、その日の朝、大島は「ママ~、ママ~」と叫んでいたそうです。それが最後に発した言葉。昔からあの人は何かあるたびに私を呼んでいましたからね。虫の知らせがあり、お別れのために私を呼び寄せようとしたのでしょうか。
大島が逝ってから早いもので1年近く経ちますが、夢に出てきたのは一度だけです。熱海の海沿いの喫茶店で二人でお茶をしている夢。それは若い頃、映画の撮影の天気待ちで行った喫茶店の情景でした。当時、大島は助監督、私は新人女優。たった一度、夢で会えたのが、なんでこの場面なのか、理由はよく分からない。人間の記憶って不思議です。
人生をやり直せるなら、もう一度大島と結婚したいですね。ただ、最後の17年とは違う生活をしてみたい。ずっとリハビリの日々でしたからね。
大島が亡くなって3ヵ月ほど経った頃ですが、自由が丘のレストランで食事をしていたとき、ふと老夫婦の姿が目に入りました。
ご主人はビールを飲み、二人で楽しそうに食事をしていた。まるであの時の熱海の喫茶店の私たち二人みたい。その姿を見て、「私が求めていた幸せは、これだったんだなぁ」と気づきました。そう思うと涙が出てきた。
かなわぬ夢ですが、なんてことのない日常をあの人と過ごしてみたかった。大島が亡くなって以来、涙を流したのはこの一度だけです。
■有名人遺族が今だから明かす 思えばあれが「死の前兆」だった(後編)天野祐吉、井上ひさし、梨元勝、谷啓
感動秘話 なぜ、あのとき気付かなかったのか
天野祐吉 享年80 天野伊佐子(妻)
忘れていた記憶が次々に甦ると漏らした
主人が緊急入院する前のことです。ベッドに横になった主人が天井をジッと見つめながら、「字が見えるんだ」と言うんです。「はっきりとは読めないけど、俺に『解読しろ』と言っているのかもしれない」と。なぜかその時、私は主人が連れて行かれちゃうと感じました。
まさかそれを読んでしまったからかどうかは分かりませんが、その2日後に突然、高熱が出て、入院。それからわずか5日後('13年10月20日)に、夫・天野祐吉は、あっと言う間に旅立ってしまいました。
亡くなる日の朝、先生が集中治療室に入る許可を出してくれました。わずかでしたが、二人きりの時間を過ごせた。その後、彼は穏やかな顔のまま苦しむこともなく、私の腕のなかで息を引き取りました。
入院したとはいえ、本人に病気の自覚は一切ありませんでした。むしろ「小学3年生の盲腸以来だ」なんて、入院を楽しんでいるくらい。3・11以降、仕事への意欲は増し、体も健康でしたからね。
でも、いま振り返れば、亡くなる半年ほど前から、「前兆」はあったような気がします。戦時中に無理やり歌わされた軍歌など、忘れていた記憶が甦るという不思議な現象があったんです。本人は「(記憶の)引き出しが開いたのかな」と話していましたが、自分の人生と向き合っていたのかもしれません。
主人は酸素吸入が必要となってから、筆談ノートを書き始めました。「病院日句」と名付けられた一冊の大学ノートには、「絶対に(君を)置いていかない」「ご飯を食べられている?」などと私を気遣う言葉が綴られていました。ページが進むごとに薄くなっていく文字。最後の言葉は「(家に)かえろかえろ」。たぶん、もう帰れないと分かっていながら……。
こんなこともありました。主人は、生前からの本人の希望でお葬式もしていないし、お墓もつくりませんでした。荼毘に付した後、せめていつも一緒にいようと思い、遺骨をペンダントに入れた、その時です。「カバン」というあの人の声が聞こえたんです。
これは何かのメッセージに違いない、と家中を必死に探しまわると、クローゼットの奥のカバンから2年前に書かれた遺言書が見つかりました。生前、「俺は悪運が強いから98歳まで生きると思う」と豪語していましたが、もしものときのために準備をちゃんとしていたんですね。遺言書は「ありがとう。またね」という感謝の言葉で締められていました。
主人の仕事場でもあった部屋は今もそのままにしています。やっぱり片付けられないんですね。愛用していたメガネも、テレビモニターの見えるいつもの場所に置いたままです。
井上ひさし 享年75 井上麻矢(三女)
父の背中に「諦め」を感じ、覚悟を決めました
そう長くはないんじゃないかな—。そう感じた瞬間は、いまでもはっきりと覚えています。それは、亡くなる2ヵ月ほど前、後ろ姿を見たときです。
私は小さいときから、父の背中ばかり見てきました。机に向かう背中です。原稿を書く父は、それこそ精気がみなぎっていました。それに比べ、病室で見た姿には諦めのようなものを感じたんです。
その頃、父は食事をあまり摂れなくなっていた。「人間は食べることと出すことが基本」、そう考えていた父ですから、ショックだったんだと思います。
肺がんで亡くなるまでの闘病生活は約5ヵ月。最後の日は'10年4月9日でした。しかし父自身は、がんを宣告される前から、自らの死期を本能的に感じていたのかもしれません。
父は最後の1年間、私に一生分といっていいほどたくさんの話をしました。社会の構造や演劇に対する心構え、父の立ち上げた劇団「こまつ座」が進むべき道、観ておくべき芝居、父は毎晩電話で熱く語った。短くて3時間、長いときは夜10時から翌朝の7〜8時まで。父に言われて観劇した芝居の劇評を述べるという宿題も、毎日のように出されました。父娘のというより、まさに私に後を託すための会話でしたね。
闘病生活の間も、そんな「授業」は毎日必ずありました。一度、話している最中に父が激しく咳き込んだことがあった。心配になって電話を切り上げようとしたら、「僕には時間がないんです。だから君も心して聞いてくれないと困る」と言われました。そのとき、「ああ、この人は命を削って、これからのことを私に託そうとしているんだ」と胸を打たれました。
前兆は、父の作品にも表れていたのかもしれません。最後の2作、『ムサシ』と『組曲虐殺』。前者は、若い人たちにエールを送りたいという思いで書き上げたもので、自分たちの存在そのものが奇跡だという、人生の賛歌です。
『組曲虐殺』は作家・小林多喜二の評伝劇。これは、人間は良い人生を送っていれば、死をも恐れない強さを身につけることができるという作品。2作とも、父の作品の中ではかなり異質で、メッセージ性が非常に強い。
父は無意識に残された時間の短さを知っていた。いま振り返ると、そんな気がしてならないんです。
梨元勝 享年65 梨元麻里奈(長女)
仕事人間だった父が、仕事を断った翌日に
がん宣告は、母と私、そして父の3人で受けました。告げられてから父は、「大丈夫」と繰り返していた。まさか2ヵ月しか生きられないなんて、思ってもいなかったんでしょうね。
肺がんのステージⅣだったんですが、父は「ステージ」の意味がよくわかっていなかったんです。「ステージはいくつまであるの?」なんて聞いてきたくらいですから。でも不安はあったんでしょう、「がんについての資料を持ってきて」と私に言いました。なかには読ませたくない内容のものもあったんですが、父の頼みを拒むわけにもいかず、病室に大量の資料を持っていった。ただ、読むのが怖かったのか、死ぬわけがないと思っていたのか、結局、父は最後まで目を通しませんでした。
父の気力の衰えを感じたのは、ずっと続けていた週刊誌の連載を「中止したい」と言ったときです。父は原稿の分量に合わせて、記事の内容を電話口でまとめて話すことができました。だから最悪の場合、書く力はなくなっても、喋ることさえできれば何とかなるということで、最後まで残していた連載です。
その最後の仕事を「辞める」と、仕事人間そのものだった父が口にしたとき、長くないのかもと思いましたね。そしてそう語った翌朝、本当に父は亡くなってしまった。
ただ、いま振り返れば、がんが発覚する1〜2年前から、父には「虫の知らせ」があったのかもしれません。母と一緒にウォーキングを始めたんです。これはそれまで仕事だけだった父からは、考えられない行動でした。結婚生活35年余りのうち、母いわく、家にいるのは「半分くらい」だったそう。おそらくウォーキングには、いままで作れなかった夫婦の時間を取り戻そうという思いがあったんでしょう。
私はいま、父と同じリポーターの仕事をしています。きっかけは、闘病中に父の仕事を少しだけ手伝ったことです。
それから3年、不屈のリポーターとして、スクープを追い続けた父には、いまだ遠く及びません。
憎めない笑顔と「恐縮です!」の決めセリフで、数多くの芸能人からスクープコメントを取った父。もっとアドバイスを聞いておけばよかった、心からそう思っています。
谷啓 享年78 渡部泰裕(長男)
認知症を患っていたのに、森繁さんの死を言い当てた
オヤジが階段から足を踏み外して滑り落ちたのは2010年9月のことです。
僕はいつものように、昼前、玄関で「オヤジ、仕事に行ってくるよ」と声をかけて出かけました。認知症が進行していたオヤジも、僕が仕事で出ていくことだけはわかったようで、僕の目をジーッと見つめてきた。言葉じゃないけれど、これが最後のコミュニケーションになりました。
仕事を終えて帰宅したら、オフクロが廊下に倒れて意識のないオヤジに寄り添っていた。救急車を呼びましたが、明け方、病院で息を引き取りました。
タバコを買いに行っても家に戻れなかったり、近所を徘徊するなど、認知症は進んでいたのですが、僕たち家族のことだけは決して忘れず、防音設備のある居間で、大好きなホラー映画をよく観ていました。
そんなオヤジが、僕らを驚かせたことがあります。亡くなる前年の11月のことです。オヤジを1階の寝室に寝かせ、僕は2階の自室にいたのですが、オヤジがパジャマ姿で、ぼーっとしながら廊下をウロウロしているんです。
徘徊が始まったのかなと思い、「もう寝ようね」とオヤジを促したのですが、「ジイサンが挨拶に来ているんだ」と言って、頑として言うことを聞いてくれない。相手にせずに、とにかく寝かしつけたのですが、その晩の11時頃、テロップで森繁久彌さん死去の速報が流れたんです。
森繁さんは舞台『屋根の上のヴァイオリン弾き』で、ずっとオヤジと一緒だったから、まずびっくり。それから、オヤジが言っていた「挨拶に来ているジイサン」とは森繁さんのことだったんじゃないかと思って、またびっくりです。
昔から、オヤジはその手のものが見える人で、自分が見た幽霊の話などもしていたんです。晩年は認知症を患っていましたし、ボケていたのか、ホラー映画の記憶とごっちゃになっていたのか、あるいは夢と混同していたのか、今となってはわかりません。
でも僕は、オヤジはあの日、森繁さんと会ったんだと思うんですよ。森繁さんが会いに来てくれたら、オヤジも嬉しいに決まっている。親しい人に会えるなら、死後の世界もまんざら悪くない。そう思ったほうが夢があるじゃないですか。
[いずれも現代ビジネス]
Posted by nob : 2014年01月25日 17:37
他者のためじゃない、誰もが自身のために生きていることを知るだけでいい、、、他者を気にしなければ、そもそも自信を失うこともない。。。
■「自信」をとりもどすための4つのコツ
社会に出てから10年以上の月日が経ち、だんだん大きな仕事を任されるようになる一方で、プレッシャーに悩まされたり、自信を失うことも多くなってきます。
そんなとき、少しでも自分の才能を認め、自信を回復し、自分の中から最大限の能力を引き出せるようなコツを日常的に身につけられたらいいなと考えていたところ、「Give Yourself the Respect You Deserve(あなたにふさわしいリスペクトをあなた自身にあたえましょう)」というアメリカの記事を見つけました。
そこに書かれていた、自分を認めてあげるための4つのコツをご紹介したいと思います。
自分を認めてあげるための4つのコツ
(1)「しなければならないこと」を減らすこと
全てをこなそうとすることで、本当に大事な目標を達成するための時間がなくなる場合もあります。実際は、「するか」「しないか」を自分で選択することができるのに、しなければならない義務のように感じ、それに時間を注いでしまっていることはありませんか?
例えば、気乗りしない誘いを受けた場合、自分がその場でどう感じるのかについて考え、相手との会話にげんなりする自分の姿が予想できるのなら、思い切って断ってよいのです。余計なものは省いて、自分が本当に楽しめることだけにエネルギーを注ぐように心がけましょう。
(2)友達に寄りかかること
Goal Groups Internationalの設立者で共同作業コンサルタントのジェニファー・ストーン氏によれば、「グループで目標を達成する場合、一人で行うよりも、はるかに作業がはかどる傾向にあります。その結果、いかに自分たちが才能のある存在であるかを認めやすくなります」と。
どんな時でも、支えになってくれる周りの人々を思い出し、その人たちに自分の日々の生活で起こっていることをシェアすることを心がけてみましょう。「自分の成し遂げたことや、葛藤していることについて、直接会って友達に話すことで、私たちのストレスは減少し、私たちの記憶は良いものとなって全体的な気分が上昇します。」とも。
もし、なかなか直接仲間と会うことができない場合は、大学時代の仲間に気楽なメールを送るだけでもOKです。
(3)リストを作る(そしてこまめにチェックする)
ロサンゼルス在住のライフコーチのキャロリーナ・カーロ氏が提案するのは、自分自身の好きなところについて、書き出してリストアップすること。書き出したリストを自分の自信が揺らぎそうな時に目につきそうな場所に置いておきます。例えば、携帯電話のメモ機能のところに保存しておくなどがいいかもしれません。
そのリストは自分の身体的な特徴から、成し遂げたこと、今までに言われた褒め言葉などまでにいたります。キャロリーナ氏によると、「女性は、他人の中に美しさを見つけるのが得意な一方、自分たちの中からそれを探すのを忘れがちです」だそう。自分のポジティブな部分について気づいて認めることで、徐々に自動的に自分を褒めることが身についていくそう。
(4)自分の中にもう一人の自分を持つ
アメリカの人気歌姫ビヨンセは、自信に満ちて生意気な「Sasha Fierce」というもう一人の分身を自分の中に持っていると言っています。そして、あなたもそんな分身を持つべきです、と精神科医で「A Happy You: Your Ultimate Prescription for Happiness(幸せなあなた:幸せのための究極の処方箋)」の著者であるエリザベス・ランバルド博士は言います。
ランバルト博士はあなたの自信に満ちた分身に名前をつけ、あなたが不安な状況に陥った時に、彼女ならどうするかを尋ねてみること、そしてそれを実行することをすすめています。「このトリックは、いったんあなたを自分自身から離れさせ、くよくよ考えるのは止めて行動起こさせるように力を与え」てくれるそう。
ご紹介した4つのコツは、具体的な方法なので実践しやすそう!
始めは自分を褒めたり認めたりするのは難しいかもしれませんが、繰り返すうちに自然に自分をリスペクトし、自分自身を大事にしてあげられるようになるといいと思います。
[Give Yourself the Respect You Deserve]
(佐々木祐里)
[MYLOHAS]
Posted by nob : 2014年01月24日 20:34
私も身体の冷えの自覚がありませんでした。。。
■腰痛、肩こり、頭痛、ひざ痛、ストレス、慢性的な疲れ……
あなたを苦しめているつらい不調の原因は「ココ」にあった!
「冷え」と聞くと、「私は冷え症じゃないから大丈夫」という方もいるでしょう。とくに男性は、「冷えは女性特有のもの」という意識からか、ご自身の体が冷えていることに気づいていない人も少なくありません。しかし「冷えは万病の元」といわれるほど、体が冷えるということは、さまざまな体の不調を招く原因になります。意外に知られていない「冷え」と「健康」の関係とはいったい?
体の不調の9割は
「冷え」を消せば改善できる!?
「冷え」。
そう聞くと、ほとんどの方が「手先、足先の冷え」をご想像するのではないでしょうか。だから冒頭でも述べたように、男性の方のほとんどが「自分は冷え症じゃない」と思われるのです(男性は女性に比べて筋肉量が多いので一般的な足先や手先の冷えを感じにくい)。
ではそんな方に質問です。
腰痛を感じている皆さん、ご自身の腰を触ってみてください。冷えていませんか?
肩こりに悩んでいる皆さん、肩に手を置いてみると冷えているな、と感じませんか?
暑がりだと思っているメタボ気味の皆さん、お腹にそっと手を添えてみると、なんとなく体の中から冷えが伝わってきませんか?
そう、実は、「体の不調がある=体が冷えている」のです。
触れてみても、あまり冷たくないから大丈夫という人でも安心できません。実は肌の表面に出てきていなくても、内臓が冷えているということもあります。なかなか疲れが取れない人は、腎臓、肝臓、副腎が、便秘や下痢ぎみの人は胃腸が冷えているのです。
どうして「冷え」が私たちの体に影響を与えてしまうのでしょうか?
疲れが取れない、風邪が治らない。
それはあなたの体温が低いからかも
突然ですが、あなたの日頃の体温は何度ですか?
こう聞かれて「自分の平均体温は~」とすぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。
「子どもの頃は36.5度だったけれど、今はどれくらいかな?」と考えてしまう人がほとんどでしょう。大人になると、風邪でもないかぎり体温は測らないという人が大半だと思います。
「体重だったら測りますけど」と答えてくれる人もいます。ダイエットをしている人だったら、気になって体重は毎日測る。なのに体温は測らない。
皆さんは体温を測るなんてあまり意味がないと思っているかもしれません。しかし、体温はご自分の体調を知るうえでとても大切な数値です。
人間の体温は36.5度が適切だといわれています。この体温を維持している状態が、最も免疫力が高まり、健康でいられるのです。だからこそ、風邪をひいたときや調子が悪いときだけ体温を測るのではなく、体調がいい、悪いに関係なく、自分の体調のバロメーターとして定期的に測っておくことが大切なのです。
実は近年、平均体温がとても低い、という方が増えています。36.5~37度の適切な体温を大きく下回る、36度台ギリギリ、下手をすると35度台という人もいるようです。
体温が35度台。
これは体にとってよくありません。自律神経や排泄機能のバランスが崩れてしまいます。こんなに低いと、便秘や肌あれ、肩こりはもちろん、消化器系の不調、月経不順、むくみ、疲れやすい、風邪が治りにくいといった症状が現れます。
このまま何の対策もしないと、低体温の状態が続きます。すると、ますます免疫力は低下、それに伴い、体調もますます悪くなってしまうのです。
がんなどの病気も体の冷えが積み重なって発症するといわれています。それほどに低体温は懸念すべき状態なのです。
体の調子が悪いな、そう思ったらまず
「冷え」を疑ってみましょう
赤ちゃんの体温は37度ぐらいが平均です。大人なら微熱かな?と思う体温です。新生児の時期はとくに高く、その後は少しずつ下がっていきます。10歳ぐらいでいったん落ち着いて、36.5度の平均を維持します。
やがて高齢になると体温は徐々に下がっていきます。若い頃と比べると、平均で0.2度ぐらい下がるそうです。なぜそうなるのかという直接的な原因は明らかではありませんが、年をとると運動機能や体の生理機能が徐々に衰えていくことと関係があると言われています。
高齢になって体温が下がるのは自然の流れなのです。
しかし問題は、若い人の低体温です。先述しましたが、まだ若いのに体温が35度台しかないという人が増えています。子どもでも36度に満たない「低体温児」が最近では珍しくありません。本来ならエネルギーに満ちあふれているはずなのに。
なぜ体温が低い人が増えているのでしょうか?
その原因は、現代人のライフスタイルにあります。
運動不足や偏食、季節を問わず体を冷やすものを食べている、多忙によるストレス、肌を露出するファッション、冷暖房が効きすぎている室内環境、さらには薬や添加物の摂りすぎなどの要因が体温を下げているのです。
つまり私たちは普通に暮らしている中でも、知らず知らず冷えを招く要因に囲まれて生活しているということになります。
だからこそ、意識して「冷え」を消すことで、あらゆる不調の改善を図ることができるのです。
次回からは「不調」と「体の冷え」についてもう少し詳しくご紹介していきましょう。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年01月20日 08:15
私も、数日前からレモン水(レモン入り生フルーツジュース)を始めました。。。
■身体にたまった毒を出すには、朝1番の「レモン水」が効果的
お正月や新年会シーズンも終わりを迎え、「気付いたら、冬太りから脱出できずにいて困っている」という人も多そうです。でもこの寒さの中、無理に食事制限をするダイエットでは、すぐに風邪をひいてしまうという悪循環にもなりかねません。そこでおすすめなのが、「レモン」を使ったデトックス。
朝の「レモン水」で、体の毒素を追い出す
フランスで話題になった書籍『CITRON MALIN』によると、食べ過ぎや飲み過ぎ、ストレスなどにより体内に蓄積された毒素を追い出すには、まず消化器系のデトックスから始める必要があるといいます。そのためには、解毒や利尿作用を促すことで、脂肪細胞内にたまった毒素や水分を排除することが重要なポイント。そのために、朝1番に「レモン水」を飲むのが良いのだそう。
1.朝食の30分前に、コップ1杯のぬるま湯にレモンを絞って飲む
2.以後、1日7〜9杯のレモン水を飲む(水約1リットルに相当)
こうすることで、血液中の老廃物や余分な水分を尿で排出する機能をもつ、腎臓のはたらきを活性化させることができるといいます。
もちろん、毎回ぬるま湯にレモンを絞っていれることは難しいので、朝1リットルのペットボトルにレモンを絞り、1日かけて飲み終えるようにするのもおすすめです。また、レモンにはビタミンCがたっぷり含まれているので、寒い冬の時期にはとっておいて損はありません。風邪対策も同時にできます。
寒い冬は、レモンでデトックス風呂
寒いこの時期はゆっくりとお風呂に入るという楽しみがありますが、ここでもレモンを使うことで、デトックス風呂が完成します。
1.39〜40度くらいのお湯に、レモン2〜3個をしぼる。この時、レモンの皮も一緒に入れる
2.お湯に20分ほどゆったりとつかることで、レモンのエキスを肌表面からとり入れる
レモンは、美容、健康、掃除に万能と言われています。フランスで人気のある『CITRON MALIN』では、レモンの効用や使い方が1,001種類にものぼって紹介されています。ナチュラルで気軽にビタミンを補給しながら行えるレモンのデトックスなら、安心して試すことができそうです。
[CITRON MALIN]
water with lemon via Shtterstock
(文:下野真緒/南仏在住ジャーナリスト・エディター)
[cafeglobe]
Posted by nob : 2014年01月15日 16:07
なるほど、、、早速試してみたいと思います。。。
■○○で効果倍増!身体ぽかぽかになる正しい半身浴のやり方
シャワーでなくきちんと浴槽につかることが、冷え性対策やストレス発散に有効なのは、もはや常識ですよね。でもどうせ入浴するなら、効果倍増したい!
そんな欲張りなあなたに『AneCan』2月号「24時間“温活”ライフ!」より、効果アップの半身浴のやり方をお届けします。
まず準備するのは「塩」。お風呂に塩を入れることで、保湿&発汗効果がアップするんです。バスソルトなど、塩入りの入浴剤もたくさん出ているので、好きな香りのものを選んでみて。ちなみに私は安売りしてたときはクナイプのバスソルト、あるいはスーパーで売ってる天然塩をひとにぎり適当にぶっこんでます。
~正しいお風呂の入り方(半身浴)~
1:食後2時間以上あけてから入浴する
2:塩を入れたお風呂の温度は38~40℃とやや低めに設定
3:入浴前に常温の水をコップ1杯飲む
4:ぬるめのシャワーを足の先から、ひざ、腰、お腹、上半身の順にかけてから湯船におへそまでつかる
5:5分たったら浴槽からいったん出て、手とひざから下にぬるま湯と熱いお湯(42℃)を交互にかけ、また浴槽にin
6:5と6を5セット繰り返す
7:1時間以上の入浴は危険! 入浴後はコップ1杯の水を飲む
半身浴って、おへその丈までぬるめのお風呂に長くつかるんだと思っていましたが、5セットとはなかなか慌ただしい!身体の芯から温めるには表面だけを温めすぎないことが大切なので、ついついのんびりしすぎるところを、ぐっとこらえて挑戦してみたいと思います。(安念美和子)
[Woman Insight]
Posted by nob : 2014年01月12日 16:14
確かに、、、依存従属心から脱却して、好きなこと楽しいことを追い求める自らに最大限リスクすること。。。
■心と体のアンチエイジング
脳を老けさせないOK習慣
脳にとっての“成人式”は30歳前後
物忘れが多くなった!と感じたことはありませんか? でも大丈夫。
今からでも十分脳は成長できるそう。そこで、専門家に脳をいつまでも若々しく保つ方法を教えてもらいました
脳の栄養は経験や体験 刺激を与えて活性化させて
「20代、30代の脳はまだまだ成長期。脳にとっての“成人式”は、30歳前後です」と話すのは、脳科学の専門家で、「脳の学校」代表取締役の加藤俊徳さん。実は、WOMAN世代は、老化を心配するよりも、脳を発達させることができる伸び盛りの時期だと認識することが大切なのだという。
“カリキュラムに沿って過ごす”学校生活から卒業し、社会人として“自分で選択する”生き方が始まる20代は、「脳が柔軟に物事を吸収しやすいとき。新しいことに挑戦して、体験や経験を積むことで、記憶や知識を蓄える脳領域が成長します」。続く30代では、20代の経験のなかから“好き”“楽しい”と感じたことを続けたり、経験を深めたりすることで、物事を理解する脳領域が活性化していくという。
「脳の神経細胞の数は、生まれたときが一番多く、年齢とともに減少しますが、使われていない未熟な脳細胞は、新しい刺激によって発達します。そして、ネットワークが強化されることにより、脳はさらに成長できるのです」。
脳の老化予防のために、やっておくべきこと、やめたほうがいいことは今回と次回で示す通り。
脳の成長力は年を重ねるほど個人差が大きくなるそう。ぜひ、今日から脳トレ習慣を身に付けて、脳の若さを維持しよう。
やっておくべきこと
脳は好奇心や前向きな考え方を持つことで、働きが活発になる。また、苦手なことに挑戦すると、普段使わない脳領域が刺激を受けて活性化する。好きなこと+少しの負荷で脳を元気にしよう!
1.楽しいこと・ワクワクすることをする
「多くのことに好奇心を抱き、楽しいことや未体験のことにどんどん挑戦して。それが脳の一番の栄養になります」。楽しい刺激で脳の成長が促進される
2.1日1回、心から「ありがとう!」を言う
感謝は相手の気持ちを感じられるからこそ出てくる言葉。脳の中で“感性”を磨く部位を使うことにつながる。普段から、小さなことにも感謝する気持ちを忘れないにしよう
3.1日1回、自分を声に出して褒める
1日の最後に、今日できたことを声に出し、自分を褒める。自分を卑下するのではなく、褒めることを習慣化すると、脳はだんだんとストレスに強くなっていく
4.利き手と反対の手で雑巾がけをする
体を動かしながら、効率のいい拭き方を考えるなど、脳の様々な部分を使う雑巾がけ。これを利き手でない手で行おう。「普段やり慣れないことは、脳を活性化します」
5.すれ違う車のナンバーを足し算する
運転やスポーツは、対向車や相手の動きを「よく見る」必要があるので、視覚系の脳領域を強化する。バスに乗ったときにも、対向車のナンバーを足し算して「見る」目を養おう
6.1日1個、新しい単語を覚える
新しい情報への関心や記憶力が衰えるのを防ぐため、意図的に脳を動かす習慣を持とう。興味がある記事で見た、意味不明な言葉を調べて覚えると、記憶力も好奇心も刺激でき◎
7.草木や野菜を育てる
植物などの生き物は、なかなか思い通りに育たない。自然環境の変化に合わせて、臨機応変に対処することで、分析力や判断力を養う脳の領域が使われる
8.入浴後に全身ストレッチをする
「体がこると、脳の運動領域の酸素消費が増え、ほかの部分への酸素供給が不足し、思考力が鈍ることがあります」。入浴後のストレッチでこりをほぐして、効率的に働く脳を保とう
9.良質な睡眠を取る
脳には休息も大事。24時前には照明を消し、睡眠時間をしっかり確保して。ぐっすり眠っている間に脳の情報が整頓されるので、翌日の思考力もアップする
[日経ウーマンオンライン]
■心と体のアンチエイジング
脳を老けさせるNG習慣
マイナス思考やマンネリ、過度なストレスは脳の大敵!
やめたほうがいいこと
「楽しい」「新しい」と感じることが脳の栄養だとしたら、脳の成長の大敵は、マイナス思考やマンネリ、そして過度なストレス。これらをできるだけなくして過ごすようにして
1.イライラする
「いら立ちの原因はいろいろありますが、その一つが脳の同じ部位を酷使すること。脳内の血流が悪くなり、疲れから怒りっぽくなる場合が」。そんなときは、深呼吸をして気分転換を
2.21時以降に食事を取る
21時以降は、脳や体がお休みモードに入っていく時間。食べることによっても脳は働くので、この時間の食事は、休むはずの脳に負担を強いることになってしまう
3.人の悪口を言う
人の悪口など、否定的な言葉を使ったとき、一番に聞こえるのは、自分の耳。「ネガティブワードは、脳の働きを鈍化させます。脳をいつまでも成長させたいなら、ネガティブな言動はできるだけ避けましょう」
4.会社と家との往復のみ
毎日決まりきったマンネリな生活では、脳が“慣れ”てしまい働きが鈍化する。通勤ルートを変えたり、寄り道したりするなど、日常生活に変化を与えるだけでリフレッシュできる
5.太りすぎる!
「肥満などの生活習慣病は、脳細胞が傷つく、原因になります。食生活に留意し、コンスタントに運動をして、脳の成長を妨げないように気を付けましょう」
6.運動不足!
日中、体を動かさないと、夜もいい睡眠が取れず、脳も休まらない。また運動不足だと、運動をつかさどる脳領域が活性化しないので、意識して体を動かそう
7.10cm以上の高さのハイヒールを履く
足首を立てて履くハイヒールは、肩や腰にもこりや痛みを生む。痛みを感じるのは脳の思考系の領域。痛みが大きくなると、その分、判断力や思考力などが低下してしまう
8.焦る・慌てる・急ぐ
ゆっくり物事に向き合って考え、行動すると神経細胞の枝が伸び、各脳領域が連動して働くので、思慮の深さが育まれる。急ぎすぎていると感じたら、ペースダウンを
9.ケータイ・スマホを手放せない
毎日のスケジュールも、友人の電話番号も書いたり覚えたりせず、ケータイやスマホに頼り続けると、次第に脳を使わなくなり、老化が進む。アナログな習慣も取り入れて
10.人の目を気にしすぎる
自分が心地よいこと、楽しいことを積極的に行うことで、脳は成長していく。人の目を気にして行動を制限すると、脳は成長しにくくなるので「自分思考」を大切にしよう
[日経ウーマンオンライン]
いずれも
脳の学校代表取締役
加藤俊徳
加藤プラチナクリニック医師
Posted by nob : 2014年01月12日 15:54
結局はバランス良く、食べ過ぎ飲み過ぎに注意する、、、そんな当たり前の食生活をするということでしょう。。。
■野菜と鶏ささみを食べればOKと思ってない!?
男性が勘違いしがちな「ヘルシー」の基準
笠井奈津子 [栄養士、食事カウンセラー]
肉のつく場所が変わってきたり、階段が億劫になったり、お酒が残りやすくなったり…と体に起きる変化に、「年をとったせいだ」とひとり密かに気がめいったことはないだろうか?でも、実はそれが悪しき習慣の積み重ねによるもので、今ならまだ取り返しがつくステージにいるとしたらどうだろう。実際、そうしたケースも少なくない。2014年は「まだまだ自分はいける!!」という自信と共に歩める年になるよう、ヘルシーな習慣について改めて考えてみたい。
“ヘルシーな生活”をしていても
「結果」を見ない人が多すぎる
そもそも、ヘルシーとは一体なんだろうか。健康的な、という意味であるはずだから、食に関していえば、結局のところ、偏りなくバランスよく食べることが基本だろう。となると、野菜を食べていればヘルシーといえるだろうか。野菜を食べない人にとって、野菜を食べることはヘルシーな行為になる。でも、野菜しか食べない人がさらに意識をして野菜を食べるという行為は、また違う意味を持つように思う。
最近、エッジのきいた3人の経営者から三者三様の“独自の健康法(食)”についての話を聞く機会があった。ひとりは「冷えは免疫力を下げるから、生のものは絶対摂らない」と言い、ひとりは「ビタミンと酵素を効率的に摂るために加熱したものは絶対に摂らない」と言い、ひとりは「○○(某牛丼チェーン店)で1日2食食べる以外は間食も酒も摂らない」と教えてくれた。
何かの道を極めた人というのは、自分が決めたことを貫く姿勢がすごいな…と思いつつ、3人の食生活を足して3で割ったくらいのバランスが一番良いのかも、と思わないでもない。でも、3人ともに共通している「定期的(週に一度以上)に体重計にのっている」「食べ過ぎない」「飲みすぎない」は確実にヘルシーな習慣である。もちろん、それができたら苦労しないよ…という声もあるはず。
でも、上記の習慣に限らず、せっかく体のために何かしているのに、結果を見ない人は意外と多い。彼らが自らの健康法が正しいと言い切るには、「健康診断の結果が良い」というデータや「疲れにくい」「集中力が途切れない」などの実感が伴う結果があってのこと。
クライアントから「大量のサプリを飲んでいる」「朝は絶対に食べない」などと言われたとき、いろいろ思うことはあるが、まずは「それによって何か良くなったような実感はありますか?それをしないと明らかに感じが違いますか?」と確認するようにしている。そして、そう聞いたときの「え?いやー、わかんないな」という答えほど、もったいない…と思うことはない。
誰だって、本来は伸び率が低いところに多額の投資はしないだろう。せっかくの努力は、結果が出ることに注ぎ込んだ方が良い。それ以前に、せっかく投資しているのであれば、結果を見た方が良い。良い習慣をとりいれることと同じくらい、“実は結果が出ていなかった習慣”の断捨離を行うことは大事なのだ。中には「もう何年も毎日飲んでいるからわからない」という人も少なくない。そういうときには、1週間ほどお酒を絶ってみたときの体感で判断しても良いだろう。
食生活の善し悪しがチェックできる
健康診断で見るべき項目は?
ビジネスマンが健康診断の結果でチェックするのであれば、まず見てほしいのが血糖値に関係するHbA1c。空腹時血糖は直前や前日の食事内容などに左右されることがあるが、HbA1cは過去1~2ヵ月の血糖値の平均的推移を示すので、「前の晩遅くまで食べていたから」なんて言い訳が通用しない。つまり、日頃の食生活への成績表。正常値内にあっても、高めだったら今こそ気のつけ時だ。
というのも、痛風のような顕著な性差は見られなかったものが、ここ数年、女性よりも男性の糖尿病患者数が如実に増えてきた。その原因がどこにあるかといえば、やはり肥満。やせ願望が強い女性に対し、男性30代以上の肥満率は3割を越えているのだ。ぽっこり出たお腹が自分のスタンダードになってないだろうか。「かっこよかった自分」ではなく「かっこいい自分」がスタンダードになっても良いのではないだろうか。
自分が肥満傾向にあるかどうかをチェックするために、もうひとつみてほしいのは中性脂肪。中性脂肪が高いというと「脂肪」という言葉から「脂質の摂りすぎに気をつけよう」と思われがちだが、気をつけるべきは、天丼のごはんの部分であったり、ステーキセットについてくるマッシュポテトだったりする。つまり、原因は炭水化物の摂りすぎにある。
摂りすぎた糖質は使いきれずにグリコーゲンとして肝臓や筋肉に貯蔵される。だから中性脂肪を減らしたかったら、まずは糖質を減らすこと。こういう人が揚げ物を避けて、他のタンパク質と比較すると糖質を多く含む豆腐や納豆などを頻繁にとれば、改善には向かいにくい。いつもと同じメニューを食べていたとしても、注文時から「ごはん少なめで」ということができたら、その積み重ねは大きい。
鶏ささみ肉、ノンオイルドレッシングに
頼り切った食生活の落とし穴
また、運動習慣のある人に特に多い「鶏ささみ肉はヘルシーである」という説も注意。各お肉に含まれる栄養を見比べてみると、それぞれに良い部分がある。たとえば、牛肉はつい不足しがちな亜鉛や鉄が豊富だし、豚肉はビタミンB群が豊富で、疲労回復効果も高い。鶏ささみ肉のヘルシーさは、低カロリー、低脂質高タンパクのイメージが強く、筋力アップのために大量のタンパク質を摂るような場合には他の選択肢がなかなか見つからないこともあるだろう。でも、通常の生活でささみ肉ばかり摂っているのはヘルシーとは言い難い。
ちなみに、脂肪を燃焼するために必要なL-カルニチンの含有量が多い順に、羊(ラム)肉→牛肉→豚肉→鶏肉、となる。ただ、鶏肉が低カロリーなのは事実なので、夜遅い時間に食べるのであれば鶏肉にする、などタイミングで決めるのもありだ。また、和牛とオージービーフを比べた際、味で見れば和牛に軍配が上がりがちだが、オージービーフの方が低脂肪、かつ、L-カルニチンが多く含まれる。
そして、気をつけてほしいのはノンオイルドレッシング。ふつうのものより体に良さそうだが、ノンオイルドレッシングの方が糖分が多くなっていることが多々ある。脂質を抑える分、味わいを出すためにいろいろ加えざるをえないのかもしれない。せっかく野菜をたっぷり摂ったのに、そこでも糖質をたっぷり摂った、なんてことになったら悲しいではないか。いつも言うことだが、毎日良かれと思って摂っているものほど、中身をよくチェックしよう。
自分のやり方を貫きがちな男性こそ
「ヘルシー」を見直そう
女性がいろんなお店にいったり、いろんな情報から気に入った部分を選び取るのと比べれば、男性は、比較的、自分が決めたやり方、食べ方を貫きやすい。だからこそ、その選択が間違っていたときには、ヘルシーさとは正反対の方向にいってしまいがちだ。健やかな心身のためには栄養バランスが命だとすれば、極端な食事法に危険がないとは言い切れない。まずは健康診断というひとつの成績表を目安に、自分のヘルシー度をはかり、自身のヘルシー習慣を見直してみてほしい。
とはいえ、フリーランスなどで定期的に健康診断を受けてない人も少なくない。そんなときに目安となるのは、“顔色”。かくいう私も、以前、「疲れを見せないのも仕事のうち。いつも顔色よくいるようにしなさい」と母にたしなめられたことがある。栄養士という仕事柄、顔色が悪いのは絶対的マイナスポイントだ。でも、栄養士に限らず、顔色が悪いことで得する職業もなかなかないだろう。冬は寒さからどうしても顔色が悪くなりがち。自分が選び取った習慣が本当にヘルシーかどうか…毎朝鏡にうつる自分の顔が答えを教えてくれているはずだ。
心に決めたことは、逃げ道を作らないように宣言してしまってもいい。というわけで、私もこの場を借りて、休肝日を作ること、英語でカウンセリングができるようになることを誓います。あなたが心に決めたことが、これからの日々にたくさんの笑顔をもたらすものとなりますように。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年01月07日 10:32
そのくらいに本当にやりたいことを見つけることは難しい。。。Vol.3/まずは入り口として。探し求める真の自らは社会性にはなく心の内に、何をするかよりどのように取り組むか。。。
■定年前にたそがれない!50代からの人生リセット術
野田 稔 [一般社団法人 社会人材学舎 代表理事]
中学生の頃に得意だったものがあなたを救う?
50代での人生リセットを可能にする意外な能力
人生をリセットするには
まずは「能力の棚卸し」が必要だ
新しく人生をリセットするとしたら、一番大切なことは何であろうか。普通は、「まずは強い思いを持つべきだ」といわれる。「Will」である。果たして自分は何をしたいのか、を考えることであるが、これは間違いだ。間違いというか、無理だ。
そうした思いが持てるくらいであれば、とっくに持ち、かつ、思いがあるなら行動に移しているはずだ。思いが持てないという頭の構造になっているからこそ、今、悩みはより深まっている。今、自分がやるべきこと、やりたいことが明確な人だったら、多分、私のこの連載は読んでいないのではないか。それでも読んでくれているとしたら、それは嬉しい限りだ。
多くの人は、やらなくてはならいこと、「Must」に頭をとらわれすぎていて、やりたいことを思いつく余裕がない。たとえ思いついたとしても、それを行うには自分には能力が足りないと思うのが普通だろう。そこで重要なことは、自分の才能、能力について、もう一度、棚卸しをして、認識することだ。
まず、考えなければならないのが、Will、Can、Mustのバランス。Mustが優勢になっていて、Willがわからない、つまり自分は本当は何がしたいのかがわからないというのが普通だが、この場合はまずCanの棚卸しから始めるのが良い。
能力は、自分で気がついている能力と、気がついていない、あるいは忘れている能力に大別される。
「あなたは何ができますか?」と聞かれて「課長(部長)ができます」と答えたという笑い話のような現実は、実は明日は我が身だ。彼の頭の中で、できることとして意識している能力は、課長職をこなしているという、ここ数年間の自分の働きぶりと、それに必要とされた能力だけになっている。
人には隠れた能力がもっとたくさんある。しかし、その中のある重要なパートは、昔は顕在化していたにもかかわらず、人生のどこかの段階で自ら封印してしまった可能性がある。昔はできたが、今はできなくなくなっている、錆びついてしまったようなCanもあるだろう。
では、能力の棚卸しの本題に入る前に、年齢と能力の関係に関する俗説に疑いの目を向けてみよう。
年を取ると創造性が鈍るとか、保守的になるとよく言うが、一概にそうとは言えない。少なくとも欧米では、シニア層が起業することも多く、しかも成功確率は高いといわれる。
若者には失うものがなく、挑戦心があるとよくいわれるが、これも疑わしい。少なくとも、本人たちはそうは思えないことが多い。失いたくないものの最たるものが未来だ。若者はこれからの人生が長いことがわかっている。それだけに、今失敗して、暗い将来が到来したらたまらないと不安になる。実は、積極的に行動をしたほうが、むしろ未来は開けることも多いのに、今の延長線上にある未来を捨てられないから、失うものが多いと感じるわけだ。自分のこれまでの乏しい経験と小さな成功が、掛け替えのないものに思えてしまう。だから捨てられない。
小学校高学年から中学生の頃に
好きだったものを思い出してみよう
さて、「Can」の棚卸しへと話を移そう。
まず、自分の能力について考える場合、顕在化している能力、つまり、会社に入ってから自らが身につけた能力、その延長線上で今発揮している能力は、いったん脇に置こう。大事なのは、自分が忘れてしまっている能力、封印してしまった能力の再発見だからだ。
そうした能力は「ノンネグレクテッド・タレント」と呼ばれる。「無視し得ない能力=原点Can」を意味する。
人にはそもそもその人が好きだったり、得意だったりしたものがあって、意外とそれらは生涯変わらない。仮説ではあるものの、多くの場合、それらの萌芽は、小学校高学年から中学生の頃に見られる。
ところが、そうした自分の原点にあるCanを人は仕事に活かしているかというと、多くの人はそうはなっていない。
なぜならば、それらは入学試験や入社試験で評価されるようなものとは限らないので、そうした時期になると親から止められたり、自分で封印してしまったりするからだ。それで普通の勉強に力を入れる。その結果、一人前にはなるかもしれないが、それ以上にはなれなくなってしまう。
たとえば当時、何よりも絵を描くことが好きだった。男の子だけど、料理が好きだった。時計を分解しては組み立てていた。とにかく人の悩みを聞くのが好きだった……などは、高校や大学受験、あるいは就職に際しては、ほとんど顧みられることはない。それでいつしかそれに時間を費やすことを止めてしまう。その上で、二番目か三番目に好きなこと、皆によくできると言われたこと。実は好きでも何でもないけど、潰しが利きそうなものを身につけて、磨いていくことになる。
その封印を解くためには、好きで没頭していたことを思い出すほうがいい。必ずしも人よりうまくできたり、褒められたりしたことに限る必要はない。まさに、“好きこそものの上手なれ”だ。人より点数が高かったとか、人より明らかにうまかったということばかりに目を向けるのではなく、好きだったことに目を向ける。それが得意でもあったらなおいい。それは間違いなく、原点Canと言えよう。
子どもの頃のCan×大人になってからのCan
2つの掛け算で幸せな人生になる
私のことを少し話させてもらいたい。私は、小さなころからしゃべることが好きだった。テレビのアナウンサーのマネをしてみたり、発生練習のようなことまでしていた。テープレコーダーを買ってもらったのをきっかけにして、友人の1人とディスクジョッキーの真似事を始めた。月曜日に録音したテープを同級生に配り、回し聞きしてもらう。それで土曜日までにリクエスト曲を書いてもらい、回収。土曜の夜にエアチェックして、リクエスト曲を録音し、日曜日に DJ番組を録音して、また月曜日に回す。
高校に入ると放送部に入り、大学ではテレビ局でバイトを始めた。放送局の雰囲気が大好きだった。就職に際しては、実はそのテレビ局から誘われもした。そのままテレビ局に入っていれば(実際に入れたかどうかはわからないが)、アナウンサーになって、しゃべることを職業にする道もあったかもしれない。
しかし、当時の私にしゃべりを職業にする気はなかった。しゃべることはただ好きなだけで、それを生業にするというのは、あまり恰好のいいことだとは思えなかった。仕事にすべきことは、学術的に鍛え上げられたものでなければいけないと思った。
しゃべることのほかに、探究心が強く、小学生の頃から科学実験が大好きだった。粘土細工でできるだけ精巧に人体モデルを作ってみたり、限られた材料でホバークラフトの製作に打ち込んだり、物事の原理原則を考えて、それを再現するのが好きだった。
その性向が数理解析に向かい、数学が得意な高校生、そして大学生になっていた。そこで、その経験を生かして、野村総合研究所の研究員となった。最初の仕事は統計分析を行ったり、シミュレーションモデルを作ったり、など嬉々として取り組むのだが、いるところにはいるものだ。所詮、一番得意ではないことで勝負しようとしても、その道を極めようと迷いのない人には叶わない。野村総研には実際、数理解析の権化のような人がたくさんいた。しまいには、私のインストラクター役であった人から「野田君って、意外と数学が苦手なんだね」などと、大変ショックなことまでいわれてしまった。
つまり、自分に顕在的に能力があると確信していたことには、比較優位性があまりなかったのだ。
ただ、野村総研の先輩たちは皆、分析のプロではあるが、オーラル・プレゼンテーションには長けていなかった。必然的に、そういう役回りは私に回ってきた。大きなシンポジウムなどの舞台上でのリハーサルの雰囲気は、やっぱり好きだった。照明に照らされたときの緊張感はたまらなかった。それでも、そうした場所でしゃべることに、あまり価値は見出していなかった。
数理解析の次は自分がマネジメントに長けていると思い込み、管理職として大成しようとも思った。そうこうしているうちに、会社を辞めて、大学の教員になるとともに、本格的に地上波でデビューすることになった。最初に言われたのが「野田さんはどうしてそんなに正確に尺(時間)が読めるのですか?」だった。尺を読んでいるつもりはないが、中学時代からの習い性になっていたようだ。
野村総研にいた当時は、研修は好きではなかった。経営コンサルタントは研修事業を下に見る傾向があるからだ。しかし、やってみると奥が深くておもしろい。「今までで一番おもしろかった」などと言ってもらえると、やっぱり、自分の才能はこれなのかと思う。そうして45歳のときに、自分の原点Canが「話す」であることに気づくのだから、私もずいぶんと遅かった。
その後は努力して自分の声も作り直し、自分の理想イメージに近づけた。大人になって培ってきたCan、すなわち分析力、論理的思考力、人脈、組織論の知識。そうしたものと“しゃべる”という能力を掛け算し始めた。研修も教壇も、テレビのコメンテーターやキャスターも、趣味と実益が表裏一体となったわけで、これに気がついて本当によかったと思っている。
最も重要なことはそこだ。原点Canを見つけたら、それと大人になって身についた大人Canを掛け算してみる。原点Canというノンネグレクテッド・タレントを活かす道を考える。その時に必要なのは掛け算された能力を仕事につなげる翻訳能力だ。そのままではどうしていいかわからない原点のCanをどう今に生かすことができるのか。
昔はバンドを組んで音楽に熱中した。だからまた大人バンドを組んで楽しもう。それは趣味としてはいいことだろう。しかし、ここで言っている意味とは違う。
私も、原点Can、つまりそもそも私が一番好きで恵まれていた才能と、もう1つあった探求心や分析力が開花して育んできた大人Canを掛け合せたときに、私なりにユニークな能力を見つけることができた。どちらか一方では差別化にはならない。いくら私がしゃべりがうまいとしても、それで一流のアナウンサーになれるわけもない。
こんな人もいた。同じ年齢の友人で、彼も経営コンサルタントだった。彼は絵を描くのが好きで、得意だったらしい。大学受験に際しては、親に嘘をついて美術系の大学に進んだ。ところが学費の滞納からそれが親にばれて、辞めさせられて、別の一流大学に入り直して経営コンサルタントになる。しかし、44 歳のとき、期せずして私と同じ日に会社を辞めて、陶芸の勉強を始めた。芸術の道が忘れられなかったのだ。職業訓練学校に入って技術を中心に学んだ。プロになるべく陶作を始めたのだが、それは正直、趣味の域を出るものではなかった。ところがしばらくして、彼もそれを悟ったのか、陶芸ショップを始める。経営コンサルの知識と才能、そして芸術に対する造詣があったので、店はゆっくりとだが成功した。そんな開花の仕方もあるのだ。
さて、あなたの原点Canは果たして何だろうか。多くの人はそれを封印している。封印を解いても、それを仕事に活かす方法がわからない。一度、活かし方がわかったら、その人は幸せだ。ごく一部の人は、封印を解き、その活かし方も考えて会社に提案して採用されたり、ことによると会社を辞めてまで新たな挑戦を始める。
辞めると将来に不安があってもイキイキしている。好きなことを生活の、いや人生の真ん中に置けるからだ。
正月休みは終わってしまったが、新春にそんなことを考えてみてはいかがだろうか。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2014年01月07日 09:33
早起きは三文の徳。。。
■早起き習慣を身につけたい人へ...継続するために大事な2つのポイント
ソーシャルメディア共有サービス「Buffer」の共同設立者Joel Gascoigneさんは、朝の日課をかなり重要なものとしてとらえています。実際、Joelさんは朝の日課を「もっとも見返りのある習慣」と呼んでいるほどです。今回は、Joelさんが「早起きを習慣付けるためにやった方がいい」という2つの大事なポイントを紹介しましょう。
私は朝の日課を愛していて、常に守るように心がけています。日課の中心は、まず日の出前に早起きすること。大事な仕事を90分間やり、それからジムに行きます。最近、自分のブログにもこの習慣ことを書きました。
今回は、朝の日課を数カ月間にわたって継続させるためのポイントと、朝の日課を習慣化するとどれだけ大きなメリットがあるかという、2つのポイントに絞ってお伝えします。
そもそも、なぜ早起きをするのか?
朝の習慣において重要な2つのポイントについて話す前に、「なぜ早起きをした方がいいのか」について、私の考えをいくつかお話したいと思います。
第一に、成功している人は早起きな人が多いということです。実際、毎朝6時に起きる習慣がある人は、人生において大抵何かを成し遂げています。私がよく知るCEOたちには、かなりの早起きで、朝4時半に起きている人が何人もいます。
さらに、早起きをすることで「その日を自分で作っている」という気分になります。朝になったらベッドから這い出て、それからいつものようにメールをチェックするのと、自ら率先して早起きをして、誰にも邪魔されない静かな時間に大事な仕事をするのでは、どちらが自分の人生をコントロールしていると感じられるでしょうか。私は後者を選びたいです。
では、早起きを習慣にしたいと思った人には、これから2つの重要なポイントについてお話していきましょう。
夜の習慣を作る
毎朝早起きをする習慣を身につけるために、私が発見したもっとも大事なポイントは、睡眠が7時間未満の日が続くと、遅かれ早かれ疲れてしまうことです。
これに対抗する最善の手段は、自分に必要な睡眠時間を把握し、自分に必要な睡眠時間が取れる時間に寝ること(私の場合は約7.5時間です)。早く眠ろうと決めてから、一日の仕事の疲れを取り、ベッドに入る時には頭から仕事が離れているようにするために、30分の癒しの時間(散歩)を設けるようにもしました。
ある程度継続して早起きをするためには、朝の習慣と同じくらいに夜の習慣も大事になるのです。
週末も早起きをする
もうひとつの大事なポイントは、長期間継続して早起きをするなら、平日と同じくらい週末も意識した方がいいということです。たまに寝坊することだってあるし、週末に気をゆるめて休むことも大事だと分かっています。しかし、個人的には週末に起きる時間を遅くしてしまうと、平日の早起きにも大きな影響があると感じました。週末も早起きするように意識してからは、早起きの習慣が長い間続くようになりました。
平日に早起きをしようと決めたら、週末にはいつもの時間より1時間以上遅く起きないようにした方がいいと思います。つまり、金曜や土曜の夜も、早く寝るようにした方がいいということになります。土曜日や日曜日にいつもより数時間も遅く起きると、月曜日に早起きしたいと思ってもできない、もしくはつらいと感じます。
ありがちなのは、月曜日に少し遅く起きるようになると、火曜日もそうなってしまうこと。水曜日には早起きの習慣が戻ると思いますが、規則的に早起きを続けていた時の、流れる魔法のような状態を感じることはできないでしょう。週末に意識して平日と同じような早起きをしない場合は、毎週末ちょっとした時差ボケのような状態になります。週末にも平日と同じような時間に起きていれば、体がゆるんでいないので、継続して早起きを習慣付けられますよ。
Two important and often overlooked aspects of creating a lasting morning routine | Joel.is
Joel Gascoigne(原文/訳:的野裕子)
[ライフハッカー]
■朝の時間は稼ぎどき〜ベットから飛び起きたくなる7つの習慣
この50年、ベッドの中で朝日を浴びたことは一度もない。 ──トーマス・ジェファーソン(第3代アメリカ合衆国大統領)
Dumb Little Man:朝日がまだ昇りきる前、ごく選ばれた人たちだけが、まどろみから身を起こし、新しい一日に向かって歩き出します。この選ばれた人々は、暖かいベッドから抜け出せない私たち凡人に比べ、はるかに多くのことを成し遂げます。
朝を支配する鉄人とはどんな人たちでしょうか?
理論上は、朝の4時に起きようと11時に起きようと生産性は変わりません。重要なのは、頭と体に十分な休息を与える時間である睡眠の質です。
こうした早起きの鉄人、生産性の申し子たちは世界を違う視点で見ています。彼らにとって朝の時間は稼ぎどきなのです。毎朝、目的意識とともに目覚め、確信とともに行動し、容赦なく達成していきます。
では、彼らはどのようにして毎朝ベットから抜け出しているのでしょうか?
1. ウォーキングの習慣をつける
人間は習慣の生き物です。人体の自然なサイクルである24時間の概日リズムに従えば、身体の機能をフル活用できます。
例えば、自分に合った時間を見つけてウォーキングを日々の習慣にすれば、目覚めもよくなり、毎朝フレッシュな気持ちでベッドから抜け出せます。
2. 朝食はリッチに夕食は質素に
人体にとって最適なのは、 朝食はリッチに夕食は質素にすることです。朝にしっかり食べれば、一日中高いエネルギーを保ちながら程よく燃焼させていけます。
夕食を軽い食事で済ませれば、就寝時には胃の中を空にできます。体が正常に機能しており胃に潰瘍もないなら、空腹のほうがよく眠れます。胃の中が空であれば、消化ではなく細胞の修復と活性化にエネルギーを使えます。
3. 目的をもって生きる
小さな子どもは夜に眠るのをいやがります。また、世界で一番、ベッドから起きだすのを待ちきれない人たちでもあります。なぜこれほど「勤勉」なのでしょうか? 子どもたちは「どんな些細なことでも見逃したくない」のです。
大人である私たちには「見逃したくない」以上の何かが必要です。人生を変えるようなワクワクするゴールが必要であり、そこへ到達するため毎日を規律正しく生きることも重要となります。命をかけるほどでなくとも、最低限、毎日を「生きる」ための目的は必要不可欠なのです。
4. 一日を計画する
目的を持って生きようと言うのは簡単です。しかし、ちゃんと計画しないとゴールを追いかけるのは来週からでいいかなとつい先延ばしになってしまいます。
計画すれば、ゴールに向けて脳も動き出し、毎日が充実します。翌日のスケジュールを整理するのに、毎晩15分もあれば十分です。
毎日のウォーキング、重要なタスクに取り組む時間、食事とリクリエーションの時間などをスケジュールしてください。きっちりすれば、目的意識を持って日々を送れるとともに、より多くのタスクをこなしながらより多くの楽しみを享受できます。人生の貴重な時間を浪費にせずに済むのです。
幸せな人々は行為を計画するのであって、結果を計画するのではない。──Dennis Wholey(テレビプロデューサー)
5. 水を飲む
寝る前に少しの水を、朝起きたときに500ccの水を飲んでください。寝る前の水は体の修復プロセスを促進します。睡眠中に新鮮な水が体の隅々に行き渡り細胞を活性化します。朝の水には2つの役割があります。一つは、心身が目覚めるための最初の水として。もう一つは、消化システムを起動させ、排泄を促すため。朝からお通じが良いと気持ちがいいものです。
6. 体を働かせる
前述のとおり、人体には24時間の概日リズムがあります。このリズムが、睡眠、食事、運動など、あらゆる身体機能に影響を与えます。
概日リズムに従えば、身体を効果的に働かせることができます。例えば、朝に運動をすれば、血流がよくなり、体も高いレベルで働いてくれます。
運動する時間がないと言う人は、すぐにその時間が見つかるだろう。病気になったときに。ー Edward Stanley(ダービー伯爵)
運動を日課にすれば、その時間が来る前には、体はエネルギーを高めて準備を整えます。体験すればわかりますが、エネルギーを高めた状態で目覚めると、ベッドから飛び起きたくなります。
7. 「私的」な時間を持つ
少しは「私的」な時間もないと充実した朝にはなりません。瞑想は心をクリアにし、集中力を養ってくれます。世界のニュースをじっくり読むのもよいでしょう。こうした私的な時間もスケジュールに組み込んでおきます。
何をすれば充実するかは人それぞれ。自分にあった活動を選んでください。ポイントは、朝目覚めたときに、ベッドから飛び起きずにいられないほど、「心から」楽しい活動を選ぶこと。本当に飛び起きますよ。ぜひ、試してみてください!
7 Simple Ways To Burst Out of Bed Each Morning|Dumb Little Man
Alex Shalman(訳:伊藤貴之)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2014年01月02日 22:40
睡眠は時間よりも質とは思うけれど、、、心がけてみたいと思います。。。Vol.2
■「8時間寝るのがベスト」は忘れよう:集中力向上につながる睡眠ハック3選
人間は平均して一生のうち24年間を寝て過ごします。しかし、この「睡眠」に関しては不可解なことが多く、健康のためにどのくらいの睡眠時間が必要なのかもわかっていません。今回は研究成果を取り上げながら、この「睡眠の謎」に迫ってみました。
睡眠に関する最大の問題のひとつは、「話題があまりにも多すぎる」ことかもしれません。必要な睡眠時間やその影響、睡眠中に起きていることなど、一般的なことは誰もが知っています。けれども、これらの知識をどこで得たのかよく考えてみると、人づての話だったり、子どもの頃に母親から言い聞かせられたりしたものがほとんどだったことに私は気付きました。
「8時間睡眠がベスト」説は忘れるべし
「自分に必要な睡眠時間」については、誰もがわかっているはずです。私も良く使うセリフですが、「8時間から9時間は寝ないとダメだ」というのが一般的な回答でしょうか。
とはいえこれは、事実無根の思い込みかもしれないのです。
睡眠研究の第一人者Daniel Kripke教授によれば、これまでに「8時間睡眠が理想的である」ことを裏付ける証拠は一切見つかっていないということです。同教授の最新の研究では、「一晩に6時間半から7時間半の睡眠を取る人が、もっとも長生きで幸福度も高く、最大の生産性を発揮している」ことが判明しています。
この研究でさらに気になるのは、「それ以上長く眠ると健康に悪い」という点です。
私自身、一晩8時間の睡眠がベストだと考えていたので、この結果には驚きました。ただ言うまでもなく、ひとつの基準が万人に当てはまるわけがありません。ヨーロッパの睡眠研究の第一人者 Jim Horne氏は、著作『眠りの科学への旅』でこう述べています。
それではまるで、人間はみな靴のサイズが25センチで、身長が170センチでなければいけないと言っているようなものです。
まずは、Kripke教授の言う6時間半から7時間半の間で、自分に最適な睡眠時間を探るのが近道のようです。私も、現在この方法で取り組んでいます。
寝不足の落とし穴:脳に与える影響とは
さて、睡眠に関するとても興味深い話のひとつをご紹介しましょう。4時間しか寝ていないはずなのに、7時間半の睡眠を取った自分と同じくらい集中力があり、頭が冴え、仕事をバリバリこなしている人に出会ったことがありませんか?
この状況からは、「極度の睡眠不足であっても、しっかりと睡眠を取った人と同程度の集中力を持ち、元気いっぱいでいることは可能」ということが言えます。実際、ある最新の研究結果によると、何らかの課題を与えられた時にベストを尽くせば、睡眠不足の人も、そうでない人と全く同じ結果を出せることが明らかになっています。変ですよね。
いっぽうで、こんなこともわかっています。
十分に寝ていようが寝ていまいが、人は誰でも、時おり集中力を失います。そんな時、十分な睡眠が取れていれば、頭がぼんやりしてきても脳がそれを補おうとし、集中力は復活します。ところが、睡眠が不足していた場合、集中力は回復しないのです。
大きな発見は、睡眠不足状態にある人間の脳も、正常に機能することはあるものの、断続的に停電のような状態に陥るという点です。
こう語るのは、ハーバード大学で研究を行なうClifford Saper教授です。
「4時間しか寝なくてもバリバリ仕事ができる」と豪語している人は、嘘をついているわけではありません。ただ問題は、集中力を失ったら最後、それを取り戻す力がないことにあります。さらにひどいのは、睡眠不足の人は自分のパフォーマンスの低下を自覚しないという点です。
睡眠不足が足かせになっていることに、本人も気が付かないのです。Saper教授は、「一見したところ、いつも通りに頭が働いているという時間帯もあるため、実行力もあるし大丈夫だろうという誤解をしてしまいます。しかし、実際には脳にひずみが生じているので、悲惨な結末を招きかねません」と説明しています。
睡眠の力を味方につけよう
寝不足は確かにつらいもの。では、睡眠の力を最大限に活用し、成果をどんどん上げていくにはどうしたらよいのでしょうか。
より良い睡眠習慣を作り上げることに焦点を絞った情報は、ネット上にあふれています。そこで、私が「もっとも賢い人」と考える数名の力を借り、快い睡眠と生産性向上のために取り組むべきアプローチを3つにまとめてみました。
その1:お昼寝習慣のススメ
Bufferで働き始めてからの2年間、私は毎日20分ほど昼寝をしています。私の大好きな作家で、SNS関連の著書が米紙「New York Times」のベストセラーリストに名を連ねるMichael Hyatt氏も長年昼寝を習慣としており、自身のブログでもその効果について述べています。
Hyatt氏は昼寝の最大のメリットを、「ほんの数分浅い眠りに落ちるだけで、脳が注意力を回復できること」だと指摘しています。
私自身は、いつも午後3時頃に能率が落ちてくるので、それに合わせて昼寝の時間をとっています。目覚めた時には生産性が100パーセント回復しており、まさに最善策といえます。
Hyatt氏が紹介している動画によれば、昼寝習慣の主な利点は疲労回復です。当然だとお思いになるかもしれませんが、まさに日々の幸福度を大幅にアップさせてくれる要因なのです。
ただし、昼寝を習慣づけるのはけっこう難しいので、成功するための3つのヒントもお教えしましょう。
* まず、昼寝の習慣を周囲にしっかりと認識してもらいましょう。同僚や上司の協力やサポートを得られれば、昼寝をうまく習慣づけるための準備が整います
* 昼寝の長さも重要です。「昼寝をしても自分には効果がない」という声をよく耳にしますが、このような場合は大抵、昼寝の時間が長すぎるのが原因です。30分以上昼寝をしてはいけません。私の場合、20分が最適な長さです
* 極めて重要な最後のポイントは、昼寝を一貫した習慣にすることです。毎日昼寝をすることと、昼寝する時間帯(生産性が低下する午後3時頃が一般的)の両方を確実に守りましょう
その2:入眠儀式を持つ
毎晩歯磨きするように、簡単に眠りにつくためにはどうしたらいいのでしょうか。答えは簡単。心地よい眠りへと自分を導く「入眠儀式」を持てばいいのです。
「習慣」と違い、「儀式」には人をその気にさせる力があります。BufferのJoel Gascoigne氏は、入眠儀式についての自身のブログ記事で、「習慣は、自分自身に無理やり課す行動であることが多いのに対し、儀式はやらずにはいられない行動」だと説明しています。
入眠儀式で大切なのは、この1日を締めくくるための行動が、「その日の仕事や活動から完全に切り離されている」ということです。儀式の例をいくつかご紹介しましょう。
* 決まったルートを決まった時間に20分ほど散歩します。頭がすっきりし、眠りへの準備が整います。就寝前の散歩については、こちらの記事の「Paulo Coelhoのスピードエクササイズ」も試してみてください
* フィクションの本を読むのも効果的です。ノンフィクションではなく小説を選びましょう。日常と完全に切り離された別の世界や観点にどっぷり浸かって、眠りに備えましょう
* 最後に、私自身に効果てきめんだった方法をもうひとつ。それは、「起床時間をきっちり決める」という方法です。そして起床時間を、起床後すぐに取り組まなくてはならない活動に結びつけます。7時30分に目覚ましをセットしても、いつもスヌーズボタンを押してしまうという人は、違った方法を試してみましょう。目覚まし時計を同じようにセットした上で、朝起きたらすぐにしなくてはならない行動とその時間を決めるのです
私の場合は、「起床後すぐの7時40分に朝食をとる」などを設定しています。Gascoigne氏は、起床時間のきっかり5分後にジムに向かうそうです。これで、ベッドから出られずグズグズする朝も減りますね。
その3:心身ともにちゃんと疲れる
『成功と幸せのための4つのエネルギー管理術―メンタル・タフネス』の著者、Jim Loehr氏とTony Schwarz氏は、著書の中で上質の眠りを得るためには、身体的にも精神的にも疲れる必要があると主張しています。
精神的に困難なタスクと、身体的に負担の大きいタスクを、最低でもひとつずつ自分に課してみましょう。熟睡につながり、全身をしっかり休めることができます。
最後にもうひとつ:女性は男性より睡眠時間が必要
最後に、非常に興味深い事実をご紹介します。平均すると、女性は男性よりもほんの少しだけ長めの睡眠を必要とするそうです。個人差はありますが、平均では20分ほど長いようです。この理由についてHorne氏は、「男性よりも女性の脳のほうが複雑な配線であるため、長めの睡眠が必要だ」と著書『眠りの科学への旅』で述べています。
How much sleep do we really need to work productively? | Buffer
Leo Widrich(原文/訳:遠藤康子/ガリレオ)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2014年01月02日 22:32
引け際の演出、、、それは創作活動の完結。。。
■小椋佳 来年9月「生前葬コンサート」
シンガー・ソングライター小椋佳(69)が発売中のオリジナルアルバム「闌(たけなわ)」を最後のアルバムとした上、来年9月に東京・NHKホールで「生前葬コンサート」を開くことが22日、分かった。
気力、体力の減退が理由という。同アルバムと異例のコンサートをもって、大掛かりな歌手活動に一区切りをつける。
「闌」は「宴も闌ですが…」などと使われる言葉。小椋は「今が真っ盛りという意味ですが、物事が終わるあいさつなんです」と話した。70歳を目前にした決意だ。「間違いなく気力、体力は減退したという実感はあります。同期で幸運にも第2、第3の職場を与えられた人でさえ隠居している。音楽活動の場合は定年はない。だから自分でけりをつけなくてはいけないと思った」。
異例のステージも決まった。来年9月12日からNHKホールで4日間連続で「小椋佳 生前葬コンサート」と銘打った公演を行う。1日25曲を予定しているが4日間で全て異なる計100曲を歌う。
[日刊スポーツ]
Posted by nob : 2014年01月02日 17:10
年の瀬に心の大掃除Vol.4/心と身体は常に繋がり合っている。。。
■アランの幸福論「笑うからしあわせなのだ」【2】
鎌田實
医師・作家
アランの『幸福論』の特徴として、心身の関係性に着目している点があります。日常的な行動やしぐさ、体操や姿勢のなかに幸福への鍵が潜んでいるという指摘は新鮮です。
「気分に逆らうのは判断力のなすべき仕事ではない。(中略)そうではなく、姿勢を変えて、適当な運動でも与えてみることが必要なのだ。なぜなら、われわれの中で、運動を伝える筋肉だけがわれわれの自由になる唯一の部分であるから」で、「ほほ笑むことや肩をすくめることは、思いわずらっていることを遠ざける常套手段」であり、「こんな実に簡単な運動によってたちまち内臓の血液循環が変わることを知るがよい」と記しています。
自分は不幸だという焦燥や不安、苦悩や怒りといった情念にとらわれている人は、まず理屈であれこれ考えるのをやめたほうがいい。その代わりに、体操をしたり、他人に微笑みかけたりするなど簡単な行動を意識的に起こすことが大切だというのです。
宗教が要求しているしぐさ、「ひざまずいたり、からだをかがめたり、また楽な姿勢にもどったり」にも、実は、「(肉体が)諸器官を解放し、生命の機能をいちだんと高める」効果があるのだろうという指摘も興味深いものです。
「『頭を垂れよ』という言葉は、(中略)まず黙って、目を休めて、柔和な心で生きることを求めているのである」とも言っています。
これに関連してアランは、われわれ現代人が忘れがちだが大切で実行可能な、幸福へのヒントに触れています。
「訪問や儀式やお祝いがいつも好まれるのである。それは幸福を演じてみるチャンスなのだ。この種の喜劇はまちがいなくわれわれを悲劇から解放する」。他人の家を訪問したり逆に自宅に来客があれば、必然的に礼儀正しく丁寧に温かい気持ちで行動することになります。それが不機嫌や苦悩を忘れさせてくれます。儀式で折り目正しいしぐさを演じれば、気分も自然とおごそかになり、お祝い事を行えば気持ちも浮き立ちます。
「優しさや親切やよろこびのしぐさを演じるならば、憂鬱な気分も胃の痛みもかなりのところ直ってしまうものだ」と語るアランは、「お辞儀をしたりほほ笑んだりするしぐさは、まったく反対の動き、つまり激怒、不信、憂鬱を不可能にしてしまうという利点がある」と分析しているのです。
僕は東日本大震災の被災地を何度か訪ねつつ、『幸福論』を読み直すなかで、いま次のように感じています。
津波で家が流され家族を失った被災地の方々にとっては、地元の祭りだ、季節の行事だ、誕生祝いだ、互いに訪問し合ってお喋りを、などと言われても、「それどころじゃない」「絶望のどん底なんだ」という気持ちでしょう。でも、そんなときだからこそ、アランの言うように儀式やお祝い、訪問が意味を持ってくるのではないかと思うのです。
たとえば東北6大祭りの1つとされる相馬の野馬追(福島県浜通りの祭り)も、昨年、実施か否かでだいぶ議論がありましたが、結局、規模を縮小して例年どおり行われ大きな拍手に包まれました。
まさにアランの言うように、それは幸福を演じるチャンスであり、われわれを悲劇から解放するのです。『幸福論』を読んだ僕がいつも自分に言い聞かせている言葉があります。
それは、「しあわせだから笑っているのではない。むしろぼくは、笑うからしあわせなのだ」という一節です。
家が貧乏で、医学部に行く授業料も生活費も全部自分で稼げと父親に宣告された僕は、学生時代、「どうやって生きていこうか」と思案しながらも、アランから学んで「笑わなくなったらおしまいだ」と考え、いつもニコニコしていました。それは現在も同じ。患者さんには笑顔のドクターと言われています。
人は自分が辛い状況にあると、次のように思い込みがちです。「あいつは、いいよな。幸せだから笑っていられる。俺は笑ってなんかいられるか」と。しかし、逆だとアランの言葉は語っています。「(自分のなかにある)よろこびを目覚めさせるためには、何かを開始することが必要なのである」と。「もしある専制君主がぼくを投獄(中略)したならば、ぼくは毎日ひとりで笑うことを健康法とするであろう」とも言っています。
アランの言うように、幸福になるには、まず微笑んでみることです。
この言葉を医者の立場から言えば、副交感神経の時間を持てということになるでしょう。ストレス社会で大半の時間を交感神経が刺激された状態で過ごしているわれわれですが、笑うと副交感神経が刺激されて血液循環がよくなり、ナチュラルキラー細胞も増えて免疫力が上がるのです。
笑えば“幸せホルモン”と呼ばれるセロトニンが出てくることも最近の研究で解明されています。しかも、本当の幸福感からの笑いではなく、表面的な笑いマネでもいいのです。笑うという行為そのものがセロトニンを分泌することがわかってきたのです。
末期がんの患者さんでも、笑って暮らしている人のなかには驚くほど余命が延びたり、たとえそうではなくても、最後までその人らしく活き活きと人生を貫く人が多いのはたしかです。
力いっぱい戦うまで負けたと言うな
最後に、アランが『幸福論』で語っているとても大切なことを紹介しておきましょう。それは、「幸福にならねばならない」ということです。つまりアランは、幸福になるのは人として誓わねばならない義務だと強調しているのです。
儒教的な道徳がしみ込んでいる日本では、他人を助けることが徳のあり方だと考えがちですが、アランは、まず「自分の幸福を欲しなければならない」「幸福は徳である」と言います。そして、「(あなたが)幸福になることはまた、他人に対する義務でもあるのだ」とも書いています。「人に幸福を与えるためには自分自身のうちに幸福をもっていなければならない」と言うのです。あなたが幸せになれば、周りも幸せにすることができるというのです。とても素敵で大切な考え方だと思いませんか。
「幸福になるのは、いつだってむずかしいこと」ではあるが、「しかし力いっぱい戦ったあとでなければ負けたと言うな。これはおそらく至上命令である。幸福になろうと欲しなければ、絶対幸福になれない」と、アランは結んでいます。
僕はアランに出遇ったことで、自分が随分変わった気がします。ふりかえってみると、アランが道を示してくれたというふうに思えるのです。
ふと開いたページに気に入った言葉を見つけ、それに線を引いたり自分なりの書き込みをしていけば、ちょっとした自分流の「生き方」本にすることができる。そういう読み方ができるのも、『幸福論』の魅力だと思っています。
※出典:『幸福論』(神谷幹夫訳、岩波文庫)
[PRESIDENT online]
Posted by nob : 2013年12月30日 20:05
年の瀬に心の大掃除Vol.3/幸福とは、気付き、探し、創るもの。。。
■アランの幸福論「笑うからしあわせなのだ」【1】
鎌田實
医師・作家
アランは、パリの名門校などフランス各地の高校で、哲学の1教師として生涯を貫いた人物。本名はエミール・シャルチエ。1高校教師でありながら社会的な事件に対して積極的に発言し、政治活動や講演活動にも参加。新聞への寄稿も精力的に行い、連載した文章は膨大な数に及ぶ。
『幸福論』はそんなアランが、第1次世界大戦前後に執筆した文章のなかから、「幸福」をテーマとしたものを集めて編纂した書だ。プロポ(断章)と呼ばれる、短くて独立したコラム的な形式で書かれているのが特徴で、『幸福論』は93編のプロポから成っている。
形式の斬新さだけではなく、内容も難解で観念的な哲学書とは異なり、一見平易な言葉で書かれた思索の本となっている。日常生活の具体的な事柄を例に幸福になるための指針やヒントが語られていて、日本でも長年多くの読者に親しまれている。
獣医で熱心な読書家だった父親の血筋を引いたアランは、理系が得意な少年だったが、18歳で入学したパリの高等学校で哲学に目覚めたと他の著書のなかで記している。影響を受けたのは、ギリシャの哲学者プラトンやオランダの哲学者スピノザだという。83歳没。『 幸福論』の初版は1925年、アラン57歳の年に60編のプロポで出版。その後に加筆された。
美しいエッセーのような哲学書
アランとの出遇いは学生時代です。いろいろな哲学書にとびついてみたなかで、『幸福論』は「これが哲学書?」と思うくらい平易な言葉で綴られていて、美しいエッセーを読んでいるような感覚で読み進めることができました。
いまでも旅に出るときには文庫版を手にし、適当に開いたページを読み直したりしています。各章が短い文章で構成されていますし、どこから読み始めても、「なるほど」と、自分の最近の言動をふりむくきっかけになるような1行が含まれているからです。
あるとき、忙しさのなかでつい患者さんを強い言葉で叱ってしまったことがありました。糖尿病の患者さんで、食事やお酒について、何度同じ注意をしても守れなかったからです。
そんなときに列車のなかで開いたページで、「不機嫌という奴は、自分に自分の不機嫌を伝えるのだ」という言葉に出遇ったのです。自分のなかにあった不機嫌を患者さんにぶつけても、少しも心は晴れません。むしろ、ますます不機嫌さが増してしまったことを思い出しました。互いに嫌な気持ちだけが残りました。自分に自分の不機嫌を、さらに伝染させたわけです。
アランは「伝染」ということに重きを置いています。喜びも悲しみも上機嫌も不機嫌も伝染するというのです。
幸福にとって上機嫌でいることが大切だと説くアランは、「これこそみんなの心を豊かにする、まず贈る人の心を豊かにする(後略)」「贈り合うことによって増えて行く宝である」と言っています。そして、たとえばレストランのボーイに「ひとこと、親切なことばを、心からの感謝のことばを言ってごらん」と書いています。
ビジネス街で忙しく働く人なら、昼食にラーメンを食べたあと、レジで「ごちそうさま。美味しかった」と一声かけてみればいいのです。それは相手にかける言葉ですが、回り回って自分を幸せな気持ちにもしてくれるはずです。機嫌のいい所作が自分を幸福にしてくれるでしょう。
一方、「憐れみについて」という章には、こう書かれています。重病人を見舞ったときに、親切心や同情から心配する口調や表情を示すのは、「そのたびに(病人に)悲しみを少しずつそそぎかける」ことになると。それは悲しみを伝染させていることだというのです。
大切なのは、むしろ病室に元気さを持ち込むことだとアランは言います。
「生命の力こそ、彼に与えねばならないのだ」「病人は自分のせいで人のよろこびが消されはしないのを見れば、その時彼は立ち直り、元気になるのだ」と。
かりに病人が職場の上司なら、礼儀としてのお見舞いのあいさつをしたあとは、「新人のA君はあいかわらずドジですが、偶然大きな契約をとったんですよ」などと笑いを誘うような話題のほうがいいということ。
僕も病院でがんの末期患者さんたちを回診するときは、患者さんに1回は笑顔を出してもらえるよう心がけています。
「悲観主義は気分によるものであり、楽観主義は意志によるものである」――日常的な言葉が多いアランの文章のなかで、この言葉はやや哲学的な匂いがします。
この言葉に続いて、アランは次のように記しています。
「気分にまかせて生きている人はみんな、悲しみにとらわれる。否、それだけではすまない。やがていらだち、怒り出す」「ほんとうを言えば、上機嫌など存在しないのだ。気分というのは、正確に言えば、いつも悪いものなのだ。だから、幸福とはすべて、意志と自己克服とによるものである」
感情や気分だけで生きていると、悲しみや嫌なことに遭遇したとき、不幸だという思いや怒りの感情に溺れてしまう。だから、感情に流されず、「いまは辛いけど明日は明るくなる」と、意志の力で楽観主義に立つ。幸福を得るには、それが大事だというのです。
これはアランの『幸福論』の重要なポイントです。
日本はいまとても厳しい状況にあります。経済が長期的に鬱々たる状態だったところに東日本大震災が起きました。
しかし、こんなときこそ、「いまは大変だが必ず良くなる」と意志の力で考えることが必要だと『幸福論』は教えてくれています。
「期待を抱くこと、それはつまり幸福であるということなのだ」という言葉も噛みしめたいものです。幸福とは何か。どうすれば手に入るのか。アランは次のように説明しているからです。
「幸福はあのショー・ウィンドーに飾られている品物のように、人がそれを選んで、お金を払って、持ち帰ることのできるようなものではない」と、アランは強調します。
赤い商品は店頭にあってもあなたの家にあっても「同じように赤いものである」のとは異なり、「幸福は、人がそれを自分の手の中に入れなければ幸福ではない」のであって、「自分の外に求めるかぎり、何ひとつ(最初から)幸福の姿をとっているものはない」というのです。
「君はすでに幸福(の種子)を持っている」のであって、期待つまり希望を抱いて進んでいくことが幸福(の開花)に繋がるのだと『幸福論』は教えてくれています。
僕が37年前に諏訪中央病院に赴任したとき、そこは累積赤字4億円で潰れる寸前でした。地元の患者さんも隣町の大病院に行ってしまうし医者も4人だけ。それを立て直すとき、われわれを動かしたのは希望でした。
医療の質では東京の大学病院に勝てないが、救急でも日曜でも絶対断らず全力で診る、患者さんに丁寧に優しく接する……そういう点では絶対負けないという医療なら、やれるはずじゃないか。そういうメッセージを出し、希望を語ることが、職員たちの心を揺さぶり、次第に変わることができました。
東京の病院がやれないようなことをやろうと、日本で初めてデイケアを始め、当時まだ在宅医療・訪問看護という制度がないのに訪問看護も始めました。薬を出すことではなく、生活指導に力点を置きました。その結果、不健康な人が多かった地域が、いまや日本有数の長寿で、しかも医療費がかからない地域に変貌したのです。
この変化のプロセスに、われわれはとても幸せを感じてきました。希望を持ち行動する。そのプロセスにこそ幸福があるのだと実感した例です。
アランは行動することの大切さについて『幸福論』のさまざまな個所で触れています。希望という強い思いも、それを行動に移さないと幸福に至りません。
「どっちにころんでもいいという見物人の態度を決め込んで、ただドアを開いて幸福が入れるようにしているだけでは、入ってくるのは悲しみである」と言っています。
さらに、「何もしない人間はなんだって好きになれないのだ」「音楽を自分で演奏するよりも聴く方が好きな者がいるだろうか」「だれだって強いられた仕事は好きではない」が、「好きでやっている仕事は楽しみであり、もっと正確に言えば、幸福である」「戦いが自分の意志で行なわれるならば、困難な勝利ほど楽しいものはない」とも記しています。
与えられるのを待っているのではなく、自分から積極的に行動すること、それが幸福への道だと語っているのです。
意志の力で希望を持ち、それを実現するために行動する。そのなかに幸福があるというのです。
※出典:『幸福論』(神谷幹夫訳、岩波文庫)
[PRESIDENT online]
Posted by nob : 2013年12月30日 19:56
年の瀬に心の大掃除Vol.2/ほんたうにどんなつらいことでもそれがたゞしいみちを進む中でのできごとなら峠の上りも下りもみんなほんたうの幸福に近づく一あしづつ。。。
■宮沢賢治の想い「かなしみもみんなおぼしめし」
齋藤孝
明治大学教授
宮沢賢治は1896年、現在の岩手県花巻市で質・古着商を営む裕福な家に生まれた。盛岡高等農林学校時代、地質調査研究のかたわら、同人誌を創刊し本格的な文学活動を開始。卒業後は東京で下宿生活をしながら法華宗・国柱会の活動にも勤しんだ。そんな中、最大の理解者であった妹トシを結核で亡くした悲しみが、『銀河鉄道の夜』をはじめ、後の作品に大きな影響を与えたといわれる。
トシの看病のため岩手に帰った後の賢治は、農学校の教師として働きながら創作活動を続け、1924年には『心象スケッチ 春と修羅』『イーハトヴ童話 注文の多い料理店』を自費出版。しかし、ほとんど注目されず、生前に刊行された作品は結局この2冊のみだった。その後はボランティアの農業指導にも情熱をそそいだが、28年に急性肺炎を発病。33年に永眠。享年37。生涯禁欲と独身を貫いた。
作家・宮沢賢治が正当な評価を受けるようになったのは、没後、遺された作品群が発表されてからである。その世界観の根底には、自らの裕福な出自と農民の困窮との対比から生まれた贖罪意識や自己犠牲の精神がある。一方、岩手をモチーフにイーハトーヴという架空の理想郷をつくり上げ、自然との交感を描いたことも作品の大きな魅力となっている。
「銀河系」を自らの中に意識する
宮沢賢治は、奇しくも明治三陸地震の2カ月後に生まれ、死の半年前には昭和三陸地震に遭遇しています。東日本大震災では賢治の愛したイーハトーヴ=岩手県が再び甚大な被害を受けました。幾層にも重なった深い悲しみの底から湧き上がってきた賢治の言葉は、震災後のいまの日本にとって、限りなく大きな意味を持っているように思います。
宮沢賢治は「本当の幸せ」が何かを生涯を通して考え続けた人でした。『銀河鉄道の夜』の中には「さいはひ(幸い)」という言葉が何度も出てきます。ジョバンニとカムパネルラは死者を乗せた悲しみの列車の中で、「ほんたうのさいはひはいったいなんだろう」「きっとみんなのほんたうのさいはひをさがしに行く。どこまでもどこまでも僕たち一緒に進んで行こう」と語りあいます。「たゞいちばんのさいはひに至るためにいろいろのかなしみもみんなおぼしめしです」「なにがしあはせかわからないです。ほんたうにどんなつらいことでもそれがたゞしいみちを進む中でのできごとなら峠の上りも下りもみんなほんたうの幸福に近づく一あしづつですから」とも語ります。
賢治の思想の根幹には、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」(『農民芸術概論綱要』)という考え方がありました。みんなが幸せになることが自分の幸せ。でも、その幸せに至るためには、いろいろな悲しみも含めて、あらゆる経験と感情を心の地層に積み重ねなければならない。よいことだけを求めるのが幸せではないと賢治は考えたのです。
いまの世の中は、ひたすら快適な状態だけを維持しようとする価値観が主流ですが、賢治の時代は違いました。東北は自然災害や凶作の多い厳しい土地で、数多くの悲しみが周囲にあふれていました。その中で本当の幸せを考え続けた賢治が辿り着いた、結晶のような言葉が『銀河鉄道の夜』の中にはたくさん詰まっています。
「僕はもうあのさそりのやうにほんたうにみんなの幸(さいわい)のためならば僕のからだなんか百ぺん灼(や)いてもかまはない」という言葉も有名です。こうした言葉には、自分よりもまわりの人々の幸福のために生きた宮沢賢治の本質がよく表れていると思います。
一方、「生徒諸君に寄せる」という詩の中には、賢治の宇宙観、視野の広さがよく表れていると思います。
「新らしい時代のコペルニクスよ/余りに重苦しい重力の法則から/この銀河系統を解き放て」「諸君はこの颯爽たる/諸君の未来圏から吹いて来る/透明な清潔な風を感じないのか」と語りかける彼の視線は、宇宙レベルの広い空間、未来へとつながる長い時間軸につながっています。『農民芸術概論綱要』にも「正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行くことである」という言葉があります。賢治は土地に根ざす一方で、大きな宇宙観を持ち、視野を広げていったその先端から自分たちを見つめ返すという発想を持っていました。
近年ようやく私たちは地球規模の環境問題を考えるようになり、原子力発電についても重大な選択を迫られています。こうした問題を考えるとき、「未来圏」という視点がきわめて重要になります。私たちの次の世代、その次の世代まで悪影響を残すことをやっていいのか? 自分の身の回りだけを見ていたらわからないことも、宇宙、あるいは未来の視点から見ることで、あるべき姿が見えてきます。
私は常々、一般の人も宇宙的な視野をもって勉強し視野を広げるべきだと思っています。いま宇宙研究の最先端では、ビッグバンの謎が解き明かされつつあり、あるいは人類の進化史についても、DNAの分析を通して何十万年というスパンでの進化が明らかになってきました。科学者でもあった賢治がもし生きていたら、ものすごく興奮することでしょう。
宇宙や人類について学び、視野を広げていけば、個人の心配事や悩みも、また違った姿を見せてきます。そこには新たな希望も湧いてくるはずです。勉強をすれば、展望が開け、そこから希望の風が吹いてくる。その風はエネルギーにあふれ、爽快感に満ちている――そんな思いを賢治は「未来圏から吹いて来る透明な清潔な風」いう言葉に込めたのではないでしょうか。
最後は有名な「雨ニモマケズ」から。この詩で私が好きなのは、「アラユルコトヲ/ジブンヲカンヂャウニ入レズニ/ヨクミキキシワカリ/ソシテワスレズ」という一節です。
この詩は「デクノボー」のイメージで受け取られがちですが、この人物、じつは「よく見聞きし、わかり、忘れない」聡明さを持っているのです。外に自分をどうアピールするかには無関心でも、聡明にものごとを理解し、判断できる人間像がここにはあります。
大事なのは判断力です。東日本大震災と原発事故でも、事態をもう少しよくするためにできた判断があったはずです。個々の人々は必死に仕事をしていたのかもしれませんが、本当の意味での聡明さと判断力を持っていなかったように感じます。
「あらゆることを自分を勘定に入れずに」というのも大事なことです。自分の利益という意識が入ってくると、人間の目は必ず曇ります。そして、個々の利益が相克し、正しい判断が下せなくなる。それでは賢治のいう「本当の幸福」にはけっして行き着くことができません。いま世の中では総論賛成、各論反対という問題がとても多い。がれき処理なども、みんな「方向性としてはいい」という。でも、話が自分の身の回りの利益に関わってくると「私はいやだ」となる。自分というものを度外視して、客観的にものが見られる「デクノボー」のような人がもっと増えれば事態は変わると思います。
しかもこの人物、いろんなところへ駆けつけます。「東ニ病気ノコドモアレバ/行ッテ看病シテヤリ/西ニツカレタ母アレバ/行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ/南ニ死ニサウナ人アレバ/行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ/北ニケンクヮヤソショウガアレバ/ツマラナイカラヤメロトイヒ」、ひたすら人のために行動する力を持っているのです。
こういう人間が集まったときにできる共同性こそ、今後の社会に必要なものではないでしょうか。政治にも、ビジネスにも、同じことがいえると思います。この詩は日本人に与えられた宝みたいなものです。すべての国民が子供のうちから音読して記憶すべきだと私は思っています。
※出典:『かなしみはちからに 心にしみる宮沢賢治のことば』(齋藤孝監修、朝日新聞出版)、『宮沢賢治全集』(全10巻、ちくま文庫)
[PRESIDENT online]
Posted by nob : 2013年12月30日 13:44
年の瀬に心の大掃除/断捨離11)以外は既にクリアできている感。。。
■溜まったストレス、すっきりさせよう! 年内に実行したい「心の断捨離」15カ条
2013年も残すところあと数日。今年はどんな1年でしたか? OLさんも、社長さんも、モデルさんも、学生さんも、みんな色々あったよね。そして、誰もが多かれ少なかれ心の中にストレスを溜め込んでいるハズ! 環境を変えるのは難しいけれど、いつもの考え方を少し変えれば、心がチョット軽くなるんじゃないかしら。
ということで、今日は、海外サイト「MindBodyGreen」で見つけた、年内に実行したい、心の断捨離15カ条をご紹介します!!
心の断捨離15か条
断捨離1) 本当にやりたいことをすることに対して罪悪感を抱くことを止める。
断捨離2) 知らない世界への恐怖を抱くことを止める。思い切ってドアを開けましょう。
断捨離3) 後悔することを止める。当時は確かにそうすべきだと思ったのです。
断捨離4) 心配することを止める。心のモヤモヤが増えるだけです。
断捨離5) 文句を言うことを止める。気に入らないことがあるなら、選択肢は二つです。受け入れるか、変えるか。
断捨離6) 自分が可哀そうだという考えを捨てる。意味のない考えです。
断捨離7) 他人のために尽くし過ぎることを止める。自分のことを第一に考えるようにしましょう。
断捨離8) 何事にも白黒つけたがるクセを止める。人生はそんなに単純ではありません。
断捨離9) 始める前からあきらめてしまうクセを止める。新しい一歩を踏み出して、新しい未来を作り出しましょう。
断捨離10) 過去の恋人に対する怒りを捨てる。終わった愛は、懐かしい想い出にしましょう。
断捨離11) 常に先回りして考えることを止める。やっているうちに分かることもあります。
断捨離12) お金のことで悩むことを止める。今持っているお金の価値を自覚し、正しい使い方を考えましょう。借金があれば返済計画を立てましょう。
断捨離13) 他人を救済しようとしたり、変えようとしたりすることを止める。みんな、それぞれが自分の人生を歩んでいるのです。他人のことは放っておきましょう。余計なお世話です。
断捨離14) 他人に合わせること、受け入れてもらおうと努力することを止める。
断捨離15) 自己嫌悪の感情を捨てる。重要なのは体重の目盛ではなく、あなたがあなた自身であることです。自分を愛してあげましょう!
要するに、考えてもしょうがないことは考えずに、自分を信じて前を向こう! ということですね。今年のモヤモヤは今年のうちに。1年の間に溜めてしまった心配事やストレスをスパッと切り捨て、ハッピーな新年をスタートさせましょう。笑う門には福来る、ですよ!!
(文=中野麦子)
参照元:MindBodyGreen
[ポーチ]
Posted by nob : 2013年12月30日 13:37
睡眠は時間よりも質とは思うけれど、、、心がけてみたいと思います。。。
■7時間以上の睡眠が必要な理由と効果「寝だめも効果あり」―米研究
3人に1人が1日6時間以下しか睡眠時間をとっていません。だるく感じたり気分も優れません。コロラド大学などの研究によると7時間の睡眠が必要な理由が分かりました。
●脳がよく働く
7時間。これが女性たちがある認識力テストで最も高得点を出した人たちの平均睡眠時間。睡眠7時間以下の人は脳年齢も4年〜7年高くなる他、毎日7時間以上の睡眠をとっている人はアルツハイマー病にもなりにくいのです。
●痛み軽減効果
十分な睡眠はどんな痛み止めより効果的。寝不足の人たちが4日間連続で10時間の睡眠をとった結果、痛みを感じることが25%減ったという結果に。
●ダメージ回復
パスタ、揚げ物などの炭水化物。これらの食べ物による血糖値上昇などのダメージも睡眠不足の人より軽くすみます。十分睡眠していると、血中のグルコースが減少します。6年間睡眠不足になると血糖値が異常になり、糖尿病にもなりやすいことがわかっています。
●乳がんのリスクが減る
7時間以下の睡眠で乳がんのリスクが62%も高まることが日本の研究でわかりました。十分な睡眠がない時、松果線がホルモン生成をコントロールするメラトニンを分泌しないことが原因だとか。
●睡眠不足は合理的思考ができない
睡眠不足はドーパミンを促してしまい、話の途中にオーバーリアクションしてしまいます。結果、合理的な考えができず、話している相手との内容もかみ合わなくなります。
●寝だめも効果的
ずっと意味がないと思われていた寝だめ。実は寝だめは寝不足分を補い、注意力も増し、回復力も早いことがわかりました。
さあ、今日から1日7時間を目標に睡眠をとってみませんか。
※ 当記事は、ハイブリッド翻訳のワールドジャンパー(http://www.worldjumper.com)の協力により執筆されました。
参考:7 Most Convincing Reasons to Get 7 Hours of Sleep
http://www.oprah.com/health/How-Many-Hours-Of-Sleep/1
[マイナビウーマン]
Posted by nob : 2013年12月30日 12:40
湧泉以外は知り及びませんでした、、、早速試してみます。。。
■手足の指先の冷え性を改善するツボ4つ
■ はじめに
冷え性は多くの女性が抱える悩みです。筆者も手足がよく冷えます。手足の指先は関節が多く脂肪が少ないため、熱を失い易く冷え易い場所だそうです。ここではツボを刺激することで、手足の血行を良くして冷えの症状を改善する方法を紹介します。ツボは体のエネルギーを調節するもので、上手に刺激すると血行を促進し冷えの症状を改善する効果が期待されます。押した時に心地よさと痛みを同時に感じる所がツボになります。
■ 冷え性とは?
・寒いわけではないのに手足が冷たい
・ベッドに入っても足が冷たいままでなかなか寝付けない
といったように体全体は寒くないのに部分的に冷えを感じる症状で、体温を調節する機能の乱れをいいます。特に女性に多いのが特徴です。
■ 冷え性の原因
・衣服による体の締め付けや薄着
・女性ホルモンの乱れ(特に妊娠時や更年期)
・食生活の乱れ(ファーストフードやスナック菓子類の食べ過ぎ)
・運動不足
以上のようなことから体の血行が悪くなり、冷えの症状を引き起こすと考えられています。
■ 手のツボ
◎ 八邪(はちじゃ)
手の水かきの部分が手の冷えのツボ八邪です。両手合わせて8カ所です。このツボは指先の抹消の血行を良くする効果が期待されます。このツボを息を吐きながら、「ちょっと痛いけど心地よい程度の強さ」で指圧します。3秒くらい力を入れて押し、それぞれ数回繰り返します。この指圧なら仕事中でも簡単にできるのでお勧めです。マッサージ後15分から20分くらいでジワーっと温かくなってきます。手が冷たく感じたら1日のうちに何度か繰り返します。
■ 足のツボ
足のツボのマッサージはお風呂に入りながらするとより効果的なようです。
◎ 湧泉(ゆうせん)
足の裏にある人の字形のくぼみの中央にあるツボです。両足にあります。息を吐きながら数秒間ツボを4から5回程指圧します。
◎ 八風(はちふう)
足の甲側の水かき部分で両足合わせて8カ所です。八風の「風」は冷気の邪を意味し、このツボを押すことで冷えを改善すると言われています。息を吐きながらそれぞれのツボを数秒間押します。これを数回繰り返します。
◎ 第二泉生(だいにせんせい)
両足の中指の付け根の少し上にあるツボで、末端の血行を良くすると言われます。ここをよくマッサージします。
以上の3つのツボを湯船につかりながらゆっくり繰り返しマッサージします。
■ おわりに
いかがでしたか。マッサージを始めてから、夜にベッドに入ってから足が冷たくて眠れないということが少なくなったのが1番嬉しいです。ぜひお試しください。
[nanapiユーザー・Molly 編集:nanapi編集部]
Posted by nob : 2013年12月30日 11:55
この何気ない日常は、、、私だけが描けるドラスティックなドラマ。。。
■【今年最後の名言】「経験は、未来の点に繋がっている」スティーブ・ジョブズ
今年もお疲れさまでした。
ちょっと心が弱ったときにそっと背中を押してくれる、そんな名言をお届けします。 今年最後となる今週は、スティーブ・ジョブズ氏のこんな言葉。
点と点がいつか何らかのかたちでつながると信じなければならない。 自分の根性、運命、人生、カルマ、何でもいいから、とにかく信じるのです。歩む道のどこかで点と点がつながると信じれば、自信を持って思うままに生きることができます。
「スティーブ・ジョブズの感動スピーチ(翻訳)字幕動画」より引用
年末になると「今年も何もないまま、過ぎていってしまう...」そんなふうに焦ってしまいがちです。でも、忘れてしまいそうな些細な経験でも、「あのときの経験は、今このときのために必要だったのだ」と思う日が来るかもしれません。
今年の経験は、未来の点に繋がっているのです。
(知恵子)
[MY LOHAS]
Posted by nob : 2013年12月29日 00:23
私もこのところ毎日二欠け前後のビターチョコレートを摂るように、、、ずっと続けるつもりです。。。
◆チョコレートの薬効
原料のカカオ豆の学名「テオブロマ」は「神様の食べ物」という意味で、古代アステカの時代にはカカオを薬草と混ぜあわせ、歯痛、喉の炎症、胃腸・肝臓病、解熱、毒消しなど万能薬として治療に用いられていました。また、ヨーロッパでは昔薬屋で扱われており、薬として栄養源として珍重されていました。
カカオ豆に含まれるテオブロミンという成分は、カフェインと同じアルカノイドの一種で、カフェインほどの興奮作用はありませんが、大脳皮質を刺激し思考力を高めたり、やる気を起こしてくれます。また、強心剤や利尿剤としても効果があります。
他にカカオに含まれる体にいい成分には次のようなものがあります。
◎ココアバター
カカオからとれるココアバターには、天然の抗酸化物質が豊富に含まれており、コレステロールや中性脂肪を減らす効果があります。
◎食物繊維
カカオには納豆や切干大根より多い食物繊維が含まれており、便秘に効果があるため、大腸ガンの予防にもなります。特に、カカオの食物繊維には、便通をよくし、血中のコレステロ−ル値を下げる働きのあるリグニンという成分が多く含まれています。
◎カカオマスポリフェノール
カカオ豆に含まれるポリフェノールは抗酸化物質のなかでも高機能といわれ、発ガン、成人病や老化の防止に効果を発揮します。
ほかに、カルシウム、鉄、マグネシウム、カリウム、亜鉛などのミネラルも豊富です。
チョコレートは、カカオマスといわれるカカオ豆のペーストに、ココアバター、砂糖、牛乳を加えて作るため、牛乳のカルシウムがプラスされ、カルシウムとマグネシウムが2対1と理想的なバランスになるといわれています。
◆チョコレート効果
ポリフェノール含有量は、緑茶、赤ワイン各100cc中、0.1g、0.3gに対し、チョコは100g中0.8g(日本食品分析センター調べ)で、抗酸化パワーを期待できそう。ほかのチョコレートの健康効果もチェックしてみましょう。
カカオマスポリフェノールは悪玉コレステロールの酸化を防ぐとともに、コレステロールが血管内に沈着するのも防止するうえに、コレステロール値を下げる不飽和脂肪酸も含んでいるため、動脈効果を予防します。さらに、遺伝子の変異を防ぐため、ガン化した細胞の増殖も抑えます。また、さまざまな炎症を起こすヒスタミンを抑える効果があるため、免疫力も高めます。
脳のエネルギー源になるブドウ糖は脳に蓄えておく機能がないため、常に補給が必要です。砂糖を含むチョコレートは脳の働きを活発にするとともに、テオブロミンという成分でやる気を起こしてくれるため、深夜の受験勉強に最適。
ポリフェノールが虫歯も防ぎ、また、カカオ成分が虫歯の元凶の菌の抑制することも証明されています。チョコを食べると虫歯を心配する人もいますが、虫歯にしないためには、口の中に糖分を残さないことがポイント!
チョコレートは脂肪分が多いため、太るのでは、と心配をされる人も多いでしょう。しかし、大量に含まれるココアバターは吸収されにくい脂肪なので、通常 1gあたり9kcalで計算する脂肪は、チョコの場合は6.5kcalでOK。太るのはチョコ自体にあるのではなく、過剰に食べることで栄養のバランスが崩れ、糖分や油分の取り過ぎになるのが原因。また、鼻血、ニキビも根拠はありません。
チョコレートにはこんなに健康パワーが秘められています。遭難時に1枚のチョコレートで生き長らえたエピソードにも納得できます。食べ過ぎに気をつけてチョコレート効果を手に入れたいものですね。
Mica Okamoto
[FINE-club]
Posted by nob : 2013年12月27日 21:47
私は120歳までは元気に長生きしてみせます!?
■若く見える人のほうが
老けて見える人より長生きする!?
「アンチエイジング」は女性に限ったテーマではありません。男性もいつまでも若々しく元気なほうが魅力的。実際に「若く見える人のほうが、老けて見える人より長生き」という研究もあるほどで、「老化を考えること」は「健康を考えること」に直結します。そこでこの連載では、男性目線でのアンチエイジングとそれを支える食について考えていきます。連載の1回目である今回は、まず「男性の老化(エイジング)」について説明していきましょう。
大事なのは「何歳まで生きられるか」ではなく
「何歳まで元気に生きられるか」
「何となく疲れやすくなった」、「鏡を見ると老けたなあと思う」、「髪が抜けてきた」、「スポーツをやると運動能力が落ちていると感じる」……。これらはあんまり嬉しくない老化の自覚ですね。年齢を重ねるごとに身体の衰えが出てくるのは致し方のないことです。
日本人の平均寿命は、2012年の調査で男性79.94歳、女性86.41歳です。1960年の調査では男性65.32歳、女性70.19歳でした。50年ほどで男女とも約15年寿命が延びたことになります。
この平均寿命より、男性で7年、女性で9年短いと言われているのが、健康寿命です。介護などを必要とせず、元気に過ごせる寿命のことです。男性で73歳、女性で77歳となりますから、ずいぶん印象が変わりますね。平均寿命も大事ですが、皆さんにとってより関心があるのはこちらの寿命ではないでしょうか。この健康寿命を延ばすのが、アンチエイジング医学の目的ということになります。
「アンチエイジング医学」というと、老化防止や長寿の妙薬があるような印象を持たれるかもしれませんが、残念ながら発展途上の分野で分からないことの方が多いのです。つまり、「誰でもこれをすれば寿命が延びる、老化が防げる」とはっきり言い切ることができないのです。これをすると老化防止や寿命に対して効果が見られたと報告している研究はたくさんあるのですが、一方で効果がなかったという報告もあり、学問的にはまだ確立していないのが現状です。
ですから、本連載ではこの点を考慮したうえで、可能な限りわかりやすい形で読者のみなさんに情報をお知らせしたいと思います。
同い年でも
若く見える人と老けている人は何が違う?
さて、老化とは何でしょう?
老化を医学的に定義すると、身体の臓器や組織の機能と構造が低下し、恒常性が失われるプロセスということになります。
例えば、心臓は加齢とともに大きくなる一方、心筋の能力は低下します。腎臓は30歳くらいを頂点に重量が軽くなり、水分の代謝量は減ります。このほか、年齢とともに、肌、内臓、骨、筋肉などの機能は衰えていきます。
ただし、老化のペースは人により、また臓器によっても異なります。同じ45歳でも30代にしか見えない人もいれば、50代と間違われる人もいます。大方の人は30代に見られた方がいいですよね。
「見かけの若さは寿命と関係ないのでは?」と思われるかもしれません。ところが、デンマークの研究では、「若く見える人のほうが、老けて見える人より長生き」という結果が出ているのです。
30代男性の
更年期障害も増加中
見かけや自覚症状によってある程度身体の老化が把握できるかもしれませんが、これはあくまで一部に過ぎません。内臓や血管等の状態をみる各種の検査をして初めて、その人の老化がどの程度進んでいるのかが分かるのです。
例えば、次の四つの検査をすると大まかな老化進行が判定できます。
(1)PWVという、手と足での動脈硬化をはかる
(2)IMTという検査で、頸動脈のエコーから動脈硬化をはかる
(3)血中のDHEAという性ホルモンの量をはかる
(4)握力をはかる
いずれも加齢による変化が顕著に表れるものです。
この検査で、実年齢よりも老化が進行しているという結果が出れば早めに手を打つことです。意外と知られていませんが、30代の男性でも更年期障害が現れることがあり、男性ホルモンや(3)のDHEAの低下があるとそれが疑われます。そうなった場合、ホルモンを補うなどの対策を実施することで様々な症状が改善される可能性もあります。
老化に対してはこのように「自分の状況を知る」ことが、アンイチエイジングの第一歩なのです。
それでは、次回からは連載のテーマである、「アンチエイジングと食」について具体的にお話ししていきましょう。
久保 明
[東海大学医学部 抗加齢ドック教授/慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授]
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2013年12月27日 21:41
創造性=オリジナリティーへの段階的ステップだと、、、稀に天から唐突に降りてくることもあります。。。
■「何を考えるか」ではなく「どのように考えるか」。本当の創造力が身につく5つの考え方
ドイツ「Amazon Buy Vip」のマネージャーのAndreas von der Heydtsannさんは、この2年間ドイツでも一番素晴らしいテック系のクリエイティブマインドを持っている人たちと多く接してきました。最近、創造力を本当に身に付けるというのはどういうことか、ということから学んだ教訓のいくつかを、LinkedInで共有しました。Heydtさんは次のように言っています。
創造力を身につけるというのは、「何を考えるか」というより、「どのように考えるか」だということが分かりました。例をあげると以下のようなことです。
* 見方を変えろ。見方を変えれば変えるほど、より多様性が生まれ、より良くなる。
* ただ受け入れるのではなく、すべてに疑問を持て。
* 身近な問題をより抽象的にすることで一般化し大まかにとらえるか、問題の細部をより深く深く追求して根本的なところまで突き詰めろ。
* 問題を表す言葉や文章を変えて言い換えろ。どんな言葉でもいいので、自分の好きな言葉を使うこと。
* 正しいとか間違っているとかはない。全体から切り離せ。
5 Habits of Creative Masters | 99U
Tanner Christensen(訳:的野裕子)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2013年12月27日 08:18
言い得て妙。。。Vol.12
■もう一度シンプルに帰ろう。人生をより豊かに味わうための3つの再発見
私はバケーションが大好きです。バケーションは世界に対する見方を変えてくれます。最高にシンプルな、別のライフスタイルを送ることができるかもしれないと教えてくれます。
激しい出世競争の中で極端なストレスにさらされながら、大金を稼いで高価な物を買っている人はたくさんいます。私は、バケーション先のハワイのカウアイ島で1人のバリスタに出会いました。彼女の仕事は、地元の人たちとおしゃべりをしながら、飲み物を作ることです。仕事がない時は、1人で、もしくは友だちとビーチに行って、打ち寄せる波を眺めています。
もちろん、バリスタではそんなにお金は稼げません。しかし彼女の生活は、自分のものではない夢を追いかけて働き過ぎている人より、豊かでリラックスしています。働き過ぎの人は、バケーションで年に2週間ほどビーチに行きますが、その間も仕事の心配をしています。バリスタは、ほとんど毎日ビーチに行き、夕陽を見ながらサーフィンをしています。
誤解して欲しくないのは、私はどちらがより良い人生を送っているかを比べているのではありません。どこに住んでいても、何をしていても、生活の中にシンプルな美しさを見出すことはできると思います。バリスタの人生の方が「賢い人生」だとは思いません。現実に目を向ければ、彼女の老後は働き過ぎの人たちより厳しいかもしれません。しかし、彼女は自然に囲まれ、シンプルな文化で生活をしているので、都会より少しは楽でしょう。
私たちは、必要以上に生活を複雑にしているきらいがあります。今回は、よりシンプルな人生を再発見し、人生を味わう3つの方法を紹介します。
1. 自然を再発見する
映画『グラディエーター』の中で私が一番好きなシーンは、主役のラッセル・クロウが手で麦の穂を軽くなでるところです。広大な麦畑の中の小道は、彼の家につながっています。そのシーンは特に重要なものではありませんが、飾り気のない美しさを表しています。そよぐ麦の穂、それを手でなでる音、風のざわめき、一体となって揺らぐ麦畑、雲と麦の動きが織りなす様々な影、すべてが自然の神秘と驚異を運んできます。これぞ生命だと思いました。
おそらく、日々のつまらない仕事によって、私たちの感覚は徐々に破壊されているのでしょう。判で押したような同じ日が何年も続くと、何も感じなくなってしまうのでしょう。締め切りや生産性は、この世のシンプルな美しさに、子どものように驚いたり魅了されたりする感性を鈍らせていくのでしょう。
絶え間ない驚きや神秘は今でもそこにあります。手の中で枯れ葉がボロボロに崩れることでも気付くはずです。最後にそんな自然を感じたのはいつですか? 自然を感じるのに、年を取り過ぎるということはありません。
枯れ葉が崩れるのは、麦の穂を手でなでるほど良いものではないかもしれませんが、ほんの少しでも自然界を感じさせてくれます。
2. 想像力と創造力を再発見する
きれいに整理整頓された机の上にノートを広げ、頭に浮かんだワクワクするアイデアを、消えてしまう前に書き留めます。頭の中にとどまらず、それを現実に創り出すことができるのはすごいことです。私は、これが人間があらゆる形のアートを好む理由だと思います。アートは、人間はものを創り出すことができる、ということを思い出させてくれます。「思い出させてくれる」と言ったのは、人間誰しも子どもの頃はクリエイティブだからです。大人になるにつれ、世間のルールに従うことで、創造力は徐々に失われていきます。
大人が物語を書いたり、絵を描いたりしようとしないのは、自分はクリエイティブな人間じゃないと思い込んでいるからです。そう思い込んでいる間は、それは真実です。
ある出版社のCEOが、クリエイティブな社員とクリエイティブではない社員の違いを見極めるために、心理学者を雇いました。調査をし始めた1年後、その2つのグループにどんな違いを見つけたと思いますか?
クリエイティブなグループは、自分はクリエイティブだと思っており、そうでないグループは自分はクリエイティブだと思っていませんでした。最初の違いは、自分のことをクリエイティブだと思っているかどうかだけでした。その後、クリエイティブではないグループの社員が、創造性を育むコースを受講したところ、最初にクリエイティブだと思っていた社員よりも、もっとクリエイティブになったのです!
誰でもクリエイティブになることができます。このシンプルな法則と、人生を実りあるものにするクリエイティブな能力を再発見しましょう。物語を書いてみるもよし、誰かに語ってみるもよし。いたずら書きみたいな絵を描くのもいいです。大切な人のために楽しい冒険を創り出してみましょう。
3. シンプルさ(ミニマリズム)を再発見する
物を所有し続ける人がいる一方で、ミニマリズムの人も増えてます。私もミニマリズムに切り替えてから、頭の中がクリアになったことに気付きました。物をあまり持たないというシンプルさは、生活や人生における美しさを教えてくれます。身の回りが雑然としていないと、家族や友だちのような大事なものに、より意識を向けることができます。
ミニマリズムというのは、物を所有するのが嫌な訳ではありません(それは誤解です)。私は、ミニマリズムになってからの方が、自分の物をより大切にするようになったので、ミニマリズムが好きなのです。例えば、お気に入りのおもちゃを1つ持っている子どもと、おもちゃ箱いっぱいのおもちゃを持っている子どもがいたとします。おもちゃをたくさん持っている子どもより、1つだけおもちゃを持っている子どもの方が、おもちゃを大事にするはずです。
Stephen Guise(原文/訳:的野裕子)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2013年12月22日 08:02
ごく当たり前に暮らすということ。。。
■ストレス解消に効果大な5つの行動
師走の字の通り、まさに忙しく駆け抜け、そのまま忘年会へ突入。疲労困ぱいなビジネスパーソンの皆様、本当にお疲れ様です…。
折しも今年の年末年始は、最長9連休という人も多いみたい。せっかくならば、日々たまったストレスをすっきりリフレッシュしたいところですが、さて、何をすることがストレス解消につながりやすいのでしょう? 『部下をうつにしない上司の教科書』などの著書を持つ精神科医・作家の奥田弘美氏によると、以下の行為は特に効果が高いそう。
□その1「8時間以上、夜にグッスリ寝る」
8時間寝る、といっても「夜」寝ることが重要なポイント。夜に寝て、朝に日光を浴びることによって体内時計をリセットし、自律神経の働きも正常化できます。
□その2「自然のなかで過ごす」
自然あふれる環境のなかに身を置くと心身がリフレッシュするだけでなく、認知機能が向上するという研究結果もあるほど。自然は心にも恵みを与えてくれるのです。
□その3「好きな人と思いっきり遊ぶ」
それは恋人なのか、気の置けない仲間なのか。自分にとってストレスにならない大好きな人と、思いっきり好きなことをやるのがストレス解消にはやっぱり効果的。
□その4「有休をとって丸一日休む」
それができれば苦労しないのに…と思う人も少なくないでしょうが、やはり仕事は現代のビジネスパーソンの大きなストレス要因。皆が働いているなか休むという背徳感も、時には大切。時計を見ず、自分の好きなことに没頭する時間を作りましょう。
□その5「残業をせず家でゆっくり過ごす」
始業時間は決めても、終業時間は決めないビジネスパーソンは大多数。明日でも良いことは明日にして、No残業Dayを作りましょう。残業代が出ないという人は、よりストレスになっている可能性もあります。長時間働くことが、会社や上司への“がんばりアピール”と考えている人は、本当にその気持ちが伝わる職場環境なのか、自分の労働生産性とともに考え直しましょう。
年俸500万年の中堅社員がうつ病などで約半年間休職した場合、会社の売り上げ損失は約2000万円といわれています。奥田先生は、「自分のストレス度合いに合わせてリラックスすること、休むこと、楽しいことを取り入れることが大切です」と、自分のストレスを俯瞰することの大切さを説きます。ストレスをゼロにすることはできません。うまく付き合いながら、2014年もがんばりたいものですね。
[R25]
Posted by nob : 2013年12月20日 15:55
以前は本当に幸せになっている人を私も1人も観たことがありませんでした、、、そして今は一番幸せの近くにいると感じられる何人かを見つけることができました。。。
■「幸せになりたい」が実現しづらい理由
人とは、個性のある生き物である。人と違うのは当り前である。
たまたま「デザイナーとアーティスト」というカップルの間に産まれたわたしは、そう育ちました。
ところがこれは、日本では大変レアなケースだと思います。
最初の難関は、小学校でした。
授業は横並びを実践していたように思います。今でも印象的なのは、国語の時間です。幼稚園教育で「ひらがな」を習得していたわたしは、教科書が面白くてどんどん読み進めていました。歩いて回っていたい先生がそれに気づき、教科書のページを今「別の生徒が読み上げているページ」へと開き直させ、「みんなと一緒のところを読んでね」と言ったのです。
その後、授業は恐ろしく退屈なものになりました。
そうやってわたし達は小さな頃から、「みんなと同じである事」を教育されていたのです。
「みんなと同じこと」が、「良いことである」「善である」――それはあなたの興味関心よりも、あなたの楽しさよりも、重要なことなのよ。
それが、ここで受けた教育だったように思います。
わたしの世代は今40代になったばかり。子どもを教育する立場にあり、社会を推進する力であるはずのわたしたちの多くは、こういう教育を受けてきたのです。
5年程、いわゆる実社会において大企業で働いた後、わたしはフリーランサーとなり、その後、起業しました。当時は上司の言う通りにやろうと必死になり一生懸命、一生懸命やったのですが、結果心が壊れてしまって、心療内科へ通いました。
それから起業し、自社の仕事に平行して4年程の間、スピリチュアル業界を学びました。これもまた本当に言う通りに、うかつな自己解釈を挟まずに、素直に一生懸命、一生懸命やったのですが、結果身体が壊れてしまって、入院をしました。
わたしは本当に不思議に思っていました。
何がおかしいのだろう? どっちも幸せにならない。楽にもならない。それって...変じゃないか?!
病後は、つながりのある実社会と、スピリチュアル業界を両方眺めながら、自分の立ち位置を見極めようとしてきました。
なぜなら、そういう経緯があったので、双方にどこか違和感があったからです。
実社会には、スピリチュアルなことを毛嫌いする人がいますし、スピリチュアル業界には、実社会の諸々を毛嫌いする人がいます。
しかし、不思議なことに、共通点がありました。
みんな、「幸せになりたい」のです。
でも、どちらを観ていても、幸せそうな人はほとんどいませんでした。
本当に、ほとんど出会えなかったのです。
これまでに出会ってきた、幸せそうに見える人たちは、自然体で、穏やかで落ち着いていて、目の奥が澄んで輝いていた気がします。
何も言わなくても、かもし出す雰囲気が、すでに幸せそうです。
実際お話を伺うと「ご自身が満足をする」という意味で幸せな暮らしをなさっていました。
でもそれはどの業界に限ったことではなく、もっと言えばとの国に限ったことでもなく、
つまり外側の条件には左右されていなかったのです。
スピリチュアル業界の中で言われているモノの中には、これは本物だなあと感じる素晴らしいコンテンツはいくつもありました。
しかし、翻訳のせいなのか、例え話が面白過ぎるせいなのか、ちゃんと中身を読めている人が少ないように感じました。
なぜだろう...? 非常に不思議でした。
実社会でも、自己啓発は非常にニーズがあり、あらゆるところでセミナーが行われ、本も売れているのですが、それで本当に幸せになっている人を実は1人も観たことがありませんでした。
わたしの言う、幸せというのは「自然体で、穏やかで落ち着いていて、目の奥が澄んで輝いている。何も言わなくても幸せそう」という感じのことです。
なぜだろう...?
本当に不思議でした。
スピリチュアルにも自己啓発にも、
ここに、「本当のこと」は、あるのだろうか? と思えてならなかったのです。
観察をしました。
なぜ、みんな、幸せになりたいのに、幸せにならないのか?
何が原因なのか?
そうして徐々に見えてきた幸せな人の共通点は、人生の何処かのタイミングで、自分自身と深く向き合ったことがある人。
そしてその自分を受け入れている人。
だった、のです。
しかし。
自分に向き合うことで幸せになれるのだとしたら、なぜ、みんなそれが出来ないのか、が不思議です。
どうしてなのか長年解らなかった理由は、わたし自身が幼少からART教育を受けていて、自分と向き合うことが日常的だったからかもしれません。
それに気がついたのは、つい最近のことでした。
自分と向き合うことが難しい理由をリサーチしていると、「自分と向き合う」=「辛いこと」「苦しいこと」という先入観があることが解りました。
だから難しいのです。
そして、そうなっている背景には、心に刷り込まれてしまった「沢山の思考」のあることが見えてきました。
そうです!
わたしの頭の中もそうでした。
「〜すべき」「〜してはならない」「〜は悪だ」などなどなど。
「〜が幸せなこと」「〜は正しいこと」「〜は評価されること」などなどなど。
経験や実体験、あらゆる意味での教育がもたらしたおびただしい数の思考によってがんじがらめになっていて、自分と向き合おうとすると、必ず否定的な思考がやってくる時期があったのです!
「幸せ」は、そういう外側に与えられた条件によって派生する言動からは生まれ難く、自分の内側からやってくるものなのだよなあ...と今は思います。
みたけさやか
Faculty works Co, Ltd. 代表取締役、ストーン・コンシェルジュ、アクセサリー作家
[ハフィントンポスト]
Posted by nob : 2013年12月19日 14:12
言い得て妙。。。Vol.10/男と女の間には、、、 「友情(で結び付く関係)」は成立しうるけれども、、、 「友情だけ(で結び付く関係)」は成立しえない、、、と思う。。。Vol.2
■大人女子と子供おばさんの恋愛の違い
「男女の友情」を成立させる3つの心構え
「男女の友情」は信じない?
子供おばさんは、頑なに男女の友情は成立しないものだと思っています。 そもそも男友達がいないので、そういった関係は理解できないのです。
逆に大人女子は、気のおけない男友達がいて、同性の友達とも恋人とも違う関係を楽しんでいます。 だから、男女の友情は成立すると思っているし、そういう関係を築くための秘訣も知っているのです。
「男女の友情は成立するか?」というのは、永遠のテーマかもしれません。 ただ、「男女の友情は成立するか、しないのか」という判断をしがちですが、実際は、「成立させられる人とさせられない人がいる」と言えるのです。
では、男女の友情に大切なことは何でしょうか?
男女の友情に大切なこととは?
男女の友情を成立させられる人は、下記の3つのことができる人が多いです。
1.異性としてよりも、“人としての魅力”を大切にできる。
2.ほどよい距離感を保てる“理性”を持っている。
3.相手に“見返り”を求めない。
1つずつ、解説していきます。
1. “人としての魅力”を大切にできる?
そもそも、異性に性的な魅力ばかりを求める人にとっては、異性との友情は難しいものです。
異性ではなく、“人として”相手を好きになれる人でないと、相手を意識しすぎてしまい、気楽な友情関係は築けません。
つまり、自分だけではなく、相手の男性がこのタイプだと友達関係を築くのは難しいでしょう。
さらに、“男尊女卑”的な発想を持っている男性の場合、フェアな友達関係は難しかったりもします。
男女の友情に大切なのは、お互いの“人間力”です。
お互いに相手を魅力だと思わないと、友情を築くことは難しいものです。ただ、その魅力が、“男が喜ぶ女の魅力”“女が喜ぶ男の魅力”に過ぎないと、人として相手から惚れてもらうことはできません。
つまり、女性は“女を使わない魅力”がある人ほど、異性と友達になれるのです。
もちろんそれは、「女性らしい振る舞いをするな」という意味ではありません。“女を使う”のと“女性らしさ”は別物ですよ?
「信頼できる」「一緒にいて楽しい」「思いやりがある」「気が合う」など、同性の友達を作るときにも大切な魅力を持っている人は、異性の友達も作りやすいでしょう。
2. ほどよい距離感を保てる“理性”とは?
例えば、相手との距離感を間違え、肉体関係を持ってしまったら、それは“ただの友達”ではありません。
性別が違う限り、時には、性的欲求が沸いてくることもあるでしょう。 だからこそ、男女の友情には、ほどよい距離を保てる“理性”が必須です。
距離とは、「物理的な距離」と「精神的な距離」の両方を指します。
物理的な距離でいうと、当たり前ですが、会う場所には気を付ける必要があります。 個室で2人っきりなんてことになると、人によっては相手を異性として好きではなくても、性欲が沸いてしまう可能性もあるからです。
一心同体になりすぎない距離感
精神的な距離についは、男女の友情に限らず、同性間でも重要なことです。書籍「大人の友情」(河合隼雄・著 朝日新聞社刊)によると、友情で壊れやすい原因となるのが、“同一視”なのだそうです。
相手に対して一心同体だと思えるほどの友情を感じられるのは素晴らしいことですが、常に相手と同一状態だと、お互いの自立の障害にもなります。さらに、自分と同じような人間だと思えたとしても、実際は別の人間です。
同一視をすればするほど、違いを感じたときには、「思っていた人とは違った!」と落胆することもあるし、ときには「私よりも優れている。悔しい!」と嫉妬してしまいます。それが友情にヒビが入ることだってあるのです。
どんなに心の距離が近くなっても、相手と自分は違う人間だと認識できる、ほどよい距離感が大切です。
どんな人とであっても、「親しき仲にも礼儀あり」なのです。
3. 相手に“見返り”を求めてない?
例えば、男女の友達同士が友達ではいられなくなるきっかけで一番多いのが、「どちらか一方の恋心」です。
そうなったとき、どうして壊れるか?と言うと、相手に愛情の見返りを求めてしまう場合が多いからです。
もちろん、好きになったら、「相手にも好きになってもらいたい」と思うのは普通のことです。
でも、もし彼が友達以上の感情を持てない時は、きちんと元の距離感に戻れるかどうかが重要です。
それでも、彼に愛情を求めるようになると、相手も気持ちに応えられなくて気まずさを感じるため、関係は壊れ始めるのです。
一方に恋心があったら、友情は成立しない?
ただ、「相手に恋心を抱いていたら、友達関係が成立しないか?」というと、そうとも言い切れません。
「関係を深めない理性」(=相手が望む距離感を保つ)や、見返りを求めずに、ただ、ただ、相手を好きでいられる人は、友人関係を維持できるのです。
これは、恋をすると、「相手が自分のものにならなくては意味がない」と思ってしまう人には、難しいことでしょう。
でもそれは、子供っぽい恋愛観です。相手の望む距離感を保つことができない人は、友情を壊すどころか、エスカレートすると、ストーカー化してしまうので、要注意です。
男女の友情は、大人だからこそできる関係
若い時の男女間の友達関係は、相手との距離感を間違えたり、一方が好きになってしまって、愛を求めすぎたりして、壊れることは多いものです。だから、先ほどの3つが出来るためには、やはり“精神的に大人”の人ではないと難しいことかもしれません。
でも、異性の友達は、人生において、同性の友達とも恋人とも違う彩(いろどり)を与えてくれる存在です。
そんな関係が築ける、大人の女性になりたいものですね。
子供おばさん……男性とほどよい距離感を保てず、友達関係を築けない。
大人女子……人間力があり、ほどよい距離感を保つ理性があるので、「男女の友情」を深めることができる。
ひかり
コラムニスト・作家・フリー記者
[AM]
Posted by nob : 2013年12月19日 13:44
言い得て妙。。。Vol.9/納得こそがすべて。。。Vol.7
■大人女子と子供おばさんの恋愛の違い
同じ過ちを繰り返す人の口癖は「でも」「だって」「わかってる」
聞く耳を持てない人は要注意!
子供おばさんは、恋愛で同じような失敗を繰り返します。
似たようなダメ男に、何度もひっかかったり、依存心から相手を束縛し、嫌われてしまったり…。
それは、失恋を通して、自分が悪かったところを省みることなく、相手のせいにばかりにしているから、同じ失敗を繰り返してしまうのです。
大人女子は、失恋をすると、それをバネにして、より魅力的になります。
失恋を通して、人の痛みがより分かるようになったり、自分の依存心と向き合って精神的な自立ができるようになり、より良い恋を掴んだりします。
では、ここでの大人女子と子供おばさんの一番の違いは何でしょうか?
失恋での大人女子と子供おばさんの違い
今回の大人女子と子供おばさんの一番の違いは「自分が変われるか否か」ということです。
大人女子は、失恋を通して未熟な自分を見直し、変わることができますが、子供おばさんは相手のせいで済ましてしまうので、変われません。
実は、子供おばさんのように、変われない人の特徴としては、主にこの2つがあります。
・人の話が聞けない。
・性格が頑固。
この特徴があるからこそ、子供おばさんは同じような恋愛の失敗から抜け出せないと言えるでしょう。
人の話が聞けない子供おばさん
子供おばさんの周りにも、彼女のことを大事に思って、「こうした方がいいよ!」とアドバイスをくれる人もいるはずです。でも、子供おばさんは、「でも」「だって」と、言い訳ばかりをして、きちんと聞くことができません。
だから、相手の言葉が心に入っていかないので、同じことを繰り返してしまうのです。
結局、「でも」「だって」と、自分を正当化してしまうのは、自分の非を認められる、“心の強さ”がないからです。心は鍛えないと強くはなれません。誤魔化してないで、心をより強くするように努めましょう。
まずは、相手の言う言葉がどんなに耳の痛いことだとしても、グッと我慢をして、きちんと受け止めることが大切です。
相手は、あなたに嫌われるのを覚悟して、愛情を持って言ってくれているかもしれないのです。それを聞けないというのは、実はとても残念な行為です。
もちろん、中には腑に落ちないアドバイスをする人もいるかもしれません。
でも、そこには、自分でも気づかなかった自分の欠点を気づかせてくれるヒントもあるものなのです。
まずは、人のアドバイスに素直に聞き耳を持てるようになりましょう。
子供おばさんの性格は頑固
頑固になって、変わろうとしないと、状況は変わりません。
例えば、浮気癖のあるチャラ男ばかりを好きになってしまう人は、そろそろ相手の本質まできちんと見られるようにならないと、同じことを繰り返してしまいます。
「好きになってしまうのだからしょうがない!」で済ませていると、同じ失敗を繰り返してしまいます。
子供おばさんの中には、「分かっているけど、できません」と言う人もいます。
ハッキリ言ってしまえば、その人は、本当の意味で「分かってない」のです。分かってないから、変わることをしないで、同じ失敗を繰り返しているのです。
本当に理解するというのは、頭ではなく“心”からきちんとその事実を受け止めることです。
分かったふりをするのではなく、本当の意味で分からないと、変われないのです。
大人女子には柔軟性があります。
だから、頑なに相手のせいにしたり、「しょうがない!」「できない」と言って済ませたりすることはなく、自分の悪かったところを直す努力をします。
だからこそ、失恋をきっかけに、より魅力的になり、さらに幸せな恋を掴むことができるのです。
子供おばさんは、少しずつでもいいから、変われるための行動を取り入れてみましょう。
少しでも変わることで、見えることや気付くことも出てくると思いますよ?
変われる人は、より良い恋を掴む
「自分」が変われば、「環境」も変わるし、「相手」も変わります。
より自分が魅力的になれば、引き寄せる状況、人も変わってきます。
人は誰もが本気で変わろうと思えば、変われないことはありません。
変われない人は、まずは、「人の話を聞けるようになること」「少しずつでも変わるための行動を取り入れる」ことを目指してみましょうね。
きっと状況が変わり始めると思いますよ?
子供おばさん……人の話が聞けなくて、頑固なため、同じような失恋を繰り返す。
大人女子……失恋を通して、自分が変わる努力をするため、より良い恋を掴む。
ひかり
コラムニスト・作家・フリー記者
[AM]
Posted by nob : 2013年12月19日 13:27
言い得て妙。。。Vol.8/納得こそがすべて。。。Vol.6
■大人女子と子供おばさんの恋愛の違い
自分を幸せにすると「また会いたい人」になれる
また会いたくなる魅力って?
大人女子は、「また会いたい!」と思われます。
でも、子供おばさんは、そこまで思われません。その違いは何でしょうか?
子供おばさんは、人に楽しませてもらおう! 幸せにしてもらおう! と思いがちです。
自分で自分を楽しませ、幸せにすることができないので、相手に託すのです。
でも、大人女子は自分で自分を楽しませ、幸せにすることができます。
自分の心を幸せの状態に持っていける人は、余裕があるので、誰かと一緒にいるときは相手に合わせるし、相手を幸せにできます。
人は、一緒にいて、楽しい人、幸せになれる人の傍にいたいものです。
逆に不幸そうで、相手に幸せにしてもらおうと依存している人には近づきたくありません。
だから、子供おばさんからは人が離れていくし、大人女子には人が寄ってくるのです。
自分を幸せにするためには、常に自分の心の声を聞き、自分を受け止め、自分が幸せになることを叶えてあげることが大切です。
つまり、自分を幸せにできる人というのは、精神的に自立をしているのです。
人に上手に甘えることはあっても、心の松葉杖にして寄りかかったりはしません。
自分一人で立てる強さがあるからこそ、上手に相手に甘えたり、相手を楽しませたりすることができるのです。
◇
たまに「一人が平気になったら、出会いが遠のく」なんてことを言う人がいます。
ハッキリ言ってしまえば、それは自分を自分で受け止められない人の言い訳です。
精神的に自立をしている同士でないと、幸せな恋愛や結婚はできません。
でも、それは「本当の愛とはなにか?」を理解しなければ、分からないことです。
本当の愛は、求めるものではなく、与えるものです。 求めているうちは自己愛に過ぎません。
本物の愛情がなければ、その恋愛や結婚は、お互いに相手から奪い合う関係となるでしょう。それでは幸せにはなれません。
与えられる人になるためにも「精神的な自立」ができるようになる必要があるのです。
心を幸せな状態に置く秘訣は?
いつもHAPPYでいられる人は、目の前にある幸せを見つけるのが得意な人です。
例えば、楽しみにしていたデートが相手の都合で急になくなってしまったとき、子供おばさんはがっかりした気持ちで1日を過ごします。
でも、大人女子は、残念な思いはあるにしても、気持ちを切り替え、その分「他に好きなことができる」と思い、そのことに時間を費やします。結果、それなりに楽しい1日を過ごせるのです。
どんな状況にも必ずと言ってもいいくらいに、メリットとデメリットがあります。
何かを得れば、何かを失い、何かを失うときには、必ず何か他の可能性を得ているものなんです。
例えば、失恋したからって、地球上の男性がその人、たった1人のはずがありません。
もっと素敵な人と恋愛できるチャンスができた、と思えばいいのです。
仕事を失ったのであれば、もっと新たなチャレンジができるチャンスなのだと、今まであきらめていた夢をまた追いかけることだってできるのです。
大人女子はいつでも、失ったものではなく、得られるものに目を向けることができます。
だからこそ、いつでも前向きで機嫌がよく、HAPPYでいられるのです。
そんなポジティブ思考を持っていたら、一緒にいる人も幸せにすることができます。
例えば、楽しみにしていたレストランがお休みだったら、新たな美味しいお店を探して、「この店に出会うために、あのお店は休みだったんだね、ツイてるね!」なんて言えたりします。
常に自分の心を幸せの方に保てる力がある人は、人の心も幸せに持っていくことができるのです。
人に「会いたい」と思わせる人は、人を幸せにできる人です。
そのためにも、まずは自分で自分を幸せにし、心の状態を常にHAPPYに持っていけるように心がけましょうね。
子供おばさん……相手に幸せにしてもらおうと依存する。
大人女子……自分で自分を幸せにし、相手のことも幸せにする。
ひかり
コラムニスト・作家・フリー記者
[AM]
Posted by nob : 2013年12月19日 13:21
言い得て妙。。。Vol.7/納得こそがすべて。。。Vol.5
■大人女子と子供おばさんの恋愛の違い
他人と自分の幸せは別もの。あなたにとっての「幸せ」は?
人の幸せを妬んでばかりいない?
子供おばさんは、人と比べることで、自分の幸せをはかります。
だから、友達が自分よりも条件の良い恋人ができたり、自分よりも早く結婚したりすると、嫉妬します。
大人女子は、人と自分を比べません。自分にとっての幸せを知っているので、マイペースに幸せを掴むからです。
以前、こんなお悩み相談が来ました。
「一緒に婚活をしていた友達が、私よりも先に結婚します。嫉妬してしまい、祝福できません。どうしたらいいのでしょうか?」
そもそも、そのお友達は、相談者さんの意中の彼を奪って、結婚したのでしょうか?違いますよね?
だとしたら、彼女は相談者さんの幸せを奪ったわけではなく、彼女にとっての幸せを掴んだ、というだけのことです。
嫉妬している人が忘れがちなのが、「相手と自分の幸せは別物」だということです。
相手が幸せになることで、自分が不幸になるのであれば、それは祝福できないかもしれません。
でも、相手は相手の幸せを掴んだだけです。だったら、自分は自分の幸せを掴めばいいのではないでしょうか?
他人の幸せから、自分の幸せのヒントを掴もう!
また、この相談者さんがもう1つ見えてないことがあります。
それは、「何かを得れば、何かを失う」ということです。
既婚者の誰もが声を揃えて言うことといえば、「結婚に必要なのは、忍耐だ」ということ。
家庭を得ることで、人は自由を失ったり、忍耐が必要になったりするのです。
その背景も理解することができれば、嫉妬するどころか、お友達を応援したくなってくるのではないでしょうか?
人に嫉妬する人は、相手の表面的なところだけを見て、羨ましいと思いがちです。
でも、その背景には、大変なこともあるし、相手も努力していることも多々あるものなんです。
その相手が幸せを得るために頑張っていることには、自分も同じような幸せを得られるヒントがあるものです。
でも、その部分を見ることなく、表面的なところしか見られてないからこそ、自分は相手と同じ幸せを得られてない、とも言えるのです。
「自分にとっての幸せ」を見つめ、選び、掴むこと
そもそも人は、どうして人と比べるのでしょうか?それは、幸せではないからです。
そういう人は、相手よりも良い環境にいれば、幸せなのだと安心し、そうではないと、不幸なのだと思いがちです。
ただ、そもそも今、幸せな人は、わざわざ人と比べたりはしません。
そんなことをして、幸せをはからなくても、自分が幸せであることは分かっているからです。
幸せは人それぞれです。
女性の誰もが、結婚して、出産して、子育てをできたら幸せとは限りません。
自由な環境と経済力を持って生きるのが幸せな人だっています。
結婚にも育児にも仕事にも、人によって「向き・不向き」があるのです。
現代の女性は、人生の選択肢が増えました。
環境によっては、専業主婦になることもできるし、結婚して働くこともできるし、一生独身でキャリアウーマンとして生きていくことも可能です。
でも、選択肢が増えれば増えるほど、幸せを感じられない女性が多いのはなぜでしょうか?
それは、「自分にとっての幸せ」が見えていないからです。
自分にとって、好きなこと、嫌いなこと、得意なこと、苦手なことは、人によって違います。幸せも同様、人それぞれです。だからこそ、自分にとっての幸せを知り、掴めている人が、幸せになれるのです。
一昔前までは、女性は結婚をしたら、仕事を辞めるのが常識だったこともありました。
さらに前は、相手のことを好きだろうが、嫌いだろうが、結婚したいだろうが、したくないだろうが、お見合いをして結婚するのが常識の時代もありました。
そんなときは、「人生、そういうもの」だと諦めなくてはいけないこともあり、むしろ「自分にとっての幸せ」を知ってしまったら、苦しい人生になっていたかもしれません。
でも、現代は違います。自分で選べるのです。
ただ、自分にとっての幸せは、一般的な価値観に流されていたり、ボーッと受け身のまま人生を歩んでいたりしたら、見つかりません。
そうなると、選択肢が増えたことで迷い、隣の芝生ばかりが青く見えてしまい、幸せを感じられなくなるのです。
「自分らしさとはなにか?」を知るというのは、実はものすごく難しいことです。
自分の心ときちんと向き合わないと、なかなか分かることではないからです。
そんな難しいことを現代の女性は求められているのだから、人生の選択肢が増えて困惑している人がいるのも、納得はできます。
でも、これは人生において、とても重要な課題です。誰もが乗り越えるべきこととも言えます。
なぜなら、本来、人は自分らしさを持たない日々を過ごしていると、自分の人生に納得できなくなるので、幸せにはなれないからです。
「結婚」が幸せのカタチではない場合も
実は現代、結婚をしていない女性の中には、結婚に向いてないから結婚していない人も少なくありません。
無意識の言動が、独身でいることを選択している場合もあるのです。
(※人生に正しいも間違っているもないので、それが悪いと言っているわけではありませんよ?)
もちろん、そういった女性に、一生独身でいるべき!とは言いません。
ただ、お友達に嫉妬するよりも、まずは「自分にとっての本当の幸せは何なのか?」「自分が結婚向きになるためにはどうしたらいいのか?」をもう一度、考えてみてはどうでしょうか?
もし結婚するためには、自分らしさを捨てなくてはいけない場合は、「それでも結婚したいのか?」「それが自分にとっての本当の幸せなのか?」も考えてみましょう。
人生はいつだって、自分との戦いです。
相手と比べたところで、意味はありません。嫉妬したところで、不愉快な気持ちが自分の内側に増えるだけです。
自分にとっての幸せを知ることがカギとなる現代。
それができている人は幸せになり、逆にできてない人には、生きづらい時代になっています。
だからこそ、「他人」のことばかりを見て比べるよりも、「自分の内側」をよく見て、自分にとっての幸せを手に入れましょうね!
子供おばさん……人と比べて、自分の幸せをはかる。
大人女子……自分らしさを知り、自分にとっての幸せを掴む。
ひかり
コラムニスト・作家・フリー記者
[AM]
Posted by nob : 2013年12月19日 13:07
言い得て妙。。。Vol.6/納得こそがすべて。。。Vol.4
■大人女子と子供おばさんの恋愛の違い
不機嫌はうつる?周りに気を遣わせる“残念な女”
あなたの態度が不愉快な思いをさせてるかも!
子供おばさんは、ツイてないことがあると、関係ない人の前でも不機嫌な態度をとりがちです。それがオフィスであろうが、どこであろうが、機嫌の悪い顔を見せ、「機嫌が悪いのは、私の勝手でしょ!」と思っています。
でも実際は、周りの人にとって、関係ないことはありません。周りの人たちに不愉快な思いをさせていしまっているからです。
大人女子は、ツイてないことがあっても、自分の機嫌は自分でとります。だから、他の人の前では、機嫌が悪い顔は見せないし、むしろ感じの良い対応を心がけます。
そうすると、周りは彼女と一緒にいると気分がいいので、彼女はどこでも人気者になります。
大人であれば、自分の機嫌は自分でとり、周りに気を遣わせるのは止めましょう!
それは、“機嫌が悪い自分を構ってアピール”なので、子供っぽい行為なのです。
世の中は、うまくできていて、「自分がやったことは、自分に返ってくる」ようになっています。
人に幸せなものを与えている人は、周りからも幸せが返ってきます。その逆も然り。つまり、自分が不機嫌になって、周りに不愉快な思いをさせたときは、結果的に、自分に不愉快なことが返ってきてしまうのです。
だから、周りのためにも、自分のためにも、人の前では機嫌良くいられるようにしましょうね。
自分の機嫌をとる秘訣とは?
では、自分で自分の機嫌をとるためには、どうしたらいいでしょうか?
もちろん、「ツイてないことの根本的な解決をすること」は、前提です。
その上で、仕事中に嫌なことがあった場合、自分の機嫌をとることが上手な人はこういったことをしています。
・ランチのときに、ちょっと奮発して美味しいものを食べる。
・コーヒーショップやコンビニに行って、お気に入りドリンクやお菓子を買う。
・好きな人にメールする。
・週末の楽しい予定について考える。
など。
これらは、一旦、気持ちをツイてないところから切り離し、自分の気持ちを上げ、怒りや悲しみをクールダウンさせる方法です。
自分を機嫌良くする方法を自分なりに見つけておくといいでしょう。
周りにいる子供おばさんが機嫌悪かったら?
周りにいる子供おばさんの機嫌が悪い時は、どうすればいいでしょうか?
実は、これに悩んでいる人は少なくありません。
お人好しな人ほど、相手の機嫌をとろうとします。その結果、相手の不機嫌がうつり、自分までブルーな気分になったりします。それでは、本末転倒です!
相手の機嫌に引っ張られるくらいであれば、放っておきましょう。
相手は相手の都合で勝手に機嫌が悪いのだから、あなたはあなたで自分の機嫌をよくしておけばいいのです。
不機嫌な人が増えれば増えるほど、場の空気は悪くなり、周りの人が迷惑します。
機嫌が悪い人と同じ土俵に乗ると、自分の方が消耗してしまうことはよくあること。
引っ張られるくらいであれば、相手に影響を受けないように、「自分を守る」ことも大切ですよ?
子供おばさんに八つ当たりをされてしまったら…?
時には、機嫌の悪い子供おばさんに八つ当たりをされることもあるかもしれません。そんなときは理不尽さを感じるし、腹も立つことでしょう。でも、そんなときこそ、自分の機嫌をとることが大切です。
相手と同じ土俵に乗って反撃するよりは、「この人は理不尽なことをする人なのだ」と理解して、冷静に対応するようにしましょう。
世の中には色々な人がいます。どんな環境でも“残念な人”もいます。でも、自分がそんな残念な人になってはいけません!
自分で自分の機嫌をとれるようになって、周りの人に迷惑をかけないようにしましょうね。
子供おばさん……不機嫌を周りの人に当たり散らし、迷惑をかける。
大人女子……自分の機嫌は自分でとり、周りの人には人当たりよく接する。
ひかり
コラムニスト・作家・フリー記者
[AM]
Posted by nob : 2013年12月19日 13:00
言い得て妙。。。Vol.5/納得こそがすべて。。。Vol.3
■大人女子と子供おばさんの恋愛の違い
いつの間にか負担に?“かまって病”2つの症状
「恋人が、友達とばかり会って、自分との時間を作ってくれない!」そんな不満を抱いている女性は多いものです。でも、原因は自分にあるかもしれませんよ?
もしかして、“かまって病”ではありませんか?
子供おばさんの大半がかかっているのが、この“かまって病”です。
“かまって病”の人が恋を壊す2つの症状
<症状1:子供おばさんは、自分のことばかりを話題の中心に持っていきがち>
もちろん、その内容が相手にとって楽しい内容であれば、話は弾むでしょう。ただ、大概そういうときは、「私ってこういう人なの」「自分を分かってほしい」「受け止めてほしい」といった“自分のため”の会話が多く、話を聞いている相手にとってはどうでも良い話題のため、退屈してしまいます。
そんな相手の様子に気が付かずに、会う度にそんな会話を繰り返すようになると、恋人は段々会うのが億劫になってくるのです。
<症状2:子供おばさんは、恋人が会う回数が減らしてくると、気を惹こうと愛情をはかる行為をしがち>
「他の男性にデートに誘われちゃった!」と、自分を放っておいたら他の人に行ってしまうよ?といったアピールをし始めることもあります。わざと嫉妬心をあおるようなことをされると、大概、人は面倒くさくなってきて、相手のことが苦手になってきます。そんな子供っぽい行為に、うんざりし始めるのです。
それがきっかけで、恋人がさらに2人の距離を空けようとすることもあるでしょう。
そんなとき、子供おばさんは、「付き合い始めは優しかったのに、優しくなくなった。彼が心変わりをした」と相手のせいにしてしまいます。
いえ、いえ、いえ、これらは全て、自分で恋を壊してしまっているのです!
“かまってアピール”をされると、むしろかまいたくなくなる人は、少なくありません。つまり、「私に注目して!」と言えば言うほど、相手はあなたに注目しなくなるのです。
結局、「私を受け止めて」という思いは、相手に対する愛情ではなく、自己愛に過ぎません。だから、人は、そういった自己愛を投げられれば投げられるほど、うんざりしてしまうのです。
“かまってアピール”をしてしまう理由
では、どうして子供おばさんは、“かまってアピール”ばかりをしてしまうのでしょうか?
・寂しさを恋人の存在で埋めたいから。
・楽しみや幸せを自分で見出すことができず、恋人と過ごすことでしか得られないから。
など、色々な原因はありますが、根本的な原因は、
・人にかまってもらっているときにしか、自分の存在価値を実感できないから
というのがあるでしょう。だから、自分を受け止められようとして、アピールばかりしてしまうのです。
“かまって病”の人は、相手にかまってもらえれば、かまってもらえるほど、自分には魅力があり、それだけの価値がある人間なんだということを実感しようとします。だから、受け止めてくれる存在がいることで安心するのです。
大人女子は、“かまってアピール”をするよりも、むしろ相手がかまいたくなるような女性でいます。相手が受け止められる余裕がないときは、わざわざ自分のことをアピールしたりはしません。
逆に彼のことをよく受け止められるので、信頼されることが多く、結果、相手から「もっと君のことを知りたい」と興味を持たれるようになるのです。
どうして、大人女子はそんな人でいられるのでしょうか?
それは、基本、「自分のことは自分で受け止められている」からです。
自分の長所だけではなく、短所も含め、“ありのままの自分”を受け止め、信頼しているので、常に心は安定しています。だから、子供おばさんとは違って、わざわざ相手に受け止められることで安心しようとはしません。
また精神的な自立をしているため、恋人に依存をすることで、自分の楽しみや幸せを見出そうとはしません。
だからこそ、かまってもらってないときも、自分の力で幸せでいるし、逆に恋人と一緒にいるときは、相手が楽しめることは何か?を考えることもできるのです。
その結果、彼にとって、一緒にいると楽しくて心地よい相手となるので、彼は共に過ごす時間をさらに増やしたくなるのです。
“北風の子供おばさん”と“太陽の大人女子”
周りにいる“モテ大人女子”の恋愛を見ていると、彼の方がかまってほしいと彼女に寄ってきているパターンが多いです。彼女たちは、どうしてそんな関係が築けるのでしょうか?
彼女たちは、恋人が友達と遊びに行くときは、「楽しんで来てね!」と優しく見送ることができるのです。だからこそ、彼らは楽しいことがあればあるほど、彼女に報告したがるし、今度は彼女を一緒に連れていきたいと思うようになるのです。
逆に、子供おばさんは、恋人が自分と一緒ではないところで楽しんでいると、嫉妬します。
それでは、恋人は楽しかったことを彼女に話したがらないし、自分が悪いことをしてきたかのような罪悪感すら抱きます。
そんなときに、今度は彼女を連れて行こう!と思うかというと、逆に「面倒くさいからいいや」と思うことの方が多いでしょう。
要は、童話「北風と太陽」と同じです。
「私も一緒に遊びに連れていけ~!私をかまってくれ~!」と北風をピューピュー吹く子供おばさんは、むしろ相手にとって重荷な存在になります。
でも、「相手がハッピーなら私もハッピー」だと思っている大人女子は、「楽しんできてね!」と相手を温かく送り出すことができます。だからこそ、楽しい経験をした分だけ、彼にとって彼女は大切な存在となるし、「今度は彼女も連れて行きたい!」という気持ちになるのです。
“かまって病”は恋を壊す!
一緒にいても、自分のことばかりを話してつまらない。友達と遊びに行ったら、機嫌が悪くなる。そんな人が恋人だったら、付き合っていくうちに、だんだん息苦しくなってきます。
そろそろ“かまって病”を治しませんか?
“かまって病”の人は、相手から幸せをもらおうとばかりします。さらに、束縛することで、結果的に相手の幸せを奪ってしまいます。逆に、相手を見守れる人は、より幸せにすることができます。
どっちが相手に大切にされるかは、一目瞭然ですよね?
“かまって病”を治して、相手が一緒に過ごす時間を増やしたくなるような女性になりましょうね。
子供おばさん……“かまってアピール”ばかりをして、パートナーの幸せを奪う。
大人女子……パートナーを見守り、幸せにできるので、パートナーが大事にしてくれる。
ひかり
コラムニスト・作家・フリー記者
[AM]
Posted by nob : 2013年12月19日 12:52
言い得て妙。。。Vol.4/納得こそがすべて。。。Vol.2
■大人女子と子供おばさんの恋愛の違い
コンプレックスからの脱却!経験よりも大切な“幸せになる思考”
コンプレックスを感じて生きるのをやめませんか?
独身の子供おばさんは、自分が結婚していないこと、子供を産み育てていないことに負い目を感じます。
でも、独身の大人女子は、結婚していなくても、子供がいなくても、そこにコンプレックスを持たずに、独身であるという「今の経験」を大切にしています。
「経験していない」ことがコンプレックスに
実は、人にとって、「経験をしていない」ということがコンプレックスになることが多いのです。
例えば、大学に行っていない人は、社会人になってコンプレックスを持つことがあります。誰とも付き合ったことがない人は、恋愛経験がないことにコンプレックスを感じます。
結婚していない人は、独身であることに、子供がいない人は、子供を産み育てていないことにコンプレックスを持ちやすいです。
でも、逆を言えば、大学に行っていない人は、大学卒の人よりも早く社会に出る経験ができたと言えます。
誰とも付き合ったことがない人は、その分、“1人で過ごす時間”を経験しています。 結婚していない人は、独身である経験を、子供がいない人は、“自分のことに集中できる生活”を経験しています。
大人になれば、誰もが必ず経験しなくてはいけない出来事なんて、1つもありません。人生それぞれです。
ある出来事を経験しないということは、“その出来事を経験しないことで得られる経験”をしている、とも言えます。
ただ多くの人が経験していないことに関する素晴らしさは、経験した人しか分からないもの。だから、それが評価されることはあまりありません。
逆に、より多くの人が経験している出来事は、その素晴らしさをより多くの人が知っています。
だからこそ、そういった多くの人が経験している出来事を自分が経験していないと、コンプレックスを持つ人は少なくありません。
でも、自分は自分なりに、素敵な経験をしているはずです。
そこに気付かないと、いつまで経っても人と比べて劣等感を持ち、自信が持てない大人になってしまいます。
今の経験を大切に!
今ある環境の素晴らしさに気付けない人は、その環境だからこそできることを見落としがちになります。
例えば、子供がいなかったら、自分のためにより多くの時間が使えます。
自分を成長させるために本を読んだり、習い事を始めたり、趣味を充実させたり、気軽に旅に出たり、オシャレに時間を費やすことだってできます。仕事をバリバリできる時間だってあります。
大人になって、そんな自由な時間を与えられている経験は、とても素晴らしいことなんです。
そこに気付かないで、結婚していないこと、子供がいないことばかりに目を向けていたら、その人は輝けません。
経験以上に大切なのは、“幸せになる思考”
もし周りに「あなたは独身で可哀想ね」と言う人がいるとしたら、その人は“独身の幸せ”を知らないだけです。
そういう言葉に左右される分だけ、あなたも「独身ならではの時間をきちんと謳歌できていない」証拠とも言えます。
ただ、逆を言えば、今ある環境を楽しめない人は、どんな環境を手に入れたところで、楽しめる思考になっていないので楽しめません。結婚しても、子供が生まれても、それ自体が幸せになれるわけではありません。
“幸せになる思考”がある人は楽しめるし、そうではない人にとっては、「自分の時間がなくなった」とやみくもに嘆くようになってしまうでしょう。
どんな環境でも良いこと、悪いことがある
どんな環境にも必ずと言ってもいいくらいに、「良いこと」と「悪いこと」があります。
独身であることの「良いこと」と「悪いこと」もあれば、結婚していることでの「良いこと」と「悪いこと」、子供がいることの「良いこと」と「悪いこと」もあります。
でもどんなときにも、「良いこと」の方に目を向けられる人は、幸せになれるし、「悪いこと」ばかりを目に向ける人は、幸せにはなれません。
つまり、今独身で幸せではない人は、「結婚したら幸せになれる!」と思っているかもしれませんが、その思考のままだとなれないかもしれませんよ?
今できる経験を精いっぱいやるべし!
はじめの話に戻ると、人は「経験していない」ということにコンプレックスを持ちやすいものなのです。
だったら、時間とお金が許す限り、今できる経験を精いっぱいやることが大切です。
人生では諦めたことが多ければ多いほど、自分の人生に納得できません。納得できない人生を送っている人が、幸せなはずがないのです。
本当に結婚という経験が必要であれば、あれやこれやと言ってないで、お見合いでもなんでもすればいいのです。
子育ての経験が必要であれば、子供は自分の希望だけではできるものではありませんが、養子をもらうという選択肢だってあるでしょう。大学に行ってないことにコンプレックスを持っているのであれば、社会人になってからでも大学へ行けば良いのです。
時間がないなんてことは、言い訳にはなりません。
知り合いの社会人の方は、多忙な生活にも関わらず、自分のコンプレックスを克服しようと、働きながら大学受験をし、夜間学校へ通い、無事に卒業しました。
「社会人になってからの方が、勉強をやろうと思って授業を受けるから楽しかった」とすら、言っていました。つまり、「社会人になってから大学に行くこと」のメリットだってあるのです。
ただ、その後、「その大学生活の経験が実際の仕事に役立つか?」というと、そういうわけではないことにも気づいたようです。
つまり、「経験していないことが、そこまでコンプレックスを持つような出来事だったのか?」というと、そうではないことも多々あるものなんですよね。
でも、その方にとってその経験は、自分のコンプレックス解消には大いに役立ったようです。
それは人生において、とても重要なことです。
今だって、大事な経験をしている!
「経験していない」というコンプレックスを持つくらいであれば、経験すればいい。 本気でやれば、なにかしら叶えられる手段はあり、経験するのが可能なことは多いです。
でも、今だって、大事な経験をしていることは、忘れてはいけません。
その自分の経験がたとえ少数派だとしても、立派な経験なのです。今の環境だからこそできる経験を大切にし、充実した日々を送れるようになりたいものですね。
子供おばさん……自分が経験してないことばかりに目を向け、コンプレックスを持つ。
大人女子……自分の経験を大切にし、誇りに思う。
ひかり
コラムニスト・作家・フリー記者
[AM]
Posted by nob : 2013年12月19日 12:35
悟りとは、、、日々移ろい変わっていくもの、、、完全な満足を追い求め続けていく過程での、その時々の自らの在り様への納得と他の受容をいう。。。
■坊主も知らない仏教の落とし穴-対談:南 直哉×島田裕巳
青森県・下北半島にある「霊場」恐山。口寄せをする「イタコ」で有名だが、山内は曹洞宗の菩提寺が管理している。院代の南直哉師は、坐禅の聖地・永平寺で約20年修行し、恐山に転じた異色の経歴を持つ。オウム事件から「直葬」の是非まで。両極を知る禅僧と希代の宗教学者との初対談は白熱し、3時間超に及んだ――。
【南】はじめまして。恐山に、ようこそいらっしゃいました。
【島田】こちらこそ。東京から新幹線を乗り継いで片道6時間。だいぶ疲れましたが、山内に漂う硫黄の効果でしょうか。見学しているうちに疲れが和らぎました。
【南】硫黄の影響なのか、外から持ち込んだ植物はほとんど根付きません。例外は境内に1本残った桜ぐらいです。その代わり、寺の境内には4つの外湯があります。源泉掛け流しで、泉質は上等です。そもそもは湯治場として開かれた場所だといわれています。
【島田】さきほど本尊の地蔵菩薩(じぞうぼさつ)を見せていただきましたが、あんなに厳しい表情の地蔵菩薩は初めて見ました。むしろ修験道系の権現(ごんげん)(※注1)にも見えますね。
(※注1:修験道は各地の霊山を修行の場とする日本独特の宗教。神道と仏教が習合しており、神仏が仮の姿で現れた姿である「権現」を祀ることがある。)
【南】お目が高い。恐山の菩提寺は曹洞宗ですが、それは1530年からのことです。由緒には862年に慈覚大師・円仁(じかくたいし・えんにん)に開闢(かいびゃく)されたとあります。円仁は天台宗の3代目座主(ざす)で、天台宗は古くから修験道と結びついていました。修験道は山岳信仰が盛んでしたから、恐山もその影響があります。何度も大火にあっているため、歴史資料が残っておらず、事実としていつから本尊が地蔵菩薩となったのかも、本当のところは不明です。
【島田】南さんは1984年から約20年間、永平寺で修行されていますね。曹洞宗の大本山であり、「只管打坐(しかんたざ)」の修行道場です。そこから、イタコや死者供養で知られる恐山に移った。2つの寺は、曹洞宗、いや日本仏教の対極です。
【南】私が恐山に入ったのは、7年前のことです。大学を出て、西武百貨店に2年ほど勤めてから、「やはりサラリーマンは無理だ」と観念して、出家得度しました。入門時は「永平寺で死にたい」と思っていました。しかし厳しい修行も、数年もすれば慣れます。自己存在の危機を解決するすべはあるのか。それを突き詰めるために入門したのに、パターン化した生活の中で、行き詰まってきたちょうどその頃、恐山山主の長女との縁がありました。道元禅師(どうげんぜんじ)の750 回忌という節目もあり、下山することになりました。
【島田】2つの寺はオーソドックスな仏教の視点では対極にありますが、その一方で、いまの「仏教ブーム」、さらにいえば「スピリチュアルブーム」の中では、一括りにされています。恐山にも若い訪問客が増えているのではありませんか。
【南】特に最近は、若い女性が1人で来るというケースが目立ちます。おととい来られたバーテンダーだという女性は、「こんなところに1人で来ると、自殺志願者だと思われますね」と笑っていました。「仏教に関心があるのですか」と聞くと、「わからない」と答える。おそらく日常に漠然とした違和感があるのでしょう。でもその違和感を処理するツールが見つからない。何かの手がかりを探しに、ここまでやって来る。そんな感じです。
【島田】南さんが永平寺に入られたのは、ちょうどバブル崩壊の前ですね。
【南】入山から3年経つと坐禅指導をするようになります。80年代の後半ですね。その頃は、焦りや苛立ちを訴える人が多かった。漠然とした強い不安、といえばいいでしょうか。それがバブル景気が崩壊して、オウム真理教の事件が起きた頃から質的に変わりました。不安ではなく、自分自身に対する違和感とか、居場所のなさを強く意識する人が来る。若い世代に限らず、あらゆる世代がそうなんです。具体的にいえば、中年以上の男性が簡単に泣くようになりました。
【島田】中年男が泣くのですか。
【南】はい。昔の男性は痛いところを突くと、怒りました。いまは泣きます。彼らは「一生懸命働いて、昇進もし、家庭を持って息子も大きくなりました」ということを淡々と話します。昔だったら自信を持っていいことなのに、それができない。逆に、自分のやってきたことはこれでよかったのか、と疑っている。だから孤独で、寂しそうです。
「真理」や「悟り」がブームになる怖さ
【島田】もっと上の世代には、そういうことはないのですか。
【南】ありませんね。団塊世代より下の世代が持つ違和感に、ブームとしての仏教が受容されているのだと思います。私はそうした「仏教に救いを求める」という考え方は危ないと思います。伝統教団も、癒やしや救済の求めに、素直に応じてきた面がある。しかし私は、仏教のユニークさや有用性は、そうした「一発回答」を示さない点にこそあると考えています。
【島田】同感です。極論すると、いまの仏教はキリスト教ではないかと思っています。キリスト教の開祖であるイエス・キリストが、具体的に何を説いた人物なのかは、必ずしも明確ではありません。イエスが直接記した教典はなく、信徒がまとめた「福音書」は複数存在します。同じように、釈迦がどのような教えを説いたのか、確かなことはわかりません。釈迦の教えを記したという仏典は、無数にあり、どの仏典を聖典とするかは宗派によって異なります。いわば、すべての仏典は「偽経」ともいえます。
また仏教は発祥地のインドではほぼ消滅しています。たとえばサンスクリット語の般若心経は法隆寺にしかありません。「ブッディズム(=仏教)」という言葉自体、西洋で生まれたものです。いま我々が親しんでいる仏教は、釈迦の説いたものとは違い、1度キリスト教をもとに再構成されたものである可能性が高い。
【南】「いまの仏教はキリスト教ではないか」というのは衝撃的なフレーズですが、よくわかります。いま「日本の伝統」とか「東洋の思想」とされるものは、ほとんどが西洋のフィルターを通したものです。これは1度、根本的に解体してみないといけない。とくに近代以降の仏教は、西洋の思考で再構築されているという点は、忘れてはいけません。
【島田】「仏教ブーム」ではテーラワーダ・ブッディズム(スリランカ、タイなどで盛んな上座部(じょうざぶ)仏教)の人たちが注目を集めていますよね。僕はそれを「スピリチュアル・ブッディズム」と呼んでいます。釈迦の説いた正しい仏教を実践している、というのが宣伝文句ですが、「正しい仏教」というものはありえません。
【南】テーラワーダ仏教の人たちは「我々は仏教のプロだ」といいますね。彼らの教えでは、釈迦の教義や戒律、僧侶の訓練方法、すべてが確定している。そして、般若心経であろうと、彼らの決めた「原典」にないものは、すべて間違いだという。私には「絶対正しいことがある」という主張自体が、仏教の「諸行無常(しょぎょうむじょう)」(※注2)の否定だと思います。
(※注2:仏法の大綱である『三法印』の1つ。「諸行」とは、この世の一切の事物・現象のこと。「無常」とは、あらゆるものは常に移り変わるということ。)
【島田】キリスト教のやり方と同じです。
【南】そうです。私はよく講義の中で「世の中の思想には、仏教と仏教以外しかない」と挑発します。仏教以外のふつうの思想は「絶対に正しいものがある」という前提から出発します。一方、私が理解する仏教は「無条件に真理のようなものを提出することはできない」ということが根本にあります。だから「真理」とか「悟り」ということを無防備にいう人は信用できないんですよ。
【島田】そうした傾向は、日本の仏教の中にも浸透していますね。
「いまここがすべて」は×。根本は「人間はダメだ」
【南】私の学んできた仏教はどう考えてもヒューマニズムではありません。根本には「人間はダメだ」という見方がある。釈尊は「苦」だといいましたが、私なりにいえば、自己存在というのは死ぬまで治らない慢性病です。「無病息災」で楽になるというのは幻想で、「一病息災」で、どこまで切り抜けていけるか。ところが、一発で気持ちよくなれる「救済」を求めます。すると仏教の側も「それを出してみましょうか」となるのです。
【島田】仏教の最大の特徴は「悟り」という考え方にあると思います。キリスト教やイスラム教にはありません。絶対神につくられた人間が、現世で超越的なものをつかむという発想はないわけです。しかし、現代では「悟り」が「本当の真理をつかむこと」と誤解されていますね。
【南】近代以降の仏教は、そうした西洋の一神教的思考を前提にした枠組みが効きすぎていると思います。その点で注目すべきなのが、親鸞聖人(しんらんしょうにん)と道元禅師です。2人とも、「真理」や「悟り」を棚上げにする方法が似ています。親鸞聖人は、念仏という行為自体に意味を見出して、そこに自我を解体していく。一方、道元禅師は、坐禅という修行そのものに意味を見出して、そこに自我を解体していく。形而上学的な思想ではなく、実践の中に自我を溶かし込んでいくわけです。
【島田】「悟り」をキリスト教の「回心」として理解すると間違いますね。キリスト教の「回心」とは、自分が罪深い存在だということを認めて、神にすべてを委ねるという経験です。「回心」の経験は、周りの人に語ることができます。
【南】そうです。「回心」と違って、「悟り」は語ることができません。道元禅師は『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』(※注3)で、とにかく一般的にいう「悟り」にあたる「見性」というアイデアを戒めています。鈴木大拙(だいせつ)氏が強調しているような「悟りの体験」について、道元禅師は関心がなかったはずです。『正法眼蔵』が難解なのは、明確な結論を出すこと自体に拒否があるからだと思います。だからどこにも結論がなく、ただ言語の過激な運動だけがある。
(※注3:開祖・道元が著した曹洞宗の宗典。87巻の大著で、難解で知られる。曹洞宗の教団では「弁道話」巻までを現代語に翻訳。現在、公開準備中という。)
【島田】親鸞や道元の思想は「正解はない」という考え方ですよね。これは笑い話ですが、センター試験に「親鸞の説いた『悪人正機(あくにんしょうき)』とは」という問題が出てくる。おそらく道元も出てくるでしょうね。4択で正解を選べというのは――。
【南】無理でしょうね(笑)。
【島田】「そんなものだ」という記号に括られてしまっているわけですよね。
【南】道元禅師は何かをいい切ること自体に不信感があるのかなと思います。禅では「不立文字(ふりゅうもんじ)」とか「言詮不及(ごんせんふきゅう)」といいますね。真理とは、いい損なうことでしか自覚できない。たとえば「成仏」とは、成仏しようとすることだというわけです。成仏というのは「はい、ここで終わり。できました」ではなくて、成仏しようと努力する過程だというわけです。
このとき問題になるのは、この教えを一般の人に敷衍できるか、という点です。下手をすると、「いまここがすべてだから、その1点に集中して日々を生きるんだ」という単純な話になりかねません。
【島田】スティーブ・ジョブズが禅に影響されている、という話は、そういうことですよね。ヒッピー運動の中心的なスローガン「Be here now」と同じです。
トヨタと永平寺に共通「生活すべてが修行」
【南】「いまここがすべて」というのは、なぜか、と問いたいですね。それは神の椅子の位置を、自分の中に変えるだけです。ただし、たしかに仏教の「無我」とは、行為の中に自我を預けていくという思想です。だから行為の善悪についての倫理を示す必要があります。そうしなければ、「それはお国のため」「村のため」「会社のため」などと、仏教とは関係のない人間に方向を決められてしまう。仏教の立場で倫理を基礎づけることができないと、非常に危ないと思います。
【島田】日本の企業社会も、そうした構図をとってきました。その象徴がトヨタ自動車です。生産過程の中に自我を溶け込ませる。カイゼン運動という形で、それを奨励する。いまの日本の豊かさをつくった思想であり、ほかの国には絶対に真似ができないものだと思います。
【南】倫理を備えた実践体系の1つですね。
【島田】浄土系では「他力本願」といいますね。庶民的なレベルで実践しようとすれば、どうしたって「会社のため」となる。日本人は仏教の考え方をいかしながら、豊かな社会をつくり出す術を編み出してきたといえます。たとえば、それをある極北で支えているのが永平寺です。「生活すべてが修行」というあり方が、1つのモデルとして美化されています。
【南】そうですね。だいたい日本の禅宗の修行体系が固まったのは江戸期ぐらいで、永平寺の場合、現在のようになったのは戦後ぐらいでしょう。おそらく道元禅師の頃には、肩を叩く警策(きょうさく)はなく、読経(どきょう)さえなかったと思います。『正法眼蔵』には「看経(かんきん)」(※注4)という言葉がありますが、あれは黙読ですから。
(※注4:看経とは声を出さずに経文を読むこと。対して、声を出して読むことを読経や諷経(ふぎん)などと呼ぶ。)
【島田】なるほど。
【南】いまのイメージとは全然違うんです。「なぜ坐禅をするのですか」と問われて、道元禅師は「釈尊も、偉大な祖師方も、みんなやっているから、君もやってみたまえ」みたいに答えています。絶対的な何かについて語らないのは、さもありなんですね。
【島田】もう1つ。僕のいう「スピリチュアル・ブッディズム」の源流は、オウム真理教なんです。オウムはヨガとチベット仏教だということになっていますが、一方で麻原彰晃がやろうとしたことはテーラワーダです。彼はネパールに行ってチベット僧に会っているし、スリランカではテーラワーダの僧と対話しています。つまり麻原は、チベット密教とテーラワーダ仏教の統合を考えていました。
【南】麻原の犯罪と思想は、分けて考える必要がありますね。彼の言説を「あれは仏教ではない」と否定することは簡単ですが、それではダメです。仏教のユニークで強力なはずの言葉が弛緩しきったところに現れたのが麻原であり、あれを超える言説を日本の仏教者はいまだに持っていません。それは認めざるをえない。
【島田】事件のとき、どの宗派も「オウムは仏教ではない」といってしまいました。いまの「スピリチュアル・ブッディズム」が修行の結果として悟りを得るというのは、オウムと同じシステムですね。
【南】オウムの評価をめぐり、島田先生が厳しい立場に追い込まれるのをみて、伝統教団の怠慢ぶりを痛感しました。実際に、オウムの信者は永平寺に来ていましたからね。ほかの教団にもスパイのように信者を送り込んでいました。伝統教団は、オウムは仏教だと認めたうえで、それを消化しなくてはいけません。
映画『お葬式』の衝撃。坊主は「サービス業者」へ
【島田】伝統教団の弛緩について、南さんはいつ頃から始まったとお考えですか。
【南】入山してまもなく、嘘の外出許可を取って、伊丹十三監督の『お葬式』(※注5)という映画を観にいきました。「これは終わりの始まりだ」と思いました。最近では火葬場で読経するだけで、戒名もつけない「直葬(ちょくそう)」が急増しています。「葬式仏教」のリアリティーが失われていけば、伝統教団の経済基盤は大きく揺らぐ。檀家制度が崩れれば、いまある寺のうち7~8割はやっていけないでしょう。
(※注5:『お葬式』は1984年に公開された伊丹十三の初監督作品。脚本は、妻・宮本信子の父親の葬式で、伊丹が喪主となった実体験をもとに書き下ろされた。)
ただ、自然葬とか個人葬が従来の葬式に代わることになるかというと、そうではないと思います。弔いというのは、やってみないとわかりません。散骨したあとで、後悔するご遺族もいるわけです。
【島田】宗教の重要な役割は、いかに死を受け入れて、それを意味づけるかという点にあります。日本では仏教がそれを担ってきました。曹洞宗は葬式仏教の祖でもあります。だから、曹洞宗の葬式はいちばん丁寧で贅沢でもありますね。
【南】だからこそ、永平寺の修行も儀礼中心主義になっていて、いまや坐禅よりも儀礼が修行として重視されています。修行僧も、釈尊のような実存の危機があって入門してくる者は多くありません。結果、職業訓練所のようになる。僧侶になったから、たまたま住職になったというのではなく、住職になるために僧侶になろうというわけです。そうなると、出家すること、僧侶として生きること自体の意味を自覚する機会が失われてしまう。
「物の時代から心の時代に入るから、仏教が求められる」という物言いでは通じません。これからのお坊さんは、消費者に選ばれる「サービス業者」なんですよ。それを自覚しないといけない。ある若い修行僧に「寺なんて継がなくてもいい」といいました。おまえたちが継がなくても、本当に必要な寺だったら必ず続く。それよりも、そもそもなぜお坊さんをやるのか。どういうお坊さんになりたいのか。その腹を決めるのが先だ、と。
【島田】日本人は「生命の終わり」への関心が高いんですね。たとえば生命倫理に関して、西洋ではクローン技術など「生命の始まり」に関心を向けます。神による人類創造に関わるテーマだからです。一方、日本では脳死問題など、死に関することに敏感です。またキリスト教やイスラム教は幼少期に洗礼を受けます。仏教では死後に「戒名」を授かるのが一般的です。つまり、日本では人生のうしろのほうに宗教がある。だから、仏教の将来も、まだ時間の余裕があるはずです。
【南】それは卓見ですね。仏教は早急に結論を出すのは絶対にダメです。もし出せても、それは「暫定解」です。一神教的な考え方は、近代社会の1つの原理ですが、それについての疑問があるから、世界的に仏教への関心が高まっているのだと思います。これからは思想的にも社会的にも、ますます混乱していくでしょう。そのときに、焦ってはダメだというのが仏教の教えです。結論が出ないままにやっていく道を探れるかどうか。折り合いをつけて、やり過ごしながら、最後の落としどころまで持っていけるかどうか。それが大切になってくると思います。
青森県恐山菩提寺院代 南 直哉
1958年、長野県生まれ。早稲田大学文学部を卒業後、西武百貨店で勤務。84年に曹洞宗・永平寺で出家得度。約20年の修行生活を経て、2005年より恐山へ。福井県霊泉寺住職も務める。著書に『恐山』『自分をみつめる禅問答』『なぜこんなに生きにくいのか』『「正法眼蔵」を読む』『老師と少年』『語る禅僧』、共著に『人は死ぬから生きられる』などがある。
宗教学者 島田裕巳
1953年、東京都生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術センター特任研究員などを歴任。著書に『オウム真理教事件』『小説 日蓮』『神も仏も大好きな日本人』『戒名は、自分で決める』『葬式は、要らない』『日本の10大新宗教』『創価学会』『オウム なぜ宗教はテロリズムを生んだのか』などがある。
[PRESIDENT online]
Posted by nob : 2013年12月19日 10:27
自分が変われば世界は変わる、、、依存従属心が諸悪を生み出す根源。。。
■日本ではなぜ、「孝」より「忠」が上なのか?
「天職」志向のヨーロッパ人と「組織」志向の日本人
以前、リクルートの転職情報誌に『ベルーフ』という名の雑誌があったのをご存知でしょうか?
ベルーフとはドイツ語で「Beruf」と書き、「神から与えられた使命」を意味しています。すなわち、これが「天職」。この考え方の元になったのがプロテスタントの価値観で、よく働きよく貯蓄する彼らのおかげで資本主義が発達したと言われています。
天職志向の下では、1つの職業をコツコツと辛抱強く、長く続ける生き方が好まれます。ヨーロッパで職種別の組合が発達したのも、元を正せばこの天職を求める考え方に行き着く。
同じように1つの道を究めることが好きな日本人ですが、私たちの職業観・労働観はヨーロッパのそれとは微妙に異なっています。
では、具体的に何がどう違うのでしょうか?
武士の中途採用禁止がきっかけ?
日本人の労働観のルーツは戦国時代に
キリスト教におけるプロテスタンティズムはもともと、それまでのカソリック的価値観に対抗するものとして登場しました。カソリックは教会が非常に強い権力と権威を持っています。これに対してカルヴァン率いるプロテスタントたちは反発し、「天国に行きたければ、天から与えられた仕事を一生懸命にこなせば良い」と言った。そして、余ったお金は教会に寄付するのではなく貯蓄せよ、と説いたのです。
政治学者で社会学者のマックス・ウェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で指摘したことですが、資本主義はこの貯蓄奨励によって発達しました。みなが一生懸命に働いて貯金をしたために、余剰資金が設備投資へと回るようになった。これによって産業革命が起こりやすくなった、とも言われています。
製造業が発展するには、毎日、地味な作業をコツコツと続ける人が大勢いなくてはなりません。「一生懸命に働けば天国に行けるのだ」というプロテスタントの考え方は、この製造業の発達にも大いに貢献しました。功利主義ではなく、価値合理的、つまり「働くことはいいことだ」と信じて疑わない人々を大量に生んだという点でも、プロテスタンティズムはものづくりの発達に非常に重要な役割を果たした、と言えると思います。
翻って、日本の場合はどうか。歴史を遡れば、私たちが持っている労働観というのは戦国時代に端を発しています。
戦国武将の織田信長は、宗教を政治の敵であるとして徹底的に弾圧しました。次に出て来た豊臣秀吉は「検地・刀狩り」をして、農本主義を徹底することで中央集権体制を確立し、社会を安定させようとしました。
私たちの労働観を形成する元になったという意味で、秀吉はもう1つ、非常に重要な刑を制定しました。「奉公構(ほうこうかまい)」というものです。
奉公構は当時、切腹に次ぐ重刑でした。この重刑が示すのは、ほかの大名に一度でも仕えたことのある武士は、別の大名に仕えてはならないという規範。つまりは、武士の中途採用禁止令です。
武士というのはそれまで、自由に奉公先を変えることもできましたが、これによって武士は転職できなくなり、嫌でも、生涯一人の主に仕えるしかなくなってしまったのです。
江戸時代に「孝」と「忠」が逆転
明治の国民皆兵でみんな“サムライ”に
江戸時代に入ると、武士の世界では仏教に代わって儒教が重んじられるようになります。歴史の教科書にも出てくる有名な「寛政の改革」では、蘭学を否定し、朱子学を幕府公認の学問として定めました。学問吟味といい、家柄だけではなく、実力も大事だということで、旗本や御家人層を対象に漢学の筆記試験なども実施しています。就職活動で面接ばかりではなく、筆記試験で実力を測ろうとするのも、このあたりに起源があるのかも知れません。
じつはこの時、武士たちに儒教精神を徹底させるとともに非常に重要な“刷り込み”が行われました。社会を安定させるために、幕府は「孝」と「忠」を意識的に逆転させたのです。
どういうことか、詳しく説明しましょう。日本ではよく、儒教が重んじる5つの価値観を「仁」「義」「礼」「忠」「孝」の順番で唱えます。しかし、中国でも韓国でも、じつは「忠」より「孝」の方が上なのです。
「孝」とはつまり親孝行の孝ですから、家へのコミットメントを指す。「忠」というのは「殿」つまり、エンプロイヤー(雇い主)に対するコミットメントです。日本では、この2つの価値観の優先順位が逆転したことで、親よりもお殿様に仕えることが重要視されるようになりました。
明治に入ると、この刷り込みが庶民にまで普及していきます。きっかけはテクノロジーの発達と国民皆兵です。
テクノロジーの発達によって、それまでプロ同士の戦いだった戦争に大きな変化が起こりました。最新の銃や鉄砲を持つ素人が古い武器しか扱えないプロに勝ってしまったのです。これをきっかけに、戦争は国を挙げた総力戦へと変わっていきました。そして、国民がみな、兵士として駆り出されるようになったのです。
このことにより、武士だけに刷り込まれていた忠義の精神が庶民の間にも広まっていきます。その影響か、日本人は今でもなぜか「サムライ」が大好きです。考えてみたら、これはとてもおかしなことです。サムライは支配階級であり特権階級ですから、本来、その特権階級が持っていた価値観を支配される側の庶民が称賛して共有するなんていうのは、どうかしています。
むろん、日本人がそのような価値観を称賛するに至った理由はほかにもあるでしょう。その1つが、戦後の財閥解体です。
GHQが指導した財閥解体により、それまでの資本家が一掃されました。これにより、日本ではサラリーマン社長が登場した。サラリーマン社長は言わば使用人のトップです。したがって、日本では「会社はオーナーの所有物ではなく、私たち社員のものだ」という特有の会社家族観が形成されることになりました。「お殿様」に対する忠誠心が、「会社」という目に見えない組織への忠誠心へとすり替えられて行った訳です。
ほんの少し前まで、日本では1つの会社に勤めたらそこに一生勤め続けるのが良し、とされていました。ですから、組織の危機はそこで働く人々の危機にも直結する。組織に何か問題が起きてもそれを公表して改善しようとするのではなく、隠蔽して組織を守ろうという方向に力が働きがちなのも、そのせいなのです。
働き方を見直すヒントは
「沖縄」にあり
という訳で、ここまで、ヨーロッパと日本を比較しながらその労働観がいかにして形成されてきたのか、を書いてきました。
じつは、ヨーロッパでも「もはやプロテスタンティズム的な勤労観で働いていたのでは、社会の変化に対応できない」という声があがり、様々な働き方の見直しがされています。
ヨーロッパ内において、日本とよく似た状況にあった国がドイツでした。ドイツではこれまで、一部のエリートを除いて高校時点で職業を決定し、生涯、その職業に就き続けるという職人教育を徹底してきた訳ですが、その結果、IT革命に大きく出遅れてしまった。カルヴァン主義以来の伝統である「天職」志向が足かせとなり、キャリアの柔軟性が失われてしまっていたのです。
IT革命以降、逆に存在感を増しているのが日本とヨーロッパの間に位置する中間地域です。文化人類学者の梅棹忠夫さんが『文明の生態史観』で書いていますが、ヨーロッパと日本というのはユーラシア大陸の両端、つまりは辺境です。
この2つのエリアは辺境であったがために、異民族の支配や横暴な専制君主の支配をこれまであまり受けずに済みました(細かく言えばいろいろとあったのですが、ここでは相対的に見てそうだった、とのみ理解して下さい)。その結果、安定した労働観の刷り込みが可能になり製造業を発達させることができた。反対に、何度も異民族の支配に脅かされていた地域では、製造業が思うように発達せず、貿易や金融を中心に国づくりをするしかありませんでしたから、もともとアントレプレナーシップが非常に強い。
変化に対してどんどん柔軟に対応していきますし、身軽で冒険心もある。19世紀の産業革命以来と言われる革命に直面して、その違いが今、あらわになってきている訳です。
では、日本人はこれからどうすればいいのか、ということになりますが、時代の流れを逆行させることはできませんから、意識の方を変えていくしかない。ヨーロッパがこれまでの「天職」志向に基づく働き方を見直し始めたように、私たちもそろそろ「組織」に忠誠を誓う働き方を絶対視するのではなく、「忠」より「孝」を大事にする生き方を含めて大きくシフトしていかなければならないでしょう。
その時に1つの参考になるのが、沖縄の人たちの生き方です。沖縄はもともと「琉球王国」ですから、内地とは異なる文化を持っています。戦国時代は中国との貿易も盛んでしたし、1972年までアメリカ軍に占領されていた歴史的経緯もあり、内地と比べて「忠」より「孝」を重んじるアジア的な文化が色濃く残っています。幸か不幸か、輸出型製造業もほとんどありません。
私は最近、仕事でよく沖縄を訪れますが、沖縄の結婚式で最前列に座るのは新郎新婦の両親です。勤務先の偉い人はもっと後ろか末席。つまり、前から血の濃い順番に並ぶのが習わし。これは、台湾や中国でも同じです。
内地の会社が沖縄に進出するとたいてい、「沖縄の人たちは使いにくい」とこぼします。やれ、地域でお祭りがあるとか、ご先祖様の行事があるというと必ず休むというのです。しかし、「忠」より「孝」を重んじる価値観からすれば、これはむしろ、当然のこと。「組織」に忠誠を誓い、家族やコミュニティの中で過ごす時間を軽んじてきた、これまでの私たちの生き方の方が特殊だった、と見るべきです。
ですから、沖縄で成功できない企業がアジアで成功できる訳はない。もっと言えば、世界で勝つなんていうことは、とうてい無理な話です。自分たちの中にある「内なるアジア」を目覚めさせることが、これからの時代を生き抜く重要なヒントになると思います。
(文・構成/曲沼美恵)
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2013年12月18日 09:02
自らの生を救えるのはいつも自分自身だけ、、、死に方は生き方の完結。。。
■がん医療のタブー…効かない抗がん剤、寿命を縮める手術が横行するカラクリ
現在、日本人の死因1位であるがん。がん治療といえば、抗がん剤や外科手術が頭に浮かぶが、慶應義塾大学医学部講師で、昨年10月に『どうせ死ぬなら「がん」がいい』(宝島社新書/中村仁一共著)を上梓した近藤誠氏によると、こうした治療は寿命を縮めるだけではなく、多くの苦痛をもたらすという。
そんな近藤氏に、
「がん患者は、がんではなく“がん治療”で苦しむ」
「がんの9割に抗がん剤は無意味」
「がんの外科手術をしないほうが寿命が伸びる」
「なぜ病院・医者は、無意味だと知っていても、抗がん剤投与や手術をするのか?」
「人間ドックやがん検診で寿命が縮まる?」
などについて聞いた。
ーー本書は『どうせ死ぬなら「がん」がいい』と、かなり挑発的なタイトルですが、なぜ、死ぬならがんがいいのでしょうか?
近藤誠氏(以下、近藤) がんは、ほとんどの場合、最後まで患者の意識はしっかりしていますし、普通の生活を送れます。また、何よりも周りにかける迷惑の度合いが、他の病気と比べて低いので、家族などに惜しまれながら死んでいくことができます。日本人の死因でがんの次に多い心筋梗塞や脳卒中では、なかなかそうはいかない。例えば、脳卒中の場合などは半身不随になって、何年も寝たきりになる人も多いですね。そういう介護生活になると、本人も大変ですが、周りにも迷惑をかけてしまいます。
ーーしかし、「がんは痛い」というイメージがあります。
近藤 皆さんがそういうイメージを持たれているのは、抑えきれないほどの強烈な痛みや苦しみを伴い、のたうち回って死ぬと思われているからでしょう。そういう痛みや苦しみは治療から来るものであって、世間で思われているほどがんは痛くはありません。つまり、患者は手術で痛み、抗がん剤で苦しむわけです。そういう治療の痛みを、がんの痛みだと思ってしまうわけです。痛いのは治療するからですよ。そして不必要な手術をしたり、抗がん剤治療をするから、苦しい死、悲惨な死になってしまうのです。
病院経営という面から見ると、がんの治療というのは、すごく大きな割合を占めています。がんが怖いから病院に来たり、人間ドックを受けたりするわけですよね。でも、医者が「外科手術はほとんど無意味だから、放射線治療でいい」とか、「抗がん剤は効かない」「がん検診や人間ドックは受ける必要がない」というようなことを言い始めたら、誰も病院に来なくなり、治療の数も減って、つぶれる病院がたくさん出てしまいます。だから、医者はそういうことを知っていても誰も言わないわけです。
それから、痛みという意味では、治療を受けて当面延命できた場合には、どこかに転移している病巣が育つ時間を与えるということです。つまり、「骨に転移が出て痛い」「脳に転移して麻痺が出た」というようなことにつながるわけです。これも、やはり治療したがゆえの痛みであり、苦しみです。
ーー外科手術でがんを切り取らないほうが、長生きできるのですか?
近藤 胃がんで外科手術というのは、間違っていると思います。とにかく食事がとれていれば胃がんでは死にません。でも、歴史的に外科医が治療に当たってきましたから、「がんというと外科手術」という風潮がまだ残っているわけです。そして、それを疑わない人が多い。固形がんの治療は、痛みが現れたときに、それを抑えたり、QOL(Quality of life:生活の質)を維持するために緩和的な治療をすればいいと思います。
ーーそれは若い人にも言えることですか?
近藤 若い人こそ先が長いのですから、QOLが高い治療を選ばないといけませんね。「まだ若いのだから、徹底的にやりましょう」と言う医者がいますが、これは罠です。徹底的にやると、臓器を全部摘出されてしまいますよ。気をつけてください。
●固形がんに抗がん剤は効かない?
ーー「がんには、抗がん剤を使うのが当たり前」と思っている人が多いと思います。
近藤 間違えないようにしないといけないのは、がんには血液がんと固形がんの2種類あって、固形がんというのは、胃がん、肺がん、肝臓がん、大腸がん、乳がんのような塊をつくるがんです。このような日本人がよくかかるがんには、抗がん剤は効かない。でも、急性白血病や悪性リンパ腫のような血液がんには効果があります。先日亡くなられた市川団十郎さんが急性前骨髄球性白血病と診断されたのは、2004年でしたね。昔ならだいたい半年くらいで亡くなられていたと思います。団十郎さんの場合も治ったわけではなくて、延命効果ですけれども、それにしてもやはり10年近くも長生きできたというのは、抗がん剤の効果もあったと考えなければいけない。
ーー本の中で、9割の人はがんという病気そのものではなく、治療に苦しめられているとも書かれていますね。
近藤 寿命を縮めるがん治療というのは、すごく多いのです。中村勘三郎さんの場合が典型的ですね。勘三郎さんの場合には、人間ドックでがんが見つかったわけですが、それまではなんの自覚症状もなかったと聞きます。いずれは食べ物などがのどを通りにくいというような自覚症状が出たと思いますが、治療をせずに放置しておけば、あと2~3年は生きられたでしょう。もちろん4月の新歌舞伎座のこけら落としにも出演できました。がん検診を受けてがんが見つかると治療に走ってしまう、これは多くの人が陥りやすい間違いなのです。自覚症状が出てから医者にかかれば十分です。
ーーがんと診断されたら、どのように治療すればいいのでしょうか?
近藤 早期発見努力をせずに、例えば肺がんであれば少し呼吸が苦しいとか、食道がんや胃がんは食べ物が通らないとか、そのような自覚症状が出てがんが見つかった場合は、それは「がんもどき」ではなく、本物のがんですね。それに対しては体が一番楽な治療、つまり外科手術は避け、臓器を残す非手術的な治療を選ぶことです。
選択の道は2つあります。例えば食道がんだと、1つは、食べられなくなっても完全放置することです。そうすると、最後には水も飲めなくなって餓死することになります。健康な人が食べたいのに食べられないというのは悲惨ですが、体が衰弱して食べようと思っても無理というときには、心理的な飢餓感は少なくなるようです。この道を選ぶのはなかなか難しいのですが、体は楽なまま死ねます。
もう1つの道は、放射線治療を選択する道です。食事をすることができるようにもなりますし、長生きできる。それに臓器を残すわけですから、QOL、生活の質の面でもいいですね。12時間もかかる、開胸・開腹手術をしなくても済みます。しかも、比較試験の結果を見れば、外科手術より放射線治療のほうが成績がいい、治療で死ぬ人が少ないというのははっきりしているのです。比較試験というのは、外科手術を受けたグループと放射線治療を受けたグループの2つに分けて、それぞれを5年後の生存率などいろいろな観点から比較するものですが、試験結果は論文などで公表されていますから、外科医も当然知っているはずですよ。
●病院・製薬会社・厚労省のタブー
ーーそうした事実を知りながらも、なぜ病院はがん患者に対し、抗がん剤投与や外科手術を行うのですか?
近藤 まず病院側は、先ほども申し上げた通り、病院経営の大きな部分を、がん検診や抗がん剤投与、外科手術をはじめとするがん治療が占めている。外科医は、手術をしなければ、自分のよって立つものがなくなってしまう。製薬会社にとっても、抗がん剤は大きな収益をもたらせる。そして厚生労働省はこうした現状を是認しているし、基本的には病院、製薬会社寄りの立場です。つまり、外科手術や抗がん剤を否定することは、病院・製薬会社・厚労省にとってタブーともいえます。
ーーそのタブーを侵した近藤さんに対し、圧力がかかったりすることはないのでしょうか?
近藤 20年ほど前、月刊誌「文藝春秋」(文藝春秋)に『がん検診・百害あって一利なし』を載せた際は、病院の上層部から呼び出されて、「謝罪しろ」と言われたりしました。また、今でも肩書は講師のままで、出世させないなどという程度の措置は受けていますが、それ以上の圧力をどこからか受けたりするようなことはありません。また、私の主張は論文やデータに基づいていますので、正面切って反論してくる人もいません。
ーー外科医の方々は、実際に自身や家族ががんになっても、手術をするのですか?
近藤 普段がん患者の手術を行っている外科医でも、自分や母親ががんになると、手術ではなく放射線治療にするケースは多いですよ。
●がん検査で発がん率上昇?
ーーCTスキャンなどを使った検査が原因の発がん死亡率は、日本が世界一だと書かれていますね。
近藤 これほど国民に被曝させている国はないですね。原発事故での被曝量が問題になったときに、特攻隊の隊長さんが27ミリシーベルトの放射線を浴びて問題になりました。ですが、CT検査を受けると普通は20〜30ミリシーベルト程度は被曝しますし、多い人だと50〜100ミリシーベルトの人もいます。CT検査を受けたことで、5~10%くらいは発がんしている可能性があります。10年以上前にイギリスで出された報告では、すでに日本人のがん死亡の3%くらいは、放射線によるものだと推定されました。
ーーがんを予防するには、どのようにすればよいのでしょうか?
近藤 喫煙者は禁煙することです。それから規則正しい生活を送り、適量のバランスがとれた食事をとるのが一番だと思いますね。太りすぎもよくないし、痩せすぎもよくない。メタボと騒がれていますが、ちょっとくらいメタボでも、それほど寿命が短いわけではありません。それから、「長生きしたければ、肉を食べるな」と言う人もいますが、そういうことをしたら逆に寿命を短くしてしまいます。肉ではないにしても、魚や卵など、良質のタンパク質は必要です。
人間は、何万年、何十万年にわたって、炭水化物、野菜、あるいは動物性タンパク質を食べて生きてきました。そして、それに適応して今の体があるわけです。ある特定の食べ物を長く断つと、体にゆがみやきしみを生じることがありますね。
ーー一般にがん予防というと、がん検診や人間ドックが頭に浮かびます。
近藤 がんの中には、大きくならず、あるいは放っておくと消えてしまうものがあります。こういうものを「がんもどき」と言っているのですが、痛い、苦しいなど日常生活で不便を感じる症状がなく、検査や人間ドックなどで見つかるがんは、ほとんど「がんもどき」です。つまり、がん検診や人間ドックなどの早期発見努力をしてがんを無理やり見つけ出すから、放っておけば消えてしまうがんもどきのために臓器を失って苦しむことになるわけです。
死ぬまで気づかずに共存共生できるがんというのは、たくさんあります。50歳以上の男性では、50%以上の人が前立腺がんを持っていますが、普通は気づきませんね。前立腺がんが原因で亡くなる男性は1%しかいない。胃がんでも大腸がんでも、同じような傾向があります。
ーーしかし、会社員は年1回の健康診断を受けなければなりません
近藤 私は、定期的に健康診断を受けさせるのは、人権侵害だと思っているのです。健康診断を義務づけている国は日本以外にありません。でも、そういうことを主張して会社と闘うのは難しいでしょうから、健康診断を受ける際には、がんが発見されそうなものはなるべくやめる。身長、体重、視力を測って、それで済めばそれだけにしておくのが一番ですね。採血検査、それから胃のレントゲンや胸部レントゲンとか、とにかくがんが発見されそうなものはなるべく省く。そうすると、はるかに長生きできますよ。
(構成=編集部)
[Business Journal]
■全身がん告白の樹木希林、転移は13個所に…お酒は飲んでも、治療薬は飲まない?
最近、芸能界のご意見番になりつつある樹木。オセロ・中島知子の洗脳騒動が起きたときには、中島が家賃を滞納したマンションのオーナーが娘夫婦であったこともあり、カメラ前に登場しコメント。30年以上別居生活を続ける夫の内田裕也が交際していた女性とトラブルを起こし逮捕された際にも、カメラ前に登場した。そして、今月8日に行われた「日本アカデミー賞」では、映画『わが母の記』で最優秀主演女優賞を獲得したが、その壇上で「全身がん」であることを衝撃告白。新潮では、その樹木に直撃インタビューをしている。
インタビューによると、樹木は04年に乳がんを患い、翌年には右乳房を全摘手術。08年頃には、腸や副腎、脊髄にがんが転移し、13個所を放射線照射で治療したという。しかし、現在もお酒を飲み続けており、さらにはがんの治療薬を飲んでいないことを告白している。
薬を飲まないのは、樹木が信仰する新興宗教の影響との噂もあるが、それにしても、なんら治療をしなくて大丈夫なのか、それなのになぜあんな元気そうなのかとの疑問がわく。『がん放置療法のすすめ』(文春新書)などの著書がある、慶応大学医学部放射線科の近藤誠医師に筆者が聞いてみると、「抗がん剤に延命効果はないので、副作用のことを考えると抗がん剤を飲まないのがベターではないでしょうか。またがんは転移した箇所だけに問題が発生する。通常、がんは脳や肺、肝臓、骨に転移し、筋肉や心臓には転移しません。樹木さんの現在の病状はわかりませんが、比較的末期のがん患者さんでも元気であることも珍しくない」という。
抗がん剤は、副作用が強いわりには、約20パーセントの患者にしか効果がないとの報道もある一方、がん治療をめぐっては、近藤氏などとは対立する“抗がん剤推奨派”の医師も多く、医学界でも議論は紛糾している。
樹木の病状はわからないが、いずれにせよ「全身がん」という言葉からは想像もつかないほどかくしゃくとした彼女の姿が、我々のがんに対する認識が揺るがしたことは間違いない。
[Business Journal]
Posted by nob : 2013年12月16日 08:45
トイレ掃除は鬱にも効きます。。。
■便器は顔が映るくらいピカピカに! トイレ掃除をする女子は「3つの美人」になります!
人のおうちにお呼ばれしたときに、そのおうちのトイレが汚かったりすると心底ガッカリしますよね。
「トイレの掃除事情」について花王株式会社が実施した調査結果を見ても「人の家に招かれたときに汚れているかどうか気になる場所の第1位はトイレ」という結果が発表されています。
しかしながら、招くほうはというと……
「人を招いて自宅でパーティーをする前の掃除実施状況」で、トイレはなんと7位!
わりと多くの人が、トイレ掃除をしないまま、人を招き入れているわけです。ビックリ!
あなたのおトイレ、お客様は注目していますよ!
トイレ掃除をしっかりすることで、女子は、美人になります。美人と言ってもいろんな美人がありますが、いったいなに美人になれるのか? ご紹介したいと思います。
1:「家主のココロもピカピカ」おもてなし美人
お客様をお迎えすることが決まったら、リビングなど目につくところばかりに目を奪われて、時間に余裕があったらトイレ掃除……という優先順位のつけ方になっていませんか?
まずトイレ掃除をする習慣を身につけましょう。お店などでも、いいお店ってトイレがピカピカですよね! そしてどことなく信頼がおける感じがしますよね。
逆にお掃除が甘いと、二度と足を運びたくない! と思ったりしますよね。
お客様に心から楽しんでいただくためにしっかり手を抜かず頑張りましょう! お客様が感じる「楽しい」は、「一番大変そうなところをキレイにしてくれている」という「感謝の気持ち」の延長線上にあったりもします。それは、とりもなおさず、こちらの「おもてなし」の心が、お客様にまっすぐに伝わったということ。
おもてなし美人を目指しましょ!
2:水まわりは「人体の流れと同じ」風水美人
風水ではトイレは「食べて排泄する」という生命を維持するプロセスにおいて大事な場所とされています。穢れを流す水の空間を綺麗に保てる人は、風水の観点においても快適生活美人です。
風水は宗教ではなく、「いかに気持ちよく暮らせるか」という「気」をテーマにしたものですから、トイレ掃除をすることで、「気」美人あらため「風水美人」になれるというわけです。
3:いわずもがなの健康美人
トイレ掃除を頑張ると美人な子供が産まれると昔から言われています。
じつはこれ、トイレが綺麗→リラックスしてお手洗いを使用できる→カラダの老廃物が溜まらない→お肌つるつる(健康になる)→健康で美人な子供を産めるというカラクリなんです!
おトイレ掃除上手なアナタ、健康美人です!
いかがでしたか? 花王株式会社は2013年の年末おそうじの提案としてクリスマス前大掃除を掲げ「ハッピークリスマスクリーニング」を推奨しており、そのホームページのなかには、楽チンにできるトイレ掃除の方法も紹介されていますので、ぜひ参考になさってみてはいかがでしょうか。
トイレ掃除。大変なことのように思えて、じつは素敵な美人になれるんです! 毎日ちょっとずつトイレ掃除をがんばってみませんか?
【参考】
※ 花王株式会社 『意外な事実!人の家で汚れが気になる場所1位はトイレなのに、自宅への来客時にはトイレ掃除をしていない実態が明らかに。』
青山 愛里
[ANGIE]
Posted by nob : 2013年12月14日 23:09
理にかなっていますので、、、レパートリーに加えてみたいと思います。。。
■二日酔いの頭痛を和らげるには、足浴ケアがいい
忘年会続きの疲れや飲み過ぎによる、翌日のキリキリとした頭痛。お酒を飲んでいる時は楽しくて、ついペースがあがってしまうものの、翌朝はこんな症状に悩まされる――。頭痛薬を飲んでも頭が重く感じるようなら、ある簡単なケアをプラスする手があります。
二日酔いで頭痛が起きるメカニズム
まず、なぜ二日酔いで頭痛に悩まされるのでしょうか。原因は「アセトアルデヒド」という物質だと言われています。摂取したアルコールは、肝臓でアセトアルデヒドに分解されたのち体外に排出されます。しかし大量にアルコールを摂取すると、血液中にアセトアルデヒドが残り、脳内の血管の周囲の神経を刺激してしまいます。これが、二日酔いで頭痛が引き起こされるメカニズムです。そこで試してみるとよいと言われている方法は以下の2つ。
足浴で血行促進
まずは、足浴で全身の血液の巡りを良くすること。足の血液を温めることで、脳の血管を圧迫していた血液の流れが良くなり、頭痛を和らげてくれます。無理して汗をかこうと全身浴をするのは、かえって危険につながることがあるので注意が必要です。
白湯におろしたてのショウガを入れる
2つ目は、白湯におろしたてのショウガを小さじ1杯加えて飲むこと。体を内側から温め血液の巡りがよくなるので、頭痛を和らげる効果が期待できます。また、ゆっくりと温かい飲み物を飲む行為は、リラックス効果も得らるのでおすすめです。
忘年会や新年会など、お酒に触れる機会が多くなる年末年始。飲み過ぎに気をつける一方で、いざという時は二日酔いの対処法を思い出してみてください。
[TopSante.com]
下野真緒
南仏在住ジャーナリスト/エディター
[cafeglobe]
Posted by nob : 2013年12月13日 20:13
そのくらいに本当にやりたいことを見つけることは難しい。。。Vol.2
■ふつ~に生きてちゃわからないこと ~「“好き”を仕事に!」なんてありえねぇ!~
じぶんでタイトルを書いていて、こう言うのもなんですが、ふつ~に生きるの「ふつ~」が、よくわかりません。
代官山に住んでいて、大手の出版社に勤務している女性(29歳・独身)はふつ~なのか?
立川市に住んでいて、小さなIT企業に勤務している女性(31歳・既婚)はふつ~なのか?
ど~なんでしょ。
あまり普通ではない(一般的ではない)生き方に、「じぶんが好きなこと、かつ、得意なことを仕事にして生きる」というものがあると思います。
わりと多くの女性が「私らしい仕事をしたい」とか「仕事をとおして自己実現したい」などと言っているようですが、ようするに「じぶんが好きなこと、かつ、得意なことを仕事にして」生きていきたいということではないかと思われます(ちがう?)。
たしかに「じぶんが好きなこと、かつ、得意なことを仕事にする」のは、むつかしい。実力も必要だし、運が良くないと「趣味」にはなっても「仕事」にはならない。
実力があるのか、ないのか、という判断基準だって、相当あやしいものです。スポーツの世界は数字で実力をはかっています。音楽や絵や、こういった文章というのは、いい/悪いの基準が常に曖昧だから、アマチュアとして死ぬまで実力をつけ続けているという、笑うに笑えない人も世の中にはいます(誰も、彼ら/彼女らのことを笑えないと思う)。
好きなことと得意なことと仕事がすべておなじになってしまうと、どうなるのか? あなたが思い描いているように、自己実現とやらができて、毎日が充実して、なりたい私になれて、非常にハッピーなのか?
ときにはそういうことを感じる日もあるでしょう、というか、あります。朝、起きたくもないのに起きる必要もない。行きたくもない会社に行く必要もない。暇な会議に出席して「もう、アニメキャラクターの顔も書き飽きたな」と、アニメキャラでいっぱいになったレジュメの裏を眺めつつ、売れない画伯のようなことをぼやく必要もない。
やりたいことを仕事にするとストレスがほぼない。いいことだ。
でも孤独です。敵は常にじぶんです。「ちょっと2日ほど休んで、気持ちをリフレッシュさせよう」と思って、遠出をしても、もれなくついてくるのは、敵であるじぶん。残念すぎる。気持ちが休まる暇がない。
こうやって文章を書くのは、ひとりの作業なので、特に孤独です。でも淋しくはない。ときどき読者が心温まるメールをくださる。
また、ときどき、「やりたいこと」を仕事にしている人と、お互いの存在をただ確認しあう。人ごみのなかで、偶然、誰かを見つけたときのように、すれ違いざまに、ふと、一瞬、確認しあう。
そんなとき、これ以上の幸せはないよなと思う。
「“好き”を仕事に!」なんてことをしれっと言える人は、好きなことを仕事にしたことがない人か、そこまで好きではない人なんだろうと思います。本当に好きなことを仕事にしている人は、そういうことを言わないから。
本当に「好き!」を仕事にしている人は、幸せをひとり静かに噛みしめて、無口に人ごみにまぎれてゆくのです。
ひとみしょう(作家/コラムニスト/作詞家)
[ANGIE]
Posted by nob : 2013年12月12日 17:04
また旅立つ君へVol.2
どんなところで
どんなことをするかではなく
どんなことにでも
どのように取り組むかということ
Posted by nob : 2013年12月11日 06:57
突き詰めれば姿勢と呼吸、、、健康と美容の必要充分条件。。。
■運動しなくても「脂肪がメラメラ燃える」何てことない生活習慣
何もしなくてもエネルギーが消費される基礎代謝は、女性では20歳以降から少しずつ低下し始めます。
それに加えて現代の便利な生活では、歩いたり、身体をこまめに動かしたりといった運動の要素が少なくなり、深層にある筋肉が衰えやすいといわれています。
今回は、この深層にある筋肉“インナーマッスル”を鍛える、毎日のちょっとした習慣を伝授します。
■たるんだ下腹を引き締めるには?
深層筋が減ると基礎代謝にも大きく影響し、基礎代謝を上げるにはインナーマッスルを増やすことが欠かせません。しかしインナーマッスルは、バーベルや腕立て伏せなどの筋トレでは鍛えられないのです。
またインナーマッスルの中でも、特に重要なのが腰の部分にあり下腹を内側から支えている“腸腰筋”という筋肉。プロポーションやダイエットにとって、非常に重要な筋肉です。
さらに、その中の“大腰筋”は上半身と下半身をつなぎ、背骨や骨盤を支えたり、太ももを上げるのに使われる筋肉で、これらの筋肉に鍛えると、たるんだ下腹を引き締めることができます。
■インナーマッスルを鍛える生活習慣5つ
インナーマッスルは持久力のある筋肉なので、鍛えるには一般的に有酸素運動が効果的。その中でもこの“腸腰筋”を効率的に鍛えるには、次のような習慣や運動がよく効きます。
(1) 姿勢を正す
立っている時、胸を張りお腹を締め正しい姿勢を意識します。
(2)お尻歩き
リラックス時にお尻で5歩歩いてみます。
(3)階段を上る
ゆっくり一段抜かしで上がると効果的。
(4)自転車
股関節や太ももを、引き上げることを意識しながら漕ぎます。
(5) ヨガ、ピラティス
脚の付け根や太ももの裏をストレッチするヨガのポーズは、大腰筋にじんわりと効き、代謝を高めてくれます。
太ももや腹筋などの筋肉を動かす場合は、糖質や肝臓のグリコーゲンを消費するのに対して、インナーマッスルを使う時は脂肪をエネルギーとして燃焼させます。
その結果、脂肪が燃焼されやすくなり、さらに体温も上げることができるので、冷え症の方にもおすすめです。縮こまりがちな寒い季節も、背筋はピンと伸ばしていきましょう!
[週刊ポストセブン]
Posted by nob : 2013年12月07日 00:42
自らの満足を目指し続ける過程に一つ一つの納得がある。。。Vol.4/納得こそがすべて。。。
■大人になるということは夢をあきらめるということ?夢をあきらめられないあなたへおくる小さなメッセージ
「大人になるということは、夢をあきらめるということでしょうか」
先日、そういう質問を受けた方の話を聞きました。これは、一度でも夢に向かって努力したことがある人は、感じたことのある思いかもしれません。社会人になり、自分で食べていかなくてはならない生活を強いられた人は、たいてい厳しい現実にぶち当たります。
これはある視点においては正しいと思います。幼いころ、まっさらな心に描いた純粋な夢は、純粋だからこそ無謀で、叶えるための手段なんてそのときは考えていません。見通しのたたない夢をいつまでも追うことに不安を持ち、堅実に働いて稼いでいく生活を選んだ人は、「自分は夢をあきらめた」と思うでしょう。
では、夢をあきらめることが、現実を生きてくということなのでしょうか。
納得できるかどうか
確実に毎月お給料がもらえる仕事とは違い、不安定で明日どうなるかわからない生活をしていると、周り(とくに親族)は、あなたを心配しているように好き勝手な正論をいうでしょう。あまりにも何度も言われていくと、だんだん心がめげて夢を追うこと自体に疑問をもってしまうかもしれません。
その反感を嫌がっていては夢は叶えられません! といえばそれまでですが、そこで納得して「確かにそうだよな、自分は結婚もしたいし子供もほしい。いつかできる旦那さんと子供のためにも、花嫁修業に時間をかけるのが先決!」と思えば、それは夢を諦めたのではなく、夢の方向を変えたということになるでしょう。
そこにはネガティブさはなく、自分の心に素直に従って出した前向きな結論があります。
納得しないまま別の選択をすると、そこには確実に後悔が生まれますから、そうなると「夢をあきらめた」という事実が付きまとってきます。人生は選択の連続といいますが、自分が納得して選択したかどうかがとても大事なのです。
後悔のない選択を
私は来年、30という、また一歩見える世界が変わりそうな年代になりますが、幼い頃から思い描いていた役者という仕事をしています。みなさんご存知のとおり、厳しい世界ですが、他の仕事で食べていこうと思ったことはありません。
今年の1月、芸人の桜塚やっくんさんと舞台で共演しました。テレビでおなじみだった、女装してお客さんを罵倒する芸風とは違い、舞台裏ではやさしい笑顔を見せ、相手を思いやって言葉をかけてくれる気さくな方でした。10月の不慮の事故の突然の訃報は、本当に衝撃的で言葉を失いました。
どんなに悩んでもどんなに苦しんでも泣いても笑っても叫んでも、自分もあっけなくこの世を去るかもしれません。それは明日かもしれないし、30年後かもしれません。
人生なにが起こるか本当にわかりません。
よくいわれる言葉ですが、それをこうやって実感することで、初めてその言葉が血を廻らせ、自分の中に生きてきます。
自分の意思で生死が決められないとすると、なにか大きな力によって勝手に決められているのかもしれません。それならば、まだこうして生かされている理由があるのですから、限りある人生をせいいっぱい生きようと思うわけです。
いつ人生が終わっても、後悔ない! と言える生き方をすることが、生きている私たちがこの世を去ていく人にできる弔いではないでしょうか。
夢を追う“覚悟”
夢を追うということは、それなりの覚悟が必要です。 夢を叶える道を選択することは、その他の選択肢を捨てるということになります。捨てるものは、平穏な生活のことかも知れません。 俳優を例にあげれば、有名な話ですが、日本を代表する名優、役所広司さんは区役所に勤めていたにもかかわらず安定した生活を捨て、劇団のオーディションを受けて、俳優としての道を選ばれました。 ハリウッドスターのハリソン・フォード氏も、大工をしながら売れない俳優生活を長く過ごされたそうです。 最近ドラマや映画でひっぱりだこの真木よう子さんや、尾野真千子さんだって、長い下積み生活で幾度も挫折しそうになったと。 一度は安定した仕事に就きながらも、自分の満たされない気持ちに向き合って転職した方や、むくわれるかもわからない辛い下積み生活を過ごされた方は大勢いらっしゃることでしょう。 でもそれとは逆に、いつまでもむくわれないままの方がいらっしゃることも事実です。夢を叶えるという選択をしても、結果的にむくわれない可能性も多いに含んでいます。それをわかっても追う覚悟があるのか。 そこは、常に自分自身に問うべきところです。
夢を目標に変える
俳優などの人気商売でなければ、もう少し違うのかもしれません。CAや看護師などは、資格に合格できるレベルまで死ぬ気で努力すれば、もう少し道が開かれることでしょう。年齢制限があるものは仕方ないですが、あきらめきれない夢がひそかに自分の中にあってむくわれない今がある方は、目指す価値は多いにあると思います。 幼い頃、純粋な心に生まれた夢は、自分の本音です。素直な「やりたいこと」です。その気持ちがいまだにあるのに無視するのは、自分を殺すのと同じことです。夢を叶えるためにじゃあどうしたらいいかと計画を立てていくと、夢は目標に変わります。 さきほどから夢! 夢! と、どこぞの若造がほえているのかと自分でもふと我に返ると恥ずかしくなりますが(爆)、実際、小さくとも夢を仕事してやれるようになると、現実的に課題が生まれます。また次のステージのはじまりです。たとえ安定とはほど遠い生活であっても、それをやれること自体に幸せを感じ、自分の気持ちに素直に従うことで、生きがいを見出せていけるのではないでしょうか。 そうはいったって、世の中の風は冷たいのが現実です。 世の中を知っていけばいろんな価値観が身につきますから、夢に対するエネルギーが最初とは変わってくることもあるでしょう。 そうなったとき、また納得して別の道を選択できるかどうか。納得すれば、それは夢をあきらめたのではなく、新しい目標を持ったということです。 後悔ないと言える人生でありたいものですね!
吉川 依吹
舞台女優。
[ANGIE]
Posted by nob : 2013年12月04日 00:38
自らの満足を目指し続ける過程に一つ一つの納得がある。。。Vol.3/自らの生を救えるのは自分自身だけ。。。
■寂しさは自分で満たせる。心の安定をキープするコツ6つ
スピリチュアルや心理学で、人がより幸せに生きるために大切と言われているのが「自己愛」。一般的にはあまり良いイメージがない言葉かもしれませんが、自分への愛が足りないと、必要以上に寂しくなってしまったり、心が満たされていないぶん他人への要求が大きくなってしまったりするんです。
でも、「自己愛」だなんて日常で意識することはほぼありません......。どうすれ自分への愛を育てられるのか、そんなヒントを見つけました。心に響いた6つをピックアップして紹介します。
(1)自分にとって価値あるものをハッキリさせる
(2)信頼し合える仲間をつくる
自分が好きなモノ・人に囲まれているだけで人って本当にハッピーになれます。個人的には、自分が本当に会いたいと思う人とだけ付き合うよう意識したところ、ストレスが減り自分にとって大切なことがハッキリしてきたように思います。
(3)心の声に耳を傾ける
例えば、何かを選択するとき、条件はいいんだけど「ちょっとモヤモヤする」なんてときは心の声を無視しているかもしれません。このあたりは、何気なく過ごしていると気づかないもの。自分の心の声にはちょっと敏感になるべきかも。
(4)有害な習慣や人間関係を断つ
(5)ヘルシーな習慣をつくったり、カラダを大事にする
心身ともに健康でいると、自然とポジティブになり自分の本当の想いにそった行動ができるようになります。お気に入りのオイルでマッサージする、などほんの少しの習慣で明るく過ごせるようになれれば嬉しいです。
(6)不要な感情は日記に書いてクリーンにする
ネガティブな思いを持ち続けていると、何でもないこともネガティブに思えてくるという悪循環に陥りがち。できるだけ早く手放す方法として効きそうです。
「自分への愛」とだけ聞くとなんだか大げさな感じがしますが、普段見逃している自分へのちょっとした気づかいのようなものなのかもしれません。ささいなことが幸せへの一歩なんだなあと思いました。
(若松真美)
[MyLohas]
Posted by nob : 2013年12月04日 00:05
依存従属からの脱却がすべての始まり、、、副業、正確には並業・複業のすすめ。。。VOl.2
■初任給から始まる不幸 ~サラリーマンに会社の本質は見えにくい~
永松 和洋
・前置きです。
ポスドクの人間にとっては、就職氷河期は今に始まったわけではなく、っと続いたままです。ならば、学部を卒業して、大学院(修士課程2年、博士後期課程3年)になんて、学しなければいいじゃないかって、言われそうですが、それでも行く人は行きます(笑)。
好きなことを仕事にできるってすばらしいことなので、ある意味、夢を追いかけているという面があるかと思います。
もちろん、就職がないといっても、ゼロではありません。公募というものがあり、定員1人のところに、50人とか100人とかが応募してくるわけです。
それを通らないと、大学の教員や研究機関の一員にはなれません。更に、任期付のポスト(2年から5年程度)も多いので、任期が終われば、放り出されます。
サラリーマンも、会社にリストラされる、会社が倒産するという恐さは、常につきまとっているかもしれません。いつ来るかわからないという心配がありますが、その点、もしかしたら、ポスドクの任期付の方が、初めから明らかになっている分、よいのかもしれないという見方もできます。
いずれにしても、うまくいっているうちに、次の一手を考えたいものです。会社に組織に完全に人生を委ねてしまう前に。
ポスドクについての考えは、「ポスドクのいくつく先」というタイトルで以前に書かせていただきました。
・本題です。
これは、以前から疑問に思っていることです。新入社員として会社に入って、 すぐに給料がもらえるというのは全くおかしな話だと思います。新入社員は、平たく言えば、創業者なり、経営者が苦心して作り出した金儲けの仕方を教えていただく、その輪の中に入れていただく立場にいるわけで、中には即戦力としてすぐに仕事をばりばりできる方もいると思いますが、そうでない方が多いと思われます。
教えてもらう身分なのに、いきなり給料がもらえるってどういうことなのでしょうか?確かに景気を良くしていた時代には、良い人材を早々に確保すべく、当たり前のことだったかもしれませんが、これからは違うような気がしています。
なんとなく会社で時間を過ごして、収益を生み出している、いないにかかわらず、一律給料がもらえてしまう事実こそ、
会社にしがみついていれば、とりあえず、給料がもらえるという幻想、錯覚を与えてしまうことになるのではないでしょうか。
なので、自分でしっかりと、結果を出す(商品・サービスを提供して代金をいただく、もしくはその輪の中の一員となる)ようになれるまでは、給料がゼロか、むしろ、会社へ授業料を払ってもいい んじゃないでしょうか。
情報の取り方って、無料か、自分がお金を払うかによって、目の色が全くかわりますよね。
高校や大学へ行って習うことよりも、すぐに役立つことを会社は教えてくれるわけです。高校や大学には平気で学費を払っているわけですから、それ以上に役に立つことを教えてくれる会社に支払っても何ら不思議はないです。
医者や弁護士、フランチャイジーになろうと思ったら、その前段階が大変なわけで、当然、時間も費用も多くかかります。
本来ビジネスにおいて、結果が出なかった場合、どんなに頑張ったとしても1円にもならない。なのに、サラリーマンをしていると、結果がでなくても、給料がもらえてしまう。
不動産の仲介業者を見ていると、大変な仕事だといつも思います。確かに一発当たると大きいかもしれませんが、基本的には、0か1の商売ですね。どんなに色々動いて頑張ったとしても、売買成立まで辿りつかなければ、本当に1円にもならないわけです。
野球でピッチャーゴロを打って、一塁まで全力疾走したんだから、給料をもらえてしかるべき という考えをまず捨てなければいけないかもしれません。
また、たとえ自分がヒットで塁に出たとしても、後続のバッターが、自分をホームに帰してくれなければ(ホームスチールという手段もあるにはありますが)、点(結果)にはならないわけです。
そう思うと、会社って本当にありがたいですね。
自分がうまくいかない時や休んでいる時でも会社がカバーしてくれますし、更に、直接、結果に絡んでいない立場にいたとしても、
しっかり給料がもらえるわけで、そこがサラリーマンには見えにくいし、会社全体の中での自分の立ち位置というのも大企業になればなるほど、見えにくいのだと思います。
社長にならなくても会社全体を見渡せる、会社の仕組みがよくわかるという意味では、中小零細企業、ベンチャー企業の方が圧倒的によいように思います。
給料を上げてほしいと経営者に言ったとしますよね。これは、八百屋さんが、お客さんに向かって、うちの大根を100円じゃなくて、200円で買ってよ!と言っているのと同じだと思ったりもします。
サラリーマンは、労働力の 対価として、給料を受け取るわけで、会社に時間と労働を売っていることになるので、とりあえず、会社に 「毎度ありがとうございます」と言うところから始まるように思います。
飲みに行って、会社や上司の悪口を言っても始まりませんね。いやなら、他の会社へ行けばいいだけの話だと思います。私はいつも感謝でいっぱいです。
本来、会社が存続できる理由って、収益を生み出す仕組みを作り出す過程で、多くの失敗があり、その中から、うまくいったものがあるからこそ、存続できるわけで、商売がうまくまわっている輪(会社)の中にいきなり入ってしまうと、それが当たり前だとおもってしまうわけです。
その仕組みなりノウハウの賞味期限がどんどん短くなってしまっているというのが現状であり、同じことをやっていて、儲けられる時代ではなくなってきているということですよね。なので、個人レベルでも、次の儲かる仕組みを考えていくという姿勢が大切なんだと思います。会社にしがみついていられるうちに。
既存の会社に就職するという行為は、楽をして所得を得ようという行為であり、その裏には、経営者の多くの失敗があり、その上に会社が成り立っているということを知る必要があると思います。
[誠ブログ]
■「失敗が悪」から「失敗しないが悪?」の時代へ
永松 和洋
小中学校で習った国語の科目の中で、大嫌いなことが2つあります。
一つは、「自然」の反対は「人工」
もう一つは、「成功」の反対は「失敗」
です。これは、どちらも うそ ですね。
後者について考えたいと思います。
最先端の科学(研究開発)の世界は、常に試行錯誤の連続です。
たとえ、1回たまたま成功したとしても、
次にはその再現性が問われます。
その再現性が問われた後は、
今度は、別の角度からの検証を行います。
更に、「いつ」「どこ」「誰」というファクターに
依存せずに、再現するかが問われます。
それで、ようやく科学になります。
従って、先の日本人のノーベル物理学賞の
小林・益川先生が論文を発表してから受賞までに、
30年以上もの年月を要するわけです。
なので、ビジネスの世界で、「法則」なんて
言葉が使われることには、強い違和感を覚えます。
お隣で、一日に、アンパンが1000個売れるとしても、
自分の家で同じようにアンパンをつくっても、
1000個売れないですよね。
さらに、今日、アンパンが1000個売れても、
明日も1000個売れる保証はどこにもありませんよね。
従って、ビジネスの世界に法則はありえません。
ありえるとすれば、
残るのはマインドくらいのものでしょうか。
法則とかノウハウとかいう言葉を使われる時には
ほとんど成功例しか示されず、失敗例が全然ないのか、
あるとすれば、その割合はどうなのかも示されないと
信憑性がありません。
「成功」の反対が「失敗」ということの他に、
「失敗は成功の元」という相反する言葉もありますね。
失敗すればするほど、成功にどんどん近づくわけです。
成功してないと思ったら、
それは、ひとえに、失敗が足りないのだと思います。
実際には、「成功」の反対は、「失敗」ではなく、
「成功」の反対は、「何もしない」 ですね。
我々は、子供の時から、「失敗は悪、間違いは悪」という
教育を常に受けてきましたし、そう信じてきました。
ところが、ビジネスの世界でも、最先端になると、
科学の世界と同じで、試行錯誤の連続なわけです。
答えなんて、わからないので、最初から正解は
原理的にありえません。
つまり、どんどん失敗をしないといけないわけで、
リスクを取る という意味にも通じると思います。
逆に、たまたまうまく行ってしまうと
疑いたくなります。何か見落としているのではないかと。
自分の場合は、不動産を通してなんとなく実感できます。
一方、1人で、try & error を実践できるので、
大家さんは、身軽な経営者だという面もあります。
ではなぜ、「失敗は悪」という文化が根付いて
しまっているのでしょうか。
それは、既に確立されたことについて習って、
それを教わった通り実践する場合、
失敗したら悪になるわけです。
生徒が学校で教わったこと、
サラリーマンが会社で教わったことを
そのまま実行する場合に相当します。
つまり、「失敗が悪」という立場の人が
多いからだと思います。
一方で、経営者は、次の新たなビジネスを
考えていかなければいけない立場にいるわけで、
サラリーマンとは正反対の資質が要求されます。
つまり、ひたすら、試行錯誤を繰り返し、
ビジネスを構築していく必要があります。
既存の収益システムが破綻する前に。
逆に言えば、
うまく収益が回っているシステムは
人任せにできるわけです。
そのシステムの中で生きているのが
サラリーマンですね。
ただ、サラリーマンがその立場から脱却し、
先のプログで述べた「時間」と「労働力」以外の
要素を新たに見つけようとすると、
積極的にリスクを取り、失敗をしていかないと
いけないことを意味します。
なので、「失敗が悪」ではばく、
「失敗しないが悪」
ということになるわけです。
もちろん、最初は、小さく失敗することが
肝要です。
このことは、研究開発の世界で、
まず、プロトタイプを作って試すということにも
通じます。
日本という国は、どうも
失敗について寛容でない
という面があると思いますが、
それは、サラリーマンの多さにも
依存していると思っています。
もう一つ、最先端の世界は、
政治の世界です。
政治の世界の難しさは、
最先端であるにもかかわらず、
試行錯誤をしずらいことです。
今回の米軍基地の問題もそうですね。
おそらく、どの人が首相になったとしても、
鳩山首相と同じような結論になってしまうのではと
思うのですがどうでしょうか?
日米関係、国際関係、様々な要因を
高いところから眺めて、考慮してもなお、
思い切った政策を取れるなら、
是非、その方に首相をお願いしたいです。
誰になんと言われても、政権を取っている間は
ご自身の信念を貫いていただきたいです。
選んだ方の責任でもあると思います。
後だしジャンケンのような批判はいくらでも
できますから。
失敗に対して寛容になること が
日本という国の将来を考える時に
重要な資質の一つだと思っています。
「うまくいった、いかない」は、一朝一夕には判断できませんね。
時間軸についての考えは、また書きたいと思います。
[誠ブログ]
Posted by nob : 2013年12月01日 12:12
依存従属からの脱却がすべての始まり、、、副業、正確には並業・複業のすすめ。。。
■副業がもたらす11個の絶大な効果
サラリーマンにとって、本業というのはあくまで人から与えられている仕事に過ぎません。一方、副業というのは自ら進んで行う仕事です。いわゆる昔ながらの内職型の仕事もよいのですが、是非、個人事業的な仕事に挑戦してみたいものです。そうすることで、会社に勤めているだけではわからないビジネスの全体像が何となく見えてくるかもしれません。
「働く女子が副業で挑戦してみたい仕事」の記事の中で紹介されているのは、「マッサージ」「翻訳」「趣味を活かした仕事」「モデル」「アフィリエイト」などです。もし、趣味が収入に結びつくとしたら、こんなに楽しいことはないですね。やりたいことがそのまま仕事になるわけですから。少しずつでもチャレンジしない手はありません。
本業(会社)がうまくいくかどうかは、自分ひとりではほとんどコントロールできません。他人に自分の人生の運命を完全に委ねてしまっている状態です。常に、「親亀こけたら皆こけた」のリスクが付きまといます。
転ばぬ先の杖として副業を考えたいところです。今、自分の生活が安定していると考えているならば、その安定がどこからもたらされているかもわかってくるはずです。もし、サラリーマンだけでしかなかったら、給料から勝手にピンハネされてしまい、ほぼ無頓着な税金についても勉強する機会を必ず得ます。
以下、副業を通して得られる効果について羅列してみました。他にもあるでしょうし、必ずしも独立な関係になっていないかもしれませんが、様々な恩恵に預かれることは間違いありません。
・様々な経費が認められ、節税の可能性がある(副業の確定申告)
・収入が増えれば、お金の余裕、心の余裕が生まれる
・会社勤めでは一部分しかわからないビジネスの全体を実体験できる
・小さく始めることで試行錯誤もでき、失敗しても大怪我にならず、経験が積める
・徐々に自信が持てるようになり、会社でも強気になれる!?
・本業への絶大なフィードバックが期待できる
・コミュニケーション能力・プレゼン能力が高まる
・様々な分野のことに興味が持てるようになる
・人脈が広がる
・信用のありがたさがわかる
・労働組合の無意味さがわかる
・(オマケ)夕飯も経費にできるかも?!(残業時)
永松 和洋
ポスドク&非常勤講師生活を経て、私立大学の教育・研究職に従事する一方でポスドク時代に不動産投資を開始。職場の行き帰りの生活だけでは極めて危ういことを知るに至り、現在は会社・社会・国に過度に依存しない生き方を少しずつ実践中。
[allabout newsdig]
■サラリーマンの「確定申告」--"副業"している場合の注意点は?
確定申告シーズンの真っ最中ですね。サラリーマンには縁遠いと思われていた「確定申告」ですが、ネットオークションやアフィリエイトなど、比較的手軽にできる"副業"が増えたことにより、「そろそろやらなくちゃいけないかなぁ」と思っている人も多いのではないでしょうか。今回は、副業をしているサラリーマン諸氏が陥りやすい勘違いと、申告時の注意点を紹介します。
20万円以上稼いだら、確定申告しなくちゃいけないの?
最近、副業をしている会社員の方に相談を受けることが増えてきました。副業規制を緩和する企業が増えてきたこともあるのでしょうが、副業を始める理由はさまざま。「独立につなげるための最初の一歩にしたい」とか、「自由な自分でいたいから」なんてかっこよくキメている人も。ただ、確定申告に関して勘違いしている人が多いのに驚かされます。
もっとも多い勘違いは、「副業収入が1年間で20万円を超えたら確定申告しなければいけない」。「雑所得が20万円以下なら申告不要」という納税ルールを知っている人に多い勘違いです。収入と所得がごっちゃになっているんですね。
収入と所得の位置づけを整理すると、次のようになります。
収入= 売上(自営業者)、額面給与(会社員)
所得= 収入 - 必要経費
給与を例に説明します。サラリーマンにとっての収入は給与収入です。いわゆる「年収」と言われるもので、社会保険料や税金などが差し引かれる前の総支給額から交通費を差し引いた額になります(交通費は収入に含まれないため)。
所得は収入から必要経費を差し引いた額です。サラリーマンの必要経費は「給与所得控除」といって、収入に応じて自動的に算出されます。そう、サラリーマンも必要経費が認められているのです! 年収から給与所得控除を差し引いたものが、給与所得となります。たとえば、年収300万円の会社員の場合、給与所得控除は108万円、所得は192万円になります。
どんなものが必要経費になるのか?
副業も考え方は同じです。副業により稼いだお金(副収入)から必要経費を差し引いた残りが所得になります。だから、1年間に得た副収入が20万円を超えても、必要経費を差し引いた残りが20万円以下であれば、原則として確定申告は不要になります。ただし、副収入が所有する不動産を貸したときに発生する家賃収入である場合は「不動産所得」となるため、所得額にかかわらず確定申告が必要です。また、後ほど解説しますが、「事業所得」となるケースもあります(ここ、かなり重要です!)。
必要経費はその収入を得るために使った経費です。たとえば、アフィリエイトをやっているとしましょう。サイトを作るのにパソコンを買ったらパソコン購入費が経費になります。インターネットプロバイダ料金や通信費、レンタルサーバー代、資料・書籍代、セミナー参加費、交通費も必要経費です。打ち合わせでかかった飲食代や自宅の一室を仕事部屋にしている場合の家賃・光熱費も一部経費に計上することができます。
家賃を経費にできるのは、仕事で使っているスペースだけです。住まいの床面積に対して副業で使うスペースがどれくらいか(割合)を算出し、「実際に払っている家賃×仕事で使うスペース割合」を経費とするのです。割合は30%、40%などとざっくりで構いません。万一、税務署の指導が入った時に根拠として言えるようにしておきましょう。
いずれの場合も、領収書やレシートが必要ですので、こまめにとっておきましょうね。
ネットオークションやフリーマーケットの収入は原則課税されない
着なくなった洋服や読み終わった漫画や単行本、子供が大きくなって使わなくなったベビーカーなどをフリーマーケットやネットオークションに出品し、それによって利益を得たとしても確定申告は不要です。家庭の不用品を売って得た収入は非課税になるからです。
ただし、1商品30万円以上で売れた絵画や骨とう品などは課税対象です。古着でも仕入れ先から購入して、すぐに転売する場合は課税されるのでご注意を。
副業で赤字が出た場合、給与所得と損益通算できるのは「事業所得」
所得税法上の所得は、給与所得を筆頭に10種類あり、それぞれの計算式に則って所得を算出します。たとえば、会社から給料をもらったら「給与所得」。株式投資で配当金をもらったら「配当所得」。競馬に当たったら「一時所得」。家賃収入を得ているのなら「不動産所得」になります。その他の一般的な副業に関しては、「雑所得」か「事業所得」のいずれかになります。
副業で赤字が出た場合に、給与所得と損益通算(ある所得の赤字額を違う所得の黒字額で相殺する)できるのは「事業所得」です。雑所得は損益通算できません。だったら、僕は事業所得で…と言いたいところですが、こちらで勝手に決められるものではありません。事業所得の定義に合致する必要があるからです。
事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」(昭和56年最高裁判決)。つまり、サラリーマンの副業は基本的に「雑所得」となります。しかし、継続的にその事業を行っていて、利益を上げるために頑張っていて、その事業を行っていると客観的に認められている場合に「事業所得」となるわけです。
平成13年の判例でこんなものがありました。ダンス教室を経営している勤務医がそれを事業所得として申告し、給与所得と損益通算していた事例です。このダンス教室は開業時から一貫して赤字が続いている点が指摘され、雑所得となりました。稼ぐ気ナシとみなされると雑所得、ということでしょう。
副業OKの会社に勤めているからといって安易に事業所得の申告を続けていると、税務署から「雑所得でしょ?」と言われる可能性があるようです。迷ったらお住まいを管轄する税務署に相談するといいですね。
会社に内緒で副業をしている場合、確定申告により所得が増減すると住民税の金額が変わるため、会社に通知が届きます。この通知を届かないようにするためには、住民税の納税方法を「特別徴収(勤務先が本人に代わって納税する)」ではなく「普通徴収(本人が直接納税する)」にするとよいと言われています。が、会社からなぜ切り替えたのかとつっこまれる可能性はありますので、就業規則をきっちり確認しておきましょうね。
柳澤 美由紀
財布にやさしく、家計に役立つ知恵を発信するファイナンシャル・プランナー(CFP(R)/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社家計アイデア工房 代表取締役)
[マイナビニュース]
Posted by nob : 2013年12月01日 11:36
亞聖さん、素敵です。。。
■町亞聖さん、母を介護した奇跡の10年「もっと一緒にいたかった」
フリーアナウンサーの町亞聖さんは大学受験を控えた18歳のとき、母親の広美さんがくも膜下出血で倒れた。介護生活は、広美さんが末期がんで亡くなるまでの10年に及んだが、町さんは「多くの気づきをくれた奇跡の10年でした」と振り返る。(文 油原聡子)
「お姉ちゃん、起きて」。平成2年1月8日。高校3年の3学期の始業式の日でした。母の様子がおかしいと、妹に起こされました。「吐き気がする」と母は言っていましたが、意識もありました。夕方になっても良くならず、父が帰宅後、病院に行ったんです。
翌日検査すると、くも膜下出血と分かりました。私は学校から帰宅後、父と妹から説明を受けました。妹は「死んじゃうかもしれない」と泣きじゃくって。
手術を受ける前、病室で母は「心配かけてごめんね」と話していました。しかし、手術後、徐々に声がかすれ、右手と右足も少しずつ動かなくなって。10日後に脳梗塞を起こした母は、言語障害と右半身不随という重い後遺症を背負うことになってしまいました。
幼い弟と妹の母親代わりをしながら、母が入院中は毎朝6時には病院に行きました。大学受験は失敗し、浪人することに。母は4カ月後、リハビリ専門の病院に移り、翌年の2月に退院したんです。
当時は在宅介護の情報がなく、試行錯誤でした。家も狭くてバリアフリーではなかったので、母が車椅子で移動するのも大変。街中も段差がたくさんありましたが、買い物などなるべく母を外に連れ出しました。車椅子でも「母は母」。母との生活は私にとって普通のこと。隠すことではなかったんです。
1浪後、大学に進学し、夢だったアナウンサーになりました。人前で話すことが好きでしたが、自分が伝えたいことが、母の介護を通じて明確になった。障害を持つ人が地域で普通に暮らすこと。老いや病気、介護は誰にでも起こる可能性があること。「もし自分だったら」と、多くの人に考えてもらうきっかけをつくりたいと思ったんです。
母も私がテレビに出るのを喜んでくれて。でも、アナウンサーとして働きながら介護を続けていた平成10年、母が末期の子宮頸(けい)がんであることが分かったんです。がんはステージIIIb。骨盤やリンパ節にもがんが転移して手術もできない状態。統計的には余命半年、と説明されました。
後にがんの取材をするようになり、早期なら死ぬことのない病気と分かりました。「気づいてあげられなかった」と大きな悔いが残り、今も立ち直れていないですね。
在宅介護で看取(みと)ることは家族で決めました。病院は非日常の世界。母が唯一、自由に過ごせる家に戻ってきてほしかった。地元の総合病院に緩和治療科があり、訪問看護を受けることができました。この頃、父の胃がんも分かりましたが、早期で手術をすれば回復するということでした。
母ががんと分かってから1年半がたった11年11月。18日は母の50歳の誕生日でしたが、誕生日を迎える前、母が激しい痛みに苦しみ始めました。痛みから救うため、モルヒネを使うことを決断。モルヒネを使うと意識のある状態には戻せない。でも、在宅介護を決めたときから延命措置はしないと決めていたんです。
9日、自分の部屋にいると、「意識が戻ったみたい」と叔母に呼ばれました。母は、それまでは目は何も見ていないようでしたが、目に正気が戻っていた。最期に父を見て、ほほ笑んだんです。
介護生活をやりきれたと思えるのは母のおかげです。
がんの末期に母は人工肛門の手術をしたんですが、初めてうんちが出てきたとき、「ほら、ほら」って私を呼ぶんです。普通は人工肛門を着けたら落ち込むと思うんですが、そんな様子をみじんも見せない。「お母さん、すごい」と思いました。完敗ですよね。
母は、障害者になったこともがんになったことも受け入れ、最期まで笑顔でいてくれた。自分の状況を嘆いたり怒ったりしたこともありません。支えていたつもりが、母に支えられ励まされていました。「この母のためなら」。そんな思いでいっぱいでした。本当に感謝しています。
母と過ごした10年間は気づきや学びがたくさんありました。20年一緒にいたら、20年分の学びや気づきがあったはず…。もっと、母とずっと一緒にいたかったです。
[産経新聞]
Posted by nob : 2013年12月01日 11:32
自らの満足を目指し続ける過程に一つ一つの納得がある。。。Vol.2
■伸びる子の育て方
漆 紫穂子 [1925年創立、中高一貫の品川女子学院の6代目校長]
自己肯定感があれば、
どんな困難にも負けない
自立した子に変わる!
世界から見ても深刻な日本の状況
財団法人「日本青少年研究所」が2011年に、日米中韓の高校生計約8000人に実施した調査で、「自分はダメな人間だと思うことがある」との質問に、「よくあてはまる」「まああてはまる」と答えた割合は、日本では83.7%でした。
これは1980年の調査の約3倍にあたります。
一方、「自分は価値のある人間だ」という質問に「あてはまる」とした割合も、日本が39.7%で4ヵ国中最低と、自己肯定感の低さが際立っているのです。こうした日本の現実を深刻に受け止めています。
私は子どもたちとすごしながら、いつも、
「子どもが伸びるために一番大切なものは何か」
「どんな困難なことがあっても、一生幸せでいるには、在学中に何が必要なのだろう」
と、考えてきました。
そして、多くの卒業生を見てきたいま、たどりついた結論があります。
自己肯定感とは
それは、「自分が好き」という気持ちをもっていることです。
自分のいいところも、ダメなところもひっくるめて、自分を認め、肯定する気持ち。それを「自己肯定感」と言います。
「それってナルシストでは?」と思われるかもしれませんが、違います。
また、周りが見えず、自信過剰な人とも違います。
自己肯定感の高い人は、小さな子どもが、「ねえママ、聞いて! 僕、こんなことができたよ」と、屈託もなく話すのと似ていて、嫌みがないのが特徴なのです。
自己肯定感の高い子は、気持ちに余裕があって、人に親切です。そして、自然と周囲に人が集まってきます。「自分が好き、人が好き、人に好かれる」。そういう好循環が生まれるのです。
自己肯定感の高い人は、ひとつのことから別のことへと、自信を「平行移動」させることができます。
「一生懸命やった何かがある人は、受験勉強も一生懸命できる」
これは、卒業生が後輩に言った言葉です。
事実、部活動や課外活動で寝る間もなかったような多くの生徒が、そこで培った能力を、大学受験などに生かして、次々夢をかなえています。
そして、その後、社会で待ち受けている荒波も、自分の力で乗り越えています。
自己肯定感を高めるために大切な2つのこと
では、自己肯定感はどうやって育まれるものなのでしょうか。
ひとつは、愛されているという実感をもつこと。
もうひとつは、やればできるという自信をもつことだと、私は考えています。
愛されているという実感は、他者からの「無条件の受容」によって生まれます。
「生まれてきてくれてありがとう」「どんなあなたも愛している」という、存在するだけで肯定される「無条件の受容」こそ、自己肯定感の源です。
しかし、親は子どもの成長とともに、つい愛情に条件をつけたり、他の子と比べたりしがちです。
それが大切な自己肯定感を損ねてしまうのです。
たとえば、「○○をしてくれるよい子だったら、あなたのことが好き」「○○をしたら嫌いになる」というような言葉がけをしたら、子どもはどのように受け止めるでしょうか。
親の愛情が、条件によって増減すると感じてしまうでしょう。
「誰が何と言おうが、私はあなたの味方」と言ってくれる人が、ひとりでもいることが子どもの支えになります。
兄弟と比較されて傷ついていたり、愛情の差を感じて悩んでいたりという生徒がいます。
特に、受験などの大事な時期は、家族の注目がひとりに集まりがちです。
事情を理解できない年齢の弟妹が、「自分はかわいがられていない」と感じてしまうということも起こります。
「しまった、もう遅い」と思われる方がいるかもしれませんが、親御さんがそれに気づき、接し方を変えることで、思春期以降でも、見違えるように表情が変わる子も見てきました。
自己肯定感を育むことは、やり直しがきくのです。
自己肯定感はまた、できないと思っていたことができたという「達成感」からも生まれます。
無理だと思ったハードルを思いきって飛び越えたとき、「私は、やればできる子なんだ!」という強い自信と誇りが生まれます。
「自分で決めた」「自分で乗り越えた」という自信が、自己肯定感を育むのです。
たくさんの失敗ともめ事を「プレゼント」する意味
社会の第一線で活躍し、自己肯定感が高いな、と感じる方に、そうした前向きな姿勢について、「いつごろからですか?」と尋ねると、「学生時代の部活動体験」と答える方が少なくありません。
何かを成し遂げたという達成感や自信が、その後の人生を支える自己肯定感を形成したのでしょう。
そうした達成感を得るために、親にできることは何でしょうか。
それは、過保護・過干渉から卒業することです。
子どもの乗り越えるべきハードルを取り除かないこと、むしろ、たくさんの失敗ともめ事を「プレゼント」してあげることだと思います。
そして、小さなことでも、子どもの成功体験を認めて、ほめること。それは、未来のために達成感や自信を「貯金」してあげることになります。
もし、子どもの自信が揺らぐようなことがあったときは、その「貯金」を思い出させてあげましょう。
たとえば、「幼稚園の年少のとき、1等賞をとったよね。あのとき、どんな気持ちだった?」というように、心の奥底に眠る満たされた記憶を呼び起こす問いかけをくりかえすことで、その「貯金」は増えていきます。
そうすることで、自己肯定感の芽が育つのです。
自己肯定感があれば、これから10年の荒波「受験、就職、パートナー探し」をくぐりぬけ、その後もずっと強くしなやかに生きていくことができるでしょう。
親の仕事は、そういう一生ものの財産を、子どもの心に残してあげることではないでしょうか。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2013年11月30日 09:21
自らの満足を目指し続ける過程に一つ一つの納得がある。。。
■どっちにもはなれない ~ツマラナイ優等生や八方美人の人生をおもろくするほ~ほ~
人には108つの煩悩があると言われていますが、自慢じゃないけれどぼくは501個とか738個くらいの煩悩があるんじゃないかと思うことがよくあります。
501とか738という数字は、今、この文章を書きながら適当にでっち上げたので数字にさほどの意味はなく、要するに世間で言われているよりもずっとずっとたくさんの煩悩があるんじゃないかと、我が身を疑い残念に思うということです。
おしゃべりでおもしろい人を見たら、おしゃべりでおもしろい人になりたいと思う。
寡黙で優秀な人を見たら、寡黙で優秀な人になりたいと思う。
この項をお読みいただいている女性にも、こういう人がいるのではないかなと思います。
どんな男性とでもすぐに打ち解ける人を見たら「あたしもそうなりたい」と思う女性もいると思う。
次の日、誰とでもすぐに打ち解けないおとなしい女性かつ、でもなぜかモテている女性を見たら「あたしもあんなふうになりたい」と思うとかね。
みんな「じぶんにないもの」を持った人に、毎日ちょっとずつあこがれる。
人は完璧ではないから、じぶんのなかの「おもしろい」要素が、不足していれば「ああ、おもしろい人になりたい」と思うし、じぶんのなかの「寡黙な」要素が最近ご無沙汰だと(なんかおかしな日本語だ)、「寡黙でかっこいい女史になりたい」と思う。
でも、誰しも、どっちにもはなれない。
どちらかにしかなれない。
あるいは、おもしろいけど寡黙なときもあるというように、なにやら中途半端な選択をするしかない。
いずれにせよ、じぶんが得意なほうひとつを選んで生きるしかない。
あこがれは哀しい。
手に入らないものだから「あこがれ」。手に入るとすれば、それは目標であり、あこがれではない。
あこがれにつまずかず、じぶんで選んだ「どっちか」の道を歩くしかない。
選ぶというのは、その瞬間は少なくとも「片方を捨てる」ということだから、ストレスがかかる。そのストレスをクリアして、我が道を歩んでいる途中に、いいことなんてなにひとつ起こらないかもしれない。
でも、人はじぶんの道を歩くしかないし、そのことを知っている女性は美しい。みんなにいい顔はできないことを彼女は知っているのだから。
ひとみしょう(作家/コラムニスト/作詞家)
[ANGIE]
■ガッカリしないテクニック ~彼氏にフラれた!彼氏を寝取られた!~
人生はダイエットに似ていると思うことがあります。
ダイエットをしようとして、たとえばフィットネスクラブで泳ぐ。最初の1ヶ月くらいは順調に体重が減ってゆく。やがて体重が落ないときが訪れる。努力して「これくらいの成果は手にしてもいいだろう」と思っていた読みが外れて、あろうことか体重が増えている。
努力が報われないこともある。思い通りにいかないことにガッカリすることもある。だから人生はダイエットに似ている。
ガッカリしないテクニック。与えられた意にそまない結果(ぜんぜん意にそまない残念すぎる結果)を見て、このほうがよかったのかもしれないと思うこと。本当はこうなるべきだったのだろうと思うこと、思えること。
大好きな彼氏にフラれた。フラれたほうがよかったのだろうと思うこと。無理にでも。
女友だちに意中の彼を寝取られた。本当はこうなるべきだったのだろうと思うこと。無理にでも。
別の言葉で言えば「そういうもんだ」と思うこと。
大好きな彼にフラれて「そういうもんだ」とは、なかなか思えないですよね。「そういうもんだ」と言えば、「そのていどの“好き”でしかなかったのか」と、周囲の人はきっと驚きますよね。
でも「そういうもん」なんです。
ガッカリする経験をうまく、ひょいっと涼しい顔をして乗り越えている人に話を聞くと「考え方の訓練」だと言います。つまり、ガッカリするたびに「そういうもんだ」と思う訓練だと思って、「そういうもんだ」とじぶんに言って聞かせると。
まあ「そういうもん」なんだろうね。人生の先達の意見って、わりと的を射ていることが多いから。
たぶん、人は「意識してやらないとできないこと」をたくさん持っているんだと思います。
たとえば小学生のころ「あいさつをしましょう」とか「いつもあかるくしましょう」という標語のようなものがクラスに貼ってあったけれど、あれは、人は放っておくと、あいさつもしないで陰々鬱々となっちゃう生きものだというのを、誰かエライ人が知っていて、だからこそ、「挨拶」や「明るく!」を意識させていたのかもしれない。
これとおなじで、ガッカリしないということも、意識的に訓練するしかないのかもしれない。オトナになるって、いろんな訓練が必要なんですね。ふう。
ひとみしょう(作家/コラムニスト/作詞家)
[ANGIE]
Posted by nob : 2013年11月30日 08:32
これも確かに。。。
■日本酒は太るは、ウソ!
友田晶子
日本酒のイベントや試飲会を行うと、たまに言われることがある。「日本酒は太るでしょ?」と。これを聞いて、私は驚く。そんな風に思っている人がいるんだと。「日本酒=太る」という図式が私の頭にはない。いわんや、「お酒=太る」という意識もない。なかには、焼酎は太らないと思っている人もいる。焼酎も太らない。
しかし、焼酎は蒸留酒なのでアルコールが高い。ストレートで飲むなら、日本酒よりアルコールが高くカロリーも高く、太りやすいともいえる。つまり、お酒のカロリーはアルコールの高さと比例しているのだ。ちなみに、
・ビールは約5%
・ワインは約12%
・日本酒は約16%
・焼酎は約25%
・ウイスキーは約40%
だから、お酒の中ではビールが最もカロリーが低いことになる。
もちろん、お酒にはアルコール以外に糖分も含まれているので多少前後する。もっと具体的に提示すると、
・ビール(350ml缶)・・・・・・・・・・・・140kcal
・ワイン1杯(120ml)・・・・・・・・・・・100kcal
・日本酒1合(180ml)・・・・・・・・・・・200kcal
・焼酎お湯割り(100ml)・・・・・・・・・・150kcal
・ウイスキー(ダブル60ml)・・・・・・・・・150kcal
(ハイボールにしてもお酒の量が同じならこのカロリー)
ざっと、こんなイメージだろう。全体的に高くないことがお分かりになるだろう。さらに、アルコール由来のカロリーは、糖質や脂質由来のカロリーと違い、代謝のいいカロリーなので体内に残りにくいともいえるのだ。
■太るもとはお酒じゃない、「おつまみ」だ!
太るイメージのあるビールは実はそんなに高くない。日本酒だって、ご覧のとおり極めて高いわけじゃない。逆に焼酎が極めて低いわけじゃない。太るもとは「おつまみ」にある。
ビールと一緒に食べるのは、なぁに? はい、唐揚げ、ピザ、カルビ、ホルモン、コロッケ、ハンバーグ、焼きそば……。ね? カロリーの高そうなものが多いでしょ。そのうえ、一緒にビールも山盛り飲んでしまう。そしたらまたおつまみがおいしくなる…と。
では、日本酒のおつまみってなに? お刺身、焼き魚、煮魚、干物、一夜干し、焼き鳥、冷奴、お浸し、茶わん蒸し、鍋料理……。ね? カロリーの低そうなものが合うでしょ? これです、これ。日本酒のアテはあっさりしたものが多いのだ。
相対的に見れば、日本酒は太るは、間違い、大間違い。だから、安心して飲んでほしい。もちろん飲み過ぎは禁物。ま、それは他のお酒も全部そうだけど。一杯飲みそうなお席の時には、お水を一緒にたくさん飲んで。できれば炭酸水ならなおいい。お腹が適度に膨れ、飲み過ぎ食べ過ぎを防いでくれるから。だからと言って、アルコールと炭酸が一緒のビールをがぶがぶは×ですよ!!
[all about/news dig]
Posted by nob : 2013年11月29日 19:48
確かにね、、、まあセックスはともかくとして。。。
■強いメンタルは1日にしてならず。ストレスに打ち勝つ21の習慣
忙しい現代人はストレスを溜め込みがちですが、ちょっとした工夫でストレスを軽減することは可能です。世界でもっとも読まれているセールスに関するブログのひとつ『Sales Source on Inc.com,』の著者Geoffrey James氏がアドバイスする、ストレスに打ち勝つための21の方法をご紹介します。
1.小さな成功を喜ぶ
私たちの多くは、実現するのに何年もかかるような大きな夢をもっています。それは良いことですが、その目標に達するまでに必要な小さなステップを達成したときにも、喜ぶようにしましょう。
2.仕事と関係のない友人と遊ぶ
仕事に関わりのある人々と多くの時間を過ごしすぎると、話の話題が仕事関連になりがちで、ストレスが増える元となります。仕事と関係のない友人と時間を過ごすことで、仕事モードから離れれば、ストレスを軽減することができるでしょう。
3.自分が心地よいと感じるサウンドトラックを流す
映画のサウンドトラックには、観客の感情を掻き立て、盛り上げる効果があります。ですので、逆に感情を落ち着かせるのには、自分の人生という映画に合った心地よいサウンドトラックをつくって、仕事中に流してみましょう。
4.手を動かす趣味を開拓する
今の仕事が主に頭脳を使う類いのものであれば、実際に手を動かして取り組むような趣味を見つけましょう。たとえば、わたしはミニチュアレンガで建築物をつくることで、ストレスを解消しています。
5.セラピー効果のあるマッサージを受ける
マッサージを受けると、ストレスを溜め込んでいる筋肉の緊張がほぐれます。マッサージを受けている最中には、仕事について考えないようにしましょう。その代わり、身体が受けている力に意識を集中し、身体の各部分が少しずつ緊張から解かれているイメージをしてみましょう。
6.視野を広げる
ストレス増加の最大の原因は、あなたが取り組んでいることの全て、そして失敗の全てが重要であると思い込むような考え方にあります。10年後には、当時なにがストレスの元になっていたかなど、きっと覚えていないのですから。
7.過去の失敗を手放す
過去の失敗を背負い続けることは、すさまじいストレスになります。過去が繰り返されるのではないか思い悩むよりも、大きな失敗が続いたあとには、大きな成功が待っていると考えましょう。一度失敗すれば、その次には成功する確率の方が高いのです。
8.暴力シーンの多いメディアの見るのを控える
多くの映画やコンピューターゲームは、いかに暴力的で露骨な描写のものをつくるかを競い合っているように見えます。こうしたメディアを多く見ると、身体が自然に「闘うか逃げるか反応」の状態に置かれ、ストレスが生じてしまいます。
9.散歩に出かける
住んでいる場所のエリアが安全であるということが前提ですが、外に出て、新鮮な空気を吸い、足の筋肉を伸ばすことは、オフィスでなにか上手くいかない際に気分を切り替えるのに効果的です。
10.祈る。または瞑想する
祈りや瞑想が身体の状態を向上させることは、多くの科学的研究で明らかになっています。これは、宗教心の有無や神を信じるかどうかという点に関係なく、得られる効果なのです。
11.笑えるものを読んだり、観たりする
笑うことは最高のストレス解消法です。自分のことを笑い飛ばすことが難しければ(これこそ、最高のストレス解消法ですが)、何か笑える材料を見つけましょう。一緒に笑って楽しめる人がいれば、なお良いです。
12.小さな仕事をひとつにまとめる
仕事の量をどのように捉えるかで、ストレス度は変化します。小さな仕事をひとつのプロジェクトにまとめてしまいましょう。たとえば「ジョーに電話する、ジルに電話する、etc」といった仕事を「電話する」という仕事のくくりにまとめてしまうのです。
13.大きな仕事を小さな仕事に分割する
1つ前のアドバイスとは逆になりますが、ある一つの大きな仕事が、あまりに圧倒されるほどの大きさである場合には、それを小さな仕事に分割して、一つ一つこなすようにしましょう。たとえば「新しいサイトを立ち上げる」という仕事を「1)見本となるサイトを見つける 2)必要なコンテンツのリストをつくる etc」と分けてみるのです。
14.一つの仕事に取り組む時間を設定する
これは、12と13の方法に適用することができるやり方です。一つのまとまった仕事、または小分けした仕事を終わらせるのに必要な時間を設定するのです。邪魔が入らない時間を確保することも忘れずに。
15.見る情報を制限する
適切な情報量について考える際に、おすすめの例えが「水」です。生きていくのに無くてはならない、しかしありすぎると溺れてしまうものなのです。インターネットというのは、あなたを情報の洪水に溺れさせるためにつくられているのです。
16.もっとセックスをする
以上。
17.面識のない人とネット上で議論をしない
政治やスポーツなど、様々な話題をめぐって加熱しているネット上の議論に参戦することは、まさにゼロの状態からストレスが生じることに他なりません。オンライン上の議論で、相手の意見を変えさせることなど、結局不可能なのです。
18.週末や夜間に仕事をしない
夜通しで仕事をしたり、週末を利用して仕事を片付ける必要があることもあるでしょう。しかし、それを習慣にしてしまうのは、自らストレスをくださいとお願いするようなものです。充電する時間は必要です。その時間をとってください。
19.深呼吸する
呼吸が浅いのは、身体がストレスを受けていることを示しています。長く、深い呼吸をすれば、身体はリラックスモードに変化します。長く、深い呼吸をしばらく意識してやってみてください。続けていると、無意識にできるようになります。
20.長い時間をかけてシャワーを浴びる、または入浴をする
バスタブに浸かっているあいだは、電気製品を使用したり、電話に出ることはできません。つまり、仕事のプレッシャーが絶対に届かない場所に身体を置くことができるのです。
21.適職を見つける
最後のアドバイスになりますが、もっともストレスの原因になるのは、自分に適さない仕事です。今の仕事が嫌だったり、なにか物足りなく感じていたとしたら、より良い仕事を見つけましょう。ストレスで病気になるまで、待っていてはだめです。
21 Great Ways to Conquer Stress I Inc.
Geoffrey James(訳:佐藤ゆき)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2013年11月29日 19:42
私も日頃実践しています、、、おすすめです。。。
■耳をひっぱると何かが起きる!? あらゆる疲れが一瞬でとれる驚異の耳ひっぱり
「気づけばなんだか、だるおも~。」「よくわからないけれど、いつも何か疲れてる…」。常日ごろ、そんなマイナー不調にお悩みの方は、少なくないのではないだろうか。
仕事に追われ、プチストレスがたまりがちな私たちの日常は、もはや、自然と疲れがたまるシステムになっているとしか思えない。
たとえば、パソコンによる目の使いすぎ、デスクワークで首や背中がコリ固まる、小難しい客先との商談で気疲れ、飲みに行ってもやっぱり疲れて、帰宅してテレビをつければ暗いニュースでどんより、お風呂に入ってよく寝たつもりなのに、翌朝やっぱり寝起きが悪い、などなど。
そんな、日々積み重なる小さな疲れをまとめてリセットしてくれる、究極かつ超カンタンな疲労解消法があるという。それはベストセラー『「疲れない身体」をいっきに手に入れる本 目・耳・口・鼻の使い方を変えるだけで身体の芯から楽になる!』(さくら舎)の著者であり、米国ロルフ研究所認定ロルファー・藤本靖氏が伝授する健康法、「耳ひっぱり」。藤本氏は、固くなった筋膜を柔らかくすることで体全体のバランスをとる手技療法・ロルフィングをもとにオリジナルなボディーワークを提唱し、人の脳と心と体の関係を研究。耳は疲れのリセットボタンであることから、耳をひっぱるワークで全身の疲れをとるメソッドを考案した。著書の『1日1分であらゆる疲れがとれる 耳ひっぱり』(藤本靖/飛鳥新社)から、注目の「耳ひっぱり」ワークの全貌をみてみよう。
●疲れやすい体ができる仕組み
本書によれば、山登りやスポーツなどの肉体疲労は、ひと晩寝ればすっきりとれる。しかし前述したパソコンや人疲れによるストレスは「精神や神経の疲労」につながり、ひと晩寝ても解消しない。そんな「神経疲れ」の解消に、なぜ「耳ひっぱり」ワークが効くのか。ざっくりまとめると、こんな仕組みだ。
・パソコン作業や苦手な人との会話、満員電車などの不快な環境にさらされると、感覚器官である「目」「鼻」「耳」「口」が緊張する
↓
・感覚器官が緊張すると、それらと筋肉でつながる頭の芯=「蝶形骨(ちょうけいこつ)」がゆがんでしまう(たとえば目が緊張すると、目を動かす筋肉を介して蝶形骨がゆがんでこわばる)
↓
・「蝶形骨」のゆがみは体の芯である「横隔膜」にも伝わり、内臓が不調になる
↓
・常に疲れやすい体になってしまう!
● なぜ、頭の芯の疲れが体の芯に伝わってしまうのか
その秘密は、蝶形骨と横隔膜をつなぐ「筋膜」にある。横隔膜はみぞおちの奥にある、呼吸をつくる筋肉だ。筋膜は、頭のど真ん中で脳を支える蝶形骨から始まって、気管や食道、血管、心臓を包みながら、横隔膜までひとつながりになっている薄い膜。蝶形骨のゆがみが「筋膜」を通じて横隔膜に伝わり、周辺の内臓や筋肉も緊張させ、その負担で体がなんだか、だる重くなる。この負の連鎖を止めるには、緊張のおおもとである、蝶形骨をゆるませる必要がある。その解決策が、「耳ひっぱり」ワークなのである。
●耳ひっぱりのメカニズム
耳をひっぱると、耳と頭の側面の間にすきまができ、頭蓋骨と蝶形骨の間に少しだけ「あそび」が生まれる。すると、蝶形骨がゆがみから解放され、頭の芯がふっと軽くなる。蝶形骨がゆるむと、筋膜経由で横隔膜もゆるんと解放されて、体が「ほっと安心する」のだそう。
さて、それではお待ちかね、「耳ひっぱり」ワークのやり方を紹介しよう。座ったままでも、立ったままでもOK。方法はいたってカンタン。
1)まず、背すじをのばし、視線を目の高さに向けて目を閉じる
2)中指を耳のくぼみに軽く入れ、親指は耳の後ろに添えて、薬指と小指は耳の付け根あたりに軽く添える
3)ひじを横に張り、そのまま両耳を頭の側面からほんの2~3ミリ浮かせるように、気持ち斜め後ろへそっとひっぱる
4)静かに呼吸しながらしばらく続けていると、頭の中心(両耳の間)あたりに小さな空間が感じられるようになる
5)頭の芯がすっきり、体もふわっとリラックス。気持ちも自然と穏やかに…
最初は1~2分程度を目標に。慣れてくれば10秒程度で疲れがリセットできるとか。1日に何回行っても大丈夫なので、疲れを感じたり、集中したいのにできないときなど、好きなタイミングでトライしよう。
その際に大切なのは、前述した「メカニズム」をイメージしながら行うこと。何も知らずにただ耳をひっぱるのでは効果半減。ひっぱることで頭の芯の骨である「蝶形骨」が自由になり、ふわっとした感覚が「横隔膜」まで伝わる様子を想像することで、実際に体の中でその反応が起こりやすくなるのだという。
「ウソだ~」と疑り深いあなたは、百聞は一見にしかず、ものは試してみてほしい。ちなみに東洋医学では、耳には無数のツボがあるとされ、たとえば耳の上部のくぼみの中には「神門」と呼ばれるツボがある。「神門」を中心に、耳をもんだりひっぱって刺激すると、自律神経が整い、肩コリや腰痛、不眠などに効果があるといわれている。
耳は小さいけれど、知るほどに奥深い。本書には「目の疲れをとる」「胃腸をすっきりさせる」「あごの緊張をとる」「骨盤のゆがみを整える」など、「耳ひっぱり」ワークの応用編も紹介されているので、心と体ほぐしの新習慣に、ぜひ加えてみてはいかがだろうか。
文=タニハタマユミ
[ダ・ヴィンチ電子ナビ]
Posted by nob : 2013年11月22日 18:01
呼吸は鼻だけでいい。。。
■緊張の前夜でもぐっすり眠れる「鼻呼吸整え法」
大事な面接やプレゼン前夜に緊張で眠れないことってありますよね。しかも、「眠らなきゃ」と思えば思うほど眠れなくなるもので......。ぐっすり眠ってシャキッとした頭で次の日を迎えるために、緊張の前夜でも安眠できる方法をご紹介します。
なんで緊張すると眠れなくなるの?
まず、緊張すると眠れなくなるというメカニズムについて。緊張して眠れないのは、神経の作用が原因になっています。眠りに関わる神経は二つあり、一つは普段眠りにつくときに活発化される「副交感神経」と、もう一つは起きているときに活発化していて、眠るときには沈静化される「交感神経」。眠れない状態のときは緊張のせいで後者の「交感神経」が活発になっているので目がさえてしまうのです。つまり、眠るためには「副交感神経」を活性化させなくてはならず、それには体をリラックスさせる必要があります。
副交感神経を活性化させるには「鼻呼吸を整える」
体をリラックスさせるには鼻呼吸を整えるのが効果的。左右の鼻の通りをバランスよくしてあげると体がリラックスして眠りにつきやすくなります。まず右の鼻の穴を塞いで左穴で数回息を吸って吐く、次に左の鼻の穴を塞いで右穴で数回息を吸って吐く。これを何度か繰り返して、左右の鼻の通りを整えましょう。その他にも、軽いストレッチを行ったり、温かいハーブティーを飲んだりして体を落ち着けるのも効果的です。
眠りやすい部屋にするには湿度調整も重要
副交感神経を整え終わったら、あとは眠るだけ。でも、眠る環境が不快だとどうしても気になって目がさえてしまうもの。自分の体を眠れるように調整するだけでなく、部屋の環境を整えるようにしましょう。まず、眠り始めの部屋の温度は18~22度が適温。湿度は50~60%が好ましいです。また、布団はしっかり干して、シーツは新しいものを使用すること。それと、部屋の電気は消すか、豆電球にしておきましょう。
緊張は誰でもしてしまうもの。眠れないときは「眠らなくてもいいや」くらいのリラックスした気分で横になっていると、副交感神経が活性化していつの間にか眠りに入っているかもしれません。眠れずに悩んでしまったときはぜひご紹介したテクニックを参考に、安眠を手に入れて、ここ一番の日に備えてくださいね。
文●うすこ
[フレッシャーズ]
Posted by nob : 2013年11月15日 14:37
見護りと寄り添いから、、、忍耐は愛あればこそ。。。Vol.2
■妻がウツになった。どのように接すればいいか
「不安なく暮らす」ための全課題
俳優 萩原流行
「胸を裂いて、苦しみの塊を取り出したい」
22年前のある日、僕が仕事から家に帰って「ただいま」といっても、妻から返事がありませんでした。いつもなら「お帰りなさい」という声が聞こえるのに、様子がおかしい。
「どうしたの? 具合でも悪いの?」
そう尋ねると、「明日、病院に連れていってほしい」と頼まれました。その病院とは数日前、NHKで紹介されていた精神病院でした。
「もう我慢できない。胸を裂いて、苦しみの塊を取り出したいの!」
妻にそういわれたときは、一瞬、頭が真っ白になりましたが、すぐマネジャーに連絡して翌日の仕事の入りを遅らせてもらい、朝一番で病院に行きました。医師はうつと診断し、妻の病院通いがはじまりました。
その頃、僕は仕事で朝6時に家を出て夜中の3時に帰るという生活をずっとしていて、妻の生活も昼夜逆転していました。しかも僕は外で弁当などを食べず、家に帰って妻がつくる食事と会話を楽しみにしていました。後から考えると、そうしたことも妻のプレッシャーになっていたのかなと思います。
うつを患った妻への接し方については、医師からこう注意されました。
「奥さんにとってあなたは旦那さんであり、父母、兄弟であり、恋人であり……。要するに奥さんにとっての全世界はあなたなんです。だから奥さんが何かいったとき、『それはダメ』という言葉は絶対に使わないでください。絶対的な存在の人に拒否されると、どうにもならなくなってしまいますから」
それ以来、僕は「ダメだ」という言葉は一切使っていません。言葉で傷つくことが多いと聞かされたので、はじめは相当、話す言葉に注意しました。ちょっとした話でも「そういうふうにとったの?」ということがあるじゃないですか。何気ない人の言葉が、心をズタズタにする。そのことが本当によくわかるようになったのは、妻がうつを発病してから数年後、僕自身がうつになってからでした。
たとえば「元気ないじゃないか」といわれると、「元気ないと思われているんだ……」と内にこもっていってしまう。相手に悪気がなくても、病気なので曲解しちゃうんですね。
逆に最近はうつの人に「頑張って」といってはいけないと広まっていますが、いわれた人が必ず傷つくわけではありません。いろんな状況があるなかで、その言葉が人を傷つける場合があるということです。その意味では、言葉の選び方が難しいのは確かですが。
相手の状況を全部把握しているわけではないのですから安易に引っかかるようなことをしゃべってはいけません。
芝居をやっていることもあって言葉が本当に重要だと僕は思います。言葉の上には感情がのっています。神経質になりすぎてもよくないですが、心の中に相手への思いやりを持って話すことが大切です。そんな気持ちがあれば傷つけても「ちょっと言いすぎたかな。ごめんね」とフォローできるでしょう。
うつは誰でもなる可能性があります。奥さんとは毎日10分でも目を見つめ合って、会話を持つ努力をしたほうがいいと思います。それでおかしな感じがあれば、「どうしたの?」といってあげる優しさが必要です。
とはいえ、普通に暮らしていた伴侶が急にうつを患っても、まずわからないでしょう。僕の場合、妻がSOSを出してくれたおかげで彼女を救うことができました。彼女は自分がSOSを出せば、僕が受け取ると思ってくれたんだと思います。だから、夫婦に信頼関係があることが大事なんでしょうね。
僕たちは青春時代を芝居で共有していたので尽きることなく話せる。会話の多い夫婦なんですよ。話題はなんでもいいから、お茶でも飲みながら2人で話をしましょう。1つの時間を2人で共有し合うことが、夫婦の信頼関係をつくるには一番だと思います。
萩原流行
1953年、東京都生まれ。世田谷学園卒業後、劇団「ザ・スーパーカムパニイ」に所属。73年初舞台。つかこうへい事務所を経て、83年フリーに。以後活動の場を舞台、TV、映画等と広げ、現在に至る。著書に『Wうつ』がある。
[PRESIDENT online]
Posted by nob : 2013年11月10日 21:18
言い得て妙。。。
■幸せになるために「絶対してはいけない6つのこと」
幸せな人々は日頃からたくさんのことを心がけています。「よく感謝をする」「楽観的である」「親切である」「ユーモアを持つ」「笑顔でいる」などなど。
そんな彼らは、幸せな状態を保つために「絶対にやらないこと」があるそうです。海外サイトの「Marc and Angel Hack Life」では「幸せな人が絶対にしない6つのこと」と題した記事が紹介されています。当てはまっているものはありませんか?
1:他人と比べる
他人と自分を比較してはいけません。周りの声に気を取られず、自分の持っているもの、自分がするべきことに集中するべきです。人にはそれぞれのペースがあり、あなた自身の人生を他人と比べることに意味はありません。
2:他人から認められようとする
他人の評価を気にしてはいけません。あなたのことを理解してくれる人がいても、あなたを正しく評価できるのはあなただけです。他人があなたをどう評価しようが、それはその人の問題。大切なのは、あなたが自分自身を認めているかどうかです。
3:幸せを他人や環境のせいにする
幸せになることに誰の許可も必要ありません。現在、不幸を感じるのであれば、それは全てあなたの責任です。あなたが全責任を負う覚悟さえできれば、同じように他人や環境に依存しない幸せを手に入れられるはずです。
4:怒りや恨みを持ち続ける
時に、他人や自分自身によって心が傷つくかもしれません。それはあなたの中にずっと残り、克服するのに時間がかかることもあります。最善の策は「許すこと」であり、そして「忘れる」ことです。「忘れる」というのは過去を「消す」という意味ではなく「受け流す」といったイメージ。小説の1章の出来事だと思い、次のページをめくりましょう。
5:ネガティブな環境に身を置き続ける
被害者意識を持った人や、不平、不満ばかりを口にしてる人が周りにいる場合、ポジティブな心を保つのはなかなか難しいものです。そんなときは、物理的に距離を取るのが最善の策。あなたの可能性を吸い取られる前に、その場を脱出しましょう。
6:現実から逃げる
嘘を付きながら生きるのはとても辛いことです。一度ついた嘘は次第に大きくなり、虚構の世界から抜け出せなくなります。真実をねじ曲げたり、隠すことはやめましょう。真実を認めることが辛いときもありますが、それが「真実の人生」を生きる唯一の方法です。
いかがでしたか? 幸せとは手に入れるもの(have)ではなく状態である(be)と良く言われます。幸せな状態を保つためには「良くない習慣」を断つことが近道なのかもしれません。
あなたはこの他にどんなリストを付け加えますか?
6 Things Happy People Never Do [Marc and Angel Hack Life]
(稲崎吾郎)
[ルーミー]
Posted by nob : 2013年11月03日 23:51
見護りと寄り添いから、、、忍耐は愛あればこそ。。。
■うつ病かもしれない友人に何ができるか
友達の様子がいつもと全然違って、すごく悲しそう。人と接するのが嫌そうなので、どう接していいか分からない──。
落ち込んでいる友達をサポートする一番良い方法とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
アメリカでは実に10人に1人がうつ病になるといいますが、本人だけでなく周りの人たちも鬱病に近い状態になってしまうともいわれています。友達を助けるのに必要なのは、心の健康の専門家からのアドバイスと、うつ病の体験談を聞くこと。この記事では、米Lifehackerのライターで、自身うつ病の経験のあるMelanieが、友だちに対するケアの助けになるよう、段階をおって説明していきます。
うつ病とは何か:まず知っておくべきこと
最初に必要なステップは、うつ病を理解することです。まわりからすればうつ病は、ただ悲しみに打ちひしがれているように見えますが、うつ病の症状は長く続き、感情の表現が極端で、日常生活を送るのが困難なほどです。臨床心理学者のジェフリー・ディグロート博士は、下記のように例をあげています。
悲しんでいる人の場合、数日間勉強が手につかず、週末に友達と出かけることもせず、仕事や学校を2、3日休んでしまうこともあるでしょう。対してうつ病の人は、数週間勉強が手につかず、何週もの間家族や友達と出かけないまま、学校で単位を落としたり仕事を失ったりするのです。
ただ悲しんでいるだけなら、冗談や励ましの声をかけ相談に乗ることで、元気にしてあげられるかもしれません。しかし、うつ病は内科的疾患のひとつで、壊滅的な結果を引き起こします(世界では30秒に1人が自殺しようとしているとのデータも出ています。もし、友達に自殺しようとしている気配があったら、すぐに専門機関に相談してください)。話を聞くだけで、うつ病の人を助けることはできないのです。
うつ病の人は、自分がなぜ極端な感情を抱くのか分かりません。コメディアンのケビン・ブリールさんはこう述べていました。
本当のうつ病は、人生において何かうまくいかない時に悲しくなるのとは違います。本当のうつ病は、人生の全てがうまくいっているのに、悲しくなることです。
私の経験を振ってみると、うつ病のときに感じたのは、自分が暗い穴の中にいて息ができず、何も感じられないような状態でした。でも、うつ病の人の多くは、周囲に心配をかけまいとして、自分を平常であるかのように見せるのです。
残念なことに、心の健康の専門家でさえも、うつ病を見つけて治療するのは難しいです。その理由は、うつ病の症状が多様だということ。一般的にいわれるうつ病から、季節性情動障害、産後うつまで多様なのです。極端に落ち込んだ状態になる人もいれば、集中力がなくなる人、心に穴が開いたような状態になる人など、うつ病のサインが人によって違うのも、発見を難しくしています。
うつ病は"ただ悲しんでいる"以上に深刻な状態なので、悲しんでいる人に対して言うべきことやすべき行動と同じ方法では対処できないということを知っておかなければなりません。
うつ病の人のために、できること
友達が急に落ち込んで、大好きだったことを楽しまなくなっているのを見るのは、つらいものです。そんな時、友達としてできることは、一緒にいて、話を聞くこと。ここでいくつかポイントを書いておきます。
心配に思っていることを正直に伝えましょう。先述したディグロート博士は、変わった行動や性格の変化などをメモしておいて、それを相手に伝えることをすすめています。
症状の出方は、人によって様々です。「悲しみに沈む」「怒りっぽくなり、社交性がなくなる(ひきこもり)」「自滅的な行為」「新しいことへの興味を失う」「食欲不振」「不眠」などが例として挙げられます。もし友達や恋人、家族などにそのような変化が見られ、本当にうつ病かどうか知りたいなら、感情の起伏や行動に関する明らかな変化をメモしておくことをおすすめします。
明らかな変化を感じるのなら、相手に最近の調子を聞いてみましょう。もしかしたら、話をしたくて仕方がなかったのかもしれません。
聞き方としては、たとえば「最近落ち込んでいるように思うけど、何か困っていることでもある?」といった伝え方がよいでしょう。
その際、アドバイスをしたり、問題を解決しようとしないでください。共感だけで十分です。間違っても、次のようなことは言わないように。
「その問題はすぐ何とかできるよ」 「良い面を見てみなよ」「日の出を見ながらヨガをしてみて」
ジェームス・アルチャーさんは下記のように書いています。
死にたい人は、いません。でも、死にたい気分の時に突然励まされて、元気になるのは難しいものです。もし「ああ、死にたい」といったら、みんなが「元気を出して、生きがいはたくさんあるよ」と言いますが、そういう言葉は聞きたくないのです。
うつ病の人の問題を解決することはできません。よりよい聞き手になって、その場にいることが大事です。ベントル・メディカル・アソシエーツによると、下記のようなことを言ってはいけないそうです。
「本当は、何も問題はないよ。考えすぎだよ」 「あなたの人生は素晴らしい。何に落ち込んでいるの?」 「その状態から早く抜け出したら?」
ディグロート博士によると、大切なのは、友達のために、いつもそばにいることを分からせること。友達が、特に問題はないと言って話したがらなかったら、うつ病だと強制的に認めさせるのはやめてください。かわりに、悲しんでいる人にする時のように、メールやちょっとした電話などで連絡をとってください。
ベントル・メディカル・アソシエーツによると、何かに一緒に取り組むのもよい方法だそうです。「その活動に興味がなくても、誰かと一緒に何かをすることは、自分が一人ではないと感じてもらえる、良い手段です」とのこと。同時に、三食しっかり食べているか、良く寝ているか、お日様の光を浴びているか、運動しているか、などもチェックしてみましょう。毎日ベッドを整える、といった小さな習慣も気持ちの浮き沈みが激しい時の助けになります。
自分の問題として、問題をとらえないのも大切です。ホープ・ラシーンさんはハフィントンポストに、愛する人がうつ病の時の接し方で、学んだことを書いています。
何がうつ病を引き起こしているか考えるのは、やめる うつ病の人の気持ちの浮き沈みに接するのはストレスになるので、自分の心の健康にも気を付けましょう
スクールカウンセラーや自殺防止のための電話相談員などの専門家や、知り合いなど他に手助けできるひとのリストも作っておき、一番良い手助けの方法を見つけましょう。共通の友人と話すことも有効です。
まわりの人にうつ病について理解してもらいましょう。自分がうつ病で苦しんだ経験があるなら、自分の経験を話して、これから起こりうる出来事への不安を取り除いてあげましょう。うつ病には、誰にでも効く解決策はない、ということを心に留めておきましょう。あなたの時にきいた方法が、他の人に効かない場合も多々、あります。毎朝ベッドに出るために治療が必要な人もいれば、心理療法が効く人もいます。
何はともあれ、うつ病を弱いことの表れだと思っていないこと、隠す必要はないと思っていることをうつ病の人に分かってもらうことは、大きな助けになります。うつ病はひどい烙印をそのひとに捺すことになり、そのために、必要な助けが得られない人がたくさんいます。
カウンセラーなどの専門家にかかることを提案しましょう。友達の抑うつ症状が学校の単位を落としたり、仕事を休んだり、引きこもったり、危険な行動など、生活に支障が出るほどなら、ディグロート博士は、精神分析医か治療専門士の治療を受けることを勧めています。
治療を受けることを渋っている時は、他の健康診断と同様、時には心の健康もチェックする必要があると説明しましょう。それでも行くのを拒まれたら、他の友達や家族にも協力してもらいましょう。胸がとても苦しい時や足を骨折した時に医者にみてもらわない人はいません。うつ病も同じく、健康に関する大問題です。
最後に、もう一度念を押して書いておきます。
友達が自分や他人を傷つける行動を起こしそうなサインがあったら、専門機関にすぐ連絡してください。日本国内では、下記のような相談窓口があります。
いきる・ささえる相談窓口 いきる〜自殺予防対策支援ページ(都道府県・政令指定都市別の相談窓口一覧)こちら こころの耳 働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜こちら
Melanie Pinola(原文/訳:曽我美穂)
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2013年11月01日 17:35
直接的要因というほどではないにしろ、私の経験値に照らしてすべて間接要因になりえるようです。。。
■発症リスクを上げる? 下げる?
冬場のうつと甘いモノの関係
天高く馬肥ゆる……ではないが、秋から冬に過食傾向に陥る方は案外多いのではないだろうか。健康的な食欲ならまだしも、どか食いを繰り返し、さらに「気分の落ち込み」が加わるようなら、季節性のうつかもしれない。
秋から冬にかけて発症するうつ病は「冬季うつ病」と呼ばれる。典型的なうつ症状に加え、甘いものやポテトチップなど炭水化物への欲求が強く出るのが特徴。日照時間が短くなると、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌量が減少する。その不足を補うためセロトニン産生に必要な糖質を欲するのだ。冬の日照時間が短い北欧では、人口の1割がこの症状に悩んでいるとされる。
さて、その北欧は東フィンランド大学から、うつ病と食事との関連について報告が出された。中高年男性の食習慣と心疾患、2型糖尿病などの関連を調べるうち、うつ病との関連が浮かび上がり、あらためて追跡調査を試みたもの。
その結果、新鮮な野菜や果物、全粒穀物、鶏肉や魚、低脂肪のチーズを中心とした「健康的な食事」はうつ病リスクの低下と関連していた。また、以前から予防効果あり、とされてきた葉酸(レバーやホウレン草などに含まれる)の摂取と、リスクの低下があらためて示された。しかし、同じく予防効果ありとされてきたビタミンB12の摂取量や、EPAなどω-3系・ω-6系脂肪酸の血中濃度との関連は認められなかった。
一方、うつ病リスクを悪化させる食物には、ハム・ソーセージなど加工肉、菓子パン、スイーツやスナック菓子、糖分が多い飲料、ポテトフライなどジャガイモの加工品と、ジャンクフードが並ぶ。ジャンクフード依存がうつ症状を招くのか、その逆かは明確ではないものの、不健康な食事が悪化要因になることは確かだろう。
気分が落ち込み「甘いもの」「口当たりのよいもの」が恋しくなるのは人情だ。ただし、うっかり耽溺するのは考えものである。この季節の落ち込みの特効薬は午前中のうちに強い光に当たること。専用の人工照明もあるが自然光で十分だ。晴れた日も、曇り空でも、カーテンを思い切り開けよう。
(取材・構成/医学ライター・井手ゆきえ)
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2013年11月01日 17:27
飲み過ぎには要注意。。。
■乾燥する前に。水を飲むとカラダにいい12の理由+正しい水分補給の方法
Dumb Little Man:最近、米大統領夫人のミシェル・オバマが、アメリカ人はもっと水を飲んだ方がいいと発言し、その後ちょっとした議論が起こりました。しかし、これには特に政治的な意図があったのではありません。正しいことを言っただけです!
毎日水を飲むことで、健康には驚くほどいいことばかりです。特に、砂糖いっぱいのジュースを飲むくらいなら代わりに水を飲んだ方が、よっぽどいいわけで。人間の体の約70%は水分でできており、医者によっては、健康のためには1日コップ8杯の水を飲むといいといいます。
水を飲むことの12の効能と、必要十分な水分を摂る方法をお教えしましょう。
水を飲むとカラダにいい12の理由
1.体の水分バランスを整える
人間の体の60%は水なので、毎日水分を摂取することが、体の水分の吸収や循環、代謝、体温調節の管理に役立っているというのも不思議ではありません。体内の水分量が少なくなると、脳は水や水分が飲みたくなる口渇機構に働きかけます。
2.カロリー摂取を抑える
水を飲むと食欲が抑えられ、食べる量を制限することができます。また、カロリーの高い飲み物の代わりに水を飲むようにすれば、間違いなく体重が減ります。炭酸飲料というのは、栄養がほとんどないカロリーだけの飲み物なので、炭酸飲料をやめて水をもっと飲むようにすれば、すぐに体重が減るはずです。食事の前にコップ1〜2杯の水を飲むと、満腹感を感じやすくなり、食べる量が減ります。
体重をすぐに減らす別の方法として、水分の多い食べ物を食べるのもいいです。フルーツや野菜、オートミール、豆類、コンソメベースのスープを摂ると、高カロリー食品よりもゆっくりと体に浸透していくので、満腹感を感じます。水を飲むことで肝機能が向上し、体脂肪も燃えやすくなります。
3.認知力が上がる
脳の機能を適切に動かすには、一定量の酸素を脳に供給する必要があります。十分に水を飲めば、脳に必要な酸素も摂取することができます。1日にコップ8〜10杯の水を飲むと、認知力のレベルが30%上がるという研究結果もあります。また、十分に水を飲むことにより、電解質レベルを高く維持することができ、神経機能を助けることにもなります。脳とメッセージのやりとりをする神経にとっては、特に大事なことです。
4.筋肉に活力を与える
運動をしている時は、一度に適切な量の水を摂らなければなりません。筋肉細胞が適切な能力を発揮するには、適度な水分供給が必要なのです。米スポーツ医学会は、運動の2時間前に約17オンス(約500ml)の水を飲むこと、運動の合間には汗をかいた分を補うだけの水を飲むことを推奨しています。十分な水分と電解質が無いと、筋肉細胞は縮んでしまい、筋肉痛を引き起こします。十分な水分を摂ることで、筋肉はより長い時間、よりハードに動くことができるので、筋肉がより早く成長します。
5.関節をなめらかに動かす
関節痛に悩まされている場合は、十分に水分を摂ることがとても大事です。関節を柔軟かつ強靭に保つには水分が必要なので、たくさんの水を飲むと、関節の動きがなめらかになり、痛みも無くなっていきます。
6.肌をよりきれいに強くする
水分量が十分な肌はきれいに見えます。水分量の足りない肌は、乾燥し、ひび割れ、しわになりやすいです。また、十分に水を飲み、肌の内側から潤うようにすると、化粧水などで保湿した水分もしっかりと閉じ込めます。適切な水分を摂取することで、湿疹などの皮膚炎や乾癬(かんせん)に負けない肌になります。
十分に水を飲んでいない場合は、体が水分を保とうとし始め、肌がむくんだり膨張したりします。アルコールやカフェインの入った飲み物は、脱水症状を引き起こし、肌を乾燥させることになるので、飲み過ぎないようにしましょう。
7.頭痛が治まる
頭痛の大きな原因の一つが脱水症状です。頭痛薬を飲む前にまずは水を飲みましょう。神経学の雑誌に載っていた研究によると、偏頭痛持ちの人が毎日コップ6杯の水を飲むようにしたところ、頭痛に悩まされた時間が2週間で21時間以下になりました。水を飲むことは、腰痛にも効果があります。
8.腎臓の働きを助ける
腎臓は体内の毒素を排出する働きをしていますが、最高の浄化作業をするためには、定期的に随分を補給しなければなりません。腎臓が排出する主な毒素は血中尿素窒素で、水分を十分に摂っていないと、きちんと排出されません。水分補給が足りていない警告のサインは、尿の色が濃くなるというもので、さらに濃縮されると異臭もあります。慢性的に水分が足りないと腎臓結石にもなります。
9.がんを予防する
水分で常に潤っている人は、膀胱がんになる危険性が50%低く、大腸がんになる危険性は45%低くなるという調査結果があります。十分に水を飲むことで、肺がんの危険性も下がることがあります。
10.インフルエンザを撃退する
水分を毎日きちんと摂っていると、免疫システムが強くなるので、関節炎やリウマチ、腸の疾患に効果があり、インフルエンザウィルスを撃退しやすくなります。
11.心臓を健康にする
体内の水分が十分に足りていない場合、心臓は新鮮な酸素を豊富に含んだ血液を臓器に送り出すのに、より懸命に動かねばなりません。ある一定期間以上それが続くと、健康に深刻な問題が起こります。カリフォルニアのローマ・リンダ大学の研究では、毎日十分な水を飲んだ人は、心疾患になる確率がかなり低いことが分かりました。
12.快便を助ける
消化器官をスムーズに動かし続けるには、十分な水分摂取が必要です。水分を十分に摂っていないと、大腸は便から水分を吸収するため、便秘になります。定期的に排便するためには、体には十分な水分と食物繊維が必要です。
必要十分な水分を摂る方法
必要な量の水分を摂っていないと、本当に水分が必要な場所や時間に関係なく、喉が渇きやすくなり始めます。12〜16オンス(約350〜500ml)のボトルの水を、常にカバンに入れて持ち歩いたり、クルマの中や机の上に置いたり、手元にあるようにします。
ペットボトルを使い捨てるのが嫌な人は、水筒などを活用してお金も資源も節約しましょう。台所にウォーターサーバーを置いて、毎週配達を頼んで取り替えるのもいいです。浄水器や浄水ボトルを買って、水道水を飲むようにすれば、もっとお金を節約できます。
冷蔵庫の中に、常にお気に入りの健康ドリンクを入れておきましょう。ジュースやスムージー、牛乳、自家製のアイスティーなどを入れておけば、砂糖入りのソフトドリンクや、カフェイン入りの栄養ドリンクを飲みたくならずに済みます。食事をしたり、おやつを食べる時には、水か冷蔵庫にある飲み物を飲めばいいのです。
Linda Cauthen(原文/訳:的野裕子)
Photo by Thinkstock/Getty Images.
[ライフハッカー]
Posted by nob : 2013年10月28日 01:43
バニック発作の効果的予防と発症時の緊急対策。。。Vol.4
いずれも発症時の緊急対策です
せん骨ショック(3回くらいまで/やり過ぎは逆効果)
仰向けに横たわり
両腕を身体の脇に下にまっすぐ伸ばし
両膝を肩幅くらい開いて立て
そのまま両腕で身体を支えながら膝から上が一直線になる高さにお尻をゆっくりと持ち上げ一旦静止
そのまま勢い良く両足を伸ばして腰を床面に打ち付けます
はじめは敷布団の上で行ってもかまいませんが畳くらいが効果的です
レスキューレメディーを購入し常時携行します
これは数種類の精油をブレンドしたものですが
即効性もありますし薬剤と異なり副作用もありません
アロマショップで購入できます
Posted by nob : 2013年10月07日 20:33
バニック発作の効果的予防と発症時の緊急対策。。。Vol.3
夜に眠れない、あるいは悪夢にうなされる、
要はセロトニンが不足してしまうことが直接の原因、
副好感神経が優位に働き過ぎると、ノルアドレナリンが過剰に分泌されて、普段なら落ち着きとか慎重くらいの基準で快適コントロールできるはずの自らの感情が、行き過ぎて不安や恐怖に変わってしまうのです。
そう解っていて、いくら思考でコントロールしようとしても、一旦スイッチが入ってそのモードに入ってしまうと、私自身も経験がありますが、まさにお手上げ状態ですから、そうならないようにしていくしかありません。
そのためには二点、セロトニンが不足しない身体づくりと、スイッチが入ってしまうような不安や焦りのような心の要素をとり除くことです。
前者は以下に説明するように、後者は自分でメンタルコントロールをして、所詮はみなつまらない取るに足りないことばかりだと、くよくよしたりしないよう思い込むようにしましょう。
セロトニンづくりは、太陽光と腹式(筋肉)呼吸とリズム運動の三点が鍵、一番のお薦めは、朝一番(起床後30分以内)のセロトニン歩きとバナナ一本で、私も当時はほぼ毎日実行していました。
朝起きたらすぐ歩ける楽な格好で表へ出ます。
準備運動を兼ねた体操と深呼吸。
深呼吸は、まずしっかり息を吐ききるところからスタート、鼻からゆっくり吸って、酸素で胸とお腹を一杯に膨らませる感じです。
それから吸う時間の3倍くらいの時間をかけてゆっくりと吐ききります。
吐ききる時には、胸とお腹を空っぽにする感じ、最後は丹田(身体の真ん中おへその下)を中心に、腹筋に力をしっかり入れて、残った空気を絞り出すような感じです。
もう数回繰り返すこの段階でかなりセロトニンがつくられていますから、すでに随分すっきりしてると思います。
それから、両手を大きく振って、下腹部にしっかり力を入れて、イッチニイッイッチニイッとリズミカルに、大股で少し息がきれるくらいのイメージでしっかり歩きます。
但し歩き過ぎは禁物、20分から最長でも25分以内に抑えます。
疲れを感じない気持ちよく歩ける範囲に留めないと、身体に乳酸がたまって、せっかくつくったセロトニンをまた分解してしまいます。
私も発症当初は、歩いてる間は苦しくないこともあって、1日中何万歩も歩き回って、悪循環に陥ってしまっていたりもしました。
以上を、天気のいい太陽の光を浴びながらできれば効果テキメン、雲りの日でもかなり効果があります。雨の日も歩きたいようなら歩いても構いませんが、体操と深呼吸だけでも構いません。
それから、冷たくない水を飲みながらバナナを一本ゆっくり食べる。
私は、それから朝ご飯をしっかり食べていましたが、朝をバナナだけにすると、数年前に流行ったバナナダイエット、昼と夜を好きなものをしっかり食べても、高いダイエット効果も期待できます。
Posted by nob : 2013年10月02日 10:50
バニック発作の効果的予防と発症時の緊急対策。。。Vol.2
ツボ押し三ヵ所
・合谷(ごうこく):手の甲側親指と人差し指の骨が交わるところの内側
・手の平の真ん中
・手首と手の平の境のシワの手首側すぐ下、小指から真っ直ぐ下ろした線の上
指でゆっくり少し強めに指圧します。
爪もみも落ち着きます。
爪の生え際の両端を、痛いくらいの強さで指でつまんで刺激します。
薬指は厳禁。
親指、人差し指、中指を各10秒ずつ、小指だけは20秒。
朝、昼、晩の食事前に、1日3回続けます。
クエン酸を心がけて摂ります。
梅干しやレモンやグレープフルーツ、お酢など、何でも構いません。
Posted by nob : 2013年09月30日 21:30
バニック発作の効果的予防と発症時の緊急対策。。。
さて、今回は、効果絶大な対策を二つお伝えしますので、どちらも是非とも試してみてください。
まず、一つ目は、肘浴です。
タライくらいの肘まで浸かれる容器に、45℃のお湯を肘から先がすべて浸かるくらいにはって、朝と晩に5分ずつ浸けます。
腕が赤くなるほどの我慢できるギリギリの熱さに、冷めても構いませんが、浸け始めは45℃を守ります。
二つ目は、蒸しタオルです。
絞ったタオルをビニール袋に入れ、電子レンジで60~70℃に温めます。
タオルをまず二回折って1/4サイズに、そして向きを変えて両側から一回たたみ込んでさらに1/3サイズにします。
それを眠る前に、肌に直接胸に置きます。
位置は、タオルの上端が鎖骨の下に来る胸の中央に横向きです。
温めはじめのタオルの温度は、我慢できるギリギリを心がけてください。
そして、タオルが冷めるまで(冷たく感じない程度に)寝転ぶ、あるいは布団の中でリラックス。
これを、2~3回繰り返します。
電子レンジを枕元に置ければベスト、これで安眠間違いなしです。
いずれも、パニック発作発症時の緊急対策としてももちろん有効ですが、平常時の予防対策としても日々こつこつ続けてみてください。
Posted by nob : 2013年09月25日 17:01
無常なる自己を生きる/変わらぬ確かなものは何処にも存在しない。。。Vol.2
たとえば江戸時代なら百姓の子は百姓、武士の子は武士になるものと限定されていましたよね。悩まずに済んだ。
ところが、いまは自己実現の自由がある。そのせいで私も「坊さんになってもいいけど、ならなくてもいいはずだ」と、子供の頃からすごく悩んだんです。
でも、日本人の幸せっていうのは、限定されたことにどう「仕合わせ」ていくか。あるいは、もう決められていることをどう寿ことほぐかというところにあるんじゃないでしょうか。
さらに言うなら、西洋的な自己が持ち込まれたことが、自殺を増やすきっかけにもなったような気がするんです。「自己実現しなさい」と言われても、その自己が見えないと、ものすごい苦しみが生まれますから。
「生活はコンパクトに、いつでも移動できるようにしたほうがいい(鴨長明・方丈記)」と言う。
ある意味では災害の多い時代の理想の生活を提案しているんですけれども、「富める人にそれを求めるわけじゃない」という一言を書いた途端、長明はハッと気がつくんですね。
「待てよ。こういう自信ありげな発言というのは、仏様のいう執着ではなかったか。自分は執着を捨てるために出家したのではなかったか」と自省する。
「その価値観だけでずっと生きていくわけにはいかない(山田太一)」とおっしゃったことにもつながっていて、まさに仏教の勘どころだと思うんです。仏教では、原理とか絶対的なものを認めません。
ただ、その瞬間ごとに絶対的な唯一の道というのはあるんですね。しかし、それはすべて方便であって、それでずっといくわけじゃない。
世の中が無常なのは誰でもわかりますが、自分自身も無常にならなきゃいけないんです。つまり、「こうではないか」と思ったことを、常に突き崩していく必要があるわけですね。
[玄侑宗久談より/DIAMOND online]
Posted by nob : 2013年09月16日 13:50
無常なる自己を生きる/変わらぬ確かなものは何処にも存在しない。。。
ある頃から日本人は、自分の至らなさや、人間それぞれが持っている限界への意識が足りなくなっているんじゃないかと思えてきました。
人間は1人ひとり限界だらけの存在でしょう。
ところが、たとえば学校の卒業式なんかでは、「君たちは全方向に可能性を持っている。努力次第で何にでもなれる」というようなことを言います。
でも、僕という人間1人をとってみても、生まれる場所も、親も、容貌も、背丈も、才能も、何も選べない。それだけでもう限界だらけですよね。
木村拓哉さんみたいなスターには、努力したってなりようがない(笑)。
その限界から目を背けて、努力すれば何でもできるって非現実的なことを言うのはおかしいと思うんです。
ですから、自分も、そして他者も万能ではないことを認識すること、いわば人間の哀しみを知ることが大事だと思うんです。
悲惨な目に遭うことも人間の心を育てますが、その一方で考えないといけないのは、その価値観だけでずっと生きていくことはできないということです。
「メメント・モリ」とよく言いますけれど、確かに死を思うことは大切です。根本的な体験を突きつけられると、いままでのくだらない悩みが無化されて、いちばん大事なものが見えてくる。
でも、それだけでずっと生きたら、人間は非常につまらない存在になります。ですから、悲劇や苦労の中で啓示された真理だけで生きていくのもまずいんじゃないかと、僕は思うんです。
小説でも、いつの間にかそうなってしまうことってありますね。
無意識から偶然に何かが出てきて、それが最初から考えていたことよりも、意味が濃く面白くもなったりすることがあります。
[山田太一談より/PRESIDENT online]
Posted by nob : 2013年09月16日 13:29
まずはすべて一切の薬を絶つことから。。。Vol.5/まずは感じそして思い悩める力は希有な才能の一つ。。。
あれっ?最近調子いいかもっ??、…くらいの感じで快復していきますから大丈夫です、、、経験者語る。。。
心も身体も、これまでの長期間にわたる小さな悪習慣の蓄積が染み付いて、癖のようになっているでしょうから、それなりに少し時間がかかるかもしれません。
薬の副作用が身体から抜けた後のこと、結局はストレスを溜めない自分自身づくりや環境整備という根本の原因を解消することが一番肝心です。
今回を絶好の機会と捉えて、自分自身と真っ直ぐに向き合い、何も持たない何もしないあるがままの自らを丸ごとそのまま受け容れるところ、まさにオールクリアゼロから始めていきましょう。
以下参考までにnikkeiBPnetの記事より、
うつ病は軽症のうちに治す! その治療法は?
和田秀樹(わだ・ひでき)
精神科医
悩みを建設的なものにする「悩み方の作法」
答えが出ないことで悩み続けるのはメンタルヘルスに悪い
姜尚中氏の『悩む力』という本が売れているようだが、その本の中では、徹底的に悩めというようなことが書いてある。
哲学者になりたい人はそれでもいいかもしれないが、我々、精神科医は、そんなことは勧めない。
答えが出ないことで悩み続けたり、悩むことで余計に悩みが深くなるようでは、メンタルヘルスに悪い。
ただ、悩むなと言っているわけではない。少なくとも、最近になってアメリカでも注目されるようになった森田療法の考え方ではそうではない。
もう少し悩み方を変えることで、悩みを建設的なものにする、適応的なものにするというのが、精神科医からのアドバイスなのだ。
実際、今の時代は、昔のような終身雇用の時代と違って、企業も悠長に待ってくれないし、前回に生活保護の利用術を書いたが、悩みに悩んだ挙句、仕事が遅いとされたり、仕事ができないという話になってクビにでもなったら、生活保護だって門前払いが増えているらしいから大変だ。
変えられないことを悩み続けるのは神経症的
では、どういう悩みが神経症的なのだろう?
一つは、変えられないことを悩むということである。
変えられないことを悩むと、それが変わらないために、余計に焦ってしまったり、気持ちがそこにいってしまう。すると悩みが余計に深くなるという悪循環を呈してしまう。
たとえば、顔が赤いことを悩む人がいるとする。顔が赤いことを、「赤くなくなれ」と思ったところで、自力では変えることはできない。
さらに、悩んでいる分、顔が赤いことが気になるし、実際に毛細血管が開いたりして余計に顔が赤くなることもある。歯が痛いことを気にすると、余計に歯が痛くなるというのは、誰しもが経験することだろう。
ある感覚に注意がいくと、余計に神経が鋭敏になってその感覚がひどくなり、そのためにさらに注意がそちらに行ってしまうことを、前述の森田療法という心の治療法では、「注意と感覚の悪循環」や「とらわれ」と呼び、この悪循環をみつけ、それを断つように仕向けることを重要視している。
変えられないことを悩むと、悩んでも解決しないからよけいに悩むことになる。悩めば悩むほど具合が悪くなるのである。こういう悩み方を見つけたら、精神科の医者としては放っておくわけにはいかないのだ。
一つのことを悩む、確率の低いことを悩む
もう一つは、人間というのは一つのことに悩みだすと、ほかのことに悩めない。頭隠して尻隠さずということが往々にして起こる。
テレビのワイドショーを見ていても、ある時期は原発ばかりに不安がいき、次にいじめばかりになるが、人間というのは同時に二つ三つのことに目を配って悩むという器用なことはなかなかできないことを如実に示しているようだ。
ダイエットを気にしている人は、それによってしわが深くなったことを意外に悩まない。我々が神経症の人を見ていても、痛感するのは、あることには思い切り悩んで思いつめているのに、大事なことへの気配りがすっかり欠けていることが多いことだ。
原発の問題を悩むのは悪いことではないが、いつの間にか二酸化炭素(CO2)の排出が増えることで起こるとされる地球温暖化の問題がどこかに吹っ飛んでしまったし(昔は、それにばかり悩んでいた感があるが)、次の地震の心配をする割には、オール電化がどこかに吹っ飛んでしまって、火事の心配をしなくていいのかというようなことが起こっている。
もう一つの神経症的な悩みというのは、確率の低いことを悩むことだ。
落ちるのが怖くて飛行機に乗れないという人がいると、病的な怖がりと思う人もいるし、自分もなんとなく納得できる人もいるだろう。
しかし、実際には、普通に道を歩いていて交通事故で死ぬ確率のほうがはるかに高い。人間というものは、一度、怖いと思うと確率的な判断ができないようだ。だから、確率が低いものに必要以上に悩んで、日常生活が不便になることが往々にしてある。
何のために悩んでいるのか?
では、どうすれば、この手の悩みが建設的な悩みになるのだろうか?
一つには、何のために悩むのかを問い直すことだ。
顔が赤いことを悩む人に、「なんで赤いのが困るの?」と聞くと、「人に嫌われたくないから」というような返事をすることが多い。
そういう際に、「そうやって人を避けているほうがかえって嫌われることが多いよ」とか、「顔が赤いことは治せないけど、どうすれば嫌われないかは一緒に考えられるよ」と誘うこともある。
あいさつの仕方を変えてみるとか、「尊敬する人の前だと顔が赤くなるんです」というエクスキューズを入れるなど、顔が赤くても人に好かれる方法はいくらでもある。
こういう人の多くは、顔が赤いのが治れば、すぐに人に好かれるような勘違いをしている。しかし、顔が赤くなくても好かれていない人はいくらでもいる。
やせればもてると思って、ダイエット依存になっている人も同じような傾向があるから要注意だ。やせても、話し方やファッションその他を変えないともてるようにならないが、この手の人はやせ方が足りないせいだと思い、余計にダイエットに走ってしまう。
するとやせ過ぎで元よりもてなくなってしまうのだ。ダイエットをしなくても、どうやったらもてるかを考えるほうが建設的だろう。実際、やせていても、もてない人はいくらでもいるのだから。
あとは、変えられることと変えられないことを峻別することだ。顔が赤いのは変えられないが、人との接し方は変えられる。
変えられることを悩んでいる限りは、あれこれ変えているうちに、いつかは目的(たとえば人に好かれること)に達することができる。話し方を変えてみる、ファッションを変えてみる、どんな話し方にしよう、どんなファッションにしようと悩み過ぎるより、あれこれと変えてみるうちに、いちばんもてるパターンがみつかるというわけである。
確率の判断、悩みの損切りが大切
もう一つ、我々が勧めるのは、やはり確率の判断である。
飛行機が落ちて死ぬ確率というのは、宝くじに2回続けて当たるのと同じくらいの確率だそうだ。意外にも計算してみると、確率の高いこと、低いことがわかる。発がん物質などの心配をする人も多いが、1万人に一人くらいのレベルでがんになるものだって、そんな風に言われるし、タバコのようにパーセントのレベルのものもある。
どれ以上の確率ならやめよう、どれ以下の確率なら割り切ろうという判断だって大切だろう。
もう一つ、言っておきたいのは、悩みの損切りの考え方だ。
今のような世知辛い世の中では、何日、何週間も悩んでいると、それこそ淘汰の対象となりかねない。ベストの仕事をしようと悩んでいたら、仕事が遅いとみなされて、リストラにあったなどというのでは目もあてられない。
何日以上悩んだら、悩むのはやめて、暫定的な答えを出して、動こうと決めておかないと、結局、答えがでないで終わってしまう。歩きながら考えるというが、やってみれば、意外にうまくいくとか、やっぱりダメだとかがわかる。それに応じて、また方針を変えていくというほうが多くの場合現実的だ。
その場その場で悩みを暫定的にでも解決していく
ということで『悩み方の作法』はそれなりに、自分が精神科医として、患者さんにアドバイスをする際に心がけていることをまとめた自信作なのだが、早速、アマゾンの書評欄で「下手な悩み方で悪かったな!」と酷評され、その方にナチの強制収容所で悩み苦しんだV.E.フランクルの本を勧められ、「深みや説得力が全く違いますから」と書かれてしまった。
私も古典的な哲学書で悩みを解決しようとするのを否定しないし、この人については、私の著書で解決できなかったのは私の力不足だろう。ただ、深みや説得力があっても、この書評を読ませていただく限り、悩みが解決したと思えないし、だから、「下手な悩み方で悪かったな」という話になるのだろう。
人生は悩みの連続であるが、その場その場で悩みを暫定的にでも解決していかないと、サバイバルは困難な時代だ。読書量にしても多いだけでは、現実のメリットは小さい。
私の本を読んでもらわなくてもいいから、なんのために悩むのかはぜひ再考してほしい。
Posted by nob : 2013年09月14日 13:23
まずはすべて一切の薬を絶つことから。。。Vol.4/医師も様々、かかるなら信頼できる医師が見つかるまで探す、、、もしくは自己治療、自ら招いた内的症状は自ら解消できる。。。
その後調子はいかがでしょう。
そろそろ多少気分が上向き始めてくる頃ではないでしょうか。
私が把握しているすべての情報を懇意にしている医師にも伝えて、率直な判断をしてもらったところ、私と同意見抗うつ剤の副作用であろうとのことでした。
うつ病患者は、自分がうつ病である自覚がないか、認めたがらないもの、様々な症状を訴えるそもそもうつ病ではない貴方が、抗うつ剤を飲むからこういうことになると一刀両断の一言、高齢者には睡眠導入剤を出すだけでも慎重を期すのに、抗うつ剤をそれもこんなに大量に出すなんて、同じ医師として信じられないと驚き憤慨していました。
結論から言って、抗うつ剤と睡眠薬を全部やめればすぐに良くなるとのことです。
一番強いパキシルでも、身体から抜けるのにそんな時間はかからないそうです。
貴方のケースは、かつての私と同じ軽いパニック障害に、加齢であちこちに生じてくる物理的な支障をうつ病のせいとの思い込んで、それらを訴える貴方に、医師が安易に薬を処方してしまつたというくらいのところかと思われます。
以前から続いている軽い幻覚も、デパスと睡眠導入剤の副作用でしょうから、このままもう飲まなければ自然に快復していくでしょう。
但し、これらとは関係ないクレストール錠 2、5mとボナロン錠 35mは、骨粗鬆症とコレステロールコントロールのために服用を続けたほうがよいとのことです。
というわけで、まずはこのまま断薬後の様子を見つつ、症状が収まってきたら、いよいよ長期的かつ本質的なストレスコントロールのトレーニングをしていきましょう。
以下参考までにnikkeiBPnetの記事より、
うつ病は軽症のうちに治す! その治療法は?
和田秀樹(わだ・ひでき)
精神科医
現代社会に多いストレッサーへの「三つの対処法」
体罰を受けた生徒が自殺したという事件があり、体罰をなくそうという声が強まっているし、大阪市の橋下徹市長の毅然とした態度も注目されている。
いじめ自殺とされる自殺にしても、今回のような体罰にしても、確かに心にダメージや傷を受けることだろう。
こういうものを精神医学や心理学では、ストレスとか、トラウマと呼ぶことが多い。
精神医学でのトラウマの意味
トラウマという言葉も日本では日常用語のように使われるようになったが、精神医学の世界では、危うく死ぬとか重傷であるようなレベルの出来事を経験するとか、目撃するとか、直面するとかいう場合に用いることになっている。つまり、ピストル強盗にあうとか、大震災にあうとか、暴力団のような集団にリンチされるとか、あるいは、それを目撃するとかである。
死ぬ生きるにはそれほどかかわらないかもしれないが(殺すぞと脅す場合も少なくないが)、レイプの場合は、このようなトラウマ的な出来事とみなされるのが通例である。ただ、精神科の世界でも、もう少し軽いレベルでも、たとえば、人前で罵倒されるとか、普通に殴られるとか、そのようなレベルでもトラウマとみなそうと考える人も少なくない。
一般的には、トラウマのレベルにまでいかない、心のダメージや負荷の場合はストレスと言われる。
仕事で嫌なことがあって、胃潰瘍になってしまうとか、うつ的になってしまうとかは、ストレス性とかよく言われるわけだ。
トラウマ的出来事とストレッサー
一般的に、いじめ(これも、殺すぞと脅す悪ガキもいるかもしれない)とか、体罰の場合は、命にかかわるとか、重傷を負うわけではないから、厳密にはストレスを受けることになる。
さて、ここで用語の混乱が多いので改めて注意しておきたいが、震災であれ、レイプであれ、いじめであれ、体罰であれ、これらそのものがトラウマとかストレスなのではない。こういうものは、「トラウマやストレスを引き起こすもの」と考えられている。
トラウマを引き起こすものをトラウマ的出来事と呼び、ストレスを引き起こすものをストレッサーと呼ぶ。
そしてトラウマ的出来事によって、生じた心の傷のことをトラウマと呼ぶし、ストレッサーによって生じた心の主観的なダメージをストレスというのだ。
ついでに言うと、そのようなトラウマ(心の傷)によって、悪夢を見たり、目の前にフラッシュバックといって、その光景が突然浮かんでくるような、トラウマ的出来事の再体験があり、またトラウマを受けてから、ぼんやりしたり、うつっぽくなったりして、そのくせ後ろでちょっとした物音がしたら激しくビクッとするような、感受性の鈍麻と過敏が入り混じったような精神状態が4週間以上続く場合に、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と呼ぶ。トラウマという心の傷にはいろいろな種類があって、すべてがPTSDであるわけではない。
殴られて怪我をすることもあれば、しないこともあるように、同じようなトラウマ的出来事を経験した場合でも、トラウマになる場合とならない場合がある。重症のトラウマの後遺症とされるPTSDに関して言えば、レイプなどを受けた人は半数近くがPTSDになるが、震災のような自然災害の場合は5%程度とされている。
善玉ストレスと悪玉ストレス
さて、何が言いたくて、この話をしたかというと、いわゆるトラウマ的出来事と呼ばれるような命にかかわる体験は、しないに越したことはないし、そのような出来事を体験させる加害者は、犯罪者として処罰される。
しかし、ストレッサーと呼ばれるものは、世の中にごまんとあるし、なくすことは困難だろう。
もちろん、職場での嫌がらせやパワハラのように、それをなくす方向を目指すことは否定しない。ただ一方で、ストレッサーがあっても、それを切り抜ける能力はサバイバルのためには不可欠なことである。
その一つが心を鍛えるということである。
実は、ストレスには「善玉ストレス」と「悪玉ストレス」というものがある。
プレッシャーとか叱責のようなストレッサーがある一定のレベルまでは、それを強めていったほうが、その人のパフォーマンスは高まる。ところが、ある一定上のストレッサーをかけると、それが強まるほど、パフォーマンスが落ちてしまう。
その限界点までのストレスを善玉ストレス、それを超えた強いストレスを悪玉ストレスと呼んでいる。
要するにプレッシャーをかけることや叱責を与えるようなストレッサーは一概に悪いとは言えないが、限界を超えると逆効果になって、メンタルにも悪いということだ。
ストレッサーに対するものの見方を変える
ただ、人間というのは、成長したり、鍛えたりしていくうちに、この善玉と悪玉の境界点が変わってくる。たとえば、子供のうちは叱られると泣き出して、パフォーマンスが落ちていたのに、成長するとそのくらいの叱責なら逆に能力が増すということがある。
いじめを撲滅という考え方もあまりに極端で、子供が小さいころから悪口や仲間外れなどを経験しないで子供時代を過ごすと、そういうものへの耐性ができず、大人になってから、ちょっと組織になじめないとか、ちょっと批判されたくらいで会社をやめてしまうとか、うつになってしまうというようなことになりかねない。
ただ、現実には、ストレス耐性には個人差があるし、うまく成長する人もしない人もいる。
そういう場合のストレッサーへの対処にはいくつかの方法が想定される。
一つは、以前、認知療法という心の治療法を紹介したが、ストレッサーに対するものの見方を変えるということだ。
怖い上司がいても、その人の怖い面だけでなく、人間的な面も見ることができるようになるとか、あるいは自分をいじめていると考えるのだけでなく、自分を育てるためにやってくれているのかもしれないと思えれば、同じように上司がストレッサーになっていても、主観的なストレスは違ってくるだろう。
「逃げる」という現実的な選択肢
二つ目は、「逃げる」ことだ。
今回の体罰を受けて自殺した生徒に置き換えてみると、転校するとか、今回のケースなら体罰のある部活をやめるということだ。
この事件では、クラブ活動をやめると進級できないなどという制約があるために、「逃げる」ことが困難だったと報じられている。いじめであれ、体罰であれ、嫌がらせであれ、激しい借金の取り立てであれ、それから逃げることができないと思ったときに、人間のストレスは大きくなるし、ひどい場合には絶望して自殺することになる。
職場のストレスの場合は、休職、配置転換の申し出、転職などが逃げ方ということになるだろう。
そういうことをするのは、負け犬だとか将来に傷がつくと思うかもしれないが、そこでメンタルをどんどん悪くしていって、仕事の能率がどんどん落ちるほうが、かえって評価が下がるかもしれない。うつ病になったり、最悪、自殺なんてことになれば取り返しはつかない。
企業の側も昔と比べて、メンタルヘルスに多少は理解を深めてきているし、社員の自殺は職場全体に影響するのでなるべく避けたいのが本音だし、うつ病で急に休職されるより、今具合が悪いから配置を変えてくれというほうがまだ対処できる。これが本音だろう。
また、企業の理解がないときでも、昔と比べたら、はるかに転職しやすくもなっている。
「逃げる」ということが考えらえないと、人間の心は追い詰められやすい。
現実的な解決法として、少なくとも選択肢には入れてほしい。
友人に慰めてもらったり、カウンセリングに行く
三つ目の解決策が、ストレス体験を共有したり、慰めたりしてもらうことだ。
社内いじめや嫌がらせ、そのほかのストレッサーがあったとしても、同僚であれ、親友であれ、泣きつける相手がいれば、心のダメージが和らぐのは確かなことだ。
そういう適当な相手が見つからない人のために、カウンセラーがいると考えていい。
さらに言うと、欧米で盛んに行われる自殺予防教育の基本は、うつ病など心の病を疑わせるようにその症状を子供にも教え、身近にいるときに、医療やカウンセラーにつなぐようにすることと、友人などから「死にたい」と打ち明けられたら、自分ならどのように対応するかなどを教えることだ。
自分から行けない場合に、周囲が気づいて、カウンセラーや医者につないでくれることが可能であればそれに越したことはない。逆に、自分の周囲でストレスを感じている人がいて、うつ病のレベルのように見えるなら、それを医者やカウンセラーにつないでいくというのが、この予防教育の趣旨だ。
さらに、自分がつらいときに、医者やカウンセラーに頼るのは悪いことでも恥ずかしいことでもないと教えていく。それで外国ではかなりの自殺を減らしている。
実は、日本でも地道なメンタルケアの取り組みで、2012年は15年ぶりに自殺者が3万人を切っている。
ストレスを感じたら、医者やカウンセラーに頼る、親友に泣きごとを言う、という当たり前の習慣が、ストレスフリーの状態に中々 ならない現代社会での重要なサバイバル術なのだ。
Posted by nob : 2013年09月13日 08:00
まずはすべて一切の薬を絶つことから。。。Vol.3
誰もがふとしたきっかけでいとも簡単に陥ってしまうのが心の病というもの、
貴方自身で感じているほどには実際はさほど深刻な状況ではない気がしています。
きっぱりと断薬してしまうことをお勧めしますが、このまま通院と薬による加療を継続していくのであれば、
薬を処方してくれた医師を頭ごなしに否定しているわけではなく、医師として常識的で理にかなった治療をしてくれているはずだとは思います。
私の知り合いに、投薬の判断には絶対の自信がある(そしてそれが治療のすべて)と公言して憚らない精神科医がいますが、そもそも本質的病因の認識と根源的治療は、彼らが受けてきた教育の範囲には含まれてすらもいないのです。
また、抗鬱剤や抗がん剤や抗生剤のような薬は、副作用の個人差が大きいものですし、まずそもそも効果があるかないかも、服用してみて初めて判ります。
服用しながら経過観察をして量を調整したり、薬を変更するわけで、ましてや複数の薬の飲み合わせによる副作用の観察など、一緒に暮らしているわけでもなし、実際は不可能と言わざるをえません。
結局のところ、患者自身が自ら判断して、その時々の状況や希望を医師に率直に伝えていくしかありません。
以下参考までにnikkeiBPnetの記事より、
うつ病は軽症のうちに治す! その治療法は?
和田秀樹(わだ・ひでき)
精神科医
うつ病は悪循環を生みやすく、放っておくと悪化する
実際、うつ病というのは、このようなダメージが意外にも悪循環を起こしやすい病気だ。
前にも認知療法について少し触れたが、うつ病になるとものの見方が悲観的になる。ところが、悲観的になるとうつ病がよけいに悪くなってしまう。うつ病による悲観を治していかないと、どんどん落ち込みがひどくなり、デフレスパイラルのようになってしまう。最悪、絶望から自殺につながることさえある。
また、うつ病になると夜眠れなくなることが多いが、不眠でよけいにセロトニンのような神経伝達物質が減るために、うつがいっそう悪くなることが多い。
とくに良くないのは、眠れないからといってお酒を飲むことだ。アルコールはセロトニンを枯渇させるとされ、一般的にうつ病のときにアルコールを飲むとよけいに悪くなるとされている。さらに、深酒が自殺の決行の契機になることも珍しくない。
あるいは、うつ病になって外出しなくなり、日光に当たらなかったり、気分が落ち込んで暗い部屋にいると、やはりセロトニンの分泌が悪くなると考えられている。
あるいは、うつ病になると食欲不振になることが多いが、あっさりしたものばかり食べて肉類をほとんど取らないようだと、セロトニンの材料のトリプトファンというアミノ酸が不足してしまう。
このようにうつ病というのは、悪循環を生みやすいし、放っておくとよけいに悪くなる要因が多い。そういう点で、うつ病の早期治療は大切だと訴えたかったのだ。
うつ病の薬の恐ろしい副作用
実は、前述の記事では、薬を早く飲んで脳内のセロトニンを早めに戻しておかないと神経がどんどん縮んでしまうという説を紹介したし、今のうつ病の薬は、昔のうつ病の薬と比べて、ずっと副作用が少ないという話もした。
そのときに、「今のうつ病の薬は、吐き気や食欲不振などの副作用がないわけでないし、たまにひどい興奮状態になってしまうという副作用も問題になっているが、そういう場合に、本人なり周囲が気づいてやめるということを知っていれば、やはり有益なことが多い」とも書いた。
ただ、その後、思うところがあって、うつ病の薬について勉強し直すにつれて、この書き方はやはり誤解を招くと反省した。
一番の問題は、この書き方では、うつ病も躁うつ病(現在は「双極性障害」というのが正式な病名である)も一緒くたにされることだ。
確かに、躁状態のない典型的なうつ病の場合は、今のうつ病の薬(SSRI、SNRIなどと総称される抗うつ剤)で、ひどい興奮状態になったり、異常行動を起こす(これをアクチベーション・シンドロームと呼ぶ)リスクは少ないが、躁うつ病の人に今のうつ病の薬を使うと、かなりひどい興奮状態を起こす。そして、最悪の場合には殺人事件にまで発展する。
1999年に起きた全日空機ハイジャック事件で、機長を刺殺した犯人は、この新しいタイプの抗うつ薬を服用していて、判決でそのことが考慮された。
そのほか、川崎の男児投げ落とし事件、京都の学習塾女児殺害事件、ドンキホーテ放火事件など、かなりの数の有名事件で、SSRIと呼ばれる抗うつ剤を犯人が服用していることが明らかになっている。
薬が効かない人もいる
SSRIの副作用が注目されるきっかけになったのは、99年に起こったアメリカのコロンバイン高校銃乱射事件だった(それ以前からも問題にする人は多かったが、一躍注目を集めたという点で)。
とくに、この副作用は躁うつ病の人に出やすいとされるが、典型的なうつ病でも起こり得るとされるようになった。
「本人なり周囲が気づいてやめるということを知っていれば」と書いたが、最初は薬が効いて調子がよくなっているという感じになるので、そううまくいくとは限らない。
確かにそんなに多い副作用ではないのだが、万が一これに当たってしまうと、ひどい場合は、本人の人生がふいになってしまうし、それ以上に周囲に大きな犠牲を及ぼすことになる。ここまでひどい副作用でなくても、私が学生時代とか研修医の時代には、日本には躁うつ病のタイプは少なく、典型的なうつが多いとされていたのだが、今は、薬で躁や興奮状態になる人が思ったより多いことがわかっている。これが薬のせいなのか、躁うつ病が昔考えられていたより多いためなのかはわからないが、注意するに越したことはない。
こういう激しい興奮のほか、うつ病の薬は、うつそのものは改善するのだが、逆に自殺のリスクは増やしてしまうことも問題になっている。うつは治りかけが危ないというが、薬そのものは悪くないのだろうが、めっきり落ち込んでいる状態から不安定な状態になったときに、自殺がどうしても増えてしまうようだ。
薬は効く人には効くというのは精神科医としては実感しているし、実際6割くらいの人には有効だとされている(逆に4割くらいの人にはほとんど効かないということも知っておくべきだろう)。おそらく、薬が効くことで、脳の変性も食い止めることができるから、早期治療で脳の障害が少なくて済み、ほとんどダメージを受けない人もたくさんいるはずだ。
カウンセリングがお勧めだが、まだ十分な環境ではない
だが一方で、激しい攻撃性や自殺のリスクがある以上、周囲がうつ病の薬は怖いことがあることを十分理解してきちんと観察しておかないと、取り返しのつかないことになる。
そういう点で、薬の副作用が大したことがないような書き方をしたのを反省したし、今回の本ではそういうことに注意を促すようにも努めた。
ただし、うつ病というのは、悪循環を起こしやすい病気だし、早期治療をしないと脳にダメージが起こるという仮説も長年の精神科医の経験からおそらく当たっていると思える。
だとすると、薬以外の早期治療を考えないといけなくなる。
一つはもちろんカウンセリングだろう。
本欄「うつ病になりやすい思考パターンとテレビ問題」で紹介した認知療法という治療法は、アメリカでも有効性が確認されているし、厚生労働省も有効性を認めている。
うつになりやすい思考パターンを変えていったり、必要以上に思いつめないで済むようにしたりしていくと、うつ病の人でも気持ちが軽くなることは少なくない。
そういう形でうつが改善しても、おそらくはセロトニンの出はよくなるようだ。
早めのカウンセリング、早めの認知療法をお勧めしたいが、まだまだそれらのトレーニングを十分に受けている人は多くないし、認知療法に本来必要なだけの時間をかけていると保健診療では赤字が出てしまうということもあって、実際には十分に受けるのは困難だ。
臨床心理士や、保険のきかない自費のクリニック(私も行っている)でカウンセリングを受けるのが理想だろうが、金額的には高くついてしまう。
早めに生活リズムを改善する
二つ目は、早めの生活リズムの改善だ。
周囲の圧力を気にせず、ゆっくり休む、体を動かす、日光に当たるなど生活の改善は、すぐにうつが治るわけではないだろうが、徐々に本調子に戻っていくためには大切な手段だ。実際、薬が開発される前は、このやり方しか治す方法がないも同然だった。
でも、それでかなりの人が治っていったのも事実なのである。
これは、休みが必要かもしれないが、お金は大してかからない(休むことで大幅な減収になる人にとっては、実はものすごい費用になってしまうが)。
三つ目は、電気や磁気による治療だ。
電気治療というのはいわゆる電気ショックのことだが、これは昔から自殺念慮を劇的に改善することで注目されていた。
私がアメリカ留学していた頃に、筋弛緩剤というのを使った無けいれん(電気ショックを受けてもけいれんを起こさない)の修正型電撃療法というものが確立され、アメリカでは高齢者には薬を使うよりこちらのほうが望ましいと習ったので、びっくりした記憶がある。
これは日本でも、いくつかの大学病院で導入されている。
入院が必要だが、保険もきくし、アメリカでは麻酔のテクニシャンがやるところを、日本ではちゃんと麻酔科医がつくので安全性も高い。
注目されるTMS治療、ただし保険はきかない
電気ショックには抵抗があるし、入院する余裕がないという人に朗報なのが、TMS(経頭蓋磁気刺激)治療である。
これは、安全性が高いうえに通いで治療を受けられるので、会社を休む必要もない。
4割くらいの人にしか効かないのが欠点だが、害がほとんどないのも嬉しい。すでにアメリカの医薬品の認可機関であるFDA(米食品医薬品局)も認可している。人によってはかなり有効なようで、私の知り合いの脚本家は何十年ぶりかですっきりした気分のなったとのことだった。
ただ、残念ながら、日本では保険がきかない。そのため1回4万円程度、大体20〜30回の治療が必要とされているので、相当な高額になってしまう。
うつ病で仕事を失った人などのことを考えると安いに越したことはないが、うつで職を失う、休職を重ねるなどの逸失利益を考えると、ある程度お金を使ってもいいのではないかという気がする。
私の自費のカウンセリングのクリニックも大して流行っていないので、愚痴になってしまうが、日本人はもっとメンタルヘルスにお金を使っていい気がする。
少なくとも、薬の危険性を認識しながら、うつは早いうちに治したほうがいいと、改めて強調したい。実際、うつは自殺のリスクがものすごく高い病気だし、免疫機能も落として、がんになりやすくなるという説もあるくらいだから。
Posted by nob : 2013年09月12日 21:15
まずはすべて一切の薬を絶つことから。。。Vol.2
■製薬会社も認めています。
臨床試験の結果によると867人中 516人に副作用が現れたそうです。
嘔吐130例、傾眠(疲れやすくすぐ寝てしまう)117例、口渇(のどの渇き)72例 食欲不振42例、めまい41例。
他には、
自殺、不安、幻覚、震え、けいれん、肝不全、肝炎などです。
[パキシルの説明書より]
■ある患者の経験談
質問の主旨は「抗うつ剤は飲まなくても大丈夫でしょうか?」
ということであれば、大丈夫と言えるのではないでしょうか。
私自身の経験からすれば、うつ病を治すのに必要なのは抗うつ剤よりも休養です。
休養せずに抗うつ剤を飲んでいるだけでは、副作用のほうが目立つと思います。
うつ病を治すには、まずは休養すること。
医者は手助けとして抗うつ剤を出すだけです。
私は7年間、うつ病で病院に通っていました。
精神科医には「一生薬が必要。うまく付き合っていきなさい」と言われていました。
たまたま、精神科の薬の副作用でうつになるというHPを見つけ内容に納得したので減薬・断薬したら、あっという間に治りました。
医師は「副作用のない薬」といって簡単に出しますが、副作用はすごいです。
早期発見早期受診・手遅れになると自殺・悪化すると大変・必ず直る病気・薬には副作用も依存性もない・薬を勝手に止めたら悪化する・・・・・・、などと製薬会社・精神科医が広めているお陰で、簡単に病院へ行き、結果病気になる人が多くいます。
薬が病気を作り出しています。
服用中は、感情がめちゃめちゃだったり、突然動悸が襲ってきたり、とにかく症状が多く出ていました。
自殺願望や、異常な言動も多々ありました。
考え方を変えてみたり努力をしても、全然治る気配はありませんでした。
減薬では、最終的にソラナックス0.4mgの半分・デパス 0.5mgの1/4量という、弱い薬&少量・・のはずでしたが、うつ症状は残っていました。
この量を1ヶ月程続け、最終的にゼロにしたら、そのとたんに、うつ症状は一切なくなりました。
びっくりするくらいです。
今の生活も相変わらずストレスはありますが、今までのような不安定な状態は全くありません。
薬を服用する前の精神状態に戻りました。
まだ、「うつ」の感覚を体験する前のような状態です。
[Q&Aウェブページからの抜粋]
Posted by nob : 2013年09月04日 12:30
まずはすべて一切の薬を絶つことから。。。
とにもかくにもまずは断薬、保有している薬剤は思い切ってすべて廃棄してしまいましょう。
薬をやめると、しばらくは様々な症状が出るかもしれません。
しかし、どんなに辛くても不安でも薬をやめる時のほんのしばらくの症状ですから大丈夫です。
断薬の際に、辛くて不安になるものだとあらかじめ受け容れる覚悟をしておきましょう。
Posted by nob : 2013年09月04日 12:22
親愛なる心の友たちへのたよりVol.2
根源的な心の問題を解消できるような外的要素はどこにも存在しない。
幸せも不幸せも、自分の心がつくりだすもので、現実の状況そのものが変わるわけではない。
あるがままの自分自身に対して、満足することは不可能としても、納得を目指して、まずはあるがままにすべてを善しとして受け容れることから始めないと、一歩も良い方向には進んでいけない。
自らに納得するために、何をどうする、何が要るとかではなく、何もできない、何もない自分自身に対して、まずはそれで善しと思えるかどうかなのだけれど、これはできてしまえば呆れるくらい簡単なことなのに、できないでいるうちは想像もできないくらいに難しく感じてしまう。
Posted by nob : 2013年09月03日 15:57
私も日々攻めています。。。
■三浦雄一郎の奇跡は「月1回食べる1.5キロのステーキ」のおかげ?
今年の5月、80歳にして3度目のエベレスト登頂に成功。“大きな夢”が身体を作り上げてきた。
三浦雄一郎さんは1932年、青森県生まれ。66年に富士山の直滑降を成功させて、一躍有名になった。53歳で世界七大陸最高峰からのスキー滑降を達成し、70歳、75歳でエベレスト登頂に成功。そして今回は80歳という世界最高齢での登頂を成し遂げた。
病気やケガも度々経験している。60代は肥満や狭心症、糖尿病に悩まされ、76歳では骨盤骨折により再起が危ぶまれた。不整脈で何度も心臓を手術している。
しかし、それらを乗り越え、今も驚異的な身体を維持している。
「健康法には“攻め”と“守り”があります。僕は無理をしない、控えるという姿勢ではなく、いくつになっても攻めるべきだと思うんです。忙しいからジムに通ったことはないのですが、いつも両足に約5キロの重りをつけ、20キロの荷物を背負って歩いています。部屋には3キロ、10キロの鉄アレイがあって、朝起きたら、ぶらぶら持ち上げたりするんです。筋力を鍛えると骨密度が上がり、成長ホルモンが出るんですよ」
三浦さんはそう話す。年をとったら「脂分は控えめに」などと言われるが、三浦さんは食生活でも“攻め”の姿勢だ。
「月1回は息子の豪太と二人で1.5キロのステーキを食べます。普段は300グラムほどの肉を週に1、2回。納豆やヨーグルトなどの発酵食品も毎朝食べます。
そして、何よりも大切なのはメンタルだという。
「たとえば、同じ年齢の人が同じ条件で手術しても、『生きるぞ』という意欲がある人はすぐ治るし、『もうだめだ』と思っている人は本当にだめになってしまうそうです。単純に言えば、プラス思考が大事。マイナス思考の人はできない理由を並べるけれど、僕は『どうやったらできるか』しか考えない。どうしてもエベレストに登りたかったから、ケガも病気も乗り越える以外なかったんです」
次の目標は、85歳でヒマラヤ山脈のチョーオユー(8201メートル)からスキー滑降すること。
「面白いからやってみたいんです。それに、健康長寿社会がこれから日本の課題になる。医学博士の豪太とともに、どうやったら元気に長生きできるかを解明したい」
人間の可能性は果てしない。三浦さんはそれを体現している。
[週刊朝日]
Posted by nob : 2013年09月03日 15:45
親愛なる心の友たちへのたより
幸いにも、ここまで堕ちてそして流されて、もう今更ながら人目を気にする必要もないのだから、自分自身の基準で、自分自身のために生きていこうと腹をくくればいいだけのことだよ。
自分自身のためなら、目標も、無理な努力も、成果も要らない…、楽しいことだけを、やりたい時にやりたいだけやればいい…。
他人の表に出たポジティブな局面ばかりに目を奪われ(私たち自身がそうであるように、また誰もがその裏には幾倍ものネガティブな局面を隠しているもの)、根拠のない劣等感や嫉妬心を抱いたりして、自らの現状の在り様を許容納得できなかったり、何とでもこれから創っていける未来に希望を持てなかったりするのも、他人や世間の基準に惑わされ囚われてしまっているだけのこと…。
自分自身のメリットを探して伸ばそうとすることが、自らの基準で自らのために生きるということ…、不安も悩みも苛立ちも、ブレる自分自身が心の中でつくりあげただけのもの…。
自分のために生きることなんて、出来てしまえば、驚くほど簡単で、憑き物が落ちたような爽快感を味わえる。
自分自身のために生きるためには、まずは自らの在り様をあるがままに善しとして許容することから…、受け容れることと諦めることは、一見似て対極的に非なるものだから混同しないように…、諦めるという否定からは、また更なる否定を生み出すだけだけれど、前向きに一旦受け容れるという肯定からは、最低限でも現状維持、前向きに何か働きかけをしていけば、それだけ好転やさらなる成長も望めるし、徐々に自分自身と周囲の状況を快適にしていける。
最後に、期待は自分自身だけに…、他者をあてにしなければ失望させられることもない。
何らの見返りも求めず、自分が気持ちよくいられるだけの範囲で他者に期待をかけるのはいいけれど、打てど響かない鐘のような他者に失望や怒りを感じるようなことは、もはや期待を通り越した依存というもの。
与えられることを求めず、与えることに喜びを見い出せた分だけ、人は初めて充実感や幸福感を感じてとれるのだから。
Posted by nob : 2013年09月01日 14:35
病は自らの心がつくりだすもの、、、進むも戻るも自らの心の持ち様次第。。。Vol.2
迷いも不安も悩みも苛立ちも
悲しみも喜びも
自分自身が頭の中で勝手につくりだす幻想にすぎない
目の前の現実はたった一つ
自らがどう捉えようともその実は何も変わらない
Posted by nob : 2013年08月31日 22:35
病は自らの心がつくりだすもの、、、進むも戻るも自らの心の持ち様次第。。。
■仕事うつ:男性会社員の3人に1人が自覚
男性会社員の3人に1人が、仕事が原因で気持ちが沈みやすくなる「仕事うつ」を自覚していることがトレンド総研が行った調査で明らかになった。また、休憩を取ることが仕事の行き詰まりを解消する上で有効だと感じている人が8割を超えることも分かった。
調査は、1〜5日に30〜40代の男性会社員を対象にインターネットで実施。「自分が『仕事うつ』だと感じることはありますか」と聞いたところ、「よくある」が8%、「たまにある」が28%で合わせて36%が「ある」と回答。一方、「ない」と回答した人は「あまりない」の39%と「まったくない」の25%を合わせ64%だった。
また、休憩について「休憩をとることは、仕事の行き詰まりを解消する上で有効だと思いますか」と聞いたところ、86%が「そう思う」と回答。また、実際に「休憩をとることで、仕事の行き詰まりを解消した経験ある」と回答した人も73%に上った。
休憩時間の過ごし方については、「飲み物を飲む」(80%)と回答した人が8割に上り、ほかに「インターネットをする」(60%)、「ガムやあめ、菓子などを食べる」(43%)、「周囲の人と話す」(38%)などが上位となった。飲むものとしては、「コーヒー」(57%)という回答が最も多く、「緑茶」(31%)や「ミネラルウオーター」(19%)、「炭酸飲料」(15%)を上回った。
精神科医の名越康文さんは調査結果をみて「気分が落ち込んでいる時は、気持ちに余裕がなくなっていることが多いといえます」と話し「思い切って長期休暇などを取れれば良いですが、忙しいサラリーマンの方は、思うように休みを取ることも難しいでしょう。ですので、そのぶん毎日の仕事中に小まめな休憩をとって、気持ちをリフレッシュさせることが大切です」とアドバイスしている。
[毎日新聞]
Posted by nob : 2013年08月20日 20:27
私の周りにも大勢います、、、これは病ではない、とつくづく思います。。。
■誰もがなり得る、「新型うつ」。なりやすい人の特徴
最近、ビジネスシーンや医療現場で話題になることが多い「新型うつ」。この病気にかかってしまう人が急増中だというが、一般的なうつ病とは何が違うのだろうか。また、どんな人がかかりやすく、万が一、新型うつになってしまったら、どのような対処をすればよいのだろうか。誰もがかかってしまう可能性があるこの病について、「ゆうメンタルクリニック」総院長のゆうきゆう先生に、その特徴や対策を教えてもらいました。
【楽しいこと・関心のあることに対しては積極的に】
まず、一般的なうつ病と新型うつには、どういった違いがあるんでしょうか?
「一般的なうつ病の症状としては、『不眠』、『食欲低下』、『うつ気分』、『無気力』、『無関心』といったものがあげられますが、非定型うつ(新型うつといった病名はなく、病院では非定型うつとして扱われます)では、『過眠』、『過食』といった症状が見られることが多く、『鉛様疲労感』と呼ばれる、手足の重さ・だるさを感じるという症状が見られることが多いですね。とても特徴的なのが、一般的なうつ症状ではネガティブな感情もポジティブな感情も含めて、感情自体を感じにくく行動全般をおっくうに感じるといった症状が見られますが、非定型うつでは不安を感じやすく、楽しいこと・関心のあることに対しては積極的に行動できるのです。嫌なことに対してはうつ気分を感じますが、好きなことに対しては積極的なんですね」(ゆうき先生)
【他人を頼るのが苦手な人は要注意】
過食や過眠など、一般的なうつ病とは違う症状が出るようだ。それに「楽しいこと・関心のあることには積極性を示す」といったことからも分かるように、気分や状況によって症状が左右されることが多いのだそうだ。
では、どんな人がなりやすいですか?
「どちらかというと、他人の言葉を気にしやすい人が多いかも知れませんね。必要以上に相手の期待に応えようとしたり、他人を頼ることが苦手で、いわゆる少しプライドが高い・相手に弱みを見せたくないタイプの人に多いでしょう」(ゆうき先生)
【できるだけ、規則正しい生活を心がけて】
新型うつにならないための予防法はありますか?
「基本的な部分で言えば、できるだけ規則正しい生活を送ることが大切です。生活のリズムが崩れていると自己嫌悪に陥りやすく、周囲の目も気になりがちです。実際に他人から指摘されているわけでもないのに、『だらしないと思われているのでは』と想像が膨らんでしまいやすいため、寝る時間や起きる時間を決めて、なるべく生活のリズムを守るようにしてみましょう」(ゆうき先生)
【辛くなったら我慢せず、周囲を頼ろう】
なるほど。生活習慣の乱れは、いろいろな病気の原因にもなりそうだ。とはいえ、仕事が忙しくなると、生活は不規則になりがち。万が一、新型うつ(非定型うつ)になってしまったら、どうすればよいのでしょうか?
「日中にうつ気分になることが多いことから、昼間に目的意識を持って行動することが勧められます。生活リズムが乱れていることも原因として考えられますので、規則的な生活を心がけましょう。お掃除や家事を計画的に行うのもお勧めです。まずは、日常生活の見直しからですね。また、どうしても辛いな〜と感じるときは、あまり悩まずにクリニックで受診することが大切です。一人で『甘えてるだけなんじゃないか』とさらに悩みを増やすよりは、症状が軽いうちに誰かに相談して安心することも大切なんですね。日頃から『自分を追い込まないこと』を心がけていきましょう」(ゆうき先生)
誰もがかかってしまう可能性を持つ新型うつ。少しでも辛いと思ったら、自分一人でがんばりすぎずに、周囲やクリニックに相談するようにしよう。
取材協力/ゆうきゆう先生
精神科医。著書多数。ゆうメンタルクリニック総院長。
[マイナビスチューデント]
Posted by nob : 2013年08月07日 13:01
感じられる、、、そのこのうえない幸せ。。。
すべての存在は
何も語らずとも
たとえ目にも見えなくとも
感じ取ることのできる人の内なる心に
静かに深く染み入ります
Posted by nob : 2013年07月24日 13:38
日々幸せを感じられない、、、
それは心の病。。。
Posted by nob : 2013年07月24日 13:33
変えることができるのは自分自身だけ。。。
■気づきのきっかけとなる「知恵の言葉」
バイロン・ケイティの新著、『新しい自分に目覚める4つの質問』には、長年に渡るワークの経験から抽出された「知恵の言葉」が集められています。最後にその中から抜粋したものをご紹介しましょう。
●答えはあなたの中に
あなたの外にあるいかなるものも、あなたが求めているものを与えてくれることはない。
●現実は変えることができない
私は、あるがままの現実を愛します。現実に抗うと、心が痛みを感じるからです。世界のいかなる考えをもってしても、現実を変えることはできません。あるがままがあるのです。
●あるがままに愛する
私はよく、悟った人なのかと聞かれます。それについては、何もわかりません。私はただ、心に痛みをもたらすものとそうでないものとの違いを知っている人間というだけです。
●現実は常に優しい
現実は、――まったくあるがままに、どんな瞬間でも――常に優しいのです。私たちの視野を曇らせ、真実を曖昧にし、世界には不公平なことがあると思わせるのは、現実についての私たちのストーリーです。現実はいつも、それについてのストーリーよりも優しいのです。
●ストレスの感覚が教えてくれること
私たちはワークを通じて、ビリーフやストーリーに対する執着がいかに苦しみを引き起こすかを発見します。ストーリーが発生する前には平和があるのですが、そこに考えが入り込むと、私たちはそれを信じ、平和が消えるように見えます。その瞬間、ストレスの感覚に気づき、その背後にあるストーリーを探求すると、それは本当ではないことに気づきます。考えを信じることにより、自分があるがままの現実に抵抗していることを、ストレスの感覚が教えてくれるのです。
●考えに対する執着が問題
私たちの問題というのは常に、私たちが無邪気に信じ込む考えなのです。ワークは、執着していると思っている対象に対してではなく、私たちの考えに取り組みます。物に対しての執着というものはありません。瞬間的に湧いてくる、探求していない考えに対する執着しかないのです。
[DIAMOND online/バイロン・ケイティ [『ザ・ワーク』著者],ティム・マクリーン(訳者),高岡よし子(訳者)]
Posted by nob : 2013年07月24日 12:13
確かに。。。
■ダイエットに効く意外な食材6つ「チーズ」と「豚肉ステーキ」「アイスコーヒー」
海外セレブのように、ほどよく筋肉のついたペタンコおなかは女子の憧れ。その憧れのおなかに向けてダイエットに励んでいる人ほど、本当に必要な栄養素を見失いがち。意外すぎる「ペタンコおなか」のための食材をご紹介!
1. グレープフルーツ
ルイジアナ大学が行った実験によると、特にダイエットを意識していない成人女性の多くが、1日3回半分に切ったグレープフルーツを12週間食べ続けた結果、1.5キロ痩せたそう。原因ははっきりしていないそうだが、研究員らは、胃が酸性になり消化が遅くなることで「腹持ち」がよくなった結果なのだと予想している。
2. アイスコーヒー
カフェインを摂(と)っていない人と比較して、脂肪燃焼率が19%も高いという結果が出ている。最近出回っているカフェインを一気に摂取できてしまうエネルギードリンクは「体に残りにくい」ので、カフェインはできるだけゆっくり飲めるアイスコーヒーから摂(と)ろう。朝が1番良いそうだが、少ない量を何回かに分けて飲むのも効果的だそう。
3. ポークチョップ(豚肉のステーキ)
豚肉には脂肪燃焼には必要不可欠なカルニチンという成分が豊富に含まれており、タンパク質も豊富。そして免疫力を高めてくれるミネラル成分のセレニウムが牛肉の5倍、鶏肉の2倍も含まれているのだ。1日に約180gのポークチョップを食べている人は、ダイエット中に筋肉を失わずに痩せることができるそう。
4. リンゴ
ペンシルベニア大学の実験では、昼食前にリンゴを1個食べた人たちは、いつもよりも187kcal低い昼食を食べたそう(ちなみにリンゴ1個128kcal)。腹持ちの良さも注目されており、食べるのに「かむこと」を要するリンゴはダイエットには欠かせないフルーツなのだ。
5. チーズ
脂肪だらけのイメージが強いチーズは筋肉作りには最適の食べ物なのだそう。デンマークで行われた実験結果によると、たとえ1日に280gのチーズを3週間食べ続けたとしても、悪玉コレステロールの数値に変化は見られないそうだ。
6. たまご
1日3回の食事では「朝」のカロリーを1番多く摂(と)ることが大切。朝食を多く食べる人はカロリー消費をうまくでき、おなかが満たされる時間が長いのだ。たまごはそんな朝食にもってこいの食材。タンパク質の豊富なたまごは欠かさずに食べよう。朝食に20-30gのタンパク質を摂(と)るのが理想的。
[マイナビウーマン]
Posted by nob : 2013年06月24日 13:38
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.19
かつて経験したことのない心身の健康を、昨日より今日、今日よりもまたさらに明日と、
どのように日々強く実感できているのか、、、
直ぐに眠れるようになり、目覚ましがなくとも毎朝同時刻にすっきりと目覚めます。
起床してまずお通じがあります。
朝食が美味い。たっぷりといただきます。
直腸反射で、食後にさらにしっかりとお通じがあります。
日常の生活や仕事上、なかなか疲れませんし、疲れが出ても短い休息により直ぐに回復します。
よく歩き、そしてよく汗をかきます。
昼食は軽めに、夕食もできるだけ早い時間に済ませることを心がけています。
好きなものを好きなだけいただき、ダイエットはしていません。
時折休肝日をもうけますが、ほぼ毎日お酒もいただきます。
なかなか毎日できませんが、その時々の身体の声を聞きながら、適切なストレッチを行います。
毎晩しっかりと入浴します。
髪の量も維持あるいは復活、肌のコンディションも歳を重ねるほど逆に整い、嫌な体臭もなくなりました。
Posted by nob : 2013年06月10日 13:15
蓄積も解消も、日々の些細な事柄の積み重ね。。。
■甘く見るな、「スマホ症候群」は危険!(2) -「首こり」で新型うつやパニック障害になる!?
「スマホ症候群」の代表的な症状のひとつである首のこり。大したことはないと放置しがちだが、じつは、新型うつやパニック障害を引き起こす可能性があり、重症になるとほとんどの人が自殺志向になる、極めて深刻な症状なのだ。
その理由として、首こり研究の第一人者である東京脳神経センター理事長の松井孝嘉医師は、「首に負担がかかると、首に通っている自律神経の働きがスムーズにいかず、自律神経失調が起こり、新型うつを引き起こす」と説明する。実際に、スマホやパソコン、ゲームの広がりとともに、新型うつと診断される患者が急激に増えているそうだ。
副交感神経の働きを低下させる「首こり」
そもそも首は、脳と体を結ぶ神経や、脳と心臓を結ぶ血管などが通る、人間にとってとても大切なパーツ。しかも、約6キログラムもある頭部を支えているため、首の筋肉にはつねに負担がかかることになる。さらにうつむきの姿勢をとり続けると、首の後ろ側の筋肉に通常の3倍の負荷がかかり、疲労が蓄積されていく。その結果、筋肉が硬化して「首こり」の状態になり、休ませても戻らなくなる。
これら首の後ろの筋肉には自律神経が複雑に絡み合っている。自律神経は、体内の生命活動をコントロールする最も大切な神経で、活動・緊張に関わる働きをする交感神経と、休息・安静に関わる働きをする副交感神経のふたつから成る。自律神経が正常に働いていれば、活発に行動する日中は交感神経が優位になり、休息する夜間は副交感神経が優位になる。しかし、首こりによってその働きが妨げられると、つねに交感神経が優位になり、心身の健康を保つ上で大切な副交感神経の機能が低下してしまう。
「副交感神経は、胃腸の動きを活発にしたり、血圧や心拍数を下げたり、たまった疲労を回復させたりする大切な神経。その働きが低下すると、全身倦怠、めまい、のぼせ、発汗異常などの不定愁訴と呼ばれる症状が起こり、幸せを感じられなくなる。さらに悪化すると90%以上が新型うつになる」(松井医師)
単なる「首こり」のはずが、新型うつ、パニック障害の原因に!
では、新型うつとはなんだろうか? 新型うつは、精神病のひとつであるうつ病とは異なるもの。そして、自殺率が高いことで社会的に問題になっている。
「自律神経失調によって起こる新型うつは、抗うつ剤を飲んでも治らない。しかし、精神病と診断されるケースが多く、うつ症状が悪化して、重症になると高い確率で自殺に至ってしまう。正しい治療で首の筋肉のこりを改善すれば、自律神経の働きが正常になり、新型うつの98%は治すことができる」(松井医師)
さらに首こりによる副交感神経の働きの低下は、新型うつのほかに、慢性的に頭が締めつけられるように痛む緊張型頭痛などの身体的な不調や、突然激しい動悸に襲われたり、冷や汗が出て呼吸が困難になったりするパニック障害など、以下の表に挙げた17種類もの不調の原因になると松井医師は言う。
緊張型頭痛
頭が締めつけられるように痛んだり、石が載っているように重く感じたりする慢性的な頭痛。頭痛の70%を占める
自律神経失調症
めまいや耳鳴り、情緒不安定など、さまざまな不定愁訴が心身ともにあらわれる
パニック障害
突然の激しい動悸や、冷や汗が出て呼吸が困難になるなど、苦しい発作が起こる
自律神経性新型うつ
精神病のうつとは異なり、全身倦怠、めまい、のぼせ、発汗異常などの体調不良が主にあらわれる
更年期障害
50歳前後の女性に多く、女性ホルモンの分泌量が急激に低下することで頭痛、めまい、のぼせなどがあらわれる
慢性疲労症候群
朝だるくて起きられなかったり気力が低下するなど、身体的にも精神的にも、ひどい疲労感が半年以上続く
ドライマウス
唾液の分泌量が少なくなり、虫歯や歯周病、強い口臭など、口腔環境を悪化させる
VDT症候群
パソコンやゲームなど、ディスプレイを長時間使うことで起こる心身の不調
過敏性腸症候群
下痢や便秘を繰り返すが、検査をしても異常が認められない
ドライアイ
涙が不足し、目の表面が乾いて傷つきやすくなるほか、殺菌力・洗浄力が落ちる
血圧不安定症
上の血圧が200前後になったり、100前後になったり、乱高下する
機能性胃腸症
検査をしても異常がないが、胃もたれや吐き気などの不快症状が続く
機能性食道嚥下障害(きのうせいしょくどうえんげしょうがい)
口から胃までのぜん動運動の機能低下により、食べ物、飲み物、唾液などが飲み込みづらくなる
めまい
回転性めまいのほか、フラフラ感、フワフワ感など、なんとなく体が不安定な感じがする
ムチウチ
追突事故やスポーツ中の事故など、何らかのアクシデントの後遺症として発生する
多汗症
全身に多量の汗をかく全身性多汗症と、体の特定の部位に多量の汗をかく局所性多汗症がある
不眠症
睡眠障害の一種。十分な睡眠が取れず、昼間の活動に支障をきたす状況が1カ月以上続く
首の状態をセルフチェック
さまざまな不調の引き金となる首こりだが、首の筋肉は疲労を感じづらい。そこで、以下のチェックリストを活用し、今の自分の首の状態をセルフチェックしてみよう。
1.首こり、肩こりがある。
2.慢性的な頭痛がある。
3.めまい、フワフワ感、フラフラ感がある。
4.ドライアイやかすみ目などの目のトラブルがある。
5.吐き気や食欲不振、便秘などの胃腸症状がある。
6.疲れやすく、起床時に体が重たい。
7.原因不明の微熱など、風邪気味のことが多い。
8.寝つきが悪く、夜中に目覚めることが多い。
9.天候によって体調がよくなったり、悪くなったりする。
10.何もする気になれず、気分が落ち込む。
●該当する項目が1〜2個
軽症程度。自分の力で治すことが可能な状態なので、うつむきの姿勢を改善するなど、生活習慣を見直そう。
●該当する項目が3〜5個
中程度の異常。首の筋肉に疲労をためないように心がけ、改善されない場合は専門医に相談を。
●該当する項目が6個以上
重症。原因不明の体調不良が続いているようなら、できるだけ早く専門医を受診しよう。
首の筋肉をゆるめて、首こり予防
予防策として有効なのが、スマホを操作する時のうつむきの姿勢に注意することはもちろん、首の筋肉に疲労をためないこと。長時間デスクワークをしている場合、首のうしろに両手をあて、30秒間頭をうしろに倒し、首の筋肉をゆるめよう。15分に一度行うと効果的だ。また、松井医師が考案した、首の筋肉のこりを防ぎ、副交感神経の働きを高める「555体操」というものがある。これを、朝晩2回行うのもおすすめだ。自己流でマッサージをすると筋肉を傷めてしまう可能性があるので、気をつけよう。
「首こりが改善されると、周囲からも分かるほど表情がいきいきし、肌つやもよくなる。心から幸せな毎日を送るためにも、きちんと首を休ませることが大切」(松井医師)
電車に乗ると、ほとんどの乗客がうつむいてスマホを操作している——もはや見慣れてしまった光景だが、このうつむいた姿勢こそが深刻な不調を引き起こす原因だ。ほんの少しの時間と工夫で首の筋肉の疲労を解消することが大切。健やかな心身を手に入れよう。
(文/小口梨乃)
[NIKKEI TRENDY NET]
■「首」の555体操 ~副交感神経アップで健康になれる!~
555体操には、背もたれのあるイスを使用し、深く腰掛けて行ってください。
①首の柔軟体操 Ⅰ

首を左右にゆっくりまわします。
頭を前方に倒して、まず左からゆっくりと一周させます。
続いて右からまわします。この運動を5回繰り返します。
②首の柔軟体操 Ⅱ

首筋をしっかり伸ばして顔をゆっくりと右に向けます。
このとき体は正面を向いたまま動かさず、左肩を軽く後ろに引きます。
そのあと顔を正面に戻します。これを5回、繰り返します。
続いて先ほどと逆の動きをします。顔をゆっくりと左に向けます。
体は正面を向いたまま動かさず右肩を軽く後ろに引きます。
この運動も5回繰り返します。
③首の後ろの筋肉をゆるめる

両手を組んで後頭部にあてて、頭をゆっくりと後ろに倒します。

倒した状態で5まで数えて、ゆっくりと頭を元に戻します。
この運動も5回繰り返します。
④首の斜め後ろの筋肉をゆるめる

右手を右の耳の後ろにあてて頭を右後ろにゆっくりと倒します。

倒したまま5まで数えてゆっくりと元に戻します。
手は戻す運動を手助けるようにします。この運動も5回繰り返します。
⑤首の斜め後ろの筋肉をゆるめる

今度は左手を、左耳の後ろにあてて、
先ほどの反対側である左後ろに倒していきます。
倒したまま5まで数えて、元の位置に戻します。
この運動も5回繰り返します。
⑥首の横の筋肉をゆるめる

右のこめかみの上あたりに右手の指を2、3本あて、頭を右肩の方に倒します。

倒したまま5まで数えてください。ゆっくり戻します。
このときも、そろえた手は、戻す手助けをしてください。
次に、左側も同じようにします。左右5回ずつ行ってください。
⑦首の斜め前の筋肉をゆるめる

左の額に左手をあてて、頭を右肩の上に倒します。

次にそのまま頭を左へまわしてできるだけ、右耳を胸骨に近づけます。

このとき顔は左上方を向いています。
この状態で5まで数えて、頭を右肩の上に戻します。
そのあと、首を立ててまっすぐ正中(正面:体の左右の真ん中のライン)に戻します。
左側も同じようにします。
右手を額の右側にあて、左肩の上に頭を倒し、
左耳が胸骨に近づくように首をまわします。左右5回ずつ行ってください。
⑧整理運動
③→②→①の順番でもう一度行ってください。
[東京脳神経センター]
Posted by nob : 2013年04月12日 16:47
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.18
心の病にかかって以来、
そこからの回復とその後の予防の過程での、
一時的に致し方ない場合を除き、自ら調整しうる限りにおいては、
これから順を追って詳細をまとめていくように、
規則正しい生活、バランスを考えた食生活、適度な(リズム)運動などを通して、
かつて経験したことのない心身の健康を、昨日より今日、今日よりもまたさらに明日と、
日々強く実感することができるようになりました。
また、自らの心身との対話力も高まって、このところではまずは予防、そして症状が生じたとしても、初期の段階での解消も容易にできるようになり、
人の心身とは、何と繊細であって、押す、さする、揉む、伸ばす、暖める、冷やすなどというちょっとした刺激により、健康の回復と維持が決して難しいことではないということに気付くことができたのです。
Posted by nob : 2013年04月06日 21:21
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.17
様々な困難に立ち向かうだけの自らの心の強さ、
さらに肉体の持続力や回復力、
長きにわたってそれらを過信して日々を過ごしてきた付けが回って、
ある日唐突に箍が緩んでしまったようです。
克服したのではなく、
ただ克服したつもりになっていただけのこと、
その時々のストレスとの葛藤や肉体を酷使してきた様々な弊害は、
知らず知らずのうちに日々着実に蓄積して、とうとう溢れ出してしまったのでした。
無理と我慢をすればしただけ、心身を鈍重にそして老化させることを知り、
ストレスには立ち向かわないで、柳のように受け流す。
疲労を溜め込まずに、充分な休息を取る。
様々な小さな不調を見逃さず、そしてなおざりにせず、その都度解消していく。
このところ今さらながらようやく身に付いてきたと実感できる、そんなスローでサスティナブルな暮らしぶりをこれからも大切にしていきたいと思います。
Posted by nob : 2013年04月03日 11:35
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.16
あらためて言及するまでもなく、いかなる心身の疾患においても、必ずそれらに至る原因と経緯があります。
予期せぬ事故などによる、重度な打撲や擦過傷、火傷や凍傷、骨折や裂傷といったような突発的な外傷、
ウイルス感染や放射能汚染、薬害や環境汚染など、化学的要因による急性発症といったような突発的な疾患については例外として、
あらゆる慢性的な疾患においては、
可能な限り原因というリスクを除外することはもちろんのことですが、
回避しきれない原因が次第に深刻化していく初期の軽度な段階での察知と適切な処置が何より大切なのです。
癌や脳疾患など重症化させてしまうまでの過程において、いかに早い段階で察知ならびに処置ができるかどうか、それは偏に自らの心身との対話力にかかっていますし、慢性的に発症するいかなる疾患も、自己免疫力と治癒力を高めることによる予防と自然治療が可能であると言っても過言ではありません。
Posted by nob : 2013年04月02日 06:30
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.15
薬剤投与は、あくまで対症療法に過ぎず、
疾患を抑え込み癒していくのは、あくまで自らの自然治癒力によるものなのですから、
あまりに痛みが強いなど、症状が我慢できないほど強くなければ、投薬は不要です。
身体は病原に対しての必要な反応として様々な症状を出しているのですから、
しっかりと休養を取りながら、そうした様々な症状を通して、自らの心と身体との対話を深めていくことがまず何より肝要なのです。
Posted by nob : 2013年03月20日 15:23
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.14
そんな私自身に、私は満足こそできたことはありませんが、
満足を目指して歩み続けんとする私自身に対しての日々の納得は、何よりも大切にしています。
ところが、私のように、
さらにはるか私など以上に真摯に、
そのような価値観で日々を送る人達の多くが、
心の病にかかったり、その予備軍だったりする、
これはいったいどうしたことなのでしょうか?
答えは簡単です。そもそも心の病など存在してはいないのです。
風邪は万病の元と言うとおり、病ではないのです。
風邪をひいて高熱を出せば、身体の内部がきれいにリセットクリーンアップされます。
したがって、解熱など、様々な身体からのシグナルや自然な自己治癒力を押さえ込んでしまうような薬剤投与などはもっての他、必要なのは休息だけです。
同じように、心の病は、日々蓄積したストレスを解消させる必要性を知らせるための、心の休息を訴えるシグナルなのです。
したがって、精神安定剤や抗鬱剤など、現れる症状を抑え込もうとする対症療法としての薬剤投与、特に一般的に見受けられるいくつかの薬剤の併用は、予期せぬ副作用を生じさせかねず、百害あって一利なしと言っても過言ではありません。
心の病と言われる基準の心にとっても、風邪と思われる基準の身体にとっても、無用な薬剤投与は、その先の様々な深刻な疾患に進展させてしまわないための、免疫力あるいは自己治癒力という自らの心身の鋭敏な働きを鈍化させてしまうばかりでなく、多くの場合逆に症状を悪化させたり、異なる疾患を発症させてしまう要因にもなりかねません。
Posted by nob : 2013年02月14日 20:20
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.13
少々独断と偏見による見解かもしれませんが、
主体的かつ積極的、繊細で根が真面目だからこそ、
心の病にもかかることができるのです。
少なくとも、私は、私自身に対して、
従属的ではなく、主体的でありたいと、
自らの頭で考え、すべての言動は自ら決定し責任もとりたいと、、、
消極的ではなく、積極的でありたいと、
良くある言い回しですが、
やらずに後悔するよりも、やって反省したいと、、、
鈍重であるより、繊細でありたいと、
見ない、聞かない、知らないから感じない日々よりも、
観察し、耳を傾け、学び、感じ取れる日々を過ごしたいと、、、
自らに甘く、都合と利害で言動し、
他人や社会に負担をかける側よりも、
自らに厳しく、あるがままに他者を受け容れ、
他人や社会から負担をかけられる側にまわりたい、、、
私はそんな私自身でありたいと思います。。。
Posted by nob : 2013年02月02日 07:34
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.12
かねてより、私の周りには、心の病にかかる人達が多かったように思います。
単に、そうした視点で意識をして見るからだけのことかもしれませんが。
そして、私自身が患うことなど、まさに青天の霹靂でしたが、
諸々考え合わせてみれば、ごく必然的な成り行きだったのだと、今では感じられます。
これは、私の経験値による認識であって、何らか確かな根拠に基づくものではないのですが、
何事にも無頓着で鈍感で、おまけに物事を深く考えもしないような人々を、まずは脇に置いて、
もともと内向的で悲観的なタイプの人は、普段から免疫ができているからなのでしょうか、心の病にかかっている例をまったくと言ってよいほど見たことがありません。
反面、主体的かつ積極的、繊細で根が真面目と来たら、いつ発症してもおかしくないアレルゲン(アレルギー反応を引き起こす抗原物質や環境要因)を有していると言っても過言ではない気がします。
私の周囲を見回してみても、程度の差こそあれ、心の病を患っている全員がこのタイプかと、もちろん私自身も含めてです(苦笑)
Posted by nob : 2013年01月30日 12:00
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.11
温まっている身体に、少し冷気があたるだけでもくしゃみが出ますし、そこで防寒しなければ風邪を引いてしまいます。
食べ過ぎ飲み過ぎは、胃腸を壊しますし、それは肌荒れや口内炎に、そして肥満にもつながり、気持ちも落ち込んでいきます。
心にストレスがかかれば、肩が凝り目も疲れますし、そして頭痛にもなります。
ストレスがかかり続けて、心が弱れば、さらに身体のあちらこちらに支障が生じ始めますし、その逆も然り、身体を壊せば、心にもさらなるダメージを与えます。
入り口はそんな日常の些細なことからでも、小さな症状がまた次の小さな症状につながり、それらが蓄積されて次第に身体を蝕んでいきます。
やさしく首筋や肩をマッサージをしたり、指先や各所の所謂ツボを刺激してみれば、あるいはストレッチ体操や入浴などで身体を柔らかく温めてみるなどしてみれば、まだ症状の出始めの段階であれば、たちどころに解消してしまうことすらありますし、根気よく継続していれば、それだけ身体は着実に回復していきますし、心をリラックスさせることもできます。
Posted by nob : 2013年01月17日 23:19
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.10
そして、貴方は、日々の暮らしの中で、貴方の身体と対話することができていますか?
疲れ、こり、痛み、痺れ、腫れ、乾き、、、など外的な、
また、咳、熱、嘔吐、下痢、冷え、、、など内的な、
身体も、様々なメッセージを伝えてきます。
それらのサインに気付かず、あるいは我慢してしまうなど、放置したとしても、
私達には自己免疫力や治癒能力が備わっていますし、
若ければ、あるいは鍛錬すれば、それだけ力も強くなりますから、
時間を置けば、大抵の不調は自然治癒されてしまいます。
ところが、心も身体も、一定の治癒能力の限界を超えてしまった途端に、重篤な病となって私達を襲ってきます。
それに、一旦治癒したとしても、実は治癒したつもりになって気付かないでいるだけだったり、
また再発させる傷跡や抗原を残していたりもするものです。
Posted by nob : 2013年01月07日 15:25
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.9
貴方は、普段、貴方自身の内なる心の声に耳を傾けることができていますか?
貴方の心は、誰のものでもない、貴方自身のものです。
ですから、貴方にしか、貴方の心の囁きや語りかけはもちろん、ましてや叫びなど聞こえはしないのです。
他人の瞳に映る自分自身から離れて、目を瞑り、静かに意識を集中して、自らの心の奥底に耳を傾けてみてください。
これは、誰にでもできて当然のことながら、実際にやってみると実に難しいものです。
しかし、はじめは何も聞こえなかったり、途切れ途切れの囁きでしかなくても、
喜び、楽しみ、悲しみ、怒り、憤り、羨み、妬み、嫉み、哀れみ、迷い、不安、怖れ、、、など、昇降陽陰様々な内なる心のメッセージを、毎日耳を傾け続けていさえすれば、やがて明瞭に感じてとることができるようになります。
誰しもが、見栄や欲望やその時々の都合やら様々な雑念から、常に自身自身をも欺かんとするのが常ですが、心の内なる奥底の心の声はいつも正直であり続けているのです。
Posted by nob : 2013年01月05日 11:33
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.8
パニック障害の対策、
まずは、一切の薬剤を絶つことから、
ここからしか、最初の一歩は踏み出せません。
そして、直接的には、何と言ってもセロトニンの分泌を高めることです。
そのためには、太陽光・呼吸・リズム運動が基本、
そんなわけで、早寝早起き、早朝の体操とウォーキング、食習慣の改善などなど、
一つ一つについては、これからこのページでまとめていきますが、
様々なこれまでの生活サイクルとスタイルの中にはなかった健康的な習慣を新たに採り入れることで、
心の不調の療養の過程で、
もともと食べ道楽呑み道楽で、高くなりがちだった中性脂肪や悪玉コレステロールの数値もすっかりと下がるなど、
身体の健康状態も目に見えて改善していきました。
まさに、心と身体は一つに繋がっているのです。
Posted by nob : 2013年01月02日 07:37
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.7
パニック障害に限らず、多くの心の病に共通の要因は、自律神経の乱れです。
自律神経のバランスが崩れる原因のひとつとして、セロトニン分泌の減少が知られています。
自律神経には、交感神経と副交感神経という二つの異なる働きの神経があります。
交感神経が優位に働くと、抑揚や興奮といった動的な感情に繋がり、
また副交感神経が優位に働くと、落ち着きや鎮静など抑制する静的な感情に繋がります。
セロトニンは、この交感神経と副交感神経の働きをバランス良く切り替えコントロールする脳内物質です。
私のケースは、長年の睡眠不足気味の不規則な生活といったいくつかの要因により、セロトニンの分泌が減少したために、自律神経が乱れ、ノルアドレナリンが過剰に分泌されて、不安や焦りや恐怖といった過剰に警戒する感情に支配され易くなってしまうようです。
Posted by nob : 2012年12月31日 11:38
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.6
また、症状が出ている間は、
自らのネガティブな気持ちを切り替えることはできないのですが、
その間も、自らがそうした症状に因われているに過ぎないという確固たる認識はありますし、客観的な自己分析も可能で、
人間の脳の働きとは、何と繊細で脆く、また深遠で神秘的なものかと、あらためてつくづく感じるのです。
Posted by nob : 2012年12月30日 06:37
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.5
知識や経験を日々蓄積し、
慎重かつ周到に、
想定しうるあらゆる事態に対しての事前想定と相応な対策を怠らないことで、
自らの不安や恐怖を克服してしまわんとするのが、私の普段の在り様なのですが、
そのようにして綿密につくりあげた鉄壁であるはずの心の砦が、
いとも容易く攻略されてしまうかのような、
これまでの自信は不安に、蓄積は執着に、安心は恐怖へと、
パニックの症状が出ると、すべてが根底から覆されてしまうのです。
Posted by nob : 2012年12月28日 21:29
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.4
数年前のある爆弾低気圧の夜のことでした。
何の前触れもなく唐突に強い閉塞窒息感に襲われ、
居ても立ってもおられず外に飛び出して、
大雨強風の中を役に立たない傘を差して、
閉塞窒息感が収まるまで、
ただひたすらに歩き回らざるをえませんでした。
それが、私が初めて経験したパニック障害の発作だったのです。
Posted by nob : 2012年12月27日 09:25
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.3
風邪を引いて、
高熱で体内清掃をしたくとも、
もうこの何年もその気配すらなく、
迷い悩み苦しむ近しい誰かの、
心の支えになることが自らの立場や役割と思い込んできた。
そんな私にある日唐突にそれは覆い被さってきたのでした。
Posted by nob : 2012年12月26日 21:59
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。Vol.2
乗り越えたと思うこと、
それこそがまさに心の鈍感さ。
どんな逆境をも心折れることなく克服し、
悲しみや苦しみも、喜びや楽しみに変えて生きてきたという自負が、
心の病の根源的最大要因であったということに、
つまりは自分がストレスに弱かったことに、
今さらながらようやく気付きました。
Posted by nob : 2012年12月25日 17:50
風邪と心の病にかかれる力は、、、まさに天賦の才。。。
風邪を引かないことが健康?
いえいえ、それはただ鈍感なだけのこと。
発熱が体内をクリーンアップしてくれるのですから、
風邪を引かないことは、
まるでそれだけ掃除をしていないゴミ屋敷に住んでいるようなもの。
心身の健康というように、
心と身体は一つに繋がっています。
したがって、内なる心の奥底の真実の声に気付かない鈍重さが、少しずつ確実に身体を蝕んでいくのです。
Posted by nob : 2012年12月24日 19:29
I wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year♪♪♪
ここは、、、
我が親愛なる心の友たちへのメッセージのページです。。。
心の友たち、、、
このアドレスまでダイレクトにどうぞ。。。
http://web-notes.jp/nob/general/mind/
Posted by nob : 2012年12月24日 19:13
怖れずに付かず離れずうまく付き合っていけばいい。。。
■うつ病を経験した誰もが恐れる再発
100%の状態に戻ってからの復帰が重要
過去14年にわたり毎年、3万人以上の人が自ら命を絶っている。厚生労働省“自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム”の調査から、自殺既遂者は、うつ病等の気分障害が自殺の要因として特に重要であることが明らかになっている。現在の厚生労働省における自殺対策の中核となっているのが、うつ病対策だ。
うつ病は心の風邪と言われる。風邪は休息と投薬などにより完治する。もちろん、うつ病も正しい対応や治療によっていつか治る。しかし、完治したかどうかの見極めが難しい。また、うつ病は再発しやすいことをご存じだろうか。うつ病を発症したほとんどの人が、再発を恐れていることも事実だ。
休職と復職を繰り返しついに自殺未遂
今回は、10年以上独りでうつ病に苦しみ、その後産業カウンセラーYさんとの出会いで、新しい人生を歩み出すことになったKさんの事例を取り上げる。
Kさん(女性、現在52歳)は独身である企業の総務部に勤務している。3人姉妹の末っ子で、母親にとても厳しく躾けられて育った。大学卒業後、会社へは親の縁故で入社した。入社当時は秘書課に配属され、女性らしく魅力的なKさんは、とても可愛がられたようだ。
入社から5年後、地方への異動辞令が出て、地方都市で寮で暮らすことになった。
「Kさんは、いじめられたと言っていましたね。彼女はずっとお嬢さん育ちされてきて、もしかしたら、ビジネスライクに言われたことを『否定された、嫌われた』と思い込んだのかもしれません。そして知らない土地で一人きりの暮らしになったことも重なった、どん底の精神状態のときにお母さんが突然亡くなってしまわれたのです」
Kさんが30代前半の頃だ。産業カウンセラーのYさんは、Kさんの話を振り返りながら語ってくれた。
Kさんは寮で、自殺を図った。発見が早かったため未遂で終わり、一命を取り留めたKさんは、地方都市の病院を受診する。病院でうつ病と診断され、会社を休職し半年間入院した。退院後、投薬を続けながら地方都市の職場に復帰するが、3か月後うつ病が再発した。精神状態を考慮した会社はKさんを本社へ戻し休職扱いにした。病院の診断で投薬を続けながら再び職場復帰したが、うつ病が再発し、また休職になった。その後何度も復職と休職を繰り返し、自殺未遂も起こした。
何年にもわたり、休職と復職を繰り返すKさんに困惑した会社の上司は、企業の相談室に行くよう指示した。
一般的に、メンタル面の悩みを抱えていても、同僚などに知られるのが嫌で相談室に行くことを躊躇する人が多い。だが、この相談室は別の建物にあったため、同僚などに相談室へ行っていることを知られることはなかった。また、カウンセラーには守秘義務があり、上司とはいえ面談内容を報告する義務はなかった。Kさんは初めて人目を気にせずに本音を言える場を得たわけだ。この相談室で出会ったのが、産業カウンセラーのYさんだった。Kさんが40代前半の頃だった。
「死にたい。何のために生きているのかわからない」
Kさんが最初に言った言葉だそうだ。発症から10年以上過ぎたにもかかわらず、うつ病は治っていなかった。通院、投薬を続けているのに、精神状態は非常に悪い状態だった。
Yさんの初期のカウンセリングは、Kさんの言葉を傾聴し、受容し、共感することだった。Kさんは「死にたい」と繰り返し、泣きながら母親の話をした。母親が大好きだった。素晴らしい女性だった。母親が言うことはすべて正しい。言いつけは守らなくてはならない。でも死んでしまったので辛くてたまらない。
絶対的な母親の教育にしばられていた
Kさんにとって母親は絶対だった。Kさんは母親の厳格な倫理観・世界観の中で生きていた。Kさんが目にする社会・周囲の人の言動は、母親から教わった倫理観を通して見ると、全てが良くないものに思えたようだ。社会はこうあるべき、女性はこうあるべき、社会人はこうあらねばならない。社会や周囲の人への不平・不満が心の中に渦巻き、蓄積されていった。しかし、誰にも言えなかった。
どうしてか? 不平を言うことなど、恥ずかしいこと、みっともないことだと母親から教え込まれていたからだ。そんな価値観を持つKさんは、他人の見方も厳しかったが、同様に自分にも厳しかった。すべての否定的な思いを溜め込み続けた末に、価値の基準である母親が急にいなくなってしまった。心のバランスが壊れ、うつ病を発症した。どうやって生きたらいいのか分からなくなり、自殺未遂に至ったのだろうとYさんは分析する。
Yさんは、Kさんの目標を“自己受容 Iam OK.”に設定し、まず自分を受け入れられるように導いた。
まずやってみたのは、コラージュ療法だった。コラージュ療法は、1970年代に米国の作業療法士ジェーン(Jane.M)が考案した芸術療法だ。コラージュはフランス語で「糊付けする」という意味で、20世紀の初めにピカソやブラックなどが使った現代美術の技法だ。雑誌やパンフレットなど既成の写真や絵などをハサミで切り抜き再構成し台紙へ糊付け(コラージュ)し、独自の世界を表現する。
コラージュで表現することで、様々な心理状態を把握できるが、YさんはKさんの心理状態を診断するというより、会社の中で自分(母親)の価値観でがんじがらめになり緊張状態で苦しんでいるKさんを、綺麗なものに触れさせて、緊張を緩めてあげたかったのだそうだ。
「“枠”が狭かったですね。自分で作り上げた社会や人と接する時の“枠”がとても狭く硬いものでした。まずは、素の自分の時間を作ってほしかった。コラージュの時間は何も心配なものがなく安心できることを認識してもらいました。その中で信頼関係も育み、心がほどけていく時間になるよう心掛けました。そして目指したのが自己受容です」
Yさんと時間を過ごすうちに、Kさんは自分の本音を語りだした。
「他者批判、つまり周囲の人への文句、愚痴ばかりでした。自分の価値観が非常に厳しく、こうあらねばならないと思い込んでいますから、不平・不満が溜まっていたのです。もちろん、良い人、できる自分を演じ続けている自分へも非常に怒っている状態でした。しかし、まだ言いたいことは誰にも言えない状態でした」
その状態の改善のために、次に始めたのがアサーション・トレーニングだ。このトレーニングの基礎を築いたのは米国の心理学者、ウォルピ(Wolpe,J.)とラザラス(Lazarus,A.A.)である。自分とともに相手も大切にする自己表現の仕方を訓練する。自分の感情や考え、要求などを適切に表現する能力を養うので、「言いたいことが言えない人」「対人関係で自己中心的な人」「引っ込み思案な人」などに有効とされる。
自分の気持ちを客観的に表現する訓練
Yさんは、アサーション・トレーニングのDESCという手法を使った。
D(Describe)=自分が困っている客観的事実をできるだけ穏やかに話す
E(Explain)=その事実に対する自分の気持ちを話す
S(Specify)=その事実に対して可能な解決方法を話す
C(Choose)=相手がOKなら良いが、Not OKならほか他の方法を再提示する
Yさんは、言いたいことが溜まっていたKさんに、毎回の面談で、アサーション・トレーニングの課題を出した。
ある日の面談でKさんは、同僚に腹を立てていた。仕事をちゃんとやってくれないそうだ。しかし、注意をする(愚痴を言う)自分が許せないので注意できなかった。実際に注意の仕方が分からない。無性に腹が立つそうだ。そこで、アサーション・トレーニングのDESCの流れで、解決方法を探った。
D=仕事をしてくれないという客観的事実を話してもらう
E=仕事をしてくれない事実に対する自分の怒りの気持ちを話してもらう
S=解決方法を一緒に考え、提案する
この場合の解決方法は、同僚に対して意見を言うことだ。同僚の仕事のやり方を見ていて、「私はこう思うが…」と気持ちを表現してみることを提案した。そして、次の面談までに実際に試すことを課題とした。
この課題は、周囲の人へ意見を言えるようにすることから始まったが、成功した時は言えたことを確認し合いながら共に喜んだ。不成功の場合は、C=また違う解決方法を一緒に考え提案し、励ましながら次の課題の成功のために、根気強く進めた。成功する数が多くなるにつれて、Kさんは自信を持ち、話し方のスキルも身に着けたようだ。自分の意見を周囲の人に言えるようになったKさんは、変わっていった。
人は簡単には変わらない。自分が変わればいい。自分を受け入れられるようになったKさんは、他人や社会に対する見方も変わっていった。Yさんと面談を始めて3年が過ぎた頃だった。
「もう大丈夫だと思いました。自分を許すことも相手を許すこともできるようになっていましたから。もう相談室には来なくていいと言ったのですが、完治してからも3年間、私が担当だった時期は毎回相談室に来ていました。愚痴を聞いてほしかったそうです。でも、愚痴の相手にも意見できているわけですからガス抜きかな。その後の再発はなかったですね」
Yさんは嬉しそうだ。
再発を繰り返すうつ病について、Yさんは問題点を挙げてくれた。
70〜80%の状態で復職しない
まず、リワークプログラムで100%職場復帰できる状態になってから職場に戻ってほしい。通常、うつ病などの気分障害で休職すると、病院で完治が認められた後に、民間のリワークプログラムに通って作業をこなしながら復職できる状態に戻していく。復職の際は主治医の診断書と産業医の承諾が必要だ。そして職場の管理者と話し合い、復職することになる。
リワークプログラムが70〜80%の状態で復職してしまった場合にうつ病は再発しやすいとYさんは指摘する。うつ病などの気分障害は、回復とともに元気になり気分も高揚するので、やる気が起こる。早く仕事へ復帰したいという焦りもあるから、強く復職を希望する人が多い。医師や管理者が、早く仕事に戻すほうがいいと考え、まだ時間が必要なのに復職させてしまうケースも多い。本人と会社のために、状態を慎重に見極め、100%復職できる状態に戻してからの復職が望ましい。休職中は傷病手当が支給される。じっくりと時間をかけて、100%働ける状態になることだ。
次に職場の受け入れ態勢も重要だ。Yさんは、受け入れる側の管理職の認識の甘さを指摘する。復職後すぐに、休職前と同じ量の仕事を何の説明もなしに渡して極度の緊張状態に追い込んだり、逆に極端に少ない量の仕事でモチベーションを下げたりする場合もある。もう完治したからと軽はずみな言動をとることは避けなければならないが、極端に気を遣い過ぎることもよくないだろう。
「管理職はメンタル不調の社員が復職した時にどう接したらいいか、どんな点に気をつけたらいいかなどの学んでほしい。復職する人が安心して帰ることのできる会社の体制作りができるといいですね」
産業カウンセラーYさんの希望は、日本の社会全体のリワークプログラムを早急に整備することだ。
[日経ビジネス]
Posted by nob : 2012年03月08日 12:37